2005年07月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

あの 「わらし仙人」 の講演を聞いた!
四国高松の番町書店の店長である「わらし仙人」の講演会が渋谷のルノアール(マイスペース)であった。会場は20台から50?台まで千差万別の人でたっぷり情熱的に3時間半の講演。どんな切り口からでも次々と言葉があふれ出てくるさすがに8万冊の図書を読破した人は違う。【あなたは決して一人ではありません、だって わらし仙人が付いているから!】信頼度100%のキャッチフレーズであることがわかった。
2005年07月30日
コメント(5)
-
それでええがな!
「ええやん関西弁!」「40代からの人生ログ」 の面白い記事をご紹介。新聞記事からの引用とのことで、内容はなんでもかんでも関西弁にしたらおもろいやん。という内容。なんと、ビートルズの「LET IT BE」は「あるがままに」ではなく関西弁では 「それでええがな!」 だって!!人生 Let it be「それでええがな!」 なんと良い響きだろう。「HELP ME!」を繰り返す歌詞では「助けてくれや! 助けんかい!! こらぁ!!!」となる。温かみがある言葉であると締めくくってありました。
2005年07月27日
コメント(1)
-
傘の頭がカメラの三脚代わりになる
折り畳み傘+デジカメ=意外な使い方としてカメラの三脚代わり(一脚)傘の頭のねじ山にカメラの三脚用の穴がぴったり合う!へえ~!折りたたみ傘の石突を止めてあるネジはカメラの三脚のネジと同じインチネジ。正確にはカメラ側はユニファイネジ UNC1/4-20。傘側が本当に同じなのかどうか(ウイットネジ1/4W20かも)は分からないが取り付けるには問題がない。これは面白い!特許になると思いませんか?
2005年07月25日
コメント(2)
-
コラム「20世紀の常識に切り込む」 から
C・D・ラミス氏の著書「経済成長がなければ私たちは豊かになれないのであろうか?」について中村達也氏がコラムで述べている。『東京の都心に雪が降ったある日のこと、ラミス氏が友人の言語学者と会話を交わした。 ビルの窓から外を見ると、眼下の公園に職場に向かう人たちの足跡が残っている。まるで定規で引かれたかのように真っ直ぐだ。ラミス氏は言う。雪国で見る野生動物の足跡は必ず曲がっている。ネズミかウサギがあのように真っ直ぐな足跡を残すのは、捕食者に追われているときだけだ、と。 そこで言語学者が問う。だったら、あの人たちを追いかけているのは何だろう。経済成長の強迫観念、とラミス氏は言いたかったようだ。 成長は20世紀の常識ではあったが21世紀の常識ではない、と彼は言う。 ゼロ成長=定常経済を提唱した論者はこれまでにもいた。19世紀のJ・S・ミルがそうであったし、既に半世紀ほども前のこの日本で、GDPの成長を福祉の増大と見なす常識に都留重人氏が疑問を投げかけていた。そうした指摘が、しばしば現実主義の立場から空想主義として批判を浴びてきた。しかし今、経済の規模も一人当たりGDPの水準も各段に増えた。他の諸国とは違って、2006年をピークに日本は人口減少社会へと転ずる。 定常経済の社会というものを現実主義の立場から構想することのできる条件が、ようやくできてきたのではあるまいか?』 以前から疑問に思っていたことへのある程度の解が書かれていた。 21世紀は環境の世紀でもあり、人類が生き延びられるか否かの瀬戸際である。 物質的な豊富さを豊かであるとに勘違いしている社会から、精神的な本当の豊かさが満ち溢れた社会への転換を期待したい。
2005年07月20日
コメント(1)
-
渋沢栄一「論語」の読み方‥‥ 書評を見て
副題が『「精神の富」と「物質の富」を一挙両得できる』 編・解説竹内均(三笠書房)斉藤孝氏のリレーエッセイから以下抜粋-------------渋沢は論語を一生の羅針盤にした。渋沢曰く「孔子の人物観察法は、視・観・察の三つをもって人を鑑別しなければならないというところに特徴がある。まず第一に、その人の外面に現われた行為の善悪正邪を視る。第二に、その人のその行為の動機は何であるかをとくと観きわめ、第三に、さらに一歩進めてその人の行為の落ち着くところはどこか、その人は何に満足して生きているかを察知すれば、必ずその人の真の性質が明らかになるもので、いかにその人が隠しても隠しきれるものではない。(中略)私は誠意を披瀝して客に接し、偏見をもたずに人と会見する。-------------シンプルだが人を見るときの原則として役立つとのこと。なるほどなあ!
2005年07月19日
コメント(1)
-
新聞の日曜版から
毎週楽しみにしている記事がある。著名な方が仕事に対する考え方を記載している記事が面白い。今回は石原邦夫氏のシリーズである。『哲学者デカルトが「方法序説」で説いているように困難な問題は分解せよというのは本当でした。私はこれを「困難の因数分解」と呼んでいるのですが、こうして困難を共有することで感動と情熱をも共有できるのです。 誰もが自分を認めてくれないと感じたら得意領域をもう少し絞り込んでみてもいい。ただ、簡単に途中で放り出さないことを肝に銘じて続けていくこと。 語学でもそうだがある一定量の学習が足りると急に聞き取れるようになる。 継続して自分の中に蓄積することで、必ず階段は高くなり目の前の視界は開ける』毎回の言葉を若い人に紹介するとともに、自身も参考にしている。
2005年07月12日
コメント(1)
-
古池に蛙は飛び込んだか?
新聞の書評(訳者:吉田直哉)にあった面白い記事『名句への卓抜な問題提起。問いの核心は「古池や」は「古池に」と同じなのか?ということである。カルフォルニア大学の数学者リチャード・ベルマンの言葉「良い問いは答えより重要だ」である。本来は数学の世界での発言だが芭蕉の名句についてもそのとおりであると言えるだろう。』何気なく親しんでいた名句に対してこんな見方で思考を凝らすことができるとは!
2005年07月11日
コメント(2)
-
企画力・創造力向上研修から
香西勉氏のセミナーを聞いた。歯切れの良い講義でテンポも良くシンプルで分かりやすい。事業を考えるポイントは3点。Whom ,What(Needs,Value),How(Where,When,How),誰の、どのニーズに対して、どうやってやれば良いのか?毎日の新聞をこの切り口で見て整理することが事業の隙間、領域を考える上での訓練になるという。キーワードは「絞込み!」
2005年07月10日
コメント(4)
-
全国の苗字について
私が珍しい苗字なので苗字には大変に関心がある。皆さんの苗字の世帯は全国でどのくらいあるかわかりますか?このサイトでは一瞬に割り出してくれます。是非一度遊んでみては?全国の苗字(名字)10万種(読みで13万種)を「漢字をベース」に「全国の苗字」と「世帯数」を調査し記載している。この方は全国の苗字は、漢字で10万2千種と推定しているとのこと。珍しい苗字で掲載されていない苗字があったら是非紹介を!
2005年07月09日
コメント(2)
-
東京の住居表示
旧い町名を強引にまとめたものだが、丁目の表示にはきちんとした規則があるとのこと。皇居に近いほうから1丁目、2丁目としてある。へえええ~!今尾恵介著「住所と地名の大研究」(新潮選書から)
2005年07月03日
コメント(2)
-
有森裕子の言葉から
『美術と音楽とスポーツは人が成長していく過程で絶対に必要な3大文化だと思っている。子らに「好きなことは一生懸命に続けて」そして「必ずフィニッシュして」と付け加える』 朝日新聞「私の視点」から 失敗とは途中で諦めること。好きなことを最後まで続けよう!
2005年07月02日
コメント(1)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- ゲーム日記
- 生放送とアニバーサリーイベント後半…
- (2025-11-15 21:00:04)
-
-
-
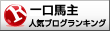
- 一口馬主について
- ペタルズダンス出走予定(11/16東京4…
- (2025-11-15 22:11:26)
-
-
-

- 寺社仏閣巡りましょ♪
- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…
- (2025-11-14 23:40:04)
-







