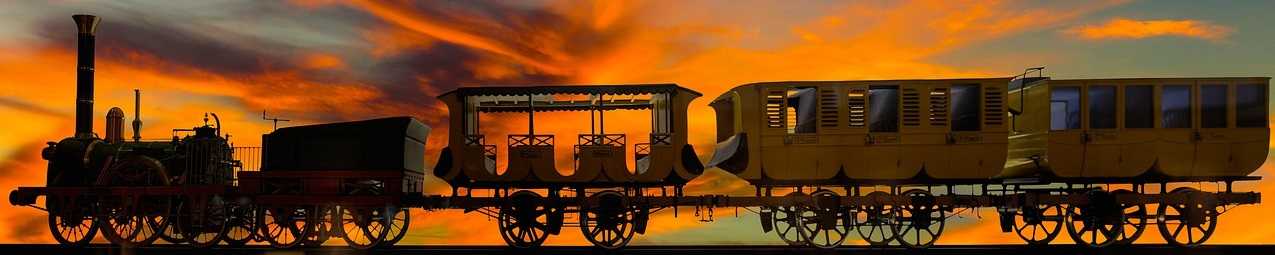2025年05月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

【 消失 】 桝塚教会の推定高見彰七作品 3
にほんブログ村 豊田市 桝塚教会は閉鎖されていました。3体のコンクリート像は失われ、石仏のみが残されていました。途方にくれましたが、すぐ近くに桝塚西町区民会館がありました。そこで桝塚協会について、職員の方に問い合わせました。すると驚くほど丁寧なご対応が頂けました。職員の皆さんで相談され、近所の方の所まで案内くださいました。ご紹介されたのは、教会の閉鎖に関わった方でした。Q) まずは、閉鎖の理由。A) 桝塚教会の御住職(?)が亡くなったため。Q) コンクリート像の行方は?A) 細かく砕いて破棄された。Q) コンクリート像の破棄はいつ?A) 2022年頃。Q) コンクリート像はいつからあった?A) 亡くなられた御住職の先代が建てられた。Q) 像の写真はありませんか?A) あったが、最近、破棄してしまった。残念ながら、3体のコンクリート像は現存しません。写真はお持ちの方はおられるかもしれません。コンクリート像は残念でした。しかし、区民会館の皆さんの親切丁寧な対応にはひたすら感謝の現地訪問でした。【前の記事】 「【 消失 】 桝塚教会の推定高見彰七作品1」【前の記事】 「【 消失 】 桝塚教会の推定高見彰七作品2」【 桝塚味噌 お味噌汁 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.30
コメント(26)
-

【 消失 】 桝塚教会の推定高見彰七作品 2
にほんブログ村 豊田市の桝塚教会に着目した理由をお話します。きっかけはネットで見た画像でした。(画像出典: https://jinja-bukkaku.net/detail.htm?jbId=35422#gsc.tab=0)解像度が悪く、最高画質でも下記の通りです。しかし独特の彩色が高見彰七作品のように思えます。Google mapで桝塚協会の住所を表示させても、ストリートビューで良い情報は得られません。(後でストリートビューに位置ずれがあったとわかりました)AIに桝塚協会を聴くと、2021年の5~6月に登記が閉鎖されたと回答されました。まず絶望的ですが、公共交通機関でアクセスできるため、現地調査しました。ローカル路線感の強い愛知環状鉄道を利用します。最寄りの駅は北野桝塚駅。改札もゲートがなく、通路やホームにあるセンサーにICカードをタッチするだけの入場・退場管理の駅です。北野桝塚駅は岡崎市ですが、600mほどの距離にある桝塚協会は豊田市になります。駅のすぐ北に市境があるようです。桝塚協会を探すのが大変かと思いましたが、意外にあっさりと見つかりました。やはりコンクリート像はすでにありません。しかしすぐ近くに桝塚西町区民会館がありましたので、お話をうかがいました。非常に丁寧な対応を頂き、情報も得られましたので、この続きは次回にご紹介します。【前の記事】 「【 消失 】 桝塚教会の推定高見彰七作品1」【 北野桝塚駅の近くには、桝塚味噌の「のだみそ株式会社」もあり 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.27
コメント(46)
-

【 消失 】 桝塚教会の推定高見彰七作品
にほんブログ村 今回は残念な報告となりました。現地確認で、高見彰七作品らしき3体のコンクリート像の消失を確認しました。場所は豊田市桝塚西町の桝塚教会。2022年9月のストリートビューをご覧ください。この3体の像は消えてしまいました。地蔵菩薩像と法然上人像?上記のスクリーンショット (ストリートビューは更新で消えるため)観音菩薩像?上記のスクリーンショット上記のGoogle mapの画像は、現地確認後に見つけました。現地確認では消失したのは1体のみと思っていました。まさか3体とは……。まずは画像を御覧になり、高見彰七作品か否かをご検討ください。なぜ桝塚教会を訪問したか、現地確認の経緯は複雑で、また、ご協力もありましたので、次回の記事で御紹介します。【 法然 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.24
コメント(42)
-

法念寺にも花入れがあった!
にほんブログ村 法念寺の聖徳太子像。これには私にとって重要な情報がありました。それは聖徳太子像の足元の花入れです。霊岩寺の地蔵菩薩像を思い出してください。高見彰七作品と推定しながらも疑問もあった地蔵菩薩像。疑問の理由は、地蔵菩薩像の傍にある花入れでした。高見彰七の花入れは当時類例がありませんでした。またそのデザインも高見彰七らしくないと感じていました。それと類似した花入れが今回、法念寺にもありました。両者を比較しましょう。まずは法念寺の花入れ。次は霊岩寺の花入れ。法念寺の花入れは破損していますが、霊岩寺の花入れとよく似ています。法念寺の聖徳太子像が高見彰七作品なら、霊岩寺の地蔵菩薩像も高見彰七作品と断定できるでしょう。今回の法念寺の新発見は、本当に私にとって重要な意味がありました。【 花入 小西陶古 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.22
コメント(34)
-

法念寺の聖徳太子像 その2
にほんブログ村 新発見の聖徳太子像、続きです。太子像には様々なお姿がありますが、今回は「聖徳太子 孝養像」です。これは父・用明天皇の病気平癒を祈り、仏に香を捧げる16 歳の姿です。(画像出典: 東京国立博物館 1089ブログ, https://www.tnm.jp/modules/rblog/index.php/1/2021/08/13/_taishi4/ )読者の皆さんも高見彰七作品の鑑定力は既にプロ級。今回も御顔立ちを一見して、高見彰七作品と感じた方が多数でした。では、容姿の次には何を見るべきでしょうか。今回は観音像の装束の特徴は参考になりません。そうですね。次に見るべきは、前後接合面のヒビ割れとモルタルの材質です。状態は良好な聖徳太子像ですが、それでも側面にヒビ割れがあります。前後を別工程で製作する、製作方法の欠点です。またこれが中大型の高見彰七作品の特徴でもあります。さらにモルタルの材質にも高見彰七作品の特徴があります。体に使うモルタルは工芸用としては粗い石(骨材)が入っています。ただし御顔は石が表面に出るのを避け、細かいモルタルを使います。これも高見彰七作品の特徴です。今回は、特に衣装の模様も綺麗に仕上げられています。ご覧ください。さて、今回、この聖徳太子像から得た新たな情報を次回の記事で紹介します。【 聖徳太子 孝養像 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.20
コメント(30)
-

法念寺の聖徳太子像 その1
にほんブログ村 高見彰七作品候補、新発見の報告がありました。今回は驚きの新発見、聖徳太子像です。発見者は多くの高見彰七作品を発見されている「FDG公式さん」です。【FDG公式さん】 「FDG公式さんのH.P.」今回はFDG(フィールドディスカバリ―ゲーム)を活用されて、このコンクリート像を発見されました。FDGの文化財ポイントにアクセスされて、この像を発見されたそうです。非常に完成度が高い丁寧に造られた聖徳太子像です。多くの高見彰七作品では、像の背面は簡略化されています。しかしこの像では背面の造形も丁寧です。初の発見となる聖徳太子像。理由は次回の記事で記しますが、高見彰七作品とみて良いでしょう。【 リンク集3 (No.8) 聖徳大師像 】 ・所在地: 愛知県みよし市三好町原 法念寺 ・製作年月: 不明 ・作家銘: なし ・寸法: 像のみの高さ 140cm, 基台のみの高さ 100cm 胸部幅 30cm, 胸部厚さ 27cm 花入れ高さ 30cm, 花入れ直径 14cm ・発見者: FDG公式さん完成度の高さから、高見彰七 円熟期の作品、傑作だと思います。また、この聖徳太子像には、重要な特徴もあります。それも次回の記事で示します。それにしても、FDGの探索機能は素晴らしい。法念寺は道路に面した手前が、広い児童公園になっています。一見して寺と分からず、私は現地確認でも迷いました。とても私の自力では、この聖徳太子像は発見できなかったでしょう。「FDG公式」さん、新発見おめでとうございます。【 長寿ういろ 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.17
コメント(41)
-

【化粧地蔵考】 その4 石仏の変質
にほんブログ村 石仏ではしばしばありますが、長い年月を経る間にその役割が変化することがあります。次の画像の化粧地蔵も、そのひとつだと思います。【玉野市梶岡の化粧地蔵】 「化粧地蔵でほのぼの (その46)」こちらの綺麗な化粧地蔵は、本来は地蔵菩薩ではないと思われます。この石仏はつぼみの蓮の花を手にしていますが、地蔵菩薩が蓮の花を持つのは違和感があります。一般的に考えると、蓮の花を手にするのは観音菩薩などです。蓮の花は泥水の中から生え出ますが、泥水に汚れることなく美しい花を咲かせます。このことから、煩悩に染まらない仏の悟りを蓮の花は象徴しています。またこの石仏は、つぼみの蓮の花を手にしています。蓮の花はつぼみのうちに、その内部に実を持ちます。つまり、誰もが本来その内に、仏になれる素質をもつことを蓮のつぼみは意味します。観音菩薩は蓮のつぼみを持つことで、悟りの本質を伝えます。本来は観音菩薩であろうと思われる石仏ですが、石仏の上部に描かれた「梵字」は地蔵菩薩を意味します。この梵字が描かれることにより、この石仏は化粧地蔵となっています。石仏の変質は、否定すべきものではありません。重要なのは地域の人々が、石仏を何と捉えているかでしょう。その意味で、地蔵菩薩の梵字が刻まれたこの石仏は地蔵菩薩です。石仏は梵字を彫刻しなおす必要がありますが、化粧地蔵であれば梵字を描きなおすだけで十分です。石仏の変質、役割の変化は、化粧地蔵であればなおさらに起こりやすいということでしょう。【 岡山デニム 3色組 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.15
コメント(28)
-

【化粧地蔵考】 その3 化粧地蔵と宝篋印塔の融合
にほんブログ村 岡山県玉野市 胸上地区の特殊な化粧地蔵について考えます。【胸上の特殊な化粧地蔵】 「化粧地蔵でほのぼの (その19)」この化粧地蔵は頭部が地蔵に見立てられていますが、体は宝篋印塔です。地蔵菩薩と宝篋印塔が融合した意味について考えます。「宝篋印塔」 (画像出典: Wikipedia)地蔵菩薩は天界や地獄の六道を歩き、亡者を救済します。地蔵菩薩は地獄に落ちた亡者すら救うのですから、実に寛容な慈悲の心を持った菩薩です。宝篋印塔は、生前または没後に建てられます。宝篋印塔に願えば、地獄に落ちてもその環境は天界の様に浄化され、亡者は救われると言います。亡者を救う地蔵菩薩と、地獄さえも浄化する宝篋印塔、そのふたつが融合すれば、まさに万能の救済となることでしょう。宝篋印塔は右回りで礼拝することで、加持があるとされます。一方、地蔵菩薩は直接語り掛け、救済を願うことができます。地蔵菩薩と宝篋印塔の融合は、直接、宝篋印塔に語り掛け、救済を願うことを容易にするものでしょう。胸上地区の化粧地蔵と宝篋印塔の融合は、まさに究極の救済なのです。【関連記事】 「石造物の正体(胸上の北向き地蔵など)【 岡山 白桃ゼリー 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.13
コメント(30)
-

【化粧地蔵考】 その2 持物の変化
にほんブログ村 児島半島南部 玉野市胸上地区「西の地蔵」をご覧ください。【西の地蔵】 「化粧地蔵でほのぼの (その4)」お地蔵様が手にした物をご覧ください。これは「宝珠」ではありません。お地蔵さまは「おむすび」を手にしています。子供達には宝珠より、おむすびの方がイメージしやすかったのでしょう。これは鯖を持った弘法大師「鯖弘法(鯖大師)」をも連想させます。【鯖大師】 「名古屋市 鯖大師 龍泉院胸上地区「沼の地蔵」の持物も難解です。仏教の知識が乏しい私はいっそう難解です。【沼の地蔵】 「化粧地蔵でほのぼの (その2)」例えば右端のお地蔵さまは「幟旗(のぼりばた)」を持っているようにみえます。これは本来「幡(はた)」ではないでしょうか。「お地蔵様の持物」(画像出典:https://saishinji.site/%E3%81%8A%E5%9C%B0%E8%94%B5%E3%81%95%E3%81%BE%E3%80%8E%E5%85%AD%E5%9C%B0%E8%94%B5%E5%B0%8A%E3%80%8F7%E6%9C%8820%E6%97%A5/ )正解かどうかわかりません。子供達もこれはなにかを推定しつつ描くので、持物も変化するのでしょう。化粧地蔵の文化が親しみを持って継承されるのであれば、お地蔵様がおむすびを持つようになっても、私は良いと思います。【 岡山県産 ひのひかり 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.11
コメント(28)
-

【化粧地蔵考】 その1 地域差
にほんブログ村 岡山県南 児島半島の化粧地蔵について、思う所を書き記します。多くの指摘がある様に、児島半島の化粧地蔵には地域差があります。その違いは、児島半島の南北で大別できます。 1) 児島半島南部 玉野市胸上地区を中心として、幾つもの化粧地蔵が点在します。 多色の鮮やかな彩色が施された化粧地蔵がこの地域の特徴です。 子供による地蔵盆での絵付けを思わせる化粧地蔵もあり、 化粧地蔵の文化が受け継がれている地域のようです。【沼の地蔵】「化粧地蔵でほのぼの(その2)」 西は大薮・山田地区、東は小串地区に化粧地蔵は分布します。 胸上地区より西の大薮・山田地区では化粧地蔵の彩色が薄れ、 化粧地蔵の文化が薄れつつあるようにみえます。 一方、西の上坂地区では石の屋根で覆われた六地蔵が多く、 彩色も鮮やかで、化粧地蔵の文化の健在ぶりがうかがわれます。【下山坂の地蔵】「化粧地蔵でほのぼの(その8)」2) 児島半島北部 正確には半島北西部、玉野市八浜地区にも化粧地蔵が点在します。 朱色のベンガラをスプレーで吹き付けた彩色が特徴です。 ベンガラの彩色は主に胴部に施されます。 吹き付けではなく塗りによる彩色の場合にも体は赤く塗られ、 顔の彩色は薄いものが多い様です。 【八浜児島淡水湖近くの化粧地蔵】「化粧地蔵でほのぼの(その38)」 朱色へのこだわりは、朱塗りによる厄除けを連想させます。 天然痘の赤を意味する彩色で病魔を避ける。 地蔵盆の主役は子供でもあり、ベンガラは厄除けの意味でしょう。 ベンガラを吹き付けても、彩色が楽になるとは思えません。 ただ、吹き付けでは、技能の差は表れ難いかもしれません。 吹き付けには、技能の未熟な小さな子供でも 彩色に参加できるようにする意味があったのでしょうか。 幅広い年齢の子供が参加できれば、化粧地蔵の文化が 継承されやすくなるでしょう。 八浜地区のベンガラの吹き付けに、文化の伝承の工夫があるなら、 素晴らしい工夫だと思います。以上の様な感じで、化粧地蔵について自由に記そうと思います。【 備前焼 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.09
コメント(28)
-

5月のナナちゃん
にほんブログ村 名古屋駅前のナナちゃん、うんこまみれになっています。このコスプレは、名古屋のうんこミュージアムのオープン記念企画。それにしても、うんこが服のデザインになる日が来るとは……。価値観は時代によって変わるものですね。【うんこミュージアムNAGOYA】 「公式H.P.」【 コスプレ用 】 < ↓ ランキングクリックはこちらから > にほんブログ村
2025.05.07
コメント(26)
全11件 (11件中 1-11件目)
1