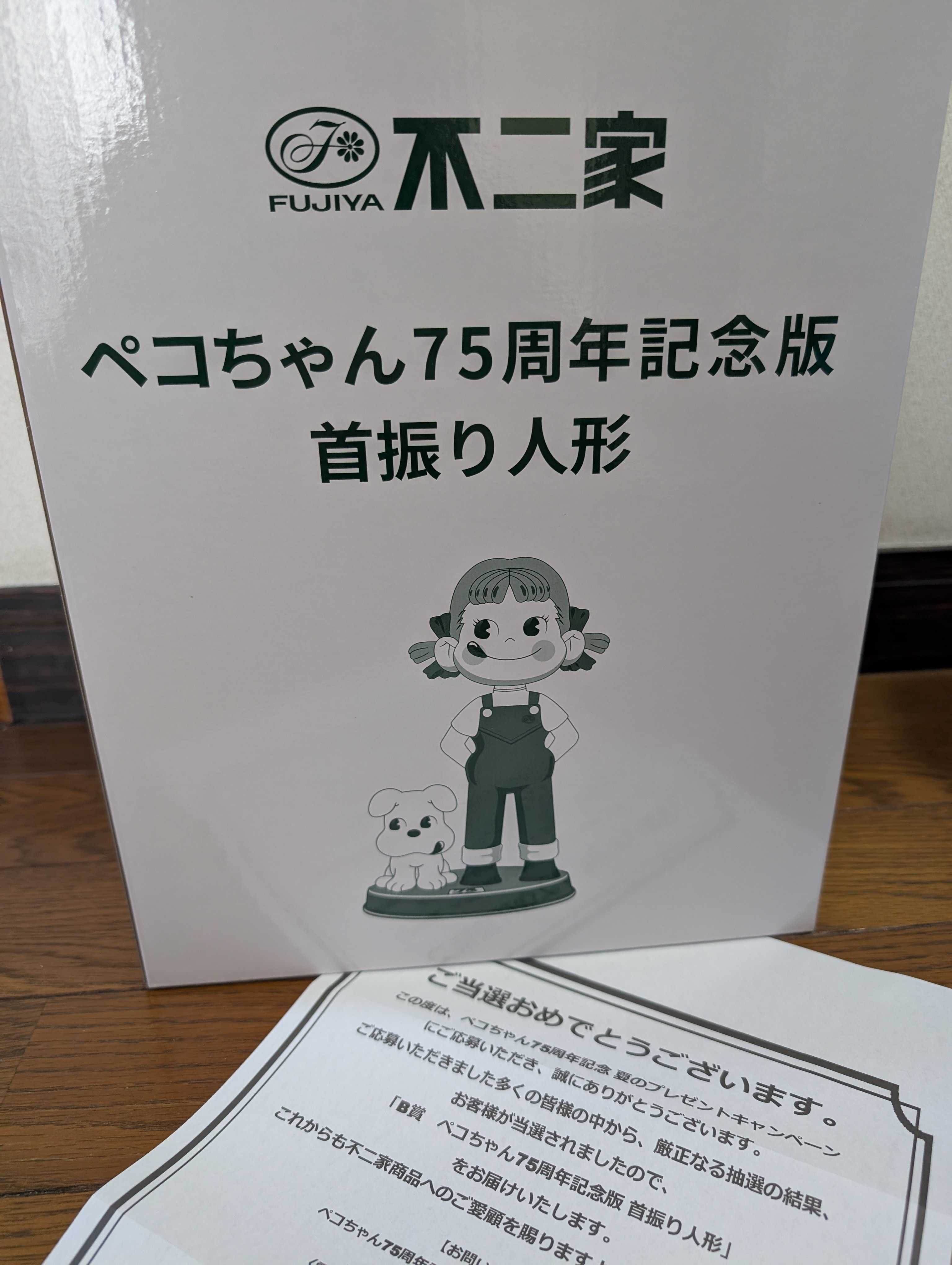2010年05月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
八日目の蝉を色々・・・。
昨日体調を崩したので、一気に八日目の蝉を読み切りました。ドラマと違って、母と娘という視点が強い描写だったなぁと思いました。なんていうか・・・女性による女性のための小説というか。ドラマは、色々な母に焦点を当てていたけど、娘側の描写はちょっと物足りなかったからね。希和子から本当の家族の元にもどった恵理菜(薫)が、「新しい」家族の中でもがく姿などは、小説の方が掘り下げられていていますね。自分の娘なのに小豆島の言葉を話して、都会の生活に慣れない恵理菜。そんな娘を見るにつれ、夫のしたこと、希和子への憎しみが募って、その不安定さを自分でコントロールできずに恵理菜にぶつけてしまう母親。それは愛情とは別なんだよね。愛情はあるけど、それでも自分の傷も深すぎて上手く表出もできないし、今以上に自分が傷つくことを恐れてしまう。母親も父親も希和子が逮捕されて事件の背景がわかるにつれ、自分達も世間から叩かれていて逃げるような生活をしていたから、心に蓋をしていた。恵理菜と向かいあう事を恐れて、夜遊びを毎日のようにする母親と、それには背を向ける父。唯一、妹だけが最初は受け入れられなかった突然現れた「姉」を、家族としてつなぎ止めようと努力をしてくれる。そんな状況の中、その状況は自分のせいではないと思うために恵理菜は希和子を憎むようになるんだよね、母親が「世界一悪い女」と言うから、その通りに。「あの女」って呼ぶ。確かに、希和子は誘拐犯で、「世界一悪い女」なんだろうし、恵理菜がいわゆる「普通の子ども」として育つための環境を奪ったという何にも変えられない罪を犯している。でも、でもね。希和子は身勝手な思いだとしても薫(恵理菜)を愛していたし、薫も引き離されるその時まで、ううん、自分が両親に愛されなければ生きていけないって思うその時まで、希和子のことを確かに愛していたんだよね。本当はずっと。彼女に思慕を抱いていたけど、それを打ち消すために「憎む」という感情に転化してしまったことは本当に悲しかった。その中で、それでも自分は家族の一員なのだと恵里奈が気が付く描写と、薫であった自分も自分なのだと受け入れる事が出来た部分は小説版の秀逸な所だと思う。 私が一番共感したのは恵理菜が「母親が、なんでもかんでも話してくるとげんなりするっていうか、なんか自分のせいみたいに思うんだよね。」って言葉。子どもの頃ってそうだよなーって思う。特に母と娘ってそうかなって気もする。どの言葉よりも一番自分の中にすーって入ってきたな。さて、原作もドラマも一つだけ突っ込みたい所が・・・。指名手配されている希和子の銀行口座、動かしたらその時点で足が着きますが、なぜエンゼルホームでバレなかったのかっていう(笑)。そのドラマ版だけど、原作よりも良いなって思った部分がちらほら。一つは、岸谷さんの文治の存在。原作だけだと、うーん。なんていうか誠実な男性の描写が全く、本当に全くなくって、「男は悪だ」っていうエンゼルホームの教えが正しいことに思えなくもない気分になっちゃうんだけど、希和子に対して誠実に愛した文治の存在は大きかったなぁ。「あんたがどんなことをした人でも、俺は裁かんよ。」って言葉はその言葉だけでなんとなく希和子が救われたなぁと。この後、薫と引き離されて、刑務所に入ることになっても誠実な男性に愛された記憶は救いかなって思った。だからこそ、悲しいけれど、薫との生活が終わることにも納得が言った。彼女が何度も何度も唱えた「私はどこまで行けば許されるのだろうか?」という思いに呼応したような台詞だったかなと思います。考えてみると。「どこまで行けば許されるの?」っていうのもドラマオリジナルなんだけど。まぁ、「ゆるされないよ」って突っ込みも入れたくなるんだけど、でも、この思いは身勝手な彼女の思いでもあり、薫への愛でもあるなぁって思った。それがとても切ないのだけどね。ただ、この事件の現況はやはり恵理菜(薫)の父親であり、彼の不誠実な態度がなければこんなことにはならなかっただろうとは思う。確かに希和子はバカな女ではあるんだけど、そのバカをだますヤツはもっと最低だ。その恵理菜の父親と母親がずっと夫婦関係を続けていたことはドラマだけではあまり納得がいかなかったけれど、実は恵理菜の母親も妊娠前の一時期不倫をしていて、最初はその男が恵理菜を誘拐したと思い込んでいたことからもお互いに事件に対して後ろ暗い思いがあり、それを打ち消すためにも被害者であることを確認し合わなければなからなかったという一文は、異常な状況の中の異常な心理という部分で納得はいった。そんな大人達の身勝手に巻き込まれた恵理菜は本当に言いようもない被害者だけれど、その彼女が最後に前を向けたことが、本当に良かったと思う。多分、今はドラマの印象が強すぎるので、もう少ししたらもう一度読みたい一冊です。
2010.05.07
コメント(0)
-
ダウト~あるカトリック学校で~
アカデミー賞ノミネート作品。時代はケネディ大統領暗殺の翌年。公民権法が制定されてすぐの頃です。アメリカのとあるカトリック学校で起こった疑惑をめぐる心理戦。学校唯一にして初の黒人男子生徒と、革新的な神父(フィリップ・シーモア・ホフマン)の関係を疑う、校長がメリル・ストリープ。最初に疑念を持ち、疑惑と真実でゆれる若い担任のシスター(エイミー・アダムス)。この3人の聖職者が主な出演者。そこに確固たる証拠はなく、あるのは「疑う心」のみ。結局、真実は最後まで明かされることはなく、しかし事実、その疑念のみで追い詰め神父は転任することにはなります。生徒と神父の間には、何かあったかもしれないし、なかったかもしれない。でも、少なくとも学校にはなじめて居なかった彼を救ったのはその神父であり、彼自身には「そういう気質」があるということが母親の口から明かされていますね。「それでも母親か?!」となじるメリル・ストリープに対して、「大事なのには、あの子を気にかけてくれる人がいること。理由はどうでもいい」と、その時置かれていた黒人としての社会の実情や、彼自身の性質など、守られてい世界にいる人間には所詮わからない現実を突きつけている所など、考えさせられます。見方は色々あると思うんです。確かに、メリル・ストリープの演じる校長は古い考え方から抜け出すことが出来ないし、おそらく黒人に対する差別も未だ持っているし、子どもには必要以上に厳格。そしてそれらを守るためには「神から離れることは結局神を守る事だ」という信念を持って、大罪である「嘘をつく」ことさえいとわない人です。でも、一方で、視力の衰えたシスターが施設に送られないように、さりげなくフォローをしていたり、差別意識を持ちつつも彼女なりに黒人生徒が不利益を被らないように「普通の生徒」として卒業できるように配慮しているんだと感じる場面もありますね。神父が、男子生徒といわゆる同性愛としての関係を持つ事件は昔から後を絶たないようです。(カトリックでは同性愛は罪です)そして彼女の今までの経験の中でもあった。だからこそ、彼女は自分の直感に絶対的な自信があった。確証はないけれど、それは、生徒を守るためでも、学校を、信仰を守るためでもあるんですね。周りの人たちは「無かったことにしよう」という態度の中で、一人だけその疑念に立ち向かう姿は、見方によっては立派です。ただ、証拠はない。そして、彼女はその証拠を作るために「嘘」をついてしまった。”神を守るためには、時には神から離れることも必要だ”という信念で。彼女は、ブッシュ大統領のメタファーだそうです。ラスト、「疑惑が・・・疑惑が・・・」と泣き崩れる姿は、自分の行動が果たして正しかったのか、その疑惑に捕らわれた姿に見えました。さて、一方で神父。この神父は、男子生徒が学校で浮いている存在だということを知っています。暴力こそ振るわれていないものの、いわゆる”いじめ”を受けている事を描写するポイントはいくつかありますね。また、生徒は父親から虐待を受けていることもあり、同情し、気にかけています。神父が生徒と二人きりになったことに対する釈明には説得力があります。でも、確かにここにも証拠はない。そして、校長がついた嘘がきっかけで転任をしたように見え、その行為だけではもしかしたら「あった」のではないかとも見えます。でも、神父は次の教会では昇進している。ただ単に昇進のための転任だったのではないか?とも思えるわけで。校長とは正反対の革新的な考え方の人であり、だからこそ彼を差別せず、彼の実情を見て彼に優しく接しているのですが、その中で「それ以上の」関係があっても、不思議ではないよね、というようにも見えなくもない。彼が嘘をついているかは解らないけれど、ただ一つ言えるのは男子生徒は彼をとても頼りにして、慕っていたということだけですね。それは、そこに大きな真実としてあると思います。アメリカのその時代が持っていたであろう社会的な背景に、さらにカトリックとしての信仰としての背景も絡み合って出来上がった疑念。その疑念を捨ててしまえば、それはそれで問題なく、何事もなく過ぎ去ったかもしれない。少なくとも、校長の「確信」を「確証」だと思い込んだ上での追求は間違いだったと言えるでしょう。でも、校長の「確信」が真実ではないという証拠もまたないわけであり。「私の経験がそう言っている」という言葉は、正直、それだけをよりどころにして人を疑いぬく怖さと、でもそれは間違っていないことも往々にしてあるなという思いで複雑に感じました。見ている私からも、結局事実はわからない。ただ、証拠がない中で追い詰める姿は人の持つ疑念や思い込みの怖さを如実に表しているなと感じました。演出面では、もともとはブロードウェイのストレートプレイだそうで。トニー賞(たぶん演劇部門)とピューリッツァー賞を取っていますね。そのためかちらほら舞台っぽい演出があります。わざとらしく電球が切れたり、雷がなったり。ベタだなーと思ったけど、舞台劇だと思うと納得。また、4人の登場人物だけで繰り広げられる密室劇だそうで。多分、舞台の方がこの問題は浮かび上がりやすいかなぁとは思いました。メリル・ストリープの鬼気迫る演技というか、疑念にとりつかれた狂気のようなものが非常に気迫があって怖かったです。でも、面白い映画だと思います。109分と非常に短い映画なので、時間があれば是非。
2010.05.04
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1