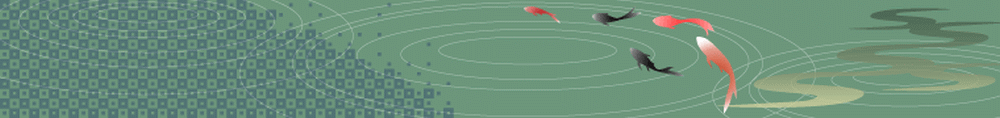-
1

三線で弾くクリスマスソング
「きよしこの夜」(本調子)工 上 老 上 四 乙 合 〇 〇 五 工 〇上 中 上 老 〇 〇 上 中 上 老 〇 〇き ― よ し ― ― こ の よ る ― ―き ― よ し ― ― こ の よ る ― ―八 〇 八 六 〇 〇 七 〇 七 工 〇 〇ほ ― し は ― ― ひ ― か ― り ―み ― つ げ ― ― う ― け ― し ―五 〇 五 七 〇 六 五 工 五 工 中 〇す ― く い ― ― の み ― こ は ―ま ― き び ― ― と た ― ち は ―五 〇 五 七 〇 六 五 工 五 工 中 〇み ― は は ― ― の む ― ね に ―み ― こ ― ― ― の お ん まえに ―八 〇 八 九 八 六 〇 七 〇 七 九 〇ね ― む ― り ― ― た も ― う ―ぬ ― か ― づ ― ― き ― ぬ ― ―七 工 中 工 〇 尺 上 四 〇 〇 八 七ゆ ― め や ― す く ―か ― し こ ― み て ―飲み会の余興ですね。笑いましょうね。
2005年12月23日
閲覧総数 2343
-
2

八重山古典民謡 「しょんかね節」(二揚)
この歌に出てくる男女は、島に赴任していた役人と、身の回りのお世話をする女性。 今は久部良港にフェリーが着きますが、昔は なんた浜に船が着いていました。 大変な航海をして赴任地に辿り着いた役人は、沢山の島の女性の歓迎を受けます。 船から上陸すると、砂浜の波打ち際には、歓迎する女性達が個々に作ったたくさんのアダン葉のゾウリが置いてあり、役人が履いたゾウリの製作者(女性)が、赴任中「島の妻」として尽くしていた。 二人は、出会った時から恋仲になり、首里に戻る役人との別れを切なく歌っています。 当時の船舶や航海術で荒い外海の航海は、死を覚悟の渡航の為、航海の安全を祈る歌でもあります。 「しょんかね節」(二揚) 読み人知らず1、暇乞(イトゥマグ)いとぅむてぃ 持(ム)ちゅる 盃(サカジキ)や 「ツィンダサヤゥ ツィンダサ」 目涙(ミナダ) あわむらし 飲(ヌ)みぬ ならぬ 「ウムイバヌ ナグリシャ」 「ンゾ ナリ ムヌ ヤゥ ハリ ションカネーヤゥ」〔愛するあなたとの別れの盃の中に、「可哀相で、可哀相で」 涙が落ちては泡が立ち、涙が落ちては泡が盛り、一口もノドを通す事ができましょうか〔様々な思いが懐かしい〕〔可哀相な人、しょうがない〕〕2、片帆(カタフ)持(ム)たしば 肝(クィム)ん 肝(クィム)ならぬ 「ツィンダサヤゥ ツィンダサ」 諸帆(ムルフ)持(ム)たしば 諸目(ムルミ)ぬ 涙落(ナダウトゥ)し 「ウムイバヌ ナグリシャ」 「ンゾ ナリ ムヌ ヤゥ ハリ ナグリシャー ヤゥ」〔船の帆が揚がり始めると、落ち着かなくなり、情けない思いが込み上げる、全ての帆が揚がり、最後の最後の別れ、胸は焦がれて、張り裂けんばかりに、泣き泣き崩れる〕3、与那国(ヨナグニ)ぬ 渡海(トケ)や 池(イキ)ぬ 水(ミジ)ぐくる 「ツィンダサヤゥ ツィンダサ」 心(ククル)安々(ヤシヤシ)とぅ 渡(ワタ)てぃ いもり 「ウムイバヌ ナグリシャ」 「カリユシ ショウリー ハリ サトゥ マイー ヤゥ」〔与那国から出て荒波が、池の水の様に穏やかに願います、心安らかでありますように、航海の安全を祈願しております〕4、なんた浜までぃや 無蔵(ンゾ)に 送(ウク)らりてぃ 「ツィンダサヤゥ ツィンダサ」 大渡(ウフドゥ)押(ウ)し 出(ヂィ)りば 美風(ミフ)どぅ 頼(タヌ)む 「ウムイバヌ ナグリシャ」 「カリユシ ショウリー ハリ サトゥ マイ ヤゥ」〔なんた浜から(約三キロのヤディク高台まで登って)見送りするのは乙女達の役目です、大海に出た後は、風と波に祈を託します〕5、与那国ぬ 情(ナサ)き 言葉(クトゥバ)どぅ 身(ミ)ぬ 情(ナサ)き 「ツィンダサヤゥ ツィンダサ」 命(ヌチ)ぬある 間(エダ)や とぅやい しゃびら 「ウムイバヌ ナグリシャ」 「ンゾ ナリ ムヌ ヤゥ ハリ ションカネーヤゥ」〔与那国の情けは「御嶽の前と海岸で最後の別れの遺言葉」と言う御言葉の挨拶がある、命がある限り問いかけ逢わせをいたしましょう〕
2005年02月14日
閲覧総数 1451
-
3

「サンシェン」の伝説
昔の中国大陸は、日常茶飯事の戦争がありました。これに嘆いたサンシェン奏者の男が、両軍の間の小高い丘に登り、この楽器を弾き語り始めました。「蒼き空の下 金色に輝く麦 風はそよぎ 木陰では乳飲み子が眠り 我は麦刈りをする」唄、音色、いや、情景が浮かんでは消えるこの感覚に、兵士は戸惑いはじめた。「蒼き空の下 金色に輝く麦 風はそよぎ 木陰では乳飲み子が眠り 我は麦刈りをする」こうして争いは収まった。歌に感情がこもれば、唄になりその唄を聞く者全てが、情景の中に居る。リンクして頂いている木の香さん提供です。感謝!津軽三味線並の大きさです。糸巻きの下の歌口に注目です。三味線のさわり加工がなく、三線の歌口です。モンゴルのお姉さんですね。うつくしい。弾き方は、やはり三味線風なのかな?小指禁は三味線薬指禁は三線しかし、何故に沖縄・与那原のフィリピンパブで演奏か 不思議です?
2005年10月15日
閲覧総数 122
-
4

待ち焦がれる女の恋愛歌・殿様節
殿様とは、ニックネームで、西表島祖納(そない)の筆者(今の役所の書記役人「1804年」に拝命された「石垣高端」。 彼は、頭が禿げ上がり、あたかも大和の殿様の月代(サカヤキ)の様だと持て囃されていた。 八重山で小町娘と評判高い「カマドマ」と言う美人を賄女としていた。 「1817年」この二人の恋愛実情を知り尽くし、大和歌にも精通していた「石垣用典」の作とされている。 殿様節1、浮世(ウキユ)に 名取(ナトゥ)たる 恋(クイ)ぬ 氏神 祖納(ソナイ)ぬ 殿様(トゥヌサマ) 我(バ)んどぅ やゆる かまどーまぬ 事(クトゥ)思(ウム)いどぅ 船浮に行くよば2、かまどーま 思(ウム)いぬ 殿様(トゥヌサマ) 抱ぎ欲(ブ)しゃぬ 立(タ)ちん びちん ぶらるぬヤゥ いらよまーぬヤゥ 立ちん びちん ぶらるぬヤゥ3、前崎先(マイザスィサクィ)から 殿様(トゥヌサマ)舟(フニ)ぬ とぅん出(ディ)だらヤゥ 船浮 かまどーま 焼酎(ショウチュ)呑(ヌ)まんでぃ しっちゃ うっちゃらヤゥ4、うりどぅ うり 殿様舟(トゥヌサマフニ)で 思(ウム)いまち ぶるけ 松田屋(マツィダヤ)ぬ 加那(カナ)ぶじどぅ 高間かい おるそぅぬヤゥ5、尚又(ナウマタ) とぅん出(ディ)たる 是(クリ)どぅ 確かに 殿様舟(トゥヌサマフニ)で 思(ウム)い かめぶるけ 西表屋(イリムティヤ)ぬ なーむぬ ビラマぬ 菜種(ナーダニ)あーしおるそぅぬヤゥ6、あまぬ 妬(ニタ)さん 照(ティ)る 太陽(ティダ)ん 闇(ヤミ)なる だきヤゥ どぅけぬ 辛酸(シンサン) くばでーさ本(ムトゥ)ば かい抱ぎ ぶたんよば7、船浮村 千秋万歳(シンシュバンザイ) くばでーさぬ 下(スィタ)なかヤゥ 脛(シニ)ぬ 傷(ヤム)むんけ 膝(つぃぶすぃ)ぬ 傷痺(ヤムン)け 立ち 待ち ぶたんよば 訳意 世間に恋の氏神とまで言われた、祖納村の殿様こと「石垣高端」とまで、浮名を立てたのは自分である。 カマドマ美人の事を思って、自分は船浮に船で行くんだよ。 カマドマ恋女の思いは、殿様役人を抱き締めたさに、立っても座っても居られないヨ、イライラして、心が落ち着かず、立っても座っても居られないヨ。 船浮村の前に突き出ている岬から、殿様の舟らしいのが、目に飛び込んできたので、船浮村のカマドマ美人は、「泡盛」のお土産を飲めると、ノド舌打ちしているよ。 今度こそは、殿様舟だと思っていたら、松田家の加那爺が高間牧場へいらっしゃる舟だった。 尚又、舟が飛び込んできたので是こそはと思っていたら、西表家の「長座癖・長いおしゃべり好き」の「ビラマ」がおしゃべりに来る舟だった。 余りにも「嫉妬」で照りつける太陽も闇にしたいくらいだよ。 その時の「苦しみ」に耐えられないので、クバデサ木を殿様と思って、掻き抱いていたんだよ。 船浮村に古くから生えている、クバデサの木の木陰で、スネが傷むほど、踵・膝が、痛み痺れるほど、立ったり座ったりして、待っていたヨ。 すごい凄い。。ここまで想いを通し、待ち焦がれている様子が、リアルに表現されています。 悪役人の歌が多いなかでの、恋焦がれる歌。「殿様(トゥヌサマ)節」 西表島に自生する(クール)と言う木の根っこで染めた布。 西表はなんと言っても、希少動物「いりおもてやまねこ」 ちなみに、この付近の島猫(野良猫)「山猫」と呼びます。 方言では、「まやー」。犬は「イン」・・「イングァ」犬小です。
2004年10月25日
閲覧総数 1831
-
5

山羊(ヒージャー)のさばき方
大きな鍋を用意します。これでも四分の一サイズかな。1、大きめのタライに塩(マース)を一握り入れておく。2、山羊(ヒージャー)の左の頚動脈を切りタライに受けておく。3、バーナーで毛を焼きながら、青草で皮表面をこする。4、表皮が茶色くなるまで焼く。5、金タワシで表面をこすり焦げた毛を落とす。6、胃袋部の皮だけを浅く切り、指を入れて穴を開ける。7、内臓を傷つけないように、二本指を先ほどの穴に入れて、指で押し広げながら少しずつ身を切っていく。8、肛門周辺を丸く切り、腸を引き抜く。9、首を切り食道を引き抜く。10、腸は胃と切り離し、ハシを使いひっくり返す。11、ひっくり返した腸は多量の塩(マース)でもみ洗いし、流水で流す。12、食べない部位は、胃・食道・腎臓・脳。13、頭部は皮・肉・舌を切り離す。14、内臓・骨付き肉を小さく一口大に切り分ける。15、2、で固まった血はもみ潰し、細かく砕く。16、14、を鍋に入れて、水をひたひた迄入れる。17、薪で炊きながら、15、を入れる。18、6時間炊き続けて、薄く調味(マースのみ)。19、どんぶりによもぎ(フーチバー)を生で入れ、その上から18、を取り分ける。20、個々で好きな塩加減と、おろし生姜で頂く。沖縄では夏にヒージャーを食べると、冬風邪をひかないと言われています。ヒージャーは大切な滋養・タンパク源で、ヒージャーグスイ(山羊薬)として、貴重な食料です。全てを食べ尽くしてこそ、大切な命を無駄にしない。子供達に命の大切さや、尊さを教える機会となります。食べ残しや、食べ物を粗末にしない。棟上や結婚式、台風一過の後かたずけ、カジマヤー(98歳の歳祝い)行事事に薬(グスイ)として振舞われます。ウチナンチュウ(沖縄県人)でも、好きと嫌いの二者に分かれます。レトルトパックも出ています。
2004年08月13日
閲覧総数 2415
-
6

八重山民謡 基礎知識
八重山民謡 基礎知識八重山民謡の基本形は、作業歌と節歌に大別される。作業歌には「ユンタ」「ジラバ」「あよう」があります。これらの作業歌は、歌詞や曲の目立った差異はありませんが、「あよう」は祭式歌とされる事が多い。いずれも古くから、野良仕事や山から帰る馬上の男女・共同作業場に群れる男女が歌う、平和でのどかな八重山情緒溢れた情景が浮かびます。その後、ユンタやジラバに三線伴奏を合わせて歌われる様になり節歌ができた。例えば「鷲(バスィ)ユンタ」⇒「鷲ぬ鳥(バスィヌトゥルィ)節」(本調子)「あがろーざユンタ」⇒「あがろーざ節」(本調子)と変化し歌われている。また、首里王府へ出司した役人が琉球古典音楽の指導を受け帰郷後、八重山内の三線音楽が発展するにつれ優れた音楽家を輩出し数多くの名曲が作られた。 「越城(クイグシク)節」(本調子)「赤馬(アカンマ)節」(本調子)「くいぬぱな節」(本調子)など八重山民謡の音階は五音・3種の音階があります。そのうち俗にいう琉球音階ドミファ・ソシドの音階の曲は、「なかなん節」(本調子)「まつぃんがねーユンタ」(本調子)などがあたります。また、「仲良田(ナカラダ)節」(本調子)「たらくじ節」(本調子)なども同音階のミの音がレに変化した名曲です。陽音階の曲は有名な「鷲ぬ鳥節」(本調子)「とぅばらーま節」(二揚)「月ぬかいしゃー節」(二揚)などがあります。ソシド・レファソ、ソファレ・ドラソの音階は、八重山民謡で最も多く使用されています。この音階の「ファ音」は特殊音で、通常の「ファ音」より「1/4音低い音」が使われています。「ファ音」を正確に謡う事によって、八重山民謡の独自性が表現できます。八重山民謡には、3拍子の民謡曲が数多いことも特徴であり、これは世界的にも珍しいです。 新良幸人パーシャクラブ/PARSHA リリイ・シュシュのすべて/サウンドトラック 新良幸人パーシャクラブ/新良幸人PARSHA CLUBver.1.02 空の風景 山里勇吉/八重山育ち オムニバス/おきなわのうた
2005年05月12日
閲覧総数 868
-
7

インド打楽器 『タブラ』
インド打楽器『タブラ』 イスラム勢力がインド支配を始めた13世紀以降、宮廷で栄えた北インド古典音楽の楽器として誕生したと言われています。 右手でたたく小さい方を「タブラ」、左手でたたく大きい方を「バヤ」、二つ対になったものも『タブラ』と呼びます。 どちらも打面にはヤギのなめし革が使われているが、胴体の素材は全く異なります。「タブラ」は紫檀(シタン)やマンゴーなどの木をくりぬいたもので、3~4キロと重く、人さし指、中指、薬指や手のひらを使って高音を奏でます。「バヤ」の胴体は鉄・銅・アルミなどの金属製や素焼き壺で、手のひらの付け根を押し付けたり擦ったりして、不思議な余韻のある低音を生み出す。 打面の黒丸部分も特徴であり、「タブラ」は中央に「バヤ」はやや偏っています。マンガンとタマリンドの澱粉を練り合わせたものが塗りつけられ、これが打面の振動に影響して、変化に富んだ音を生みます。 20種類近くあると言われる音には、それぞれ「ナァ」「ディン」「キィタ」「ダァハ」「テテ」「トゥー」などと名前がついています。奏者は師匠の演奏を少しずつ模倣しながら、その名前の連続を歌のように覚えていきます。打法や打つ場所の違いでさまざまな音が出る為、世界で最も演奏が難しい打楽器とも言われています。右手指を酷使する楽器として、過酷な練習を要します。カーンという甲高い音。トン、テンという軽い音。シュルシュルという摩擦音。ドゥーンと響く低音。ビートルズのアルバムにも登場した打楽器タブラは、多彩な音色でジャズ、ロック、ポップスなどさまざまな音楽に自在に溶け込む事のできる、人の奏でるリズムマシーンですね。バンドなどのドラムユニットでの「ズンズンチャカズンズンチャ」などを、タブラでは「ダァハ ダァハ テ テ ダァハ ダァハ トゥー ナ」(kayada)と演奏します。 タブラ・バヤ(Tabla Bahya)/PLAY WOOD 【インド直輸入】インド音楽(タブラ)CDRhythm
2005年04月09日
閲覧総数 299
-
8

時期外れのエイサーですが・・・。京太郎(チョンダラー)の役割と由来について
「エイサー」とは、沖縄で旧盆に先祖の霊を迎え送るための踊りです。 大太鼓・締め太鼓・パーランクー・手踊り・三線などで構成され、地元の青年たちが家々を一軒一軒まわって、先祖を敬い、土地にマブイ〈魂や祈り〉をこめていくお盆の神事です。 チョンダラーの本来の役割とは、 観客を笑わせたり、盛り上げたりします。 一般的には、カチャーシーをすすめたり、 拍手をすすめたり、 飛び跳ねたり、 指笛を鳴らしたり、 時には客に酒をすすめたり注いだりする事もあります。 一方でエイサーのリーダー的な役割も担います。 曲の間や途中で、 エイサー隊の列を整えたり、 衣装を整えたり、 三線のリズムを調えます。 太鼓の指揮をとり、 曲と踊りのリズムを抑え、 三線のキュー(合図)もチョンダラーの役目です。(例えば、隊列を組み移動して、曲の間奏の繰り返しで列が揃うと、チョンダラーがエイサー隊にキューを出して、囃子〈フェーシ〉を出させ、三線にキューを出して唄が始まる。という具合です。) エイサー隊員の汗を拭き、 水を飲ませ、 クバ扇で風を送り、 折れたバチの交換等、 常にエイサー隊をサポートします。 チョンダラーは、エイサーの流れを熟知しているという事が第一条件です。チョンダラーの名の由来は、 この呼び方はいろいろで、京太郎と書いてチョンダラーと読みます。 他にも狂言ぁ〈チョギナー〉〈チョウギン〉、 間る者〈マルムン〉〈マヌムン〉、 中分かち〈ナカワチ〉、サナジャー、 三良〈サンラー〉、三良小〈サンダーグァー〉などと呼ばれ「チョンダラー」と言う呼び名以外では「サンダーグァー」がよく使われている様です。 京太郎と書くことから、京都と関係があります。 京都の念仏踊り〈ニンブチャー〉として沖縄に伝わり、 沖縄に定着したと言う事です。 旧盆にエイサー隊が太鼓で先祖の霊を送り帰す習慣が定着する頃に、チョンダラーが献酒を霊の代わりに飲んで回る事が、樽を担いだチョンダラーや腰に着けた酒瓶で表現されています。 また、薩摩藩のスパイだという説もあります。 チョンダラーに似た格好のお祭が福岡県や兵庫県、千葉県など、全国各地に広がっていったという説もあります。 被差別民であり、宗教の一派だったという説もあります。 戦で亡くなった方々を埋葬(運び屋)をしながら日々の糧を、あるいは坊さんのように死者の供養をして生活していたそうです。 それが、エイサーの「道巡願い」〈道ジュネー〉(一軒一軒を練り歩く)につながったとされています。 又、海外では朝鮮半島に同じような役割をする一派が存在します。
2005年01月26日
閲覧総数 6845
-
9

八重山古典民謡 「しゅうら節」(本調子)
「しゅうら」「シュウラ」とは、沖縄本島言葉「美(チュ)らしゃ」「ちゅらさん」と同じ。 略語で「可愛らしい」 この歌では、「可愛らしい嫁」をさす。 「かいしゃ」とは、八重山方言「美しゃ(うつくしい)」 「しゅうら節」(本調子)1、なをしゃる子(ファ)ぬどぅ 如何(イキァ)しゃる子(ファ)ぬどぅ 我(バ)嫁(ユミ)なりくーでぃね エイシュラジャンナヤゥ 〔どんな可愛い子が、如何に器量の良い子が、私の嫁になってくれるだろう〕2、島々(スィマズィマ)ぬ 村々(ムラムラ)ぬ かいしゃ あすからよ エイシュラジャンナヤゥ 〔島々の各村々の選び抜きの美しさ、器量の勝れる可愛い娘から〕3、かいしゃ あすから 白(シル)さ あすから なりくーで だらよ エイシュラジャンナヤゥ 〔美人の娘から、色白の器量勝れた可愛い娘から〕4、かいしゃ あだでん 白(シル)さ あだでん 縁(イン)どぅ 肌 添(ス)ゆる エイシュラジャンナヤゥ 〔美人であっても、どんなに色白でも、縁があってこそ、肌に触れる事ができる〕5、かいしゃぬ かまりゆみ 白(シル)さぬ 呑(ノ)まりゆみ 肝(クィム)どぅ 肝(クィム)やゆる エイシュラジャンナヤゥ 〔美人が食えるものでもない、どんなに色白でも飲めるものでもない、お互いの心と心、真心が肝心である〕6、かなさる子(ファ)や 野(ヌ)ぱんぬ 枝(ユダ)し ぴくぃすんぐり 見やむなよ エイシュラジャンナヤゥ 〔可愛い子ほど(野ぱん・川原人参)の枝で、鞭打って教訓する方が良い〕7、きなさる子(ファ)や バラぬ すぃずぃし ぴくぃすんぐり 見やむなよ エイシュラジャンナヤゥ 〔憎い子ほど、バラの芯繊維の柔らかなもので、鞭打って躾けた方が良い〕 「赤馬節」の(ちらし)として使う場合、曲調は同じで歌詞を変える。 1、今日(キユ)ぬ日(フィ)ば 黄金(クガニ)日(フィ)ば 本(ムトゥ)ばし ヤゥ エイ シュラ ジャ ンナヤゥ 〔今日の吉き日を、黄金の様な日を基礎として〕 2、夜(ユ)ぬ七日(ナンカ) 昼(フィ)ぬ百日(ムムカ) 祝(ユワ)いす ヤゥ エイ シュラ ジャ ンナヤゥ 〔夜の七日間お祝いし、昼の数日間も続けて祝賀する〕 「ニフェーデービル」は、沖縄本島方言の「ありがとうございます」の意。 あと一日で本年最終日。ありがとうございます。
2004年12月30日
閲覧総数 1120
-
10

沖縄の魚の方言名と和名
沖縄の魚 方言名 和名アーラミーバイ/まはた アカアーガイ/ぶだい アーガイ/ひぶだい アカイユ/すえつきえびす アカグチャ/ぶだい アカジン/にせすじはた アカジキラナー/きへりもんから アカシチュー/ふえだい アカナー/はらふえだい アカバター/たまめいち アカバニーカマサー/おおめかます アカヌチャ/しまちびき アカマチ/はまだい アカユー/ほしえびす アカレー/きつねべら アマクチン/にじはた アマミー/きあまだい アマイユ/くろさぎ アヤガーラ/かいわり アヤガチュー/かつお アンダーカーサー/つばめうお アカジューグルクン/うめいろもどき アカミーバイ/ゆかたはた アチヌイユ/かじき イーキブヤー/きかめきんとき イサジューマ/きつねうお イシミーバイ/かんもんはた イラブチャー/ぶだい イジュキン/ももいとより イナクビタロー/たてふえだい イナフク/ふえだい イナフク/まだらたるみ イヌバー/いとひきふえだい イノーサーラ/よこしまさわら イノーマクブ/くさびべら イノームルー/いとふえふき イングヮンダルミ/あらぶそこむつ インチョウシルイユー/ぎんだい ウージ/うつぼ ウーアカジンバー/りゅうきゅうあかひめじ ウキシジャー/てんじくだつ ウキムルー/かんぱち ウジュル/ほしぎす ウフミージューマー/いとたまがしら ウルアカマー/うろこまつかさ エーグァー/あいご エチオピア/しまかつお オーナシミーバイ/ほおきはた オーバーチャー/なんようぶだい オーマチ/あおちびき オームルー/ほおあかくちび オオシマナガイユ/くさやむろ オモナガー/きつねふえふきガクガク/ほしみぞいさき カチュー/かつお ガチュン/めあじ カーエー/ごまあいご カースビー/ごまふえだい ガーラ/ひらあじ カタカシ/ひめじ カマサー/かます ガラサーミーバイ/いしがきだい クサバー/ごいしべら クサバー/きぬべら クサラー/にじようさば クジラフッタイ/ぶだい クチグヮーミーバイ/さらだはた クチナジ/いそふえふき クチヌイユ/こち クムイクチナジ/はまふえふき クルキンマチ/ひめだい グルクマー/ぐるくま グルクン/たかさご クルシチュー/くろめじな クルバニーアカジン/すじはた クルビンクスク/くろもんつき クレー/こしょうだい クワガナー/ことひき コージャヒラー/はなたかさごサンスナー/うすばはぎ サンバナー/せんねんだい サーラ/さわら シーヌクワー/うめいろ スブター/そうだかつお ジキランカーハジャー/いそもんがら シジャー/だつ シチュー/めじな シチューマチ/あおだい シチューグルクン/ゆめうめいろ シッジューマススイ/てんぐはぎ シバチャーシチュー/くろしょうだい ジューグワークレー/くろだい ジュサカーヒーチー/ほうせききんとき ジュシルーミーバイ/おもんはた ジューマー/たまがしら ジュリグヮークスク/なんようはぎ ショウカー/つまてんぐ シルイユー/だい シルイチャー/あおりいか シルタマン/しもふりふえふき スーミツガーラー/ごばんあじ スビナクー/おきふえだい スナフウヤー/おきえそ センスルー/そうしはぎ ソージ/よろいあじ ダイカマサー/おおかます タイクチャーマチ/あおぐちいしちびき タカバーミーバイ/つちぼぜり タコクェーミーバイ/なみはた タチヌイユ/たちうお タマン/はまふえふき ダルマー/よこしまくろだい チチルカマサー/おにかます チバー/へだい チムグチャー/むねあかくちび チョウチンマチ/ちびき チールアチ/まかじき チン/みなみくろだい チンシラー/きじぬ チンスアカジン/すじはた チンバニー/きはだまぐろ チヌマン/てんぐはぎ トカキン/いそまぐろ トカジャー/かんからはぎ トカジャー/くろはぎ トルバイー/なかのはだい ナガアカバター/ながめいち ナガジューミーバイ/ばらはた ナカビーキャ/いちもんじぶだい ナンドウラー/しちせんべら ナンバナー/ふえだいハイイユ/さより ハマシジ/だつ ババシチュウ/みなみいすずみ ハラランジャー/たいわんだつ バレン/ばしょうがじき ハンゴーミーバイ/あかはたマーアカジン/にせすじはた マーシジャー/おきざより マンビカー/しいら マーマチ/おおひめ マクブ/しろくらべら マクブクサバー/てんす マット/いすずみ ミジュン/やまとみずん ミータンゴーガツン/めあじ ミーバイ/やいとはた ミーバイクレー/ちょうちょうこしょうだい ミミジャー/ひめふえだい ミンタナーアカレー/あかまつかき ミンチャーガツン/ほそひらあじムチヌイユ/のこぎりたい ムルー/ほおあかくちび ヤーミーバイ/しろぶちはた ヤキ/あまみふえふき ヤキータマン/あまくちび ヤナクレー/むすじこしょうだい ヤナトナガイユー/つむぶり ヤマトビー/にせくろほしふえだい ユダヤーガーラ/ひいらぎ ユダヤーミーバイ/まだらはた ヨナバルマジク/たいわんだい ンジャーアチ/くろかじき
2005年07月30日
閲覧総数 1920
-
11

沖縄民謡の定番 「十九の春」は鎮魂歌だった
「十九の春」は、「昭和五十年頃」歌手・田端義夫が歌って大ヒットしました。 が、作曲者が不明のままだった。 この歌のルーツは、第二次大戦中に奄美大島沖で米軍の魚雷攻撃を受けて沈没した貨客船の鎮魂歌「嘉義(かぎ)丸の歌」だったことが判明。 大勢の犠牲者の霊を慰めようと、島唄者「朝崎辰恕(たつじょう)」が、生存者から体験を聞き取り作詞作曲した。 しかし、戦時下で「戦意喪失の恐れあり」と軍当局から歌うことを禁じられ曲調だけが残り、別の歌詞が付けられて歌い継がれた。 元歌は、米軍に沈められた貨客船「嘉義丸の歌」。太平洋戦争中の昭和十八年五月二十六日、大阪から沖縄へ向かう「嘉義丸」が魚雷攻撃で沈没、船体はたった八分で海底に姿を消し、約三百人の犠牲者が出た。 当時、奄美・加計呂麻島民で船の生存者の治療に当たった鍼灸師で三線(さんしん)の名手だった「朝崎辰恕」が、その嘆きに心を痛め犠牲者を慰めようと、生存者らから聞いた体験談をもとに作詞・作曲。同年六月十八日に島の集会所で発表した。 「朝崎辰恕」は戦前、大阪でバイオリンを習ったことから、「嘉義丸の歌」をバイオリンを使い五線譜で作曲した。だが、当時は洋楽器を愛用することは非国民と受け取られかねない雰囲気で、三線を伴奏に歌っていた。 「朝崎辰恕」は歌う前に、その都度黙祷をしていた。 歌は奄美で一時期流行ったが、「歌詞が戦局の不利を伝えるもの」として軍当局から歌うことを禁止され、なおかつ戦後、米国への配慮から禁じられて、次第に忘れ去られていった。 当時、多くの奄美島民が沖縄に働きに行ったことから、歌詞抜きの曲だけが“一人歩き”したのだと思う。三線によく合うし、替え歌が好きな沖縄の人たちに広まったのではないだろうか。 「嘉義丸の歌」 歌詞(抜粋) 「十九の春」の曲調で読んでみてください。1、散りゆく花はまた咲くに ときと時節が来るならば 死に逝く人は帰り来ず 浮き世のうちが花なのよ 2、戦さ戦さの明け暮れに 戦火逃れてふるさとへ 帰りを急ぐ親子連れ 嘉義丸頼りに船の旅 三、ああ憎らしや憎らしや 敵の戦艦魚雷艇 撃ち出す魚雷の一弾が 嘉義丸船尾に突き当たる 6、親は子を呼び子は親を 船内くまなく騒ぎ出す 救命胴衣を着る間なく 浸水深く沈みゆく 9、波間に響く声と声 共に励まし呼び合えど 助けの船の遅くして 消えゆく命のはかなさよ 「嘉義丸」は、「1907年」に完成した2508トンの貨客船。 大阪から疎開者ら400人余が乗船、奄美・沖縄に向け航行中、「1943年5月26日」護衛艦二隻が引き返して間もなく、名瀬沖東経129度32分・北緯28度5分の海上で、米艦の魚雷を受け船首を真上に垂直に8分で沈没。 救助された人は100人、乗船していた軍人約30人の戦死の記載が残されたのみで、軍が沈没の公表を封じて犠牲者の名簿はない。 このアルバムには「朝崎辰恕」の娘さんが「十九の春」(田端バージョン)を歌っています。
2005年01月24日
閲覧総数 5762
-
12

昔防寒具 「丹前」と「ドテラ」と「カイマキ」
寒さが続いていますね。温泉地や旅館(特に寒い地方)では丹前(たんぜん)を浴衣以外に備えていますね。「丹前(たんぜん)」承応・明暦(1652年~1657年)頃江戸神田四軒町雉子町の続は、松平丹後守(まつだいらたんごのかみ)屋敷があった。この屋敷の前に町風呂があり、湯女を置く一種の遊所として大繁昌していた。丹後守殿の前にあったことから、この風呂屋を「丹前風呂」と呼ばれ、そこへ通う遊客の伊達な風俗を丹前風と称していた。襟・袖口・フキに綿を沢山入れた一種闊達な仕立て方が、風呂上りの湯冷めを防ぎ、伊達な遊び着として扱われたのが始まりです。当時、丹前と同じ構造をした着物があったわけでもなく、後に「丹前」と呼ばれるようなドテラ風の小袖を丹前と俗称したのが起源とされています。当時一般的には、寒さ対策として、小袖の上に小袖を重ね着た着こなしであり、打ち掛け風に小袖を羽織る事が主流でした。その後、縞紬や縞木綿に染形も稀にある新しい形の着物が流行りだした。仕立て方は、綿入れ小袖に準じて広袖に作る。男物は、黒八丈。女物は、黒ビロードの掛襟をするのが一般的。「丹前」と「江戸ドテラ」の違い「丹前」は、蒲団と同様に数ヵ所を綴じ糸で綴じている。「江戸ドテラ」は、けっして綴じる事はない。綴糸があり、やや大形に製したモノを「カイマキ(掻巻)」と称して夜具に用いた。伝法な人達は、カイマキを外出着や部屋着に用いた。娼家の主人、博徒といった遊民、あるいは娼妓などは自家で常に着ていたようです。 本場久留米綿入長丹前 絵かすり丹前 おくるみ丹前 スーパートルマリンエナジーどてら送料無料、代金引換手数料無料保温・通気性にも優れたリラッ... ナカノヒロミチの家紋男物はんてん(男専科) 婦人用 あったか~い中わた入り半天 送料無料! シルクの感触がたまらなく気持ちいい!【東京西川】真綿かいまきふとん ポーランド産ホワイトグースダウン93%羽毛かいまき布団(綿衿カバー付) キャメル100%毛布かいまき
2006年01月03日
閲覧総数 4483
-
13

沖縄民謡 「川平(カブィラ)節」八重山古典民謡 「かんつぃ節」(本調子)
沖縄本島で流行している「川平節」は、そもそも八重山の「かんつぃ節」の歌詞だけを改作して歌われている。 石垣市川平村に居た、兄「大浜善得」と弟「平田善元」の兄弟が協同で「かんつぃ節」を(1721年)作。 兄「大浜善得」は、諸役人を経て総横目職から座敷職に昇進した出世頭(79歳で他界) 弟「平田善元」二十歳、兄「大浜善得」三十九歳の作 屋号・大名家(ダイミョウヤー)「カンツィ美人」 屋号・後浜家(シハマヤー) 「ナベマ美人」 この二人の美人に会う為に、川平村まで20kmの山道・悪路をひたすら歩き続け、二人の美女に憧れて通い続ける。 「川平節・かんつぃ節」1、世間(シキン)沙汰(サタ)しゆる 大名家(ダイミョウヤー)ぬ かんつぃ いつぃぬ 夜(ユ)ぬ 露(チユ)に 咲かち すゆが スリ 〔世間に取り沙汰されている、大名家のカンツィ美人を、何時の夜の露で、咲かせてみようか〕2、時(トゥクィ)ゆ 待ち みしょり 節(スィツィ)ゆ 待ち みしょり つぃぶでぃ 居(ウ)る 花ぬ 咲かな うちゅみ スリ 〔時期を待って下さい、機会を待って下さい、青春の蕾の花は、咲かずにおれようか〕3、時(トゥクィ)待つぃんで 居(ヲ)るけ 節(スィツィ)待つぃんで 居(ヲ)るけ 人(プィトゥ) 為(ダミ)に ならば 我(ワ)んや ちゃすが スリ 〔時期を待っている内に、機会を待っている内に、他所者と恋愛してしまったら、自分はどうなるのか〕4、人(プィトゥ) 為(ダミ)ん なさぬ ゆす為(ダミ)ん なさぬ 島(スィマ)ぬ ある までぃん かんどぅ やゆる スリ 〔貴方以外の人に恋はしません、他所者に なびく様な もろい女性ではありません、この島がある限り、二人は偕老同穴の契りであります〕5、又ん 沙汰しゆる 後浜家(シハマヤー)ぬ なべーま たんでぃ とーどぅ みやらび 語(カタ)られ ひりゃな スリ 〔又も 世間の評判になっている、後浜家のナベーマよ、どうかお願いです、私の恋人になって下さい〕6、語られ ざーぎ ひーるか ゆばりてぃ ざーぎ ひーるか 金(キン)ぬ 屏風ん うやすでぃ 確かに うやすんどー スリ 〔私の恋人になってくれるなら、水も漏らさぬ仲となってくれるなら、黄金の屏風を記念として、確かに差し上げましょう〕7、すぃかし でん あらぬ ゆくし でん あらぬ 新城(アラスク)びらまん 阿波連(アフワリ)びらまん 知っちょんどー スリ 〔嘘を吐(つ)く 口実でもない、だます手段の言葉でもない、新城ビラマも、阿波連ビラマも良い証人です〕8、生(マ)りる 甲斐 かんつぃ 産(スィ)でぃる 甲斐 なべーま 沖縄(ウクィナ)までぃ とぅゆまれ いけい すっつぁいら スリ 〔生まれる甲斐があったカンツィ、産まれでる甲斐があったナベーマ、沖縄本島までも評判になって、羨ましいことである〕9、歌(ウタ)聞(スィ)きば かんつぃ 声(クィ)聞(スィ)きば なべーま やますぃめーぬ びい びい 余韻(ユイン) 勝(マサ)る スリ 〔カンツィもナベーマも歌が上手で、声を聞くと素晴らしい美声である、二人とも、山で鳴く蜩(ひぐらし)よりも勝っている〕10、歌ぬ 出(ン)でぃ 口(グチ)や 新城(アラスク)びらまどぅ やしが 亦(マタ)ん 出(ン)でぃ 口(グチ)や 阿波連(アファリ)びらま スリ 〔新城ビラマ、阿波連ビラマの両人は、歌の名人で音楽家でもある、二人とも優劣つけ難い〕11、大名家(ダイミョウヤー)ぬ かんつぃ 島(スィマ)ぬ 夫(ブドゥ) 持(ム)つぃか うふん 井戸(ガー)ぬ 水(ミズィ)や 甘水(アマミズィ)なるはずぃどー スリ 〔評判高い、大名家のカンツィが、万が一にも島の百姓を夫に持つ様な事が有れば、海水混じりのウフン井戸の水も、淡水に変わるであろう〕12、後浜家(シハマヤー)ぬ なべーま ふんぬ夫(ブドゥ)持(ム)つぃか うなや井戸(ガー)ぬ 水(ミズィ)や 詰酒(ツィミザキ)なるはずぃどー スリ 〔取り沙汰されている、後浜家のナベーマが、万が一にも島の百姓を夫に持つ様な事が有れば、淡水のウナヤ井戸の水が、詰酒に変わるであろう〕13、たんでぃ とーどぅ なべーま があら とーどぅ かんつぃ 夜(ユル)ぬ片時(カタトゥクィ)や 遊(アサ)ばれ 給(タボ)り スリ 〔どうかお願いします、ナベーマ美女よ、命掛けてのお願いです、カンツィ美女よ、20キロの険道の道程を歩いてきた私達二人に、同情して夜の僅かな時間でも会って下さい、慰安して下さらないか、二人の恋人よ〕 青春ですね。 内地の平安時代、歌を読み、お目当ての美女に面会を願う様に、歯の浮く台詞も、歌で聞かせる。 「はずぃどー」は、沖縄口(うちなーぐち)の「~はず」と同じで、標準語の「はず」とはニュアンスが少々異なり難解。 「~について責任は持てないけど、私はそう思う」の感じ。「それ食べてもいいはず」は、「責任持てないけど・・・」が付く。 「偕老同穴」とは、夫婦仲睦じく、生きてはともに老い、死しては穴を同じゅうして、葬られようと誓いあう。を言う。 島の井戸(ガー)は、掘る場所により、海水・汽水・淡水の水が出る。 海水井戸は、主に洗い物(洗濯等)に使う。 汽水井戸は、農業用水 淡水井戸のみ、飲料水 この本は、三線譜面と五線譜で構成してあり、ギターやピアノで弾く事が出来る様になっています。 とても見やすいですが、フルコーラスには難点があります。 三線とピアノのセッションやギターセッションで、沖縄民謡をするには最適です。 三線初心者で、工工四譜面(三線専用譜面)のメロディーラインが解からなくなった時に見るのも一考かと思います。
2004年12月10日
閲覧総数 771