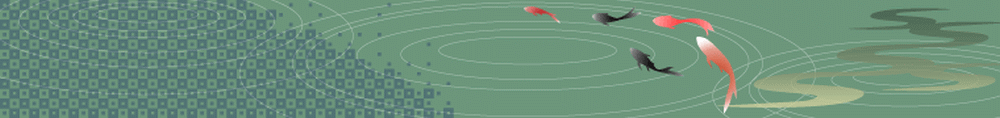PR
X
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 沖縄民謡について(105)
カテゴリ: 沖縄関係
「十九の春」は、「昭和五十年頃」歌手・田端義夫が歌って大ヒットしました。
この歌のルーツは、第二次大戦中に奄美大島沖で米軍の魚雷攻撃を受けて沈没した貨客船の鎮魂歌「嘉義(かぎ)丸の歌」だったことが判明。
大勢の犠牲者の霊を慰めようと、島唄者「朝崎辰恕(たつじょう)」が、生存者から体験を聞き取り作詞作曲した。
しかし、戦時下で「戦意喪失の恐れあり」と軍当局から歌うことを禁じられ曲調だけが残り、別の歌詞が付けられて歌い継がれた。
元歌は、米軍に沈められた貨客船「嘉義丸の歌」。
太平洋戦争中の昭和十八年五月二十六日、大阪から沖縄へ向かう「嘉義丸」が魚雷攻撃で沈没、船体はたった八分で海底に姿を消し、約三百人の犠牲者が出た。
当時、奄美・加計呂麻島民で船の生存者の治療に当たった鍼灸師で三線(さんしん)の名手だった「朝崎辰恕」が、その嘆きに心を痛め犠牲者を慰めようと、生存者らから聞いた体験談をもとに作詞・作曲。同年六月十八日に島の集会所で発表した。
「朝崎辰恕」は戦前、大阪でバイオリンを習ったことから、「嘉義丸の歌」をバイオリンを使い五線譜で作曲した。だが、当時は洋楽器を愛用することは非国民と受け取られかねない雰囲気で、三線を伴奏に歌っていた。
歌は奄美で一時期流行ったが、「歌詞が戦局の不利を伝えるもの」として軍当局から歌うことを禁止され、なおかつ戦後、米国への配慮から禁じられて、次第に忘れ去られていった。
当時、多くの奄美島民が沖縄に働きに行ったことから、歌詞抜きの曲だけが“一人歩き”したのだと思う。三線によく合うし、替え歌が好きな沖縄の人たちに広まったのではないだろうか。
「嘉義丸の歌」 歌詞(抜粋)
「十九の春」の曲調で読んでみてください。
1、散りゆく花はまた咲くに
ときと時節が来るならば
死に逝く人は帰り来ず
浮き世のうちが花なのよ
2、戦さ戦さの明け暮れに
戦火逃れてふるさとへ
帰りを急ぐ親子連れ
三、ああ憎らしや憎らしや
敵の戦艦魚雷艇
撃ち出す魚雷の一弾が
嘉義丸船尾に突き当たる
6、親は子を呼び子は親を
救命胴衣を着る間なく
浸水深く沈みゆく
9、波間に響く声と声
共に励まし呼び合えど
助けの船の遅くして
消えゆく命のはかなさよ
「嘉義丸」は、「1907年」に完成した2508トンの貨客船。 大阪から疎開者ら400人余が乗船、奄美・沖縄に向け航行中、「1943年5月26日」護衛艦二隻が引き返して間もなく、名瀬沖東経129度32分・北緯28度5分の海上で、米艦の魚雷を受け船首を真上に垂直に8分で沈没。
救助された人は100人、乗船していた軍人約30人の戦死の記載が残されたのみで、軍が沈没の公表を封じて犠牲者の名簿はない。

このアルバムには「朝崎辰恕」の娘さんが「十九の春」(田端バージョン)を歌っています。

この歌のルーツは、第二次大戦中に奄美大島沖で米軍の魚雷攻撃を受けて沈没した貨客船の鎮魂歌「嘉義(かぎ)丸の歌」だったことが判明。
大勢の犠牲者の霊を慰めようと、島唄者「朝崎辰恕(たつじょう)」が、生存者から体験を聞き取り作詞作曲した。
しかし、戦時下で「戦意喪失の恐れあり」と軍当局から歌うことを禁じられ曲調だけが残り、別の歌詞が付けられて歌い継がれた。
元歌は、米軍に沈められた貨客船「嘉義丸の歌」。
太平洋戦争中の昭和十八年五月二十六日、大阪から沖縄へ向かう「嘉義丸」が魚雷攻撃で沈没、船体はたった八分で海底に姿を消し、約三百人の犠牲者が出た。
当時、奄美・加計呂麻島民で船の生存者の治療に当たった鍼灸師で三線(さんしん)の名手だった「朝崎辰恕」が、その嘆きに心を痛め犠牲者を慰めようと、生存者らから聞いた体験談をもとに作詞・作曲。同年六月十八日に島の集会所で発表した。
「朝崎辰恕」は戦前、大阪でバイオリンを習ったことから、「嘉義丸の歌」をバイオリンを使い五線譜で作曲した。だが、当時は洋楽器を愛用することは非国民と受け取られかねない雰囲気で、三線を伴奏に歌っていた。
歌は奄美で一時期流行ったが、「歌詞が戦局の不利を伝えるもの」として軍当局から歌うことを禁止され、なおかつ戦後、米国への配慮から禁じられて、次第に忘れ去られていった。
当時、多くの奄美島民が沖縄に働きに行ったことから、歌詞抜きの曲だけが“一人歩き”したのだと思う。三線によく合うし、替え歌が好きな沖縄の人たちに広まったのではないだろうか。
「嘉義丸の歌」 歌詞(抜粋)
「十九の春」の曲調で読んでみてください。
1、散りゆく花はまた咲くに
ときと時節が来るならば
死に逝く人は帰り来ず
浮き世のうちが花なのよ
2、戦さ戦さの明け暮れに
戦火逃れてふるさとへ
帰りを急ぐ親子連れ
三、ああ憎らしや憎らしや
敵の戦艦魚雷艇
撃ち出す魚雷の一弾が
嘉義丸船尾に突き当たる
6、親は子を呼び子は親を
救命胴衣を着る間なく
浸水深く沈みゆく
9、波間に響く声と声
共に励まし呼び合えど
助けの船の遅くして
消えゆく命のはかなさよ
「嘉義丸」は、「1907年」に完成した2508トンの貨客船。 大阪から疎開者ら400人余が乗船、奄美・沖縄に向け航行中、「1943年5月26日」護衛艦二隻が引き返して間もなく、名瀬沖東経129度32分・北緯28度5分の海上で、米艦の魚雷を受け船首を真上に垂直に8分で沈没。
救助された人は100人、乗船していた軍人約30人の戦死の記載が残されたのみで、軍が沈没の公表を封じて犠牲者の名簿はない。

このアルバムには「朝崎辰恕」の娘さんが「十九の春」(田端バージョン)を歌っています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[沖縄関係] カテゴリの最新記事
-
新築記念に唄われる歌 2009年03月30日 コメント(4)
-
懐かしき故郷(沖縄民謡) 2008年06月22日
-
かいされー(沖縄民謡) ジントヨー 2008年06月15日 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.