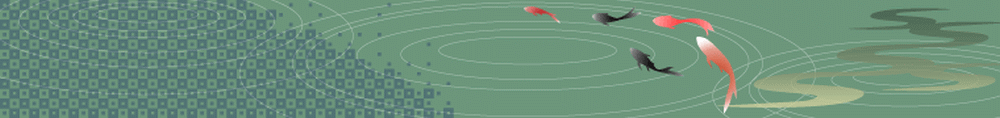PR
X
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 沖縄民謡について(105)
カテゴリ: 沖縄関係
「三線(サンシン)」の由来
中国の唐の時代、三線〈サンシェン〉が琉球国に伝わり、三線〈サンシン〉となった。その後、戦国時代に大和国に伝わり三味線〈シャミセン〉となった。
琉球国の書物の中に、西暦1372年琉球王国から明への招諭(朝貢とも言い、大陸への献上参り)が始まり、その後西暦1500年前後に琉球王国に伝わり、琉歌の伴奏楽器として発展しました。
大和国への三線流入については、「糸竹初心集」(1664年中村宗三著)の中に『永禄年間(1558年~1569年)に「石村検校〈けんぎょう〉」(当時、目の不自由な方に役職を与え、収入を得る制度が有り、その役職の最高幹部の役名)なる琵琶法師に、琉球からの献上品である三線〈サンシン〉を弾くよう、朝廷より命ぜられ京都で改良し、弟子の「虎澤検校」に譲られ、虎澤は「山野井検校」に伝授して広まりました。
「御湯殿上日記」記載の天正8年(1580年)の条文に
『河原の者 山しろといふ しやみせん ひかせらるる』
の記述があります。
河原の者とは、定居を持たず文字どうり川原で仮居を建て、雑芸能〈ぞうげいのう〉や、女性は身を売りながら生計をたてている人達の事。
「蛇皮線」とは、
『蛇皮線を伴奏に、高三隆達が隆達節〈りゅうたつぶし〉を始めた。』の記述がありました。
沖縄の「蛇」と言うと、多くの大和人は「ハブ」を連想しますが、三線〈サンシン〉の皮は「ニシキヘビ」であり、ハブではありません。
三線〈サンシン〉が大和国に渡った時代、ニシキヘビの皮は渡来品であり非常に高価で、大和国では簡単に手に入る代物ではなかった。
がしかし、三線〈サンシン〉の音色に魅せられた「河原者」(貧しい階級の大道芸人)は、身近な(何処にでも居る)「猫」皮を代用しました。
後の、改良により携帯に便利な二分割式や、サオを丈夫にする為に太くし、犬皮を用いた物も作られました。
もし、「三線」が〈ジャミセン〉なら「三味線」は〈ネコガワセン〉と呼びますか?
つい最近まで、一部の大和人は沖縄をべっ視する傾向があり、その象徴として「三線」を〈ジャミセン〉と言い、「河原者」同様 沖縄文化は大和文化の下にある様なニュアンスがありますので、沖縄のオジーオバーの前では言わない方がいいかも。
琉球国での「三線の文化的位置付け」
琉球国では、仕官制度(現在の国家公務員)に琴・三線に秀でた人たちを基準として採用試験が行われていました。
それは、大陸文化の窓口として中国や朝鮮との交易の「歓迎レセプション」として琴・三線を披露しました。
現代に置き換えると、数カ国の言語をマスターし、パソコンを使いこなし、最新技術を持って海外訪問するスーパー外交官のようなもの。
上記には、歴史上の記述が多く 琉球王国・大和国と表現しましたが、現代では精神的にもすべてを含んで、日本国です。
御笑止下さいませ。

ダイ那覇さん大丈夫?
中国の唐の時代、三線〈サンシェン〉が琉球国に伝わり、三線〈サンシン〉となった。その後、戦国時代に大和国に伝わり三味線〈シャミセン〉となった。
琉球国の書物の中に、西暦1372年琉球王国から明への招諭(朝貢とも言い、大陸への献上参り)が始まり、その後西暦1500年前後に琉球王国に伝わり、琉歌の伴奏楽器として発展しました。
大和国への三線流入については、「糸竹初心集」(1664年中村宗三著)の中に『永禄年間(1558年~1569年)に「石村検校〈けんぎょう〉」(当時、目の不自由な方に役職を与え、収入を得る制度が有り、その役職の最高幹部の役名)なる琵琶法師に、琉球からの献上品である三線〈サンシン〉を弾くよう、朝廷より命ぜられ京都で改良し、弟子の「虎澤検校」に譲られ、虎澤は「山野井検校」に伝授して広まりました。
「御湯殿上日記」記載の天正8年(1580年)の条文に
『河原の者 山しろといふ しやみせん ひかせらるる』
の記述があります。
河原の者とは、定居を持たず文字どうり川原で仮居を建て、雑芸能〈ぞうげいのう〉や、女性は身を売りながら生計をたてている人達の事。
「蛇皮線」とは、
『蛇皮線を伴奏に、高三隆達が隆達節〈りゅうたつぶし〉を始めた。』の記述がありました。
沖縄の「蛇」と言うと、多くの大和人は「ハブ」を連想しますが、三線〈サンシン〉の皮は「ニシキヘビ」であり、ハブではありません。
三線〈サンシン〉が大和国に渡った時代、ニシキヘビの皮は渡来品であり非常に高価で、大和国では簡単に手に入る代物ではなかった。
がしかし、三線〈サンシン〉の音色に魅せられた「河原者」(貧しい階級の大道芸人)は、身近な(何処にでも居る)「猫」皮を代用しました。
後の、改良により携帯に便利な二分割式や、サオを丈夫にする為に太くし、犬皮を用いた物も作られました。
もし、「三線」が〈ジャミセン〉なら「三味線」は〈ネコガワセン〉と呼びますか?
つい最近まで、一部の大和人は沖縄をべっ視する傾向があり、その象徴として「三線」を〈ジャミセン〉と言い、「河原者」同様 沖縄文化は大和文化の下にある様なニュアンスがありますので、沖縄のオジーオバーの前では言わない方がいいかも。
琉球国での「三線の文化的位置付け」
琉球国では、仕官制度(現在の国家公務員)に琴・三線に秀でた人たちを基準として採用試験が行われていました。
それは、大陸文化の窓口として中国や朝鮮との交易の「歓迎レセプション」として琴・三線を披露しました。
現代に置き換えると、数カ国の言語をマスターし、パソコンを使いこなし、最新技術を持って海外訪問するスーパー外交官のようなもの。
上記には、歴史上の記述が多く 琉球王国・大和国と表現しましたが、現代では精神的にもすべてを含んで、日本国です。
御笑止下さいませ。

ダイ那覇さん大丈夫?
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[沖縄関係] カテゴリの最新記事
-
新築記念に唄われる歌 2009年03月30日 コメント(4)
-
懐かしき故郷(沖縄民謡) 2008年06月22日
-
かいされー(沖縄民謡) ジントヨー 2008年06月15日 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.