PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(2)読書案内「日本語・教育」
(22)週刊マンガ便「コミック」
(79)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(74)演劇・芸能「劇場」でお昼寝
(5)映画「元町映画館」でお昼寝
(130)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(119)読書案内「映画館で出会った本」
(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(29)読書案内「現代の作家」
(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(33)読書案内「近・現代詩歌」
(56)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(13)映画「パルシネマ」でお昼寝
(32)読書案内「昭和の文学」
(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(23)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(39)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(22)ベランダだより
(167)徘徊日記 団地界隈
(137)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(27)徘徊日記 須磨区あたり
(34)徘徊日記 西区・北区あたり
(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」
(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」
(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東
(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(25)映画 香港・中国・台湾の監督
(40)アニメ映画
(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(41)映画 イタリアの監督
(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(29)映画 ソビエト・ロシアの監督
(14)映画 アメリカの監督
(99)震災をめぐって 本・映画
(9)読書案内「旅行・冒険」
(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(14)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(5)映画 フランスの監督
(52)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(13)映画 カナダの監督
(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督
(9)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督
(12)映画 ギリシアの監督
(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督
(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督
(5)映画 アフリカの監督
(3)映画 スイス・オーストリアの監督
(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ
(7)週刊マンガ便「小林まこと」
(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」
(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督
(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介
(19)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」
(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」
(5)徘徊日記 神戸の狛犬
(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」
(11)読書案内・映画 沖縄
(10)読書案内 韓国の文学
(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代
(9)映画 ミュージシャン 映画音楽
(11)映画 「109ハット」でお昼寝
(3)読書案内 エッセイ
(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」
(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝
(5) 吉田浩太「スノードロップ」元町映画館no324
週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(1~3)」(集英社)
ベランダだより 2025年11月5日(水)「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・」ベランダあたり
アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸no339
EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ
トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸no338
徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」団地あたり
阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット
週刊 読書案内 草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より)
三宅唱「THE COCKPIT」シネリーブル神戸no336
週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(1~3)」(集英社)
ベランダだより 2025年11月5日(水)「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・」ベランダあたり
アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸no339
EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ
トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸no338
徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」団地あたり
阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット
週刊 読書案内 草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より)
三宅唱「THE COCKPIT」シネリーブル神戸no336
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
小野和子「あいたくて ききたくて 旅にでる」
(パンプクエイクスPUMPQUAKES) 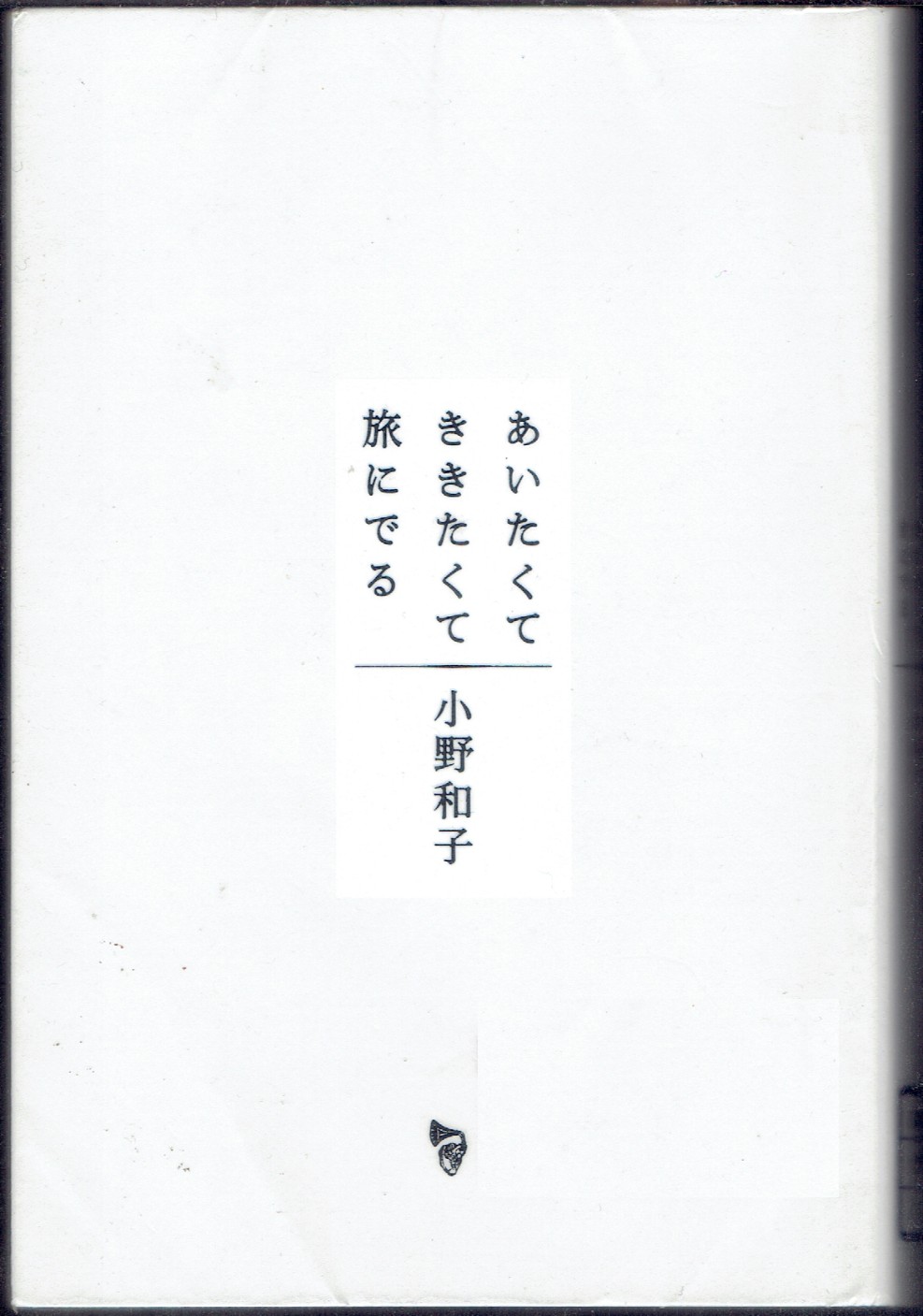 笠間直穂子
という方の 「山影の町から」(河出書房新社)
の中にある書評で知って読みました。 宮城県
の 仙台市
に暮らしておられる 小野和子
という方の エッセイ集
です。
笠間直穂子
という方の 「山影の町から」(河出書房新社)
の中にある書評で知って読みました。 宮城県
の 仙台市
に暮らしておられる 小野和子
という方の エッセイ集
です。
書名は 「あいたくて ききたくて 旅に出る」(パンプクエイクスPUMPQUAKES) です。
本書を、ここまで読んできて、 彼女 の 「ききたい」 という気持ちと出会った 村の老人たちの姿 が、一人一人、印象に残るのですが、ここで、 彼女の気持ち をうしろから支えた 御夫君 の姿にカンドーして
なにはともあれ、採話された 「民話」 の面白さ、 旅の出会い の面白さ、何よりも
いかがでしょう、きっと、驚かれると思いますよ。
追記 2025・03・19 なんという、偶然でしょう。 小野和子さん
の紹介記事が 2025年3月8日(土)
の 朝日新聞
の 「be」欄
に出ていました。 90歳
だそうです。お元気そうでなによりです(笑)。
なんという、偶然でしょう。 小野和子さん
の紹介記事が 2025年3月8日(土)
の 朝日新聞
の 「be」欄
に出ていました。 90歳
だそうです。お元気そうでなによりです(笑)。
(パンプクエイクスPUMPQUAKES)
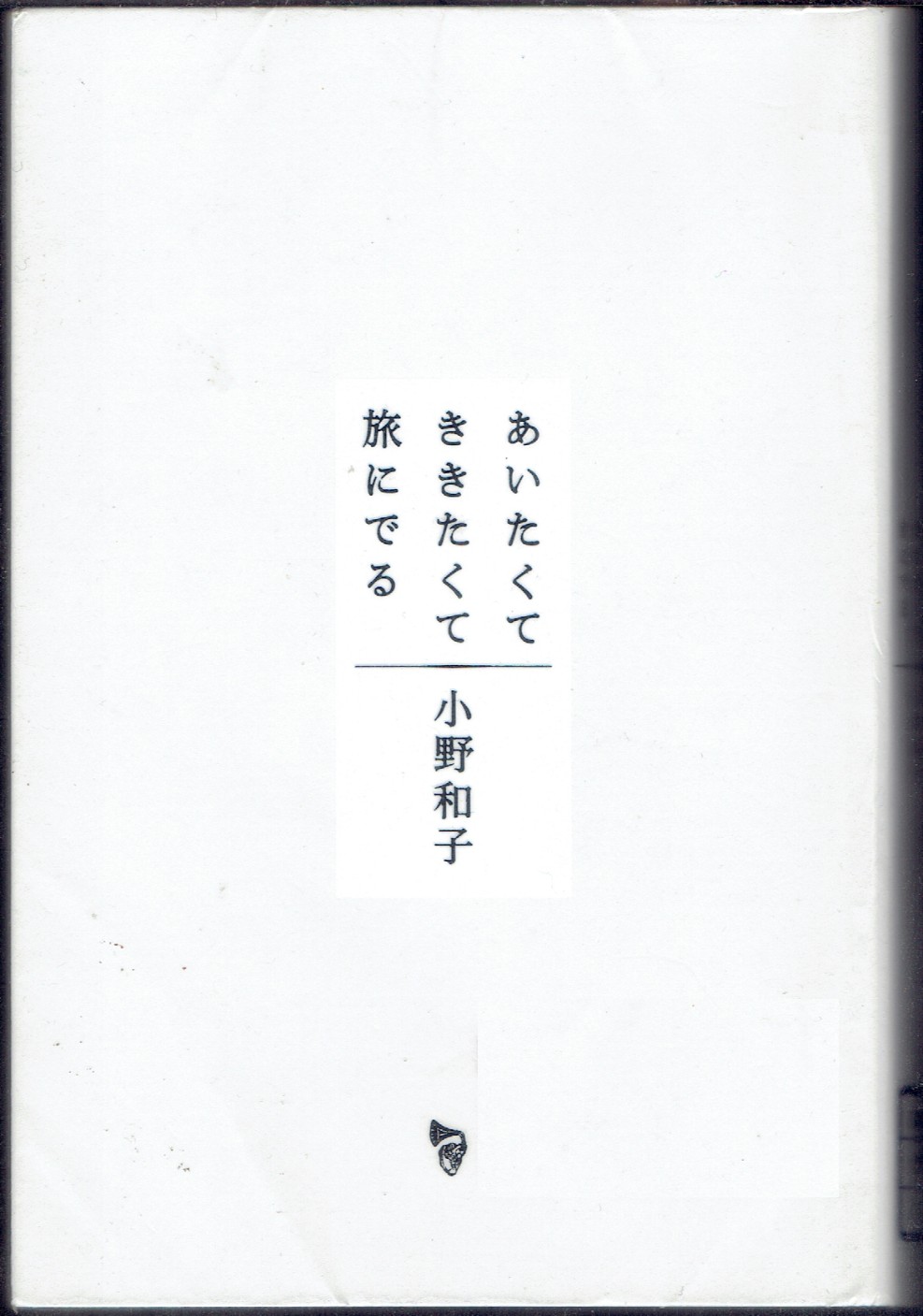
書名は 「あいたくて ききたくて 旅に出る」(パンプクエイクスPUMPQUAKES) です。
手許にある植物の株を、声をかけ合って、分ける。散った株が、それぞれの場所に根づいて、そこからまた、散る。この感じから思い浮かんだのは、植物の本ではなくて、小野和子の「あいたくて ききたくて 旅にでる」だった。 笠間直穂子 の 書評 の書き出しです。ここから、 小野和子 の本の具体的な引用があってこんなふうにまとめられます。
1969年以来、宮城県とその周辺の村々で民話採訪をつづけてきた著者が、八十歳になったのを機に手製本を制作した。「『民話』の足もとで見え隠れしたものを記し」たという、その本の増補版である本書は、著者の言葉どおり、いわゆる民話集ではなく、民話の「足もと」、つまり、民話を語り語られる関係が生まれる現場、さらに言えば、現場に立つ相手と自分の心身の動きを、丹念に見つめたものだ。(P180 ~181 )
経済状況でであれ、家庭環境であれ、その他どのような背景によるものであれーいや、突き詰めれば、背景はあまり関係なく、もっと普遍的なものかもしれない—苦しさ、寂しさをかかえた人間に、小野和子は引き寄せられるようだ。そのような土壌があってこそ、ひとは語る。 東京 から 秩父 に越してきた 笠間さん の庭先に咲く花をめぐっての近所づきあいから紹介されている本書ですが、 「読書案内」 としてボクが付け加えることは、まあ、ほとんどありませんね。ただ、 「あいたくて ききたくて 旅にでる」 という本書の題名について、
民話といえば、「むかしむかし」と語り出される「笠地蔵」や「猿蟹合戦」や「花咲か爺」を思い起こす人が多いだろう。現にこのわたしだってそうだった。そして、陽だまりの縁側で綿入れの胴着を着た年寄りが、孫に語って聞かせるのどかな風景を思い起こす人も多いだろう。
だが、実際にわたしが歩いて聞く「話たち」は、ほとんどまとまりがなくて、なにかの断片のようなものが多かった。いや、話というよりはつぶやきのような、ため息のような、傷口のようなそんなものばかりを、わたしは聞いてきたような気がする。
聞こうとするひとがいて、話は伝えられる。そして、受けとったひとの手許に残る。その話は、語るだれかにとってそうだったように、受けとるだれかにとっても、生きるつらさをしのぐ糧になるかもしれない。伝統の継承といったこととはまったく別のレベルで、受け継がれ拡散する宝物である「話たち」は、わたしにはやはり手から手へ渡って枝葉を伸ばす草木と似たものに見える。(P184~185)
ああ、そうだったんだ! という記述が、最後の 「最終話にかえて ゆめゆめのサーカス」 の冒頭にありましたから、それを載せておきます。
子どもは三人いた。初めて採訪に出た頃は、八歳、四歳の女の子に歩き始めたばかりの息子がいた。核家族だったから、子どもの面倒をみてくれる年寄りも身内もいなかった。それで、大学の教師だった夫の休日をねらって、私は旅にでるのだった。 小野和子さん が民話の採訪を始められたが 1970年代の末ごろ だそうですから、ほぼ、 50年前 の述懐です。
カレーライスを山のようにつくっておくのが習わしだった。上の娘にこれを温めてくれるよう頼んで、まだ寝起きで機嫌の悪い次女の目から隠れるようにして家を出た。夫はネンネコ半纏で息子を負ぶって、玄関の外にいて、
「気をつけて行けよ。無理をするなよ。」
と、いつものセリフでわたしを送り出してくれた。
これという明確な目的もなく、ただ喉の渇きを満たすような頼りない行為であったが、わたしは民話を求めてあてのない旅をしたかったのだ。それは三人の子持ちの主婦の無謀とも言える願いであったが、夫はそれを大事に受け止めてくれた。(「あいたくてききたくて旅にでる」P332)
本書を、ここまで読んできて、 彼女 の 「ききたい」 という気持ちと出会った 村の老人たちの姿 が、一人一人、印象に残るのですが、ここで、 彼女の気持ち をうしろから支えた 御夫君 の姿にカンドーして
「なあ、この旦那さん、スゴイやろ。」と同居人に声をかけると
「世の中には、そんな夫もいてはるんやねえ。」 と、ちょっと白い目を向けられてしまった シマクマ君 でした(笑)。
なにはともあれ、採話された 「民話」 の面白さ、 旅の出会い の面白さ、何よりも
「ききたい」人がいて、「語る」人がいるという、「手から手へ」の情景 には胸打たれました。
いかがでしょう、きっと、驚かれると思いますよ。
追記 2025・03・19



追記
ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID
をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「社会・歴史・哲学・思想」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 坂上香「根っからの悪人… 2025.08.11 コメント(1)
-
週刊 読書案内 隈研吾「日本の建築」(… 2025.07.31 コメント(1)
-
週刊 読書案内 木田元「なにもかも小林… 2025.07.26 コメント(1)
Re:週刊 読書案内 小野和子「あいたくて ききたくて 旅にでる」(パンプクエイクスPUMPQUAKES)(03/06)
ミリオン さん
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










