PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(2)読書案内「日本語・教育」
(22)週刊マンガ便「コミック」
(79)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(77)演劇・芸能「劇場」でお昼寝
(5)映画「元町映画館」でお昼寝
(131)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(120)読書案内「映画館で出会った本」
(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(29)読書案内「現代の作家」
(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(33)読書案内「近・現代詩歌」
(58)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(13)映画「パルシネマ」でお昼寝
(32)読書案内「昭和の文学」
(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(23)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(40)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(22)ベランダだより
(167)徘徊日記 団地界隈
(138)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(27)徘徊日記 須磨区あたり
(34)徘徊日記 西区・北区あたり
(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」
(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」
(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東
(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(25)映画 香港・中国・台湾の監督
(40)アニメ映画
(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(41)映画 イタリアの監督
(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(29)映画 ソビエト・ロシアの監督
(14)映画 アメリカの監督
(99)震災をめぐって 本・映画
(9)読書案内「旅行・冒険」
(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(15)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(5)映画 フランスの監督
(53)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(13)映画 カナダの監督
(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督
(9)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督
(12)映画 ギリシアの監督
(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督
(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督
(5)映画 アフリカの監督
(3)映画 スイス・オーストリアの監督
(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ
(7)週刊マンガ便「小林まこと」
(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」
(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督
(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介
(19)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」
(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」
(5)徘徊日記 神戸の狛犬
(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」
(11)読書案内・映画 沖縄
(10)読書案内 韓国の文学
(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代
(9)映画 ミュージシャン 映画音楽
(11)映画 「109ハット」でお昼寝
(5)読書案内 エッセイ
(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」
(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝
(5) エナ・センディヤレビッチ「Take Me Somewhere Nice」元町映画館no325
山田洋次「TOKYOタクシー」109シネマズ・ハットno70
週刊 読書案内 金時鐘「見えない町」(「猪飼野詩集」より)
マイク・リー「ハードトゥルース」シネリーブル神戸no340
週刊 読書案内 金 時鐘「猪飼野詩集」(東京新聞出版局)
ロバート・レッドフォード「リバー・ランズ・スルー・イット」パルシネマ新公園no49
徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここが西門!」 ここは鬼ノ城・その2 岡山・総社あたり
週刊 読書案内 池澤夏樹「されく魂 わが石牟礼道子」(河出書房新社)
週刊 マンガ便 ハロルド作石「THE BAND 2」(講談社)
徘徊日記 2025年11月8日(土)「ここは梅田の太融寺!」 大阪、梅田あたり
山田洋次「TOKYOタクシー」109シネマズ・ハットno70
週刊 読書案内 金時鐘「見えない町」(「猪飼野詩集」より)
マイク・リー「ハードトゥルース」シネリーブル神戸no340
週刊 読書案内 金 時鐘「猪飼野詩集」(東京新聞出版局)
ロバート・レッドフォード「リバー・ランズ・スルー・イット」パルシネマ新公園no49
徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここが西門!」 ここは鬼ノ城・その2 岡山・総社あたり
週刊 読書案内 池澤夏樹「されく魂 わが石牟礼道子」(河出書房新社)
週刊 マンガ便 ハロルド作石「THE BAND 2」(講談社)
徘徊日記 2025年11月8日(土)「ここは梅田の太融寺!」 大阪、梅田あたり
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
横尾忠則「飽きる美学」(実業之日本社)
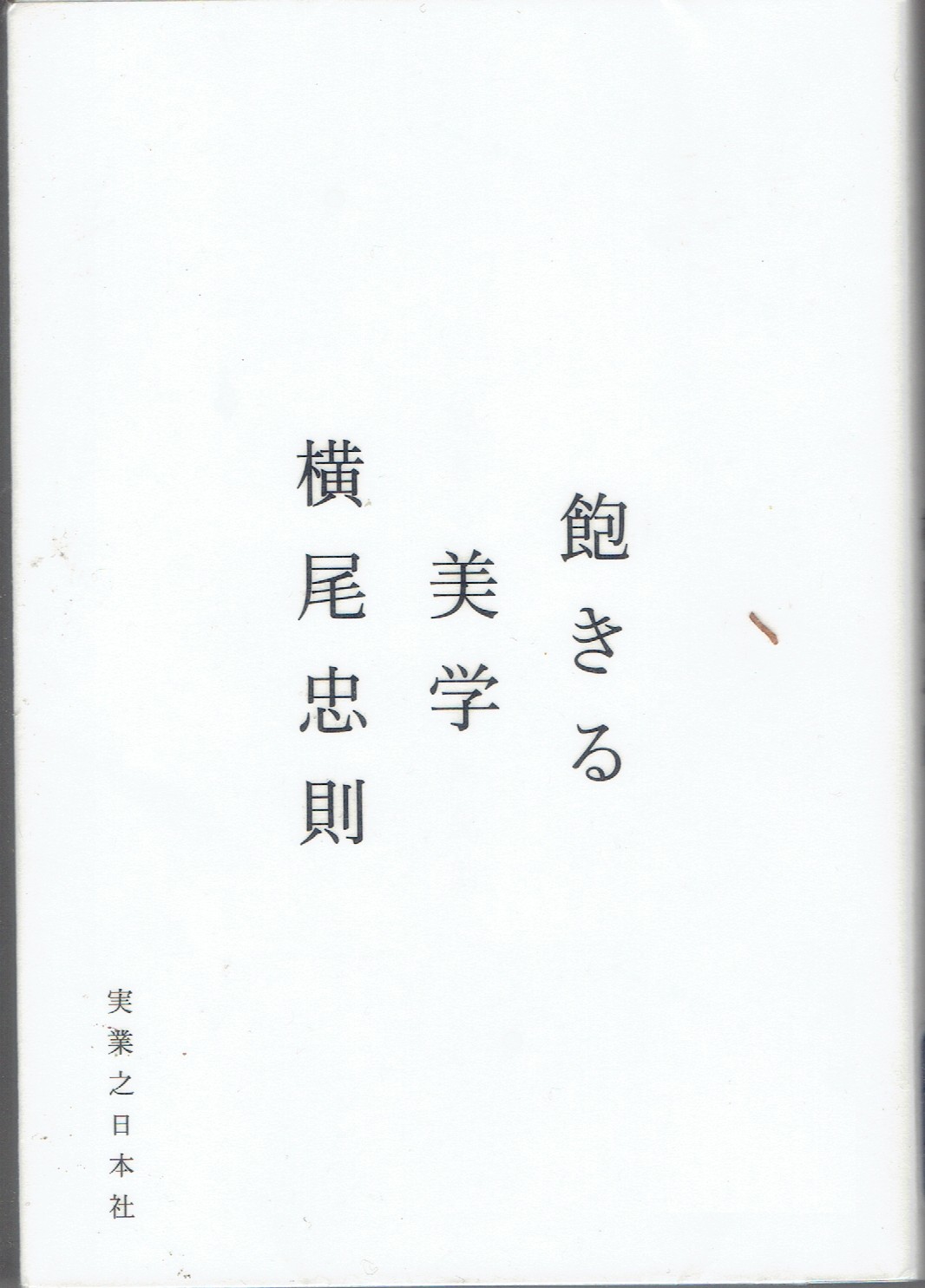 市民図書館
の 新刊
の棚にありました。 2024年の12月31日
の 新刊
です。 横尾忠則
の 「飽きる美学」(実業之日本社)
です。字が大きくて読みやすいです。
市民図書館
の 新刊
の棚にありました。 2024年の12月31日
の 新刊
です。 横尾忠則
の 「飽きる美学」(実業之日本社)
です。字が大きくて読みやすいです。
そういえば、 横尾さん 、 兵庫県 の 西脇 の人で、 高校 は 県立西脇高校 です。実は、昨年亡くなった、 同居人のお母さん が、 彼 と 高校の同級生 だったんですね。
まあ、それにしても、お元気そうでなによりです、 知らんけど 。でした。
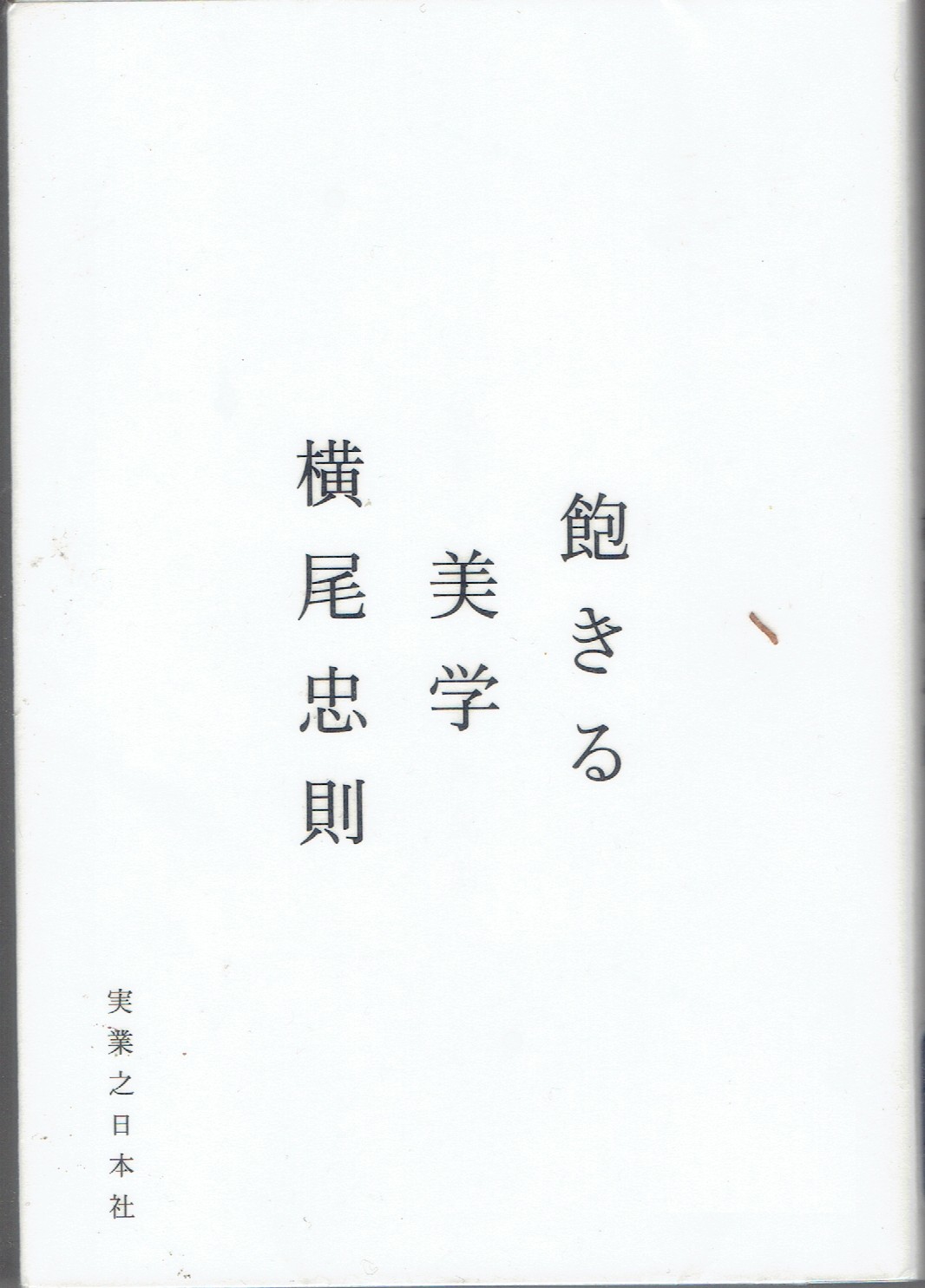 市民図書館
の 新刊
の棚にありました。 2024年の12月31日
の 新刊
です。 横尾忠則
の 「飽きる美学」(実業之日本社)
です。字が大きくて読みやすいです。
市民図書館
の 新刊
の棚にありました。 2024年の12月31日
の 新刊
です。 横尾忠則
の 「飽きる美学」(実業之日本社)
です。字が大きくて読みやすいです。「絵を描くのに飽きた!」 とまあ、こういう書き出しです。で、まあ、 「飽きた」 ということについての蘊蓄があれこれあって、たとえば、
と言ったり書いたりしたもんだから、「エエーッ」と驚いた人がずいぶん沢山いたのに驚いた。驚いた人たちの多くは、この「飽きた!」という言葉にえらい新鮮さを覚えたというのです。
「飽きたが!」 そんなに新鮮なのかな?
だって僕は3歳からずっと88歳になるまで絵を描いているんですよ。だから飽きて当然じゃないですか。(P2)
三島由紀夫さんの死は結局生きることの意味や必然性がなくなった結果だったのかもしれません。つまり人生に飽きたわけでしょう。 などという、まあ、過激極まりない発言まであって、
飽きない間は不自由なんです。自由が見つからないから飽きないのです。 という展開ですから、
ああ、はあ、そうなん!? と、わかったような顔でもして、うなづくほかないわけですが。結論はこんな感じです。
まあ僕的に言えば、「飽きた!」状態で描く絵はどんな絵なのか、それを見てみたいという好奇心があるのです。ここからが「飽きる」始まりなんです。つまり「飽きる」というのは無意識行為なんです。意識して飽きるのではなくて、気がついたら飽きていたのです。「気がついたら、こんなんできてましたんや」というのが「飽きる」美学なんです。浅田彰さんが僕の作品は「無意識の底が抜けている」と言いました。つまり底が抜けないと「飽きた!」とは言えないんです。無意識の底が抜けるということは他力と自力が一体化したことではないかと思います。 とこうなって、論議は、もう一息続いて
他力と自力が一体化は死とギリギリです。 と、まあ、 「飽きる美学」 が 解説(?) 、 宣言(?) 、いや、ボクには 無意識の呻き として述べられているんじゃないかという感じがしますが、深いような、浅いような、
で、もちろん、その向こうには 「霊性」 ですね。
他力と自力の一体化は三島流に言えば霊性です。霊性は言葉では説明できません。それは霊性イコール徳だからです。 「飽きた!」 ことは無意識の底の抜けた陰徳です。
駄法螺エッセイ(笑)のはじまりです。 この エッセイ集 の中で、 関西弁 の 「知らんけど」 という、何かわけありげに言った後にくっつける言い回しに言及していらっしゃったのが、ボクには一番面白かったんですね。こういうのが、面白い人には面白いと思うのですがと勧めたところ、うちの 同居人 は
眠くなる! と言って放り出してました。
そういえば、 横尾さん 、 兵庫県 の 西脇 の人で、 高校 は 県立西脇高校 です。実は、昨年亡くなった、 同居人のお母さん が、 彼 と 高校の同級生 だったんですね。
「おかーちゃん、横尾さんって、さん付けやったけど、あんまり、ええようには言わんかったなあ。」 というのが 同居人 の記憶ですが、 高校時代 に 「郵便友の会」 とかに熱中している 男子同級生 に、いい思い出を持つ 女子高生 は少ないでしょうね。 知らんけど(笑) 。
まあ、それにしても、お元気そうでなによりです、 知らんけど 。でした。


追記
ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID
をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 山本陽子「入門 日本美… 2025.01.22 コメント(1)
-
週刊 読書案内 シャーロット・マリンズ… 2025.01.04 コメント(1)
-
週刊 読書案内 荒勝俊「日本狛犬大全」… 2024.11.20
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










