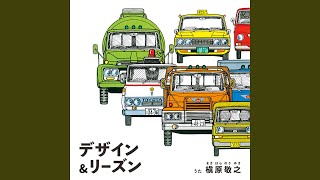2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2004年07月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
武士道
新渡戸稲造の「武士道」によると、古来より日本人が寡黙であまり感情をおもてに出そうとしなかったのは「礼」の精神によるもので、優雅に立ち振る舞い品性を高めることを目標とする者にとってのひとつの表現方法だということだ。他人を不愉快にさせないようにするために、たとえプライドを傷つけられても笑顔をやめない。あるいは虚栄心を満たされても大喜びしたりしない。儒教の教えのひとつである「礼」は、そんなカタチで武士の心に根付いていった。寡黙が美徳とされる「武士道」という規律の中で生きる武士たちは、普段感情をおもてにださない代わりに、俳句や詩文で喜びや悲しみを表現したという。どちらかというとオレは普段のときの感情をおもてに出してしまいやすい性格だから、仕事のときも不愉快と思ったときは不愉快だということを、正論になぞって理論的にそして比較的紳士的に伝えようとするけれども、ほとんど誰にも伝わらない。おそらく間違いなく意思は伝送されてはいるが、対策がなにも講じられない状況、これは「伝わっていない」のと同じことだ。おそよ中学生の「誰もわかってくれない」と同じ意味のことをオレはいまいっているけれども、いくら大人になっても、いやなものはいやなのだ。仕事などの対外交渉の場においてあまり嫌々いうのも武士としての礼に反するが、俳句や詩文の技術も持ち合わせていないオレはこうしてネットで作文を書くことによって、猛る血や荒れる気を鎮めたりしようとしている。「自分のケツを自分でふけない」ということをオレはこないだどこかで言われた。確かに自分でキレイにケツを拭うという習慣がない家にオレは生まれたから、たれ流しても死ななきゃOK、なような価値観が生き方の根拠になっているかもしれない。という意味では、自分のケツを自分でふけない、というよりも、自分のケツを自分で拭かない、といったほうが近い。ただ、汚れたケツを、誰かに拭いてもらうのはたまらなく嫌だ。自分のケツもろくにふけないようなオレが、どういうわけかここ半年ぐらい、他人のケツを拭ってあるくような仕事ばかりやらされている。前任者の失敗をフォローする仕事のことだけで、半分ぐらいの時間が浪費されている。しかも前任者はいずれも、次の仕事にとりかかっていて忙しく、前の仕事にはおおむね無関心になっている。欠陥住宅を建ててただ去る悪徳業者のように、「次の仕事があるから」といって昔のことには関わろうとしない。結局、現場に取り残されたオレらが、ほとんど無償で改築工事をしなければならない。悲惨なシステムに出会うたびにオレは、イチから作り直したい欲求が湧き上がってくるけれども、オレの欲求にはどこからも金が出てこない。
2004.07.27
コメント(0)
-
レンタカー通勤
しかし暑い。我が家のエアコンは本来の能力を発揮できておらず、設定温度をはるかに超えた熱風しか吐き出してはくれない。東京大手町では39.5の記録的猛暑を記録したらしい。ニュースでは「この暑さによる死者が全国で15人にのぼりました」というようなことが伝えられているけれども、ほとんどこれは災害に近い。オレと同じように、「暑さ」を題材にした日記が書かれた数も、今年一番を記録したのではないかとも思うのである。なんだかんだいってもニッポン、陸続きだ。陸続きといえば、レンタカーによるクルマ通勤は4週間目をむかえた。1ヶ月の契約もあと残りわずかということになる。暑い日が続くなか、クルマの中だけは快適で、交差点で信号を待ちながら暑そうな顔のサラリーマンたちを横目に右折レーンで待機してるときには内実、かなりの優越感がこみあげたりしているが、どちらかというとストレスのほうが多い。渋滞とかマナーの悪さとかそういうことに苛立つというよりも、なんというか他のクルマの「意思」みたいなものが伝わってくるということが、デリケートなオレの精神に負荷をかけているのだ。怪我人を乗せているから急ブレーキを踏むわけにはゆかず、よって前のクルマとは一定以上の車間を開けて走行している。するとその車間に隙間には、容赦なく車線変更車が進入してくる。仕方なくまた侵入車との間をあける。また入り込まれる。やがてオレのいるレーンは隣よりも混雑してきて、今度は後ろの車が車線を変えようとする。「おまえの後ろじゃダメだ」というような苛立ちがハンドルさばきに現れている。都内のクルマの約8割が苛立っているとオレは思っている。街の歩行者もおそらく、それぐらいの割合で苛立ってるはずだが、クルマは歩行者よりも匿名性が高く、つまり苛立ちを表現したとしてもそのリスクは少ない。乱暴な運転をして他人に不快な印象を与えたとしても、「やあねえあのひとなあに?」とか言われることを気にせず立ち去れるからだ。そういうことをいちいち考えなければならないクルマという乗り物はオレの性には合わない。涼しくて快適ではあるけれども、悪魔に魂を売っているような気がしてならない。ただの暑さしのぎのためのレンタカー通勤ではない。嫁が足の骨を折り、松葉杖で電車に乗る体力も根性も持ち合わせていないことから、毎日タクシー通勤をされてしまうことを危ぶんだ苦肉の策だったともいえる。たまたま暑さをしのげている快適は「怪我の功名」といえるかもしれないが、圧倒的に時間が拘束されてしまうことと、ちょっと一杯やってから帰るということができないことの負担は、ストレスというカタチでオレに重くのしかかっている。とにかく今は、ビアガーデンとかそういうところに行って、前後なくなるまで飲みたい。でないともう夏が終わってしまう。
2004.07.20
コメント(0)
-
踊る大銀行統合戦
UFJ銀と東京三菱の統合の話が日経新聞によりすっぱ抜かれた。そのことを今朝のワイドショーで知ったオレは騒然となった。秘密というわけではないけれども、UFJの子会社で働いている。といっても正確には、UFJ銀のIT部門を受け持つグループ会社から仕事をもらっているソフトハウスと契約して働いているわけであり、たとえば新国会議事堂建設を請け負うゼネコンからの発注をうけた土建業者のもとに集められた日雇い労働者のようなものだ。そのUFJの子会社に日雇いの分際で朝10分遅れて出社するとオフィスは鎮まりかえっていた。ワイドショーで「ギガバンク誕生」の噂を知ったオレは、朝マックの途中でコンビニへ行って日経新聞を買った。140円もした。知りうる限りの情報は入手した上で出社したわけだけれだども、とくに痛恨で慌てていたというわけでもなく、たんに面白そうだったから、もっと情報が欲しいと思っただけだった。オフィスは鎮まりかえっていた。アタマの中は「統合」でいっぱいなのに、話題にしていいかどうかわからない。そんな感じの沈黙だった。オレは、そのニュースを知らないような顔をしていつもの仕事にかかった。まもなく「部長様」がやってきた。行員一同は、ひれ伏しながら、部長様の言動に注目した。子会社といっても社員は十中八九銀行からの出向だから、所属はほとんどUFJ銀行だし、数少ない子会社直参の社員であろうとも、その母体は統合前の旧東海銀システム部だったりする。みな銀行員のためのトレーニングは受けてきているし、エリートとしてのプライドも感じられる。ちなみにエリートなだけあって仕事はできる。ただし、江戸時代のような「封建体質」が未だに、行内には痛々しいほど根付いている。「上」の命令は絶対的だし、「下」の扱いは奴隷なみだ。上司は部下のプライドを絶対に尊重しない。つまり上司の役割は、部下のプライドを崩壊させることが第一だといっていい。なるほど部下たちはふるいにかけられ、耐えられなければやめてゆくし、仕事ができればかわいがられる。たたき落とされながら上司の「いじめ」に耐えうるものだけが残されてゆく。そうやってエリートが出来上がっていくわけだ。「新聞みたか?やってらんねえよなまた統合なんて」注目されていた部長さまが口をひらいた。かなりのエリートだから、身内(行員)にたいしてはどんなぞんざいな言葉を使ってもいいし、誰のプライドを傷つけたところでとがめられない。部長さまは、大杉蓮に似た感じだ。部長のこの言葉は、閉塞したオフィスの状況を打開する一手になった。しかしこれによってオレは、今朝日経がすっぱ抜いた「東京三菱との統合」が、行員に全く伝わっていなかったということを知った。よく不祥事を起こした企業の本社に取材がいって、出勤する社員に今のお気持ちを求めるレポーターがいて、たいがい逃げるようにして社員は入口を目指していて、視聴者が期待するようなコメントは一切聞かれない。実際のところ、末端の行員は、この重要な決定事項に関して何も情報を与えられていなかった。そのことは、「ひとつきいていいですか?」というときに立てる人差し指のそり方が美しいキュートな銀行員とランチへ行ったときに、それとなく核心に迫ってきいてみたことで明らかになった。「まあ、まだウワサですからね。。」と歯切れ悪くキュートな銀行員はいった。「なぜすぐに情報が伝わってこない?」と我々現場の作業員は、エリート銀行員たちによく叱られる。すると我々はありったけの情報をしぼり出して「上納」する。その割に、「上」からの情報は全く伝わってこない。企業内の情報は、下から上へ行く経路しか確保されていない。「なんでもっと情報おろしてくれないんすか。所轄には所轄の意地があるんす。約束したでしょう?オレは現場でがんばるから、ムロイさんは上へいって組織を変える、って。」オレはランチのとき、キュートな銀行員にいった。どこかできいたような話だ。事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ。
2004.07.14
コメント(2)
-
アボルダージュ
7月10日、アボルダージュ~接舷攻撃~という舞台を観に武道館へ行った。「KANSAI SUPER SHOW」として山本寛斎制作総指揮のイベントだ。「アボルダージュ」とは、「接舷攻撃」のフランス語で、日本で最初の海戦といわれれる宮古湾海戦で行われた作戦名称でもある。大政奉還や五か条のご誓文などにより、300年つづいた徳川幕府は失墜し、朝廷中心の新政権が樹立された。抵抗する残存勢力としての旧幕府軍。対、新政府軍の戦闘は、江戸から流山、甲府などを経、やがて東北を北上してゆくことになる。宮古湾海戦の舞台である宮古湾は、現在の岩手県宮古市にある。「接舷攻撃」とは、船の「舷」つまり「へり」どうしをくっつけて、そこからゲリラ部隊がへりを飛び越えて浸入し、相手方船内の水夫を殺戮し、敵艦もろとも強奪せしめよう、という作戦である。宮古島海戦には旧幕府軍として新撰組の土方歳三も参加した。「戊辰戦争」と呼ばれるこの一連の戦闘群は、やがて函館五稜郭において、旧幕府軍の降伏、つまり土方側の敗北、という結末をもって終結する。このころの新撰組には、かつての隆盛はない。「鳥羽伏見の戦い」という頂上決戦にもやぶれ、近藤勇は処刑され、沖田某は肺結核で死んだ。「生き残り組」としての、土方歳三率いる新撰組残党は、自分たちの死に場所を探すためだけに、半狂乱になりながら泥沼のような戦いを繰り広げ、そして散っていった。この悲しくもはかなく美しい男たちのエピソードは、司馬遼太郎の小説「燃えよ剣」に描かれていて、多くテレビドラマ化されたりしている。ちなみにこの「燃えよ剣」、ダヴィンチの読者により新撰組物語No.1に選ばれていて、オレもだいぶ最近読んだけれども非常に面白かった。司馬氏は土方歳三を、新撰組としての落日が始まったところから、つまり敗戦を繰り返しながら函館を目指していた頃が、彼の本領発揮だったという観測で話を書いている。新撰組はかつての隆盛を失い、近藤や沖田といった仲間も失い、土方だけが生き残っている。一番死ぬべきだった自分だけが生きていて、逆に取り残されているようだ。そう思った時点で土方は死を覚悟した。死を「受け入れた」といってもいい。死ぬことが恐くない男は、どんな無茶なことでもできる。「燃えよ剣」の土方歳三をみて、オレはそんなことを思った。話はそれるが、たけしの映画が好きでほとんど観ている。よくよく考えてみると、たけしの映画に出てくる主人公はみな、「生」への執着がない。いつも「死」を受け入れられる体勢になっている。だから暴力的だし、限りなく強い。「BROTHER」なんかは、たぶん新撰組の話がもとになっていると思っていて、かの映画でたけしが演じた主役は、土方歳三をモデルにしたに違いない。そういえば、大島渚の「御法度」で土方役をやっていたのもビートたけしだったような気がする。おそらくたけしは、いつ自分が死んでもいいと思っていて、だからこそ土方歳三の生き方に共鳴もする。死とか失敗とかそういうことを恐れないから、いい映画が作れる。このことは、「死への恐怖がない男」ほど、いい仕事ができる、というふうに言い替えられるかもしれない。宮古湾海戦における土方隊は、さぞいい仕事をしたのだろうと思う。そのときの作戦、「アボルダージュ」をモチーフにした舞台を観にいった。
2004.07.10
コメント(0)
-
切腹お家取り潰し騒動
先日、「犬を憂える会議」が開かれた。会議といっても、コビックが珍しくオレにMNSメッセンジャーで話しかけてきて、雑談のまま時が過ぎようとしていた矢先に副主将がコビックに誘われた。「何の話してたですか」副主将はいった。友人の結婚式で祝辞をやらされるハメになってしまったことへの愚痴と、コビックが歌いたいカラオケの選曲の話だけで、副主将が期待していたような会話は、オレとコビックの間では繰り広げられていなかった。とその旨を副主将には伝えた。「そうですか。。。」がっかりしたような感じにもとれる副主将の相槌が示すその先の言葉がわかってしまった。オレは先回りをしようと思って次のようなことをいった。「3人そろったし、犬を憂える会議でもするか。」「犬解放」をスローガンに掲げたオレが左翼の代表だとするならば、コビックは「解放反対」の急先鋒として真っ向からオレの挑戦を受けてたった唯一の人間で、保守派としての右翼代表といってもいいだろう。思わぬ強敵の出現と、孤立しはじめていたことへの焦燥感が募ってきたこともありオレは、最終兵器を投入することに決めた。「犬」からの撤退と、リバースつまりここの閉鎖だ。時代劇にたとえると、「切腹・お家取り潰し」の沙汰である。しかし実際に死ぬわけではないし、やり直しはいくらでも利くぶん、時代劇の世界ほどのリスクはない。「死ぬわけじゃない」と思えば、わりと無茶そうなことでも平気でできる、ということを最近よく思う。犬からの撤退と、リバースの閉鎖。これを出した時点でオレが出せるカードは全て無くなったわけだった。同時に、この「犬解放」というテーマもどういうわけか、飽和点に達してしまったようだった。オレの失敗やその責任を問う書きこみその後一切無かったし、どちらかというと「切腹・お家取り潰し」というような古めかしい責任の取り方にたいする反対運動が巻き起こったぐらいだった。そのこと事体はオレは非常に嬉しかったわけだけれども、反面、ふりあげたものをふりおろすことが出来ないという事態にも陥ってしまっていた。半狂乱のように、「閉鎖をかけて勝負!」といった手前、閉鎖しないと物語が完結しない。かたや「逃げるはヒキョウナリ」という世論もオレに働きかけている。選択の岐路に立たされたオレがこの物語を完結させるために参考にしたのは、「スターウォーズ」だ。まだ続きがあることにすればいい。オレは勝負に負けてURLを消さざるをえなくなった。一応正規軍は勝利をおさめハッピーエンド、命だけは助けてもらったオレは「負けたよ」という言葉を残し満身創痍で「リバース」という獄に幽閉され、そこでサラコナーのように心身を鍛え、来るべき復讐のときにそなえている。というような感じで3部作ぐらいで完結させるという方法もあったことに気づいた。コビックがオレに話しかけてきたのはそんな矢先だったが、ほとんど雑談に終始するのみで、なかなか「犬」のことについては切りだそうとはしなかった。やがてコビックが、同じチャットの中に副主将を連れてきたことで、座の方針が定まった、とオレは思った。余談だが、たとえば、帰りたい空気がただよっていてみんな疲れてうなだれそうになっているのになかなか終わらない宴会のときに、「じゃそろそろ帰ろうか」などと言い出すのは決まってオレだ。いいたいことを言いにくそうにしている奴の顔色を読んで、代わりにいってやる役目を請け負ったりすることも多い。たぶんてんびん座のO型だからだろう。「犬を憂える会議」が始まるとすぐ、カラコも呼ばれた。今夜の「犬プロジェクト」は、この4人で行われた。大半の時間は雑談で埋められたが、オレはこれに「会議」という属性をあたえるために、常に軌道修正を図った。たとえばコビックがばかばかしいことを言って笑ってしまっている指先でもって「やっぱり犬は解放するべきだ」といってみたりというようなことをした。あまねく人の精神構造が複雑で一枚岩ではなく、常に自己矛盾を孕んでいるのといっしょで、オレの指先と、その時々の表情や感情は必ずしも一致しない。また余談になるが、「あのときあんなことをいってたのに、今といってることが違う、それはおかしい」という感じでネット上ではよく論争が繰り広げられているけれども、その時々で感情なんか違うわけだし、気軽に一部の感情の断片を「書きこみ」という制約のある環境下でいくつか披露したとして、それら全体が限りなく矛盾していたからといって、それが「人格」を語る要素にはならない。とある論争のなかで矛盾を発見したライバルは決まってそのことを取り上げて「やーいやーい」とかいわんばかりになるけれども、まるで子どものようだ。こんなネット上の戯言なんか、「あれは嘘だった」なんて後からいってしまえばたとえホントでも済むことだし、その中で出会ったホントに付き合いたい人とだけ話してれば大概の欲求は満たされるわけだから、いまさら「犬」というたんなる媒介の完全性にこだわるよりも、というより、組織としての有るべき姿や正論に固執したりするよりも、もっと機能的に使っていこうじゃん?というのがオレの、「解放」への動機でもあり、そのことはこの日の、「犬を憂える会議」でも伝えたつもりだ。が結局、「解放よし」としたいのはここでもオレだけだったことなどから、「会議」は物別れのうちにおわった。どうも穏やかな進行になってきたと思っていたら、カラコなどは途中で爆睡してしまっていたらしい。堂々たる議員っぷりである。ともあれどうやら、切腹はまぬかれ、50万石ぐらいから7万石ぐらいに減らされたものの、取り潰しも免除となり、つまりリバースは、続けられることになりましたありがとうございました。「犬vol.2 復讐編」にも乞うご期待。
2004.07.07
コメント(2)
-
解放
「犬を盛り上げるためにはどうしたらいいですかね」「犬」という掲示板にかつてのような活気や隆盛を取り戻したい、という副主将の意欲を反映させるためにはどうしたらいいか。一度栄光を経験し、やがて廃れていってしまったものをまた元に戻そうということは、一度別れた女とよりを戻そうとすることに似ている。カタチだけ元の鞘におさまったとしても、一度離れた心はなかなかくっつかない。副主将は、昔の仲間にまた「犬」への関心を取り戻してもらいたいと思っていた。終わりつつある恋愛の相談を受けるときオレは決まって、「そんな奴のことなんか早く忘れちゃってさ、新しいピチピチのいい男探したほうがいいよ」というアドバイスをする。心の離れた男ほど女にたいして残酷なものはないし、新しい男のほうが優しいにきまってるし、一緒にいて楽しいに違いない。犬の「心」が副主将から離れてしまった以上、この破れた恋の辛さを忘れさせるためには新しい恋が必要で、そのためには新しい犬を飼えばいい。「犬をもう一度盛り上げる」という話をオレは勝手に、そう変換した。このことは、犬というシステムの大前提である「閉鎖性」に魅力を感じられなくて、犬との接点を失っていたオレのニーズとも一致した。この掲示板には唯一「ルール」と呼べるものがあり、それは「けして晒してはならない」というルールだった。たいした宣伝もせずにどうやって人が増えていったかというと、犬にいるメンバーの「つて」だけがたよりで、いわばクチコミで広がっていった。広がったといっても、正確にはどれぐらいかわからないが、最低でも50人は知っているだろうし、ともすれば100人は通過したかもしれない。自然と、階層構造が出来上がっていった。当然目には見えないし、等級や勲章や報酬といった差もないが、誰が誰かを連れてきて、といったシステムはマルチまがいに似ている。人が増えてゆくにつれ組織が巨大化してゆくにしたがって、組織の「トップ」と、「末端」の格差が生まれていった。そのことは、「けして晒してはならない」というルールの恩恵という点においても示された。誰がここを知っていて誰が知らないのか、という全体図を把握しているトップ側のメンバーは、秘密にするべき情報と公開してはならない類の情報が判断できる。ところが新しくやってきた人には、誰と誰がどうつながっていて、誰に何をしたら許されないのかというボーダーラインがわからない。そういうことが、階層構造の中の「格差」として、このシステムには根付かせていってしまうような性質があった。かたや、「全員がフェアでありたい」とする健全な意志も犬にはちゃんと存在していて、だからこそ、「いやあ、久しぶりにのぞいてみたけど、知らない人が増えててるね、賑やかなのはいいことだね」などというような、権威を誇示する書き込みは、ほとんどなかった。逆にそのことも、書き込みが減った原因のひとつなのかもしれない。階層構造は存在するのに、フェアであろうともしたい。環境と理想とが相容れないところにいるから、あいさつ一つするにしても気を使う。だから書き込みは次第に減ってゆく。新しく来た奴は、誰がいるのかもわからない、誰に見られているのかもわからない掲示板に魅力を感じない。「秘密の掲示板」である、VIP待遇であるというルールの恩恵を受けられない。魅力的ではないから書き込まない。悪循環だ。オレは沈みゆく船のような「犬という名のweb掲示板」を再生させるという目的を得た。目的を達成させるためには、「けしてさらしてはならない」というルールを取り除く必要があると思った。そして一つ前の日記に犬のURLを書いた。結局、URLを晒してしまったことは、「犬」の世論には受け入れられなかった。具体的には、反対的な意思や意見が5とか6とかそれぐらいなのに対して、賛成者はというと、ゼロだった。全面的にオレは負けてしまった。負けたから、URLは消した。みっともない話だ。
2004.07.01
コメント(3)
全6件 (6件中 1-6件目)
1