2006年11月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
読解力をつける魔法の言葉
本を読むと読解力がつく。そして賢くなる。確かにその通りだろう。しかしただ読むだけではいけない。何も考えず字面だけをだらだら読んでもだめだ。ましてや他のこと考えながら読むなんてもってのほか。本を読むときは読書に集中する。本に書かれてある内容を考えて読む。そうすれば、読解力もつき賢くなる。では、考えながら読むにはどうずればいいのか。「考えながら読みなさい」そう言われてできる子は、もともと読解力がある。読解力があまりない子は、そう言われてもなかなかできない。実は子どものころ私がそうだった。「読んでいるとき、頭に映像が浮かんできますか。 頭に映像を浮かべながら読んでごらん」子どもたちにはそう言って本を読ませている。「山」という字を読めば、山の映像が頭に浮かぶ。「山に登る」ならその映像が頭に浮かぶ。頭に映像を浮かべながら読む。これは「考えながら読む」のきっけになるのではないか。
2006.11.30
コメント(1)
-
師走間近で走り回る日々
卒業アルバム用の写真撮影が終わった。2週間前に1回おこなった。その日欠席していた子もいたので後日2回目を行う。そして今日がその3回目。掃除時間と昼休みを使い行った。欠席していた子が所属するクラブ・委員会での撮影もする。そのクラブや委員会の子らや先生方にも集まってもらう。1つや2つならすぐに終わる。しかしクラブが2つ、委員会が4つも残っていた。おまけに撮影場所がそれぞれ違う。運動場・玄関前・教室とあっちゃこっちゃ移動しなければならない。これを掃除時間と昼休みに終了させるのだ。5分きざみの計画書を作成し、関係の先生方10名に手渡す。それぞれにこの時間ここに来てくださいとお願い。そうして何とか予定通り終えた。フ~、とため息が出るのもつかの間、5時間目の図工。電動ノコの準備。なんと5台とも刃がない。これでは話にならぬ。大急ぎで、刃を取り付ける。5時間目が終了すると、子どもたちを早急に下校させ、そのまま社会見学の下見。大阪歴史博物館とピース大阪に向かう。どちらも4:30までに入館しなければならない。これまた大急ぎであった。目が回るくらい慌ただしい1日である。しかし明日から毎日のようにこんな日が続きそうだ。明日から卒業文集に取りかかる。明後日は、環境教育実践校の発表。来週は、…。もう書くのをやめよう。とにかく師走。教師も走り回る日々が続くのだ。
2006.11.29
コメント(0)
-
史上最年少、焙りたてコーヒーを作る小学生
最近おいしいコーヒーを飲まれましたか。数年ぶりに西洋料理店に行くことがありました。食事はおいしくいただけました。ところが食後のコーヒー。これが実に単調かつ浅薄な味。インスタントコーヒーかなと思うくらい。もちろんドリップコーヒーでも、市販のコーヒーはほとんど酸敗しているので、おいしくありませんし、体にも悪いです。やはり、コーヒーは家で飲むに限る。そう確信して店を出ました。家には、6種類のコーヒー豆を瓶詰めしています。もちろん全て生豆。焙りたてやか島珈琲使用の生豆です。それらを週に1,2回、焙煎して冷蔵庫に入れておきます。飲みたいときにミルで挽いて飲めばいいわけです。焙煎後のコーヒーの賞味期限は、「豆で7日、粉で3日、たてて30分」ですからいつでも新鮮な焙りたてコーヒーが飲めるのです。最近は、小4の娘がコーヒーを作ってくれます。豆を挽き、お湯を沸かし、紙フィルターを折り、ドリッパーとサーバーで淹れてくれます。焙煎だってやっちゃいます。今日は私が水と豆の量だけ教えると、後は全部やってくれました。私は座って本を読んで待つだけです。「お父さん、できたよ」飲むと実にうまい。深い味わいなのにスッキリします。歯がつるつるしてきます。今日は、ガテマラとモカのブレンド。先の料理店の方に飲ませてあげたいくらいです。焙りたてコーヒーの授業を過去3回やりました。いずれも小学5年生です。娘は4年生。おそらく大阪では史上最年少の焙りたてコーヒーを作る小学生でしょう。今度は小2の娘にも教えようかと思っています。そうすれば記録はさらに伸びそうですね。
2006.11.28
コメント(2)
-
11月下旬なのに暖かい朝、これも温暖化か
今朝、起きて驚いた。全く寒くない。どちらかといえば暖かい。部屋の温度は16℃。我が家では薪ストーブを焚くとこれくらいの室温になる。暖かいはずだ。「日中の最高気温は19℃」ラジオからそう流れたが一瞬、耳を疑った。今日は11月27日ですよ。今日は土曜日の学習発表会の代休。朝から薪ストーブを焚きつ読書と原稿をと思っていたのだが…。結局、今日は薪ストーブを使わなかった。夜は室温17℃だったのだ。「オーストラリア政府の当局者は7日、最近の干ばつが過去1000年で最悪の規模になる可能性があると指摘した」 温暖化の影響だろうか。
2006.11.27
コメント(2)
-

もてなしの心を師匠から学ぶ
Wヤング・平川幸男師匠のご自宅を訪れた。eco-windさんとご一緒に。玄関で師匠はすぐスリッパを出してくれた。「床が冷たいから、履いてください。 どうぞ」私は恐縮しつつスリッパを履いた。「寒いから、温かいもんでもいれましょか」「あ、はい」しばらくすると師匠が、とろみのある生姜湯を持ってきてくれた。温かくておいしい。「寒くないですか」「明かりはこれくらいでいいですか」「お茶菓子でもどうですか」「ヤクルトでも飲みまっか」師匠はいろいろと気遣ってくれた。夜は師匠お薦めの焼肉店。ごはん大盛り3杯でしっかりいただいた。ごちそうさまでした。師匠の息子さんは演歌歌手の秋岡秀治さん。私と同じ丙午生まれだ。浪花のおんな|夢絆息子さんと同じ歳の私を、丁寧にもてなしてくれた師匠の心遣いに、多くを学ばせていただいた。
2006.11.26
コメント(0)
-
ネタ一新のECO漫才
たった1週間で子どもたちはネタをがらりと変えていた。平川幸男さんの漫才授業からの1週間である。今週月曜にはECO漫才に注文をした。ECOな要素を入れ30秒延長とした。今のネタに30秒つけ加えるだけ。私はそんなつもりで注文した。しかし子どもたちは違った。ネタを全面改定していたのである。今週は祝日があり正味4日しかなかった。その4日間で、ネタ作りからネタ合わせまでをしていたのだ。しかも、そんなことは知らずに私は今週、ECO漫才の練習のために、授業時間を使うことはほとんどなかった。国語・算数・社会など他の学習も進める必要があるからだ。そこで子どもたちは、わずかな休み時間を練習時間に使っていた。そして今日の学習発表会。多くの方々が見に来られた中を子どもたちはECO漫才を披露した。そのとき初めて私はネタが一新されているのを知った。1分30秒という短い時間にECOな要素をきっちり入れていた。よく調べたなあと感心した。新エネの仕組み、パークアンドライド、待機電力・原発などなど。よく調べないとできないネタばかりだ。少ない練習時間でよくぞここまでできました。子どもたちに拍手である。
2006.11.25
コメント(0)
-

リヤカーマン効果の1904
リヤカーマン永瀬忠志さんの特別番組があった。昨日のことである。見られましたか。残念ながら私は見れなかった。我が家にはテレビアンテナがないのである。6年1組の子らは、ほとんどの子が見たようだ。録画をしている子もいた。今朝の毎日新聞の3面下にも永瀬さんが登場していた。「よっしゃ!」と気合いの入った永瀬さんがリヤカー牽いて振り向いている。毎日新聞社から『リヤカーマン』を出版されたようだ。おめでとうございます。リヤカーマン「昨日、テレビ東京系 全国ネットで 2時間スペシャル 大反響! 」(毎日新聞2006.11.24)その影響だろう。昨日この「電脳掲示板」の訪問者(アクセス)数が1904もあった。今日は1730。Googleで「リヤカーマン」を検索すると3番目にこの「電脳」が出た。Yahooでは2番目だ。驚きました。10月27日永瀬さんの2回目の特別授業は延期となった。延期となった特別授業をいつ行うか。学期末は予定が詰まりぎみ。それ以上に永瀬さんの予定はぎっしりだろう。果たして特別授業はできるのか。箕面での講演会の話もある。永瀬さんに相談しよう。
2006.11.24
コメント(0)
-
どろだんごは子どもの手がよく似合う
北小の「かんたろう祭り」に娘2人と参加。たった100円でたっぷり遊べた。焼き板・フランクフルト・豚汁・ポップコーン・飲み物・…。全部ひっくるめて100円だった。どろだんごを作った。おそらく30年ぶりであろう。小学生の時はよく作ったものだ。こんなの簡単と思いきやなかなかうまく作れない。え、こんなはずでは…。少々アセル。ぎゅっと握る。するとひび割れしてくる。子どもの頃に比べて握力が強い過ぎるのだ。またまたアセル。しゃがんだままの姿勢だから足腰が痛くなる。トホホホである。横にいる娘たちの方が断然うまい。しかたないから長女に代わってもらった。慣れた手つきで上手に作る。うまいもんだと感心した。どろだんごは子どもの手に合っていますね。ところで、今日リヤカーマンの特別番組があった。うちのテレビにはアンテナがないので見れなかった。どなたか録画されていませんか。
2006.11.23
コメント(2)
-
字が丁寧でない場合
字を丁寧に書く。朝一番に黒板にそう書いた。もちろん丁寧な字で。子どもたちには、字を丁寧に書くよう話した。おおむね昨日の記事の通り。百問わり算を毎日1分30秒ほどで終わっている子らも、今日は2分前後だった。字を丁寧に書くよう意識したからだ。それでいい。百問わり算は3分以内にできれば合格だ。私の学級では1人を除いて全員3分以内でできる。(その1人とは私のことです)数名、字が丁寧でなかった。そう言う場合はどうするか。簡単である。やり直しをさせる。ただそれだけだ。「○○さん」「はい」「名前が丁寧に書けていません。 丁寧に書き直しなさい」「はい」これで丁寧に書いてくる。どの子も意識すれば丁寧に書けるのだ。学習帳・連絡帳・豆日記。字を丁寧に書こうと意識していた子どもたち。これからもずっとこれでいこう。本日の時間割1理科 水溶液の実験2里科 水溶液の実験3算数 分数のかけ算「たしかめよう」4国語 「マザー=テレサ」読解問題5社会 前試験「明治時代2」放課後 研究授業研究討議会
2006.11.22
コメント(1)
-

上手な字を書くコツ
字が乱雑だ。「丁寧に書こう」という意識が少ないのだろう。子どもたちの字を見ていると、そんな字に出くわすことがある。丁寧に書ける子は確実に増えてきた。全員、1学期よりは丁寧に書けている。だからこそ、乱雑な字が目立つ。卒業文集に取りかかる時機になってきた。しめ切りは年内だ。先輩職員に聞くと、この作業が大変らしい。何回も書き直させることもあるようだ。そのときになって慌てないように、普段から丁寧な字を書く。連絡帳・学習帳・豆日記・感想文・試験など。丁寧に書く意識を持たせる。もちろん私も。「上手な字」の大原則1 縦画はまっすぐ、横画は右上がりに2 起筆でアクセントをつける3 字の中心をつかめば、崩れないし、曲がらない4 点画を確実に接する5 のびやかに大きく書く山下静雨『もっと「きれいな字!」が書ける本』(20頁)より
2006.11.21
コメント(5)
-
ECO漫才に注文
Wヤングの平川幸男さんに絶賛された子どもたちのECO漫才。確かに抱腹絶倒であった。しかし私としては、もう少しECOな要素を入れて欲しい。でも1分ではなかなか難しい。私がやったECO漫才は1分30秒だった。そこで、子どもたちに注文。「ECO漫才はECO発信の一部です。 もう少しECOな要素を入れましょう。 そのため漫才の時間を30秒延長します。 1分30秒のECO漫才です」今週25日(土)の学習発表会で、子どもたちはこのECO漫才を披露する。
2006.11.20
コメント(1)
-
お薦めの家族映画(2)
昨日お薦めの家族映画をお尋ねした。「あなたが観てきた映画の中で、家族で楽しめるお薦めの映画はありませんか。あれば、ぜひ教えてください。よろしくおねがいします」すると、早速4人の方からお便り(コメント)を頂いた。うれしい。ありがとうございます。今度の日曜日に貸しビデオ店で探してみようと思う。もしまだ他にもあるぞ、という方、ぜひここのコメント欄に書き込んでください。(赤線部分はクリックできます)心に残るいい映画を観ると自分の世界が広がる。家族で観ると共通体験ができその後の話し合いも実に楽しい。そんなことを実感しております。
2006.11.20
コメント(0)
-

お薦めの家族映画
休日に家族で映画を観ている。週に1回は貸しビデオ店に行っている。105円で1週間借りれるからありがたい。今日は「キッド」を借りた。私も主人公と同じ40歳。まだまだ夢を持ち続けて人生を楽しもう。観て良かった。10歳と8歳の娘たちも楽しめたようだった。今度は何を借りよう。実は私、映画には疎い。映画よりも本、の人生を歩んできた。映画に費やす時間がもったいないと思っていた。ところが、家族で1つの映画を一緒に観る、というのはいいことのように思えてきた。そこで、おたずねしたい。あなたが観てきた映画の中で、家族で楽しめるお薦めの映画はありませんか。あれば、ぜひ教えてください。よろしくおねがいします。【われわれ家族が最近観た映画】 ネバーランドビッグ・フィッシュ オリバー・ツイスト
2006.11.19
コメント(4)
-
箕面スパに三顧ならぬ五顧の礼
先月、箕面スパーガーデンにポスターとチラシの紹介をお願いした。「エコロジストたちの詩」のポスターとチラシである。事務所の方は快く了承してくれた。毎日、箕面スパーガーデンに行くが、ポスターもチラシも見あたらない。去年は玄関前にポスターを掲示してチラシも置いてくれたのに…。1週間後、ポスターとチラシを持って再び事務所を訪れた。「ああ、これこの間のポスターですね」「少し手直しした新しいポスターです」「じゃあ、差し替えておきますね」「よろしくおねがいします」事務所の同じ方とこんなやりとりをした。はて、差し替えるということはどこかに掲示してくれているのか。私は毎日箕面スパーガーデンに行き確認しているが、掲示されてはいないのだ。次の日も次の日もそして次の日も、掲示されていなかった。それから1週間後またまた事務所を訪れた。「ポスター、どこにも掲示されていないようなのですが…」「え、そうですか。担当者に渡したのですがね。 今その担当者がいないので、また言っておきます」「よろしくおねがいします」しかし次の日もポスターは掲示されていなかった。もちろん、チラシも置いていなかった。それから4日後4度目の事務所訪問。今度はその担当者がいた。「前、頼んでおいたポスターとチラシ、どうした?」事務所の同じ方が担当者にそう言った。「え、ああ、あれ…」そう言って机の一番下の引き出しから、ポスターらしきものを取り出した。事務所の方は少し慌てたように、「ああ、このポスター、去年と同じところに貼っておきます」「よろしくおねがいします」4回目のこの日も私は終始にこやかにお願いした。以前の私なら激昂していただろう。ところが次の日、ポスターは掲示していなかった。すぐに事務所に行く。これで5度目だ。れいの事務所の方はいない。しかし担当者がいた。昨日の今日だから、担当者は私を覚えていた。「箕面エコロハスのものですが、ポスターはどこに掲示していただきましたか」「昨日、営業の方に回しましたよ」「私は、ここの会員で毎日スパーガーデンに来ているのですが、ポスターはどこにも見あたりません」会員証を提示すると、担当者はすぐに営業部の方へ走った。他の授業員の方々も、「おかけになってお待ちください」「申し訳ありません」などと親切に対応してくれた。ここでも私は終始にこやかである。ぜんぜん怒ってなんかいない。なのにみなさん、大あわてであった。事務所を出てスパーガーデンに入ると、営業部の方がポスターを貼ってくれていた。ありがたいことです。ジムで筋力鍛錬をし温泉で汗を流す。私が帰る頃には、ポスターは出口付近に掲示してくれていた。チラシも3カ所に置いてくれていた。1つは何と受付に置いてくれていたのだ。私は箕面スパーガーデンが大好きだ。
2006.11.18
コメント(1)
-

平川幸男さん直伝の漫才授業
Wヤングの平川幸男さんが昼休みに来校された。漫才授業は6時間目に行う。少し早めに来てくれた平川師匠。緊張と期待で、そわそわわくわく状態の子どもたち。5時間目のはじめ、「5分間だけ、ネタ合わせの時間をとります」私がそう言うと、「よっしゃー」と子どもたちは歓声を上げた。やる気満々である。子どもたちは、一週間後の11月25日(土)、学習発表会でECO漫才を披露する。その漫才を事前に、平川師匠に見ていただき指導を受ける。これが今回の漫才授業の趣旨だ。 15組の漫才を披露する予定であった。しかし数名の欠席があり14組の漫才となる。相方が欠席したコンビには急遽、同じ班の子が相方となった。1人で2回漫才をした子が3人もいる。今日になってほんのわずかな時間にネタを覚えた3人には驚いた。 子どもたちが漫才をした後、平川師匠が指導助言を行う。「声を大きくしてはっきりとしゃべったらもっといい」「泣きまねなどの動作は大げさに」「台詞を忘れないために、もっと練習しよう」「ネタがとってもよかったね」「○○さんの突っ込みがとってもよかった」「コンビ名がとても面白い」(などなど)子どもたちの漫才の後、平川師匠のご指名により私も漫才をした。相方は同僚のM先生。台詞をM先生に渡したのが1週間ほど前だった。「これなら、できそうです」そう言って、私と漫才をするのを快く引き受けてくれたのだ。ありがたい。実は、M先生、当初、漫才をすることにかなり抵抗があったようだ。それはそうであろうと思う。そこで負担のないネタを考えたのである。前日にネタ合わせを職員室でやろうとした。「原田先生、明日、漫才ですよね」M先生が自らそう言ってくれたのである。ところが何と私は自分が考えたネタを覚えていなかった。「ごめんなさい。明日やりましょう。 必ず覚えてきます」そして今日の昼休みに1回だけネタ合わせを行った。たった1回である。 前回、前々回、私は平川師匠と漫才をした。それぞれ1時間近くネタ合わせを行った。前回は夜の某小学校。前々回がなんばグランド花月の楽屋。それなのに、今回はM先生と1回きりのネタ合わせだった。平川師匠に知れたら叱られそうである。「原田先生、漫才、なめたらいかんぜよ」と。ところが何とかM先生と漫才はできたのだ。平川師匠にも、「さすが先生、声も大きく分かりやすい。 最後のオチもよく考えていた」と褒められた。子どもたちの漫才・我々教員の漫才と続き最後はプロ。Wヤングの漫才をビデオ視聴した。 抱腹絶倒のロボット漫才に子どもたちは大爆笑。文字通り、腹を抱え笑い転げる子どもたちである。質疑応答では、子どもたちから絶え間なく質問が続いた。「お弟子さんは何人いますか」「漫才をやろうとしたきっかけは何ですか」「漫才をしているときネタを忘れたことはありますか」などなど。平川師匠はそれぞれの質問に丁寧に答えてくれた。子どもたちは熱心に聞いていた。特に、ネタを忘れたときの切り抜け方に多くの子が、「ああ、そうやるのかあ」と大いに納得していた。身を以て体験した子どもたちだから平川師匠の言葉が身にしみる。これで来週の学習参観でのECO漫才にさらに磨きがかかった。1組1分の漫才であったが、30秒上乗せしても大丈夫だ。またもや楽しみができました。
2006.11.17
コメント(2)
-
「もうじき卒業なんだなあ…」
1時間目から6時間目まで卒業アルバム用の撮影の1日であった。個人写真・班写真とつづき、授業風景やクラブ活動の撮影もあった。放課後は、卒業アルバムや卒業文集の件で打ち合わせもした。子どもたちが毎日書いている「豆日記」がある。2人の子がそれにこんなことを書いていた。「もうじき卒業なんだなあ…」ばたばたしていた1日であったが、これを読み、そんなんだなあと思った次第。本日の時間割1国語 (個人撮影) 先習い熟語など2家庭 1日の食事 3理科 水溶液の性質4理科 水溶液の性質5社会 「小村寿太郎」6クラブ
2006.11.16
コメント(0)
-
平川幸男さん直伝、とっておきの漫才練習場
明後日は漫才授業。Wヤングの平川幸男さんが来校する。子どもたちの漫才を全て見てくれる。1組1組に指導助言もしてくれる。15組の漫才コンビは緊張の舞台に立つわけだ。平川さんは芸能生活50周年の超ベテラン漫才師。吉本の芸人さんの中で今最も長い芸歴の持ち主だ。その超ベテラン漫才師の平川さんに自分たちの漫才を見てもらう。緊張の舞台にならざるを得ない。しかし子どもたちには思い切ってやって欲しい。思い切るとは、思いを切ること。緊張の思いを切って精一杯の漫才を披露して欲しいのである。そこで今日は運動場で漫才の練習をした。思いっきり漫才をするのには最高の場所だ。実は、私も3年前、某小学校の運動場で漫才の練習をした。相手は、平川さん。3年前の漫才授業で平川さんと漫才をすることをすすめられたのだ。正直、いやだった。というよりも、恐れ多いことだった。だって、そうでしょ。あのWヤングの平川さんと漫才をするのですよ。初代Wヤングの漫才を私は小学生のときにテレビでよく見ていた。テンポのいいシャレづくしの漫才に笑い転げていたものだ。相方の中田さんが亡くなったときの新聞記事も見た。目頭を押さえる平川さんの顔写真が大きく掲載されてもいた。そんな有名な平川さんと漫才をするなんて思っても見なかった。恐れ多いことではあったが、私は漫才をすることにした。思い切ったのだ。漫才の時間は2分。途中、子どもたちの暗唱を挟むので、正味のしゃべりは1分ほどの漫才である。ネタは私が作ることになった。Wヤングの本を読んだり、CDを聞いたり、ビデオも見たりした。そうして、A4の紙に2枚のネタを完成させた。早速、平川さんに見てもらった。「長いでんなあ。 この半分でええんとちゃいまっか」平川さんの指示に従いA4の紙1枚にネタを書き直した。ネタを覚え、平川さんに漫才の稽古をつけてもらった。某小学校の夜の運動場であった。「原田先生は声がちいさい。 そんなんじゃあ、後ろのお客さんまで声が聞こえませんで」そう言われ、運動場の先の方に声を届かすように大声を出した。正味1分の漫才を何回も何回も繰り返した。読み書き計算の徹底反復と同じである。1回終わるたびに、平川さんが助言をする。助言が終わると、「ほな、もう1回、いきましょか」こうして1時間は稽古をつけてもらった。たった1分の漫才にこれだけの時間をついやすなんて考えてもみなかった。おかげで、ネタがすっかり身に付いた。稽古後の帰り道でも平川さんとネタ合わせができるくらいになっていた。漫才を甘く見てはいけない。そのときそう実感した。そんな話を運動場に出る前、子どもたちにした。子どもたちは真剣に聞いていた。運動場に出ると、どの子も大きな声で練習をした。恥ずかしがる子なんて全くいない。全員もれなく漫才に打ち込んでいた。いよいよ明後日だ。
2006.11.15
コメント(0)
-
寒くない日の珍客
帰宅すると娘がうれしいそうに珍客を紹介してくれた。「お父さん、小鳥!」「え?」「すずめ!」かごの中に1羽の雀がいた。「捕まえたん?」「ううん」「どうじたん?」「帰ってきたら、薪ストーブの中におったの」「ええ?」「煙突から入ってきたんちゃう」「ほー」先日、火入れ式を行ったが、この3日間は薪ストーブに火を入れていない。寒くないですからね、11月というのに。あわてんぼうのサンタクロース雀。よく見るとススで所々黒い。火がついていなくて良かったです。
2006.11.14
コメント(0)
-
漫才のネタ作りを楽しむ6年生
漫才授業まで後4日。ようやく今日、ネタ作りを行う。次の3点だけを指導する。1 1分前後の漫才にする。 前後は5秒間。2 笑えるネタを1つ以上は入れる。 下品でなく、上品な笑いを。3 ECOな情報を入れる。 ECO発信だから当然だ。その後「漫才ネタ用紙」を配る。子どもたちはそれに台詞を書いていく。隣同士和気藹々と歓談しあい書いている。決して騒がしくない。30名もれなく漫才ネタを楽しんで作っているのだ。実にいい光景である。私はうっとりしつつ子どもたちの活動を眺めていた。本日の時間割1国語 「愛を運ぶ人 マザー=テレサ」連れ読み2総合 英語5回目「お昼は何を食べますか」3算数 分数のかけ算4総合 ECO発信 漫才のネタ作り5国語 3色読み→意味調べ6社会 明治時代(2) 作業用紙 (エネルギー学習)
2006.11.13
コメント(0)
-
火入れ式前の挨拶まわり
やっと火入れ式。実はこの日を待っていた。文字通り温暖化の影響で、この冬はまだ薪ストーブに火を入れてなかったのだ。火を入れる前に、ご近所にごあいさつ。聞くところによると、煙突から出る煤(スス)が洗濯物についたことがあったらしい。「たまにですけどね」ご近所の奥さんはそう笑って話してくれた。去年から初めて使った薪ストーブ。乾燥した広葉樹ではなく、針葉樹の木材を薪に使ったこともたびたびあった。針葉樹は油が多く煤が出るのだ。「ごめんなさいね。 でも今年は大丈夫です。 十分に乾燥させた広葉樹の薪ですから。 よろしければ今度家に来てください。 薪ストーブの火って、いいですよ…。 でもまた何かあったら言ってくださいね」
2006.11.12
コメント(1)
-

ダグラス=ラミス『憲法は、政府に対する命令である』
憲法を変えたい人がいる。権力者は変えたくて仕方ない。憲法は権力者に対する縛りでもあるという。まさしく「憲法は、政府に対する命令である。」。憲法は、政府に対する命令である。確かに、日本国憲法は「押しつけられた憲法」である。しかし「憲法とはそもそも押しつけるものである」(65頁)。問題は「誰が誰に何を押しつけたのか、ということである」(66頁)。今の憲法が変えられるとどうなるのか。今まで当たり前であったことが当たり前でなくなることも起きるに違いない。
2006.11.11
コメント(0)
-

パント末吉さん特別授業「パント末吉のエコロハス」
環境問題を笑って伝えるメッセンジャー。 パント末吉さん。まずはサックスを演奏しての登場であった。間近で聞く生演奏の迫力に子どもたちは圧倒された。つぎにパントマイム。見えない壁や窓にビックリ仰天。パントさんの一挙手一投足に注目する子どもたちである。これでもうつかみは完璧。たらこ先生・バイトおじいさん・プーママに変身。 「エネルギーをムダに使って顔を汚くする方法は…」たらこ先生のアイロニカルな授業である。そして某洗顔剤に隠された暗号を解読。「シミ・ソバカス・ミルミル・デキル」 バイトおじいさんでは、洗濯の仕方を選択。合成洗剤よりも炭の方が水を汚さず洗濯できる。プーママではゴミ問題の入り口を学べた。 パント末吉画伯の描いた本が間もなく書店にも並ぶ。ぼくを救ってくれたシロ
2006.11.10
コメント(0)
-

静粛のテニスボール
静かだからうるさい。6年1組の授業中はこんな感じだ。子どもたちは静かに勉強する。私語など皆無だ。それゆえうるさいのだ。ギーギー、ガーガー、と。原因は椅子。これが実にうるさい。静かな教室だから際だってうるさい。そこで登場したのがテニスボール。「使えなくなったテニスボールがあれば持ってきて」そう呼びかけると、Tさん・Oさん・Uさんが持ってきてくれた。これを1つ1つカッターで十字の切り込みを入れる。なかなか力とコツのいる作業だ。危なっかしいので子どもたちには頼めない。だから私一人でもくもくと作業をした。2回ほどカッターの刃が親指を直撃した。痛かった。試しに4号車(机の縦並びの4番目)に全部つける。全くつけていない2号車と比較をする。「2号車の人、立ってください」ギーギー、ガーガー。やはりうるさい。「4号車の人、立ってください」……(無音)。「オオ~」教室中がどよめいた。思った以上に音が出ない。これはいい。全ての椅子にこのテニスボールがつくと教室は相当静かになる。あと70個なのだ。
2006.11.09
コメント(0)
-
伝説の超ベテラン漫才師が小学生に漫才の基礎基本を伝授
今年度は大阪市の環境教育実践校でもある。テーマは「ほんまもんに学ぶエコロハス」。現場で活躍されている「ほんまもん」から「ほんまもん」を学ぶ。その学びをエコロハスにつなげようという実践だ。6年生を中心に現在実践中である。これまでの経過をふりかえる。1 「温暖化」「エネルギー問題」「エコロハス」原田誉一2 「エコライフはじめの第一歩」平石年弘さん 3 「エネルギー問題と未来の新エネルギー」落合雅治さん4 「エコロジストの詩 南米・欧州編」松本英揮さん5 映画「デイ・アフター・トゥモロー」鑑賞そしてこの間、環境文庫を開設した。ECO発信の班編制も11月1日にした。これまで学んだECOな学びを伝える取り組みがECO発信だ。1班 新エネルギー班2班 環境先進国3班 省エネルギー4班 森林破壊5班 エネルギー問題6班 生物種の絶滅7班 地球温暖化人に伝えるにはどうすればいいか。学んだことをそのまま話してもなかなか伝わらない。関心のない人が対象ならなおさらだ。そこで伝え方をも学ぶ。ほんまもんから。まずは、パントマイム。エコロマンことパント末吉さんから学ぶのだ。パントさんは環境問題を笑いで伝えるメッセンジャー。子どもたちの感性を大いに刺激してくれるだろう。パントさんは明後日10日(金)に来阪する。そして、漫才。洒落づくしという伝説の漫才を確立した漫才コンビ。Wヤングの平川幸男師匠を講師に招く。平川さんは今年で芸能生活50周年を迎えた。伝説の超ベテラン漫才師だ。その記念の年に本校で漫才授業を行う。日時は2006年11月17日(金)14:40~15:25。場所は本校(大阪市立新東三国小)第2音楽室。実は今年度の子どもたちはもれなく漫才ができる。先月ためしに日本史漫才を全員に課したがお見事だった。漫才をよく知らないと言っていた子ものりのりであった。さすが大阪の子だ。今度の漫才はECO漫才。ECO発信の第一弾となる。
2006.11.08
コメント(1)
-

学校映画館で「デイ・アフター・トゥモロー」
学校で「デイ・アフター・トゥモロー」が見れた。デイ・アフター・トゥモロー 特別編エネルギー教育の予算で購入したDVDやスピーカー等を使う。広い講堂で音響効果が予想以上にいい。講堂がちょっとした映画館になった気分だ。2時間ほどの映画だが、子どもたちは最初から最後まで食い入るように見た。私は3回目の鑑賞だがやはりしっかり見れた。新たな感動もあった。観賞後、子どもたちの顔がとてもよかった。目がパッと開き澄んでいた。浄化されたといったらいいだろうか。DVDを使って私が行った初めての映画会。来週はいよいよ「東京原発」だ。東京原発
2006.11.07
コメント(0)
-
子どもが熱を出したとき
「ただいま」「……」いつもなら「おかえり」と元気な声がするが、今日はそれがない。部屋の奥では小2の次女が寝間着姿でぐったりしている。39℃の熱を出し早退したと連れ合いから聞く。「インフルエンザかも…」こんなときはとにかく静かに休ませることだ。無理に食事をとらせる必要はない。喉が渇けば倉田水を飲ませる。2,3日安静にする。それでも良くならないときに病院にいけばいい。「しんどいなあ。 今体の中で、悪いウイルスを免疫さんがやっつけてくれている。 だから体がこんなに熱いんやで。 今はしんどいけど、寝ているうちにだんだんよくなるよ。 明日にはだいぶよくなって、明後日にはもうなおるから安心しいや」娘のおでこに手を当てながらそんなことを話した。娘も少しは安心したようだった。
2006.11.06
コメント(0)
-
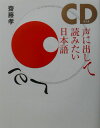
荒井健一著『2つの発問で組み立てる授業』(フォーラムA、2006)
荒井健一著『2つの発問で組み立てる授業』(フォーラムA、2006)を読了した。1時間ほどで一気に読める。テンポよく流れる文体だから誰でも速読できそうだ。それにこれを読めば、誰でも授業ができそうな気になる。よしこれでいけるぞ、という気にさせてくれるのだ。その秘密が2つの発問。マルチ発問とセレクト発問。拡散的発問と集中的発問である。オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンともいう。この2つの発問で次のように展開すれば誰でも授業はできそうだ。【序】マルチ発問をする。 (補助的発問や音読などもする。)【破】セレクト発問をする。 (理由の発表、討論などもする。)【急】セレクト発問の結論を出し、学びを得る。 (実験や教師の解説があり、今日学んだことを書かせる。)(157頁)確かに「誰でもできる」とはいうものの授業はそんなお気軽なものではない。教師という存在が、学びのメンター(賢者)となるには、主人公である子どもたち以上の努力がやはり必要なのです。1つの解をせまるセレクト発問をする以上、教師は常に学び続ける必要があります。(99頁)これは主に【急】にいえることである。また【序】や【破】でもさまざまな教育技術を駆使する場合がほとんどだ。しかし実はそういうところまで本書はきっちり解説してくれてあるからありがたい。新任の先生はもちろんベテランといわれる先生方にもぜひ読んでもらいたいオススメ本だ。私はあまり本を買わない。資料的価値のある場合だけ本を買う。この本の前は夏に買った齋藤孝さんの『CDフ゛ック声に出して読みたい日本語』だけだ。明日の授業や次の時間の授業の展開をどうしよう。そんなときはこの本をパッと開いて授業展開を構築できる。速読しやすいからそういうこともできるのだ。実はこの本はまだ市販されてはいない。来年3月、私の本と同時に発売される予定である。詳細はここをクリックして欲しい。CDフ゛ック声に出して読みたい日本語
2006.11.05
コメント(1)
-
長女の誕生日に10年前と後をしみじみ思う
長女が10歳の誕生日を迎えた。ああ、生まれてから10年たつのかあ。長女の出産に私は立ち合ったが、そのときのことを今でも鮮明に覚えている。病院ではなく助産院で長女は生まれた。経験豊富な産婆さんお一人だけに取り出してもらった。私はすぐそばで連れ合いを励ますだけだった。そのときの話を娘たちに話して聞かせる。長女は神妙な顔だった。もう10年たつと長女は成人。10年前と10年後のことを思う父親なのだ。
2006.11.04
コメント(0)
-
思いっきり睡眠で再生し秋の夜長をエコロハスの面々と飲み通す
昨日は夜8時過ぎに寝た。起きたのが今朝6時過ぎ。思いっきり眠れた。おかげで数ヶ月間の疲れがスッキリとれた。体が細胞から再生された感じだ。ところで今日は文化の日。娘2人と図書館に行く。しかし本日は休館日とのこと。文化の日に図書館が休館だとは何とも解せない。午後は娘の誕生日会。誕生日は明日なのだが今日にしたようだ。友達8人が来てにぎやかな誕生日会となった。私は皿洗いやビデオ映画会など普段ご無沙汰の家族奉仕をした。夜8時からは箕面エコロハスの集い。昨日寝た時刻からの開始となったが全く眠くない。思いっきり寝たから当然である。Mさん・Tさんご夫妻・Oさん・Hさん・Kさん。箕面市在住の箕面エコロハスの仲間が我が家に勢揃い。夕食後の8時からの方が集まりやすいようだ。今回は12月9日(土)の松本英揮さんの講演会に向けての集まり。ポスター・チラシ・前売り券の分担をする。FMタッキーで流すラジオCMの収録もした。20秒のスポットCMで、Oさんの原稿を各自一言ずつ収録できたのだ。日本酒に始まりウイスキー4種を味わいつつ秋の夜長を語り合う。気がつけば夜中の11:45。私はそれでも眠くはなかった。泥酔することなく頭も冴えていた。片づけや皿洗いなどもバッチリこなすことができた。
2006.11.03
コメント(1)
-

アウロワックスで心地よい教室が増えるだろう
教室の油びき。学期末の大掃除では恒例である。しかし私は、これをやらない。一斗缶に入ったあの合成樹脂ワックスが苦手なのだ。油びき後の教室に入るとクラクラする。授業どころではない。おそらく石油系化学物質の影響だろう。ホルムアルデヒドやトルエンといったものが放出されているのかもしれない。その代わりに私は6年ほど前からアウロを使ってきた。学年末の大掃除のときに子どもたちとアウロで床を磨いている。AUROフロアー用ワックス0.5L通常のワックスのようなテカリはない。しっとりとした感じの床になる。そもそも油びきとは、木に必要な湿度と油分を与え、木の美しさを長持ちさせることにある。ゆえに油びきやりましたというあんなテカリなんて必要ないわけだ。アウロ後は柑橘系の爽やかな香りがほのかに教室を包む。石油系のくらくら臭よりも私は断然この方が体に合う。さて、本校ではじわじわとアウロの良さが知られてくるようになった。私が使っていると何人かの先生がそれぞれの教室で使うようになったのだ。最近では公費でも買ってもらえるようになった。そして今月、とうとうあの石油系一斗缶ワックスが底をつきた。これを機に本校ではアウロでいこうという機運が高まっる。そして今日の職員会議。アウロでいきましょう、ということになった。異議なし、である。これで私もよその教室に行きやすくなりました。
2006.11.02
コメント(4)
-
汗と涙の2時間目
「先生、玉ネギ、炒めて…」「え? うわっ! 忘れた~」家庭科室の戸を開けた瞬間、CCLのTさんにそう言われ、大いに慌ててしまった。今日と明日の5年生の「総合」は「カレーで始まる国際理解」。インドカレー作りを通してインドの文化に触れる学習である。講師はカレー大王でDJかつ映画評論家のサニー=フランシスさん。本校では5年前からこの「カレー…」を5年生の総合で行っている。「総合」担当の私は毎年CCLのTさんと連絡を取り合ったり、オルターから食材を調達したりもしている。毎年つぎの手順で「カレー…」を行う。1時間目 玉ネギを炒める2時間目 サニーさんの抱腹絶倒面白インド文化講話を聴く3時間目 インドカレー実習4時間目 インドカレー実習後、試食もう今回で5度目であるから…、という慣れが生じたのだろう。事前に玉ネギを炒めておくのを忘れてしまったのだ。不幸中の幸いというか、2時間目、6年1組は理科。理科は専科担当だったから、私は空き時間。この空き時間に貯まった書類仕事を片づける予定ではあったがそんなことはしていられない。サニーさんが5年1組で講話中の2時間目。CCLの2人のTさんと私の3人は家庭科室で玉ネギ40個と格闘していた。ぼろぼろ涙を流し玉ネギを切る。大量に切った玉ネギを大急ぎで炒める。私は2つのフライパンを両手に持ち小刻みに動かしつつ炒めた。コーヒー焙煎7年の技術とアームカールで鍛えた腕力で何とか大量の玉ネギを炒めたのだ。3時間目、無事、家庭科室ではカレー実習が行われた。私は教室にもどり算数の授業を始めた。今日から11月というのに汗をかきつつの授業であった。本日の時間割1体育 走り幅跳び2理科 大地をさぐる3算数 立方体に色をぬろう4国語 音読 読解基礎問題5総合 修学旅行まとめ ECO発信班編制 席替え
2006.11.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- ★資格取得・お勉強★
- 国の予算と世界のお金の流れ!税金・…
- (2025-11-29 00:00:15)
-
-
-

- 懸賞フリーク♪
- 第36回 ヤマザワ レディースサロン …
- (2025-11-28 22:43:47)
-
-
-

- ひとりごと
- 丸山純奈 Sing & Sing- Live at WWW X
- (2025-11-28 21:10:35)
-






