2008年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
肉離れ寸前
5時間目は合同体育。子どもたちとトラック10周を走った。気負うことなく同じ調子で走ったのだが…。走り終わると左脚ふくらはぎに違和感を覚えた。去年やってしまったあの肉離れを思い出す。まさに同じところである。まあこれくらいは大丈夫。そう思い今度は子どもたちと長縄をする。3回目で違和感が痛みに変容した。イテテテテ。帰宅するときは少々左脚を引きずるようにしか歩けなかった。肉離れというのは、急激な運動でなくても、持久走のような緩い運動でも起こりうる危険性があるのだなあと身をもって体験した次第。今日の学びである。
2008.01.31
コメント(0)
-
まずは足元から
教室や廊下にゴミが1つ落ちている。ついこの間までなら決して誰1人として拾わない。しかし今ならどうだろう。3時間目に彫刻刀で版木を削った。授業が終わると子どもたちは机の上にかためておいた木くずをゴミ箱にきちんと捨てていた。中には、床に落ちている木くずを拾う子もいる。それだけではない。箒や塵取りを持ち出し掃除を始める子も数名いる。自分のところだけでなく友達のところも掃除している。月曜日の家庭科の授業で、ゴミ拾いの話をした。ゴミを拾う行為そのものは決して難しい行為ではない。しゃがんでゴミをつまみ拾い上げそれを運搬しゴミ箱に捨てるだけである。屈伸運動も1回だけだから体力的にしんどくなるはずはない。ゴミも軽い物がほとんどだ。実に簡単な行為なのである。簡単な行為ではあるのだがほとんどの子は自分からすすんでゴミを拾おうとはしない。人に言われてはじめてしぶしぶするのが残念ながら今の子どもたちの大部分だろう。いやいや子どもたちだけではない。大人も含めて圧倒的多数の人々が実はそうなのではないだろうか。まあそんな話を私の実体験をふまえて話したのである。そんな拙い私の話だが何人かの子には通じたのだろう。それからごみを拾う子どもたちの姿をちょいちょい見るようになった。最近は新聞などでも環境問題がよく取り上げられるようになっている。いい傾向だ。ところが足元にあるゴミを拾う人はどれくらいいるだろう。「環境問題は、地球規模で考えて、実践は足元から」最近読んだ本の中にそのようなことが書かれてあった。いい言葉だ。
2008.01.30
コメント(0)
-

室温8℃の暖かい朝
朝起きると室温は8℃。どうり、寒くないはずだ。久しぶりに迎えた暖かい朝3時半である。このところこの朝の室温が6℃を超えることがなかった。昨日は5℃であった。ところが教室の室温が8℃だと寒さを感じる。子どもたちが登校し太陽が昇り出すことには10℃を超え暖かくなる教室だが、今日は雨で室温の上昇が見込めそうにないのでガスストーブで暖をとったほどだ。同じ8℃でも暖かく感じたり、寒く感じたりするのはなぜなのか。この体感温度の違いは何なのか。木造作りとコンクリート造りの違いによるのかも知れない。今日は5年生の特別授業で「いい家塾」の釜中さんが来校されていた。釜中さんならおそらくその考えを支持してくれるだろう。もう一つは「ねむるんば」のおかげであろう。全員プレゼント付き!シーツの下に敷くだけで、驚くほどの保温効果と心地よい快眠の世界へエンバランス 健康快眠シート「眠夢波」(ねむるんば) ホワイトバランス株式会社 【消費税相当額サービス】これを布団にしいて眠ると、凍えそうな寒い夜も直に暖かくなる。背中からじわ~っと我が体温が上昇してくるのを感じる。ゆえに朝起きると湯上がり状態に近い感じでもあるのだ。電気も使わず暖かくなるのだから実に不思議な敷物ではある。この生地でできた衣服などがあれば無敵だろうなあ。
2008.01.29
コメント(2)
-
3日目から美味くなる
金曜日に連れ合いがキムチを漬けこんだ。私はスルメイカ2杯で塩辛とスルメの仕込みをした。翌日土曜日にキムチを試食。少々塩味がしたが美味しくいただいた。塩辛は試食せず箸で突き刺すようにしつつかき回す。スルメはそのままデッキの物干しに洗濯ばさみで干したまま。翌々日の日曜日。キムチの塩味が和らぎ昨日より格段に美味い。塩辛は少々塩味がたりないので今度は岩塩を補給しまた箸でかき回す。スルメはそのまんま。雪や雨が降っても我がデッキには昨年作った屋根があるので心配無用。そして3日目の今日。キムチは実に格調高い本場の味である。塩辛はもうたまりません状態でうまいのなんの。次女も喜んでごはんと一緒に食べていた。スルメはまだ半生状態。みぞれ降る中を1枚だけ取ってきて薪ストーブの中で焙る。あつあつを裂いて食べる。そのままでも美味いのだが今度はやはりマヨネーズ醤油で味を付ける。これはもう最高の肴である。本日とうとう封を切ったマッカランとも抜群にあった。娘たちも美味しい美味しいと食後のおやつとして食べていた。キムチ・塩辛・スルメは3日目から美味くなるのだなあ。明日はもっとうまいのだろう。フフフフフ…。
2008.01.28
コメント(0)
-
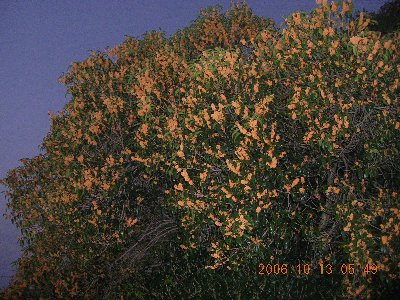
消えた雑木林
道を隔てたすぐ西向かいの雑木林がなくなった。もう悲しくてたまらない。一昨日から木を切っているということを連れ合いから聞いた。間伐でもしているのだろう。そのときはそう思っていた。昨日は朝からチェーンソーの音がけたたましく響いていた。どうやら全部伐採するようだ。マンションでも建つのか。「売りもんにならんから切るそうやで。 昨日そう言っとたわ」近くを通った知り合いの植木屋さんはそう教えてくれた。確かにこの雑木林には売り物にならないくらい巨大な金木犀がある。金木犀といえばせいぜい3mほどの高さだが、ここの金木犀は5m以上はある。10月ころになると甘い香りを存分に放ってくれる。近所の人々もそれが楽しみだったのにと目を潤ませていた。 「もう鳥がこなくなるなあ」Hさんはそう言って私と一緒に切られていく雑木林を見ていた。作業は2日間におよんだ。昨夜はやしの例会から帰るといつと違う風景に違和感を覚えた。床につくと朝のチェーンソーの音が耳鳴りのように響いてきた。そして今朝。すっかり変わった風景にため息をつく。 野鳥が1羽、切られた枝の上をぴょんぴょんとんでいた。巣でも探しているように見えてしまう。
2008.01.27
コメント(0)
-
学びの多いサークルはやしの例会
大阪教育サークルはやしの例会に参加。今年はじめての例会だ。場所はいつもの街山荘。玄関付近がおしゃれに少々広くなっていた。私を含め今回は10名が集う。それぞれが自分の課題をもち参加している。最近した授業の報告。これからする授業の相談。指導法に関する提言。私も話すことはあるのだが今回は聞き役に徹した。2時間半の例会で10名。久しぶりに参加する仲間もいる。きっと話したいことあるのだろう。話すより聴く方が今回はいい。案の定みんなの話は実によかった。荒井さんの模擬授業には毎回脱帽する。いつの間にこんな手の込んだ授業を作るのか不思議でならないほどである。今回は4つもの模擬授業。「震災の日に」「公共施設」「世論と公約」「ハンセン病と差別」ただただもうすごいのであります。他の仲間からももちろん多くを学んだ。・「ごんぎつね」を5時間で授業する手だて・MさんのDVDサッカー指導・Nさんの「説明文指導」と「討論の授業」の手順2次会では新年会そっちのけでMさんご夫妻のおめでたを祝った。おめでとうございます。次回は2月23日(土)。よ~し。
2008.01.26
コメント(0)
-
2匹目のテントウムシ
1匹のテントウムシを透明な容器に入れる。その上に透明なガラス板でフタをする。テントウムシは外に出ようとするが出られない。透明な壁やフタに何度も阻まれるのである。やがてテントウムシは外に出ようとしなくなる。あきらめたのか飛ぶことさえやめてしまう。飛ぶことを忘れたテントウムシ…。そこへ2匹目のテントウムシを入れる。そして今度はフタをしないでおく。しばらくすると2匹目のテントウムシは容器の中から外に飛んで行く。するとそれを見ていた1匹目のテントウムシ。飛ぶことを思い出したのか続いて容器の外へと飛んで行った。先日お会いしたビジアクの松江隆明さんに教えてもらったこの話。道徳の授業の最後に紹介した。「ムリ」という言葉の影響であきらめることを刷り込まれている人。子どもたちとて例外ではない。そんな子どもたちにこのテントウムシの話は心に響いただろうか。ムリと思うなできると思え、なのだ。
2008.01.25
コメント(0)
-
U先生と坂本達さんの話を聴けた
坂本達さん。「4年3ヶ月も有給休暇もらって世界一周55000kmを自転車で走ってきた走ってきた男」である。その坂本さんの記念講演がある。ということで大阪府公立小学校教育研究会の第44回中央研究発表大会に参加した。坂本さんの記念講演の前に、第40回教育研究論文・実践報告の優秀賞の先生2人がそれぞれ20分間の発表をした。坂本さんの話を聴くために参加したのだが、2人の先生方の話もきっちり聴いた。特に2人目に発表した中学校の国語のU先生の話は面白く聴けた。U先生は国語の授業で毎回「読み聞かせ」をしたそうだ。相手は中学生である。果たして中学生相手に「読み聞かせ」ができるのか。それも毎回の授業で。しかし、当初は興味を示さなかった中学生たちも次第にU先生の読み聞かせを静かに聴くようになったという。U先生の気迫が生徒たちを圧倒したのかも知れない。そうU先生の話しぶりには気迫があった。決して流暢な話しぶりではないが、自分の信念に基づいた気迫があるのである。U先生のような気迫をもった話しぶりを見習わねばと強く思った次第。もっとU先生の話が聴きたい。そう思った私は休憩時間にU先生ところに行った。「先生、さっきのお話、とっても面白かったです」「おお、そうですかあ!」「もっと先生のお話が聴きたいのですが…」そう言うと、次の発表の日を教えてくれた。「案内を送りますから連絡先を教えてください」そう言われ私は自宅の住所などを紙に書きU先生に渡した。U先生はおそらく50歳前後で私より確実に教員生活が長い。しかも初対面なのだが実に親しく話し合えた。この後はじまった坂本達さんの記念講演ももちろんよかった。「人のせいにしないで決断したのは自分であることを忘れてはいけない」「相手が大切にしているものを大切にする」「人に親切にすることで自分が豊かになる」そんな私の心にしみ入る言葉を自身の経験に基づいて話してくれた。U先生や坂本達の話。本日はここに書ききれないくらいの学びを得たのである。
2008.01.24
コメント(0)
-
地球環境を意識した行動をつづける子どもたち
環境問題を解決するには次の3つが大事である。1 事実を知る2 できることからはじめる3 人に伝えるこれまで子どもたちは環境問題の事実を多く学んできた。オゾン層破壊・地球温暖化・エネルギー問題・水質汚染・森林破壊……。事実を知った子どもたちは実際どんなことしているのか。・買い物に行くときに袋をもっていく。・こまめに電気を切っている。・食べ物を残さずいただく。・使わない電化製品のプラグをコンセントから抜く。どの子も自分でできることからはじめていたのだ。中には、「クーラーを使わず扇風機だけで夏を過ごした」という子もいた。聞いてみると、6年1組だけで4人もいる。これにはもうびっくりである。ヒートアイランドで夏は日本一暑い大阪市内である。あの暑い中クーラーなしで過ごしたのだから脱帽だ。まいりました。地球環境を意識した行動を実践している子どもたち。この3学期は3つ目の「人に伝える」活動に出る。それがECO発進だ。どんなECO発進になるか楽しみである。
2008.01.23
コメント(0)
-
大阪弁で音読する
「落語の招待席」という文章が国語の教科書にある。作者は桂米朝さん。米朝さんがそのまま話しているように書かれてある。この文章を音読するにはやはり大阪弁がいい。ところが音読となるとどうしてもやや共通語的なものになってしまう。これではだめだ。いやいや、これではあかんなあ。ほんで、「ここはいっちょう、大阪弁で読んでみようや」ということにしたんどす。おっと、これは京都弁。ここで威力を発揮すんのが、つれ読み。私が音読したところを子どもたちが復唱する読み方や。私は米朝さんになりっきて音読する。子どもたちもはりきって音読しましたがな。音読後はとてもええ感じがしましたで。やっぱ大阪弁はよろしいなあ。
2008.01.22
コメント(0)
-
モノよりコトの誕生日
本日1月21日で42歳になった。42は「死に」ということで男の大厄である。女の大厄は「散々」の33歳。いずれも、「語呂合せにすぎず、その基底には年齢集団の折り目を神事の役年とする思想がみられる」という。(『百科事典マイペディア』より)「まあええ歳やから用心しいや」ということだろう。はい、わかりました、なのだ。「お父さん、何、ほしい」娘にそう聞かれしばし悩んだのが昨日。「う~ん、……お酒やなあ」そうして次女は私の誕生日プレゼントに酒を買ってくれた。沖縄の酒・泡盛である。長女にも同じことを聞かれ同じように答えた。ところが次女とはちがうものを買いたいらしい。ここでさらに悩んだのだ。お酒以外にほしいもの……。思い浮かばない。まあ確かに、燃料電池や風力発電・太陽光発電といった発電装置はほしい。しかしそんなものは高額で私でも今は手が出せない代物(シロモノ)だ。ああ、チェーンソーや薪ようの丸太がほしいぞ。やはりそれも長女には酷である。「ようし、じゃあ、100点の試験10枚」「うん、わかった」モノをもらうよりもしっかり勉強してくれるコトの方が私はうれしい。モノよりコトである。次女が買ってくれた泡盛それ自体ももちろんうれしい。しかしそれ以上に私のことを思って買ってくるコトがうれしいのですね。家に帰ると、連れ合いが知人たちとキムチ作りの準備をしていた。タライほどもある大きなタルやバケツに大量の白菜を塩漬けしている。キムチ作りの名人Yさんによると今週の金曜日から食べれるようだ。キムチ大好き人間の私はもう心の底から喜びに満ちあふれたのであります。これから毎日自家製キムチをふんだんに食することができる。もちろんそれ自体も喜びの極みなのだが連れ合い自らがキムチ作りをするコトに私は最大級の喜びを感じるのである。ありがとう。やはりモノよりコトである。食卓には長女がこねて作った手作りハンバーグ。真ん中には連れ合い特製のリンゴケーキにロウソク。それに昨日鶴橋で買ったキムチに大盛りごはん。もちろん次女から贈られて泡盛もある。大厄もなんのその。幸先のいい出だしである。みんな、ありがとう。
2008.01.21
コメント(2)
-
キムチのために鶴橋へ
【写真】鶴橋でなじみのキムチ店午前中、娘たちと3人で鶴橋に行った。鶴橋の商店街をぐるりとまわる。キムチ・衣料・寝具・鮮魚…。韓国の市場を思い出す。キムチ用の唐辛子1kg。すりごま1kg。白えびの塩辛500g。しめて1900円を購入。連れ合いが知人とキムチを作るという。たのしみだ。それまで待てないのでキムチも買おう。鶴橋でいつも買うキムチ店に直行。300gのキムチ3袋で700円を購入。次女が前からほしがっていたイカキムチも購入。こちらは1パック500円也。夕食前に酵素食としてキムチを試食。うまい。夕食時にはあつあつごはんの上にキムチをのせて頂く。たまらないの大満足だ。イカキムチは本日中に全てわれわれの胃袋におさまった。トラックバックめちゃめちゃ美味しいキムチもらいました ほしいんだもの 【冷蔵限定】ホタテ貝柱入り・韓国宮廷キムチ500g×2個セットこの、韓国宮廷キムチなるものをいただいたのですが、これが美味しいのなんのって…!!!今まで食べたキムチのなかで、一番美味しいです。辛さと酸味がまろやかに感じるキムチなんて初めてです。食べ物で久々...(2008.01.22 21:31:41)
2008.01.20
コメント(1)
-
視覚化で意識化させる
先生のための学校に参加。本日は久保先生の「国語授業の実践と批評。図書先生の「遅れがちな子とさかのぼり指導」。子どもたちの普段の会話には文脈がある。話の流れや筋があり論理的でさえある。ところが授業となるとそうはいかない。文脈から逸脱するような発言も少なくない。それどころか発言さえしない子もいる。その隔たりをどううめていくのか。久保先生は授業の初めに簡単な問答をする。そうして話し合う場の雰囲気を和ましてから主発問やミクシイ(理由聞き)をするという。いわばジャブをくり出しストレートやカウンターで授業を展開するわけだ。図書先生の講座を久しぶりに聴いた。ああ自分の実践の根底にあるのは図書先生の実践だったんだなあと実感した。20代のころ当時「落ち研」(現在「学力研})の全国大会で図書先生の実践に感銘を受けたのである。子どもに理解させるには視覚化が有効だ。見えるようにすることである。筆算では計算過程を小さな数字で視覚化する。これを図書先生は確か「赤ちゃん数字」と言っていた。そう言えば図書先生は自身の指導法に面白い名前をつける名人だ。「波のりちゃっぷん方式」「ガチョンガチョンショワッチ方式」「日本地図旅行」「基礎計算チャレンジ月間」「全校漢字大会」こうした名付けも視覚化と同じく意識化されやすい。ここ数日ようやく冬らしい寒さになってきた。わが家の薪ストーブも大活躍で積んであった薪が目に見えて減ってきた。おおこうしてはいられない。明日は薪割り作業をしなければ…。薪の減り具合で燃料不足が実感する。これも視覚化なのだ。
2008.01.19
コメント(0)
-
懐かしい我が風景の如意谷団地
夜6時半からほんまもん実行委員会の会議。11時すぎまでの長丁場であったが眠気もせずきっちり話し合いができた。今年の通天閣で知るほんまもんは6月1日(日)に開催。前日にはエアディナー大会の予選やビジネスアクションコンテストも行う予定。企画の大阪ケナフの会は10周年を迎える。弟5回の通天閣で知るほんまもんはさらに進化発展で盛大なものとなるだろう。途中Iさん差し入れのカツ丼が1日1食の我が空腹を満たしてくれてしみじみうまかった。帰りはOさんに車で送ってもらう。新御堂を北上し箕面ヴィソラの橋をくくると、どでかい箕面トンネルが見えてきた。はあー、このあたりもずいぶんと変わったなあ。間近に箕面トンネルを横目で見てつくづく思う。5年前まで私はこの近く如意谷団地に住んでいた。まだ箕面トンネルはもちろん箕面ヴィソラもできていないころだ。田んぼや畑があったのを思い出す。御堂筋のドンツキを左に折れると如意谷団地が見えてくる。ああなつかしい。このあたりの風景はあまりかわっていなくてうれしくなる。娘たちがまだ幼いころや新婚当時のこkとまでも思い出す。わずか数分の車窓からの変わらぬ風景がじーんと心にしみてくるのである。
2008.01.18
コメント(0)
-
古傷の痛み
3学期になり私は朝の全員遊びに毎日参加している。左脚ふくらはぎの肉離れも治り長年とれなかった右肩の痛みもなくなりよ~し毎日参加するぞという目標をたてたからだ。体力および気力も万全だと確信したのである。ところが今日は少々危ないめに合った。いつもはドッジボールなのだが今日は探偵。ドロケイもしくはケイドロとも呼ばれる鬼ごっこ系の遊びである。昨日の学級会で、「毎日ドッジボールというのもいかがなものか」といことが話し合われ、「ならば探偵というのがあるぞ」と私が提案してのである。そこで今朝の全員遊びは探偵になった。私にとっては3年ぶりの探偵だ。全力疾走は控えたもののラグビーでいうステップを小さくきってみた。すると左脚ふくらはぎがじわじわ痛み出したのである。ちょうど肉離れになったところだ。幸い大事には至らなかった。5時間目の体育では子どもたちと一緒に5分間走もできた。でもなわとび(短縄)はあまりできなかった。やはり左脚ふくらはぎにひびいてくる。子どもたちに交じって長縄をすると今度は腰に痛みを感じた。これも幸い大事には至らなかった。「あまり無理はせんとぼちぼちいきや」神様からの伝言なのだろう。1週間前の夜は脚がつったりしてのたうちまわったが今夜は何事もなく熟睡できた。まあ無理をせず徐々に体力向上に励んでいこう。来週21日(月)に42歳になる。
2008.01.17
コメント(0)
-
寝入り前30分のクラシック
9時に寝て3時半に起きる。目覚ましが鳴る前には目を覚ます。これが私の理想的な早寝早起きである。毎日ほぼこの理想的な早寝早起きで心身ともに絶好調だ。ところがここ数日は8時半には寝床につくようにしている。寝床で古典音楽(クラシック)を聴く楽しみが増えたからである。ラジオNHK-FMで夜7:30~9:10にクラシック番組があるのを一昨日みつけた。それ以来の3日間は毎日聴いている。といっても聴いているのはおそらく十数分といったところだろう。疲れからかすぐに寝てしまうのだ。昨日はおそらく5分ほどではなかったか。あらかじめ時間を設定し自動的に電源を切るようにしている。今は30分で切れるようにしているがこの調子だと10分でもいいかもしれない。しかし10分で切れてしまうと眠りに入ったところで逆に目覚めてしまう。ワカリマスネ。だから今は30分なのだ。番組は7:30に始まるから夕食後つけてもいいなあ。家族に相談してみよう。
2008.01.16
コメント(0)
-

肯定的解釈でいい気分
運動場での全校朝会。私は前に立ち子どもたちを見ていた。後ろを向いたり隣の子とおしゃべりをしたりする子は1人もいない。朝礼台の上に立つ校長先生を見てしっかり話を聞いている。おお素晴らしい。2学期にはなかったことだ。3学期が始まって1週間。子どもたちもそれぞれ目標をもち、残りわずかな小学校生活をきっちりすごそうとしているのだろう。感心、感心。立派な子どもたちの姿を見ると頼もしく思うのだ。子どもたちに感化され私も背筋を伸ばす。ああ今日も1日たのしくすごせそうだ。実際今日も1日平穏無事にたのしくすごせた。そういえば3学期はずっとこんな調子である。本日読了した『勉強に集中する方法』(須崎恭彦、ダイヤモンド社)に、ストレスの原因は「出来事」ではなく「解釈の仕方」というのがあり、我が意を得たりと納得した。「感情は次の3つのステップで生まれます。 1何か出来事を【知覚】します ↓ 2その刺激を脳の中で「あっ、これはこういう意味だな」というふうに【解釈】します ↓ 3その解釈を元に、ある特定の【感情】が生まれます」(71頁)勉強に集中する方法肯定的な解釈をこころがけ毎日をたのしくすごしていこう。
2008.01.15
コメント(0)
-
孤食から解放される
昨日までの3日間、家族とともに食事をとることがなかった。私は今でも1日1食の人生である。その1食は夕食にとる。ゆえに私にとって夕食は実に貴重な黄金時間なのだ。その夕食を家族と共にとる。食卓を囲んで次女が私の隣、長女が向かい、連れ合いが左斜め向かいの席につく。当然テレビなんてのはない。大盛りごはん片手に私は家族との会話を楽しみつつその日はじめて口にする食事をいただく。ああおいしい。幸せだ。ありがとう。1日1回は必ず感動と幸福と感謝の心が湧き出てくるのである。それが3日間なかった。1日目は久しぶりの飲み会で楽しかったが、2日目・3日目は1人で食べた。孤食である。これがつづくやはり精神的によろしくない。独りで寂しいからテレビをつけての食事となる。ああ~。腹は満たされるが心が満たされない。しかし今日は4日ぶるに家族で夕食をとった。もう私は実に実にうれしい。おいしい。幸せだ。ありがとう。そんな言葉を心で思うだけでなく何回も口にした。そんな私のはしゃぎぶりを家族はハイハイと実に落ち着いて受け流していた。それでも私はうれしいのである。
2008.01.14
コメント(0)
-
干せばいいんだね
玄関にあるさつまいもが目についた。そうそうれいの干し芋まだ作ってなかったなあ。今日あたり作ってみるか。おっとその前に夕飯の支度だ。午前中から連れ合いと娘たちは奈良に行った。奈良の友達の雑貨店「ゑり甚」で若草山の山焼きを見るらしい。ということで私と愛犬ゴロウは明日まで留守番。夕飯も自分で作ることになった。そうそうそろそろできているかなあ。と思いつつぬか床から大根を抜き出した。やわらくていい感じだ。水洗いせずぬかがついたままで一口大に大根を切る。ほどよい感触でスーと切れる。中までぬかの成分がしみ込んでいるのが見てわかる。一口食べてみた。うまい。こりゃあまさにたくわんだ。やわらくてコリッとした歯ごたえがたまらない。そうか大根は干せばいいんだね。今まで何回か大根のぬか漬けを作ったことはあるがこの歯ごたえは出せなかった。大根を干さずに硬いまま漬けていたからだ。あのたくわんのような歯ごたえはどうすれば出るのか。そういえばご近所のNさんは庭で取れた大根をたくさん干していたぞ。ひょっとして干してから漬ければいいのかなあ。そこで今回の大根は1週間ほど干したのを3日間ほど漬けこんだのだ。だからうまいんだね。思った通りである。庭にはまだ十数本の大根が早く抜いてくれと待っている。明日はそのうちの数本を抜いて干してやろう。大根だけでなく明日は薪割りしたあと薪も干させばならない。う~ん、どうやら干し芋づくりはまた後回しになりそうだ。
2008.01.13
コメント(0)
-
東大で原発報道を考える
東京大学に行く。あの東大である。「科学技術と社会安全の関係を考える市民講座」に参加。主催は独立行政法人・原子力安全基盤機構と東大大学院工学系研究科原子力国際専攻。後援は経済産業省と原子力安全・保安院。弟5回目の今回は「科学技術と報道を考える」がテーマ。参加者は200名ほどで会場は満員であった。講師は次の3名の方である。前原子力委員会委員で元日本原燃社長の竹内哲夫さん。朝日新聞編集委員の竹内敬二さん。東北放射線科学センター理事の高倉吉久さん。「マスコミは原発事故を針小棒大に報道しすぎる」そんな話になるのかなと思っていたらおおむねそうだった。例えば去年おきた中越沖地震による柏崎刈羽原発の事故。「変圧器火災の映像ばかり流すのはサブリミナル効果でよくない」「プール水もれの9万ベクレルは13人分の放射能で大したことはない」確かにそうなのかもしれないけれど、だからといって原発事故を軽く扱ってはいけないだろう。「原発には潜在的リスクが大きいから小さな事故であったも報道すべきだ」朝日新聞の竹内さんの意見に納得。方や原子力学会の竹内さんは、「皆で原子力を愛そう」日本には現在55基の原子力発電所がある。日本のエネルギーの3割以上は原子力である。愛するか否かはともかくわれわれは原子力についてもっと知る必要はあるだろう。そのためにも推進側も報道ももっと分かりやすい説明をしてほしい。
2008.01.12
コメント(2)
-
決して酔っぱらったわけではない
夜は某NPOの集まりに参加。二次会で居酒屋に。10時を過ぎたあたりから睡魔が襲う。ああ、だめだ。と思ったが背筋を伸ばしつつ首だけ折れて寝てしまった。9時就寝3時半起床の毎日。今週は3学期も始まり体力も気力もかなりつかっていたのだろう。おそらく10時半過ぎに店を出て自宅に直行。明日からの3連休はゆっくりしたいのだが…。
2008.01.11
コメント(0)
-
のたうちまわる夜
朝の全員あそびに参加。これで3日連続の参加。今朝も男子対女子のドッジボール。女子の方が人数も多く強い。がんばれ男子。5時間目は合同体育。5分間走となわとびを子どもたちと一緒にする。ジャンバー・オープンジャージ・ラグビージャージの3着を脱ぎTシャツ1枚になった。暑いのだ。帰宅前に箕面温泉のジムで筋トレ。まだまだ昨年ほどではない。がんばろう。そうそう通勤途中に軽く走った。信号直前からやや全力疾走気味にも走れた。左脚肉離れはもう完治したようだ。ところが夜。眠りについて45分ほどに両脚が痛み出した。筋肉疲労か。夕食時には岩塩を食しミネラル分に問題はない。クリスタルバレー倉田水(活性水素水)も充分補給した。なのにこむら返り以上の脚の痛さ。激しく疲労したラグビーの試合後に数回経験した痛みである。イタタタ…。部屋中を歩き回ったり柔軟体操したり水を飲んり。3分ほどでおさまり再び寝床でグー。しかししばらくするとまた脚に激痛が走る。レム睡眠中のできごとでもうろう気味にまたもやのたうちまわる。家族はみんな屋根裏部屋で静かに寝ていた。あああ。
2008.01.10
コメント(0)
-
3つの目標
始業式に校長先生から3つの目標をたてましょうという話があった。1,勉強の目標2.生活の目標3.運動の目標3というのは使えるいい数だ。三脚・三段跳び・三国志。新東三国小学校は東三国三丁目にある。6年生は3組あり信号も3色。現役時代わたしの背番号も3(右プロップ)。鼎談なんて見るからに安定感がありそうではないか。三人が向かい合って話をすること、それが鼎談(ていだん)。多少強引かも知れないがかまわない。3というのは安定感があり記憶に残りやすい数なのだ。昨日子どもたちが書いた目標から各自この3つの目標を選択する。昨日書いた紙の裏に3つの目標を書く。言葉だけでなく絵もかき色もしっかりつける。これでさらに意識化でき目標が実現されやすくなるはずだ。今年も1日1食1冊1文が基本目標だが3つの目標もたててみよう。1,実践の成果を1冊の本にまとめる2.朝日を拝み感謝しつつ鼻呼吸で深呼吸をする3.筋力および走力の保持増進に努める今こう書いた瞬間に実現できそうな気がしてきましたぞ。よ~し。
2008.01.09
コメント(0)
-
新たな目標をたてよう
目覚まし時計よりも先に目を覚ます。時計を見ると3時半。朝の儀式を終え学校へと向かう。今日から3学期がはじまるのだ。どういうわけかすこぶる体調がいい。信号の手間で走ったりすることもできる。去年、左脚ふくらはぎを肉離れしたのがウソのようだ。これなら全力疾走もできそうだ。朝の全員遊びでドッジボールをした。驚いたことにボールを投げれる。実は2年ほど前に肩の痛みを覚えそれ以来ボールを思い切って投げることができなかったのである。ところが今日は違う。全力投球できるのだ。よ~し。これなら毎日でもドッジボールができそうだ。講堂での始業式を終え2時間目から早速授業。冬休みの宿題の答え合わせをし冬休みの思い出を1人30秒ほど前で話す。3時間目は自分の目標を思考地図(マインドマップ)方式で書く。「目標」という言葉から思いつく言葉をどんどん紙に書く作業だ。それをもとに50日後に達成したい目標を一つ選ぶ。50日後はつまり卒業式なのである。その目標を細長い紙に書きセロハンテープで机の右前方にはる。これで毎日その目標を見て意識化できる。一年の計は元旦にありという。3学期の始業式に自分の目標をたてるのはとても大事なことだと思うのだ。私も2008年になり新たな目標をいくつかたてた。全員遊びのドッジボールに毎回参加する。これもそのひとつに加えてみようか。
2008.01.08
コメント(2)
-

網棚の忘れ物に感謝する
シーナ兄貴の新刊『トンカチからの伝言』を電車の中で読んだいた。トンカチからの伝言あまりにの面白さに夢中になっていたのだろう。電車内の網棚にかばんを置いたまま電車を降りてしまった。降りた駅は大阪環状線の西九条駅。今日は卒業遠足の下見でUSJに行くのである。西九条から桜島線に乗り換えユニバーサルシティ駅へと向かう。駅や電車内でも私は『トンカチからの伝言』を読んでいた。ユニバーサルシティ駅で降りたときに身軽な自分に気づいた。あれ、何だか軽いなあ…。ああっ、カバンが、な…い。慌てても仕方がないので心を落ち着かせ冷静になり駅員さんに事情を話した。幸いカバンには着替えと本が1冊あるだけだ。こんなこともあろうかと貴重品のたぐいは全て身につけている。重要書留等は決して持ち歩かないようにもしているのだ。それにしても網棚にカバンを置き忘れるなんて今までに一度もなかった。電車に乗るとカバンは網棚に置き立ったまま読書をする。降りるときは必ず網棚からカバンを取って降りる。これをもう1万回以上はくりかえしすでに我が習慣として定着しているはずなのに…。シーナ兄貴の新刊『トンカチからの伝言』には我が習慣をも変えうる何かがあるのだろうか。油断は禁物でっせ。明日から3学期でっしゃろぉ。気ぃひきしめて行きなはれやぁ。これは「トンカチからの伝言」ではなく神様からの伝言なのだ。そう思えばありがたいことである。ありがとうございます。ということでUSJの下見ではカバンを持たず手ぶらでできた。荷物を預けるとお金を取られるがこれなら無料。そう楽観的に考えれ落ち込むこともない。帰りに若い女性の駅員さんに聞く。「すみません。 カバンを忘れた原田というものですが、カバンは見つかりましたか」「ハイ、見つかりましたよ。 桜島駅にあります」「ありがとうございます」桜島駅はユニバーサルシティ駅のすぐとなり。さっそく桜島駅に行きカバンを受け取り大阪駅行きの電車に乗った。さすがにこのときばかりはカバンを網棚には置かなかったのであります。
2008.01.07
コメント(0)
-

毎日朝日で心身ともに蘇る
今年になり意識して毎日朝日を見るようにしている。新聞のことではない。新聞なら「毎日」「朝日」は学校で、「讀賣」は家で読んでいる。そうではなく毎朝意識して朝の光を見るようにしているのである。日の出を拝む。朝日を全身に浴びている。そういってもいいだろう。なぜそんなことをしているのか。文句なしに気持ちがいいからだ。朝、真っ赤な日の出を見て思いっ切り背伸びをする。それだけでもう元気になる。さらにゆっくり鼻呼吸を3回してみる。もう完璧だ。60兆個もある我が細胞が一つ一つ再生する、つまり生まれ変わる感じがする。さあやるぞと気合いも入る。自然と力がみなぎってもくる。「うおっー、ありがとう」ここで思わず感嘆の言葉と感謝の言葉を叫びたくなる。本当に叫んでしまうとご近所の方々がびっくりするだろうから今は心の中で思いっ切りそう叫んでいる。年末年始、立て続けに次の3冊を読んだ。しあわせの雑学ツキを呼びこむ!朝2時間の早起き『早起き』は生きる力!1日は24時間。一方、われわれが寝たり起きたりをくりかえすのに働く体内時計なるものは25時間。つまり地球と人間の1日に1時間のズレがある。この1時間のズレを修復してくれるのが朝の光なのだ。朝日を浴びることで地球の周期に体を合わせることができるのである。近藤勝重さんの本から引用しよう。「朝の光は健康にいいのだそうです。 朝日を浴びると脳内物質の一種、セロトニンがでやすくなる。 セロトニンがたくさん出ると、脳がイキイキしてくる。 このあとに意気込む何かがあるわけではくても、『さァー』という気分になってくる。 体調を整えてくれるのですね」 (『しあわせの雑学』146頁より)これからも意識して毎日朝日を見るようにしよう。
2008.01.06
コメント(0)
-
芦原温泉でカニづくし
サンダーバードで芦原温泉に行った。数年ぶりに家族でカニを食べた。カニの食前酒。カニの刺身。カニ鍋。焼きガニ。ゆでガニ。カノの酢の物。カニの天ぷら。………。カニづくしである。もうほんとうに食べれない量だ。しかしこれらをおかずにごはんを4杯はきっちりいただいた。もう満腹の大満足である。もうこれで終わりと思ったがまだ出てきた。エビと野菜の天ぷら食べ放題。カニ召し。カニの赤だし。茶碗蒸し。いちご・オレンジ各2ケ。どひゃあ、である。さすがに天ぷらの食べ放題は辞退し家族で2人前だけ注文。我が胃袋は破裂寸前までに達していた。食後軽く温泉に浸かり9時前には素早く寝る。ごちそうさまでしたの一日であった。
2008.01.05
コメント(0)
-
1月4日という日
1月4日。確か20年前のこの日、友人Tと広島に行った。大正駅で青春18切符というのを買い、列車を乗り継ぎ乗り継ぎしてようやく広島に着いた。手持ちの金が心許なくなり郵便局に向かった。ところがあいにく郵便局は閉まっていた。ああまだ休みなんだと思った。ところが今日、郵便局は開いていた。民営化になりそうなったのか。年明け年賀というので年賀状もまだ売っている。なんでも年賀状は贈り物なのだそうだ。それはともかく今日は仕事始めの日である。やはり郵便局も1月4日からは開くのだろう。20年前のあの日は1月3日だったのかもしれない。私も学校に行き仕事をした。資料整理・文書作成そして何より3学期の準備。やればやるほどやることが出てくる状態だった。帰りに図書館に寄った。箕面中央図書館は水曜と金曜は夜7時まで開いている。ところが今日は閉館。仕事始めなのになぜだ。よく見ると閉館だが中では図書館の人たちが本の整理などの仕事をしていた。やはり仕事始めなのだ。気をとりなおして箕面温泉へと向かう。箕面温泉は年末年始も開いている。しかも今日から年末年始は閉まっていたジムも開く。今年初めての筋肉鍛錬をしようと意気込んだのだ。ところがジムは夕方5時に閉まっていた。仕事始めの1月4日なのに休日営業の5時までだったのである。ああ。仕方なく浴場に向かった。実は今朝早朝、薪仕事をしていて腰を少々痛めていた。仕事始めで少々くたびれてもいる。温泉でゆっくり休めということだろう。明日から土日の連休。骨休めで腰を治そう。
2008.01.04
コメント(2)
-
徹底反復的お正月
家族で街山荘に行った。毎年恒例の新年のごあいさつである。街山荘は私の父の店。丸太小屋風ショットバー。生演奏(ライブ)などもできる多目的室もある。もう何回かこの「電脳通信」で紹介しているとおりだ。街山荘のパソコンで「原田誉一の電脳通信」を見た。去年の今頃は何をしていたのだろう。そんなことが気になり覗いてみたのだ。2007年1月3日の記事。おおこの日も街山荘に来ていた。やはり「恒例」なのだ。ついでに同年同月の1日・2日のそれを見る。ありゃまあ今年とよく似ているぞ。2006年ではどうか。これもほぼ同じ。ただ両年とも2日目から原稿を書いていたが今年はそれに追われてはいない。わりとのんびり日本の正しいお正月を過ごしている。さあ明日から仕事始め。気持ちを切りかえよう。明日やることを思い浮かべるとわくわくしてきた。
2008.01.03
コメント(0)
-

岡田尊司『脳内汚染からの脱出』
脳内汚染からの脱出子どもの誕生日やクリスマスのプレゼントに覚醒剤を与える親はいない。もちろんおじいちゃん・おばあちゃんだってそうだ。しかしテレビゲームやパソコンならどうだろう。おもちゃ感覚で子どもに与える大人は多いのではないか。岡田尊司『脳内汚染からの脱出』を読むと、テレビゲームやインターネットには覚醒剤なみの依存性があるということがよくわかった。子どもにテレビゲームやパソコンを与えることは覚醒剤を与えるのと同じこと、もしくは覚醒剤以上に子どもに害を与える行為なのかもしれない。そう思えてならないのだ。「1日30分だけという時間制限を設けてるから大丈夫」そんなことをよく聞く。毎日30分のテレビゲーム。それは毎日覚醒剤を投与する行為とどこがちがうのだろう。本書では「依存にならないため」、「1日30分より、土曜日に2時間」(220頁)ということもすすめている。テレビゲームやパソコンにはまった子どもたちを救うための具体的な手だてが他にも多く紹介されてある。表紙の裏にはこんな記述がある。「最新の研究では、いじめやADHDの増加との関連性も明らかになった。 ゲーム依存に陥った子どもにはどう対照すべきか 新しい『親の必読書』」全くもってその通りである。
2008.01.02
コメント(2)
-
元日はおせち料理にかぎるのだ
今年も連れ合いの実家でおせち料理をいただいた。ふりかえってみると我が人生、元日には必ずおせち料理である。これは実に実に有り難いことだ。と今「有り難い」と漢字で表現した。文字通り有り難いことであるからだ。というのも最近おせち料理を作る家庭が減ったという。おせち料理ではなく元日からパンを食するところもあるようだ。ひょっとして某ハンバーガー店や某フライドチキン店で購入したファーストフードがおせち料理の代用食になっているところもあるかもしれない。久しぶりに見たテレビの宣伝(コマーシャル)にそのような場面を見てしまった。確かに、おせち料理を作るのは面倒かもしれない。通常の料理より手間と時間がかかるだろう。それよりファーストフードなどの出来合ものを買えば楽チンである。電子レンジでチンして温めればできたて感もする。電磁波や放射線照射による影響はないものにすればいいのだ。しかし私はそんなものは食べたくない。まして1年の計は元旦にありの元日からそんなものは絶対に嫌である。やはり元日にはおせち料理をいただきたい。それもできれば出来合ものではなく手作りのおせち料理がいい。作るのに時間と手間がかかるのはよくわかる。実はそれがいいのである。手間ひまかけて作ってくれたおせち料理を感謝をしていただける元日。なんとも素晴らしいではないか。そんな話を家族にすると、「じゃあ、自分が作れば」と言われた。なるほど、それは面白い。来年のおせち料理づくりに私も参画しよう。私だけでなく家族全員で挑んでみたい。おせち料理という日本の伝統食を守っていきたいとも思うのである。
2008.01.01
コメント(1)
全31件 (31件中 1-31件目)
1









