PR
X
カレンダー
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 読書(9626)
カテゴリ: 本日読了
2022/10/30/日曜日/霜月始まりの薄い日差し
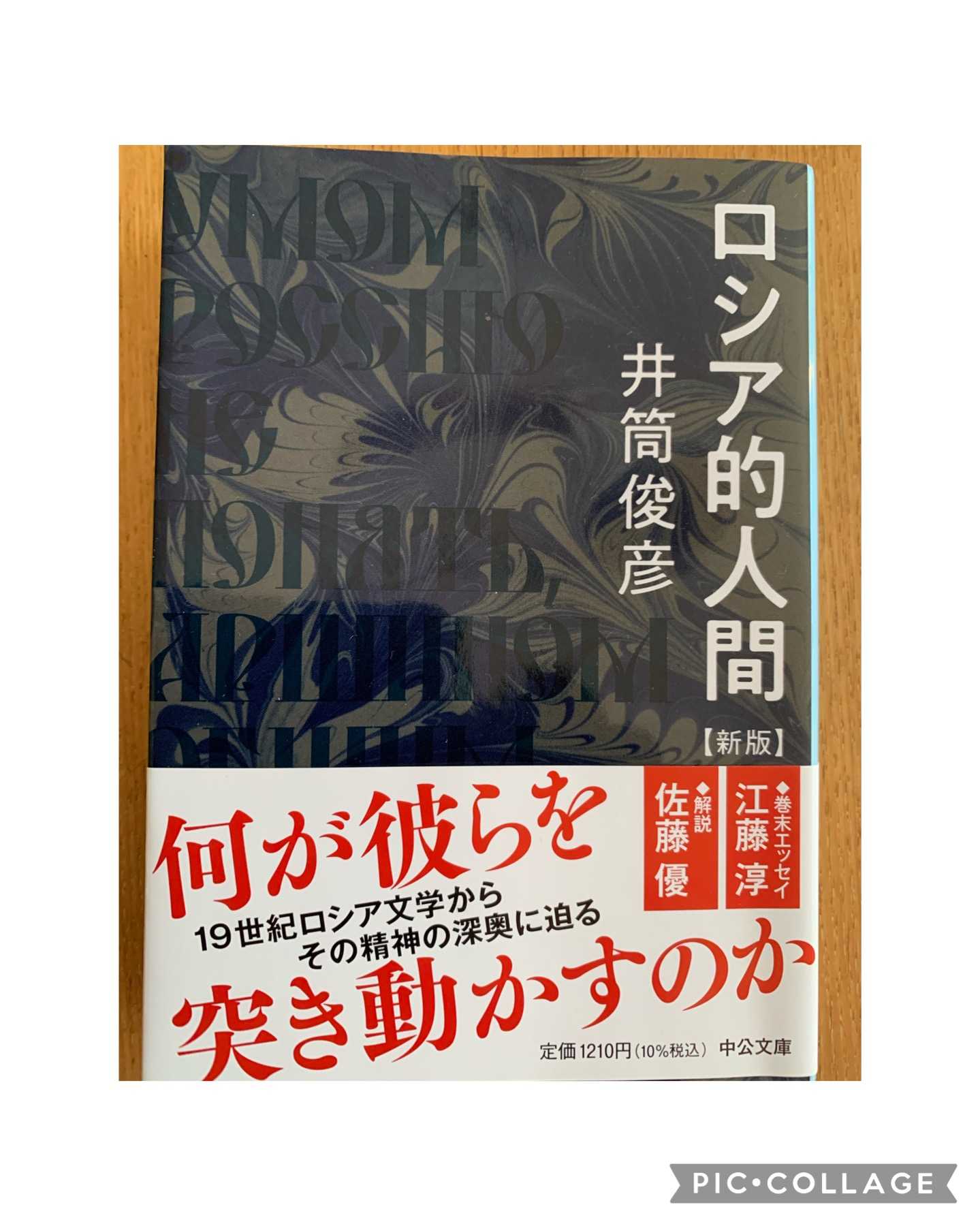
〈DATA〉
中央公論社/ 著者 井筒俊彦
1989年1月10日 初版発行
2022年7月25日 改版発行
中公文庫
〈私的読書メーター〉〈
留めておきたい言葉や詩がいくつもいくつもある本は、壁をくり抜いて作った特別な書架へおく。
そして心がすっーと何かに惹かれ、求めるように身体が動くとき、その小さな書架に手を伸ばす。
この本はそこに置かれる。
例えばレールモントフ17歳の、こんな詩
「天使が夜半の大空を翔けながら
静かな歌を唄っていた。
月も、星々も、群れなす雲も
浄らかな歌に聴き入っていた。
……
天使は、いま生まれようとする魂をいだいて、
悲しみと涙の国へ運んで行くところだった。
歌の言葉こそ忘れたが、幼い魂は
その調べをまざまざと憶えていた。
不思議な憧れに胸ふたがれて
彼はこの世に、永く悩み悶えた。
地上のくだらぬ歌や詩は
かの天上の歌声の代わりにはならなかった。」
など。
井筒氏は、トルストイとドストイェフスキーについて
〈19世紀ロシア文学はこの両者に至り、峰の絶頂に達し、プーシキンに始まるロシアの人間探求も究極の高みに到達〉し、
〈ロシア精神の深奥の秘密を世界の全面に暴き出した告白であり、人間宇宙の謎に関しロシアが吐きえた最高の、そしておそらくは最後の言葉〉
であると。
トルストイという無数の矛盾の巨魁のような人間の秘密を
自我中心主義の問題で捉えるとき西ヨーロッパの作家の中でトルストイに近い人として、氏はゲーテをあげる。
かつ両者の決定的な違いを力強い意識のありようにみる。
自我と芸術の乖離を生じさせず、内的葛藤なく自我深層の探求をゲーテにおいて遂行せしめた、と。
キリスト教的世界の只中にぽっかり咲き出した異教精神の二つの花、ゲーテとトルストイ
ゲーテにおける異教がギリシャローマに対し、トルストイはもっと根源的、原始的な、大地的生命である、と氏は指摘する。
そうであるならば、一個の近代人がそれだけの深奥にまで存在の根源を求める恐ろしさは想像もつかぬ。
「自然性と意識性、トルストイの内面に相剋するこれらのニ性質を、それぞれの方向にどこまでも辿っていくとき、その極限に至って我々は全く別人のようなトルストイに逢う…」
この章の中で、私にとり重要な点は、トゥルゲーネフが『アンナ・カレーニナ』のレーヴィンを評して
「レーヴィンという男が誰かを愛するということができると考えられるだろうか。いや、絶対にそんなことは思ってもみられはしない。一体、愛というものは我々の自我を滅する情熱の一つだ。ところがレーヴィンは、自分が他人に愛され、しかもそれで幸福を味わいながら、そのくせ自分自身の自我に執着して離れない男なのだ。…彼は骨の髄までエゴイストた。」
という件。しかもレーヴィンは誰がどう見てもトルストイに他ならないのだという。
毎週のレッスンで音楽を受入れ表現する、私の芸術的時間において、先生に言われる「自分から出ていく」。
さて、この感覚を「自我を滅する」情熱と理解するなら、それは音楽への愛、なのだろうか。
しかし出ていく、というのは滅するとは違う。消し去るのではなく、自我を離れる、が近いのではないか。
また音楽への愛というと、何やらそれは愛でる対象物になり変わる。それはまた違う。音楽、歌と連帯して歌そのものとなる。
人間はそんなふうに存在できるものかは。
さて、ドストイェフスキーの章に入り、
プーシキンが開拓した「自然と愛の喪失、不能が近代的人間の最大の悲劇」主題をトルストイも続行し、自然性探求の道を窮める流れを見た上で
ドストイェフスキーの認識は
「自然喪失と愛の不能は派生的現象であり、それらの底には根源的な神の喪失」であり、彼にとって失われた神の探究が最大課題となる、とする。
「旧い人が罪に死んで、新しい人となって甦る瞬間に人間と共に死に、かつ甦る新しい自然だ。ドストイェフスキー的世界においては、人が自然の美に対してどの程度の感受性を示すか、自然の美にどの程度まで共感できるかということは、その人間がどの程度まで宗教的に進んでいるかのパロメーターである。」
これなどはヒロシマナガサキチェルノブイリフクシマを経て更に地球温暖化、気象異変の只中、新しい人の新しい宗教?信仰となりうる未来的思索ではなかったか。
そして19世紀ロシアは最後にチェホフを据える。
氏は、
「透明な叡智の結晶体のようなプーシキン的芸術に始まり、一世紀のあいだ荒れに荒れ、乱れに乱れた揚句、また始めと同じ冷たい硬い叡智の静けさにもどってしまう。」
と記す。
19時のロシアの作家たちはやがて来る無神論的革命の匂いを嗅ぎ分けた。チェホフはドストイェフスキーのようにそれを拒否せず、医師でもあるリアリストの目を通し、「人間が本当に人間であるために」労働し始めると予見した。
新生活によって実現した人間の幸福なるロシア世界は、チェホフから12、30年を経て、井筒氏の執筆から約70年を経て、今私たちが目にするのはドストイェフスキー的黙示録なのかもしれない。
全ての兵士が大地を抱擁するならば。
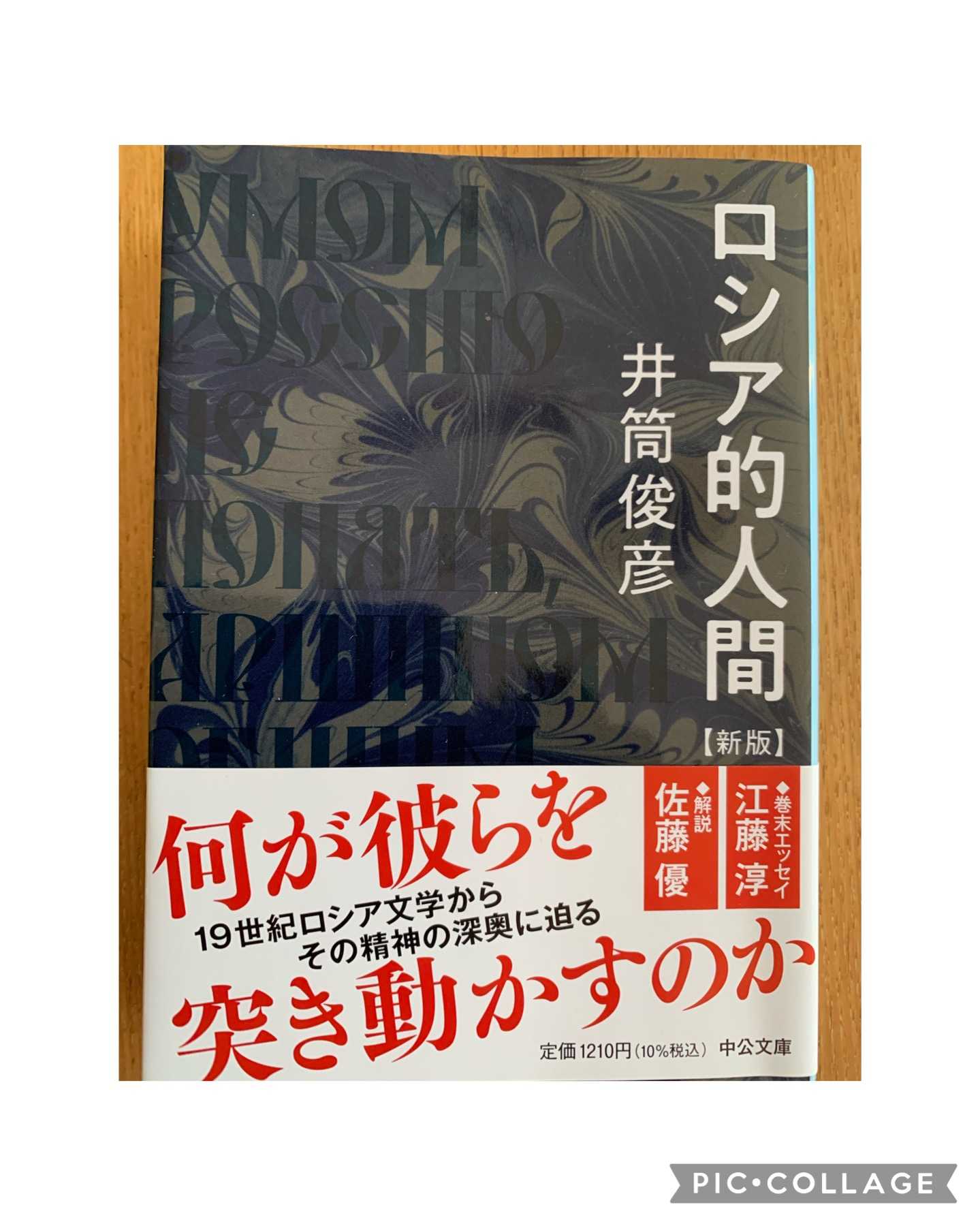
〈DATA〉
中央公論社/ 著者 井筒俊彦
1989年1月10日 初版発行
2022年7月25日 改版発行
中公文庫
〈私的読書メーター〉〈
留めておきたい言葉や詩がいくつもいくつもある本は、壁をくり抜いて作った特別な書架へおく。
そして心がすっーと何かに惹かれ、求めるように身体が動くとき、その小さな書架に手を伸ばす。
この本はそこに置かれる。
例えばレールモントフ17歳の、こんな詩
「天使が夜半の大空を翔けながら
静かな歌を唄っていた。
月も、星々も、群れなす雲も
浄らかな歌に聴き入っていた。
……
天使は、いま生まれようとする魂をいだいて、
悲しみと涙の国へ運んで行くところだった。
歌の言葉こそ忘れたが、幼い魂は
その調べをまざまざと憶えていた。
不思議な憧れに胸ふたがれて
彼はこの世に、永く悩み悶えた。
地上のくだらぬ歌や詩は
かの天上の歌声の代わりにはならなかった。」
など。
井筒氏は、トルストイとドストイェフスキーについて
〈19世紀ロシア文学はこの両者に至り、峰の絶頂に達し、プーシキンに始まるロシアの人間探求も究極の高みに到達〉し、
〈ロシア精神の深奥の秘密を世界の全面に暴き出した告白であり、人間宇宙の謎に関しロシアが吐きえた最高の、そしておそらくは最後の言葉〉
であると。
トルストイという無数の矛盾の巨魁のような人間の秘密を
自我中心主義の問題で捉えるとき西ヨーロッパの作家の中でトルストイに近い人として、氏はゲーテをあげる。
かつ両者の決定的な違いを力強い意識のありようにみる。
自我と芸術の乖離を生じさせず、内的葛藤なく自我深層の探求をゲーテにおいて遂行せしめた、と。
キリスト教的世界の只中にぽっかり咲き出した異教精神の二つの花、ゲーテとトルストイ
ゲーテにおける異教がギリシャローマに対し、トルストイはもっと根源的、原始的な、大地的生命である、と氏は指摘する。
そうであるならば、一個の近代人がそれだけの深奥にまで存在の根源を求める恐ろしさは想像もつかぬ。
「自然性と意識性、トルストイの内面に相剋するこれらのニ性質を、それぞれの方向にどこまでも辿っていくとき、その極限に至って我々は全く別人のようなトルストイに逢う…」
この章の中で、私にとり重要な点は、トゥルゲーネフが『アンナ・カレーニナ』のレーヴィンを評して
「レーヴィンという男が誰かを愛するということができると考えられるだろうか。いや、絶対にそんなことは思ってもみられはしない。一体、愛というものは我々の自我を滅する情熱の一つだ。ところがレーヴィンは、自分が他人に愛され、しかもそれで幸福を味わいながら、そのくせ自分自身の自我に執着して離れない男なのだ。…彼は骨の髄までエゴイストた。」
という件。しかもレーヴィンは誰がどう見てもトルストイに他ならないのだという。
毎週のレッスンで音楽を受入れ表現する、私の芸術的時間において、先生に言われる「自分から出ていく」。
さて、この感覚を「自我を滅する」情熱と理解するなら、それは音楽への愛、なのだろうか。
しかし出ていく、というのは滅するとは違う。消し去るのではなく、自我を離れる、が近いのではないか。
また音楽への愛というと、何やらそれは愛でる対象物になり変わる。それはまた違う。音楽、歌と連帯して歌そのものとなる。
人間はそんなふうに存在できるものかは。
さて、ドストイェフスキーの章に入り、
プーシキンが開拓した「自然と愛の喪失、不能が近代的人間の最大の悲劇」主題をトルストイも続行し、自然性探求の道を窮める流れを見た上で
ドストイェフスキーの認識は
「自然喪失と愛の不能は派生的現象であり、それらの底には根源的な神の喪失」であり、彼にとって失われた神の探究が最大課題となる、とする。
「旧い人が罪に死んで、新しい人となって甦る瞬間に人間と共に死に、かつ甦る新しい自然だ。ドストイェフスキー的世界においては、人が自然の美に対してどの程度の感受性を示すか、自然の美にどの程度まで共感できるかということは、その人間がどの程度まで宗教的に進んでいるかのパロメーターである。」
これなどはヒロシマナガサキチェルノブイリフクシマを経て更に地球温暖化、気象異変の只中、新しい人の新しい宗教?信仰となりうる未来的思索ではなかったか。
そして19世紀ロシアは最後にチェホフを据える。
氏は、
「透明な叡智の結晶体のようなプーシキン的芸術に始まり、一世紀のあいだ荒れに荒れ、乱れに乱れた揚句、また始めと同じ冷たい硬い叡智の静けさにもどってしまう。」
と記す。
19時のロシアの作家たちはやがて来る無神論的革命の匂いを嗅ぎ分けた。チェホフはドストイェフスキーのようにそれを拒否せず、医師でもあるリアリストの目を通し、「人間が本当に人間であるために」労働し始めると予見した。
新生活によって実現した人間の幸福なるロシア世界は、チェホフから12、30年を経て、井筒氏の執筆から約70年を経て、今私たちが目にするのはドストイェフスキー的黙示録なのかもしれない。
全ての兵士が大地を抱擁するならば。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[本日読了] カテゴリの最新記事
-
『三島由紀夫と歌舞伎』 2025.11.25
-
『奔馬』 2025.11.20
-
『三島由紀夫の来た夏』 2025.11.14
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










