PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(58)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(108)読書案内「映画館で出会った本」
(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(25)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(31)読書案内「近・現代詩歌」
(51)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(14)映画「パルシネマ」でお昼寝
(41)読書案内「昭和の文学」
(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(32)ベランダだより
(133)徘徊日記 団地界隈
(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(26)徘徊日記 須磨区あたり
(26)徘徊日記 西区・北区あたり
(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」
(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(22)映画 香港・中国・台湾の監督
(36)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(36)映画 イタリアの監督
(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(14)映画 ソビエト・ロシアの監督
(6)映画 アメリカの監督
(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(5)読書案内「旅行・冒険」
(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(4)映画 フランスの監督
(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(6)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(5)映画 トルコ・イランの映画監督
(8)映画 ギリシアの監督
(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督
(2)映画 ハンガリーの監督
(4)映画 セネガルの監督
(1)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5) 徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり
徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり
ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり
週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)
週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)
イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249
ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり
週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)
ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248
ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44
徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり
ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり
週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)
週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)
イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249
ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり
週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)
ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248
ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内「昭和の文学」
堀田百合子「ただの文士」(岩波書店) 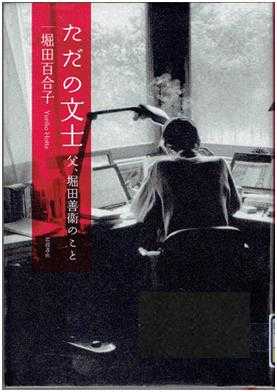
今日は 2022年
の 1月17日
です。神戸の震災の 「思い出(?)」
はいろいろありますが、あのあと、職場の同僚の数人で始めた 「小説を読む会」
が今でも続いています。
今日は 2022年
の 1月17日
です。神戸の震災の 「思い出(?)」
はいろいろありますが、あのあと、職場の同僚の数人で始めた 「小説を読む会」
が今でも続いています。
なんで、そんなことを始めたのかといえば、忙しかったからです。土曜、日曜にクラブ活動の 「指導(?)」 とかで出勤することが当たり前の職場でした。
「あっ、その日はだめです。ベンキョー会があります。」
とか、なんとか、そんな言い訳のいえる日を作りたかったというのが、ぼくの本音でした。
で、その会の今月の課題が 堀田善衛 の 「方丈記私記」(ちくま文庫) なのです。はじめからのメンバーの一人が提案なさいました。20数年、作家の数でいえば、年に20人ほど、合計すれば500人ほどの 「作家」 の著作を読んできたのですが、そういえば 堀田善衛 って読んだことがありませんでした。
推薦なさった方は、最近 「めぐり合いし人びと」(集英社文庫) をお読みになって提案されたようです。 サルトル とか ネルー とかいう人との出会いも出てくる、作家の晩年、1990年ころに書かれた回想集です。その本に対して 「方丈記私記」 は70年ころの著作です。
堀田善衛 といえば、押しも押されぬ戦後文学、 第二次戦後派の巨星 ですが、 「方丈記私記」 は芥川賞受賞作の 「広場の孤独」、「審判」・「海鳴りの底から」 などの初期(?)、 1950年代~60年代 の小説群のあと、 70年代 の 「ゴヤ」 に始まる 評伝の大作群 の仕事の入り口で書かれた中期の傑作で、のちの大作 「定家明月記私抄」 (ちくま学芸文庫) の肩慣らしのようなところもある作品ですが、いわば 堀田版「鴨長明論」 ともいうべき評論だったなあという、ちょっとあやふやな記憶が浮かんできましたが、そのとき、ふと、思いました。
堀田百合子「ただの文士」(岩波書店) ですね。
何かの雑誌の連載なのか、書下ろしなのかはよくわかりませんが、 1998年 に亡くなった 堀田善衛 のお嬢さんである 堀田百合子さん が、最後の日々には 「センセイ」 とお呼になるようになった父上のことを、その記憶の始まりからを思い出して書いていらっしゃるエッセイ集です。
変な言い草ですが、読んでいて便利なのは日時を追ってエピソードが語られ、エピソードに合わせて、その当時の作品が、 堀田百合子さん によって読み直されているところです。
目次はこんな感じです。
もちろん、最後は晩年の 堀田善衛 の姿が描かれるわけですが、 東京大空襲 から 25年 たって 「方丈記私記」 を書いた作家が、その後、 ナポレオン戦争の 「ゴヤ」(集英社文庫・ 全4巻 ) 、 「紅旗征戎非吾」の 「定家明月記私抄 」(ちくま学芸文庫上・下」) をへて、 「エセー全6巻」(岩波文庫) の ミシェル・ド・モンテーニュ の肖像 「ミッシェル 城館の人」(集英社文庫・全3巻) の大仕事の話題がこの思い出の後半のメインです。
で、ぼくの 老爺心 の本音は、







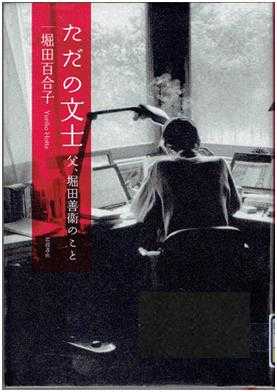
今日は 2022年
の 1月17日
です。神戸の震災の 「思い出(?)」
はいろいろありますが、あのあと、職場の同僚の数人で始めた 「小説を読む会」
が今でも続いています。
今日は 2022年
の 1月17日
です。神戸の震災の 「思い出(?)」
はいろいろありますが、あのあと、職場の同僚の数人で始めた 「小説を読む会」
が今でも続いています。
なんで、そんなことを始めたのかといえば、忙しかったからです。土曜、日曜にクラブ活動の 「指導(?)」 とかで出勤することが当たり前の職場でした。
「あっ、その日はだめです。ベンキョー会があります。」
とか、なんとか、そんな言い訳のいえる日を作りたかったというのが、ぼくの本音でした。
で、その会の今月の課題が 堀田善衛 の 「方丈記私記」(ちくま文庫) なのです。はじめからのメンバーの一人が提案なさいました。20数年、作家の数でいえば、年に20人ほど、合計すれば500人ほどの 「作家」 の著作を読んできたのですが、そういえば 堀田善衛 って読んだことがありませんでした。
推薦なさった方は、最近 「めぐり合いし人びと」(集英社文庫) をお読みになって提案されたようです。 サルトル とか ネルー とかいう人との出会いも出てくる、作家の晩年、1990年ころに書かれた回想集です。その本に対して 「方丈記私記」 は70年ころの著作です。
堀田善衛 といえば、押しも押されぬ戦後文学、 第二次戦後派の巨星 ですが、 「方丈記私記」 は芥川賞受賞作の 「広場の孤独」、「審判」・「海鳴りの底から」 などの初期(?)、 1950年代~60年代 の小説群のあと、 70年代 の 「ゴヤ」 に始まる 評伝の大作群 の仕事の入り口で書かれた中期の傑作で、のちの大作 「定家明月記私抄」 (ちくま学芸文庫) の肩慣らしのようなところもある作品ですが、いわば 堀田版「鴨長明論」 ともいうべき評論だったなあという、ちょっとあやふやな記憶が浮かんできましたが、そのとき、ふと、思いました。
「若い人たちは、そもそも 堀田善衛 とかご存じなのだろうか?」 まあ、大きなお世話なわけで、お読みになって興味をお持ちになれば、他の作品も、というふうでいいわけですが、なんだか妙な老爺心が浮かんできてしまって、
「ああ、あれがいい、あれを案内しよう」 と思ったのがこの本です。
堀田百合子「ただの文士」(岩波書店) ですね。
何かの雑誌の連載なのか、書下ろしなのかはよくわかりませんが、 1998年 に亡くなった 堀田善衛 のお嬢さんである 堀田百合子さん が、最後の日々には 「センセイ」 とお呼になるようになった父上のことを、その記憶の始まりからを思い出して書いていらっしゃるエッセイ集です。
変な言い草ですが、読んでいて便利なのは日時を追ってエピソードが語られ、エピソードに合わせて、その当時の作品が、 堀田百合子さん によって読み直されているところです。
目次はこんな感じです。
目次 1949年生まれ の 百合子さん の思い出が彼女自身の記憶としてくっきりとしてとしてくるのが 「モスラのこと脱走兵」 のあたりからで、 百合子さん が小学生のころのことです。
「サルトルさんの墓」
「芥川賞と火事」
「モスラの子と脱走兵」
「ゴヤさんと武田先生の死」
「スペインへの回想航海」
「アンドリンでの再起」
「埃のプラド美術館」
「夢と現実のグラナダ」
「バルセロナの定家さん」
「半ばお別れ」
一九六一年。 ちなみに、 「方丈記私記」 の話は 一九七一年 、ぼくにとって長年、懸案になっている 「ゴヤ」 の話題が出てくるのは 一九七二年 です。
「三十余年の眠りから醒め 蘇る幻の原作!」
「えッ、この3人が原作者?安保闘争の熱気さめやらぬなか、戦後文学をだ評する3人の作家たちが、新しい大怪獣つくりにいどんだリレー小説。知る人ぞ知る、映画「モスラ」幻の原作、初の単行本化。遊び心と批評精神あふれる想像力の世界」
これは1994年に筑摩書房から出版された「発光妖精モスラ」の、何とも大げさな帯の文章です。初出は1961年の「週刊朝日別冊」、中村真一郎氏、福永武彦氏、堀田善衛、3人の合作小説(?)です。
映画になりました。砧の東宝の撮影所に、父と見学に行きました。中村先生、福永先生もご一緒でした。モスラが撮影所の真ん中にどーんと鎮座していました。モスラくんは大きな芋虫もどき、ゴジラより私は好きでした。七月、「モスラ」は全国の映画館で封切られ、なかなかの人気でした。夏休みが明け、学校に行くと、休み時間にどこからともなく、「モスラーヤ、モスラー」という歌が聞こえてきます。
私は穴があったら入りたかった。この原作に父も加わっていることを友達に知られたくなかった。この映画が、いかに、どのような意味がこめられていようとも、そんなことは子供にわかるはずがないのです。子供社会は難しい。モスラの子(?)などと、絶対に言われたくなかった。(P43)
一九七二年前半のころ、「朝日ジャーナル」誌より、翌73年からの連載の依頼がありました。「ゴヤ」です。父は、まだ早い、まだ取材が済んでいない、まだ見なければならない絵がたくさんある、と言って連載の依頼をいったん断りました。 と、まあ、こんな感じなのですが、それぞれのトピックは 「モスラ」 の話であれば、ベトナム戦争に従軍するアメリカの脱走兵をかくまう話とか、 「ゴヤ」 であれば、親友 武田泰淳の死 であるとかと重ねて思い出されています。そこに、 堀田善衛 という作家の社会や歴史に対する基本姿勢のようなものが浮かび上がってきて、ぼくには印象深い話になっていました。
母は言います。
「来年は五五歳にになる。「ゴヤ」を書くには体力がいる。今、始めなければ、もう書けない。残りの取材は書きながらすればいい」と、父のお尻を叩きました。
父は色よい返事をしないまま、七三年六月にA・A作家会議常設事務局会議に出席するためにモスクワへ出かけました。帰国後、父は言います。
「来年からゴヤをやることにする。モスクワからの帰りがけ、パリとマドリードへ寄った。何とかなるだろう。半年連載して、半年休み。その間に次の取材をする」
大仕事を開始するときに、父は家族に向かって一大宣言をするのが慣わしでした。そして最後に、「よろしく頼む」と言うのです。
「ゴヤ」のときはもう一言ありました。
「取材費はすべてこちら持ち。朝日には頼まない。それで手枷、足枷がつくのはご免だ」
「今までさんざん自前でやってきたじゃないの」と、母は笑っていました。
この後、母は「ゴヤ」執筆に父が専念できるよう、父の前に立ちはだかりました。編集者の方々は、母の関門を突破しないと、父に原稿の依頼ができません。父が電話に出ることはめったにありませんでしたから。出版界で噂されていたそうです。「披露山のライオン」と・・・・・。(P77)
もちろん、最後は晩年の 堀田善衛 の姿が描かれるわけですが、 東京大空襲 から 25年 たって 「方丈記私記」 を書いた作家が、その後、 ナポレオン戦争の 「ゴヤ」(集英社文庫・ 全4巻 ) 、 「紅旗征戎非吾」の 「定家明月記私抄 」(ちくま学芸文庫上・下」) をへて、 「エセー全6巻」(岩波文庫) の ミシェル・ド・モンテーニュ の肖像 「ミッシェル 城館の人」(集英社文庫・全3巻) の大仕事の話題がこの思い出の後半のメインです。
で、ぼくの 老爺心 の本音は、
「せっかく、堀田善衛を読むなら、ここまで付き合ってあげてね!」 とでもいうべきものです。テレビのグルメ番組のようなことをいってますが、若い読書グルメの皆さんが、前菜 「方丈記私記」 に続けて用意されている、メインディッシュに気づいて頂きたい一心の案内でした。 まあ、腹いっぱいどころではすまない量ですがね(笑)。



お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「昭和の文学」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 永井荷風「濹東奇譚」(… 2024.02.25
-
週刊 読書案内 幸田文「木」(新潮文庫) 2024.01.03
-
週刊 読書案内 野上彌生子「森」(新潮… 2023.07.16
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.













