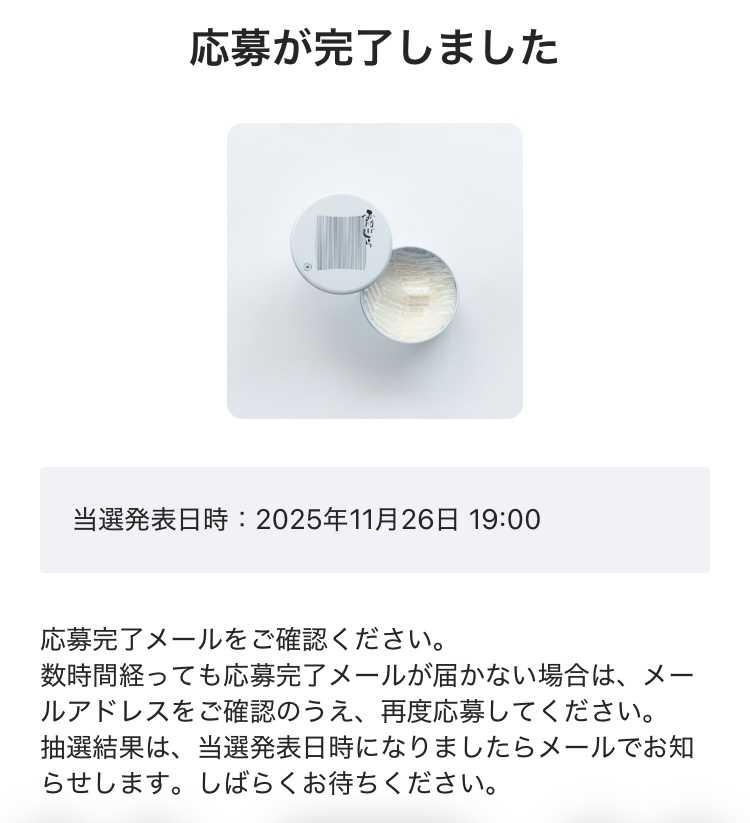2007年06月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
オマージュを別のかたちで。
『株式会社という病』は、順調に売れているようである。黙っていても、企業が次から次へと不祥事を起こしてくれるので宣伝になっているのである。いわば、敵失で得点しているようなもので、あまり喜んでばかりはいられない。この本は、前著で試みたビジネスの構造を描くところから一歩踏み込んで、ビジネスの肉体とでもいうものを記述して見ようと思って書いたものである。ただ、そこには、もうひとつのひそかな「思い」があった。最後までお読みいただいた方は唐突に、二行の詩句が挿入されることにお気づきかもしれない。「光を集める生活は それだけ深い闇をつくり出すだろう」という、清水哲男の『短い鉄の橋を渡って』という詩の一部である。俺は、このブログにも清水哲男については、何度か書いていると思う。こんな感じでね。短い鉄の橋を渡って私が出発したとする激流からの距離が磁石が鉄をひくように私の悲しみの位置を定めたとするこの「出発したとする」というまさに、「出発」の取消しを含む表現にまず圧倒される。私は出発していないのである。哲男さんは、絶対伊東静雄を意識していると思う。勿論それは、「わが人に与うる哀歌」である。太陽は美しく輝きあるひは 太陽の美しく輝くことを希ひ手をかたくくみあはせしづかに私たちは歩いて行つた二行目が一行目を打ち消すような文体。ここでも、太陽は美しく輝いていないのである。この屈折によって、伊東静雄は日本浪漫派の他の詩人から抜きん出た表現者の位置を獲得したと言ってもよいと思う。一見、そうは見えないが、哲男さんは抒情の前線@(清岡卓行)で耐えている詩人であると思う。日本浪漫派のしっぽを残しているといってもよい。それを、このようなモダニズムの衣にくるんで湿気をぬいて、硬質な抒情として表現してみせた。いまはもう君はこんなふうに話さないだろう死んでゆく小鳥が最後に放した枝のように深い息づかいを世界につたあえてむしろ忘れられることを望むのだ光を集める生活はそれだけ深い闇をつくり出すだろう 70年代の後半、俺の元に届いた現代詩年鑑にその詩は掲載されていた。それまで、鮎川信夫や、北村太郎、田村隆一といった荒地派の詩人たちの作品に耽溺したものである。そして、かれらの作った重厚で深みのある戦後的な世界にほとんど窒息しかけていたのだと思う。清水の詩句に出会ったとき、目の前の霧が晴れるように視界が開け新しい空気が流れ込んでくるような爽快な気持ちであった。ただ、その詩が持っていた、易しく鮮烈な言葉と輻輳して読む度に色合いを変える意味がつくる感覚は、その後三十年以上にわたって、のど元に引っかかることになる。それが何かは、ひとことで言い表すことはできない。また、うまく言える自信もない。いつか、清水のこの作品のようなものを何か別のかたちで表現できないものかという思い込みが残ったとでも言うべきかもしれない。もうお分かりだろうが、『株式会社という病』は、現在のビジネス状況を分析するビジネス書として書かれてはいるが、同時に清水哲男へのオマージュでもある。献辞には、なにも書かれていないが、「清水さんへ」と見えない文字で書いたような気持ちでいた。そして、昨日、その清水さんと仕事でお会いすることになったのである。実際に、この詩人とお会いするなどということは考えてもいないことであった。俺の中にある清水さんは、京都の町に逼塞しながら、輝くような言葉を携えたゲリラ戦士のように詩を書き付ける紅顔の青年であり、会うことのない兄貴分といったところであった。実際にお会いした清水さんは想像よりは、お年をめされていた。数時間の邂逅ではあったが、俺は、身体ごと一気に「あの頃」へ送り戻されたような気持ちになった。忘れていたことをたくさん思い出させてくれる会話というもの。それが、楽しくないわけはない。そして、かれとお会いできることになった僥倖に感謝したい気持ちにもなったのである。世の中は、捨てたもんじゃない。生きていれば見なくていいものを見、聞かなくてもいい声を聞かなければならない。それは、あまり楽しいことではないがいいこともある。
2007.06.29
コメント(8)
-
三代目の資質。
内田くんが俺のブログに言及してくれているお陰で、アクセスが急上昇である。もうすぐ100万アクセスを突破する。カウンターの桁が100万以上はないので、どうなるのかが楽しみである。文字の色が変わるとか。確変マークがでるとか。さて、俺は「一年で全て解決する」と総理が言明したことに関して「そりゃ、お里が知れる。誰か総理をサポートしてやれ」といった(ちょっと違うけど)私見を書いた。これに対して、内田くんは、一年以内の解決は無理だということはむしろ周知の事実であり、本邦の総理もさすがに、それは分かっているはずだとして、こんなコメントを書いている。― つまり「1年以内」というのは技術的な評価ではなく、政治的な言明だということである。もちろん総理だって、1年以内に問題が解決するはずがないことは知っている安倍総理は、参院選をにらんで、かれにとってより重大な「戦後レジームからの脱却」が、こんな「浮世の心配」ごとで頓挫しないように(つまりは、参院選での歴史的な敗北とそれに続く失脚を回避するために)できないと知りつつ、できると宣言した「はずである」と書いている。マヌーバーを使ったということである。(表現はちょっと違うけど)いちいち引用するのがめんどうなので、だいたいこういうやり取りだということでご勘弁願いたい。ともかくも、二人とも結構「意地の悪い」ことを言っている。さて、そこでである。安倍総理が、技術的には解決不能な問題を、それと知りつつ政治的な言明として、表出したというのは、可能性としてはありうる。しかし、俺はどうも、すこし疑問に思っているのである。(その疑問の由来が、「お里」という表現になったわけである)どういう疑問か。俺も総理がそのようなことを知りつつ、ただアナウンス効果の最適化を狙っての方便としての、政治的な言明を行ったと思いたい。俺とて、政治家に清廉潔白、高潔無垢などは期待の外で、かれの祖父がそうであったように、政治の場面において、清濁併せ呑む、腹芸の使い手であってかまわないと思っているのである。いや、そうあるべきだと思う。しかし、ひょっとして、わが総理は「本当のこと」を言おうとしたのではないかと考えて見る。「自分は本当のことを言っていると思っている」と思えるふしがあるのである。つまり、総理の言明は、言っていることそのままではないか、ということである。かれは自分が一年で解決できると言えば、それは解決できるのだと思っているとしたらどうなんだということである。俺はそこに、かれの政治家としての「お里」を見てしまうのである。高名な政治家の家系に生まれて、かれは同世代のどんな子供たちよりも「不可能との直面」という事態から隔離された境遇であったのではないかということである。勉学やキャリアのためならば、欲しいものは手に入り、経済的な労苦はなく、将来の憂いもない。かれの周囲にいただろう「教育係」は、祖父たちの行ってきた政治のダークサイドに関しては、それを「なかったこと」としてかれに伝え、かれもまたそれを「なかったこと」として受け取らなければかれは青年期を、負債なしで潜り抜けることはできなかったと想像してみる。(そのことはかれの責任ではないし、他人からとやかく言われる筋合いはない。ただ、そういうことはありうるかもしれないということを言っているだけである。)そういった曲折を経て、かれは己の清廉潔白を信じるような、義に篤いタイプの政治家になったという可能性は、排除できない。かれの祖父は、そうではなかった。「国体」を維持し、経世済民、のみならず一族の利権も存続してゆくためには使えるものはそれが、無法のものであろうが、アメリカであろうが、悪魔であろうが何とでも手を結ぶし、黒いものも白と、何の自責の念も無く言い募ることで、自らの政治的な生命を全うしたのだとおもう。(勿論それを、どう評価するかは別の問題である。 よく言われるように、政治家とはつねに、かれが何を考えていたかではなく、かれが何を実現したかということで評価されるべきだからだ。)これは意地の悪い想像なのだが、若き日のわが総理が、自分が正しいと信じ、こうしたいと思ったことがなぜかそのまま実現してしまうというような三代目の若旦那という境遇に対して、かれが疑念を抱いたというようなことはあまりなかったように思える。(疑念を抱いたとすれば、かれは政治家という人生を選択しなかったはずだから。青年にとっては、自分が恵まれているという、まさにそのことが最大の恥辱になったりするものだ。)しかし、かれは政治家になった。若旦那の希望を適えるために、その意を汲んだり、慮ったりしながら、周囲が動くということが無かったとは言い難い。かくして、かれは政界のプリンスになったのである。今回の問題のように、国政における、さしせまった損得勘定の範囲で、この若旦那の「無垢のちから」が発揮されているうちは、どっちに転んでも致命的な問題にはならないような気がする。どこかで官僚システムのフェールセーフ機構が機能するだろうし、国民は成熟している。内政において、やることが山積みになっているということは、政治的には大変に好ましい状況だと言わざるを得ない。もし、やるべきことが一段落したとき、「義に篤い」政治家は何を考えるだろうか。「教育係」が教えてきた「戦後レジームの不純」といったストーリーラインを学んで、倫理の問題として、「憲法の改正」や「レジーム変換」を自らの政治的使命だと思ったとすれば、それこそ、国民全員を「かなり危険な」賭けに随伴させることになるだろうと俺は危惧するのである。歴史の中で、腐敗した権力というものは確かに、国民を絶望的な気持ちにさせるかもしれないが、人々はおのおのの工夫で生活をつくってきた。しかし、おのれの「正義」をなすために、国民を動員する権力者は、しばしば国民の生活そのものを、「正義」と交換することを要求してきたからである。
2007.06.26
コメント(1)
-
年金問題解決法。
昨日は、年金の問題について思うところを書こうと思って書き始めたらミート・ホープの偽島田洋七の話になってしまった。ま、似たような羊頭狗肉話なのでどこかで話の筋がこんがらがってしまったのである。年金については、与党も野党も、蕎麦屋も床屋も、質屋も銀行マンも、月給取りも給料泥棒もあーでもない、コーディアルと勝手気儘なことを言っているが本当のことは実は誰も言っていない。いや、何が本当かなんて誰にも分からないし分かったところでどうすることもできないのであるが、年金問題で分かっていることは誰もが、「払ったものは返してくれよ」と言っており、誰も「俺が悪かった」とゴメンを言わないってことぐらいだろう。要するに「何が何だかわからない」ということである。俺はかつてデータベースの10万件のデータの整合性チェック泥沼にはまり込み会社にひと月泊まりこんだ苦い経験があるのですこしばかり、今回の事件の肝がどういうものか実感できるのである。今回のケースは何とまあ5,000万件のゴミ(データ処理の文脈の話ですよ。)の処理である。政治的な責任やシステムの問題も確かにあるが、今となっては、これは純粋に技術的な問題なのである。そして、俺の体験から生まれた実感から言わせていただければ、これはもうあかんということである。つまりね、あれ、もうどうやっても駄目だぜということである。いじればいじるほど、ゴミが増えることはあっても、無くなることはない。たぶん、データベースエンジニアなら、名寄せソフトを使おうが、人力に頼ろうが、もう正規のものに復元することができないと判断するだろう。これは、もはや、こんがらがってブツ切れになったスパゲッテイの残骸なのである。ASAHI.COMによると、次のような事情が報道されている。「国民年金制度が発足し、「国民皆年金」が実現した61年以降、社保庁は保険料を徴収する市町村に5年は台帳を保存するよう指示していた。地方分権一括法によって同庁が自ら集めるようになった02年度以降は、そのルールもなくなった。 それは市町村の納付記録がきちんと社保庁に伝わり、管理されているという前提だった。だが、ほころびが露呈し始め、同庁は昨年8月、改めて市町村に記録保存を求めた。領収書などがなく、社保庁で記録が見つからない人にとって、市町村に残っていた記録が命綱になることもある。」さて、今回の問題が露見して以来、野党が責任の追及を開始し、安倍首相が一年以内にすべて解決するなどと言い、法律関係者や社会保険のプロなどから構成される第三者委員会(実に三百人規模)が設置され、システムをつくったNTTデータ社に確認し、各自治体の原本照会をするといった具合に、一見解決に向けて動き出そうとしているかのように見える。しかし、すでに述べたように、五千万件のデータ不整合と、原本の散逸といった事態の解決は、データベース的にはほとんどミッション・インポシブルなのである。それを、一年以内で解決なんて宣言してしまう総理は、お里が知れるっていうものである。情報処理に詳しい下々は、青くなっているだろう。誰か、ちゃんとアドバイスできないのかね。で、問題を整理して見る。現在、基礎年金番号や、住基台帳などを元にして、国民データをコンピュータで一元管理することを考えている政治家が多いようだが、これがどんなに危険なこと(システム的にですよ)か、今回の事例を教訓とすべきだろう。今回の件も、もし各自治体毎に管理していれば、リスクは限りなく分散されていたはずである。膨大なデータを、いくつかの異なるシステムで運用するというリスク分散は、コンピュータの世界の常識である。ひとつには、軍事的な理由から、もうひとつは運用の容易さという理由からである。勿論、この「原理」は生物のエコロジカル・ニッチという生存戦略にも適合している。これが忘れられるようになったのは、コンピュータの情報処理量が飛躍的に増大したこと、中央集権的な管理の方が効率がよいと考えられたからである。その驕りと、慢心をこれを機に改めるべきだろう。では、目下の年金問題に関してはどうすればいいのか。これに関しては、ほとんど絶望的なのだが、まったく出口がないわけではない。今回の問題は、確かにデータはゴミの山のようになっているが、失われてしまったわけではない。(一部失われたものもあるようだが)これをデータベース的に正規化する経験と、推理能力を持った有能なスーパー・データ・ベースアーキテクトに全国から名乗り出てもらうということである。つまり、賞金稼ぎの天才ガンマンに頼るということである。このスーパーエンジニアは、数人いればよい。あとは、権限を与えられた彼らの下で処理を請け負う有能なエンジニア群が必要である。(三百人もの第三者委員会は、結局何もできない)これが、もっとも有効な「手」のはずだが、誰もこれを言わないね。 もうひとつは、どこかで解決をあきらめて、落としどころを決めるということだろう。つまり、誰かがゴメンと天下に宣言して、それに対して国民的な合意のもとで、全体の支給額を減らすか、どこかから財源を見つけ出してきて、不明者の自己申告を一定の枠の中でそのまま(証拠がなくとも)認めるということである。つまり、最低受給額だけは、無条件で確保する。それじゃ、いままで正直に納めてきたものとの間に、不公平が生じるじゃないかって?「そりゃ、その通りだが、そこはひとつ大人の解決を」っていって頭を下げる。まあ、これも年金残高が本当に生きていることが条件だけど。こういうことがあっても、暴動にならないところがこの国の救いである。(これも戦後レジームのお陰だぜ)コクミンの慈悲を請うってのは無様だが、政治的にはこれしかないのである。だいいち、不公平なんて、いまに始まった話じゃないし。
2007.06.25
コメント(2)
-
善悪もまたあざなえる縄のごとし。
雨ふる日曜日。まるの歯を磨く。まるは歯槽膿漏が悪化している。歯茎から血が出て、吐息が臭い。歯ぐらい自分で磨けよ。そう、つぶやきながら、ごしごしと磨いてやる。やはり、医者で根底的に歯石をとらないとだめなのかもしれない。俺も歯槽膿漏で苦しんだ。喫煙が歯茎に悪い影響を与えるという。まるも、俺に隠れて喫煙しているのだろうか。ヘビースモーカー犬。酒も飲むのか。酔いどれ犬。暗い雨ふる日曜日に、加齢臭のおやじが、加齢臭のポチと散歩している図は長寿国の未来図である。哀愁はあるが、悲惨とは言えない。豚肉を牛肉と偽って売っていた業者がいた。食べて見ると、牛肉の色をしていて、牛肉の味がするそうである。「がんもどき」ならぬ「牛肉もどき」である。鉄分調合と味覚の研究を重ねて、コストダウンを図ったのであろう。♪どうせあたしを、だますなら だまし続けて欲しかったほかに、何が言える?このおっさんを、極悪非道の罪人であるとマスコミも識者も指弾しているが、競争優位、コストダウン、利潤追求をつきつめればこれは「経営努力」のひとつの必然ではないのか。俺は、この「島田洋七もどき」(似ている!)のおっさんを弁護するつもりはないけれど、このおっさんが、商品に「牛肉」と表示せずに、「牛肉風」と表示すれば何の問題もなかったということなのか。だとすれば、かれの罪はただ、表示を偽ったこと「だけ」である。魚肉ソーセージが、大好物であった俺はつい、そんなふうに思ってしまう。残余は、己の味覚に騙されて食った奴の自己責任である。騙された方が悪いというのは、自己決定、自己責任、自己実現を旨とするグローバル市場主義の必然的な結果であって、みんなで市場経済に加担してきたのである。「利潤」は透明な記号で、その中にはいかなる倫理も道徳も含まれてはいないと。「利潤」が試算表の数字になった瞬間に、それを生み出した製造プロセスの文脈が外されて、経営手腕や立身出世の物語が始まるのである。商工リサーチや、帝国データバンクの信用調査の文脈の中に製造倫理や販売倫理といったものはカウントされることはない。金融機関の与信設定も、同じである。試算表に計上される数字だけが信用の担保だということにしてきたわけだ。このような製造プロセスと、資本蓄積プロセスの乖離の総体を俺は「病」と呼んだのだと思う。しかし、だからと言って、企業およびその活動のすべてが腐っているといいたいわけではない。腐っているものはすべて廃棄すべきだとも思わない。同時に、この病が発症して引き起こされた企業不祥事の原因がすべて倫理観の欠如した悪しき経営者にあるわけでもない。先の爆発エステの社長や、偽装建築士や、今回の偽島田洋七に対するヒステリックな難詰の声の主たちは、正義は我にありとでも思っているのだろうか。しかし、世界は善と悪、平和と戦争、勝者と敗者によって成り立っているような単純で分かりやすいものではないだろう。単純で分かりやすい思考の中にだけ、単純で分かりやすい世界があるだけである。本当は世界は単純でもなければ、必要以上に複雑にもならない。アダム・スミスが言ったように、人間は自分がそうしようと思うこととは違うことを実現してしまうということである。だから善悪はあざなえる縄のごとく映ずる。そのことの意味が分からなければ、善は悪に、平和は戦争に、勝者は敗者に容易に入れ替わる。人間は、自分に似せて病を内包したシステムを作り出し、その上で生きているということに自覚的であるべきだといいたいだけである。(じゃあ、どうすりゃいいと言うんだよ。)だから、何度も言っている。病は無くなりはしない。必要なのは、病の自覚と、そこからしか導き出されない「節度」だと。夜半に雨が上がる。溝口健二の『赤線地帯』を見る。このリアリズムは悲惨だが、絶望的とは言えない。
2007.06.24
コメント(6)
-
一体、この世界はどんなふうにできているのか。
以前、「偶然の街角、偶然の車窓」というエントリをしたことがあった。3月4日の話である。横浜駅から京浜東北に乗り込んで、つり革にぶら下がると、目の前に、前日酒席をともにしていただいた三遊亭円丈師匠が座っていた。その少し前、目黒駅近くのルノアールでいつものように『株式会社という病』の原稿を書いていたら、そこに偶然にも、木村政雄さんが入ってきた。木村さんとは、一年ぐらい前にも都ホテルのラウンジで偶然にお会いしていたので、そのときの偶然が何か見えない必然の糸の終端を俺が踏んでいるような気がしたのである。木村さんと前回お会いしたときは、俺が『反戦略的ビジネスのすすめ』を書き始めた頃だった。日曜日の夜に、お江戸日本橋亭で、円丈師匠の落語を聞いた。明けて月曜日、秋葉原の伊万里という骨董カフェで打ち合わせをしてオフィスに戻る途中でばったりと再び三遊亭円丈師匠にお会いした。「あ、どうも」「あ、いや、どうも」打ち合わせの席で、円丈師匠の話をしたばかりであったので、俺はあまりの偶然にどぎまきしたのである。世界で最大の人口がひしめく東京の街角で同じひとに、二度会う偶然は、確率的にはどのくらいのものなのだろうか。俺は円丈師匠に二度会い、木村さんに二度あった。話はそれで終わらない。偶然がいくつか重なると、信じられないようなことが起こる。以下は、一滴の虚構も、脚色も混じっていない実話である。2005年5月にも俺は「偶然の旅行者」というエントリを書いている。そこにはこんなことが書かれている。― この一週間、会うはずのない人々とお会いする機会が頻発している。シリコンバレーでお隣で会社を経営していた茂田さんから突然、電話がある。「偶然、ブログを拝見しまして」「おお、お久し振り、それじゃ月曜日にでもお会いしましょう。」この二日前、やはりシリコンバレーのビジネスカフェでオフィスマネージャーだった奥山くんからメールが入る。「帰ってきました。」「おお、元気?それじゃ今晩飯でも食いましょう。」今日は、アーバン時代からの社員だった待場くんがニューヨーク役者修行から戻ってきたという。「お久し振りです。」「おお、じゃいまから寿司でもくいにいくべ。」こんな風にして、おそらくはそのまま生き別れになってもおかしくはない人々が偶然にも集まってきたのである。さて、この日の俺のブログをインターネットで偶然に発見し、以後ずっと読み続けてきた人間がいた。だいぶ前にカリフォルニアで会って以来、再び会うことがあるだろうかと思っていた人間である。『東京ファイティングキッズ』にも登場する東京から家出して、カリフォルニアにたどり着き、そこで、ヒスパニックの家庭にホームステイした吉田光博くんである。通称ミッツ。彼の流浪の旅がそこから始まり、最後に俺の会社に流れ着く。十年の歳月を経て、ミッツと俺は仕事で、彼の流浪の出発点であったカリフォルニアに出張し、その地で、ヒスパニックの家族に面会してみようということになった。その顛末は、『ファイティングキッズ』に記したが、あたかもハートウォーミングなテレビドラマを見ているような感興があった。さて、本日、新宿のラジオカフェで仕事を済ませて俺は、先日の『高橋源一郎・内田樹・平川克美の三酔人経綸問答』をイヤホンで聞きながら、山手線に座っていた。ふと顔を上げると、俺のまん前のつり革の男と目が合った。男の顔がゆがんだ。「社長。」「え。」「連絡しなくて申し訳ありませんでした。」俺は一瞬目を疑った。「おお。よせやい。ホントかよ。」その男は、本を読んでいて、ふと目の前のベンチの俺を見て俺が以前彼が勤めていた会社の社長であることを悟ったのである。これも、偶然という言葉で説明できるものなのだろうか。まるで、ハートウォーミングな韓流ドラマのようじゃないか。「僕、帰ってきたんです。連絡できなくて、胸が痛かったのです。社長が丁度、「偶然の旅行者」というブログを書いたときに「偶然」サイトを発見して、それからずっと社長のブログ読んでいたんです。」その男、吉田光博くん、すなわちミッツと、俺はこうして出会うことになったのである。出会うことのありえない、カリフォルニアと東京の空間を圧縮した混雑した山手線の中で。彼は、読んでいた本のカバーを外して、俺に見せてくれた。表紙には『株式会社という病』と書いてあった。
2007.06.21
コメント(2)
-
ニキビ面の高校生に、二度なった週末。
あー、忙しい。眠い。土曜日は、『ラジオの街で逢いましょう』の収録がふたつ。ラジオ関西で放送されている、ラジオデイズの対談番組である。一人目のゲストは原賀真紀子さん。シカゴトリビューンや、アエラに寄稿しているフリージャーナリスト。大手都市銀行勤務の後、アメリカの大学院でジャーナリズムを学ぶという経歴。それって、俺の一番苦手な、「外資熱」に罹った、その手のおなごじゃないのか(いや、勿論偏見ですが)「アキバ熱」@柳家小ゑん、も厄介な病だが、「外資熱」はさらに始末が悪いのである。「わたし、つんけんしているように見られますがコテコテのドメなんですよ。」という言葉に、うれしくなって、初対面にも拘らず、なんだか意気投合。いい奴だと感じていた期待が裏切られた場合は、もう二度と面見せるんじゃねぇぞといった気分になるが、逆の場合は干天に雨に会ったような気持ちになる。「雨ふるふるさとはだしであるく」といった按配で、そのままラジオのスタジオまで来ていただいた。ジャーナリズム論、コミュニティ論を語っていただいた。二人目のゲストは内田くん。エイハブ船長といった風情で、右足を引き摺りながらの登場。(このあたりの事情は内田ブログに詳しい。)マイクロフォンを立てて、内田くんと面と向かって話をするなんてことができるのだろうかと、思っていたが朝カルでの対談以来、こんなかたちでしか、まとまった話をしていない。こっちはホストなので、ホストっぽい声を出したら「よせやい、ヒラカワくん。気持ちワリイ」とクレームがつく。結局、内田くんとは、どこでどんなシチュエーションで話をしても居酒屋のカウンターの酔っ払い話になってしまう。その夜は、朝日新聞の大槻さん主宰の『小池昌代さんを囲む会』ではなく、『東京ファイティングキッズ』打上げ。内田くんは、これを「クラスの美少女を前にしたにきび面の高校生」と形容。うまい。まったく、聡明な美女の前では俺たちはいつも、にきび面の高校生である。この年になって、高校生気分を味わえることを、至福と言う。翌日曜日は、『高橋源一郎VS内田樹対談』の収録であったが、「ヒラカワくんもいっちょかみするんでしょ。ね、そうしようぜ」ということで、何だか訳の分からない鼎談になってしまった。その瞬間俺は、高名な小説家を前にした「にきび面」の高校生になってしまったのである。文学の現在についてもっとも真剣に思考し、思考の海のもっとも深いところから言葉を拾ってきて小説を書いたとすれば、それは、高橋源一郎の書くような「小説」になるはずである。しかし、『さようならギャングたち』の頃に誰がそれを見抜くことができただろうかと思う。(吉本隆明がいたんだね)そんな話を、この偉大な着流しのあんちゃん風の巨匠にお聞きするという「いっちょかみ」であった。俺にとっては、面白いというよりは極上の酒を味わっているような至福の座談であった。その後の、内田、高橋対談は、砂かぶりで四つ相撲を見入るような贅沢な時間。(なお、この対談は、9月以降に、ラジオデイズで販売される予定である)仕事がはけると夜はお江戸日本橋亭へ直行。ぬう生、喬太郎、小ゑん、円丈、モロ師岡。蕎太郎の、古典の皮を被った古典と銘打った「おせつ徳三郎」に酔う。さらに、一夜明け、翌朝は会社で会議をやってそのまま大阪へ。木村政雄さんとお仕事の話をしてから140Bの株主総会へ出席。おなじみの関西連合の面々に囲まれて酸欠状態となる。息を抜く暇が無い、というかずっと、息を抜きっぱなしにせにゃ、生きてはいけない状態であった。
2007.06.19
コメント(0)
-
お詫びと愚痴と著作権と。
前回のエントリーで、ラジオデイズで上野茂都の曲を流すという告知をしましたが、本日アップされたサイトで聞いて見ると音曲部分がカットされている。え、な、何故。(俺は約束しちゃたし)実は、JASRACと、インターネットストリーミング放送に関する契約で、話し合いをしておりまして、まだ結論が出ておらず、とりあえず今回はやむなくカットして放送ということになりました。上野『煮込みワルツ』を期待されていた皆様には伏してお詫び申し上げます。だもんで、とりあえず、どうしても聞いて見たいという方はお金を払ってお買い上げいただくしかないのである。すまない。http://ironbridge.exblog.jp/i24上野さん自身は全く権利問題には興味はないようでご本人も著作権の委託をしていないのであるが、彼の音源を製作した会社が、JASRACに全権委託をしているため、縛りがかかった訳である。まあ、お金払えば問題ないのであるが、インターネット放送に関してはあいまいな点が多く現在JASRACに問い合わせ中ということである。俺はこの、著作権問題というものを考えると人間のさかしらに悲しさを覚えるのである。勿論、著作者には、なにがしかの権利がある。その著作物を販売するものは、著作者に対して、お金を支払うのは当然である。しかし、そこにはおのずと、限度というものがある。知的財産権が今日のような形でクローズアップされたのはレーガン政権のときである。対日批判で名を馳せた元ヒューレット・パッカードのジョン・ヤング会長(当時)が、ヤング・レポートを書いて、知的財産権意識の薄い日本などの貿易国を非難したのである。レーガノミクスといえばまさにレッセフェールを強力に推し進めた市場万能の競争的な経済思想である。知的財産権は、この競争的な世界観なしには成り立たない概念で、ヤング・レポートにおいては、製造業に低迷していたアメリカで、製品が売れないのは、自国内の問題ではなく、日本を始めとしたモノマネ上手な国家がアメリカの知的財産を侵して、作ったものを自給したり、輸出したりしているからだとして、貿易国を知的財産権というもので締め上げようといった戦略が示されたわけである。(いや、読んでいないので詳細はわからないけれど、まあ、そういったことが当時報道されていたと思う。)それは、自国の知的な優位性を固定化するための競争的な戦略であり、これによって、台頭してくる新勢力を押さえ込むというものであった。まさに、アメリカ的な、持てるもののいやらしい戦略である。その後、アメリカはパテント優位の政策を徹底し、多くの訴訟を起こし、膨大な賠償金を請求し、それによって競争優位を固定化するという政策に邁進することになったのは記憶に新しい。グローバリズムの流入とともに、このアメリカのパテント戦略にいじめられてきた日本においても、対抗的にパテント戦略をとることになる。国家的な競争戦略として知的財産権というものが利用されるということについては、確かにいやらしいことだとは思うが、国益とは畢竟するところ自国のエゴであり、政治家とは自国のエゴの擁護者であるわけで、文句を言っても始まらない。国家は地球を分割し、資源を囲い込む争いをしてきたわけである。その延長上に、かたちのない知的な財産まで、国家戦略として囲い込もうとしたところにヤング・レポートの功績があったわけだろう。でもさ、個人までそのような競争戦略をあたかも自然権でもあるかのようにありがたがる必要はないじゃないかと、俺は思う。高橋源一郎さんも書いているように(『文学なんかこわくない』)、人間というもののアイデンティティをどこまでも切り刻んでいくと最後に残るのは母国語としての言語というたよりない根拠に逢着する。その根拠さえ絶えず揺らいでいるのが人間の世界というものである。個人にとっての知的な財産とは何だろうか。それもまた、行き着くところは言葉ということになるのではないか。勿論美術や、音楽という表現まで含めた広い意味での言葉、マルクスが言うところの意識と同じだけ古い言葉である。俺たちは日本語で考え、日本語で他者と結びつく。俺が小説を書く。詩をつくる。音楽を作曲するときに、俺は俺だけの日本語、俺だけの音感でそれらを作っているわけではない。日本語というものもまた、日本人というものが意識されてからこの方、歴史の中を受け継がれ引き継がれてきたものである。つまりそれは、俺のものであって、俺のものではないのである。およそ、文化というものが成立する基底にはこの「俺のものであって、同時に俺のものではない」ということが「あたりまえ」に含意させていなければならない。そうでなければ、人間は人間とコミュニケートしたいとは思わないし、自分のものを他者のものと交換したいとも思わない。「自分だけが知っている価値」という言い方自体が言語矛盾なのである。そのような基底を背景にして生まれてくる知的な創造物は、では誰のものなのか。俺は詩を書いたとして、それは俺のものではない共有地にあった言葉を拾い集めてつくり、俺の記憶の中に堆積していて俺が気がついていない俺のものではない感覚を呼び覚まし、俺のものかどうかいまひとつ判然としていない「ヒラカワカツミ」というサインで署名するのである。果たしてこれは俺のものだと大声で主張することは恥ずかしくないことなのであろうか。ややこしい言い方をして申し訳ないが、要するに純粋にいち個人だけに属するような知的財産などは存在しないということである。いや、存在した瞬間にそれは、他者にとってはまったく無用で無意味なものにならざるを得ない。勿論、それが存在するかしないかは、時と場合によることは俺だって知っている。ひとつは、法律文書の中であり、もうひとつはビジネス上の価格の中である。つまり、知的な財産権を大声で主張するのは、それが競争的な場に引き出された場合に限定されてしかるべきではないだろうかと、俺は思うのである。それ以外の場合は、まあ、ひとことで言ってしまえば了見の問題である。九十年代以降、やたらと知的な財産権、著作権を叫ぶ声が大きくなったように思うのは俺だけだろうか。そして、その声が大きければ大きいだけ、そいつの了見が無限小に縮んで見えるのである。知的財産権の主張。それは「青年の主張」と同じぐらい恥ずかしい主張だ。
2007.06.15
コメント(3)
-
ちょっとしたお知らせ。
長らくお待たせいたしました『株式会社という病』が今週金曜日発売となります。写真のような美しい装丁がタイトルのおどろおどろしさを中和させてくれて手に取りやすい本に仕上がりました。書店にてお買い上げいただければ幸いです。(内田くんが書店ポップ用の「内容保証書」を作ってくれました。どこかでお目にかかれると思います)さて、ラジオデイズの「ラジオ番組」に今週あたり、上野茂都さんとの対談がアップされる予定です。以前より何度も書いてきたので耳にたこでしょうが、その音曲をこういったかたちで、お届けできるのがうれしい。スタジオ実演の『煮込みワルツ』です。お楽しみください。
2007.06.13
コメント(0)
-
天の配剤。
忙しい週末であった。八日金曜日は、武蔵小山アゲインでの『ラジオデイズ落語会』。柳家ろべえ、入船亭扇遊、桃月庵白酒。扇遊師匠は、「浮世床」「試し酒」白酒師匠は、「転宅」「長命」。ご両人とも、安定した高座で大いに堪能。会がはねてご一緒にばれ話に花を咲かせて飲んでいるときの写真がこれ。白酒さん、何といっても顔が得をしている。南シンボー以上にオムスビなのである。それが、伝法な女をやらせたら一変、得体の知れない色っぽさのオーラを出す。扇遊師匠の実演は初めての経験であったが、実にほどよい味をにじませることのできる師匠である。だいたい、やり過ぎちゃうからね。ほどよいとは、これほど心地よいものかと思う。翌土曜日は、国立演芸場での『ワザオギ落語会』。チケットの入手困難なほどの人気。会場に着くと何と、ワザオギプロデューサの大友浩さんが、CD売り場で、売り子をやっている。大入り袋がでた、華やかな雰囲気でこちらも、うきうきする。俺の連れは文鳥舎主宰にして、ラジオデイズ女プロデューサの大森美知子。(公式にはお忍び観覧という話である)古今亭駿菊柳亭市馬柳家喜多八柳家喬太郎といったワザオギレーベルおなじみのいまやスタープレイヤーとなっている四名プラス関西から笑福亭鶴光DVD収録の落語会なので近日中に、ワザオギから発売される。機会があれば是非ご覧ください。特筆すべきは、市馬師匠の『片棒』。まさにはまり芸。あのまま、木遣唄をずっと聴いていたいほどの美声を響かせてご当人も気持ちよさそうに演じていた。勿論、喜多八師匠の『あくび指南』喬太郎師匠の『反対車』は、抱腹絶倒。で、日曜日がやってくるわけである。まあ、毎週日曜日はやってくるのであるが、今週は気配というか、運気というか何か感じるものがあった。日曜日は「白髭橋の会社」のゴルフコンペがあったのである。俺は最近はもう、ゴルフというものに飽きていて3ホールぐらいで、「もう帰って寝ようか」といった気分になるのであるが、この日は、朝から雷雨の予感。実際に5ホール終わったところで雷、中断、早い昼飯。帰ろうかなと思っていたところに、再開のアナウンス。七番。130ヤードのショートホール。俺は躊躇なく8番アイアンを持つ。理想的なショットであったと思ったらなんと、なんと、これがホール・イン・ワンである。JALから国内お二人様旅行券。こんなところで、一年分の運を使い果たしてしまった。いや、運転免許取消し以来、不運続きだったのでお天道様が、運気の配剤をしてくれたのかもしれない。よほど、これまで不運を貯めこんでいたのだろう。たぶん次は、箱根恒例麻雀での九蓮宝燈だろう。まいったねこりゃ。しかし、こんなところで、こんなかたちで運を使いたくはなかったぜ。お天道様も人が悪い。(いや、人じゃないか。)
2007.06.11
コメント(4)
-
ロングセラー、ロングテール。
以前から奥村組にいる旧友の森田くんに頼まれていた講演に行ってきた。「日本非開削技術協会」という聞きなれない団体の年次総会が平河町の海運クラブで行われたのである。会場に到着するとスーツにネクタイ、精悍な顔つきの「暗い谷間の労働運動」を潜り抜けて今は会社の幹部になっているような男くさい方たちが大挙押し寄せてきていた。こわもてである。昨日や今日ぽっと出のネットベンチャーや、金融小僧とは体つきが違う。「あのう、この会のパンフレットか何かありますか。どういう会なのか、事情を知らないままに来ちゃったもんで」と、受付に挨拶して資料をもらう。いただいた資料をめくると次のような説明が目に入ってくる。「JSTT・日本非開削技術協会は、わが国の電力、ガス、通信、水道、下水道などの地下パイプラインにかかわる各事業分野の関連企業が連携し・・・」理事の名簿を見ると錚々たる会社が並ぶ。大学の教授もいる。いや、おみそれいたしました。あなたたちだったんですね。この日本の地面を支えてきたのは。まあ、そんな気持ちになると同時に、いったい俺はこの方たちに、何をお話すればいいのかと少々不安になる。会場に入ると、百数十名のスーツがいっせいに「何だ、このやろうは」といった目つきでこちらを見ている。年代的には、俺と同年代か、すこし上の方が多い。お題は先だっての日本工業大学に続いて、『反戦略的ビジネスのすすめ』である。まだ、この演題で、講演のご注文をいただける。言って見れば『岸壁の母』のようなロングセラーである。まさに、「流行らない歌はすたれない」である。少しばかり固くなりながらも、小一時間、「ビジネスにおける二重の交換」という自説をお話する。ビジネスの要諦は、ビジネスが繰り返されるということにある。商品と対価の交換の背後ではつねに誠意と信用の交換という見えない交換が行われており、「繰り返し」を担保するのはこの見えない交換であるという毎度のお話である。奇妙なことだが、最近の社会保険庁の不祥事、コムスンの営業停止、こういった不祥事が俺の話に説得力を与えてくれる。事例があとからやってくるのである。はなは水を打ったような会場であったが、次第に、「何だ、このやろう」氏が、あちらこちらで俺の話に頷いてくれるようになる。― さて、続けて「給与とは何か」というお話をしたかったのですが、お時間がきてしまいました。実は「給与とは何か」は、「ビジネスの二重の交換」よりもずっと面白いのですが、それはまた次の機会に。先日の神田愛山先生の話切れのネタをそのままつかわせていただいた。万雷の拍手であった。無骨であたたかい音である。懇親会の席で、別の団体で「給与とは何か」を話してくれないかと、ご注文をいただく。森田君、事務局長の重責ごくろうさまでした。また、貴重な機会をありがとう。
2007.06.08
コメント(0)
-
可塑的な精神。
ちらちらと、テレビに出てくる片山さつき「議員」を見ていると(見たくないんだけどさ)思わずテレビごと裏山へ放り投げたくなる。(残念なことに裏山がない)悪党だろうが、偽善者だろうが俺は人間に対してはかなりな程度寛容なのであるが寛容にもおのずと限度というものがある。このお方だけは、なんつうか、ご勘弁願いたい。人間のもっとも重要な資質とは精神の可塑性だろう。人間は変わりうるということである。さればこそ、本を読み、絵画を堪能し、人の話を聞く。悪党は改悛し、偽善者は羞恥する。実際にはそういうことはあまり起こらない。それでも、どこかに可塑性のための開先があると信じられているわけである。あるいは、どこかで自分も幾分かは悪党であり、幾分かは偽善者であるという後ろめたさとともに生きている。それはやっかいなことだが、やっかいなのが人間というものである。ごくまれに、これはだめだろうなというような「自己確立」を果たしたような人間に出会うことがある。彼/彼女には、精神の可塑性というものを基底にした人間の関係に思い至ることがない。打倒するか、平伏すか。訓致するか、飼育されるか。抹殺するか、介護されるか。どこまでいっても、二者択一の平板な世界観の実現を自分の使命だと信じ込む。彼/彼女は、どこかで精神の可塑性を喪い、それゆえに、自分は世界に良きことをなしていると思えるようになる。喩えて言えば闘犬である。闘犬はいつも必死である。良きことを実現するために。しかし、良きことをせんとして悪をなすのが人間である。さて、車谷長吉の『贋世捨人』を読み終わり続けてまた高橋源一郎の『さようなら、ギャングたち』を読む。まったく、色合いの異なる作風の作家の作品なのになぜか、同じような呼吸でこちらの胸中に響いてくる。作風や文体に関する限り、ふたりに共通点はほとんどないのだが、ひとつだけあるとすれば、ふたりとも、「小説」の終わったところから書き始めさりながら、深く「小説」を信じているということだろう。その、「信の強度」がなければ、このような作品を書き続けることに作家は堪えることができない。
2007.06.06
コメント(1)
-
病が癒えてきたので「私小説」でも読むか。
ラジオデイズのサイトで先だっての小池昌代さんとの「対談」が聞けるようになっている。http://www.radiodays.jp/ja/program/俺は、体調最悪であったが今聞いてみると実に楽しそうである。ラジオ的にはもっと準備をして、構成的にやればよかったと思うのだが小池さんも実に楽しそうにやってくれているのが救いである。すこしづつ気管支炎が癒えてきて、本などを読み始めている。近々に高橋源一郎さんにお会いすることになっているので『虹の彼方に』あたりから読み始める。初期三部作の最後のやつであるが、手元にこれしかなかったので、読んだのである。病から癒える時期というのは小説を読むにはもってこいなのである。一読、ああ、これは高橋さんの「私小説」なのだなとおもうた。(おっと、文体が車谷長吉になってしもうた。)『贋世捨人』を続けて読んでいるのでどうしても、こうなる。高橋さんの小説をどう読むかはもちろん読者の勝手である。吉本隆明が「修辞的な現在」と形容した八十年代の現代詩に親しんだ目からみればなるほど、「修辞的な現在」の中から生まれてきた「私小説」というものはこういった形をとるのではないかと思わせるものがあるということだ。誰も、かれの作品を「私小説」とは思ってはいないだろうが。言葉は屈託無く、自由自在に遊んでいるように見えるのだがたぶんそうではないだろう。フロイトの夢のように巨大な「抑圧」が存在しており、その「検閲」を潜り抜けてきた言葉だけが小説の表面に浮かび上がって「修辞的な私小説」を再構成しているといった印象であった。どうしてそんな印象を持ったのかって?それは、読後の俺のこころもちが、純良な「私小説」を読んだ後のように身につまされたからである。― 私はこれからは、時代の最先端を見据えながら、併しそこから距離をとって、時代の最後尾、びりっ尻を「蝸牛の歩み」で歩いて行こうと思うた。いや、少なくとも自動車の運転免許証だけは取得しないで、生きていこうと決意した。あれま、また車谷にループしてしまった。やはり、「私小説」なのである。
2007.06.04
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1