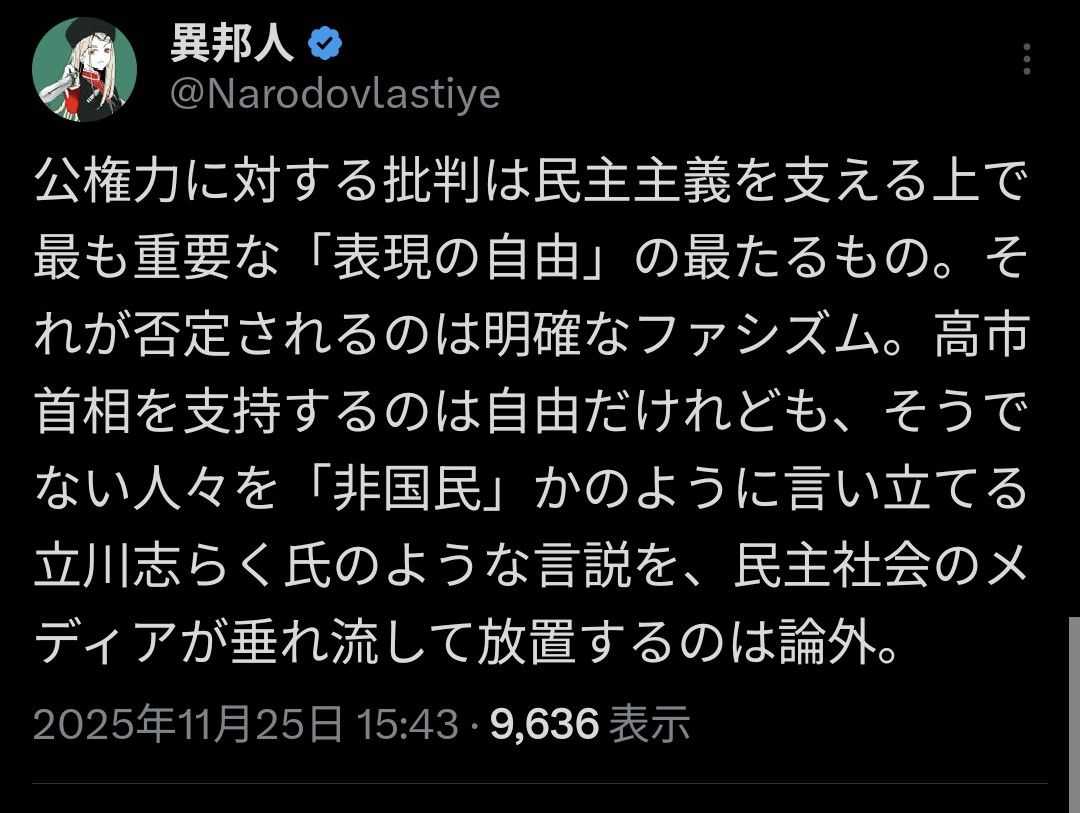2007年07月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
明るさを消さずに、悲しみを表現するということ。
NHKの3チャンネルを見ていたら作家の森村誠一が三波春夫について熱く語っていた。ウィキペディアを見ると、三波の経歴としてこうある。1944年に陸軍入隊し、満州に渡る。敗戦を満州で迎える。敗戦後ハバロフスクの捕虜収容所に送られ、その後約4年間のシベリア抑留生活を過ごす。番組の中で森村は、この体験の凄まじさについて印象的に語っていた。満州で三波のいた軍隊は置き去りにされる。そして、シベリアでの抑留体験。誰もが精神的な負債なしでは潜り抜けることができないような状況にあって、三波はつねに明るい歌声を響かせていた。「三波の明るさは、天性のもの。遺伝子そのものが明るい。おそらく、戦場やシベリアにおいて多くの人間の命を救ったのだと思う。」だいたい、こんなことを語っていた。三波がデビューした当時、推理作家森村もまた苦しい独り身の修行時代を迎えていた。紅白歌合戦というものを、安アパートの一室で見る大晦日。「紅白歌合戦というものは、団欒の中で見るものであり、独りで見るものではないとつくづく思いました。独りで見るということは、つらく残酷なことです。」判るような気がする。太宰なら「家庭の幸福、諸悪の根源」と言ったところだろう。しかし、と森村は続ける。「三波春夫の歌だけは、独りで聞いていても侘しくなく、楽しめたのです。」そして、最も好きな歌として、「チャンチキおけさ」を挙げた。俺はどちらかといえば、三波春夫よりも、ライバルと目された村田秀雄や、三橋美智也が好きであった。しかし、いつだったかあらためて三波の歌を聞いて凄いな、こりゃ凄いよと思ったのである。そのとき、ラジオから流れてきたのは「チャンチキおけさ」だった。以前、このブログにもそのことを俺は書いている。― 温泉で、芸者をあげて、さあ無礼講という場面で流れるのが「チャンチキおけさ」だと、俺は、何となく思っていた。ガード下の屋台で、上司に対する罵詈雑言で盛り上がり、小皿叩いて怒鳴るように歌うのがチャンチキおけさであると。それがとんでもない勘違いだとわかったのは随分経ってからのことである。だいぶ以前の話だが、ラジオを聴いていたときこの歌を歌う三波春夫が意外なことを言っていて、それが妙に心に残った。三波春夫は、こんな風に言葉を切り出したと思う。「こんな悲しい歌はありません。にぎやかで、陽気な歌だと勘違いされている皆さんが多いのですが、これほど、悲惨で、孤独で、暗い、つらい歌はありません。」え。どういうことなんでしょという気持ちで、俺はかれの呟きを聞いたように思う。で、もう一度歌詞を反復して見る。時代は、1957年。俺は1950年うまれなので、七歳ということになる。かすかな記憶のかけらがまだ、身体に残っている。日本が、戦前よりも貧しかったと言われた戦後の数年間を経て、相対的には安定期に入りかけた時代の話である。川本三郎に言わせればベルエポックということになる。しかし、戦争の傷痕が癒えるに従って、新たな敗者も生まれてくる。 月がわびしい 露地裏の 屋台の酒の ほろにがさ 知らぬ同士が 小皿叩いて チャンチキおけさ おけさ せつなや やるせなや ひとり残した あの娘 達者で居てか おふくろは すまぬすまぬと 詫びて今夜も チャンチキおけさ おけさ おけさで 身を責める 故郷を出る時 もって来た 大きな夢を 盃に そっと浮かべて もらす溜息 チャンチキおけさ おけさ 涙で 曇る月これが、陽気で、馬鹿騒ぎの歌と思われているチャンチキおけさの歌詞である。浪曲師三波春夫の歌謡曲デビューであった。ここにあるのは、出稼ぎや、集団就職で東京へ出てきたが、芽が出ない敗残者の嘆き節である。無産で、無国籍な人々が吹き寄せられた場末の風景である。やけっぱち、というよりはデスペレートな空気が全体を覆っている。とても、芸者をあげて大騒ぎする歌ではない。そうやって、もう一度、この歌を聴いて見る。聴いて見るといっても手元にレコードがあるわけではない。頭の中で路地裏の屋台に並ぶ酔客の顔を反芻するだけである。三波春夫は確かこんなことを言っていた。「どうやって、この悲しみを表現したらいいのか。そこが悩んだところでした。」ここまでが以前ブログに書いたことである。今回の番組で、その「チャンチキおけさ」を歌っている三波春夫の映像を見ることができた。金糸銀糸の見事な和服の衣装でマイクの前に立った三波は思ったよりも静かな調子でこの歌を歌いだす。そして、その瞬間鳥肌が立った。「明るさを消すことなく、悲しさを表現する」この三波が悩んだアポリアは、彼はその歌の全体で、見事に突き抜けているように思えた。森村誠一が見ていて自然に涙が流れたと語ったように、俺も三波の歌を見ていて、泣きたいような気持ちになった。泣きそうにはなったが、暗くはならなかったのである。
2007.07.31
コメント(7)
-
秋刀魚の歌と選挙。
7.31(火)「AGAINIGHT 3」上野茂都ライブOpen 19:00~Start 19:30~入場料 2,000円選挙があろうが、台風が来ようが、観客があろうがなかろうが上野茂都は変わらない。いつものごとく、淡々と侘しく、細棹を鳴らして大根や蓮根や、メロンや、秋刀魚を歌う。明日が、第三回目のアゲインライブである。さあ、皆でこのすがれた時間に埋没して秋刀魚を焼く歌を聴こうぜ。予約は、アゲインのサイトで。予約なしでも、入れると思うけど。選挙の結果は、ほぼ、思ったとおりであった。国民は古い自民党にも、新しい自民党にもノーと言った訳である。憲法や、経済に関しての基本的な理念というものが自民党の中でも分裂しており、民主党の内部でも分裂してねじれている。ねじれているだけではなく、党派内部での闘争のエネルギーも著しく衰退しているように見える。(歴史的敗北をした党首の続投宣言に、内部から誰もきちんと異議をとなえられない)党派というものがほとんど意味を失っているということである。利害だけがあって、理念を共有できない政治党派を国民は選択することができない。結局のところ、立候補者個人で選ぶか、代表者の顔で選ぶということになる。しかし、選択の基準は必ずしも明確ではなく、イメージが先行する。この場合イメージを左右する最も大きなファクターはかれが何を為したかということの評価よりも何に失敗したかといった「しくじり」によるマイナスイメージということになる。今回の選挙では、それが如実に現れたというべきだろう。一国の大臣が、顔の絆創膏を説明できないのでは失点もやむをえまい。イメージ選挙。一概にそれを悪いことだとは言えない。人間はもともと多様であり、考え方は変わるものであり、イメージはしばしば、言説よりも信ずるに足るものだからである。人間は本来、党派的なものではない。じっくりと自分に関係した問題を考えて、是々非々で対応する。そして自分の考え方の代弁者といったイメージを発散させている人物を選ぶ。もし、そういうことなら、それでいいじゃないかと思う。しかし、先日テレビを見ていたら、若者インタビューでは、選択の基準のトップは「実行力」とか「行動力」ということらしい。ほんとは、何を、どのような形で実行するかが問題のはずだが、ただ、強引で有無を言わせぬ行動力なるものに期待してしまうという傾向が現れている。「叱ってくれる親父」待望論に似ている。何をどのようにするかというよりも、誰かが決然と行動し、白黒はっきりさせてほしいと思っているとすれば、ちょっと違うんじゃないかと半畳をいれたくなる。それはほとんど民主主義というものの否定であるが、それ以前に成熟できないガキの選択だということである。ガキにはガキしか選べない。個人的には今回の選挙で、こいつらだけは、選んじゃいけないよきちんと落としてやらなければだめだぜと思っていた人間がふたり当選していた。
2007.07.30
コメント(0)
-
銀シャリの味。
昨夜は、大阪から140B中嶋社長来社。軽い打ち合わせの後、御苑前にある「干物と銀シャリ」の店『こころむすび』で飲む。うめぇのなんの。秋刀魚、さば、のどくろ、そのたもろもろ山陰浜田港直送の干物の炭火焼きオンパレード。俺と和尚が日本酒(純米)、中嶋社長はビール(純麦)。話のほうは、先日の当ブログの「キャリアアップ主義者」のことや、落語の人情話まで。居酒屋から教育に転進する前に、自分のところの味をなんとかしたらどうかねとか、まあ、酔っ払いの話です。〆は当然ながら、お香こと、かまどで炊き上げた銀シャリ。まずかろうはずもない。「日本人でよかった」ってのはこういうときに言うのだよ。丸川くん。食いすぎで、ダイエットまたもや失敗。明けて本日は、ラジオデイズの番組収録。作家高橋源一郎さんと女優烏丸せつこさん。高橋さんとは、先日の内田対談以来二度目であるが、何十年も身近にいる隣人といった感じで話をしていてまことに心地よい。こんなに息が合う人に会うのもめずらしい。息が合えば話も弾む。話が弾めば、防御も緩む。番組的にも大変面白い話となった。一方、烏丸さん。素敵な女優である。クラリオンガールからの転身であるために誤解されやすいが、大変な演技力の持ち主である。日本アカデミー賞では、主演女優賞、助演女優賞、新人賞を受賞している。(たいしたことないわよ)(いやいや、たいしたことですがな)この度のラジオデイズの企画では正津勉さんとのセッションで、詩を朗読してもらった。いわゆる女っぽい声ではない。しかし、目に力があるように、声に大変力がある。ちゃきちゃきしていて、竹を割ったようなという形容そのまま。俺の方は、スクリーンでしか見ていない女優を前にして、どぎまぎしているうちに収録終了。さて、いよいよ、参院選である。久しぶりに、何かが起きることが期待できそうな選挙である。俺はしかし、その前にやることが山済みになっている。土曜日の朝は病院に行く。母親の病状に関して医師と話をしなければならない。その足で、富士吉田まで、昭和大学空手部の合宿に行く。辛夷会として、阿久津師範と俺が年一回の合宿の指導に出向いている。投票は合宿から帰ってからその足で投票所へ飛び込む予定である。
2007.07.27
コメント(1)
-
自然の慎み深さ。
抗菌コンクリート協会という団体の総会で、講演をたのまれて竹芝のホテルに行く。ビル群に囲まれた東京湾を望むホテルのカフェで息をつく。浜松町の駅から汗をかきながら歩いてきたが、カフェの内部はクーラーが利いていて気持ちがよい。窓から海を眺めていると海面が波立っているので風が吹いているのが分かる。風は、それ自体は見えないが木の葉のそよぎや、水面の動きがその存在を証明している。「深い息づかいを世界につたえてむしろ忘れられることを望むのだ」また清水哲男である。竹芝桟橋。昔は今とは違う風景が広がっていたのだろう。小笠原へは、ここから船でひたすら南下して25時間以上かかる。かつてこの群島のひとつで戦史に残る戦闘があったわけである。父島にも、母島にも俺は行ったことがない。行ったことはないが、記憶の中には確かにある。そういう風景が、誰にでもいくつかはあるものだ。先日テレビを見ていたら小笠原の特集をやっていた。人口2000人の日本から一番遠い島。東洋のガラバゴスと呼ばれているらしい。最近、ここに外来種が繁殖しはじめてテレビは、小笠原の自然が危なくなっているということを伝えていた。自然はその前からずっとそこにあったがこれからも残り続けるという保証はなくなった。健康で文化的な生活を目指して人間はひたすら自然を破壊してきた。エコロジストに嘆きがあるとすれば、かれの存在自体が自然破壊への加担そのものであるということに思い至るときだろう。自然から見れば、人間そのものが外来種なのである。アル・ゴアは「不都合な真実」を徹底的には暴くことができない。健康で文化的であることを断念できないからだ。自然と共生するには人間の欲望は節度を知らないし、自然の一部として生きるには人間は増えすぎている。自然はもっとずっと慎み深い。エコロジーを守りたいという声も自然の慎み深さの前では過大に響く。だから諦念し、断念せよと言いたいのではない。自分たちの欲望に自覚的になれば、足元を固めることや、沈黙の日々を紡ぐことの意味が変わるはずだと言いたいだけである。
2007.07.25
コメント(1)
-
現実的な問題。
昨夜から腹の調子が悪い。胃の辺りの膨満感が消えない。飲み過ぎ、食い過ぎというわけでもないのに。漱石は、慢性胃病だったから、結論の出ない不倫関係をあのように掘り下げたのか、それともそのようなテーマに固執し続けたから胃病に苦しむことになったのか。病人の思考は病的になるというのは言い易いが必ずしもそうではあるまい。漱石の作品は、はたして健康だろうか、病的だろうか。健全で健康な文学というものがあってもよいが、そんなものを誰が読みたいだろう。だいいち、いつも心身ともに健康であると思っている人間は小説など書きたいと思わないだろう。梅雨空から一転、今日は気持ちのよい青空が広がっている。気温はかなり高いが、乾いた風が吹いていて気持ちがよい。これで、体調がよければ俺はそのまま糸の切れた凧になってどこか温泉の沸くところへ飛んでいくところだが、今朝は腹を抑えて白髭橋の会社へ向かう。体調の悪いときは、仕事がいいのである。選挙が近い。相変わらず戦後レジームからの脱却なんていう言葉が一人歩きしている。ほとんど、意味不明である。むしろ、経済は市場原理主義、政治は国家主義とでも言った方が分かりやすい。対するに、福祉国家の実現、平等な経済分配、政治的多元主義ということになるのだろうか。市場原理主義に、対応する言葉は何なのかと思う。社会民主主義ではない。(こっちは社会体制だからね)勝敗があまりに苛烈にならないように、市場をある程度制限する。やはりケインズ主義ということになるだろう。修正資本主義といってもいい。一長一短。どちらの政策もその政策が生まれてくる文脈の中で見る限りは正しそうに見える。これは、憲法論議にも共通することだが、両論があって、どちらも正しそうに見えるということはどちらも正しくはないということであると思った方がよい。いや、もっと精密に言うなら、正しいか正しくないかというような問題ではないということである。多くの場合、ほとんどの経済問題、政治問題をそれが正しいか正しくないかというような問いの立て方をしているが本当は、ただ単にどちらが有効であるかどうかといった効果の予測に過ぎない。そして、効果の測定とはどれだけの時間的なスパンで測定するのか、どれだけの地理的な広がりで考えるのか、ということを抜きにしてはほとんど意味をなさない。現実的な問題は、ただ、現実的に考えることの中でしか解決しない。あたりまえだけど。
2007.07.24
コメント(2)
-
フラガール。
まる13本抜歯して、無事アクア動物病院から生還。案外元気である。不満といえば、抜歯前の絶食らしい。手術後、早く飯を食わせろとせがむ。やはり、しぶとい雑草育ちの駄犬である。世評の高い『フラガール』を見る。エンタテイメントとしてひとつの到達点を示している。笑えて、泣けて、しんみりさせてくれる。賞を総なめにしたのも納得できる。主演の蒼井優がかわいい。岸部一徳がいい味である。常磐ハワイアンセンターができたときのことをうっすらと覚えているが、背後にこんなドラマがあったのかと思う。ドラマはお気楽な虚構だが閉山は事実である。それが、この映画に不思議なリアリティを与えている。炭鉱史は生活史という目で見れば実に様々な悲喜劇を生み出したということだろう。軍艦島のかつての繁栄と現在の荒廃を見るときにいつも、感じることである。そして、そのほとんどは、言葉にされていない。言葉にならない感情というものが確かにあり得る。言葉にしたいというのも感情だが、それを言葉にすることを押しとどめるというのも感情にはある。この映画を見ているとそれをうまく切り取っている場面に何度か出遭う。朝鮮名を持つこの若い監督について、俺は何もしらないが、彼にはそのことがよく分かっているように思える。
2007.07.22
コメント(1)
-
唐様で書く政治。
57回目の誕生日。感慨はないが、五十路を抜けてゆく車窓からの眺めは、特急列車のごとし。この調子だと、あっという間に還暦、ちゃんちゃんこである。本日、母親馬込の松井病院に入院。午前中一杯、入院の支度や、医師との相談。随分へたっている。人生の秋である。ベッドに寝かしつけたところで新宿のラジオカフェへ向かう。道中、母親の人生とはなんだったのか、いや、人の一生とはなんなのだろうという思いを反芻する。小ゑん師匠、大友浩さんらと編集・企画会議。御苑前から見えるビッグ・ベン(NTTドコモビルの時計台)に夕闇が降りる頃、先だってのホールインワン記念食事会と称して腹をすかせた同僚らにラッキーのおすそ分けをするために御茶ノ水アスターへ向かう。気もそぞろであったが笑いの絶えない宴会となった。御茶ノ水の日版ビル21回の窓から大手町方面に林立するビルの夜景が今日は空々しく見える。選挙間近で、世間が騒々しい。安倍内閣のダッチロール状態が続いている。いろいろな原因はあるのだろうが、この内閣が三代目内閣であるということが大きいような気がする。「気がする」ってのは、あくまでもそう「感じる」ってことだが、この「感じ」は下手な論証命題よりも正鵠を射る場合が多い。戦後このかた、自民党は、地盤・看板・鞄を引き継いで組織を存続させてきたわけで、戦後六十年とは、初代から数えてちょうど孫の代が惣領となる時期に重なる。三代目ともなると、経世済民の手触りは惰性に変わる。借り物で、実感の乏しい空理を組み立てているようなものである。内閣全体に、三代目気質が蔓延しているのである。「売り家と唐様で書く三代目」という気質である。首相は、岸信介を崇拝しているらしい。顔に絆創膏を貼って、なんだか中学生みたいな答弁をしていた赤城農林大臣は、絵に描いたような三代目である。昨日のアルツハイマー失言の麻生外相もどこか、三代目のボンボン気質が見てとれる。今は昔の党人気質で、かれらは、祖父の代の遺産で食っている。川柳の三代目が売ったのは持ち家だが、三代目の内閣が売るのは国家であったり、国民生活であったりするのだろうか。
2007.07.20
コメント(5)
-
台風一過。
台風一過。夏の空が広がっている。俺の身辺周辺の台風も小休止であった。数日前に母親が倒れ、救急車で病院に運ぶ。入院できずに、自力歩行できない彼女を実家まで連れ帰り連休中、看病と、実家の改造を行う。来月は父親の方の入院手術が決まっている。掘りコタツに座りテーブル、敷布団という日本風の生活様式をテーブル、ベッドの洋風スタイルに変えたのである。齢八十を超えた足腰の弱った老夫婦には、日本風行住坐臥が困難になっている。過日お見舞いに出向いた折、昭和初期の生活そのままのゴミに埋まった台所や、残骸の詰まった茶箪笥を見て、心が痛かったのである。女房と汗だくになりながら、ゴミ袋二十個ほどを運び出し、ベッドを入れ、テーブルを組む。途中で会社の加藤君が手伝いに来てくれた。(ありがとう)すったもんだしながら、やっと70年代一億層中流あたりの生活環境に改造することができた。一億総中流。現実はそうではなかっただろうが、もし、人々がそういった幻想を持ちえたとするならばそれは、政治というもののひとつの成果だといわなければならない。今は、病院も介護施設も、身体の痛む老人で満杯である。経済成長とか、グローバル標準とか言っているうちに随分と酷薄な環境になったものである。未来はあまり明るいとはいえない。そういえば、先日、内閣官房からお二人の方が会社にやってきた。これもまた、台風のようであった。二人の手には、付箋でいっぱいになった『反戦略的ビジネスのすすめ』と『株式会社という病』があった。相当熱心に読み込んでおられた。委細はここに書くことはできないのだが、お二人のご意見では、このまま市場主義ではアメリカも、アジアも持たないということらしい。(まあ、そりゃそうだろう)そこで、「店主のお考えを実効的な施策に落とし込みたいのでご協力願いたい」とのことである。(まさか、ご冗談でしょ)「教育政策はウチダ先生の案で」とも言う。「東京ファイティングキッズ」が日本を動かす?大丈夫かね。いや、俺にもウチダくんにも(たぶん)そんな暇はないと思う。足元の竃さえ動かせないで往生しているのである。以下、お知らせです。以前、江弘毅パーソナリティーのラジオ番組『ラジオの街で逢いましょう』にご出演いただいた、関西を席巻する講釈師、旭堂南海さんのライブが、あの武蔵小山アゲインで開催されます。ラジオ収録時のアシスタントの五十川藍子さんが、その語りに衝撃を受けて、ご自分でプロデュース、企画した執念の独演会です。彼女の惹句をご紹介します。*****************************最近、講釈(講談)師の語りを聞いて「物語を伝える力」に、驚きました。まさに語りのプロ。物語を語ることが仕事って、やっぱりすごいんです。この話は、どうして、こんなに響いてくるのだろうなんで、風が聞こえてくるんだろう(効果音なんかないのに)「物語を伝える」って、どういうことなんだろう…もっと知りたい!そして、この感動を、みんなと分かち合いたいと思いこのイベントを開催することにしました。数ヶ月前、ラジオ番組でお会いした方なのですが私は聴いていていすから落ちそうになりました。語りのスペシャリストです。そして、こんな文化と芸が日本にあるということがうれしい。そんな気持ちになりました。※転送大歓迎!どうぞお友達も誘っていらしてくださいませ。【イベント概要】・日時:8月4日(土) 14:00~16:00(開場 13:00)・場所:「アゲイン」(ライブハウス) 東急目黒線、南北線/都営三田線直通・武蔵小山駅東口下車 30秒品川区小山3-27-3 ペットサウンズ・ビル B1F TEL/03-5879-2251アゲインhttp://www.cafe-again.co.jp/地図はここhttp://www.cafe-again.co.jp/access.html・参加費:4000円・人数:40人限定少人数での開催のため、料金は4000円と高めですが、(勿論、収益なんかありません。)南海さんの芸を東京で見ることができる稀有の機会です。俺も勿論駆けつけます。申し込みは書きフォームから。http://www.semimaru.biz/apply.php?sid=397
2007.07.16
コメント(10)
-
キャリアアップ主義者の面影。
神戸北野ホテル宿泊。さきほどまで、仕事がらみで鷲田清一先生と夕飯。大林組の長谷川常務、船橋くんらと歓談。密談。相談。大阪大学の学長になることが決まって超多忙なのであるが、それでも、哲学者鷲田さんは、悠揚として迫らぬはんなりとした風情で話は転々、淀川の川原に転び心地よい時間を過ごすことができた。大林組がタクシーチケットを出してくれたので、そのまま北野ホテルへ向かった。以前築地の場内すし屋をご案内した永末支配人からご案内状をいただいており、一度はその「世界一」の朝食を食ってみたいと思っていたからである。車中、ひとつの考えが浮かぶ。いや、この間ずっと考えていたことである。違法な行為があったとか、態度が気に入らないとか言うこととは別にコムスンの社長、ヤンキー先生、ワタミの社長は同じ穴の住人であるということである。ここに、ホリエモンを加えてもよい。あるいは、石原慎太郎も。彼らは、成功者であったか、あるいは今でも成功者であるように見える。しかし、俺は彼らの成功にどんな意味でも賞賛を与える気持ちにならない。ただ、ことさらに持ち上げる必要もなければ、貶める必要もないやりきれない凡庸さだけがあるだけだ。彼らは、それぞれ、一緒くたにしてほしくはないだろうが俺にとっては同じ穴の住人に見える。どんな穴か。それをご説明するにはすこし長いたとえ話をする必要がある。それはある青年の一代記である。たとえば、駅前にたこ焼き屋を開いた青年がいたとする。(コロッケ屋であったかもしれないし、小さな工場主であったかもしれない。だから、たこ焼き屋とはひとつの職種の記号だと思っていただきたい)彼は、このたこ焼き屋でちょっとした、小金をためることができた。彼の店は立地に恵まれ、コストバランス、営業感覚に意外な才能を発揮した。彼は小金を貯めて、小さなレストランを開業した。このレストランも大いに繁盛し、彼は小金以上のものを貯えた。彼はその小金を元手に金貸しをはじめ、金融の世界でもちょっとした成功をおさめる。そして、彼はこの町の町会議員に立候補し、見事に当選する。そしてついに、彼に国家からお声がかかる。「ひとつ君の才能を、もっと人々のお役にたたせていただきたい。」彼はそうやって国会議員に立候補するか、あるいは国家機関の一員にリクルートされることになったのである。これは、ひとりの立身出世の物語である。同時に、手のひらの確かな感覚を他者に届けるところから出発した彼の職業が、サービス、金融、公職といった高度ではあるが手のひらの実感から遠ざかってゆく場所へと階梯をのぼりつめてゆく歴程でもある。かれの描いたキャリアパスは、人々のリスペクトを集める場所へ自らを押し出してゆくということであった。キャリアパスというものを考えたとき、誰もがこのように考えるかもしれない。ただ、彼はもう最初のたこ焼き屋や、コロッケ屋や、小工場主に戻ることはない。「それは象徴的にいえば、田中康夫が県知事になったとき、彼(高橋源一郎)が野球や競馬のテレビ評論家になったことからも推論することができる。(途中略)わたしはためらいなく田中康夫は少しだけ文学の休暇をとったつもりでも、それは文学の放棄につながるだろうが、高橋源一郎は呼べば即座に活気意を持って文学に戻ってこられるに違いない。そんな完黙の詩心を失っていないまま、競馬や野球の仲に入っていることがよくわかる気がした」これは、吉本隆明が高橋源一郎を評した言葉である。わたしは、この吉本の評言に「錆付かない批評眼」というものを見る思いがした。だれも届かないような見事な分析である。吉本はこの部分に続けて、県知事としての田中よりも、競馬評論家としての高橋のほうが二枚も三枚も上手であると言っている。コムスンの社長は、商社をスピンオフして、遊興ビジネスの世界で大きな成功をおさめるところから出発した。週刊誌を開くと、かれは安倍首相と握手をしたり、クリントンと肩をならべた写真を誇らしげに公開している。(勿論、介護ビジネスで大成功したからである)ヤンキー先生に関しては、こちらにほとんど知識がない。しかし、ひとりのどこにでもいるしがないヤンキーが、先生になることで人生に逆転があることを象徴的に示した事例としてマスコミや、教育再生委員会が持ち上げた(らしい)ことは容易に理解できる。今度は、参議院議員に立候補だそうである。ワタミの社長もまた、居酒屋チェーンから出発して、学校をつくったり、委員会の委員になったりして、キャリアを駆け上っていったのだろう。世直しなんてことまで、考えるようになっているのだろうか。ドラえもんも国会議員に立候補しちゃったよね。そこにあるのは、あの立身出世の階梯を上っていた青年と同じ、どこにでもいて、誰にでもある志向性である。学校経営者が居酒屋になったり、国会議員がプロレスラーになるといえば、俺は拍手したいが、そういうことはほとんどない。それは、ある意味では自然なプロセスである。しかし、吉本の言葉を借りるなら、彼らに欠けていたのは、出自である職業に息づいていただろう「詩心」である。いや、かれらには、階梯の先端はよく見えていたが、出自に対する「詩心」など最初から持ち合わせていなかったのかもしれない。俺は、遊興ビジネスの世界の成功者が、介護ビジネスに進出すべきではないと言いたいわけではない。(すこしは言いたいけれど)ただ、出自の世界から、社会的にリスペクトを集める職業にステップアップしても、もう一度元の場所へといつでも戻れるのでなければ、それは最初から出自の世界への矜持も愛情も持ってはいなかったと同じだということが言いたいだけである。かれらは、ただ脱皮を繰り返して、キャリアアップしたに過ぎないということであり、そこにあるのはやりきれない凡庸さだけである。もし、彼らのうちの誰かが、もう一度凡愚の世界へ引き返すというのなら、話は別だが、そのようなことは決して起こらない。だから、かれがどんな成功をおさめようが、どんな業績を残そうが、俺はリスペクトを与える気持ちになれないのである。もっといえば、彼らの指導者面にはうんざりだということである。
2007.07.11
コメント(9)
-
記憶違い。
アマゾンの中古本で申し込んでおいた『エリュアール詩集』が届いた。モノクロームの色調にタイボグラフィーという洋書風のカバーのついた飯塚書店の美しい本である。発行は1964年。飯塚書店は、世界現代詩集というものを刊行しており、嶋岡晨のほかには、片桐ユズル、中桐雅夫など早々たる詩人が翻訳者として名を連ねている。鮎川信夫、田村隆一はいないけれど「荒地」の空気が濃厚である。モダニズムと反近代、抵抗詩と叙情の分水線が不分明だった時代。少なくとも「詩」にとってはよい時代であったと思う。言葉が時代を切り開いてゆくと信じられていたからである。エリュアールの他にはドブジンスキーブレヒトネルーダヒクメットロルカエフトウシェンコギリェンがある。知らない名前がちらほら。みんな何処へ消えたのか。やはり、俺はブレヒトに目が行く。で、嶋岡晨はPoissonをどのように訳していたのか。以下に、全文を引用しよう。魚、泳ぐ者、船などが水のかたちを変える。水は易しく、ひたすらに触れてくるもののために動く。魚はすすんでいく、手袋のなかの指のように。泳ぐ者はゆるやかに踊る、そして帆は呼吸する。けれど優しい水は動く、触れてくるもののため、魚のため、泳ぐ者のため、船のため、かれらを乗せて運び去る。どうです。なんか、いいよね。嶋岡さんの言葉は、いつもやわらかい。そして、俺はこのかれの翻訳を「それでもやさしい水は動く」というように記憶していたわけである。よくあることである。
2007.07.09
コメント(12)
-
故障訓。
しかし、まあいろいろなことがあるね。コメント欄に、かつて俺の会社で働いていた連中のコメントがちらほら。なつかしいものである。あれから、もう十年近く経っているわけだからいろいろあるのは、当然だろう。それぞれ、順風満帆というわけではないらしい。でもさ、雨露をしのげる場所を確保して生きていられればよしということである。たまには、お銚子の一本もつけられれば上出来だと思った方がいい。別に、大金持ちになったところで人間の寿命はそれらを使い切るほどには長くはないし。使い切れずに残せば、骨肉の紛争の種になるだけである。紅羅坊名丸(べにらぼうなまる)先生みたいになってしもた。それ誰だってか?いや、高名な心学者です。横丁の。空手の稽古を続けていると万全の体調で稽古をできるなんていうことは一年のうちで数えるくらいのものである。ほとんどの場合は、膝が痛かったり、肩を脱臼していたり、微熱があったり下痢に苦しんでいたり、咳が止まらなかったりといった具合でどこかが故障している。しかし、一年のうちのほとんどの日がどこかが故障しているのだとするならばこれこそが常態であると考えるべきだろう。万全の体調の方が、異常な事態なのである。問題は、万全の体調を待つことではない。生死のあわいの心身を見つめるという武道の稽古においては「ちょっと、待って」はあり得ないことなのである。それゆえ、故障を抱え込みながら如何にして稽古を続けていけるかということが大切なのである。(そういえば、このところ俺はなんだかんだと用事が重なって、稽古も思うにまかせない)生きてゆくことにどこかで接合していなければ稽古をしている意味もまた薄れる。万全の体調と、現下の故障と付き合うということもまた生きていく上での重要な示唆を含んでいるのだろう。完全や、完璧を求めるとは畢竟、それがなしえないことに対するエクスキューズを含むということになる。故障と付き合うとは、故障を認め、それを肯定するということである。おそらくは、故障を積極的に肯定できるようになることが武道というものの極意になるのだろう。なぜなら、人間なら誰にでも訪れる「老い」というものを肯定できなければ、武道を続ける意味も無いからである。まるは老い、俺も老いてきた。なかなか、それを肯定することができない。前防衛相みたいに「しょうがねぇな」とは言いたくない。しかし、それでもけっこうきつい。老いを楽しむ境地は、見えてはこない。まるのほうが、自然に老いを受け入れているように見える。駄犬に一本取られている自分に、あきれることがある。
2007.07.06
コメント(2)
-
本たちに侘びる。
前回のエントリでは発作的にポール・エリュアールを引用してしまった。原詩は、インターネットの中で見つけ訳は俺がつけたのだが、頭の中には昔読んだ、嶋岡 晨の名訳が残っていたと思う。うろ覚えなのだが「それでもやさしい水は動く」というフレーズを、鼻歌のように長いこと反芻していたからである。今回原詩を読んで見ると全体の構造と脚韻の美しさにしびれた。ほんと、いいぜ。この魅力を翻訳するかたちがなかなか見つけられないのである。ひょっとして、嶋岡晨は俺のうろ覚えよりもずっとうまくやっていたかもと思って書棚を探したが、見つからない。思潮社版の安東次男訳『エリュアール詩集』が出てきたが、これにはPoissonが載っていない。安東次男は、俺の最も尊敬する詩人の一人であり、安東訳は名訳ではあるが、この度は、どうしても、嶋岡訳のPoissonが読みたくなってアマゾンで注文してしまった。いつか、チェーザレ・パヴェーゼを読み返して見たいと思って書棚を探したがこれも見つからなかった。二度の引越しの間に、大切に思っていた本が散逸してしまっているのである。そのときは、もういいやと思って古本屋へ持っていってしまったのかも知れない。俺は、本を読むときに買ったそばから腰巻を外し、カヴァーを外し裸にして持ち歩く。風呂場でも読むし、便所でも読む。それで、痔にもなった。気に入った箇所は、やたらと折り目をつける。分厚い本は、カッターで切って数冊の冊子にして持ち歩く。『戦争と平和』はそうやって、ちびちびと読んだ記憶がある。ドストエフスキーは、部屋にこもって、人間関係を図解しながら読んだ。登場人物が多いのと、同一人物に三通りほどの呼び方があったりするからである。読んだ本は部屋の空き地に、ただ積み上げてあり、周囲に埃がたまっている。掃除をすると、山崩れが起こりそうなので放置している。あんなにお世話になったのに、随分、失礼な扱いをしたものである。この度のエントリでは、何人かの方にコメントをいただいた。お礼もうしあげます。しかし、詩と批評の関係に関しては簡単にはお答えできないし、すべきでもないと思う。いづれ、どこかで、何らかの形で書いて見たいとは思う。でもまあ、お約束はできない。このところは渡世の仁義を通すだけでもなかなかの荷なのである。
2007.07.05
コメント(1)
-
生きている魚を。
月刊ラジオデイズという『月刊新聞』の巻頭では「今月の顔」という特集をしている。しばらくは、俺がその執筆担当ということになっている(らしい)。先月は、小池昌代さんについて書いた。「降りてきた詩人、到来する言葉」というタイトル。「言葉の方から、やってくるっていうときがあるんですよね」という彼女の言葉に「きた」からである。今月は、内田樹くんについての、文章を書いた。タイトルは『毎日一万人の読者から、二万枚の目鱗を落とす大学教授』である。いづれ、どこかで背筋を伸ばして「内田樹論」を書きたいとは思っているのだが、書くかも知れないし、書かないかもしれない。内田くんについては俺はよく知っているような気もするし、何も知らないような気もする。知っていることを書くのはつまらないし、知らないことは書けない。それは、何も内田くんについての評言に限らない。筆者としては、自分が知らなかったことが書く(キーボードをたたく)ことで、モニター上に活字となって映し出されることを期待しながら、書くということになる。自分の知らないことを書く。そんなことが、起こりうるのだろうか。起こりうるのである。言葉というものは不思議なものである。現に、今書いているこの文章も、あらかじめ俺の頭の中にあった意味に形式を与えるといったものではない。意味は書いているその同じ瞬間に生まれる。そして、ときにそれは事後的にもやってくる。最初に一行を書く。それは、真っ白な画用紙に一本の線を引くのと同じである。一本の線に意味は無いが、画用紙の上で二つの領土が意味を主張し始める。意味が現れるためには、その線それ自体の意味は消えなければならない。言葉も同じだ。最初の言葉はほとんど意味が無い。しかし、それがなければ、何も生まれない。(これが最初の贈与である)その一行によって、次に続く言葉が降りてくる。そうやって、自分が何を書いたのかを事後的に知ることになる。それが、文学とか詩とか呼ばれる言葉の秘密である。たぶん、そのようにしてたとえばエリュアールは書いたのだと思う。Mais l'eau douce bougePour ce qui la touche,Pour le poisson,pour le nageur,pour le bateauQu'elle porteEt qu'elle emporte.それでもやさしい水は動く触れてくるもののため魚のため、泳ぐもののため、舟のためにそれらを支え、そしてうながす勿論、自分がすでに分かっていることを書くという行為は、こういうこととは本質的に異なっている。それは、ただ分かっている意味を成型するために道具としての言葉を、一定のロジックに沿って並べるだけである。そうした作業を俺は苦手ではないが、概して退屈であるとは言えるだろう。事務的な言説であり、機能主義的な言葉である。そういう言葉に慣れすぎると世界もまた事務的かつ機能主義的なものとしてしか顕現しなくなる。死んだ魚である。
2007.07.03
コメント(11)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- 楽天写真館
- 26 日 ( Wednesday ) の日記 旅 …
- (2025-11-26 05:15:43)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「ちょっとだけエスパー」ラスト5分…
- (2025-11-26 13:00:04)
-