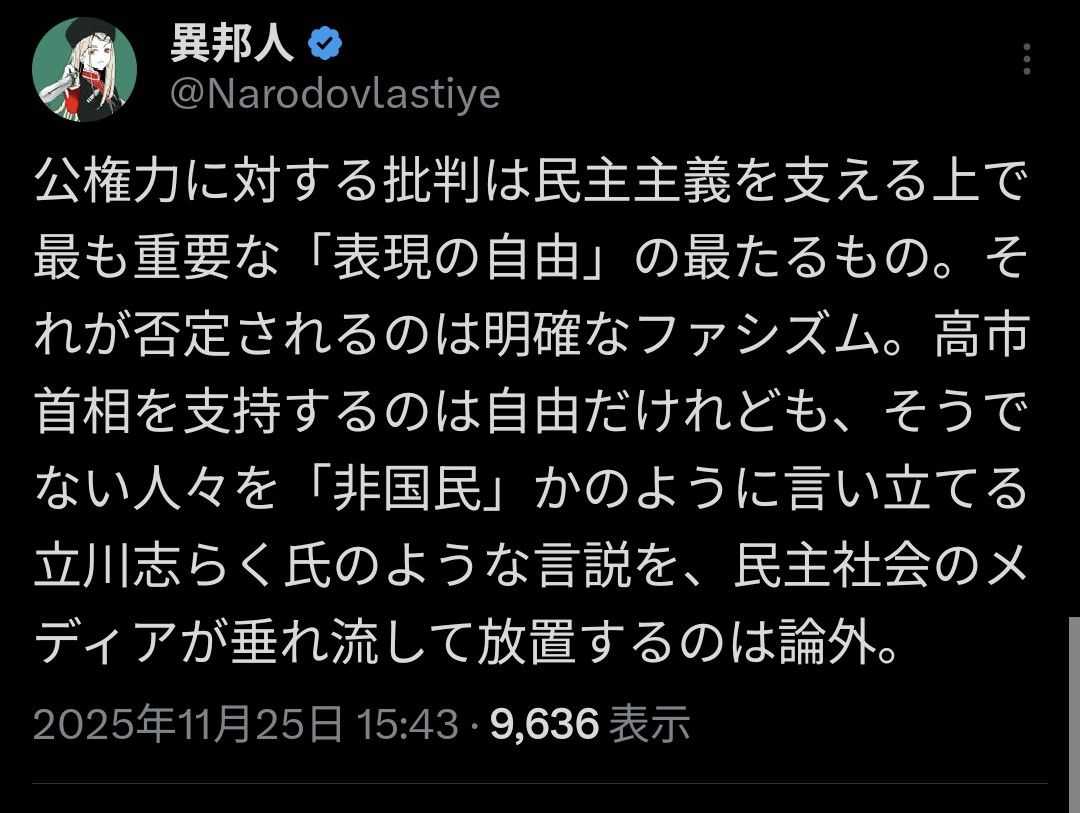2007年11月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
快楽亭ブラックは、生ける伝説である。
なんか、風邪気味の日々が続く。崖っぷちを歩いているのであるが、向こう側へもこちら側へも落ちないで微妙な均衡を保っている。このまま、一冬越えたいが、そうは問屋が卸してくれないんだろう。ということで、微熱を抱え込みながらお江戸日本橋亭へ。快楽亭ブラックを聞きに行くためである。最初の出し物は『反対車』(車に人偏をつけてね)体力のいる芸である。つぎが、上方落語の『今度の御用日』。心臓に不安を抱え、人生に波風を喰らい、崖っぷちの高座で身体を張っている師匠、大丈夫ですか。かような、過酷な出し物を連発するなんて。しかも、収録だし。ワザオギのサディスト(@ブラック師)川崎さんが、収録が無駄にならないように、周到にブレーキを踏んでおいてくれたらしい。エロネタは、お控えください。天皇ネタも、差別語ネタも、お控えあれ。ブラック師匠と、デーブ川崎の間には誰も入ってはいけない。「死ぬ気でやります」と師匠。どうやら、本気らしい。いや、いつもこの人は本気なのだろう。客席に医者はいたのか。で、高座が始った。何と、まくらで、一通り『反対車』の筋を解説してしまう。しかも、笑いどころまで、指定している。この話、どうやって始末をつけるつもりなのか。見ているこっちが、おたついているうち、おもむろに噺に入った。こりゃ、想像を絶する展開である。俺は、このタイトロープの上だけで生きてきたお方の芸の凄みに圧倒されっぱなしであった。『今度の御用日』もまた、開いた口がふさがらなかった。凄絶な落語会は終わり、師匠は、生還した。師匠、死ぬまで生きて、笑わせておくんなさい。俺はどこまでもついて行きますぜ。とは、言えません。そりゃ、無理ってもんだ。誰も、快楽亭ブラックについては行けない。もはや、渡世の彼岸まで、歩き出しちゃってるんだからさ。
2007.11.30
コメント(0)
-
知者との邂逅。
今年もあと一ヶ月となった。いつもと同じように年賀状の季節になった。年賀状に「ゆきつもどりつ」と書いた。来年はそんな年になるだろうということである。去年は、会社の賀状に、「知者との邂逅」と書いた。そうしたら、今年はそれが本当になった。毎年、何か新しいことが起こるが、今年はラジオデイズをオープンしたこともあり、これまで、経験のなかったようなことが、次々と待ち受けていたのである。いやぁ、面白い一年であった。いや、思いもよらぬ一年というべきかも知れない。思いもよらない出逢いということでは詩人の清水哲男さんと、ラジオをご一緒したことである。折にふれ、口ずさんできた言葉の紡ぎ手を目の前にして、大丈夫か、俺は、と思ってしまった。洟垂れのころ、病気で高熱を出すと母親がバナナをくれた。(バナナは貴重品であったのだ)バナナを食いながら、俺は死んじゃうのかと思った。メロンだったら、死んでいただろう。清水さんとの邂逅という事件は、病床のバナナであった。(何を書いているんだ、俺は)勿論、関川夏央さん、高橋源一郎さん、養老孟司さん、小池昌代さん、烏丸せつこさんらとの出逢いも、忘れることができない。先日は、大瀧詠一さんのご尊顔まで拝むことができたのである。出逢いの半分は、三年前にウチダくんと『東京ファイティングキッズ』を書いたことによって、ウチダつながりで実現したものである。西方に浄土あり。足を向けて寝られない。友とはありがたいものである。 今週末は、上野茂都さんらと、丹沢の温泉で、忘年会をやることになっている。『煮込みワルツ』を聞きながら、煮込みをつつくという趣旨である。体内から煮汁が染み出すことであろう。上野茂都との出逢いも今年を象徴する出来事であった。残すところあとひと月。このようなゆるい時間ばかりが続いてくれればよいのであるが、お天道様はそこまでは甘やかせてはくれない。もう、これ以上仕事は入れられないと思っていたのであるが、またひとつ引き受けてしまったからである。発端は、このブログにエマニュエル・トッドの『帝国以後』について書いたことである。それを、藤原書店の編集の方が、お読みになっていて、トッドの新作について、寄稿をしてくれないかというご注文をいただいた。他の仕事は入れられないが、お相手が、藤原書店であり、題材がトッドであれば、お断りする勇気が俺にはないのである。で、明日どっさりとゲラが手元に届くことになっている。土日は、温泉で溶けている。平日は、年末の追い込みで超多忙である。締め切りはすぐそこである。読む時間も書く時間もほとんどない。いったい、いつ、どこで作業をすればよいのであろうか。まあ、体力を余すな、である。こうやって、やせ我慢を続けて、それで、本当にやせてくれれば、それにこしたことはない。
2007.11.28
コメント(1)
-
武蔵小山で、伝説とおめもじする。
オフィスで、朝から昨晩のたけし主演の『点と線』の話題で盛り上がっている。挨拶がわりの勝手放談が、リナックスカフェの朝の風景である。「たけしって、やっぱり凄いよね」「他の役者は、どうだったの」「高橋克典がかっこいい」「そうかね、俺はちょっと役者が違うような・・・」「で、さ、あれはやっぱし、昭和三十年代の東京のセットを見るドラマだよね」遅れて会話に混ざった俺は、話題を変えようと昨日の大瀧詠一さんとの、鼎談のことを話しの中に割り込ませた。「大瀧さんがさ・・・」「え、何処に出てたの」「何の話?」「だから、大瀧詠一だってば」とうやら、ももちゃんは、大瀧詠一と聞いて、大滝秀治が、ドラマに出ていたと勘違いしているらしい。オオタキ違いだぜ、ももちゃん。というわけで(どんな訳だ)、昨日は「朝から風邪気味」であったが、そわそわしていたのである。ビンに漢字が一杯書いてある正体不明の栄養ドリンクをひっかけて、武蔵小山アゲインへ向かう。アゲイン店主にしてナイアガラ伝道師の石川くんや、内田くんからなみなみならぬ熱意で語られてきた大瀧(師匠)詠一さんとのラジオデイズ鼎談があるからである。鼎談の模様は、両氏のホームページに詳しくレポートされることになるはずである。不思議なことに、俺は70年代中期を境に、道玄坂ライオンの住人になってしまい、音楽的潮流から取り残されてしまったので、日本におけるポップスの系譜的なことがよく飲み込めていない。(勿論、大瀧サウンドは、石川くんから回ってくる音源で、何度も耳にしているし、その音がこれまで聞いてきたものと違うのに、生まれる前から聞いていたような気持ちにさせられるといった体験は持っている)それでも、石川くん、内田くんから何度もお名前をお聞きしているうちに、とても偉い人なんだという大瀧イメージだけは、ふくらんでいたのである。いるでしょ。遠くにしか見えないけど、その存在自体に我知らず影響を受けてしまっているような伝説的な人物。で、その伝説と実際にお会いして、お話を伺う(というのが、どんな気持ちなのかということを確かめたい)というのが、今回の企画の趣旨であった。いやぁ、面白かった。音楽だけでなく、落語、色物、芸能、野球、映画、音響機器、コンピュータと実に多様な引き出しから、含蓄のある大瀧節が聞こえてくる鼎談となった。鼎談にもかかわらず、俺はほとんど笑いっぱなしであったので(そういえば、内田くんも石川くんも笑いっぱなしだったような気がする)、果たして、これが音源収録されて、どんなものになるのか、皆目見当がつかない。福生の仙人が、どんな声で何を語ったのかについても、よく憶えていないのである。大瀧さんの音声収録は、今年始めてだとおっしゃっていたので、たぶん、これが唯一の2007年大瀧トークとなるはずである。大瀧さん、内田くん、石川くん、ありがとうございました。風邪が直りました。(この音源は、来年早々に、ラジオデイズでアップされる予定です。)
2007.11.26
コメント(0)
-
葉桜の季節に、多忙であること。
昔の事はよく憶えているのについ最近のことが思い出せない。それでも、過ぎ去った時間を取り戻すわけにはいかない。耄碌した分だけ、荷が軽くなるってこともある。未来の約束に関しては、「まあ、過ぎたことは」なんていう言い訳ができない。「思い出せないってことは、やらなくてもいいってことだね」違うだろ。「分かっちゃいるけど止められない」と云いなおすべきである。つまり、この性格が、ダブルブッキングの原因をつくっている。あたふたするのは、記憶が戻ってきてしまうからである。何事も書いておく必要があるね、ということでやるべきことを書き出すことにする。勿論仕事のことが大半であるが、お約束している書き物についても、なんだかこんがらがってきているので、書き出してみる。書き出す前に、バックグラウンドミュージックが必要であると思い立つ。先日ダウンロードしておいた、竹内まりやのアルバムがあったので、セットする。いいねぇ。「人生の扉」。時間をテーマにしたポップスなんて、あっただろうか。コーヒーを飲みながら、白髪まじりの鼻毛を抜きながら、聞きほれる。あやうく、何か書き出すということを忘れかける。まずは、朝日新聞の『風雅月記』、これは月曜日に入稿予定。ラジオデイズ関連は、『月刊ラジオデイズ』の「関川夏央」小論。毎月のコラムは、まだ何も決めていないが、これも来週締め切り。出版関連は、『小笹―平川対論』の長い前説を書かなければならない。同時に、『反戦略的ビジネスのすすめ』新書版の前説と本編の手入れがある。おっと、みずほ総研の雑誌記事『グローバリズムに物申す』も今月中に上げないといけない。これで、全部だと思うが、何か忘れているかもしれない。(もし、忘れていたら誰か教えてね)いやあ、これで仕事をする閑があるのだろうか。委細は勿論、こんな場所に書くわけにはいかないのだが、本職の方は、年末を控えて結構ヘヴィなことになっているのである。ここで、力を抜くと、年末の帳尻が合わなくなってしまう。無理を承知で、無理を通さねばならないときもあるってことである。まるとの散歩の後の二度寝をつぶすしかないのか。いや、まるとの散歩をつぶしちゃおうか。(すまん、まる)♪信じられない速さで時は過ぎ去ると知ってしまったらどんな小さなことも憶えていたいと、こころが云ったよ・・・と、竹内まりやが歌っている。だけどね、それが、憶えていられなくなるのである。「人生の扉」がさび付くってこともある。「ご隠居は、耄碌してくたばることを忘れちゃったんじゃねぇか」(@子ほめ)うん。こうありたいものである。落語には、人生の理想があるね。葉桜の季節に(@歌野昌午)忙しくなり過ぎるってことは因果なことである。
2007.11.24
コメント(0)
-
タバコを止めてみる。
急に寒くなってきた。朝のまる散歩がつらいのである。ガリガリと戸をかきむしるのが散歩の合図である。「おい、早く起きろよ。散歩の時間だ。腹減ってるんだしさ。いつまでぐずぐず寝てるんだよ」まあ、こんな按配である。初天神まいりの金坊である。寒くなると俺は明るくなるまで布団の中でまどろんでいたいわけであるが、我が家の金坊のほうは、小便が近くなって五時半には騒ぎ出すのである。外はまだ真っ暗じゃねぇか。と言うわけで、今日も早起き、調子が悪い。ここのところ、夜中まで読んだり書いたりしていたので自然と煙草の量が増えてしまった。鏡で見たら、歯の裏が、お歯黒をつけたようになっている。これを続けていると、俺も全身灰皿人間になってしまうということで、秋葉原の新しいビルの中にある歯医者に行って口の中を掃除してもらうことにしたのである。実は、昨晩ふと思いついて煙草を止めようかと思ったのである。いや、禁煙じゃない。紙巻煙草を止めて、パイプにしようかと。それで、目黒駅近くにあるそれ専用の店に行き、パイプと掃除用のこより、葉っぱなど一式を買い揃えた。新しいことをはじめるというのは楽しいものである。うきうきしながら家に帰り、早速パイプに葉っぱを詰め、火を点ける。いいね。團伊玖磨じゃないの。オットー・クレンペラーのようでもある。このパイプという奴は、還暦に近くならないと、似合わないアイテムである。板につかないとは、このことである。俺も、パイプが板につく年齢になったということか。で、本日も会社にパイプを持参して、折に触れて、パイプに葉っぱをつめて、上から叩いて、火をつけて。しかし、面倒くさいものである。これを面倒だと思っているうちは俺もまだ、ケツの青いガキだということである。ああ、早く大人になりたい。(五十七歳)
2007.11.21
コメント(3)
-
落語のちゴルフ、ときどきけん玉とマラソン。
17日の土曜日は、昔の会社の仲間とゴルフ。ところが、これがダブルブッキングであった。しかも、ゴルフ場が潮来の先と遠い。どうしたらよかんべか。早起きして、まると散歩をし、車に腐りかけのゴルフバッグを放り込み、I-POD を持って出掛ける。道中、十代目金原亭馬生の『お富与三郎』1-4までぶっ通して聞く。馬生の語りを聞いていると、膝づめで兄貴分から町内の逸話を聞いているような気持ちになる。流麗でもなければ、けれんがあるわけでもなく、むしろ訥々とした語り口なのだが目の前にありありと情景が浮かんでくる。しがねぇ恋の情けがあだ・・・道中130分、「木更津」から「与三郎の死」まで上質のモノクロームの映画を見ているような気分で、馬生の話芸を堪能。そうこうしているうちにゴルフ場到着。わいわいと楽しいゴルフを午前中のハーフラウンドで切り上げ、ダブルブッキングのもうひとつの方へ車を走らせる。二時間のゴルフを楽しんで、二時間半かけてきた道を同じ時間をかけて戻る。田園調布駅前にあるカフェのDECOさんが、『犬は自分の生き方を決められない』(@講談社)という本を出版し、その記念パーティーがあった。俺は、同じ駄犬のオーナー兼カフェ仲間として乾杯の音頭をとるようにと命じられていたのである。パーティーでは、けん玉日本チャンピオンの方が超絶的な技巧を披露してくれる。当然、俺も昔とった杵柄に触れてみるが、これが思うようにいかない。明けて、日曜日は朝からそわそわしていた。久方ぶりの野口みずきを見れるからであった。レースは、中盤までは一進一退。最後は圧勝で、格の違いを見せつけた格好である。すごいね。マラソンというのは、見ている方も疲れるものである。俺もまた、精神的には42.195キロを走っているのである。見終わった後は、ぐったりとして、そのままベッドに倒れこんだ。いや、無駄のない、いい日曜日であった。(何もしないで終わった休日)(ラジオデイズ投稿原稿)ダイアローグに関する断章第4回 あらかじめ失われた友人からの挨拶 年賀状の季節がやってきた。私の場合にはいつも、年末ぎりぎりになって、大慌てで賀状を書き、年が明けてから投函ということが多いのだが、師走に入った頃には、すでにあらかたの賀状を書き終わっているという方もおありだろう。 高校生時代の友人である彼も、そのような律義者のひとりであった。武蔵小山にある高等学校を卒業以来、毎年元旦には彼からの写真入の賀状が私の手元に届けられた。 彼と私を結びつけたのは、部活であった。彼は水泳部の主将で自由形の選手、私はバタフライの選手であった。1960年代、場末の都立高校の水泳部がどれほどの実力を有していたかは、推して知るべしである。私たちが勝てるのは地元にあるもうひとつの高校(この高校にはプールが無かった)だけであり、大きな大会では、まったく歯が立たない弱小クラブであった。 私たちはお互いにレギュラーであったので、メドレーリレーのチームのメンバーでもあった。この四人の共通点はほとんど無かったが、ひとつだけ確実なのは四人ともに劣等生であったということである。私たちの高校は一応受験校ということになっており、地元の東京工業大学への入学者は全国で常に一位か二位であった。夏休みともなれば、膨大な数学の宿題が課せられた。教室や図書館で青息吐息で勉学に励む学友を尻目に、私たちの夏休みはプールサイドでの甲羅干しと、25メートルダッシュの日々であった。 日が西に傾く夕方の空を、練習が終わった後のプールサイドに寝転んで見上げていると、快い疲労感が濡れた身体を包み込んだ。同時に、学友に遅れをとっているというちょっとした焦燥感も襲ってきた。私たちは、この疲労感と焦燥感を共有する友であった。優等生を結びつけるのは、受験に役立つような情報だったかもしれないが、彼らは結びつくよりは競争を好んでいるように思えた。私たちは、劣等意識で連帯し、喫茶店に入り浸ったり、ときには教師の目を盗んで飲めない酒に酔い、春歌を歌って街を彷徨ったのである。水泳部は、この高校では常に「第五列」であった。 一年の浪人の後、彼は北海道の大学に行き、私は早稲田大学に行ったので、以後はほとんど顔を合わせるということが無くなった。大学を出てから、彼は自動車販売会社に職を得、私の方は自分で翻訳の会社をつくった。お互いに忙しくなり、彼との交友はますます疎遠になっていった。それでも年賀状の交換だけはその後もずっと続いていたのである。 その年も、彼から年賀状が届いた。富士山をバックに、オートバイの傍らで、太った体を革ジャンが包んでいた。フルフェイスのヘルメットを被っているので表情は良くわからない。手書きで、「今年もよろしく」とあった。彼の年賀状は、毎年判で捺した様に「今年もよろしく」であった。何が「今年もよろしく」だ。 私は、少し腹を立てた。彼に対して腹を立てたのではない。もっとつかみどころの無い、目に見えない、巨大なものに腹を立てていた。それを、時間といってもよいし、運命といってもいいかもしれない。 まさか、年賀状が届くとは思っていなかったのである。こんなことがあるんだ、と私は時間の不思議に撃たれたのだと思う。それは、いつもの正月の、恒例の儀式のようなものであり、何の不思議もない当たり前のことなのだが、この年に限っては、あってはならないことであった。こんなことが、あるんだ…… 彼が晦日29日に脳溢血で倒れ、元旦の朝永眠したという通知が年賀状よりも少し早く私に届いていたからである。
2007.11.20
コメント(0)
-
都築学園総長と会ったときのこと。
先日、九州を拠点とした大手学校法人グループの理事長が強制わいせつで逮捕されたと報ぜられた。読売新聞のネットニュースは、次のように報じている。「学校法人グループ・都築総合学園(本部・福岡市)の総長、都築泰寿容疑者(71)による強制わいせつ事件が起きた第一福祉大(福岡県太宰府市)で、女性職員たちが都築容疑者のわいせつ行為について度々上司に相談し、大学側が被害状況を学園本部に報告していたことがわかった。」なるほど。何か聞いたことのある名前である。俺は、この都築という男に5-6年前、どこかで会っている。そして、このブログにその時のことを書いたことがあった。(正確には、フジサンケイビジネスアイの『平川克美のビジネスの流儀』という連載に書いた記事をブログに転載している。(記事自体は、都立大学駅前にあるたこ焼き屋について書いたものである)もう一度それを転載してみよう。「人間四十になったら顔に責任をもつべきである」とは、エイブラハム・リンカーンの言葉だが、こういう利いた風な言葉というものは独り歩きするものである。誰も本当は、自分の顔になど責任を取れない。ただ、こういった言葉が年を経ても言い継がれるには、やはりこの言葉のどこかに真実が含まれており、誰もが思い当たる経験を持っているからだろう。私も時々、この言葉が頭の中に浮かんでくる。その時私は、ちょいとした買い物をして小腹が減り、駅裏の路地に面して、間口一間ほどにカウンターをこしらえたたこ焼き屋を見つけた。「どうだい。商売は。」「見てのとおりでさ。場所がワルいのかなぁ」「食い物屋はやっぱり、場所でしょ。」「味には自信あるんだけどね。 どう、一杯。ビールおごるから」「いや、そんなわけには。」「やっぱり、場所かな」「場所でしょ」あやうく、じり貧のたこ焼屋にビールをおごられるところであった。駅前の屋台は、私も食べたことがある。味はこっちの閑古鳥の方がいい。しかし、どう見ても場所が悪い。地の利というものがない。それで、おやじはひがな、大沢在昌のミステリを読んでいる。出来上がったたこ焼も、なんとなくハードボイルドである。後日同じ場所に行ってみると、シャッターが降り、このたこ焼き屋はつぶれていた。「ビールどうだい」と言った時の人の良い顔が思い出された。いい顔をしていたのだ。 俗に、天の時、地の利、人の和というが、こういうことを、商売の要諦のように言うものは大体信用できない。いつぞや、九州から出てきて、渋谷の駅前に土地を買いまくり職業学校やら、ビジネスセンターやらを手広く開業している学校経営者の演説を聴いたことがあり、その時にその思いを強くしたのである。その社長は、駅前五百メートルに、立地するのがビジネスのコツである、と息巻いてこう続けた。「人生すべからく、天の利、地の利、人の利。」おっさん、そりゃ違う。天の利じゃなくて天の時だ。あんたは、何でもかんでも「利」に結び付けて考えている。そりゃ因業ってものだ。フロイトは、いい間違いには、その人間の深層心理にある欲望が現れると言っている。この社長の場合は、いい間違いというよりは、記憶違いだろうが、まさにその記憶の仕方のなかに、本人の欲望が現れている。「利」の独り占めであり、反対に言っていることの「理」は薄い。こういう経営者の下で働くのは大変だろうと思って聞いていると、壇上に社員数名が呼び出された。社長は彼らをあたかも手下か、奴隷のように「こいつらは頭は無いが、汗は人一倍かける根性だけはある」といった意味の言葉で紹介した。わたしは、少々げんなりとして、ご招待の席を立って、会場を後にした。彼の顔が嫌だったのである。その顔はこう言っていた。「皆さんだって利にしか興味はないんでしょ。」それは一片の真理だが、それでも私は同類にされたくなかったのである。(記事おわり) 事件は、「強制わいせつ」という言葉の強さによって、この学校法人グループがひとりの変態男によって支配されていたかのような印象である。しかし、上の記事で俺が言いたかったのはそういったことではない。彼がどのような人間であるのかについて、俺は出会った瞬間にある種の危険を感じたのである。それは、彼の強欲によって自分の中の倫理感や職業観が蹂躙されるかもしれないという危険ではない。彼の中にある欲望というものが、俺の中にも(誰の中にも)存在している欲望を目覚めさせてしまうかもしれないという危険を感じたのである。人間の欲望というものは、個々によって強弱や濃淡はあっても、誰にでも同じように潜んでいるものである。人間が、社会生活を営むことができるのは、この欲望をだましだまし使うということを覚えたからである。規矩とは、己の内部の正義や倫理の名前ではなく、己の欲望に対して自らその使用を禁じるということに他ならない。「皆さんだって利にしか興味はないんでしょ。」と言われれば、いや俺は利には全く興味なんぞありませんよとは言い難い。ただ、その欲望の使用を禁じているだけである。なぜ、それを禁じるのか。おそらくは、自分で自分をリスペクトしたいという、次元の異なる欲望があるからだろう。自分に対するリスペクトとは、自分が何を得たかということよりは、自分が何を断念できたかということの中にしか生まれてこない。それは、断念によってしか獲得できない境地というものが確かに存在しているからである。リスペクトとは、他者をコントロールできる権力だと勘違いしているうちは、どこまでいっても欲望の次元を繰り上げることはできない。
2007.11.16
コメント(11)
-
モチベーションの原風景。
白髭橋の会社の13階にある喫煙室の窓の下には、隅田川が蛇行して流れている風景が見える。今日のように快晴の日には、新宿、池袋のビル群の遥か後方にくっきりと、白雪を置いた富士山。八ヶ岳、丹沢連峰まで見渡すことができる。気持ちがいい。昨日は、リンクアンドモチベーションの小笹社長と銀座の本社にて、長時間の対談。モチベーション、働くことをめぐる随談のようなものである。随談とは、随筆のような談話ということで、ラジオデイズの大森美知子の造語らしい。要素還元的な思想を排すというところでは俺も、小笹さんも概ね同じような考え方を持っているので、どうしても議論というよりはもうすこしゆるいものになる。それで、随談なのである。キャリアデザインも、モチベーションも、インセンティブも90年代後半から盛んに日本で使われ出した言葉である。こういう言葉が、脈絡無く出てくるときは、注意が必要である。なにか、新しいものが生まれたことを告げるよりは、失われたものを隠蔽する場合の方が多いからである。つまり、こういった外形的な概念を持ち出さなければ、やっていけないような現実的、心理的な問題が仕事の現場のほうで、顕在化しはじめているということに他ならない。95年以降、アメリカの産業は、モノづくりやサービスの提供といった商品を中心としたサプライヤーと顧客の間のコミュニケーションに基礎付けられたビジネスから、金融、知財ビジネスの方へ大きくシフトしてきた。ITビジネスもまた、そのような流れを加速するところにリソースを集中してきたといえるだろう。それ自体は、産業資本主義から高度資本主義の流れの中でのなかば必然的なプロセスを辿ってきたということであり、短期的な功罪を論じても何か新しい知見が見出せるわけではない。ただ、商品創造や、サービス提供といったビジネス本来の手触りや興味といったビジネスプロセスそのものの中に生まれてくる充足感や、満足感、矜持といったものに代わって、情報システムや金融システムがはじき出す結果がもたらす計量的なものが、ビジネスの方法も、価値観も支配するようになった。プロセスよりも、結果だよということである。情報システムや金融システムは、労働プロセスというものの標準化、効率化にしか興味を示さなくなった。しかし、それがどんなに標準化されようが、それらのプロセスを支えているのは、充足感や、満足感、矜持といったものを糧として生きている人間である。労働の現場そのものに胚胎していた労働への意欲そのものを脳化したビジネスは、プロセスから追い出したのである。その結果、失われた労働への意欲を恢復するためには、労働の現場の外側に欲望点火の幻想を作り出す必要があった。それが、モチベーションであり、キャリアデザインであり、インセンティブといったよく訳のわからない、言葉である。誰かが、あるいは何かが、個人の内面の中にこういった価値を吹き込んでくれるという物語である。でもさ、個人の内面をどれだけ掘り進んだところで、誰も労働への意欲や、キャリアへの渇望といったものを探り当てることなんかできないのは、自明のことだ。モチベーションがあるから働くんじゃないのだ。働いているうちに、自分の内面に広がってくる充足感こそが、あえていうなら、モチベーションというものの原風景だろう。まあ、そんなことを、小笹社長と話したわけである。(ほとんど違うけど)この対談は近日中に、ラジオデイズで公開される。同時に、年が明けて桜が咲く頃、本にもなる予定である。
2007.11.13
コメント(2)
-
無為と連帯。
ベローチェは、コーヒー一杯160円である。広々とした店内は、いつ行っても結構空席があって本を読んだり、書き物をするには具合がいい。コーヒーの味も、悪くはない。(勿論、旨いというわけでもない)リナックスカフェの一階で、サントリーの関連会社と実際のカフェを共同で運営したことがあるのだが、カフェというものが、利の薄い商売であることをそのときに知った。200円ぐらいのおあしを積み重ねてもなかなか地代家賃と従業員の給与を支払ってなお、利を確保するところまでは届かない。ベローチェが潰れずにやっているのはなかなか大変だろうと思う。広い店舗を維持運営するための、工夫や努力というものがあるのだろう。日曜日の昼間、いつもとは河岸を変えて、戸越銀座のベローチェに行ってみた。そして、この店が、地元にしっかりと根付いていることを知ったのである。広い喫煙スペースには、年配の客が本を読んだり、新聞を広げたりしており買い物途中のおばちゃんたちの四方山話に花が咲いている。商店街の中に、共有地(コモンプレイス)を提供しているのである。ここには、効率的なものは何もないが、無為に過ごすという贅沢が、許されているということである。すこし前、高橋源一郎さんと、ラジオで対談したときに「マイアミって行った?」と彼が聞いてきた。1950年代に生まれた者たちが、出会った瞬間に前から知り合いだったような錯覚に陥るのは何故かといった話をしているときであった。勿論、マイアミは知っている。いや、お世話になった。「レイモン・ルフェーブルオーケストラがかかっていてさ」。壁には、電光で光る本当のマイアミの風景写真が掲げられ、客はほとんどがどんよりとソファに沈み込み始発電車が走るまで時間を潰すのである。かびと生ゴミの匂いがする地下の店は、帰巣の時間にはぐれた人間たちの避難場所のようでもあった。そういう都会の吹き溜まりのような場所を俺(たち)はうろついていたということである。そういう体験の共有によって、人間の距離というものは縮まる。何もしなかったという体験。一緒に映画を見たとか、同じ地域に住んでいたとか、ビジネスで関係していたとか、同じ夢をみていたというのとは少し違う。ポジティブな体験を共有したところで、必ずしも連帯意識は生まれてはこない。「ネット難民のはしりだったんだよね」そういうことだ。俺(たち)は、当時の世界を、難民として過ごしてきたのである。孤独な難民であった。隣の座席に座っている人間と会話をすることなどないし、その場所から何か生産的なものが生み出されたということもない。それでも、いやそれゆえにこの無為の時間を共有しているということが、何かの意味のある種子を残していたとも言えるのである。夢の共有によって連帯感が生まれるよりは、夢のない無為の共有によって連帯感が生まれるということを学んだのは、それから何十年も経ってからである。
2007.11.11
コメント(1)
-
年に2冊の本を書き。
少し前に、共同通信から頼まれて、ウォルマートに関する本の書評を書いた。チャールズ・フィッシュマンの『ウォルマートに呑みこまれる世界』である。あれ、その後どうなったのかなと思っていたら、本日書評掲載紙がどさっと送られてきた。四国新聞、徳島新聞、河北新報、鳥取新聞、神戸新聞、などなどなど。15ぐらいの地方紙に掲載されていたわけである。なるほど、通信社と地方紙の関係はこうなっているのか。飼い主を離れた拙文が一人歩きしているという訳である。逃亡したまるが、日本中の電柱にマーキングしているようなものである。さて、本日洋泉社の渡邊くんとリナックスカフェの第二会議室『伊万里』で打ち合わせ。『伊万里』は、ねこ耳と尻尾ある女の子が闊歩する秋葉原では、唯一、老人が憩える喫煙喫茶の孤塁を守っている。なにしろ、囲炉裏がしつらえてあり、天井から鉄瓶がぶら下がっている。かび臭い地下室には当然携帯電話の柱は立たない。カウンターの中の婆さんが淹れてくれるコーヒーの苦味を味わうべし。彼女の人生を啜りながら、これからどうすんべと話をする。『反戦略的ビジネス』が洋泉社新書で、来春に出版されることになりそうである。以前にもこのブログで、書いたけれど、この本は、俺にとっての処女作であり、最も愛着のあるものである。内容的にも、その後のどんな本よりも遠くまで歩み出せたものじゃないかと密かに思っているのである。単行本出版のときは、書評らしい書評も出ず、世評的にはほとんど、無視されたのだが、熱心な読者の方から、気合の入った感想や、思わぬ方から、共感のエールをいただいた。それは俺にとっては思ってもいなかった反応であり、自分の中では、本望を遂げたと孤独な祝杯を上げたのである。てんで、来年は夏までに1冊が、リンクアンドモチベーションの小笹さんとの共著が一冊。なんだか感心できないカーネギーのベストセラー『人を動かす』のパクリで『自分を動かす』(仮)なるモチベーション論。もう一冊が、復刻版『反戦略的ビジネスのすすめ』(大幅加筆版)である。乞うご期待。
2007.11.08
コメント(3)
-
最も危険な場所。坂田の戦い。
気持ちよく晴れ上がった日曜日。WBA世界フライ級タイトルマッチが、埼玉アリーナで行われた。午後2時からというので、俺はまるの散歩を済ませ、自分の朝の排便を済ませ、爪を切り、近所のコンビニでするめを買って、テレビの前で気合を入れていたのである。ゴングが鳴り、俺はするめを噛みしめた。真昼間のアリーナは、なんとなく縁日のリングのようで散漫とした雰囲気であった。リングサイド向こう正面には、浜田剛史の四角い顔。この試合の意味について、よく理解しているボクサーのひとりである。メキシコでは、同じ日に亀田三兄弟の三男の試合があって、翌日のマスコミは、そっちの方を熱心に報道していた。それが誰であれ、ルーキーが勝ちあがってくるのを見るのは楽しいことだ。しかし、今日はルーキーには用はない。おれは、この埼玉の地味な試合に注目していたのである。ボクシングは、薄汚い場末の賭場のようなリングや、この日の埼玉のような、縁日の見世物のようなリングが似つかわしい、何となく俺にはそんな偏見がある。拳闘とは、鉦と太鼓とスモークで演出されたアトラクションでもなければ、健康や、精神の鍛錬の先にあるような麗しいスポーツではない。自ら望もうが望むまいが、そういった市民的範疇の中では生きられない野卑と野蛮がこぼれ出してしまうのが拳闘のリングである。スポットライトに照らされていようが、裸電球が揺れていようが、あるいは日曜日のけだるい日差しの中であろうが、そこは素人が、容易に上がれる場所ではないのである。それが、神聖であるからではない。人間にとって最も危険な場所だからである。チャンピオンの坂田健史が、大変危険な挑戦者を選んだことはゴングが鳴ってすぐにわかった。大振りだが、切れのよい右のフックが坂田の左あごをとらえ、そのまま、坂田は腰から落ちたのである。デンカオセーン・カオウィチットは、42戦40勝1敗1分けのベテランである。しかし、老獪なファイターというよりは、ボクシングというものを知り尽くしたテクニシャンである。ベテランにしては、きれいな顔をしている。こういったボクサーには、注意以上のものが必要だ。戦況は一進一退であった。ただ、回が進むにつれて、テクニシャンのほうに疲労が見え坂田のほうは、無尽蔵とも見えるようなスタミナで追い足を使い続ける。どちらの心が先に折れるのか。中盤以降は、精神力だけで体を引きずるような消耗戦になる。こういう消耗戦を見ているのは疲れるものである。後半何回か、カオウィチットの心が折れそうになるのが分かった。そして、その時俺は、これが坂田のボクシングなのか、リスキーだが、拳闘の原点のような戦い方だと思った。坂田は、チャンピオンになるまでに、三度世界戦を戦い、三度失敗している。その中には、ロベルト・バスケスをあと一歩のところまで追い詰めたが惜敗に終わった試合があった。防衛戦で、もう一度バスケスと戦い、雪辱を果たす。2005年に亀田興毅が協栄ジムに移籍してきてからは、常に亀田の脇役のポジションに立たされ、スパーリングパートナーまでつとめてきた日陰を歩いてきたチャンピオンなのである。結果はドローであった。メキシコで亀田の弟が脚光を浴びているときに、息詰まるような白昼の消耗戦を戦って、負けなかったこと。いかにも、苦節を耐えて這い上がってきた日陰のチャンピオンらしい冴えない防衛であった。するめのような試合。いいじゃないか。冴えない防衛だったが、凡庸な試合ではなかった。拳闘らしい拳闘とは、こういうものなのだ。
2007.11.05
コメント(3)
-
ラジオの日々。
「ラジオの街で逢いましょう」は相変わらず、好調である。i-Tunes のポッドキャスティング総合27位。パフォーミングアート部門1位は揺るがない。ラジオデイズのサイトでは、清水哲男さんと俺の対話がアップされている。昨日深夜、この番組を聴いて、なんだか独りで幸福な気分になった。是非、皆様にもお聞きいただきたい。俺は、この六十年代現代詩を代表する詩人の前で、恋焦がれた憧れの女と対面したうぶな中学生のように緊張し、へどもどし、告白までしちゃっている。清水さんは、いつもと変わることなく独特のリズムと、落語でいうところのフラのある(ちょっと違うか)滋味深いユーモアを漂わせている。いやあ、いいね。まいったね。この日は、昼間に番組の収録があって、国際政治解説者の田中宇さんと、落語作家の本田久作さんをお迎えして楽しい時間を過ごさせていただいたのである。俺より10歳年少の本田さんは、不思議な人である。中学生のときに、すでに100本の落語を振り回していたそうである。その後、伝説的なパンクバンド「変身キリン」のリーダーとして活躍していたが、また落語の世界にもどってきて、毎年、落語台本コンテストで賞を取り続けてきたのである。いったいどのような機縁が後押ししてこのような不思議な作家が生まれてくるのかということに興味津々であったが、対談後も、謎は謎のまま残ってしまった。俺は密かに彼の新作「全日本納豆壊滅プロジェクト」という噺を入手して読んでいたのであるが、このべらぼうな笑いが、どこから出てくるのかはわからずじまいであった。誰か、やってくれないかなぁ。この噺。田中宇さんとは、三年ぶりでお会いした。以前、俺の会社の一階にあるカフェで彼に声をかけ強引に俺の主宰するセミナーでお話いただいた。久しぶりにお会いする田中さんも61年の生まれで俺より9歳年下である。世界を旅して、どうして世界はこのように、多様で、多彩な出来事で満ち溢れているのかにうたれたそうである。そして、世界を掴むことのできるような唯一の視座というものなどどこにも存在しないことを発見する。なぜなら、どんなニュースも見解も、必ず何らかのフィルターがかかっているからである。このアポリアを解決する方法は、ただひとつ、左右前後、すべてのニュースを並列的に並べて、ニュースコンテンツではなくそこにかかるバイアスが何であるのかを知ることである。その試みが「田中宇の国際ニュース解説」というメルマガなのである。「世界はこれからどうなるのか」について、三十分足らずの収録では十分にお聞きすることはできない。それでも田中さんらしい慧眼が随所で光る。こんどは、三時間ぐらい時間をとって、じっくりとアメリカの凋落、イラクとイランの今後、ロシアパワーと中国の戦略などについて、お聞きしたいと思う。
2007.11.03
コメント(0)
-
行商人、ヒラカワの栄光と悲惨。
ポッドキャスティング配信を始めた「ラジオの街で逢いましょう」が好調である。本日は総合で44位。アート部門2位。パフォーミングアート部門1位。何だかうれしい。俺も、この番組をI-POD に入れて通勤しているのだが、大変に面白い。手前味噌が、こんなにもおいしいとは、思わなかった。しかも、賞味期限切れの材料を使ったり、日付を誤魔化したりしていないから新鮮である。まあ、やっている俺たちはだいぶ賞味期限が過ぎてはいるがね。自分が聞きたいと念願していた番組を作ったのだから当たり前といえば当たり前だが、いい番組である。六丁目食堂のマスターにも、おすそ分けしておこう。もうひとつ宣伝めいて、恐縮だが、ラジオデイズの落語30選を、まるごとVoice Treckに放り込んで発売という暴挙を思いついた。これが、マシン込みで、39,800円と馬鹿高いシロモノである。宣伝用の惹句は、「銭のある奴ぁ、俺んとこへ来い!究極の大人買い! 戦慄の太っ腹企画。笑い死に、永久保存版30選。「ええぃ、面倒だ」「みんなまとめて面倒みてくれ」という剛毅な落語ファン(貴方のことです)に贈る。ラジオデイズプロデューサーによるお奨め30選。「ダウンロードなんて面倒だ。エレキものは苦手で、買うことができない。何でもいいから端から端まで見繕って俺んとこまで持って来い!」とおっしゃる太っ腹、豪快無比、かつわがままな貴方。お見それしました。分かりました。ラジオデイズプロデューサーが厳選した落語30選を、まるごとオリンパスのプレーヤーに収録して、機械ごと貴方のお手元にお届けします。」確かに暴挙である。誰だ、こんな下品なコピーを作ったやつは、って。俺だよ。てんで、しばらく荷を担いで、行商の旅に出なくてはならなくなった。ちなみに、まっさきに「お、いいじゃないの。」と買ったのは誰かって。俺だよ。(ラジオデイズのサイトで買っていただけると、俺の荷も軽くなるのだが売れるかな。売れねぇだろうな、やっぱり)
2007.11.01
コメント(1)
全13件 (13件中 1-13件目)
1