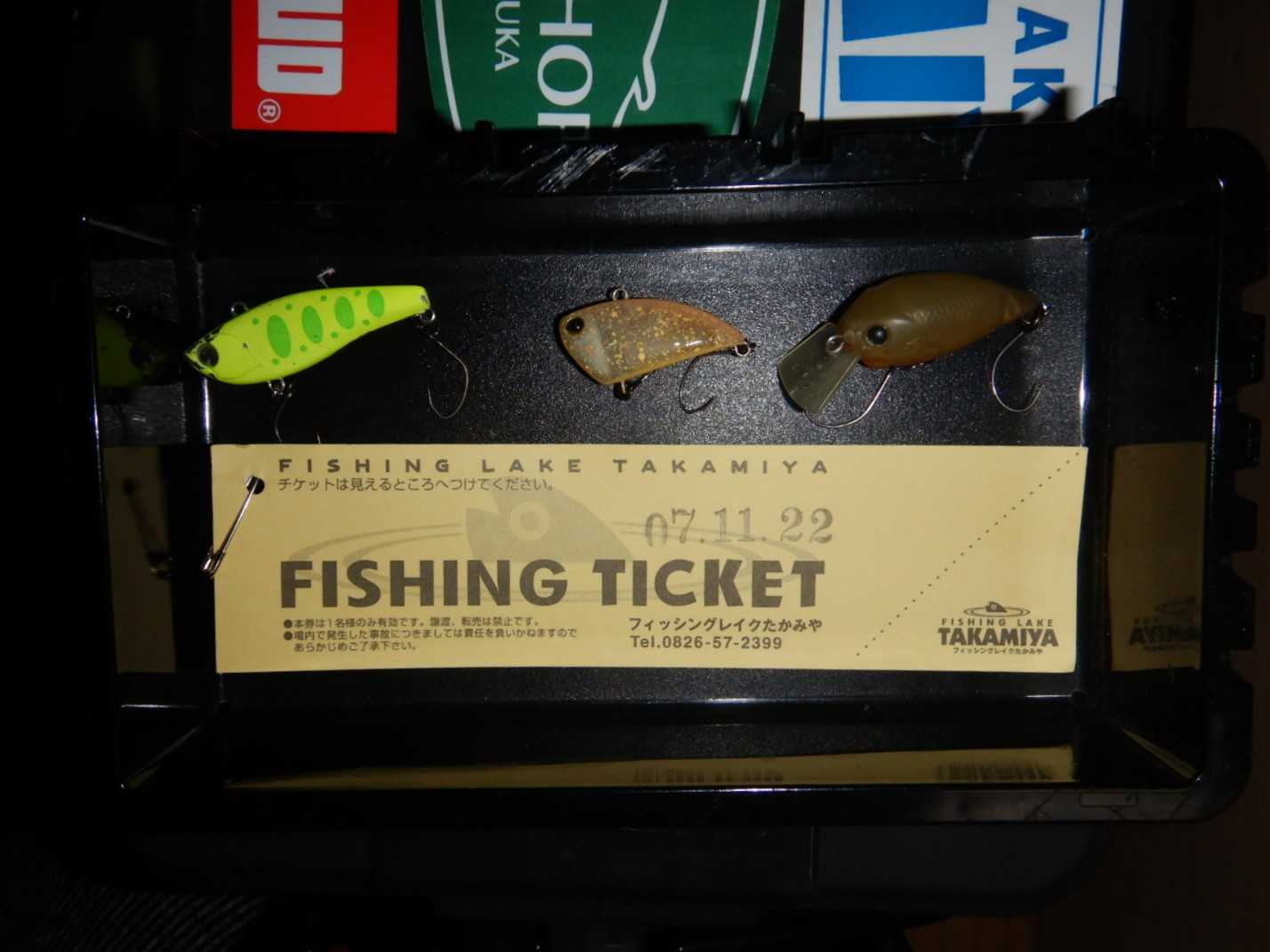2024年12月の記事
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-

鳥類の飛翔を支える翼のいろいろ
新年の準備が一段落し、落ち着いて書籍に目を時間がようやくできました。入手していた文一総合出版刊行の「華麗なる野鳥飛翔図鑑」を見ながら過去撮影した鳥類の飛翔のシーンを復習してみました。解説を見ながら見返す楽しい時間でした。(翼の4種類の形)斎藤(2024)では、つぎの4つに区部しています。(1)尖翼(せんよく:先端が尖っている翼)(2)裂翼(れつよく:先端が分かれている翼)(3)円翼(えんよく:丸い翼)(4)扇翼(おうよく:扇型の翼)の4種類に区分しています。(1)尖翼カモ科がこのタイプで、高速で羽ばたきスピードに乗って直線的に飛びのが特徴です。写真1枚目オオヒシクイ、2枚目コクガン、3枚目オオハクチョウ、4枚目ビロードキンクロは尖翼で腕の長い長腕型です。斎藤(2024)は、長腕型に区分される種類では胸筋に長時間の飛行を支える赤色筋を多く含まれていると述べています。また、中腕型に区分される種類では羽ばたきやすく、オシドリのように林内を巧みに飛翔したり、多くのカモのように猛禽類が飛来した際に素早く飛び立ち、上空に移動する特徴を述べています。(2)裂翼写真5枚目のアオバトがこのタイプです。中腕型で翼を力強く羽ばたくことができ高速で飛行できるので、岩場に降り立った際に波が打ち寄せても退避する能力に優れます。6枚目のチュウヒ、7枚目のノスリも中腕型に属します。チュウヒの羽ばたきと滑空を交えて葦原を滑翔する動き、ノスリの帆翔しての探索飛行を可能としているのがこのタイプの翼です。(3)円翼写真8、9、10枚目のコミミズクがこのタイプです。ゆっくりとした羽ばたき、滑空を交えて飛翔し、獲物を発見すると急降下をして捕獲する行動を支えています。(4)扇翼写真11枚目のハクセキレイがこのタイプです。自由度の大きい落差の大きい羽ばたきと跳躍飛行を行うことができるのはこの翼によるものです。(写真)1枚目:オオヒシクイ2012年12月23日稲敷市、2枚目:コクガン2016年3月12日谷津干潟、3枚目オオハクチョウ2019年11月25日蕪栗沼、4枚目:2016年2月24日浦安市、5枚目:アオバト2019年8月3日大磯町、6枚目:チュウヒ2018年1月6日印旛沼、7枚目:2018年3月11日稲敷市、8枚目コミミズク2015年2月22日、9枚目:コミミズク2020年4月6日手賀沼沿岸、10枚目:2020年1月4日手賀沼沿岸、11枚目:ハクセキレイ2009年3月29日手賀沼沿岸(参考)斎藤安行.2024.華麗なる野鳥飛翔図鑑.pp291.文一総合出版.我孫子市鳥の博物館.2015.第73回企画展.飛んでいる鳥展.飛翔型コレクション.展示解説集.pp23.
2024.12.31
コメント(0)
-

印西市笠神、新たな水を張った水田エリアにハクチョウが飛来
印西市笠神のハクチョウの郷が借地終了で従来のような水を張った田んぼは終了したと発信をさせてもらいました。鳥友から新しい情報をもらいました。内容は、新しく水を張った水田が誕生し、12月27日現在771羽飛来したとのことでした。25日に500羽が飛来し、さらに増加して771羽に増加した模様です。また、地元の小学生や教職員の皆さんの願いを込めた竹短冊も設置されたと聞き、ほっとしました。(写真)2024年11月4日撮影(これまでの飛来地の近くの水の張っていない水田に降り立った光景)、2024年1月27日撮影
2024.12.30
コメント(0)
-

柏市内の谷津田はコサギの採餌を観察できるプライベートステージ
柏市のオフィス近くにある小さな谷津田は、小鳥類、カワセミ、猛禽類と出会えるフィールドです。また、小さな池と水田の近くで待機しているとサギの採餌行動を間近で観察できます。特に、コサギは足を震わせるように細かく動かし小魚を追い出して捕獲したり、水田の縁を機敏に動いて捕獲している光景を目にします。このフィールドで観察できたらと期待しているのが、嘴を疑似餌とした漁法です。坪島(1994)が「自分のくちばしに魚をおびきよせて採食する行動を観察している」、「くちばしの先端を水面につけ、水面を振動させて波紋をつくり、その波紋に近づいてくる魚をくわえとる」と報告内容を目にしたことがあるからです。このほかにも、濱尾ほか(2005)が、嘴の振動で波紋を起こすことで魚をおびき寄せ捕らえる行動を報告しており、それらを目撃できたらと密かに期待しています。今朝は、複数のコサギとダイサギ、アオサギが池、水田に降り立ち、餌探しをする光景を観察できました。また、コサギが池上空にカラスが登場した折、上空に目をやったと思ったら頭部の羽毛をふくらませる仕草を目撃。このほか、池の葦原の茎をつつき、葉鞘(茎を覆う皮のようなもの)の下に隠れているカイガラムシ類を採食する姿もありました。今冬は、毎年姿を目撃しているルリビタキ、ツグミ、アカハラなどの姿を見かけません。年明けにはきっと姿を見せてくれると期待しています。(写真)2024年12月30日撮影(一枚目のシジュウカラは2024年2月14日撮影)(引用)坪脇遊.1994.コサギによるくちばしを疑似餌とした採食行動.Strix.第13巻.p221-223.日本野鳥の会.濱尾章二・井田俊明・渡辺 浩・樋口広芳.2005.サギ類の餌生物を誘引・撹乱する採食行動 -波紋をつくる漁法を中心に.Strix.第23巻.p91-104.日本野鳥の会.
2024.12.30
コメント(0)
-

ようやくベニマシコ、ツグミ、オオジュリンと出会えました(手賀沼冬鳥探鳥記)
印西市から柏市東端までの手賀沼流域を探索しました。スタート地点でコハクチョウ2羽、オオハクチョウ10羽の姿を発見しました。オオハクチョウは9日には6羽だったものが増加していました。次に手賀沼の葦原の面積が広いエリアに移動し、小鳥の姿を探していると、ピッポッと鳴き声がしたと思ったら上面が褐色で下面に縦斑のあるベニマシコ雌、チューイーンと鳴き声がする方向に目をやるとオオジュリンの姿、くわえて葦原の中をツグミが移動する姿を発見しました。水面には、ユリカモメ11羽(うち2羽は雨覆に褐色斑のある若鳥)が休んでいる姿がありました。くわえて、浅瀬で足を震わせて餌探しに余念のないコサギを見ていると嘴基部がピンク色で飾り羽があるのを発見。真冬では初めての観察経験でした。その後は、柏市側に移動し、遊歩道近くに水草が堆積しているエリアでオカヨシガモ、マガモ、ダイサギ、コサギが羽を休めている姿を発見。近くに電線に亜種オオカワラヒワが止まっていました。頭部がオリーブ褐色の雄、頭部が灰色味の強い雌の両方の姿を観察できました。(写真)2024年12月29日撮影
2024.12.29
コメント(0)
-

メジロの音声言語について
12月22日に開催された鳥類学大会2024で第4回バードリサーチ賞を受賞した近藤雅也さんによるメジロは何をしゃべっているのか?―メジロの音声言語と混群構成種との関係―についての報告が行われました。内容は、近藤(2021)は、メジロの鳴き声の機能や使い分けについて明らかにすることを目的に音声機能に関する実験・調査を行った報告によるものです。報告によると、メジロのチーという音はコンタクトコールとしての機能があり、頻繁に鳴き交わすことで互いの位置を共有している、遠く離れた個体ともコミュニケーションが可能であり離れてしまった番相手や群れを探すのに利用している可能性があると述べています。さらに、連続音をどのような状況で出しやすいかについて調べた結果、群れにおける個体数 が少ない、群れにおける異種数が少ない、敵が周囲に存在する、枝にとまっている、非繁殖期で連続音を出しやすいと報告しています。これらから、チーという声と連続音は使い分けていると記しています。これまでは、蒲谷(1996)が声紋データとともに「チイーチイーチュチィーチィー」と金属的な高く大きな声でさえずる」「地鳴きはチーッと聞こえる鋭くきつい声」「警戒と思われるキリキリキリ、チリチリチリと聞こえる連続したきつい声も出す」と報告していたのみでした。近藤(2021)がチーという声と連続音の使い分けを指摘している点は、フィールドで確かめてみたいと思いました。(引用)近藤雅也.2021.メジロは何をしゃべっているのか?―メジロの音声言語と混群構成種との関係―.pp7.バードリサーチ調査研究支援プロジェクト第4回バードリサーチ賞選考結果.(写真)2015年3月29日柏市内、2021年11月20日柏市内で撮影
2024.12.28
コメント(0)
-

チバエナガのルーツは縄文時代に
鳥友から通称チバエナガのルーツについて質問をもらいました。チバエナガは、望月(2022)が報告しているように分類学的な種名、亜種名ではないが眉がわずかに薄いまたは眉がほぼ真っ白なエナガを通称チバエナガと呼んでいます。千葉県北西部を中心に生息していることが知られていますが、最近の知見では千葉県全域でその生息が確認されています。また、2010年以降は東京都、埼玉県にも同時に侵入したことが知られています。ただし、濃い眉の個体の中に眉の薄い個体が混じっていたとの状況で、眉の薄い個体だけでの群れの記録はない模様です。亜種シマエナガと亜種エナガの交雑の可能性を検証する遺伝的なアプローチが必要と研究者から指摘されています。さて、昆泰要(2023)が、チバエナガの分布域は縄文海進時(*)の地形に関連性があるとの報告をしています。縄文海進時に本州から隔絶されて島となっていた千葉県に生息していたエナガ個体群が眉斑の薄い特性を獲得したものがチバエナガである可能性がある。再び千葉が本州と陸続きになった後もアシ原などが生息や移動を制限する役割を果たしたと述べています。このため、通常エナガとチバエナガが容易にお互いの生息域を行き来することができなかったと指摘しています。(*)寒冷であった旧石器時代から縄文草創期が終わり、温暖な時代が到来すると、地上にあった氷河が溶けて海に流れ込み海水面が上昇(縄文海進は標高8メートル前後が水面)し、本州から隔絶され島となったと言われています。(引用)昆泰要.2023.千葉県周辺におけるエナガ(Aegithalos caudatus)の頭部白化個体群の分布について 日本生態学会第70回全国大会 (2023年3月、仙台) 講演要旨.(写真)2015年11月30日柏市内、2021年12月24日柏市内で撮影
2024.12.27
コメント(0)
-

吉川美南にベニマシコとツグミがやってきた(吉川美南探鳥記)
師走の吉川美南駅西口と東口の調整池を探索しました。西口調整池の周囲の遊歩道下の草地でベニマシコ雄3羽、雌1羽がアキニレと思われる実をついばんでいました。また、ケッケッと声を出しながら枝にツグミが降り立ちました。カモはマガモ、コガモが水面で羽を休めていましたが、水辺ギリギリの草地に釣り人が立ち入ったのに驚いて北西方向に群れで渡去してしまいました。次に訪ねた東口調整池では、マガモ、コガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、オオバンが水面で羽を休めている姿、電柱に止まり何度も地面に降り立ち餌を捕獲していたチョウゲンボウの姿を観察しました。(写真)2024年12月26日撮影
2024.12.26
コメント(0)
-

キタホオジロガモ似のホオジロガモにドキドキした思い出(ホオジロガモの特徴)
今シーズンもそろそろ三番瀬あたりにホオジロガモがやってくる時期です。歳末の仕事を片付けてから探しに出かける予定です。氏原(2015)が述べているように、頭頂部の高い三角形の頭部が特徴的です。ところが、2014年2月に三番瀬で見かけたホオジロガモ(写真一枚目)は頭頂部が高く、後頭部の羽毛が後ろに張り出したように見えてキタホオジロガモではないかとドキドキした思い出があります。眼先下の大きな楕円形でキタホオジロガモの半月型(三角形)とは異なっており、その上端が眼よりも高い位置に出ていないこと、体上面は白色部が多く、キタホオジロガモ(*)雄生殖羽の黒地に白斑が並ぶ状態ではないことなどでホオジロガモでした。このほか、雄生殖羽と第一回冬羽、雄個体と雌個体についてその特徴を復習。写真と共に提供します。参考になれば、幸いです。(*)キタホオジロガモの観察記録日本野鳥の会野鳥記録委員会(1987)につぎの観察記録が報告されています。キタホオジロガモ1987.03.26北海道上磯郡上磯町函館湾.香川裕之.雄1羽.雌3羽。前記のほか、1997年2月11日北海道根室市春国岱で雌2羽が観察、1998年12月5日から1999年2月11日石川県七尾湾西で観察記録が寄せられているが、日本産鳥類目録編纂委員会(2014)が鳥類目録の根拠となる出版物がないため検討種としたと報告しています。日本野鳥の会野鳥記録委員会.1987.StrixFieldNote.野鳥情報・観察記録1986.8-1987.12日本産鳥類目録編纂委員会.2014.日本鳥類目録改訂第7版で「検討中」とした種および亜種について.p132.(雄生殖羽と雄第一回冬羽)写真二枚目から四枚目は、雄生殖羽です。頭部が緑色光沢があり、眼下先の白斑は楕円形で上端は眼よりも高い位置ではありませんでした。虹彩は黄色、肩羽は白地に黒い腺があります。また、四枚目は、頭部を後ろへ倒すヘッドスローディスプレーです。倒しはじる時から記録できたらよかったのですが、この先は一枚だけの記録にとどまりました。また、お目にかかりたい光景です。これに対して写真五枚目、六枚目の雄第一回冬羽は、虹彩は黄色、眼下にぼやっとした白斑があり、翼は白色部が黒い部分で数段で区切られている印象があります。(雄生殖羽と雌個体)七枚目の写真は、雌個体です。嘴は黒く、先端に黄色の斑があります。虹彩は黄色で、頭部は茶色で雌生殖羽の黒褐色とは違っており、雌第一回冬羽ではと思われました。(写真)一枚目:2014年2月22日三番瀬、二枚目から四枚目:2016年2月21日三番瀬、五枚目と六枚目:2018年2月3日浦安市、七枚目:2022年12月26日浦安市で撮影
2024.12.25
コメント(0)
-

ヨシガモの囲い込み行動、はじまる(柏の葉公園冬鳥探鳥記)
北西の冷たい風が吹いていましたが、柏の葉第一水辺公園、柏の葉第二水辺公園を探索してみました。それぞれ小さな池ですが、周囲の草むらなどの遮蔽物があり、落ち着いて休むことができるのでヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、コガモ、オオバンの姿がありました。個体数が最も多いのは、ヨシガモでした。その個体数は80羽。鎌状の三列風切で揃った雄20羽ほどが2羽程度の雌を囲い込むように泳ぎ、自分への興味を引くようにいろいろなポーズでアピールしていました。今日は遭遇できなかったのですが、一番は頭と尾を同時に上向きに反らす姿勢です。その行動後、ペアを獲得しているようです。雄エクリプスが生殖羽に換羽中の個体は、鎌状の羽が整っていないのでエントリーできていませんでした。このほか、ヒドリガモは雄生殖羽と雨覆に白い羽縁が目立つ雌非生殖羽、マガモは成鳥雄生殖羽、雌非生殖羽、カルガモは各羽の羽縁が雄よりも幅広で体全体が淡色の雌生殖羽、体上面が黒褐色の雄成鳥、ハシビロガモは雄生殖羽、雄エクリプスが生殖羽に換羽中の個体を観察できました。また、茂みの中で風をさけて羽を休めていたゴイサギ若鳥の姿も目撃。(写真)2024年12月24日撮影
2024.12.24
コメント(0)
-

高崎自然の森の冬鳥探鳥記
朝から北西の風が強く、風を避けて冬鳥を観察ができるつくば市高崎自然の森に出かけました。待機していると、複数のルリビタキ、シロハラ、シジュウカラの鳴き声が聞こえてきました。待機していると、頭上から腰にかけて青色、風切外縁に褐色味のある雄第四回冬羽の個体が登場しました。(雄第三回目冬羽は頭上から腰にかけて褐色味を帯びた青色)その後、頭上から腰にかけて青色で風切外縁が濃青白の個体が登場。雄第四回冬羽と思われました。(雄成鳥は、風切が黒褐色で外縁が褐色と青色ですので第四回冬羽から成鳥冬羽に換羽中の個体と思われました)ルリビタキが登場したエリアの隣にある畑地ではシロハラが地面を掘り返して餌を物色している光景、ふわふわとした飛翔をして登場したカケスが登場したり、楽しい時間を過ごしました。(写真)2024年12月23日撮影(現地へのアクセス)園内に駐車場は整備されていますが、JR牛久駅からTXみどりの駅行き路線バスがあり、 高崎入口停留所下車徒歩5分(所要時間約20分)です。なお、日中は一時間に一本程度なので調べてからお出かけになることをおすすめします。
2024.12.23
コメント(0)
-

カモが越冬する池(湖沼)と姿のない池(湖沼)について
鳥友から印旛沼には多数のカモが休んでいる姿があるのに、手賀沼では休んでいるカモの姿は少なくその差はどんなところにあるのかと質問をもらいました。(印旛沼と手賀沼の個体数密度について)我孫子市(1995)は、全国ガンカモ類一斉調査のデータを用いて手賀沼、印旛沼、茨城県涸沼、菅生沼、牛久沼の5ヶ所の種類別個体数密度(個体/平方キロ)を比較し示しています。手賀沼は196.9/平方キロ、印旛沼387.7/平方キロ、牛久沼373.5/平方キロ、菅生沼1139.2/平方キロだったと記しています。この結果から手賀沼は面積の割にガンカモ類の個体数が少ないことがわかります。また、夜間採餌を行い昼間湖面で休息していることが多いマガモとカルガモは、休息する水域が岸から距離のある湖沼の方が安心して休息でき個体数密度が高くなる傾向が認められたと報告してます。さらに、昼間、湖岸のヨシやマコモの中で休息しているコガモは湖岸で植生が少ないか認められない湖沼では個体数密度が低くなると指摘しています。そして、むすびとして、手賀沼では休息のため訪れるカモ類の比率が高く、採餌場所として訪れるカモ類の割合が低いと述べています。(カモが休むところとそうでない池の条件)数のカモが休む池とそうでない池が存在するのはなぜかという点について文献を調べてみると、武田(1990)が近畿地方中央部の池252か所について調査した結果を整理し報告しています。それによると、カモ類が越冬地として選択する池の条件で最も重要なことは、周囲との遮蔽の状態であり、とくに水辺の環境が重要であると考えられ、水面をおおうように生える常緑樹林、水中に生えるアシ原やヤナギ林の存在、そして上陸しやすい水辺が最も重要であると考えられたと記しています。カモ類が越冬地として選択する池の具体的な条件として、つぎの内容をあげています。(1)水深が30cm以上あること.(2)上陸しやすい安全な水辺があること。護岸は材質より緩傾斜であること、棚状の部分があること(3)完全に遮蔽されている池では10m程度の幅でも定着しているが、水ぎわまで人が立ち入れる池で島や密生した樹林、アシ原など遮蔽された場所を背にできる池では30m以上、全周囲に人が立ち入れる池では75m以上の幅があること(4)餌づけなどが行なわれていない場所でカモ類と人間との間に必要な距離は30m以上なお、カモ類のみられる池と水質(富栄養,貧栄養,COD)との関連を指摘する報告もあるが、採食場と休息地は必ずしも一致している必要がないためか、陸ガモ類については明確な関連は認められなかったと述べています。(引用)武田恵世.1990.カモ科鳥類の越冬する池の環境条件.Strix9:89-115.日本野鳥の会.我孫子市.1995.我孫子市自然環境調査 鳥類調査報告書.37-42.(写真)一枚目:マガモ2024年11月18日、二枚目:2024年12月4日手賀沼、三枚目:2024年1月27日印旛沼
2024.12.22
コメント(0)
-

流山市のタゲリ、イカルチドリ、冬鳥観察記
流山市と野田市の境界の水田地帯を探索しました。前回、タゲリの小群が採餌していた水田に複数のイカルチドリの姿を見つけました。長めの嘴、細いリングの黒斑、スマートな体型、いつ出会っても惚れ惚れします。タゲリは水田で採餌をしていたのですが、埼玉県側に渡去し、記録写真はかなわず。このほか、電柱に止まっているチョウゲンボウが地面を注視していると思ったら地面に降り立ちネズミらしき餌を捕獲し、電柱にまた戻って食す姿を観察。その近くにはモズの雌雄の姿があり、食する姿をじっと睨んでいました。(写真)2024年12月21日撮影
2024.12.21
コメント(0)
-

千駄堀池の冬鳥探鳥記
師走の松戸市千駄堀池を訪ねました。すっかり周囲の光景は真冬の景色となり、池の水面にはカモ類の個体数が増えました。到着直後、カシの木の枝にアオバトが止まりうとうとしていました。アイリングがプルーで小雨覆と中雨覆が赤紫の雄個体でした。地元の方によると、午前中は地面にあったドングリを食していたとのこと。春から夏は花のつぼみや芽、夏に熟す木の実などを食べているのに、 秋から冬はシイやアラカシなどのドングリを主食にしている山野の鳥です。池の水面では、マガモ、オカヨシガモ、ヨシガモ、コガモ、キンクロハジロ、カイツブリ、芝生に降りて種子をついばんでいたカワラヒワを観察しました。このうち、オカヨシガモ雄は額から頭頂、後頭が暗色で、褐色の頬、耳羽に分かれている個体でした。ヨシガモは雄エクリプスが生殖羽に換羽中の個体、雌個体でした。また、キンクロハジロは体上面と胸に黒味が目立つ幼羽と思われる個体でした。このほか、池にはカイツブリ、芝生の上で種子をついばんでいたカワラヒワを観察しました。(写真)2024年12月20日撮影
2024.12.20
コメント(0)
-

ツグミは今、とこまで来ているの?
山野の冬鳥の代表的なツグミですが、ホームグランド手賀沼とその周辺地域では11月18日が初認でしたが、その後まったく姿を見かけていません。複数の鳥友からツグミ、アカハラ、ホオジロ類などを見かけないと聞いています。(2024年冬のツグミの飛来状況)バードリサーチ(2024)を見ると、9/30までに観察されたのが富山県と秋田県、それ以降東京都、宮城県、熊本県、香川県で観察記録が寄せられたと報告しています。梅垣(2019)は、日本列島を南下するルートが2ルート(*)がある鳥として、ツグミ、タヒバリ、アトリ、ハギマシコ、オオマシコを例示しています。(*)日本海を横断するルートのみをとる種とあわせて日本縦断ルートも存在する2タイプ)ルートを日本地図で見てみると、朝鮮半島から九州地方へのルート、日本海を横断しての能登半島などの北陸地方へのルート、日本海を横断し北海道のルートにくわえて日本を縦断するルートです。バードリサーチ(2024)が報告しているツグミ初認と渡りルートの関係に注目してみると、富山県の記録は日本海を横断して北陸地方へのルートでのもの、秋田県の記録は日本海を横断してのか、北海道に渡ったものが南下したのかのどちらかと思われるものです。さらに、熊本県、香川県の記録は朝鮮半島から九州のルートではないかと考えられます。平年であれば、前記ルートで日本に渡ってきて、群れで山林で行動した後各地へ分散し、平野から山地の森林、草原、農耕地、都市部に移動し越冬すると言われています。どこか食べ物の条件の良いところにとどまっているのか、繁殖地での繁殖が芳しくなく個体数が激減しているのか、考えられるのはこの2点です。(過去同様のケースについて)2011年から2012年の小鳥の越冬でも同様のことがあったのを思い出しました。日本野鳥の会が当時の状況を報告しており、「ツグミについて最も北からの情報である旭川では例年と変わりない。東北、関東ではシーズン当初、ほとんど見かけなかったが1月中旬以降小規模な群れが見かけられるようになった。その他の地方では、極端に少ない」と報告しています。(昨シーズンの柏市内のツグミの個体数)2023年11月、12月のツグミの観察記録を振り返ると、11月14件22羽、12月42件73羽で12月に入っても大半が単独の姿だったものが12月31日にのツグミ15羽を観察しました。今シーズンも同様なのかと注視しています。(引用)日本野鳥の会.保全のための調査・研究.https://www.wbsj.org/activity/conservation/research-study/2011-2012-winterbird/梅垣佑介.2019.日本周辺の鳥の渡りルート.日本の渡り鳥観察ガイド.p35.文一総合出版.バードリサーチ.2024.季節前線2024.https://www.bird-research.jp/1_katsudo/kisetu/index_kisetu_kekka.html(写真)2023年12月16日、同年12月20日柏市内で撮影
2024.12.19
コメント(0)
-

大町自然公園の冬鳥探鳥記
久しぶりに市川市大町自然公園を探索しました。大町駅前のパーキングに愛車をとめて公園まで徒歩で移動し、園内を見て回りました。藪の中から複数のウグイスの笹鳴き、複数のメジロ、シジュウカラ、アオジが鳴きながら移動する姿やアカゲラの鳴き声を耳にしながら遊歩道をすすむとカッカッと声がしたと思ったら林縁暗い空間をルリビタキが移動していきました。若鳥冬羽または雌のいずれかと思われましたが、翼角に青色があるか、上面に青色があるか、雌であれば尾以外に青色がないはずですが、これらを観察しようと思ったらカメラマンが出現した際に渡去となり万事休す。次回のお楽しみとなりました。帰路、駅近くのパーキングの近くの電線にコサギが止まっている姿を見ていたら、右脚に環境省リングを装着しているのを発見しました。(写真)ルリビタキ以外は、2024年12月18日撮影ルリビタキは2013年2月16日柏市(上面に青色がないので雌ではないかと思います)、2022年1月12日大町(翼角に青色があり雄若鳥と思われます)、2022年12月12日柏市で撮影(尾以外に青色がないので雌ではと思います)
2024.12.18
コメント(0)
-

我孫子市側手賀沼遊歩道からの冬鳥観察記
青空が広がり暖かでしたので冬鳥との距離が近い我孫子市水の館から沼東端の岡発戸までの遊歩道を往復5キロ探索して歩きました。スタート直後、水面に複数のカンムリカイツブリの姿がありましたが、うちの一羽が遠目にみて真っ白に見えたので待機し観察してみると、虹彩は赤色、頭上の黒色部はほんの少しで、顔から前頸は白色、体上面の黒色部は未完成、嘴の色は薄いピンクの個体でした。若鳥から冬羽に換羽している途中の個体では思われました。ガンカモ科の鳥では、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒトリガモ、コブハクチョウ、水辺の鳥ではカワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、ユリカモメ、セグロカモメを観察できました。また、遊歩道上にあるベンチで男女の若人がお弁当を食べているところを上空から覗き込みようにトビが接近する光景、遊歩道脇の草地ではモズの雌雄、ジュリジュリと鳴きながら8羽のエナガが登場したり、日だまりでお日様を楽しんでいるようなスズメたちと盛りだくさんの出会いでした。(写真)2024年12月17日撮影
2024.12.17
コメント(0)
-

人見知りが強いカイツブリと人に慣れたカイツブリ
12月11日に松戸市千駄堀池でカイツブリ成鳥と若鳥の親子連れを目撃しました。千駄堀では観察者が近くにいても警戒している様子は見受けられず、慌てて逃げる様子もなく頻繁に潜水も行わずで人に慣れたタイプです。同様のカイツブリを都内北区浮間公園でも見かけたことがあります。ところが、木の中に身を潜めていることが多く人の気配を感じると奥に移動していってしまうという人見知りが強いカイツブリが存在します。カイツブリにどんな学習能力があるのか興味を持ち、文献を調べてみました。琵琶湖博物館(2017)は、琵琶湖のカイツブリ類について滋賀県民が参加する調査を実施し、その結果を毎年報告しています。報告の中に、カイツブリには「人見知りが強いタイプ」と「わりあい人に慣れたタイプ」の 2 タイプがあると述べています。人の近くで生息するカイツブリは、人の各種の行為が自分に利害を及ぼすものかどうかを学習している可能性を示唆していて、「 釣り人の竿先から10 mほどのところに近づき、そこで潜って採餌をした。釣り針付近に魚がいることを承知して、意図的に近づいているように見えた」という報告があり、カイツブリが人を利用している様子がわかったこと、「人が居ることでトビ、カラスから守られるので人の 近くで子育てをしている」との報告も寄せられたと記しています。琵琶湖全体では500羽ほどの個体数しか確認されていないけれど、漁業者や農家の人 釣り人、水辺に住む人 など普段自然に接する機会が多い方たちの目には留まっていて共存しているのが琵琶湖沿岸のカイツブリと人々の特徴と結んでいます。(引用)滋賀県立琵琶湖博物館.2017.フィールドレポーターだより.2017年度第1号(通巻49 号)カイツブリに会いに行こう調査報告.pp21.(写真)1枚目:2024年12月11日松戸市千駄堀2枚目:2023年3月14日我孫子市高野山3枚目:2023年2月3日我孫子市高野山4枚目:2023年6月13日都内北区
2024.12.16
コメント(0)
-

菅生沼のハクチョウと水鳥観察記
茨城県南西部にある菅生沼にでかけました。面積85ha、水深 1 mに満たない沼で、ヨシ ・マコモ が 生い 茂っていて水鳥に採食 可能な環境が残っている環境です。10月20日にコハクチョウが飛来し、越冬する個体数が増加しています。今日、常総市菅生の水面で休んでいたのは、コハクチョウ152羽、オオハクチョウ6羽、コガモ36羽、オオバン6羽、タシギ12羽でした。このほか、上空をノスリ、トビ、水路沿いに複数のカワセミの姿、沼の浅瀬でセグロセキレイが水浴びをしている姿、葦原を鳴きながら移動するベニマシコの姿、葦原の中で鳴いていた複数のクイナを観察できました。ベニマシコは、写真では、翼帯が記録できませんでしたが、2本の白い翼帯が目立ち、体は褐色で下面に縦斑があったことから成鳥雌と思われました。(菅生沼ではなぜ日中にコハクチョウの姿があるのか)渡辺(2010)が報告しているように、多くの越冬地では朝、ねぐらを飛び立ち日中は水田で過ごし、夕方に内水面に帰還して夜を過ごすのが越冬生態です。ところが、コハクチョウにパンの給餌が行われており採食している様子が見られます。こうした関係で日中に沼に姿があります。今日も2羽のコハクチョウが地下茎を採食している様子が見られましたが、大半は人による給餌をお目当てにしています。ただし、それだけでは満たされないので夕方前に近郊の水田に10羽未満の小群で出かけて落ち籾などを食べています。(菅生沼でシギ・チドリが見られる要因)渡辺(2011)は、菅生沼の鳥類についてマコモ群落との関係に着目し調査をした結果を報告しています。それによると、冬季にマコモが枯れると泥が露出し地表面や浅い地中の小動物を採食しやすくなり、イカルチドリ、タゲリ、タシギといったシギ・チドリ類が飛来していると記しています。(写真)2024年12月15日撮影(引用)渡辺朝一.2010.コハクチョウ.Bird Research News Vol.7 No.3.p4-5.
2024.12.15
コメント(0)
-

吉川美南駅東口と西口調整池の探鳥記
北西の風4メートル前後の風が吹き抜ける朝となりました。10日ぶりに吉川美南駅東口(第一調整池)と西口の調整池(中央公園前調整池)を探索してみました。東口調整池ではマガモ、カルガモ、コガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、オオバンと種類は揃っているものの個体数は少なく、タカ類が飛翔した後なのか近郊の採餌場所に移動したのかは不明です。その後、西口調整池では、マガモとカルガモがそれぞれ群れをつくって羽を休め、10羽未満のコガモの姿が見られたのみでした。(東口調整池と西口調整池のカモの違い)・東口では水底採餌型のホシハジロ、キンクロハジロの姿を観察できますが、西口では今のところ姿を見かけていません。・東口では水面採餌型でろ過採餌型として知られるハシビロガモの姿が見られるのに対して西口では姿を今のところ見かけていません。・東口では一度だけオシドリ成鳥雄を観察しましたが、西口では今のところ見かけていません。採餌行動は見かけなかったので、一時的に休息をとっていた可能性が高いと思われます。キンクロハジロとホシハジロは、沈水植物の越冬芽を餌としますので、東口にはそうした餌生物が存在すると想像できます。また、水生植物および昆虫、動物プランクトンを餌とするハシビロガモが東口でのみ記録され水面で渦巻採食と呼ばれる円を描くようにぐるぐる回り水面採食を行っている姿を見かけています。1年を通じて、記録できる種類の変化、個体数の変化を記録してみないと、採餌場として依存しているのか、休憩場所として使っているだけなのかは結論づけることができませんが、東口と西口で記録できるカモの違いを通じてカモの暮らしが理解できたらと思っています。(写真)マガモ(成鳥雄生殖羽、成鳥雌非生殖羽)、コガモ(成鳥雌非生殖羽)、オオバン、カイツブリは2024年12月3日撮影オシドリは2024年11月10日、ハシビロガモは2024年11月10日撮影
2024.12.14
コメント(0)
-

世界南限のミコアイサ繁殖地について
昨日成田市坂田ケ池で観察したミコアイサは雄が白く雌の頭が茶色い特徴的で、パンダガモと呼び親しまれていると探鳥会で説明を受けたことがある方が多いと思います。鳥友から国内での繁殖はいつ頃観察されたのか、どんな環境が必要なのかについて質問をもらいました。(主要の図鑑類での国内の繁殖、分布についての記載)吉井(1988)が「日本では北海道で少数が繁殖するが大部分が冬鳥として渡来」桐原(2000)が「ユーラシア大陸亜寒帯で繁殖し(中略)日本では北海道で少数が繁殖」、叶内(2011)が「冬鳥で北海道北部で少数が夏鳥」、氏原(2015)が「主に淡水域に冬鳥として飛来するほか北海道で少数が繁殖」、石田(2015)が「北海道では少数が繁殖する」と記しています。いずれもいつ繁殖が確認されたのかは、記載がありませんでした。その後、文献を見ていくと、藤巻(2023)がサロベツ原野の鳥類の調査結果を報告している中に「1961年に稚咲内の砂丘で雌と幼鳥の家族群が観察され繁殖していることが確認された」とあり国内最初の繁殖記録と記されています。また、この報告により、日本産鳥類目録(第4版)まで冬鳥とされていたミコアイサが日本産鳥類目録(第5版)で北海道北部で繁殖とされるようになったと報告されています。長谷部(2019)は、ミコアイサの繁殖に関する知見と調査結果を報告しています。それによると、「1970年代までに北海道開発局や環境庁の調査で、複数つがいが確認されてきました。しかし、1980年代に行われた調査では1つがいしか確認されず、繁殖数の減少が懸念されていました」と述べています。さらに、「2012年に北海道豊富町と幌延町の境界付近で親子が確認された後は、繁殖生態は明らかになっていませんでしたが、2019年に行われた調査で雛8羽連れの親子が発見」と記されています。さらに、繁殖できる環境として、水位が低下していない砂丘林の沼とミコアイサの雛が外敵から身を隠すことができる岸辺のヨシ原が必須で、ミコアイサ親子が砂丘林で針広混交林に囲まれた狭い水域を好む傾向があるがあるのはそうした背景があることを示唆しています。(引用)吉井正.1988.コンサイス鳥名事典.p484.三省堂.桐原政志.2000.日本の鳥550.水辺の鳥.p152.文一総合出版.叶内拓哉.2011.日本の野鳥.p94.山と渓谷社.石田光史.2015.野鳥図鑑.p57.ナツメ社.長谷部 真.2019.サロベツ海岸砂丘林 世界南限のミコアイサ繁殖地.Bird Research Water Bird News.2019年12月.藤巻裕蔵.2023.サロベツ原野の鳥類・1961年利尻研究第42巻.p01-04.利尻町立博物館研究紀要.(写真)成鳥雄:2021年2月7日茨城県神栖市成鳥雌:2013年2月1日茨城県神栖市雄エクリプス:2019年12月21日茨城県菅生沼
2024.12.13
コメント(0)
-

坂田ヶ池の冬鳥観察記
朝から晴れとなったものの北北西の風が5m以上で、鳥見には不適でした。しかし、風が避けられてカモの仲間を観察できるフィールドの中から成田市坂田ヶ池総合公園に出かけることにしました。到着して池にいる水鳥を見ていくと、マガモ、カルガモ、トモエガモ、コガモ、ホシハジロ、ミコアイサ、オオバンが羽を休めていました。今季まだ姿を観察できていなかったミコアイサは、成鳥雄、目先が黒くない雄エクリプス、目先が黒い雌恋を観察できました。トモエガモは頭部が暗色に見えて目の下に黒条痕があり長い肩羽が目立った雌個体でした。頬を膨らませる光景も披露してくれました。このほか、ハシビロガモはエクリプス個体が生殖羽に換羽中の個体、雄生殖羽個体、オオバンは白い顔板の大きい成鳥、小さい若鳥を見つけました。また、帰り際にヒッヒッと鳴き声がしてその方向を注目すると、後頭部が白いジョウビタキ雄の姿を見つけました。(写真)2024年12月12日撮影
2024.12.12
コメント(0)
-

千駄堀池の冬鳥探鳥記
11月上旬に雄若鳥と熾烈な縄張り争いをしていたカワセミ成鳥雌は、11月下旬には縄張りを確保しました。その後の様子を見に松戸市千駄堀池を訪ねました。ねぐら近くの枝でお日様を受けながら羽づくろいをした後、水面を何度も飛翔し餌探し。池のカモ類は、例年姿が見られるオカヨシガモの姿がなく、マガモ、カルガモ、コガモ、キンクロハジロ、カイツブリの親子連れの姿があるだけでした。コガモは生殖羽個体にくわえて、まだエクリプスから生殖羽に換羽中の個体、雌非生殖羽個体といろいろな羽衣が観察できるのもここの特徴です。キンクロハジロは、冠羽は見えない状態で嘴基部の白色部分は小さいので雌幼羽と思われました。カモ以外の水辺の鳥は、ダイサギ、コサギ、アオサギ、山野の鳥はハクセキレイ、セグロセキレイの姿を観察できました。なお、例年と大きく異なるのが、小鳥の姿をほとんど見かけないことです。ツグミ、シメ、アオジの姿といった小鳥は観察できずでした。暖冬の影響で渡来が遅れているのか、それとも繁殖地での繁殖が少ないなどの要因があるのか気をもんでいます。(写真)2024年12月11日撮影
2024.12.11
コメント(0)
-

ふれあい江戸川のベニマシコ、冬鳥観察記
松戸駅西口の川の一里塚があり、ふれあい江戸川と呼ばれる草地と雑木林に囲まれたエリアがあります。毎年ベニマシコ、アオジなどの小鳥たちと出会えるので楽しみです。堤防を降りて川沿いの道を進み、江戸川の水面に目をやるとカンムリカイツブリ成鳥と若鳥(顔から頸に縞模様)の姿を見つけました。その後、高い葦がたくさんあるエリアで待機していると、シジュウカラ、メジロ、ジョウビタキが登場し、葦の中からピッポッと今季初のベニマシコの鳴き声。待機していると1羽は雌、もう1羽は鳴き声だけで性別不明でした。例年でしたら、ツグミ、アオジ、ホオジロの姿も観察できるのですが、今日は見かけず。次回のお楽しみとなりました。(写真)2024年12月10日撮影
2024.12.10
コメント(0)
-

北西の風が吹き抜ける水田地帯と手賀沼探鳥記
北西の風が吹き抜ける日となりました。このため、我孫子市と印西市の境界にある水田地帯からスタートし、我孫子市側の遊歩道を探索しました。スタート地点の水面にオオハクチョウ6羽(成鳥4羽、若鳥2羽)の姿を発見しました。位置関係を考えると、先日出かけた印西市笠神の水田が借地権終了で水を張ることができなくなり、ハクチョウ(オオハクチョウ)の姿が見られなくなりましたが、この影響で印西から飛来したのかもと思われました。今後、注視していきたいと思います。このほか、同じ水面にカンムリカイツブリ、近くの水田にタゲリ11羽の姿も発見。あわせて、複数のチョウケゲンボウが電柱に止まり獲物が動くのを注視している姿やハイイロチュウヒ、トビが飛翔する姿を目撃できました。この後は、我孫子市側の手賀沼遊歩道に移動し、ミコアイサをはじめとするカモたちの姿を探索。しかし、北西の風の影響で大半のカモたちは沼北側の葦原の中、入り江で身を潜めていて期待どおりにはいきませんでした。帰り道、縄張りを確保したモズ雌雄、逆光でしたがジョウビタキ、草地に出入りしていた嘴基部が黄色のスズメ冬羽、頭から後頚が灰色で三列風切外弁の白色部が幅広い亜種オオカワラヒワを複数見かけました。(写真)2024年12月9日撮影
2024.12.09
コメント(0)
-

コクガンの秋期から春期までの動向
先日出かけていた宮城県の鳥友から南三陸湾にコクガン100羽超の姿があったとニュースをもらいました。千葉県内で九十九里沿岸、谷津干潟でその姿を観察したことがあります。どのくらいの個体数が日本に飛来しているのか、どんな環境を好むのかなどについて文献を調べてみました。(東アジアに飛来するコクガンは世界の2%)藤井(2015)が報告しているように、他のガン類と比較して内陸の河川や湖水より内湾や漁港・沿岸などを好む種類です。世界で約50万羽が生息すると推定され、東アジアに渡来するコクガンは世界の生息数の約2%1万羽程と言われてきました。日本では1000羽以下と数の少ないガンと考えられてきました。(コクガンの個体数と分布)藤井(2017)は、コクガンの個体数と分布についての調査結果について報告しています。北海道東部の野付湾に6300羽以上のコクガンが秋期に通過しており、冬期よりも秋期に多く飛来していると述べています。さらに、日本およびアジア太平洋地域のコクガン個体群の秋期、冬期、春期を通とおした季節的な個体数について調査が行われ、結果の報告を報告しています。それによると、秋期は各年度共に北海道東部の国後島、野付湾、風連湖、厚岸湾に集中し、冬期は渡島半島東部,函館湾などの北海道南部と陸奥湾周辺、宮城県南三陸などの本州北部に比較的広く渡来、春期は秋期と同様に、北海道東部の国後島,野付湾を中心に合わせて3,100 羽以上が集中的に渡来、主な越冬地である北海道南部と本州北部にも春期の調査時の3月下旬から4月上旬の時点で200-700羽が残留していたと記してます。(日本に飛来しているコクガンの分布)藤井(2017)は、日本に渡来しているコクガンの分布の季節変化を3年間の全国一斉カウント調査をもとに概略した結果について報告しています。それによると、秋期の初認となる10 月中旬以降から徐々に渡来数が増加し、11 月に入ると北海道東部のアマモの藻場がある各湾内を中心に8,600 羽以上が渡来していた。その個体数は、野付湾と国後島南部には83.2-93.4% が集中していた。その後、12月以降,北海道東部の各湾内の凍結が始まりアマモを採食することができなくなると一部の越冬群を除き徐々に北海道南部や本州北部などの越冬地への南下・移動が本格化していたと述べています。前記文献に目を通した結果、千葉県で観察したコクガンは、北国の湾が凍結しアマモを採食できなくなった個体が南下してきたものと思われます。(引用)藤井 薫.2015.コクガン.Bird Research News Vol.12 No.3.p4-5.藤井 薫.2017.日本におけるコクガンの個体数と分布(2014-2017年).Bird Research Vol. 13, pp. A69-A77.(写真)一枚目、二枚目:成鳥、2012年1月2日旭市下永井海岸で撮影、三枚目から六枚目:成鳥2016年1月2日旭市で撮影七枚目、八枚目:成鳥、2016年3月12日谷津干潟で撮影九枚目、十枚目:若鳥、2020年11月21日旭市で撮影
2024.12.08
コメント(0)
-

師走、水元公園のカモと水辺の鳥観察記
師走に入ってはじめて水元公園にカモと冬鳥の小鳥を探しに出かけました。JR金町駅から三郷団地行バスで桜土手で下車し、公園東端に到着。ごんぱち池でヨシガモの雌雄を観察し、小合溜方面にスタートしました。展望台近く東屋がある近くで450羽をこえるホシハジロ、20羽前後のキンクロハジロ、80羽前後のヒドリガモが羽を休めていました。その群れの中に頭が赤褐色、胸があずき色、虹彩が黄色、体上面に黒味があり、脇に細かい縞模様がある(印象としてはホシハジロ雌に近い感じ)1羽を発見しました。全体の印象ではホシハジロ似ですが、ホシハジロは胸が黒く、虹彩が赤、体上面は白っぽく違いがありました。ホホシハジロとメジロガモの交雑と思われました。なお、嘴先端の黒斑が嘴爪に限られるのか、そうでないのかは観察できませんでした。このほか、水生植物園近くにある池で複数のオカヨシガモ雌雄の姿を見つけました。カモのほかには、カイツブリ、カンムリカイツブリ、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、ユリカモメ、セグロカモメ、カワセミ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、アカハラ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワの姿、鳴き声を観察しました。(写真)2024年12月7日撮影(12/10訂正)頭が赤褐色、胸があずき色、虹彩が黄色、体上面に黒味があり、脇に細かい縞模様がある(印象としてはホシハジロ雌に近い感じ)1羽を発見し、ホシハジロとアカハジロの交雑でホシハジロに近い個体と報告しましたがホシハジロとメジロガモの交雑と訂正させてもらいます。当日同じ水面で観察していた方から、ホシハジロとメジロガモのハイブリッドではないかとご指摘をいただきました。目の白っぽさはどちらも同じ傾向になりますが、頭部が赤みが強くて、アカハジロとの雑種の場合によく出る緑光沢がない気がするとの見解をいただき、訂正します。
2024.12.07
コメント(0)
-

笠神のハクチョウの郷の思い出(借地権終了でハクチョウの郷終焉)
印西市笠神に冬になると水田の中に約1,000羽近くのハクチョウが渡ってくる郷があります。日本国内でも2番目に多いともいわれているスポットと聞いたことがあります。このスポットが借地終了で従来のような水を張った田んぼは終了しました。32年の長きにわたる有志の皆さんの管理、さぞや大変なご苦労があったものと思います。1992年冬に6羽が飛来したのがはじまりで2012年冬に1300羽超のハクチョウたちが羽を休めました。今冬は、周辺地域に分散し過ごしている模様です。1992年以降、観察させてもらった野鳥を振り返ると、コハクチョウ、オオハクチョウの所謂ハクチョウの他に学術的にも貴重な種類の飛来がありました。管理をしてくださった皆さんに感謝の意を表すと同時に写真と簡単なコメントを整理してみました。ご笑覧ください。(冬鳥の思い出)冬季に観察した鳥類を振り返ると、カモ科ではハクガン、コハクチョウ(亜種コハクチョウと亜種アメリカコハクチョウ)、カルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、トモエガモを観察しました。写真は、マガン(2021年11月28日成鳥、同年12月19日成鳥、2023年12月8日若鳥)、ハクガン(2016年12月24日)、コハクチョウ(2021年11月7日)、アメリカコハクチョウ(2013年11月24日)、アメリカコハクチョウ(2016年1月20日)、ハシビロガモ(2021年11月7日)、トモエガモ(2020年11月8日)、ゴイサギ(2012年1月8日)、ソデグロヅル(2012年1月8日)、ノスリ(2015年12月20日)、チョウゲンボウ(2021年11月7日)です。このうち、ソデグロヅルは、世界で3000羽程度の個体数と言われ絶滅危惧種に区分されている希少種です。この飛来地が失われたのは国際的、学術的に考えても損失です。
2024.12.06
コメント(0)
-

公園と谷津田の柿の実をめぐる争奪
オフィス近郊にある公園と谷津田を探索して歩きました。ようやく成熟した渋柿には、メジロ、シジュウカラ、ヒヨドリ、オナガと次から次に飛来し実をついばんでいました。ついばんでいる柿の実は大きいもの、そして見るからに熟して糖度が高そうなものが好まれているようでした。2021年12月に紹介した研究論文(*)で報告されていたメジロが色よりも栄養(糖度)に反応している件は、シジュウカラ、ヒヨドリ、オナガが同じ柿の実に飛来する頻度が高いので同様ではと思いました。なお、人気の実をついばんでいる種類がいる場合、その近くの柿の実をやむなくついばんでいました。柿を食べたヒヨドリがついばんでいたセンダン(センダン科)は、叶内(2006)によると苦味が強いと解説が記されていました。柿の甘さとは対極にある苦味のあるものを口にするのびっくりしました。(参照文献)Stanley, M.C., Smallwood, E. & Lill, A. (2002) The response of captive silvereyes (Zosterops lateralis) to the colour and size of fruit. Aust. J. Zool. 50:205-213.(引用)叶内拓哉.2006.野鳥と木の実ハンドブック.p59.文一総合出版.(写真)2024年12月5日撮影
2024.12.05
コメント(0)
-

ぽかぽか陽気、師走の手賀沼探鳥記
柏市から印西市までの手賀沼とその隣接する水田地帯を探索しました。スタートした柏市大井新田先の沼の水面では、あちこちにカンムリカイツブリや水面に浮かぶユリカモメ、遊歩道脇の電柱に獲物を狙うチョウゲンボウの姿を見つけました。その後は、手賀沼大橋から東側のエリアに移動し、水面を凝視するとマガモ、カルガモ、コガモ、ホシハジロ、ハジロカイツブリ、杭に止まっているミサゴの姿を見つけました。さらに、沼の東端では、マガモ、カルガモ、コガモ、トモエガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、カンムリカイツブリ冬羽と生殖羽が残る個体、セグロカモメ、ユリカモメが羽を休めていました。その後、水田地帯に移動し、田んぼを耕起しているところを注目していると、タゲリ13羽を発見しました。土がおこされたところで餌を物色。地面を足でたたくような動作を見せたり、いきなり方向を変えたり千鳥足を何度も披露。その後、群れが一斉に飛び立ったので振り返ると小型のタカが登場したのが原因でした。耕起している田んぼに戻るだろうとその場に待機していると群れが21羽に増え帰還。タゲリの帰還するまでの間、水路をみていたらコハクチョウ3羽が寝込んでいました。首をすぼめていたので種類の同定は無理だと諦めていましたら、短時間移動するのに顔を見せてくれコハクチョウと判明。(写真)2024年12月4日撮影
2024.12.04
コメント(0)
-

吉川美南駅西口と東口調整池の探鳥記(冬の生殖羽ハクセキレイを観察)
吉川美南駅西口と東口の調整池を探索して歩きました。西口調整池では、到着直後からジョウビタキ雌が登場し水面のカモを観察している私の方に何度も接近し自分の縄張りを主張しているようでした。水位が高いので浅瀬がなく大半のカモたちは水際の縁で羽を休めていました。その後、東口の第一調整池にむかう途中、水路沿いをオオタカが飛翔する姿を発見。餌探しで動き回った影響なのか整池に羽を休めるカモの姿はコガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロをあわせても30羽強でした。おそらく近郊の河川などに避難したものと思われました。帰路につき駅に向かっている途中、複数のハクセキレイ、セグロセキレイか鳴きながら移動している姿を見つけました。そのうち、ハクセキレイ7羽のうち1羽は頭上が黒く、黒い過眼線、胸は黒みがかった灰色で全体的に生殖羽(夏羽)が残った個体でした。師走にハクセキレイの生殖羽、はじめての遭遇でした。もっとも、コサギ、シロチドリが12月に生殖羽(夏羽)を見かけたことがありますから、その逆もあるものだなあと思いました。(写真)2024年12月3日撮影
2024.12.03
コメント(0)
-

東北地方でのオジロワシについて
先週、蕪栗沼でオジロワシが岸辺の木の枝に止まり獲物を狙う姿があり、その後マガンやヒシクイが沼に帰還する姿をめがけて飛翔する姿を観察できました。捕獲したかどうかは不明でしたが、その迫力に圧倒されました。蕪栗沼、伊豆沼を訪ねるたび、オジロワシの姿を目撃しますが、いつ頃から飛来するようになったのかと、東北のオジロワシについて調べてみました。環境省(2013)は、資料調査によって海ワシ(オジロワシ、オオワシ)の出現記録を整理したものを報告しています。そのうち、オジロワシについては、次のように記しています。注目すべきは、1980年代後半、銀鮭養殖が盛んになった三陸沿岸で多くみられるようになり、沿岸部よりも、内陸部の大きな河川や湖沼の近辺を越冬地としている様子が示されたと報告されている点です。(年代別の出現記録の変化)(1)1969年以前1969年以前の出現記録は青森、岩手、宮城の1~2 箇所と非常に少ないと述べています。(2)1970年代1970年代は、主に宮城に出現事例が多く、なかでも三陸沿岸や内陸の伊豆沼周辺に集中して見られたと述べています。(3)1980年代1980年代では宮城県は1970年代と同様であるが、特に三陸沿岸の志津川湾(50 件)や女川湾(23 件)に多く見られた(1980 年代後半から志津川湾で銀サケ養殖が盛んになる)と述べています。(4)1990年代宮城での出現件数は減少し、岩手の三陸沿岸(最大24 件)、青森の十三湖(23 件)、小川原湖(13 件)や廻堰ため池(35 件)、秋田の八郎潟(13 件)などで増加した。また内陸部では岩手の北上川流域(最大19 件)、秋田の雄物川流域(最大32 件)で出現記録が増加したと述べています。(5)2000年代2000年代は、大きな傾向は1990 年代と同様であるが、秋田の雄物川、岩手の北上川流域など内陸部での出現範囲が広がったと述べています。(6)2010年代観察記録の累積年数が5 年間であり、記録数は他の年代に比べて少なくなっていると述べています。(オジロワシの狩りと捕食事例)オジロワシの狩りと捕食事例を整理し報告しています。捕食例としては、ハクチョウ、コウノトリを襲い、捕食した例、カモ、鮭を食べた例、を紹介し、鮭を食べた事例が複数あると述べています。狩りでは、遡上する鮭を狙った事例、牧場から出た廃牛を餌とした例、負傷したマガン、ヒシクイを襲った事例、漂流物であるアザラシやオットセイの死体を餌とした事例、シカの残渣を餌とした事例、オオタカやハヤブサが捕獲した鳥を横取りした事例を報告しています。(引用)環境省.2013.3)東北地方における海ワシ類の分布および生息状況.平成25年度風力発電施設に係る渡り鳥・海ワシ類の情報整備委託業務報告書.調査結果 2-3).(写真)一枚目、二枚目は2024年11月28日撮影三枚目:2016年12月23日撮影、四枚目:2018年12月15日撮影いずれの個体も上面は褐色と淡色のまだら模様が目立つので若鳥と思われました。
2024.12.02
コメント(0)
-

カリガネとマガンを比較すると
27日から28日に蕪栗沼、伊豆沼とその周辺地域を探索してきました。28日にカリガネを観察できましたが、マガンとの識別について質問をもらいました。写真一枚目から四枚目が2024年11月28日に観察したカリガネです。また、五枚目から八枚目の写真はマガンです。(1)嘴基部から額と上嘴と額の角度カリガネは、嘴基部から額にかけて白色部分が頭頂に達します。また、上嘴が付け根で明瞭な角度があり、頭部全体が台形に見えます。これに対して、マガンは額全体が白く、上嘴と額の角度は小さく、頭部全体は台形には見えません。(2)鳴き声カリガネはキューキューと聞こえる鳴き声、マガンはキャハハンと甲高い声で鳴きます。(3)採食についてカリガネはアルファルフアなどの牧草を好んで食べます。マガンは立ち止まって時間がある採食ですが、カリガネは草の先端部をむしり食べます。池内(2023)が「カリガネはマガンと似ていると言われますが、多様な環境で容易に採食が可能なマガンは“Generalist”とされる一方で、カリガネは“Habitat pecialist”と称され、本来の自然環境であれば「スズメノカタビラ」を好み、人為的な耕地では、イタリアンライグラス、オーチャードグラス、アルファルファなどを採食しています。カリガネが水田を利用する場合でも、落ちモミよりは切り株から伸びた葉や、他のイネ科の雑草を食べています」と述べています。(4)カリガネの成鳥と幼鳥雁の里親友の会(2020)が見分け方を報告しています。それによると、カリガネ成鳥では腹部の黒い斑がありますが、幼鳥にはないこと、幼鳥では額の白い部分が欠けていること、胸から腹の羽の先端部が青海波のパターンとなっていると解説しています。(引用)雁の里親友の会.2020.カリガネ識別資料.池内俊雄.2023.宮城県で越冬するカリガネの個体数変動.Bird Research Water Bird News.2023年1月号.p2-3(写真)一枚目から四枚目は2024年11月28日に観察したカリガネです。五枚目から八枚目はマガンです。五枚目:2014年12月14日登米市で撮影六枚目:2016年12月23日栗原市で撮影七枚目:2018年12月15日栗原市で撮影八枚目:2024年11月27日栗原市で撮影
2024.12.01
コメント(0)
全32件 (32件中 1-32件目)
1