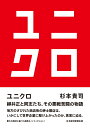2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2002年05月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
みこころロープ -進路を決める時-
教会生活を続けていると、祈って、神さまのみこころを求めることを勧められます。(進路、結婚など) 祈りつつ、神さまの声を聞き、導きを求めていくということです。 かつて、自分の中に、「みこころ」について、無意識のうちに、あるイメージがありました。そのイメージとは、何かを選択する場合、すでに神さまの目から見た「みこころ」が定められていて、その正解を選択しなければならないというものでした。いわば、選択肢の数だけ、「みこころ」ロープが、天井から目の前にぶら下がっていて、定められたロープを引けばOK。そうでない「はずれ」を引くことは、イコール失敗というか、祝福を受け損ねることを意味していました。だから、「みこころは何ですか?」「みこころを示してください。」「どの道を進めばよいのですか?」という祈りは、常に、「はずれ」を選んだらどうしようという恐れと表裏一体でした。超自然的な夢とか幻とか見るわけでなし、おそるおそる進路を自分で決定するんですが、どこかで自信がないというか、不安なんですよね。怖いんです。みこころじゃなかったらどうしよう?!って。そして、その後、へんなことがあると、やっぱりみこころじゃなかったのかもしれない、なんて、よけい心配になっちゃったり!!!エンドレス。今思えば、何と窮屈な、それこそ、神さまの求めておられない道を歩んで来たのかと思うと我ながら、びっくりてしまいます。(ハッズカシ~) しかし、ある時、「選んだことがみこころ」という話を聞きました。「定められた正しいみこころ」を選ばなければならないと思いこんでいた自分にとって、 最初は、禅問答のように、要領を得ない言葉、はぐらかしのように思われ、かえって戸惑い、混乱させられましたが、しかし、心にとどめているうちに、だんだんとその意味を教えられ、ついには、自分が間違った固定観念で「みこころ」を求めていた、そのこと自体に気づかされることとなったのです。 この間、数年。 進学・就職はおろか、結婚・転職を経ながらの過程でありました。 聖書をちゃんと読めば、ちゃんと書いてあったんですよね。聖書自身が教えてくれているんです。 「神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、 事を行なわせてくださるのです。」 ピリピ2:13祈って選び取る時、すでに、神さまがうちに働いて志を立てて下さり、事を行わせてくださるんです。だから、どんな選択でも、祈って決断したことは、背後に、すでに神さまの促しと働きがあってのことだから、大胆に進めばよかったんですね。 「何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、感謝をもってささげる祈りと願いによって、 あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに まさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。」 ピリピ4:6~7ぽんのHPのトップページにも引用している、大好きなみことばです。みこころロープなんてない!って解放されつつある頃、心に響いてきました。以来、大好きなみことばです。人のすべての考えにまさる「神の平安」が、「心」と「思い」を守ってくれる! なんで、こんなすばらしいみことばに、長い間、目が閉ざされていたんでしょうか。(ウ~ン ザンネンザンネン! デモ キヅケテ カンシャカンシャ!!!) 「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神が すべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。」 ローマ8:28 神さまの愛に触れ、神さまに立ち返る時、すべてのことを働かせて益とされるとあります。「すべて」ということは、きっと過去の事も含むのだと思います。私にとっては、ちょっと恥ずかしいこの経験があってこそ、今の自分があること。究極の意味は、神さまだけがご存じですが、私にとっては、このことが、最善の方法で、益にされているのです。(はず?)また、聖書の中の物語を見ていく時、いかに多くの偉大な信仰者たちが、つまずきながら、失敗しながら、時に神さまから離れ、裏切りつつ、しかし、神さまは決して見捨てず、あきらめず、その結果、神さまに立ち返り、成長していくのを見ます。時に、祈らずして出した結論があったかもしれません。時に、「違うよ、危ないよ」という神さまの声が聞こえていても、あえて、逆らうことがあったかもしれません。それでも、主に捕らえられた人々は、いつの日か、主の愛に涙し、立ち返り、悔い改める時、そのことさえ、肥やし、ステップとして、豊かに用いられる、それが、「すべてのことを働かせて益としてくださる」ことと思うんです。 昔は、聖書読んでても、その場面場面での学ぶべきよい行い、避けるべき失敗なんて、短絡的に善し悪しを判断していましたが、そんなことに気づかされていくうちに、聖書の読み方が、勧善懲悪、道徳的教え、単なる信仰的美談ではなく、「失敗しても大丈夫」になりました。仮に失敗したとしても、裏切ってしまったとしても(できればそうしたくないですが、そうしちゃった場合でも)そんな自分のために、イエスさまが十字架で身替わりになって命を与えてくださいました。それほど、私たちを愛して下さっているんです。仮に、私たちが、どこまで落ちていこうと、イエスさまは、そのために祈り、そのさらに下に先回りし、幾重にも幾重にも、ネットをはって、何回でも何回でも、復帰(悔い改め)のチャンスを与えようとしておられるように思えてきました。(帰れや~、我が家へ~)だから、間違いや失敗、罪で、自分を安易に裁かず、かえって、感謝して悔い改めて続けていきたいと、強く願わされます。そのことさえ、神さまは益と変えることのできる方なのですから。
2002年05月28日
コメント(6)
-
北の国から
の亡命事件で、この問題が、国際社会でも、ようやくクローズアップされ始めました。背景には、いろんな問題が絡んでいるので、まとめてみたいと思います。(個人的こだわりというか、何か気になって気になって仕方ない問題なんです。)・南北の分断 = そもそもの悲劇・北の体制 = 実質的に独裁政権 恐怖政治 5人組・隣組のような監視・密告制度 ソ連のKGB、日本の天皇制(特に戦時中)、中国の文化大革命、これらの施政者に とっていいとこ取り(=人民にとって最悪の状況)が50年以上続いているという人も・北の経済 = 農工含め生産・流通が麻痺 経済停滞 深刻な食糧不足 モラルの著しい低下・北の宗教 = 共産主義 = 実質的に宗教否定・飢餓難民を認めない中国 = あくまで不法入国者として検挙、強制送還 中国人で難民をかくまったことがばれれば、年収半分相当の罰金 難民が、中国国内潜伏中、盗みや強盗化する場合も 流出民を取り締まる北の工作員と、中国の官憲が協力、拘束・送還・南への亡命成功しても、適応できず、生活できないリスク 北では、大して働かなくとも、何らかの職が与えられ、近年の食糧不足がなければ、食べるには 困らなかった。韓国では(当然だが)、自分で職を探し、職に就き、競争社会を生きて行かねば ならない。しかも、北ではコネが能力以上に有効な社会であるため、適応できない亡命者も。 中には、公に韓国批判したり、自殺してしまう場合もあるという。 ・亡命者問題ではないが、北による日本人の拉致疑惑も。 そうそう、横田めぐみさんのご両親は、悲しみのうちに、宣教師を通じ、信仰を持たれた。 この問題に触れ始めると、どのように関わればよいか、何を望めばよいか、祈ればよいか、分からなくなってくる。 飢えがなくなること? 迫害がやむこと? 福音が広がること? 体制が崩壊すること?中国が難民を受け入れること? 南北が和解すること?‥‥ 祈ろう、ただ祈ろう。そう、すべては主の御手のうちにあること。隣人として、関心を持ちつつ、心を痛めつつも、しかし、期待しつつ、委ねつつ、祈ろう。すべては、主の許しがあって起きていることなのだから。 北の実態と宣教http://www.omsholiness.org/news/northkorea1.htmlhttp://homepage2.nifty.com/matiz/revival.html 韓国:キリスト教団体が亡命支援http://csd-news.gospeljapan.com/d_base/news/news2002/0205260101.html
2002年05月24日
コメント(2)
-
570km 5500km そして今日の私は900km
さて、ここ半月ほどの懸案であり、スタックしていたある事件が、昨夕から今朝にかけて、大きな展開を見せた。亡命事件である。かつて奉天と呼ばれた沈陽。その舞台は、清王朝発祥の地でもある。そして、この町から、今朝未明に、5人がたどりついたソウルまで、実は、ダイレクトフライトもあり、公称570km、所要1時間45分である。かつては鉄路でも結ばれ、750km。この間に国境一つと、休戦ライン一つ。昨日から今朝までに、5人が実際に移動した距離、中国-マニラ-ソウル = 5500km。東京からだとシンガポールまで行ける距離。まず、難民が発生する異常事態を放置している国があり、難民を公には認めず、これまで不法入国者として強制送還してきた(今もしている?)国があり、ぽわわ~ンとしている国がある。この政治的に複雑な理由が、この10倍の距離、15日という日数となって現れる。複雑なり、朝・中・日・韓! かつて、半島北部は、古くからキリスト教宣教が始まり、また、よく受け入れられた地域であった。平壌は東洋のエルサレムと称されるほどに、キリスト教の拠点だった。戦時中、日本の教会はクリスチャンに対しても神社を拝むよう強制されたが、もっとも強く反対し続けたのが平壌の信徒たちであった。かの地に、もう一度、福音が宣べ伝えられんことを、切に祈りつつ。また、中国は、政府の許可した教会しか活動を認められていない。昨日の新聞だろうか、この亡命事件の数日後に、亡命者を支援している韓国人宣教師が拘束されたとの記事が載っていた。中国の地で、正しく福音が広められますように。また、困難の中、亡命者を支援している団体が守られ、主のみ技だけがなされるよう、祈りつつ。 ちなみに、今日は東京に日帰り出張。朝、電車とバスを乗り継ぎ、伊丹から羽田へ。 公称マイル 278マイル=約450km神谷町の本部で、人事考課を受けつつ、夕方、飛行機まで少し時間があったので、銀座とお茶の水をぶらり、というか、キリスト教書店をはしご。銀座はK文館。3階のキリスト教書籍売場の入口には、新刊紹介、ベストセラー展示平積みの隣りのコーナーに、ヘンリー・ナーウェンコーナーが設置されていて、びっくり。 ゲットしたもの 「今日のパン、明日の糧」 ヘンリ・J・M・ナウエン 聖公会出版 「数に入らぬものであっても -女性として選ばれた喜びと祝福-」 下條末紀子 プレイズ出版 「礼拝と賛美」 小牧者出版 CD「テゼの祈り ジュビラーテ 歓喜」 女子パウロ会のどかな丸の内線でお茶の水へ。OCCビルの5階で、ちょうど今日から謝恩セールをやっていて、(いのちのことば社のバーゲン?)、中には半額のものも。買ったうちの半分は、値段につられて。 ゲットしたもの 「クリスチャン生活百科」 「祈りの時を変える黙想」 オズワルト・チェンバーズ 「御翼の陰に隠されて」 エミー・カーマイケル 「魅力ある人間関係」 田中信生 「唯一神は愛なり 日英韓 聖書翻訳の一考察」 上野亘 CD-ROM 「デイリー・グレイス -朝ごとに-夕ごとに-今日の知恵 明日の知恵-」 教会学校生徒用に、「キミはオンリーワン」8冊帰りも、羽田から伊丹に戻る。 公称マイル 278マイル=約450km今日の合計フライト距離 公称278マイル X 2 = 約900kmということは、今日一日で、沈陽-ソウル間以上の距離を移動したことになる。 帰宅すると、妻は、またもや「渡る世間は鬼ばかり」を見ていた。
2002年05月23日
コメント(0)
-
如安さんからの手紙 -ぽん5月7日づけ「さようなら片岡先生 また天国で」に対して-
5月7日づけ日記「さようなら片岡先生 また天国で」に対して、楽天仲間の如安さんからメールをいただきました。含蓄の深い内容で、私1人のものにしておくには、もったいなく思いました。以下、如安さんの許可を得た上で、掲載させていただきます。迷いましたが、如安さんのメールに、私のコメントも合わせてみました。 「>」「●」は如安さんのオリジナルです。 > 如安さんが引用して下さった、私(ぽん)の原文です。 ● 如安さんのコメントです。 ぽん 私のコメントです。唯一メールに挿入したものです。===================================如安です書き込みが長くなりそうだったのでメールにしました。片岡伸光さまのご冥福をお祈りいたします。まだ見ぬ人を感動を持って聞くことは最近少なくなりましたが、片岡さんの生きざまを感動を持って拝見しました。もう、こんな人はいなくなりましたね。>KGK(キリスト者学生会)の総主事として長年奉仕され、●KGKの活動は今後どうなるのですか?後継者はいるのですか?意志が継がれると良いですね。 ぽん 片岡先生は、3年前にKGKの働きを退かれ、シンガポールの日本人教会の牧師として赴任さ れました。なので、KGKの責を直接負われてはいませんでした。 KGK50数年の歴史のうち、主事、総主事として28年間、KGKに関わられた片岡先生の 遺志は、十分引き継がれています。 ↓KGKのHPはこちらから。 http://www.246.ne.jp/~kgkjapan/ >病院の話では、ふつうの人では、意識を失ってもおかしくないくらい血圧が上がっていたにも関わらず、 全エネルギーを使って、応対して下さった。●こう言う人が宗教人にはいるんですよね。僕の恩師のP.アヌイ神父もそうでした。ガンが大腸に転移 しても僕の前ではイスに背筋を伸ばして坐っていました。召される2日前のことです。アヌイ神父は日 本にグレゴリオ聖歌を広めた人で、日本の音楽者のほとんどが師事をした方です。僕は最晩年の弟子で 僕が最後の弟子になるでしょう。 ぽん P.アヌイ神父、きっと素晴らしい方だったんでしょうね。如安さんが、偉大な功労者のお弟 子さんであると知ると、ちょっと緊張しちゃいます。(汗) 天国でぜひ、お話ししたいです。 グレゴリア聖歌、今日(5月21日)の如安さんの日記でも触れられていますね。 センスも音楽的専門知識も、ラテン語知識もなく、西洋と東洋という違う文化の中にいる自分 には、真の意味に到達するのは無理でしょう。それこそ、生涯学習の中ではじめて、その深み を味わえるのでしょうが、日記をお読みしつつ、じっくり聞いてみたいと思わされました。 数百年前、あまたの作曲家たちをして、教会の中で神と格闘し、作品を生みだす原動力となっ た音楽、2000年間育まれた音楽、その片鱗に少しでも触れることができればと思いました。 ↓ 検索かけたら、カトリック川越教会のHPに到達しました。グレゴリア聖歌聞けます。 ファイル大きい?注意? http://www1.nyan.ne.jp/~kawagoe/10guregorioseika.html>「あんな人生の終わり方、あるんですね。まわりの人、みんな『よかった、よかった』言いはるんですよ。 ほんま感動しましたわ。」人生の最後の時まで、キリストを述べ伝えた先生だった。●僕は音楽を通しての関係から、カトリックの信者の臨終に立ち会うことが多いです。とくに昔気質の信 者の中には信仰を貫いた臨終風景を時おり遭遇します。そんな時、信仰の強さを感じます。 ぽん 天の故郷。帰るべきところ。再会の確信、希望。死は終わりではない。キリスト者でよかった と思う1つです。明治のキリスト者の姿勢には共通するものがあるようですね。よく筋金入り と形容されますね。そんな信仰を与えられたいものです。>先生は50年後の日本の教会を意識されていたという。また、サラリーマンへの福音伝道において、ご 自身の自らのノウハウ、知識が、全く無力で役に立たないことを実感され、試行錯誤されていたという。●「50年後の日本の教会」についてのお考えはとても興味を持ちました。それらしい話がありましたら 是非聞かせてください。もしかして、プロテスタントとカトリックが統一的行動に出るのではないでし ょうか?教義の合意がないと不可能でしょうが、今のカトリックでは人は、魂は救われないと思ってい ます。片岡牧師のような方は、カトリックでは稀有かもしれません。そういう人を、霊的指導者を人は 求めているんですよね。 しかし、53才はあまりにも短すぎる。でも牧師さんご自身にとっては長い一生だったのかもしれませ ん。引き際をしっていらっしゃったのでしょう。 神様から“ご苦労さま”と言われたのではないでしょうか。 片岡伸光牧師先生のご冥福とご家族へのご加護を、3日間の「ロザリオの祈り」を唱えてお祈りいたします。ヨハネ・パウロ高橋如安=================================== ぽん 50年後が、はたしてあるか。もしかしたら、再臨が訪れているかもしれません。 マタイ24章にあるように、人々の心はますます冷え、戦争、飢饉は拡大しています。 終わりには、「惑わし」が増えるとありますから、教義的、組織的には、かえって真なるもの こそ、かき回され、分裂、混乱させられるのかもしれません。ただ、たとえば、国の枠組みで は不可能であっても、NGOや個人、民間レベルで連携できる課題があるように、教会の枠組 みは、そのままで、もしくはさらに細分化(分裂)しつつ、一致できる部分、共通認識の部分 で組織横断的な交わり、連携は可能だと思いますし、今後、増えていくのではないでしょうか。 これまで、別の教派で、交わりがなく、相手を知らなかったが、話してみると、一致できる部 分、同じように考える部分をお互い見つけ、親しさを感じるような形で。インターネットとい うツールを用い、このように如安さんとも、すてきなお交わりをさせていただけることも、そ の一つでしょうか。 キーワードのひとつは「霊性」。メールでも差し上げましたが、カトリック司祭ヘンリー・ ナーウェンの本は、ここ数年、プロテスタント教会でもたいへんよく読まれ、大きな影響を与 えています。聖書を通し、祈りを通し、主イエスと個人的に、人格的に、語り、交わること。 信仰の根本に、違いはありません。 主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。 エペソ4:5 「癒し」なることばが流行する混沌の時代、多くの人々が、傷つき、疲れています。 みことば、救いが必要だと痛感します。主の救いと愛と恩恵が、宣べ伝えられますように。 そういえば、如安さん、片岡先生と同じ年代でいらっしゃるんですね。(奥様の誕生日日記で 計算。)一日一生、主からいただいた命の日の限り、一日一日、全力で生き、いただいた使命 を果たしたく思います。 如安さん、本当にありがとうございました。遅くなってしまい、すみません。如安さんのメールを、かえって読みにくくしてしまったかもしれません。(すみません。)これからも、楽天の仲間たちと、いろいろなお交わりができれば、この上ない喜びです。 皆様の上に、神さまの、豊かな豊かな豊かな恵みがありますよう、祈りつつ。
2002年05月22日
コメント(4)
-
献金 恵み 乞食
礼拝のプログラムの最後の方に、献金の時間がある。オルガンやピアノの奏楽の中、かごがまわされ、感謝の表れとして、いくばくかを献げ、最後に誰かが、感謝のお祈りをする。自分もそのお祈りの奉仕をしていて、今日は、1か月に1回ほどまわってくる自分の番だった。罪は神さまのもっとも忌み嫌う、汚れたもの。しかし、そんな汚れたわたしたちを、神さまはなおも愛し、近づいてくださるというメッセージを聞きながら、どうしても「乞食」のイメージが頭にこびりついて、離れなくなってしまった。教会ではよく、主イエスの救いを、神の「恵み」と表現するが、何年か前に、ある人が「恵み」のことを「施し」と呼んだ。文脈から考えて、確かに「恵み」に相当する部分を「施し」と表現していた。違和感を感じたが、自分としては、聞き慣れない用法だったこともあるが、なんとなく「乞食くさい」=何となく教会にふさわしくないと、思ったことも理由だったように思う。そんなことも忘れていたある時、この「施し」のことを、ふと思い出し、1つの明白な結論に導かれた。神の恵みがなければ、自分が滅びるにすぎない存在だということ。自分が、与えるものなど何もない「施し」「恵み」が必要な乞食同然の者だということを。救いも能力も、何もかも、ただ、神さまから与えられていることを。教会で「恵み」というと、何となく、きれいな、やさしげなイメージがあるけれど、自分こそ乞食のように、汚く低い者で「おめぐみを」と、ただ受け取るだけの(受け取り続けなければならない)存在であることを。礼拝メッセージで、その時の記憶が引き出され、献金感謝のお祈りをしている間、喉まで「乞食」という表現が出かかった。ただ、公の場なので、必死にこらえた。(ほんと、たいへんだった。頭にこびりついてたのだから。)「あなたから遠く離れた者で、あなたに敵対していた者でした。」「何ももたない貧しい者です。」と、ことばを選びつつ、何とかとりつくろったが、おかげで、頭は真っ白になり、しどろもどろの祈りになってしまったが。(冷汗)そういえば、日記りんくしてもらっているneotaroさんの日記に、そんなこと書いてあったっけ。http://plaza.rakuten.co.jp/neotarohome/diaryold/20020501/neotaroさんも、「施し」を使っていらっしゃった。改めて読ませていただき、完全に「恵み」「施し」によってのみ生かされていることを、主に教えていただき、仕える者、へりくだる者とさせていただきたいと、強く強く思わされた。 神さま、neotaroさん、ありがとう。
2002年05月19日
コメント(4)
-
なんと本間家 引っ越しか?!
会社から家に帰ると、妻がテレビドラマ「渡る世間は鬼ばかり」を見ていた。すると、栄作(植草克秀)と長子(藤田朋子)が会話をしているシーンで、どうやら、本間一家は、栄作の地元大阪に引っ越すことになったようである。手を洗いうがいをしてもどると、娘の日向子(大谷玲風)が、「大阪はいや。東京の学校がいい。」といやがっている。http://www.tbs.co.jp/oni/story_7.htmlhttp://www.tbs.co.jp/oni/corre_6.html我が家も、3年前に大阪に引っ越してきた。当時、子供は3歳と1歳半、妻は現長男を妊娠中だった。しかも転職での引っ越し。思えば、思い切った決断をしたものだと、つくづく思う。でも子供が物心ついてたら、どうだったかなぁ。(その直前まで、信仰のスランプ状態にもあったっけ。)本間家の引っ越し模様を見ながら、昔を少し思い出した。この3年間だけでも、いろんな浮き沈みがあった。その前の浮き沈みがなければ、この3年間もなかったし、大阪に住んでいることもなかっただろう。しみじみ。沈みつ浮き上がり、行きつ戻りつ。でも、振り返ると、ちゃんと1本の道筋になっていて、少しずつ少しずつ上っている、そんな足跡を見た気がした。すべてが、主の御手にあること、益とされていることを思い、ただ感謝。ぽんっ ♪ちゃらら らららら ら~ら~ ちゃ~ら~らら~おなじみの音楽が流れ、番組が終わる、と、最後のタイトルバック、なんか、この楽天ページの壁紙の配色とそっくり(かな?) 楽天広場の初期設定の壁紙だが、なんだかパクったみたい。 (一部の方へ なんちゃってタイトル お許しを)
2002年05月16日
コメント(0)
-
脱習慣 脱プログラム
両親がクリスチャンだったため、生まれる前から教会に行っており、小学校に入ってからは、教会の日曜学校に出席するようになった。大人の通常の礼拝の時間の1時間ほど前に始まるため、時に(たまに)1人でバスや電車に乗り、先に、10キロ弱離れた教会に行ったことも記憶している。(親もよく行かせたものだ 笑)教会学校に出席すると、聖書のみことば〔暗唱聖句)入りの豆カードがもらえ、当時の楽しみの1つだった。そして、1年分の豆カードを張ることができる専用のアルバムがあった。確か、1ページに2枚か3枚の豆カードをのり付けできたと思う。さて、その豆カードアルバムの裏表紙には、確か「朝の祈り」「夜の祈り」「食事の祈り」が印刷されていた。そして、それが、とても大切だという父とのやりとりがあり(それが覚えるように勧められたのか、いつどのように覚えたか、その辺の記憶は残念ながら飛んでいるが)、いつしか、その祈りを覚え、毎日、祈るようになっていた。 「かみさま、あたらしい朝をあたえてくださり、ありがとうございます。 今日もおまもりください‥‥。」 「かみさま、今日も1日、おまもりくださり、ありがとうございました。 たくさんの罪をおかしてしまいましたが、おゆるしください‥‥。」 「かみさま、おいしい食べ物をあたえてくださり、ありがとうございます。 じょうぶな体にしてください。‥‥。」これらは、一字一句間違いなく覚えているわけではないが、起きる時、寝る時、食べる時に、その文脈が、今でも、無意識のうちにも出てくるほど、強烈な印象として残っている。そして、このような信仰の基礎が、小さい時に与えられたことを感謝している。ここ数年、こうした「習慣」が、一長一短であることを学ばせられている。意味の分からないままでも、「習慣」を続けていくうちに、いつかその本当の意味と深さに出会えることは、すばらしいことと思う。この時間差は、時に小さな短所ともなりうるが、自分が、何気なく続けてきたこと、教えられてただやってきたことが、実は大きな意味をもっていることに気づいた時の感動は、何とも言えない。(たまに、もっと早く気づいていればと思ったり。) 一方で、危険性。・いわゆる「習慣」あるいは「マンネリ」化=考えることなしに機械的に、無条件反射的に ただ行うだけになる危険性・形式化=まったく心が伴わない・目的化=しさえすればいいと考える危険性・条件化=しない(できない、続かない)と失格と考えてしまう危険性暗記した祈りも、そのままであれば、いつまで経っても暗記に過ぎない。グループや家族での食前の祈りが形だけ、また「こなし」がちになっていないか。また、デボーション(毎日、聖書を読んで祈ること)などが続かないことで、挫折感、劣等感を感じないか。また、していない(できない)他者を裁く思いがないか。こんなことを考えながら、ちょっとひねくれ者の自分は、いろいろ考えた。礼拝のこと。聖書通読のこと。祈りのこと。賛美のこと。聖餐のこと。暗唱聖句のこと。いわゆる儀式的なこと、プログラム、教会文化、教会で教育的指導されることの意味を、もう一度、考え直してみることを。一度、概念を壊してみて、自分なりに咀嚼(そしゃく)し、もう一度建て直すことを。といっても、むやみやたらに否定し破壊することが目的ではない。ただ、いったんゼロに近いところから考え始め、なぜそれが始まり、なされ、続いているかを、考えたいのだ。そのもともとの意味や、もともとのはじまり、意図・目的などをじっくり考え、本当の意味で自分のものとしたいのだ。結果的に、スタイルは変わらないかもしれない。しかし、その背後の深い意味、時には信仰の先人たちが到達したところの道しるべ、遺産に出会えるかもしれない。あるいは、もともとの意味を知っていく時に、もし、現行のスタイルよりも、自分にとってよりふさわしい適切な方法があるのなら、あえて固執しこだわり続ける理由はなくなる。(もちろん集団で行っていることは、吟味と配慮は必要です。変えるとすれば、個人の分野と、心の持ち方、向け方で。)理屈・頭の信仰理解からの脱出をめざしつつ、理屈っぽくなってしまう矛盾を抱えながらも、これが、ひねくれ者の「脱習慣」「脱プログラム」「脱儀式」「脱既成概念」である。主よ、いのちの息を吹きこんでください。
2002年05月15日
コメント(1)
-
教会学校50周年
出席している堺大浜キリスト教会で、教会学校が始まって50年。午前は記念礼拝、午後は記念会が開かれた。礼拝では、教会学校創設時、当時18歳で教会学校教師を担当していた、現 活けるキリスト一麦西宮教会の下條末紀子先生のご奉仕。子供向けのメッセージは、マタイ9章から。 イエスがそこを出て、道を通って行かれると、ふたりの盲人が大声で、「ダビデの子よ。 私たちをあわれんでください。」と叫びながらついて来た。(27節)この人たちは目が見えませんでした。目が見えないということは、このきれいな花も、見えません。美しい空や海の色も分かりません。そんな人々は、道ばたで乞食のような生活をしていました。ある日、通りが騒がしくなりました。目の見えない人たちも、何か違いに気づきました。そのうち、イエス様が来ていることが分かりました。そして、「ダビデの子、イエス様、助けてください。」と叫び始めたのです。目が見えない彼ら。イエス様がどの辺にいらっしゃるのか、まったく見当もつきません。とにかく、人混みの方についていきながら、「ダビデの子よ、ダビデの子よ。」と叫び続けたに違いありません。まわりの人は、びっくりしたかもしれませんが、目の見えない人たちは、かまわず、大声で叫び続けました。「ダビデの子、神様、あわれんでください。」そして、この人たちは、その信仰の通りに、イエス様によって、目を開かれました。祈りはきかれます。必ずきかれるんです。いじめられたり、仲間はずれにされたりするかもしれません。そんな時、祈ってください。イエス様がどこにいるか分からないかもしれません。でも、叫んでください。祈りは、必ずきかれます。続いて大人のメッセージは、「神の恵みに生きることの大切さ」 ところが、神の恵みによって、私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは、 むだにはならず、私はほかのすべての使徒たちよりも多く働きました。しかし、それは私では なく、私にある神の恵みです。 ?コリント15:10 この箇所には、「恵み」ということばが3回登場。神の恵みを知ることは、自分の罪に目が開かれることから始まる。「恵み」も「罪」も、頭で分かること、説明できることと、本当に分かることとは違う。(先生自身、25歳の頃、突然、示されたとのお証) パウロのめざましい働きも、ただ、神の恵みを知ったことが原動力。次にルカ15:25~32 放蕩息子の兄の箇所から 放蕩息子のたとえ話 裕福な家に兄弟がいて、弟が、遺産を先に自分にくれと父に願い、財 産の半分を手にし、遠い国に旅立ち、そこでさんざん遊びまくり、財産を湯水のように使い果 たしてしまう。間もなく飢饉がその国を襲い、弟はぶたのえささえ食べようかと思うほど、落 ちぶれた。その時、ふと、弟は裕福だった家を思いだし、父のところに帰ろうと決意する。 「おとうさん。私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私は、あな たの子と呼ばれる資格はありません。雇い人のひとりにしてください。」しかし、父親は、そ んな彼に、よい着物を着せ、指輪をはめさせ、「死んでいたのが生き返り、いなくなっていた のが見つかったのだから。」と祝宴を始めた。 ところで、兄息子は畑にいたが、帰って来て家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえて来た。 それで、しもべのひとりを呼んで、これはいったい何事かと尋ねると、しもべは言った。『弟 さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、おとうさんが、肥えた子牛 をほふらせなさったのです。』すると、兄はおこって、家にはいろうともしなかった。それで、 父が出て来て、いろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。『ご覧なさい。長年の間、 私はおとうさんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友だちと楽しめ と言って、子山羊一匹下さったことがありません。それなのに、遊女におぼれてあなたの身代 を食いつぶして帰って来たこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったので すか。』 父は彼に言った。『おまえはいつも私といっしょにいる。私のものは、全部おまえの ものだ。 だがおまえの弟は、死んでいたのが生き返って来たのだ。いなくなっていたのが見つ かったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。』」クリスチャンには2種類。 1、律法主義 別名ネコ信者 「教会行かニャーならん」「聖書読まニャーならん」 結果 こんなにやっているのに 必死に守ってるのに 比較 優越感と劣等感 ねたみ 怒り 2、恵みに生きる 結果 感謝 比較しない 喜んで奉仕兄の姿は、律法主義そのまま。その兄に対し、父は声をかける。 「おまえはいつも私といっしょにいる。私のものは、全部おまえのものだ。」すなわち、「いつも共にいるのに、うれしくなかったのかい。子ヤギ一匹くれなかったっていう けど、求めたっことあったかい。欲しいっていえば、なんだってあげたんだよ。財産はすべて、 お前のものだったんだよ。」 兄の救いはどこにあるのかな、と今まで思っていたが、はっとさせられた。共にいたのだ。相続人として莫大な財産をもらう権利をもっているのだ。求めればいいのだ。この兄のような愚かさを犯していないか。当然いただけるものを、求めずして、くれないと愚痴ってしまうことはないか。「見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。」(マタイ28 : 20)とおっしゃる主が共にいることは、素晴らしいことなのに、どこかで、きびしく減点する審査員のように感じ、自分で勝手に窮屈に過ごしていないか。深く、考えさせられた。午後の記念会は、さながら同窓会のよう。当時の子供たちは、そろそろ孫ができているような年代にさしかかっている。思い出話、暴露話、懐かしい写真の披露など、終始、和やかな記念会だった。教会学校は50周年だが、教会自体は11月で30周年。ある家族が教会学校を開始して、そのもと生徒たちが礎となり、のちに教会が建てあげられた。すばらしい主の働きだと感じた。牧師先生が、最後の挨拶の中で、地域の子供に対するアプローチの必要性を、ビジョンの1つとして語った。教会メンバーの子弟の教育と、地域の子供への関わりの両立は、難しい面があるとのことらしいが、それは、まさに必要なことと感じている。今、この混迷の時代、教会のみが、平和と平安を、子供たちに与えられる。競争時代に、子供たち自身の価値を教えてあげられる。そして、何よりも、今の教会の成り立ちを見せていただき、子供たちに福音を伝え続けることこそ、この教会らしい歩みではないかと思わされた。先月、天に召された片岡先生は、50年後の教会を意識されていた。はたして、50年後の我が教会は、また教会学校はどのようになっているのだろうか。
2002年05月12日
コメント(1)
-
さようなら片岡先生 また天国で
ふと気がつくと、電車は岸和田駅に停まっていた。特急の追い越し待ち合わせで数分停車後、走り出す。右手に岸和田城。ああ、1ヶ月前、この町のどこかで、片岡先生が最後の1週間を過ごされたのだ。そして、その早すぎる人生の終止符を打たれたのかと思うと、胸が熱くなった。電車はやがて、連絡橋を渡り、関西空港へ。ああ、片岡先生の帰りのない最後の旅路、ここに降り立たれたのかと思うと、つい涙腺が刺激されてしまった。先生の最後の片道旅行、その末端区間を逆にたどったような、そんな気持ちになった。 昨日(5月6日)、4月6日に逝去された故片岡伸光先生の関西での記念会が、自分の出席教会で開かれた。先生は、KGK=キリスト者学生会の総主事として長年、奉仕され、3年前からは、シンガポールの日本人教会牧師として奉仕されていた。昨年、任地のシンガポールですい臓癌発見、緊急帰国され、東京で手術。例年より早く桜が咲く3月31日に再度帰国、岸和田の奥様の実家で過ごされ、4月6日、53歳の生涯を閉じられた。学生時代、KGKの全国集会や、委員会などで、何度かお会いし、お世話になった。プロレスが大好きで、気さくな、豪快な主事だった。残念ながら、お会いできた機会は、主事が当初関西、そして東京に住んでおられたため、年に1~2回くらい。決して、深い親しいお交わりをもてたわけではなかったが、大学生を相手に、いつも全力で奉仕される姿は、忘れることができない。 記念会は、終始和やかに、時に爆笑につつまれながら、時間を大幅に超過して行われた。先生の大胆さ、無鉄砲さ、無邪気さという面を持つ反面、裏では緻密で繊細な部分をお持ちだったこと、また、何事にも透明であられようとした先生の思い出、エピソードが、多くの出席者の口を通して語られた。何よりも、再会の希望にあふれた記念会であった。 ・全体写真を撮るスペースがなかった時、片岡先生自信が電柱によじ登り、見事、すばら しい写真を撮ってくださった。 先月、シンガポールにお見舞いに行った時も、病院の 話では、ふつうの人では、意識を失ってもおかしくないくらい血圧が上がっていたにも 関わらず、全エネルギーを使って、応対して下さった。 ・ある集会で、ある参加者がコンタクトレンズを落とし、参加者全員で探すことに。 次のプログラムの時間に突入しても、捜索を中止せず、皆で一生懸命探した。その時は なぜプログラムを優先しなかったか、分からなかったが、でも、今では、そんなことが 一番の思い出として残っている。 ・「狭い門から入るンや。そして、進む時は、いてまえや!」 学生時代に、このように片岡主事に言われ続け、進路選択でも狭いところへ。その場所 でも順調で「これは広いな。狭いところはどこやろ。(たとえばクリスチャンドクター のいない職場)」と次の職場・進路へ。片岡主事のすりこみのおかげで、今の職場に。 先生の最後を看取った後輩の主治医が、連絡をくれた。「あんな人生の終わり方、ある んですね。まわりの人、みんな『よかった、よかった』言いはるんですよ。ほんま感動 しましたわ。」 人生の最後の時まで、キリストを述べ伝えた先生だった。 告別式での弔辞で他の人が「片岡先生には狭い門から入れって言われました。」ああ、 この人、どこでも、同じこと言うてはったんやな。(会場爆笑) ・先生ご自身に間違い、落ち度があった時、年下の自分に対しても「そんな気持ちにさせ てたんか。ほんと、すまんかった。」と頭を下げてくれる先生だった。 ・「アッポ~!」当時のKGK梅田事務所からは、毎日、こんな謎!の叫び声が聞こえて きた。片岡主事が、学生たちにわざをかけ始めるのだが、次第に学生たちがプロレスに 熱中してくると、決まって「キミたち、いつまでやっとんねん。」とかけたはしごを、 はずす主事。学生たちに慕われていたのも、こんなところが1つの要因かもしれない。遺された奥様のごあいさつの中から。闘病中の日記の一部の紹介。 「復活された主はマリヤに、顔と顔をあわせてお会いしてくださった。主と顔をあわせ、 交わっているか。ややもすると、東洋人として、孤独の中、1人で悟りを得る傾向はな いか。」 また、ヘンリー・ナーウェンの著作も、よくお読みになっていたらしい。記念会が終わってからも、話は尽きず、とうとう、当日の帰宅を断念する人々まで現れたとか。(話は、深夜3時まで続いたらしい。) 片岡先生が、いかに皆に慕われていたか、また、それぞれの人脈の中心にいらっしゃり、それらの人々をつないでいらっしゃったかを感じる。記念会で配られたしおりに目を通していくと、先生は50年後の日本の教会を意識されていたという。また、サラリーマンへの福音伝道において、ご自身の自らのノウハウ、知識が、全く無力で役に立たないことを実感され、試行錯誤されていたという。霊性についての関心も深く、海外留学も考えられたこともあったという。激動する現代社会の中、教会が、またキリスト者が進むべき、選ぶべき道は何か。大きな課題と、問いかけと、使命を、私たちに残しつつ、先生は一足先に、人知を越えた最もふさわしい時に、天国に帰られた。いつか、御国に行き、再会した時、主のみもとで、思いっきりお交わりしたいと思う。
2002年05月07日
コメント(11)
-
きょうのできごと 礼拝と交わり
まずは礼拝。今日のメッセージ箇所はエゼキエル29章から、聖書のいうところの神の再確認のメッセージ。 1 聖書の神は、すべての人にとっての神=すべての人が、この方により裁かれる。 人は神の被造物であり、好む好まざるに関わらず、例え否定したとしても、すべての者が、つくら れた者として、例外なく関係のあるお方。 例え) 重力 目に見えない、信じないといって、それから自由にはなれない。 無視して行動しても、落としたり、落ちてしまうだけ。 2 神が、すべての良きものの源=良きものはすべて、神からの賜物。 「エジプトの地は荒れ果てて廃墟となる。このとき、彼らは、わたしが主であることを知ろう。 それは彼が、『川は私のもの。私がこれを造った。』と言ったからだ。」 エゼキエル29 : 3 古代エジプトの繁栄は、ナイルの賜物と呼ばれたとおり。また、ナイルから運河を巡らす大きな努力 もあったため、上記のエジプトの表現も、あながち根拠のない誇りでもない。しかし、努力以前に、 すでに、ナイル川をそこに存在せしめたのは神。ナイルが先にあったからこそ、努力もでき、繁栄 もできた。 「自分の努力で何事もなし得ると考える人は幸せ。どんなに努力しても不可能なこともあるから。」 (河合隼雄氏のことばの引用 聞き書きなのでかなり省略 不正確、しかしこんな文脈) 我々も、自分の努力の結果を、ことさらに誇ることはないか。学校で、会社で、家庭で、他で。 しかし、視覚、知能、体、日々の食べ物‥‥。 日常生活に必要なものが与えられているが、それは、決して当たり前のことではない。 そして、それらが与えられていることゆえに、努力もできる(できた)。 努力できる恵みに感謝。 3 すべての出来事は、神の支配のもと起きている=神さまから見れば、どんなことも意味のあること。 エゼキエル29章は、かつてバビロンと拮抗するほどの勢力を誇った大国エジプト滅亡の預言。 事実19年後にエジプトは、この預言とおり滅亡。歴史に介入し、支配される主。 「神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを 働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。」 ローマ8 : 28 我々の生活の中で、「あの時、ああしておけば」「あれさえ、なければ」「○○が、裏切らなければ」 などという失敗、後悔や、原因探し、責任転嫁をしてしまいがち。 しかし、キリスト者にとっては、たとえ一見、よくないこと、心地よくないことを含め、すべてのこと に意味があり、理由があり、目的があることを信じる信仰を神から与えられることは何と心強く励まさ れることか。しかも、神は、私たちの見えるところ、目の前の状況だけを変えて、よくして下さるので はない。「すべてのものを働かせて益としてくださる」すべてを支配されるお方である。 メッセージのあと、聖餐式。十字架で命を捨てて下さった主と、最後の晩餐を想う。 昼食は、グループに分かれて、分かち合いをしながら。うれしかったこと、感動したことを1つずつ。 Nさんが久々に教会に。教会には古くから来ているようだが、まだ、洗礼は受けておられない。教会に、続けて来る時もあれば、しばらくお休みの時もある。そのNさんが、分かち合いの中で話してくれた。「一昨日、昨日とある人と会っていた。その人を見ていて、神さまを第一とすることを思い出させられた。今の自分にとって、必要なこと、そして欠けていた、忘れていたのはこのことだった。その人を通して、神さまが、自分にそのことを語って下さったように思う。」Nさんは、とてもとても子供たちの面倒見のよい人。半分冗談で、保父さんになれば、なんて話したことも。今は仕事をしながら、健康食品のビジネスもかけもちで。もしかしたら、何か試練があるのかもしれない。もしかしたらビジネスの成功を望んでいるのかもしれない。でも、いつになく真剣な眼差しで、熱く語るNさんを見ていて、何かが彼の魂に触れ、語っていることを確信させられた。主よ、みこころの時に、みこころのままに、Nさんを捕らえて下さい。 Iさんは、最近、別の教会から移ってこられたおばあさん。おばあさんといっても、白髪をうすい紫に染めたり、ユニークな服を着こなすおしゃれな方。 「祈ることがとっても楽しく、1日でも祈っていられる。だけど、イエスさまとばかり交わっていると、だんだん、今までの楽しみやお友達、人間関係なんかが、喜びでなくなってくる。自分は子供がいるわけでなし、人と関わっていくことが、もともとおっくうな方だから、そのままにしておくと、関係が途切れてしまう。でも、イエスさまをお伝えしたくて、人間関係が途切れてしまわないように努力しているの。」 うーん。お聞きしながら、心の中でうなり込んでしまった。以前は、(確か)服飾学校の校長まで務められた方。ご主人とのドライブ中、雨上がりにこの世のものと思えない虹を見て、神を感じ、教会の門をたたかれた。ある時、聴覚の大部分を失うこととなり、今は補聴器での生活だが、それさえ、雑音から解放され静かに神さまと交われる喜びとおっしゃるIさん。そして今、主との深い交わりゆえに、この世の交わりから離れつつ、そこに福音をお届けしたいと強く強く強く願う姿に、二重の感動(というかショック)を覚えた。 キリストにはかえられません 世の宝も また富も このお方が わたしに代わって死んだゆえです ※ 世の楽しみよ 去れ 世の誉れよ 行け キリストにはかえられません 世の何ものも キリストにはかえられません 有名な人になることも 人のほめる言葉も この心をひきません ※ キリストにはかえられません いかに美しいものも このお方で 心の満たされてある今は ※まさしく、↑ 聖歌521番のとおりに生き、その喜びをお伝えするため、努力されるように、つくりかえられる姿を見、ただただ、神さまのなさるわざの不思議さ、すばらしさをほめたたえずにいられない。主よ、完全な明け渡しを教えて下さい。Iさんをお用い下さい。参考 キリストにはかえられませんhttp://www.ylw.mmtr.or.jp/~johnkoji/hymn/2-195.htmlhttp://www.wlpm.or.jp/100man/0204/gr.htm 明日は、うちの教会を会場にKGK(キリスト者学生会)のもと主事で、最近天に召された片岡先生の関西での記念会が行われる。
2002年05月05日
コメント(2)
-
ちょっとした うれしかったこと
クリスチャンリングに、私も登録しているのだが、試しにランダムで、いろいろとんでみた。適当に飛びつつ、とあるページで、PROFILEをクリックしたら、自己紹介にハンドルネームと違うニックネームを載せていて、知人と判明。学生時代、KGKで関わった兄弟で、ある委員や、全国集会で同じ班になっただけなので、会った回数もせいぜい片手分くらい。特に手紙とかで、連絡をとりあった時期があるわけでなし、そういう意味で、長い深い交わりだったわけではない。しかし、自分の中では、彼のもつストレートな信仰が、うらやましかったことを思い出すところをみると、大きなインパクトを受けていたことは確かだ。そうそう、10年ほど前か、INTERNET時代到来前のパソコン通信(ふっる~い!)全盛時代に、NIFTYのクリスチャンFORUMで、遭遇したこともあったな。ほんの数回あっただけなのに、なぜか、とてもなつかしく、いつか、札幌に会いに行きたいという衝動にかられれている。それにしても、クリスチャン世界が狭いことは狭いけれど、NET社会のこの便利さ(同時に怖さと危険も潜むが)には、びっくりびっくり。昔の自分の状態をも、少し思いだしながら、主に感謝。
2002年05月03日
コメント(1)
-
オルグ そしてストライキ
世間はゴールデンウィークだが、我が社は春闘で盛り上がっている。会社側が突然、給与体系の見直し、すなわち、業績にリンクした年収と、人事考課の結果を賞与に反映させることを提案してきたため。伏線があり、3月の団交では、4月まで待て、4月になると5月8日の本社の業績発表を見ないと、何とも答えられないと、組合の要求に、まったく誠意を見せていない。しかも、組合が会社側の真意をつっこんで聞いたところ、会社業績、人事考課ともに最高だとしても、現状を下回るものを想定しているらしい。先週は、組合の執行部が地元にやってきて、ストライキ権行使について、組合員の意見を集約していった。同業他社で人事考課リンクさせた会社では、昔の学校の5段階評価でいえば、新入社員など若手が軒並み「5」、高給取りのおじさんたちは「1」と、ただ単純に人件費削減に利用された例もあるという。これでは、モチベーションの持ちようも無くなる。なんのための人事考課だろうか。(必ずしもこのようになるわけではないが。)結局、4月30日の段階でも、会社側は5月8日の業績発表をたてに、何の前進回答もなし。5月1日はメーデーで休みだったため、翌2日が決行日となった。5月8日を待つことは、会社のいうところの業績リンクを認めてしまうことになるという危機感がある。自分の職場は今日は対象でなかったが、東京と大阪の職場では、午後1時半を期して、組合員=管理職以外ほとんどが離席。2時間の時限ストということで、近くのレンタル会議室や喫茶店で待機したとのこと。午後5時半過ぎから、組合と会社と交渉するも、結局、交渉相手自体が、何の決定権を持たず、5月8日を待つしかないの1点張りで、決裂。翌5月3日、現場でのスト回避は不可能に。私は3日から6日まで休みなので、ストに直接参加せず。明日は、管理職によって、業務は遂行される予定。大きな支障も出ない予定。 ああ、主よ。このような争いの場、何が正しいか分からない場にあって、正しい選択をしていけますように。あなたの栄光が現されますように。 このような中にあって、頼るべき土台を知り、その上に立っていることは何と幸いなことでしょうか。 主よ、ただみこころをなし給え。
2002年05月02日
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1