2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010年09月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
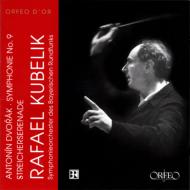
「新世界より」
「名曲100選」 ドヴォルザーク作曲 交響曲第9番「新世界より」アメリカ・ニューヨークのジャネット・サーバー夫人から、彼女が経営する「ナショナル音楽院」の院長という職への要請が、チェコのアントニン・ドヴォルザーク(1841-1901)に届いたのは1891年の春というエピソードは、先日のドヴォルザーク「チェロ協奏曲 ロ短調」の記事で書いています。 その頃のドヴォルザークは既に8つの交響曲、ピアノ曲、室内楽作品、オペラなどを発表しており、ヨーロッパでは大作曲家の一人でした。 その彼に当時のヨーロッパからすれば「新世界」の国の人々に音楽教育をして欲しいと要請されたのです。アメリカはまったくの異質の新しい人種が建国した国ではなく、すべてヨーロッパから移民した人種でした。クラシック音楽には素養もありました。新しい国に音楽教育が必要で、そのために立派な音楽家を必要と考えたサーバー夫人だったのでしょう。受託までは紆余曲折がありましたが、ドヴォルザークは1892年9月15日にニューヨークに向けて旅立ちました。 ニューヨークには9月26日に到着しました。 それから約2年半彼はアメリカに留まります。その頃のアメリカは、すでに大陸横断鉄道が完成しており、1793年に独立を果たして109年目を迎えていました。ドヴォルザークがアメリカについて驚いたのは、活気にあふれた街並みでした。 まだエンパイア・ステートビルは建っていませんが、大きな建物がブロードウエイに立ち並び、行き交う群衆の活気あふれる姿に驚いたそうです。 祖国の田舎町とは比較にならない活気ぶりでした。 もう一つは「黒人霊歌」や純朴なアメリカ民謡に大きな感動を受けたそうです。 アフリカから奴隷として売られてきた黒人たちの歌う「黒人霊歌」は、虐げられた人々の救済への祈りと願いを込めた歌ですが、ドヴォルザークはその歌にいたく感銘を受けて、自宅に黒人歌手を呼んで彼らの歌に耳を傾ける機会が非常に多かったそうです。ドヴォルザークは、それまでアメリカ人には不当に低く見られていた「黒人霊歌」の価値を高く認めた、最初の大作曲家であったそうです。 彼は美しく変化に富む黒人霊歌を「土の産物」として評価していました。「ナショナル音楽院」の忙しい職務のかたわら、1893年の約半年間新しい交響曲への構想をまとめて草稿を仕上げています。 その年(1893年)の夏に休暇を取ってニューヨークから遠く離れたアイオワ州の町へと旅立ちます。 この時にはドヴォルザークはかなりひどいホームシックに陥っており、音楽院の弟子の勧めでわざわざ遠いアイオワまで出かけたそうです。そこはスピルヴィルという小さな町ですが、そこにはボヘミアから移住してきた人々が数多く住んでいた所で、母国語を気兼ねなく話すことが出来、祖国の料理を楽しめる、祖国の雰囲気を味わえる土地でした。 アイオワの自然は祖国のそれと似ていたのかも知れません。 ボヘミア移住民と接することで彼の郷愁も少しずつ和らいでいったそうです。こうして新しい交響曲は短期間で書き上げられています。 それが交響曲第9番ホ短調「新世界より」なのです。 初演はその年(1893)の12月16日にニューヨークで行われており、大成功に終わったそうです。「新世界より」はドヴォルザーク自身が付けた副題で、当時ヨーロッパでは「新大陸」と呼んでいたアメリカを指す「新世界」ですが、音楽にはアメリカ・インディアンの民謡と思しき旋律や、黒人霊歌の旋律らしいものが使われていますが、彼が何故「新世界より」と「より」を付けたを考えると、決して「新大陸」を表現した音楽ではなくて、遠くアメリカからボヘミアを望郷の想いで書いたことは容易に想像できます。 この「新世界より」は、ドヴォルザークが故郷ボヘミアを想って書き綴った「手紙」のような音楽でしょう。 アメリカ的な匂いがすると感じれば、その「手紙」をアメリカで書いたからと思えばいいのではないでしょうか。この作品中、最も有名なのが第2楽章「ラルゴ」です。 イングリッシュ・ホルンによる郷愁を誘うような美しい旋律は一度聴けば忘れられない、ほのぼのとした哀愁を誘う旋律で、今では「家路」という名前で合唱曲にさえなっている有名な旋律です。 小学校の下校時の音楽もこの旋律を使っている学校が一体何校あるでしょう。 ほとんどの学校が使っているほど家路に着く旋律にぴったりです。1957年、私がクラシック音楽に興味を持って聴き始めた時に、小学校の恩師が貸してくれたLPがこの「新世界より」でトスカニーニ指揮 NBC交響楽団の演奏で、何度も何度も第2楽章「ラルゴ」を聴いていました。私がクラシック音楽を聴く原点の一つでもありました。 愛聴盤ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団(ORFEOレーベル ORFEO596031 1984年録音 海外盤) いまはこの1984年の演奏会ライブ録音での、クーベリックの緊張をはらんだ、しかもボヘミア色に塗りつぶされたような色彩感のある、一音一音をしっかりと奏でている演奏に魅かれて、このCDばかりを聴いています。その他の愛聴盤トスカニーニ指揮 NBC交響楽団ケルテス指揮 ウイーフィルハーモニー管弦楽団ゲオルグ・ショルティ指揮 シカゴ交響楽団ヴァツラフ・ノイマン指揮 チェコフィルハーモニー
2010年09月30日
コメント(1)
-
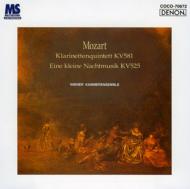
クラリネット五重奏曲
「名曲100選」 W.A.モーツアルト作曲 クラリネット五重奏曲 イ長調 クラリネットという管楽器は、現代ではクラシック音楽、流行歌、ジャズ、ポップスまで広く使われています。しかし、この楽器は1700年頃にクラリネットの前身から改良されて、モーツアルト(1756-1791)の時代にようやくオーケストラに使われ始めたそうです。モーツアルトとクラリネットの出会いとこの楽器への愛着については定かではありませんが、モーツアルト自身が少年の頃からヨーロッパを父と共に、ピアノのコンサートツアーを行なっていましたから、そのツアー先で出会った可能性もあるやも知れません。記録として残っているのは、モーツアルトがマンハイムを訪れた時にそこの宮廷楽団がすでにクラリネットをオーケストラ楽器として採用されていて、ザルツブルグ(モーツアルトの故郷)にもクラリネットがあれば・・・、という想いをモーツアルト自身が抱いていたそうです。モーツアルトがザルツブルグを離れてウイーンに移住したのが1781年でした。その頃のウイーンでもまだオーケストラにはクラリネットを使っておらず、必要になった時には客演奏者として招かれていたそうです。その頃のクラリネット奏者がアントン・シュタットラーという人で、ここで初めてモーツアルトとクラリネット、モーツアルトが書いたクラリネット音楽、そしてシュタットラーの名前が音楽史に残ることになる出会いとなったのでした。モーツアルトとシュタットラーはお互いが意気投合したのか、友人としての交際が始まり、とりわけ目に見えて凋落・貧困になっていくモーツアルトをシュタットラーは精神的にも物質面でも援助を惜しまなかったそうです。そうした緊密な交際の中で、モーツアルトがシュタットラーからクラリネットについて様々なことを学んだのでしょう、1791年にモーツアルトが亡くなる4年ほど前から、さかんにクラリネットを使った曲を書いています。 「ピアノと木管のための五重奏曲」「ピアノ、ヴィオラ、クラリネットのための三重奏曲」「クラリネット協奏曲」「クラリネット五重奏曲」などがその例です。先日のブラームスの「クラリネット五重奏曲」の記事でも触れましたが、作曲家と演奏家の出会いが楽器への興味や音楽表現への可能性の広がりを助長することがあり、このクラリネットでは奇しくもモーツアルトもブラームスも、その生涯での晩年に出会っているのです。「クラリネット五重奏曲」はモーツアルトが亡くなる2年前の1789年に書かれており、ブラームスの「人生の黄昏」という老境に入った心境が淡々と表現されているのと比べても、モーツアルトの曲は長調で書かれているせいか、優美で、典雅で、気品を保ちながらもしみじみとした諦観すら感じられ、澄み切ったようなクラリネットの音色はモーツアルト晩年の心境を悲しいまでに表現しており、特に第2楽章「ラルゲット」には、微笑みを湛えながら、何か悲しさに耐えて涙を浮かべているような楚々とした婦人の哀愁といった感じを受けるのは、はたして私だけでしょうか?まさにクラリネットの名曲中の名曲と呼べるのはではないでしょうか。愛聴盤アルフレート・プリンツ(クラリネット) ウイーン合奏団(DENONレーベル COCO70672 1979年録音)ブラームスのクラリネット五重奏曲の記事でも書きましたように、私が持っている盤はモーツアルトとブラームスの五重奏曲を収録した盤ですが、同じ演奏家・同じ録音盤となると、この曲では上記紹介盤となるようです。 カップリングは「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」です。 DENON CREST1000 シリーズの1枚です。 尚、同じDENON CREST1000シリーズで、モーツアルトの「クラリネット協奏曲」とカップリングした盤もあります。どちらも1000円盤です。
2010年09月29日
コメント(0)
-
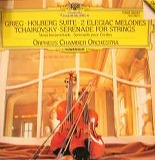
弦楽セレナーデ
「名曲100選」 チャイコフスキー作曲 「弦楽セレナーデ」作品48チャイコフスキー40歳の作品(1880年)。 曲冒頭に演奏される「ドー・シー・ラー」の旋律が強烈に存在感を示す、チャイコフスキー会心の名作。 ワルツを愛し、ワルツ音楽を書くことが得意だったチャイコフスキー(バレエ音楽などでワルツの魅力を楽しませてくれる)の真骨頂がこの作品にも表れており、第2楽章に「ワルツ」が使われていて華やかな色彩に彩られている。チャイコフスキー自身が「初演の日を待ち切れないほど愛している作品」と書いているだけに、彼としても会心の作品だったのだろう。 チャイコフスキー音楽の最上の魅力とされる「親しみやすい甘美な美しい音楽」であり、「スラブ的な郷愁を誘う旋律美」であり、弦楽合奏だけなのに「実に見事な色彩」に満ちあふれた素晴らしいチャイコフスキーの音楽世界を味わえる一品。セレナードは本来は恋人の家に忍び寄り、彼女の窓の下で囁くように歌う「恋歌」でしたが、この曲は演奏会用として書かれた規模の大きな曲です。蛇足ですが、4楽章構成で弦楽五部(第1、第2ヴァイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス)で演奏され、この曲は第2楽章に「ワルツ」が入っているものの、全編にロシアの哀愁のような、チャイコフスキー独特の哀切で、美しく華麗な旋律美に溢れた弦楽合奏の名作です。 第3楽章などはエレジーとして暗く、哀愁に満ちた、チャイコフスキーの甘美な旋律を堪能できます。 悲愴なムードいっぱいの実にロシア的な切なさに溢れた楽章で、私のチャイコフスキー音楽で最も好きな内の一つです。1970年製作のロシア映画「チャイコフスキー」では、この「弦楽セレナーデ」が非常に効果的に使われていました。チャイコフスキーが初演などの不評に打ちのめされて、ロシアの荒れ地を徘徊する様などに、第3楽章「エレジー」が使われており映像と共に強烈に印象に残っており、それがこの作品のロシア的哀愁を余計に感じるのかも知れません。愛聴盤 オルフェウス室内管弦楽団(グラモフォン原盤 F00G27093 1984年録音 廃盤)ユニヴァーサル・ミュージックに現在は販売権が移行していますが、私が購入した時には日本ポリドール社が販売していました。 現在は廃盤になっているようです。 指揮者を置かないニューヨークの室内管弦楽楽団で、アンサンブルの美しさは見事です。カラヤン指揮 ベルリンフィル盤(1967年録音)と共に楽しんで聴いています。
2010年09月28日
コメント(0)
-
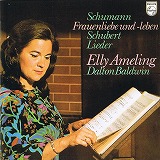
女の愛と生涯
「名曲100選」 シューマン作曲 連編歌曲集「女の愛と生涯」女性の生涯を描いた藝術作品がいくつか残されています。 森 光子の芝居で有名な林 芙美子の「放浪記」や、フランスの作家ゾラの「女の一生」などがあります。 アメリカではマーガレット・ミッチェルの「風と共に去りぬ」などもこのジャンルに入る小説かもしれません。それではクラシック音楽ではどうでしょうか。 それがあるんですね。 ロベルト・シューマン(1781-1831)が書いた「女の愛と生涯」という全8曲から成る歌曲集です。音楽史上でも有名なシューマンとクララの恋愛。 シューマンのピアノの師F.ヴィークの娘クララと長年の紆余曲折を経て、ようやく1840年、30歳になった時にシューマンはクララと結婚します。 そして結婚前夜にクララに贈った歌曲集が「ミルテの花」でした。シューマンは、それまでは主にピアノ曲を書いていましたが、この「ミルテの花」を贈ってからは、結婚後1年間に100曲以上の歌曲を書いています。私はシューマンのことを「カメレオン」と呼んでいるのですが、それは彼の作曲する曲が随分と変わっていくからです。 結婚1年の年は歌曲集、翌年は交響曲、さらにその翌年は室内楽曲とジャンルがころころと変わって書かれています。 ちょっと変わった作曲家です。そのシューマンが集中して結婚1年の年に書いた歌曲集の中に「女の愛と生涯」があります。 「あの人にお会いして以来」「あの方は一番素晴らしい男性」「わからないわ、信じられないわ」「私の指に光る指輪」「手伝ってちょうだい、妹よ」「優しい友よ、あなたは不思議そうだわ」「私の心に、私の胸に抱かれて」「今はじめてあなたは私に苦しみをお与えになりました」の8曲が歌われています。この曲は、一人の女性が娘時代に出会った男性と恋に落ち、結婚し、そして母親としての喜びを知るのですが、夫に先立たれて、未亡人としての寂しさをしみじみと味わうという内容の歌曲集で、シャミッソーという詩人の詩に作曲しています。この作品はあるまとまった物語として構成されて書かれており、こういう形式の歌曲を「連編歌曲集」と呼ばれるそうです。 同じシューマンの歌曲集「詩人の恋」も連編歌曲集と呼ばれるそうです。不思議なのはクララとの愛に身を焦がすばかりであったシューマンがどうしてこんな歌曲を書いたのか? 天才的な芸術家だけが神から許された予知能力で書いたのでしょうか? 「あなたは静かに眠っています。 死の眠りについてしまったとは、ひどい方です。 残されたわたしに、この世はうつろです。 わたしは激しく愛し、生きてきました。 しかし、わたしはもう生ける骸です」 これは第8曲「今はじめてあなたは苦しみをお与えになりました」の詩です。第7曲まで一貫して「女の喜び・母としての喜び」を幸せいっぱいに表現されていたのに、この最後の歌では一転して夫の死に直面。 悲しみに打ちひしがれて残酷な運命に襲われた女のうつろな心が痛切に歌われています。 第1曲「あの方にお会いして以来」を回想するピアノ後奏が痛烈に聴く人の心を打ち、効果的です。熱烈な恋をしてシューマンと結ばれたクララでしたが、彼に先立たれて長い未亡人生活を送ったのは、妻のクララ・シューマンでした。 この第8曲にクララの心情がつぶさに表現されているようです。 あたかも予言するかのように、それをクララとの愛の絶頂期にいたシューマンが書いたとは。愛聴盤(1) エリー・アーメリング(S) ダルトン・ボールドウイン(P)(Philips原盤 17CD-78 日本フィリップス 廃盤)すでにPhilipsもなくなり現在では入手するにはボックスセットとしての海外盤しかないようです。(2) アンネ=ゾフィー・フォン・オッター(Ms) ベングト・フォスベルグ(P)(グラモフォン・レーベル 445881 1993年録音 海外盤)
2010年09月27日
コメント(0)
-
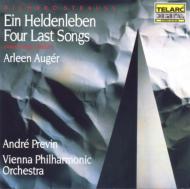
「英雄の生涯」
「名曲100選」 R.シュトラウス作曲 交響詩「英雄の生涯」R.シュトラウス(1864-1949)は「ドン・ファン」「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」「ドン・キホーテ」「死と変容」「マクベス」などの交響詩を数多く書いています。 シュトラウスはこの「英雄の生涯」の後交響詩を作っていませんので、交響詩の総決算的な作品だということは言えそうです。タイトルとなっている「英雄」は,シュトラウス自身のことを表しているそうです。 自らを「英雄」と呼んではばからないシュトラスのこの作品のスケール感と多彩な響きの充実感を聴くと圧倒されて納得してしまいます。シュトラウスが35歳の時にこの曲を作っていますが、最後の交響詩としてこういう題材にして自分の業績を振り返るというのは、この若さで何とも大胆な作曲家ですが(シュトラウスはこの後半世紀も長生きします)、その辺がシュトラウスらしいところかもしれません。内容としては,ベートーヴェンの英雄交響曲を意識している作品だと思います。 同じ変ホ長調でホルンが効果的に使われているところなど似ています。 彼の交響詩「ドン・キホーテ」とは反対の内容作品で、「ドン・キホーテ」が闘争に敗れた騎士だったのに対し、「英雄の生涯」では成功した人間を描いていると言えるでしょう。 このことはR.シュトラウス自身が語っているそうです。曲は,自由に拡大されたソナタ形式で、6部構成のように成っていて、切れ目なく続けて演奏されます。 「英雄」を象徴するホルンと低弦による力強い主題で始まります。この主題はかなり長く,全曲の中心主題となっています。いちばん最初に出てくる低音から高音へと沸き立って行くような、文字通りヒロイックで誇らしげな部分が、実に豊穣な音楽で特に印象的です。この部分をはじめとしてこの曲には,8本のホルンが出てきますが,最初から最後まで主役のように活躍します。 これが音楽に厚みと豪華さを添えています。「英雄の敵」や「英雄の伴侶」「英雄の戦場」などを描いて、「英雄の平和時の仕事」に至るとこれまでの交響詩に使われている動機が主題と絡み合うところなどは、やはり「総決算の交響詩」といった感があります。オーケストレーションの多彩なことは他の交響詩と同じですが、いっそう磨きがかけられて豊穣な、分厚いハーモニーを美しい旋律が織り成す、豪華絢爛たる曼荼羅絵巻のような「英雄」の生き様があますところなく表現されています。愛聴盤 (1) アンドレ・プレヴィン指揮 ウイーンフィルハーモニー(テラーク レーベル CD80180 1988年録音 海外盤)ウイーンフィルと相性がいいのか、1980年代に数多くの録音を残したプレヴィン。 この演奏は実に雄渾にスケールの大きい表現で「英雄」を描いています。 ウイーンフィルの極上にブレンドされたハーモニーの美しいこと! それにテラークの優秀な録音技術がシュトラウス音楽に華を添えています。(2) ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィル(ドイツ・グラモフォン 439 039 1982年録音 海外盤)カラヤン美学の最たる演奏だと思います。 磨きに磨き上げた手兵ベルリンフィルを自由自在に操りながら、彼らの最上にブレンドされた極上の響きを引き出して、R.シュトラウスはこう演奏するんだと言わんばかりの、美しい響きと豪華絢爛たる色彩に彩られたカラヤン最後の「英雄の生涯」の録音盤です。 まるで人生の黄昏を迎えたカラヤン自身の生涯を聴かされている錯覚に陥る演奏です。
2010年09月26日
コメント(0)
-
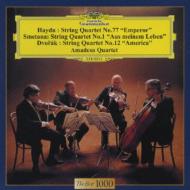
ハイドン「皇帝」
「名曲100選」 ハイドン作曲 弦楽四重奏曲第77番 「皇帝」ヨゼフ・ハイドン(1732-1809)が作曲したこの「皇帝」四重奏曲は、ナポレオン戦争と呼ばれる19世紀初頭のヨーロッパを巻き込んだナポレオンが引き起こした大混乱と関係しています。フランス革命が起こったのが1789年。 この革命が野火のようにオーストリア、プロシャ(ドイツ)などを戦争状態に巻き込み、それに乗じてフランスのナポレオンが全ヨーロッパを征服すべく戦争を仕掛けていきました。 約20年間ヨーロッパは戦争状態となります。それが19世紀の幕開けでした。オーストリアも1809年、ウイーンに怒涛のようになだれ込んだナポレオン軍から激しい砲撃を浴びせられました。 この砲撃でハイドンの大邸宅地も砲撃のために地震のように揺れ、邸内の人たちは悲鳴を上げて逃げ惑ったと言われています。大作曲家ハイドンは少しも騒がず、「皆の者、怖くはない、怖がることはない。 このハイドンがいる限り、何にも起こることはないのだ」と邸内の人たちを励まし、砲撃される中を自らピアノに向かい、自身が作曲した「皇帝賛歌」を演奏したと伝えられています。この時から3週間後の5月31日にハイドンは亡くなりました。 葬儀はウイーンで行われましたが、すでにナポレオン軍の占領下でした。 それでもフランス軍からも葬儀に列席してこの大作曲家を追悼したそうです。ハイドン最晩年の最高傑作である弦楽四重奏曲第77番ハ長調「皇帝」の第2楽章に使われている主題と変奏曲が、彼の死の3週間前にフランス軍の砲撃中に演奏した「皇帝賛歌」です。この弦楽四重奏曲第77番は、この「皇帝賛歌」が第2楽章で使われているために「皇帝」という副題がつけられています。 「皇帝賛歌」とはハイドンがオーストリア国家として書いた作品です。それが何故現在ドイツ国家になっているのでしょうか?その前にハイドンがオーストリア国家として書いた経緯は、イギリス国家にあります。 ロンドンのザロモンという興行師から再三招かれてイギリスにわたって、「ザロモンセット」と呼ばれる12曲の交響曲を書いたハイドンは、イギリス滞在中に聴いた熱狂的なイギリス国民の国歌への愛着と祖国への熱い想いが、人一倍愛国心の強かったハイドンを刺激して、オーストリアのためにと書いたのが「皇帝賛歌」と言われています。その後長くオーストリア国歌として親しまれてきましたが、ヒットラー率いるナチス・ドイツに占領され、この国歌も歌詞を替えられてドイツ国歌となり、終戦後もそのまま西ドイツ国の国歌となってしまい、東西ドイツ統一後もそのままとなって現在に至っているそうです。ナポレオンのオーストリア砲撃から人々を鼓舞してきた「皇帝賛歌」、第2次世界大戦後も国を違えて国歌となった「皇帝賛歌」。ハイドンの思いはこんな結果になって今なおも世界の人々の心を癒してくれています。愛聴盤アマデウス弦楽四重奏団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5091 1963年録音)ハイドン「ひばり」「皇帝」、モーツアルト「狩り」の3曲が収録された1000円廉価再発売盤。 愛聴盤と言ってもこの紹介盤を持っているわけではありません。 同じ音源の「皇帝」と「狩り」だけが収録されたCDで聴いています。現在求めうる盤として上記を紹介しました。
2010年09月25日
コメント(0)
-
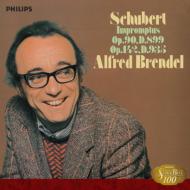
即興曲集
「名曲100選」 シューベルト作曲 「即興曲集」D.899 & D.935フランツ・シューベルト(1797-1827)は、その生涯に600曲以上の歌曲を書き残していたと言われており、別名「歌曲王」と呼ばれてもいます。その生涯と言ってもわずか30年です。作曲を始めてからの勘定になれば20年もないでしょう。 それで600曲以上とは! 驚きです。 「歌曲王」と呼ばれるはずです。ところがシューベルトは9つの交響曲、15曲の弦楽四重奏曲、21曲のピアノ・ソナタも書き残しています(100曲程のピアノ作品を書き残しているとも言われています)。 私はそれらの全てを聴き親しんだことがないので、ことさら論評が出来ないのですが、彼のピアノソナタ、持っているCDでの曲数は10曲くらいですが、それだけでも確実にいえることがあります。 彼のピアノ・ソナタには主題の繰り返しが多いと。 それで冗舌な感じを拭えません。 一言で言えば「長過ぎる」のです。ロベルト・シューマン(1810-1856)はシューベルトのピアノ音楽を評して「ベートーベンをも凌駕している」と書いているそうですが、私は「それはないでしょう」と言いたくなります。 わずか10曲のピアノ・ソナタを聴いているだけで上に書いたように感じられるのですから。ピアノ・ソナタにはそんな特徴があるのですが、この「即興曲集」はこうした感じは微塵も感じられません。 まさに美しく輝くような、珠玉のピアノ曲集と言えると思います。まるでこんこんと泉が湧いてくるように紡がれる美しい旋律の数々と言えるでしょう。 構成的にしっかりとした音楽の流れを組み立てる必要のあるソナタのような大曲よりも、こうした「即興曲」や「楽興の時」のような短い曲の方が書き易かったのかも知れません。彼は決してピアノの名手ではなかったと言われています。 そこがモーツアルトやベートーベンと違うところなのでしょうか。 彼の生涯を読んでみましても決してピアノを習っていたという記述は見当たりません。 それどころか自分のピアノさえ29歳まで持てなかったと言われています。そんなシューベルトが書き残した「即興曲集」はドイツ番号899と935の、まあ言えば第1巻と第2巻として分けられる2つの曲集があり、それぞれ4曲ずつ書かれています。 演奏時間は5分くらいの作品から12分ほどかかる曲まであります。「即興曲」とは音楽の形式にとらわれないで、作曲家の自由な裁量で書き綴られた作品のことで、シューベルトのこの作品を聴いていると、上に書いたようにまるで「こんこんと泉の湧き出る」如くに旋律が綴られています。「楽興の時」と共にシューベルトのピアノ作品で最も好きな小品集です。愛聴盤(1) アルフレード・ブレンデル(ピアノ)(旧Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7042 1972年録音)(2) 内田光子(ピアノ)(旧Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD50029 1996年録音)(3) クリフォード・カーゾン(ピアノ)(デッカ・レーベル 456757-2 1941年/1951年録音)
2010年09月24日
コメント(0)
-
長老の叔父逝く
昨日の昼食後に近所の米屋さんから米5kgが届いた。 袋にのし紙が貼られてあり私の母方の兄、つまり叔父からのお彼岸のお供えだった。 こちらはうっかりとしていた。母の実家でもあるので毎年春秋のお彼岸とお盆にはこちらからお供えをしている。 今年はそれを忘れてしまっていた。慌てて果物屋に掛け込んでお供えののし紙を貼ってもらって同じ町内の自宅のご仏前に供えた。 そこでその叔父の奥さん(叔母)から、叔父が昨日救急車で運ばれて入院したと聞かされた。痰が切れずに困り病院で吸い出してもらおうと入院したという。 病名は肺炎。 もう満で95歳になる叔父。 肺炎と聞いて嫌な予感がした。高齢者の肺炎の罹患は危ない。しかし、叔母は「大丈夫。あと1週間もすれば戻ってくるさかいに、見舞いは止めといてや。頼むで」と言う。 叔母と1時間ほど話し込んだあとスーパーへ買い物に行って帰宅したのが午後5時。 それから40分後に電話が入った。 「叔父が息を引き取った」と。訃報が信じられずに電話の前で呆然とするしかない。 辛うじて息子夫婦が臨終に間に合ったらしい。80歳からパソコンを始めキーボードを叩く指も危なげな様子だったが、「自分史を書きあげる」と頑張っていた。それを完成したのかは不明。一度そのことを尋ねなければと思いながら忘れていて、この訃報。2週間前に訪ねて言葉を交わしたのが最後だった。ベッドで寝そべりながら右手を軽く挙げて「おッ」と言ってくれたのが強烈な印象で残っている。享年95歳。 安らかにお眠り下さい、叔父さん。合掌
2010年09月23日
コメント(2)
-
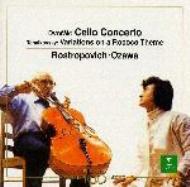
チェロ協奏曲ロ短調
「名曲100選」 ドヴォルザーク作曲 チェロ協奏曲ロ短調 作品104アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)が、アメリカの「ナショナル音楽院」の院長をしていた頃に生れた作品で最も有名なのが交響曲第9番「新世界より」。 その「新世界より」同様にアメリカ滞在中に生れた傑作が他にもまだあります。 ドヴォルザークの最高傑作と言われている「チェロ協奏曲ロ短調 作品104」がその一つです。ニューヨークのジャネット・サーバー夫人から請われて「ナショナル音楽院」の初代院長として、1892年の秋にドヴォルザークはアメリカに赴き約2年半の滞在期間中に書いた作品で「アメリカ三部作」とも呼べる3曲があります。 一つは「新世界より」。 二つ目は弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」作品96。 三つ目がチェロ協奏曲ロ短調 作品104。チェロの前身は「ヴィオラ・ダ・ガンバ」(足のヴィオラ)という楽器で、バロック期から通奏低音楽器として使われてきています。チェロはよく 女性の体形と比べられますが、良く似た小型のヴァイオリンが明るい高い澄んだ音色であるのに対して、ヴァイオリンよりも女性体形に似ているチェロはとても男性的な音を響かせます。 温かくて深く、朗々とした響きを出す楽器です。「チェロは、歳月と共に年をとるどころか逆に若くなり、ますますほっそりと、しなやかに、そして優雅になってくる美女の如し」と、チェロを形容したのがパブロ・カザルス(チェリスト・指揮者)でした。チェロを独奏楽器として位置づけたのは大バッハではないでしょうか。 パブロ・カザルスによって発見された「無伴奏チェロ組曲」によって、バッハがすでにこの楽器の性能をよく知っていたことを証明しており、「チェロの旧約聖書」と呼ばれ、のちにベートーベンが書いた「チェロ・ソナタ」が「新約聖書」と呼ばれており、チェロの市民権が確立しています。ところが協奏曲となると、ボッケリーニ、ハイドンが書いて以来本格的な協奏曲は数少ないのです。 19世紀後半になってサン=サーンス、シューマン、ラロなどの協奏曲が生まれていたのですが、このドヴォルザークの曲で影が薄くなってしまいました。ドヴォルザークは、音楽院在任中に一度祖国へ帰っています。 よほど郷愁に駆られていたのでしょう。 このチェロ協奏曲も一時帰国前から書かれており、「新世界より」と比べてもよりいっそうボヘミア的郷愁を感じさせる音楽になっています。アメリカに再度帰ってきてもドヴォルザークは契約任期を務めることが出来ずに、1895年の春、永久にアメリカに別れを告げて帰国しました。 この曲は帰国後プラハで最終楽章の手直しをして完成させ、翌年1896年の春にロンドンで初演されています。この曲の魅力は第1楽章は、序奏がなくていきなり低弦とクラリネットで第1主題提示を終わって独奏チェロが奏でられると、まるで歌舞伎の千両役者の登場のような趣きがあります。 また独奏者にとっても弾きがいのある部分ではないでしょうか。 ロマンティックな情緒の第1主題の旋律からして、すでにボヘミヤ的な情感がたっぷりです。 展開部でチェロがお休みというのも面白い趣向です。 第2主題が五音階で牧歌的主題が奏でられて、この2つの主題が軸となっています。 いかにもロマン派の、国民樂派の協奏曲という貫録たっぷりの楽章です。私が一番好きなのは第2楽章です。 独奏チェロによるボヘミヤ的な哀愁が漂う旋律が素晴らしく、これほどまでにドヴォルザークの郷愁が高まっていたのかと思うくらいに、哀感漂うしみじみとした情緒がとても美しい楽章です。 とてもノスタルジアに満ちたセンティメンタルな情緒が、チェロの深みのある、甘く抒情的な音色で美しい音の世界が繰り広げられています。第3楽章は、ボヘミア的な民族舞曲風の旋律がとても印象的で、華麗なチェロの技巧が活躍する溌剌とした音楽で、この楽章を帰国後プラハで手直しをしたという経緯から、故郷に戻ってきたドヴォルザークの喜びを謳い上げているようです。それに独奏チェロだけでなく管弦楽部も非常に活躍する作品で、特に管楽器がこれほどまでに美しい旋律を歌わせる協奏曲も珍しいのではないでしょうか。 「メロディ・メーカー」とも呼ばれたドヴォルザーク。 その美しい旋律がキラ星のごとく輝いている作品の一つがこのチェロ協奏曲ロ短調でしょう。ブラームスがこの曲を聴いて「私は何故こういう書き方に気がつかなかったのだろう」と絶賛した有名なエピソードが残っています。最初にドヴォルザークの最高傑作と書きましたが、おそらくチェロ協奏曲の最高傑作であることは間違いないと思います。 とても好きな曲です。愛聴盤大好きな曲ですから色々なチェリストの演奏で聴いてみたいという想いが強くて、他の協奏曲に比べてディスクの数も多くなっています。(1) ロストロポーヴィチ(チェロ) 小沢征爾指揮 ボストン交響楽団 (エラート原盤 ワーナー・ミュージック WPCS21056 1985年2月録音)朗々とした音色、スケール雄大な幅の広い表現が見事。 テンポを自在に動かし、音色を多彩に使い分けた演奏は独壇場。 最強音から最弱音までの情感豊かな表現。 絶え入るようなピアニッシモは圧巻。(2) ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ) アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団(マーキュリー原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7075 1962年7月録音)鋭利な刃物のような感じを与える音色で、朗々とした響きはロストロポーヴィチと変わらないが、非常に精緻な表現の音色で、一度聴くとたちまち人を引き付ける魔力のようなものを持った技巧の素晴らしいチェロ。(3) ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) バレンボイム指揮 シカゴ交響楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE59051 1970年5月録音)私が付け加える言葉がないほどに絶賛されている「世紀に一人」と言われる女性チェリスト。 激しい情熱が噴き出す物凄い演奏。 初めてLP盤で聴いた時には、言葉を失って聴いていた記憶があります。 1971年に26歳で難病の「多発性硬化症」を発病してから闘病生活をつづけ、1987年に42歳で亡くなった空前絶後と言いたくなる別格のチェリスト。(4) ピエール・フルニエ(チェロ) ジョージ・セル指揮 ベルリンフィルハーモニー (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5051 1962年録音) 「高貴なプリンス」と呼ばれたフルニエとセルが繰り広げる格調高い演奏。 ロストロポーヴィチやシュタルケルのような豪放さや荒々しさもない、実に品格のあるチェロで穏やかに、柔和にボヘミアの郷愁を切々と語った名演。(5) ピーター・ウィスペルウエイ(チェロ) ローレンス・ネレス指揮 オランダフィルハーモニー(CHANEL CLASSICS CCS8695 1995年12月録音 海外盤)「力強さ」と「優しさ」「柔和さ」で聴く者を柔らかく包み込んでくれるような表現のチェロの音色です。 ボヘミアの郷愁がを吹き渡るかのような音色が部屋を満たしてくれます。ロストロポービチやシュタルケルのような剛毅さでもなく、デ・ピュレのような情熱的な激しさでもなく、チェロの音色を汚れなく美しく響かせて、それでいて決してBGM的な音色にならずに、ステレオ装置の前でじっと耳を傾けて聴き入ってしまう、稀有な演奏家の一人です。(6) オーフラ・ハーノイ(チェロ) マッケラス指揮 プラハ交響楽団(RCAレーベル 09026 68186 2 1994年9月録音 海外盤)7枚のディスク中、最もテンポを自在に動かした演奏で、思い入れたっぷりな非常に個性的な演奏。 一時期よく日本で演奏会を開いていたが、最近は来日のニュースも聞かないがどうしているのだろうか。 彼女の演奏はヴァイオリンのソネンバーグのような奔放とまで言わないが、自在にテンポを動かして強弱をたっぷりと付けて「妖艶」な演奏が魅力。(7) アニア・タウアー(チェロ) マーツァル指揮 チェコフィルハーモニー(グラモフォン原盤 タワーレコード PROA62 1968年録音)タワーレコード ヴィンテージコレクション第3集の内の1枚。2006年12月のリリース、1000円盤。1945年(?)生まれのタウアー。 既婚の医師と恋愛関係となり原因不明の医師自殺で、相当なショックを受けて彼女も自殺をしたのではと言われている。謎の美貌のチェロ奏者。デュ・プレと同じ年齢。演奏は正攻法というかハーノイのような大きな動きをしない。しかし音は実に艶やか寝響きで力強く、ダイナミック。 デュ・プレのような演奏。 28歳で亡くなったというのが通説になっているが、この演奏を聴くとその若死にが惜しまれてならない。
2010年09月22日
コメント(108)
-
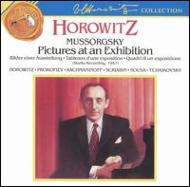
展覧会の絵
「名曲100選」 ムスルグスキー作曲 組曲「展覧会の絵」モデスト・ムソルグスキー(1839-1881)の代表作として最も有名な曲が組曲「展覧会の絵」です。「ロシア音楽」が音楽史上で言葉となったのは19世紀後半と言われています。 「ロシア五人組」と呼ばれている、ボロディン、リムスキー=コルサコフ、パラギレフ、キュイ、そしてムソルグスキーの5人を指してそう呼ばれています。この5人が書いたロシアの民族音楽・旋律・リズムが強烈にロシアを匂わせて独特の色彩を持った音楽として世に出たのです。その頃には欧州のあちらこちらから自国の民族音楽が、クラシック音楽作品の中に顕著に表現されるようになりました。 チェコのドヴォルザーク、ノルウエーのグリーグなどの作品がそれです。 ムソルグスキーはロシアの色彩濃厚な民族的音楽を書き残しています。彼の音楽のどれを切っても「ロシアの大地」があふれ出てくると表現してもいいほどに、最もロシア的な旋律と色彩を塗りこめた音楽に満ちています。42歳という若さで生涯を閉じたムスルグスキーは、晩年はアルコール中毒となり、貧困と精神錯乱状態にあえぎながら亡くなったと言われています。 そうした悲惨な晩年を支えてくれた友人が一人いました。ヴィクトル・ハルトマンというムソルグスキーと同年輩の芸術家で、建築や絵画で認められていた人だそうです。ムソルグスキーとハルトマンの親密な交友期間はわずか4年間だったそうですが、経済的に何の不自由もない医者の子であり、建築家・画家として地位を確立していたハルトマンは、生活苦の中にいるムソルグスキーに理解の手を差し伸べていた貴重な友人だったようです。そのハルトマンが心臓病のために37歳で急死したのです。 ムソルグスキーは嘆き悲しみ、友人にこんな手紙を書いているそうです。「ねえ、君、何という痛恨事だろう! 馬やねずみや犬が生きているのに、ハルトマンのような愛すべき友だちが亡くなるなんて!」友人たちによってハルトマンの遺作展覧会が1874年に開かれて、それを観たムスルグスキーが亡き友人の思い出のために個々の絵画を観た印象を書いたのがピアノ独奏曲、組曲「展覧会の絵」です。10枚の絵を採り上げているのですが、曲の冒頭に「プロムナード」が置かれており、今から絵を鑑賞しますよといった意味のテーマが演奏された後に第1曲へと移っていきます。 絵から絵に移るたびにこの「プロムナード」が効果的に表われてきます。私が最も好きな部分は「古城」の侘しげな表情を伝える旋律、目の前を通りすぎていくかのような描写の見事な「牛車」それに最後の壮大な伽藍を思わせる「キエフの大門」です。10枚の絵の印象をピアノで多彩に描いており、実に個性的な作品です。ピアノで紡ぎ出される1枚、1枚の絵の印象を頭の中で「どんな絵なんだろう」と想像することはとても楽しいひと時です。しかし、この曲はムスルグスキーの生前には公開で演奏されることなく、彼の死後6年を経て楽譜が出版されたそうです。現在最も人気のある曲の一つに数えられていますが、20世紀になってモーリス・ラヴェルやストコフスキーなどによって、このピアノ曲を管弦楽演奏用に編曲されていっそう華麗な色彩の音楽となって生まれ変わったからでしょう。特に「オーケストラの魔術師」と言われたラヴェル編曲版が最も有名で編曲版として定着しているようです。愛聴盤 (1) ウラディミール・ホロヴィッツ(ピアノ)(RCAレーベル 09026.60526 1947年録音 海外盤)原曲版ではなくて、ラヴェルの管弦楽版をホロヴィッツがピアノ版に編曲して弾いているので、原曲ピアノ版よりも色彩豊かに鳴り響いている音楽です。(2) エフゲニー・キーシン(ピアノ)(RCAレーベル 09026.63884 2001年録音 海外盤)オーケストラ版(ラヴェル編曲)ではフリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団(RCAレーベル BMGジャパン BVCC37146 1957年録音)その他にカラヤン指揮 ベルリンフィルショルティ指揮 シカゴ響トスカニーニ指揮 NBC響デュトワ指揮 モントリオール響ドラティ指揮 デトロイト響などの盤を聴いて楽しんでいます。
2010年09月21日
コメント(0)
-
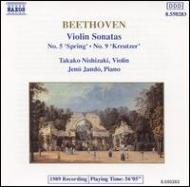
スプリング・ソナタ
「名曲100選」 ベートーベン作曲 ヴァイオリン・ソナタ第5番「スプリング」ベートーベン(1770-1827)はヴァイオリン・ソナタを10曲書き残しています。 そのちょうど真ん中に位置するこの第5番は、まだ「英雄」交響曲が完成される以前の1801年ごろに書かれたと推定されています。 この曲は副題として「スプリング(春)」と呼ばれていて、名前が付いていることからも知名度が高くなっていることは第9番の「クロイツェル」同様ですが、それだけではなく非常に完成度の高い作品に仕上がっていることと、ベートーベンにしては珍しく、あの肖像画に似つかわしくないほどの優しさに溢れ、誰の心も和ませる流麗な旋律に満ち溢れた作品です。肖像画からは堅物で気難しさが覗える性格ですが、この曲は優しさに溢れ心和むような流麗な旋律に満ちています。曲の冒頭でヴァイオリンが奏でる流れるような美しい旋律は、明るく晴れやかでベートーベンが書いた音楽の中でも屈指の名旋律だと思います。 この気分が全曲を通して貫かれており、ピアノ部分も伴奏の域から大きく飛び立って、ベートーベン自身の言葉通り「ヴァイオリンとピアノためのソナタ」であることは、音楽が明瞭に物語っています。この曲を「春」と呼ぶのは(日本だけでなく欧米でもそう呼んでいます)ベートーベンが名付けたのではなくて、誰かが後に名付けたと言われていますが、真に言い得て妙なる名前で、その命名の理由がわかるような、実に溌剌とした情感豊かな春の訪れの喜びをいっぱいに表現しているような名旋律です。4楽章構成で、この冒頭の気分が終楽章まで持続している、ベートーベンにしては珍しく喜びをいっぱに表現した音楽です。 愛聴盤 (1) 西崎崇子(ヴァイオリン) イエネ・ヤンドー(ピアノ)(NAXOSレーベル 8.550283 1989年録音)西崎のヴァイオリンは誰の耳にも心地よく響いてくる音色で、音楽を楽しんで弾いているような、特に技巧がずば抜けて素晴らしいという感じでもないのに、いつまでも聴いていたいと思わせる不思議な演奏で、無個性の個性と言いたくなるほど模範的ともいえる演奏です。 鈴木メソッドの一番弟子、世界で最も録音数の多いヴァイオリニストというキャッチフレーズ通り、普遍的な名演奏だと思います。 カップリングはベートーベンの「クロイツェル」ソナタ。私の知人でヴァイオリンを奏でる人の話。この西崎のCDを自分の先生に聴いてもらったそうです。 先生の感想「こんな演奏やったら私でも弾けるやん」でした。 それほどに何の個性も特色もない演奏なんですが、心和む演奏とはこういうものを指しているのでしょうか。(2) アルトゥール・グリュミオー(Vn) クララ・ハスキル(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP9521 1959年録音)高校生時代に初めてこの曲を、この演奏で聴いて以来長い間聴き親しんだ録音盤です。柔らかなグリュミオーとハスキルの音色はサロン風の温かい雰囲気でベートーベンの美しい旋律を紡ぎ出しています。(3) ダヴィッド・オイストラフ(Vn) レフ・オボーリン(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7040 1962年録音)この演奏もLP時代から長い間聴いてきました録音盤で、遅めのテンポで歌うオイストラフとオボーリンの力強く熱っぽい、ロマンティックな演奏に魅了され続けています。
2010年09月20日
コメント(0)
-
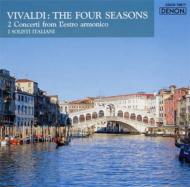
「四季」
「名曲100選」 ヴィヴァルディ作曲 協奏曲集「四季」アントニオ・ヴィヴァルディ(1678-1741)の代表作 「ヴァイオリン協奏曲集 四季」。ヴィヴァルディは、バロック音楽(チェンバロやチェロなどの通奏低音を伴う音楽で、1600年頃から1750年ごろまでの音楽)の代表的な作曲家で、1955年, 59年にイタリアのイ・ムジチ合奏団がフィリップス・レーベルに録音した、このヴィヴァルデイの協奏曲集「四季」のLP盤がリリースされて大ブレーク現象が起こり、バロック音楽が日本で確立した契機となった音楽です。 このLP発売と同じ時期にドイツからカール・ミュンヒンガーとシュトットガルト室内合奏団が来日して、バロックブームに火をつけたというタイミングもありました。 日本の音楽史上でこれほど大ブレークが起こり、その後40年間にもわたり愛し続けられた音楽というのは、おそらくこの「四季」だけではないでしょうか? それまでの演奏会、レコード界での定番は「運命」「未完成」「新世界」「悲愴」であり、突如現れた「四季」に人々は魅せられたのでした。高校2年生だった頃に25cmLP盤モノラル録音のイ・ムジチ合奏団の四季(1959年録音)を買って初めてこの曲を聴きました。 バロック音楽の愉悦と優雅さを初めて味わった喜びを今でも覚えています。「四季」は12の協奏曲集から成る「和声と創意への試み」という作品の中に含まれる最初の第1番~第4番の「春」「夏」「秋」「冬」という標題付き協奏曲集で、これを一まとめにして「四季」と呼ばれています。 ヴィヴァルデイ自身が名付けた副題ではありません。これら4曲はどれも3楽章構成で書かれており、それぞれの楽章にはソネット(小さな詩)が書き添えられています。 春夏秋冬の自然を描写したソネットで、その季節の気分を表しており、スコアにもその楽器が何を表現しているかが書き込まれています。 これをロマン派の標題音楽のルーツと見る人もいます。 それほど書き添えられたソネットと音楽がぴったりの協奏曲集です。 イタリアの春夏秋冬を見事に音楽で描写しており、曲はヴァイオリン協奏曲の形を採っていて、速いテンポと緩やかなテンポの音楽が交互に書かれており、華麗なソロ・ヴァイオリンと合奏部の掛け合いなどが魅力的な、ヴィヴァルデイ音楽の最も美しい姿を残す音楽です。耳にやさしく、心に愉悦を伝える極上のバロック音楽の代表作です。 愛聴盤 (1) イタリア合奏団(DENON CREST1000 シリーズ COCO70617 1986年録音)伝統のバロック音楽の流麗さを見事に表現した超優秀録音盤で、現在求め得る1000円のお買い得盤です。(2) チョン・キョン・ファ(Vn) オーケストラ・オヴ・セント・ルークス(EMIレーベル 557012 2000年9月録音 海外盤)これまでの「四季」演奏とは異なるインパクトの強いもので、リズムは強く、テヌートを多用して強烈な効果をあげており、21世紀のスタイルを示唆する画期的な演奏だと思います。
2010年09月19日
コメント(0)
-

クラリネット五重奏曲
「名曲100選」 ブラームス作曲 クラリネット五重奏曲有名作曲家とクラリネット奏者との邂逅の機会が,そのクラリネットの名曲を生んでいるという出来事があります。 モーツアルトには、あの「クラリネット協奏曲」や「クラリネット五重奏曲」がシュタットラーという奏者との出逢い、ウエーバーもやはりベールマンという奏者との出会いを機会に2曲の「クラリネット協奏曲」や「クラリネット五重奏曲」を書いています。このクラリネット五重奏曲もヨハネス・ブラームス(1833-1897)がマイニンゲンの宮廷オーケストラの首席クラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルトに出逢い、その音色に魅せられて書いたという有名なエピソードのある曲です。ブラームスにはベートーベンという偉大な先人が残した曲のために、作曲には非常に慎重になったようです。 ベートーベンの9曲の交響曲が彼の前に聳え立つように遺されていたために、ブラームスは第1番のシンフォニーを完成させるのに20年の歳月を費やしています。 ベートーベンと並び賞される、あるいは超える曲を書くのに苦労したのでしょう。室内楽曲でもやはりベートーベンの偉大な作品群の前に筆が鈍ったのでしょうか「弦楽四重奏曲第1番」を書いたのは40歳になってから、「弦楽五重奏曲」にいたっては57歳になってようやく作曲しています。音楽評論家の故門馬直美氏の畢生の大作「ブラームス」(春秋社刊)を読みますと、この「弦楽五重奏曲」を完成した57歳の頃(1890年)にはもう作曲意欲を喪失している 頃だったそうで、非常に寡作になって いた頃でした。そんな彼に創作意欲を奮い立たせたのが前述のクラリネット奏者ミュールフェルトでした。彼の美しい音色に魅かれてブラームスはクラリネットのための曲を書き始めました。 そして現代ではモーツアルトのそれと2大名曲として輝くほどの名作を書き残してくれました。この曲が書かれたのは、すでにブラームスに「人生の秋」が訪れていた頃ですから、非常に美しい旋律の中に、「諦観」めいた哀愁漂う曲となっていて、第2楽章などはジプシー風の音の響きが東洋的な渋みのある 雰囲気を漂わせています。 クラリネットと弦楽の絡むブラームス独特の寂しさを漂わせており、全曲にわたって人生の落日を思わせるかのような美しい曲です。 彼の交響曲第4番と同じように「人生のたそがれ」「人生の秋」を感じさせるクラリネットの名曲中の名曲です。 愛聴盤 アルフレート・プリンツ(クラリネット) ウイーン室内合奏団員(DENON CREST1000 COCO70673 1980年4月ウイーン録音)プリンツのクラリネットに魅せられる演奏です。 最高音から低い音までピッチはびくとも揺れることのない一貫した音色を保ち、ゲルハルト・ヘッツェル(Vn)などのウイーンフィルの弦楽奏者による、柔らかいウイーンの響きともいえるアンサンブルが聴く者をひきつけます。 カップリングは、同じくブラームスのクラリネット三重奏曲です。 私が聴いています盤はモーツアルトのクラリネット五重奏曲とのカップリングです。
2010年09月18日
コメント(0)
-
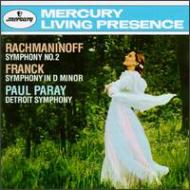
交響曲ニ短調
「名曲100選」 フランク作曲 交響曲ニ短調セザール・フランク(1822-1890)はベルギーで生まれた人で、ベルギーはフランス・オランダ・ドイツなどの近隣諸国の文化などから、多分に影響され反映してきた国で、言葉も自国語の他にフランス語、オランダ語、ドイツ語の通用するヨーロッパ(EU)特有の特質を持つ国の一つです。私は1970年代と1990年代に訪れたことがありますが、立ち寄ったレストランのメニューがフランス・オランダ・ベルギー語でした。 また街の建築、特に協会の建物がフランス風だったのが印象的です。フランクはパリの「パリ音楽院」で音楽の勉強を積み、後に「サン・クロティルド教会」のオルガン奏者として迎えられるほどのオルガン弾きの名手となり、彼も生涯オルガンを愛した音楽家でした。 彼の作品にはオルガン曲が多数あり、バッハのオルガン音楽と並び賞されるほどの曲が遺されています。 ブルックナーの音楽人生にも例えられる「大器晩成型」の典型で、世に有名となったのは50歳を過ぎてからでした。 この点は同時代のアントン・ブルックナー(1824-1896)と非常に似たところがあります。彼の音楽はフランス流の明快さとドイツ音楽の渋い、重厚さを兼備えている作品があり、ベルギーという国の伝統性がここにも表れているのでしょう。 この「交響曲ニ短調」は、フランクが書きました唯一のシンフォニーで、彼のフランスとドイツの融合した音楽の特質が明確に刻まれている曲です。彼はこの曲で音楽史上に画期的ともいえる「循環形式」を用いています。 この形式は初めに出てくる主題が全曲を通じて表れて、有機的に、まるで単一楽章のように音楽を構成しているのが特色です。 のちにフランスの交響音楽に大きな影響を与えています。音楽はフランス風の軽快さ、明快さとオルガンを愛したフランクらしい重厚な響きに溢れており、バッハ、ベートーベン、ブラームスなどのドイツ音楽にも表れている強固な音の積み重ね、重厚な音響などドイツ音楽の影響というか、ベルギーという国自体がドイツやフランスに似た面が数多く遺されていることを物語る音楽の一つだと思います。愛聴盤 (1) ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団(マーキュリー原盤 ユニヴァーサル・ミュージック 434368 1958年録音)ステレオ初期の録音ですでに50年以上を経過していますが、最新録音であるかのような優れた音質で、演奏もパレーの指揮を代表するかのように「淡白でストレートに」音楽が重なって行く様は何度聴いても圧巻。LP時代から愛聴している演奏・録音です。ラフマニノフ 交響曲第2番が併録されています。(2) ジャン・マルティノン指揮 フランス国立管弦楽団 (エラート原盤 ワーナーミュージックジャパン WPCS21022 1968年録音)LP時代から好きな演奏で実に爽やかな肌触りで全編を楽しめるディスクです。現在はワーナーミュージックからこの型番で1000円盤としてリリースされています。サン=サーンス 交響曲第3番が併録されています。
2010年09月17日
コメント(0)
-
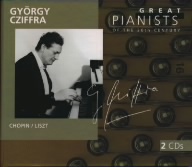
練習曲集
「名曲100選」 フレデリック・ショパン作曲 「練習曲」集ポーランドの「ピアノの詩人」フレデリック・ショパン(1810-1849)が書いた「エチュード集(練習曲集)。 ピアノを習う人、練習する人ならチェルニーやハノンといった指使いのための「練習曲」で音階練習をしていますが、今日採り上げますショパンの「練習曲」(エチュード)はそうした教則本の類ではなくて、曲自体に風情や情緒、感情が盛り込まれている曲で、情感豊かな「練習曲」です。 練習曲で実用的な題材ながらも深い芸術性を湛えていて、ショパンの偉大さを表している曲集です。「練習曲集」は作品10と25に、それぞれ12曲ずつ作曲されており、他に作品番号の付されていない3曲があるので、計27曲からなる曲集です。39歳という若死にですから、これらの曲は19歳から26歳に間に作曲されており、この二つの曲集には副題が付けられているのが多くあります。作品10の第3番「別れの曲」、 第5番「黒鍵」、 第12番「革命」などや、作品25の第1番「エオリアン・ハープ」、 第9番「蝶々」、第11番「木枯らし」などがあります。 特にポーランドを離れてパリに行き(1830年20歳)、祖国がロシアに占領されてしまい、二度と祖国の土を踏むことのなかったショパンのふつふつとした情念が噴き上げてくるような「革命」(1832年作曲22歳)には、嘆き、悲しみ、怒りのような情感が伝わってくるようです。また「別れの曲」は有名なピアノ協奏曲(2曲)とほぼ同時期に書かれていますので、当時彼が想いを馳せていた女性コンスタンチア・グラドコフスカへの惜情の想いでしょうか。深い精神性と豊かな情感の溢れるこれらのエチュードを今日は聴いてみたいと思います。愛聴盤ジョルジュ・シフラ(ピアノ)(Philips原盤 456 760-2 1962年録音 海外盤)10年ほど前にレーベルを超えて「20世紀の偉大なピアニストたち」という100組(200枚)のCDがリリースされました。国内プレス盤は当時270,000円という高値だったのですが、HMVから電話で輸入盤なら35,000円で販売します、と連絡をもらい早速購入しました。勿論重複するピアニストの録音もありましたが、それには目をつぶって買いました。その中の中の1枚がこのシフラ演奏の「練習曲集」全曲です。 おそらくこのブログでシフラの演奏を紹介するのは初めてだろうと思います。 超絶技巧を誇るピアニストで、私が高校生の頃はリスト弾きとして有名なピアニストでした。アシュケナージの演奏と共に聴いています。
2010年09月16日
コメント(0)
-
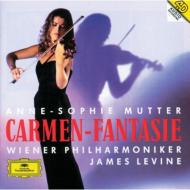
ツィゴイネルワイゼン
「名曲100選」 サラサーテ作曲 「ツィゴイネルワイゼン」パブロ・サラサーテ(1844-1908)と言えば「ツィゴイネルワイゼン」。 パガニーニもそうでした。超絶技巧を誇るヴァイオリニストであったようです。ピアノではリスト。 彼らは自分の得意の楽器を演奏するだけでは物足らず、作曲それも超絶技巧を駆使して作曲をして演奏家として作曲家として名声を確立しています。サラサーテも自分のヴァイオリンの技巧を示すために、「アンダルシアのロマンス」「カルメン幻想曲」や「マラゲーニャ」などの技巧曲を書いており、この「ツィゴイネルワイゼン」もそのうちの1曲です。曲はハンガリーのジプシー音楽や民謡を素材にしています。 大きく分けて前半の「ハッサン」と後半部の「フリスカ」で構成される「チャルダッシュ」というハンガリーの舞曲形式をとっています。前半の「ハッサン」は2部構成で、緩やかな哀愁に満ちた憂いいっぱいの旋律で彩られた第1部、弱音器を付けて甘く、美しく奏でられる旋律の第2部で、ヴァイオリンのむせび泣くような音色に胸をしめつけられるような魅力がありあます。後半は速いテンポの「フリスカ」で、ヴァイオリンの目の覚めるような技巧が華麗に繰り広げられています。 曲名はドイツ語の「ツィゴイナー」から由来しており、これは「ジプシー」を意味しています。ジプシーと言えば、スペインやハンガリーを思い起こす人が多いと思います。私もそのうちの一人でした。 学生時代に読みました中央公論社の「世界の歴史」を読むまでに、ジプシーの起源はスペインか、ハンガリーだと思っていました。この曲の解説(当時のLP盤)にもハンガリーの民族音楽としか書かれていなかったからです。ジプシーの起源は、インドの北西部にあるパンジャブ地方に住んでいたアーリア系民族が起源とされています。 彼らの一部はパンジャブ地方から、シルクロードの中継地であったタール砂漠に移住していったのです。10世紀頃、タール砂漠(ラジャスターン地方)から、西へ西へと移動し始めた民族は、ロマと呼ばれていたそうです。 このロマがジプシーにあたる言葉です。彼らは居住地を定めず、特定の宗教を持たず、特定の伝承も文字も持たない民族で、独特の民俗・慣習(ヒンドゥのカースト制度に由来すると言われる職業階級、同族同士の内婚など)は厳格に守られているそうです。職業は、行商や馬具・金属の加工、修理業(自動車の修理、解体業)、馬の売買(今は中古車売買)に従事する人たちが多くいます。しかし、芸能に関わり、占星術、遊芸や舞踊などを職業とするロマが有名です。俳優の故ユル・ブリンナーは、ロマ出身です。彼らはイラン、トルコなどで定住したのち、14世紀末~15世紀初頃にバルカン半島にまで到達して、ブルガリアやマケドニア周辺から欧州各地、ロシアや北アフリカなどに分布していきました。インド北部から始まったジプシーの旅は500年をかけてこうした地域にまで足を延ばしていました。ジプシーの歴史に想いを馳せながら「ツィゴイネルワイゼン」を聴いています。愛聴盤 アンネ・ゾフィ=ムター(Vn) ジェームス・レヴァイン指揮 ウイーンフィル(ドイツ・グラモフォン 437554 1992年録音)先日ラロの「スペイン交響曲」紹介時に掲載しましたムター盤は1984年録音でした。その8年後にウイーンフィル、レヴァインの指揮で録音したのが当盤で、音質ははるかにこの盤が勝っており、演奏も旧盤よりも濃厚にジプシー音楽を表現しており、「タイスの瞑想曲」、ベートーベンの「ロマンス」などが収録されています。
2010年09月15日
コメント(0)
-
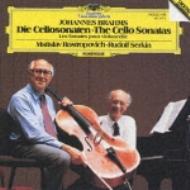
チェロ・ソナタ
「名曲100選」 ブラームス作曲 チェロ・ソナタ第1番 ホ短調ヨハネス・ブラームス(1833-1897)は室内楽作品を書き残してくれています。 3曲のヴァイオリン・ソナタ、2曲のクラリネット・ソナタ、2曲の弦楽6重奏曲などがあります。そしてチェロ・ソナタも2曲書き残しています。 今日は第1番ホ短調を採り上げました。私は「ブラームス大好き人間」で、おそらくベートーベンよりも好きだと思います。 何故? ブラームスのくすんだ、翳りのある、分厚く、渋い音色に魅かれるのでしょうね。 交響曲、ヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲、ヴァイオリン・ソナタやチェロ・ソナタなどの室内楽、ピアノ曲、どれを採ってもこれらの形容詞があてはまる曲ばかりです。 日本のお寺で言えば、奈良や京都の観光客がいつも訪れる有名なお寺でなく、名刹ではあるけれどどこか寂れた趣きがあり、壁などの漆喰にくすんだ風情のあるお寺。 ブラームスの音楽にはそういう、くすんだ名刹の風情がオーヴァーラップしてきます。 そういう趣きの音楽に弾かれます。さて、今日の話題曲のチェロ・ソナタ 第1番ですが、これはもう「渋い」としか言いようのない曲で、まさに上に書いた情緒そのままの音楽です。 第1に、楽器がチェロですからヴァイオリンに比べると、一段と渋い音色になります。 そこへ北ドイツのようなくすんだ色彩に溢れた音楽が展開するんですから、渋さに渋さを重ねたような趣きです。 しかし、ブラームスのどの音楽にも言えることですが、「渋さ」の中にブラームス特有の熱いたぎりが秘められていて、そこが彼の音楽のたまらない魅力になっています。 クララ・シューマンへの密かな想いが影響していると言う人もいますが、私はブラームスが北ドイツの生まれであることが、彼の音楽の特質に多大の影響を与えていると思います。曲の冒頭第1楽章で、第1主題が独奏チェロで歌い出されると、もういきなりメロメロの状態になってしまいます。とても穏やかで、たおやかな情緒でありながら、もの寂しさいっぱいの情感に包まれており、ピアノに受け継がれて音楽が昂揚していきます。心に染み込んでくるような抒情的な旋律とその展開に酔ってしまいます。第2楽章は、哀愁のただようメヌエットで、侘しさや寂しさを湛えた音楽で、これは1865年2月2日に亡くなった母への哀悼の歌とされています(この曲は1865年夏に完成しています)。第3楽章は、フーガ構成のような音楽が展開していきます。第1主題はバッハの「フーガの技法」から採られていると言われています。劇的に昂揚しながら、チェロとピアノが熱いたぎりをみせて燃焼していく様は感動的です。愛聴盤(1) ムスティラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ) ルドルフ・ゼルキン(P)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG1119 1982年録音)現在この商品番号で入手可能かどうかは調べていません。すみません。(2) ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ) ダニエル・バレンボイム(P)(EMI原盤 EMIジャパン TOCE14092 1967年録音)現在国内プレス盤として入手可能なディスクです。
2010年09月14日
コメント(0)
-
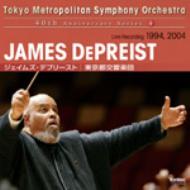
交響曲第2番
「名曲100選」 ラフマニノフ作曲 交響曲第2番ホ短調 セルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)はロシアの香りをいっぱいに携えて、その薫りをふんだんに散りばめた、叙情性に溢れた美しい音楽を数多く書き残した作曲家でした。 まさに上品で気品の漂う音楽がロシア・ロマンティシズムに包まれて濃厚な気分で表現されています。ラフマニノフは12歳からモスクワ音楽院で学ぶほどの、「天才的」な音楽家であったようで、チャイコフスキーとも面識があり、尊敬をしていたようです。 だからラフマニノフの音楽はチャイコフスキーの作風を受け継ぐかのような濃厚な、ロシアの哀愁を歌い上げていますが、ラフマニノフの音楽にはどこか上品さとか気品とかのエレガントな美しさ・情緒を醸し出しているのが、チャイコフスキーの音楽との大きな違いであるように感じます。ロシア帝政時代の貴族の生まれであったラフマニノフの子供時代からの育った環境というものが、色濃く彼の音楽に映し出されているように思えます。ラフマニノフは1897年(28歳)に交響曲第1番を発表しましたが、酷評とも言われるほどの不評が彼を精神的病苦に追い込まれてしまいました。 それまでにはピアノ協奏曲第1番が初演されて、新鋭作曲家として音楽界に迎えられていただけに、また自信を持って発表した第1番の交響曲だったようで、繊細な神経が災いしてノイローゼとなってしまい、2年間ほどは全く作曲活動が出来ないほどだったようです。その彼を救ったのがニコライ・ダール博士という催眠療法の名医でした。 ダール博士はラフマニノフをわずか4ヶ月でもとの精神状態に戻したのでした。 そして再び作曲意欲に燃えて書かれたのが、最も有名な「ピアノ協奏曲第2番」でした。 1901年10月の初演が大成功に終わり、彼は作曲家として、ピアニストとして再び栄光の道を歩み始めました。しかし、その頃のロシアは帝政の歪みが現れ始めており、騒がしい世の中に変化して行き、彼自身も病を患って静養を兼ねてドイツのドレスデンに移りました。 そこで書かれたのが今日の話題曲の交響曲第2番ホ短調 作品27でした。 そして1907年の春に曲が完成しています。「ピアノ協奏曲第2番」で大成功を収めたあとの交響曲で、全体に濃い、ロシア的なリリシズムに彩られた音楽で、第2番の協奏曲の作風をそのまま踏襲しているかのような暗く、切ない、ロマン的な、まるで映画音楽のような美しい旋律が、全楽章を覆っている音楽です。叙情的な旋律に満ちており、音楽の色彩感は豊穣で、ロシア的なメランコリックな情緒が漂う、濃厚なロマンティシズムに包まれた音楽です。特に、第3楽章の「アダージョ」は有名で、メランコリックで、甘く、濃厚なロシア的なロマンの薫りが匂い立つような音楽で包まれた楽章です。 私はその美しさはチャイコフスキーの音楽以上だと感じています。 ドレスデンで書かれたこの曲は、ラフマニノフにとっては望郷の想いだったのかも知れません。映画広告風な言葉ですと「ハンカチをご用意下さい」楽章で、失恋した人、誰かを亡くした人、ブルーな気分の人、落ち込んでいる人は聴かない方がいいかも知れません。 それほどに聴く人の心に、甘美な寂寥感が入り込んでくるアダージョです。 ハンカチがやはり必要でしょうね。逆に愛する人と聴くときは、優しく懐に包まれて聴きたくなるような気分にさせる音楽です。愛聴盤 ジェイムズ・デブリースト指揮 東京都交響楽団(FONTECレーベル FOCD9240 1994年11月7日 東京文化会館ライブ録音)凄い演奏が現れたものだと買ってすぐに聴いた感想でした。 今までにスヴェトラーノフ盤、オーマンディ盤、ポール・パレー盤、プレヴィン盤、ザンテルリング盤、それにジンマン指揮のボルティモア管の生演奏などで、随分と素晴らしく、美しい演奏を聴いてきましたが、今までの演奏が何だったのかと思うほどの素晴らしい演奏で、しかもこれが定期演奏会の録音であることに驚きです。ラフマニノフ特有の息の長いフレーズをしなやかに歌わせており、情熱的な第2楽章も決して大げさにならず慎ましやかでありながら、ラフマニノフの情熱がどのフレーズにも息づいているような表現が素晴らしく、特に第3楽章の「アダージョ」は都響を自在に操りながら、長い美しいフレーズを連綿とした情緒で歌わせています。しかもこの時の演奏会がデブリーストと都響のデビューだったと知って、なお更驚いた演奏です。
2010年09月13日
コメント(0)
-
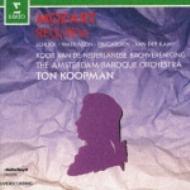
レクイエム
「名曲100選」 モーツアルト作曲 「レクイエム」ニ短調「レクイエム」作曲を始めたのはモーツアルト(1736-1791)が亡くなった1791年の7月頃のことだと言われています。ちょうどオペラ「魔笛」を書いていた頃だそうです。 その作曲の経緯はこうです。1791年のある日のこと、灰色の服を着た、痩せた背の高い男がモーツアルトを訪ねてきました。 何か不気味なオーラに包まれた感じの男だったそうです。 彼はモーツアルトに「私のご主人様があなた様にレクイエムの作曲を依頼致しております」と言って、多額の謝礼金を差し出したのです。依頼主の名前を一切明かさずに、モーツアルトが承諾するとすぐに帰って行ったそうです。この名前のわからない高額の「レクイエム」作曲依頼と不気味な感じの使いの男によって、モーツアルトは次第にこれを「地獄の使者」のように感じて脅迫観念に獲り付かれように感じたそうです。モーツアルトは、死の年には多額の借金を抱えており、この作曲の高額依頼は渡りに船と言った感じでした。そしてその年の9月にオペラ「魔笛」の初演が終わると、この「レクイエム」の作曲にとりかかったそうです。その頃には起きて曲を書き続けることが難しくなってきたほどに、彼の体は衰弱が激しくなってきて、とうとう床に就いてペンを走らせる事態になり、弟子のジュスマイヤーに「この曲は僕自身のために書いているんだ」と言うほど、自分の死が遠くないことを自覚していたようです。そしてその年の12月4日の夜、モーツアルトは八小節で止まっている「ラクリモザ(涙の日)」の楽譜をジュスマイヤーに見せながら、涙ながらに残りの音楽を書く指示を与えて、数時間後の12月5日午前零時55分に息を引き取ったそうです。 彼の言葉通り、この「レクイエム」はモーツアルト自身の死を弔う曲となってしまいました。ウオルフガング・A・モーツアルトはこうして1971年12月5日、35歳の若過ぎる死でその生涯を閉じています。愛聴盤 (1) トン・コープマン指揮 アムステルダム・バロック管弦楽団 オランダ・バッハ協会合唱団(エラート原盤 ワーナーミュージック WPCS-11102 1989年10月ライブ録音)(2) カール・ベーム指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団・合唱団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG4639 1971年録音)(1)は1000円盤 (2)は現在国内プレス盤として入手可能なディスクです。
2010年09月12日
コメント(0)
-
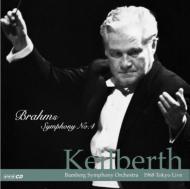
ティル
「名曲100選」R.シュトラウス作曲 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」私がリヒャルト・シュトラウスという作曲家を知ったのは1962年、高校2年生の頃でした。 そのときはあの有名な「ワルツ王」と呼ばれたヨハン・シュトラウス一家の人で、同じようにワルツを作曲している人かと思ったものでした。何故か理由を覚えていないのですが、この人の書いた交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(以下テイルと略します)という曲があることを知って聴きたくなり、カール・ベーム指揮のドレスデン国立歌劇場管弦楽団のモノラル録音の45回転EP盤を買って聴いたのが、最初のリヒャルト・シュトラウス体験でした。 この体験を何故自分から望んだのか今もって不明です。曲を聴いてこの人のオーケストレーションをいっぺんに好きになりました。それまで聴いていたハイドン、モーツアルト、ベートーベンやブラームス、チャイコフスキーなどの曲とは次元が違う音楽で、華麗で精緻な音の響きに魅了されました。それからはこのR.シュトラウスの曲のLP盤がリリースされる度に指をくわえて我慢の子でした。その頃はちょうどイタリア歌劇団が来日して、イタリアオペラにも夢中になっていた時代で、とても両親から何枚ものLP盤を買ってもらうことができなかったので、「レコード藝術」や朝日新聞などで紹介されるシュトラウス音楽の記事を読んでいるに過ぎない時が過ぎていきました。そして大学生になってから友人がオープンリールのテープレコーダーで、「ツァラトゥストラはかく語りき」を聴かせてくれて、すっかりシュトラウス音楽の魅力にとりつかれてしまいました。そんな折のこと、名指揮者ヨゼフ・カイルベルトが手兵のバンベルグ交響楽団を率いて来日、その時に東京に居ました私は上野の東京文化会館に足を運びました。 1968年5月20日のことでした。プログラムはこの交響詩「ティル・・・」、ハイドンの「時計」交響曲、ブラームスの第4番の交響曲でした。 ブラームスも目当ての曲でしたが、何と言っても「ティル」でした。 これが生演奏でしかもドイツの名門オケとカイルベルトですから、当日までに興奮気味の日が続いていたのを今でも覚えています。今でこそR.シュトラウスを演奏するコンサートがあっても、皆さんはさほど興奮もしないと思います。 日本のオケもうまくなり、これを演奏することは難しくない時代になっていますし、レコード・CDは夥しい数の演奏がリリースされています。しかし、1968年はまだこの曲はマイナーだったのか、曲の終わり部分であたかも終わったかのように音楽が途切れる部分があります。そこで聴衆の半分くらいが拍手をするというような時代でした。 オイゲン・ヨッフムが初めてアムステルダム・コンセルトへボーを率いての来日公演(1965年?)でも、この曲を演奏したのですが、彼が客席を振り向いて「シー」という仕草をやったという嘘のような、本当の話があるくらいに、この曲はまだまだマイナーでした。話は逸れましたが、この演奏には心も体も震えるほどの感動を味わいました。R.シュトラウスの見事な、美しく、精緻なオーケストレーションに客席で、音楽に酔っているのかのような至福の時を過ごしていました。この音楽の物語は1500年ごろのドイツの民話で、いたずら好きなティルが様々な悪いことをやって、最後には捕まって死刑になるのですが、その物語をわずか15分間くらいの音楽で描写した交響詩です。 そのいたずら振りを彼特有の華麗で、豊穣な響きに満ちたオーケストレーションで描いています。R.シュトラウスの音楽は管楽器、特に金管楽器が重要な役割を持たされていて、その響きやハーモニーがことのほか美しいという特徴がありますが、この曲も同じです。金管楽器や打楽器が非常に効果的に用いられていて、情景が膨らむかのように描き出されています。この音楽はディズニーの「ファンタジア」のようなアニメにして、音楽とアニメを一緒に味わえたら最高に面白いだろうと常々思っています。愛聴盤 (1) ヨゼフ・カイルベルト指揮 バンベルグ交響楽団(キングレコード KICC 422 1968年5月20日 東京文化会館ライブ録音)このCDは上述しました、私が客席で聴きました演奏会の録音で音源はNHKです。 当時FMでも放送されて大変話題になった演奏会です。ハイドンのみ収録されておらず、アンコール曲のワーグナーの「ニュルンベルグのマイスタージンガー」前奏曲も収録されています。(2) ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG70017 1986年録音)R.シュトラウスと言えばカラヤン、という私の心には定番となっている指揮者で、60年代のウイーンフィルとの録音、1970年代のベルリン・フィルとの録音と3枚も聴き比べをしていますが、一番音のいい状態がこの86年盤なのでここに紹介しました。このほかにルドルフ・ケンペ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン、アンタル・ドラティ指揮デトロイト響の演奏も楽しんで聴いています。
2010年09月11日
コメント(0)
-

八重奏曲
「名曲100選」 シューベルト作曲 八重奏曲ヘ長調 D.803先人、先輩の芸術作品を範として後の人や後輩が作品を作るということがありますが、今日の話題曲のフランツ・シューベルト(1797~1828)が書き残しました「八重奏曲」もその典型的な一つの例かも知れません。この曲は室内楽というジャンルに属する音楽ですが、室内楽とは2つ以上の楽器で演奏される音楽を指して呼んでいます。 例えばヴァイオリン・ソナタ。 これは正確には「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」と呼ぶのが妥当かも知れません。 ベートーベンのヴァイオリン・ソナタは彼自身がそう楽譜に書いています。ピアノ三重奏曲や弦楽四重奏曲など小編成の曲があれば、もっと大きな規模の室内楽曲もあります。 例えばメンデルスゾーンの弦楽八重奏曲やベートーベンの七重奏曲などがあります。 それにモーツアルトの「セレナード K.388」や「ディヴェルトメント K.251」などもあります。シューベルトはピアノ三重奏曲やピアノ五重奏曲、それに弦楽四重奏曲などを書き残していますが、大きな規模の室内楽はこの曲の作曲以前には書いていません。 彼が何故こうした大編成の室内楽を書こうとしたのか、その理由は明確ではありませんが、作曲にあたりベートーベンが若いときに書いています七重奏曲作品20を範として書いたと言われています。同じ6楽章形式であり、楽章の型などもよく似ています。 アダージョの序奏つきアレグロであったり、第2楽章はアダージョだったり、第4楽章は変奏曲だったり、クラリネットを際立たせていたり(第2楽章)、ベートーベンの七重奏曲とよく似ています。 楽器編成では、シューベルトは第2ヴァイオリンを付け加えて八重奏曲としているだけで、2つのヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、クラリネット、ホルン、ファゴットから編成されていて、第2ヴァイオリンを除いてベートーベンの七重奏曲と同じです。一説には当時のクラリネット好きの伯爵から「ベートーベンに似た作品」の作曲依頼をされたためとも言われています。音楽はシューベルト特有の、豊かな情感と泉が湧き出るかのような美しい旋律にあふれ、弦と管楽器が織り成す多彩に変化するハーモニーの美しさが室内楽を聴く醍醐味を味合わせてくれます。 演奏時間約60分の大曲です。愛聴盤 ウイーンフィル管楽器奏者とウイーン弦楽四重奏団(Camerataレーベル 30CM-470 1997年4月ウイーン録音)
2010年09月10日
コメント(0)
-
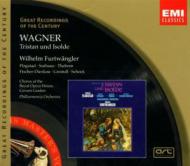
トリスタンとイゾルデ
「名曲100選」 ワーグナー作曲 楽劇「トリスタンとイゾルデ」ヨーロッパには中世の「トリスタン伝説」という物語が語り継がれていたそうです。 この「トリスタンとイゾルデ」はその伝説を基に書かれた楽劇で、物語は中世。 アイルランドの王女イゾルデは、政略結婚の犠牲となりイングランドのマルケ王の許に嫁ぐために船で祖国を離れます。 舞台はその船から始まります。 イゾルデを迎えに来たのはマルケ王の甥であるトリスタン。 以前トリスタンと、イゾルデの婚約者である公爵が決闘をして、トリスタンは傷つきます。 秘法の治療を知るイゾルデはトリスタンに好意を持ち、傷を治して逃がしてやります。 しかし、自分の意思とは関係なしにマルケ王に嫁ぐ際の迎えがトリスタンとは。 再会した二人は複雑な心境であり、イゾルデは毒酒を呷って死んで二人で清算しようと図りますが、イゾルデの侍女ブランネーゲが毒酒の変わりに「愛の酒」を二人に飲ませてしまいます。やがて二人はこの酒によって愛するようになるが、イゾルデはマルケ王妃。 それでも二人は愛の焔を燃やし続けますが、ついにマルケ王に知れることとなって、トリスタンは死に、イゾルデも「愛の死」を歌って幕となります。簡単に物語を書きますとこんな風になるのですが、この楽劇の特徴の一つに登場人物の少ないことが挙げられます。 こうした物語の筋が人物によって語られていきます。 また舞台装置も簡素な上演がほとんどで、この楽劇が深い精神性ー男女の満たされぬ愛ーを湛えていることを象徴しているようです。この楽劇を書くきっかけになったのは、ヴェーゼンドンクという富裕家がいて、若い美貌の妻マティルデからせがまれて1軒の住居を、スイスのチューリッヒに提供します。 当時はワーグナーは結婚しておりお金に窮する生活であったので、その住居に妻と引越しますが、妻との間はもうとっくに冷え切っていたそうで、ワーグナーとマティルデ・ヴェーゼンドンクの間に愛が芽生えていきます。 しかし、許されぬ恋・愛でした。直接には関係がないかも知れませんが、この時のワーグナーの心情が「トリスタン伝説」を音楽化・楽劇化したいと思ったきっかけであるように思われているそうです。イタリア・オペラやこれ以前のワーグナーのオペラ「タンホイザー」「ローエングリン」のように、一つのアリアが区切りを示すような表現でなく、音楽は数多くの動機(風景、人物の心などを表している短い音楽)によって繋がっていき(示導動機・ライトモチーフ)、まるで音楽の流れ・旋律が無限のように書かれています(無限旋律)。全曲演奏には4時間近くかかる長大な楽劇です。 音楽は、許されぬ二人の愛の絆と、愛と官能に陶然としていく様を、まるで糸の紡ぎ合いのように、しかもそれが巨大な波のうねりのように大きくなって、旋律は休みなく昂揚していく様は、聴く方が麻薬に取り付かれたような、痺れるような感動・快感を味わいます。 とりわけ、「愛の酒」を飲んだ第1幕の幕切れから第2幕の二人の「愛」を歌う場面は、音楽史上にこれ以上ないと思われるほどの官能にむせ返る音楽に圧倒されます。初めて聴く人には難解なオペラ(楽劇)かもしれませんが、この愛の陶酔に溺れ、許されぬ二人の終末までの「無限旋律」にはまってしまいますと、もうワーグナーの世界から抜け切れない、それこそ彼の仕掛けた「酒」に溺れてしまいます。 所謂「ワグネリアン」となって行くことでしょう。ところでワーグナーと例のマティルデ・ヴェーゼンドンクですが、彼女の夫に知られることになり、ワーグナーはこの「住居」を去っていきます。そして二人の愛がワーグナーに作曲意欲をかきたたせたこの「トリスタンとイゾルデ」は、ドイツ・ミュンヘンの宮廷劇場で1865年に初演されています。この初演の指揮者が、名指揮者と言われたハンス・フォン・ビューローなんですが、まだ話は続きます。 マティルデの許を去ったワーグナーは、今度はビューロー夫人のコジマ・ビューローと恋仲に陥り、駆け落ちまでした後、めでたく夫婦となります。 そして、このコジマこそがあの大作曲家フランツ・リストの娘なのです。そうして二人は仲むつまじく暮らし、ジークフリートという息子を授かります。 息子誕生後の妻コジマの誕生日に自宅階段で、お祝いの曲「ジークフリート牧歌」を初演したエピソードはすでにこのブログで紹介しています。 その頃のワーグナーには、もう「トリスタンとイゾルデ」の「愛の形」とは違う「平安な愛」に囲まれていたのでしょう。愛聴盤 (1) フルトヴェングラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 キルステン・フラグスタート(S) ルードヴィッヒ・ズートハウス(T) ヨーゼフ・グラインドル(Bs) コヴェントガーデン王立歌劇場合唱団(EMI原盤 東芝EMI TOCE11318~21 1952年録音)(2) カール・ベーム指揮 バイロイト祝祭管弦楽団・合唱団ヴォルフガング・ウイットガッセン(T) ビルギット・ニルソン(S)マルッティ・タルヴェラ(B) クリスタ・ルードヴィヒ(Ms)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG3848 1966年ライブ)
2010年09月09日
コメント(0)
-
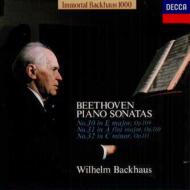
ピアノ ソナタ第31番
「名曲100選」 ベートーベン作曲 ピアノソナタ 第31番変イ長調 作品110ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーベン(1770-1827)はピアノ・ソナタを32曲書き残しています。これら32曲のソナタを後世の人は「ピアノ曲の新約聖書」と呼ぶほどに、これらの32曲のピアノ音楽には、「楽しみ」から「威厳の確立」とも呼べる程に孤高の厳しさのにじみ出ている見事な音楽空間があります。この第31番のソナタが作曲されましたのは1822年とありますから、彼の死の5年前で難聴は進み内臓疾患なども患っていた頃に書かれた作品です。 ベートーベンの作曲時期を3期(前期、中期、後期)に分けて論じられていますが、その意味では勿論この曲は晩年の作品であり、特に最後の30番、31番、32番は後期3大ソナタと呼ばれており、それまでのピアノソナタとは一線を画して論じられています。32曲書かれたソナタのうち、この後期3大ソナタを聴きますとそれまでの作品とは明らかに作風が異なっています。それまでの音楽形式にとらわれず、最後のソナタ、第32番などは自由な形式で書かれていること、そうした形式・手法から生まれてきたベートーベン晩年の想いが、詩的な情感の豊かさにあふれています。この第31番は美しい叙情性と終楽章に聴かれる深い精神的内面の吐露が交錯する清澄な音楽で、いっそう詩的な雰囲気・表情が漂っています。自ら色々な病に冒されながら、ひたすら忍耐と立ち向かっていく気迫と悲哀の感情が、ベートーベン自らスコアに書いた「嘆きの歌」と呼ばれる終楽章のアダージョは、特に私は胸を打たれる思いで聴いてしまいます。この楽章は「フーガ楽章」と呼ばれるベートーベンの独創的な形式で書かれており、長大な序奏のあとに、「嘆きの歌」と呼ばれる悲痛な想いのような旋律が奏されて、やがてフーガの部分となり、そのフーガのあと、もう一度「嘆きの歌」が戻ってきます。そして最後にフーガへと戻り、堂々とした音楽で曲を閉じています。そうした音楽の終わらせ方にベートーベンが悲嘆にくれているのではなく、それに立ち向かっていく気迫のようなものを感じます。辛い時、哀しい時など心が沈んでしまいそうな時に聴きますと、私は随分と励まされるピアノ音楽の名曲です。 まさにベートーベンが登りつめた、第32番と共に孤高の境地の最高傑作だと思います。 愛聴盤 (1) ウイルヘルム・バックハウス(ピアノ) (DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD9163 1963年録音)(2) ルドルフ・ゼルキン(ピアノ)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCG2043 1987年ウイーン・ライブ)両盤とも第30番、31番、32番の最後の3大ソナタが収録されています。
2010年09月08日
コメント(0)
-

ヴァイオリン協奏曲
「名曲100選」 シベリウス作曲 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調ヴィヴァルディなどのバロック音楽時代を経て、バッハ、モーツアルトに受け継がれてきたヴァイオリン協奏曲が、「サロン風」音楽から劇場型音楽に変えたのがベートーベンでした。 音楽は優美さと雄渾さ・雄大さが備わった協奏曲が、やがて交響楽的な響きのブラームスの協奏曲が生まれてきました。その後ロマン派作曲家の、ヴァイオリンという楽器の特性をフルに生かした個性ある美しい曲の数々が生まれてきました。 メンデルスゾーン、ブルッフ、ラロ、チャイコフスキー、ドヴォルザークなどを経て、20世紀にはバルトーク、プロコフィエフ、グラズノフ、ストラビンスキー、ハチャトリアン、ショスタコービチなどに受け継がれてきました。その中でもシベリウスの協奏曲は人気があり、ヴァイオリニストたちの心をかきたてる曲の一つとして演奏会や録音でよく採り上げられています。シベリウスの祖国フィンランドは「湖沼の国」と呼ばれるくらいで千の湖と深い森林に覆われた国です。国土の70%が原始林に占められており、ごつごつとした岩だらけの風土に、暗い厳しい寒さという、過酷な自然環境に包まれています。シベリウスの作曲した交響曲や交響詩などは、こうしたフィンランドの森、湖を想像させるような情緒を醸し出した音楽で、清冽な美しさに満ちています。 私も仕事の出張で訪れたことがありますが、あの深い森とそこに点在する湖に立ってみて、初めてシベリウスの音楽が心に染み渡るようになりました。霧に覆われた神秘的な湖や、奥深い森の情景がまざまざと目に浮かんできます。 ある音楽評論家が「シベリウスの音楽世界には人が誰もいない」と表現していますが、そういう情緒を湛えていることは確かです。このヴァイオリン協奏曲もこうしたフィンランドの情景を彷彿とさせており、幻想的な美しい旋律が散りばめられた傑作です。 フィンランドの風が吹き渡るかのような清冽さにみちた美しい音楽が全楽章を包み込んでいます。シベリウスは謎の隠遁生活を送っていた1957年の9月20日に、脳出血のために91歳の生涯を閉じています。彼の訃報は全国に伝えられて、フィンランド放送番組は中断されて、シベリウスの名作「トゥネラの白鳥」が流されて哀悼の意を表したほど国民から愛された作曲家でした。シベリウスは、ヴァイオリン演奏でも優れた演奏家で音楽院で勉強中には、すでにメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を弾きこなしていたそうです。ただ彼はヴァイオリニストの道を歩まなかったのは、ステージに立つとあがってしまう性格だったので、ヴァイオリン演奏の道を断念したというエピソードが残っています。彼がヴァイオリニストとして研鑽を積んでステージに立つ道を選んでいれば、今私たちが聴いている素晴らしい音楽が生まれていなかったかも知れません。愛聴盤 (1) キョン・チョン・ファ(Vn) アンドレ・プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7007 1970年録音)有名なキョン・チョン・ファの1970年の録音盤で、第1楽章の清冽なリリシズムとフィンランドの清澄な空気、そこはかとなく秘めた寂寥感がたまらない魅力です。LPからCDに変わっても何度も再発売を繰り返されてきた名盤です。(2) 五嶋みどり(Vn) ズービン・メータ指揮 イスラエル・フィルハーモニー(SONYクラシカル SRCR9651 1993年録音)キョン・チョン・ファの演奏に力強さが加わったような、たくましいシベリウスとなった名演だと感じています。
2010年09月05日
コメント(2)
-
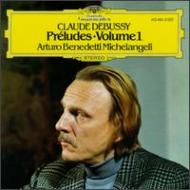
前奏曲集
「名曲100選」 ドビッシー作曲 「前奏曲集」クロード・ドビッシー(1862-1918)の作品は、管弦楽曲、室内楽曲、器楽曲、オペラなどの分野にわたって書かれていますが、それらの作品の中でも最も重要なジャンルはピアノ曲ではないでしょうか?彼自身が、ショパンの直弟子だった人に師事してピアノを勉強したと言われていますから、ピアノ演奏はかなりの技量であったと推測されます。 その彼のピアノから生まれたのが「ベルガマスク組曲」「版画」「映像」「子供の領分」「前奏曲集」です。 これらの曲は、印象主義音楽技法で書かれており、彼自身が見聞したものからインスピレーションを得て、ピアノの音としてその印象を音楽として表現しています。 彼が最初に印象主義音楽として書いたのが「牧神の午後への前奏曲」と言われています。 その後「夜想曲」や交響詩「海」などを書いて印象主義音楽を完成させていったのですが、今日の話題曲「前奏曲集」はこうした印象主義を顕著に表したピアノ音楽の傑作の一つです。この曲に限らないのですが、特に「前奏曲集」ではドビッシーの特徴を随所に聴くことができます。 それはメロディよりも音色そのものを重視していることです。 ハーモニーや音色を大切にした音楽なのです。 ドビッシー以前のシューベルト、シューマンは勿論のこと、ショパンやリストでさえ書いていない新しい作曲技法で書かれたピアノ音楽です。「前奏曲集」は1曲ごとに題名が付けられているのですが、それは曲の内容を表す題名です。 それらはドビッシー自身が見たり、聞いたり、読んだりしたこと(風景、絵画、文学など)から受けた印象をピアノの音として表現したいます。 しかし、題名と音楽は、「標題音楽」のように密接に関連しているとは思えないのが曲を聴いた感想です。 標題音楽ではない、という彼のメッセージなのかもしれません。「前奏曲集」は第1巻と第2巻があり、第1巻は、「音と香りは夕べの大気のなかに漂う」「アナカプリの丘」「雪の上の足あと」「西風の見たもの」「 亜麻色の髪の乙女」「 さえぎられたセレナード」「沈める寺」「パックの踊り」「吟遊詩人」「水に映る影」から構成されており、第2巻は、 霧 枯葉 ヴィーノの門 妖精たちはあでやかな踊り子 ヒースの荒野 奇人ラヴィーヌ将軍 月の光が降り注ぐテラス 水の精 ピクウィック殿をたたえて カノープ 交代する三度 花火 で構成されています。誰もが書いたことのない新しいピアノ音楽の世界を示してくれたドビッシーは、やはり素晴らしい作曲家であると改めて思います。愛聴盤 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(ピアノ) (グラモフォン・レーベル 413450 1978年録音 海外盤)このディスクは第1巻のみ収録されています。(グラモフォン・レーベル 427391 1988年録音 海外盤)こちらは第2巻の収録です。尚、このミケランジェリ演奏盤は国内プレスで第1集と第2集収録の全曲盤が1枚のCDでもリリースされています。そちらの方がはるかにお買い得です。
2010年09月04日
コメント(2)
-

ブランデンブルグ協奏曲
「名曲100選」 J.S.バッハ作曲 「ブランデンブルグ協奏曲」ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685-1750)は、65歳の人生で教会音楽と呼ばれる「宗教」の行事に使われる音楽と、「世俗曲」と呼ばれる教会で演奏されるものと関係がない2つの音楽ジャンルの作品を書いています。 前者が「カンタータ」や「ミサ曲」、「オルガン曲」などで、後者には「管弦楽組曲」、「ヴァイオリン協奏曲」、「無伴奏チェロ組曲」、「無伴奏ヴァイオリンソナタ」、「平均律クラヴィーア曲集」、それに「ブランデンブルグ協奏曲」などがあります。バッハには「ワイマール時代」とか「ケーテン時代」とか「ライプチッヒ時代」とか呼ばれている時期があります。 それは彼が一時期を過ごした場所を示す時代を表しています。 それぞれの時代にその場所の王侯・貴族に遣えて「音楽長」なる職務を与えられていたことを表す言葉です。「ワイマール」では9年半の間、「宮廷オルガニスト」「宮廷楽員」としてつかえて、最後には「楽士長」となっています。 その「ワイマール」の後バッハは紆余曲折を経て、ケーテン公レオポルドに熱心に請われて公の宮廷楽団の楽長のポストに就いて約5年半を「ケーテン」で過ごしました。 1717から1723年のバッハ32歳から38歳の時期です。 ケーテン公は非常に音楽の好きな人だったそうで、バッハを手厚く扱っていたためにバッハ自身も自分の書きたい曲を思う存分に書いていたそうです。上記の「世俗曲」はほとんど「ケーテン時代」に書かれたと言われており、バッハ65歳の生涯で「最も幸せな時代」であったと言われています。その「ケーテン時代」に書かれた作品の中に「ブランデンブルグ協奏曲」(全6曲)があります。 イタリアのヴィヴァルディ(1678-1741)に代表されるイタリア・バロック音楽に「合奏協奏曲」(独奏楽器群と合奏楽器群の競演)という音楽スタイルがあり、ラテン特有の華麗な音楽に人気がありました。 バッハはその「合奏協奏曲」スタイルに、よりがっしりとした骨組みを作ってドイツ精神のようなものを吹き込んだ作品に書き上げています。使用される独奏楽器群は6曲それぞれに異なっており、曲自体に様々な彩りを与えています。 各曲の独奏楽器群は、「第1番」 ホルン2本と3本のオーボエ「第2番」 トランペットとリコーダー、オーボエ、ヴァイオリン「第3番」 独奏と合奏の区別無く、弦楽器のみ「第4番」 2本のリコーダーとヴァイオリン「第5番」 フルートとヴァイオリン、チェンバロ「第6番」 独奏と合奏の区別なく、弦楽器での演奏となっており、ヴィヴァルディ・スタイルを踏襲しているのは「第2番」「第4番」「第5番」と言われています。 他の3曲はバッハ独自のスタイルとなっているそうです。音楽は華麗さとドイツ音楽の重厚な構成による骨太の音楽となっていて、それぞれの曲の多彩な曲趣を味わえる作品です。この曲は、「ケーテン時代」に書いて宮廷演奏会で演奏されていた作品から6曲を選び出して、1721年にルードヴィッヒ・ブランデンブルグ辺境伯に献呈されています。 この曲の名前はこのルードヴィッヒ伯爵に献呈されたことに由来しているそうです。私がこの「ブランデンブルグ協奏曲」を初めて聴きましたのが高校1年生の時で、今では何故この曲を選んだのか理由は定かではありませんが、カール・ミュンヒンガー指揮 シュトットガルト室内管弦楽団の録音したLP盤から第2番のみをプレスしたEP盤を買って聴きました。 トランペットの華やかな音色に魅されて毎日この「第2番」を聴いて楽しんでいました。愛聴盤(1) ルドルフ・パウムガルトナー指揮 ルツェルン弦楽合奏団(DENONレーベル COCO70387 1978年録音)ヨゼフ・スークのヴァイオリン、オーレル・ニコレのフルート、ギィ・トゥーヴロンのトランペット、クリスティアーヌ・ジャコテ(チェンバロ)などをソリストに迎えた、少しの遅めのテンポでゆったりとした素朴なドイツ・バロック音楽といった感のある、聴くほどに味のある演奏です。 DENEON CREST1000シリーズの一組として再発売されて2枚組で1500円という廉価盤です。(2) ジャン=フランソァ・パイヤール指揮 パイヤール室内管弦楽団(DENONレーベル COCO73022 1973年録音)パウムガルトナー盤のような重厚さはありませんが、フランス・サロン音楽風のバッハでランパルのフルート、モーリス・アンドレのトランペット、ジャリのヴァイオリンなどの独奏者を迎えての名人芸を楽しめるディスクで、現在はDENON CREST1000シリーズで1000円盤として再発売されています。第1番を除いて5曲収録されています。
2010年09月03日
コメント(0)
-

無言歌集
「名曲100選」 メンデルスゾーン作曲 「無言歌集」フェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847)は交響曲、協奏曲、室内楽、器楽曲、歌曲、オラトリオなどを数多くの名曲を残していますが、今日はそれらの作品の中からピアノ曲「無言歌集」を採り上げました。メンデルスゾーンは、38歳の生涯で1829年から1845年までに「無言歌」集を書き綴り、全8巻48曲のピアノ曲として残しています。無言歌(Lieder ohne Worte 〔独〕)という名称は、メンデルスゾーン自身が命名しており文字通り“歌詞のない歌曲”という意味です。歌詞のない歌ですから、それぞれの曲にタイトルが付けられています。 ピアノ曲としての器楽的な音楽と、歌曲としての旋律的な音楽が渾然一体となった、親しみのあるピアノ曲です。メンデルスゾーンは「音の風景画家」と言われるように、風景を音楽で表現すると実に巧みに描いています。 交響曲第3番「スコットランド」、第4番「イタリア」、序曲「フィンガルの洞窟」など、その音楽を聴いていますとその場に誘われていうるかのように感じる程に、美しく巧みに描いています。ピアノを弾く人に聴いた話ですが、この「無言歌集」の大部分の曲は左手が伴奏和音型、右手が旋律型という構成で書かれています。 わかりやすく言えば、歌曲演奏のピアノ伴奏者が歌手のパートまで受け持って、一人二役の役割で歌曲を聴かせてくれている、と私は想いながらいつも聴いています。これら48曲の中でも、とりわけ有名なのは「春の歌」や「ヴェニスの舟歌」(3曲あります)「紡ぎ歌」などです。 私の一番好きな曲は第1集1曲目の「甘い思い出」です。これら48曲のピアノ音楽はメンデルスゾーンを捉えた風景、イメージをピアノで叙情性豊かに語り尽くした「音の風景画家」の「詩」でもあると思います。愛聴盤 (1) 田部京子(ピアノ)(DENONレーベル COCO70450 1993年録音)田部京子の透明感あふれるピアノが美しく、曲に対しては叙情豊かに表現しており、ギーゼキングの録音が古くなった現在では、この盤が定番となり得る素晴らしい演奏です。 48曲の中から25曲が選ばれています。紹介の型番は1000円盤です。(2) イルゼ・フォン・アルペンハイム(ピアノ)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD4030 1980年録音)こちらは全8巻の全曲盤です。Philipsからリリースされた1995年だったかに購入して聴き親しんでいるディスクです。 メンデルスゾーン生誕200年の昨年に国内プレス盤として再発売されています。
2010年09月02日
コメント(3)
-

スペイン交響曲
「名曲100選」 ラロ作曲 「スペイン交響曲」 ニ短調 エドゥアール・ラロ(1823-1892)は弦楽器が好きであったのか、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロなどを演奏していたそうです。 この「スペイン交響曲」は名前こそ交響曲と名付けられていますが、実際は全5楽章からなるヴァイオリン協奏曲です。 いかにもヴァイオリンを知り尽くしたラロらしく華麗な協奏曲となっており、この曲を当時の優れたヴァイオリン奏者で作曲家でもあったサラサーテ(1844-1908)に捧げられています。ラロはフランス人ですが、祖父の代までは純粋なスペイン人だったそうで、ラロにもスペインの血が脈々と流れていたのでしょう。 しかし、彼の名前が作曲家として認められるようになったのはこの曲を発表してからだそうです。 42歳まで独身で生活に追われていた彼がアルト歌手と結婚して、その彼女から熱心に作曲を勧められてから本格的に活動を始めたそうです。この曲はヴァイオリン協奏曲としては2番目の曲になり、名前もヴァイオリン協奏曲として残っている曲があります。 その協奏曲や「チェロ協奏曲」やオペラ「イスの王様」などを書いています。ラロの名前は名実共にこの「スペイン交響曲」によって音楽史上に確立されていますが、時にラロが52歳という晩年でしたから、フランスのセザール・フランクやオーストリアのアントン・ブルックナーと同じく「大器晩成型」だったのでしょう。曲は濃厚なスペイン的情緒に溢れており、 曲の冒頭の独奏ヴァイオリンの華麗な、むせ返るような情熱的なメロディを聴いた瞬間から聴き手はスペインへと誘われたような気分になります。 血が騒ぐ闘牛場の熱気、フラメンコダンスのむせ返る官能的な情緒、熱くかき鳴らされるスペインギターの音色、地酒のワインとパエリャの香りが一度に部屋中に沸き立つかのような曲の始まりです。 そしてその気分が終楽章まで持続しています。尚、この1800年代後半はヨーロッパでは「旅」が頻繁に行われるようになったせいでしょうか、「エキゾチック(異国情緒)」ということに作曲家が魅かれており、チャイコフスキーの「イタリア奇想曲」、R.コルサコフの「スペイン奇想曲」やフランスのシャブリエの「スペイン狂詩曲」などにも窺えます。ラロ自身もこの曲同様に他のヴァイオリン協奏曲にサブタイトルを付けています。 彼は全部で4曲の協奏曲を書いており、2番にあたるのが「スペイン」、3番が「ノルウエー幻想曲」、4番が「ロシア協奏曲」と言う風にラロも流行のエキゾチック・ムードに乗って書いたのでしょう。しかし、この曲については、ラロに流れる「スペインの血」がこうした音楽を書かせたのかと思います。またチャイコフスキー不朽の名作「ヴァイオリン協奏曲」は、彼がサラサーテの弾くこの曲を聴いて感動して書くようになったと伝えられています。 それは彼の支持者だったロシアのフォン・メック夫人宛の書簡に書かれているそうです。 大げさに言えば、この「スペイン交響曲」がチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を生んだという穿った見方もできます。愛聴盤 アンネ=ゾフィー・ムター(Vn) 小澤征爾指揮 フランス国立管弦楽団 (EMI原盤 EMIジャパン TOCE13284 1984年5月録音)カラヤンに認められたのが76年、ムター13歳。 その翌年14歳でカラヤンと共演して一気にヴァイオリン界の妖精として、カラヤンと立て続けに演奏会・録音をこなしてきて、7年後の1984年に小澤征爾と組んでようやくカラヤンから離れた時の録音で、これが21歳の演奏かと思うほどに、もう完全に自己主張を堂々とやってのけている記念碑的演奏・録音です。 奔放で溌剌として、情熱的に弾きまくり、劇的緊張感も兼ね備えながら、色彩豊かな歌心たっぷりに聴かせてくれます。 この演奏に、現在のムターの姿がすでに見え隠れしていると感じます。この盤には「ツゴイネルワイゼン」が収録されていて、これがまたすごい演奏で情感たっぷりのムターのむせるようなヴァイオリンの音色。 この盤を聴いた時に、これが21歳の演奏か、と唸ってしまう位に情熱的な、情感たっぷりの演奏です。ただこの演奏がベストという意味ではなく、他にも優れた演奏がたくさん録音されています。グリュミオー盤、パールマン盤、サラ・チャンなどの優れた演奏盤も持っていますが、私が初めて購入した記念すべきCDの第1枚目にあたる盤でもあり(型番CC-30-9071)、現在の3,000枚のライブラリーの出発点になったという意味で、この再発売盤をここに紹介させていただきました。
2010年09月01日
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-
-
-
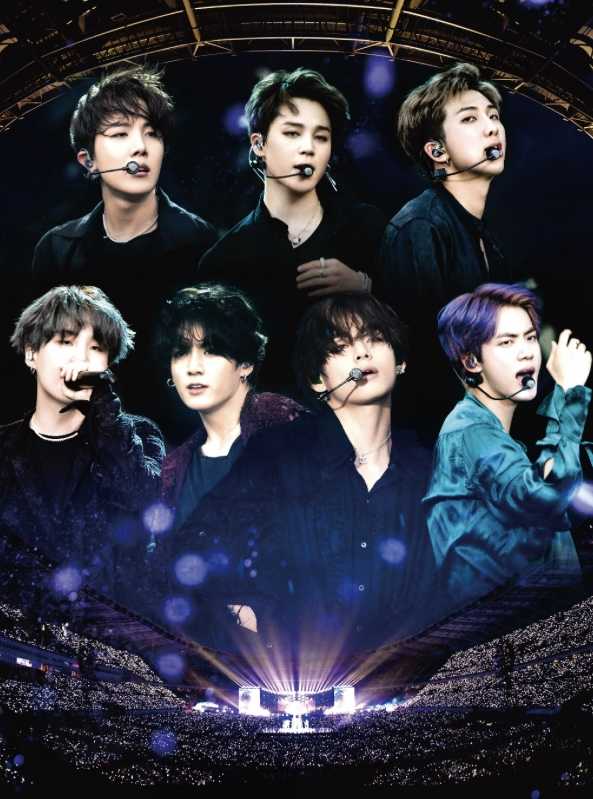
- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…
- (2025-11-21 18:37:01)
-







