2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010年02月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
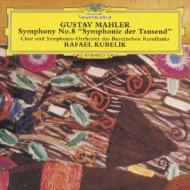
千人の交響曲
「今日のクラシック音楽」 マーラー作曲 交響曲第8番「千人の交響曲」「千人の交響曲」って何? 演奏に千人もの人が必要なの?この曲を「千人の交響曲」と名付けたのは、あまりに大規模な編成を要する音楽なので、楽譜の出版商人が付けたそうですが現代でもこれが通称になっています。マーラー自身が「宇宙が震え鳴り響き、もはや人間の声でなく運行する惑星か太陽の声」と述べたそうですが、それほどにこの曲を演奏するには大きな編成が必要です。古典派のオーケストラ編成の2倍もある管弦楽に、チェレスタ、オルガン、ピアノ、マンドリンが加わり、舞台の外にも4本のトランペット、3本のトロンボーンが配置されるというスケールの大きな編成。 それにまだ2組の混成合唱団、8人の独唱者までが加わります。ではそれで千人? いや、そうではないそうです。実際には800名ほどで足りるそうですが、この曲が初演されたのが1910年9月12日。 マーラー自身の指揮で初演されたそうですが、その時の演奏者数が1,030名だったそうです。オーケストラが総勢170名であとは合唱・独唱者の数だそうですが、文字通り「千人の交響曲」だったようです。愛聴盤ラファエル・クーベリック指揮バイエルン放送交響楽団・合唱団、北ドイツ放送合唱団、西ドイツ放送合唱団、レーゲンスブルク大聖堂少年聖歌隊、ミュンヘン・モテット女声合唱団、マーティナ・アーロヨ(S) エルナ・スポーレンベルク(S)、エディット・マティス(S)ユリア・ハマリ(アルト) ノーマ・プロクター(アルト)ドナルド・クローべ(T) フィッシャー=ディースカウ(Br) フランツ・クラス(Bs)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG3954 1970年録音)
2010年02月26日
コメント(1)
-

幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」
「今日のクラシック音楽」 チャイコフスキー作曲 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」チャイコフスキーには文学作品を音楽にしたのがあります。 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」や「ハムレット」、それに「マンフレッド交響曲」などがあります。現代では文学作品・小説・随筆などは雨後のタケノコのように出版され、またインターネットでも読むことが出来る世の中ですが、チャイコフスキーの生きた1800年後半では文学作品を読めることは貴重な体験だったのでしょう。チャイコフスキーは、ワーグナーの「バイロイト音楽祭」柿落しに招かれてバイロイトまで出かけたのが1876年(36歳)、その旅行中にダンテ「神曲」に感動を覚え、とりわけフランチェスカ姫とパオロの悲恋物語(「神曲」地獄編 第5部)に心を打たれたと言われています。その感動によって生まれたのが幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」です。私はこの物語を読んでいませんので、文学の解説はCDのライナー・ノートによるものです。 フランチェスカ姫は13世紀に実在した美しい女性だそうです。 その姫は醜い武将ジョバンニに嫁ぐのですが、その夫の弟パオロという美青年と恋に落ちてしまいます。 それを知って嫉妬に狂う夫に殺害される悲恋物語ですが、これをチャイコフスキーは役25分の音楽にしています。曲は序奏付きの三部構成のような形式で、重苦しい雰囲気の序奏部から主部になると、地獄の有様を描写しているアレグロとなり(第一部)、やがてフランチェスカとパオロの甘い恋物語を語るようにロマンティックな旋律にあふれる第二部、そして第一部の再現とコーダによって曲は閉じられるます。「ロメオとジュリエット」に比べるとかなり地味な作品なので、演奏会や録音などに採り上げられる機会があまりありませんが、悲恋にもだえてやがて殺されていく無念さが伝わってくるロマンの香り高い作品です。この幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」が1877年の今日(2月25日)、モスクワで初演されています。愛聴盤ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮 ソヴィエト国立文化省交響楽団(エラート原盤 ワーナー・ミュージック WPCS4016-6 1990-91年録音 廃盤)
2010年02月25日
コメント(0)
-
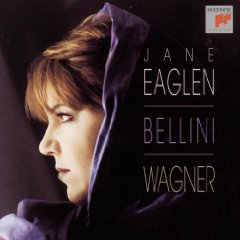
ワグネリアン・ソプラノとベル・カント
今日のクラシック音楽 ソプラノ歌手 ジェーン・イーグレンワーグナーの劇的なアリアを歌う(例えば楽劇「トリスタンとイゾルデ」のイゾルデ役)ソプラノが同時にイタリアの「ベル・カント」オペラ(例えばベルリーニの「ノルマ」のノルマ役)を歌う歌手は極めて稀で、ごくわずかの歌手しかいない。戦後ではマリア・カラス、モンセラット・カバリエくらいしか浮かんでこない(椿姫のヴィオレッタと楽劇「サロメ」のサロメ役を歌ったテレサ・ストーラタスはいるが)。 つまりこの両役を歌うことには大きなリスクが伴うからでしょう。 あのイギリスのジョン・サザーランドでさえ、ベル・カントを中心に活動を始めるとワーグナーは歌わなかったのです。「喉」、「声」そして正確な「技術」がないと歌手生命を縮めてしまうと言われています。コロラトゥーラとワーグナーの劇的な歌唱を歌い分けることは、神から授かった「喉」「声」「正確な歌唱技術」がなければ、一人で出来ることではないと言われています。 それほどにベル・カント(コロラトゥーラ)とワーグナーのドラマティック・ソプラノの歌い方が違います。それは聴いていてもわかります。そこに登場したのがイギリスのソプラノ歌手ジェーン・イーグレンです。 1960年生まれですから今年はもう50歳になる人ですから、引退をしているでしょう。 日本ではあまり話題にならなかったのですが、1996年11月にソニー・クラシックからリリースされたCDがその驚異的な喉・声を収録しています。 ベルリーニの「ノルマ」とワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」を歌っているのです。コロラトゥーラという高い技術と歌謡性を要求されるベル・カント。 強靭な喉と声を要求されるワーグナーのヒロイン。 オペラ・ファンに馴染み深いグルベローヴァ(ソプラノ)がイゾルデを歌っていると想像すればいいのです。まず考えられないことですが。イーグレンの、このCDで披露されている歌唱は、圧倒的な声の輝き、そして力強さ、それに役にはまり込んだ表現、と聴く者を圧倒してきます。 1960年生まれでこの録音が95年ー96年ですから、彼女が30代に入ったころで若さに溢れたエネルギーをふりまきながらの歌唱は見事というほかはありません。ベルリーニにしろワーグナーにしろ、もっと最上のソプラノがいて録音あるいは上演されていますが、ベル・カント(ベルリーニ)とワーグナーを歌ったジェーン・イーグレンに「乾杯!」と叫びたくなります。このCDです。ジェーン・イーグレン(ソプラノ)マーク・エルダー指揮エイジ・オブ・イントライトゥメント管弦楽団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団収録曲1. ベルリーニ オペラ「海賊」~その無心の微笑みで オペラ「ビアンカとフェルナンド」~お立ち下さい、お父様 オペラ「ノルマ」~清らかな女神よ2. ワーグナー 前奏曲~(楽劇「トリスタンとイゾルデ」) 愛の死~(楽劇「トリスタンとイゾルデ」) ブリュンヒルデの戦いの叫び~(楽劇「ワルキューレ」) ブリュンヒルデの自己犠牲~(楽劇「神々のたそがれ」)(SONYクラシカル SRCR1776 1995-96年録音)
2010年02月24日
コメント(0)
-
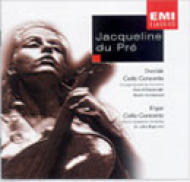
エルガー チェロ協奏曲/椿
『今日のクラシック音楽』 エルガー作曲 チェロ協奏曲独奏チェロで奏でられる曲は、ピアノやヴァイオリンに較べて極端に作品数が少ないですね。 チェリストのミッシャ・マイスキーはあまりに曲の数が少ないので、シューベルトの歌曲をチェロ独奏(ピアノ伴奏付き)で演奏して録音するなど、チェリストにとってはレパートリー確保に大変だと思うときがあります。その数少ない独奏チェロによる演奏曲の中でも、ハイドン、ドヴォルザークなどの名曲と肩を並べて人気の高い作品に、イギリスの作曲家エドワード・エルガー(1857-1934)が書き残した「チェロ協奏曲ホ短調 作品85」があります。この曲はエルガー晩年の最後の大作で1919年に書かれています。曲の冒頭に独奏チェロが奏でる旋律は「ため息」のような情緒を醸し出しています。 それ故に雰囲気は愁いに満ちており、20世紀に書かれた現代音楽とは思えないロマンあふれる情緒で曲は展開していきます。 それでも音楽は高まりながら緊張をはらんでいき、クライマックスを築いてのちに初めの旋律が戻ってきて静かに第1楽章を終わります。曲は切れ目なしに第2楽章へと進み、憂鬱な感じの音楽が支配しています。 この感じのままで、まるで迷走するような音楽が、やがて静かに音が落ちていき、スケルツオ風に軽快な次の楽章へと進んでいきます。第3楽章は非常に短い音楽でありながら、瞑想のような美しい旋律が現れて「夢の世界」への誘いのような音楽が広がっています。終楽章は語りのようなモノローグ風に音楽が始まります。 それが力強い主題の提示へと進み、「空想」へと向かうような中間部のゆったりとした旋律が奏でられる様は見事です。 最後には第1楽章の冒頭の「ため息」のような旋律が独奏チェロで現れて、音楽は一気に高められてドラマティクに曲を閉じています。 比較的単純で簡潔な構成でありながら、色彩豊かに彩られた19世紀ロマン派音楽のような佇まいを帯びて、エルガー独特のロマンティックな音楽です。 チェロの憂いある音色の魅力を最大限に引き出しており、20世紀に書かれたチェロ作品でも屈指の名曲だと思います。憂愁な佇まいと瞑想的な旋律に彩られたチェロの美しい響きを味わうのに最適な作品の一つだと思います。 第3楽章の神秘的な美しさは筆舌に尽くしがたい程です。今日はそのエドワード・エルガーの命日(2月23日)です。 その命日にちなんでこのチェロ協奏曲を聴こうと思っています。愛聴盤 ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ)、サー・ジョン・バルビローリ指揮 ロンドン交響楽団(EMIレーベル 5555272 1965年8月19日録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 椿
2010年02月23日
コメント(0)
-

チャイコフスキー 交響曲第4番
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 交響曲第4番ヘ短調作曲家と女性の交際が生んだ名曲が音楽史上に多く残されています。 ロシアの作曲家ピョートル・チャイコフスキー(1840-1893)にもそんな1曲があります。 交響曲第4番ヘ短調 作品36がそれです。チャイコフスキーを語る時にいつも見え隠れするのが当時のロシア鉄道王カール・オットーの未亡人ナジェージダ・フォン・メック。 夫亡き後の莫大な資産を抱えたこのメック夫人は、チャイコフスキーには破格の経済援助を与えていました。 二人の接触は夫人の家に出入りしていたコチェークというチャイコフスキーの教え子であるヴァイオリニストの紹介でした。当時のチャイコフスキーが経済的には苦しい状況にあったことをコチェークはよく知っていました。 それでメック夫人に援助の話を持ちかけたと言われています。 メック夫人の夫亡き後の楽しみは6男6女の子供たちの成長を見守ることと、好きな音楽を楽しむことであったようです。 かねがねチャイコフスキーの非凡な音楽才能を買っていたメック夫人は、コチェークからの依頼に二つ返事で答え、チャイコフスキーに小品の作曲を委嘱して、二人の交際が始まったのです。 法外な謝礼によってメック夫人に興味を持ったのが1876年の冬のことだと言われています。交際と言っても二人は生涯顔を合わせることがなく、手紙だけでの付き合いであったようです。 1200通余りの手紙がチャイコフスキーからメック夫人に書かれているそうです。 法外な謝礼はやがて月額となって決まった金額の援助がなされました。 チャイコフスキーのモスクワ音楽院教授就任の初任給が50ルーブルで、「白鳥の湖」への謝礼が800ルーブルだったそうです。 それに比べてメック夫人の援助が月額6000ルーブルだったそうで、まさに破格の法外な謝礼と言えるでしょう。経済的に落ち着いた環境でチャイコフスキーは、精神的に随分と余裕を得て作曲活動を行っていたようです。そんな彼にとんでもない女性が現れてチャイコフスキーを悩ませます。 1877年のことです。 彼の教え子にアントニーナ・ミリューコヴァという9歳年下の女性がいて、彼に熱烈な恋文を書いて結婚を迫ってきました。 押し切られる形で結婚を承諾したチャイコフスキーは彼女に失望したのは結婚後すぐだったようです。 メック夫人に宛てた手紙には妻となった女性は、彼の仕事が何たるかを理解しないどころか、彼の音楽の楽譜の1枚すら知らなかったようです。 結婚3か月で別れてしまい、それがチャイコフスキーに深刻な精神的ダメージを与えたようです。弟の提案でチャイコフスキーはスイス・イタリアへ旅行をして、徐々に回復していったようです。 そこで書かれたのが交響曲第4番でした。 メック夫人からの経済援助を受けた後の初めての大作でした。この曲はよく「人生と運命」を表現した音楽と言われています。 チャイコフスキーはこの曲をフォン・メック夫人に献呈しており、この曲の作曲の動機・内容について、細かく手紙に書いています。 手紙にはこう書かれています。 「この交響曲を書いていた冬の間中、私はひどくふさぎこんでいましたが、この曲は当時私が経験したことを忠実に反映しています」と。第1楽章 冒頭の旋律は、この交響曲全体の精髄であり、生命であると述べており、第1主題は、幸福を妨げ、魂の毒を注ぎ込んでくる力で、絶望して諦めを余儀なくされるが、それでも夢に浸りたくなる。 「運命」と「夢」が交錯する激しい音楽。まるで激しいドラマが開始するかのような、第1楽章冒頭のホルンとファゴットによる劇的・熱烈な旋律が奏されると、聴き手はもう激しいこの曲のドラマの中へと引き込まれていきます。 この旋律は「運命の動機」と呼ばれています。 この動機がベートーベンの第5番のシンフォニーのように、他の楽章の楽想にも表れ、この曲の中心的な動機となっています。まるで情熱と嘆きの交錯するような、激しさと哀愁が同居しているような、チャイコフスキーが自分の人生を語るかのようなドラマティックな展開をみせて壮烈なコーダへと進み、たたみかけるような激しさのクライマックスを迎えます。第2楽章「悲哀の楽章」とチャイコフスキーが書いています。 「仕事に疲れ果てた人が放心したように座っている時の憂鬱な気分の状態」と書かれています。 「いっとき過ぎし日を懐かしむ気分になるが、新しいことに挑戦する勇気がない」とも書かれています。オーボエの寂しさから始まり、それがとても印象的です。 まるで今までの人生を思い出しているかのような風情が楽章を貫いています。 寂しさ、悲しさ、切なさが同居する音楽です。第3楽章「気まぐれな気分の楽章です。 酒に酔った時のようなとりとめのない感情です」と書いています。弦楽器によるピッチカートで始まり、主部はこれのみ。 三部形式のようで、2部はロシアン・ダンスのようなリズムで軽快に管楽器で刻まれ、またピッチカートに戻ってマーチ風に展開して終わります。 まるで人生の、つかの間の「うたた寝」のような楽章です。第4楽章「人生を楽しんでいる人たちに飛び込んで行こうとすると、あの運命の動機が現れます。 しかし生きる希望を持てるまで、人生を楽しむ人たちの幸せを喜んであげたい」と書かれています。この曲のクライマックスだと私は思います。 3つの主題ー激しい第1主題、ロシア民謡風の優しい感じの第2主題、力強く明るい第3主題、これらが交互に現れるロンド形式です。 この楽章に、チャイコフスキーがイタリアの燦燦と明るい陽射しに触れて、生きる喜びを熱烈に表現しているのではないかと感じられます。 激しさを加えて豪快にクライマックスを迎えて明るく曲を閉じます。「人生」「運命」という言葉がメック夫人に宛てた手紙に何度も現れており、この曲も全曲を通して暗い色彩に彩られており、ミリューコヴァとの不幸な結婚生活の痛手が影を落としているかのようです。交響曲第4番は、1877年にこうして対照的な女性との接触・交際、結婚・離婚から生まれた曲と言えるでしょう。1878年の今日(2月22日)、この交響曲第4番が初演されています。愛聴盤 ピエール・モントー指揮 ボストン交響楽団(RCA原盤 BMGジャパン BVCC37166 1959年録音)カラヤン/ウイーンフィル、 ムラビンスキー/レニングラード、 ザンテルリンク/ベルリン放響、 ゲルギエフ/ウイーンフィル、 ロジェストヴェンスキー/レニングラードフィル(BBCライブ)など名演目白押しの曲ですが、熱い情熱と生命力豊かなモントー盤に最近ははまっています。ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG20005 1984年録音)エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮 レニングラードフィルハーモニー (グラモフォン レーベル 4197452 1960年ロンドン録音 ユニヴァーサル・ミュージック)クルト・ザンテルリング指揮 シュターツ・カペレ・ドレスデン(TDK FM東京音源 TDKOC009 1973年東京ライブ録音)
2010年02月22日
コメント(0)
-

俳優 藤田まこと 逝く/しだれ梅
俳優 藤田まこと 2月17日逝く最近にない哀しみとショックに見舞われています。今月だったかな新作の「剣客商売」をTVで観たばかり。まるで狐に抓まれたような感じがする。コメディー出来る、殺しが出来る、靴底減らして歩く刑事役も出来る。 戦争時代の軍人役もできる。それでいて、いつも観ている人たちには親近感を感じさせる大物俳優だった。 悲しい! ほんとに哀しい。ご冥福をお祈りいたします。 合掌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「しだれ梅」
2010年02月19日
コメント(4)
-

サンシュユ
春を招ぶ花 サンシュユ花芽が膨らんでくる状態を様々な言い方があるそうです。 早い順番から書きますと「芽ぐむ」「芽ばる」「芽ざす」「芽吹き」があるそうです。この花が咲けば春らしくなります。サンシュユの黄色い花芽が出てきました。
2010年02月18日
コメント(0)
-

リスト P協奏曲/ファンタジー アルバム/椿
『今日のクラシック音楽』 フランツ・リスト作曲 ピアノ協奏曲第1番変ホ長調1855年の今日(2月17日)、フランツ・リスト(1811-1886)が作曲しました「ピアノ協奏曲第1番変ホ長調」が初演されています。今日の私の音楽カレンダーを見ると、すごい一日です。 それで随分と迷いました。1885年 初演 リスト ピアノ協奏曲第1番1859年 初演 ヴェルディ オペラ「仮面舞踏会」1904年 初演 プッチーニ オペラ「蝶々夫人」1962年 逝去 ブルーノ・ワルター(指揮者)ワルターのマーラー交響曲を採り上げようか、「仮面舞踏会」にしようか、「蝶々夫人」にしようかと、あれこれ迷った末に昨年購入しましたフランスの若手女流ピアニストのクレール=マリ・ルゲの、リストのピアノ協奏曲第1番がとても印象に残っていますので、この曲を採り上げることにしました。リストには有名なロマンスとして、カロリーネ・ヴィトゲンシュタイン公爵夫人との恋物語があります。 その夫人がリストに語った有名な言葉があります。 「ピアノ演奏は消えてなくなってしまうけれど、立派な作品はいつまでもこの世の宝として後世に残るものよ」と。この言葉でリストがピアノ協奏曲を初めて書く気になったと言われています。 初演の数年前には完成していたそうですが、加筆補正されてようやく1855年の2月17日に、当時リストがワイマール宮廷楽団の指揮者で作曲者として迎えられていたワイマール宮廷劇場で初演の運びとなったそうです。曲はリストらしく華麗で、技巧に彩られており、4楽章全曲が切れ目がなく演奏されます。 華やかなピアノを知り尽くしたリストらしい協奏曲です。尚、この初演にはリスト自身がピアノを受け持って、ベルリオーズ指揮というまさに豪華で、個性の強い二人の”世紀の初演”、”胸躍る初演”であったと想像することができます。 愛聴盤クレール=マリ・ルゲ(P) 指揮: ルイ・ラングレー リエージュ・フィルハーモニー管弦楽団(Accord レーベル 472 728-2 2002年7月録音)しなやかなピアノの音色で、ロマンチックな傾向の強いピアノ演奏です。 オグドン、ベルマン、アルゲリッチなどのアクの強いピアノに親しんでいました私にはとても新鮮なピアノタッチです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チャイコフスキー ファンタジージャケットの英文タイトルには「チャイコフスキー・ファンタジー」と銘打ってありますが、1曲だけスクリャービンのピアノ・デュオ用遺作「幻想曲」が収録されています。あとの曲はチャイコフスキー作品、それも管弦楽作品としては超有名曲「イタリア奇想曲」バレエ音楽「白鳥の湖」~ロシアの踊り、スペインの踊り、ナポリの踊り(編曲はクロード・ドビッシー)、「眠りの森の美女」~序奏 リラの精、アダージョ パ・クダシオン、パノラマ、ワルツ(ラフマニノフ編曲)、それに「スラブ行進曲」(パダリーナ編曲)というラインアップどの曲も数え切れないくらいにオリジナルの管弦楽で聴いた馴染みの作品ばかり。ところがどうでしょう、ピアノ連弾で聴くと作品その物が明確に明快に訴えてきます。 こんなに楽しい旋律だったの、こんなに激しいリズムだったの、と新発見するばかりでした。 今から15年前だったかな、このCDが発売になってすぐに買って聴いたのは。 その時はPHCP5309というマーキュリー・ミュージックが発売していました。何年ぶりかで取り出して聴いてみました。 こういう古いCDを取り出して聴いてみると、それを買った頃の自分を思い出します。私は50歳の頃で一番脂ののった仕事をしていたころかな。一ヶ月でインド・イギリス・中国・韓国・USAと飛び回っていた頃で、自宅に持って来る物は洗濯物だけという忙しさ。 帰国すると会社の女性社員が空港で待っていて、「お疲れ様です。これが明日からの出張の航空券です」という頃でした。 家内から「私はクリーニング屋?」と言われていた頃。それにしてもラベック姉妹はほんとにうまい。唖然とします。ピアノ:カティア&マリエル・ラベック(Philips レーベル 442778 94年5月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・椿
2010年02月17日
コメント(0)
-

冬チューリップ
長居植物園では「冬チューリップ」と呼んでいるけれど、これは「春のチューリップ」とどこか違うのかな?今週は海の荒波を撮影したいと思っていれけれど、交通費などかけずに泊まりもなしで、海の男性的な様相を撮れる処と言えば、近いところで和歌山県の「新和歌の浦」かな?
2010年02月16日
コメント(0)
-

はこべ
友人宅の庭の中で見つけました。あわててカメラを取りに帰宅。マクロレンズと三脚も持参しての撮影となりました。 もうすぐ春が来るんだなと思いました。
2010年02月15日
コメント(2)
-

水仙
今日の写真 冬の貴重な花 水仙花が少ない冬。 その中で「水仙」は貴重な花の一つであり、アングルによって多彩な表情を写し撮ることが出来ます。これは逆行を利用して撮った水仙。 しかし、ピントを合わせるところをまちがっています。 中央の花にすべきなのに奥の右手寄りの花に絞っています。大失敗です。
2010年02月14日
コメント(2)
-

バイロイト音楽祭/水仙
リヒャルト・ワーグナー「バイロイト音楽祭」という言葉をクラシック音楽そ好きな方には、耳にしている言葉でしょう。世界にはどれだけの音楽祭があるのか、その数は知りませんが「バイロイト音楽祭」はよく目にしたり、耳にしたりする有名な音楽祭の一つです。これはリヒャルト・ワーグナー(1813-1883)が創設した音楽祭で、自分の作曲した歌劇・楽劇を上演するために作った音楽祭です。ここではワーグナーの音楽が会期中に上演される、おそらく世界でただ一つの、一人の作曲家のための音楽祭でしょう。ワーグナー音楽を愛好する人を「ワグネリアン」と呼んでいますが、こうしたファンが毎年夏になると(7月下旬から約1ヶ月間)「バイロイト詣」が行われます。 南ドイツのバイロイトへワーグナー音楽を聴くために出かけることを指しています。 バイロイトは南ドイツ・ミュンヘンから北へ約200キロ離れた人口約6万人の田舎町ですが、この時期はワグネリアンによって国際色豊かな町に変貌するそうです。このバイロイトに在るのが「バイロイト祝祭歌劇場」1876年8月13日に柿落し公演が行われており、楽劇「ラインの黄金」(「ニーベルングの指輪」序夜)が舞台に掛けられてそうです。そうして「ニーベルングの指輪」の4夜連続公演が行われ、それが現代まで続けられています。 この時に招待されたチャイコフスキーは「音楽専門の私でも4夜連続で聴くには疲労困憊だったのに、熱心に聴いていた一般聴衆の疲れはどんなに大きかったろう」と述べているそうです。1883年の今日(2月13日)、リヒャルト・ワグナーは70歳の生涯を閉じています。彼の命日に因んで今日は久しぶりに「ニーベルングの指輪 管弦楽曲集」というCDを聴いてみようと思っています。ロリン・マゼール指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(テラーク原盤 マーキュリー・ミュージック PHCT1213 1987年12月録音 廃盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水仙
2010年02月13日
コメント(0)
-
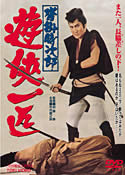
遊侠一匹
沓掛時次郎 遊侠一匹股たび物映画の話。 今日は東映映画「沓掛時次郎 遊侠一匹」(加藤 泰監督 中村錦之助・池内淳子主演 1966年製作)の話です。原作は長谷川 伸の戯曲。 「股旅」という言葉は、長谷川 伸が「股旅草鞋」という戯曲を書いて使われたのが始まりらしい。 この作家には「瞼の母」「関の弥太っぺ」などの有名作品があります。 今では死語に近い「股たび」という言葉。 男気いっぱいで、腕が立って度胸がある。 一本どっこの渡世人。 映画のポスターなどによく使われた言葉。誰もが一目置くやくざ。 その典型的な姿が沓掛時次郎。 脇役の渥美 清があこがれる「やくざ・渡世人」の姿、時次郎。その本人が一番やくざを嫌っている。 やくざ稼業から足を洗って堅気になりたいと願っている。 それでも「一宿一飯」の仁義世界でないと暮らしていけない「悲しい性」のやくざ。ますます嫌悪を感じる渡世の世界。 そこに悲劇が生まれてこの物語が、いつまでも人の涙を誘う。 人の生き方の無情を訴えてくる。やくざ世界には「一宿一飯の仁義」という業界のきまりがある。 江戸時代なら「草鞋を脱ぐ」という言葉があって、やくざ稼業をしておれば一門や親分から破門されていない限り、全国の親分衆を訪ねて行って「ただ飯」を食べさせてもらい、寝る場所も与えてもらえる。しかし、世話になったその親分からの頼みごとを断ることはできない。例えそれが人を斬ることでも「いやです」とは言えない。言えば今後どこの親分も「ただ飯」「ただ寝」をさせてくれない。 それを「一宿一飯の仁義」と呼んでいる。時次郎もこれが嫌でならない。しかし、自分の生きる場所はそこしかない。 渡世人の逃げることが出来ないジレンマがある。 この映画と同時代に一世を風靡した「任侠映画」が描いた、明治以降から現代までの「やくざ渡世」が直面した問題がこの「一宿一飯の仁義」でした。この「沓掛時次郎 遊侠一匹」の特色は、時次郎が「やくざ世界」から抜け出したい、堅気の世界で行きたいと願っている姿が胸を打ってきます。その例を原作にはない朝吉という人のいい無垢な気持ちのやくざを登場させて(渥美 清)、時次郎を粋な一本どっこの、いなせな渡世人として理想を求め慕わせて、挙句にやくざの醜い汚いやり方で惨殺される話を挿入して、時次郎の「嫌いなやくざ」を一層浮き彫りにしています。そして鴻巣一家に草鞋を脱いで「一宿一飯の仁義」から、何の恨みもない六ツ田の三蔵(東 千代乃介)を斬り殺す。三蔵が息を引き取る前に「あっしの女房・子供のことを」と頼まれて引き受ける時次郎。三蔵の女房おきぬと子供を連れての道中旅。 旅をしながらお互いに魅かれていく二人。 恋する時次郎。 それをわかっているおきぬ。 しかし、お互いにそのことは口に出して言えない。 またもや義理と人情に引き裂かれる時次郎。映画では時次郎とおきぬは初めての出会いではない。家に帰る道中で時次郎に出会ったおきぬ。この最初の出会いのシーンが何とも美しい。 柿を一つ時次郎に「旅人さんもどうぞ」と渡す。人の女房らしい人からの親切。心に灯がともるように顔を綻ばせる時次郎。 渡し船は実に絵になる。澄んだ川の水。そこを渡る船。まるで人と人、男と女を優しく包み込む。川と渡し船は股旅ものには欠かせない絵となる。 そして加藤 泰監督はこういう男と女のぎりぎりの心の中を抉るのが巧い。 藤 純子主演の「緋牡丹博徒 花札勝負」でもお竜を足元から徐々に上にカメラを向けて「任侠映画」では比類のない美しさを演出している監督。話を戻そう。 そうした時次郎の悩みを知っているおきぬは突然子供を連れて姿を消してしまう。 おきぬも義理(夫の仇)と人情(時次郎への慕情)の狭間に揺れて姿を消してしまう。また夜の闇が宿場を覆う。場面は冬の雪の夜。時次郎は酒を呑みながらおきぬを想い瞼を濡らす。 おきぬを想う時次郎に「新内流し」の門付の三味線の音が聞こえる。雪道を今にも血を吐きそうなか弱い体で少し首を傾け、手拭で顔を被った女を、足元から見上げようとカメラは捉えている。ここにもお竜と同様の映像美を見せてくれる。 前の場面で時次郎がおきぬを想って泣いていたから、この場面の情感の濃い深さは比類がない。斬った男の女房に惚れてしまった男に、永劫に愛の告白は出来ない。 時次郎には三蔵を斬ったことが原罪で、おきぬがキリストの十字架のようになっている。この映画を初めて観たのは封切の時ですから今から44年前。昨年44年ぶりにDVDで観ましたが、この記事を書きながらこのシーンを想い出すとまた涙が滲んできます。それほどに哀しくも美しいシーンでした。再会したがおきぬは労咳(結核)病みとなり、治療に金のいる時次郎。 またも喧嘩の助っ人で金を稼ぐことになり、喧嘩のあと金を持って帰ってくるがおきぬは不帰の人となっていた。おきぬが亡くなる直前に口に紅を差す。その女心に涙を誘う。最後の場面は遺された子供を背負って街道を歩く時次郎。そこへやくざに憧れる朝吉のような男が時次郎に脇差を向ける。 時次郎の脇差が腰の鞘から抜けるや、その男は土を血で染めた。刀をほり投げて「もう二度とやくざに戻るまい」と子供をしっかりと背負って歩いて行く時次郎。 その後ろ姿にフランク永井の渋い低音で流れてくる主題歌「遊侠一匹」が重なって「終」となる。「何でもあり」「何でも手にはいる」現代から観ると、自分の心を殺して生きていた、昔の古い日本人がとても美しく見える、そんな映画が「沓掛時次郎 遊侠一匹」です。
2010年02月12日
コメント(0)
-

白梅
今日の写真 白梅昨日の続きで「股旅物」映画について書こうとしているのですが、少し資料不足ですので今日はこの画像のみにしておきます。
2010年02月11日
コメント(0)
-
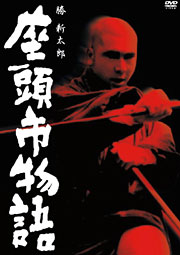
いいなあ~、時代劇!
股旅もの礼賛私は小学生の頃から映画が好きでした。 私の家から徒歩2分のところに映画館があって、3本立てで50円くらいだったと記憶しています。 母が美容院を経営していたので、店にはいつも映画雑誌や芸能雑誌が置いてあり、それを見て育ちました。 またその近所の映画館には比較的時代劇映画をかけることが多かったので、子供のころから時代劇ファンでした。時代劇といっても様々なジャンルの映画があります。剣豪・剣客物、平次・半七などの捕り物帳、仇討物、お家騒動、股旅・任侠物等があります。そうした中でも一番好きな時代劇は「股旅物」です。股旅は長谷川 伸によって始まったのだそうです。 長谷川 伸は昭和初期の作家で、今でも映画・ドラマ・流行歌などで目にする・耳にする「瞼の母」(番場の忠太郎)の作家です。股たびの何が私を惹きつけるのか? 一言で表現するなら「追われやくざの悲しき性」でしょうか? 「座頭市物語」を例にして話しましょう。 座頭市は「やくざ」ではありませんが、ほぼ同じような境遇を生きている「やくざ・按摩」とでも呼べるでしょうか。原作は子母澤 寛(新撰組始末記や勝 海舟などを書いた作家)。 彼の随筆「座頭市物語」(中央公論社の「ふところ手帳」に収録された短かい随筆集)で、子母澤は述べている。「な、やくざあな、御法度の裏街道を行く渡世だ、いわば天下の悪党だ。こ奴がお役人と結託するようになっては、もう渡世人の筋目は通らねえものだ。 俺達あ、いつも御法というものに追われ続け、堅気さんのお情けでお袖のうち隠して貰ってやっと生きていく。それが本当だ」これこそ股旅ものの真骨頂。 汚れて、追われて、堅気(世間)さまから蔑まれ、最低の場所にまで身を落として、破れ三度笠に薄汚れた道中合羽を羽織ったやくざ一匹。 法の世界の悪を斬る。正義だ、格だ、道徳だなんてご大層なイデオロギーを振りかざすこともない。 武士のようにお家のため、主君のため、なんて大義名分もない。 幕末志士のようにお国のためなんてこともない。 あるのは裏街道しか生きられない日陰者の意地か。この「汚れてしまった最後の意地」がやくざ一匹を支えている。 それが股たび物の良さだと思います。明日からこれまでに心に残った「股旅」映画について紹介していきましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・白梅
2010年02月10日
コメント(0)
-

椿/シベリウス ヴァイオリン協奏曲
今日のクラシック音楽 シベリウス作曲 ヴァイオリン協奏曲ヴィヴァルディなどのバロック音楽時代を経て、バッハ、モーツアルトに受け継がれてきたヴァイオリン協奏曲が、「サロン風」音楽から劇場型音楽に変えたのがベートーベンでした。 音楽は優美さと雄渾さ・雄大さが備わった協奏曲が、やがて交響楽的な響きのブラームスの協奏曲が生まれてきました。その後ロマン派作曲家の、ヴァイオリンという楽器の特性をフルに生かした個性ある美しい曲の数々が生まれてきました。 メンデルスゾーン、ブルッフ、ラロ、チャイコフスキー、ドヴォルザークなどを経て、20世紀にはバルトーク、プロコフィエフ、グラズノフ、ストラビンスキー、ハチャトリアン、ショスタコービチなどに受け継がれてきました。その中でもシベリウスの協奏曲は今でも人気があり、ヴァイオリニストたちの心をかきたてる曲の一つとして演奏会や録音でよく採り上げられています。シベリウスの祖国フィンランドは「湖沼の国」と呼ばれるくらいで千の湖と深い森林に覆われた国です。国土の70%が原始林に占められており、ごつごつとした岩だらけの風土に、暗い厳しい寒さという、過酷な自然環境に包まれています。シベリウスの作曲した交響曲や交響詩などは、こうしたフィンランドの森、湖を想像させるような情緒を醸し出した音楽で、清冽な美しさに満ちています。 私も仕事の出張で訪れたことがありますが、あの深い森とそこに点在する湖に立ってみて、初めてシベリウスの音楽が心に染み渡るようになりました。霧に覆われた神秘的な湖や、奥深い森の情景がまざまざと目に浮かんできます。 ある音楽評論家が「シベリウスの音楽世界には人が誰もいない」と表現していますが、そういう情緒を湛えていることは確かです。このヴァイオリン協奏曲もこうしたフィンランドの情景を彷彿とさせており、幻想的な美しい旋律が散りばめられた傑作です。 フィンランドの風が吹き渡るかのような清冽さにみちた美しい音楽が全楽章を包み込んでいます。シベリウスは謎の隠遁生活を送っていた1957年の9月20日に、脳出血のために91歳の生涯を閉じています。彼の訃報は全国に伝えられて、フィンランド放送番組は中断されて、シベリウスの名作「トゥネラの白鳥」が流されて哀悼の意を表したほど国民から愛された作曲家でした。シベリウスは、ヴァイオリン演奏でも優れた演奏家で音楽院で勉強中には、すでにメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を弾きこなしていたそうです。ただ彼はヴァイオリニストの道を歩まなかったのは、ステージに立つとあがってしまう性格だったので、ヴァイオリン演奏の道を断念したというエピソードが残っています。彼がヴァイオリニストとして研鑽を積んでステージに立つ道を選んでいれば、今私たちが聴いている素晴らしい音楽が生まれていなかったかも知れません。このヴァイオリン協奏曲が1904年の今日(2月8日)、フィンランドで初演されています。愛聴盤 (1)キョン・チョン・ファ(Vn) アンドレ・プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7007 1970年録音)キョン・チョン・ファの1970年の録音盤で、第1楽章の清冽なリリシズムとフィンランドの清澄な空気、そこはかとなく秘めた寂寥感がたまらない魅力です。LPからCDに変わっても何度も再発売を繰り返されてきた名盤で、今では1,000円で求めることが出来ます。(2)五嶋みどり(Vn) ズービン・メータ指揮 イスラエルフィルハーモニー繊細で内に秘めたる情熱が迸っているかのような美しいヴァイオリンの音色。 あとは聴く人の好みになるでしょう。私はキョン・チョン・ファに次いでとても好きな演奏です。(3)アンネ=ゾフィー・ムター(Vn) プレヴィン指揮 シュターツ・カペレ・ドレスデン(グラモフォン レーベル 447895 1995年録音 海外盤)ムター35歳の録音。 私が聴いた同曲で最も情熱的な演奏。これも好みで評価が分かれるでしょうね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・椿
2010年02月08日
コメント(4)
-

椿/ラロ 「スペイン交響曲」
今日のクラシック音楽 ラロ作曲 「スペイン交響曲」エドアゥール・ラロ(1823-1892)は弦楽器が好きであったのか、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロなどを演奏していたそうです。 この「スペイン交響曲」は名前こそ交響曲と名付けられていますが、実際は全5楽章からなるヴァイオリン協奏曲です。 いかにもヴァイオリンを知り尽くしたラロらしく華麗な協奏曲となっており、この曲を当時の優れたヴァイオリン奏者で作曲家でもあったサラサーテ(1844-1908)に捧げられています。ラロはフランス人ですが、祖父の代までは純粋なスペイン人だったそうで、ラロにもスペインの血が脈々と流れていたのでしょう。 しかし、彼の名前が作曲家として認められるようになったのはこの曲を発表してからだそうです。 42歳まで独身で生活に追われていた彼がアルト歌手と結婚して、その彼女から熱心に作曲を勧められてから本格的に活動を始めたそうです。 この曲はヴァイオリン協奏曲としては2番目の曲になり、名前もヴァイオリン協奏曲として残っている曲があります。 その協奏曲や以前にもこのページで紹介しました「チェロ協奏曲」やオペラ「イスの王様」などを書いています。ラロの名前は名実共にこの「スペイン交響曲」によって音楽史上に確立されていますが、時にラロが52歳という晩年でしたから、フランスのセザール・フランクやオーストリアのアントン・ブルックナーと同じく「大器晩成型」だったのでしょう。曲は濃厚なスペイン的情緒に溢れており、 曲の冒頭の独奏ヴァイオリンの華麗な、むせ返るような情熱的なメロディを聴いた瞬間から聴き手はスペインへと誘われたような気分になります。 血が騒ぐ闘牛場の熱気、フラメンコダンスのむせ返る官能的な情緒、熱くかき鳴らされるスペインギターの音色、地酒のワインとパエリャの香りが一度に部屋中に沸き立つかのような曲の始まりです。 そしてその気分が終楽章まで持続しています。尚、この1800年代後半はヨーロッパでは「旅」が頻繁に行われるようになったせいでしょうか、「エキゾチック(異国情緒)」ということに作曲家が魅かれており、チャイコフスキーの「イタリア奇想曲」、R.コルサコフの「スペイン奇想曲」やフランスのシャブリエの「スペイン狂詩曲」などにも窺えます。ラロ自身もこの曲同様に他のヴァイオリン協奏曲にサブタイトルを付けています。 彼は全部で4曲の協奏曲を書いており、2番にあたるのが「スペイン」、3番が「ノルウエー幻想曲」、4番が「ロシア協奏曲」と言う風にラロも流行のエキゾチック・ムードに乗って書いたのでしょう。しかし、この曲については、ラロに流れる「スペインの血」がこうした音楽を書かせたのかとも思います。またチャイコフスキー不朽の名作「ヴァイオリン協奏曲」は、彼がサラサーテの弾くこの曲を聴いて感動して書くようになったと伝えられています。 それは彼の支持者だったロシアのフォン・メック夫人宛の書簡に書かれているそうです。 大げさに言えば、この「スペイン交響曲」がチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を生んだという穿った見方もできます。この「スペイン交響曲」が1875年の今日(2月7日)、フランスで初演されています。愛聴盤サラ・チャン(Vn)シャルル・デュトワ指揮 ロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団(EMI原盤 EMIジャパン TOCE14237 1995年1月録音)ムター盤(小澤征爾指揮)を長い間聴いていましたが、サラ・チャン15歳の時のディスクも忘れられません。 今の若い演奏家はどうしてこうも技巧的に鮮やかなんでしょうね。惚れ惚れする技巧です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 椿
2010年02月07日
コメント(110)
-
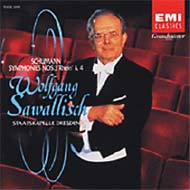
素心蝋梅/シューマン「ライン」
今日のクラシック音楽 シューマン作曲 交響曲第3番変ホ長調 「ライン」10年もの長いロマンスの末に結ばれたロベルト・シューマン(1810-1856)とクララ・シューマンの「夫婦愛」は有名な話で、シューマンが精神に異常をきたして亡くなっているので、余計にその夫婦愛が語り継がれているようです。私はそういうエピソードよりもロマンティックな情緒に溢れたシューマンの作品に魅かれています。 その中でも飛び切り好きなのがこの交響曲第3番変ホ長調「ライン」です。実に牧歌的情緒に満たされており、またロマンティックな情感に溢れかえっている名作・傑作交響曲。 曲の始まりからドイツの田舎的な描写が耳にこびりつくほどの、牧歌的でのどかな香り豊かな旋律が印象的。実はシューマンの交響曲を本格的に聴き出したのが、社会人になってからだと記憶しています。そして彼の交響曲を本当に好きになったのが、この「ライン」を聴いてからでした。第4楽章の壮麗なゴシック建築を想像させるような旋律は、初めて聴いた時には鳥肌がたった程でした。4つの交響曲の中ではこの「ライン」は秀逸のロマン派作品だと思います。そのシューマンの交響曲第3番「ライン」が1851年の今日(2月6日)、作曲者自身の指揮によってデュッセルドルフで初演されています。愛聴盤ウォルガング・サヴァリッシュ指揮 シュターツ・カペレ・ドレスデン(EMI原盤 EMIジャパン TOCE3265 1972年録音)バーンスタイン盤、ジンマン盤、ハインティンク盤も聴いていますが、やはり古色を感じさせるこのサヴァリッシュ盤を聴く機会が一番多いようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の写真 素心蝋梅今が旬の花。黄色い花をあまり好みませんが、この蝋梅と菜の花は別ですね。
2010年02月06日
コメント(0)
-
朝青龍引退表明
横綱 朝青龍引退表明昨日午後4時頃に高砂親方と記者会見を開き、横綱朝青龍が引退を表明した。 この初場所中に起こった朝青龍の泥酔殴打事件への責任を取って、自ら身を退くことになった。 場所中に朝方まで酒を呑み泥酔すること自体が、全力士の鑑となるべき横綱の風格・威厳・誇りなどを汚すあるまじき行為で、これだけでも相当重い懲罰が下されるべきであるところに、一般人への横綱からの暴行まであれば(しかも最初は協会への虚偽の報告だったそうだ)、協会からの処分を待たずとも自分でけじめをつけるべき問題だった。その意味で当然の帰結と言えるのだが、今回の騒動はこれだけには終わらない。いや終わらせないと協会はすべきである。 この引退表明によって全てが幕引きされたのでは、真実がうやむやになってしまう。協会は引き続き真相を解明する調査を続けて、その結果を公表する義務がある。それをやらなければ、貴乃花親方を新理事に据えて協会の改革を願う「新しい波」は絵空事になってしまう。 今回の理事選挙で公職選挙並みに公平さを望んだ協会が、結果は立浪一門の造反者探しという「反省会」開催という、珍事態を引き起こして安治川親方の廃業騒ぎまで起こった古い体質丸出しの相撲界。「新しい波」によって改革を進めて行かなければファンはますます離れていく。 今私がここで主張していることは、一般社会では「改革」でもなく「当たり前」の「常識」に属することなのだ、ということを協会は肝に銘じて欲しい。朝青龍引退表明を聞いて、記者インタビューで涙を流して悲しんだ横綱白鵬の姿を協会は何と考えるのか?
2010年02月05日
コメント(2)
-
電車内での化粧
電車内で化粧する女性女性が電車内で化粧をしているのを時々見かけるが、平手打ちをしてやりたいくらいに腹がたつ。 これほどまでに礼儀をわきまえない女性がいるのかと怒ると同時に悲しく情けなくなる。化粧は本来の姿を隠す仕業であり、公衆の面前でやるべきことではない。 私の最寄駅からその線の終着駅まで各駅停車で45分かかる。 私が駅から乗り込んだ時には、その女性はもう座席に座って化粧をしていた。 それが終着駅まで延々と化粧を施している。まあ、この女性の場合は例外に属するだろうが、それでも大概20分ほどかけて施している。私のこういう思いは現代では「時代遅れ」なのだろうか? 出来れば女性の意見を聴きたいと思わずにはおれない問題だ。
2010年02月04日
コメント(12)
-

ヒメツルソバ
今日の写真 姫蔓蕎麦蓼科ヒマラヤ原産明治時代に伝来指揮を通じて咲いている花
2010年02月01日
コメント(0)
-
ヒメツルソバ
今日の写真 姫蔓蕎麦img src="http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/28/0000050928/82/img61c2ef02zik7zj.jpeg" width="426" height="640" alt="ヒメツルソバ">蓼科ヒマラヤ原産明治中期に遠来丈の低い草花が絨毯のように群生していく。年中どこかで見える花
2010年02月01日
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
-

- 好きなアーティストは誰??
- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…
- (2025-10-26 11:00:38)
-
-
-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 【輸入盤】ミニ・アルバム:ラッシュ…
- (2025-11-25 00:00:11)
-
-
-

- 吹奏楽
- ちくたくミュージッククラブ7thコ…
- (2025-11-22 23:43:42)
-







