2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010年06月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

花蓮/大相撲の危機
「大相撲の危機」賭博特に野球賭博に関連する不祥事に厳しい意見が出された。 野球賭博に関与した現役力士の出場辞退、大嶽親方、大関琴光喜の解雇もしくは除名。 時津風親方の降格、協会幹部役員12名への謹慎等の厳しい条件を呑んだ上での、名古屋場所開催と協会の臨時理事会で決まり、協会としての処分は7月4日に行われる。この決定は当然のことだと思う。 野球賭博は必ず胴元がいないと成立しない賭けごとであり、暴力団などの反社会的勢力でないと胴元となって仕切ることがない賭けごとであり、このことを全く知らずにやっていた力士もいるらしい。このような反社会問題を起こして幕内力士7人までも、それも上位に位置する力士の名古屋場所出場不可となった状態で開催される本場所の意義について、私は大いに疑問を感じる。いびつとなる15日間の取り組み、幕内上位の力士が歯抜けのように居なくなっての千秋楽への高まりの激減(横綱白鵬の優勝と決めてかかる前にやはり場所前の他の力士への優勝の可能性を抱いて)等、場所への興味が減ってしまう。更に、もし警察が必要と判断した場合の、出場力士からの傍証を取る必要が生じた時に、力士の場所への集中力の散漫を恐れる。 ならば昔、私がまだ子供だったころに「準本場所」というのがあって、名古屋と福岡場所がそれだった。年間4場所制の頃だったかな。 当然「準」で残した成績は公式記録とされなかった。来月どうしても名古屋場所を開催するなら「準本場所」にすればどうだろう?そうすればNHKも放映中止の判断が出来るだろう。 一場所語とに五億円を相撲協会に放映権料として払っているNHKが現在逡巡するのは理解できる。これが民間TV局ならスポンサーがつかないだろうと思う。 NHKは国民の税金と受信料の徴収で成り立っている放送局。 五億円ものお金を払って放送する可否を考えるのは当然。どうしても開催するなら異例の措置として「準本場所」とすべきだと思う。ここまで大相撲を傷つけた代償は高くつくが、夢を叶えたいと相撲道の扉を叩いた若者もいる。その人たちが尚も夢を見ることが出来るように「大相撲」は努力をしてもらいたい。それを願うばかりだ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 花蓮~三室戸寺京都 三室戸寺にてカメラ Pentax K-10Dレンズ Tamron 28-300mm XR Di
2010年06月30日
コメント(0)
-
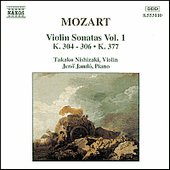
名曲100選~モーツアルト/花菖蒲
「名曲100選 モーツアルト作曲 ヴァイオリン・ソナタ第28番 ホ短調」今日もモーツアルトの作品から。私はあまりモーツアルト(1756-1791)の音楽を好んで聴きません。 あまりに明るく過ぎて華麗でロココ調そのままという音楽が私に合わないのだと思います。 同じ古典派ではハイドンの音楽は素直に心に入ってきますが、モーツアルトはそういう訳にいきません。感動はしますが心に入り込んできて琴線を震わせることがあまりないのです。これはクラシック音楽を聴き始めてから54年来続いており、今でもその理由はわかりません。 ピアノ・ソナタ、弦楽四重奏曲、その他の室内楽作品、協奏曲、交響曲など心に入り込んでくるのはごくわずかの曲です。モーツアルトのほんとに感動する作品は短調の曲が多いのです。ほとんどの作品が愉悦感にあふれ華麗で明るく、典雅な調べに対して、終世貧乏で過ごしたモーツアルトが本音で書いた「悲しみ」を表したのが短調の音楽のように思えます。故小林秀雄氏(評論家・随筆家)が「疾走する悲しみ」と名言を残していますが、モーツアルトの悲しみは後のチャイコフスキーなどのようなアダージョで書かれた直截的な悲しみ表現ではありません。アレグロで書かれた悲しみはいっそう人の心に入り込んでくるのでしょう。 代表的なのが交響曲第40番のト短調であり、25番のト短調交響曲です。アレグロで書かれた悲しみは聴く者の胸をえぐるような悲哀感があります。 ト短調で書かれた弦楽五重奏曲もそうです。こうした短調の曲に感動を覚えるのは、どれも劇的な感じがして、モーツアルトの本心を吐露した音楽・作品だからだと思います。今日の話題曲ヴァイオリン・ソナタ第28番もホ短調で書かれており、40曲以上にのぼる彼のヴァイオリン・ソナタの中でも唯一の短調の作品です。他のヴァイオリン・ソナタに比べて劇的緊張感が2楽章の音楽全体を覆っており、ハッと耳を澄ませて聴いてしまう音楽です。モーツアルト特有の伸びやかな旋律が少し暗い雰囲気を醸し出して、彼の悲しみをひたひたと訴えてくるような感じがします。 「何故、そんなに悲しいの?」と問いかけたくなるほどです。彼の時代は室内楽はまだ「ハウス・ムジーク」(家庭内音楽)として定着していたころですから、華美に華麗に典雅に書かれた音楽が王侯貴族に好まれる時代でしたから、他のヴァイオリン・ソナタもほぼその傾向にあり、この第28番だけは異色です。音楽にも深さがあり彫刻的な美しさにあふれた音楽が、わずか15分足らずの間にモーツアルトの別の世界に引きずり込まれるような感じがしてなりません。愛聴盤 西崎崇子(Vn) イェネー・ヤンドー(P)(Naxosレーベル 8.553110 1994年録音)Naxos社長夫人でもあり、ヴァイオリン教授の鈴木メソッドの最初の生徒であり、世界でも一番数多く録音を遺している西崎の美音はとても素直で、個性のない個性とでも呼べる心を預けて聴ける数少ないヴァイオリニストの一人です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 花菖蒲大阪府堺市大仙公園内 日本庭園にてカメラ Pentax K-10Dレンズ Tamron 28-300mm XR Di
2010年06月29日
コメント(0)
-
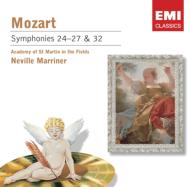
名曲100選 モーツアルト/花菖蒲
「名曲100選」~モーツアルト作曲 交響曲第25番 ト短調W.A.モーツアルトは35歳の生涯で番号を付けられただけでも交響曲は41曲。それらの中で短調の曲は2曲だけで、他の39曲はすべて長調で書かれていて底抜けに明るい音楽ばかりです。 しかもこれら2曲の短調はどちらも「ト短調」で「走りぬける悲しみ」として表現されるようにアレグロという速いテンポの中に「悲しみ」が塗りこまれています。2曲のト短調のもう一つの方は有名な第40番です。 私はベートーベンやブラームス、ブルックナー、それ以前のバッハ、ヘンデル、ハイドンなどの音楽に比べてあまりモーツアルトを好まないのですが、彼の書いた短調にだけはどうしても耳が寄っていきます。弦楽五重奏曲第4番、ピアノ四重奏曲第1番、ピアノ三重奏曲(いずれもト短調)、それにピアノ曲では「イ短調」の第8番、ハ短調の第14番、ヴァイオリン・ソナタではホ短調の第28番、それに協奏曲では第20番ニ短調など彼の短調の曲はすべて好きです。アレグロで迫ってくる速めのテンポの悲しみは、いつ聴いても私の胸をえぐってくるような哀しみ・悲しみを誘います。モーツアルトの「悲しみ」は後のロマン派やロシアの作曲家のような遅いテンポでのたうちまるような「悲哀」でないところに深い共感を覚えるのでしょうか。 彼は純粋な心を持った人間であったと研究者は書いています。 目の前に起こる現象や人の言葉をそのまま受け入れる純粋な魂の持主であったと言われています。モーツアルトのエピソードの中にこういうのがあります。 彼は子供の頃から同じ質問をするのが好きで、「僕のこと好き?」と訊き「好きだよ」と言われると飛びあがって喜び、「好きじゃじゃないさ」と言われると両目にいっぱい涙をためていたそうです。この第25番はモーツアルト17歳の頃に書かれたと言われており、第40番に対して「小ト短調」とも呼ばれる作品ですが、41曲の交響曲の中でたった2曲しか書かなかった短調の曲は何を意味しているのでしょうか? 第1楽章冒頭等の劇的とも言える「悲しみ」の表現は「目にいっぱい涙をためている」17歳のモーツアルトが、心の悲しみを精一杯に訴えてくるようです。愛聴盤 ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団(EMIレーベル 5864222 1987年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 花菖蒲大阪府堺市大仙公園内 日本庭園カメラ機種 Pentax K-10Dレンズ Tamron 28-300mm XR Di
2010年06月27日
コメント(2)
-
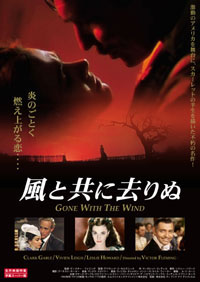
名曲100選~映画音楽/花菖蒲
「名曲100選」~映画音楽からクラシック音楽ではありませんが、それと同様に私の心に残っている音楽~バッハやベートーベン、ブラームスの音楽同様に~についても書いてみたいと思います。映画そのものと共に残っている音楽、しかも今なお聴き続けている音楽。 たくさんの映画音楽がありますが、その中からどうして外せない音楽を挙げてみました。1.「タラのテーマ」~「風と共に去りぬ」(マックス・スタイナー)2.オープニング・テーマ~「大いなる西部」(ジェローム・モリス)3.「ベン・ハー」序曲(ミクロス・ローザ)4.「ひまわり」のテーマ(ヘンリー・マンシーニ)5.「ゴジラ」(伊福部 昭)これら5つの音楽は、今でも聴き続け、これからも生きている限り聴いていきたい、クラシック音楽と変わらぬ永遠なる輝きを持った音楽だと感じています。 1.は映画のみならず原作までを彷彿とさせる様なマックス・スタイナー会心の音楽でありスカーレットが、去って行ったバトラーのことを「レットを取り戻すことができる。みんな明日、タラで考えよう。 明日は明日の陽が照るのだ」とつぶやく、人間に無限の勇気を与えてくれる言葉が読みがえってくる素晴らしい音楽です。2.はウイリアム・ワイラー監督が「ローマの休日」の翌年(1958年)に撮った西部劇で、この当時主流だったガンマンを主人公にせずに広大な西部に生きる男女の人間模様を描いており、気宇壮大な西部の光景と人間、しかし大地ではなくてもっと広大なる「海」を航海した船長との闘いを格調高く謳い上げた西部劇映画の傑作で、オープニングに奏されるこの音楽は、映画の駅馬車の車輪を背景に、高らかに「人間賛歌」を讃えているように思います。3.これもウイリアム・ワイラー監督の1959年の製作。ここで何かを言えば蛇足となりますので何も書きません。超有名映画ですから。その音楽も荘厳と愛と勇壮に満ちており、1961年にシネラマ上映館の大スクリーンで観て、まだ絵が現れないときに流れたこの音楽に鳥肌立った思い出が忘れられません。4.哀しい映画音楽の代表として採り上げました。「自転車泥棒」以来の反戦をテーマにした、イタリア市民男女の恋愛をこれほどに哀しく、これほどに戦争を憎む映画があったでしょうか。映画終わりの場面、それぞれの家族を持つかつて愛し合った今でも愛している二人のローマ駅での別れのシーンは何度観ても涙があふれてきます。マンシーニの最高傑作ではないでしょうか。5.1954年(昭和29年)の「ゴジラ」第1作。 「ドシラ・ドシラ・ドシラ」と刻む音楽は一度聴いたら忘れられない名旋律。「ゴジラ」の代名詞とでも言える音楽です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 花菖蒲大阪府堺市大仙公園内「日本庭園」にてカメラ機種 Pentax K-10Dレンズ Tamron 28-300mm 1:3.5-6.3 Aspherical XRDi
2010年06月26日
コメント(0)
-

紫陽花~墨田の花火
日本サッカーティームが決勝トーナメント進出を果たした。デンマーク戦を堂々と3-1で下しての進出。海外でのW杯では初めて。 凄いぞ、ニッポン、頑張れ、ニッポン!!明日からまた名曲100選を書かなければ。大阪市立長居植物園にてカメラ機種名 Pentax K-10Dレンズ Pentax 100mm マクロレンズ
2010年06月25日
コメント(2)
-

顎紫陽花
自宅庭に咲く花であれば出来る限り花に近づいて、マクロレンズの世界で面白い構図などを撮れますが、この画像は大阪市立長居植物園での撮影ですから、花に近寄って撮影するのに限度があって中途半端な構図になっています。以前紫陽花に咲き乱れる中に入り込んで撮影をしていると、学芸員や警備員に注意されたことがあって、この撮影ではロープの中に入らずにおとなしく優等生の振る舞いで撮影。大阪市立長居植物園にて大阪市立長居植物園にてカメラ機種名 Pentax K-10Dれんず Pentax 100mm マクロレンズ
2010年06月24日
コメント(2)
-

オギタリス
ジュリエッタ・シミオナートが亡くなっていた。イタリアの世界的メゾ・ソプラノ歌手。私にとってオペラを好きにさせてくれたデル・モナコ(テノール)、レナータ・テバルディ(ソプラノ)と共に正にオペラの原点となる歌手だった。5月5日100歳の誕生日を1週間後に控えて亡くなった。その事実を知ったのが一昨日の夕刊。ひどい衝撃。いずれ気持ちが落ち着けばこの人のことを書いてみようと思っている。大阪府和泉市にてカメラ機種名 Pentax K-10Dレンズ 100mm マクロ・レンズ(Pentax)
2010年06月23日
コメント(0)
-

紫陽花~シチダンカ
撲協会の理事たちは社会の常識からかけ離れたところで協会を運営しているのか、と思いたくなるような最近の迷走ぶり。賭博をやったことを自主申告すれば「厳重注意」処分に留めるから申告しなさい、なんてこんなふざけた話は社会では通用しません。例えば一般の企業内で賭博に関わった事件が起こり、「自主申告すれば厳重注意処分に留める、警察には言わない」なんてことがありますか?しかもこれだけの申告者(大関などの力士、部屋持ちの親方衆など)が野球賭博(胴元がいる賭博です。賭け麻雀や賭けゴルフではありません)に関与していたと告白しているのに、名古屋場所を行うか否かを7月4日に決めるなんて、何を言ってるのかと問いたい。 場所の初日は7月11日ですよ。力士たちの名古屋入りは6月27日なんですよ。力士への暴行事件、麻薬吸引事件、暴力団との交際、今度の賭博事件。 これだけ次々と事件を起こしたスポーツ団体しかも公益法人(税金の納税を確か20%までに許されているはず)がありましたか?いい加減にしろよ、元相撲取りのおじさんたち!、と言いたくなります。大阪市立長居植物園にて撮影機種 Pentax K-10Dレンズ Pentax 100mm マクロレンズ
2010年06月22日
コメント(6)
-
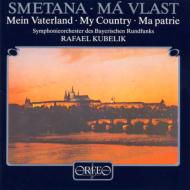
「わが祖国」 名曲100選(2)
スメタナ作曲 交響詩「わが祖国」クラシック音楽には強烈に母国・祖国を誇り高く謳いあげた作品が数多く遺されています。フィンランドの作曲家シベリウスが書いた交響詩「フィンランディア」がもっとも有名曲の一つでしょう。またスペインのグラナドスが書いている「スペイン舞曲」やチェコのドヴォルザーク作曲の交響曲などもその例にもれません。そのチェコでももう一人有名な作曲家で作品名がそのものずばりの「わが祖国」という連作交響詩が遺されています。現在世界中で様々な音楽祭が催されていますが、開幕日と開幕のコンサート・プログラムが発足以来変わることのない音楽祭があります。 それはチェコの「プラハの春」と呼ばれるフェスティバルです。第2次世界大戦後すぐに催された音楽祭で、開幕日は5月12日でオープニング・プログラムはペドルジーハ・スメタナ(1824-1884)作曲のその連作交響詩「わが祖国」が、初めての音楽祭以来変わることなく続けられています。それはこの5月12日は「チェコ音楽の父」とチェコ国民から呼ばれているスメタナの命日になるからです。チェコスロヴァキアは長い年月オーストリア帝政時代の占領統治下にあり、その圧政に国民が疲労困憊の状態でした。 ヨーロッパ全体が帝国主義国によって支配されていた国が多かったのですが、スメタナの時代になって欧州に民族主義運動が広がっており、政治・文化の両面で大きな運動の波が押し寄せており、スメタナが生まれたボヘミアでも民族主義運動が高まっていた時代でした。スメタナは熱烈な愛国者であり「民族自立」へ熱い志を持っていて、オペラ「売られた花嫁」によって見事に民族音楽への基礎を確立したあと、この連作交響詩「わが祖国」がスメタナの祖国愛の迸りから生まれていて、祖国の大自然や歴史的英雄の回顧や土地などを題材にしており、6曲の交響詩から構成されています。 これらの音楽には、チェコスロヴァキアの豊かな緑に恵まれた自然をスメタナの限りない祖国への愛情で音楽として表現されています。オーストリア圧政の時代にも、1968年の旧ソ連の軍事介入による悲劇の時代にも、チェコの人々に勇気を与え続けた音楽で、「プラハの春」音楽祭開幕をスメタナの命日にあたる5月12日として、そのオープニング・プログラムがこの「わが祖国」でチェコフィルハーモニー管弦楽団によって演奏されると決められたのでした。スメタナはベートーベンと同じく難聴で苦しんだ作曲家でした。 この「わが祖国」の第1曲「高い城」の作曲に取りかかった時にはスメタナ50歳で、もう難聴はかなりひどい状況で、第2曲「モルダウ」が作曲された頃には、完全に耳が聞こえないという何とも痛ましい病状だったそうです。作曲家・音楽家にとって痛恨の病状のなかで、スメタナは5年の歳月をかけて6曲の音楽を完成して1882年に全曲が初演されたのですが、その時には自分の書いた音楽を「音」として自分の耳で聴くことが出来ない状態だったそうです。 その頃には精神錯乱を起こすようになっており、2年後の1884年5月12日に、祖国独立のため、民族音楽のために戦い抜いて、もう成す術がなく「矢折れ、刀尽きた」とばかりに、60年の生涯を精神病院で壮絶な最後を遂げたと言われています。第1曲「高い城」ハープによって憧憬に満ちたような美しい主題が冒頭から奏でられます。 モルダウ河のほとりには中世ボヘミア王国の古城ヴィシュフラッドが現在でも建っており、そこには伝説の吟遊詩人ルミールが住んでいたとされており、英雄の歌や愛の歌を歌っていたのです。このハープによる主題はルミールの竪琴を表していて、この旋律は第1曲の主題だけでなく、全曲を通じての重要な主題となっています。この主題が変奏されてかつての栄光の祖国への回想と、ボヘミアの栄枯盛衰の歴史をつぶさに眺めてきた「高い城」によって祖国愛を語っていると思います。第2曲「モルダウ」「わが祖国」中で最も有名な曲で単独で演奏会や録音などで採り上げられています。 「モルダウ」とはチェコ中央部を流れる大河モルダウ河のことで、その河の景観を描いています。曲冒頭ではボヘミア南部の森の水源から湧き出す水を表現しているような旋律によって河の起こりを表しており、次第に水かさを増し川幅を広げてやがて大河となってボヘミアの森と野を流れプラハに至る様を、美しく、とうとうとした旋律で表現されており、全曲中最も美しい部分でこの作品の白眉となっています。そして河の周囲に住む農民たちの踊りや、静かな月光の夜の水の精や、河の急流や、高い城が描かれていき、まるで河を船で下るかのような音の絵巻物のような音楽にあふれた、メンデルスゾーンも脱帽の「音の風景画家」といった、あらゆる交響詩の中でも最高の名作かと思います。第3曲「シャルカ」チェコの伝説に「シャルカ」という伝説の女王がいたそうです。 スメタナは彼女の伝説を採り上げて、祖国の栄光の歴史を偲んでいるようです。伝説では、シャルカは恋人に裏切られ男への復讐を誓うのですが、シャルカを討つために派遣された騎士ツティラートは、彼女を捕らえますが、木に縛られて苦しむシャルカの美しさに魅かれて彼女を彼女を解放します。シャルカはツティラートとその部下に酒をふるまい酔っ払ったところで、ホルンで女性軍を呼び寄せ追討者たちを全滅させてしまいます。この曲はこういう伝説を音で描いています。第4曲「ボヘミアの牧場と森から」「モルダウ」に次いで親しまれている曲です。 輝く陽光が降り注ぐボヘミアの草原、収穫に感謝する農民の歌と踊り、森を吹き渡っていく風、小鳥たちのさえずり。 ここにはボヘミアの自然と森への感謝を込めた「自然賛歌」があります。 親しみやすい美しい旋律の曲です。第5曲「ターボル」「ターボル」とはチェコ民族主義運動の一つの象徴で、チェコの「フス戦争」時代に最も急進的で独立政権が樹立されたこともある町のことです。中世にはチェコスロヴァキアにも宗教戦争がありました。 その時代の祖国のフス教徒の英雄的な戦いを描いています。15世紀初頭、フス教徒たちが宗教改革運動がボヘミアに広がるのを機に、カトリック教と対立するのですが、逆に弾圧によってフス教徒は火炙りの刑に処されてしまいます。これによって「フス戦争」という民族独立戦争にまで発展してゆきます。この曲はフス教徒のコラールが主題で、チェコ民族主義運動への強い決意と意志の力を表現しているかのようです。第6曲「プラニーク」「プラニーク」はボヘミアにある山の名前で、プラニーク山には騎士たちが永遠の眠りについており、祖国に危機が訪れると眠りから起きて祖国を救うために現れるというボヘミア伝説を採り上げて、スメタナは祖国の自主独立を願ったのでしょう。第5曲「ターボル」で奏でられたフス教徒のコラールが、この曲で主要な旋律として再び使われています。 スメタナにはプラニーク山に眠る伝説の騎士はフス教徒であったのかも知れません。スメタナは、全曲を締めくくるこの第6曲で民族独立の賛歌を高らかに歌い上げ、第1曲「高い城」の主題が再現されてを高らかに誇るかのように「わが祖国」を閉じています。愛聴盤 ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団( OREFEOレーベル ORFEO115841 1984年ミュンヘンライブ録音)クーベリックが祖国チェコへアメリカから帰国後「わが祖国」を、チェコフィルを振って感動的な祖国復帰を成し遂げた後に、そのチェコフィルを伴って来日を果たしてくれました。その公演の際に東京で行われた「わが祖国」の演奏はまさに感動的でした。わたしはあれほどの演奏をいまだ聴いたことはありません。公演ではなくてNHKの「芸術劇場」で放映された番組を観ただけなのですが、今でも録画画面でその感動を繰り返し味わっています。このCDも手兵だったバイエルン放送交響楽団を振って、東京公演と変わらぬスメタナと祖国への想いを切々と訴えかけてくるかのようなリズム処理、旋律線の際立った美しいラインなど、いつ聴いても惚れ惚れとする演奏です。ヴァツラフ・ノイマン指揮 チェコフィルハーモニー管弦楽団 (DENON CREST1000シリーズ COCO70604 1982年11月5日 東京ライブ録音)「わが祖国」初演100年を記念して行われた東京公演ライブ録音で、ここでもノイマンの卓越した民族色豊かな表現を味わうことが出来ます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 アマリリス自宅庭にて
2010年06月21日
コメント(0)
-
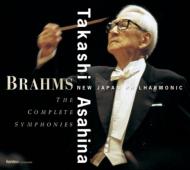
名曲100選(1)
またまた長い休眠状態でした。特に体調不良でもなく時間もなく、という理由ではなくて何となく書く気力湧かずにいた、というのが本当のところのようです。 さあ、いつまで続けることが出来るのか全く自信のようなものがないのですが、頑張って書いていきます。ブログそのものは「プレリュード」ですが、従来と変わらずクラシック音楽を主流にしています。その日の記念曲や作曲家・演奏家の誕生日・命日に因む曲を採り上げて書いていましたが、今日からは「名曲100選」と銘打って私の独断と偏見で選びました100曲の作品を主流にして書いていきます。ブラームス作曲 交響曲第2番ニ長調 作品73ヨハネス・ブラームス(1883-1897)は私の大好きな作曲家の一人です。彼は4曲の交響曲を残していますが、最初の交響曲第1番の作曲に20年という歳月をかけて書いていたことは有名な話です。 ベートーベンの交響曲が壁になっており、それらを超越する作品を書くためにこれだけの年月を費やしたと言われています。 もしこれほどの年月を要さずにせいぜい2~3年で書きあげてくれていたら、もっと数多くのシンフォニーを私たちは楽しんで入れたかも知れないと想像しますと、ちょっぴり残念という気もします。 その第1番は古典的様式美を保ちながらロマンの香りを漂わせる畢生の名曲 として完成して現代では指揮者、オーケストラの重要なレパートリーとなっています。 また録音では夥しい数のディスクが発売されています。その第1番のあとに書かれた交響曲第2番は約4か月で完成しています。 おそらく大好評だった第1番で交響曲作曲家として絶大な自信を得た結果であろうと推測されます。 あるいは20年の間に交響曲作曲のとしてのノウハウを得ていたのかも知れません。 ブラームスとしては早書きとして特筆すべきことだと思います。この交響曲第2番は2つの地で書かれています。 1877年の夏、南オーストリアの避暑地ベルハッチャで書きだされています。 ベルハッチャは写真で観ると南オーストリアの山々に囲まれたヴェルター湖畔にある美しい、風光明媚な避暑地です。 ブラームスの友人宛に送った手紙に書かれたベルハッチャの美しさに心を奪われたことが書かれているそうです。 そして二度にわたり夏にはここで過ごすブラームスは、よほどこの地を好んでいたのでしょう。曲はドイツのバーデン・バーデン近郊のリヒテンタールで9月から10月にかけて完成しており、初演は1877年12月30日にハンス・リヒター指揮 ウイーンフィルハーモニーによって行われています。 この初演は大成功だったそうです。 第3楽章が終わると熱狂した聴衆がアンコールを要求して再度演奏されてから終楽章へと移ったという有名なエピソードが残されています。ブラームスは、作曲時の風景や環境・雰囲気を作品に反映させる作曲家であったと言われていますが、この第2番もブラームス好みの風光明媚で明るいペルハッチャで作曲が大いに影響しているのでしょう。 第1番の劇性の強い曲とは対照的な作品に仕上がっています。 別名「ブラームスの田園」と呼ばれることもあるこの曲は、とてものどかで、柔和で温和、人間的な深みを増しており、喜びにあふれています。 しかしこの音楽を聴いて何を空想するかは聴き手に委ねられますが、この作品は表題音楽ではなくて、やはり絶対音楽として書かれています。 第1番のような規模の大きさでもなく、暗から明への解放、苦悩から歓喜へという推移もみられないし、調性も短調ではなく全楽章が長調で書かれています。 木管をふくらみのある音にしてみたり、トロンボーンやテューバを弱く吹かせたり、柔らかい音色を出すことに苦心しています。終楽章のコーダは、まさに喜びの爆発とでも言えそうな音楽で閉じています。古典的形式美という造形を踏まえながら、音楽はロマンの香りをまき散らしたような美しい交響曲です。愛聴盤朝比奈 隆指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団(フォンテック・レーベル FOCD9206 2000年10月14日 サントリーホール・ライブ)おそらく今まで聴いた最上の演奏と断言できるくらいに、曲の隅々まで血が滾っているような、息を呑むことさえ遠慮しなければならないような凄い一期一会とでも言えるようような、白熱した演奏記録が刻まれています。実はこのCDは3枚組のブラームス交響曲全集で、どの曲も素晴らしい演奏ですが特にこの第2番は特筆に値する記録です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 キキョウソウ 大阪市立長居植物園にて
2010年06月20日
コメント(10)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-
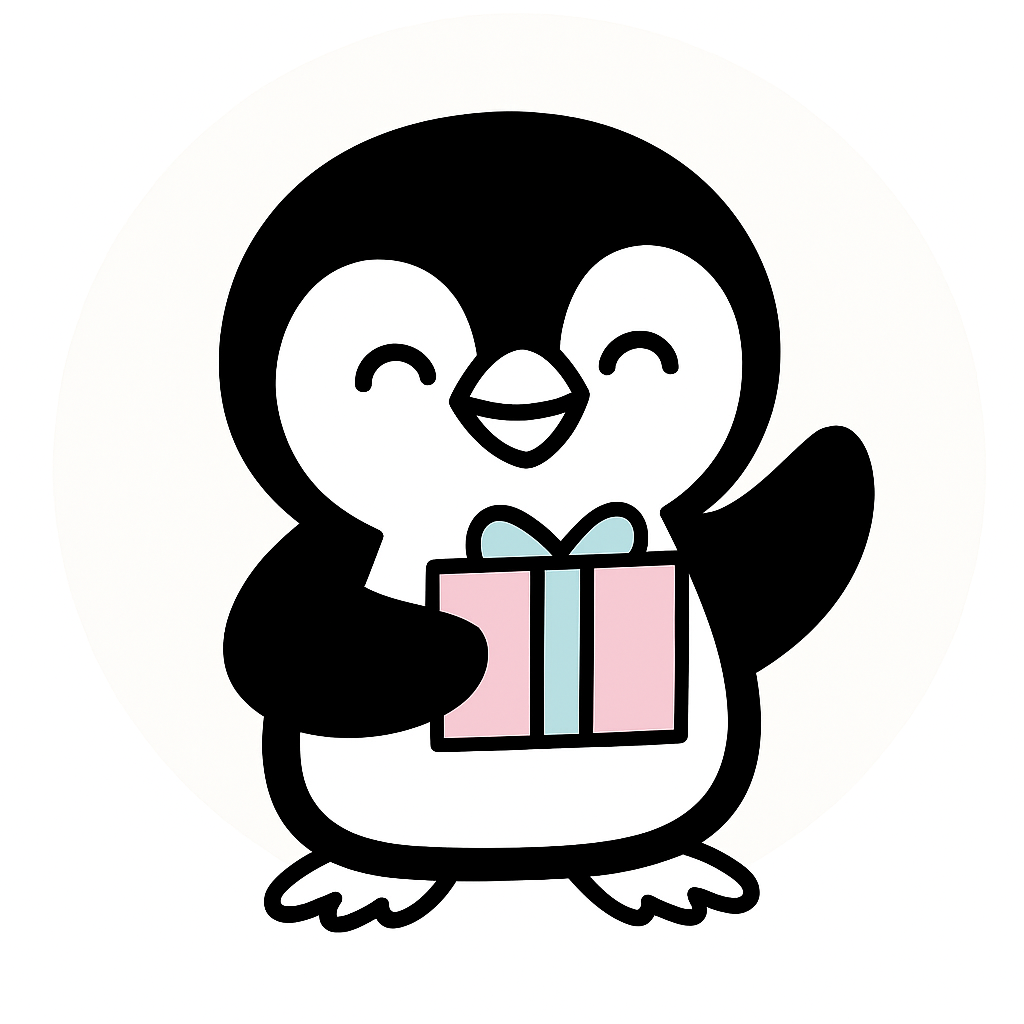
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-
-
-
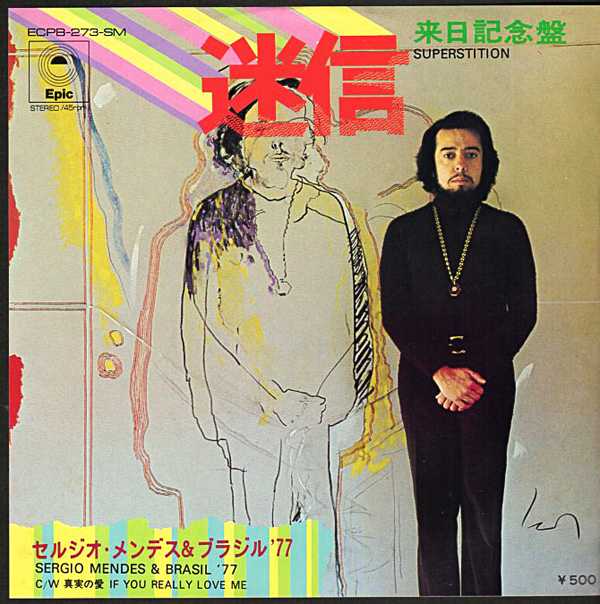
- 今日聴いた音楽
- セルジオ・メンデスとブラジル'77『…
- (2025-11-24 05:40:11)
-
-
-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 【輸入盤】ミニ・アルバム:ラッシュ…
- (2025-11-25 00:00:11)
-







