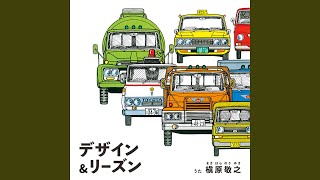2007年04月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
その後の出版実績
出版なんでも相談室(その後の出版実績)1か月ほど前に、当方の出版実績をご紹介しましたが、その後、この1か月間に次の本が出版されました。「インテリアコーディネーター合格!」(小野あゆみ著:彰国社)「3人の愛妻と大資産を手に入れた私の成功法則」(藤田隆志著:マキノ出版) 「ざっくり分かるファイナンス」(石野雄一著:光文社)「アメリカのフードビジネスに学ぶこれからの繁盛飲食店」(京原和行著:同文舘出版)「こんな一言があなたを美人にする」(美藤いづみ著:日本実業出版)テーマはそれぞれまったく異なりますが、タイトルをご覧になって、「面白そうだな」と感じた本がありましたら、ぜひご覧ください。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月27日
コメント(0)
-
メールだけじゃ、信用できない!
出版なんでも相談室(メールだけじゃ、信用できない!)お問い合わせをされる方のなかには、「メールだけじゃ、信用できない」ということで、直接お会いしたいと言ってくる方もいらっしゃいます。(もっとも、「信用できない」とはっきり言う人はおりませんが)そのお気持ちはとてもよくわかります。メールだけのやり取りでは不安になるのも当然です。そんなときは、いつでもお会いさせていただいております。面と向かって話をするうちに、その方の考え方やお人柄が伝わってきますし、企画の内容もイメージしやすくなってきます。不思議なことに、面談を望む方の多くは東京近郊の方ではありません。地方の方、特に大阪や兵庫の方が圧倒的に多いのです。わざわざ新幹線に乗って、会いに来られるのですから、そのエネルギーには驚かされます。大阪や兵庫の方は、自分の企画に対する思い入れが強いので、お話をうかがっていて、こちらが引き込まれていきます。そんな会話ができるのも、この仕事の楽しみの1つです。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月25日
コメント(0)
-
メールで企画のイメージをつかむのはむずかしいのでは?
出版なんでも相談室(メールで企画のイメージをつかむのはむずかしいのでは?)前回のブログをご覧になった方から、こんなご質問が寄せられました。「メールのやり取りで企画のイメージをつかむのは大変では?」たしかに、一見するとメールで企画のイメージをつかむのは大変なように思えます。しかし、これまでの経験からいいますと、何度か質問していくうちに、イメージは鮮明になってくるものです。そして、その質問とは、企画の立案者がそれまで考えてみたことのない質問だったりします。そんな質問に接していくうちに、立案者の頭の中で、企画の内容がはっきりしてきたり、新たな発想が浮かぶことがあります。要するに、私の頭の中で企画のイメージが明確になるだけではなく、立案者も改めて自分の企画のイメージを鮮明にすることができるのです。この作業を繰り返すことで、企画の良さが浮き彫りになってくるのです。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月23日
コメント(0)
-
企画書の形式は一切問いません。こんな感じのメールで結構です
出版なんでも相談室(企画書の形式は一切問いません。こんな感じのメールで結構です)このブログを開始してから、これまでにいろいろな企画が寄せられてきました。そこで気がついたことがあります。企画を寄せてこられる方の多くが、「しっかりした企画書を作ったうえでメールしなくてはならない」と感じていらっしゃることです。送られてくる企画書を拝見すると、いかに形式を整えるかに腐心されている様子がとてもよくわかります。しかし、そんな気づかいは一切無用です。「こんな企画を考えているのですが、どうでしょうか?」といった感じのメールで十分です。そのあとで、私のほうからいくつか質問させていただきますので、それに答えていただければ企画のイメージはつかめますし、メールでのやり取りを何度か繰り返すうちに、きちんとした企画書に仕上がっていきます。一発で決めようとする必要はありません。何度かメールでのやり取りをするなかで、少しずつ前に進んでいけばよいのです。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月21日
コメント(0)
-
出版セミナー「こんな企画が出版社に採用される」
出版なんでも相談室(出版セミナー「こんな企画が出版社に採用される」)6月2日(土)に東京で出版セミナーを開催します。場所や時間はまだ決まっておりませんが、決まり次第、このブログでお知らせしたいと思います。セミナーのテーマはズバリ、「こんな企画が出版社に採用される」です。これまで多くの本の出版のお手伝いさせていただきましたが、その間に得た「出版社に採用される企画のツボ」をお話いたします。抽象的な話は極力避けて、実例をあげながら説明しますので、身近に感じていただけると思います。「自分の企画には見込みがあるだろうか」と不安を抱いている方や、「将来出版したい」と願う方には、ぜひお薦めいたします。決してむずかしい話ではありませんので、ご安心ください。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月19日
コメント(0)
-
執筆サポートの進め方は?
出版なんでも相談室(執筆サポートの進め方は?)前回と前々回、執筆サポートについて触れましたが、これに関し、「執筆サポートはどんな感じで進めるのですか?」というご質問が寄せられました。原稿を全部書き上げて、それを私がリライトすると思っている方が多いようですが、そうではありません。塾生に1項目分(1章分ではありません)書き上げるごとに原稿を送ってもらい、それを私が順次リライトしていきます。そして、リライト原稿が1章分になった時点で、それを塾生に送り返し、確認していただきます。なぜこうしたやり方をするのかといいますと、それは次の3つの理由からです。(1) 塾生が原稿執筆に専念できる1項目リライトするごとに塾生に原稿を送り返してしまうと、塾生のもとには次々とリライト原稿が送られてくることになり、執筆に専念できません。そのため、リライト原稿が1章分たまった時点で塾生に送り返しています。(2) スピーディ1項目ずつ原稿を送ってもらえば、その都度リライトに応じられるため、スピーディです。1章分まとめて送ってこられると、そのリライトが完了するまでにかなりの時間を要しますが、1項目ずつ送ってもらえば、塾生が次の項目を執筆している間に、私はリライトを進めることができるからです。(3) コミュニケーションがきめ細やかになる1項目ずつ送ってもらえば、原稿を拝見して疑問に感じたことがあれば、すぐに塾生に質問できます。塾生はその項目を書いた直後に質問を受けることになり、回答しやすくなります。1章分をまとめて送ってこられると、それに対する質問も多くなりますが、そうなると塾生も回答するのに時間がかかりますし、1つひとつの質問に対する回答も荒くなってしまいます。以上の理由から、執筆サポートでは原稿を1項目ずつ送ってもらうようにしています。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月17日
コメント(0)
-
執筆サポートを受けた塾生の採用率は?
出版なんでも相談室(執筆サポートを受けた塾生の採用率は?)前回、執筆サポートのことに触れたところ、こんなご質問が寄せられました。「執筆サポートを受けた塾生の採用率はどれくらいですか?」要するに、執筆サポートを受けて、出版社に原稿が採用された確率、ということです。決して自慢するわけではありませんが、採用率は100%です。執筆サポートを受けて、原稿がボツになった塾生は1人もおりません。全員出版をはたしています。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月15日
コメント(0)
-
こんなくやしい思いをしたことが何度もあります
出版なんでも相談室(こんなくやしい思いをしたことが何度もあります)出版社に企画が採用(内定)されたものの、いざ原稿を書いたら没になった、というケースは意外に多いものです。その理由は、これまでお話してきましたように、原稿の精度が低いからです。実は、正直に言いますが、当方の塾生にもそのような方がおります。出版社に企画書を送って、好感触を得たものの、原稿を送ったとたんに、出版社からなんの連絡もなくなった、というケースです。そうならないために、当方では原稿執筆のサポートもさせていただいておりますが、それを塾生に強要したり強制したりすることはありません。原稿執筆のサポートを受けるかどうかは、あくまでも塾生本人の判断にまかせております。多くの塾生が執筆サポートを希望されますが、なかには自力で原稿を書き上げたいという方もおります。「この塾生の執筆力ではきびしいかな」と思うこともありますが、だからといって、執筆のサポートを強要したりすることはありません。ところが残念ながら、自力で原稿を書いた塾生の中には、出版社に原稿を送ったとたんに、出版社からなんの連絡もなくなってしまった、というケースはこれまでに何度もありました。そうなると、もうサポートのしようがありません。そんなくやしい思いを、これまでに何度もしてきました。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月13日
コメント(0)
-
塾生のメルマガやブログの購読者数は多い?少ない?
出版なんでも相談室(塾生のメルマガやブログの購読者数は多い?少ない?)前回、メルマガやブログの購読者数が多ければ出版への道が開けるというものではないとお話しました。実は、当方の塾生にはメルマガやブログを発行している人も多いのですが、彼(女)ら発行するメルマガやブログの購読者数は決して多くはありません。購読者数が100人程度のものもあります。それにもかかわらずメジャーの出版をはたせたのは、メルマガやブログで取り上げている内容(テーマ)に魅力があるからです。これを見れば、「購読者数」よりも「内容」が重要だということがおわかりいただけると思います。メルマガやブログから出版への道を開くのであれば、購読者数を増やすことよりも、内容のグレードアップに努めることが大切です。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月11日
コメント(0)
-
メルマガやブログの購読者数が増えれば出版社から声がかかるか?
出版なんでも相談室(メルマガやブログの購読者数が増えれば出版社から声がかかるか?)メルマガやブログを発行されている方から、よくこんなご質問が寄せられます。「購読者数を増やせば、出版社から声がかかるでしょうか?」要するに、メルマガやブログの購読者数が増えれば、出版社が関心を示し、出版のチャンスがおとずれるのでは、ということです。たしかに、購読者数が増えれば、関心を示す出版社がでてきます。しかし、それはたんに関心を示すだけであって、そのことが即採用につながるというわけではありません。やはり内容が大切です。読者数が多くても、肝心のメルマガやブログの内容が編集者の眼鏡にかなわなければ、採用されることはありません。購読者数を増やすことに気をとられるのではなく、やはり、どこまでいっても内容のレベルアップを図ることが大切です。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月09日
コメント(0)
-
私がメルマガやブログを見せてはいけないと言う理由
出版なんでも相談室(私がメルマガやブログを見せてはいけないと言う理由)前回、出版社にはメルマガやブログを見せないほうがよいとお話しました。当方の塾生の中にもメルマガやブログを発行している人がいますが、私はやはり出版社には見せないほうがよいとアドバイスしています。その理由は、出版社が企画に関心を示しても、メルマガやブログを見せたとたんに、反応がなくなるケースが多いからです。塾生は自分のメルマガやブログに自信をもっているのですが、プロの編集者から見たら、まだまだということが多いのです。そんな塾生は少なからずショックを受けるようですが、これが厳しい現実というものです。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月07日
コメント(0)
-
メルマガやブログを出版社に送ってもうまくいかないワケ
出版なんでも相談室(メルマガやブログを出版社に送ってもうまくいかないワケ)出版社に企画を売り込む際に、メルマガやブログを出版社に送る人がいます。要するに、メルマガやブログの内容を出版したいということです。しかし、多くの場合、失敗します。その理由は2つあります。まず第一に、メルマガやブログを送るということは、「これを読んで企画の内容を理解しろ」と言っているようなものだからです。企画の内容をアピールするのなら、きちんとした企画書を作成して、それを見せるべきです。ふたつめの理由は、メルマガやブログというのは、えてして精度が低いからです。自分では「まずまずの出来だ」と思っても、プロの編集者の目から見たら、かなり精度は低く見えるものです。そのため、メルマガやブログを送ったら、「なんだ、この程度か」と思われ、アピールするどころか、かえって評価を下げてしまうのです。ですから、出版社に売り込む際には、メルマガやブログを送るのではなく、きちんとした企画書を作成して送ることをお勧めします。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月05日
コメント(0)
-
編集者が原稿を見る目はきびしい
出版なんでも相談室(編集者が原稿を見る目はきびしい)出版社の編集者が原稿を見る目はかなり厳しいといえます。全国の書店に並べて売るわけですから、それも当然です。ところが、このことを理解しない人は意外に多いのです。一般の人が「原稿はまずまずの出来だ」と思っていても、プロの編集者から見ると、合格ラインにはほど遠いということはよくあります。というよりは、ほとんど、といってもよいくらいです。そのため、企画書を送って、出版社から声がかかり、「原稿を見たい」と言われて、ろくにチェックもせずに原稿を送ると、その後、なんの反応もなくなってしまいます。いくら問い合わせても、なんだかんだと理由をつけられて、結局は自然消滅してしまいます。ですので、出版社に原稿を送る際には、念には念を入れて原稿をチェックする必要があります。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月03日
コメント(0)
-
原稿の出来が悪いと、編集者は・・・
出版なんでも相談室(原稿の出来が悪いと、編集者は・・・)前回、日本の出版社の多くが中小企業であるとお話しました。そのため、編集者はひとりで複数の企画を抱えたり、編集以外の仕事をしなくてはならないことも多いのです。そこへ企画が持ち込まれ、面白いと思って採用したものの、いざ原稿を書いたら、あまり出来が良くなかったとなると、「やっぱり、やめた」となってしまうのです。持ち込み原稿で時間と手間をとられるよりも、自ら立案した企画に集中したい、となるわけです。「原稿のココを直してください。アソコを修正してください」と著者に伝えても、最初に送った原稿の出来が悪いと、「修正してもらっても、あまり期待できない」と思い、いちいち修正の依頼はせずに、うやむやにして自然消滅させてしまうのです。出版なんでも相談室(畑田)h.hatada@xa.ejnet.ne.jp出版塾塾長の顔写真と出版塾の新聞記事出版塾「自分の本」を出版する方法
2007年04月01日
コメント(0)
全14件 (14件中 1-14件目)
1