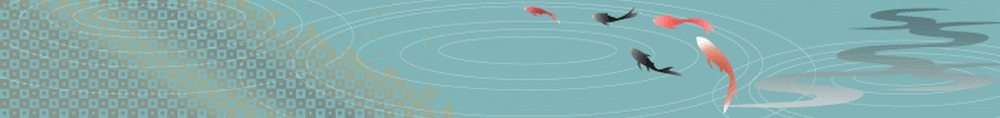2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年10月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
着物で行こう!名石庭園!!
上 清澄庭園 着物で行ってみたいのが、やはり日本庭園!!そんな方にお勧めなのが、東京都江東区にある「清澄庭園」です。 ここはかつて大名屋敷だったところですが、後に三菱の創業者である岩崎家の邸宅と社員の憩いの場になっていたものを一般公開したものです。 特徴はなんといっても海運会社らしく、全国から奇岩を持ってきて各所に置いてあること。それはこの庭園の特色でもあります。 着物で歩きたいときには今の時期、ここは歩きやすいし最高ですよ!!
2005年10月31日
コメント(10)
-
日本始めてのラーメン!!!
上 水戸藩らーめん 昨日からラーメンネタですみません! ラーメンの歴史は江戸時代にさかのぼり始めて食べたのはあの水戸黄門こと水戸光圀だといわれています。 水戸光圀は徳川家康の孫ですが、水戸藩を継いだとき、中国の明という国が滅んで清という国が出来ました。その清は異民族王朝なので、日本に亡命した漢人が多かったのですが、その中で朱瞬水(しゅしゅんすい)という人がいて光圀の家庭教師をしていました。その瞬水が伝えたのが今のラーメンだといわれています。 水戸では「ラーメン発祥の地」としていろいろなところに「水戸らーめんン」とか「黄門らーめん」が売られらり食べられたりしています。 その中で有名なのが「金龍菜館」のらーめんでしょう。日本発のらーめんを文献で忠実に再現しているそうです。右側の5つの薬味を入れて食べます。スープはかなりあっさりしていてクコやマツの実が入っています。 少々高いですが水戸に行く方は話のネタに食べてみてはいかがでしょうか?□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月30日
コメント(4)
-
スペシャル麺の中身!!
をお伝えするのを忘れていました!! これの具はほとんど湯麺です。そこにチンゲン菜や豚肉が入っている感じですかね。ただスープが四川風で辛いので、「四川風湯麺」というのが正しいかと思います。 ちなみに料金は1000円!!です。同じ店でフカヒレらーめんが1050円だったのでそちらにすればよかったと今になって思います。 らーめんといえば面白いラーメンを発見しました。後日ブログでご紹介します!!!お楽しみに!!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月29日
コメント(2)
-
スペシャルらーめん!!
上 中国のうまみが凝縮されたスペシャル麺 上のらーめんは東京の錦糸町に行ったとき、たまたま通った「万豚記」というお店で、に入ったときに食べたもの その名も、「中国のうまみが凝縮されたスペシャルそば!!」 中国好きとして食べなければ!!と思いました。 それで食べてみたのですが・・・普通の麺のほうがよかったような・・・一応少しづつ、特産品らしいのが入っているのですが、羊肉とかふかひれはないでした(ふかひれは当然か・・・) 値段が高い分、「ネギらーめんにしとけばよかったな」と思わせるいっぴんでした。 追伸 これから出社なもんで前日までのお返事、後で書かせていただきます。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月29日
コメント(4)
-
結城紬を見に行く!!
本日は、大島紬と並ぶ織りの代表格である結城紬の製造元を見に行ってきました。大島紬と同様に製品にすばらしい「こだわり」があるのです。 自分も織りを体験しましたが、「難しい!!」の一言です。後日、詳しくお話しいたしますので、着物好きの方、ぜひ楽しみにお待ちください!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月28日
コメント(5)
-
元祖てんぷらの具だ!!!
昨日予告いたしましたように江戸時代のてんぷら屋台に復元された当時のてんぷらの具です。 内側に野菜類、外側に串に刺さっているのが魚介類などです。 野菜にはかぼちゃ、サツマイモなど今でもよく作られることが多くいのですが、外側の魚介類には海老(これは今でも定番ですね)があるのですが、ほかに鶏肉やホタテのような貝、アナゴなどが見られるのが楽しいですね。鶏肉といっても焼き鳥でなくやはりてんぷらです。アナゴのてんぷらは「さすが江戸」といった感じですね。 今のてんぷらとは全く違って本当に当時はファーストフードであったことが解りますね。 当時の江戸は火事が多かったので、てんぷらを揚げることは屋敷地や大奥などでは禁止されていたので、川際で営業する「てんぷら屋台」は格好の「庶民の味」になっていったようです。 今では「高値の花になってしまった・・・・」□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月28日
コメント(10)
-
てんぷら屋だ!!!
復元 てんぷら屋 先日、てんぷら屋のお話をしましたが、これがその江戸時代の「てんぷら屋」です。 完全に屋台形式ですが、今のような車輪はありませんね。 壁の脇には油の入ったとっくりがあり、串にささって衣のついた具をそのまま向かって左側の鍋でてんぷらにします。真ん中の茶色い壺にタレが入っていてそれにつけて完成です。 今の焼き鳥やフランクフルトのような食べ方をしていたことが解ります。 先日、「当時のてんぷらはどのような具だったのか?という質問をいただきまして、それを次回のブログでお送りしたいと思います。 歴史好き、食べるの好き、てんぷら好きの方、楽しみにお待ちください。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月27日
コメント(9)
-
電車が止まる!!
東京在住の方は影響を受けた方もいるのではないでしょうか?新橋で、電車が動かないということでラッシュが一時期パニックになっていました。 当然のごとく私も影響を受けえらいもんでした。仕事は遅れますし・・・ 今日は借りていた映画を観て寝かせてもらえます。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月26日
コメント(6)
-
義経はやはり格好いいね!!
上 義経 安田ゆきひこ画 上の画はかつて「きははぎ」でご紹介した日本画家の安田ゆきひこ画伯によりかかれた義経の画です。 この画には義経の向かって右側に兄の頼朝が描かれており、ちょうど黄瀬川というところで兄弟が初対面したシーンが描かれています。いわゆる「黄瀬川の出会い」というやつですね。 義経と頼朝はこの後昨日ご紹介した平重衛ら平氏を滅ぼすも兄弟で喧嘩になり、反目していきます。 しかしこの義経、タッキーばりに男前ですね。しかしご存知な方も多いかもしれませんが、義経が死んだとされる岩手県平泉の中尊寺の彼の肖像画はとてつもなくブ男です。おそらくこちらが真相でしょう。 義経に同情するものは当時も後世も多くだんだん義経は美男子になっていったようです。 しかし、いつの時代も兄弟喧嘩はしたくないですね。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月25日
コメント(9)
-
焼き討ちして後悔!!
上 法然上人絵伝 部分 昨日の夜、日本シリーズの合間にたまたまチャンネルをNHKにしたら、ちょうど、後白河院(当時の権力者)と義経が話してるシーンがあって、「平重衛(たいらのしげひら)が死んだ」という内容でした。 平重衛は平清盛の5男で奈良の東大寺を焼いてしまうという暴挙をした人物です。後に、源氏に捕まり鎌倉へ送られます。 戦乱の時代とはいえ、重衛は相当後悔したんでしょう。上の写真の左が平重衛で右が法然です。彼は死ぬ前に法然に懺悔しているのでしょうか。悩みを打ち明けているように見えます。 彼はこの後、死刑が確定して首をはねられました。29歳の若さでした。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月24日
コメント(3)
-
江戸時代のてんぷら!!
上 てんぷら屋 てんぷらが入ってきたのは桃山時代ですが、後に日本料理に定着していきます。ただそれは江戸時代になってからで、とても最近だったりします。 しかも、現在高級志向が高い料理ですが、江戸時代はファーストフードで屋台が中心です。今のような「日本庭園を眺めながら」という感覚はありませんでした。 上の写真が、当時のてんぷら屋の屋台です。なぜか頭から布をかけて食べている人がいますが、刀をさしているからこれは武士ですね。 当時のてんぷらはあくまでファーストフードで一般人の食べる下賎な食べ物だったので、そこそこの身分の人はこのように顔を隠して食べたのです。 身分を問わず当時からおいしかったてんぷら。今では顔を隠さなくても食べれますね。お金があればですが・・・・□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月23日
コメント(15)
-
てんぷらを食べる!!
今日、てんぷらを食べてみました。 うん、うん、てんぷらはやはりおいしいですね。そんなことで考えてみました。 外国人が食べたい日本食、価格の高いイメージがありますが、以前はどうだったのでしょうか?□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月22日
コメント(0)
-
グリーンカレー!!
上 グリーンカレー 先日、新宿のタイ料理店で食べてみたグリーンカレーです。 私はご存知の方も多いと思いますが、大のカレー好きです。 タイ料理を全く知らない私は勢いで注文してしまいました。 おいしいのですが、やはり私は以前ご紹介した「明治カレー」のような「日本的カレー」が好きです。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月21日
コメント(2)
-
那須旅行に行って来ました!!
と表題を付けてみたのですが、これは私ではなく母親です。 先日、母親が体調を崩した折、多くの心ある方から暖かいメッセージをいただきました。 なんとか復調しまして、休養を兼ねていっております。 おかげで私が下手な家事をやっているんですが、母親に少しのんびりさせてあげられてよかったです。 明日に戻るのですが、元気になってくれればいなと思っています。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月20日
コメント(1)
-
申し訳ございません!!
またまたパソコンが故障してしまい、突然とまってしまいました!!いつも遊びに来ていただいている皆様、申し訳ありません!! またそぐ復旧いたしますので、よろしくお願いいたします!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月19日
コメント(5)
-
悲しいたまがきのお話し。
上 たまがきの手紙 今から数百年前の室町時代、今の岡山県の新見というところでの実際のお話しです。 当時、京都の貴族やお寺は全国に「荘園」という私有地をもっていて、そこから上がるお米を京都に送らせて生活していました。 しかし地方の農民の力が強くなりだんだんお米を送ってこなくなったのです。 京都駅の近くに「東寺」というお寺が今でもありますが、岡山の新見の荘園がお米を送ってこなくなってしまいました。 東寺は「祐清」というお坊さんを現地に派遣してお米を送らせることにしました。その時独り身では大変ということで、彼の生活のお手伝いをしていたのが「たまがき」という21歳の若い女性でした。 たまがきは祐清のことがだんだん好きになっていったようです。 しかし、祐清は鳥取県の近くで、農民と対立し殺されてしまいました。 一人残ったたまがきは彼の勤めていた京都の東寺に一枚の手紙を送ります。上がその写真です。 そこには祐清が残した形見の着物や畳を自分が引き取りたいという内容が書かれていました。左下に「たまがき」の字が見えますね。 この手紙が現代まで東寺に残り、たまがきの存在が知られるようになりました。 当時の庶民女性の手紙が残ることはほとんどなく貴重だからです。 その後たまがきがどういう人生を送ったかは全くわかっていません。ただ一枚の書状を残したのみです。 ただ、確実にいえることは今、日本のどこかの土になっていることと、祐清のいる天国に旅立ったことだけです。 岡山の新見では今でもたまがきと祐清の供養がつづけられ、多くの人の心に感動を与えています。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月18日
コメント(7)
-
着物好きに送る!!
上の絵は江戸時代の呉服屋さんの商売している様子です。そろばん勘定に余念がありません。 実は現在の呉服業界の流通関係はかなりこの時代と変わっていないんです。 現在、アフェリエイトをはじめ流通の流れはどの業界も大きく変わり、一時期は撤退した外資もまた巻き返しえしてくる可能性があるのですが、いつまでたっても呉服屋は同じなんです。 私の考えですが、これからの呉服屋は大きく3つの業態になると思っています。 1)接客サービスという付加価値を創造してある程度の価格で販売する専門店(マナーなどのサービスが低下すると失格) 2)「あまから」のようなネットを使って流通経費を減らし安く売る (常時、最新情報の更改をしないと失格) 3)リサイクル品(古着) どれもよいところあり悪いところありです。消費者の方々はご自身がお求めになっている着物がどこにあてはまるか、またお求めを希望する場合どこを選択するのかを一つの「指針」として上のことを考えていただけたらと思います。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月17日
コメント(13)
-
満州国のエレベータ!!
上 満州国国務院エレベーター 上が、先にご紹介した、国務院の中に設置されたエレベーターです。 エレベーターは日本では明治からすでに作られていましたから、そう珍しいものではなかったと思いますが、当時の中国では相当珍しかったようです。 このエレベーターは電動式で中に入るとレバーと各階のボタンがついていて、ボタンを押してレバーでドアの開け閉めをしていたようです。 エレベーターの歴史は古く、江戸時代からそれらしいものがあったらしいので、そんなところも紹介できたらと思います。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月16日
コメント(12)
-
70年前の冷蔵庫と電子レンジ!!
上 冷蔵庫と電子レンジ 前述の満州刻国務院の中には当時の大臣の執務室があるのですが、そこには電子レンジや冷蔵庫がありました。 執務室は見学できませんが、冷蔵庫他は見ることが出来ます。写真のしたが木造冷蔵庫、上が電子レンジ、その上はミルク温めるための電子レンジです。 電子レンジなどは今の大きさとほとんどかわりません。冷蔵庫などは木造ですが、現代と遜色ありません。これらができたのは昭和5~8ねんごろです。う~ん、恐るべき日本人・・・□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月15日
コメント(10)
-
中国の国会議事堂??
満州国国務院 昨日まで多くの方の励ましのお言葉、本当にありがとうございました。本日より気持ち新たに更改していきたいと思います。 上の写真、日本の国会議事堂に似ていませんか?これは実際の国会議事堂を模して造られた建物です。 ただ場所は中国の長春というところにあります。 これは今から70年ほど前、日本が中国に作った傀儡政権である満州国の国務院という最高行政機関の建物として日本人により建てられたもので、当時のまま残されています。 満州国というと、日本が侵略して作ったイメージが強いのですが、日本はこの満州という中国東北部に当時の先端技術を導入していきました。 この建物はその象徴でなんと中にはエレベーターや電子レンジ、電気冷蔵庫まであるのです!!昭和一桁の時代なのに! 後日にそれらをご紹介していきたいと思っています。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月14日
コメント(6)
-
皆様ありがとうございます!!
昨日の日記に多くのコメントをいただき、ただただ感謝であります。 母親はやはり疲れが出たようなので、すぐよくなるようです。 大変、ご心配、ご迷惑をお掛けいたしました。 今後ともよろしくお願いいたします!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月13日
コメント(7)
-
母親の体調が
ここ最近あまりよくありません。ですが以前よりよくなってきましたが、少し休憩が必要なようです。 昨年、父親を亡くしましたから無理もたたったのでしょう。自分も家事に精をださなければいけませんね・・・・ コメントなどのご返信、明日させていただきます。申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月12日
コメント(10)
-
日本人すべてがお世話になっている先生!!
上 ヘボン先生 明治学院大学HPより 現在、PCをローマ字で打ってる人がほとんどだと思いますが、この人がいなければありえなかったでしょう。上の写真は今から140年ほど前に活躍したヘボン先生、ローマ字の発明者です。 ヘボン先生はアメリカの医者でしたが、私財を投げ打って日本に奥さんと来て、外国人が迫害されていたなかで献身的に医療行為を行い、多くの日本人から慕われました。 後に日本語の研究をはじめ、ローマ字を考案、辞書までつくっています。その中には「あこぎ」といった通俗的な日本語まで翻訳されています。 ヘボンの奥さんはその傍らで近所の子供を集めて英語の学校をつくりました。通称「ヘボン塾」です。 ヘボン塾は後に生徒数が増加し、ヘボン先生帰国後も東京に移転し発展を続け、明治学院になります。 ヘボン塾や明治学院は後に戦争に走る世間に対して、徹底的に反戦を唱え続け、島崎藤村や高橋是清といった著名人を輩出します。特に高橋是清は政治家として戦争反対を唱え続け2・26事件で戦争賛成派に殺されてしまいます。死ぬまで反戦を貫いたわけです。 現在、明治学院は大学となり、東京高輪にありヘボン先生の意思をついで多くの学生が学んで多くの卒業生を輩出し続けています。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月11日
コメント(11)
-
畳が敷かれた時代!!
上 銀閣(慈照寺観音殿) 昨日、中世の「家」について少し触れましたが、「畳がしかれるようになったのは?」というとまず思い浮かぶのがこの慈照寺の観音殿です。要は「銀閣寺の銀閣」ですね! 銀閣寺は足利義政という将軍さんがおじいさんの義満が別荘に金閣をつくったのをまねて京都の東山に作った別荘の一部として建てられました。 この足利義政さんは政治の世界より芸術の世界で才能が開花した人で、その才能は建築にも及び、この別荘の屋敷も自分で設計したのですが、その一部としてこの銀閣と東求堂というものが残っています。 ともに畳がびっちり敷かれていて現代人の住居の「原点」になっています。 当時は今から約500年前、室町時代中期ですが、現代に残る文化が他にも出来上がっています。着物もまたしかりです。いつかお話ししたいと思いますね。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月10日
コメント(7)
-
これが県知事のお宅です!!
石山寺縁起絵巻 受領の館 奈良時代に完全に整備された国家は今と同じく中央と地方に分かれていました。どうしても中央が目立ちますが、地方はどうだったのでしょう? 上は平安末ころの県知事のお屋敷です。県知事は当時は国司(こくし)とか受領(ずりょう)といって中央の命令で地方に行きました。お米の取れる量によって国(今の県)にレベルがあってどこの国の県知事になるかで地位も違ってきました。県知事になると一財産が築けるのでなり手は京都にたくさんいました。おうちもゴージャスですね。 上の写真をみてください。人がいるところにのみ畳がひいてあります。当時、畳は座布団とか、ベットのように使用され、板敷きの床です。畳が床中に敷き詰められるのは室町時代からです。 次回ブログはその畳の初めて敷き詰められた建物のお話をしましょう!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月09日
コメント(5)
-
1300年前の人間コピー??
上 写経 ちょうど奈良時代ころ、日本では全国支配の制度が確立し、また仏教の発展に伴い、文書やお経の需要が激増しました。 そこで生まれたのは役所の文書やお経を写筆する機関です。その復元マネキンが上の写真です。 これは平城宮や東大寺などに存在していたようです。まるい硯を使ってみんなで使える様になっていますね。 当時、写筆は相当の激務だったらしく、記録によると待遇と仕事の量に対してストライキまで起こっています。 当時の人が今の社会を見たら・・・絶句するのが目に浮かびます。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月08日
コメント(6)
-
恐るべきトンカツ!!
上 特厚 とんかつ 以前「冷やしかつどん」のご紹介させていただきましたが、今回は「超特厚とんかつ」をご紹介します! これは東京の新小岩というところにある「すぎ田」というとんかつ屋さんのとんかつです。レギュラーサイズもあるのですが、あえて特大とんかつを食べてみました。 きれいに盛られてくるのですが、太さをみてもらうため敢えて崩して撮影してみました。 なんでしょうか?この厚さは・・・太さが5センチほどありますね。恐るべし・・・ これを食べた数日後、友人から「お前太ったんじゃないか」といわれたのはいうまでもありません・・・・□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月07日
コメント(16)
-
平安期、女性話に花が咲く!!
安田ゆきひこ画 きははぎ 源氏物語はいわずと知れた平安時代を舞台にした小説ですが、そのなかで「きははぎ」という条がでてきます。難しい字を書くのでここではひらがなにて表記します。 これは若く成熟してない光源氏が親友の頭中将(とうのちゅうじょう)らとともに、プライベートで女性の話に花を咲かせている場面で、それを日本画にしたのが上の画です。プライベートなので胸を開いてしゃべっていますね。 「やっぱりこういう女の子はいいよね~」「あの女の子なんかかわいくていいよね~」といったかんじでしょうか? 千年前の男も、現在の男も話すネタは変わらないものね。と紫式部に見透かされているような場面です。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月06日
コメント(16)
-
道真を追い落とした人はプレイボーイ!!
上 北野神社縁起絵巻 藤原時平 道真のタタリは落雷のみならず、そのほかの人にも襲いかかります。道真を追放する直接命令をした醍醐天皇まで死んでしまいます。 そして当のライバル、藤原時平も病に倒れてしまいます。時平は道真のタタリだとばかりに、神社の建設を命じます。そのときが上の写真です。 この藤原時平という人、今昔物語によると相当のハンサムで頭がよく、女性にももてたとあります。自分の年老いた叔父の美人の奥さんを言葉巧みに自分の奥さんにしてしまう話が出てきます。 この時平は39歳でタタリで死んでしまいますが、弟の忠平が後の権力を握り、そのひ孫があの道長です。 しかしタタリというのは怖いというお話でした。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月05日
コメント(6)
-
京都の町に直撃弾!!
上 北野神社縁起絵巻2 今回の話は流石にご存知の方が多いようです。スミマセンがお付き合いお願いしますね!! では続きを・・・ 道真死後、京都の町では不穏なことが次々と起こりました。とりわけ道真を追放した人が相次ぐ不審死をとげていきます。 そんななか、あるとき、京都の西の方から、真っ黒の雲が動いてきました。町の人が「なんだろう」と思ってみていると、その雲は天皇の住む御所の上に止まりました。 当時、御所内の「清涼殿」という天皇の住む建物では陣定(じんのさだめ)というところで大臣の会議が開かれていたのですが、そこにいきなり雲から雷が落下し直撃します。 上がそのときの写真です。倒れ、逃げ回る貴族たちが描かれています。 人々は無念の死を遂げた道真のタタリだといううわさを言い合いました。このタタリをなくすにはどうしたらよいでしょうか?・・・ 明日は道真を追放した藤原時平という人にスポットあててみます。明日のお楽しみですが、この人、とってもプレイボーイでした。初めて聞くという方もいると思いますので、楽しみにお待ちになってください!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月04日
コメント(8)
-
天神様が出来た訳!!
上 北野天神縁起絵巻 今回はご存知の方も多いとおもうのですが、天神様のお話しです。 天神様といえばご存知菅原道真のことですね。道真は平安時代、学者の家に生まれて県知事を歴任していましたが、当時の宇多天皇に請われて朝廷に入ります。 朝廷では藤原さんが要職を独占し始めたころ、道真はその対抗馬でしたが、藤原時平という人の讒言にあい、九州の大宰府の閑職に飛ばされてしまいます。 上の写真は道真が大宰府のあばら屋で一年前に天皇の前で詠んだ詩を誉められ、天皇からもらった着物を前にして悲しみにくれている有名な画です。 道真はこの後、失意のうちに死んでしまいますが、道真の「タタリ」が平安京に襲い掛かることになります。 その「タタリ」とは、次回ブログにてお話ししましょう!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月03日
コメント(5)
-
400年前の紅葉も美しい!!
観楓図 狩野秀頼筆 秋も本格的になってきてそろそろ紅葉を見に行くにはいい季節になりました。紅葉を見に行く計画を立てている方も居られるかもしれません。 上の写真は桃山時代、狩野秀頼という人が描いた「観楓図」といい、国宝に指定されています。 この画は「風俗画」という新しいジャンルの発祥なのです。 場所は京都高雄の清滝川べりで、お弁当を持ってきた子づれの人たちが、紅葉と川のせせらぎに囲まれて楽しいひと時を過ごしています。 左には天秤棒を持った「お茶屋さん」がお茶の販売をしています。当時のお茶屋さんは湯飲みも持ってきていてお椀に入れて売っているのがわかります。 大変風流な大好きな画です。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月02日
コメント(14)
-
吹きこぼした味噌汁の友情???
中国ネタは終わりといっておきながら最後にもうひとつお話ししたいことがあります。 成田から北京に向かう日航機で私の隣にロシア人のご夫婦が座っていました。最近の飛行機はすごいもので、オセロや将棋のゲームが付いています。私はついつい夢中になっていたのですが、そのときスチュワーデスさんに、「味噌汁はいかがですか?」といわれました。私はいらないといったのですが、ロシア人のおじさんは意味がわからないまま味噌汁を頼んでいました。 そのときです、何を思ったのかおじさんはウォッカのごとく一気飲みしてしまいました。当然熱いスープなので思い切り吹き出してしまい、私のほうまで飛んできました。 おじさんは必死に「スイマセン」といっていましたが、私が「大丈夫です」というと、それから英語と中国語を混ぜて仲良く話すようになりました。 そのご夫婦はモスクワから来ていて、初めてのアジアだそうです。日本では京都と東京に行ったそうですが、京都について「こんな神秘的な世界は始めてみた。こんな世界があるとは話には聞いていたが、行ってみて本当に感激した。」といっていました。「今度来るときには日本の文化をもっと勉強してきたい。必ずまた来たい」ともいっていました。 日本史を学ぶ者としてうれしい限りでした。 ご夫婦は北京に2泊してモスクワに帰るそうですが、北京空港で別れたとき、「あなたもぜひモスクワに来てください。ロシアもいいところです」と言い残されました。 味噌汁が飛んできたのには驚きましたが、旅の途中でのいい出会いでした。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年10月01日
コメント(5)
全33件 (33件中 1-33件目)
1