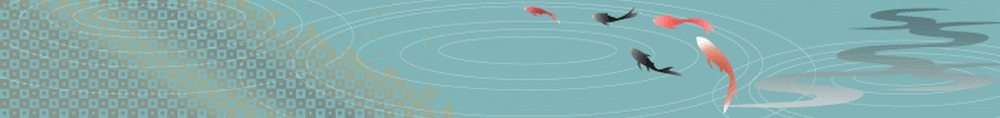2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年06月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
梅雨まっただなか!!
東京では今朝もえらい雨が降っていますね。今日で6月も終わりますが、梅雨明けまでもう少しの辛抱です。 江戸時代の鈴木春信の浮世絵で銭湯に行く女性が途中で雨に降られて困って歩く画があるのですが、梅雨の季節になるとその画を思い出します。 こんど皆様にお見せするとしましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月30日
コメント(0)
-
奄美大島梅雨明け!!
昨日で奄美大島の梅雨が明けました。それと同時に北陸や東北が入梅したとのこと。 日本の気候は北と南で違うとはいえなんかスゴイ。ちなみに東京は梅雨のまっただなかです。 奄美の大島紬を作っている職人達も気合が入っていることでしょう。観光シーズンも控え、興味のある方は奄美大島をぜひご覧になってください。 職人たちの心のこもった手作業は多くの感動を与えてくれます。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月29日
コメント(2)
-
北海道に行ったら行ってみて!!パート2
上 北海道開拓庁外観復元 昨日お話しました芝生の上にたっていたのがこの北海道開拓庁です。 現在札幌市の開拓期の建物を集めたテーマパークに建っています。明治期の写真をみるとこの白亜の美しい建物がまだなんにもない札幌の町にポツンと建っています。 この建物では現在の北海道の基盤になる「開拓計画」が練られていたことでしょう。 当時北海道ではお米が取れなかったので、お米の品種改良をするとかアメリカ式農法を取り入れじゃがいもやビール、乳製品の製作を行うなど。 北海道は見事に自然と都市が調和した美しいところになりましたが、この建物がまさに「原点」です。 美しい北海道を札幌の郊外で静かに見守っています。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月28日
コメント(2)
-
北海道のなぞの芝生??
上 北海道開拓庁跡 昨日ご紹介しました北海道旧本庁のとなりになんだか芝生があって石碑が建てられています。なんじゃこれは? 北海道は明治中ごろまで都府県の扱いを受けず政府の直営で開拓が行われました。その時まであったのが「北海道開拓庁」というものです。 その開拓庁は木造の洋風建築で白亜色をしていて札幌のまだ未整備の街で異彩を放っていました。その北海道開拓庁があったのがこの芝生部分です。 この開拓庁の前では日本で始めてチーズやバターなどの乳製品が作られています。 この開拓庁、もうないのですが建物の外観が北海道郊外に復元されています。こんどはその開拓庁を実際見てみるとしましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月27日
コメント(0)
-
北海道へ行ったらぜひ行ってください!!パート1
上 北海道旧本庁 北は北海道、札幌駅から歩いていける所にかつての北海道の庁舎があります。 北海道は鎌倉時代から日本人が住み始め、明治時代に函館から開拓が始まりました。 明治政府は時代が変わってリストラされた人がたくさんいたため、彼らへの新天地として、開拓にえらい労力をかけました。 北海道は日本の農業よりアメリカの農法があっていると、アメリカから先生を呼んで開拓をおこないました。 明治6年には函館から札幌に本庁を移転させ、札幌の街をつくり多くの人が移住して生活しました。 上の建物は明治20年代につくられたもので真ん中の塔以外は殆ど当時のままです。こんな近代建築の前や札幌の碁盤の目をした街を着物をきて歩いたらオシャレだと思いますね。 明日はこの庁舎の前身についてお話ししましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月26日
コメント(4)
-
古代米カレー????
上 古代米カレー 千葉県の佐倉市の歴史民族博物館があります。そこの食堂に実際あるメニューがこの古代米カレー。 古代米は弥生時代に作られた作物で,紅い色のお米に黒い色のお米が混じっています。最近栄養学的に注目され売っているところもかなりあるそうです。 この古代米カレー、実際食べてみたのですが、個人的に申しますと白いお米のカレーライスのほうが美味しい気がしました。 一度、みなさんも話のネタに古代米を食べてみてはいかがでしょうか。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月25日
コメント(4)
-
江戸時代の喫茶店!!!
左 鈴木春信画 笠森お仙 江戸時代は今の、情報通信産業が本格化した時代です。かわら板や浮世絵で多くの情報が飛び交っていました。 当時、江戸では今の喫茶店にあたる「水茶屋」というのがあり、ちょっと高級で美人のウェイトレスが置かれていました。 そこに美人がいると早速情報媒体で紹介され、多くのお客が女の子目当てでやってきました。 そのなかでも特に有名なのが谷中の笠森稲荷の「笠森お仙」で、鈴木春信や蜀山人らが紹介してお客が殺到しました。 彼女は13歳から父親の営む喫茶店で働いていたのですが、有名になったあと、20歳で結婚してからは全くお客さんがこなくなってしまいました。 結婚後は全く普通の人になったお仙ですが、今でも春信の画で当時の美貌を伝えています。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月24日
コメント(2)
-
リフレッシュ!!
最近帰宅が遅くなることが多く、帰宅後、すぐ寝てしまっています。新しい面白日本史を伝えたいのですが、なかなか資料集めがはかどりません。 しかし、明日は久しぶりに自由にできるので、新たな気持ちでお伝えしたく思っております。 楽しみにしていた皆様!申し訳ありませんが明日までお待ちください!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月23日
コメント(2)
-
江戸城にあった幻の天守!!!
左 江戸城天守 昨日ご紹介しました、江戸城天守台の上にのっかっていた天守が左のもの。この天守には特別な設計がありました。それは火事対策にえらい気を使っていることです。 屋根がわらは銅版葺きで、壁はご覧のように黒いのですが、これは黒漆喰で塗り固められています。すべて防火対策のためでした。 しかし、建ててからたった20年ほどで、大火事により燃え落ちてしまいました。明暦の大火というもので、天守が炎に包まれたとき火の竜巻が起こって燃えてしまったといわれています。 それ以来江戸城には天守が建てられることは2度とありませんでした。江戸にそびえていた天守は数枚の画によりかろうじて現代に存在を残しています。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月21日
コメント(0)
-
江戸時代の高層タワー!!
上 江戸城天守閣跡 江戸時代、政治の中心は現在皇居になっている江戸城です。 日本史の中で260年ほど、政治の中心だったわけですが、何度も内部は変遷しています。 江戸城には天守閣があったのですが、場所が変わったり、建物が変わったりしています。 その中でも徳川家光の時んみ作られた天守閣は大変大きいもので、50メートル近くあったといわれています。江戸の町のどこからでも見えたと思いますね。 その天守閣が乗っかっていたのが写真の石垣の上です。この天守台は高さが1メートルもあり、えらい巨石が加工されて作られています。 明日は、この天守台に乗っていた天守閣を見てみましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月20日
コメント(2)
-
ふぐの天ぷら!!
私の友人に築地に勤めているものがいて、ふぐをくれました。今日はそれを天ぷらにして食べたのですが、季節はずれとはいえ旨いですね!! 徳川家康は鯛の天ぷらを食べて腹痛を起こし、おそらく異ガンだったといわれていますが、死んでいます。 静岡県の藤枝というところに鷹狩りに出ているときに起こったことですが、鯛とふぐの違いはありますが、なんか家康を思い出しました。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月19日
コメント(2)
-
鎌倉期の経済とは??
上 東勝寺橋 鎌倉 「太平記」は室町時代に書かれた有名な本ですが、そこにこんな有名な話が載っています。 鎌倉時代の引付衆(裁判官)だった青砥藤綱という人が10文のお金を橋からおっこどしてしまいました。落としたのが上の写真のところです。 藤綱は川に落ちた10文を夜中まで探し、50文でたいまつを買って探させました。 当時の人々が「損してるじゃないか」といっていることに藤綱は、「川に落ちた10文は二度と人の手に渡らないけど、たいまつを買った50文は人の手に渡りせその人の生活を支えるのだ」という内容の言葉を言っています。 脚色した可能性が高い話ですが、当時、貨幣経済が中心になってきたことを如実に示したお話しといえるでしょう。 ここにくると藤綱の家来が川に入って必死に探してる姿が目に浮かびます。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月18日
コメント(2)
-
着物のルーツはやっぱりこれ!!
左 平安時代女房装束「風俗博物館」HPより引用 現在、まず着ることがないながら多くの人が知っている「十二単」。 十二単は通称で公式な当時の女房装束をいいます。ただ天皇家などでは結婚式のときとか、いまだにこの形を踏襲してますね。なんでだかしりませんが。 また、十二単は「唐衣裳」ともいうんですよ。 下の部分が裳といって中に紅い袴をはいています。これは現代のとは違いえらい長くてズルズル引きずっているもの。 更に裳引腰なんていう尻尾みたいなものまでつけていて、この状態で「いかにゆっくり歩くか」が大事とされました。ゆっくり歩く女性が美しいとされたのです。 上の部分は表着、打衣、ウチキと羽織っていて、この袖の色を多彩に、感性をよくして、それを几帳というカーテンから「ピラッ」と出すことが色っぽいとされました。 確かに美しいですが、大変だったでしょうね。当時の女性は。 追記 昨日は体調を崩し失礼いたしました。皆様からもらったメールには必ず返信させていただきますので、もうしばらくお待ちください。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月17日
コメント(0)
-
体調を・・・・・
崩してしまったようです。季節の変わり目だからでしょうか?何とか、体力回復し明日より再スタートをきれたらと思います。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月16日
コメント(4)
-
東京の清水寺!!!
上 上野寛永寺 安藤広重 上の写真は今の上野公園の今の様子を安藤広重が描いたものです。現在の上野公園は江戸時代には寛永寺というお寺でした。このお寺は東の比叡山ということで、東叡山という山号をもっていました。 右上に赤くて小さな舞台になっているお堂が描いてありますが、これは清水観音堂(きよみずかんのんどう)といいます。 京都の清水寺を真似たかどうかはわかりませんが、土手の上に張り出した形になっていて、さながら清水寺のミニチュアです。 ちなみにこの建物、現在までしっかり残っています!国の重要文化財になっていて、当然入ることもできます。 随分迫力のない清水寺ですが、ここの舞台に立つと、ちょっと清水寺にいった気分になります。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月15日
コメント(0)
-
よみがえった中世庭園!!
上 鎌倉円覚寺妙香池 北鎌倉にある有名なお寺、円覚寺の庭園が復元されたということで早速いってきました。 この池は妙香池といって数年前まではただ殺風景な方形の池だったのですが、江戸時代の記録をもとに再現されました。 鎌倉時代や、室町時代の日本庭園は特色があり、禅宗の影響を受けたものがおおくあります。 また、池岸に珍しい形の石を置くのもこの時代の特色です。この庭園はその面影を良く残していますね。 また、これは崖の多い鎌倉ならではなのですが、崖を削って庭を造っていますね。正面の崖を削ったような石は「虎頭石」といわれている有名な石です。 こんなところを着物を着て歩いてみたら風情があっていいですね。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月13日
コメント(8)
-
昔も歯痛はやだね!!
左 病草子 部分 最近、歯痛にくるしむ奄太郎ですが、昔の人もそりゃ同じ。 左の写真はかつて「肥満女性」で取り上げた「病草子」の部分。ごはんを食べてるときに、なんか歯がヘンだ。 一生懸命歯をいじって苦しんでいます。そう、この人、歯槽膿漏なのです。 歯医者は嫌だけど歯医者もまともなのがいない時代。たいそう痛そうですね。 ちなみにこの絵巻で重要なのはこの「お食事」平安時代末から鎌倉期にかけてのごはんはこんな感じだったんですね。「食の歴史」なんかでよくとりあげられてます。 歯が痛ければ、歯医者は嫌といわず、歯医者もいなかった昔の人の苦労を思い出し、歯医者にいきましょう!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月13日
コメント(2)
-
河川敷になったお城!!
上 古河城跡 ここは茨城県、渡良瀬川の河川敷です。一見どこにでもある風景ですが、柱がポツンとたっています。 「古河城本丸跡」???「本丸」とはお城の一番大事な所ですがこんな河川敷になにがあったのか? 「古河城」は実際江戸時代にあったお城。渡良瀬川の流れろ天然の要害として造られていました。 江戸時代の地図が残っているので解るのですが、たいそう立派なお城。 江戸時代、将軍は江戸幕府の創業者がいる家康さんに会うため、日光にいくことがありましたが、必ずこのお城に泊まっています。 江戸時代も終わると、お城も必要なくなり、氾濫の多い渡良瀬川の河川改修のため、河川敷の中に埋もれてしまいました。 この河川敷を上空よりX線撮影すると今でもお城の掘割が見えるそうです。 古河の町のお城はなくなりましたが関東地方のド真ん中で今でも城下町のたたずまいを残しています。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月12日
コメント(0)
-
不美人な娘のお見合い!!!
上 男衾三郎絵巻 部分 昨日の続き。男衾三郎は自分の「不美人な」娘を交際を所望した群馬県知事と面会させました。 その部分が上の画。 当時としては美男子な知事が「話が違うじゃねーか!!」といわんばかりに、そっぽを向いてしまっています。 この物語は途中でなくなってしまっていて、ここまでしかお話がわかっていません。 しかし、私は外見がよくなくても仲のいい夫婦や、生活が豊かでもいつか必ず没落するということなど、様々な教訓を教えてくれている気がするのです。 奥さんが不美人でも、だんなさんがブ男でも幸せな夫婦がとっても印象にのこります。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月11日
コメント(4)
-
こんな人が鎌倉時代の不美人!!!
上 男衾三郎絵詞(部分) 埼玉県の東武東上線を下るところに「男衾」という駅があります。鎌倉時代のその場所の空想のお話が男衾三郎絵巻になって残っています。 男衾三郎は兄がいました。兄はとっても豪邸に住んでいて、綺麗な奥さんがいて、娘もすごく可愛いのです。しかし男衾三郎の奥さんはとっても醜くかったのです。でも仲のよい夫婦でした。 あるとき男衾兄弟は盗賊をやっつけるため出陣するのですが、そこで三郎の兄が亡くなってしまったのです。 兄は亡くなる前、三郎に自分の家族、特に娘をよろしく頼むといって死にました。 上の画像はその男衾三郎夫婦の絵。奥さんの顔が当時の人から見た「綺麗でない女の人」です。現代からみるとどうでしょうか? そんな時、兄から預かっている娘に当時の群馬県知事から「お見合いしたい」と依頼がくるのですが、娘は拒否します。 こまった三郎は母親似のやはり「醜い」娘を代わりにお見合いさせることにします。 ではこの2人から生まれた「醜い」娘とは?次回ブログで登場してもらいましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月10日
コメント(6)
-
清少納言のかき氷!!
上 清少納言 枕草子絵巻 だんだん夏の蒸し暑さを感じるようになりましたね。そうなると食べたくなるのがアイスや氷菓子。それは昔の人も変わりません。 平安時代の清少納言も千年前の夏に氷を食べるのが好きだったようで、枕草子にこんなことを書いています。 「あてなるもの、削り氷にあまずら入れて新しきかなまりにいれたる。」 「あまずら」とは「あまかずら」という蔓から採った蜂蜜みたいなもので、現代の砂糖と比べるとぜんぜん甘くないのですが、当時の人にとっては贅沢な甘いものです。 清少納言の言葉を現代風にいうとこんな感じ。 「削った氷に甘い蜜かけて新品の鉄のお椀にはいっているのって上品よね~」 夏に氷を食べるため、当時は氷室というところの氷を貯蔵しておいて夏に食べました。当然、特別な人しか食べれません。 感性の強い少納言はこのかき氷をただ食べるだけでなく、その盛り付け姿に目をつけているのが彼女らしくて面白いですね。 みなさんも、これからかき氷を食べる機会があったら、千年前に蒸し暑い京都で美味しそうにかき氷を食べている清少納言のことを思い出して下さい。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月09日
コメント(2)
-
江戸のミニチュア富士山!!
上 高田富士塚 江戸時代のちょうどこのころ、富士山の山開きがありました。 当時は江戸のいたるところから富士山が見えたので霊峰富士は江戸っ子の信仰の対象になっていました。 多くの人が富士山にお参りにいったのですが、体の不自由な人やお年寄りは当然箱根を越えることはできません。 そこで、江戸の多くの神社の一角に「富士塚」という富士山のミニチュアのかわいい山を造って富士までいけない人の信仰の対象になっていました。 上の写真は現代の早稲田大学あたりにあった富士塚の画ですが、東京千駄ヶ谷駅近くの鳩森神社というところにとてもよく残っている富士塚があります。 わざわざ富士山から溶岩の岩をもってきて5メートルくらいの高さの山にし、富士五湖までかわいい池で残っています。 東京にお住まいの方の近くにも富士塚があるかもしれません。もしあったらぜひ江戸時代の人になったつもりで「登山」してみてはいかがでしょうか?□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月07日
コメント(5)
-
中世女性、旅をする!!
上 石山寺縁起絵巻 部分 鎌倉時代、いまから7~800年前、だんだん主要道路が整備され、日本のいろんなところに行きやすくなりました。 そんな時代、一番流行ったのが「物詣」、つまり神社やお寺まで旅をしてお参りすることでした。 その時、物詣をしている女性の姿が絵巻物に描かれています。 壺折(つぼおり)という旅用のラフな格好をしています。 もっと特徴をいうと、市女笠という薄い布のついた帽子を被っています。これは虫除けや人目をはばかるため。 また、胸には懸守という四天王寺伝来の布をつけています。これはまさに「お守り」ですね。 女性の旅は現代以上に危険であったのでしょう。服装も当時としてはラフな格好なのですが、今からみれば大変なもの。 十二単とかはなやかな着物史が取り上げられる中、こんな「旅用の着物」もあったんですね。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月06日
コメント(4)
-
本当の女性の美しさ!!
平安時代に「今昔物語」という本が書かれました。誰が書いたか解っていないのですが、天皇、貴族から一般庶民まで登場する面白い本です。その中のお話。 当時、貴族は何人も奥さんを持てるわけですが、正妻から、若い奥さんに移ってしまった貴族がいました。当然正妻は生活には困りませんが、さびしい思いをしていました。 その貴族があるとき、今の大阪の海岸を歩いていると、はまぐりに海松(みる)が、かわいくくっついた珍しいものを見つけました。 その貴族は「これは趣があるな~」と京都に住む若い奥さんにプレゼントを家来に命じて送らせました。 しかし、その家来は勘違いして、正妻に送ってしまったのです。 最近めっきり相手にされなくなっていた正妻は突然のプレゼントに驚きながらも、たらいに水をはってそのはまぐりを入れて海の香りを楽しんでいました。 京都に戻った貴族は若い奥さんに「プレゼントはどうした?」と聞くと届いていません。プレゼントの話をすると若い奥さんは「はまぐりなら焼いて食べたら美味しいし、海松なら酢漬けにしたら美味しいのに」と食べることしか言わないのです。 とりあえず正妻からプレゼントを返してもらうよう言うと正妻はこの詩を送ってはまぐりと一緒に返してきました。 「海の包思いはぬかたにありければみるかひもなく返しつるかな」 (この海のお土産は私あてではないそうですから、見て楽しむこともなくお返しします) この詩を聞いた貴族は、食べることしか考えない若い奥さんとは大違いに風流を解せる正妻に感動し、正妻の元に戻っていきました。 外見でない女性の美しさをこの物語は伝えています。実際風流な女性はご年配になっても美しいですね。 着物はタンスにいれとくより、召してこそ風流なもの。そんな女性が多くなってご本人にも喜んでいただくのが私たちの仕事です。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月05日
コメント(6)
-
なんだ?この不気味な巨像は!!!
上 大串貝塚 写真をご覧ください。なにやら芝生をひいた公園に不気味な巨像がたっています。なんでしょうか? 皆様は「貝塚」をご存知でしょうか?縄文時代の人が採って食べた貝殻のゴミ捨て場で、貝殻が散乱しているものです。海が当時より後退して海から離れた陸の上に貝殻が散らばっています。 ここは茨城県水戸市近くの「大串貝塚」という貝塚です。 今の時代だからこそ貝塚の意味がわかるのですが、今から1300年くらい昔の人は陸地(しかも海からかなり離れている所)に貝殻が散らばっている意味が解りませんでした。 当時、奈良にあった朝廷は「各地の様々なことを一冊の本にせよ」という命令を出し「風土記」という本を作るのですが、その中にこの貝塚が出てくるのです。 その内容は「都からはるか離れた茨城県に海からずっと離れたところに貝が散らばっている。地元の古老にきくと 「昔、ここに「だいだらぼう」という巨人が住んでいて、ずっと先の海に手を伸ばして貝を食べてここに捨てた」 といったと書いています。 現代からみたらトンデモナイ大嘘なのですが、海から離れた所に貝が散らばっていることに、昔の人も不思議に思いこんな逸話を作っていたんですね。 「だいだらぼう」は空想なのに現在は像となり、今でも海に手を伸ばして貝や魚を採っているみたいです。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月04日
コメント(1)
-
申し訳ございません!!!
本日、奄太郎、家を出たのが朝6時ごろ、帰宅が12時前でございます。明日、面白ネタをお送りしますので、今日はこのまま就寝いたします。 楽しみにしてくださっていた方、申し訳ありません!!!
2005年06月03日
コメント(0)
-
銘仙はいいですね!!
左 加藤まさを画 大正末期 着物をお召しになるかたはご存知の「銘仙」。写真の通りです。 銘仙は丈夫な絹織物なので昔から庶民に親しまれた着物です。普通は上の絵のようにシンプルな柄が多いのですが、今はいろいろな柄があります。それにはワケがあるのです。 明治末期(1908年)学習院に裕仁親王(のちの昭和天皇)が入学するのですが、彼のおじちゃんの明治天皇は孫の指導も含めて、乃木稀典(のぎまれすけ)という戦前の人なら必ず知っている軍人を院長にして教育係としました。 乃木は当時華族の子供の多かった学習院生を厳しく指導、女子の着物は「銘仙以下!!」としたのです。 当時の女子学生は友禅縮緬が主でもっとオシャレしたいのに「大ショック!!」 でもここで呉服屋や織物屋が黙っていません。「もっとオシャレな銘仙を造ろう」と群馬県伊勢崎の機屋と研究を重ね、シンプル柄が多かった銘仙に様々な柄をいれることに成功。 たちまちそれは学習院の女子学生に大人気となり全国の女性のハートをとらえました。 こんな織物もとっても味があっていいものです!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月02日
コメント(8)
-
なんじゃ!このそばは???
上の写真をご覧ください。なんだか変だと思いませんか? そう、まったく汁がないのです!!!そばなのに!! このおそばは東京の玉川にある「そばバリュー」というお店の「冷やし油そば」といいます。 「おそばと油が合うの」と思われるかたも多いと思いますが、これが実にうまいんですよ!! ここのおそばは十割そばなのでとても美味しく、ざるそばなんかも最高です。麺類好きの奄太郎イチオシのそばやです!!東京近郊の方、東京にこられる方、ぜひ食べてみてください。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年06月01日
コメント(4)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- パンを焼こう!
- 《画像》甘納豆ちぎりパン 作りまし…
- (2025-11-22 07:24:24)
-
-
-

- 今日行ったお店について
- 【三越前】フージンツリーでランチ
- (2025-11-21 08:51:41)
-
-
-

- バレンタインの季節♪
- 再入荷!RURU MARY’S ルルメリー「シ…
- (2025-02-21 23:46:54)
-