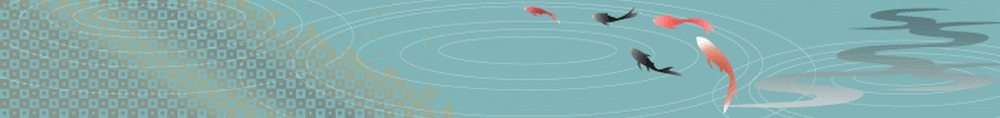2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年11月の記事
全36件 (36件中 1-36件目)
1
-
義経の夢・・・
岩手 毛越寺跡 この間、大河ドラマ「義経」をたまたま観たら、義経一行が平泉に向かうところでした。 平泉、それは今から900年ほど前、京都からはるか彼方に忽然と現れた「小さな極楽」でした。 平泉は藤原清衡という人から4代続き、義経を引き取ったことで敵対する源頼朝に攻撃され滅亡しました。 ただ、その後、京都のように人家が立たず、田地になったことから、地面の中に遺跡がそのまま眠ることになり、有名な毛越寺、観自在王院(観自在とは観音さんのこと)などの庭園が発掘され建物以外は当時の姿が残されています。 その庭園は当時流行った「浄土を現世に作ってしまう」浄土庭園で庭園だけでも言い表せない美しさがあります。当時はこの池の周りに朱塗りの堂が幾つも建っていたことがわかってます。 義経はこの平泉で死ぬことになりますが、平泉では今なお発掘調査を続けていてこれから「当時の平泉」が現れることになるでしょう。 義経の見た平泉がこれから蘇ってきます。
2005年11月30日
コメント(11)
-
二重橋でない二重橋??
江戸城跡 石橋 昨日の古写真の場所ですが、皇居の写真でした。写真が撮られたのが明治2年ごろなので、130年以上後に同じ場所から撮ってみました。 多くの方、「二重橋」のお答えいただきありがとうございました!!でも、ちょっとイジワルなのですが実はこの橋、二重橋ではないんです!! 古写真を見ると解るのですが、手前の通称「二重橋」の奥にもう一つ橋がありますね。これが二重橋です。手前の橋は単に「石橋」といいます。 なんでこんなことになったのかというと、奥の橋は高いところにあって下に板の橋を架けてから人が歩く橋を架けて二段になっていたからとか、古写真を見ると手前の橋と二重に見えるからとかいろいろな説があります。 でも多くの方が手前の橋が二重になっているので二重橋と思われています。 ちなみにこの奥に櫓がありますが、これが伏見櫓といいその奥に皇居の宮殿があります。宮殿の場所は江戸時代は将軍を退職したいわゆる「大御所」が住んでいた西の丸というところで、当時の政治の中心ではありませんでした。 はとバスのお姉さんのようなウンチクになってしまいましたが、皇居を訪れた際は知らない方に教えてあげてください。
2005年11月29日
コメント(10)
-
此処はどこ??
上の写真、ずいぶん古い写真ですね。江戸時代から明治時代にかけて写されたものです。 よく見ると刀をさしたお侍さんんが写ってたりしますね。 実はこの写真に写っている場所は、今では大変有名なところになっています。 感のいい方、もしくはこの写真を見たことがある方はご存知かもしれません。次回はこの写真の場所の現在の姿をみていただきましょう。
2005年11月28日
コメント(8)
-
日本文化とは!!
上 山本亭にて 以前、中国に行ったとき「日本文化ってどんなのですか?」という質問を受けどう答えたらいいのか困ったことがあります。 しかし、今、自分が日本史を学び色々なことを考えるようになりました。そこで考えたのは、日本文化とは一言で言うと「小宇宙的なもの」ということです。 日本はご存知の通り島国ですが、話す言葉は日本語、書く字は中国語をアレンジしたもの、そして明治以降の欧米文化のアレンジと外国のものを受け入れて使えるものをチョイスして独自の文化を創ってきました。 そこには「外国の影響は受けるがあくまで独立国!」というイメージがわいてきます。それこそ、アジアの海の上に浮かぶ「小宇宙」だと思います。それを究極に表したのが日本独自の小さな「寺院」であり室町期にできた「茶室」であり、中国とも韓国とも違う「着物」とかだと思うのです。 小さい宇宙の文化、これが日本的美しさとして外国人には受け入れられるのではないでしょうか?
2005年11月27日
コメント(9)
-
浅草の大好物!!
最近、食事ネタブログになってしまい、恐縮です。 私には大好物が幾つかあるのですが、その中の一つが上の飴です!!! これは浅草では年中売っていて、観光客に混じって地元の私も買って食べるのが大の楽しみです。 でもこれ、屋台の看板には「あんずあめ」とあるのですが、どうみてもスモモあめなんですよね。 最近ではソーダあめとか梅ジャムあめなんかもありました。「梅ジャムあめなんかうまいのか?」と屋台のオヤジに聞くと「一回食ってみろ」ということだったので、食べたらうまいもんでしたね。 でも私はやっぱりスモモあめです!!
2005年11月26日
コメント(9)
-
究極の粗食!!
上 庶民の食事 昨日、お話ししましたように、1300年前の庶民の食事を再現したものが上のものです。 う~ん、見ただけで粗食とわかりますが、「お品書き」を見てみましょう。 庶民の食事メニュー 左 玄米ごはん 上 ノビルのゆでもの 右 アラメ(海藻の汁) 下 塩(調味料) 最近、「粗食のススメ」なるものが流行ったりしますが、これはあまりにも粗食しすぎです、というより栄養的に問題があることは明白ですね。 当時の寿命が短いのも医学の発展だけでなくこのような問題もあるんでしょうね。 あなたはこの粗食に耐えられますか?ちなみに私は全く耐えられません!!
2005年11月25日
コメント(13)
-
開設200日!!
おかげさまで本日でブログを立ち上げてから200日が経ちました。 いつまで続くのか半信半疑で始めたブログでしたが、おかげさまで今では私の「生活の一部」になってきました。 これからも面白い、多くの方に読んでいただけるブログを目指しますのでよろしくお願いいたします。
2005年11月24日
コメント(11)
-
古代の食事!!
上 下級役人の食事 今から1300年ほど昔の飛鳥、藤原時代の下級役人の食事を復元してみたものが上のものです。 当然、あくまで推定であり、また上級貴族はもっといいものを、庶民は質素なものをたべていました。 飛鳥時代の下級役人のメニュー 玄米ごはん(左下) 鰯の煮付け(左上) カブの漬物(真ん中) きゅうりの漬物(右下) アサツキの味噌汁(右上) 酒糟を湯に溶かしたもの(お酒の代わり)(右下) 真ん中下の塩で味付けします。(当時、しょうゆはまだありません) 今の時代からみるとかなり質素ですね。まして当時は一日二食なのでお腹がすいたのではないでしょうか? 次回ブログではもっと質素な庶民の食事を見てみましょう!!
2005年11月24日
コメント(8)
-
お経十万回??
上 必死に読経する道長 石山寺縁起絵巻 このブログでもよく取り扱う平安時代の代表人物である藤原道長は、前にお話したように「御堂関白記」という日記をつけていましたが、これは彼の死の直前までかかれています。 道長は記録によると体調不良と目が見えなくなっていったとあり、今で言う「糖尿病」で他界しているのですが、当時はこんな病気わからないので、必死に死ぬ前に極楽に行けるようにと仏様にお祈りするのです。 道長は自分の死を悟ると出家して「南無阿弥陀仏」を毎日唱え続けました。その姿が上の画です。彼の日記の死の前は「今日はお経を何回唱えたか」という記述のみになってきます。 そのなかで「読経十万回」なんて書いてある日もあります。24時間でどうやって10万回唱えたかは彼のみぞ知るところですが、かつての権力者の面影はありません。 道長は子供が多くいて、長女と長男は千年前なのに80代まで生きるほど元気だったのですが、その子供たちに看取られ、また歴史に名前を残し、56歳でこの世を去りました。 彼が極楽に行けたかどうかはわかりませんが、彼の日記を読むと「行けてればいいな」と思います。
2005年11月23日
コメント(6)
-
女性天皇!!!
推古天皇 想像画 最近、天皇継承問題などが取りざたされていますが、女性天皇を認める可能性がたかいようですね。 昔、女性の天皇がいたことは多くの方の知るところですが、その一番手が推古天皇です。 ただ、女性天皇は彼女を含めて数人しかいません。また私の思うところ大きく2つの理由がある場合です。 1、政治的に好ましいとされたとき。 2、次期天皇が幼い時に成長する間。 日本では王様である天皇は政治的には力をもたない時代が多く、だからこそ曲がりなりにも長く続いているといえるのですが、推古天皇の時代は天皇の力がまだあったと思えるので、彼女は2にあたる「つなぎ」の天皇として即位したと考えられます。 彼女が実質的に政治を行わせたのが有名な聖徳太子ですね。聖徳太子は次期天皇候補の1人でした。(お父さんが用命天皇という天皇でした) ただ、残念なことに次期天皇候補者は推古天皇より先に、太子を含めみんな死んでしまったのです。 「つなぎ」の天皇だった始めての女帝は36年も天皇をすることになってしまいました。 彼女の胸中はいかがだったでしょうか? 歴史的には古代史に燦然と輝く女帝の時代のイメージがあるのですが、実際は複雑な「事情」があったのです。
2005年11月22日
コメント(6)
-
プレゼントいただきました!!
いつもお世話になっております、「ラッピングライフ」を運営されている、みらい2000さんよりキリ番が私ということで、ブログ上で予告されていたクリスマスのラッピングペーパーをいただきました。(写真はブログ上からお借りしました) 私、ブログやらせてもらい半年になるのですが、頂き物は始めてでした。みらい2000さん、本当にありがとうございました! みらい2000さんのラッピングのブログは和ものが多く、着物もお召しになる方なので、ラッピング素人の私も大変勉強させていただいております。 これからもご指導、よろしくお願いします!! WRAPPING LIFE(みらい2000さんブログ) http://plaza.rakuten.co.jp/wrappinglife
2005年11月21日
コメント(6)
-
砂金を採る!!!
上 戸肥金山 砂金堀り 伊豆半島の付け根に「戸肥金山」という金の出るところがありました。江戸時代の金山といえば「佐渡金山」が有名なのですが、こちらも全盛期はかなりの採掘が行われたようです。 ここは伊豆観光のテーマパークになっていて上のように「砂金摂り」が体験できます。 大きな長細い水槽の中に砂が入っていて大きなお皿で砂をすくい振ると小さな砂金が入っています。 とっても腰に負担のかかるものですが、砂のなかから砂金が出てきた時は格別です。摂った砂金は持って帰ることも出来ます。 それでは伊豆特集は終わることにします。楽しい旅行でしたし、見ていただいた方々ありがとうございます。 次回よりまた「歴史ブログ」再開いたします!!
2005年11月20日
コメント(5)
-
船盛り!!
伊豆松崎 「味世」の刺身定食 伊豆半島は東側は電車も通っていて発展していますが、西側は電車がなくあまり発展していないので、その分自然の宝庫です。 伊豆半島を一周する折、松崎港というところで食事をしたのですが、そこの「味世」という店で私は「刺身定食」を頼んで出てきたのが上のものです。 これは都会人にとって完全に刺身定食でなく「船盛り」ではないですか!しかも近海ものということがありえらく新鮮でした。 大学時代の親友I君!おごっていただきありがとう!また食べさしてください!
2005年11月19日
コメント(7)
-
牛乳発祥地!!
牛乳の碑 伊豆半島の下田はかつてペリーが来航したところでもあります。それから下田は幕末の外交史の中心となり、その史跡も残っております。 江戸幕府がアメリカと通商条約を結んだとき、始めてアメリカの領事館がおかれましたが、これが玉泉寺というお寺です。 当時、米国旗を掲げた跡なども残っているのですが、ここは牛乳の発祥地でもあります。 当時の日本では牛乳を飲むという習慣がありませんでした。(古代にはあった)そこで領事館だったハリスは牛乳を飲めないことに悩んでしまい、幕府に牛乳を飲めるように乳牛を用意してもらったのです。 そこからここは「牛乳発祥の地」として石碑が建てられています。 当時から130年ほど後の現在、牛乳を飲めない場所は、日本にほとんどなくなりました。ハリスが知ったらどう思うでしょうか? このお寺の境内には「ここで牛乳を飲もう!」といった看板まであります。 さて、次回ブログでは伊豆の「海の幸」が登場します!乞うご期待!!
2005年11月19日
コメント(2)
-
江戸時代の製鉄所!!
上 韮山反射炉 江川英龍は自分の領内に近代的製鉄所をつくりました。これが写真の反射炉です。 ここでは主に鉄砲や大砲、そして弾などを西洋を見習って作っていました。下の部分で製鉄を行い、煙が上の煙突から出る仕組みでした。 当時、江戸時代末、外国の文化を受けてこのような製鉄所が各地につくられてのですが、当時のまま残っているのはここと山口県の萩のものしかありません。 当時の開明的な人々が必死に近代化に取り組んだ行動が、今なおのこされています。 さて、次回ブログでは「牛乳発祥の地」にいってみましょう!!
2005年11月18日
コメント(5)
-
甥っ子!!!
私の甥っ子(1歳3ヶ月)が前述しました「パン祖のパン」を食べています。 こんなに硬いのにずいぶん気に入ってしまったらしく半分ほど時間をかけて食べてしまいました!! なんという食欲!! 家族ネタでスミマセン!!
2005年11月17日
コメント(9)
-
パンの祖先!!
上 パン祖のパン 昨日お話した江川英龍が作った「パン」のレシピをもとに再現したのが上のパンです。直径6センチ、厚さ1センチほどでしょうか。 パンはもともと桃山時代に入ってきましたが、その後製造を禁止されていました。 西洋式軍隊をよく知っていた英龍は当時の軍隊の携帯用保存食としてこのパンを作ったのです。それまでの携帯食といえば「焼きおにぎり」でした。 いざ食べてみると・・・・こえはカンパンです!!間違いなく。決して美味しいものではないと思いますが、ご興味のある方は伊豆で食べてみてください!! 追伸 現在いただいたコメントなどのお返事が諸事情により遅れております。申し訳ございません!!
2005年11月16日
コメント(5)
-
パンの祖先!!
上 江川英龍自画像 伊豆とかかわる歴史人物は多くいますが、その中でも一番有名なのが江川英龍ではないでしょうか? 英龍は江戸時代末の伊豆の韮山というところの代官ですが、領内統治に定評がある「名君」として有名でした。 ちょうどそのころ日本は外国の船が頻繁にやってきて、鎖国がピンチになっていました。英龍は江戸で学んでいたこともあり「西洋」に大変興味をもっていました。 江戸幕府の将軍徳川家慶は幕府を改革してピンチを逃れようと「天保の改革」を行いましたが、そこのこの英龍を大抜擢しました。大抜擢された中には遠山の金さんこと「遠山景元」もいます。 英龍は領内に製鉄所を作ったり、保存食として「パン」の製造をおこないました。 天保の改革は失敗し江戸幕府は滅びますが、英龍死後、子供の英武は明治政府に仕え、ヨーロッパに留学し父親がやり始めた「近代化」を継承していきました。 最近、当時のレシピで再現した「パン」が出来ました。伊豆に来ると食べることができます。 次回ブログでは当時の「再現パン」をお見せしましょう。
2005年11月15日
コメント(10)
-
隠れた名焼肉店!!!!
上 「丑はる」の焼肉 上が修善寺「丑はる」の焼肉です。上がカルビ、下がホルモンですね。 カルビは厚さ、味、料金、どれをとってもなかなか大都会では味わえない一品です!! またホルモンの美味しさも評判!!味付けから大変美味しいです。 「伊豆めぐり」の前にまずは腹ごしらえということで、いきなり「食の話」をしてしまいましたが、次回から歴史がでますよ~!!。また海の幸も当然出ますのでご期待ください!!!
2005年11月14日
コメント(5)
-
丑はる!!!!
上 伊豆修善寺 丑はる 夕方東京を出て、一時間ほどで三島に到着した私は友人と合流して、車で修善寺方面へ。 一時間ほど走るととある一角に「丑はる」という焼肉店が見えてきます。 ここは私の友人の従兄弟が経営する小さな焼肉屋です。店内が大変狭いのですが、安い値段でよいお肉が出るので、地元の常連客が絶えません。 友人4人で食べる予定が1人パチンコにはまってしまい遅刻。3人で食べ始めました。 次回ブログで、その「美味なるお肉」をお見せします!!!
2005年11月13日
コメント(1)
-
静岡より帰りました!!
上 石廊崎(伊豆半島の最南端) 前ブログでお話しましたように、大学時代の親友の招待で静岡の伊豆に行ってきたのですが、日曜日、無事帰りました。 東京間の交通費以外は全ておごっていただきまして、この場をお借りして伊豆の皆様に厚く御礼申し上げます。 おかげさまで美味しいもの、楽しい歴史の話などを豊富にご用意いたしました。 「日本で始めてのパン?」や「牛乳発祥の地」などなど面白い歴史が目白押しです!! 明日以降、載せていきますので、ご愛読いただいている皆様、楽しみにお待ちください!!
2005年11月12日
コメント(5)
-
静岡に行ってきます!!
突然なんですが、本日より静岡に行くことになりました。 大学時代の親友の招待なのですが、地元の友人も連れてくるとのことです。 現在朝の5時ですが、そのまま行ってしまう予定なので、コメント等いただいていた方、申し訳ないのですが少々お待ちになってください!! 静岡の情報についてもこれからお送りしていきたいと思っています。
2005年11月11日
コメント(8)
-
藤原ファッション!!
上 藤原ファッション 奈良時代、平安時代と有名な時代がありますが、その前は「飛鳥時代」といいます。奈良県の飛鳥が政治の中心だったからなのですが、その一番の成熟期が「藤原時代」といいます。 今の飛鳥盆地の北側に条坊制(道が縦横まっすぐなもの)を採用した日本で始めての都市「藤原京」が中心でした。 「藤原時代」は694年~710年までとたった16年しかありません。710年に更に盆地の北に都を作り直したのです。これが「平城京」すなわち奈良時代ですね。 なんで引っ越したのかは、今まで「藤原京が狭くなったため」といわれていましたが、最近は違う説が出てきて真相は謎のままです。 しかし、発掘調査の結果、当時の風俗や生活がわかってきて、上の写真のような格好をした人たちがいることがわかりました。 飛鳥時代とも奈良時代ともビミョーに違う16年でした。
2005年11月10日
コメント(6)
-
荷風先生のチキンレバーソース!!!
上 アリゾナキッチン チキンレバーソース 引っ張りまして大変失礼しました!! 上が荷風先生の好物だったチキンレバーソースです。ランチのメニューで再現されています。 チキンとレバーがトマトソースで煮込んである一品!食べてみたら美味しい~のです!! また、くっついてくるパンも温かくて美味しかったです。 荷風先生は初めタンシチューばかり食べ、その後このレバーソースばかり食べています。 浅草にお越しの際は、かつての「文士」になった気分でぜひ行かれてください!!
2005年11月09日
コメント(8)
-
アリゾナで
食事をしている荷風先生の姿が写真に残っています。上がその写真。 この時はおそらく昭和30年前後だと思いますが、ここで荷風先生が食べているものが「チキンとレバーのソース」というものです。 これは現在アリゾナで復活しているメニューです。 次回ブログにて公開します!!(今日中に!)
2005年11月09日
コメント(5)
-
荷風先生といえばこの店!!!!
上 アリゾナキッチン 荷風先生の行き着けの店といえば多くの人が知る浅草の「アリゾナキッチン」。東武浅草駅のすぐ近くです。 ここは荷風先生の日記「断朝亭日乗」にもよく出るお店。 ここでも荷風先生は最初はタンシチュー、その後はカレーライスとレバーソースを食べ続けています。 このお店は一時期閉店していましたが、数年前に再開されたものです。 それでは明日は「荷風先生の食べたレバーソース」をご紹介しましょう。 ご期待ください!!
2005年11月08日
コメント(4)
-
荷風先生のカツ丼!!!
上 大黒屋 カツ丼 荷風先生のグルメをたずねて、いきなり浅草から京成電車に乗って千葉県の八幡に行ってみました。 京成八幡駅前の「大黒屋」という定食屋兼居酒屋があります。ここは荷風先生が近くの菅野というところに住んでいた時によく行きました。 荷風先生はここでも同じテーブルでいつも「カツ丼」を食べ続けました。この店は津川雅彦さんが荷風先生を演じている映画「墨東奇譚」にもカツ丼を食べるシーンで出てきます。 味はどんなでしょうか?食べてみると普通のカツ丼でした!! 東京から成田空港に行くとき、八幡駅前に電車の進行方向左側にあります。機会があったらご覧になってみてください。 次回ブログはまた浅草へ戻ります!!!ご期待ください!!!
2005年11月08日
コメント(6)
-
大好物のかしわ南蛮!!!
上 浅草尾張屋 かしわ南蛮 それでは荷風先生のグルメをしてみましょう。 東武浅草駅と雷門の間に「尾張屋」いう大きいてんぷらの天そばや天丼を出すお店があるのですが、そこが毎日のように荷風先生がかよったお店です。 ただ、荷風先生はてんぷらには目もくれず、毎日上の「かしわ南蛮」を食べていました。というよりこれしか食べません。また唐辛子などは一切かけず、食べてる間は一言もしゃべらないのが「荷風流」です。 荷風先生は食べ物には池波正太郎さんなんかとは違い「毎日同じ店で同じものを同じ場所で食べる」というコダワリ?があり、他のメニューには見向きもしません。また自分がいつも食べている席に人が座っているととても不愉快になってしまう人でした。 荷風先生は180センチほどの身長にスーツに下駄、しかも傘に買い物用のおばちゃんカバンという格好で毎日来るので店の人に初めは気味悪がられたそうですが、「えらい作家」といわれ初めて気づくことが多かったようです。 この江戸風のごま油の効いたかしわ南蛮、浅草らしくちと高いですが来たら食べてみてください。850円です。
2005年11月07日
コメント(8)
-
浅草に来ました!!
浅草に来てみたといっても私にとってはただの地元なので、いつもの軽いノリで来てみると、とにかく人だらけ・・・平日なのに。休日はもっとすごいですからね。 まず、今回のブログ用に今の浅草の象徴であるアサヒビールを写してみました。 ちょっと余談ですが、アサヒビールはキリンビールと同じ会社だったのをご存知でしょうか? もとは「大日本麦酒」といって戦前はビールシェアの80%を独占していました。 戦後、アメリカの指導のもと、健全な資本主義をするために切り離されたのです。 横道にそれましたが、荷風先生のたどった道を歩いてみましょう。
2005年11月07日
コメント(6)
-
ぶっとんだ小説家!!永井荷風!
上 永井荷風 偏奇館にて 小説家というのは変わった方が多い?と思いますが、その中で死後も輝いている一人はやはりこの永井荷風でしょう。 荷風は明治初期、高級役人の子供として産まれるのですが、中学のころから学校をさぼって落語家に弟子入り! 後、アメリカ留学、女遊びに熱中し「あめりか物語」を書く。 フランス留学するが全く懲りずに同じことをやり「ふらんす物語」を書くが発禁処分。 文豪、森鴎外に認められ、勧められて慶応義塾で仏文学を教えるも、学生を遊郭に連れて行くなどとんでもない先生ぶりで大学側と対立、とっとと辞めてしまう。 神谷町の「偏奇館」に住み、銀座や浅草を徘徊し特に女性を題材にした小説を書くも空襲で千葉の市川へ。 そこから、浅草へでかけてブラブラしストリップ劇場などに出入りする。 後に文化勲章を受賞。昭和34年死去。 一生をかけて「女性の美」を追求した荷風、彼が書いた小説や日記には当時の女性だけでなく江戸の女性まで生き生きしてでてきます。 その有名な日記に書かれている荷風の通った浅草グルメを明日ご紹介しましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年11月06日
コメント(9)
-
隠れた名庭園!!!
上 東京都葛飾区「山本亭」 日本にはたくさんの庭園がありますね。特に欧米人で日本庭園が好きな人は意外と多いのですが、そんな欧米人、また日本人にも大変人気のある庭園ってありますね。 桂離宮なんかがそうですが、欧米人に人気のあり、以外に知られていないのがこの「山本亭」です。東京の柴又の片隅にある小さな庭園ですが、木の配置や庭園構成などピカイチの感性がひかります。 この庭園は大正末から昭和初期に造られ、家屋も当時の屋敷が残っています。その屋敷から撮影したのが上の写真ですが、この景色を見ながら抹茶を飲むこともできます。 きものでお出かけを考えている方で、もしまだここに行かれてない方、平日がオススメですよ!! ただ、たまに部屋が貸切になることもあるので、葛飾区役所などに聞いてからいかれたほうがいいかもしれません。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年11月05日
コメント(6)
-
三井越後屋が復活!!??
上 三井越後屋ステーション 三井越後屋といえば、江戸時代中期、アイデアを駆使して日本の呉服業界に大旋風を巻き起こした着物屋さんですが、その越後屋が復元?されました。 東京日本橋の三越の反対側にある「三井越後屋ステーション」。そこだけ江戸時代の呉服屋さんになっています。 ただ、呉服を販売しているわけでなく、一種の町の再開発の情報発信をしているようです。 期間限定らしいので、東京においでの方は立ち寄られてみてはいかがでしょうか?詳しくは下記HPをご覧ください。 http://m-echigoya.jp/□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年11月04日
コメント(11)
-
江戸期のエレベーター(おまけ)
の通り道?を上から覗くと下のような感じです!おまけでした!!
2005年11月03日
コメント(3)
-
日本発のエレベーター!!!
上 エレベーター? 偕楽園好文亭内 以前、昭和一桁時代のエレベーターに多くの方がご驚嘆いただいたので、調子に乗ってエレベーターのご先祖を見つけに行きました。 これは日本三大庭園の水戸偕楽園の中にある好文亭という建物のなかにあります。好文亭は水戸斉昭(最後の将軍徳川慶喜のお父さん)が作ったものです。彼は「烈公」というあだ名をもっている文武にすぐれた殿様だったそうですが、なかなかアイデアマンで自分が設計した建物の中にエレベーターを作ってしまいました。 ただ、これはもちろん人が乗るものでなく配膳用です。つまり一階で作った食事などをこれに乗っけて二階に運ぶのです。上の木のでっぱりに紐をつけてあげていました。もちろんこのエレベーターの上は二階まで上がるように天井がありません。 「江戸時代のエレベーター」というと人が乗っているイメージを持たれた方が多いと思います。スミマセン!! 日本発のエレベーターは「物」を乗っけるものだったんですね。
2005年11月03日
コメント(11)
-
サブウェイ!!!
最近食事ネタで本当にすみません。 「サブウェイ」というサンドウィッチのお店がありますが、そのお店、私の大好きなお店です。 その中でも必ずいつも頼むのが上の「ターキーブレスト」。七面鳥のハムを使った低カロリーで美味しい一品です。 「ちょっと体重を落としたい」と考えている方や、ヘルシー嗜好の女性にはおススメです。 明日、先に好評でした、エレベーターの歴史について、ついに「江戸時代のエレベーター」が登場します。ぜひご期待ください!!!
2005年11月02日
コメント(10)
-
美人!!!(奈良時代の)
上 鳥毛立女(部分) 上の女性、実際は全身が画かれているのですが、奈良時代(いまから1200年ほど前)の絵の顔のアップです。 当時の美意識は今と当然違いまして、こんな女性が美しかったようです。ずいぶんぽっちゃりしていますね。 これは当時の中国の女性画がやはりこのようなぽっちゃりな女性が多く、その影響を受けているものと思います。 今は、欧米の美意識が追求されがちですが、当時の先進国は中国、その影響をふんだんに受けています。 となると、当時の中国の楊貴妃や日本の光明子もこんな感じだったのかもしれません。
2005年11月01日
コメント(11)
全36件 (36件中 1-36件目)
1