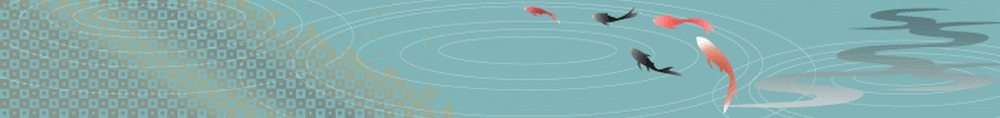2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年05月の記事
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-
信じられます?同じところですよ!!
上 高輪大木戸画 上の写真をご覧ください。昨日のブログ写真の場所の、今から200年ほど前の様子です。 真ん中が東海道で旅人が往来していますね、画の左側に芝生の石垣がありますが、これが昨日ブログの塚になってオフィス街にポツンとのこっているのです。 しかし驚くことは、すぐ後ろが「海」なんですね。今では埋め立てた上、ビルが立ち並んでいて、海までこの場所から数百メートルもあり考えられないですね。今ではちょうど、帆船が浮かんでいるあたりが東海道線や新幹線が走っています。 東京の方は山手線で品川あたりを通過するとき、新幹線で東京にこられる方は品川、東京の間、「二百年前はここに帆船が浮いていた」とこの画をぜひ思い出してください。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月31日
コメント(11)
-
都会の中に奇妙な森が???
上 高輪大木戸跡 ここは国道1号線の泉岳寺の近く、オフィスビル街に正体不明の森があります。 よく見ると高さが3メートルほどの塚になっていて周りは石垣になっています。歩道もこの塚を避けるように蛇行しているのです。こんな邪魔な塚は壊せばいいのに・・・・ ところが壊せません!!これは「高輪大木戸跡」といってれっきとした江戸時代の史跡で国が管理しています。 当時の東海道は江戸の日本橋出発でしたが、この高輪に両側を石垣で囲った木のドアがあり江戸の市内と郊外を分けていたのです。すなわちここ田町と品川の間が江戸時代の市内。だから新宿も渋谷も池袋も品川も江戸時代はのどかな田園か宿場町。江戸ではなかったんです。 当時の江戸っ子は東海道を旅する友人などをこの場所まで出迎えたり、送ったりしました。その石垣の片っぽがかろうじてオフィス街の中に残っているのです。 では江戸時代はこの場所はどんなだったの? それを描いた画を次のブログでご紹介しましょう。現代と比べたらびっくりしますよ!!お楽しみに!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月30日
コメント(2)
-
着物をだらしなく着るススメ??パート2
左 竹久夢二画 「春を待つ日」大正9年 竹久夢二の画にかかれる女性の多くが、うつろな目にだらしない着物の襟元とその着物の疲れ果てている感じの画が多いです。 当時、ビシッと着物を着た女性画が多い中で、夢二のこのような画は、日頃みせる着物女性のまなざしやしぐさに本当の美しさを出そうとしている感じますね。 現代でも、着物を着るとき、美容院行って、お化粧して、シトヤカに歩いてとそれを楽しむこともいいことと思いますが、もっと普段着っぽく自分の好きなように着崩す美しさも着物の出来る芸当です。 お着物をお召しになる方、着たいと思われている方、ぜひ「夢二スタイル」楽しんでみてはいかがでしょうか?□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月29日
コメント(12)
-
着物をだらしなく着るススメ??
近代を代表する絵描きさんである竹久夢二をご存知の方もおおいはず。彼は「港屋絵草子店」というお店を経営して、そこでみすからもデザイナーとして口絵を描いたり、半襟や封筒を売ったりする、いわばデザイナーズショップの経営者でした。 そこでたくさん女性の絵を描いた、そんな夢二が描いた女性とはいかなるものか?夢二はこんな内容のことを昭和6年にいっています。 「新しい物好きは、民衆の好むのを狙い欧米調のデザインを着物に反映さえるのをこのんでいるが、自分は古いものの中にこそ新しい物があると思う。特に土地のローカルカラーを出しているものが要求される時代がくる!」 では具体的に、夢二の描いた女性の絵を次のブログで見てみましょう!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月28日
コメント(2)
-
鎌倉時代の肥満女!!
上 病草子 部分 上の絵は「病草子」という絵で中世の病気をいろいろ描いた絵巻物の中の一部なんですが、すごい体型してますね。題名はまさに「肥たる女」。 1人で歩けないくらい太っているので、両側を支えてもらって、息切らしてなんとかあるいています。 彼女は借上(「かりあげ」、もしくは「かしあげ」)といって当時の高利貸し屋さんですので、いい利益があったんでしょう。どうも利益をかなり食費に使っていたようですね。 現代でも肥満は健康の大敵ですが、当時(鎌倉時代)も「病気」として位置づけられているので、今と変わらないんですね。昔人も健康の大敵であることを知っていたようです。 いつの時代も食べすぎ、飲みすぎしないうようにしましょうね!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月27日
コメント(12)
-
「大奥」第二段!!!!
上 中西立太画 大奥呉服の間 昨日書いた大奥ネタが好評だったので、第二段やりたいと思います。1)1日豆腐を600丁仕入れる!! これはみんなで食べていたのではありません。なんと手の脂をとるために使っていたのです。脂取り紙みたいな感じで。そごいですな。2)夏は軽装よ!! 時代劇の大奥シーンを見ると必ず正妻は打掛に足袋をはいていますが、夏はあんなのあついのでスズシの単衣ですごしますし、足袋もはきません。時代劇で夏に打掛着てたらウソです。3)大奥専用の「そり」があった!! 大奥では力仕事も女性がやらねばならないので、重いものを運ぶときは「ズリ」といってソリ状の板に紐がついているものがありその板の上に荷物をのっけてズルズル滑らせて荷物を運んでいました。そんな器具あったんですね!! 他にも大奥ネタはたくさんありますがまた改めてお話ししましょう!!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月26日
コメント(0)
-
江戸時代の着物屋さんの上得意先!!
上 中西立太 復元画 大奥呉服の間 江戸時代の着物屋、すなわち呉服屋のお得意先、それはいわずもがな「大奥」です。大奥には認可をもらった呉服屋がえらい出入りして着物屋の荒稼ぎの現場となっていました。 着物を仕立てることは、大奥内の数十人のお針子さんがいて、身分の高い人の着物を縫っていました。彼女たちは自分専用の支給された針をなくすとクビが飛ぶという厳しい職業環境だったようです。 しかし、そんな彼女たちには役得もあり、大奥で注文した着物の歯切れなどをもらえたのです。大奥で購入する着物は当然高価なものが多く、かなりいい着物が出来る状態になったといいます。 ちなみに、たくさん着物を欲しいのは女性の常ですが、当然幕府のお金で買うわけですからそっちのほうがピンチになってきます。 江戸幕府の創業者は例の徳川家康さんですが、彼自身は倹約家で生活も貧しく、お金も十分貯まっていました。更に豊臣さんを滅ぼして豊臣家のお金をパクッてきて東照宮に貯めていたので幕府の財政は満ち溢れていたのです。 しかし、家康さん死後数十年でちょっと財政がやばくなってきたので、大奥に節約するようお触れを出したのですが、家康さんの曾孫で犬公方といわれた綱吉さんのころになると元禄文化の風潮もあり家康さんの貯めていたお金もスッカラカンになってしまいました。当然、大奥が一枚噛んでいます。 将軍綱吉さんはお母さんが京都の呉服屋のお玉ちゃんという一町人だったため、そのお母さんの計らいで、不景気な西陣の回復の為、膨大な発注をかけています。現在、西陣の着物が全国区になったのはこの影響が大きいですね。 まあ、このころから幕府内部では表(政治場)の節約命令と奥(大奥)の贅沢行為のいたちごっこが始まります。 当時の彼女たちの服装などはまた、改めてお話しするとしましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月25日
コメント(11)
-
「義経の時代を作った人は日本一の大学生で同性愛者??}
前ブログにてお話ししました藤原頼長さんの続きです。 彼は前述したように本が大好きだったのですが、更にマメに日記をつけていました。当時の貴族は大概日記をつけていたと思いますが、彼の日記である「台記」(たいき)はかなりプライベートなことまで書いてあり、当時の歴史を知る上で欠かせない資料となっています。 彼は日記に大晦日になるとその年に読んだ本のタイトルを全部書いていたり(なんと千冊以上です!)風俗店にいったことから、ある人を殺し屋をやとって殺したなどモロに書いているんですが、その中で男性との性交渉したことを書いています。しかも複数人。 ただ、男性のみに愛情を持ったわけでなく、愛妻もいたし複数の奥さんがいて子供もいました。 いわゆる「両刀」なのです。しかしなんでこんなことになったんでしょうか? それは、当時女性の社会的地位が落ちたことや、男が春を売っていい役職につこうとしたなどがあげられます。詳しいことはそれでテーマを設けてお話ししましょう。 ちなみにこの藤原頼長さんはお兄さんと財産の奪い合いになり、その時、天皇家でも財産争いをしていてお互いが2つに別れて大喧嘩していました。両チームとも当時、力をもってきた武士を雇って戦争に突入します。保元の乱といいます。 その時頼長さんチームと反対側についたのが、平清盛や義経の父の源義朝などでした。結局頼長さんは負けてしまい、舌を噛んで自殺しました。37歳でした。 しかしその直後、こんどは平清盛と源義朝が対立し戦争します。平治の乱といいます。 今度は義朝さんが負けてしまい平清盛さんが実権を握りますが、義朝さんの子供たちの頼朝、義経らにより清盛さん死後の平氏を滅ぼし、更に義経がお兄さんの頼朝に滅ぼされ、源頼朝のベンチャー政権が鎌倉に確立します。 これにより天皇家や藤原さんの力は大幅に縮小されかつての勢いはなくなっていくのです。藤原頼長さん自殺後30数年後のことでした。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月24日
コメント(1)
-
義経の時代を作った人は日本一の大学生で同性愛者??
上 藤原頼長画像(摂関御影図より部分) 大学生が一般論としてですが、あまり勉強しなくなって久しいですが、かつて平安時代末に「日本一の大学生」といわれた人がいました。 これは鎌倉時代に「愚管抄」(ぐかんしょう)という歴史記録のなかで慈円という藤原氏出身のお坊さんがいっているのですが、この「大学生」とは藤原頼長(ふじわらのよりなが)という人です。 「愚管抄」の場合「大学生」と書いて「だいがくしょう」と読み、「たくさん勉強する人」の意味で今の「大学生」とは違うんですが。 頼長はバカがつくほど本を読むのが好きで、「太平御覧」(たいへいぎょらん)という当時の百科事典を牛車の中に入れて出勤したり、移動したりしていました。 当時、移動しながら本を読む習慣がなかったので、現代社会で通勤社内で読書する人のはじめてみたいな人ですね。 また、当時、和歌山の熊野神社にお参りに行くのが貴族の間で流行っていたのですが、貴族らが乗った船が嵐で沈没しそうになり、パニックになり、自分も死ぬかもしれないのに、彼だけは全く周りを気にせず持参した本を読み続けていました。 また、当然蔵書の数がものすごく、しかも本が宝物なのですから、それを収めるために、自分専用の図書館まで自分で設計して造ってしまいました。 図書館自体は残ってないのですが、彼が設計した図面が残っていまして、周りを垣根で囲ったり、水堀を掘って防火対策をするなどえらい気の使いようです。 ではその彼がなぜ「義経の時代を作り」また「同性愛者」なのでしょうか?その部分は本日中のブログでお話ししましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月24日
コメント(3)
-
奄美大島は水が命!!
奄美大島には前述したように独特の固有種が存在するのですが、その理由はいくつかあり、その中でも大きな理由は南から流れてくる黒潮の影響です。 黒潮(日本海流)は沖縄の東を流れ、奄美の手前で流れを左に変えて奄美の上でまた東にもどってくるのです。奄美大島を取り囲むように流れているんですね。 すなわち奄美は海流によって周りの島と遮断されているんですね。だから海流の流れる北にある屋久島には冬があり、雪も降るのですが、海流という壁がある奄美は亜熱帯気候で冬がありません。一年の平均気温が21度もあります。 また奄美大島は大きくありませんが、川の流れも豊富で森から流れ出た水は海水と混ざったところ(汽水域)に「マングローブ群落」を形成して、多くの生命を育んでいます。 ひとまず奄美の話はここまでにして、またお時間があったら奄美大島の歴史や文化をお伝えするとしましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月23日
コメント(0)
-
奄美大島はの生き物たちの歴史!!
先のブログでお話したように、奄美大島のある南西諸島は新たに陸地が海から盛り上がって出来たのですが、それが、弧を描くように小さな島々が並ぶ形になりました。 そこで、西南諸島には台湾側と日本側から全く種類の違う動物がやってきて混ざり合っていたのですが、島の分断と共に島特有の生物のご先祖になっていきました。 具体的に言うと、トカゲ、カエルなどは陸続きの時に来たので各地に形を変えて分布していますが、哺乳類、やヘビといった新しい種類が日本から南西諸島に来たときには、屋久島と奄美大島の間に大きな海峡(トカラ海峡)が出来ており、屋久島より下にはこれなくなりました。 逆に、南から来たハブやアマミノクロウサギなどは奄美大島までしかこれませんでした。屋久島と奄美大島間で北と南から来た動物が向かい合う形になりました。 更に今から150万年ほど前から海面が急激に上昇し、現在より100メートルほども上がりました。これにより標高の高い奄美大島は生態系が守られ、独特の動物のいる島となっていきます。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月22日
コメント(0)
-
この島どんな島?奄美大島!!
上 南西諸島奄美近辺地図(上が鹿児島、下は沖縄) 大島紬は着物の紬の中で異彩を放つ、まさに「紬の王者」です。 そんな大島紬を生み出した「奄美大島」という島の成り立ちを今日はご紹介しましょう。 今から2億年以上前、日本の本土も奄美も海の中にありました。 1億年ほど前の恐竜がいた時代ですが、だんだん日本の本土が大陸から切り離されていきました。しかしまだ奄美をはじめ南西諸島は海の中に沈んだまま。 南西諸島が海から顔を出すのは6千5百万年前から百八十万年前ごろなので、本土より新しいんですね。 奄美大島はその中でも特に大きい島で、更に海流の流れの影響もあり、ちょっと上にある屋久島とは気候も風土も文化も大きく違います。 次回はそのその気候や生態系なんかもお伝えしましょう。 上の地図を次回ブログでもご参照下さい。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月21日
コメント(0)
-
羊の脳みそカレー!!??
上 羊の脳みそカレー(左側) 最近、女性の間で人気のある羊肉ですが、そんな羊肉の専門店があります。それは東京代々木にあるその名も「ひつじや」というお店。 羊肉の料理ももちろんありますが、その中でも私が大好きなのは写真の「羊の脳みそカレー」! 「えっ!!ヤダ~」といった方、東京にお住まい、もしくは来られる方、ぜひご賞味ください。 牛の脳は狂牛病なんかで食べれませんが、羊の脳はおいしいんですよ!少し歯ごたえのある豆腐みたいな感じですね。それが辛目のカレーにはいっているんですね。 思わずご飯が進む一品です。代々木にはテレビ「笑点」でおなじみ日本ラーメン党の林家木久蔵師匠のラーメン屋さんが有名ですが、私が代々木に行くんだったら(最近めったに行かないですが)ここのカレーを食べますね。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月20日
コメント(0)
-
学校の歴史が嫌いだった皆様へ!!
「歴史がきらーい」といわれる方はかなり多いです。ただただ年号を覚えて、人物覚えて、「朝廷」だの「幕府」だの覚えて、ただ覚えるだけ。 高校や大学受験中心の勉強方法をして、歴史をつまらなくさせているのは文部科学省や大方の学校教員だと思います。 人にものを伝えるとき大事なことは「興味」をもってもらうこと。そこからはいらないといけません。 私は大学出ですが、英語はどんなに勉強しても覚えなかったし、出来なかった。なぜなら理由は簡単、アメリカやイギリスという英語圏に興味がなかったからです。 私は今、趣味で中国語にはまっていますが、時間があると中国語のテキストを開いて声をだして読んでいます。スラスラ覚えてしまいます。なぜなら中国が好きだからです。 大学生のとき、一時的に塾の講師をして歴史を中学生に教えることになりました。女の子が多かったのですが、彼女たちは一様に「歴史は嫌い」といいました。 私は彼女たちに年号など一切教えず、絵だけで、今ブログでやらせてもらっていることを教えました。すると彼女たちはメキメキ覚えていったのです。 私はこのブログを通して、歴史全般、そして着物全般に興味をもっていただける方がひとりでも増えるため、自分の経験を生かしてやらせてもらっています。 かつてテレビで歴史を教える先生が、江戸時代を教えるとき江戸時代の町人姿に変装して教えて生徒に受けている場面を見たことがありますが、あれくらいできたら「いい先生」ですね。それで生徒たちの中に必ず興味をもつ人が出てくるはずです。 これからも面白い歴史と面白い着物話をお伝えしますのでよろしくお願いします。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月20日
コメント(0)
-
「お金で買えないもの」を教えてくれた親友
昨日、私の親友Tさんが経営する会社にお伺いしました。 その親友とは知り合ったのは2年ほど前、ひょんなことからでした。彼は不動産会社の、私は呉服販売会社のサラリーマンと「畑」がまったく違うのですが、お互い野球が好きだったこともあり大変仲良くさせてもらいました。また彼は人脈も広く、利益とかお金とかお構いなしに私に有益な方を紹介してくれました。 その後彼は独立して会社を興す決心をします。その時私は病に倒れていたのですが、退院後、彼は仕事を休んで私の大好きな野球に連れていってくれました。 現在、彼の仕事が軌道にのってきて、ついには部下をもつようになりました。しかし彼はいいます。「オレの部下といっても彼らを尊敬しているよ」と、また彼はこんなこともいっていました「人間いいときもあれば必ず悪いときもある、どんなに結果をだしても天狗になっちゃいけないよ」多くの方々、年齢が上の方にも聞かせてあげたい言葉です。それに気づかない人が10年ちょっと前のバブル期にいっぱいいましたし、自分もそんな人を見てきました。 また、昨日は彼の部下である元野球選手のYさんをご紹介いただきました。Yさんもスポーツの世界で生きて、アメリカでも野球をしてきたまさに「苦労人」です。今後とも多くのことを学ばせていただけたらとおもっています。 親友Tさん、そしてYさん、Oさん、T・A社の皆さん、本当にありがとうございました。自分が苦境に立ってるとき、助けてくれる方は本当の友人です。 私も親友Tさんのように「お金で買えないもの」を人にあげられる人間になっていきたい。今後の私の大きな目標がまた1つできた1日でした。 □□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月20日
コメント(0)
-
紅茶すきですか?私は好きです!
本日のニュース記事に「英国での紅茶の需要が減っている」というのがありました。それが健康志向のためということだそうです。 酒が飲めない私は紅茶は大好きで毎日1回は飲んでいるんですが。 英国の紅茶需要の減少が記事になるのには、紅茶が英国の代表的飲料という理由だけではありません。 英国人の紅茶好きは、かつて世界の歴史をも動かしていました。 お茶を生んだのは中国人ですがその中国が混乱の近代史を歩んだのも、インドが植民地化されたのも、アメリカの独立にも紅茶が一役かっているのです。 紅茶ではありませんが日本文化にもお茶は欠かせませんね。 紅茶の歴史なんかも今度詳しくお伝えさせていただきましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月19日
コメント(0)
-
平安時代のセクハラ!!
上 紫式部日記絵巻復元図 岡本元史氏HP (http://www.hcn.zaq.ne.jp/internet-gallery/index.htm)より引用 上の写真は「紫式部日記絵巻」という絵巻物があるのですが、原本が国宝ながら相当古くて見にくいものなので、岡本元史画伯がこのたび忠実に再現され、当時の美しい絵巻物を見れるようになったものです。 「紫式部日記」はご存知紫式部が綴った日記ですが、現代の日記のように毎日書くものでなく、思い出に残る出来事を断片的に書いているものです。 上の絵巻のシーンは1008年、当時の10月16日の彼女の日記に出てくるもので、藤原道長の娘で天皇と結婚した彰子(しょうし)が皇太子を出産した時の道長邸での宴会シーンです。紫式部は彰子の家庭教師でしたから参加していたのです。 宴会で酔っ払った連中がだんだん暴走していくのですが、絵巻上のほうで十二単着た女性にからんでいるのがいます。これが藤原顕光(ふじわらのあきみつ)という人で道長のいとこ。当時65歳にも関わらずカーテンを破ったり、女性に絡んだりとやりたいほうだい。女性はやがってますね。 また絵巻下では藤原実資(ふじわらのさねすけ)という人(道長の遠い親戚)が女性の重ね着した袖をめくっています。かつてお話ししたように「女性の袖はミニスカート」のようにセックスアピールの意味があるのでそれを許可なくめくるとはよろしくないですね。だから女性の方も扇子をかざして抵抗しています。 藤原実資はとっても几帳面な人で「小右記」という日記をことこまかにつけたり、小野宮流なんていうお作法の第一人者なのですが、酔っ払うとこんなことしてしまうんですね。 ちなみに紫式部はあまりに宴会がはちゃめちゃなので途中で会場から出て行ってしまいます。 紫式部はさすが女性なのでこれらの男性の行為を見逃さず日記にかいてついには千年後の現代にのこることとなりました。某大学教授はこれを「歴史に出てくる最初のセクハラ記事」といっていました。 セクハラするとひょんなことから千年も語り伝えられてしまうんですね。いつの時代もセクハラはいけませんよ!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月19日
コメント(1)
-
見せたくないものを見たい!!
先日ニュースで「子供を持つ親がみせたくない番組」でテレビ朝日系「ロンドンハーツ」「クレヨンしんちゃん」フジテレビ系「ワンナイ」がエントリーされたそうで、すべて昨年に引き続いてのエントリーだそうです。 親が見せたくない理由は「くだらない」が1位だったそうです。 実は私はこの3つの番組、全部大好きなんです。子供の教育という面ではどうかと思うところもありますが、3つの番組とも「くだらない面白さ」を感じます。 数ヶ月前、日本橋三越で「ザ・ドリフターズ」の展覧会をやっていて「ドリフファン」を自認する私も見に行ったのですが、かつてPTAなどから抗議が相次いだコントを放送していて年配の方も、ドリフをあまり知らない世代の人も当時では「下らない」といわれたコントを見て大笑いしていました。 今回、親たちから嫌われた番組も20年後くらいには「ドリフターズ」みたいになる気がします。歴史は動いているんですから。 ちなみに「下らない」とは江戸特有の言葉です。江戸時代、江戸では京都や大坂の品物は高級扱いされていて「下り物」と呼ばれました。つまり「下らない」とは「高級でない」とか「品がない」という意味として使われ、意味を拡げて現代に残りました。 やっぱり最後は歴史にこじつけてみました。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月18日
コメント(0)
-
着物はポストだった??
左 竹久夢二「都より」 今の時代、パソコンや携帯のメールはかなり必需品になってきました。このブログを読んで頂いている方の多くもそうかと思います。 しかし、いつの時代も一般論ですが男性より女性のほうが「筆まめ」な気がします。これは明治、大正期も同じでした。当時はもちろん直筆の手紙です。 近代(明治時代以降)になると女子教育が少しづつ発展し始め、当時の義務教育は小学校までだったのですが、その後、高等女学校、女子大学と進む女子が増えていき、その彼女たちはよく手紙を書きました。 当時、彼女たちは相手に手紙を書くと直接本人に持っていき、相手の着物の袂に入れておくことが多くありました。また、相思相愛の男性の袂に手紙を持っていき、男性側が返信を相手の女性の襟元にいれるなんていうこともあったそうです。 着物はまさに手紙を受け取る「ポスト」の機能があったのです。 また、当時の女子は便箋が自分の美意識を反映するため、おしゃれでかわいい便箋をいくつも集めることが多く、「ベニバナ社」や「日出づる国社」などの便箋がヒット商品として受けていました。 洋服が発展すると、当然その習慣は薄らいでいきましたが、「手紙を女性の袂に入れる」とか「襟元にさす」手紙の出し方っていいですね!着物の魅力はこんなところにもあるのです! お着物を召されれる女性方、相手もお着物姿なら携帯メールはやめて、このような風流な手紙の出し方をしたらいかがでしょうか。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月18日
コメント(2)
-
あまりハミガキしないで!!
本日、歯医者に行ってきました。上奥歯の歯茎がどうも硬くなっている感じ、ハミガキしてるのに痛みも出てきたのでおかしいと思い病院へ行った。 先生によると歯茎の硬いのは「骨」が露出しているからだそうです。理由はハミガキのしすぎで歯茎が磨り減ってしまったため・・・ 一生懸命磨いていたのに裏目にでてしまうとは、情けないことで・・・ これから治療を行いますが、自分の歯茎を移植しなければならないかもと先生は言う。まいったな・・ 歯痛や虫歯は、もちろん昔からあって、中世に書かれた「病草子」(やまいのそうし)に歯槽膿漏で歯がグラグラしている男性が描かれています。 ある研究によると鎌倉時代で8%の人が虫歯で、その後増えていったなんてゆう本を読んだことがあります。 これを機会に「虫歯」の歴史を調べ始める奄太郎でした。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月17日
コメント(0)
-
土の芸術のお城!!
上 山中城跡 上の写真、箱根の山を静岡県側にくだる途中にある「山中城」というお城の跡ですが、なんか変な地割れがありますね。これはなんでしょうか? これは「障子堀」といって戦国時代、いまから500年前~400年前にかけて小田原に本拠地をもっていた北条氏のお城です。今でも小田原にいくと「北条五代」などの言葉を見つけることができますがその北条氏です。(早雲、氏綱、氏康、氏政、氏直) たしかに「障子」に見えますがなんでこんな堀を造ったのでしょうか?これは穴の部分にヘドロや粘土層の土を入れることでそこに落っこちた敵が出てこれないようにするためです。いわば「戦国時代のアリジゴク」といったことろでしょうか? 今までは関東特有の堀といわれていましたが最近関西なんかからも出土するようになり研究が進んでいます。 ちなみにこの山中城、今では国の史跡になり、芝生をはった公園となりかつての血生臭い時代を忘れるようにピクニックするにはもってこいの場所になっています。 特にここから静岡側を見ると伊豆半島や三島、沼津、そしてぼんやり牧の原まで見渡すことができるという絶景を堪能できます。 関東在住で箱根に行かれるかた、お勧めポイントですよ!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月17日
コメント(0)
-
着物業界に思うこと!!
今日は私が所属する着物業界について、一部分をお話ししましょう。 着物業界は今から10年前と比べると市場規模が約半分近くまでさがってしまいました。 「なんでこんなに小さくなるんだろう」とか「昔はよく売れたのに」とは多くの着物業界の人の言葉。 でも理由は簡単。消費者が着物を着なくなったことと着物業界の多くの経営努力不足が原因と考えています。 この間あるテレビ番組で百貨店のバイヤーが出て休日もライバル会社の視察をされている人が出ていました。その方は「今の時代、百貨店だってあぐらをかいてられないんです」「自分の好きなデザインと消費者に売れるデザインは違う」といわれていました。 百貨店であぐらをかけないんですから一着物屋なんでもっとあぐらをかけないでしょう。 以前日経ビジネスでヨドバシカメラの社長がこんな内容のことを言われていました。 「小売業で一番大事なことは業界や日本で一番店になるより消費者のニーズにこたえ続けることだ」小売業は決して忘れてはいけません。 以前展示会の仕事を終えたある女性社員が「自分が気に入らなかったり、よくないデザインの着物は売りたくないの!」といっていましたがそれを決めるのはあくまでお客さんです。売り手ではありません。 着物の販売は人との絆が強いのでお客さんを知っている方ならいいんでしょうが私はこれが新規のお客さんを「入りにくくしてるのでは」と思いますし、まさに「消費者不在」状態です。 これが改善されない限り市場規模は縮小し続けるでしょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月16日
コメント(0)
-
「中国式」和洋折衷??パート2
上 珠海円明新園復元西洋楼 写真が復元した西洋楼です。こんなに立派だったんですね。前にはヨーロッパを想わせる石廊があり、後ろには中国風の屋根をもった建物があります。 この復元建物はマカオの手前の珠海市の「円明新園」というところにあります。日本でいえば愛知の「明治村」や「日光江戸村」みたいなテーマパークですね。 でもこの建物、美しいと思いませんか?前には噴水もあるんですよ。 日本にも「和洋折衷」がありますが中国も日本も他国の文化が融合すると独自の文化になり、なんともいえない美術的なものになります。 着物も、明治以降、舶来の草花(バラやチューリップなど)をあしらった着物が人気がありました。これからのブログでも「和洋折衷の美しさ」を紹介していけたらと思います。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月15日
コメント(0)
-
「中国式」和洋折衷??
上 北京円明園西洋楼跡 今日はちょっと中国の歴史についてお話ししましょう。上の写真はヨーロッパのギリシアあたりの遺跡のようですが、中国の北京市北部の遺跡です。 今から300年ほど昔でしょうか、当時の中国は「清」という王朝がありましたが、この王朝の王様が代々百年以上かけて造った「円明園」という庭園の跡です。 写真の部分は「西洋楼」といってヨーロッパの庭園と中国の庭園をミックスして造ったもので、この西洋楼の前には噴水まであって、まさに「中国の中のヨーロッパでした。 当時清王朝は鎖国をしていましたが、イタリア人の画家や知識人が清の王様に重宝されたのでこのようなものができたのでしょう。 ただ残念なことに、清王朝が揺らいでからアロー号や義和団事件で外国の軍隊にことごとく壊され写真のような無残な状態になって残っています。 ただ、この建物、中国南部の珠海というところで復元されました。当時の「中国式」和洋折衷言うならば「華洋折衷」の美しい映像を次のブログでご紹介しましょう。上の写真と見比べたら面白いですよ!ご期待ください!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月15日
コメント(0)
-
「アイデア着物屋!!」パート2
それでは三井高利のアイデア商法とは? 「現金掛け値なし!」当時の呉服屋さんはお得意様の注文を聞いてからお伺いして商売をすることが中心でした。「こんなの持って来て」「ヘイ毎度」という感じですかね。当然裕福層が中心でした。 また、決済をすぐ行わず、年に1回、もしくは2回などの年季払いが中心でした。当然金利もつくので値段が高かったのです。 そこで高利は「あくまで現金販売のみでツケやクレジット販売をしない商法を考案しそのかわり値段を安くして消費者に還元したのです。 また、「反物売り」といって着物の生地のバラ売りを始めました。当時はあくまで着物一着作れる量の反物の販売が中心でしたからこれは珍しいことでした。 更に着物の仕立て時間を短縮するためテイラーを雇って販売した着物をすぐに仕立てられるようにしました。着物の仕立ては今でも時間がかかるものですが、すぐに着たい人の需要に答えたのです。 テイラーを雇ったことで更に先を行き、着物をある大きさに作ってしまい、それを客の目が届く天井からかけたのです。着物のプレタポルテですね、これを始めてやりました。バーゲンのビラ配りなどもやっています。 当時新たな商法の出現に江戸の呉服屋は様々な形で嫌がらせをしました。(今と変わらないですね)しかし経済の発展で急成長した消費者の多くは三井越後屋を支持したのです。 高利は更に両替商(今の銀行みたいなもの)の設立を幕府に献策して認められ幕府の御用商人として、三井越後屋は現代の経済や小売業のありかたの基本になっていきました。 今の時代、多くの人が高利になろうとしています。「あまから」もそうであるし、私の友人にもそのような人が多くいます。「消費者のため」に行動すれば必ず目標は実現するはず!私自身もそうでありたいと思っています。 その後の三井越後屋についてはまた別の機会にお話ししましょう。 (訂正)三井高利の出身は滋賀県ではなく三重県松坂市でした。滋賀県は三井家の発祥地です。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月14日
コメント(0)
-
アイデア着物屋!!
上 鳥居清長画 三井越後屋「三井文庫HP」より引用 現在の三井グループの原点は呉服屋さんだったことはとても有名。でもなんでただの呉服屋さんがあんなに大きな会社になっていったんでしょうか?今回は草創期の「三井越後屋」の商法についてお話ししましょう。 創業者三井高利(みついたかとし)は滋賀県で生まれます。ちょうど徳川家康が6年前に亡くなっていて、江戸時代が本格的にスタート、国全体が平和を回復し始めたときでした。 平和な時代になれば商業や文化が発展してきます。三井高利はそんなよい時代背景のなかで商業の勉強を松坂、京都でし始めます。 ある程度波に乗ると今度は江戸に呉服店を出店します。当時の駿河町、今の日銀新館あたりでしょうか。ここで様々な商法を本格的に展開するのです。 その商法とは?本日の次のブログでお話しさせていただきましょう!ぜひご覧ください!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月14日
コメント(0)
-
小泉首相のダイエット餃子??
写真の餃子、なんだと思いますか?これは品川近くにある「壇太」というラーメン屋の餃子です。普通ギョーザに比べるとかなり小さいですね。大きさは長いところで6センチといったところでしょうか、あっさりした一口ギョーザです。 この餃子、あの小泉首相が首相就任時以前からの大好物だそうで、首相就任時以降にも首相官邸に出前をとるくらいだとか。そういえば首相はどうも以前よりも人気は落ちたみたいですが、相変わらずスマートでいらっしゃいますね。 今が「正念場」という首相、ダイエットしておられるかは解りませんが、このギョーザなら食べ過ぎることはないでしょう。「ギョーザは食べたいけれどダイエットしている方」ここのギョーザオススメですよ。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月14日
コメント(0)
-
「着物の袖はミニスカート??」パート3
いにしへの人が袖をふる。今から1300年以上昔の話、額田王(ぬかだのおおきみ)という人がいました。ご存知の通り「王」といっても女性です。 彼女は大海人皇子(おおあまのみこ)の奥さん状態で子供もいましたが、のち彼の兄の天智天皇(元の中大兄皇子(なかのおおえのみこ)大化の改新をした人として必ず教科書に出てきますね。))のお気に入りになり後宮に入りました。つまり弟の奥さんを兄がもっていってしまったのです。 大海人皇子は額田王が忘れられず、ある時、天皇が遊狩を今の滋賀県の琵琶湖の東岸でした時(当時の都は滋賀県にあった近江京)に彼女を見ると思いっきり袖を振ったのです。 それを見て彼女は有名な詩を詠います。 あかねさす紫草野(むらさきの)行き標野行き野守はみずや君が袖振る (万葉集巻1.20) (紫草野行って、標野行って、警備員の野守がみてるんだから私に手を振るのは止めてよ。気づかれたらどうするの?)こんな感じでしょうか?袖を振る行為が愛情を表す行為だったことがわかります。 大海人皇子はこう返詩します。 紫草(むらさき)のにほえる妹を憎あらば人妻故に我恋ひめやも (万葉集巻1.21) 「妹」とは「イモ」と呼び、現代の妹の意味でなく、男からみた愛している女の人の呼び方です。今で言うと「愛人」「彼女」「恋人」「妻」などですね。これ以上訳文は書かんでもいいでしょう。 手を振る行為は残っても、袖が短い洋服ではあまり効果がないのでは?これを読んで頂いている女性の方、ぜひ「着物で袖を振って下さい!!」女性の魅力が倍増すること間違いなし! 男性の方は奥様や彼女に着物を着せてあげて下さい!袖を振られると今まで以上の魅力を感じるはず!お試しを! ただ奥様や彼女を間違っても「イモ」と読んではいけません。これは古代人だけですから、現代人が言ったら張り倒されますよ!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月13日
コメント(0)
-
「着物の袖はミニスカート??」パート2
「袖を振る」という行為について、2人の人が別れる所を思い出して下さい。「バイバーイ」と手を振りますよね。女性がこれをやるのには問題ないはず、しかし男性の場合は別なんです。 男性が女性と別れるときは手を振ること、つまり「袖を振る」ことがあるのですが、男性同士が別れるとき袖を振って思いっきり「バイバーイ」とうやっていたらどう思いますか? 例えば、会社帰りの同僚サラリーマンが別れるとき、手をあげることはあっても、「バイバーイ」と手を思い切り振っていたら「気持ち悪いな?」とか「特殊なご関係かな?」と思いませんか? 手を振る、つまり「袖を振る」という行為は自分のセックスアピールの意味があるのです。つまり愛する人へ愛を伝えることなのです。女性はそもそも袖があったので洋服になってもその習慣が残っていますし男性も異性や、愛する女性には袖を振って愛情を表現しましたし、習慣としてのこりました。 では歴史歴史人物が実際袖を振って愛情表現したところを次の回で観てみましょう。お楽しみに!□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月13日
コメント(0)
-
着物の袖はミニスカート??
着物の袖はミニスカート?? 日本の着物には必ず「袖」があります。勿論洋服にもありますが、それより「袖」に重要な要素があるのです。 着物では年齢と共に袖が短くなっていきます。若ければ振袖のように長く、結婚すれば30センチちょっと(1尺3寸)に短くします。更に加齢するともっと短くすることがあります。 これは着物の袖には女性の色っぽさを感じることができる日本人特有の文化があるからです。袖がユラユラなびいているのが色っぽいんですね。だから若いうちは色っぽくして年齢を重ねると色っぽさを抑えるんですね。 これって今の女性がミニスカートを履いたりヒールの高い靴を履いたりするのと同じことなんでないですかね。 ところでみなさん、着物を着ない現代でもその「袖」を意識した行動が残って普段とっているのをご存知ですか?そのことは本日中のブログの中でお話ししましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月13日
コメント(0)
-
明治時代の高層ビル!!
浅草十二階「凌雲閣」古写真 浅草十二階は明治23年(1890年)英国人技師により造られました。当然当時の日本で一番高い建物で、日本初のエレベーターが設置されていましたが、途中で安全面で問題があると使用中止となっています。したがってらせん階段を上まで登っていきました。結構しんどかったんではないでしょうか。 階の途中で甘酒が振舞われ、最上階からは東京都心部が全部見渡せたそうです。また古老の話によると、最上階に行くと少し建物がグラグラ揺れていたそうです。怖くて登れなかった人もいるんではないでしょうか。 大正時代になると浅草は文化の発信地になり、当時の流行の洋服や着物を着た人たちが集まり、たいへん発展します。その当時の写真や絵には必ずこの十二階が載っています。 しかし大正12年(1923年)関東大震災で8階から上がポッキリ折れてしまい、周りに密集していた家も焼けてしまいます。震災直後の無残な姿の十二階が焼け野原にポツンと建っている写真は震災を扱った書物に必ずといっていいほど載っています。 十二階は二度と再建されることはなく、震災後、浅草は文化の発信地から後退していきます。たった33年の命だった十二階は当時を知る人々の心に残り、語り伝えられ現在に至っています。 現在日本にはたくさんの高層ビルがありますし、最近は六本木ヒルズなんか有名ですが、十二階はそれらの「おじいちゃん」みたいな気がします。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月12日
コメント(0)
-
戦国時代の着物美人!!
左の女性像をご存知の方も多いとおもいます。織田信長の妹お市の方の肖像がです。高野山の持明院というお寺にあり、重要文化財に指定されています。 お市の方というと織田信長の妹で政略結婚で浅井長政に嫁いだが兄と夫が対立し戦争になり敗れた夫は3人の娘を残し自刃。後、信長の重臣柴田勝家と再婚するが今度は夫が豊臣秀吉と対立して敗北、共に自殺する。という戦国時代の「悲劇の女性」というイメージが強いですね。 また、彼女の長女は豊臣秀吉の夫人、三女は徳永家康の子供秀忠の夫人、徳川家光の母となり、政治的にも重要な人です。 しかし、今日話したいのは彼女の着ている「着物」について。彼女の着物は「現在の着物」の原型となった「小袖」という着物です。よく「着物は昔から日本女性は着ていた」という言葉を聞きますが、「今の着物」の形が出来たのはたかだか500年ほど昔のことなので日本有史から考えるとそんなに長くないんです。 彼女の着物は白地に菊桐文の小袖に、立湧を地紋とした紅地の華やかな打掛を腰に巻いています。打掛は当時着用するというより腰に巻くパターンでした。 また、注目は袖。袖がくくってあって手の出る所だけ穴が開いているのです。小袖の特徴であり現代の着物に残される特徴です。以前より機能的にするため。 彼女は当時、最高の美人であったといいますが、この着物を着用してるからの美人なんですね。まぁ洋服着た美人は当時はいないでしょうが。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月12日
コメント(2)
-
東京にいながら京都へ旅行できる??
上の写真は京都の景勝地、嵐山を渡月橋から見たところです。でも現地へいったことのある人なら「嘘をつくな!」と思うはず。でも新緑の嵐山なのです。 現在開催している「愛・地球博」では世界の国を疑似体験できるパビリオンが盛況との事ですが,疑似体験したい気持ちは江戸時代の人も現代人も同じ。 写真は東京都文京区にある「小石川後楽園」、江戸時代に御三家の水戸徳川家の庭園です。水戸徳川家は徳川家康の末っ子の頼房から始まり、その子供が水戸黄門こと光圀です。(水戸黄門のおじいちゃんは徳川家康です)。 この親子は教養があったけれど殿様なので勝手に旅行にいけなかったんですね。(水戸黄門の話は空想です)また、水戸家は「江戸在勤」といって当時の大名さんたちがしていた参勤交代を免除されていて水戸より江戸にいることが多かったんですね。それが彼らを庭園造りに駆り立てたのかもしれません。 小石川の広大な土地に全国の景勝地のミニチュアを造って「行った気分」になっていたのでしょう。写真は嵐山ですがちゃんと「ちっちゃい渡月橋」もあります。他には以下のようなミニチュアが残っています。 ○京都の清水寺を模した居水観音堂と音羽の滝 ○京都の愛宕坂 ○菅原道真が詠んだ紅葉のきれいな龍田川 ○西行が景色の美しさに足を止めた駐歩泉 ○伊勢物語の舞台である八つ橋 ○琵琶湖と竹生島、そして近江八景の唐松 ○鳴門海峡の鳴門 ○信濃路の山間を流れる木曽川 ○中国杭州の西湖堤 など、江戸にいながらいろんなところに行くという「疑似体験」が出来るのです。江戸にはこのような施設が他にもあります。追々お話しするとしましょう。 「疑似体験できる」ということは現代の集客やマーケティングにも生かせるんでしょうね。 「小石川後楽園」は飯田橋駅から歩いて数分、GWに「どこもいけなかった人」や「旅行なんて出来ない」東京在住の方、ぜひ江戸時代の「疑似体験旅行」されては如何でしょうか。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月11日
コメント(0)
-
こんなぶっ飛んだ首相がいた!
日本が内閣制度を始めてから百年以上、現首相の小泉さんまでたくさんの首相がいました。みなさんそれぞれの人生を経て首相になっているのですが、今日はその中で大正時代に首相になった「高橋是清」という人の人生について。 彼は江戸時代、ペリーの来た次の年に仙台藩士の子供として江戸に生まれた。彼は仙台藩費で当時多くの藩士が毛嫌いした英語の勉強をした。学校は当時のヘボン塾、今の明治学院の前身だった。彼のぶっ飛び人生はここから始まります。 英語の上達した是清はアメリカ留学を命じられるが、ブローカーにだまされて奴隷として売り飛ばされてしまう。 明治になって外人に変装して税関を突破し帰国。英語が出来たので森有礼(福澤諭吉の門下生)の家に居候しながら開成学校、今の東大に通うが、英語力が買われ教官になってしまう。 収入が安定すると茶屋遊びにハマり、学校をクビになり芸者の付き人になる。 借金がかさんだので九州の唐津で教師として就職するがこんどは酒に溺れ、授業の前から酒を飲みまくる。本人曰く「一日三升飲んだ」アル中状態、喀血する。 再度上京して大蔵省に入るが上司と喧嘩して辞職する。 大学の試験を受けて授業料を翻訳で稼ぎながら学ぶ。今度は文部省から声がかかり英語学校の教師になる。 今度は農商務省に入り外国を回って近代特許制度の確立を行う。 役人なのに今度は事業に興味を示し、ペルーの鉱山業に乗り出すがこれが大失敗。日本でも牧場経営や鉱山経営をやるがことごとく失敗。1500坪の屋敷から家賃6円の借家に引っ越す。奥さんは内職して家計を支える。「ドン底生活」 突然、日銀総裁から誘われ丁稚状態で日銀へ入行、財政を学んで、外債や軍事公債を次々と集め明治の終わりには日銀総裁になってしまう。 大正時代から大蔵大臣を歴任、ついには大正10年首相になっちゃった! 昭和初期、金融恐慌(バブル崩壊)が起こり貨幣流通量が減って全国の銀行がパニックになるなか、大蔵大臣として紙幣の大増刷を行い、国民の救済にあたる。(大急ぎで紙幣を刷ったため片面しか印刷していない紙幣を発行) 日本経済が危機的状況になり、軍国主義的風潮が高まる中、それに反対して財政政策で国の建て直しを図る。(歴史学ではよく「高橋財政」という) 昭和11年、陸軍皇道派(急進的主戦派)の青年将校達に寝起きを襲われ赤坂の自宅で暗殺される。享年83歳。 芸者さんの付き人やった首相は彼ぐらいではないでしょうか?彼の人生は「成功」と「挫折」の繰り返し。でもいつもついて回ったのは人との「出会い」と「人脈」そして「めげない気持ち」と「好奇心」なんではないでしょうか? 高橋是清は多くの人脈をもっていたように大変人々から好かれる人柄で、大柄のはげ頭に白い大きなあごひげという風貌から「だるま大臣」と呼ばれていました。 高橋是清が暗殺された場所は「高橋是清記念公園」として胸像があり、彼が暗殺された時の建物は小金井の「江戸東京たてもの園」に移築され公開されています。 大臣を歴任した人物にしては粗末な建物で、そこには愛用の眼鏡、愛読していた新聞、孫との写真などが展示されています。 ご興味のある方はいってみて下さい。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月11日
コメント(0)
-
今が旬!たけのこがやってきた!
昨日、兼好法師のみかんの話をしたのですが、いきなり家に巨大な輸送物が届いた。なんだこれ?送り主は大学時代の同級生で静岡のJAに勤めるT・Iから。開けてみるとでかいたけのこがごろごろ入っていた。母親は大喜び!すぐに友人に電話したところ「家の裏山で採れたものだから食べてよ」とのこと。庭のみかんでなく、たけのこが届いた!ありがとうです!また、この場を借りて、静岡に遊びに行った折、親切にして頂いた友人の同僚の「JA伊豆の国」のみなさん、ありがとうございました。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月11日
コメント(0)
-
現代に通じる兼好の考え
徒然草(つれづれぐさ)は日本を代表する随筆で有名な吉田兼好が書いた書です。随筆なので思うがままに140段ほど書いてあるのですが、その中の11段にこんな話があります。 兼好が京都の郊外を歩いていたとき、ひっそりと建つ庵があった。筧にしたたる水の音以外はなにも聞こえない。でも閼伽棚に綺麗に花を生けてあったりして住人は不在だったが「こんな自然の中で住んでる人は趣があるなぁ」と思っていると庵のむこうに実をつけた大きなみかんの木があった。その木に厳重に柵がしてあるのをみて兼好は興さめて、「この木がなかったらなぁ」と思った。 せっかく自然の中で家財をすて出家しているのにみかんの実にはなんで「自分のもの」と独り占めしてしまうのか。兼好はそう感じたのだと思います。 世の中「自分が」「自分が」と自分の所有や権利ばかりいっていると必ず人間関係はギスギスしてきます。所有や権利は大事なことですがそれより大事なのは人間関係。私は多くの方に恩恵を受けてきたのでなおさら感じます。 私がもし自宅にみかんの木を持てるようになったら実がなっても柵はしないような人間になりたいです。なぜなら私の友人はそういう人が多いですから。 兼好さんは他にも色々なことをいっているので今後ともご登場願いましょう。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月10日
コメント(0)
-
一番いい季節
私は今が一年で一番好きな季節です。でもわたしだけではないでしょう。今日、神保町を歩いたのですが、気に入った本探しにもうってつけの季節。早速私の好きな歴史書を物色!創元社から出ている「ローマ教皇」という本を買いました。私は日本史が好きなのですが、このあいだヨハネ・パウロ2世が亡くなられ「コンクラーベ」というのをやっていたので調べてみようと思ったのです。 少し読んでみたのですがなんとヨーロッパ中世には教皇の位に値段が付けられ売買させていたそうです。 そんな時代があったんですね・・・詳しく読みましたら面白ネタをご報告します。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月10日
コメント(2)
-
奄太郎です!
始めまして、本日よりブログをやらせていただきます奄太郎です。メカオンチの私ですが、こんな私がブログやるとは思ってもいませんでした。時代の流れってスゴイですよね。現代社会、ブログは広告以上のツールになりつつあるなんて聞いていましたが。とにかく今の時代に感謝していろいろなことを書かせて頂きたいと思っています。至らない点もあるかと思いますがよろしくお願いします。□□□■■■-------------------------------本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから) http://www.amakara.jp -------------------------------■■■□□□
2005年05月09日
コメント(2)
全38件 (38件中 1-38件目)
1