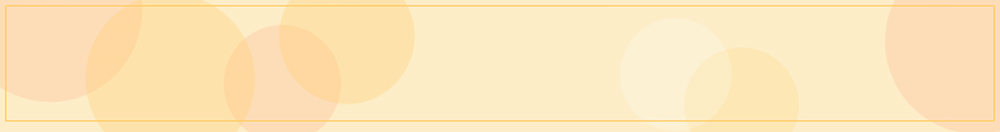2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年04月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
ブラームス弦5 第12回練習
第2ヴァイオリンを除く4人での練習でした。弦5の前に死と乙女の練習が同じ場所であったため、その第1ヴァイオリンに残ってもらい、客観的に聴いてもらいました。主に、前回の先生練習の復習と、先生にちゃんとやった方がいいと指摘された音程を中心に進めました。2楽章はテンポ変化について先生に指摘されたので、弾きながら確認していきました。1楽章についても、冒頭からひとかたまり(練習番号1まで)のテンポ設定がなかなかしっくりいっていなかったので、そこを練習しました。また、先生に指摘されたテンポ変化の部分(74小節目や201小節目など)を確認しました。3楽章は先生に提示されたテンポにするかどうか相談しましたが、そこまで速くはないが、これまで練習してきたテンポよりは速いテンポぐらいで、energicoの雰囲気を出そうということになりました。検討した結果、二分音符=95~100に設定することにしました。また、全体を通して、第2ヴァイオリンと合わせないといけないポイントを確認し、次回の練習で一緒に練習することにしました。4人だけでしたが、そろそろ通した時の感じをつかんだ方がいいので、最後に初めて通してみました。時間は20分強。第1ヴァイオリンと第2ヴィオラは、弦5の前の弦4の練習で「死と乙女」の初通し(40分強!)を経験していたのですが、それと比べるととてもあっさりという感じでした。とはいえ、中身は濃い曲なので、大変です。今まで練習してきているとはいえ、通してみると、落ちてしまう箇所があったり、音程が崩れたり、とウィークポイントがたくさんでてきました。練習はホール練習も含めあと2回。頑張らねば・・・。(Vn:K.N.)
April 29, 2008
コメント(0)
-
死と乙女の4人での練習6回目
今日は前回の先生練習の復習をして、最後に通して演奏しました。3楽章:TRIO のテンポ確認をしました。前回の先生練習のときは丁寧に弾いたのもあってゆっくり目になっていました。そのときよりは少しテンポを速目にしました。TRIO で最初にテンポを作るのは第2ヴァイオリンです。第1ヴァイオリンのテンポ感と合っていることが重要です。前回先生に言われた、「内声と溶け合うメロディ」を意識しました。柔らかい音色を出そうとすると、音量が減ってしまうので、音量が減らさずに柔らかい音色を出す練習をしました。また内声(第2ヴァイオリンとヴィオラ)との音量バランスも調整しました。第1ヴァイオリンの TRIO の最後の一つ前の音、A(ラ) を外さないようにするために、色々工夫をしました。その2小節前をはっきり入ってテンポを崩さない(あわてないように)すること、A のある小節をすこしゆっくりにして、跳躍する時間を稼ぐこと、です。4楽章:前回練習で言われた「アップを意識する」練習をしました。また、「ここは合わせる」ポイントを作っていきました。PRESTISSIMO も、合わせるポイントを作り、速いテンポでも崩れないように練習しました。通し練習:最後に全曲通しました。1・2楽章は久しぶりだったので、これまでのことを思い出しながら演奏する感じになりました。3・4楽章は最近の練習の成果か、とても安定した演奏になりました。また、この曲は譜めくりが大変な部分があり、その対策がまだ足りていないことが分かりました。次回は、1・2楽章中心の練習にすることにしました。(Vn: T.Y. 記)
April 29, 2008
コメント(0)
-
アメリカ(木五編):アンサンブルは譲り合いの精神で
さて、本日は先生練の復習です。■3楽章からフレーズの感じ方、アクセントの感じ方、、どうやら皆さん先生のアドバイスを覚えています。さらに、ダイナミクスレンジを広げるため、音量の調整を行いました。■2楽章旋律の歌い方、伴奏の音色、改善されています。伴奏パートの各管の音量の調節や、リズムの感じ方、また、流れが停滞しないように、拍の頭の発音を注意していきました。■4楽章この楽章は時間がなくて先生に見ていただけませんでした。他の楽章で注意された、フレーズやリズムパートの音形、掛け合いなど注意しながら練習しました。■1楽章有名な16分音符の出だしの部分。フルートから始まり、途中でクラリネットが便乗。途中でクラとオーボエが交代。オーボエ奏者:「なんで途中で交代するんだ!ずっとクラが吹けばいいのに!」と、怒り狂う少しこぼす。長い連続した16分音符は、拍を感じることと、旋律を聴くことで合わせましょう。***********全体を通して各自多かった発言。「そこは音量を抑えて!」いろんな要素が存在し、また、どの要素も重要。重要だと思うから、「聞かさなきゃ」と吹いてしまう。各自その調子だと、なんだかゴチャゴチャした、捉えどころのない音楽になってしまう。こういう時こそ、最も活かさなければならないパートを理解しなければならない。決して、重要パートを飛び越えないように。また、音量的に抑えた方が、結果、聴こえてきたりもする。和声も聴こえてくる。アンサンブルは譲り合いの精神が重要。そういえば、私の師匠(Fl)が言っていた、「アマチュアの人で、小さい音で表現できる人は少ない」と。大きな音を出せるのはインパクトがあるしとても魅力的であるが、小さい音でも表現できることも重要だしとても難しい。アンサンブルをやっていると、小さい音の表現が必要な場面が多い。細い音、柔らかい音、空気または他のパートに同化する音、場面によって、要求される小さい音は様々であるが、それを巧みに使い分けることができたら、木管五重奏ならではの色彩豊かな和声が聴こえてくることだろう。今回はギャグなしです。K.I(FL)
April 27, 2008
コメント(2)
-
死と乙女の先生練習2回目
今日は、七澤清貴先生にみていただきました。前回は、1・2楽章を中心にみていただいたので、今日は3→4→2→1の順でみていただきました。<3楽章>SCHERZO は大体良いとのこと。Trio は、第1ヴァイオリンの音が立ちすぎてしまっているので、もっと内声と溶け合うような音色にすると一体感が出て良い。ということで、弓を指板寄りにして弾いてみると、今度は弱すぎるとのこと。なので、指板寄りだけれども、弓圧を強くして弾いてみると、良い感じになりました。でも、まだまだ研究が必要です。<4楽章>小節の弱拍のところ、つまりボーイングがアップになるところ(私たちは、四分+八分+四分+八分という音形を、ダウン、ダウン、アップ、アップで演奏しています。また、八分音符が6個続くところの4つめの音)が揃っていないので、このアップの部分をそろえる意識を持つほうが良い、とのことでした。特に、7小節目、15小節目、32小節目などです(32小節目の部分は、31小節目の休符の後、ダウンから始めています)。アップを意識することによって、音の粒が前よりも揃うようになってきました。最初のフェルマータ(88小節目)の後の第1ヴァイオリン、D線で第1ポジションで弾いていたのですが、「そこはG線!!」と指摘されました。。第1ヴァイオリン、何箇所か音が跳躍する場所があります。262, 273, 620, 631, 682 小節目など。ここを外さないように、とのことでした。が、どうすればいいのやら。。133小節目からや173小節目からなど、片方のヴァイオリンが八分音符で刻んで、もう一方のヴァイオリンが長いフレーズで歌うところがありますが(後半にも出てくる)、長いフレーズが遅れがちになってしまうので、前目に歌うのがよいとのことです。<2楽章>最初のテーマの部分の音程合わせをしました。また、pp で non vibrato で弾く部分をつくったりして、めりはりを付けました。第1変奏のところは、内声がメロディなので、内声が歌うようにすると、オブリガートの第1ヴァイオリンも弾きやすくなりました。第3変奏は、第1ヴァイオリンは、なるべくビブラートをかけるように、とのことでした。第4変奏の最後、153小節目からの音程あわせをしました。<1楽章>第1楽章は、時間が無くて、通すだけで終わってしまいました。練習から時間が経ってしまって、だいぶ忘れてしまってます。本当はもっといろいろと教えていただいたのですが。。しかも、第1ヴァイオリンのことばかりしか書けなくてすみません。。(Vn: T.Y.記)
April 20, 2008
コメント(0)
-
フルート四重奏の練習10回目
七澤清貴先生に見ていただきました。各楽章を通しながら、その都度アドヴァイスをいただきました。前回の先生練で、音程についてゆっくりから合わせるようにとのご助言をいただき、音程合わせ重視の練習をしてきました。全体を通して音程は常に指摘される部分ではありますが、前回に比べるととても減りました。だいぶ効果があったようです。1楽章:Var. II はヴァイオリンがメロディーの変奏曲です。ヴァイオリンの16分音符をもっと短めにと言われました。残りの3パートは同音の伸ばし、あるいはスラーで動いています。スピッカートで弾くとバイオリンが際立つようになりました。Var.III はヴィオラがメロディーの変奏曲です。フルートとヴァイオリンには装飾音符がついています。これまではヴィオラのメロディーを消さないように装飾音符を控えめに弾いて(吹いて)いましたが、アクセントのつもりで強調するようにと言われました。そうしてみると、伴奏にメリハリがついて曲の雰囲気ががらっと変わりました。Var.IV はチェロが細かい動きをしている変奏曲です。チェロはメロディーではないけれど、元気そうな雰囲気ではっきり弾いた方がよいとのことでした。特に音の立ち上がりが重要です。右手の指先を意識するよう言われました。2楽章:冒頭、フルートとヴァイオリンのフレージングについて指摘されました。トリオでは、フルートの装飾音符の付け方について指摘されました。これまでの付け方よりも難しそうに聴こえますが、かえってアクセントが効いてよい感じです。3楽章:この楽章はこれまでの練習回数が少ない楽章です。音程が合ってない箇所を指摘していただきました。最後に一回通し、おさらい&録音をして終わりました。練習で1番長い時間を費やしているのは1楽章だったので、仕上がり具合は練習時間に比例してる印象です。(Vc: Y.M.記)
April 20, 2008
コメント(0)
-
ブラームス弦5 11回目:2度目の先生練習
2回目の先生練習です。前回それほど丁寧にやっていなかったので、2楽章からやりました。Grave ed apassionato 冒頭を弾き出すと、すぐに「響きが違う」と言われてしまいました。音程と音量バランスの問題のようです。チェロ以外は少し音量を落とし目にしました。2楽章は全体に渡って音程が難しいのですが、チェロ以外の楽器は要所要所のフィンガリングを先生にアドバイスいただきました。それにしたがうと、今までなんでこんなに苦労していたのだろうと感じるぐらいに楽になる箇所がいくつも...。フィンガリングはとても重要だと改めて感じました。Allegretto vivace最初のpizz.の伴奏を8分の6拍子らしくした方がいいとのことでした。そうすると見違えるように音楽が生き生きとしてきます。そして、バイオリンの付点のリズムのメロディーは、16分音符をきつめにとった方がいいようでした。全体的にppやpの音楽だけれども、大きすぎると指摘されました。差をつけるためにpを大きめに弾いていたのですが、やはり小さく弾いた方がいいようです。TempoI(80小節目~)90小節目に到達するまでの数小節が崩壊しやすいので、ちゃんと構造を理解しないとだめ、とのことです。いまだに不安感があるので、要練習です。95小節目~のagitatoはしっかりやり、98小節目でもとに戻るといいとのことでした。110小節目~は一小節ごとにメロディーが第1バイオリン→第2バイオリン→チェロ→第1バイオリン→チェロと移り変わっていくので、メロディー以外は控えめにした方がいいようです。Presto143小節目の第2バイオリンの動きを出した方がいいとのことでした。TempoI(164小節目~)184小節目~の第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラに出てくる7連音符(4連音符+3連音符)で歌おうとして遅くなってしまっていたようですが、そうすると、楽章の終りに向けてどんどんゆったりしていってしまい、最後から9小節前にあるritard. moltoが効かなくなってしまうとのことです。7連音符はむしろ先に行くぐらいのつもりで弾いた方が歌えるし、音楽が停滞しなくていいようです。次いで、3楽章をやりました。自分たちのテンポで弾き出したところ、それでは遅いとのこと。Allegro energicoなのですが、energicoの感じが出ないようです。先生の提示されたテンポでひととおり最後まで弾いたところ、細かい動きなど今は不慣れなせいもあり崩れてしまいましたが、雰囲気ががらっと変わり、確かにエネルギッシュさが出ました。また、中間部の3連音符のメロディーラインもとても歌いやすくなりました。ただ、このテンポで弾くには、もっと個々人の練習と慣れが必要です。今は、これまでの遅めのテンポに慣れていて、速いパッセージで弓をたくさん使っているので、コンパクトに動くことを気をつければ、この速さにも対応できそうな気がします。最後に1楽章です。前回よりもよくなっているとのことでした。練習番号1~、練習番号7~はちょっと崩れてしまうことがありました。ここについては、今回も音程確認を行いました。練習番号8~の第1ビオラのメロディーを、185小節目~第1バイオリンが弾きますが、歌い方が足りないとの指摘をうけました。第1ビオラは男性、第1バイオリンは女性なのですが、先生のお話によると、男性の方がロマンチストで、色気のある演奏ができるそうです。世界的に大変有名な某女性バイオリニストは、誰もが彼女のことを大変セクシーだと認めると思いますが、「色っぽい演奏は男性にかなわない」と言っていたそうです。201小節目~は遅くした方がいいようです。私たちはその前の209小節目でrit.しようとしていたのですが。前半も同じです。1楽章の最大の課題はPiu moderatoでした。やはり和音の音程が問題のようで、特に内声、第2バイオリンやビオラの音程が重要のようです。また、217小節目~の第1バイオリンと第2バイオリンのメロディーの受け渡しをもっとスムーズにした方がよさそうです。218小節目~は第2バイオリンがメロディーとのことです。今回も、全体的に、音程をもっとちゃんとやりなさい、とご指摘受けました。調性の中の、鍵となる音(ドミソの和音の音など)の音程が外れると、どうしても汚く聴こえるようです。逆にいえば、そうした音の音程を確実にすれば、他の音が多少ずれてもそう気にならないというわけです。各自、自分の譜面の中の、そうした鍵となる音を把握し、そこを確実に音程とる練習をする必要があります。次回は4/29で、またもや第2バイオリンを除く4人の練習です。その次は5/10に第1ビオラを除く4人での練習です。なかなか5人揃う日がありませんが、ともかく、次回は4人で、音程や先生の指摘されたテンポ変化や弾き方を固めていかないといけません。(Vn:K.N.記)
April 19, 2008
コメント(0)
-

アメリカ(木五編):アンサンブルはスキンシップだ!
前回に引き続き、本日もObの森先生に見ていただきました。今回は、残りの2,3,4楽章の予定。やばい状態の楽章から見てもらいましょう。ということで、3楽章から。■3楽章先生曰く、まじめに拍に合わせようとしすぎて、全体的に重く、遊び心がないように聴こえる。とのこと。この楽章は、3/4拍子のMolto vivace 。2拍目アクセントのパターンが多く、下手すると1拍目がアウフタクトと錯覚してしまいがち。油断すると拍がくずれてしまうので、ガチガチになってしまっていたらしい。ということで、以下についてアドバイスを頂きました。・3/4拍子を1拍子に感じましょう。・フレーズは2小節ごと、または4小節ごとに雰囲気を変えましょう。・細かく動くリズムパートはコンパクトに。それによって、リズムに遊び心が出てきます。・この曲は踊りたくなるはずだ!さて、今回の『心に残るで賞』アドバイスは、、アクセントは作業ではない!スキンシップでアクセントを感じよう!2拍目アクセントのパターンが多いことは触れました。そのアクセントの時、互いにどう意識するか。レガートなフレーズの時には、 ⇒相手に肘で、「この~」と突く感じで。元気のいいフレーズの時には、 ⇒アメリカ人のように、ハイタッチ!「へ~イ!」大らかに盛り上がるところでは、 ⇒ビールで乾杯!ジョキで「カチ~ン!」(ホルン奏者とクラリネット奏者は、これでかなりじゃれ合ってました。こらこら、はしゃぎすぎ!)互いに触れ合う意識で、遊び心ある、アクセントの出来上がり!これぞアンサンブルって感じです。今度から、木5メンバーの挨拶はハイタッチにしようと思う。■次にやばいのが2楽章この楽章は、6/8拍子、Lent d-moll。短調だけれども、音は明るく伸びやかに。伴奏パートは、以下の3パターンの組み合わせが多い。・8分音符のベースの刻み・16分音符のアルペジオ・シンコペーションの刻みこれらが旋律の下で延々と刻まれる。この時、赤ちゃんをだっこしてやさしく揺らすようなイメージで。(深刻な音だと、赤ちゃんは不安がります)この伴奏により、冒頭のObの旋律、その後に続くFgの旋律がよりやわらかい表情を出すことができます。2楽章の旋律はとても美しい。その旋律を、手を変え品を変え、いろんなパターンで演奏します。中でも先生の説明で面白かったこと。FlとOb、「出会い、そして別れ」のシチュエーション。FlとObが3度でハモる美しい旋律。しかし、ある時別れを決意し、それぞれの道を歩むのでした。↓あぁ、ドラマがあります。2楽章を終えたところで時間切れ。残念なことに、4楽章を見ていただくことはできませんでした。しかし、教えていただいたことを応用して、自分たちなりの4楽章を作り上げましょう!森先生、ありがとうございました!*-*-*-*-*-*-*-*予定では、ピツィカートについて書こうかと思っていましたが。2楽章の終わりに出てくる、「arco」「pizz」の奏法をどう区別するか、多少の論議がありまして。スタッカートで吹くべきか、それとも、舌ではじいた感じを出すか。しかしどれをとっても、弦楽器のように、弦をはじいた後にヴゥィ~ンと音が残りません。結果的に、音の長さと緊張感を持たせることで、区別しようということになりました。弦楽器は奥が深い。しかしそれにとらわれずに管楽器ならではの表現を追及していきましょう!K.I(FL)
April 19, 2008
コメント(0)
-
フルート四重奏の練習9回目
フルート奏者が遅れるとのことだったので、前半は弦分奏をしました。前回、3楽章の音程合わせをやったので、1楽章のテーマから順番に練習しました。ちょうど var.IV のチェロの練習をやっているところでフルート奏者が来たので、フルートも一緒に1楽章最初からやりました。全員での練習では、各ヴァリエーションのテンポの確認をしました。Var.IIの4~6小節目では、ヴァイオリンのメロディーの16分音符とチェロの16分音符が合いませんでしたが、チェロが焦ってテンポ感がなくなってしまっていたのが原因でした。5、6小節目もチェロの付点8分音符をアップで弾くと合うようになりました。Var.III ではテンポを確認しました。ヴィオラのメロディーは比較的ゆっくりめなので、Var. II の終わりをゆっくりにして、Var.III との間も結構あけるようにしました。Var.IV のメロディーはフルートですが、チェロの聴かせどころなので、はっきり弾くことを確認しました。(Vc: Y.M.記)
April 12, 2008
コメント(0)
-
ブラームス弦5 10回目の練習
前回先生練習でしたが、次回も先生練習なので、その間の唯一の練習ということで、午後・夜間と場所をとり、長時間練習する予定でした。しかし、第2バイオリンの都合がつかなくなり、結果的に、15時~19時過ぎまでは4人で、その後22時近くまで5人で練習しました。《4人での練習》前回先生から「音程とリズムをもっとやった方がいい」と最後にご指摘を受けたので、1楽章から順に、少々ゆっくりのテンポで音量を落とし目にして、弾いていきました。特に先生につかまったポイントや気になった箇所はとめて、音程や縦の線などを調整したり、反復練習していきました。1楽章冒頭のテンポの確認21小節目までのレガートな音楽と22小節目~のスタッカートの音楽の対比練習番号1~45小節目、練習番号7~8の「プロでも難しい」箇所の練習(今回やると意外にうまく行きました。)177小節目~の第1ビオラのちょっと前に行くメロディーの裏の8分音符の伴奏は、短めにはぎれよく弾くことにしました。Piu moderatoの音程確認2楽章音程に注意しながら進めました。途中から、同じ練習場所の別の部屋でやはり練習していたFlカルテットのバイオリンが聴いてくれました。Prestoは、8分音符の動きの後に出てくる、スラーのフレーズ(123小節目~、133小節目~など)の弾き方がそろっていないとのこと。同じ動きという認識が足りなかったようです。スラーの弾き方、音色も合わせました。Prestoの151小節目~、155小節目~の第2バイオリン、ビオラ2本の8分音符の音程合わせを、5人揃ってからやろうということになりました。3楽章先生のご指摘のとおり、スタッカートなしはデタッシェで、ありはスタッカートで弾くことに注意して進めました。練習番号1~、練習番号3~4にかけては、落ちてしまうことがあったので、反復練習しました。50小節目や141小節目のsubit pを効果的にするために、その直前のクレッシェンドをかなりやることにしました。そして、pに落とすときは若干間をあけるようにしました。98小節目のアウフタクトをそろえるようにしました。Prestoからはまだ慣れていない感じあったので、テンポを落として練習しました。《5人での練習》1楽章から順に流しながら進めました。1楽章の冒頭のテンポの確認と反復練習音程が気になるところ、前回先生にアドバイスいただいたところ、4人での練習で新たに弾き方を決めたところなどをひとつひとつ確認していきました。2楽章までで大半の時間を費やし、3楽章はあまり手をつけられませんでした。次回はまた先生練習ですが、先生がいらっしゃる前に30分ほど3楽章を練習することにしました。(Vn:K.N.記)
April 12, 2008
コメント(0)
-
死と乙女の4人での練習5回目
もともとは明日が練習日だったのですが、チェリストの都合が悪くなり(前回の練習参照)、急遽、今日練習することになりました。後半の楽章の練習が進んでいないので、3楽章から練習しました。3楽章はメロディがアウフタクトから始まります。メロディのフレーズの最後は、3拍子の2拍目で終わり、次のメロディがアウフタクトで始まります。この間を少し開けるかどうかを試してみました。いろいろと試した結果、f→pとなるところでは開けて、それ以外はあまり開けないようにするとうまくいきそうな感じでした。トリオは音程合わせをしました。4楽章は、前回宿題になった、278から始めました。宿題の部分を何度か合わせ、ようやく誰も間違えずにできるようになりました。その部分から最後まで練習してから、4楽章の冒頭に戻り、278小節目までを練習しました。395小節目、第一バイオリンは適当なタイミングで音を変わっていたのですが、そうするとカウントして入っている第二バイオリンの八分音符と合わなかったので、第一バイオリンはきちんと数えて音を変わるようにしました(←当たり前。。)。610小節目からは第一バイオリンの音程合わせをしました。時間が少なくなり、第1楽章か第2楽章どちらかしか練習できなくなりました。第2楽章を通すことにして通し始めたのですが、最後まで行く前に、練習場所の終了の音楽が鳴ってしまい、最後まで練習できませんでした。次回は先生練です。個人練習、頑張りましょう!
April 5, 2008
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪『久保史緒里*卒業コンサ…
- (2025-11-27 21:54:21)
-
-
-

- 洋楽
- ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・…
- (2025-11-25 04:17:42)
-
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-