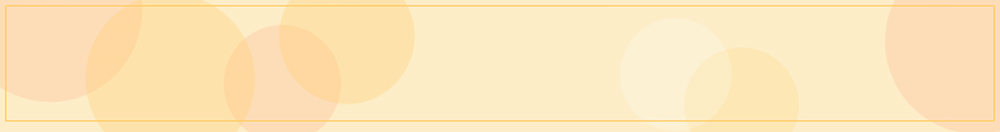2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年03月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
ブラームス弦5 9回目:初めての先生練習
弦5初めての先生練でした。午前・午後と場所をとり、午前は5人で練習し、午後は先生に見ていただきました。午前中は、久々に5人が揃った(27日ぶり!)ので、1楽章から3楽章まで流しました。そして、出だしのテンポなど、気になったところを調整しました。3楽章はまだ練習不足という感が強かったので、今日の先生練は1・2楽章を中心にしようということになりました。近くの公園でのんびりお昼を食べた後、いよいよ先生練習です。弦5はやはりビオラの曲ということで、第2ビオラがレッスンについているビオラの先生に見ていただくことにしました。まず、1楽章を流した後、以下の箇所をやりました。練習番号1から46小節目までと、再現部の同じ部分である練習番号7から8をやりました。先生曰く「プロでも難しいポイント」だそうで、34小節目以降(161小節目以降)のシンコペーションで崩れやすいそうです。33小節目(160小節目)の付点のリズムは、特に強調した方がいいようで、ボーイングをПП∨∨ПП∨∨としていましたが、ПП∨П∨П∨…を勧められました。また、42小節目(169小節目)~は第2バイオリンと第2ビオラとチェロのハーモニーが主役とのことで、音程とバランスを調整しました。33小節目~と同じく、全体的にこの楽章はリズミックなところはリズムを強調した方がいいとのことです。例えば、冒頭からは朗々としたメロディーが流れますが、22小節目で一変してスタッカートな音楽に変わります。この手前まではレガートで、22小節目からリズムを強調するように、付点をきつめに演奏すると、めりはりがついてとてもよくなりました。譜面を見ていると、たまに同じ音形が続くところなどスタッカートの指示が省略される場合がありますが、ブラームスの場合は、アーティキュレーションはすべて譜面に書いてあるそうです。そのため、スタッカートの有無は譜面に書いてあるとおりにしなさいとのことでした。Piu moderatoからがうまくないと指摘されました。ここは、メロディー以外のハーモニーが重要なところで、不安げな和音から解決の和音への移行がうまくいっていませんでした。そのため、第1バイオリンが抜けて、4本で音程を合わせていきました。 次いで、3楽章をやりました。「3楽章は先生に聴いていただける状態じゃないんです…」と説明しましたが、容赦なく(笑)「とにかく、弾いみて」と。ゆっくりめのテンポで流していきました。まず、「とにかくenergicoに!」とのこと。冒頭の第1ビオラから始まる8分音符のフレーズは、何もないところはデタッシェで、スタッカートがあるところはoff(飛ばし弓で)とのことでした。50小節目からのsubit pは効かせた方がいいとのことでしたが、その直前までがクレッシェンドで激しく弾いているところなので、なかなか難しいです。また、練習番号4番は、第2バイオリンのアウフタクトの入りが難しいようで、何度も練習しました。アウフタクトの直前は3連のリズムで、3連から2連へのカウントの切替えが難しいのと、譜面も書かれ方が間違えやすいためのようです。要注意ポイントです。最後に2楽章をやりました。冒頭メロディーの3拍目の3連音符は、すべてアップにした方がいいとのことでした。弓順の都合に妥協せず、弾きたい弓で弾いた方がいいとのことです。「ヨーヨーマなんてそうだろ?」と。最後のTempoIの、173小節目や175小節目のsfをダウンにもっていけるよう、弓順を変更しました。休憩後、再び1楽章に戻り、流しました。全体的に、内声と低音、つまり、第2バイオリン、第2ビオラ、チェロに対する指摘が多かったです。やはり、ブラームスは厚みのあるハーモニーが特徴的だと思いますが、ここから作っていくものなのかもしれません。また、これまで一緒に練習する機会が少なく、また内声で音程がとりづらいためか、全体的に第2バイオリンの音程への指摘が多かったように思います。先生のレッスンは、こと細かく指摘された訳ではなく、いくつかアドバイスいただいただけだったのですが、それだけで5人の演奏が変わり、今までは譜面の音を出すだけで精一杯だったのが、全体的に曲らしくなり、大きく飛躍した感じでした。何が変わったかはみんなわからないのですが…。5人とも大満足でした。ただ、最後に先生から、「音程とリズムをちゃんと弾いてね」と一言いただきました。次回は、先生練習の復習と、音程とリズムの確認です。(Vn:K.N.記)
March 30, 2008
コメント(0)
-
死と乙女の4人での練習4回目
朝9時から練習でした。いつも一番到着の遅いチェリストが、今日は一番乗りでした。珍しいと思っていたら…。今日はまだ弾くことに慣れていない3、4楽章を重点的に練習してから、1、2楽章を練習することにしました。まずは3楽章。Scherzo のテンポを決めました。だいたい1小節=90 程度。慣れるためにこのテンポで何度か繰り返し練習しました。Trio も今までより少しテンポアップしました。29小節目の rit. を合わせ、その後 33 小節目で a tempo に戻すことにしました。また、気になる部分の音程も合わせていきました。次に4楽章。こちらもテンポを決めました。付点四分音符=168 程度。133 小節目からや 174 小節目からは、メロディが伸びやすいとのことでしたが、気持ちよく弾いてしまうというよりも、八分音符に合わせようとして遅くなってしまっているのが原因のようでした。八分音符をなんとなく聴くようにして演奏すると、伸びることはなくなりました。278 ~ 308 小節目は、どのパートも休符を数えるのを間違いやすく、ちょっとした難所になっています。何度やってもうまくいかず、第2バイオリンがうまく入れていないようでした。ビオラが弾くのをやめて、スコアを見ながら確認すると…。実は第2バイオリンではなく、チェロが1拍多く休んでいたため、第2バイオリンの入りが間違っているように感じていました。原因が判明したので次はうまくいくと思ったのですが、1拍多く休むのに慣れてしまったようで、この場所は次回練習へ繰り越しとなりました。Prestissimo の速さは限界に挑戦です。741 小節目から、チェロはリズム的にどんどん速くしたくなるようなので、他の3人は頑張らないといけません。ここで一旦休憩にすると、チェリストが、「すみません、次回練習出られません…」とのこと。次回練習の次は先生練なんですけど…。「この度結婚することになり、次回練習日が両家の初顔合わせになってしまいました…」とのことでした。おめでとうございます。ということで休憩なんかしていられないので、練習することに。2楽章は主に音程合わせです。テーマの音程をゆっくり合わせていきました。第1バリエーションのバイオリンの練習、第2バリエーションのチェロの練習、第4バリエーションでバイオリンの練習をしました。また、最後の 153 小節目以降も、音程合わせをしました。最後に、1楽章のテンポ変化の確認をしました。やはり、次回練習の代替が必要だろうということで、日程合わせをして、練習場所確保に動くことになりました。先生練(4/20)の前に、4人揃って練習することができるでしょうか…?(Vn: T.Y.)
March 23, 2008
コメント(0)
-
アメリカ(木五編):我ら木5合唱団
どうも!アメリカ木5合唱団です。本日は、オーボエ奏者の森先生に歌のレッスンをして頂きました。というのは、冗談で。(ドテッ)呼吸・息のスピード・発音・響き・フレーズの渡し方などを、楽器を吹かずに口で歌うことで意識改善を行う指導内容です。口で歌った時の、顔の向きは?腹部の状態は?楽器を持ったとき、状態が変わってしまっていないか?要は、楽器という媒体がある場合でも、いかに自然にリラックスして演奏できるかなのです。今回は1楽章を重点的に見ていただきましたが、この歌の指導による『Before⇒After』は如何に!?◆ミュージカル「タラララ・ラ~ンラ・ラン!」オーボエとフルートの掛け合いについて。私たちはミュージカルのように、身振り手振り交えながら歌いました。スッ(息を吸う)「タラララ・ラ~ンラ・ラン!」(手を振り上げながら)まるで、「タララ・・」と会話をしているように。なんということでしょう。今までは、ただ交互に吹いていただけだったのが、一つの音楽に聴こえてきます。◆浮かび上がるファゴット他のパートが音符を刻んでいる中でのファゴットの旋律について。体をリラックスして「あー」と発声。もっともやわらかく声が伸びる感覚をつかむ。なんということでしょう。今までは、音量を出しても聴こえづらかった旋律が、音量関係なく、浮かび上がって聴こえてきました。リードの振動もあまり聞こえません。◆犬になったフルート4分音符のアクセントの奏法について。大きな声を出した時の体の状態をつかむために、「ワン!ワン!ワン!ワン!」と犬のように吠えました。この息の状態・腹部の状態と同じように、楽器で吹いてみました。すると、なんということでしょう。今まで、ふわっとした感じだったのが、エネルギッシュなアクセントに変わりました。匠の技が光ります。その他、冒頭の16分音符の意識の仕方、フレーズを伸びやかに歌う奏法、リズムパートの奏法、リタルダンドの位置、などなど、たくさんのアドバイスを頂きました。最後の5分間、3楽章の冒頭だけ見ていただき時間切れ。大変、意義のある時間でした。森先生、ありがとうございました。次回の練習は約1ヵ月後で、2回目の先生練です。残りの2,3,4楽章を見ていただく予定です。*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*今回は『アメリカ(木管五重奏編曲)』コラムはお休みです。筆者な気まぐれによるものなので。。。K.I(FL)
March 22, 2008
コメント(0)
-
死と乙女の先生練習1回目
今日は、七澤清貴先生にみていただきました。1楽章から順にみていただきました。1,2楽章は練習が進んでいたのですが、3,4楽章はあまり練習が進んでいなかったので、1,2 楽章を中心にみていただきました。最初に、1楽章を通しました。意外に音程は全体的にいいとのことでした。冒頭はどの楽器も開放弦が入った和音なので、音程は合いやすいです。5小節目からの第1バイオリンの音程が外れると目立つので、要注意です。7小節目、11小節目は、「D線で」と言われたのですが、音程に自信がなくA線を主張すると「A線でもD線ぽく」と。頑張ってD線で弾くかもしれません。14小節目のフェルマータは、音が動く第2バイオリンに他の楽器が合わせると合わせやすいとのことでした。25小節目のsubit pの入りは、内声の3連符にメロディが合わせた方がうまくいきそうでした。62小節目からの第2主題は、メロディはビブラートをよくかけて。ここからビオラの三連符は、前半の動きがない10小節間は淡々と演奏して、後半の動きが出てきたところは、だんだんと前に行く感じで演奏すると、メロディとしっくりいくことが分かりました。83小節目からの第1バイオリンの16分音符は、遅くならないように気をつけて。ビオラとチェロも遅れがちになるので気をつけること。102小節の直前の第1バイオリンは、思い切りルバートかけてもOK。弾きやすいように。141小節目の第2バイオリン、C の音程気をつけて。145小節目の第1バイオリン、Gis の音にビブラート。163小節目から、第1バイオリンとしてはゆっくり弾きたくなるのですが、チェロはなるべくインテンポで弾きたいようです。この曲は、こういった軋みが他にもたくさん出てきて、メロディは制限を受けながら演奏する部分が多くあります。187小節目アウフタクトから、チェロがゆっくりになり、だんだん速くして198小節目の再現部で冒頭のテンポになるのが理想です。178小節目のビオラである程度テンポを戻してしまうという手もありますが、私たちは、再現部に向けてだんだん速くしていくことにしました。しかし、再現部に達しても、テンポは元に戻りません。でも、再現部自体が省略されて短くなっているので、冒頭よりもテンポが落ちていても長くは感じないとのことでした。197小節目の入りは、チェロの移弦を見て入ると合わせやすくなりました。299小節目からは、白玉の音符はなるべく音を切らないようにとのことでした。300小節目の第2バイオリンとビオラは、2小節の休みをカウントするだけではなく、チェロのロングトーンが充分 p になるのを待って入る。328小節目の第1バイオリンの b の音は、小指ではなく薬指で押さえていい音でビブラートをかけて。2楽章も一通り通しました。1楽章と比べると、音程に難あり、でした。まずはテーマで音程合わせをしました。第1変奏では、第1バイオリンの音程が重要とのことでした。長い音符は必ずビブラート、付点三連符(?) にもビブラート、でした。第2変奏では、チェロの音程重要です。「死ぬ気で」と言われてました。第3変奏の後半の前半(81小節目から)は、内声(第2バイオリンとビオラ)がメロディだと思っていたので、第1バイオリンは遠慮して弾いていたのですが、「もっとしっかり弾くように」言われました。第4変奏は、第1変奏同様、第1バイオリンの音程が重要とのことでした。2楽章はちょっと時間切れの感がありましたが、3楽章へ。これも、一通り通しました。Trio は、内声の、付点四部音符-八分音符-四分音符、のリズムを聴くように、とのことでした。4楽章も、一通り通しました。ゆっくり目のテンポでした。まだ、弾きこなしていないので、練習方法を教わりました。冒頭のパターンは、弓の場所を4人で揃えると良いとのことで、その練習をしました。次回の先生練習までに、1楽章はテンポの変化を、2楽章は音程、3・4楽章は慣れとテンポアップが課題です。(Vn: T.Y.)
March 9, 2008
コメント(0)
-

アメリカ(木五編):オールマイティなClの定めか?なんでもやりまっせ!
本日は、Obが体調不良でお休み。4本での練習となりました。次は先生練で1楽章と3楽章を見ていただく予定なので、その楽章を主に練習しました。さて、第3回目の練習内容■3楽章テンポを落としてメトロノームで合わせる。8小節ごとのフレーズがほとんどですが、次のフレーズの頭が遅れがちです。原因は、・前のフレーズの後半で遅くなる。・次のフレーズの1拍目の反応が遅い。とにかく体に覚えさせようと、同じ箇所を繰り返し練習。そして、リズムの掛け合いが曖昧。ほとんどのリズムが八分音符の組み合わせなので、1拍目から入るリズムのパートと2拍目からのパートが正確に組み合わさるように意識する。大抵は、2拍目から入るパートが遅れがち。それを正確な位置に修正すると、まるでこだまのように響いてきます。この感覚を忘れないようにしましょう。実はこの3楽章、オリジナルの弦楽四重奏より短い。オリジナルにはコーダらしきものがあるが、木管五重奏編にはない。■2楽章・4楽章通しただけ。■1楽章旋律と、リズムパートのコントラストをつけるため、旋律のレガートを活かすように、リズムは音を硬めに演奏してみました。molto rit. → in tempo が随所に出てくるので、イメージを統一する作業をしました。ということで、時間切れ。ふぅ。やればやるほど、難しいと感じてしまいます。思えば、選曲会議の時にはじめてアメリカを演奏したときは楽しかった。何も知らなかった、あの頃が懐かしい(←遠い目)■録音を聴いてみて気になった点・音が溶け合っていない。5種類の異なる音質を持つ楽器ではあるが、編曲はそれを活かしたものにしている。ところが、楽器が入れ替わる度にボコボコしてしまっている。傾向としては、リード楽器に対してのフルートとホルン。リード楽器は割りと音がダーク(Obは明るいが)で締まって輪郭がはっきり聴こえるが、それに比べてフルートとホルンは、明るく開放的。この特徴を理解した上で、もっと芯のある音を出さないと浮いて聴こえます。・ファゴットの旋律が埋もれてしまっているファゴットの高音部の旋律の箇所は、他の楽器は1~2段階音量を落とす必要がありそう。ちなみに、低音のリズムは良く聴こえる。・音程やリズムの乱れが目立ちやすい弦楽四重奏のスコアを見て気づいたのが、もともと一つの楽器で一つのフレーズを演奏するところを二つの管を組み合わせたりしている。だから、ちょっとでも音程やリズムが乱れると目立ちます。問題山積みです。*-*-*-*-*-*-*-*さて、連載『アメリカ(木管五重奏編曲)』コラム(←いつまで続く?)「オールマイティなClの定めか?なんでもやりまっせ!」アメリカでのクラリネットは忙しい。散々細かいパッセージを吹かされる合間に、2ndVnのオブリガードが急に出てきたり、また、1stVnの旋律があったり。 ◆ネットで、面白い記事を発見------ モラゲス木管五重奏団のパスカル・モラゲス(Cl)さんとデビッド・ワルター(Ob)さんのクインテット談義です。※ワルターさんは、今回使用するアメリカ木管五重奏編曲をした人です。 ワルター:「クインテットで演奏したときの音のイメージが、おのずと私の頭に浮かんでくるんですよ(笑)。ええ、弦楽四重奏の譜面 を見たときに‥‥。音出しをしてみて、細かいところを手直しすることはもちろんですが。」 ↑さすがですね。だから、オリジナルの弦楽四重奏と比較してかなりシャッフルされているんですね。そういえば、ファゴット奏者が「Vnパートの音を見つけた!」といってました。 ワルター:「パスカルは何でも吹けてしまうので、「これは難しい」と思ったパッセージは、クラリネットに担当させれば大丈夫なんです(笑)。 」モラゲス:「‥‥(苦笑)。」 ↑これです。パスカルさんがすごいというのもありますが、オールマイティなクラの定めとも言える。--------------------------------クラリネットは、音域が広い。さらに、どの音域でも強弱のニュアンスをつけられる楽器です。ちょっと、各管の音域比較をしてみました。 ※ClはB♭管クラリネットそう言えば、フルートの低音域とのコラボが多い。(今、気づきました)前回演奏した、ミヨー「ルネ王の暖炉」でもコラボしました。ホルンやオーボエは大変だけど、クラリネットは弱く吹くぶんにはまったく問題ない楽器だからでしょうね。ということで、いろんなところで起用される楽器。大変だけど、がんばれクラさん!次回、「どうする?魅惑のピツィカート!?」をお楽しみに!(クドイようですが、未定です) K.I(FL)
March 9, 2008
コメント(0)
-
フルート四重奏の練習7回目
今日の練習は、前回の七澤先生練を踏まえて音程を合わせました。テーマ冒頭の音程からはじめました。ヴィオラのEをまず正確にとってから、チェロ・ヴァイオリンの順に合わせていきました。ヴィオラがEを取るときにヴァイオリンが開放のEを弾くと指標にできて音程が取りやすくなるようです。その後の練習も、組み合わせとしては最初にヴィオラ・チェロで合わせ、次にヴァイオリン、フルートの順に加わっていきました。ただヴィオラ・チェロで合わせるのにすごく時間がかかったので、フルートの出番は練習を始めて約1時間後でした。。ヴァリエーションでも、それぞれメインの楽器を除いた3パートで音程を合わせ、メインパートを加える、という方針で練習しました。1楽章をじっくりと全部、2楽章をさわりだけ練習しました。次回までこの感覚が残っていて欲しいです。チェロは音程がきちんと取れてない部分がけっこう多く、原因はポジショニングだったり、指を弦から大きく離してしまったりすることだったりします。できればどれかひとつでも改善して本番に望めればなぁと思っています。(Vc: Y.M.記)
March 8, 2008
コメント(0)
-
ブラームス弦5 第7回練習
1か月以上ぶりの、5人そろっての練習でした。そのため、全楽章やることにし、最も時間がかかりそうな2楽章からとりかかりました。ところが...死と乙女の第一バイオリンにも客観的に聴いてもらいながら進めたのですが、2楽章の冒頭から音程を中心にとひっかかってしまい、Grave ed appassionato(1~31小節目)だけで1時間弱かかってしまいました...。(練習時間は3時間弱)これまでに感じていたことではありますが、2楽章は非常に難しい曲です。死と乙女の第一バイオリンにも、「客観的に聴いていてもなかなかわかりづらい。弾いてたらなおさらわからないでしょう。」と言われました。何が難しいかというと、まず音程が難しいです。シャープが4つの上に、臨時記号が多く、また、5本の楽器の和音も複雑で、自分たちで弾いていてもよくわからなってしまいます。しかも、音程が難しい部分で、基準になる音のパートを見つけづらいときています。(他のパートはその基準のパートの音程に合わせます)音程も難しければ、リズムや動きも複雑で入り組んでいることが多く、場所によってはメロディーラインがどのパートか判断しかねます。結局、今日は2楽章に3時間半かけて、練習終了。でも、客観的に聴いて指摘してもらったおかげで、練習開始時点と比べれば、少しすっきりしてきた気がします。死と乙女の第一バイオリンさん、どうもありがとうございました♪=今日主に練習した内容=Grave ed appassionato(1~31小節目)冒頭メロディーの音程(第2ビオラを基準に!周りは音量控え目で。)9小節目の3連の音程Allegretto Vivace(32~79小節目)付点のリズムの16分をもっとしっかり弾く。ppとpの差をつける(かなりpは思い切りよく弾く。次のmfが実際にはffになるぐらいの勢いで。)leggeloの弾き方はよくわからない・・・→先生に聞く。第1&第2バイオリンの掛け合いを確認。TempoI(80~116小節目)95~のagitatoをどうするか?テンポは速めたくないので、あまりやらない?また、Va以下のメロディーの核がどのパートなのかよくわからなかったが、第2ビオラのよう。第2ビオラが聞こえる音量で弾くと、とてもすっきりきこえた。Presto(117~163小節目)122小節目~の第2バイオリン。出だしを勘違いしていたので、確認。150小節目~の第2バイオリンとVa2本の8分音符の音程と弓順の調整。TempoI(164小節目~最後)4連+3連の感じ方。前回2楽章をやったときは7連ととらえた方が流れるということだったが、今回やってみると4連と3連に分けて感じた方がよさそうだった。(Vn:K.N.記)
March 2, 2008
コメント(0)
-
死と乙女の4人での練習3回目
今日は4人揃っての練習でした。まずは、前回練習した3・4楽章の復習をしました。3楽章の Trio は、なんとなくメロディを弾くと、オブリガートに合わせようとしてしまうようです。普段、細かい音が聞こえると、無意識に合わせようとしてしまうようです。メロディを弾く人は、なんとなくオブリガートを聴いて、合わせようとはせず、合っているなぁ、というくらいの感覚で演奏するといいようです。オブリガートは、メロディよりも細かい音を弾いてますが、大きい単位でメロディに合わせて弾くようにしました。4楽章は、少しテンポを落として練習しました。まだ弾き慣れていない部分が多く、慣れる練習という感じが強かったです。それでも、「タイミングを合わせるポイント」を確認しながら進めていきました。278小節目からの再現部の手前の部分は、入りがなかなか合わず、苦労しました。次々回へ持ち越しとなりました。何とか最後まで練習して、1楽章に戻りました。1楽章も、タイミングを合わせるポイントを確認していきました。ピカルディの3度さんのシューベルト: 弦楽四重奏曲第14番 d D810「死と乙女」(その2)の譜例の「七つの違い」ですが(私たちの譜面はベーレンライターなので若干譜面が違うのですが)、を上段のメロディは、アウフタクトの八分音符の長さを左手でコントロールし、1拍めのアクセントをビブラートを指で表現して、アクセントの部分がスラーの山の頂上にして弾くようにしました。下段は、メロディのアクセントの部分をチェロのアクセントと一緒にあわせて弾くようにして、上段とは弾き方を変えました。実はこれは、私の個人レッスンでヴァイオリンの先生に教えてもらったことの受け売りです。。2楽章も、復習をかねて全部を通しました。その後、第1変奏と第2変奏のテンポを確認しました。最後の変奏の、スタッカートの飛ばし具合や最後、どのようにゆっくりしていくかなども相談していきました。次回は先生練習です。当初は全楽章見ていただく予定でしたが、1・2楽章中心に見ていただくことにしようと思います。(Vn: T.Y.記)
March 2, 2008
コメント(1)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- LIVEに行って来ました♪
- サーカスパフォーマーまおのライブ
- (2025-11-23 13:17:54)
-
-
-

- 吹奏楽
- ちくたくミュージッククラブ7thコ…
- (2025-11-22 23:43:42)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-