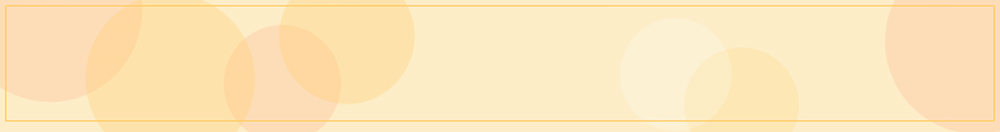2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年05月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
第4回演奏会御礼
あいにくの雨でしたが、それでも200人近い方にご来場いただき、誠にありがとうございました。また、たくさんのアンケートへの記入、どうもありがとうございました。いろいろありましたが、一人でも多くのお客さまにご満足いただけたなら幸いです。また来年も頑張りたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 (代表 記)
May 24, 2008
コメント(0)
-
ブラームス弦5 ホール練習
ホール練習では、本当は、お互いの団体のホールでの演奏を聴き合い、アンケートにまずい点や感想を書き、それを演奏にフィードバックすることにしているのですが、今回、弦5は全員揃っての練習時間が十分にとれていないため、特別に他の団体がリハーサル中に、別な場所で練習させてもらいました。別室での練習前回1楽章を密度濃く練習したので、2・3楽章をメインにやりました。3楽章途中で落ちる危険があったので、1回流して、気になった部分をあとから返してやりました。ユニゾンで音階を駆け上がるところの音程や、練習番号4の入り(入りのタイミングを間違えやすい)、早くて音も跳躍して大変な部分をテンポを落として確認するなどしました。2楽章出だしが重要かつ難しいので、1楽章の終りから続けて冒頭を弾く練習を繰り返しました。また、いつもどうしても縦の線が合わないような箇所、崩壊しやるい箇所などをピックアップして練習しました。ホールでのリハーサルまず、音量バランスをみてもらうために、1楽章の冒頭(全体的な音量バランスと自分たちの響きの確認)2楽章の冒頭(チェロのメロディーと周りの楽器のバランス)を弾きました。今回の配置は、チェロを中央に、客席に向かって右手にヴァイオリン2本、左手にヴィオラ2本としています。舞台上で弾いてみると、ヴァイオリンとヴィオラの位置はお互いの音があまりに聴こえなくて、驚くとともに少々不安を覚えました...。本番、お客さんが入れば、多少音の発散は抑えられるかもしれませんが...。音量のバランスは、第2ヴァイオリン、第1&第2ヴィオラの中間の音域の3本がもっと出した方がいいとのことでした。2楽章の冒頭のバランスは、割とよかったみたいです。そのあと、全楽章を通しました。通してみると、いろいろと事故(落ちる、入りを間違えるなど)が起こりました。これまでに5人揃っての練習がなかなかできなかったことがその一因なのだろうと思います。2楽章は、しっとりと歌う部分のフレーズの入りや終わりは5人で呼吸を合わせることができ、以前よりもまとまった感じがしました。しかし一方で、盛り上がって音量が出てくると、お互いの音が聴こえないために、第1ヴァイオリンと第1ヴィオラで派手にずれてしまうという一面もあり、注意しながら演奏しないといけません。次回はいよいよ本番です。当日の練習で、落ちたり入りを間違えやすい箇所を再度確認しておく必要がありそうです。(Vn:K.N.記)
May 18, 2008
コメント(0)
-
死と乙女のホールでの練習
夜は、ウィーンホールでの練習でした。最初に気になる部分のバランスをチェックして、その後通しました。4人で和音を作るところが、チェロが同時か遅れ気味になっているので、チェロを先に出る感じにしたほうがよさそうです。アクセントのつけかたが、比較すると、ヴァイオリンの方が低弦よりも鋭い感じなので、統一する必要がありそうです。全体的に、合わせるポイントを再確認する必要がありそうです。ウィーンホールはとても響くので、中低弦の細かい動きはもっとクリアにしたほうが良いようです。ただ、本番はお客さんが入って響きが減るので、そこら辺を考慮する必要があります。。和音(重音)の音程確認が必要です。第1ヴァイオリンは外してはいけない音を3箇所ほど外したので、練習が必要です。。4楽章のテンポが、冒頭に比べて再現部が落ちているので、統一が必要です。演奏会前のリハーサルでチェックする予定です。(Vn: T.Y. 記)
May 18, 2008
コメント(0)
-
死と乙女の4人での練習8回目
今日は午後練習室で練習をして、夜はホールで練習です。京王線が不発弾処理で止まっていたため、2人遅刻して、45分ほど遅れての練習開始でした。3楽章:SCHERZO で転ばないように練習しました。冒頭のアウフタクトのタイの音の次の四分音符二つがつまってしまうことがあるようなので、つまってしまわないように意識するようにしました。TRIO の入りのテンポをもう一度確認しました。4楽章:冒頭のテンポと最後の Prestissimo のテンポを確認しました。133小節目からなどの、一方のヴァイオリンが八分音符で刻み、もう一方が長いフレーズのメロディーを演奏するパターンについて、これまでは、2本のヴァイオリンだけに注目して合わせるようにしてきていましたが、ヴィオラやチェロの、音の変わり目や、四分音符+八分音符+延ばしの音のリズムをヴァイオリンの八分音符に合わせるようにすると、もう一方のメロディのヴァイオリンがとても弾きやすくなることが分かりました。282小節目からのそれぞれの楽器が交互に入る場所ですが、チェロがまたはまってしまいました。これまで、数えて入るようにしていたのを、他のパートを聴いて入るように研究したようですが、うまくいかないようです。何度も練習するうちに、ヴィオラやヴァイオリンの他の人も間違えるようになり、どつぼにはまりそうになってしまいました。。結局、全員きちんと数えながら、メロディも頭に入れて演奏するようにして、なんとか脱出しました。第1ヴァイオリンの音が飛ぶ部分を、何箇所か練習しました。1楽章:15小節目からのテンポの確認をしました。72小節目からの2つのヴァイオリンのメロディの音程合わせをしました。240小節目で少しテンポが緩む場所の確認をしました。2楽章:第2変奏のテンポの確認をもう一度行いました。第3変奏の第1ヴァイオリンの16分音符が、pp のときに少しきつく、チェロのメロディの流れを阻害しているとのことで、チェロの流れを邪魔しないように、柔らかく演奏するようにしました。この後、ホール練習で通すことになっているので、午後の練習では通さないことにしました。(Vn: T.Y. 記)
May 18, 2008
コメント(0)
-
フルート四重奏の練習ホールリハーサル
ホールでのリハーサルでした。他の曲の演奏者が客席でバランスなどを聴いてくれました。フルート、ヴァイオリンの響きは良く、ヴィオラはもう少し音量を出してもよさそうです。チェロは、音の立ち上がりがよくないようなので、発音をしっかりするように心がけます。本番、頑張りましょう!(Vc: Y.M. 記)
May 18, 2008
コメント(0)
-

アメリカ(木五編):ホール練習、そしてモラゲス風スタイル
いよいよ本番1週間前、本日はホール練習です。ここで、最終的な音のバランスを確認します。 木管五重奏の場合、管によって性質が異なるため、ホールでのバランス確認はとても重要です。ホルンはベルが後ろ向きになっているので、どこに音を反射させるか壁探し。ファゴットは筒が上に向いているので、ステージ上と客席に聴こえるギャップを計算。フルートは音が響きすぎて生音が聴こえづらく、音の長さ・タンギングの調整に苦しむ。オーボエとクラリネットは、、、まぁ問題ないでしょう。※ちなみに、ファゴット奏者、ホルン奏者、クラリネット奏者は楽器を新調(アップグレード)!ホールの響きを堪能するお三方です。 会場となる府中の森ウィーンホールならではですが、まるでお風呂の中で吹いている状態は、戸惑います。さらに、客席に人が入った状態だと響きが変わってきますので、最後まで柔軟な姿勢で演奏していくことが大切です。 今回の演奏会のための練習回数は、全部で7回。正直、練習回数が足りなくて、まだまだ研究が必要という状態ではありますが、限りある時間の中で精一杯練習したのではないかと思います。ここまで一緒にアンサンブルをしてきたメンバーに感謝!本番は、愛情をもって、支え、支えられ、いい音楽を表現できたらと思います。あぁ、じ~んときた。酸欠で死にそうになったのもいい思い出です。 演奏するアメリカ木管五重奏版は、以前にも触れていますが、モラゲス木管五重奏のオーボエ奏者であるワルターさんの編曲のものです。私たちは、モラゲスに敬意を表して「モラゲス風スタイル」で演奏することに!アメリカの譜面の表紙にある黒シャツメンバーの写真をみて、「これで行こう!」と決めました。せめて見た目だけでも、という実に単純な考え。(←おばか?)モラゲス風スタイル?↓オーボエ奏者;「やはり詰め襟じゃないとまずいスか?」「シャツは(ズボンから)出してもいいスか?」と真剣に確認。誰かが「並び方もこのスタイルで行きましょう」と、言い出したり、、最後までふざけた内容ではありますが、これでアメリカ木管五重奏の練習日記は終了です。それでは、本番がんばります!K.I(FL)
May 18, 2008
コメント(2)
-
フルート四重奏の練習12回目
明日はリハーサルなので、実質最後の練習です。今回も、前半弦分奏・後半フルート合流の形で練習しました。1楽章:テーマから音程の確認をしました。ゆっくり弾いて、自分のくせを確認する感じです。第2変奏のヴァイオリンのメロディーとチェロのリズムが合いにくいので、何回か合わせました。第3変奏をやっているところで、フルートが合流しました。その後、全楽章を通してこれまでの復習をして、最後に通しました。(Vc: Y.M. 記)
May 17, 2008
コメント(0)
-
フルート四重奏の練習11回目
前半は弦分奏、途中からフルートが合流しました。前回練習の録音を参考にして気になる部分を合わせていきました。弦分奏3楽章:冒頭のヴィオラとチェロの四分音符の音価を揃えました。チェロの方が短めに弾いていました。2楽章:チェロのフレーズの取り方が短かくて、スラーの切れ目で音が切れてしまっていたのでヴィオラと音の長さのバランスを調整しました。1楽章:テーマから音程重視で順番に合わせていきました。チェロの第4変奏をやっているところでフルートが合流しました。合奏3楽章:メロディーのフレージングを確認しました。メロディーでスラーが切れている部分があるのですが、それを出すようにすると雰囲気が変わりました。また、伴奏の強弱の意識合わせをしました。134小節目から遅くする部分のテンポを確認しました。最後の2小節間の4分音符の長さとタイミングを合わせました。最後に通しました。(Vc: Y.M. 記)
May 11, 2008
コメント(0)
-
ブラームス弦5 第13回練習
第1ヴィオラを除く4人での練習でした。第2ヴァイオリンの旦那さん(ヴァイオリニスト)と、死と乙女の第1ヴァイオリンの2人に聴いてもらいながら進めました。予定では、前回練習した内容を第2ヴァイオリンに伝えながら、1楽章から3楽章まで全部やるつもりだったのですが・・・1楽章から始めたところ、冒頭から練習番号1までのひとかたまりでも、二人の聴衆からいろいろとだめだしやアドヴァイスをされるという具合で、結局のところ、1楽章しかできませんでした。その代わり、大変密度の濃い練習ができたのですが・・・。内容は、冒頭のメロディーをもっと歌った方がいい。リズミカルな部分(付点のリズム)で、リズムを立たせようとするあまり、どっしりしすぎた音楽になっていて、もっと推進力があった方がいい。34小節目~がただ音を並べてるだけに聴こえるので、もっと歌った方がいい。54~56小節目の四分音符の長さが上げ弓と下げ弓で違う。66小節目~付点四分+8分のリズムが、ヴァイオリンと第1ヴィオラの3本と、残りの2本とで互い違いに出てくるところがうまくかみ合わない。→第2ヴィオラとチェロがはっきりめに弾くのと、お互いに聴くようにすることで改善。などなど、自分たちではそうやってるつもりでもそのとおり聴こえてなかったというように、5人だけでの練習ではわからないことをたくさん指摘してもらいました。この曲は、音程にしても縦の線にしても弾きながらだとよくわからないことが多く、5人だけではそこの整理がしきれていないのと、そういった基礎的な部分に時間がかかるのと曲が難しい(複雑に入り組んでいて、時にはどのパートが旋律がわからないような箇所がある)ために、これまで曲想を細やかに作っていくステップになかなか踏み込めなかったことを、とにかく痛感しました。それに加えて、なかなか全員揃っての練習時間がとれないことも、このような結果の原因となってると思われます。あとはホール練習と本番を残すのみです。ちゃんと仕上がるのか不安を覚えますが、頑張るのみです!(Vn:K.N.記)
May 10, 2008
コメント(0)
-
死と乙女の4人での練習7回目
今日は前回の反省から、1・2楽章を中心に練習し、最後に通して演奏しました。1楽章:フレーズの始まる部分で、以前にも「ここは合わせよう」と決めていたところがしばらく練習しないうちに合わなくなってしまったようなので、このような部分を取り出して練習しました。72小節目からの2つのヴァイオリンのメロディの音程がところどころ合わなくなっていたので、音程合わせをしました。84小節目の、流れるメロディから16分音符の刻みに切り替わる部分のテンポ変化を確認しました。123小節目から4小節間がなんとなく停滞する感じだったので、アクセントを活かして停滞感を出さないようにしました。最後の piu mosso のテンポが上がりきらないので、piu mosso のテンポの確認をしました。2楽章:冒頭のテーマのテンポが、前回の通し練習を聴いてみたところ、とても停滞して感じられたので、テンポを上げることにしました。第1変奏のテンポの確認をしました。第5変奏の2括弧(129小節目)から、合わせるポイントをいくつか作りました。133, 137, 139, 141 小節目などです。145小節目からの、第1ヴァイオリンの3連符のメロディのテンポを確認し、143小節目からのテンポ変化の練習をしました。通し練習:今回は、前回と比較すると、先ほどの練習の成果か、1・2楽章共に気合を入れた演奏になったため、4楽章で体力(精神力?)が持たなかったのか、4楽章が崩れてしまいました。3楽章も、前回よりも安定感が崩れてしまいました。1・2楽章で気合を入れすぎるとよくないようです。ペース配分を考えないといけないようです。あるいは、そういった状態になっても崩れないように、もっと弾き込んだほうがいいのかもしれません。(Vn: T.Y. 記)
May 10, 2008
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- クラシック、今日は何の日!?
- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…
- (2024-09-21 22:11:23)
-
-
-

- 楽器について♪
- 2025年冬のハープコンサートのお知ら…
- (2025-11-23 00:18:07)
-
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-