2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2011年06月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

OLYMPUSからM4/3の新型三機種出揃う
ついに出ましたね、OLYMPUSの新型三兄弟がそろい踏みです。上の画像を作る過程で気付いたのですが、E-PL3とE-PM1って、実は縦横のサイズが109.5mm×63.7mmで全く同じなんですね。ネーミングから言っても立ち位置から言っても、てっきりE-PM1の方が一回り小さいはずと思い込んでいたのですが、実際には奥行のみの違い(37.3mmと33.95mm)でした。その差、わずか3.35mm。思った以上に僅差です。全体的に言えることは、かなり気合が入っているな、と。特にガラリと印象が変わったE-PL3を見ていると、どこか煮え切らない雰囲気が見え隠れしていたE-PL2までと違い、何かこう、吹っ切れたものを感じます。それはおそらく、E-三桁機との決別を決め、これからはリソースをM4/3に絞って生き残って行こうという一種の覚悟のようなものが背景にあるのではないかと思われます。久々に、OLYMPUSの本気を見たような気がしました。WEB界隈を見ていると、根っからのM4/3ファンは、対Panasonic比でのスペック競争や、現行機種からどのくらい性能が向上しているか、画期的な新機軸が盛り込まれているかなどに興味津々な様子が伺えますが、僕自身はそこんとこはあまり気になりません。なぜかというと、OLYMPUSくらい技術力の高い会社が、そうそう変な仕事をするわけがないと呑気に構えているから。このへんは、十数年もの間、AF性能の面で長いこと他社の後塵を拝してきたPENTAXのファンを伊達に辛抱強く続けてきたわけではないというか(笑)、よしんば少しくらい差があったとしても、二回りもすれば技術は満足いくレベルまで平均化するという経験則的な確信があるので、ちーとも焦らないのでした。逆に言うと、エンゾーがウザイくらい形状のことをネタにするのは、スペック面と違い、モノの造形はそう簡単に良くなったりしないから。製品の形状には、その会社のポリシーや理念が色濃く反映されるもので、理念は一朝一夕には形成されませんから、なかなか路線が変わりません。そういう意味で、今回大幅にシンプルになったE-PL3と、そこからさらに機能を削ぎ落したE-PM1の登場は、OLYMPUSにとって、きっと良い兆しではないかと思えるのでした。
2011.06.30
コメント(1)
-

とりあえずスルー
このネタは触れるか触れまいか、相当悩みました。RICOHと並ぶエンゾーのご贔屓ブランドであるPENTAXが、大々的に発表した「PENTAX Q」。新マウントを採用し、極小ボディで、レンズラインナップも一気に五本を揃え、やる気満々です。ただ、なんか…盛りあがりに欠けるんですよね(´・ω・`)ショボーン。既にあちらこちらで言われていることですが、嗜好の問題とは言え、あのデザインが、どうにもこうにも、そそられません。「最初はブサイクだと思ってたけど、見慣れた今では可愛く見えるよ!」というのもアリなんですが、出来れば直感的かつ問答無用でハートを鷲掴みにされるような姿を期待していただけに、肩透かし感は否めないというか。都内で行われた新製品発表会での詳しい内容はデジカメWatchに譲るとして。「Q」が生まれてくるまでの流れを要約すると、次のようになります。◯ミラーレス機の登場や低価格化により、購入検討者が急増中。◯しかし本体が大きい・持ち運びにくい・操作が難しいと感じ、踏み切れない。◯一方で、ユーザーは画質の良さやレンズ交換によるメリットにも注目している。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓結論:「素子を小さくしちゃえば、システムを小さく出来るよね!Wow!」…えっ?そうなる?(*_*;PENTAXは、大素子市場で他社フルサイズ機との直接対決を避けて645Dに行きましたので、一応、ニッチ狙いという意味では戦略が終始一貫しています。ただ、エンゾーがコンパクトカメラユーザーから機材のステップアップについて相談された際、彼らの多くはこう希望しました。「そろそろ被写体の前後をボカした写真が撮りたいんだけど、何買えばいい?」こういう根源的なニーズは、時代が変わってもあまり変化がないので、その辺のプライオリティをぶっ飛ばしたこの製品には、どうしても誰得感がつきまといます。もちろん、PENTAXもそこのところは良くわかってますので、「Q」ではハードではなくソフト的にボケ感をコントロールする機能が搭載されているとのこと。後ろボケだけでなく前ボケも作れるそうです。コンパクトカメラならともかく、レンズ交換式のシステムカメラがそんなんでいいのかという話は置いておいて。この点について、実はかなり以前にこのブログで「PENTAXおよびNikonが極小素子のミラーレス機を検討中」という噂話をネタとして取り上げた際、冗談半分で「もし本気でそんな製品を作るとしたら、ボケはボディ内の画像処理で解決するつもりなのでは?」と予想していたのですが、その通りになってしまいました。うへー。このヘボ予想は外れて欲しかったなあ。ポジティブな見方をすれば、パンフォーカスな画作りをしたい時には無類の強さを発揮するシステムという言い方も出来るわけで、解像感の高さにも注力しているとのことなので、この辺に関しては実写サンプルが待たれます。そういえば、この「Q」、なんとマグネシウム筐体を採用しています。国産のミラーレス機でマグネシウムを採用した機種は、現状ではGXRだけです。GXRやGRDのかっちりしたカタマリ感は何物にも代えがたい安心感がありますから、趣味性の高い「Q」にマグネシウムを採用したこと自体は慧眼だと思います。ただし、その代償は小さくなく、価格が小型センサー機とは思えないほど跳ね上がってしまいました。標準レンズ付きキットの予想価格が7万円前後となっています。うーん、高い…。返す返すも、デザインがもう少し何とかならなかったのかと…いや、これ以上は言いますまい(T_T)。P.S.PENTAXは、「Q」とは別にAPS-Cサイズのミラーレス機を秋頃に出すのではないかという噂があります。これが本当なら嬉しいのですが、フランジバックが超長いPENTAXのことなので、またまたマウントを新規開発する必要があり、リソース的に見ても、この噂はホントかいなと疑ってしまうところです。とは言え、あの名機K-5を世に送り出したPENTAXですから、同じ血を引く硬派なデザインに仕立ててもらえれば、非常に魅力的なシステムになると思います。この際、既存のリミテッドレンズのことはさっぱり忘れて、専用設計のソリッドでぺったんこなパンケーキレンズ群を出して欲しいです。そんなカメラをずっと待ってますが、今までのところ「ミラーレス=女子カメ」という構図を逸脱するカメラが出てきていないので、ぜひPENTAXに先陣を切ってもらいたいです。ただし、一眼レフをこよなく愛するエンゾーとしては、心の片隅で、ミラーレスへの傾注がDSLRの衰退と直結してしまったOLYMPUSの徹は踏んで欲しくないなあと思う部分もあり。E-5がどれほど素晴らしく、また松レンズや竹レンズの性能がピカイチであっても、もはやフォーサーズは風前の灯です。世の中が小さいものを求めるのは変えられない動きと言えます。そういう意味では、商業的な成功をおさめるかどうかはともかく、実は「Q」はシステムカメラの未来を占う上でターニングポイントになりうる存在かもしれません。ナチュラルな(ハード由来の)ボケと、画像処理によってもたらされるボケがほとんど見分けが付かなくなり、かつ、高感度域での画質も破綻しないということになった暁には、本当に大きなシステムを用意する必要がなくなるわけで、そう考えると、たまたま今回の「Q」がイロモノ的な存在としてスタートしただけで、5年先には立派なメインストリームとして幅を効かせているコンセプトになっていたりして。手ぶれも歪曲もノイズも当たり前にボディ内で補正がかかり、中級機にまでアートフィルターが入り込んでいる時代ですから、あと一つくらい補正要素が加わったところで、驚くには値しません。そんな未来が喜ばしいかどうかは別にして。
2011.06.25
コメント(8)
-

小ネタ
相変わらず、Facebookの更新に追われてブログまで手が回りません(T_T)。小ネタその1少し前に聞こえてきた、OLYMPUSのE-XXXが復活するって噂はどうなったんでしょうかね。個人的にはE-420のセンサーが大幅に良くなった奴が出たら、ぜひお散歩用に欲しいところなんですが、まず無いだろうなあ。ううう。小ネタその2コシナから、ノクトン35mmF1.2のセカンドバージョンが出るようですね。最短撮影距離を70cmから50cmへと短縮したもので、ミラーレス機でのレンズ遊びがしやすいように改良を加えたものと言えます。新旧ともに7群10枚なので、エレメントに大きな変更があったかどうかは定かではありませんが、最大径こそ変化がないものの、重量で20g、全長では15.8mmも短くなってますので、ひと回り小さくなった印象があります。とは言え、このレンズをライカでしか使わないエンゾーには無用の長物ですし、レンズ遊びのためだけに買い換えるつもりもないので、ぷぁす!小ネタその3新しいレンズを買ってしまいました。てへ。なんなのかは、明日以降で。(おいおい)
2011.06.20
コメント(3)
-
オリンパスも3ライン?
デジカメinfoによれば、まもなくOLYMPUSからミラーレスの新型がリリースされるとのことです。現行のE-PL2&E-P2の体制からE-PM1、E-PL3、E-P3のスリーラインになるとのことです。それぞれの概要は次の通り。E-PM1GF2より小さくGF3より若干大きい。ボディ内手ブレ補整搭載。E-PL3E-PM1より若干幅広く厚い。チルト可能な液晶モニター採用。フラッシュなし。E-P3液晶は固定式、フラッシュ内蔵。ボディはE-P2とほとんど同じになる。SONYやPanasonicがEVF非搭載型のミラーレス機を上下2ラインに分けたのに対し、OLYMPUSは狭いジャンルに3ライン詰め込むことにしたわけですが、ここまで細分化する必要があったんでしょうかね。WEB界隈で、「なんでPanasonicのGやGHに相当するEVF内蔵型が出て来ないんだ」と嘆く声が上がるのも分かる気がします。もっとも、リソースの少ないOLYMPUSとしては、ファインダーが必要な人は(復活の噂もある)E-XXXシリーズに行って欲しいという思惑があるのかもしれません。エンゾー的には、やはり新登場となる最小モデル・E-PM1が気になります。このクラスに手ぶれ補正が入っているのは実用的なので、デザイン次第ではヒットする可能性があります。ただ、ここのところOLYMPUSのミラーレス機は造形・質感の両面で、価格相応の高級感を演出することに成功しているとは言いがたいので、そのへんの課題をどうクリアしてくるかに注目したいと思います。それにしても、E-P3のデザインが、E-P1からほとんど変化なしというのも寂しい話ですね…。まだ現物を見てみるまでは何とも言えませんが。
2011.06.16
コメント(0)
-

ミラーレス一眼の明日はどっちだ
Panasonicから、正式にGF3の発表が行われましたね~。全体的に、エッジを落としてヌルッとした丸みを帯びています。軍艦部の大きな出っ張りといい、このへんの造形は賛否が分かれそうですが、そういう部分とは違うところで、一つ良くなったと感じるところは、意匠がシンプルになったことです。GF2までは、グリップに細いシルバーのプレートでアクセントが入り、ボディ前面にも誇らしげに「FULL HD」の文字がプリントされていましたが、今回のGF3からは、どちらも外されています。G、GF、LXとしつこいくらいこの路線を変えてこなかったPanasonicが、ここに来てようやく少し方針を変えたことは、個人的にはちょっと嬉しいのでした。あともう一歩進めて、金色の「L」マークを諦めてくれたら最高なんですが…それはさすがに無理だろうなあ(^_^;)。一方で操作性の面では、背面・軍艦部ともに、これ以上ボタンは減らせないだろうというくらいシンプルなレイアウトになっています。全面的にタッチパネルを活用する方法論が、いかにもライバルであるNEXそっくりです。ただし、SONYがEVFの無いミラーレス機を最初からNEX-3とNEX-5の2ラインで展開したのに対し、PanasonicはEVF内蔵のGシリーズと無しのGFという分け方をしており、GFそのものにバリエーションがありませんでした。ところがここに来て、Panasonicから「GFシリーズを2つのラインに分割し、プロ~ハイアマチュア(experienced photographers)に狙いを定めたGFを発表する」という公式見解が飛び出しました。ソースはここ。正直、GFは代を重ねるごとにどんどんライトな方向に流れていっており、GF3に至っては、メーカーのプレスリリースページではっきりと「カメラ女子向け」とうたっているくらいなので、エンゾーのようなマニアとは縁が薄くなってきたなあと寂しく感じていたところでした。2ラインになることが事実であれば、GF3で録音マイクがモノラルに戻ってしまったことにも合点が行きます(動画を撮らないエンゾーにはあまり関係ないけど)。ところで、ミラーレスの話になる毎回出てくるのが、ハイエンドミラーレスの落ち着く先はどこなのか?というネタです。いつも話がややこしくなるのは、ミラーレスの定義が表向き「コンデジからのステップアップ層向け」ということになっているから。例えば今回のGF3は忠実にそれを守っていますが、それとは別のラインを増やすとPanasonicが宣言したということは、一眼レフからミラーレスに降りて来たい人たちには、同じものでは訴求しないという結論に至ったのだと思います。つーか、もちろんそんな事は早い時期から分かっていたと思いますが、GFも三代目を数えて、いい感じに市場も育ったことだし、ここらでそろそろ「ステップアップ組」と「ハイアマ組」に細分化しても十分採算取れるんじゃね?という判断が働いているのではないかと思われ。が、ここでちょっとばかり面倒なのが、そういうハイアマチュアが欲しい物はさらに二分しているということ。可能なかぎり小さくしたレンズ交換システム(一眼レフの代替機)が欲しい人と、従来のハイエンドコンデジくらいのボディサイズに、M4/3やAPS-Cくらいの大素子を積んで明るいレンズを搭載した軽快なスナップ機(ハイエンドコンデジの代替機)が欲しい人がいるわけです。そして今のところ、どちらのニーズについても、要求を完璧に満たすものは出てきていません。そういう意味では、GXRは非常に惜しいところをかすめている気がしますが…いや、皆まで言いますまい(T_T)。ともあれ、Panasonicがどこまで思い切った差別化を図るのかが、今から楽しみでもあり、怖くもあります。
2011.06.14
コメント(0)
-
うーむ・・・
SD1のβ機によるサンプル画像がチラホラと上がってきてますね。あんなトコやこんなトコ。β機なので断定は避けますが、過去DPシリーズを使ってきた経験と合わせると、やはり緑の表現が苦手なのかなあと感じました。全体的に、マゼンタかぶりの傾向が見受けられます。インプレでは、銀塩のポジのようだという批評をよく目にしますが、個人的には、むしろネガをスキャンしたもののような印象かも。より正確に言えば、情報の密度感はポジ的、でも発色はネガ的というか。ただし、インプレの言う「ポジ的」という意味の根っこは、むしろ「デジタル臭がしない」というニュアンスなので、その点では全くその通りだと思います。それにしても、ヨドバシのインプレにある、ジャガード織の椅子の質感描写は鳥肌モノです。ローパスレスだとここまで出来るんですね。すげえ。
2011.06.11
コメント(2)
-

NEX-C3
NEX-C3が正式にリリースされました。見た限りでは、正常進化と言えるのではないかと。グリップの形状が、よりホールドしやすい形になっているなど、細かい使い勝手の改良にSONYらしいこだわりが感じられ、好感が持てます。また、天板も樹脂からアルミ素材になったそうで、全体的に初代3よりもチープさが薄らいでいるように感じます。使用電池は同じで、撮影可能枚数が330から400にUP。その代わり?、連射速度は約7枚/秒から約5.5枚/秒にダウン、動画も1,920×1,080から1,280×720へとダウングレードしています。この辺、初代3は上級機の5と遜色なかった部分なので、こういう手法で上級機と差別化を図っていくのだとしたらちょっと残念です。レンズは、相変わらず素っ気ないデザインですね。マウントアダプターを噛ませて色々なレンズを取っ換え引っ換えしてみると分かるのが、やっぱレンズにクビレは必要だな、ということ。一眼レフ用も含め、ソニーのレンズは所有欲を刺激しない寸胴な形状をなんとかしてもらいたいところです。震災の影響もあってか、NEX-7(?)のリリースはもう少し先になりそうですが、C3が初代より丸みを強調してきたので、反対に7はユーザー層を見据えて直線基調なデザインで出てきそうな気がします。P.S.そう言えば、3の後継はC3なのに、5の後継はどうして7なんでしょうね。いや、まだリリース前ですから5後継機種の正式名称は分かりませんが。
2011.06.08
コメント(5)
-

落車
激痛です(T_T)。
2011.06.07
コメント(7)
-

こんなん出ました
既にご存じの方も多いかと思いますが、パナソニックの新型機・GF3の姿が海外のプロモーションビデオを通してリークされました。GF1/GF2と並べてみた感じは、次のとおりです。だいぶ小さくなりましたね。 マウントが軍艦部にめり込んだようなデザインは、NEX-5とも似て非なるものであり、往年の銀塩APS機であるニコン・プロネアSを彷彿とさせます。操作系の大部分をタッチパネルに割り振っているとのことで、GF2に引き続き、軍艦部はツルンとして突起のないデザインとなっています。 WEB界隈では、今のところ7:3から8:2くらいで「ブサイクだ」という意見が大勢を占めているようです。エンゾーはと言うと、GXRやK-5のような直線的なデザインのカメラが好きなので、曲線を多用した今回のGF3は、正直あまり好みではありません。とはいえ、この時期に海外のソースからリーク画像に辿り着くような人は、自覚のあるなしに限らずみんなマニア(笑)ですから、そこがパナソニックの想定する実際の購買層の最も大きい分母であるとは思えません。少なくとも、この不鮮明なGF3の姿を見る限りでは、シリーズ中で最も丸っこいカタチになっていますので、今まで以上にカメラ女子寄りに舵を切ったように見えます(くだんのPVでも、女性アーティストに持たせてますしね)。その辺は、ホットシューを切り捨てたところにも現れていて、外付けEVFを始めとするマニアックなドレスアップを考慮に入れていないことが伺えます。ユリシーズ的には、GF1の頃からパナソニック製品用のボディスーツを作る機会を逸してきたわけですが(正直、GF1には作りたかったです)、今回のGF3にケースを製作する可能性は、上のような理由から、今のところ低いような気がします。あ、以下の件に関して質問が多いのでもう一度。現在開発中のボディスーツは、X100・XZ-1・DP1&2(新型)の三種類です。
2011.06.06
コメント(4)
-
クールスキャンやばい
世の中で「ヤバイ」が「それはとてもイイ!」と言う意味で使われるようになってだいぶ経ちますが、今日のネタはフツーにBADな方の話。銀塩を使い続けているモチベーションの一つに、撮影後のスキャンの楽しみがあります。粒状感、階調、雰囲気、どれを取ってもデジタルとは方向性が異なり、それはフィルムでしか味わえないものです。で、エンゾーが長いこと愛用しているフィルムスキャナはニコンの「クールスキャン5000ED」ですが、実は64bitには対応しないことが分かりました。なんですと!?今のところ、つないでいるパソコンの環境は32bitのXPであり、OS的には32bitのVistaまでフォローしているので、まだかろうじて守備範囲です。が、次にパソコンが壊れたときには、もう7にするしかないので、そうなると64bitはもちろん、32bitにしたとしても動作の保証はありません。むむむ、困った。(XPモードで使うという手はありますが、出来れば避けたい)一応、キャノンのフラットベッドスキャナも持っているので、最悪の場合はそちらでやっていくことになると思いますが、フィルム専用スキャナの恩恵は絶大なので、使えなくなるその日が来るのが怖くてたまりません。うーん、こういう事態に追い込まれるのが意外と早かったなあ(-_-;)。まあ、その日が来るまで精一杯楽しむことにします。
2011.06.05
コメント(10)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…
- 🎀✨天板つきスラックスハンガーが優…
- (2025-11-26 13:39:31)
-
-
-
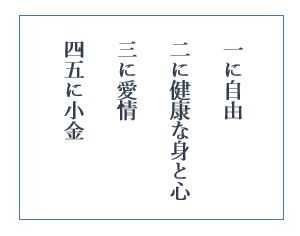
- 日記を短歌で綴ろう
- 〇☆〇この日1日のこと
- (2025-11-25 07:34:20)
-
-
-

- DIY
- 子ども部屋DIY|押入れが“おこもりス…
- (2025-11-25 18:00:05)
-







