2025年08月の記事
全39件 (39件中 1-39件目)
1
-

☆◆☆8月も終わりの花火大会。花火の歌6首
♪ シートから熱砂伝わる海浜の空に半月夕暮れてゆく 昨日は、関東から九州で最高気温35℃以上の猛暑日が続出し、午後5時まででに231地点で猛暑日となった。関東から東海の4地点で最高気温が40℃を超えたらしい。 今夏、全国で40℃以上の酷暑日になったのは8日目で、年間の酷暑日日数としては歴代最多。 名古屋は40℃には届かなかったようだ。知多市では37.6℃までいった。 こんな日に野球の練習と試合があった孫。試合が早く終わったので、花火大会のある新舞子で下りるのをやめて直接我が家へ。市役所前から出るシャトルバスで行くことに。朝倉駅より近く、2分で行ける。 一人で電車に乗れるのが嬉しかったようで、疲れも見せずにご機嫌だった。切符を買って戻る。15分ほど経過。あと900m。 10分ほどで到着。砂浜にシートを広げて場所を確保。孫は早く帰りたいので新舞子から電車で帰ることになり、混雑するので前もって切符を買っておくことに。 そのためには「ファインブリッジ」を往復せねばならない。往復2キロ弱ある。本人はさすがに歩きたくない。しょうがない、私が買いに行くことに。 電車が着くたびに大勢の人が押し出され、橋を渡って来る。この猛暑の中、浴衣を着ている若い娘もけっこういる。 橋の上は片側通行となっていてかなり狭い。そこを逆方向に、すき間を見つけてすり抜けていく。 19時。やや斜め前方の台船の上から打ち上げが始まった。♪ 満開のひまわりの花なき浜にファイヤーフラワーいま咲き始む♪ 金属の色の魔術と制約を秤にかけた花のきらめき♪ 細心の注意払いて花火師は危険操る猛獣使い♪ 煙火消費保安手帳をふところに空に宇宙をひらいてみせる♪ 星を生み星を重ねし大玉の大空高く闇を深めり 大企業の少ない知多市は、協賛も集まりにくい。東海市などに比べると花火の規模は小さい。でもまあ楽しかった。
2025.08.31
コメント(0)
-
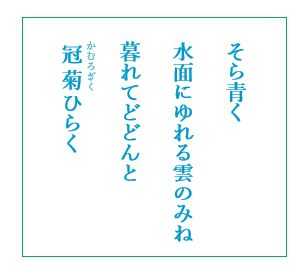
☆◆☆この夏最後の花火大会
♪ そら青く水面にゆれる雲のみね暮れてどどんと冠菊(かむろぎく)ひらく 夕べは気温はそれほどでもなかったが、湿度が高かったようで蒸し暑かった。 最低気温が30℃以上の夜を便宜上、「超熱帯夜」と呼んでいて、今年はまだないが、過去にはけっこう有ったらしく、特に2023年は顕著だったようだ。*8月9日 佐渡市:30.2℃、境港市・松江市:30.1℃、*8月10日 松山市:30.1℃、佐渡市・米子市・松江市:30. 4℃、境港市:30.7℃、上越市:30.8℃*8月11日 東京都:30.4℃ whikipediaより 8月も終わりに近いというのに、今日・明日はトンデモナイ高温予想が出ている。暑さ疲れが出てきそうだ。 でも、前線が近づいていて北海道の太平洋側や東北日本海側では雨が強まるらしい。 来週になると前線や低気圧が北日本付近を通過し、来週中頃には、秋雨前線がゆっくりと本州を南下する予想となっている。 これは “天の恵み” というより “天の罪滅ぼし” の雨だ。 知多市は、雨が降っても微々たるものかもしれない。気温は高いし、蒸し暑いだろう。でも、これで一息つけるのも確か。 知多市は今日、最も遅い時期に花火大会がある。 去年は台風10号の影響で大雨となり、予備日の翌日も雨で中止。予定行事を消化するため、11月2日(土)18時30分から、約30分間に短縮しての打ち上げがあった。インターバルなしで予定の花火を全部打ち上げたのだから、さぞかし見ごたえがあっただろうに、残念ながら行きそこなった。 今日は快晴、2~3m(m/s)の西の風で煙は向こうへ流れていくし、砂浜で見る分には絶好の条件のようだ。 この夏、近隣でも最後の花火大会となるのだろう。規模は小さいが、広い公園があってキッチンガーデンなどもあり、例年、4万2000人ほどが訪れる。 新舞子の駅で孫と待ち合わせ。孫はこの日一日、野球の練習日で半田で試合があたりする。急いで家へ戻って着替えをし、榎戸駅へ自転車で走って電車にのる手筈になっている。 砂浜にビニールシートを敷いて、約1800発:約40分の花火をのんびり見物できる。楽しみだなぁ。冠菊(かむろぎく)
2025.08.30
コメント(0)
-
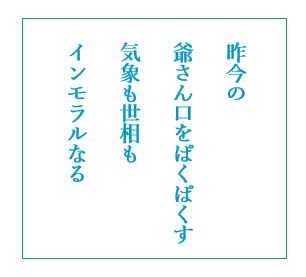
☆◆☆朝のスナップ
♪ 昨今の爺さん口をぱくぱくす気象も世相もインモラルなる 夕べは湿度が低かったのか、深夜になってアランが布団に乗って来た。猫にとっても割りと涼しかったのだろう。私が起きてもまだ夢の中。スタンドを点けても微動だにしなかった。 6時に起床して忘れないうちに先ず、庭の水遣り。うっかり忘れると大変だ。 切り戻した百日紅は満開となっているが、あちこちに種をばら撒いた朝顔が、やっと1本伸びて花をつけていた。 中3日のウォーキング。早朝とはいかず6時半ごろに出た。曇っていて空の写真も期待できない。 朝のうちは良いが、昼過ぎには気温がどんどん上がっていく。今日は36℃の予想だが、明日は40℃に迫る。地獄の釜の蓋が開くらしい。 何時もの右回りコース。いつものように秋葉神社の階段を駆け上がる。一昨日、駅の階段を駆け上がって調子が良かったので、パークロードには出ず、久し振りにダラダラ続く坂を駆け上がってみることに。 460mほどの真っすぐ続く上り坂。半分のところで足が止まった。少し歩いて息継ぎし、残りをなんとか駆け上がった。ヨタヨタと、走ってるんだか歩いてるんだか分からないような走りにならないように、“ももを上げろ、モモをアゲロ” と心の中で呟きながら・・。国土地理院 断面図 最初の部分は左ドッグレッグしているので、ストレート部分だけ。 平らなところは走る気がせず、坂になると駆け上がりたくなる変な性格。少しづつ慣らさないとさすがに無理だ。 ショートカットしたので1時間で戻って来た。アランはまだ布団の上だった。目は覚めているが、涼しかった眠り心地を反芻するような顔でまったりしている。爺ちゃんどこ行ってたの? 息子から預かって管理している「ガジュマル」。元気に葉を伸ばしている。住まいのベランダの環境が悪いのか、葉が茶色くなりかけていた。それが嘘のようだ。 摘心し忘れたバタフライピーはちっとも花が咲かず、遅れて摘心したものの効果なし。この西日しか当たらない場所でも十分だという事は分かった。来年は上手くやりたいが・・。 しかし、種が1莢しか出来ておらず、それがちゃんと芽を出してくれるかどうか。 「冷蔵庫に保管して、秋に撒く」のが基本らしいが、そんな風にはした事がない。どんなものか・・。
2025.08.29
コメント(0)
-
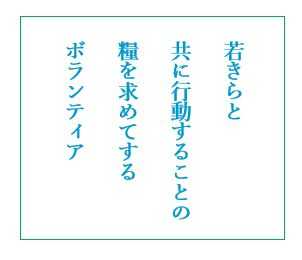
☆◆☆名古屋アジア大会2026のボランティア 採用イベント
♪ 若きらと共に行動することの糧を求めてするボランティア 来年9月19~10月4日に開催されるアジア大会のボランティアの採用イベント、最後の受付があったので参加してきた。 老人の部類に入る私は、来年のことなどどうなるか分からない。予定よりも多くの応募があったということなので、どうしようか迷っていたが、折角の機会なので参加することにした。分からない先のことを心配してもしょうがない。希望したのは吹上ホールの午後の部。 申込時に与えられたID(5桁の数字)と本人確認書類(免許証)で受付登録し、三つのカテゴリーに分けられた席へ。 大会の説明とあらましのスケジュールなどの説明を受ける。 大会の呼称は「愛知名古屋2026大会」とする。第1回はインド・ニューデリーで始まり、日本は第20回となる今回が2度目の参加。45の国と地域、41競技に1,500人の参加者。 9月下旬に採用が確定すると、共通研修があり(スマかPCを使って自宅でする)、役割が来年2月に決まればその研修がある。その間に、不定期で演習大会や交流会がある。 この日は、交流を深めるという事でちょっとしたゲームをやった。椅子席2列が一組となり、籠の中のゴールやプラスチックのハート形や星形のおもちゃを、片手に箸を1本持って、協同して外の袋に移すというもの。タイムスケジュールがあって、司会者の指示に従ってやっていく。 先ずはグループごとに4分間の自己紹介。最年長の私が口火を切った。グループは7人で、私の他は女性ばかり。マレーシアとフィリピン人がいて、名古屋ウィメンズマラソンに参加経験のある人が2人いた。2分の作戦タイムがあり、4分のゲームをする。4つを袋に入れることが出来た。 2回戦目も同じように行って合計数を競うわけだが、2回目は〇。 結果は最高が6個で4個は2番(複数組)という事になった。1~2個しか出来なかったグループもあったようなので、チームワークは良かったわけだ。 ゲームの間に言葉のやり取りする機会もあった。若いマレーシアとフィリピン人の女性は日本語も上手で、初対面かと思って訊いてみると、日本在住7年目と6年目で同じ会社に勤めているという。母国の選手やスタッフとの交流やサポートをしたくて応募したのだろう。 マラソン選手2人は、いつも大会ですごくお世話になっているので、今回はそのお返しをしたいので応募したという。皆ちゃんと目的意識を持っている。 いろんな人と交流が出来るというのは楽しいことだ。 昔はこういう団体行動が苦手だった。しかし、ここまで年を取ってくればこだわりも無くなり、苦手なこともない。歳をとると忘れることが多くなり、新しいものは入らなくなる。無くなる一方なのでどんどん空になっていく。それはピュアになるということ。 しかし、私のようなお爺さんが相手では話題にも困るだろうなぁ。 あらゆる場面でサポートが必要で、その殆んどすべてをボランティアが担当する。どんな部署に配置されるのか分からないが、まあ、うまくやっていけるだろう。マンネリの生活に非日常が入ることで短歌の題材(ネタ)にもなるし、心身ともにいい刺激をもらえるだろう。健康を維持する必要も増すので、その面でも前向きになれる。 ユニホームのサイズ確認をしたり、アクリディテーション(認証)・パス用の写真撮影をしたりした。 交流会の後には、「ボッチャ」体験や、会場に飾る千羽鶴を折るコーナーが用意されており、千羽鶴を折ってやろうと始めたのはいいが、途中で分からなくなった。ああ、物忘れがこんなところにも・・。 この日、階段を幾つ上り下りするのかチェックしてみた。朝倉駅41段、名古屋駅31段、地下鉄61段、46段。往路は数えていたが、帰りには数えるのを忘れてしまった。しかし、少なくともこの倍以上、400段以上は上り下りしただろうと思う。一段飛ばしで上ったりもした。 大して疲れを感じなかった。「ランジ」を時々やっているのが効いているのだろう。改めてこの調子を維持できるように意識してして、1年先に困らないように備えていきたいと思う。 1. 足を肩幅より大きく、前後に開く 2. 上体をまっすぐにしたまま、股関節と膝を曲げていく 3. 前足の膝がつま先よりも出ないように注意する 4. 前足の膝を90度まで曲げたら、ゆっくりと元の姿勢に戻る 10回(左右5回ずつ)×3セット ・手の位置は腰に当てても前で組んでもOK ・足は大きく踏み出し、戻したら「気を付け」で一時停止 ・キツくなっても踏み込む深さをキープ ・勢いよくつま先に突っ込み過ぎないように スクワット以上に・大臀筋・大腿四頭筋・ハムストリングスが鍛えられる。 スプリットスクワットとランジの主な違い。 *「スプリットスクワット」は足を前後に開いたままの位置で留まり、その場で繰り返し腰を落とす動作を行うため、負荷が高く、より安定して筋肉に刺激を与えたい場合や、ランジの基礎を作る練習に適している。 *「ランジ」は足を一歩踏み出して動作を終え、足を元の位置に戻すため、瞬間的な負荷と高いバランス能力が求められます。
2025.08.28
コメント(0)
-

☆◆☆人は騙されるように出来ている。
♪ 願わくば許せるほどに美しい花螳螂に喰われて死にたい 新聞にこんなカットがあった。エッシャーで有名な騙し絵というやつだ。朝日新聞「百年 未来への歴史」 いわゆる無限階段というやつで、上手く描いてある。最初、どうしてこうなるのか分からなかった。 階段の方向とステップの数に注目すると、この絵を描くためにはどうすればいいかがわかる。段差だけを一定にして、曲がってからの角度を変える事で距離が変り、同じ段差の階段が描ける。距離が変わってステップの数が「3→4→5→6」と増えている。エッシャーの無限階段 騙し絵には「脳の思い込み ⇔ 錯覚」が潜んでいる。生活の習慣や慣れ、思い込みが錯覚を生み、事故を起こしたり犯罪に利用されたりする。 犯罪者は常識や楽観バイアスを巧みに利用して、その裏をかいてくる。いつもこの無限階段の絵を頭に置いて、“世の中は無限階段で出来ている” と、まず「疑ってみる習慣」を持った方がいいかもしれない。 警察官、市役所職員、弁護士・裁判官などを名乗ってかかってきた電話は、無限階段の絵のショッピングカートだと思わなければいけない。とんでもないところへ連れていかれるかも知れないのだ。 以前、「The Escherian Stairwoll」という無限階段を映した動画を観たことがあった。 階段を上ったはずなのに、元の位置に戻って来たというもの。この絵はクラウドファンディングで資金集めの時に使われたもの。 Escherian Stairwollの動画を解体して、そのからくりを暴いて見せている動画がある。そのテクニックを制作者が書いたものを基に、詳しく説明している。英語なのでよく分からないが、文字起こししてゆっくり見れば凡そのことは分かると思う。 MAICHAEL LACANILAOという映像アーチストが作ったものらしい。詳しくはYouTubeで確認してください。 特殊詐欺の電話が自宅の固定電話ではなく、携帯電話にかかってくるケースが多くなっている。それで、愛知県警察本部は、詐欺の疑いがある電話がかかってきた場合に、警告のメッセージを表示するアプリの提供を25日から始めている。 愛知県警の公式アプリ「アイチポリス」からインストールできる「詐欺バスター」。25日から年末までの間、インストール可能で、90日間無料で使用できる。 このアプリは詐欺の疑いがある電話がかかってきた場合、利用者の携帯電話に「詐欺電話の疑い」などという警告のメッセージが表示される仕組みになっている。機種によっては、詐欺の疑いがある電話からの着信を自動で拒否することができる。 また、投資に関する広告を見た人がSNSのやりとりを通じて多額の現金をだまし取られる被害も相次いでいることから、広告やSNSのやり取りの画面をAIに分析させて、チェックできる機能などもあるという。◆ 手口一覧と今日からできる対策 ◆─【 手口一覧 】─ オレオレ詐欺以外にも巧妙な詐欺が多様に存在しますので、手口の特徴をしっかり把握し、対策しましょう。
2025.08.27
コメント(0)
-
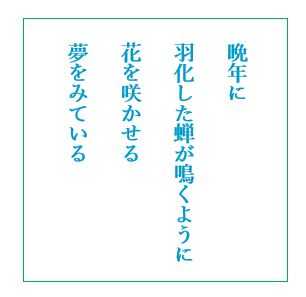
☆◆☆ミシェル・ルグランのジャズ・アルバム
♪ 晩年に羽化した蝉が鳴くように花を咲かせる夢をみている 「ルグラン・ジャズ / ミーツ・マイルス・コルトレーン」このレコードは良い。大好きだ。 50年代の録音とは思えないモダンで若々しいサウンドで、いかにも洗練された上品なジャズに仕上がっている。 この時、ルグラン(1932年生まれ)は若干26歳。 ジャズ・ピアニストとしても活動していて、ジョン・コルトレーン、ジャック・ジョーンズ、ジョニー・マティス、リナ・ホーン、サラ・ヴォーンら大物ミュージシャンとの共演作品も数多い。 マイルスは1955年に、ジョン・コルトレーン、レッド・ガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズのメンバーで、第1期クインテットを結成。1957年に、ルイ・マル監督の映画『死刑台のエレベーター』の音楽を制作している。1958年は、バンドはキャノンボール・アダレイを加えて6人編成となり、1959年には『カインド・オブ・ブルー』でモード奏法を初めて取り入れている。 ハードバップからモードに移行する前のマイルスは、私の一番好きな時期でもある。 録音は、6つ年上のマイルス(1926年生まれ)の黄金時代。あの気難しいマイルスを説得して録音にこぎつけ、すばらしいアルバムをリリースしてみせた。 ミシェル・ルグランは、映画音楽で活躍し「シェルブールの雨傘」「ロシュフォールの恋人たち」、「華麗なる賭け」(主題歌「風のささやき」)「おもいでの夏」、「愛と哀しみのボレロ」「栄光のル・マン」「ネバーセイ・ネバーアゲイン」など、数々の映画音楽を創作し、20世紀後半のフランス映画音楽界を代表する存在。 アカデミー賞、ゴールデングローブ賞、グラミー賞など数限りない栄誉に輝くマエストロだ。その彼がジャズ・アルバムを制作したのだ。快哉の傑作アルバム。 「ミシェル・ルグラン自伝」によると、ジャズにのめり込みはじめた16歳の時、ルグランは「交響曲作家か、バップ作曲家か、どちらの道を取ろうか? どうやって選ぼうか? あるいは、そもそもなぜ選ぶのか? これらの文化を全部混ぜ合わせて結びつける方法は存在しないのか?」という疑問を抱いていたという。 早熟の「バーチュオーソ」の言う事に、彼のマイルスも従う他なかったのだろう。才能に裏打ちされた理論とアイデア、構成とアレンジは、他の楽団とは一味ちがう。納得の結果がこのアルバムのすべてだ。とに角、マイルス以外のメンバーも凄い。 A面4曲目の「ジャンゴ」はMJQの名盤として知られている。それを凌駕するためにハープとヴィブラフォンをフィーチャーして、マイルスのソロをジョン・ルイスが目指した、「ジャズとクラシックの融合」を体現するような典雅な演奏へと誘っている。 編成はA、B、Cの3種類。マイルス、コルトレーン、エバンスは「A」のみの参加だ。 特に5曲目の「チュニジアの夜」は、デューク・エリントン、ギル・エバンスを敬愛しつつ、独自色を出した得意のビッグバンド編成。 トランペット4本、トロンボーン2本、アルト・サックッス2本、テナー・サックス、バリトン・サックッス各1本。ピアノ・ダラムス・ベースのリズムセクションに、フレンチ・ホーンにバイブを加えた、クラシックと融合したような音楽を演出している。 よく有るパターンを巧みに崩した構成とアレンジが、何とも心地よく展開していて飽きさせない。 ダンス音楽、クラシック、ビ・バップ、それぞれの特徴を取り入れながら、ルグランにしか出せないオリジナリティーを余すところなく発揮していて、何度聴いても新鮮さを失わない。 何と言っても、ジャズの巨匠・マイルスに遠慮せず一切の妥協を許さず、思い通りに編曲した作品を企画した通りに演奏させた手腕が凄い。「50年代末のジャズ・シーンにあって、きわめて特異な輝きを放つ作品」という評も頷ける。 50~60年代のジャズが一番好きな私としても、特殊な1枚としてこれか何度も聴くことになるだろう。その度に新しい発見をしたりして、ますます好きになっていくのだろう。
2025.08.26
コメント(0)
-
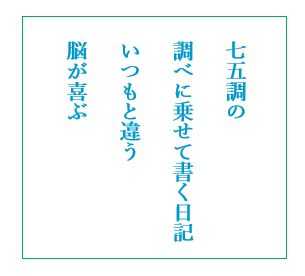
☆◆☆夕方にウォーキング 七五調で・・
♪ 七五調の調べに乗せて書く日記いつもと違う脳が喜ぶ 中3日など直ぐに来るウォーキング。早朝に出そこないしの夕方の、図書館までを歩くべし。テレビ笑点、大喜利の開始を合図に家を出る。スマホに金輪取り付けて、ぶらぶら下げて歩き出す。 雲フェチの習性なりて見上げたる、空にもくもく入道のいずこに雨を降らせるや。カンカン照りのわが地域、産めよ増やせよ雲の峰、ゲリラもゴリラも雷も招待状の用意あり。 いつもの裏道坂の道、どこまで走って上れるか、爺の冷水よっこらと走るモードに切り替えぬ。ホイホイホイと駆けだすも、200歩過ぎておみ足は動かすことを放棄せり。少し歩いてなだめやり再びギヤを上げたるも、とつとつとつと元気なくスローテンポの乱れ足、駆け足などはどこへやら、徒歩(かち)徒歩(かち)山の亀さんが坂を上ってゆくごとし。 ちょうど夕陽の落ちるころ、今日のひと日を照りつづけ、人を虐めて弄び、あまねく嫌われ憂しきもの。鈴鹿の山のその向こう、大き赤玉浮かばせて、二ッと嗤らっているような。 いにしえの常滑街道経由して、一里足らずの山の道。キジバト2羽が電線に、今日の暑さを語るのか、はたまた愛を語るのか、仲良さそうな風景を見ながら坂を下りゆく。 図書館に着きて真っ先、給水の場所へ勝手に足が向く。うんぐうんぐと冷水を、喉に流してクーラーの風に息つくその刹那、亀は兔となりにけり。 借りるべき目的の本探すべく、書棚に行けば見つからず。近くの係に声をかけ、探してもらうこと数秒、あっという間に見つかりぬ。探し物下手棚に上げ、「さすがはプロ」とヨイショして自己憐憫を胡麻化せり。 今日の仕事、為し終え明日の準備にと、身を隠したる日没の帰路は薄暗がりとなり。裏の坂道回避して表通りをぶらぶらと、無月の宵の中を行く。 美濃川のみず満々と流れゆく。そうか今宵は新月の大潮満潮時刻なり。たっぷりの水眺めつつ、遠くハゼ釣りせし記憶、水面に浮かび流れゆく。 家間近、喉がビールを欲しがりてファミマに足の向くことの、自然現象うべないて、あと3分で着くことの、すべてデジャブーなりしかな。 往復およそ6キロの、その汗流しクーラーの効く部屋で飲む缶ビール。最高の、一番美味い飲み物と、この時ばかりは思うべし。
2025.08.25
コメント(0)
-

☆◆☆まともが世界を壊すというパラドックス
♪ アサッテの向こうにきっと夢がある儚くもまた美しきもの 今夏、巷にある音が人工的なもの以外は本当に少ないと感じる。鶯は細々と啼きだした春、とうとう時鳥の声を聞かずに済んでしまった。鶯にしても以前は夏でも樹木の多い場所近くへ行けば、いつでもその声を聞くことが出来が、今年はそれもほとんど聞こえない。 アオスジアゲハも来なくなったし、カマキリもいない。周りに土と草がないのだから当然とも言える。 公園には子どもの姿もなく、親子で虫取している姿は今やアゲハチョウを見るよりも珍しい。 先日、早朝ウォーキング中にツクツクボーシの声を聞いた。弱弱しく鳴く声を聞いて、充電し忘れたスマホをどこかに置き忘れてきたような心持ちだった。 変わらないのはキジバトとカラスとムクドリくらいのもの。最近、ムクドリ20羽ほどがお隣の庭の上を通っている電線でしきりに啼いている。情緒もへったくれもない、ただの雑音だ。前の畑に伸び放題のキウイ木などがあり、そこを塒にしているのかもしれない。朝、出かける前のセレモニーかなにか知らないが、やけにうるさくて敵わない。 カミさんが最近、夜に我が家の庭とも言えないところでコオロギが鳴いていたと言う。そんなところで鳴いているコオロギが可哀そうであると同時に、情緒が消えていくことが哀れに思える。ワビ、サビどころか、侘しさばかりが巷に溢れている。 昨日は、二十四節季の処暑だった。「暦の上で暑さが治まるころ」とされている。 こいうものも縁遠くなって、俳句でもやっていない限り言葉さえ知らないまま過ぎて行ってしまう。「暑さが治まるころ」なんて言われても、まったく実感できないのだからしょうがない。季節が当てはまらなくなってきていて、あまり意味をなさないということもある。 しかし、星としての地球は確実に運行しているわけで、太陽の角度や位置が変わってい季節が移行しているのは確か。それが目に見える形、五感で感じられないものになっているのが悲しい。 いつの世でも「昔は良かった」と言い、それが繰り返されるうちに、最初がどうだったかもわからなくなっていく。 伝統は守るものではなく継承していくものという。しかし、自然は守らなければ継承も出来ない。“変わりゆくことが自然なことだ” と言ってしまえば、気は楽になるかも知れない。 変化を求めるのが人間である以上、“過去にない世界を築いて行くことが最良の道” 。だとすれば、失われてゆくものなどに囚われず、新しいものを生み出すことだけに血道を上げるのが本筋ということになる。 「未知そのものが人類の求めているものであって、そのために脳を発達させてきた。」AIに訊けばきっとそう答えるに違いない。 自分の行動から意味を剥奪すること。通念から身を翻すこと。世を統べる法(のり)に対して、圧倒的に無関係な位置に至ること。これがあの頃の僕の、「アサッテ男」としての抵抗のすべてだった。 まったく脈絡のないものなのにこの本が頭に引っ掛かっている。アサッテの方向に生きることが、人間には必要なんじゃないか。そう思える人がいることで、世界はかろうじてバランスを保つことが出来る?
2025.08.24
コメント(0)
-

☆◆☆ 老若男女の四者会談「麻雀(マージャン)」がブーム。
♪ 即興のドラマつぎつぎ変化して牌に四色の個性が躍る 昨日は孫が来る日。暑いしやることも無いので麻雀の練習でもするかと。先日、お盆に一家で来た時にもやって、結構うまくできたのでとても興味を持っている。実はその時のことを思ってカミさんが、孫とママが早く役を覚えられるようにと、カミさんが麻雀入門書を買ってきてあった。 それを渡すと孫は、にっそっと笑ってパラパラとめくって見るも、嬉しさを隠すような表情をしていた。内心はうれしくてしょうがない様子。東京・品川区のカルチャースクールで月2回開催(2024年8月) 12台の卓は、小学校低学年から中学生の子たちでいつも満席(NHK) 6年前に、ギャンブルとの決別を宣言したプロリーグ「Mリーグ」が創設され、ネットで中継されるようになると、かっこいい“頭脳スポーツ”と子どもたちの憧れに。 マージャンをテーマにしたマンガの連載やテレビアニメの放映もあって、人気はうなぎのぼりに。モデル・タレントとしてテレビなどで活躍している岡田紗佳(さやか)も女雀士だということは周知のこと。 ママの帰省で実家へ帰れば、従妹たちとマージャンをすることもある。小学生の間でもマージャンが流行っているらしく、近所の同級生にも誘われることがあるようで、マージャンの波は大きくなるばかり。 そんなこんなんで、孫は急速にマージャンに興味を持ち始めている。 3人打ちなので回るのが早いし、いい手ができやすい。ちゃんと点数も数え、私が大負けをして孫に借金したりする。そんなこともいい勉強になっている。 分からないなりに本でチラッと見た国士無双の牌を集めてみたり、何の役になるのか本で確認したりして楽しそう。「普通の単純なやつ」とか言いながら「メン・タン・ピン」でリーチしたり、自摸上りしたりもしてなかなかのもの。 わたしも借金を返しながら楽しい時間を過ごして、買い置きの缶ビールがなくなってしまった。孫も、「おもしろかったぁ!」と呟いていたので、正月はきっと盛り上がることだろう。 「子どもの勢いには負けるなぁ」とか言っているママにも、しっかり役を覚えてもらわないと。子どもの記憶力とか吸収力には目を見張るものがあるので、あっという間に差を付けられそうだ。 子どもが麻雀をするようになると「処理速度」がアップし、IQもアップすることが分かってきている。 「マージャンは牌を覚えたり、考えながら手を動かしたりするなど、目で情報処理をおこないます。そういった部分が、短期記憶や集中力の向上につながっていると考えています」 「マージャンは、小さな子どもたちが、おじいちゃんやおばあちゃんなど、幅広い世代と同じ目線で交流できるすてきなゲーム。将来はマージャンがいろいろな交流の場で用いられることに、この研究が役立てばうれしいです」横浜市立大学 東島威史医師(プロ雀士)。 豊田市では、【年長~中3】第3回 子ども麻雀大会(2025年8月11日)があった。 集中力、観察力、記憶力、判断力、論理的思考力、忍耐力、大局観、感性、度胸など、さまざまな力がバランスよく求められる高度な頭脳スポーツである麻雀。 7月には「第1回全国高等学校麻雀選手権大会」が行われている。朝日新聞が創設 全国180校から286チーム572選手が参加し、東京都立小石川中等教育学校のチームが初代王者に輝いている。全国の高校生らが2人1組のチーム戦。 こちらは4人一組での対戦。1チーム10万点持ちで、点数を引き継いで打つ【咲-Saki-】方式で競います。先鋒・次鋒・副将・大将戦をそれぞれ1半荘行い、最終的に最も所持点数が多いチームが優勝となります。8月30日に決勝戦。YouTube:麻雀ウォッチチャンネルで放映 全国の子どもから高齢者、障害のある方も含め全国から愛好家が集い交流する健康マージャン大会「全日本健康マージャン交流大会」なんてのもあって、老若男女が盛り上がっているようだ。長崎・出島メッセ長崎 コンベンションホール 他には、文部科学大臣賞「全日本健康麻将選手権」とか、「日本健康麻将協会」とかがあって、全国的に教室や大会などを開催しているようだ。 いやはや、今後の日本は「マージャン」が合言葉になるのかも知れない。会った時に両手で牌を倒すような仕草をして、「やってる?」なんて・・。しかし、座りっぱなしでまったく動かない、こういうものをスポーツと呼んでいいものか・・。頭脳を使うスポーツと言う位置づけはコンピュータゲームの世界も同じだが・・。
2025.08.23
コメント(0)
-
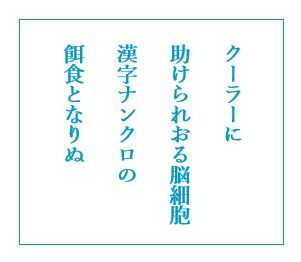
☆◆☆朝のウォーク メダカ 漢字ナンクロ
♪ クーラーに助けられおる脳細胞漢字ナンクロの餌食となりぬ今朝の日の出 相変わらずの猛暑が続く。連日、朝までクーラーを点けているなんて初めてのこと。 クーラーのお陰でよく寝られるので、朝の目覚めも早い。 今朝も5時にウォーキングに出た。先日は少し歩きすぎたのでセーブしてショートカットの予定で・・。寺本駅より 寺本駅まで14分。いつものように60段を駆け上がる。上りの始発が05:43なのでまだ誰もいない。 秋葉神社まで10分。120段を一気には駆け上がれなくなり、真ん中で息を入れて上がる。それでも、最後はやっとこさ状態。歳をとった(体力が落ちた)のを思い知らされる。 右の踊り場から先は、階段がかなり傾いたり乱れたりしていて、駆け上がるリズムが狂うので余計な筋肉を使う。 めずらしく東の空は曇っていて、昇り始めた朝日もその威光を遮られて大人しくしている。 11分後、パークロードへ出るとようやく雲の向こうに太陽が顔を出した。東南東の空は晴れていて、南へ向くほどに雲がなくなっていく。パークロードから離れて帰途へ。日が差し始めたが薄日のために影がない。 涼しいかと言えばそんなこともなく、18日の朝よりも蒸し暑い。朝は東北東の風だったが、西寄りの風から南寄りの風に変り、熱低→台風→熱低と変化しながらノロノロと進んでいる低気圧が、高気圧を刺激してその熱風が伊勢湾に向かって吹き込んでくるらしい。 どうせ今日も37℃以上の猛暑になる。 途中、散歩中のシベリアンハスキーを見かけた。きっとクーラーの効いたところで大事にされているのだろう。涼しい顔をして歩いて行った。何故かリードを持った飼い主が、にそっと微笑んで通り過ぎていった。 スプリットスクワットなどやったりして体調がよかった。ショートカットした分、(120歩、20歩、160歩、100歩と小さい坂だけだが)久し振りに駆け上がったりした。ちょっと若返った気分になって戻って来た。8,800歩。このぐらいがちょうどいい。 夕方、家庭菜園や畑仕事をしている奥さんが、「多分メダカだと思う」といって大小10匹ほどを、飼育ケースに入れて持ってきてくれた。カミさんが新しい血を入れたるためにメダカが欲しいと言っていたのを思い出し、水撒き用に農業用水を溜めてある水槽にいたのを持ってきてくれたらしい。 いつも自然農法の美味しい野菜を持ってきてくれる奥さん。何と気配りのある親切な人だこと。 その小さな魚が、メダカなのかカダヤシなのかすぐには判断できず、取りあえずもらっておいた。カダヤシなら水撒き用のタンクに入れて孑孑を食べてもらえばいい。 以前、捕って来たのを調べた事があり、その時の情報(上の図)からメダカに間違いないことが判明。今朝、メダカの甕に入れてやったらしい。今は、カミさんに管理を任せているので写真を撮る間もなく、この事案は「解決済み」という事になった。 漢字ナンクロに嵌っているカミさん。少しでも時間があると首ったけになって、テレビが点いていても目に入らない。話しかけても上の空だ。 こんな嵌るほどに夢中になるとは思わなかった。毎日、新聞に載っているクイズはすべてクリアしないと気が済まない。右脳より左脳の方が優勢のようなのだ。 しかし、ホワイト漢字ナンクロは苦手で、最後まで手を付けずに残してある。それじゃあ私がやるかと、アタックし始めると興味が湧いてくる。それでバトンタッチしてやる。 かなり難しいが頑張ってやっていると、徐々に解けていくので感心する。スマホで調べないと無理な部分も多いが、嫌いじゃ端から出来るはずもない。やっぱり好きなんだねぇ。拡大 最初の糸口を私が見つけ、そこから先はカミさんに任せる。我慢してやり続けられるかどうかがポイントだ。 かなり出来て、最後の詰めのところで停滞する。それで私も参加し、どうにかクリアまで漕ぎつける。まあ二人の共同作業みたいなものだね。真っ白だったものがすべて埋め尽くされると、さすがに快感がある。
2025.08.22
コメント(0)
-
○◆○南アルプス 地蔵岳登山9 (無謀な計画に悪戦苦闘)
9 そう言えば、今日は誰ともすれ違わなかった。下から上って来る人は一人もいなかった。ドンドコ沢にいたのは俺ひとりだけ。昨日の同宿の客も他のルートへ行く人ばかりで、同じコースを下るという人はいなかった。二日間とも天気が良く、最高の登山日和だった。苦しかったが下りてしまうとあの辛さが懐かしく愛おしくさえ思えてくる。来てよかった。思い切って行動して、やってみれば何らかの答えは返って来るものだ。何か自信が付いた気がする。やればできるのだ。苦しいけどガンバリ通せば必ず返ってくるものはあるものなのだ。久し振りに新鮮な気持ちになれた。山はいい。また登りたくなる。下りてきたばかりだというのに。ビールを飲みたいところだが、今ビールを飲んだら疲れがドット出て車の運転どころではなくなってしまう。 10時50分、青木鉱泉を出発。小武川に沿って国道20号線へ向けて走る。韮崎から越えて来た林道とは違って途中からは舗装までしてあり、楽々の道だ。韮崎の駅から車(マイクロバス?)で御座石鉱泉まで乗って1,500円とか。あっという間に国道へ出、そのまま北上して伊那辺りから中央自動車道へ入る事にする。左に甲斐駒ヶ岳を見ながら走る。さすが頂上付近は険しそうだ。木曽駒ケ岳よりも高く2,966mあり、南アルプスでは一番人気のある山だろう。南アルプスには北岳もある。槍ヶ岳の3,180m、奥穂高岳3,190mをも凌ぐ3,192mで富士山に次ぐNo,2だ。 諏訪の手前を左折し256号線を高遠へ向かう。この杖突峠越えの道はかなり走り甲斐のある道だ。峠から見る諏訪湖や八ヶ岳連峰もなかなかのもの。しかし、峠越えから高遠の町までかなりの距離があり、昼過ぎで腹も減ってきたことからゆっくり景色を見る余裕はなかった。峠で蕎麦でも食えばよかったと思ったが通りずぎてしまって、後の祭り。高遠から伊奈インターへ入り、駒ケ岳サービス・エリアで休憩、食事。午後1時だ。青木鉱泉を出て2時間余り。家に電話を入れる。ガソリン10リッター入れ、セルフでタイヤに空気を入れる。40分後に出発し、一路名古屋へ。5時前には家に着けそうだ。 ここまで順調に運転してきたがさすがに疲れが出て来たか、眠くなってきた。そりゃそうだろう、疲れない方がおかしい。恵那サービス・エリアで一服。運転中は何ともないが歩くと腿が痛い。しばらくベンチで横になる。うつらうつらし、少し眠った様だ。30分ほど休んだだろうか、だいぶ元気が戻る。少しでも眠るとスッキリする。このまま一気に自宅までノンストップだ。 春日井インターで下り、19号線を経由して名古屋へ。庄内川を越えるのに渋滞に会い、時間をロスした。小牧インターから41号線を南下するよりこっちの方が早い気がするが実際はどうだったのか。 5時半少し前に家に着く。途中で買ったビール大瓶2本を一気に飲んだ。充実の二日間であった。走行距離は586km。 後年、取材した滝をテーマにした作品「cascade」が、中部染色展で最高賞を受賞することに。123456789
2025.08.21
コメント(0)
-
○◆○南アルプス 地蔵岳登山8 (無謀な計画に悪戦苦闘)
8 しばらく休んで気を取り直す。とにかく下りなければならないのだ。こんなところに居るわけにはいかないのだ。重い足を引きずってでも下りなければならない。昨日一緒だった中年夫婦やおばさんの二人連れは今頃どうしているのだろう。ガンバッテ登っているのだろうか。俺ほど疲れてはいないかも知れないが、それでもキツイのは同じだろう。皆がガンバッテいるのに自分だけがこんな所で泣き言を言っていては笑われる。素人だからと甘えた事をいってられない。自分一人で自分の力で下山して、車のところまでたどり着かねばならない。誰も助けてくれない。助けを求めることも出来ない。 きのうは途中、下山してくる人何組かと声を交わしたが、考えてみればきのうは日曜日で土日をかけて入山している人が多かったわけだ。今日は月曜日で、ひょっとすると誰にも会わないかも知れない。このドンドコ沢にいるのは自分一人だけかもしれない。捻挫とか腹痛とか不慮の事故で動けなくなっても誰にも助けてもらえない。3~4日一人で誰かが通るのをジッと待っていなくてはならないかも知れない。甘い考えは捨てて確実に一歩一歩下って行くしかない。 再び下り始める。この辺りはきのう登ったところだと、その時の記憶が鮮明によみがえってくる。やっとここまで来たかと、その場所の石の組み具合とか根っ子の出っ張りの様子とか、登って来た時の事を思い出す。この辺りで道に迷いかけたとか、あまりに急勾配なのに驚いた事、下りはどうやって下りるんだろうとか、登る度に新鮮な発見と驚きがあった。そういう思いをたどりながら下って行くのも悪くないものだ。そういう意味では下りは登りよりも気が楽かも知れない。まったく先が見えず予測も出来ない、すべてが初体験の連続の登り。前ばかり上ばかりしか見ておらず、後ろを振り返るような余裕もない。次から次からやって来る難関を突破する事ばかり考えていて、それが精いっぱいで他に何かを考える余地がない。 下りは気分的に少しは余裕がある。視界も広く開けている。登る時は登る道の壁しか見えないが下る時は前方の景色を眺めることが出来る。注意深く足元を見ながら、必死になって急な段段を下りながらふと前方を見ると、富士山が見えたりする。登る時にまさかこんなところで富士山が見えるなんて思いもしないし、後ろを振り返る余裕もなかった。下りには登りとは違う発見がある。鳥の声も良く聞こえる。時間帯の違いもあるのだろうが、立ち止まって鳥の姿を探す気持ちのゆとりが聞く耳を持たせるのだろう。一度通った道には安心感がある。状況や距離がつかめ、先が読めるし計算が立つ。同じ道を引き返しているという安心感。 そうは言っても下りはやはりキツイ。肉体の方はとうに限界を越しているはず。下る時に使う腿の筋力は登る時の倍は必要だ。勢いが付くと制動が利かなくなる。勢い余って崖から転落なんて事にもなりかねない。登山の事故はこういう状況で起こる。そうならない様に使うエネルギーは登りのそれとは比べ物にならない。注意力も怪我をしないための用心も、登りの時には必要なかったものが要求される。登る時はただただ一歩ずつ足を運んでいれば良かったものが、下り一歩ずつという訳にはいかない。どうしても勢いがついて二歩三歩と動いてしまう。そうなると一歩分の制動力ではなく三歩分の力が要る。それだけ余計に疲れることになる。 一番下の滝に着くころの足は、とうへんぼくのデクノ棒状態。右足のくるぶしの治り切っていない傷に靴のヘリが当たって痛い。登りの時と違って体重が足にもろに掛かるため靴が食い込んで来るし、つま先にも体重がかかるため痛くてしょうがない。ジョギング・シューズでは体重が支えきれない。下る時はまともにつま先に体重が掛かるため、底の厚いキャラバンシューズのような靴でないと指先が負けてしまう。 南精進ヶ滝の看板の下にベンチがあり、そこで靴を脱いで横になり、足を休める。この場所には登山中に事故で息子を亡くしたのか、両親の名入った碑が立っており、何か痛々しさを感じて落ち着けなかった。 ここからの下りが、また思ったよりキツかった。今までの階段状の登山道から変わって、砂泥のそれもかなり急な下りはどうしても歩くというより走る感じになってしまう。ゆっくり歩こうと思っても地面が斜めに下がっているため、後傾になると滑る。前傾姿勢で爪先に体重が掛かると痛いので、ついつい走るような形になるのだ。下ったと思ったらまた上がり、上がるとまた直ぐに急な下り。爪は痛いし、腿はビンビンに痛いのを通り越して、感覚が鈍くなって力が入らず、その分余計につま先に負担がかかる。この辺りではほとんど悲鳴を上げながら、歩くでもない走るでもない中途半端な変な格好で下って来た。泣きながら、独り苦難に耐え、息も絶え絶えの難行苦行の数時間。まるで拷問だ。どうしてこんな変な道を作ったのか、どうして下ったと思ったらまた登ったりするのか。何でこんなに急なのか。階段の様に段が付いていればまだ歩き易いのに。後半はもうほとんどギブアップ状態。1分歩いては休み、ジグザグの折り返しのたびに休む。爪が痛くてもどうにもならない。休んでも治らない。行くしかない。下りるしかない。 遠くの方に見覚えのある沢が見えて来た。青木鉱泉が近い。ここまで来れば着いたようなもの。気を取り直して、一気に下ってしまおうかなどと思ったりする。しかし、そうはいかない。なかなか近づかない。歩けど歩けど、沢が近づいてこない。確かに水音は聞こえる。音が少しずつ大きくはなって来ている。しかし、なかなか沢が見えてこない。道は相変わらずアップ・ダウンを繰り返している。いい加減に頭に来た。もう動けん。休憩だ。クソ。 青木鉱泉に10時10分に辿り着く。所要時間4時間10分。コースタイムは3時間半と書いてある。まあまあだ。それにしてもキツかった。クタクタのガクガク。ベンチで横になり、死んだ様に休む。一瞬死んでいたかもしれない。青木鉱泉のおかみさんに駐車料を払う。1,000円也。風呂に入りますか?と聞かれ、料金を聞くと800円という。高いんだねえと言うと、こんな山の中にはもったいない色白の品のいい美人のおかみさんは、心も優しい女神だった。駐車料金と共で1,500円にまけてくれた。 「ここは沢の水をそのまま引いて沸かしているので、この料金は決して高くはないはず」と言う。地図を見ていて鉱泉の意味が分からなかったが、温泉と名乗るには条件があり湧出温度が何度以上という決まりがあるというのを思い出した。或る成分を含んでいて、冷たいままのものを鉱泉と呼ぶのだろう。おかみさんに聞くと、鉄分を多く含んでいて胃と貧血に良いとかで、飲んでもよろしいとの事だった。客は他に誰もおらず、たった一人沸かしたての風呂に入る。身も心も洗われる思い。拷問から解放されて自由の身になった、奴隷のような心境。 良い気分だ。幸の一字。他に何もない。一人は良い。登山は独りが一番だ。誰にも気兼ねなくマイペースで自分の思うままに、思い通りに行動できる。 9へ続く123456789
2025.08.21
コメント(0)
-
○◆○南アルプス 地蔵岳登山7 (無謀な計画に悪戦苦闘)
7 それにしても皆タフだ。疲れを知らないやつばかり。それも自分より年上ばかり。キャリアを積んで少しずつ体を作っていった結果だとは思うが、今日の自分のだらしなさと比べると雲泥の差どころではない。おばあちゃんに負けている。最近の女性の進出には目を見張るものがある。あらゆる分野に変化が見られる。飲み屋に行っても女性だけのグループがたくさんいる。ゴルフにしてもフルマラソンにしても、トライアスロンまでも女性の参加が目立つ。登山にしても昔は女性登山家はめずらしく、よっぽど男勝りか女を捨てたような人が多かったが、今日の中年二組の場合はごく自然な形で溶け込んでいる。肩ひじ張らず何の抵抗もなく自分が登りたいから登るだけと、ごく自然に楽しんでいる。体力も充分あり、この位のことをしていないとエネルギーがあり余ってしょうがないといった感じ。 忍耐力も男に勝るとも劣らず、肉体も精神も男よりは鈍感に出来ているのかも知れない。苦痛を感じる度合いも男と女では随分違うように思う。特に持久力は断然、女性の方が上だろう。ある高度に達すると女性ホルモンがエネルギーに変るという実験データもある。登山は女性に向いているのだ。筋力は男性に劣るが、登山の場合は筋力よりもむしろ持久力の方を要求される。皮下に蓄えられた脂肪を燃やしながら幾らでもエネルギーを捻出できる女性の方が確かに有利のように思う。遭難しかかってもチョコレート1枚で生き延びたという記事を目にしたりする。逆境に強いのである。最後には女性が勝つのである。平均寿命も長い。何も無くても生きて行けるのが女性。即物的であるが故にその場その場で変幻自在に形を変え色を変えて順応していく。 女性が強くなったということをよく聞くが、強くなったというより男性が弱くなったという方が正しい。女性の側はもともと持っていた能力が時代の変化によって自由に発揮できるようになったに過ぎない。男のエゴや風習、伝統や価値観によって抑えられ、長い間に本質が隠されてきた。女性自身もその状況に甘え、表に出ることをしない出来た。それが自分たちも何かが出来るのではないか、男が出来ることは自分たちにもできるのではないかと、それまでの生き方に疑問を持つ人が増えて来た。不利な部分をカバーして余りある女性の潜在能力が発揮され始めたということだろう。 炬燵でしばらく話をし、7時頃にはみんな寝てしまった。山の夜には独特の雰囲気がある。暗いというのは、真っ暗闇ということ。街灯もなければネオンもない。月があれば月明かり、晴れていれば星明りが有るにしても、心底ピュアーな世界なのだ。雑音もない。電車の音もしない。電話もなければテレビもない。水道の代わりに谷から引いた水の音だけがはっきり聞こえる。暗い中で懐中電灯も点けずに食器を洗う音が聞こえる。外は少しは明るさが有るかもしれないが、小屋の中から見たところでは真っ暗に見える。真っ暗な中で、ヒゲの兄ちゃんがいつまでもゴソゴソ動き回っているいて、同じ人間ではないような気がしてくる。遠い原始時代の生活を思う。昔の方が時間は長かった。同じ1日でも今の24時間とは違ってはるかに長い1日だったろう。 暗くなってから夜が明けるまでの暗闇の中で、昔の人は何を考えていたのだろう。何もしないでいるというのは、今の時代、最も優雅な過ごし方である。心が洗われる。何もしないが故の豊かさ。夜7時に寝るなんて健康体である限り考えられない。普通ならとても眠れるものではない。酒でも飲んでうだうだと時間を潰し、そこそこの時間が来ないととても寝ようという気にはならない。しかし、今夜は別だ。疲れているし、何もすることがない。真っ暗だ。毛布にくるまって寝るだけだ。客が少なく毛布もたっぷり使わせてくれた。一人5枚ずつと言われたが実際には7枚ほど使った。 9月の上旬、山はさすがに冷える。日没直後には息が白く見え、気温は10度そこそこだったと思う。ストーブは気温で決めるのではなく、しかるべき時期が来ないと火を入れないのだそうだ。それもそうだろう、寒いからと言って燃やしていては燃料の薪がいくらあっても足りなくなる。前日の最低気温は5度くらいだった聞いた。平地の真冬の気温だ。セーターは持ってきてない。長袖のアンダー・シャツの上に上着を着て、ジーパンに靴下を履いたまま毛布にくるまった。朝方、寒くて目が覚めるかもしれないと、覚悟して。 未明の3時過ぎからもう起きてゴソゴソしている人がいる。懐中電灯を点け、何やら出発の準備をしているらしい。中年女性の二人組が3時半に目覚ましをセットするとか言っていたのを思い出した。地蔵岳でご来光を見て、観音岳、薬師岳を経て夜叉人峠へ下る予定だと言っていたっけ。まったく元気な人達だ。そのうちに他の人達も起き出したらしく、ますます騒がしくなってきた。合繊の擦れる音やシートをたたむ音か、可成りうるさい。みんなこんなに早く起きてどうするのだろう。 知らない内にまた眠ってしまったらしく、目が覚めた時はもう夜は明けていて明るかった。5時少し回ったぐらいか。もう日が昇りかけて、射しこんで来る朝日が眩しい。起きて見まわしてみると、何とたった3人。単独行動の男3人だけしかいない。みんなご来光を目指して早や立ちしたらしい。昨夜のうちに弁当を作ってもらい、4時半ごろには出発したらしい。早起き組がいる事は分かっていたが皆が皆いなくなるとは思ってもみなかった。山小屋の朝は早いのだ。 夜7時に寝て3時に起きれば睡眠はたっぷり8時間。5時過ぎまで寝ている方がおかしい。10時間も寝たことになる。お蔭で疲れはだいぶ取れた気がする。腿の痛みはまだ有るが、なんとかなりそうだ。 5時半、朝食。これぞ日本の朝ごはんという定食だ。ご飯、みそ汁、玉子、のり、漬物。3人でなんだか侘しい食事。あまり喋ることもなく、ご飯のお代わりをするでもなく、静かな静かな朝食であった。食後、きのう見た富士山を写そうとカメラを持って出掛けるが、時間がおそかったか赤富士は見られず。ご来光を迎えれば赤富士だったかも知れず、少しガッカリして小屋へ戻った。 6時ちょうどに下山スタート。軽やかに歩き始める。が、昨日の疲れが残る太腿にはや痛みが来た。これは先が思いやられるぞ。覚悟しろ、というところ。一番上にある五色の滝まで来るのにほとほとくたびれてしまった。きのう地蔵岳からの下りでいかに下りが大変か、いかにしんどいかを思い知らされている。この時すでに限界がきていた。もう一歩も下りの道は歩けないところまで疲労が来ていた。やっとのことで小屋までたどり着き、小屋の前の沢の上に突き出たテラスにへたり込んでしまった。その時の完璧につかれた状態がもう早々とやって来たのだ。 一晩ぐらい休んだところで急激に痛めた筋肉が回復するはずがないのだ。普段、ジョギングぐらいで階段の上り下りなどしているわけでもなく、腿の筋力はほとんど使っていない。それを無理やり酷使して登って来たのだ。その結果がこうだ。当然だ。筋肉にも限界がある、頑張るにもほどがある。気持ちだけでは体は動かない。リュックを下して座り込んでしまった。横になって足を投げ出したい気分だがそんな適当な場所もない。 8へ続く123456789
2025.08.21
コメント(0)
-
○◆○南アルプス 地蔵岳登山6 (無謀な計画に悪戦苦闘)
6 頂上付近はさすがに木が生えてはいないが、すぐ下にはダケカンバが木陰を作り、殺風景な風景に色どりを添えている。トウヒ、シラビソ、コメツガやヒノキなどが生い茂り、さわやかな木陰を提供してくれる。南アルプスの3,000m近くの山々がすべてそんな感じなのだ。地蔵岳の頂上からは、目の前に甲斐駒ヶ岳、東に八ヶ岳連峰、南側には雲の上に頭を出した富士山が静かにたたずんでいる。ほぼ快晴で、ふもとまで手に取る様に見える。あまり天気が良すぎるのも情緒がない。少し雲がかかるか、靄が掛かっているぐらいの方が美しい。 富士山はすぐに雲が全体を覆ってしまった。頂上はやっぱり気持ちがいい。しばらくそこらの大岩の上に横になって、山の空気を存分に吸った。抜けるような青空は、吸い込まれそうに深い色である。余りに穢れがなく澄んでいて、ジッと見ていると目眩がしそうだった。そのまま目を閉じて風に吹かれている。あんなに辛かった今日の登山だったが、このひと時はすべてを忘れていい気分だった。 しばらくして、風が冷たくなって来たのでぼつぼつ下ることに。砂走り風の道はやはり走って下りることになる。靴の中に砂が入る。急な坂を走って下るのはけっこうキツイものだ。調子づいてここで走ったのが後になって効いてきた。如何にも足がくたびれている。小屋まで登って来て精も根も尽き果てたののに、それから余分に1時間、最もキツイところを登って来ている。足が動かなくなってきた。腿が痛い。登る時と違う痛さがある。登りと違ってゆっくり歩を進めるということが出来ない。どすんどすんと下りる。そのたびに腿に力が加わり、ビリビリっと来る。後ろ向きに下りるのが楽だ。だからといってすっと後ろ向きで下りられるものでもない。急な段の部分だけ後ろ向きに下りる。木につかまり、根っ子にしがみつき、出来るだけ足に力を入れない様に上半身を使いながら下りる。腕の力を利用してぶら下がる様にして、ゆっくりゆっくり下りる。どんなにシンドくても今日はここで泊まるのだ、我慢が出来る。小屋へ着けばもう今日は何もしなくていいのだ。食事して寝るだけだ。酒を飲んで寝るだけだ。 夕食までの間、掘りごたつに入って泊り客と小屋の主人と歓談する。真っ暗の中、わずかにランプの明かりが有るもののほとんど相手の顔は分からない。5時半ごろには日も落ちて、山は静かな眠りに入ってしまう。ワンカップの酒を飲む。500円。この暗い中で本を読んでいる宿のオヤジは、生活に暗順応している。我々ではとても本など読める明るさではない。 夏の本格的登山シーズンは終わり泊り客も少ないので、本がよく読めると言う。一日一冊のペースとか。 夕食は5時半。この時だけ小型の発電機を回す。薄暗い蛍光灯の下での食事。今夜はカレーライスの簡単料理。山小屋でカレーを食べるとは思っていなかった。熱いご飯に山菜に魚、それに味噌汁とかを想像していた。昨晩はキノコを出したそうで、そういえば登山中にも食べられそうなキノコが何種類か生えていたのを見た。白いシメジの様なもの、チャコールグレーのもの、茶色のもの紫いろのものなどあり、白いのとグレーのものなど食べられそうだった。カレーなんかよりキノコが食べたかった。 夕食後、夕陽に輝く富士山を見に行く。もう一つの登山ルート、御座石鉱泉ルートを少し下がったところから富士山が見えるという。真っ赤に染まる富士山を期待したが、ピンク色からすぐグレーに変わって、そのまま暗くなってしまった。小屋の周囲の山は夕陽を受けてオレンジ色に染まっていたのに、富士山は思ったような鮮やかな色には染めてくれずがっかりして小屋へもどる。しばらく炬燵で談笑する。 今日の客は中年以上の熟年登山者ばかりで、男の最年少が34歳。あとは俺が2番目で、50代の夫婦夫婦や40代の後半から50代初めぐらいの女性二人のパーティー。それに独身女性の二人組。40代の男性。他に何人かいたようだが顔を見ていないので良く分からない。昭和11年と15年生まれのご夫婦は子離れし、孫がいるとか。共通の趣味を登山にして楽しんでいるらしい。50歳の奥さんは俺と同じドンドコ沢を登って来たそうだ。41歳の自分があんなに苦労して登って来た道を孫のいる(おばあちゃんとはまだ呼びにくい)人が登って来たということに驚いた。自分がいかに登山の素人か、甘い人間かを思い知らされた。 そして中年女性の二人連れにも驚かされた。年に6-7回の他に月に一回は登ると言い、疲れた風もなく淡々としていてこのぐらいの山は朝メシ前という感じ。夕陽を見に行った時もこの二人はヘッドランプを着け、一眼レフのオートマチック・カメラを派手にガシャガシャやっていて、いかにもこういうシチュエーションに慣れている。34歳の男性は学生時代に良く山登りをしたが、結婚して子供が出来て遠ざかっていたが久し振りに登ったのだとか。お盆休みに4日程縦走して今日また一人で出て来たという。 3-4日の登山となると、テント、シュラフ、食料などなど何と20kgのリュックを背負って登るという。ビール大瓶20本入りワンケースの重さだ。とても考えられない。5kgでヒーヒー言っている私には10kgだって無理だ。知人の神谷氏も家族で涸沢へ行った時は20kgほどを担いで登り、徳沢で一泊して涸沢に着いた時はメシもノドを通らなかったと言っていたっけ。 7へ続く123456789
2025.08.21
コメント(0)
-
○◆○南アルプス 地蔵岳登山5 (無謀な計画に悪戦苦闘)
5 それにしても疲れた。こんなにしんどいとは思わなかった。登る前までは日帰りも考えていた。苦しいだろうがもっと楽しいイメージを描いていたものだ。空気が旨く、水が冷たくて大変美味しい。休憩中に見る下界の景色。眼下に見える雲海。遠くに見える山々の稜線。さわやかな風。苦痛から解放された満足感。それらのことごとくを楽しむ余裕がない。まったく無残な姿だ。ただ黙って喘いでいるだけ。声も出ない。ぐったりと座り込んで、俯いて悪魔が去り行くのを待つだけだ。体を蝕んでいる病原菌が死滅するのをじっと耐えている瀕死の原始人。悪霊に憑りつかれた病人の心境だ。打ちのめされ魂を抜かれた生きた屍。百年間、毎日使い続けた雑巾の様にボロボロになった足腰。もう一歩も歩けそうにない。このままずーっと横になって朝まで、疲れが回復するのを待っていようか。 午後1時を回って、やはり風が冷たくなってきた。天気は良いが少しづつ雲も出て来て、太陽を遮ると途端にひんやりしてTシャツのままではいられなくなってきた。ここで仮にも夜を過ごすことなどとうてい無理な、嫌―な感じの冷たさだ。山の夜はかなり冷えるのだろう。セーターを持っているわけでもないし、あまりゆっくりはしていられない。20分ほど休んだだろうか。最後の力を振り絞って小屋まで登ることにする。 小屋に泊まることに決めてからは随分と気が楽になった。この出鱈目にキツイ登山道を今日は下らなくてもいいと思うだけで、逆に登るためのエネルギーが湧いてくるというもの。確かに登る方が楽だ。下るには登る力の数倍の力が必要だ。今の疲れ具合では、滝一つ分も下りられそうにない。最後の意地で登ってやる。やっつけてやる。 一つの稜線を越えて沢へ下り、河原の石だらけの道を登る。この石の道を歩くのが思ったよりキツイ。足が痛くなってくる。なるべく石の上に乗らず砂の部分を歩くようにするがどうしても石の上を歩かねばならず、膝から下が棒の様になってくる。石の河原も過ぎ、平坦な川沿いの道を暫らく行くと小屋が見えた。随分、時間がかかった様に思う。 見えたが、屋根のほんの一部が見えただけということもあって、あまり立派な小屋には見えない。一瞬、目的の鳳凰小屋ではないのかとガッカリしたが、近づくと小屋はまともになり、小屋の前にヒゲ面の青年が立っていて「お疲れ様」と言ってくれた。やっと着いた。やったぞ。しかし、疲れた・・・。 時計は3時を指していた。一体何時間かかったのだろう。6時半に登り始めたわけだから、8時間半。うへー、普通の足で5時間のコースを幾らゆっくりしていたからと言っても8時間はかかり過ぎだ。自分の能力の無さを思い知らされた。この程度なのだ。41歳のおっさんなのだ。気が若くても体力は年相応なのだ。自分を過信して日帰りも考えていたなんて・・・。 缶ビールを飲む。600円也。ぐったりと足を投げ出して休む。数人の人が何やら食事でもしているのか、ゴソゴソと動いている。ヒゲのお兄ちゃんは無口だけど優しそうないかにも山の男という感じ。こいつが山の主人かな、いやに若いが。しばらくするとどこかで昼寝でもしていたらしく「寒くなってきた」とか言いながらオヤジが起きて来た。こっちが小屋の主人らしい。宿泊手続きをする。 このオヤジがまたぶっきら棒な奴。一々言うことに愛想というものがない。必要な事を羅列するだけ。まるで思いやりとか気遣いというものがない。素泊まり?食事付き?なら5000円。それだけ。おしまい。取り付く島もない。山の男ってみんなこんな感じかしら。ヒゲの兄ちゃんは「お疲れさん」「泊まりますか?」とかけっこう愛想が良かったのに。 「山と渓谷」9月号に山小屋の特集があり、アンケートで人気の山小屋一覧があった。南アルプスでは圧倒的に「北岳山荘」と「北岳肩ノ小屋」が人気の小屋だ。特に展望や立地がダントツの高得点。このアンケートの中に「ふとんが気持ちいい」というところに、こ鳳凰小屋が6位にランクされている。その他のアンケートには名がなく、ふとんのところだけに登場するというところを見ても、あまり特徴のある小屋という訳でもないみたいだ。事実、眺望が良いわけでもないし「主人の人柄に触れられる感じ」でもない。「プラスアルファの魅力がある」というのでもないし、「食時がおいしい」というのでもなさそうである。ま、山小屋というところに泊まるのは初めてなので、すべてが物珍しく、新鮮な体験ばかりでだ。 食事の時間までは間があるし、他にすることもない。小屋の中は暗いし、本が読めそうな感じでもない。小屋の正面に地蔵岳が岩を露出した一風変わった姿をみせている。聞くと、1キロほどで1時間で登れるという。明日はあの地獄のような下りが待っている。あす頂上に登ってから下山という力は残っていない。ならば今日中に登らないと登り損ねてしまう。せっかくここまで来て一泊するのだし、登らずに帰る手はない。疲れているが荷物は置いていけるし、1時間程なら登れるんじゃないか。ゆっくり登ればいいことだ。缶ビールの勢いも手伝って、登れそうな気がして来た。 よし、行こう。上まで行かなきゃ登山して来たとは言えないぞ。 標高差約300m。さすがにキツイ。頂上直下だから一番きついのは当たり前だ。小屋までの途中の岩だらけの道とは違って、木の根と土のアスレチック・コースの様だ。根っ子をつかみよじ登るように登って行く。小一時間かかって頂上直前まで来ると、ここからが亦大変だった。砂地になっていて、靴が滑ってやけに疲れる。まるで富士山の砂走を踏み固めた様なところを登っていく様だ。空気も薄いのだろう、息が切れる。しかし、大きな石の山とも呼べる頂上が目の前に迫っている。大きな石が聳え立ち、こんな山は見たことがない。雄大な姿。どうしてこんな石が頂上に残ったんだろう。転げ落ちもせず、ちょうど米粒をタテに重ねた様な形で安定している。あそこまで行けば四方の山々を眺められる。富士山も見える。ガンバッテ登ろう。 頂上はまるっきり石の山だ。ケルンの様に石を上へ上へと重ねて、その真上に当たるところに最も大きな岩をタテに突き刺したような感じ。かなりの高さがあり、とてもその岩のてっぺんまでは登れない。ハーケンとザイルでもなければ不可能だ。フリークライミングのプロなら登っても登れない事はないかも知れないが、登ったとしても下りることができそうにない。つるんとした角のない岩で、北アルプスなどの山で見かけるゴツゴツした角のある岩ではなく、川原にある様な表面が丸くなったツルツルの岩である。いったいどうしてこんな丸みを帯びた岩がこの山の頂上にあるのだろう。日本昔話の様に、だれかがどこかから運んできて、おむすび山のてっぺんに積み上げたという感じ。自然の不思議さを思う。 北アルプスの風情とは全く違う南アルプスの山々。岩肌がむき出しの処はあまり無く、樹木が茂って優しく包み込んでくれる。険しいと言っても刺々しさはなく、自然の溢れた土の香りのする山という感じ。 6へ続く123456789
2025.08.21
コメント(0)
-
○◆○南アルプス 地蔵岳登山4 (無謀な計画に悪戦苦闘)
4 ここまで来て初めて人に会った。上から下りて来た人が滝で休んでいるところへ俺もちょうど到着したところだった。挨拶をしたと思ったら話をする間もなく下りて行ってしまった。男みたいな女だった。かなり大きなリュックを担ぎ、どんどん下って行ったところを見ると、かなりのベテランだろう。ああいう人は山で他人にあってもトクに口も利かないのだろう。 こんな山の中で見知らぬ男に変な事でもされたら逃げようもない。そういう危険を避けるためにもめったな口を利かず、接触をしない様にしているのかも知れない。しかし、失礼だがどう見ても男に襲われるタイプには見えなかった。 三つ目の滝は白糸の滝といい名前の割には情緒がなくどこにも白糸の滝のイメージはない。中途半端な大きさで、スケール、風情などこれといって取り柄がない。糸の様に千条の水がいかにも可憐に落ちて来るという姿を想像していたのでとてもガッカリした。どうしてこんな名前が付いたのだろう。もっと水量が多い時はそういう感じの滝になるのかも知れない。 富士山麓にある白糸の滝も水量の多い時は、シネマスコープのワイドスクリーンのように横に広がる180°のパノラマで糸状の水が無数に落下する。その様は白糸の滝の名にふさわしい美しい滝だが、水量が少ないと貧弱で見る影もない。たった一度見ただけで良いとか悪いとかを簡単に判断するわけにはいかないが、その時々のそれなりの味を見せてくれるのが名瀑というものなのだろう。ここの白糸の滝に関しては今年のこの時期の姿はあまり美しくない。本当の姿を見たいものだと思う。スケッチする気も起らない。時間はたっぷりあるが疲労のために集中力も欠いていて、とてもゆっくり絵など描いている気にもならない。 この辺りで昼食のラーメンを食べようと思っていたが、沢まで下りる事が出来ない。急斜面の向うに沢があり、危険そうで水の流れている場所まで行けそうもない。朝5時半に稲荷ずしを3個食べただけなので腹は減っているはずが、あまりに疲れているせいか空腹感がなく、もう少し先に延ばそう。そして、次の滝が最後ということもあり、ここでゆっくり時間を楽しもう。そうは思ったものの10分休んで次の滝を目指して登り始める。 道は増々険しくなる。かなりの勾配だ。身長ほどのところを3段4段で登る。そういう登りがづーっと続く。登っては下を見てみる。とても下るのは大変だ。どうやって下りるのだろうと思うようなところが幾つもある。木の根をつかみ、何かを掴まえながら体を支えないと登れない様なところもある。あと少し、あと1時間がんばれば最後の滝が見られる。ここまでまあまあ満足な滝に出会えた。苦労して登って来ただけのことはあった。 こんな辛い思いをして頂上まで行く事が出来れば、この苦労はきっと何かの役に立つはずだ。創作に行き詰りイライラの毎日を過ごしていた。その欲求不満と頭のモヤモヤが晴れることは間違いなしだ。脳のパイプが詰まり心の窓が曇り、自信を無くして自己嫌悪の毎日だった。これがすべて雲散霧消してリフレッシュ出来るだろう。こんな苦しい思いをし、苦しくても尚それ以上に頑張るなんてことは登山以外には考えられない。めったに体験できないことだ。人々が登山の虜になり、苦しいけれど山へ登る魅力はそういうところにある。人間は弱い生き物だ。出来れば楽をしたい。自然のままにまかせて生きていれば、楽な方へ自然に流されてしまう。いつの間にか自分を見失い、流れの上の泡沫の様に流されてしまう。こんな事を考えながら、苦しいのにまだ上に向かって登って行く姿を愛おしいと思ったりする。 登山というものは自己満足の最たるものだ。ただ山に登るだけで人生を知り、人の心を感じ、自然の雄大さを知り、己の内面を見つめる事が出来る。誰にも文句を言われず、嫌になったら自分を甘やかすことも出来る。それでもなお頑張る力が出てくるのは登山の魔力ではないだろうか。多くの人が一度経験すると病みつきになる登山。こうも単純で、それでいて奥深いスポーツがあるだろうか。たった一人で、自分だけの、メンタル的な地味な戦いのスポーツだ。 苦しくても辛くてもまだ登る。目的地に着くまでは登りつづけなければならない。そうしなければ行き倒れするだけだ。入山届けが出してあるわけでもなし、滅多に人に合わず、遭難しても身元がなかなか分からない。この時期に遭難というのはそう有る事ではないと思うが、一歩間違えば可能性はある。これだけ苦しい思いをすれば体中の毒素が全部出てしまう様な気がする。 1時間ほどして最後の滝に到着。五色の滝という。標高2,280m、美しい滝だ。スケールも大きく落差もある。すぐ下まで下りることが出来、ここでしばらく時間を過ごすことにする。まずラーメンを食べて、大きな一枚岩の上で横になる。滝の音ですべての雑念が消し去られ、うつらうつら。晴天の空に幾筋かの雲がかなりのスピードで流れて行く。山の天気は変り易いというが、大した変化もなく快晴に近く午後になっても上天気。多少の雲は有った方いい。空に動きが出て面白い。 滝の水を上からポイントを決めて追っていくと面白い。塊となって落ちてきた水が筋となって落ち始め、途中からその筋が点に変る。下の方ではほとんど点の集合で、それぞれの水が独立して落花してゆく。岩盤の上を流れ落ちる滝は、縦波となって「くの字」を下に向けた波型を作って落ちていく。どの滝を見ても糸を引くように落ちていくものなどなく、落差があればあるほど下の方では粒となって落下していく。ただ、落差がなくて傾斜のある、変化に富んだ岩盤を滑る様に落ちて来るものは、幾筋もの線を描いて交差しながら落ちていく。こういう滝が絞り染めでは表現しやすいだろう。どう表現するかは時間をかけて、じっくり温めてイメージが広がるまで待った方が良いと思う。 5へ続く123456789
2025.08.21
コメント(0)
-
○◆○南アルプス 地蔵岳登山3 (無謀な計画に悪戦苦闘)
3 しかし、夜中に出発してこんなところで引き返すなんてプライドが許さない。ヒマラヤとか北極点とかの頂点目前で引き返す時の気持ちはこんなものではないだろう。何年も何カ月も準備をし、トレーニングをし、莫大な金を使って来ているわけで、目前で引き返すというのは他にたとえようのない悔しさだろうと思う。自分だけではなく家族や友人、知人、会社の人など大勢の人々の協力と援助を受け、一身にそれ等の期待と思いを受けて出発したはずだ。色々な思いが頭の中を過ぎるだろう。こんな小さな登山でも自分との戦いがある。天候や怪我などのどうしても避けようのないものが理由なら仕方がない。しかし今の俺はたった2時間歩いて草臥れて、ギブアップしそうで、どうしようというまるでお笑い種の戦いである。 ヒマラヤを想ったら元気が出た。登ることに決めた。とに角もう少し登ろう。あといくつかの滝は見よう。その時点でもどれるか上へ登って小屋で泊まるか考えよう。こんなチャンスはそう何度もない。またすぐ出直すということも出来はしない。たぶん来年になってしまうだろう。いやそれもどうだか怪しいものだ。それなら全力を出し切ってやれるところまでやってやろう。何とかなるだろう。行き倒れになるかも知れない。でもそうはなるまい。人間の力はその気になりさえすればかなり出る。ダメだと思っても実際はまだ余裕があるものだ。 この南精進ヶ滝はまあまあの滝であった。落差もありスケールも大きく苦しい思いをして登って来た甲斐があった。ただ滝の下までは下りられず、途中から不安定な場所で眺めるだけしか出来ない。荷物を持ったまま行くのは無理な場所で、絵を描いたりできそうもない。仕方がないので写真だけ撮り、頭の中に描いて焼き付けておくことにする。この滝が良かったので次の滝への期待が膨らむ。 ここからの登りは小さな山を尾根伝いに登って行き、小山を一つ越える格好だ。根っ子の間や石の間を真上に登るような急な道で、一歩一歩がかなりキツイ。しばらく登ると今度は沢に下り、沢を横切り、再び向こう側の山腹を前と同じように登る。沢を二つ越して漸く二つ目の滝、鳳凰の滝が見えて来た。ここまで来るのに小一時間かかった。この滝はかなり上から落ちて来る、左側からと右の奥からとの二方向からのかなりスケールの大きな滝だ。しかし、距離があり過ぎるのと河原に大きな岩がブラインドとなって、右側の本流の滝が良く見えない。遠くの山から水が落ち込む垂直の滝からここまで10m以上もあるだろうか。もう少し良く見えればかなり面白い滝だと思うのに。ここでもスケッチすることは出来ず、写真撮影だけで、あまりゆっくり眺める気にもならず、少し休んで次の滝を目指すことにする。 かなり疲れているが体が慣れてきたのか、けっこう急な道だが何とか登って行ける。地図で見ると次の滝までの距離が一番近く、30分でたどり着けそうである。それにしても登りは増々キツクなる。階段と梯子の中間ほどの傾斜がある。それを真っ直ぐ上に向かって登って行く。キツイが登りはけっこう登れるものだ。ヨイショ、ヨッコラショと思わず声が出る。クソッタレ、ナニクソと力が入る。絶対登ってやる。征服してやる。負けるものか。一歩一歩に声をだして力を振り絞る。富士山に登った時よりキツイ。登山道の巾が狭く直登攀ばかりでジグザグに登って行くというより真上へ向かってハシゴをよじ登っていく感じだ。登りもキツイが下りはもっとキツそう。とても今日おなじ道を下る気にはなれない。下っても途中でギブアップだろう。 登る時は一歩一歩目標に向かって時計が秒針を進めるように、着実に前へ進むという本能的闘争心みたいなものが、苦痛を超えて足を前へと運ばせる。まさしく山と格闘している気分だ。頂上を極めることを征服という言葉で表現する、まさにそういう気持ちで登っている。やっつけてやる、負かしてやるという思いで一心不乱にその事だけを考えて登る。周りの景色や他のことに気を回す余裕がない。ただただ足元の木の根や石の露出したワイルドで不規則な地面を見つめながら、他の人が付けた靴跡を同じように踏みしめていくだけだ。他の人に出来て自分に出来ないはずはない。他人が登った山に登れないはずがない。 靴跡というのはけっこうな存在意味のある貴重なものだ。ほとんど人には会わず、小鳥以外の動物にも会わない。最初の滝までの道で猿をチラッと見掛けた以外は、心を通わす対象や意志の交感をするものが何もない。靴跡だけがそこに人間の存在を証明するものとしてあり、登山コースの案内役でもある。道に迷いそうになった時に周囲の靴跡を見つけることによって正しいコースを発見することができる。もし最後に通った登山者の靴跡が雨で流されてしまったとしたら、迷ってしまうだろうと思われる所が数か所あった。 登山者にとって、雨の日と日没後の登攀はかなり危険なものだ。雨が降れば流されてしまうコースや鉄砲水で水没したりして通れなくなる所や、がけが崩れて通行不可能になる所など至る所にある。夜間の登攀も怖い。今回は雨具も懐中電灯も用意しておらず、もし途中で雨が降ったらずぶ濡れになって体温が下がり、当然気温も急降下するため体力を消耗して衰弱していまう。下山途中で日が暮れてしまえば真っ暗で一歩も歩けず、ビバークを余儀なくされる。その結果、寒さに凍えて遭難という事にもなり兼ねない。 今日はどう足掻いても下山して車に戻ることは無理になって来た。30分ほどで着くはずが1時間近くもかかってやっと三つ目の滝にたどり着いた。何とキツかったことか。もうどんな事が有っても下山ということは考えられない。足がもたない。登るよりも数倍疲れる感じ。今から下山したとしても、とても明るい内に麓までたどり着けそうにない。 登り始めてから4時間以上経っている。10時50分。コースの所要時間をもうじき過ぎようとしている。考えが甘かった。思ったよりも山は手強かった。日帰りなどとんでもない話だ。標準タイムもクリアできない。まだもう一つの滝を越えて、それからかなりの距離を登ってやっと鳳凰小屋までの所要タイムとなる。この分だと小屋まで行くのに7時間以上掛かりそうだ。標準の5時間を2時間も余分に掛かることになる。もうこうなったら小屋で泊まるより仕方がない。そうと決まれば急ぐことはない。今日一日をゆっくり過ごせばいいわけだ。たっぷり時間をかけて滝を観察し、山登りというものを堪能すればいい。 4へ続く123456789
2025.08.21
コメント(0)
-
○◆○南アルプス 地蔵岳登山2 (無謀な計画に悪戦苦闘)
2 5時半ごろに目覚め、丁度日の出の時刻で八ヶ岳と富士山が朝もやの中に浮かび上がっていた。これから全身に朝の化粧を施すところで、淡いブルーにピンクがかった雲が少しづつ色を変えていく。一日の始まりの儀式がおごそかに進行していく。薄ねずみ色の富士が少しづつ明るさを増し、辺りの山々に威容を誇るように雄姿を表そうとている。これからの今日一日のすべての成り行きを静かに見守ってくれるという、頼もしさと心強さを感じている。 さあいよいよ、林道を上って登山口までたどり着かなければならない。まずは第一関門である。林道の入り口は直ぐに見つかって、ドンドン上って行くことにする。上り始めてすぐに大変な道に入り込んでしまったと思う。急こう配な上に殆ど整備されておらず、車の腹はつかえるし悪くすると途中で岩などが道をふさいで通行不能になっているかも知れない。少し上ると「一般車通行禁止」の看板があった。迷わず無視して上る。こんな所でウロウロしていては目的地の滝どころか登山口までたどり着けない。途中、林業用のワイヤーロープが渡してあり、まさしく林道なのだと思う。とても一般の乗用車が通る道ではない。 一瞬、何時だったか美しヶ原へ裏道から上る道で、雪のために上ることも下ることも出来なくなって思案に暮れ、幸いにもジープに引っ張ってもらって難を逃れた時のことを思い出した。この時も一般車どころか車両通行止めの看板を無視して上って行った挙句のアクシデントだった。この時は4月か5月のまだ雪が残っている最悪の時期だったが、今回は秋だし雪が残っているはずも無く雨も降っていない。それほど道が荒れているとは思えない。しかし、4WDでも上れないところが有るかもしれないという心配がずっと付いてまわった。 30分も走ると道も落ち着いてきてゴロゴロする石などもなくなり、尾根に近づいたのが分かった。空が開けてきて向こう側の山々が見えた時はさすがに安堵した。尾根伝いの道ならば水の出てくる処もなく急な坂もないので安心して走ることができる。ここへ来て初めてセカンドギヤが使えるようになった。ずっとローギヤのままで上ってきたのだ。ここまで来ればもう時間の問題。写真を撮って一息入れ、一気に目的地へ向かう。 青木鉱泉に6時半着。1時間も掛かった。あんな山道を1時間も走って来れば疲れるはずだが、心はもはや滝にありだ。直ぐに車を置いて登山道へ。「無断で車を止めて登山しない様に」との看板をここでも無視して登り始める。 ルンルン気分だ。2時間で最初の滝に着けるはず。ガンバレば2時間も掛からんのじゃないか。どんどん登るがけっこうキツイ。上ったかと思うとすぐ下ってしまい、また上がる。足場は砂と土の平らな道で歩きやすいが、けっこう急なのだ。途中、山砂が斜面を覆っており、上から雪崩の様に道が流れているところがある。その急な斜面を横切る形で道が続いている。かなり高い。もし足を滑らせて落ちれば岩に当たって怪我をせずには済まないだろう。慎重に腰を低くしへっぴり腰でどうにか通過する。そうかと思えば、沢を横切る時に大きな岩を越えないと先へ行けない所がある。上るのはいいが下りるのがチョット大変で、バランスを崩せば真っ逆さまに転落なんていう恐いところも有る。こういう登山道を歩く経験がないので、とに角初めての体験ばかり。 だんだん道に変化が現れてくる。滝は近いに違いない。そう言えば水の音がする。あれはきっと滝に違いない。自分の居る場所は谷からは距離があるが、かなり大きな滝なのだろう。音に釣られて喜んで登っていくと滝などはなく、谷川にコースが近づいて水音が聞こえただけのこと。がっかりだ。結構疲れて来た。チョコレートを齧りながら歯を食いしばって登る。8時頃にやっと滝らしいところへたどり着く。登り始めて1時間半。やっぱり地図のコースタイムより30分も早かった。あれだけ一所懸命登って来たんだから当然だ。やれやれだ良くやった。ひとまず休憩することとする。 しばらく写真など撮ったりして休む。次の滝までの体力を回復しなければいけない。かなりきつかった。草臥れた。それにしてもあまり大した滝でもない。2段になってはいるが規模が小さく裏切られた感じ。まあ一番下の滝なのだからこんなものかも知れない。次を目指して登るしかない。ここまで来たんだから是非、全部の滝を見てみたい。頑張って登ろう。 気持ちを入れ替え新たなエネルギーを湧き出させて、次の滝を目指して登り始める。30分も登るとすぐまた滝があり、今度は立派な看板が立っている。「南精進ヶ滝」と書いてある。さっきの滝は何だった。名前も付いてない只の滝。どうりで小さな貧弱な滝だと思った。ここまで2時間かかっているわけだ。そうすると地図にあったコースタイム通り2時間たっぷりかかって最初の滝まで登ってきたことになる。あれだけ目一杯に人一倍早く登ったつもりだったのに一般の所要時間どおりだったなんて。 ここから小屋まで3時間と書いてある。今まで2時間歩いてきて腿はパンパンに張っているし、かなり草臥れている。これからますます登りの道は険しくなるだろう。2,000m以上の山だから空気も多少は薄くなるかもしれない。この調子でコースタイム通りの3時間で小屋まで行けるのだろうか。 今の疲れ具合からみて、今までのコースの事を考えるととても3時間では登れそうにない気がしている。それどころか最後の一番上の滝までたどり着けるだろうか。もし途中でギブアップしたとしたら同じコースを下って、車の有るところまで戻らなければならない。膝も腿もかなり疲れている。下るにしてもかなりキビシイのではないか。足が言うことを聞かず無理をして滑落でもしたら大変だ。ここまでまだ半分も登っていないところで弱気になっている。やはり無理だったのだ。41歳、若くはないのだ。日ごろ足腰を使っていないのだから急ににこんな本格的な登山は無理なのだ。今からなら引き返せる。もっと上まで行ってから戻るのは体力的にも無理な気がする。 3へ続く123456789
2025.08.21
コメント(0)
-
○◆○南アルプス 地蔵岳登山1 (無謀な計画に悪戦苦闘)
中年に差し掛かろうとする頃、悪戦苦闘して登った山の手記が見つかったので、記録として残しておきたい。脱サラして染色作家としてスタートし、作品作りに取り組んでいた時期で、テーマとモチーフを追い求めていた。「南アルプス 地蔵岳登山」 (1990年9月8日~10日)1 滝をテーマに作品を作りたくなり、さっそく登山行となった。思いつくと直ぐにやらないと気が済まない。何はともあれ登山に行くのだと決めたのが前日の金曜日。地図を広げて岐阜県を中心に滝をマークしていくい。岐阜県は滝が多い。あちこちにあって、不動滝とか大滝という名の付いた滝が無数にある。場所はやはり山岳地帯の上の方に偏っており、当たり前だが簡単に行けるところに滝はない。 状況から考えても険しい山岳地帯でなければ滝などあるはずもない。それもある程度の規模と雰囲気のある滝となると、条件は限られてくる。結局、岳人別冊「‘90の夏山」の付録地図によって、南アルプスが中央自動車道が使えるところに絞った。甲斐駒ヶ岳の東南に位置する鳳凰三山に四つの滝が連なっているのを発見。それも、一つの登山ルートを登って行けば四つとも見られるようなのでこれ幸いと、ここに決めた。 ドンドコ沢という沢沿いの登山道で最初の滝までおよそ2時間。そこから鳳凰小屋まで滝を順に見ながら3時間で登れると、地図にはコースタイムが書いてある。片道(登り)5時間、下りが3時間20分で、計8時間20分。写生をしたり写真を撮ったり、昼食のラーメンを作って食ったりすると10時間ほどの必要最小限のタイムとなる。コースタイムの通りに登れれば滝だけ見て日帰りも可能かと思えた。 地図で見るとほんのわずかな距離にしか見えない。登山道の入り口までの林道の長さの方がはるかに長く大変なように見える。ところがだ、等高線をよく見れば分かるのだが、標高差が林道とは全く違うのだ。そんなこともロクに考えずに標高2000m以上の山へ、ロクな準備もせずに登るというのだから無茶な話だ。 心は久し振りの登山でウキウキしているし、以前からどこかの山へ登りたくてウズウズしていたところだ。滝を見たいというのは口実に過ぎなかったのかも知れない。今年は息子と富士山へ登る約束までしていたくらいだ。小型のリュックはだいぶ前に買ってあったし、今年の夏のキャンプに必要だからとキャンプ用のガスコンロも買った。登山に必要だからという気持ちが半分以上を占めていたように思う。 自分を試してみたいという思いもあった。ヒザが弱って来ていて、運動は必要だがあまり激しい運動は止めた方が良いと医者に言われていたこともあって、果たして登山が出来るのかやっぱり無理なのかを確認したい気分もあった。息子との富士登山は、息子が風邪をひいたり身内に不幸があったりで行く事ができずにいた。来年こそ行こうと言ってはみたが膝の不安を持ったままだ。密かに試す機会を待っていたのだろう。これでダメなら諦めるしかないなと、覚悟の登山だった様に思う。 妻と結婚前に富士山に登ったのが20代の半ば過ぎ。その時以来の山登りということになる。スポーツらしいものは何もしておらず、普段から運動不足気味である。週2~3回の7kmのジョギング程度では筋力を維持するのは難しい。しかし、何もしてないよりはましだろう。 日帰りが無理なら上にある鳳凰小屋に泊まればいい。地蔵岳の頂上途中ににあり、泊まると決まれば頂上まで登ることも夢ではない。2,700m程の山へ一日で登れればままあ自信を持ってもいいのではないか。しかし、富士山以外に2,000m級の山へ自力で登ったことはない。乗鞍はスカイラインの終点から少し歩くだけで頂上に立てる。木曽駒にしてもロープウェーでほとんど登ってしまうのだから、これらの山へ登ったとしても登山をしたとは言えないだろう。 とにかく登れるものなら地蔵岳の頂上までは行って見たい。一応日帰りと泊まりの両方を頭に入れて準備をする。車での仮眠用に毛布とシュラフ。どちらが良いか使って見て決めることにする。それにクッション。運転はなるべく楽な方が良いので短パンに草履を履いていく。リュックには二日分の昼食用のラーメンにガスコンロ、長そでシャツ(アンダー用と上着)、ベスト。セーターを入れたいが入らず止める。食器と鍋。鍋は柄が邪魔なのでビスを外しておく。カメラ・フィルム、厚手の靴下の予備、タオル、バンドエイド、スケッチブック、地図。たったこれだけでリュックが一杯になった。重さを量ってみたら丁度5kg。俺の体力ではこれぐらいが限度だろう。 夜10時ごろに出発すれば、早朝登山で涼しくて気持ちがいいだろう。時間の配分からいっても充分のはずだ。夕食後、少し眠っておこうと思ったが甥っ子二人が泊まりに来ており、落ち着かなくて眠ることができない。10時に甥っ子に「早く寝なさい!」と一喝して、Tシャツに短パン、草履履きでいざ出発。 小牧インターまで1時間もかかった。41号線が工事中でまことに走りづらく、思ったよりも時間がかかってしまった。途中、恵那で仮眠し、韮崎に2時半頃に着く。深夜スーパーで朝食の稲荷ずしとパンを買い、ついでに林道の入り口までの道を聞く。甲斐駒ヶ岳に登るなら白洲から入る人が多いと店員が言うが、自分はすぐ近くの林道から上がる予定でいる。地図を出して来てくれ、凡その道を教えてもらう。言われたとおりに行って見るが深夜の事で入り口が分からず、もし間違えてとんでもない道へ入り込んでも大変なので、とりあえず夜が明けるまで眠ることにする。Tシャツ短パンのまま毛布をかぶって寝たがやはり少し寒かった。 2へ続く123456789
2025.08.21
コメント(0)
-
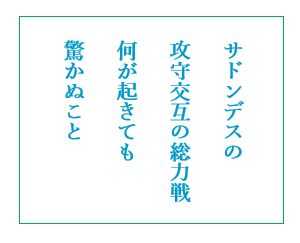
☆◆☆甲子園 準々決勝が一番面白い
♪ サドンデスの攻守交互の総力戦何が起きても驚かぬこと 高校野球はベストエイトの準々決勝が一番面白い。まさにその醍醐味を見せてくれた昨日の試合。 第1試合:「去年の優勝校・京都国際×山梨学院」 大谷翔平(二刀流&盗塁王)の再来と言われる2年生のエース・菰田陽生(身長194センチ、体重100キロ、50メートル走6秒4の俊足)は、疲れが出て四回途中降板したものの、五回には走者一掃の三塁打を放ち、結局11:4で快勝。 前の試合は、岡山学芸館を相手に6回途中1安打無失点の快投、打っても4打数3安打3打点の活躍。3回に150キロを計測(自己最速の152キロ)して、その片鱗を見せつけている。14:0の大勝。 今日1日休養日があるので21日、準決勝:第2試合の沖縄尚学戦で、投打に活躍する姿が見られるだろう。 第2試合:「日大三×関東第一」の東京同士の対決。5:3で日大三が接戦を制した。 4回に代打で登場し先制のタイムリーヒットを打った豊泉悠斗選手は、これがこの夏、地方大会も含めて初めての打席。「必ず出番が回ってくる」と信じて、朝も夜も時間があるときには素振りを続け、準備を怠らなかった。 この試合に向けて「相手エースのカーブだけにねらいを絞る」と左投手のカーブに設定したピッチングマシーンを使って練習取り組んできたという。 三木有造監督は、そんな豊泉選手を「チームでいちばん練習をしているし、変化球を打つのも得意」と、四回1死一、三塁に代打で起用。期待に応えて3球連続のカーブの後、5球目の外角のカーブをミートして三塁走者を呼び込み、打線に勢いを与えて3点をものにした。 高校球児の鑑となって、語り継がれていくことだろう。 第3試合:「選抜優勝校・横浜×県岐阜商」 痺れるほどの好試合。県岐の藤井監督は「100回やったら99回負ける相手、その1回を掴むための心得を選手の心に叩き込んだ。「いろんなことが起こるだろうが、すべては想定内。甲子園で『お祭り』をしよう」 五回を終えて4点リード。勝利がチラつき始めるとミスが起きる。六回の守備で、1死満塁で二ゴロのダブルプレーチャンス。一塁手の足がベースに届かずセーフとなり、焦った一塁手が無人のホームへ送球してしまい、2者が生還。 八回にもエラーで追いつかれ、延長タイブレークの十回にもエラーで3失点。 そんな窮地でもベンチは、「いいゲーム!いいゲーム!」と、明るい言葉だけが飛び交ったという。坂口の適時打で三塁走者和田は生還し、サヨナラ勝ち すかさず3点を奪い返し、同点の十一回裏2死一、三塁。ミスをした一塁手のライナーが三遊間を破りサヨナラ勝ち。気が付けば、3試合で1失点の横浜から16安打8得点。 あらゆるアクシデントを「想定内」とポジティブにとらえ、延長十一回の壮絶な戦いを「快哉のお祭り」にして魅せた。「明るくないと楽しくないし、楽しくないとうまくならない。常に明るく、前向きに夏のてっぺんを取りに行こう」と、ことし春の岐阜大会で準々決勝で敗退したあと、3年生が集まってみずから目標を立てたのだという。 九回のサヨナラのピンチ。レフトがピッチャーとサードの間に入り、「内野5人シフト」を敷いた。この内野5人が前進守備の状況で、スクイズを強行したことに驚いた。 軽く当てれば打球が頭上を越える可能性と、スクイズが成功する確率を考えるとどうなんだろう? 転がったボールを捕った、ファーストのグラブトスは見事だった。スクイズを見事に阻止したのは、月に1度は練習していたという成果が、見事に出た瞬間だった。
2025.08.20
コメント(0)
-

☆◆☆なんてことないことをそこはかとなく・・
♪ 休肝日なくて労う臓のため服用している百薬の長 昨日、16,700歩も歩いてしまった。距離にして12キロほど。朝のうちはまだ下半身に疲れが残っている。 復路はけっこう疲れて、“こんなに歩くんじゃなかったなぁ” と後悔するものの、7キロを過ぎたあたりからウォーキングハイとでもいうのか、体が軽くなる感覚があった。残った力で家までゆうゆうと運んでくれた。 2時間半ほどの早朝ウォーク。ついでに庭の水遣りもし、シャワーを浴びることも無かった。 やはり、こういう事は涼しいうちにやるべきだと実感した次第。 16時ごろ用事があって出歩いたが、一番暑い時間帯で37℃ほどあったようで、ものすごく暑かった。クーラーの効いた部屋からいきなり猛暑の中に出るわけで、身も心も悲鳴を上げる。 暑いさ中、郵便配達がバイクで簡易速達を届けに来た。 「暑いので大変だねぇ!」と声を掛けると、「冷感スプレーを下着に掛けておくと涼しいんです」 「へえ、どのくらい効いてるんですか?」「8時間は大丈夫ですねぇ」「クール何とかという涼しいシャツが有るでしょう、それに掛けると、10数時間ずっと涼しいですね」「夜、それを着て走っていたら寒かったくらいです」「普通のシャツなら裏表に掛けるんですけど、これならチョン、チョン、チョンと掛けるくらいでいいんです」「肌が弱い人はかぶれたりするらしいです」 なんだかよく喋る人で、「冷感スプレーの営業マンみたいだねぇ」と。「クーラーの効いたところに行く場合は、防寒着を持っていくんです」 「メンソレータムと同じ成分なんだろうね」「一日中外で作業する人にとっては有難いねぇ」「良い時代になったもんだ」 私が知らなかっただけで、巷ではこの猛暑に対抗するために様々な工夫と、そのためのグッズが色々用意されているようだ。【2025年版】最強の冷感スプレーおすすめ20選!【服・肌用など目的別に紹介】 1日中クーラーの効いた部屋で好きな時間を過ごす。 外へ出たついでにコンビニへ立ち寄って、缶ビールとワインを買って帰る。 顔見知りの店員は、酒はま全く飲めないらしく煙草も吸わないという。でっぷりと出たお腹はそお反動なのかもしれない。 シフト制だがほぼ一定の日時に決まているらしい。以前、名古屋短歌大会に出した歌は彼らを詠んだもの。 「北鮮の番兵のごとく真夜中を立ちつづけおるコンビニ店員」 ある日、客が居なくて暇そうにしているので「こんな日は楽でいいねぇ」と声を掛けたら、「そんなことないです。荷物は入って来るし、やることがいっぱいあるんで!」とため息混じりの言葉が返って来た。“暇で楽” なんて仕事はないんだよなぁ。 この日は夕前からワインを飲み始め、ほぼ1本飲んでしまった。チリ産の安いワインだけれど、「ぺヴィーノメルロー」辛口・ミディアムボディーは美味しい。12%の度数はほろ酔いまで。久し振りのワインで、ノメルロー好きな私はいくらでも飲めてしまう。
2025.08.19
コメント(0)
-

☆◆☆早朝ウォーキング
♪ 雲の嶺遠く浮かべて海原は熱きエナジーいや増すばかり 今日はまたトンデモナイ猛暑の予報が。名古屋でも39℃とは・・。 知多市でも38℃となっている。ウォーキングを早朝に済ませることにし昨夜は早めに寝た。クーラーは点けっぱなしで階下で寝た。21時ごろにアランがちゃっかり、私の枕を使って寝ていたのはかわいかった。 今朝は4時過ぎに起きた。ちゃんと起きられたのはエライ。軽く準備運動をしていざいざ。 こんな時間にウォーキングに出るのは何年振りだろうか。一応、右回りの定番コースで秋葉神社経由で、調子が良ければ佐布里池まで行くつもり。 「明けの明星」を見るのは何十年振りだろうか。その上には木星が見える。 寺本駅の跨道橋から東の空を見る。日の出は5時14分。まだ少し間がある。ほぼ快晴の空。わずかでも雲があると空に表情が出る。秋葉神社なんとか駆け上がって、定点観測の場所へ。この伸び放題の草の向こうに日が昇ってくる。足で踏み倒して端まで行かねばならない。 日の出前の東の空を、飛行機雲が一部に日を受けながら伸びていく。その先端はモノクロの軌跡となって、よく分からない。そのまま先へ先へと伸びていく。 上空はかなり湿度が高いことが窺われる。 10分後のパークロードから眺める飛行機雲は、白く輝いて飛んでいく鳥のシルエットを浮かび上がらせている。 過去にない暑さをもたらす太陽が、ズンと顔を出した。 5時過ぎともなると、歩いている人も増えてくる。今朝は10人ほどに声を掛けただろうか。挨拶をしてもまともに返してくれる人は少なく、みんな無口。反応があっても、声は小さく活気がない。向こうから挨拶してくれたのは、中年のおばちゃん一人だけだった。 キジバトがあちこちにいて、同じメロディーで啼いている。かなり近づいても逃げない。何かを伝えあっているのだろうか。 縄張り争いをするようなタイプには見えず、おっとりした風貌のとおり、争いが苦手な鳥なのだろう。 庭作りの上手な主らしい、気の利いた植栽に感心させられている家。行灯仕立てのノウゼンカズラが満開で、その花に朝日が当たってひときわ目立つ。 別方向からのジェット機が、新たにタテの白線を引いている。勝手に熱を上げて調子づいている空に、くさびを打ち込むごとくに。 ギラギラとその本性を表そうとする太陽が、鏡のごとき水面を利用してその威力を誇示して見せる。 トランプが、プーチンが、自己顕示の威光を光らせるごとく、太陽までもがたっぷりと蓄えた熱量をかさに着て、ギラギラとその魔性を振り撒き始めている。 何の抵抗も出来ない無力な生きものたちは、ただじっと耐えいるばかり。 空中に溶け込んで消えてなくなる振りをして、黙って引っ込んでいるようなことはない水という魔物の化身。太陽と結託して、過剰と渇望をランダムに繰り出しては人を手玉に取る。 高砂百合があちこちに花を咲かせている。繁殖力が強くその数を増や続けている。 花言葉は「純潔」と「無垢」となっているが、その白い楚々とした花の姿からのイメージでしょう。結婚式でも葬儀で使われる、便利で使い勝手がいい花で、それは個性がないということにもなる。まるで個性を殺し、目立たないように気を遣って生きる日本人そのもののよう。 トランプとプーチンの会談には是非、この高砂百合で会場を飾ってもらいたいものだ。
2025.08.18
コメント(0)
-

☆◆☆熱帯地域よりも暑い。米ロは逆に冷たい関係のまま・・
♪ 暑くても熱(ほとお)る珈琲しか飲まず汗にぬれおるホットなパンツ 夕べは暑かった。雲って空には蓋がされた状態で放射冷却もなく、その上に風もほとんどなかった。気温も27~28℃もあり、湿度が90%台と熱帯地域以上の暑苦しさ。 こりゃあベトナムよりも暑いわ。日中の最高気温で見ると、日によって4℃~9℃も違う。 赤道直下のインドネシア(ジャカルタ)でも、東京以西は日本の方が暑い。日本の夏は熱帯地域よりも暑いという、トンデモナイ国になってしまった。 高気圧が居座り、太平洋の水温は上がる一方。赤道付近と大差が無いし、高気圧の縁を回って南から熱せられた空気と海水が押し寄せてくる。海水温GPV Weather予想気温 これにフェーン現象が重なってくる。山岳国であるがゆえの日本独特の気候とも言える。 2016年の調査で、外国出身者の8割が『日本の夏は母国より過ごしにくい』と答えている。 熱帯地域出身者でも6割が『母国より過ごしにくい』と感じている 。9年後の今は、その割合はもっと増えているだろう。 何度もこんなことを書いている私の頭も、かなりおかしくなっているかも知れない。10時になって、この部屋はすでに34℃まで上がっている。 本当はトランプのことが書きたかったはずだが、横道に逸れてからなかなか元に戻らない。 15日(日本時間16日早朝)アメリカ・アラスカ州のアメリカ軍基地内で行われた首脳会談。プーチンに異常なほど気を使い、赤絨毯まで敷いて迎えたトランプの顔は、緊張でいつもの覇気もなく終始口数も少なく、主役を奪われてしまった感があった。 共同会見では、トランプ大統領もプーチン大統領も停戦について言及もせず、プーチンが主導的な立場で一方的にしゃべっただけの会談だったようだ。アラスカは1799年、当時のロシア帝国が所有を宣言。その後、クリミア戦争で敗れて財政不足に陥り、1867年にアメリカに720万ドル(現在だと220億円に相当)で売却された。 プーチンにとっては、トランプ大統領と直接会談を行ったうえ、トランプ大統領の専用車に同乗するという破格の厚遇を受け、プーチン大統領は「孤立している」という自身への見方が大きく転換し、「世界の重要な問題はロシア抜きでは決めることができない」という印象をつけられたという論説があったぐらい。インドなどへの石油の2次関税を先送りすることにも成功している。 トランプ大統領は会談の手応えについて問われ、「10点満点だ」と述べて、みずからの成果を強調して見せたが、実情は「0点」だったというのが本当のところだろう。
2025.08.17
コメント(0)
-

☆◆☆飼い猫アラン 歌3首
♪ 潰したと思いし蟻が歩き出す暑さはいまだ衰えしらず アランは人のそばにいないと安心しない。特に私のそばが良いようで、どこにいても近くにやって来ては横になっている。 そんなアランの8月の様子を、スナップ写真で見てみよう。国内最高記録41.8℃が出た日。クーラーを点けたリビングに布団を持ち込んだら、その上に乗って来た。この日もかなり暑い。何を思ったか、PCの机の下に入ってきた。カミさんの掃除機の音に驚いている。九州で大雨が降った日。立ってTVを見ていたら、その足に頭をもたげて横になっている。私が行く前からPC後ろの本箱の上で寝ている。この頃は、夜もこの上で寝ているらしい。どこぞの猫が家の中に入って来て、追いかけられた日以来しばらく続いていた。前日から雨で涼しかった。久し振りにベッドに乗ってきて、朝までずっと一緒に寝た。先に起きたが、しばらくここで寝ていたようだ。日本列島、大雨で水浸し。涼しいので如何にも嬉しそうだ。こんな姿はしばらく見られなかった。日が落ちて、アランも一所に夕涼み。座ってやれば、ピタッとくっ付いてくる。暑いと出来ないが曇りだったので、アスファルトも灼けておらずいい気分。暑さがぶり返して、一層暑く感じた日。クーラーを点けたら涼しすぎたらしい。となりに部屋に避難してピアノの上に。冷たくて気持ちがいいらしい。夜は、そばに来てもすぐに、クーラーから離れた場所に移動して横になっている。 今食べている餌が気に入らない。何度も私に向かって要求して来る。同じ餌ばかりもよくないので交互に変えるようにしている。この前に食べていたのがお気に入りの様で、食べ具合がまったく違う。 しょうがないので、高級なのを少しだけ混ぜてやる。するとその混ぜたものだけを選んで食べてしまう。そして、しばらくするとまた擦り寄って来てはにゃーにゃーと鳴く。 鼻先を押し付けたり、足の周りにまとわりついて鳴く。最初は何を言っているのか分からなかったが、鳴きながらする寄って来るのは餌が欲しい時だとようやくわかった。餌はさっきやったばかりなので、違う事を要求しているのかと思っていたが、違うのだ。鳴いて甘えているのは、ただただ餌が欲しいだけなのだ。 それで無視していると、しばらくは大人しくしている。やつも考えていて、インターバルを取って気をそらし声色も変えて、新たな雰囲気を作りあげて再び鳴きに入る。 それでも分かってもらえないと腹が立ってくるようで、終いには “ガプっ” と噛みついて来る。甘噛みとは思えない痛さで、そうなるとこっちも腹が立ってくる。 「俺はお前の餌係じゃないんだよ、たいがいにしてほしいわ」 呼んでも返事をしないし、こっちの言うことはまったく馬耳東風、猫の耳に説教。一方通行もいいところで、逆走したくもなるというもの。可愛いんだか憎たらしいんだかわからなくなってくる。♪ ツンデレノ猫ニ爺サン斑斑(ムラムラ)シ憎サアマッテ仲良シコヨシ♪ じゅうにぶんかぞくにありてなにもせずひがなねているねこにさちあり♪ 恣意自由正体不明自然体猫科猫属優美生物
2025.08.16
コメント(0)
-
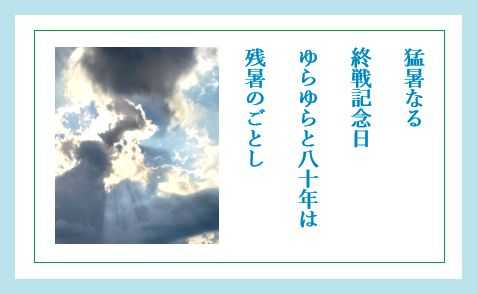
☆◆☆ウォーキングと短歌
暑くなるので朝早くにウォーキングへ行くつもりだった。それが、よく眠れたお蔭で寝坊してしまった。何だかんだで、結局、家を出たのが7時50分。 朝のうちは雲っているが間もなく晴れて来るという、固まる前の茶わん蒸しのような空だった。秋葉神社から定点観測境内はまめな管理がされていないようで、草が繁っている。 境内に幾つかの高砂ユリが咲いていた。神社から少し行くと、畑の横にも幾つか咲いていた。この時期、あちこちで咲いているようだった。♪ 高砂や笹に鉄砲白百合のゆれて乙女の立ち話かな8時半ともなれば太陽は銀ギラ銀だ♪ アイドルに銀ギラ銀を歌いたるマッチたちまち還暦をこゆ♪ 朴の葉の箱をはみ出す裏の顔白き歪みを見せられているトランプ大統領をイメージしています。 ♪ 藤の実のあまた下がりぬ国民の義務とて五人の子を生せし父母♪ 立秋を踏みつつ歩き見上げれば空を占拠のああ 夏ばかり
2025.08.15
コメント(0)
-
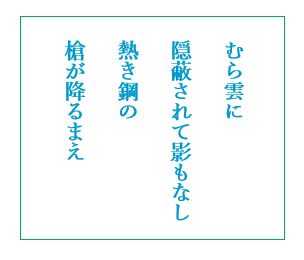
☆◆☆フェイクの空にカラスの声がひびく
♪ むら雲に隠蔽されて影もなし熱き鋼の槍が降るまえ 新暦お盆も始まっ田中、暑さがぶり返してくる。大雨を降らせた前線は高気圧に蹴散らされて消滅し太平洋高気圧が日本全土を覆ってくる。 沖縄や九州から近畿、北陸は、真夏のような強い日差しが照りつけそう。午後は山沿いを中心に雨雲が湧いて、雷を伴った激しい雨が降る所もある。 東海や関東甲信は雲が多めながらも、昼前後を中心に晴れ間が出そうです。午前5時現在、静岡県から山梨県を中心に雨雲がかかっている所があり、夜にかけてもあちらこちらで雨が降り、午後は雨脚が強まる可能性。 東北と北海道は晴れ間が出ますが、次第に雲が増えるでしょう、夜は日本海側で雨の降りだす所がありそう。 「日本気象協会 tenki.jp」の気象予測「JWA統合気象予測」、2025年1月~6月の予報精度結果が発表されている。“雨が降ると予報した日に、実際に雨が降ったか”という点に着目し、「当日の降水の有無の適中率」の検証したもの。 気象庁よりもわずかに精度が高い。「当日の降水の有無の適中率」は、朝5時発表の予報をもとに、その日の5時から24時までに合計で1mm以上の降水があるかどうかを評価。 このため、ある地点で雨が降る時間帯が予報と実況で異なっていたとしても当日のどこかの時間帯で雨が降れば(もしくは雨が降らなければ)、天気予報が当たった(適中)として評価される。「翌日における1時間ごとの天気予報の適中率」 いずれの月においても気象庁の適中率を上回っている。 かなり厳しい評価基準を設けて、独自に算出していているようです。 気象庁の「天気分布予報」の翌日の天気予報を用い、実際の天気として気象庁の推計気象分布の「天気マーク」を用いて、1時間ごとに比較し、予報の適中・不適中を判定。晴れ・曇り・雨・みぞれ(雨または雪)・雪の予報と実際の天気が、1時間単位でぴったりと当てているかどうかを厳しく評価している。 例えば、ある1時間で晴れと予報しても、実際に少し雲が広がり、曇りになった場合の適中の判定は「外した・不適中(×)」となる。 いつも、エリア単位(知多市)の天気を気象協会の予報と、ウェザーニュースの予報の両方を確認しているが、日によってはかなりの差がある。 観測している場所が違う事もあるが、県単位の予報よりも制度は高いはずだが、気温が2度以上、降水確率もかなり違う時があるのでどんなものかと思っていた。 精度は、やはり気象協会の方が高いと思う。 ウェザーニュースは “最も当たる天気予報” と宣伝しているが、こんな精度比較などはしていないだろう。☆ 「日本気象協会」は1950年気象庁から独立し財団法人となって、しばらくは外郭団体の立場だった。1993年に天気予報が自由化され、ウェザーニュースが躍進するのに対抗し、2009年にウェザーニュースと競争できる組織編制となる。 そして様々な予報サービスを提供するようになり、国内ではウェザーニュースに引けを取らないコンテンツを持っている。 朝から曇天で、モノクロの空をバックにハシボソガラスが電柱の上でしきりに啼いていた。 体を前に伸ばして頭を上下させながら喉の奥から絞り出すようにして啼いている。2~30メートル先で、こっちを向いて啼いているのでかなり喧しい。 英名で「Carrion Crow(死肉を食うカラス)」という。啼いては周りを窺い、再び啼くというのを繰り返している。 ハシブトガラスならそれほどでもないが、昆虫類・鳥類の卵や雛・小動物・動物の死骸・果実・種子など何でも食べる雑食性のハシボソは、如何にも下卑た品のなさを感じる。 緑地帯で蝉の死骸を食べているらしく、毎日のように2羽が餌を物色している姿を見かける。 市役所前のヒマワリは花の時期も終わり、下を向いて最後の結実の時を待つばかり。 曇っていて涼しい風が吹いているので、如何にも盛夏は過ぎたような雰囲気だが、これはフェイクだ。真っ黄色な嘘だ。 黄色は、高貴な色、ポジティブな色という印象があるが、キリストを裏切ったユダを指す色ともされている。また、衰退・病気・憂鬱など、否定的な意味も持っている。 灰色の空に朽ちかけた黄色の花、そして、まっ黒なカラスの啼き声が響く、お盆の朝だ。
2025.08.14
コメント(0)
-
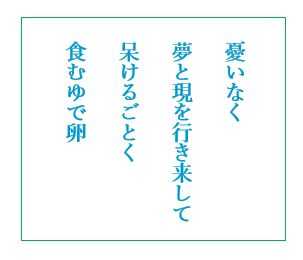
☆◆☆「騎士団長殺し」を読んだ
♪ 憂いなく夢と現を行き来して呆けるごとく食むゆで卵 決して読書家とは言えない私が村上春樹の「騎士団長殺し」を読んだ。上・下巻あるかなりの長編。いつもは集中して読むことが出来ず延長したりすることが多いのに、今回は真面目に向き合って上・下それぞれ10日ほどで読み終えた。 第1部 顕れるイデア編、第2部 遷ろうメタファー編というタイトルからして難解そうなもの。村上ワールドへ一足一足、探るように踏み込んでいった。 小説は虚を書くものであり、そのことを思い知らせてくれる村上作品だが、イデアが姿を成して介在して来るという発想には驚くばかり。そして後半にはメタファーが・・。 詳しいことを書くには及ばない。「note」に思考家、文筆家の佐々木敦氏が「村上春樹『騎士団長殺し』論」で詳しく書いているので、興味のある方はそちらをどうぞ。 この分厚い本を飽きさせず読み続けさせるには相当の技とテクニックが要る。次へ次へと展開の先を読みたくなるような文章に引っ張られて、ページをめくらせる技量ははさすがのもの。 記憶というものが人間の根幹をなすものであり、人は記憶で作り上げられていると言ってもいい。多くの小説家は記憶をテーマに据えて物語を紡いでいく。この物語もそのようなもの(時間)が重要な要素になっている。第2部 遷ろうマタファー編(拡大) 何かによって引き起こされたものが、どこかで繋がっているというようなことは、小説ではよく出てくるが、この小説も登場するものすべてが繋がっていて、それは結局、自分そのものなのだというところに帰結する。 佐々木敦氏が書いている。イデア(事物の本質)によって引き起こされるそれらのものは、「私」そのものなのだ。「免色渉」=「白いスバル・フォレスターの男」=「顔のない男」=「私」という等式、「メタファー」の連鎖が成立する。「秋川まりえ」=「コミ」=「ユズ」=「ムロ」という等式が存在する。 この小説はミステリーではなく、村上春樹自信を描いた小説であると。 村上春樹は直喩を多用する作家だ。時々それがあまり上手い表現ではないと思うことがあって、意図的にそうしているのかと勘繰ったりする。 また、この小説に限ってのことなのか、説明が過剰に感じる部分が幾つもあって、そこまで書く必要はないんじゃないかと訝りながら読んだ。そういう無駄な部分を省いたら、もっと短く出来るのにと思ったりする。それもまた、ある種のテクニックなのだろうか。 読みながら、彼はもう “別の世界に行こうとしているのかも知れない” などという思いがずっとあった。読み終えたあとで佐々木敦氏の文を読み、その思いは確信に近くなっていた。 この作品の後に上梓した15作目の長編小説、『街とその不確かな壁(上・下)』。これは、村上が以前に「中途半端な形」で発表した作品を完結させたいという思いから、約3年の歳月をかけて完成されたものとか。 確かな根拠はないが、今後そういう形でしか長編の作品は書かれないかもしれない。2025年4月23日発売
2025.08.13
コメント(0)
-
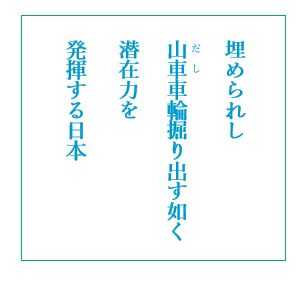
☆◆☆日本の将来は明るい
♪ 埋められし山車(だし)車輪掘り出す如く潜在力を発揮する日本 BSフジの「プライムニュース」はよく観ている。 2025年3月、メインキャスターの反町理が部下の女性社員に対してハラスメント行為を行っていたことが判明して降板となり、8月からサブキャスターだったフリーアナウンサーの長野美郷が正式にメインキャスターとなっている。*現在は(肩書の記載無しは、フジテレビアナウンサー) メインキャスター竹俣紅(月 - 水曜日) 長野美郷(水 - 金曜日)- フリーアナウンサー キャスター 梅津弥英子(月・火曜日) 小室瑛莉子(木曜日) 梶谷直史(金曜日) お堅い番組だが大きく転換し、女性が仕切る番組になってずいぶん柔らかくなった気がする。 月曜日の11日「失われた30年の原因とニッポン経済の未来予測」 ゲスト 千本倖生×モーリー・ロバートソン 二人とも口をそろえて日本の将来は明るいと、楽観的な展望を描いて見せた。 過去の繁栄とその甘い汁の味から離れられずに、守勢に回ってチャレンジ精神を失っていた日本だが、潜在的な能力は世界をけん引していけるだけの確固たるものがあると。 リスクを張ってチャレンジする、意欲的な若い経営者が必ず現れてくるという「希望的楽観論」ではあるでしょう。「千本氏」は、過去の実績で培われた精神と、稲盛和夫氏の「挑戦をやめるとき初めて失敗が確定する」という言葉に叱咤激励されて、苦境を乗り越えてきた実感をもとに語る言葉には説得力がある。拡大 半導体の中心部分は外国企業(TSMC、インテルなど)に敵わないが、その周辺機器は日本(東京エレクトロン、東レなど)がトップのシェアを持っている。それが無ければ機械を動かせないというとても有利な立場にある。「ラピダス」に国が巨額の投資をしているが、最後は民間がリスクを背負って必死になってやっていけば、必ずや道は開けると。「ロバートソン氏」は、金属加工とアニメ・漫画が鍵を握っているという。 金属加工はAIが真似のできない高度な技術ものを持っている。製造ではない分野のアニメや漫画、コミケの世界には天才的な才能を持った若者がたくさんいる。無責任なほどの発想の突飛さとアイデアとユーモア。それらの中にはアメリカでは発想できないトンデモナイ奇想天外なものが含まれている。 これらのものと金属加工する匠の技が、一つのグラデーションで結びついている。様ざまな伝統工芸などが一つのパズルとなってモザイクとして繋がっている。それに気づいた時に、新しい付加価値として大きく飛躍するはずだという。 まったく新しい価値を生み出せば、インターネットであっという間に世界を席巻することになると。 雲を掴むような話かも知れない。ただ、歴史的に客観的に眺めるとこういう結論になるというのは分かる気がする。 ロバートソン氏は言う。アメリカはせっかくいい状態だったのにトランプの諸々の政策でぶち壊しとなってしまい、今後は発展どころではなくなるだろうと。 千本氏は、復元力があるので政権が代わって、再び復活していくだろうという。日本が相手にしていくべき国は、アメリカと中国そしてアジアだろうと。 私も悲観論ばかり書いているようだが、日本を見限っているわけではない。政治が悪いだけで、民間の力には素晴らしいものがあると信じている。 失われた30年を経験し、トランプの政策のお蔭で “変わることが出来るタいいイミング” だ。なんだかんだ言いながら、民間企業は着々とその準備を進めている。 どんな優れた発明や技術でも、必ずそれらに替わるまったく新しいものがが出現する。GAFAMだって、このまま永遠に続くわけではない。そこに割って入っていくのが、日本人の持っている特異なセンスと融通無碍な潜在的能力なのかもしれない。
2025.08.12
コメント(0)
-
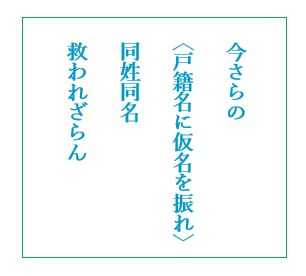
☆◆☆漢字は面白い。「箍」は見慣れない文字だ。
♪ 今さらの〈戸籍名に仮名を振れ〉同姓同名救われざらん 面白い漢字があるものだ。パーツが偏と旁ばかり「たけかんむり、てへん、はこがまえ、はばへん」の4つで来ている。なかなか今ではお目にかからないしあまり聞かない言葉だ。「たがが外れた」という時の「箍(たが)」の字。読める人は少ないんじゃないかな。 桶(おけ)や樽(たる)などをしめる竹や金属製の輪のことで、「―がゆるむ(しまりがなくなる)とか、―が外れる」とか言う。【 字形 】会意文字:竹+手+匝。 匝は、めぐる、めぐらす、とりま、の意。異体字は「帀」。【 部首 】は竹かんむりで、音読は「コ」。画数は14画。漢検1級の文字。「たが」は別字で「𥶡」、異体字で「笟」とも書くらしいが、「箍」の方が分かりやすいかも知れない。※会意文字とは 2つ以上の漢字を組み合わせて、新しい意味を持たせた文字。漢字の造字法である六書(りくしょ)のひとつで、「意味を会(=合)わせる」という意味がある。 大概の会意文字は偏と旁が2つか3つで出来ていて、これも「匝」の字があって3つで構成されている。「匝」を知らないので面白いと思ったわけだ。 この漢字・漢和辞典-OK辞典⇒⇒「会意文字一覧(画数別)」は、一字一字の生い立ちが説明してあって面白い。想像を絶するようなものも多く、目から鱗の文字の成り立ちだ。 24角までの文字が載っているが、何故か14角の「箍」の字が載っていない。 この「オンライン漢字辞典」もとても便利。様々な方向から漢字を検索できるようになっている。常用漢字、人名用漢字の区別もしてある。 ただ、「箍」は単独で検索すると出てくるが、何故か、竹かんむりや画数で検索しても出ておらず、読みで検索しても異体字の「笟」しか出て来ない。 * 読み検索(漢字を読みから検索 “音訓検索” ) * 画数検索(漢字を画数から検索) * 部首検索(部首の画数から検索) * 構成検索(読み方がわからない漢字を構成 “パーツ” から調べることができる) * 漢検級検索(漢字を漢検の級 “習う学年” から検索) * 詳細検索 * 検索ランキング(デイリー検索ランキング) 昨日10日から九州では大雨。夜間からは熊本県で線状降水帯が停滞して記録的な大雨となり、今日6時30分現在も荒尾玉名・宇城八代に大雨特別警報が発表された。 今日6時30分の時点で、八代市、玉名市、宇城市、長洲町、氷川町に大雨特別警報が発表され、自治体からは警戒レベル5の「緊急安全確保」の避難情報が発令されている。 11日から明日12日にかけて、近畿地方では断続的に雨が降るでしょう。局地的にカミナリや突風を伴い、京阪神などの都市部でも、道路が冠水するほどの降り方になるおそれがある。12日まで前線が停滞する
2025.08.11
コメント(0)
-

☆◆☆種が減り続けているプラネット。地球という名の水の惑星。
♪ ゆっくりと気づかないほど密やかに種の減り続くプラネットアース 朝起きると、キジバトが啼いている。猛暑が続いている間は啼かないでいたが、雨が降って涼しい今朝はさっきまで啼いていた。 キジバトの啼き声は、ウォーキングしていても良く聞くし、そんなに珍しいものでもない。しかし啼き声は時どき違ってきこえる。 絶対音感は持ち合わせていないし、それどころか普通の音感も怪しいのでどうかと思うが、まあこんな感じで啼いている。 いつもは4拍子なのに、3拍子で啼いていることがある。 雨を喜んでいるのは植物も同じ。ホッとして、根も葉も花も生気を取り戻しているところでしょう。宮城野萩は相変わらず旺盛だ。 百日紅は花の塊が大きすぎてお辞儀をするようにさいていたので切り詰めてやった。6月25日 細かい枝を伸ばして二度目の花が満開となっている。この方が安定していてバランスもいい。 早くも散り始めていて、花は色褪せて薄くなっている。 唐綿(アスクレピアス)やキバナコスモスは、暑さにはめっぽう強い。唐綿も切り詰めてやったが、再び大きく茎をのばしている。地植えにしたのが良かったのか悪かったのか。 隣の紫宝花は塩ビの中に植えてあり、水遣りが足りなかったこともあってあまり大きくなっていない。 シラサギカヤツリの花の茎に絡んだ朝顔が花を咲かせている。 朝顔の種を庭のあちこちにばら撒いてあるのに、あまり出てきていない。勝手に生えてやたらに伸びてこまったりするのに、意図してやるとうまくいかない。 夜になると玄関の灯りに来る虫を狙って、ヤモリがお出ましになる。それをアランが下でじっと見ていたりする。 いつもの夏の風景だが、こういうものもいずれは無くなってしまうのだろう。 ものすごい勢いで虫が減っている。「世界の昆虫の41%が絶滅の危機。英国の田園地帯の蝶は1976年以降46%減少。ドイツの自然保護区の昆虫が26年間で75%減少。渡りで有名な北米のオオカバマダラは10年間で80%減少」。日本も例外ではない。 現在は地球史上6回目の大量絶滅期という。どうやら、昆虫界も大絶滅に向かっているようで、人間以外の生物種は、地球史的時間軸で見ると、現在すさまじい勢いで減少しているらしい。でもこの地球史的大絶滅を気に留める人は、ほとんどいないそうで、そのこと自体が深刻な問題なのだ。 昆虫は既知の生物種の極めて大きな部分を占めており、地上と淡水内の食物網と密接に関連している。昆虫がいなければ、多くの鳥、コウモリ、爬虫類、両生類、小型の哺乳類、魚類は、餌がなくなるため姿を消すだろうといわれる。 すべての植物種のうち87%は、授粉のために動物を必要とするが、その動物の大半は昆虫だ。人間が栽培する作物の約4分の3は、授粉に昆虫を必要とする。その役割は世界全体で、年間2350億~5770億ドルの価値を持つという。金銭的価値はさておいても、授粉の仲介役がいなければ、世界の人口を養うことはできない。 昆虫の重要性はしばしば、エコシステム上の役割によって説明される。授粉のほかに、テントウ、ハナアブ、オサムシ、クサカゲロウなどの昆虫は、害虫駆除などに役立っている。木材を餌とする虫は、枯れ木の栄養分のリサイクルを助ける。 トビムシ、シミ、ワラジムシなどの無脊椎動物は落ち葉の分解を助ける。糞虫や蝿がすぐに糞に集まってこなければ、牧場は獣糞の山になる。彼らによってリサイクルされた糞は植物の栄養になる。動物の死骸は、シデムシやウジの餌とならなければ、腐り果てるまで何カ月もかかってしまうだろう・・・・。「世界の昆虫、絶滅の危機。大量絶滅期は既に始まっている」から一部を引用させていただいた。興味深いことがとても詳しく綴られている。
2025.08.10
コメント(1)
-
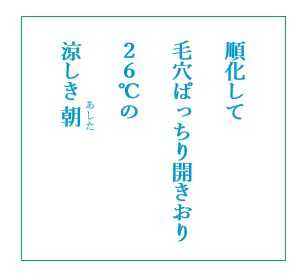
☆◆☆全長41kmのサイクル農道
♪ 順化して毛穴ぱっちり開きおり26℃の涼しき朝(あした) 夕べは涼しかった。西寄りの風から、朝方は北寄りの風に変ったせいか、ちょっと寒いくらいだった。それでも気温は26℃を下回っていなかったらしい。ウェザーニュースウェザーニュース気象協会気象協会ウェザーニュース気象協会 3連休は雨。ところによっては災害級の大雨が。 今年も九州は猛烈な雨に見舞われている。まったくお気の毒でならない。 3 日の日曜日、河和からの帰りに「すいせんロード」なる道に出た。聞き慣れない名前だったが、調べてみたら知多広域農道の一部で、「知多市〜南知多町」を結んでいる、全長41kmのサイクルロードにもなっているらしい。 知多半島の内陸部を縦断して半島先端付近まで行けるこのルートで、自転車乗りの間では良く知られているらしい。 佐布里池の西、梅が丘2丁目交差点から南へ伸びている「知多満作道」のことはよく知っいて、半田へ行く時などよく通る。それが、そのまま師崎まで行けるらしい。 味覚の道、ふるさとロード、すいせんロードと名付けられた知多広域農道を乗り継いで、最終的にR247へ。 ドライブするにも、車も信号も少ないのでストレスなく走ることが出来る。 知多エリア「知多満作道」 常滑エリア「味覚の道」 美浜エリア「ふるさとロード」 南知多エリア「すいせんロード」 internet BIKE Joho より 半島の中央部を通っているので海は見えないし、景色の変化は期待できそうにない。どちらかと言えば、自転車よりもオートバイのツーリング向きだろう。 夏の海水浴シーズンなど、大渋滞を回避するのには良さそうだ。 ただ、一本道というわけにはいかず、何カ所かのコースチェンジがあり、そのポイントをしっかり調べて間違えないように行かないと、思わぬ遠回りをすることになりかねない。 まあ、こんな猛暑の中をツーリングする人はあまりいないだろう。あの、夏になると出没する「爆音族」も、さすがにこの暑さじゃ出る気にもならないようだ。お陰で今年はとても静かだ。
2025.08.09
コメント(0)
-
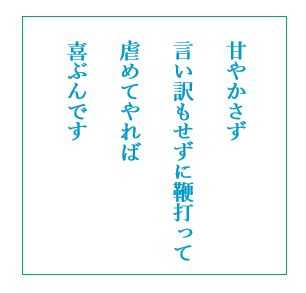
☆◆☆暑さが柔らいだチャンスを逃さず、ウォーキングへ
♪ 甘やかさず言い訳もせずに鞭打って虐めてやれば喜ぶんです 昨日は、ささやかながら雨も降って割合過ごしやすい一日だった。ずっとご無沙汰していたウォーキング。ようやく行く出る気になって、前日から準備をしていた。 日中は晴れ間も出て暑くなるので、午後4時ごろに家を出た。気温が最も高い時間帯で、ヤップの下にヘッドスカーフを濡らしてかぶる。今夏はじめてのスタイルで。 体力が落ちているのを自覚しているし、この機会を逃すと当分まともなウォーキングは出来ないかもしれない。どの程度歩くか、どっち方面に行くかちょっと迷ったが、マリンパークまで行くことにした。久し振りに、鈍った体を虐めてやろう。 市役所の職員駐車場から、駅前の新庁舎の建設が始まっている裏の道を南へ向かうお決まりのコース。2026年11月末頃に完成し、2027年5月に開庁を予定。2025年7月南西の空西知多産業道路 全体の幅は100m取ってある。初代の市長が主張して実現したもの。分岐する場所にある歩道橋が南に移動。完成しているがまだ使えない。常滑セントレア方面行き。15分おきに通過してゆく。マリンパークへの橋のたもとにナンキンハゼに木が数本あった。ここでも鳥さんのエサが採れるなぁ・・。 親が見守る前を、13~14歳の子が自転車の練習。トライアスロンの選手?見てる間だけでも、フルスピードで5往復していた。夜には雨が降るらしいが、東の空は晴れている。午後6時近くなって、すでに渋滞が始まっている。新舞子の入り口から繋がっているらしい。日長インター近くの陸橋から、朝倉まで約5キロある。旧堤防道路を北へ向かってひたすら歩く。西の空は晴れていて、夜に雨が降る気配は感じられなかった。 出発点に戻り着いたのが6時50分。下半身を虐めること2時間50分。約17,700歩のエクササイズ。疲れはしたが、くたびれ果てたという感じはなかった。 シャワーを浴びて、直ぐに夕食。 なぜかとても口が乾くので、コンビニへ缶ビールを買いに行った。その帰りの足が重かった。わずか390メートルの距離がえらく遠く感じた。 久し振りに涼しい夜。いい疲れにビールも入って、ベッドで本を読みかけたがすぐに眠くなった。トイレに起きることも無く、朝の5時までぐすり。 何も思わずにいるとろくに歩かないまま、一週間があっという間に過ぎていく。そうでなくても筋力やいろんなものが衰えている。放っておくと坂道を転げるように劣化していく。 足腰が衰えて歩けなくなったり、転んで骨折したりする人を見ていると、ああいう風にはなりたくないと思う。
2025.08.08
コメント(0)
-
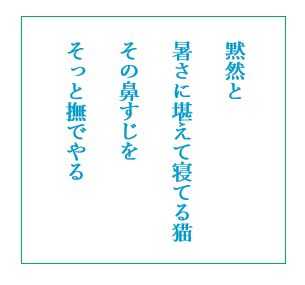
☆◆☆カオス的な未知の天体となりつつある
♪ 黙然と暑さに堪えて寝てる猫その鼻すじをそっと撫でやる 今日7日は、二十四節気の「立秋」だ。知多地方には久し振りの雨(と言うより “お湿り” 程度だが)で、ちょっと涼しい。もっと降ってほしいが、天は機嫌が悪くどこまでも意地悪だ。 しかし、日本海を東進する低気圧と前線が本州を通過するため、日本海側は大雨の予想。 日本海の海面水温が異常に高いままで、雨雲が発生しやすい状態が続いている。 何と冷酷なことをする天気だこと。水田の水不足を解消するにはもっと穏やかに降ってくれないと・・。大雨で冠水するようなことになっては大変だ。 作況指数が悪くなる予想が出ている上に、これじゃあまりにも酷い。そして、雨が降るのに気温は30度を上回るというありさま。 ベトナムに仕事で1週間滞在して戻って来た人の話だと、日中の気温が33度くらい。スコールがあったりするらしい。昔の日本の夕立ちを思い出す。 夜中に大雨が降った翌日、バイクで山間部に行った時は寒いくらい(20度くらい)だったとか。ベトナムは日本からすると、避暑地と言ってもいいくらいのもの。島国の日本と違って、フェーン現象などは無いのだろう。 地球について “いい事” を書こうとしても、いい情報がどこにも出て来ない。 地球は完全に狂っている。もう何が起こるか分からない。何でもありの、スーパーコンピュータでも追いつかない、カオス的な未知の天体となりつつある。Reuters(ロイター) 7月26日に50℃を超える気温が観測されたトルコ。各地で大規模な山火事が発生し、数週間で少なくとも15人の死亡が確認されている。熱波による乾燥に加え強風も影響し、トルコ国内では26日だけで84件の山火事が発生したとか。 大規模な山火事は隣国のブルガリアでも発生している。ブルガリア全体では、7月28日までに東京・大田区ほどの広さが焼失している。「イット!」7月30日放送 これは酔っ払いの放火が原因。馬鹿なやつが、悪霊にそそのかされて地球の怒りを代行している。
2025.08.07
コメント(0)
-
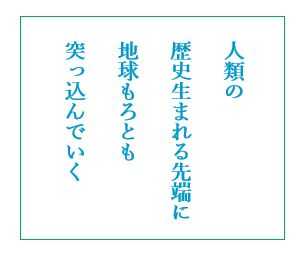
☆◆☆箝口令敷いて「暑い」というのは禁止に・・
♪ 人類の歴史生まれる先端に地球もろとも突っ込んでいく 朝のうちはクマゼミが60㏈ほどの騒音を、はや炎天の空に響かせているが、昼下がりともなると静まり返っている。 いっそのこと、箝口令でも敷いて「暑い」というのは禁止したらいい。意外性があって初めて話題にする意味がでてくるが、暑いのが当たり前の毎日に、当たり前のことを言っても意味がない。 群馬県伊勢崎市で41.8℃を記録。過去の歴代最高気温を大幅に超え、歴史的な暑さとなった。40℃以上は関東の14地点で観測され、過去最多記録を大幅に更新。 水田はカラカラとなり、ダムの水も0%のところもある極端な水不足。そこへ6日(水)午後から7日(木)朝にかけて、北陸や東北を中心に、警報級の大雨となるおそれ。 乾ききった大地には水が浸みこみにくく、表層を勢いよく流れてしまうばかりか、鉄砲水となって被害を大きくする恐れも。 地球の未来は、この異常高温に内包され、象徴されている。新しい時代の幕開けだ。どう足搔いたところでなるようにしかならない。 繁栄というお祭り騒ぎはもう間もなく終わる。トランプによって世界同時不況、世界恐慌が引き起こされる。必然的地球破壊によって天変地異が当たり前となる。 先進国最悪の借金財政。暴落のまぐまが溜まる日本国債。政府も国会もマスコミも、そんなリスクが存在しないかのような姿勢を取り続けてきた。 消費税減税の声が響くたびに、国債の格下げを招き、価格が低下し金利が上昇する。 3年前の英国トラスショックは、国債発行による大規模減税策を打ち出したところ、国債、ポンド、株のトリプル安を招いて、トラス首相が在任わずか1カ月半で失脚した。 不都合に目をつぶり、自滅の道を突き進んでいる日本は、英国よりもはるかに症状は深刻だ。 自由主義が刹那主義へ移行し、自己中心主義が横行し、暴動・略奪が日常化し、ヒットラーが再来する。 どう?、少しは涼しくなりましたか。 単なる作り話、都市伝説的ウソ話と思って一蹴してしまった人は、この最悪の罠に落ち込む可能性が高い。
2025.08.06
コメント(0)
-
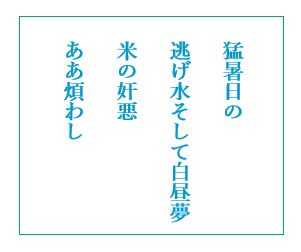
☆◆☆エリック・ドルフィーを聴く
♪ 猛暑日の逃げ水そして白昼夢米の奸悪ああ煩わし 昨日は薄曇りで対して熱くはなかった印象があるが、実際の気温は高かったようだ。 日中はクーラーを入れたが、夜には切ってしまった。3日間一階でクーラー点けっぱなしで寝ていたが、きのうは二階で寝た。 日中は4~5mの南寄りの風が吹いていたが、夜になって凪いできて深夜を過ぎてからはほとんど無風状態。扇風機をタイマーセットで回していたが、3度更新したような有様だった。 日中はそんなに暑く感じなかったのは湿度が低かったからだ。汗がよく乾くので涼しく感じたようだ。汗をかくことを厭わず、毛穴を機能させているお陰。 これ以上は出来ないというノースリーブのシャツにホットパンツ。首には「濡れ手ぬぐいを」巻いていて、コンビニに行く時もそのままで出かける。これがとても効果があって、耐えられる暑さの基準を押し上げてくれる。 それでもクーラーの涼しさを知ってしまうと、つい点けたくなるのが人間という生き物の軟弱なところ。 月曜日の午後はカミさんが居ない。プレーヤーの機嫌も良くなったので久し振りに、涼しい中でのレコード鑑賞。誰もいないことをいいことに、ビールなど飲みながら横着な格好で。 エリック・ドルフィーの「OUT TO LUNCH!」、これがいい。プレーヤーと針を替えてからは、初めて聴く。超人ドラマーのアンソニー・ウィリアムス=トニーのドラムスの音が、際立って聞こえる。今までの装置では聞けなかった生々しい音。この時、弱冠18歳。16歳でマイルスに見いだされてレギュラーに加わって、その才能を開花させていった。 もちろんドルフィーの演奏は言うまでもない。60年代というジャズの全盛期に「モードとフリー・伝統と前衛」を同時に体得し、コルトレーンとも共演しながら、稀有なセンスと独特のインプロビゼイションに磨きをかけて行った。この演奏はいつ聴いても痺れてしまう。マルチ楽器プレーヤで、アルトサックスはもちろんバスクラリネットもフルートも吹きこなす人など他にはいない。 ずっと金銭的に恵まれず、糖尿病で突然死したのが36歳。このレコーディングの4年後だ。わずか6年の間に70のレコーディングに参加しているが、生活は常にどん底だったという。 猛暑日にビールを飲みながら聴くドルフィーは、素潜りで深海へ向かうマーヨールを思わせ、また単独で無酸素登攀する孤高のアルピニストを思わせ、怠惰な老人のこころを震わせる。 この日、最初に聴いたのはKee Konitzの「VERY COOL」こちらもなかなか本格的なクールジャズで、マイルスが49~50年に出した「クールの誕生」にも参加している。 57年にこのアルバムを吹き込むまで、前衛派としてレニー・トリスターとともに活動してきた若い頃の彼の代表作。ただ音が悪くてあまり聴いていなかったが、新しい装置で聴くと全く印象が違う。 まさしく Cool なサウンドは、真夏のクーラーの効いた部屋で聴くにはもってこいの1枚だ。これはもう1枚持っている、「the real Lee Konitz」とほぼ同時期に録音されたもの。 ひとしきり聴いてから、気分を替えて読書に切り替えた。 何とまあ贅沢なひと時でしょう。猫がそばで寝ているのであまり大音量で聴くわけにもいかず、多少不満があるものの、クーラーが無かったらこうはいかない。 電気の消費量が “うなぎ上り” に増加しているだろうに、電気が不足しているというニュースは流れて来ない。原発なんか使わなくても間に合っているというわけだ。 化石燃料を使わない発電方法が研究され実用化され、もっと効率のいいものも出てくるだろう。問題は余った時の電気をどうするか、今のところ無駄になっている。もっと効率のいい蓄電方法の開発が求められる。
2025.08.05
コメント(0)
-

☆◆☆お寺で、伝統工芸でもある絞り染め体験
♪ 古刹にて板締め絞り染に興ず十人十色に暑さ溶け行く 全忠寺での「板締め絞り」体験教室は、猛暑を避けて午前中に。クーラーの効いた広い部屋で、ゆっくりと出来たのは有難かった。参加者が少な化たので息子に参加を呼びかけてくれ、老婦人数人と大学生6人という面白い組み合わせとなった。 子どもがいない分落ち着いた雰囲気で、和気藹々の内にのんびりと始まった。 いつものようになるべく自由に、周りと同じにならないようにと。初めての人には難しい指示をして、「適当にって、それが一番難しいのよ」とか言いながら、ああでもないこうでもないと、たっぷりの時間をかけて・・。 手の早い人、じっくり考えてなかなか進まない人。同時にスタートしたはずなのに、最後は大きな開きが出てしまう。二度目を染めて、最後に板を外す。 その出来上がりを早く見たいところだが、みんなが一緒に見られるようにしなしと散漫になる。全員が揃うまで我慢してもらった。そして一斉に「オープン」 想像と違う出来上がりに、あっちこっちで歓声が上がる。自分のを見て隣のを見て、その違いに驚いて・・。 折角なので、二人ずつ前へ出ての見せ合いっこ。つぎつぎ並ぶは、同じ作業をしたとは思えない十人十色の花盛り。われ目算の通りとなった出来栄え、皆のお目目が丸くなる。 大学生はユニークに、ご婦人たちは精巧に、その持ち味の特徴がはっきり出ていたのが面白い。 クーラーの効いた座敷の華やぎに猛暑を忘れ、時を忘れて楽しい真夏の思い出。2時間ほどかかった。もう一回やってみたいと思うところ、来年のお楽しみとして解散となった。 お庫裏さんには色々お世話になりました。 ご住職も、会えたので誘ってみたが、大きなお寺だけに忙しく、この日も法要とか色々あって、無理とのことだったが、興味はありそうだった。 そう言えば、お庫裏さんにも是非やってもらいたかったが、ウッカリしていた。 檀家の奥さん方のグループにも体験してほしいと思うが、活動日が月曜日で、この日は私は足がない。それを聞いたメンバーが、「それなら迎えに行きますよ」と言ってくれたらしい。 片道1時間のところを2往復することになるが、時間はたっぷりあるという事のようだ。涼しくなったら考えてみよう。信渓山 全忠治 愛知県知多郡美浜町河和古屋敷60−1
2025.08.04
コメント(0)
-
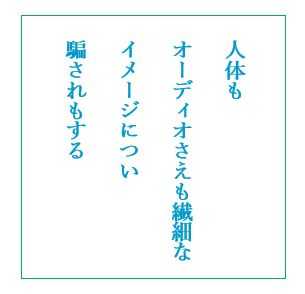
☆◆☆あれもこれも暑さで狂っている
♪ 人体もオーディオさえも繊細なイメージについ騙されもする 昨日も知多市では37.3℃までいった。猫もいることだし、クーラーを点けた。それで33℃の日よりも涼しい一日を過ごした。当然、夜も連夜の点けっぱなし。今後を思うと、電気代が思いやられる。 せっかくのこの涼しい中で、プレーヤーの不具合をチェックしてみる気になった。 「プレーヤーの底板をはずして、アームからの出力リードを半田付けしてある端子のチェック」。「半田付け端子から、ケーブルピン出力の間の断線のチェック」をしてみることとなった。 底板を外してはみたものの、プリント基板が見えるだけで、目視で分かるものなんか何もない。テスターがあるわけでもないし、リード線なんてプリントしてあるだけで、「出力リードの半田付け端子のチェック」なんて出来やしない。 銀色のシートをめくってみても何も変わらない。 色んなものを分解して遊んでいるので、見たことはある。でも「チェックしてみて」とあったのを真に受けたのが、まったく電子機器の素人だ。分かるわけがない。 まあ、それでも見える範囲で確認した限り、当然おかしなところは見られない。すぐに元へ戻した。 あとやれることと言えば、カートリッジとアームの接点の確認くたい。締め付けなおして、何か変わるかもしれない。 カートリッジをセットして「出来るだけしっかり締め付け」してみた。 なんと! 直ったみたいだ。右側からのちゃんと音が出るし、BARANCEつまみを回してみるとちゃんと働いている。 やっぱりここか。こんな単純なことで不具合が出るのは、設計ミスかと思う。 純性部品はまだ試してないが、フリーアームとして他のカートリッジが使えるようになっている以上、もう少し精度を上げてもらいたいものだ。 でも、これもこの暑さのせいかもしれないと思い始めている。 この日は朝から南知多町美浜の全忠寺で「板締め絞り」の体験教室がある。8時には出かけなければならずブログも途中まで、アップ出来なかった。 35℃を上回る予報が出ていて、参加を控える人もあったりして参加者はあまり多くはない模様。それでも名古屋の39℃予想より4℃も低いが、実際はもっと暑いらしい。 主な観測条件と観測方法「気温」: 風通しが良く、日陰で、地表面からの反射の影響が少ない場所で、地上1.2~1.5メートルの高さで測定。直射日光を避けるため、通風筒の中に温度計を設置し、電動ファンで外気を送り込んでいる。 室外機の排熱もなければ、アスファルトやビルの照り返しもない。直射日光が当たらない日陰で、地上1.2~1.5メートルの高さで風通しもいい。 そんな条件で測ったものが発表されているわけで、現実の、さまざまな現場の数値とは大幅に違ってくる。 それにしても静かだ。 子どもの声はもちろんのこと、鳥も蝉さえも声を潜めて暑さに耐えている。まったく異常もいいところで、電車さえ止まっているかと思うほどの静けさだ。
2025.08.03
コメント(0)
-
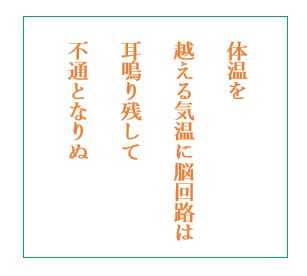
☆◆☆板締め絞りの二色染め
♪ 体温を越える気温に脳回路は耳鳴り残して不通となりぬ 知多市でもついに15時に「37.7℃」を記録。名古屋と同じ気温となったのは意外なこと。 当然、クーラーを点けた。夜はクーラーのあるリビングで、29度に設定して寝た。夜中の2時に、冷えてきたので切った。 5時に目覚めて、カミさんが暑そうにしているので部屋の温度を見たら、なんと30℃あった。そんなにあるとは。自分はそれほど暑く感じなかった。カミさんは「暑がりの寒がり」で、体温調節があまりうまくできない体質。私とは感覚がまったく違うので困ることがある。 夫婦が温度設定で揉めるという話は良く聞く。部屋を別にしないといけなくなるが、我が家のリビングは広いので、場所を変えれば調整は効く。 久し振りに「板締め絞りの体験」イベントを美浜の「全忠寺」で、明日(8月3日)にやります。まだ受け付けていますので是非ご参加を。 「全忠寺」電話:0569-82-0080 その要領を思い出すたのに丁度いいし、孫が自由研究のテーマが決まっていないというので、取りあえずやらせてみることに。面白いんだから! 大判のハンカチを使用。畳んで板で挟んで輪ゴムで固定。染める前に必ず水に浸けること。2色目が染まったところ。 畳み方、板の当て方で千変万化する。白を残し、二色目が染まる部分とのバランスをとる。 a色とb色 、布の白、aとbの混ざった色の、計4色の模様になる。一色で染めるだけに比べると、段違いの面白さだ。どんな風になっているのか、最後に布を広げてみるまで分からない。 最初は、これを自由研究にするのは、少し渋っているようだった。でも、3枚染めて全部違うものが出来たのが面白かったのか、どうやらその気になったらしい。 上手にまとめてくれると嬉しい。センスもいいのできっとみんなとは一味違うものが出来るんじゃないかな。期待しているよ~。
2025.08.02
コメント(0)
-
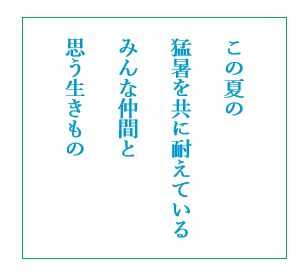
☆◆☆小さな生き物たちは、この暑さの中でも平気なようだ
♪ この夏の猛暑を共に耐えているみんな仲間と思う生きもの 暑い暑いとばかり言っていてもしょうがない。そんな空気がニュースや天気予報を見ていても漂っている。 それは誰にも止められないのだし、逃げ出すことも出来ない以上、何とかやり過ごして生き延びなければならないのだから当然だ。 幸い、内陸部ではない知多半島はフェーン現象とは縁遠く、3~4℃低いことが多い。しかし今週はその恩恵も期待できない。台風の影響もあって東風が熱風を送り込んでくる。 これでも昨日はクーラーは点けなかった。東の風が通り抜けて、それほど暑く感じなかった。それで、2度目の雑巾掛けをしたくらいだ。 今日、明日は、熱帯に移住したような異常な暑さ。内陸部の盆地などは、昨日に引き続きトンデモナイ気温が予想されている。。名古屋市で39℃、岐阜県多治見市では40℃まで気温が上がりそう。最高気温は名古屋より2~3℃低い。 夕方、ビールを買いに行くついでに市役所前庭の欅へ、蝉の抜け殻の様子を見に行った。 ヒマワリが西に傾いた太陽を背にして、ちょっと意外な感じに並んでいる。夕方にはこうなるものなの? あまりに暑いので、一日中太陽に背を向けていたりして・・・。 蝉にとっては暑さは大歓迎の様で、暑いからと言って元気がないようなことはない。それよりも雨の方が問題。地中から出てくる時に大雨が降ると、溺れたりして具合が悪い。 この夏、これまでに相当な数の蝉が羽化したようで、おびただしい抜け殻が転がっている。 「セミの寿命は一週間」というのはどうやら間違いのようで、捕まえたセミを長く飼うことが難しいのでそういう風に言われてきたらしい。 夏の間にセミの死骸をあまり見ないのを疑問に思って、実際に調べた高校生が岡山にいる。 一人で約2カ月もかけて調べた結果、アブラゼミ32日、ツクツクボウシ26日、クマゼミ15日。捕まえた前と後も生きていることを考えると、もっと長いかもしれない。 西洋朝顔の葉がいつの間に、かまるボーズになっていた。 下に種だか何だか黒い粒々が落ちているのは知っていたが、芋虫が喰い荒らしているなんて思いもしなかった。 以前、ヤマイモの葉に大きな芋虫が数匹いて、葉っぱを全部食べてしまったことがあった。たぶんそれと同じものだろう。 ガの一種の「セスジスズメ」の幼虫が複数いたに違いない。とても大きくて存在感がある。虫嫌いが見たら大きな悲鳴を上げるのは間違いない。昆虫写真図鑑「ムシミル」より糞 夜行性なので、昼間はどこかに隠れている。それで気づかなかったのだろう。土に潜って蛹になり、越冬して夏に出てくるらしい。 今ごろ、近くの土の中に潜って良い夢でも見ているのだろう。
2025.08.01
コメント(0)
全39件 (39件中 1-39件目)
1










