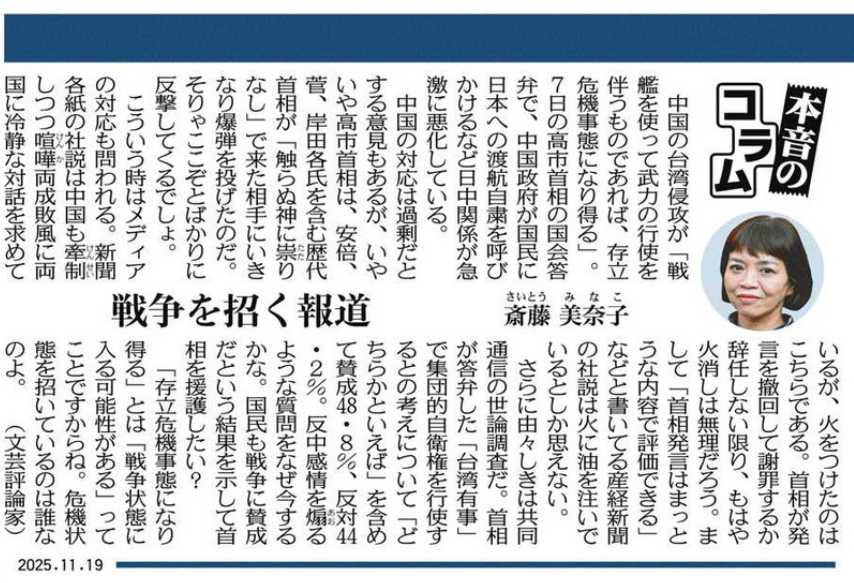2016年01月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
第十六代徳川家達――その後の徳川家と近代日本(感想)
徳川慶喜の後、徳川宗家を継いだ徳川家達は、ワシントン軍縮会議全権大使を務め、徳川一族のまとめ役、貴族院議長(明治36年~昭和8年)、第6代日本赤十字社社長(昭和4年11月2日~昭和15年6月5日)、国際連盟会会長などとして活躍しました。 ”第十六代徳川家達――その後の徳川家と近代日本 ”(2012年10月 祥伝社刊 樋口 雄彦著)を読みました。 大政奉還の4年前に生まれ最後の将軍・慶喜から徳川宗家を4歳で継ぎ、太平洋戦争の前年に亡くなった76年の生涯を紹介しています。 樋口雄彦さんは、1961年静岡県生まれ、1984年に静岡大学人文学部人文学科を卒業し、1984年から沼津市明治史料館学芸員を経て、2001年から国立歴史民俗博物館助教授、2003年から総合研究大学院大学助教授併任、2007年から国立歴史民俗博物館准教授、総合研究大学院大学准教授併任、2011年から国立歴史民俗博物館教授、総合研究大学院大学教授併任しています。 徳川将軍家は江戸幕府の征夷大将軍を世襲した徳川氏の宗家ですが、明治維新後の1884年には家達が公爵の爵位を授けられて徳川公爵家となりました。 華族制度廃止後は、単に徳川宗家と呼ばれています。 家達は田安徳川家の7代当主で、1863年に江戸城田安屋敷において、田安家の徳川慶頼の三男として誕生しました。 田安徳川家は徳川氏の一支系で御三卿の一つで、第8代将軍吉宗の次男宗武を家祖とし、徳川将軍家に後嗣がないときは御三卿の他の2家とともに後嗣を出す資格を有しました。 家格は御三家に次ぎ石高は10万石で、賄料領知を武蔵・上野・甲斐・和泉・摂津・播磨の6ヶ国に与えられました。 慶頼は14代将軍・徳川家茂の将軍後見職であり、幕府の要職にありました。 家達は家茂および13代将軍・徳川家定の従弟にあたります。 1865年に実兄・寿千代の夭逝により田安徳川家を相続し、1866年に将軍・家茂が後嗣なく死去した際、家茂の近臣および大奥の天璋院や御年寄・瀧山らは家茂の遺言通り、徳川宗家に血統の近い亀之助の宗家相続を望みました。 しかし、わずか4歳の幼児では国事多難の折りの舵取りが問題という理由で、また静寛院宮、雄藩大名らが反対した結果、一橋家の徳川慶喜が15代将軍に就任しました。 最後の征夷大将軍となった慶喜は、大政奉還の後に征夷大将軍を辞職し、一旦は兵を挙げたものの新政府に恭順し謹慎しました。 慶喜は隠居して、御三卿の一つ田安徳川家から家達が養子に立てられ、徳川宗家の相続を許されました。 第16代当主となった家達は、新政府により駿河・遠江・伊豆に70万石を改めて与えられて駿府に移住し、駿府の町を静岡と改名して静岡藩を立てました。 1869年に華族に列せられ、廃藩置県を経て、1871年に東京へ再移住しました。 その後、家達は、明治時代の終わりから昭和時代の初めに至るまで、長らく貴族院議長を務め、嫡子の第17代当主・徳川家正は、戦後、最後の貴族院議長を務めました。 歴代の徳川将軍の中で、現代においても個人としての事蹟に関し詳細な研究が続けられ、小説やドラマなどに取り上げられることで一般にも広く周知されているのは、家康、家光、綱吉、吉宗、慶喜でしょう。 明治期における徳川慶喜は、あくまで陰の人です。 本書で取り上げるのは、明治あるいは近代における徳川家を考える際、むしろ慶喜よりも重要な仕事を残した徳川家達という人物です。 16代当主として徳川宗家を継ぎましたが、当然ながらもはや将軍ではありませんでした。 廃藩置県により東京に戻り、イギリスヘの留学を経験しました。 貴族院議長をつとめ、さまざまな社会事業団体や国際親善団体の責任者ともなり、1914には、辞退したものの総理大臣就任のチャンスもありました。 1921年にはワシントン会議の全権委員となり、軍縮問題に取り組みました。 国際協調を旨とする親英米派と目され、軍国主義が台頭するなかで右翼に命を狙われました。 議長の職を辞したのは、満州事変を経て、日本が国際連盟を脱退した年です。 その後、時代は日中戦争へと突入していきますが、1940年に76年の生涯を終えました。 忘れられた巨人とも言える徳川家達について、今だからこそ知っていただくことに意味があるといいます。第1章 第16代徳川家達の誕生 第2章 70万石のお殿様第3章 若き公爵、イギリスへ第4章 幻の徳川家達内閣第5章 協調路線と暗殺未遂第6章 一族の長としての顔第7章 徳川家の使用人と資産第9章 日米開戦を前に死去徳川家達・略年譜
2016.01.25
コメント(0)
-
明治ふしぎ写真館(感想)
”明治ふしぎ写真館”(2000年6月 東京書籍刊 横田 順彌著)を読みました。 明治・大正時代のおもしろ・ふしぎ写真や挿絵に、あれこれ解説をつけて紹介しています。 むかしの不思議な写真や面白い写真がたくさん紹介されています。 写真技術については、紀元前に小さな穴からもれた光が壁に景色を写すことが知られてます。 15世紀に、フランス画家たちの間で、箱にレンズをつけた装置=カメラ・オブスキュラでの写生が行われました。 16世紀に、凸レンズを利用して明るい像を得るカメラ・オブスキュラが考案されました。 1826年に、フランスのニエプス兄弟がカメラ・オブスキュラを改良し、8時間かけて1枚の写真を撮影しました。 写真の始まりです。 1839年に、フランスのルイ・ジャック・マンデ・ダゲールがダゲレオタイプ=銀板写真を発表しました。 世界で初めてのカメラであるジルー・ダゲレオタイプ・カメラが発売されました。 1841年に、世界初のネガポジ法であるカロタイプ=タルボタイプが、イギリス人のウイリアム・ヘンリー・タルボットによって発表されました。 写真プリントの始まりです。 1848年ごろ、日本に写真技術が伝わったとされています。 1851年に、イギリス人のフレデリック・スコット・アーチャーが湿板を発明しました。 ガラス板の上に感光材料をぬることで、鮮明な写真を実現しました。 1857年=安政4年に、現存する最古の日本人が撮影した写真、島津斉彬の肖像が撮影されました。 1871年に、イギリス人のリチャード・リーチ・マドックスが湿板を改良し、ゼラチンを使った乾板を開発しました。 感光材料の工業生産が可能になりました。 1889年に、乾板のガラス板の代わりにセルロイドを用い、巻いて収納できるロールフィルムが、アメリカのイーストマン・コダック社から発売されました。 写真の一般への普及が始まりました。 1903年=明治36年に、小西本店、現在のコニカミノルタから、日本最初のアマチュア向けカメラ、チェリー手提暗函が発売されました。 横田順彌さんは1945年佐賀県生まれの小説家で、法政大学法学部を卒業、小学生時代からSF好きで、高校時代に古典SFに関心を抱き、大学在学中は落語研究会に所属するかたわら、SF同人誌に作品を寄稿しました。 1971年から本格的作家活動に入り、ユーモア、パロディー、だじゃれ、ナンセンスが渾然一体となった独自のSF路線を確立する一方、日本古典SF研究の第一人者としても知られています。 豊富な資料をもとにした明治研究も磨きがかかり、明治ものを次々と発表しました。 明治・大正時代も、ずいぶん昔のことになってしまいました。 しかし、当時の書籍や雑誌を読んでいると、現代では考えられないような、おもしろい、また、ふしぎなエピソードが山のようにある、といいます。 その明治・大正時代のおもしろ、ふしぎエピソードに、すっかりのめり込み、数冊の関連書を刊行しました。 明治・大正時代のおもしろエピソードを紹介する時、一番困るのは写真やイラストが非常に少ないことです。 この記事に写真があったら絶対におもしろいのに、といつも思っていたそうです。 また反対に、おもしろいふしぎな写真やイラストがあるのに、文章がおもしろくないという記事にも、時々出会ったとのことです。 そんなおり、文章はともかく、おもしろい、あるいは、ふしぎな写真を紹介してみましょう、という話があったといいます。 しばらく考え、それは相当難しいけれど楽しそうな作業だと始めることにしました。 とにかく明治・大正時代の、おもしろ・ふしぎ写真やイラストを掘り出してきて、文章をつけました。 つまらないという人は、写真とイラストだけ見ていただけばいいです。 このたび開業いたしました〔明治ふしぎ写真館〕でございます。 館名にいつわりなく、あれこれ珍奇・不可思議な写真を取り揃えておりますが、やはり最初は美女の写真紹介からまいろうかと存じますこの美女は誰だ/大森カツラと文士劇/サンダウ氏は強いぞ/アメリカ女子野球の不思議/日本の大仏、これにあり/嬶がほしいと一人百首/読まなきゃ判らん挿絵とは/ミストル前田、英京に闘う/おなじ顔した銀月の旅行記/懸賞まですこぶるバンカラ/東京見物スタイルブック/明治のお嬢のやることは判らん/チョンマゲ野球軍団/科学と不思議は仲良しか/ヒコウ少女の日米競艶/これでいいのか海国日本/あめゆきさんオンパレード/開化版の美女と野獣/明治の偉人は天狗のおじさん/丸刈りの忠直卿/薬靴を履いた猫君/三百歳の大走嬢、ガゴールとは/元祖YAWARAちゃん/牛童とは荒武着のことと見つけたり/百とまとめて、おめでとう/乃木坂にその名を残す武の男/横細さんはでっかい象/元祖マルチーライター/ヨッ、これぞ人気の大紋領/やあ、嬉しいな、お伽噺だ/主人公のアルバム付き小説/愉しき誌上紙芝居/画人の描く。夢十夜/最後の浮世給師が描く怪物
2016.01.17
コメント(0)
-
マリを知るための58章(感想)
マリは、面積124万平米、人口2012年1630万人で、その名は、かつてこの地にあったマリ帝国の繁栄にあやかって名づけられました。 マリとは、バンバラ語でカバという意味で、首都バマコにはカバの銅像があります。 ”マリを知るための58章 ”(2015年11月 明石書店刊 竹沢 尚一郎編著)を読みました。 かつてフランス領スーダンと呼ばれ独立時にマリ共和国となったいまの通称マリについて、知られざる奥深い魅力をさまざまな角度から紹介しています。 マリは西アフリカに位置する共和制国家で、西をモーリタニア、北をアルジェリア、東をニジェール、南をブルキナファソ、コートジボワール、南西をギニア、西をセネガルに囲まれた内陸国です。 国土の北側3分の1はサハラ砂漠の一部であり、残りの中南部も、ちょうど中心を流れるニジェール川沿岸だけが農耕地となっている以外は、乾燥地帯です。 竹沢尚一郎さんは、国立民族学博物館教授、総合研究大学院大学教授で、専攻はアフリカ史、アフリカ考古学、社会人類学です。 執筆者はほかに、京都府立大学名誉教授・赤阪賢氏、バマコ大学教授・イスマエル・ファマンタ氏、日本学術振興会特別研究員・伊東未来氏、上智大学総合グローバル学部教授・稲葉奈々子氏、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究科研究員・今中亮介氏、名古屋学院大学現代社会学部教授・今村薫氏、京都精華大学人文学部教授・ウスビ・サコ氏、独立行政法人国際協力機構長期専門家・尾上公一氏、東京都立大学名誉教授・門村浩氏、立教大学文学部教授・川口幸也氏、南山大学人文学部教授・坂井信三氏、中部大学中部学術高等研究所客員教授・嶋田義仁氏、日本学術振興会ナイロビ研究連絡センター所長・溝口大助氏、バマコ大学教授・ムーサ・コネ氏、特定非営利活動法人カラ=西アフリカ農村自立協力会代表・村上一枝氏となっています。 編著者は、1981年に大学院生としてはじめてマリをおとずれ、首都バマコの空港に降り立ったそうです。 当時マリは、独立に際してフランスと対立したことで社会主義路線を採用し、旧フランス植民地の共通通貨であるセーファー・フランから脱退しました。 内陸国でさしたる輸出品目をもっていなかったマリに、経済的自立が可能であるはずはなかったのです。 マリの通貨であるマリーフランは互換性をもたず、海外の製品は入って来ませんでした。 首都の中心部にる大きな商店に行っても、陳列棚に商品がなにもありませんでした。 車もほとんど走っておらず、首都の目抜き通りも自転車とバイクで埋め尽くされていました。 それと比べると、近年のマリには大きなビルがあいついで建てられ、街には色とりどりのブティックが立ち並んでいます。 壊れかかった車が多いとはいえ、道路は車で埋め尽くされ、道を渡るのさえ一苦労です。 2011年にはじまったトゥアレグ人の分離独立運動の余波はいまだつづいているとはいえ、首都にいるかぎり、人びとは陽気に語りあい、生活をエンジョイしているように見えます。 マリは、西アフリカでもっとも豊かな歴史をもつ国であり、現在のマリを知るためにも歴史を理解することが必要です。 マリは、3~17世紀にかけてガーナ王国、マリ、ソンガイ帝国として栄えました。 1920年にフランス植民地となり、1960年にマリ共和国としてフランスより独立しました。 1968年にトラオレ中尉による軍事クーデターにより、1969年にトラオレ軍事政権が成立し、1979年にトラオレ大統領が就任しました。 1991年にクーデターによりトゥーレ暫定政権が成立し、1992年に新憲法成立、大統領選挙、コナレ大統領選出が行われました。 2002年の大統領選挙でトゥーレ大統領が選出され、2007年に再選されました。 2012年に一部国軍による騒乱が発生し、トゥーレ大統領が辞任し,トラオレ国民議会議長が暫定大統領に就任しました。 2013年の大統領選挙でケイタ大統領が選出され、国民議会選挙が行われました。 マリを知るための歴史の要点は、三つあげることができます。 まず、遠い過去です。 現在のマリの地では、紀元7世紀頃からニジェール川中流域に、ガーナとガオ、マリなどの国家があいついで誕生しました。 これらの国家を支えたのは、旧大陸最大とされたマリを含む西アフリカの金でした。 それに向けてサハラを越えてイスラム中東文明が運ばれてきたことで、北の砂漠の文化と南のサヘルーサヅアンナの文化が混じりあう、トンブクトゥやガオに代表される独特の都市文化が形成されました。 第二に、そうした経済的・政治的発展を実現した結果、マリの人びとは西アフリカ中に移動しながら、各地に綿織物や鉄製造、商業やイスラムを伝えていきました。 やがて19世紀になってフランスがアフリカ大陸の広い範囲を支配すると、マリの人びとは下級の行政官や商人として各地に散っていきました。 その結果、隣国のセネガル、コートジボワールには数百万単位でマリ出身の人びとが住んでいます。 ほかに、遠く離れた両コンゴやカメルーン、ブルンジ、さらにはフランスなどにも数十万単位でマリ出身者が住んでいます。 それらの土地から送金される金額は、マリの国家予算の5分の1ともそれ以上ともいわれています。 第三に、独立後の有為転変を理解することです。 旧宗主国のフランスと対立したマリは社会主義路線を歩み、独自の通貨を採用しました。 その結果、マリは国営企業を中心に計画経済を推進する一方で、文化と歴史の独自性を強調する政策をとりました。 独立後、各地域の文化の発掘と啓蒙につとめ、2年ごとに若者を対象に文化とスポーツのビエンナーレを全国規模で実施しました。 他方、計画経済を採用したマリは、最重要な輸出品目であるワタの取引と綿布の製造をはじめ、すべての基幹産業を国営化しました。 その結果、買い上げ価格が低く抑えられたことを嫌気した農民がワタ栽培に熱を入れないなど、マリの経済は悪化する一方でした。 1980年代になって自由化されると、マリの農民の生産意欲はいちじるしく高まりました。 マリのワタ栽培はアフリカ1の地位を占めるまでになっただけでなく、金の採掘も活発になりました。 それによって、富が農村にまで循環するようになった結果、マリの社会全体が一定の豊かさを達成すると同時に、民主的な社会の実現に成功しました。 日本とマリのあいだの関係は薄く、マリ大使館が東京に開設されたのは2002年、日本大使館がマリに開設されたのは2008年に過ぎません。 とはいえ、マリの人びとの大なつこさと、したたかさの入り混じった親切さは、一度出会ったなら忘れることができません。 また、文化と歴史の豊かさもあり、今後、日本とマリの関係がいっそう密になり、マリに平和が訪れることを願っているといいます。1 地理2 歴史3 民族4 四つの世界遺産と主要都市5 生活と社会6 アートと文化7 政治と経済8 世界の中のマリ
2016.01.11
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1