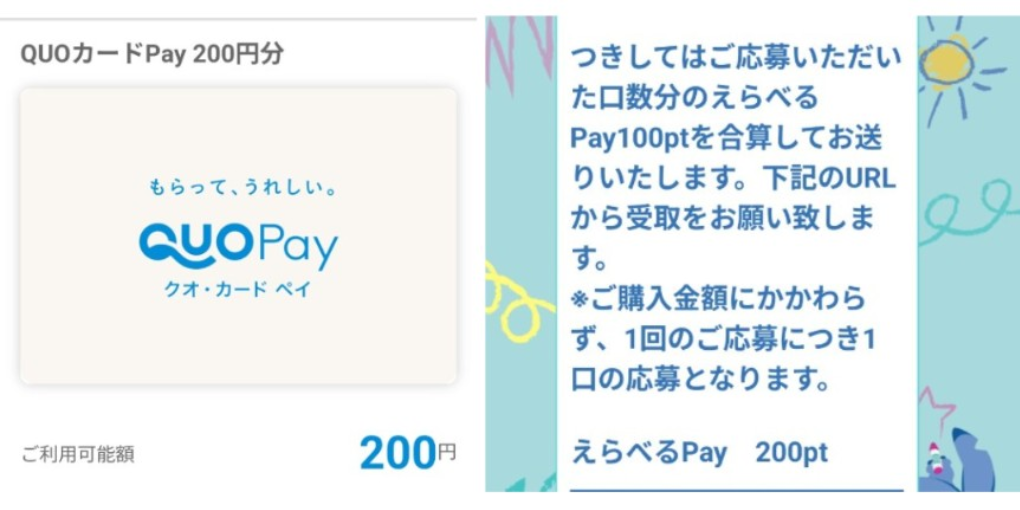2022年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

ニッポン巡礼(感想)
「隠れ里」は日本の民話、伝説にみられる一種の仙郷で、山奥や洞窟を抜けた先などにあると考えられた隠れ世です。 ”ニッポン巡礼”(2020年12月 集英社刊 アレックス・カー著)を読みました。 「隠れ里」は、日本の魅力が隠されているかくれ里を、滞日50年を超える著者が自らの足で回った、全国津々浦々から厳選した10カ所を紹介しています。 猟師が深い山中に迷い込み、偶然たどり着いたとか、山中で機織りや米をつく音が聞こえた、川上から箸やお椀が流れ着いたなどという話が見られます。 住民は争いとは無縁の平和な暮らしを営んでおり、暄暖な気候の土地柄であり、外部からの訪問者は親切な歓待を受けて心地よい日々を過ごしますが、もう一度訪ねようと思っても、二度と訪ねることはできないとされます。 一方「かくれ里」は、東奔西走する姿から「韋駄天お正」とあだ名された白洲正子の随筆のタイトルです。 世を避けて隠れ忍ぶ村里であり、ひっそりとした寺社、山間の集落、海沿いの棚田、離島の原生林、城下町の白壁、断崖に囲まれた自然の入り江などを指しています。 著者はかくれ里の、 吉野・葛城・伊賀・越前・滋賀・美濃などの山河風物を訪ね、美と神秘の漲溢した深い木立に分け入り、自然が語りかける言葉を聞き、日本の古い歴史、伝承、習俗を伝えています。 アレックス・カーさんは1952年アメリカ生まれで、1974年にイェール大学日本学部を、1977年にオックスフォード大学中国学部を卒業しました。 イェール大学在学中の1972年に、国際ロータリー奨学生として慶應義塾大学国際センターに留学して、日本語研修を受けました。 同年から京都府亀岡市に居を構え、書や古典演劇、古美術など日本文化の研究に励んでいます。 景観と古民家再生のコンサルティングも行い、徳島県祖谷、長崎県小値賀町などで滞在型観光事業を営んでいます。 本書は、季刊誌「kotoba」2018年夏号から2019年夏号まで、および、ウェブサイト「集英社新書プラス」で2019年8月から2020年7月まで連載したものを新書化したものです。 日本の文化には「表と奥」、「顕と密」のように、常に二つの要素が備わっているように思うといいます。 そこでは「表」より「奥」が、「顕」より「密」が、神秘的で深い意味を持つとされています。 つまり、簡単に見ることができず、人目を少々忍ぶくらいのものの方が、すばらしいのです。 1971年に、白洲正子が「かくれ里」という本を新潮社から著しました。 当時は高度成長期の只中で、観光ブーム幕開けの時でしたが、白洲正子は金閣寺、銀閣寺などを避けて、主に山奥を巡り、あまり知られていない寺や神社から、日本美の神髄について思考を巡らせました。 著者は1994年に、「本物とは何か」というテーマの対談で知り合って以来、彼女のものを見る厳しい目から、たくさんのことを教わったといいます。 白洲正子は1910年生まれで1998年に亡くなった随筆家で、東京市麹町区に父樺山愛輔と母・常子の次女として生まれました。 祖父は海軍大将で伯爵だった樺山資紀で、母方の祖父に海軍大将で伯爵だった川村純義がいます。 1928年にハートリッジ・スクールを卒業し聖心語学校を中退し、1929年に白洲次郎と結婚しました。 白洲次郎は1902年神戸市神戸区生まれで、連合国軍占領下の吉田茂の側近として活躍しました。 終戦連絡中央事務局や経済安定本部の次長を経て、商工省の外局として新設された貿易庁の長官を務めました。 吉田政権崩壊後は、実業家として東北電力の会長を務めるなど多くの企業役員を歴任しました。 白洲正子は1964年に随筆「能面」で第15回読売文学賞を、1973年に随筆「かくれ里」で第24回読売文学賞を受賞しています。 アレックス・カーさんはメリーランド州ベセスダで生まれ、父親はアメリカ海軍所属の弁護士でした。 父親に付き添って、ナポリ、ホノルル、ワシントンD.C.に滞在し、1964年に来日して横浜の米軍海軍基地に居住しました。 国際ロータリー奨学生として留学中にヒッチハイクで日本中を旅して、旅の途中で訪れた徳島県三好市東祖谷に感銘を受け、1973年に約300年前の藁葺き屋根の古民家篪=ちいおりを購入して、修復した上で居住しました。 庵の名は趣味のフルートから竹の笛の意で名付けたもので、現在、国の登録有形文化財に指定されています。 1998年から2007年まで、旅行記者のメイソン・フローレンスさんとの共同所有を経て、現在は特定非営利活動法人により管理がなされており、冬期を除き宿泊体験ができます。 アレックス・カーさんは、1974年から1977年までローズ奨学生としてオックスフォード大学ベリオール・カレッジへ留学し、中国学学士号と修士号を取得しました。 1977年に宗教法人大本国際部基金により再来日し、1997年まで日本の古典美術研究を行いました。 1989年より、庵での生活や歌舞伎、美術コレクションなどに関する自身の経験に沿って、変わりゆく日本の様子を執筆し、「新潮45」にて連載しました。 1993年にそれらを1冊にまとめた「日本の残像」を出版し、1996年には、英訳版「LOST JAPAN」を出版しました。 同著書が日本での執筆家活動のはじまりとなり、以降数々の著書を出版しています。 2001年には日本の景観、自然環境、公共事業のダメージに伴う観光の低迷など、日本が抱える諸問題について研究したものを、「犬と鬼」にまとめて出版しました。 1986年から1993年まで、米国系不動産開発会社トラメル・クロー東京代表、1996年に国際日本文化研究センター客員助教授を務めました。 1997年からタイに第二の活動拠点を設け、タイを中心にミャンマー、インドネシア、ラオスなど東南アジアの文化研究を進めています。 現在は、日本とタイを行き来しながら、文化活動の幅を広めています。 日本では京都の町屋再生事業、コンサルティング事業を手がける株式会社庵=いおりを2003年に創業し、講演、執筆、コンサルティング事業も手がけています。 これまで古民家再生の仕事で全国を走り回ってきましたが、それはほぼ僻地巡りの日々だったといえます。 加えて、この数年は白洲正子の跡を辿るように、神の力、仏の力とは何か、ということを考えながら、折あらば、かくれ里を探し歩くようになったといいます。 今日では表となる社寺や町並みには大勢の観光客が押し寄せて、特別感が薄れてしまっています。 それゆえに、誰もが行けるところより、知る人ぞ知るちょっと隠れた場所が魅力的に感じられ、それを見つけた時に心は大きく癒やされるそうです。 日本にはお遍路のように、何世紀も昔から巡礼の習慣がありますが、古民家再生もかくれ里を訪ね歩くことも、どちらも一種の巡礼であり、その中で数々の発見があったそうです。 そのような隠された本物の場所を紹介したいという思いをもとに、2017年から2年をかけて、あらためて「ニッポン巡礼」の旅に赴きました。 ジャーナリストと写真担当者と三人で、秋田の奥地、奄美大島の突端、伊豆諸島の青ヶ島と、長い時間をかけて辿り着く地は、文字どおり現代の「かくれ里」といえるところばかりです。 もう一つ、「かくれ里」とは「忘れ里」の意味もあると考えていて、大津市の日吉大社と三井寺、山口県の萩市、東京近郊の三浦半島など、僻地でないところにも足を運びました。 名だたる観光地を訪ね歩いているという人でも、そこから少しはずれた場所は素通りしていることが多いものです。 となれば、その人は日本の真髄を見逃しているのかもしれないと思うそうです。 そこで、読者のみなさんと一緒に巡礼に旅立ちたい。「人が知らないところは、人に知らせたいし、知らせると、たちまち汚されてしまうのは、ままならね世の中だと思う」(白洲正子)といいます。 それゆえ、ここで紹介する場所には、ぜひとも行かぬよう、最初に心からのお願いを申し上げておきます、とのことです。1 日吉大社、慈眼堂、石山寺(滋賀県)/2 羽後町田代、阿仁根子(秋田県)/3 能登半島(石川県)/4 八頭町、智頭町(鳥取県)/5 奄美大島(鹿児島県)/6 萩(山口県)/7 三井寺(滋賀県)/8 南会津(福島県)/9 青ヶ島(東京都)/10 三浦半島(神奈川県)[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]ニッポン巡礼 集英社 アレックス・カー / 集英社新書ヴィジュアル版【中古】afb【中古】 日本のたくみ 新潮文庫/白洲正子(著者) 【中古】afb
2022.01.29
コメント(0)
-

真相解明「本能寺の変」 光秀は「そこに」いなかったという事実(感想)
本能寺の変は、天正10年6月2日(1582年6月21日)早朝に、京都本能寺に滞在中の織田信長を、家臣・明智光秀が突如謀反を起こして襲撃した事件です。 本能寺は京都市中京区下本能寺前町にある法華宗本門流の大本山の寺院。で、本能寺の変の舞台として知られています。 ”真相解明「本能寺の変」 光秀は「そこに」いなかったという事実”(2021年7月 青春出版社刊 菅野 俊輔著)を読みました。 明智光秀が京都の本能寺に滞在中の信長を不意に襲い自害に追い込んだと言われる本能寺の変について、明智側の古文書が石川県内で見つかり、これまでの定説をくつがえす可能性があるといいます。 信長は寝込みを襲われ、包囲されたのを悟ると、寺に火を放ち自害して果てました。 信長の嫡男で織田家当主の織田信忠は、宿泊していた妙覚寺から二条御新造に移って抗戦しましたが、まもなく火を放って自刃しました。 これにより信長、信忠を失った織田政権は瓦解しました。 6月13日(西暦7月2日)の山崎の戦いで光秀を破った羽柴秀吉が、豊臣政権を構築していく契機となりました。 光秀が主君で天下人の信長を討った本能寺の変は、光秀の謀反の真相が明らかでなかったため、これまで日本史上最大の謎とされてきました。 しかし、本能寺の変について、その真相を語る新たな史料が令和3年(2021年)1月に発見されたといいます。 金沢市立玉川図書館近世史料館に、加賀藩前田家の史料が収蔵されていて、膨大な史料のなかに加賀藩士が古老の聞き書きをまとめた、『乙夜之書物』三冊本がありました。 新発見史料は、日本の歴史上、最大の謎といえる、本能寺の変の真相を語っているそうです。 菅野俊輔さんは1946年東京生まれ、早稲田大学政治経済学部を卒業、現在、歴史家・江戸文化研究家として、講演、著述、テレビ・ラジオ出演など多方面で活躍しています。 早稲田大学エクステンションセンター、朝日カルチャーセンター、毎日文化センター、読売・日本テレビ文化センター、小津文化教室で古文書解読講座の講師を務めています。 本能寺は、当初は本応寺という寺号で、応永22年(1415年)に、京都油小路高辻と五条坊門の間に、日隆によって創建されました。 寺地は北を五条坊門小路、南を高辻小路、東を西洞院大路、西を油小路に囲まれた地でした。 応永25年(1418年)に本応寺はいったん破却され、日隆は河内三井(本厳寺)・尼崎(本興寺)へ移りました。 永享元年(1429年)に帰洛して、大檀那・小袖屋宗句の援助により、千本極楽付近の内野に本応寺を再建しました。 永享5年(1433年)に檀那・如意王丸から六角大宮の西、四条坊門の北に土地の寄進を受け再建し、寺号を本能寺と改めました。 その後、本能寺は法華経弘通の霊場として栄え、中世後期には洛中法華21ヶ寺の一つとなり、足利氏の保護を受けました。 応仁の乱後、京都復興に尽力した町衆は、大半が法華宗門徒で、法華宗の信仰が浸透し題目の巷と呼ばれ、本能寺は繁栄を極めました。 天文5年(1536年)の天文法華の乱で、延暦寺・僧兵により堂宇はことごとく焼失し、一時堺の顕本寺に避難しました。 天文年間の戦国時代に帰洛し、日承上人が入寺して本能寺8世となりました。 天文14年(1545年)に平安京の東・西洞院大路、西・ 油小路、北・六角小路、南・四条坊門小路にわたる一町約120メートル四方に寺地を得て、伽藍が造営され、子院も30余院を擁しました。 その後、歴代貫主が地方に布教し、日承の時代には末寺が畿内、北陸、瀬戸内沿岸諸国さらに種子島まで広布し、本能寺を頂点とする本門流教団が成立しました。 織田信長は上洛中の宿所として妙覚寺を使用することが多く、本能寺を宿所とすることは3回と稀でした。 しかし、天正10年6月2日(1582年6月21日)は息子の織田信忠が妙覚寺に逗留しており、信長は本能寺を宿所としていました。 その本能寺を明智光秀の率いる軍勢が包囲し、襲われるという本能寺の変が起き、その際の兵火で堂宇が焼失しました。 『信長公記』では同寺で信長が切腹したとしていますが、遺体は発見されず、その最期は明らかではありません。 しかし一般的には生害地とされ、光秀を破って京に入城した織田信孝は、16日、焼け跡に光秀の首と胴、その手勢3,000の梟首を晒させて供養しています。 7月4日、信孝は同寺に御触を出して、信長の御屋敷として造成された焼け跡を墓所とするように、離散した住僧は戻るように命じています。 天正19年(1591年)に、豊臣秀吉の命で現在の寺域の中京区下本能寺前町へと移転させられました。 伽藍の落成は天正20年(1592年)で、現在の御池通と京都市役所を含む広大な敷地でした。 元和元年(1615年)に、江戸幕府から朱印地40石を与えられ、寛永10年(1633年)の『本能寺末寺帳』によれば、末寺92を数える大寺院になっていました。 織田信長は天文3年(1534年)に織田信秀の嫡男として、尾張国・勝幡城で生まれ、幼名は吉法師と言いました。 天文15年(1546年)に元服し織田三郎信長を名乗り、後見役を織田家の忠臣・平手政秀が務めました。 天文16年1547年)に吉良大浜にて駿河勢の今川義元方と対陣し、初陣を果たしました。 天文18年(1549年)に尾張と敵対していた美濃国の領主・斎藤道三と織田信長の父・織田信秀が和睦し、濃姫を妻として迎え、斎藤道三の娘婿となりました。 天文21年(1552年)に父親の死去により家督を相続し、天文23年に清洲城に移転しました。 永禄3年(1560年)に駿河の今川義元を桶狭間の戦いで討ち、永禄6年に居城を小牧山城に移転しました。 永禄11年(1568年)に室町幕府15代将軍・足利義昭を擁して上洛し、将軍職就任を助け天下を取ることを目指しました。 永禄11年(1570年)に越前国・朝倉家の征伐を開始しましたが、途中、織田信長の妹・お市の方が輿入れした、近江国・浅井長政が朝倉方に付きました。 元亀2年(1571年)に浅井・朝倉軍を匿った比叡山延暦寺を攻撃し、元亀4年に足利義昭を畿内から追放し、室町幕府は滅亡しました。 天正2年(1574年)に伊勢長島で起こった長島一向一揆を鎮圧し、拠点に立てこもる一揆勢の助命嘆願を拒み虐殺しました。 天正3年(1575年)に長篠の戦いで武田勝頼軍を、織田・徳川連合軍にて討ち、大量の鉄砲が戦果を挙げ、のちの戦術や戦法に多大な影響を与えました。 天正4年(1576年)に琵琶湖東岸の安土山に安土城の築城を開始し、楽市・楽座令などの自由経済政策で城下町の繁栄を図りました。 この年、第三次信長包囲網によって、京都を追放された足利将軍、本願寺僧兵、越後国の上杉軍、中国勢の毛利軍、さらに家臣の丹波国・波多野秀治や、但馬国・山名祐豊らが、相次いで反旗を翻しました。 天正8年(1580年)に北条氏政による従属の申し入れを受け入れ、東国まで支配を拡大し、106代天皇・正親町天皇の勅命のもと、石山本願寺と和睦しました。 天正9年(1581年)に京都内裏東において、織田軍を総動員した京都御馬揃えを催しました。 明智光秀は享禄元年(1528年)に斎藤道三の家臣で、土岐氏の分家である明智光綱の長男として美濃多羅城に生まれ、その後、明智城へ移りました。 天文2年(1533年)に斎藤道三が、稲葉山城から美濃の守護・土岐頼芸を追放して城主となり、実質的に美濃を支配下に治めました。 天文4年(1535年)に父 明智光綱が死去し、明智光秀が家督を相続し、叔父で明智城主の明智光安の後見を受けました。 天文13年(1544年)に稲葉山城の斎藤道三を織田信秀が攻め入りましたが、道三の計略で織田軍は大敗を喫しました。 弘治2年(1556年)に道三と長男・義龍が長良川の戦いで争い、道三は討ち死にしました。 このとき、義龍に明智城も攻め落とされ、明智家は離散し、明智光秀は浪人となって、諸国遍歴に出ました。 永禄5年(1562年)に朝倉家に仕え、加賀一向一揆では、鉄砲隊を50人預かりました。 永禄6年(1563年)に明智光秀と煕子に娘・明智玉、のちのガラシャが誕生しました。 永禄8年(1565年)に、三好三人衆と呼ばれた三好長逸、三好政康、岩成友通と松永久秀が二条御所を襲撃し、第13代将軍、足利義輝を暗殺し、光秀は朝倉家を去りました。 永禄11年(1568年)に足利義昭の足軽衆になり、足利義昭と共に織田信長がいる美濃へと移りました。 織田信長が足利義昭を立てて上洛し、義昭は第15代将軍に任じられました。 元亀元年(1570年)に足利義昭と織田信長が対立を深め、「金ヶ崎の戦い」で、浅井長政が織田信長を裏切り、織田軍は撤退しました。 このとき、豊臣秀吉、池田勝正と共に明智光秀がしんがりを務めました。 「姉川の戦い」で、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突し、織田・徳川連合軍が勝利しました。 元亀2年(1571年)天正元年に織田信長の命で、明智光秀らが比叡山焼き討ちを実行しました。 数々の功績が認められ、織田信長より近江国滋賀郡5万石を与えられ、坂本城の築城を開始しました。 元亀3年(1572年)に「小谷城の戦い」で織田信長に従い、琵琶湖上から水軍を率いて攻撃し、近江の浅井長政を攻めました。 天正元年(1573年)に光秀は「槇島城の戦い」で織田信長側で出陣し、足利義昭は降伏して京を追放され、室町幕府が滅亡しました。 この年、坂本城が完成して連歌会を催し、「一乗谷の合戦」で、織田信長が朝倉義景を破り朝倉家を滅ぼしました。 天正2年(1574年)に、武田勝頼が東美濃を攻めた「明智城の戦い」に出陣しました。 天正3年(1575年)に織田軍は「長篠の戦い」で、鉄砲戦術により武田軍を大破し、勝利を収めました。 その勢いのまま、越前一向一揆を討伐し、信長はさらに勢力を広げ、丹波攻略に力を入れました。 天正4年(1576年)に織田信長の命を受けて、1570年から続く浄土真宗本願寺勢力の本山・石山本願寺を攻めました。 この時期に亀山城の築城にも着手しましたが、妻・煕子が病にて死去しました。 天正5年(1577年)に松永久秀の居城「信貴山城の戦い」に参戦し、の戦いで久秀は自害しました。 天正6年(1578年)に光秀の娘・玉が細川忠興に輿入れしました。 天正7年(1579年)に織田信長が丹後国を配下にし、明智光秀に一国29万石が与えられました。 天正8年(1580年)に光秀が横山城を大改修して、福知山城に改名しました。 天正10年(1582年)に織田信長の命により、安土城において徳川家康への接待役を務めました。 そして、軍を京に転進させ、本能寺にて織田信長を自害させました。 この点についてこれまで諸説がありましたが、江戸時代の17世紀後半に成立した『乙夜之書物』に収録された、「斎藤利宗遺談」の発見により新たな事実が分かったといいます。 斎藤利宗は明智光秀の重臣、斎藤利三の三男・利宗で、当時16歳の利宗は父・利三に従い、本能寺襲撃に加わりました。 その利宗によれば、本能寺を襲撃したのは利三率いる先発隊2000余騎で、光秀は本能寺から約8キロ南の鳥羽に控えていたといいます。 光秀の謀反は突然に思い立ったもので、光秀と重臣の密儀であることが分かったそうです。 この発見により、秀吉・家康・朝廷(天皇・公家)・宣教師の関与説、あるいは黒幕説は成り立たないことになりました。 謀反の理由についても、斎藤利宗遺談を語った加賀藩士の井上重盛(清左衛門)が、後年に『乙夜之書物』の編著者で加賀藩士の関屋政春に語った、次のような話が、政春の10年後の編著『政春古兵談』に収録されていることがわかりました。 光秀は、稲葉一鉄が旧家臣の斎藤利三の取り戻しを信長に訴えた件で、信長から「稲葉家に返せ」との命令を受けましたが、承諾しなかったため、3月に信長の甲斐出陣にお供したとき、信濃諏訪において、信長や小姓たちから執拗な打擲を受けました。 また、3月中旬に、安土城を訪れた徳川家康一行の饗応役を信長から命じられましたが、その仕様が思し召しにかなっていないとして、できあがってきた膳椀などの器物を堀に捨ててしまうという、衆目のなかで大変な恥辱を与えられました。 この2つの出来事は、利三ら光秀重臣の知るところとなり、重臣たちは光秀が謀反を思い立つに違いないと確信し、いまかいまかと光秀の決心を待っていました。 光秀が決心したのは、信長父子が京都にいることを知った5月29日のことと推測され、中国出陣の当日となる、翌6月1日の亀山城での軍議の席で告白したといいます。 光秀の謀反は、このような理由・経緯による突発的なものであり、目的は信長と信忠父子を討ち取ることの一点でした。 当然、死を覚悟した謀反であり、信長父子を討ったあとのことは、光秀の意識にはなかったといえます。 それゆえ、その後の手配りも万全を欠くものであり、とくに長岡(細川)藤孝と筒井順慶を味方に付けることができませんでした。 また、短時日のうちに中国大返しで畿内に戻ってきた羽柴秀吉との合戦の日を予想より早く迎えてしまいました。 生涯、城攻めばかりで、会戦の経験のなかった光秀にとって、13日の山崎の戦いは勝利の見通しについて自信が持てない戦いだったかもしれません。 光秀の三日天下とされる、6月2日~13日の11日間は、家臣の努力はあったものの、信長重臣としての光秀の才能はまったく発揮されていませんでした。 信長あっての才能だったのであり、13日の山崎の戦いの敗戦後に、不慮の死が待っていたのも、必然ともいえる事態の推移です。 そして何よりも、光秀の謀反により天下人信長と後継者信忠の父子二人が同時に死去するという突発事態が現出したことは、山崎の戦いで勝利した秀吉にとって、一躍、歴史の表舞台に主役として登場する契機となりました。 天下人秀吉の誕生は、ライバル光秀の「謀反」のおかげということができるといいます。第1章 信長と光秀の“蜜月”-近年発見の史料で見えてきた特殊な関係(信長と光秀が出会うまで/信長と義昭の“連立政権”/天正年間の”蜜月”時代/武田攻め中国出陣/第2章 謀反の真相ー新発見『乙夜之書物』が明らかにした定説を覆す事実(本能寺襲撃/そして、山崎の戦いへ)/第3章 斎藤利宗と『乙夜之書物』-光秀軍の残党が徳川家旗本になって遺談を残すまで(遺談の主・斎藤利宗のその後/斎藤利宗遺談と進士作左衛門遺談/『乙夜之書物』の編著者・関屋政春)/第4章 “三日天下”の真実ー古文書解読でわかった「本能寺の変」のその後(その後の「本能寺の変」/光秀の“三日天下”/光秀、窮余の”秘策”)/終章 本能寺の変で“勝利”したのは誰か [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]真相解明「本能寺の変」 光秀は「そこに」いなかったという事実 青春新書INTELLIGENCE / 菅野俊輔 【新書】本能寺の変 織田信長、明智光秀 登城記念 御朱印帳、御城印帳の日本のお城のカード 家紋 戦国武将 桔梗
2022.01.22
コメント(0)
-

明暦の大火 「都市改造」という神話(感想)
明暦の大火・明和の大火・文化の大火を江戸三大大火と呼びますが、明暦の大火における被害は延焼面積・死者ともに江戸時代最大であることから、江戸三大大火の筆頭としても挙げられます。 ”明暦の大火 「都市改造」という神話”(2021年9月 吉川弘文館刊 岩本 馨著)を読みました。 世界史上最大級の惨事といわれる明暦の大火が従前の江戸市街地を滅ぼし、その後の都市改造が新たな江戸を創り上げたという通説を検証し、大火と復興の実像に迫っています。 関東大震災・東京大空襲などの戦禍・震災を除くと、日本史上最大の火災であり、ローマ大火、ロンドン大火、明暦の大火を世界三大大火とする場合もあるようです。 明暦の大火は出火の状況から振袖火事、火元の地名から丸山火事といわれる、明暦3 (1657) 年1月18~19日の江戸の大火です。 1月18日未の刻(14時ごろ)、本郷丸山の本妙寺より出火し、神田、京橋方面に燃え広がり、隅田川対岸にまで及びました。 霊巌寺で炎に追い詰められた1万人近くの避難民が死亡し、浅草橋では脱獄の誤報を信じた役人が門を閉ざしたことで逃げ場を失った2万人以上が死亡しました。 1月19日巳の刻(10時ごろ)、小石川伝通院表門下、新鷹匠町の大番衆与力の宿所より出火し、飯田橋から九段一帯に延焼し、江戸城は天守を含む大半が焼失しました。 1月19日申の刻(16時ごろ)、麹町5丁目の在家より出火し、南東方面へ延焼し、新橋の海岸に至って鎮火しました。 焼失町数約500~800、旗本屋敷、神社仏閣、橋梁など多数が焼け、さらに江戸城本丸はじめ大名屋敷も多く焼亡しました。 焼死者は約10万に及んだと言われ、江戸時代初期の町の様相は失われました。 火災後、身元不明の遺体は幕府が本所牛島新田に船で運び埋葬し、供養のため現在の回向院が建立されたと言われます。 幕府は米倉からの備蓄米放出、食糧の配給、材木や米の価格統制、武士・町人を問わない復興資金援助を行いました。 松平信綱は合議制の先例を廃して老中首座の権限を強行し、1人で諸大名の参勤交代停止および早期帰国などの施策を行い、災害復旧に力を注ぎました。 岩本馨さんは1978年北九州市生まれ、2000年に東京大学工学部建築学科を卒業し、2002年に同大学大学院工学系研究科修士課程を、2006年に同大学博士課程を修了し博士(工学)となりました。 2006年に京都工芸繊維大学助手となり、その後、助教、講師を経て、2017年から准教授を務めています。 明暦の大火については、その後の幕府の都市改造が新たな江戸を創り上げたという通説について、裏付けのないエピソードを避け、信頼性の高い記録から災害時の天候や焼失範囲などの事実関係を確認し検証しています。 本妙寺の失火が原因とする説は伝承に基づいており、振袖火事の別名の由来になっています。 「お江戸・麻布の裕福な質屋・遠州屋の娘・梅乃(数え17歳)は、本郷の本妙寺に母と墓参りに行った。その帰り、上野の山ですれ違った寺の小姓らしき美少年に一目惚れ。ぼうっと彼の後ろ姿を見送り、母に声をかけられて正気にもどり、赤面して下を向いた。梅乃はこの日から寝ても覚めても彼のことが忘れられず、恋の病か、食欲もなくし寝込んでしまった。名も身元も知れぬ方ならばせめてもと、案じる両親に彼が着ていたのと同じ、荒磯と菊柄の振袖を作ってもらい、その振袖をかき抱いては彼の面影を思い焦がれる日々だった。しかし痛ましくも病は悪化、梅乃は若い盛りの命を散らした。両親は葬礼の日、せめてもの供養にと娘の棺に生前愛した形見の振袖をかけてやった。」 「当時、棺にかけられた遺品などは寺男たちがもらっていいことになっていた。この振袖は本妙寺の寺男によって転売され、上野の町娘・きの(16歳)のものとなる。ところがこの娘もしばらくして病で亡くなり、振袖は彼女の棺にかけられて、奇しくも梅乃の命日にまた本妙寺に持ち込まれた。寺男たちは再度それを売り、振袖は別の町娘・いく(16歳)の手に渡る。ところがこの娘もほどなく病気になって死去、振袖はまたも棺にかけられ、本妙寺に運び込まれてきた。」 「さすがに寺男たちも因縁を感じ、住職は問題の振袖を寺で焼いて供養することにした。住職が読経しながら護摩の火の中に振袖を投げこむと、にわかに北方から一陣の狂風が吹きおこり、裾に火のついた振袖は人が立ち上がったような姿で空に舞い上がり、寺の軒先に舞い落ちて火を移した。たちまち大屋根を覆った紅蓮の炎は突風に煽られ、一陣は湯島六丁目方面、一団は駿河台へと燃えひろがり、ついには江戸の町を焼き尽くす大火となった。」 この伝承は、矢田挿雲が細かく取材して著し、小泉八雲も登場人物名を替えた小説を著しました。 伝説の誕生は大火後まもなくの時期であり、同時代の浅井了意は大火を取材して作り話と結論づけたといいます。 次に、江戸の都市改造を実行するため、幕府が放火したとする説があります。 当時の江戸は急速な発展による人口の増加にともない、住居の過密化をはじめ、衛生環境の悪化による疫病の流行、連日のように殺人事件が発生するほどに治安が悪化するなど都市機能が限界に達していました。 もはや軍事優先の都市計画ではどうにもならないところまで来ていましたが、都市改造には住民の説得や立ち退きに対する補償などが大きな障壁となっていました。 そこで幕府は大火を起こして江戸市街を焼け野原にしてしまえば、都市改造が一気にできるようになると考えたのだといいます。 江戸の冬はたいてい北西の風が吹くため、放火計画は立てやすかったと思われます。 実際に大火後の江戸では都市改造が行われていますが、明暦の大火では江戸城にまで大きな被害が及んでおり、幕府側も火災で被害を受ける結果になっています。 次に、本妙寺火元引受説は、本来、火元は老中・阿部忠秋の屋敷でしたが、火元は老中屋敷と露見すると幕府の威信が失墜するため、幕府が要請して阿部邸に隣接する本妙寺が火元ということにして話を広めたとする説です。 これは火元であるはずの本妙寺が大火前より大きな寺院となり、さらに大正時代にいたるまで阿部家が多額の供養料を奉納したことなどを論拠としています。 災害復興のため幕府貯蔵の金銀は底をつき、江戸幕府の勘定奉行の荻原重秀が元禄時代行った貨幣改悪の遠因となりました。 明暦の大火を契機に江戸の都市改造が行われ、御三家の屋敷が江戸城外に転出するとともに、武家屋敷・大名屋敷、寺社が移転しました。 また市区改正が行われ、防衛のため千住大橋だけであった隅田川の両国橋や永代橋などの架橋が行われ、隅田川東岸に深川など市街地が拡大され、吉祥寺や下連雀など郊外への移住も進みました。 さらに防災への取り組みも行われ、火除地や延焼を遮断する防火線として広小路が設置されました。 現在でも上野広小路などの地名が残っています。 幕府は防火のための建築規制を施行し、耐火建築として土蔵造や瓦葺屋根を奨励しました。 しかし、その後も板葺き板壁の町屋は多く残り、「火事と喧嘩は江戸の華」と言われる通り、江戸はその後もしばしば大火に見舞われました。 紀元64年7月にローマは燃え、大競技場付近から起こった火は、風に煽られてまたたく間に燃え拡がり、6日間にわたって市街地の7割以上を焼きました。 当時のローマでは木造建築が不規則に密集していて、それが甚大な被害につながったと考えられます。 大火後のローマでは、皇帝ネロのもとで、規則正しい街区の形成、道路の拡幅、建築の不燃化などの都市改造が行われたとされます。 当時のローマの人々は、もしやこの大火は、暴君ネロがローマを改造するために仕掛けたものだったのではないかと噂したといいます。 それから1593年後の明暦3年1月に、ローマ大火などとともに世界史上最大級の惨事として挙げられるほどの明暦の大火災が江戸を襲いました。 ローマ大火と明暦の大火は、時代は遠く隔たってはいますが、その語られ方については不思議と符合します。 都市災害のなかで、火災はとりわけ人災としての側面が大きいです。 そもそも火災は意図的に発生させることが可能なうえに、狭隘な市街地、燃えやすい建築、未熟な消火システムによって被害が拡大されえます。 それゆえ大火に遭ったとき、人々は自らの都市が抱えていた問題点に向き合わざるを得ません。 焼失した都市が大火後に改造されて相貌を一新したというような説明、あるいはさらにそこから飛躍して、大火はそもそも都市改造のために引き起こされたのだという陰謀論は、その点で人々にとって分かりやすいです。 明暦の大火についても、放火説はともかく、大火が従前の江戸市街地を滅ぼし、その後の都市改造が新たな江戸を創り上げたという流れは、通説としてさまざまな書籍などで記述されてきました。 明暦の大火を江戸の都市史の劃期として捉える史観は、古くは戦前の書籍も見られ、さらに大元をたどれば近世にまで遡る伝統的なものでした。 しかしここに挙げられている都市改造の内実については、必ずしもきちんとした実証がなされてきたわけではないため、改めて検討される必要があるように思われると言います。 20世紀段階では、明暦の大火前の江戸について知るための手がかりは、飯田龍一・俵元昭『江戸図の歴史』の「寛永描画図群」と呼ばれる一連の木板図がほとんどでした。 これらは江戸の中心部のみを図化したものでした。 江戸全域らしい範囲を描いたものとしては「正保江戸図」の存在が知られてはいましたが、これは随所に不自然な空白や欠落があり不完全な図でした。 大火前 江戸の全体像を知ることはこの時点では不可能だったのであり、それゆえ大火後の江戸の拡張も過大に評価されがちでした。 ところが、2006年に大分県臼杵市で寛永末年、西暦1642~43年の江戸の全貌を描いた「寛永江戸全図」が発見され、翌年には仮撮影版が刊行されました。 また2007年には、大火直後の明暦3~4年、西暦1657~58頃の江戸を描いたとみられる、三井文庫所蔵の「明暦江戸大絵図」の全体を高精細撮影して索引を付した書籍が刊行されました。 これら新たに発見・紹介された江戸全体図によって、誰もが大火前後の江戸の変遷を詳細に追うことができる環境が整ったのです。 そこで本書では、裏付けのないエピソード類の利用を可能な限り避け、信頼性の高い記録から事実関係を押さえることを基本方針としています。 あわせて、江戸図類に記載される情報の悉皆的なデータ化により、空間的な変遷を把握することで、明暦の大火とその後の復興の実像に迫っていきたいといいます。「都市改造という神話」-プロローグ/大火の日(大火前後の江戸と絵図〈江戸の実測図/大火前の江戸図〉以下細目略/明暦三年、正月/三つの大火/大火の被害)/「復興」の実態(焼け跡から/大火後の被災地/郊外へ)/大火以前・以後(江戸のスプロール/始まっていた「改造」/「改造」は前進か)/神話化する大火(『むさしあぶみ』の功罪/「都市改造」幻想)/大火がもたらしたものーエピローグ/明暦3年元日時点の大名一覧[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]明暦の大火(532) 「都市改造」という神話 (歴史文化ライブラリー) [ 岩本 馨 ]【中古】 江戸の大火と伝説の龍 / メアリー・ポープ・オズボーン, 甘子 彩菜, 食野 雅子 / KADOKAWA/メディアファクトリー [単行本(ソフトカバー)]【メール便送料無料】【あす楽対応】
2022.01.15
コメント(0)
-

山寺立石寺 霊場の歴史と信仰(感想)
立石寺=りっしゃくじは、山形県山形市山寺にあり、広く「山寺」の通称で知られています。 ”山寺立石寺 霊場の歴史と信仰”(2121年9月 吉川弘文館刊 山口 博之著)を読みました。 慈覚大師円仁の開創と伝わり、霊魂の帰る山とか幽冥を分ける聖地として知られる、立石寺における信仰の形と背景を、霊場を切り口に解明を試みています。 立石寺は慈覚大師円仁が開いたという天台宗の寺院です。 全山が凝灰岩からなる宝珠山の懸崖に多くの堂宇が配置され、東北の叡山ともいわれました。 鎌倉時代には幕府から禅宗に改めさせられましたが、衆徒が従わず、旧に復しました。 その後、兵火で焼失し、1356年に山形に入った斯波兼頼が、本堂の根本中堂を再建しました。 16世紀にも焼き討ちにあいましたが、室町時代中期建造の根本中堂は、入り母屋造り、5間4面、ブナ材の建築物として、日本最古といわれる天台宗の仏教道場です。 山門、仁王門、納経堂、開山堂、五大堂、如法堂など、山内の建物を結ぶ参道の石段は1000段を超えます。 山口博之さんは1956年山形県生まれ、1980年山形大学教育学部卒業、2006年東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士(文学)です。 山形県立博物館学芸専門員を経て、現在、東北学院大学東北文化研究所客員です。 立石寺は、山形県山形市にある天台宗の仏教寺院。山寺の通称で知られ、古くは”りゅうしゃくじ”と称しました。 詳しくは、宝珠山阿所川院立石寺と称します。 本尊は薬師如来で、古来、悪縁切り寺として信仰を集めています。 蔵王国定公園に指定されていて、円仁が開山した中尊寺・毛越寺、瑞巌寺との四寺を巡る四寺廻廊を構成しています。 ほかに、若松寺と慈恩寺を含めて巡る出羽名刹三寺まいりを構成しています。 山形市と仙台市は東西に隣接する都市で、その間に奥羽山脈という地理的障壁があり、この山中に立石寺はあります。 二つの都市をJR仙山線がうねうねと結び、最寄は山寺駅です。 ホームの北側に岩が屏風のように広がり、断崖絶壁、奇岩怪石の上に、堂宇がちょっと心配になるようなバランスで点在しています。 宝珠山立石寺は、慈覚大師円仁が清和天皇の勅許を得て開いたという名高い霊場寺院です。 860年慈覚大師創建の古刹であり、一相坊円海が再興したとされます。 創建が平安時代初期に遡ることと、円仁との関係が深い寺院であることは確かですが、創建の正確な時期や事情については諸説があります。 立石寺文書のうち”立石寺記録”は、開山を円仁、開祖を安慧と位置づけており、子院の安養院は心能が、千手院と山王院は実玄が開いたとされています。 安慧は円仁の跡を継いで天台座主となった僧であり、心能と実玄は円仁の東国巡錫に同行した弟子です。 安慧は844年から849年まで出羽国の講師の任にあり、東国に天台宗を広める役割を果たしたことから、立石寺の実質的な創立者は安慧であるとする説もあります。 また、円仁が実際に東国巡錫したのは829年から832年のこととされ、この際、弟子の心能と実玄をこの地に留め置いて立石寺の開創にあたらせたとの解釈もあります。 鎌倉時代には幕府の保護と統制を受け、関東御祈祷所となり寺は栄えました。 本尊薬師如来坐像は1205年に修理されており、この時に本堂の修造が完了して十二神将像を造立しました。 後に兵火により伽藍を焼失し、13世紀中頃には幕府の政策により禅宗に改宗となりました。 1356年に、源氏の斯波兼頼が羽州探題として山形に入部した後、兼頼により再建され天台宗に戻りました。 1521年に寺は天童頼長の兵火を受けて一山焼失しました。 1520年に頼長は山形盆地に進出した伊達稙宗と戦いましたが、この際、立石寺が伊達側に加勢したために頼長の怒りを買い、翌年焼き討ちを受けました。 焼き討ちの際には、比叡山延暦寺から分燈されていた法燈も消失しました。 1543年に最上義守による再建に際して再度分燈を受けましたが、1571年の比叡山焼き討ち後の再建時には、立石寺から逆に分燈されました。 延暦寺不滅の法灯は、織田信長の焼き討ちののち立石寺から継ぎ、東北の比叡山として有名です。 山形城主であった最上家と関係が深く、同家の庇護を受けていました。 最上義守の母・春還芳公尼は荒廃した堂宇の再興に努め、その孫にあたる最上義光も立石寺を保護しました。 凝灰岩の岩盤に建つ釈迦堂・開山堂、慈覚大師入定窟と旧国宝如法経所碑、根本中堂などが建ち並ぶ、奥深く静かな景勝地であり、1932年に国名勝史跡指定を受けました。 本書では、立石寺が中世霊場として盛んであった期間を1期~4期に分け、前後を含みつつ中世考古学の視点で霊場に歴史を読んでみたいといいます。 一歩足を踏み入れると、ここでは不思議な静寂に包まれ、俳聖松尾芭蕉も感じたらしいです。 芭蕉がここを訪れたのは1689年夏、奥の細道の旅の途中でした。 今から300年以上前の旅人は、山形領に立石寺と云山寺ありとして、”閑さや岩にしみ人蝉の声”の名句を残しました。 なぜ、芭蕉はこの地でセミの声が岩に染み込むような静けさを感じたのでしょうか。 絶景にして物の音が聞こえず寂寞の中にある空間であり、芭蕉の感じた閑さは霊場への共感によって得られた境地ではないでしょうか。 ここは真夏でも不思議な静寂に包まれます。 そびえ立つ露岩に寄り添うように建ち並ぶ堂宇の数々、清和天皇宝塔、露岩に刻まれた一面の岩塔婆、風穴に納められた小五輪塔、そしてたくさんの後生車があります。 これらは参詣する人に寄せられたものではなく、供養者によりここに寄り集う霊魂のために用意されたものなのです。 ここは霊魂の帰る山と目されていた、あの世と此の世の境界、幽冥を分ける場所、霊場なのです。 霊場は神仏の霊験あらたかな場所の意で、神社・仏閣などの宗教施設やゆかりの地など、神聖視される場所をいいます。 古くから信仰の対象になっており、現在でもお遍路や修験者などの往来の多いところがあります。 恐山、比叡山、高野山など数多くの霊場が存在し、その多くは山岳信仰に根ざしたものですが、全ての霊場が山にあるとは限りません。 志度寺のように海沿いの霊場や、弁天洞窟のような地下霊場も存在します。 この場所には信仰に基づく行為の結果、見ることのできる資料が残されました。 信仰は無形ですが、霊場で信仰に使われた資料は有形であり調査が可能です。 著者は立石寺に隣接する山形県天童市に生まれ、小学校六年生の遠足は学校を出発して立石寺の奥の院まで、往復16キロほどを歩いたといいます。 子供の足では霊場はすごく遠く、信仰心を試すように道も悪く、担任教師がバイクで伴走していたのが羨ましかったそうです。 これ以外にも登山好きの父親に連れられ、何度も奥山寺の登山コースを巡りました。 また、立石寺へ歯骨を納めたという話、魂が立石寺へ飛んだのを見たという話を聞きながら成長してきたそうです。 膝元に住んでいたわけではありませんが、皮膚実感として立石寺を感じていました。 なぜ中世考古学研究の対象かといえば、霊場に残されるのは史料もありますが、資料が圧倒的に多く中世考察古学の対象となるからです。 これは地域の中世史を再構築する試みでもあります。 地域の中世史を描くことが難しいのは、歴史を語る史料がないからです。 史料をもって歴史を語ることは困難な場合、考古学資料やその他の資料をすべて活用しながら解明を進めるしかありません。 モノ資料を総合化しつつ、個別の資料の関連性を広く読み解く作業は、地域の中世史を語るのに有効な方法論なのです。 その対象として、さまざまな資料の残る霊場は好適といえます。 著者が考古学を志したとき、先輩からいわれたのは、文字が読めない者はスコップを持てでした。 自分で掘り出す考古学資料は一次資料であり、自分か歴史を変える発見ができます。 中世霊場の考古学資料を分析するときには、史料の読み込みは不可欠です。 考古学資料と同時代の史料が残されているのですから、逆にいえば活用しない手はありません。 本書でも「霊場を知る」「霊場を定める」「霊場に参り納める」の各章はこのような立場であり、霊場分析のためあらゆる資料を活用しています。 最終章の「霊場復興」は史料に中心をおいて構成していますが、残されている史料が多いからであり、これも中世考古学の範囲なのだとご理解いただきたいといいます。霊場寺院の中世―プロローグ/霊場を知る(立石寺の概要と画期/立石寺の発達と画期/山寺立石寺景観の時空/立石寺来訪)/霊場を定める(古代の立石寺/街道と立石寺)/霊場に参り納める(三回にわたる入定窟の調査/その後の研究と成果/如法経所碑と経塚/中世の納骨と信仰/中世から近世の納骨と供養/立石寺と中世石造物)/霊場復興(一相坊円海の時代/法灯の帰還―円海と月蔵坊祐増/法灯の返還―円海と正覚院豪盛/円海と最上義光の関係、鳥居忠政との確執)/今を生きる寺―エピローグ[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]山寺立石寺 霊場の歴史と信仰【中古】奥の細道「図説 出羽路の芭蕉」/ 山寺豊 ( 宝珠山 立石寺)
2022.01.08
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1