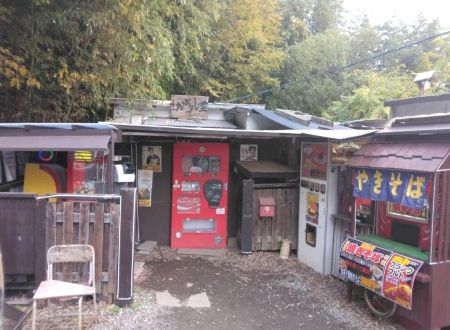2016年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
コンビニ難民-小売店から「ライフライン」へ(感想)
コンビニと宅配便は、いまや日本を特徴づけるサービス産業の代表格になっています。 ”コンビニ難民-小売店から「ライフライン」へ ”(2016年3月 中央公論新社刊 竹本 遼太著)を読みました。 全国津々浦々にあっていまや社会インフラとなっているコンビニに、徒歩で行けないコンビニ難民の現状と将来を展望しています。 コンビニは、東京23区では500m圏で人口の99%がカバーされる一方、日本全国では68%と、郊外や地方では相対的に徒歩圏に居住する人口割合が低いです。 竹本遼太さんは、1981年京都府生まれ、東京大学工学部卒業、東京大学大学院情報理工学系研究科修了、2006年野村證券に入社し、2012年に三井住友トラスト基礎研究所に変わり、副主任研究員として現在に至っています。 現在のコンビニの国内の総店舗数は5万5千店、年間売上高は10兆円、1ヵ月の来店者数は14億人となっています。 これまでコンビニ市場の急成長を牽引してきたのは、若者ではなく実は中高年層であるといいます。 1989年の来店客の6割強は20代以下の若者で、50代以上の来店客割合は1割未満でした。 それが、2013年には50代以上の来店客が3割、40代を加えると中高年層がコンビニ客の半数を占めるようになったそうです。 20代以下の若い層の来店は2倍になりましたが、50代以上の来店は16倍になりました。 若い頃からコンビニに慣れ親しんだ世代が高齢期に入ってきたことに加え、生活のさまざまな便利なサービスが利用できるようになったことが主因と思われます。 小売業から物流、金融、そして公的手続きや災害支援など、コンビニは社会インフラとしての役割を担い始めています。 雇用の創出や買い物難民の一助になるなど、日本が持続的発展を遂げるためにかかる期待も大きいです。 若者のたむろ問題やエネルギーの過剰消費、ブラックバイトや地域商店への影響など、課題はあるものの、結果として私たちの生活に不可欠な存在となっています。 しかし、東京23区内では高齢者の86%が最寄りのコンビニから300m以内に住んでいる一方で、日本全国では高齢者人口の徒歩圏カバー率は39%に過ぎず、高齢者の61%が徒歩によるコンビニへのアクセスに不便を感じているといいます。 この層のことをコンビニ難民と呼んで、その実態を浮かび上がらせて課題を探ろうとしています。 その数は、単身高齢者、高齢夫婦世帯で言えば800万人以上と試算され、日本が今後も持続的な成長を遂げるためにその解消が一つのカギになるということです。 近年、経済や社会インフラとして、明らかにコンビニの重要性が高まってきています。 コンビニは買い物ができるだけでなく、預金の出し入れ、宅配便の受け取り、住民票入手など行政手続きのほか、いまや地域の防犯・防災の拠点にさえなっています。 最近は高齢者の利用も増え、私たちの生活はコンビニなしではもはや、成り立たなくなってしまいました。 高齢化や過疎化の進展によって、そのコンビニが使えなくなるコンビニ難民が今後、増えるかもしれません。 そうなると日本の未来を左右しかねないといいます。 高齢者のコンビニ難民率が高い人口20万人以上市区町村をみると、茨城県つくば市の83.7%が最も高く、新潟県上越市が83.2%、津市が79.0%、松江市が78.7%、新潟県長岡市が76.4%となっています。 過疎化が進んだ農村部と、かつてのニュータウンなどがある都市郊外を中心に、60歳以上の高齢買い物弱者は全国に600万人程度存在するとされています。 今後も高齢化が進展する日本では、高齢者のさらなる高齢化、単身世帯の増加、共働き世帯の増加が想定されています。 目前に迫る超高齢社会において、生活のあらゆる場面で、近くて便利なコンビニが貢献する可能性は大きいです。 コンビニは、徒歩圏で24時間1日中利用可能な、身近で便利なライフラインのワンストップサービスの提供拠点としての役割を増していくと思われます。 すでに日本中に張り巡らされたコンビニをどう活用するか、そのことについて一考すべきタイミングが今なのではないでしょうか。序章 あなたは「コンビニなし」で暮らせますか1章 社会的課題と向き合うコンビニ2章 超高齢化社会と向き合うコンビニ3章 高齢者の約6割が「コンビニ難民」である4章 「コンビニ難民」を減らすことはできるのか
2016.06.26
コメント(0)
-
慶滋保胤(感想)
慶滋保胤は、933年に陰陽家賀茂忠行の次男として生まれました。 字は茂能、唐名は定潭、法名は寂心で、世に内記入道と称されました。 父子の姓が違うのは改姓したからです。 陰陽道の専門家を父としながら、それとは異なる紀伝道に進みました。 ”慶滋保胤”(2016年4月 吉川弘文館刊 小原 仁著)を読みました。 平安時代中期にわが国初の往生伝集を編纂した、慶滋保胤の生涯を紹介しています。 ”池亭記”はその代表作であり、往生人の事跡を集めた”日本往生極楽記”1巻の著があり、源信の”往生要集”とともに宋に送られました。 往生伝集は極楽浄土に往生した人々の伝記を集めた書物で、”日本往生極楽記”は唐の浄土論や瑞応伝にならって日本の往生者の伝を集めたものです。 42項目45人を、僧尼・俗人男女の順に漢文体で記されています。 国史別伝・故老口伝を素材とし、以後に編纂された往生伝集の範となりました。 小原 仁さんは1944年北海道生まれの日本史学者で、1967年北海道大学文学部史学科卒業、1972年同大学院文学研究科博士課程単位取得退学、聖心女子大学文学部教授を務めました。 慶滋保胤は紀伝道の学生となり、対策に及第して、位階は六位から五位に、官職は文筆官僚たる内記に至りました。 菅原文時を師とし、門弟中文章第一と称せられました。 一方、早くから弥陀を念じ、964年には学生有志と勧学会をおこして、その中心となって活動しました。 しかし、内記としての活躍の時期は、円融朝と花山朝の5~6年にすぎず、986年4月に突然の出家を遂げました。 若いころからの信仰心の昂揚と、花山朝政の行き詰まりを慮ってのことと思われます。 源信をはじめとする当時の浄土教家と交流があり、諸国遍歴後、東山の如意輪寺に住み、1002年70歳ほどの生涯を終えました。 伝記・逸話は”今昔物語集”等に伝えられ、家集”慶保胤集”2巻は今日に伝わってはいませんが、その詩文は”本朝文粋””和漢朗詠集”等に残っています。 保胤は時代を代表する詩文家でもあり、紋切り型の公文書の作成ばかりでなく、公私の詩会において大いに詩文の才をふるい、後代まで愛唱された詩句を遺しました。 10代から20代にかけては、天下の才子と褒めそやされました。 保胤について、今日、その名を知る人はそう多くはないでしょう。 ましてや、その著作が読まれることはあまりないでしょう。 もし保胤の名やその著述が多少とも知られているとすれば、それはいくつかの日本史の教科書に作品名が採りあげられているからですし、また幸田露伴の最晩年の傑作”連環記”によるものでしょう。 ”連環記”は、保胤=寂心と大汗定基=寂照の師弟を中心とした物語で、諸記録や詩文や説話などの基本史料を広く探し求めて創られました。 慶滋保胤という人は、詩文の才に長けた文人貴族であり、また文筆をもって勤仕した官僚でした。 次に、終始一貫してきわめて熱心な浄土宗信仰者でした。 保胤の人物像は、この2つを骨格として形成されています。 そして、その肉付けに不可欠なのが自他の詩文です。 保胤自身あるいはその周辺の人々の詩文は、保胤の人物像を具象化する優れた証拠となるはずです。 平安時代中期の藤原氏の権勢下で、官吏として出世する道を閉ざされた中下層貴族たちの生き方が忍ばれます。第1 誕生と出自(保胤の生年/保胤の家族)第2 学生保胤(大学入学/才子保胤/善秀才宅詩合)第3 勧学会(勧学会の草創/勧学会の次第/保胤と勧学会/勧学会の衰退)第4 起家と改姓(起家献策/詩合・歌合への出仕/慶滋改姓)第5 内記保胤(公私の文筆活動/池亭の家主保胤/浄土信仰とその著述/花山朝政と保胤)第6 沙門寂心(心覚から寂心へ/横川登山/八葉寺の創建/寂心の死)第7 慶滋保胤の記憶
2016.06.19
コメント(0)
-
ハーフが美人なんて妄想ですから!!(感想)
厚労省の人口動態統計年報によると、2010年に生まれた子供のうち、両親の一方が外国籍のハーフは2万2000人いるそうです。 街なかで外国人を見かけることは珍しいことではなく、今日、誰にでも一人くらいはハーフの友達がいる可能性があります。 ”ハーフが美人なんて妄想ですから!!”(2012年6月 中央公論社刊 サンドラ・ヘフェリン著)を読みました。 ドイツ人と日本人のハーフである著者が、日本におけるハーフを取り巻く環境と国際感覚のない純ジャパの特徴を紹介しています。 ハーフだから容姿端麗、ハーフだから金持ち、ハーフだから社交的、ハーフだからバイリンガル、いやトリリンガルくらい当然、ハーフだからインターナショナルスクールなどの出身など、幾重もの色眼鏡でみられるといいます。 でも、実際には、不美人なハーフもいれば、日本語しか話せないハーフもいれば、貧乏なハーフもたくさん暮らしています。 サンドラ・へフェリンさんは、本名、渡部里美、1975年にドイツ人の父親と日本人の母親との間でロンドンで生まれました。 幼少期に父親の出身地であるドイツへ移住し、短期間、千葉県の公立小学校へ通学していた時期を経て、ミュンヘンで育ちました。 1997年に再び日本へ立ち、一般企業での勤務を経て、TBS系列放映の”ここがヘンだよ日本人”にパネラーとして出演したのを機に、タレントとしての活動を始めました。 現在、日本を拠点に、作家、著述家、タレント、ナレーターとして活動しています。 日本人には外人顔に見え、メールや電話では問題はないものの、実際に対面したときに相手が顔と名前のギャップに混乱を起こすといいます。 かつて、アレキサンドラ・ヘーフェリンやヘーフェリン・アレキサンドラと名乗っていたこともあるそうです。 ”はじめに”で、ハーフあるあるを3つ掲げています。 1つ、初対面で、ハーフの男と聞かされた友人の友人は、ウェンツ瑛士やJOYのような、線の細い男をイメージするらしい。 2つ、ファーストフード店で、マクドナルドでカウンターに立つと、メニューをひっくり返して英語メニューにされる。 3つ、過度な期待で、勝手に股間に超巨大モンスターが付いていると思われている。 そんなハーフを取り巻く環境と、国際感覚のない純ジャパの特徴を紹介しています。 ハーフ・マトリックスには、理想ハーフ、顔だけハーフ、語学だけハーフ、残念ハーフがあるといいます。 理想ハーフは、語学が堪能で見た目も美しい、滝川クリステルのようなハーフです。 顔だけハーフは、容姿は目を見張るほど美しいが、使える言語は日本語オンリーです。 語学だけハーフは、日本語も外国語も自由に操れますが、容姿が普通の人たちです。 残念ハーフは、純ジャパの考えるハーフの特権を全くもっていない人たちです。 困った純ジャパには、積極的すぎる人々、思考停止する人々、偏見のある人々、親があるといいます。 積極的すぎる人々は、ハーフに対して好奇心旺盛で、初対面でいろいろと質問してきます。 どこの国のハーフ?、両親のどっちが外国人?という質問から、納豆は食べられる?、異性は日本人と外国人どっちが好き?まで尋問のようにまくしたてます。 思考停止する人々は、ハーフのガイジン顔を見ると頭のなかが真っ白になります。 外国人に話しかけられたと勘違いして動揺するタイプに多く、いくら日本語で話しかけても英語で返されたり、自分は日本人だと説明しても理解してくれません。 偏見のある人々は、外国人の女は軽いと根拠もないのに信じていたり、フランス人とのハーフの子供に生意気だ、調子に乗るな、と嫌味を言ったり、外国人というと不審者という価値観を持っていたりします。 困った親たちは、ハーフの子がほしい、だってそしたらモデルになれるから、欧米人と結婚したい、だって子供がブルーの目になるからとか思ったりします。 ほかにも、日本で暮らすハーフならではの苦労や体験談がいろいろと語られています。 ハーフにとってありがたい純ジャパは、現実を直視していて現実を理解できる人とのことだそうです。 また、ハーフでいて良かったと思えるのは、どちらの国にも”ただいま”と言えることであるということです。 第1章 ハーフと言ってもピンからキリまで第2章 ハーフのまわりの困った純ジャパ第3章 ハーフの「揺りかごから墓場まで」第4章 日本社会の片隅でハーフが叫ぶ
2016.06.12
コメント(0)
-
日本がわかる経済学(感想)
日本経済はいまどうなっているのでしょうか。 ”日本がわかる経済学”(2014年9月 NHK出版刊 飯田 泰之著)を読みました。 日本経済の仕組みを知るという、NHKラジオビジネス塾の番組の内容を書籍化したものです。 ビジネスシーンに活かすことを目的として、ビジネスに密接に関わる日本経済の仕組みや政策をわかりやすく解説しています。 NHKラジオビジネス塾は、35歳からのスキルアップを目的として月替わりでテーマを設け、中堅社員に向け仕事を進めていく上で必要な知識や情報を、様々なアングルから提供していく番組です。 飯田泰之さんは1975年東京都生まれ、海城中学・高校、東京大学経済学部卒業、東京大学大学院経済学研究科修士課程修了、同博士課程単位取得退学しました。 2003年駒澤大学経済学部現代応用経済学科専任講師・准教授を経て、2013年明治大学政治経済学部経済学科准教授を務めています。 ”日本経済の仕組みを知る”という番組は、2014年10月~12月に放送されました。 GDPってなんですか?、物価ってなんだろう?、経済は三本の脚で成り立つ、景気ってなんだろう?~統計から景気を読み解く~、 移す・積む・慣れる~成長のための3つの方法~、競争市場はもう存在しない?~差別化と価格硬直~、有効な財政政策と無効な財政政策、金融政策って何をすること?、 資産価格と安心、景気の”気”は気分の”気”、ビジネストーク”日本の経済政策と企業”(前編)、ビジネストーク”日本の経済政策と企業”(後編)でした。 経済学の理論は、大まかにミクロ経済学とマクロ経済学に分類されます。 ミクロ経済学は、個人や企業といった、何かを決める最小単位の経済活動から出発して、ボトムアップ式に、経済全体を語り起こしていこうとする経済学の分野です。 経済学という思考法の基礎にあたるのが、ミクロ経済学といってよいです。 このような特徴を持つミクロ経済学を学ぶことは、スポーツで言えば基礎練習、武道でいえば”型”を身につける訓練に似ています。 この型を身につけておけば、少なくとも合格点は取れるという、ビジネス思考の型を身につけ、それを実戦の中で磨き上げていく方が、成果は得やすくなると考えられます。 これに対して、マクロ経済学は、一国、ときには世界の経済全体を対象とする経済学の分野です。 たとえば、日本国の景気、失業、経済成長率、インフレ率など、経済全体に共通する指標が、どのように推移していくか、また、お互いにどのように影響し合っているか、といったテーマを扱います。 ビジネスや日常の生活とはあまり関係ないのではないか、と思われかもしれませんが、自分たちを取り巻く状況に応じて、とるべき行動、効率的な選択は変わってくるはずです。 たとえば、経済全体が好景気に向かって拡大していくとき、どのような投資に力を入れるべきでしょうか。 今自分たちが置かれている状況を知らなければ、いくら多彩な型・技を知っていても、それを有効活用することはできません。 私たちが生きていく上で知っておくべき、戦場の情報=自分たちは今、どんな場で戦おうとしているのか、を把握するのに役立つのが、マクロ経済学の知識です。 経済政策はマクロの経済環境に大きく影響しており、経済学の知識は民主主義下の国民の必煩知識です。 本当は、1970年代から需給バランスを重視した経済政策をとるべきだったのに、たまたま国際環境の変化や企業努力などによって、上手く乗り切れてしまっていました。 そのため、ここまでの日本は、需要管理政策=マクロ経済政策を軽視してきました。 そのツケが回ってきた1990年代、需要が不足することによって、売れないからつくらない、つくらないから企業は人を雇えない、雇用が悪化するから、ますます需要が不足する、という悪循環に陥っていきました。 そのとき、政府は有効な対策を講じられませんでした。 長引く不況の中で1990年代の日本企業が陥った罠が、短期的な収益を上げるために人を切るという方法でした。 企業がリストラを推し進め、海外生産の比重を高め、人件費を浮かせて、少ない売り上げで利ざやを確保するというのは、確かに合理的な面もあるかも知れません。 しかし、このような収益確保の方法は、企業にとって、さらには日本経済にとってタコ足配当です。 自分の足を食べて一時しのぎをしたところで、長期的には自滅への道です。 不幸にも、多くの日本企業は、この状況から脱却するのに時間がかかってしまいました。 2013年以降、わずかではありますが明るい兆しが見えるようになってきました。 人を育て、その育てた人が、また自分の会社に貢献してくれるようになるという、働き手と雇う側がWIN-WINになるような関係の構築が求められています。 働くこと、人を雇うことの位置づけが変わることこそが、現代の日本に必要とされているのではないでしょうか。第1講 豊かさを表す数字を知ろう!-”GDP””物価””景気”第2講 政策は幸福のためにある-”幸福の経済学””経済政策”第3講 成長はこうして生み出す!-”経済成長””価格硬直性”第4講 景気対策はどう効くか?-”財政政策””金融政策””資産価格”第5講 分配システムはどうあるべき?-”効率と平等””年金”第6講 経済学で人を動かす!-”割引率””アーキテクチャの力”第7講 人口から日本の未来を考える-”これからの企業””これからの都市”第8講 私たちはどこに立っているか?-”戦後の日本経済史”
2016.06.05
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1