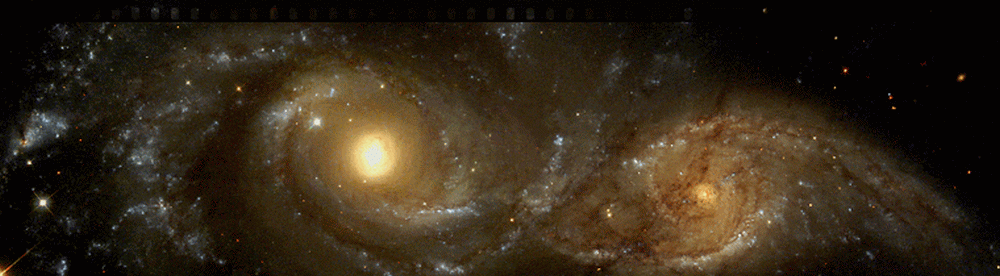2020年11月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-

柱だけの作りかけの家?(ラオス回想その60)
正月の正装(モン族)↑↓(2007年12月15日、ビエンチャン、ラオス) 4つ目は、至る所に、作りかけの家のようなものが建っていますが、どうしてなのか不思議です。柱が立ったまま野晒しになっている家。一見すると、解体中の家にも見えます。聞けば、お金が無いので、途中で作るのをやめているという。こういう家の建て方は、あちこちで見かけます。「お金が少しできたので、柱を4本建てることができた」とも解釈できます。面白いのは、ある程度できると住み始めてしまうことです。窓がまだ入っていなかったり、壁が入っていない家で、食事を御馳走になったことが何度かあります。お金ができたら一気に家を建てたほうがいいような気がします。でもよく考えたら、お金ができた時に、とにかく家の一部を作っておいて、お金がほかのものに使われないようにしておくのは、とてもいい考えだと思います。(了)【Bon appétit !】 Generally, houses in Laos are traditionally self-built and owner occupied. The most common type of house is built on columns to leave a space below the houses for various functions. Construction of the traditional houses uses mostly local building materials and local labour, which means lower costs, since transport costs, among others, are very low. Traditionally built houses often require more maintenance than modern building, but maintenance is easy since the building materials are locally available.(http://www.hdm.lth.se/fileadmin/hdm/alumni/papers/icm1999/icm1999-14.pdf)
2020.11.26
コメント(4)
-

働く子供たち(ラオス回想その59)
中学生たち↑(2010年1月21日、ビエンチャン)村の子供たち↑(2007年12月15日、ビエンチャン) 3つ目の不思議は、どうして、子供が学校に行かないのか不思議です。地方の村に行っても小学校があり、教育には熱心に見えます。学校に通う子供たちもよく見かけますが、よく聞くと、学校に行っていない子供が多いといいます。確かに、町中では日中でもたくさんの子供たちが働いている場面を目にします。学校建設の支援がいたるところで行われていますが、就学率の向上には結びつきません。支援国がただで建物を作ってくれることに反対する村はありませんが、学校という建物ができることと、就学率が上がることは、別問題です。どうして、子供が登校しないか、あるいは、登校させないのか、その理由を知りたいと思います。あるラオス人は、教える先生がいないし、教材もないと言います。また、学校で勉強しても、学問を活かす場所がありませんので、学校に行っても無駄だと言う人もいます。また、ある人は、子供は、親の生活を助けるのが本業だと言います。どうも、子供に投資しても無駄だという考えが親の側に強いような気がしますが、真相はどこにあるのでしょうか。(続く)【Bon appétit !】 Education is compulsory, free, and universal through the fifth grade; however, high fees for books and supplies and a general shortage of teachers in rural areas prevented many children from attending school. There were significant differences among the various ethnic groups in the educational opportunities offered to boys and girls. Although the government's policy is to inform ethnic groups on the benefits of education for all children, some ethnic groups did not consider education for girls either necessary or beneficial.(http://factsanddetails.com/southeast-asia/Laos/sub5_3d/entry-2981.html)
2020.11.25
コメント(2)
-

必需品より贅沢品?(ラオス回想その58)
掃き掃除する子供↑(2007年12月2日、シェンクワン、ラオス)棚田で農作業↑(2007年12月2日、シェンクワン、ラオス) 2つ目の不思議は、国連の分類では、最貧国と言われるラオスですが、人々はぜいたく品と思えるものを購入します。どうして、必需品よりぜいたく品を好むのか不思議です。食べるものに困っていないということが背景にあるのでしょうが、どうも、食べるものを我慢してでも、ぜいたくなことにお金を使いたいようです。貴金属をよく購入します。大音量の音響セットを購入して庭でパーティーを頻繁に開催します。結婚式なども何百人という人が出席します。(続く)【Bon appétit !】 Income inequality in Laos remains a pressing issue although general poverty levels are decreasing. The Laotian Gini coefficient, which measures income inequality, increased from 0.311 to 0.364 from 1993 to 2013. This inequality rose amongst all ethnic groups in Laos and across both rural and urban regions. However, despite the rise in overall inequality, “access to publicly provided services (primary education, lower secondary education, access to health care and household access to the electricity network) has become more equal.” In addition, the absolute poverty rate in Laos has been cut in half from 46 percent of the population living in absolute poverty to only 23 percent.(https://borgenproject.org/top-10-facts-about-living-conditions-in-laos/)
2020.11.24
コメント(0)
-

現金は何処から?(ラオス回想その57)
真っ赤な道↑(2007年11月25日、ビエンチャン)四つ手網による魚とり↑(2007年11月25日、ビエンチャン) ラオスは素晴らしい国であるが、同時に、とても不思議な国です。 不思議の一つは、どうして、人々が現金を持っているかということです。収入を聞けば、月に30ドル以下しかない人はそこら中にいます。それなのに、ラオス人は、月給の何倍もするような携帯電話やテレビを持っています。どこに、そのお金があるのかとても不思議です。海外にいる親類からの仕送りだという人もいます。どこから自動車を購入するお金がでてくるのでしょうか?(続く)【Bon appétit !】 Despite rapid growth, Laos remains one of the poorest countries in Southeast Asia. A landlocked country, it has inadequate infrastructure and a largely unskilled work force. Nonetheless, Laos continues to attract foreign investment as it integrates with the larger ASEAN Economic Community, its plentiful, young workforce, and favorable tax treatment.(https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Laos)
2020.11.23
コメント(0)
-

様々な環境指標の記録が必用(ラオス回想その56)
祭の日↑(2007年11月24日、タートルアン、ビエンチャン)お祈りする人々↑(2007年11月24日、タートルアン、ビエンチャン) 以上の例は、支援国が現象だけを見て、短絡的に解決策を持ってくることにより生じた事例です。ラオス支援に当たっては、現象だけに注目しないで、そこに横たわる原因をしっかりと把握する必要があります。支援国でうまくいっていることであっても、ラオスではうまくいかないことがあります。ラオスの伝統的な文化や蓄積された知識を育てる方向で支援をする必要があります。ラオスが今ある理由を無視してラオス固有の文化や知識が安易に外部のシステムにとって代わられることがないように支援をする必要があります。特に、従来からの農法や伝統的な種子、森林管理方法、土地の使い方等を発展させる支援が必要です。 開発とは別に、ラオスで行うべき急務は、環境に係る現状の記録です。どのドナーも開発にばかり目が行き、現状の記録がおろそかになっています。 ラオスの開発が、先進国の二の舞になることは目に見えています。その緒に着いたばかりの今だからこそ、今のうちに、さまざまな環境指標を記録しておき、それらがどう変化していくのか追跡していくことが必要です。例えば、動物の体内に含まれる汚染物質濃度、母乳に含まれる汚染物質、空気の汚染度、川の汚染度、生物多様性等を追跡することです。開発段階を追うごとにそれがどう変化していくのかを知り、データとして記録しておく事が、証拠に基づいた開発へ導くカギとなります。(続く)【Bon appétit !】 Laos is among the least developed and poorest countries in Asia, but significant economic growth in the past decade has benefited the country. Challenges remain, however, and the Lao economy remains dependent on external demand for its natural resources, particularly mining, hydropower and forestry. Regulatory capacity and knowledge of market economies within the Government of Laos is limited and threatens future sustainable growth and the country's ability to address economic vulnerabilities.(https://www.usaid.gov/laos/economic-growth-and-trade)
2020.11.22
コメント(2)
-

汽車のマスク懐紙(新型コロナウイルス対策)
汽車のマスク懐紙↑(2020年11月14日、東京) 汽車の絵が描かれたマスク懐紙が使われていました。 マスク懐紙という言葉が市民権を得ているのかよくわかりませんが、使用したマスクを外した時に、マスクの一時的置き場として使用するものです。 最近はレストランで抗菌紙を二つ折りにしたマスク懐紙が用意されていますが、たいていは白無地の紙が使用されています。 先日訪問した京葉線潮見駅前のホテルのレストランでは、しゃれたマスク懐紙がテーブルに用意されていました。私の好きな蒸気機関車の絵が描かれているマスク懐紙もあり、大喜びしました。 I was glad to see a mask case with an illustration of a steam locomotive which had been prepared by a restaurant in order not to put an used face mask directly on a table.【Bon appétit !】 These discoveries led public health groups to do an about-face on face masks. The World Health Organization and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) now include face masks in their recommendations for slowing the spread of the virus. The CDC recommends cloth face masks for the public and not the surgical and N95 masks needed by health care providers.(https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-mask/art-20485449)
2020.11.21
コメント(2)
-

住民の選択肢がない支援(ラオス回想その55)
水牛の親子↑(2007年11月20日、ビエンチャン)牛のために稲刈りは穂首刈り↑(2007年11月20日、ビエンチャン) また、ある村人は次のように語った。 「農業生産改善プロジェクトで、ドナー国の指導で新しい品種を導入した。新しい品種は、在来の品種より収量が高くなるとのことだった。実際使ってみると、生育方法に不慣れであることに加え、新品種は土着の品種に比べて病気や虫害に弱いので、上手く育てられなかった。しかも、在来品種のようにこの地域の病虫害に強くなかったので、新たに農薬を使用した。今後、農薬を買うお金はないし、在来品種に戻りたくても在来品種の種子の生産は取りやめてしてしまったので、これからどうしたらよいか困っている。」 開発支援と言いながら、村人に押し付けているような支援が見受けられるのが現状です。住民と十分話し合って支援をすべきですが、多くの支援機関は、まず支援ありきで来ていますので、住民の選択肢はあまりないのが実態です。(続く)【Bon appétit !】 Agricultural policies in Laos are aligned to make the country self-sufficient in terms of cereal production. As the nation has reached self-sufficiency in rice production, the export ban on rice is removed and the Laotian Ministry of Agriculture and Forestry aims to export 1 million metric tons of rice to its neighboring nations (like China) by 2020. There are collaborative research programs in Laos, with the International Rice Research Institute (IRRI), for the development of better varieties, suitable for the Laotian climate.(https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/seed-sector-analysis-laos-industry)
2020.11.20
コメント(6)
-

歓迎される洪水もある(ラオス回想その54)
タムマークフン(パパイヤサラダ)を作る↑(2007年11月20日、ビエンチャン)子供と豚↑(2007年11月20日、ビエンチャン) ある村人が次のような話をしてくれました。 「ここの農地は、毎年のように洪水が起こっていた。数年前、洪水が起こらないように川の護岸工事を行ったが、そのために、肥沃な泥が運ばれなくなり、作物の生産量が極端に減った。また、川岸は、乾季の間の優良な畑として使っていたのに、護岸工事のせいで川岸が使えなくなってしまった。」 私は、次のような経験をしていましたので、彼の言うことが良く理解できました。サワンナケート県のある村に行った時、ブルドーザーが道を整地していました。村長が言うには、洪水のせいで道路が流れたので、整えているのだそうです。さらに、その辺りは、毎年のように洪水に見舞われるのだと言います。それならしっかりした堤防を作ればいいのではないかと聞いてみようと思いましたが、話をしていて、村長が洪水を歓迎してるということに気が付き、私自身かなり驚いた経験があります。(続く)【Bon appétit !】 The 2018 Laos dam collapse was the collapse of Saddle Dam D, part of a larger hydroelectric dam system under construction in southeast Laos's Champasak Province, on 23 July 2018. The dam collapse lead to widespread destruction and homelessness among the local population in neighbouring Attapeu Province. As of 25 September, 40 people were confirmed dead, at least 98 more were missing (maybe as many as 1,100 more people), and 6,600 others were displaced.(https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Laos_dam_collapse)
2020.11.19
コメント(4)
-

化学肥料の利用は慎重に(ラオス回想その53)
稲刈り↑(2007年11月7日、ルアンパバン、ラオス)料理↑(2007年11月6日、ルアンパバン、ラオス) 農業での化学肥料の使用に関して、次のような話を聞きました。 「収量を上げるために化学肥料を導入したら収量は増えた。ところが、化学肥料により土地がやせるので、さらなる化学肥料が必要となる。化学肥料は、現金で購入する必要があるので、現金が必要となり貧困になってしまう。化学肥料をやめるにも、土がぼろぼろで元に戻せない。」 開発援助は、草の根的なアプローチが必要です。住民が今までどのようなことに工夫を凝らし、何を必要としているかです。そもそも農民が現在の収量をふやす必要を感じていないのであれば、無理して収量を上げる必要はありません。収量を増やすとしても、土地や労働力が有り余っている場合には、面積を増やせばいいだけで化学肥料を使って単位面積当たりの収量を増やす必要はありません。そもそも現金を得る手段が無い人々に化学肥料を使わせることには無理があります。従来通り、水牛の糞や、洪水のときに運ばれる土壌を当てにする方法のほうが合理的なことが多い。(続く)【Bon appétit !】 Despite around 70 percent of Laotians working in the agricultural sector, subsistence farming is still the norm and traditional production methods do not produce enough to meet market demand. Many families struggle to even meet their own household food requirements – let alone having surplus for export – making malnutrition a critical issue.(https://theaseanpost.com/article/why-agriculture-investment-lao-lacking)
2020.11.18
コメント(0)
-

越中島支線のDE10とチキ
チキ編成貨物列車を牽くDE101697↑↓(2020年11月14日、江東区、東京都) 越中島貨物駅(江東区)近くを歩いていたら、踏切がありました。総武本線の貨物支線で、小岩駅と越中島貨物駅を結んでいて、一日3往復の列車ダイヤが組まれています。 丁度、貨物列車が通過しました。DE101697が牽引するチキ編成の貨物列車で、積み荷は鉄道のレールです。これは、越中島貨物駅にある東京レールセンターから発送されたものでしょう。 DE10は向かって左側の赤色灯を一灯だけ点灯しています。これは、入換動力車標識の印です。貨物線を走っているのになぜ入換標識か不思議ですが、その理由は、越中島貨物駅から3.1kmまでの区間は駅構内の取り扱いになっているので、同区間は入換運転のため、入換動力車標識を表示して運転することになっているとのことです。 DE101697は、なんと、平成20年11月12日 天皇皇后両陛下とファン・カルロス1世スペイン国王陛下夫妻ご利用のお召し列車が運転された際、常磐線藤代駅にある交流・直流切換を行うデッドセクション区間における非常時に備えて待機していた機関車です。 I happened to meet one of freight trains which run three times a day on the Etchujima Freight-traffic Line in Koto Ward, Tokyo.【Bon appétit !】 It would seem that the only remaining trains on the line are JR East maintenance trains, carrying welded rail sections from the yard in Shiohama, where it appears the rails are delivered by ship and assembled into longer lengths before being loaded on strings of flat cars rigged with frames to carry them. A few small switchers work the yard, and DE10 locomotives appear to be the usual motive power on the maintenance trains.(http://www.sumidacrossing.org/Prototype/JRFreight/NonFreightLines/)
2020.11.17
コメント(0)
-

メコン川の危機(ラオス回想その52)
メコン川の魚↑(2009年7月19日、ビエンチャン)メコン川に浮かぶ灯籠舟と流し灯籠↑(2007年10月26日、ビエンチャン) 2010年の初め頃、あるラオス人から次のような話を聞きました。 「タイ企業によるラオス西部サイニャブリダムの開発は大変なことになる。これは、中流域のメコン川本流に作られる初めてのダムだ。流域の住民に多大な影響を与えるだけでなく、生態系に与える影響は計り知れない。タイの企業によりダム建設が進行中で、将来の電気の一部は既にタイに売ってしまっているようだ。もう諦めるしかない。」 サイニャブリのダム建設に対しては、下流のカンボジアやべトナムは猛反対していました。また、メコン川の開発は国際機関であるメコン委員会では、更なる環境影響調査を行うべきとしていましたが、ラオスは、環境に影響なしとして開発にゴーサインを出していました。ラオスはこのダムから得られる電力をタイに売却して外貨を得ることを考えていました。メコン川にいるメコンオオナマズや川イルカへの影響は必至です。また、ダムの下流域では洪水が起こらなくなり、今まで洪水によりもたらされていた肥沃な土壌が運ばれなくなる可能性もあります。(続く)【Bon appétit !】 Drought linked to a changing climate and dozens of hydroelectric dams are damaging the Mekong ecosystem. When drought ends and the inevitable floods begin, the effects of Mekong dams on flood pulse dynamics over the entire Lower Mekong are poorly understood.(https://en.wikipedia.org/wiki/Mekong)
2020.11.14
コメント(2)
-

村人の共有林が無くなる(ラオス回想その51)
手前の卵は孵化寸前の卵を蒸したもの(カイルーク)↑(2007年10月25日、ビエンチャン)出安居の日のお祈り↑(2007年10月26日、ビエンチャン) 「ラオス南部でも、かなりの木材が伐採されていて、サワンナケートからベトナム国境のデーンサワンへ行く舗装道路は、違法伐採木材を積んだ過積載トラックの影響で、短期間でぼろぼろだ。村人の共有林が地方政府に取り上げられて、木材が伐採された。」という話もあちこちで聞きます。 私が、初めてラオスの地を踏んだ2007年には、この道路はとても快適であったが、数年後には、穴だらけで、穴をよけながら走行しなければならなくなったと聞いています。 村の共有林は、住民に自然の恵みをもたらす大切なセーフティーネットとなっています。共有林は一定の面積が未開発のまま残っていますので、開発業者が共有林を自分たちの物にして手を入れる例があとをたちません。村民の権利を守るための支援をしている日本のNGOが、開発業者の手から村の共有林を守る活動を行ってきていますが、当該共有林を守ることができても、隣村の共有林まで守ることはできないことのむなしさを語ってくれたことがあります。開発業者の提示する魅力には大きなものがあります。例えば、共有林や保護林を開発する見返りとして、寺の改修、学校建設、道路改良等の支援を申し出ます。目先の利益に負けて開発を許す事例が後を絶ちません。共有林が使えなくなることは、村人の生活が大きく変化することを意味します。森林や川で生計を立てることができなくなりますので、村人たちは、食料を手にするために現金が必要となり、それは、それまでの裕福な生活から貧困な生活に陥ることを意味しています。(続く)【Bon appétit !】 This National Road No. 9 improvement project is one of the priority projects in the Government’s development plan for 2000-2015, as Lao PDR has no sea border, this road will be a strategic link to sea ports in neighboring countries and provide transit for freight transportation. The National Road No. 9 improvement project makes an important contribution to basic transportation infrastructure development within Savannakhet as well as Lao PDR by raising standards to international levels. It also enables Lao PDR, a land locked nation, to become a transit country for the sub-region.(https://www.mpwt.gov.la/en/news-en/provinces-news-en/389-opening-road-no9-news-en)
2020.11.13
コメント(2)
-

将門塚改修中
臨時遥拝所↑(2020年11月10日、大手町、東京)工事の壁で取り囲まれた将門塚↑(2020年11月10日、大手町、東京) 大手町の、将門塚の回りが工事中の壁に取り囲まれていました。 壁の一部が臨時の遥拝所になっていました。 説明文によると、この工事は、1961年の第1次整備工事以来数えて第6次目の改修工事となるとのことです。工事期間は来年4月末までだそうです。 They are working on maintenance of area of the kubizuka (head-mound) of Masakado in Otemachi, Tokyo and will complete the work in April, 2021. 【Bon appétit !】 Over the centuries, Masakado became a demigod(神格化された英雄)to the locals who were impressed by his stand against the central government, while at the same time feeling the need to appease(和らげる、なだめる)his malevolent(荒ぶる、悪意のある)spirit. The fortunes of Edo and Tokyo seemed to wax and wane(盛衰する)correspondingly with the respect paid to the shrine built to him at the kubizuka ― neglect would be followed by natural disasters and other misfortunes. Hence, to this day, the shrine is well maintained, occupying some of the most expensive land in the world in Tokyo’s financial district facing the Imperial Palace.(https://en.wikipedia.org/wiki/Taira_no_Masakado)
2020.11.12
コメント(2)
-

湿地帯の危機(ラオス回想その50)
タートルアン湿地帯↑(2009年12月26日、ビエンチャン)四つ手網漁↑(2007年11月25日、ビエンチャン) また、次のような意見も耳にした。 「ビエンチャン郊外の湿地帯の開発が予定されているが、ここは、村人に食料となる魚を供給している場所だ。湿地帯は、水の浄化作用を担っていいて、天然の汚水処理場だ。実際、かなりの汚水をこの湿地帯が処理している。」 湿地帯を失ったら、ビエンチャンの汚水を処理する施設を新たに作る必要となり、ますます、大きな投資が必要となる。また、魚が取れなくなれば、魚に代わる食料を購入するための現金が必要となり、現金を持っていない人は、貧困になります。(続く)【Bon appétit !】 In the mid-1990s it was estimated that Vientiane Prefecture contained almost 1,500 km2 of permanent and seasonal waterbodies, floodplains, swamps and marshes. These wetland areas supply a wide range of economically valuable goods and services, including fisheries, farming and natural resource collection activities, flood attenuation(減衰), maintenance of water quality and supply, and treatment of domestic, agricultural and industrial wastes. That Luang Marsh is the largest of these urban wetlands. Situated on the outskirts of Vientiane City, it provides important resources and agricultural land for local communities both in the city and in the bordering rural areas. It also functions in flood protection and water treatment for the urban center.(https://iwlearn.net/files/pdfs/Gerrard%202004_Integrating%20wetland%20ecosystem%20into%20urban%20planning.pdf)
2020.11.11
コメント(0)
-

森林の過剰伐採(ラオス回想その49)
稲刈りの風景↑(2007年10月17日、ビエンチャン)水牛たち↑(2007年10月17日、ビエンチャン) 私は、2009年の雨季にメコン川の水が少なく中洲が見えていたことに危惧を感じていました。知人のラオス人に理由を聞いたら、中国が上流にダムを造ったからだと答えてくれました。確かにその影響はあるかもしれませんが、限定的と考えています。メコン川は大河です。さらに、たくさんの支流があります。中流域にダムが建設されたら、壊滅的な影響は避けられませんが、はるか上流にダムができたくらいでは水はなくなりません。その意味では支流のダムによる流れ込む水の減少の影響はあると思います。しかしながら、私は、むしろ問題にすべきは、ラオス北部の森林の過剰伐採であろうと考えています。過剰伐採のために、山に保水力が無くなっています。水源が減少しているのです。本来であれば、降った雨は、山に保水されます。しかし、過剰伐採が起きている現場では、雨が降れば保水できずに、雨水が一気に川に流れ出します。実際、洪水が無かったビエンチャンで、2008年にはメコン川が30年ぶりに氾濫を起こしています。山に保水力が無くなれば、洪水は頻繁に起こるようになります。(続く)【Bon appétit !】 The extent of deforestation across Laos has been obscured by the rise in illegal logging, despite reported efforts to reverse the destruction in recent years. A 2015 study from the World Wildlife Fund revealed the true extent of the illegal logging trade, with exports to China and Vietnam reaching 1.4 million cubic meters in 2013, environmental news website Mongabay reported, a figure four times above the national quota and falling just short of 10 times the registered annual haul.(https://thediplomat.com/2018/01/with-its-environmental-crisis-is-laos-missing-the-forest-for-the-trees/)
2020.11.10
コメント(2)
-

開発の現状(ラオス回想その48)
朝の風景↑↓(2007年9月27日、サワナケート、ラオス) 開発の現状はどうなっているのでしょうか? ラオスに投資している国は、ベトナム、中国、タイの3カ国が従来から上位に食い込んでいます。近年は、中国の伸びが目立っています。 投資部門は、発電や鉱業が多く、次いで、サービス業、農業、工業・手工業となっています。 ラオス人や開発業務に携わっている人から様々な意見を耳にしました。 「中国の開発支援はすごい。道路、鉄道、陸上競技場、ゴム林、セメント工場等目立つ支援を行っている。彼らは、見返りとして、鉱山資源、木材、居住権等をラオスから得ている。その結果、ラオス北部の山は、過剰伐採により丸裸。開発すると称して、開発予定地にある木だけ持って行ってしまうこともあると聞いたことがある。」 私は、2009年の雨季にメコン川の水が少なく中洲が見えていたことに危惧を感じていました。(続く)【Bon appétit !】 Lao PDR will not only need to attract more investment but also to make sure investors act responsibly. Lao PDR also faces governance issues, with private sector representatives complaining of a wide-ranging lack of transparency, constant policy uncertainty and inconsistent application of the law.(https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276055-6-en.pdf?expires=1604841158&id=id&accname=guest&checksum=83BFB9B1BB974A27CE27762A29A3BF37)
2020.11.09
コメント(9)
-

健気な柳に涙す
新しい枝を出す、伐採された柳の木↑(2020年11月2日、皇居)説明文↑(2020年9月10日、皇居) 切り倒された柳の木から、新しい枝が伸びていました。 切り倒されてもなお生き延びようとするその生への執着に涙してしまいました。 皇居のお濠端にあるこの木は、街路樹診断の結果、樹形生育不良、腐朽空洞度50%で倒木の危険があるC判定と診断されました。 強風等による倒木の危険があるということで即伐採されました。 頑張って生き延びようと新しい枝を生やしましたが、間もなく、抜根されるようです。 New branches are extending from a trunk of cut willow on the moat of the Imperial Palace. I was moved by its capacity to sustain life, though the tree is destined to be pulled up by the root soon. 【Bon appétit !】 Proper pruning(剪定)is essential when it comes to tree care. After all, when incorrectly pruning, you make your tree vulnerable to any sort of illness, not to mention pests as well. When you prune your trees, you encourage new growth, as well as prevent decay. Last but not least, you make your trees structurally sound. Make sure that tree trimmings focuses on removing dead branches. Also, you should aim at eliminating crossing branches, as well as having a canopy(樹冠)lift.(https://www.treeserviceslittlerock.net/how-to-treat-sick-tree/)
2020.11.08
コメント(2)
-

自分たちは貧困だと知らされた(ラオス回想その47)
村の家族↑(2007年9月26日、サワナケート、ラオス)昼食↑(2007年9月26日、サワナケート、ラオス) ラオス人に聞くと、「自分たちは、これまで貧しいと思ったことはなかった。それが、諸外国からの援助が来て初めて、自分たちが貧困だと知らされた。」という答えが返ってきます。 現在の貧困は、過去から続く慢性的なものではありません。桃源郷のような生活がラオスにはあったことは、多くの昔の紀行文から伺い知れます。実は、桃源郷のような生活は今もあります。現代の物差しでは、それを貧困と呼んでいます。 開発する側にいる人間が、ラオスに貧困という言葉を持ち込みました。確かに、貧困は、過去から続く慢性的なものではありません。近年になってもたらされたものです。援助機関は、貧困削減、近代化という名目で開発します。当のラオス人は豊かな生活を送っているのに、いきなり、「お前たちは貧しいから助けが必要だ。」と言われます。 開発により、自然の恵みや村人の知恵と助け合いの仕組みをはじめとするセーフティーネットが破壊されることを私は恐れます。さらに、開発の結果として、現金に依存する生活を強いられ、本当に貧困に陥ることを私は恐れます。(続く)【Bon appétit !】 In addition to strictly agricultural activities, the daily lives of rural people involve a number of other tasks, such as fetching water from wells, hunting for game, and gathering various forest products. Common forest products include small game, birds and eggs, fruit, honey, spices, medicines, resins, latexes, dyes, and wood for fuel and for making charcoal, as well as structural materials such as rattan, bamboo, wooden poles, and various fibres.(https://www.britannica.com/place/Laos/Daily-life-and-social-customs)
2020.11.07
コメント(0)
-

満開の十月桜
上野公園の十月桜↑(2020年11月2日、上野、東京)お堀に浮かぶ鴨たち↑(2020年11月4日、皇居) 上野公園の十月桜が、満開でした。 上野公園では今年の10月に一部のソメイヨシノが開花するという事態が起こりましたが、十月桜は、例年同様に10月頃からしっかりと咲いています。 October Cherry is in full bloom now at Ueno Park. 【Bon appétit !】 The most popular variety of cherry blossom in Japan is the Somei Yoshino. They bloom and usually fall within a week, before the leaves come out. Winter sakura or fuyuzakura begins to bloom in the fall and continues blooming sporadically throughout the winter.(https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_blossom)
2020.11.06
コメント(10)
-

豊かな貧困(ラオス回想その46)
小学生等↑(2007年9月26日、サワナケート、ラオス)高床式家屋の床下には家畜↑(2007年9月26日、サワナケート、ラオス) ラオス人の所得水準は低く、1日2ドル以下で暮らす人は国民の7割近いと言われています。国家公務員の給与は他業種に比べて低い。私がラオスへ行った2007年の新規採用者は年収220ドル。中堅クラスで年収600ドル。局長級でも年収1,000ドル。 ビエンチャンに住んでいれば、確かにこの額では、どうやって生活しているのだろうかと疑問に思います。ほかに収入が無ければやっていけないのでしょう。公務員の多くは、副業を持っていますので、そちらの収入が当てにされているのかもしれません。私が知っている局長級の国家公務員は、朝、魚取りをして市場で売ってから出勤しています。食堂を経営している人も見かけます。子供から大人まで家族全員体制で働いているのでやっと生活できるということでしょうか。 でも、貧困は感じられません。物質的にも豊かです。ビエンチャンでは、大きな家や車を所有する人は多い。携帯電話を持っている若い人も多く見かけます。世間一般で言われる貧困とかけ離れています。 ラオス人に聞くと、「自分たちは、これまで貧しいと思ったことはなかった。それが、諸外国からの援助が来て初めて、自分たちが貧困だと知らされた。」という答えが返ってきます。(続く)【Bon appétit !】 GENEVA (19 June 2019) – The Lao People’s Democratic Republic should urgently adopt widespread reforms to alleviate poverty, protect the rights of people in poverty and ensure economic growth benefits the poorest, an independent UN expert said in a report released today. The Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Philip Alston, urged the Government to eliminate corporate tax loopholes(抜け穴), reassess its dependence on dubious(うさんくさい)infrastructure projects and land concessions, and invest in education, health and social support.(https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24710&LangID=E)
2020.11.05
コメント(2)
-

自給自足から現金に依存する暮らしへ(ラオス回想その45)
ある日のディナー↑(2007年9月25日、サワナケート、ラオス)乗り合いバス↑(2007年9月21日、ルアンパバン、ラオス) ラオスは、国連が定めた分類によれば、最貧国と分類されます。ラオスは経済的に絶望的な貧困状態にあると理解している人が多い。ラオスに初めて来た人が驚くことの一つは、ラオスの人は皆が豊かなことです。 自給自足的、物々交換的生活が多いため、経済指標に表れないのがその理由の一つです。 最近恐れていることがあります。ラオス人が時間をかけて育んできたセーフティーネット崩壊の恐れです。村人たちは豊かに生活するために、様々な仕組みを従来から作り上げて来ました。その中で、お互いに助け合うこと、自然の恵みを活用すること等のセーフティーネットができあがっています。セーフティーネットのお陰で、人々の暮らしは豊かでした。ところが、最近は、開発が進められていく中でセーフティーネットが壊れ始めています。人々が本当に貧困になっていく恐れがあります。 ラオス人の所得水準は低く、1日2ドル以下で暮らす人は国民の7割近いと言われています。(続く)【Bon appétit !】 The economy continues to be dominated by an unproductive agricultural sector operating largely outside the money economy and in which the public sector continues to play a dominant role. Still, a number of private enterprises have been founded in industries such as handicrafts, beer, coffee and tourism.(https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Laos)
2020.11.04
コメント(2)
-

皇居に来た白鷺
寄って来た白鷺↑(2010年11月2日、皇居)巽櫓を見る白鷺↑(2010年11月2日、皇居) 寒くなって来て、皇居のお堀には、たくさんのカルガモが泳いでいて賑やかです。 白鷺(ダイサギ)も、お堀でそろりそろりと魚を獲っています。なかなかお上手に、魚を口にくわえます。 魚を獲る白鷺を見ていたら、こちらに向かって飛んできて、足元に降り立ちました。人に慣れているのでしょうか。 暫く一緒にいましたが、その後、お堀に沿って飛び立っていきました。 I saw a heron catching fish in water on the moat of the Imperial Palace. The heron suddenly flew up and came to my foot and stayed with me looking at the moat. 【Bon appétit !】 For over 250 years, Japan was ruled by the Tokugawa shogun during what was known as the Edo Period – Edo being the old name for Tokyo. The current Imperial Palace, known as Koukyo in Japanese, sits on the former site of Edo Castle. However, in 1868, the shogunate was overthrown, and Japan’s capital was moved from Kyoto to Tokyo, with the Imperial Residence moving with it.(https://www.gotokyo.org/en/story/guide/a-noble-look-at-tokyos-imperial-palace-a-guide-to-the-royal-residence/index.html)
2020.11.03
コメント(4)
-

従来のシステムが破壊されている(ラオス回想その44)
雨上がり↑(2007年9月15日、ビエンチャン)花屋さん↑(2007年9月15日、ビエンチャン) ラオスが抱える第4の問題点は、開発援助の多くが、ラオスを食い物にしているという問題です。投資と言う名目で、鉱物資源が奪われています。また、土地が国外企業に占有され、多くの外国人が移住しており、山に植えられている木がどんどん姿を消しています。また、ラオスが有する伝統的な知識や文化に関係なく、先進国のシステムが持ち込まれるために、従来のシステムが破壊されています。特に、自然の恵みを生かした生活、村の中にあるセーフティーネットの仕組みが失われています。伝統的な農法、種子、森林管理方法が失われています。(続く)【Bon appétit !】 The Mining industry of Laos which has received prominent attention with foreign direct investments (FDI) has, since 2003–04, made significant contributions to the economic condition of Laos. More than 540 mineral deposits of gold, copper, zinc, lead and other minerals have been identified, explored and mined.(https://en.wikipedia.org/wiki/Mining_industry_of_Laos)
2020.11.02
コメント(2)
-

食料偏在の問題(ラオス回想その43)
サンドイッチ(カオチーパテ)屋台↑(2007年9月15日、ヴィエンチャン)市場のパン売り場↑(2007年9月15日、ヴィエンチャン) ラオスが抱える第3の問題点は、食料です。生産、流通、衛生の問題があります。 生産の面からみると、食料の量は潜在的には十分にあります。自然の恵みに恵まれていますので、食料が足りなくなることはありません。ただ、農産物の正確な生産量が把握されていませんので、国全体としての食料需給状況を把握できず、例えば主食である米不足の事態を事前に察知することが難しい。また、地域ごとの食料需給状況もわからないために、食料の偏在が生ずることがあります。近い将来人口が爆発的に増えることが想定され、自給自足的社会が崩壊することとなりますので、生産力の増強を今のうちに行っておく必要があります。 食料を流通の面からみると、流通は、道路等のインフラの未整備、流通そのものの未整備から、国内における食料の偏在が避けられません。また、価格情報が十分に伝わらないことが、食料の偏在に拍車をかけています。 食料を衛生の面からみると、基本的には自給的消費を行っていますので、それほど大きな問題とはなっていません。現状では、冷蔵施設や定温流通システムの必要性は低いかもしれませんが、将来流通が発達してくれば衛生は大きな問題となるでしょう。 ラオスが抱える第4の問題点は、開発援助の多くが、ラオスを食い物にしているという問題です。(続く)【Bon appétit !】 According to the Global Hunger Index (2018), Laos ranks as the 36th hungriest nation in the world out of the list of the 52 nations with the worst hunger situation(s). In 2019, the UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights conducted an official visit to Laos, and found that the country's top-down approach to economic growth and poverty alleviation(軽減)"is all too often counterproductive(逆効果), leading to impoverishment and jeopardizing the rights of the poor and marginalised.(https://en.wikipedia.org/wiki/Laos)
2020.11.01
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
-

- あなたの旅行記はどんな感じ??
- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい
- (2025-11-16 22:43:16)
-
-
-

- 日本全国の宿のご紹介
- 【静岡*焼津・藤枝・御前崎・寸又峡…
- (2025-11-18 15:50:22)
-
-
-

- フランスあれこれ・・・
- 【PARIS】【illuminations de Noëlク…
- (2025-11-19 04:20:29)
-