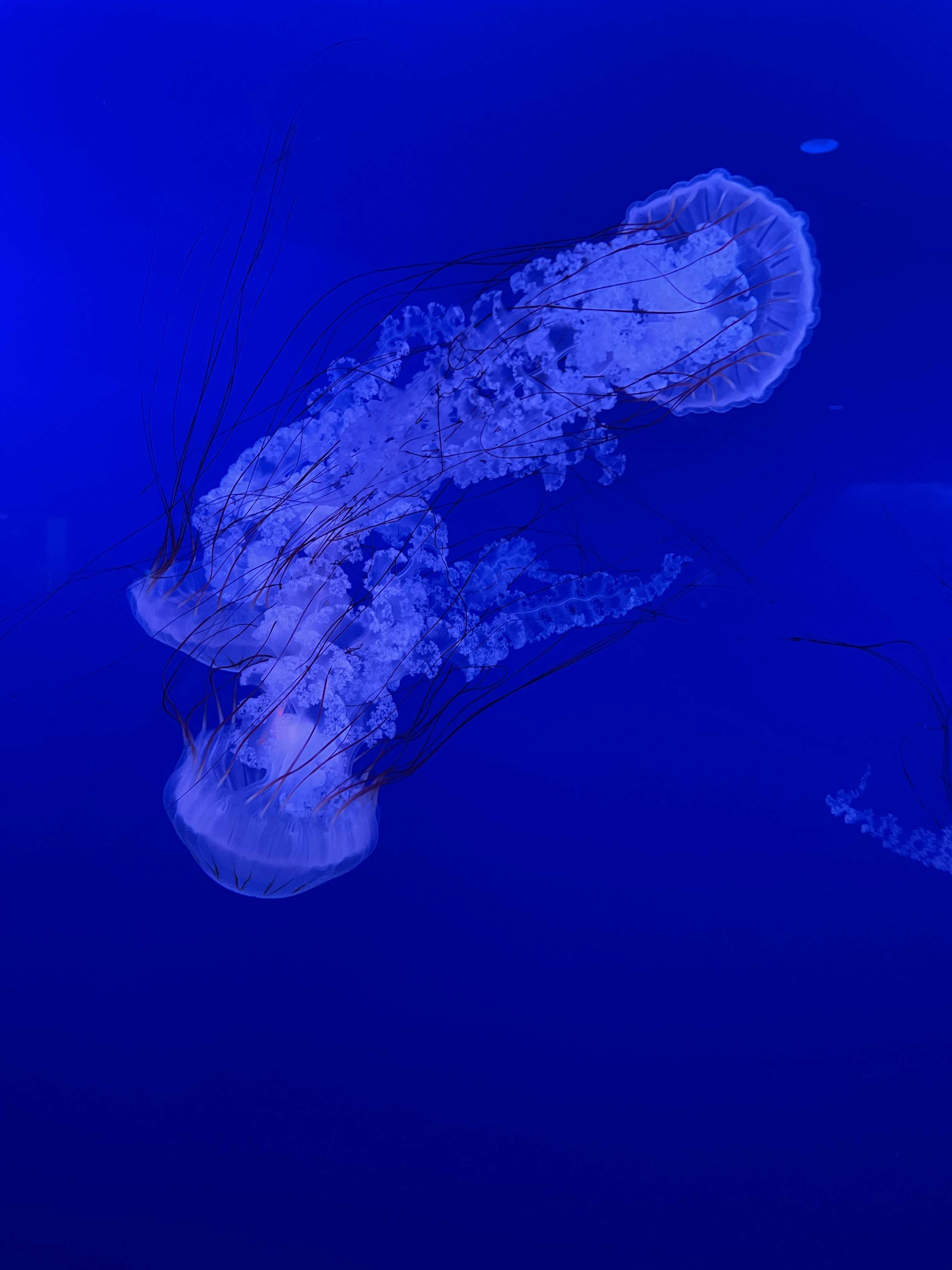2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年04月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
朝井を続投させた持ちがよくわかる。
楽天に限らず、今年は全般的に投手陣が奮闘しているので、防御率成績が凄まじいことになっている。その中で朝井の防御率3点台後半は、岩隈、田中、永井が0点台、1点台、2点台と上出来だけに物足りないと映るかもしれない。しかし5試合投げての3勝2敗は昨年の8勝からすれば申し分ない。だが投球回数の少ないということは彼の投球スタイルからすれば物足りないといわざるをえない。なぜなら、それなりの速球を投げるとはいえ緩急を使う投手は速球派というよりは技巧派なのだから、9回を投げるだけの体力を計算に入れた投球をしてもらいたいというのがある。しかも年齢も24才と岩隈より若く永井とタメなのだから、鉄腕の田中を別にすれば体力的には問題がないはずだ。では肩や肘に不安があるかといえばそうともいえない。それを言えば故障で低迷していた岩隈には球数を気にしながら投げさせたいところになる。結局、朝井の投球回数の少なさは首脳陣の信頼度の低さからきているのだろう。投球回数が少ない割合での被本塁打の高さ、防御率そのものが示すものは要所で打たれていることの実証となるわけだが、与四球・与死球の数字をみると、技術的なことや体力や握力の低下というよりも精神面に脆さがあるのではないかと観えてしまう。緩急を使う投手の狙いは打者にタイミングを合わさせないことにつきる。打たれたとしても長打を封じ大怪我をしないということが持ち味でないといけない。だが朝井の場合は要所で打たれまいとし過ぎてしまうのだ。前に飛ばされても野手の守備範囲に飛べばOKという達観が、ピンチになると気負いへと変貌してしまう。その気持ちがコースをつきたがるがゆえの四球や死球となり、力で押しきれない直球に力みが加わり棒球へと変化してしまう。それは球種の違いをモーションの変化で曝すことにもなるだろう。そこで朝井に必要なのは精神面での投球術であり、その投球術とは力が入るとことで力を抜くというイチビリ精神である。ストレートをより速く投げようとして失敗するよりは、緩いカーブをより緩く投げて打者を待ちきれなくして翻弄するぐらいの精神面での優位さが欲しいのだ。いわゆる「開き直り」とでもいおうか。もっと良い言葉を使えば「達観」である。それさえ得られれば朝井は良かったときのパウエルの域までは充分届く素材である。むろん首脳陣もそこまで期待しているに違いない。だからこそ越えていかねばいけない壁に直面したとき、あえてそこに挑ませる判断を下したのだろう。それができるのも三本柱が充実しているからである。四本柱、完投カルテットは楽天が優勝するためには必要な看板となる。その一角を担って欲しい朝井には他の三人で勝てる間に壁越えを挑戦させる。その結果に明暗のわかれがあったとしても、その方針はどちらに転んでも朝井の経験、チームの次の段階へのステップという糧になる。今日の試合の場合でも8回のピンチは修羅場としては持ってこいだった。こいう「課題を絞った」ところが「経験の積ませどころ」なのだ。勝算はある。勝算できるだけの装備もある。その使い方もわかっている。そのわかっている使い方を間違えなければ結果は得られる。間違えなければ正解を知る。間違えても不正解を知ることができる。不正解を繰り返してもいずれ消去法で正解を得られるだろう。しかも「何が間違いなのか」を知った後での正解である。朝井のような投手は完投のコツを覚えれば何度も完投できるようになる。将来本当にそうなるかは朝井しだいだが、首脳陣はそう思っていると思えるし、自分は確実にそう思っている。朝井で勝てば最高、投手を替えて敗ければ最悪。では朝井で敗けるのと投手を替えて勝つのではどうだろうか。朝井の続投で敗けるとも限らない。投手を替えて勝てる保証もない。プレイオフが導入されて3位に入りさえすれば日本一のチャンスは残される。この時期は5割ラインにいればいい。トライできるだけの貯金もある。朝井への投資はチームへの投資でもある。貯金を一つ賭けるだけの価値は充分ある。そして真に完投カルテットが完成したとき、日ハムやロッテが旋風したとき以上の投手王国が東北の地に築かれることになるだろう。朝井続投の首脳陣の判断に間違いといえる要素は皆無である。もちろんそれは自分の単なる感想というだけの話なのだが。
2008.04.29
コメント(2)
-
未だに小椋を重要な場面で使う気持ちがわからない。
結果的に抑えたなどというのは文字通り結果論にすぎない。プロで重要なのはその過程を観て判断するということ。「見」るのではなく「視」て「観」て「診」ないといけない。今の小椋はストレートの勢いと荒れ球ゆえの的の絞り難さで「たまたま」もっている程度の投手だということだ。「経験を積ませれば」などという発想では甘いといえる。なぜなら抑えられる根拠ができあがっていないのだから。「経験を積ませて抑えられる根拠を学ばせる」という理屈は確かに存在する。しかしそれはもう少し上のレベルの選手に当て嵌まることだろう。「やることはやる」、「できることはできる」といった投手が、それをどこに当て嵌めれば良いかを経験を通して判断力を身につけていくのだ。残念ながら小椋はまだそのレベルまでにも達していない。簡単にいえば装備が足りない。「荒れ球ゆえの的の絞り難さ」は、それを打てる打てない見逃す見逃さないは打者に選択権のある「結果論要素」であるから計算が成り立たない。よって「ストレート1本」という武器、しかも制球難というマイナス要素はクリティカルヒットの低さを示すものであり、「当たればそれなりに効くが当たる確率は低いソード系の装備」というだけのことである。RPGでは序盤の中キャラぐらいにはそれなりに効果はあるだろうが、それ以上の武器が手に入れば当然手放すであろうし、自身のHPが高くなれば1ランク低い値段であっても確実に相手のHPを奪う武器に持ち替えるはずだ。つまりより信頼できる左投手が現れれば当然のごとく入れ換えとなるし、チームの得点力が上がればゼロで抑えるよりも最小失点で切り抜けてくれればOKといった具合にハードルが下がり、球が遅くても確実にストライクの奪れる安定感のある投手を中継ぎに据えるはずである。そこで小椋に「コントロールを良くしろ」と言っても無駄なのはわかっている。言ってそれができるなら話が早すぎて話にならない。求めるとすれば球種を増やせる方が現実的といえるだろう。それも「決め球になる変化球」などと高望みをしても駄目の上塗りである。思ったところにストレートでストライクが奪れない投手にフォークボールを研けというのはもってのほかで、ここまでストレート1本で何とかやってきた左腕に緩急をつけろといってもそれができるなら最初から世話がない。結局できるとしたらストレート系の変化球ということに絞られる。すなわちスライダーとツーシームである。それもより曲げようと意識して捻りだすと却って墓穴を掘ることになるだろう。両球ともストレートを投げるつもりでその握りで投げるだけで充分だと思う。ほんの少し打者の手元で変化してポイントがずれるだけでいい。その方がストレートが生きるというものだ。思えばホークスの速球左腕には晩年に活躍しだすというが前例がある。吉田にしても渡辺にしても、もともとは速球派の先発型投手だった。しかし両者ともそれでは結果が出ず中継ぎに転向し、要所で投げるスライダーが研かれていき、その延長でたまに投げるパームやチェンジアップが効果絶大となったのだった。小椋が模倣するとすれば吉田より球の速さで勝った渡辺だろうか。ストレートと変化球の比率からいってもそうなるだろう。中継ぎやワンポイントはいきなり走者を背負っての登板が多いものだが、だからといって三振を狙ってはリスクもまた大きくなる。獲るものが大きければ失うものも大きくなる。勝負とはそういうものだ。現に三振を狙って本塁打を喰らうというケースがホークスには少なくない。そういう配球をするからこそコースが甘くなって持っていかれるのだ。ここは「凡打を狙って安打される」方がマシなのだから、中継ぎ投手は欲張らないことだ。その無欲が結果的に併殺であるとか三振を生むのである。「打てそうなところにタイミングを外して緩い変化球が来る」強くなったロッテや日ハムによくみられる配球である。かつてのホークスができていたことだが、今ではホークスがそれを見習うばんである。なぜなら順位も3位であり、している野球も褒められたものではないのだから。
2008.04.29
コメント(0)
-
野球理論は変貌していくということ。
球界には不思議な格言がある。「ボール球を巧く使え」という言葉もその一つである。プロアマを問わず指導者の立場にある者は口にしたことがあるだろう。中継を観ているとそのように語る解説者も多く、その影響からか素人さえもセオリーのように思っている者が多い。しかしそれは大きな間違いである。いや、広義の意味で正しいのは間違いない。しかし指導や解説の中で言うことにおいては間違いなのだ。なぜなら「巧く使え」などという言葉に何ら「指導の要素」がないからである。考えてみればわかることだが、「巧く使え」という文言は、付け加えれば全てが正論になる修飾語だからだ。「ボール球を巧く使え」「緩い球を巧く使え」「厳しい球を巧く使え」当り前である。「甘い球を巧く使え」「四球を巧く使え」「死球を巧く使え」デメリットがあることさえも「巧く使え」で終われば「巧く使うこと」ありきの内容になる。反論したとしても「だから『巧く使え』と言っているんだ。『巧く使え』なきゃ言われる通りデメリットしかない。」と言われてしまう。つまり「巧く使え」を付けると、最善手を保証した結果からの逆引きとなる。どのようにして最良の結果に導くか、その手順を教えるのが指導であるし、それを事前に解き明かすのが解説というもののはずなのに、それでは全くの逆である。「ボール球を巧く使え」という前に、どの場面でどのようにボール球を使うことが「巧い使い方」なのか、それを説明してこそ指導であるし解説といえる代物になるはずだ。それを語らずして「巧く使え」というのは、「最良の結果を出しなさい」と言っているに過ぎない。それでは打撃において「ホームランのサイン」や「タイムリーヒットのサイン」を出しているぐらいの馬鹿らしさである。「ボール球を使って最良の結果を出しなさい」などというのは格言とは言えない。むろんセオリーでもない。「ボール球をこのように使うと最良の結果が出る」と言えてこそ初めて格言たりえるのだ。そして「ボール球をこのように使うと最良の結果が出る」を実践し、期待の結果が得られなかったばあい、そこは柔軟に対処しなくてはならい。それができていないのがホークスである。首脳陣が「ボール球を巧く使え」というものだから、投手にボール球を沢山投げさせてしまっている。しかも根拠ある組み立てを指導していないが為に、ストライクとボールを交互に散らす程度の配球になってしまっている。そのボール球が本当に意味があるのなら、打者はボール球に引っかかっているはずだ。2ー3のカウントになる前に打者は討ち取られているはずである。なのにそうはなっていない。ボール球を打者は簡単に見逃しているだけでなく、次の球への布石だと見透かしてしまっている。失敗している戦術に対し、見直しすらできていない始末である。近年の野球は機動力野球に原点回帰されている。それは千葉ロッテ、日ハム、中日と連続して同系統のチームが日本シリーズを制したことからも明らかだ。機動力野球は守備力重視の野球でもある。攻撃面ではビッグイニングを作るよりも1イニングに確実に1点を取り、9回で9点をせしめる野球である。守備面では1イニングに最高でも1点までの失点に抑える野球である。打たせないのはもとより、走らせないことを重要視しなければならない。その為には無闇に2ー3のカウントを作ってはいけない。2ー3のカウントを作らない為には、2ー2の並行カウントを作るかどうかの選択肢から考えておかなければならない。2ー1のカウントを作れたら、ここで一球遊ぶか勝負かであるが、好投手を作るためには大きな割合で勝負した方がいい。むろんその勝負の中にはボール球で勝負というのもあってよい。要は打者がボール球を振ってくれるかどうかを見抜くのは捕手の洞察力なのだ。アジアを制した上記の3チーム既にやっているし、楽天も既にやってのけている。その事からいってもイーグルスの野球はホークスの先を行っている。昨年ホークスが負け越したのは必然だったのである。ホークスの捕手は洞察力で配球を考えるのではなく、こうしておかないと首脳陣に叱言をいわれると思ってやっているように見えてしまう。その首脳陣からして論理や観察や洞察ではなく、今までこうしてきたからという慣例にそった野球観に囚われているように思えてならない。ホークスがそのような古い野球を見直さない限り、今季のBクラスは確定したといっていいだろう。
2008.04.20
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 続く物価高!切り詰めなきゃ生きてい…
- (2025-11-19 00:00:06)
-