2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年07月の記事
全34件 (34件中 1-34件目)
1
-
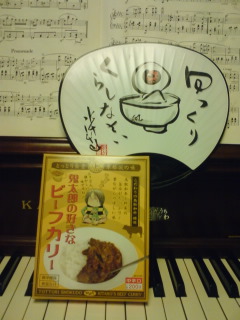
ゆっくりくらしなさい・・・うちわのメッセージ。
ゆっくりくらしなさい・・・ということば、最近身にしみて感じます。朝は寝床でぐうぐうぐう・・・とできるのは土曜日くらいですが、今日はそんな感じにしました。BS2で朝ドラの再放送を見ていたら、番組のおわりに少し映る調布の風景、2週間ほど前に深大寺に行った時のことも思い出しました。そこで、見つけたうちわに、「ゆっくりくらしなさい」とあったので、とても気に入って使っています。1週間前に眼科にいったとき、せんせいが、目玉おやじのような眼球の模型で、目の裏側の説明をしてくださいましたが、模型がそっくりでした。昼間は、「鬼太郎が好きなビーフカリー」という鳥取県産の和牛入りのカレーを。これも深大寺の中で見つけたもの。けっこうおいしかったです。妖怪舎http://youkai.ciao.jp/order/8_1705.html●あしたは、ピアノを弾くことになっていて、練習しておりました。新しく弾く曲と、4年ぶりに弾く曲と、楽譜はその一部です。シューマンのファンタジーな世界が伝わればと思います。4年ぶりに弾く曲は、前よりもお散歩気分になればうれしいです。ピアノを弾く場所は、ルネ小平というホールです。http://www.runekodaira.or.jp/index.html
July 31, 2010
コメント(2)
-
徳川15代以降の家系図を見て19代のホームページとブログを見る。
軽井沢のことが特集になっている雑誌を眺めていたら、徳川家の家系図を見つけました。徳川家・近衛家・細川家が混じったもので、華麗なる・・・というものにふさわしい感じ。徳川15代将軍、徳川慶喜から書かれていて、遠い過去のことかと思えば、徳川19代に当たる方は、自分自身とほぼ同年代で、驚きました。ざっと、こんな感じでいままで至っているようです。●徳川15代将軍徳川 慶喜(とくがわ よしのぶ)1837(天保8)年9月29日-1913年(大正2年)11月22日御三卿・一橋徳川家の第9代当主。江戸幕府第15代征夷大将軍(将軍在職:慶応2年12月5日(1867年1月10日) - 慶応3年12月9日(1868年1月3日))。徳川16代徳川 家達(とくがわ いえさと)1863年(文久3年)7月11日 - 1940年(昭和15年)6月5日)第4代貴族院議長、ワシントン軍縮会議首席全権大使、第6代日本赤十字社社長などを歴任。徳川17代徳川 家正(とくがわ いえまさ)1884年(明治16年)3月23日 - 1963年(昭和38年)2月18日)大正、昭和時代の外交官。政治家。16代当主徳川家達の長男。トルコ大使。第13代貴族院議長に就任し、戦後、貴族院の廃止、参議院への移行に伴い最後の貴族院議長徳川18代徳川 恒孝(とくがわ つねなり)1940年2月26日 - 徳川宗家第18代当主(1963年-)。実父は東京銀行会長・松平一郎。17代家正の養子になる。元日本郵船副社長。財団法人徳川記念財団初代理事長。社団法人横浜港振興協会会長。徳川19代徳川家広(とくがわいえひろ)1965(昭和40年)2月7日- 翻訳家・政治経済評論家公式ホームページあります。http://www.tokugawaiehiro.sakura.ne.jp//ブログもあります。http://d.hatena.ne.jp/tokugawaiehiro/ 坂本竜馬や西郷隆盛がいなければ、19代将軍さまになるかたなのだろうかとか、ありえないことをつい考えてしまいました。時代に翻弄されたご先祖様の末裔の方は、きっと壮大な歴史観もお持ちだろうとも思い、著書とか少しは拝読したくなりました。フィギュアスケートで活躍中の織田家の方とともに、不思議な21世紀に遭遇してるような気がしています。
July 30, 2010
コメント(200)
-
シューマンとゴッホと7月29日
ロベルト・シューマン1810.6.8-1856.7.29フィンセント・ファン・ゴッホ1853.3.30-1890.7.29晩年は何かといろいろあった2人の芸術家の命日は同じなんだと、あらためて日付をみて感じることとなりました。46年とか47年とか、生涯の長さもほとんど同じくらい。<ネットでみた近々の催しもの>軽井沢八月祭ロマンティック・シューマン(生誕200年)http://www.karuizawa8.com/schedule/ohgahall/schumann.html 没後120年ゴッホ展http://www.gogh-ten.jp/index.htmlこうして私はゴッホになった 国立新美術館 2010.10.1-http://www.gogh-ten.jp/tokyo/●「天才は生きているうちに、すべての人たちから天才という評価を勝ち得たわけではない」BGM:シューマン 幻想小曲集 Op.73 (ホルン&ピアノ)http://www.youtube.com/watch?v=BQVaFKReojsピアノしか弾かない人、聴かない人は、作品番号が20番くらいまでの曲が中心になるのは、私自身も含めてそうだったかもしれませんが・・・、それでは、あまりにももったいないということに気付かされます。op.73とかop.70とかop.94とかアンサンブルの作品はもっと知られた作品になっていいと思っています。p.s.早く寝すぎて、思わぬ時間に目覚めてしまいました・・・。
July 29, 2010
コメント(200)
-
じょいふる・じょいふる
SONGSという番組、最近気に入っているもののひとつでよく見ています。今日は平原綾香さんが出演、ほとんど予備知識もないのですが、洗足音大出身でもとはサックスプレイヤーということも知りました。後輩の皆さんと楽しそうに歌う姿は音楽の醍醐味そのもの、こうでなくてはと心から思いました。メロディラインのきれいな曲をポップスに変身させるのはそんなに簡単なことではないですし、小さい頃からクラシック音楽を聴いていたからできることなのかもしれません。すばらしいです。聴き比べて遊んでみることにしました。●joyfuljoyful 平原綾香http://www.youtube.com/watch?v=BcoZQ69g770ベートーヴェン第九 第4楽章より サイトウキネンオーケストラ 小澤征爾http://www.youtube.com/watch?v=heJZ616bfGs&feature=related (合唱のところから)http://www.youtube.com/watch?v=8tolyq2qZOU&feature=related (フィナーレ)ベートーヴェン第九 第3楽章 (この静かな楽章好きなので聴いてみたくなりました。)(この楽章だけ聴いているときもあるくらいです。)http://www.youtube.com/watch?v=ne5qOdGsuEs (3楽章前半)http://www.youtube.com/watch?v=OenN4kOlGoM&NR=1 (3楽章後半)☆威風堂々 平原綾香http://www.youtube.com/watch?v=RQtbn3xmohM威風堂々第1番 (プロムス2008より イギリス第2の国歌といわれる由縁ここにあり)http://www.youtube.com/watch?v=3XVFttMYdLg☆jupiter 平原綾香http://www.youtube.com/watch?v=G_lxcZT2G6MHolst ThePlanets "Jupiter"http://www.youtube.com/watch?v=Nz0b4STz1lo
July 28, 2010
コメント(2)
-
なやまないれんしゅう
コンビニで雑誌をぱらぱらと見ていました。結構本を置いている場所は多く、中国人の店員さんは結構無頓着。気がづいたら長居したりすることもあります。めったに見ることが最近ではないのですが、見出しに引きずられて、読んでいました。プレジデントという雑誌です。「悩まない練習」 というのが大きなタイトルなかなか深いテーマで、まじめに見てみることにしました。いろんなテーマで、いろいろな方がコラムで語っているのですが、2回も登場している人がいて、気になりました。酒井雄哉(さかいゆうさい)天台宗大阿欄梨比叡山飯室谷不動堂長寿院住職 とありました。名前で検索するとホームページもありました。http://www.sakai-yusai.com/特攻隊基地で終戦を迎え、40歳で仏門に入り、7年かけて4万キロも歩かれたとか。失敗を引きずらない練習としての3カ条・失敗は踏み台だと思う。・人の顔色を見ない。・落ち込んだら歩く。嫉妬しない練習としての3カ条・好きになりすぎない。 ・高い視座から見る。 ・距離を置く。たくさん修行された方のメッセージに深いものを感じました。落ち込んだら歩くということ、なるほどと思いました。● BGM:メンデルスゾーン 真夏の夜の夢(A Midsummer Night's Dream)「序曲」http://www.youtube.com/watch?v=4h1MGAlkqno10日ほど前に聴いたコンサートでこれも印象に残っています。コンサートのオープニングには明るくてよかったです。
July 27, 2010
コメント(0)
-
ウィーンの森の物語
先週末、ピアノトリオで、ヨハン・シュトラウスのウィーンの森の物語を聴かせていただいたのですが、ずっと耳に残っています。それだけすばらしかったということなのでしょう。ムジカーザという代々木上原の会場はアンサンブルに向いているのでしょうけど、本当に楽しい思いをしました。子供のころ、家にもヨハンシュトラウスのレコードがあって、レコードのA面は、美しい青きドナウではじまり、ポルカをはさんで、ウィーンの森の物語で終わるというもので、そんなことも思い出しました。BGM:ヨハン・シュトラウス ウィーンの森の物語 Op.325http://www.youtube.com/watch?v=poAb0MhEvmk ●来週、某所でピアノを弾くことがあり、3曲目に弾くつもりでいるところの後半ワルツの箇所で、ウインナワルツのようになればいいと思っているところがあります。微妙な拍感は、このあいだのコンサートで聴いたウィーンに住んでおられるようにはいきませんが、あやかりたいものだと思っています。2年前の8月はウィーンの郊外、ハイリゲンシュタットとあたりは、たくさんお散歩もしたし、そういうあたりのイメージができてくればいいのでしょうか。(ベートーヴェンの散歩道)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200808090002/(ハイリゲンシュタット)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200808100000/(ヨハン・シュトラウス像 ウィーン市立公園)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200808100001/ 風邪でピアノのレッスンを休んだのは、過去12年で2回目。39度でも台風でも通っていたことがあったのですが、今日はそこまでという気になれず。夏ばてに気をつけなければ・・・。ウィーンの森の物語を聴いて、少しは気分が楽しくなりました。
July 26, 2010
コメント(0)
-

館山と白い砂2号
房総半島の南には、はじめて行きました。館山城跡は、戦後立て替えられたものですが、滝沢馬琴の南総里見八犬伝の舞台にもなったところ、場内では、昭和48-49年ごろ、NHKの人形劇「新八犬伝」でやっていたときの人形も飾られていました。坂本九さんの名口上とともに音声久々に聴きました。「仁義礼智忠信考悌」という八個の玉のことも思い出しました。お城の上からみた、海岸の景色と、涼しい風と、これは気分よかったです。 ● 館山は、東京から128.9kmとありました。駅前は、東京駅八重洲口行きのJRバスと、JR東日本と競合している状態、仲良くやればいいものの、道路事情がよくなっていることもあって、バスに乗る人も案外多いです。帰りも「白い砂」に乗りました。この電車に乗りたい人、大きなカメラを引っ提げた人、結構いました。 外房線は単線区間も長く、途中で15分くらい停まっていたときに。(大原駅)帰りは寝るだけになるかと思いきや、夕暮れ時に東京へ向かい、独特の高い音を出しながら、一生懸命走っている実感がわき、なんだか楽しくなってきました。両国の3番ホームにまた戻ってきたのですが、いつまでもシャッターを持っている人がいて、「白い砂」という看板の大きさを感じました。昨年臨時快速として10年ぶりに復活したそうなのですが、あと2週間週末元気に走ってほしいものです。 赤いじゅうたんが階段の真ん中に敷かれている両国駅3番ホーム、鉄道ファンを盛り上げてほしいです。
July 25, 2010
コメント(0)
-
白い砂1号
日曜の朝早くの両国駅、珍しい臨時快速の登場にカメラマンたくさん。 両国駅の3番ホームは楽しい雰囲気でした。 発車30分前に、隣の駅で指定券の残席数席のところ、ぎりぎりでリザーブ。 席の心配なく、同じように写真撮影。 たくさん揺れる車両は携帯打つには向いていませんが昭和の当時の車両だしそれも納得ずみ。 窓はなるべく開けないでくださいというアナウンスは生まれて初めて聞きました。 両国駅を出たあと千葉に着きました。 これから外房線経由で館山へ行きます。 早起きできてよかったです。
July 25, 2010
コメント(0)
-

小石川植物園で3時間半待って「ショクダイオオコンニャク」をみる。
小石川植物園は、丸ノ内線の茗荷谷駅(後楽園のとなりの駅)から歩いて15分ほどのところにあります。世界最大の花「ショクダイオオコンニャク」というニュースで見て、今日まで咲いているということを知り、土曜日に早起きする理由ができたとおもい、出かけました。小石川植物園、正式名称は、東京大学大学院理学系研究科付属植物園という長い名前、もとは、徳川幕府の御薬園として設置され、約320年の歴史を持つそうです。入園したときのいただいたプリントによると、、今回、ショクダイオオコンニャクがこの植物園で開花の見込みとなり、スマトラ島の絶滅危惧種であり、開花することが稀であり、多くの方に見ていただこうということで、鉢を温室から屋外に出して展示公開に至ったとのことです。開花してからの寿命が2日間という短いもの、日本での開花は、今回のもので6例目です。330円の入場券は飛ぶように売れ、これだけ多くの入場者の前例もほとんどないようでしたが、5000人来ても、10000人来ても、対応できるように、園内のスタッフのボランティアを含めて、とても頑張っているように見えました。炎天下のなか、長時間待つことには変わりありませんが、サクラの太い木があるところに誘導して木陰になり森林浴できるようなところに比較的長くいることができましたし、こちらの学生さんが並んでいる列の人へ、冷えたペットボトルのお茶を野球場のスタンドのように販売してくださったり、手作りのなかに暖かいものも感じました。やっぱり、イチバンではないといけないのだと思うことと、温室の部屋が老朽化していて建て替えの資金が必要になってきていることとか、見るだけで疲れることもありましたが、いろいろなことを知ることができました。午前10時前に小石川植物園につき、入場券を買うだけで30分、その後、列に並んで3時間、読書タイムにもなりましたが、猛暑日4日連続の4日目、記憶に残る日になりました。開いていたものはすでに閉じていましたが間近で見れてよかったです。 小石川植物園ホームページhttp://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/ショクダイオオコンニャク 現在の花の状況 (ここ数日の観察記録は貴重です)http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/koishikawa/+Amorphophallus/+A.titanum2010/titanum.html
July 24, 2010
コメント(1)
-
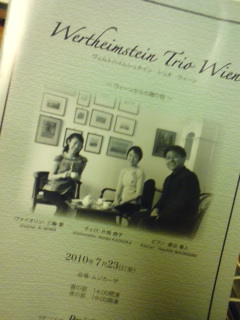
ヴェルトハイムシュタイントリオのウィーンの森のアンサンブル
ムジカーザですてきなアンサンブルを聴きました。ヴェルトハイムシュタイン・トリオ・ウィーン(ヴァイオリン:三輪愛、チェロ:片岡典子 ピアノ:渡辺泰人)ベートーヴェン ピアノ三重奏曲第4番 変ロ長調 Op.11 「街の歌」ショパン ノクターン第2番 変ホ長調 Op.9-2 (チェロとピアノ)ショパン マズルカ第23番 ニ長調 Op.33-2 (ヴァイオリンとピアノ)ショパン ワルツ第6番 変ニ長調 Op.64-1 「子犬」 (ピアノソロ)**ヨハン・シュトラウスII世 ワルツ ウィーンの森の物語 Op.325 行進曲「とても楽しかった」 Op.467 ~喜歌劇「くるまば草」から~ ポルカ「クラップフェンの森で」 Op.336ヨハン・シュトラウスII世・ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ「狩り」 Op.373ヨハン・シュトラウスII世/中原達彦編曲 ワルツ「南国の薔薇」 Op.388(アンコール)ヨハン・シュトラウスII世 ウィーン小行進曲****今年で結成10年、日本でのコンサートは8年続けて。ウィーン・オーストリアを拠点に活躍されていている方々のアンサンブルウィーンの森をテーマにした今回は、お話のなかでもウィーンの街の様子を話してくださり、自分自身も3日ー4日旅したこともあるので、そのときの風景を思い出しながら音楽聴きました。あちらの写真を展示したり、食べ物、飲み物を用意してくださったり、ヨーロッパでのサロンコンサートをそのままの雰囲気で楽しめた感じでありがたかったです。ピアニストはウィーン国立歌劇場バレエ学校のピアニスト、写真のなかから日々の生活をいかに楽しんでおられるのかがわかって、こちらも楽しくなりました。ヴァイオリン、チェロ以外にも小鳥の音や馬車の鞭とか、小道具もたくさん、音楽はこのように楽しむものということを肌で感じました。●昨年、私自身も、同じようなことをしていたみたいです。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200907240000/●このアンサンブルのブログがありました。http://ameblo.jp/wertheimsteintrio/●コンサートのなかで、PMFオーケストラの話があったので、少し調べてみました。三輪愛さんはコンサートミストレスを1999年にされていたそうです。現在は、ウィーンフォルクスオーパー管弦楽団の団員。http://www.pmf.or.jp/http://www.pmf.or.jp/jp/attend/artists/2009/aomember.htmlhttps://www.pmf.or.jp/jp/about/history/1999/main.html
July 24, 2010
コメント(200)
-

花から花へ350000アクセス超えました。
暑中お見舞い申し上げます。本当に暑い毎日です。昨日の夜の銀座4丁目の定点観測。蓮が元気よく咲いていました。30度はまだあったように思います。●お陰さまで350000アクセス超えました。ブログ名:pingpongpang総アクセス数:350037 アクセス(平均 176 アクセス/日)開設日数:1984日(開設日:2005/02/16)日記記入率:92.4%アクセス記録7/22 190 7/21 267 7/20 317 7/19 281 7/18 223 7/17 292 300000アクセス超えたのは、昨年の年末でした。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200912280000/季節が逆なこともあって、時間のたつことの早さも感じます。最近来ていただく方が増えたことで、たいへん感謝しております。1984日なのかと、1984年の話を朝に書いていたので、これも記憶に残りました。今日は、朝は病院、昼はコンサート、夜は飲み会。休みが休みになっていない感じですが、するべき検査はして、聴きたい音楽に感動し、3カ月ぶりの異業種でのお話、よい1日だったと思います。 ●いつも「花から花へ」と書いていますが、切り番の最初のころ、CD聴いていてその流れになっています。 椿姫のオペラ前半のハイライト。とても好きで、これだけよく聴いています。 ヴェルディ オペラ「椿姫」より 花から花へhttp://www.youtube.com/watch?v=SSPK7Ayuw3sアンナ・ネトレプコ(so)シンプルで斬新な演出のものをみてたいへん驚きました。第一幕の最後の曲、いろいろな葛藤のなかでの歌声お見事です。絵をみていて、ザルツブルク音楽祭での舞台もずいぶん変わった気がします。装飾品がたくさんの椿姫の舞台のイメージが一変しました。また見に行ける機会作れるように・・・と元気をもらった感じです。
July 23, 2010
コメント(2)
-
♪が半人前で♯が半歩
あさイチ、NHKの8:15から、見ています。有働さんの番組の進め方、話の振り方がおもしろいので、家にいるときは、少しの時間でも楽しみにしています。ゲストのトークで・・・、ベッキーが歌手になって、ベッキー♪♯♪は八分音符で半人前の意味で♯が半歩ずつ上がるということで話されていました。 全部自分で考えたとかということも含めて、この人はすごいと思いました。 あの高いテンションを保てるようにはなりたいと思うもののテレビの世界の人だから、と冷めた感じになったりもします。 1984年生まれということで、1Q84という本を思い出しました。はじめて東京に自分が来たころの風景ともに。
July 23, 2010
コメント(0)
-
18切符は7月20日からということを学びました。
この前の週末に旅をするにあたって時刻表を買ったので眺めています。このあいだ間違えたことがひとつ。青春18きっぷを旧新橋停車場に行った勢いで買ったのはよかったのですが、利用期間が7月20日からで、このあいだの3連休(7月17日-19日)は対象外の日だったこと。身支度していて、路線図を調べていたときに、発覚したこと。楽しみは後にとっておこうと思いました。時刻表を眺めていると、臨時列車の特集、結構面白いものありました。列車のネーミングを見て、いったいどこを走っていいるのだろうと、時刻表を見るという感じです。風っこもぐら 渋川→越後湯沢ジオパーク 糸魚川→南小谷まほろば 新大阪→奈良白い砂 両国→館山一村一山 上野→土合(水上の近くの駅)ほくほくひまわり 新潟→長岡→十日町こがねふかひれ 仙台→気仙沼 ・・・言われてみればというもの、見当もつかないものいろいろ。はちおうじ日光 八王子→東武日光 ・・・そのまんまやん、、、というのもありました。せっかくなので、どれかの臨時列車に参加してみたくなりました。●SLやトロッコ列車の路線もずいぶん載っていました。自分も旅は好きなので、地方のコンサートに行った翌日とかに探して乗ったりしました。過去ブログを探してみたら、そこそこあったのでご紹介します。SLばんえつ物語 新潟-会津若松(磐越西線)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200807130000/トロッコ 大分ー由布院(九大本線)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200805200000/奥の細道最上川ライン 酒田ー余目(陸羽西線)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200705010001/ BGM:ベートーヴェン 交響曲第8番 ヘ長調 Op.93 第2楽章 ギュンター・ヴァント指揮 北ドイツ放送交響楽団http://www.youtube.com/watch?v=ceSsoAhpT_oかつて旅番組でBGMに流れていて、あまりに絵にあっていてうまいと感動した曲。田園風景が浮かびます。
July 21, 2010
コメント(2)
-

小牧での七夕短冊から
見知らぬ街へ行き、見知らぬところを歩いて、すなおに感動できる風景に出会えることが楽しいです。小牧七夕まつりでのたんざく、とても気に入りました。七夕のお祭りは東北だけではないことも知りました。●次の日に渋谷のセンター街を歩いたこともあって、地方の普通の駅でのあまりにも人の少ないことに驚きました。暑いのでどうしようかとおもったとき、流しのタクシーなんて、 走っていないんだということに改めて気付きました。駅まで戻らないとタクシーはいません。地方のコンサートホール、自動車でコンサート会場へ向かう人90%。これもカルチャーショック。土地がたくさんあるので、駐車場も広々。東京での常識は地方での非常識。●地方のコンサートホール、ときどき行ってみると、面白いことにたくさん気付きます。岐阜のサラマンカホールも、別府のアルゲリッチ音楽祭のビーコンプラザも、サイトウキネンフェスティバルのまつもと市民芸術館も、山形・余目というところにある響ホールという田んぼのど真ん中のホールも。この数年間に歩いていて多くのことを知ることとなりました。箱モノだけではないかと批判もあるものの、箱がなければはじまらないことも事実。この20年、日本のクラシック音楽での環境はとても進歩したと思っています。世界をまたにかける音楽家が増えたからできたこと。そういう意味ではレベルがあがっていると感じています。なんとか、そういう環境が発展できるようになればと、願っています。外国の音楽祭とどうちがうのかと、サイトウキネンの事務局の人と話をしたこともありましたが、実際の目でみたことを伝えられるようになりたいです。日本が停滞しているというニュースを見るなかで、なんだかいろいろ考えてしまいました。
July 20, 2010
コメント(0)
-

どーるはうすとピアノ
この日、電車の旅をして、海を見たり、江戸時代の絵を見たあとは、渋谷の松濤にあるタカギクラヴィアにて。品川駅で「こだま」から降りたあと、30分で到着できる場所であることがわかりました。そんなあわただしい風景も、部屋に入れば穏やかな気分に。プレリュードを中心としたピアノの演奏を聴いたり、お菓子をいただいたりして和んでいました。ドールハウスを見せていただき、3年ほどかかったといわれる作品を見て感動。おおざっぱで緻密なことが得意でない自分にとって、才能のちがいを感じることになりました。こんな家に住みたいという理想があってのことだと思い、少しでも夢のある毎日を送りたいものということも感じました。たいへん癒されました。プレリュードは、いろいろな作曲家が書いているもののなか、やっぱりショパンとドビュッシーのいくつかが響きます。「穂」が聴けてうれしかったです。大田胃酸で有名なプレリュード7番がイ長調で胃腸ということばをかけていること、今になって気付きました。いまはやりの、ととのました・・・という感じ。しばらく会っていなかった方と、談笑できたのは、うれしいことでもありました。ゼロからスタートのゼロを知っていると、半年ぶりであれ、2年ぶりであれ、ありがたいものだとつくづく思いました。 今回の4連休、いいお休みになった感じがします。●新幹線とか車中に読んでいた本、資生堂の名誉会長の福原義春氏のことば、「よく動く人は、本人も知らないうちに、偶然や運の種をまいている。」本のブックカバーにありましたが、運の種をまきたいものです。
July 19, 2010
コメント(6)
-
由比・東海道広重美術館にて
東海道線を東京方向に移動するなかで、ぶらりと途中下車したくなりました。 前から気になっていたところへ。 静岡から東に5つ、東静岡、草薙、清水、興津、由比。 このあたりは電車も三両編成。街の人、夏の旅の人とそれぞれです。 由比から東海道広重美術館というところへ。 この前のほおずき市で浅草の仲見世でみた絵葉書が残っていたのかもしれません。 旧東海道の宿場町沿い、由比本陣公園のなかにありました。 広重の絵を分解して色使いや筆使いでの濃淡の解説がありました。 またゴッホが真似して書いた絵が並んでいてゴッホ流の浮世絵のようなものも見れました。これはなかなかよかったです。 http://www.yuihiroshige.jp 東海道五十三次漫画絵巻で個性ある東海道の様子も楽しみました。 ● 由比は東海道五十三次では17番目のところ、箱根が11番目のところ、 三島が12番目のところ。 広重の画集と東海道本線の車窓を見ながら三島へ移動中。
July 19, 2010
コメント(4)
-
小牧・ロマンティック シューマン
東京をせめて1日くらいは脱出しようと、コンサート目的もあり西へ。 八年前に住んでいた名古屋も地下鉄の路線は増えていました。 環状線になっている名城線から名鉄が乗り入れしているのは今日になって気付きました。 小牧という地名は歴史上の古戦場だったり、名神高速道路の終点ということで名前は昔からよく知っていました。 歩いてみて、七夕の短冊がたくさん、暑い夏にお似合いでした。 地方のコンサートホール時々行きますが、こちらもでんとして風格ありました。 ロマンティック・シューマンというテーマで中部フィルハーモニー交響楽団第19回定期演奏会 指揮:秋山和慶 メンデルスゾーン:真夏の夜の夢 作品21より序曲 シューマン:ピアノ協奏曲イ短調 作品54(ピアノ:三輪郁) シューマン:交響曲第3番 変ホ長調「ライン」 作品97 オーケストラは全般的に若々しいダイナミックな流れでの演奏でした。 シューマンのピアノ協奏曲のブログラムノート、今回は1845年の初演ではクララがピアノを弾いて、メンデルスゾーンが指揮したことが書かれていました。 ファンタジーの世界を堪能することとなりました。 ラインの交響曲はN響アワーではいつもさわりだけ聴いているのですが、本当に久々に全楽章。 第1楽章て第5楽章は「生き生きと」Lebhalt の標題。 これを見ると何だか元気が出ます。 秋山さんの指揮も見れてよかったです。 見知らぬ街のコンサートホールめぐり、またライフワークの続きもしたいです。
July 18, 2010
コメント(0)
-
新橋と京橋で、文化的な1日。
ようやく梅雨明けしました。今日は涼しげな催しに足を運んでいました。●新橋旧新橋停車場で、「正岡子規と明治の鉄道」という催しがあり、その足跡と、当時の鉄道の様子、時代背景とか展示されていました。http://www.ejrcf.or.jp/shinbashi/index.html正岡子規「はて知らずの記」という旅行記があり、明治26年(1893年)7月19日から8月23日まで芭蕉の足跡を訪ねて東北地方を旅したそうです。明治24年に上野ー青森間は、日本鉄道会社が全通させ、所要時間は26時間30分。3等車で行けば、3円64銭が汽車賃。船の輸送から鉄道へと時代が変わることになったそうです。正岡子規の旅の行程は、鉄道・徒歩・人力車・馬車・船と、バラエティに富み、きっとそれなりにリーズナブルに考えたものでしょうけど、見ているだけで楽しくなりました。みちのくへ 涼みに行くや 下駄はいて汽車みるみる 山をのぼるや 青嵐汽車待つや 梨くふ人の 淋し顔短夜や 一番汽車に 乗りおくれ正岡子規に贈った、夏目漱石の絵葉書も展示されていて、気配りあふれる雰囲気も含めて感動ものでした。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200705010002/3年ほど前に最上川に行ったときのことを思い出しました。●京橋 銀座1丁目からしばらく歩いて京橋・宝町・・・この界隈は、小奇麗な画廊が多く、落ち着いた感じのするところ。銀座の隣町でもありますが、また佇まいも変わります。夏の企画として、「歩いて探すアート」という京橋界隈2010が開催中。http://www.kbkw.jp/東邦画廊http://www.tohogarou.com/「もっと先の心の中の宇宙へ」というテーマで76回目のになる堀本恵美子さんの個展に伺いました。続けることの大切さと信念について学ばせていただいています。青と波の絵は1年ぶりに拝見いたしました。今回淡い青と黄色の波の絵がおだやかで結構な時間眺めていたように思います。貴重な時間をいただけた気がして感謝したいです。絵を見て、何か浮かんだ音楽は???という問いかけも画廊であったのですが、ドビュッシーの次の3つの曲が浮かびました。前奏曲1巻No.2 帆前奏曲1巻No.8 亜麻色の髪の乙女水の反映
July 17, 2010
コメント(2)
-

神代と深大寺
会社を夏季休暇で休んでいて、昼間に朝ドラの「ゲゲゲの女房」を見ていました。極貧生活のこのドラマ、ようやく7月半ばに入って灯りが見えてきた時代に。5月・6月のひどい状況を見ていたなかでしたので、今日の質屋さんから全部質入れしたものを取り戻すシーンは爽快でした。今日の午後は、所要で、調布にある神代郵便局というところへ、どうしてもこの場所に行かないとできない用事がありました。平日でないとでいないことが、このご時世でもあるようです。場所を調べると、京王線のつつじが丘の駅前でした。用事を済ませて、まっすぐ帰ろうと思っていたら、駅前のバス停に、深大寺(じんだいじ)行きのバスが、留まっているのに気付きました。時計を見ると午後4時過ぎ。不思議なご縁もきっとあるものとおもい、気が変わってバスに乗り込み、深大寺まで行きました。天台宗の古いお寺は、七夕の短冊もたくさんあり、華やいでいて、朝ドラでも紹介された雰囲気を楽しみました。 かわやでは、一枚の張り紙が。「急ぐとも 西や東に垂れかけな 皆見(南)る人が 汚(北)なかりける」ユーモアがわかるお寺だと感じました。深大寺そばも、記念にいただきました。冷たい山菜そばは、こしのしっかりとした伝統の味を受け継いでいる感じでした。 鬼太郎茶屋というお店もありました。水木しげる氏は、2003年8月 日本経済新聞「私の履歴書」に出ているそうで、その内容にプラス幸福論を書かれた本に出会いました。・成功や栄誉や勝ち負けを目的に、ことを行ってはいけない。・しないでいられないことをし続けなさい。・他人との比較ではない、あくまで自分の楽しさを追求すべし。・好きの力を信じる。・才能と収入は別、努力は人を裏切ると心得よ。・怠け者になりなさい。・目に見えない世界を信じる。幸福って何だろうと自問自答されたなかでの7カ条のこと、「アホでいい。好きなことだけ やりなさい。」と本の帯に書かれていること、40代後半から、ようやく売れ出した作家の実感のこもったお話、共感いたしました。8月に松屋銀座で、水木しげる米寿記念画業60周年、ゲゲゲ展があるそうです。お店で案内いただきました。http://natalie.mu/comic/news/34574 BGM: シベリウス ヴァイオリン協奏曲 (NHK芸術劇場より) http://www.youtube.com/watch?v=wXYXUd_N2YI&feature=related テレビでは神尾真由子さん、すばらしいです。 ネットではヒラリーハーンさんの演奏、 第3楽章好きなので、聴き比べて楽しむことにします。
July 16, 2010
コメント(4)
-
ぼんやりとした不安・・・
昨日買った雑誌は、とても1日で読み切れないのですが、適当にページを開いては、眺めていました。最近テレビで引っ張りだこのような感じがする、池上晃さんの、2ページのコーナーありました。「今月買った本」ということで、1か月に読んだ本の感想を書くことで、原稿料がもらえるというおいしい仕事をされているように思います。いつもわかりやすい説明をされ、それでかつシンプルなので、響くことばも多く、尊敬してしまいます。本のタイトルでもないのに、見出しにひとこと、「ぼんやりした不安」これが今月言いたかったように思います。芥川龍之介の「僕の将来に対する唯ぼんやりした不安」という自殺の動機にもなったことからはじまる2ページはお見事としかいいようがありません。アウトプットとして書かれている中、相当な読書量がきっとあるのだろうと、ぽんぽんぽんと10冊ほど紹介しているものを見て感じました。何をテーマに乱読しているのかということもわかりやすいです。●講演会でも聴いたことがあるのですが、池上氏の「伝える力」という本を読み返しています。目次を見るだけでも、キーワードがわかりやすいし、気になるところから読めばいいという感じで、こういうアプローチができるようになりたいものです。第1章 「伝える力」を培う ・・・では、 何を取り、何を捨てるか という編集のノウハウ プライドが高い人は成長しない という長く見ている人間観察からのひとこと特に共感するところ多く、「謙虚にならなければ物事の本質は見えない」ということも身につまされることが多くなってきた気がしています。第7章 この言葉・表現は使わない。 「そして」、「それから」、順節の「が」、「ところで」 「さて」 「いずれにしても」・・最近、自分自身もあまり使わなくなった感じですが、順節の「が」は使っているかもしれないです。「いずれにしても」は何かの説明でごまかして押し切ろうとしたとき、つい使ってしまっている気がするので、気をつけなければと感じました。 第5章 文章力アップさせる ・・・のなかに、 「もう一人の自分」を育てる というのがあり、これはこの間、姜尚中氏の講演会での話と共通しているものを感じました。 「ブログを書く」ということもタイトルにありました。 誰かに読んでもらうことを前提に書いているので、日記や備忘録とは決定的に違うとありました。 文章力の向上を考えた場合、誰かの目に触れて、批判を受ける環境にあるブログとそうでない日記の対比については、確かに違うことは実感持っています。 こちらのブログも5年5カ月たち、もうすぐ2000日くらいになりそうで、 いろいろな方に批判をうける環境にあったのは事実だし、 身に余るようなことを言ってくださったこともあるのも事実ですし、 そういうなかで鍛えていただいているのかと思っています。 ときどき読み手の方を想像して書くのもコメントするのも面白く、ありがたいと思っています。 ぼんやりとした不安・・・は、ずっと付きまとっていますが、 いろいろな方に励まされているということ、「伝える力」という本を見て改めて気付きました。ありがとうございます。久しぶりにというか、今日は今年初めて楽譜を買いました。ぱりっとして、短い曲でも・・・という助言もうけて、ベートーヴェンのバガテルでもと思って、2-3ページのものをこの週末に練習でもしてみることにします。Op.126の2曲目、ものすごくお気に入りの曲でちょうどいいかなあと思っています。
July 15, 2010
コメント(2)
-
予言という文字の中吊り広告から・・・
家に帰る途中、地下鉄の中吊り広告を見るのが趣味だったりします。月・水曜日は雑誌が多く出ることもあって気にしたりもしています。文藝春秋の8月号のこと・・・「的中した予言50」http://www.bunshun.co.jp/mag/bungeishunju/http://www.bunshun.co.jp/mag/bungeishunju/adv/1008.htm三島由紀夫「日本はなくなり、無機的な、ニュートラルな、からっぽな国が残る」松本清張「日本人の休日の増額は欧米の謀略である。」この雑誌、入院したとき、長い距離の飛行機に乗るとき、たいへん重宝した記憶があるのですが・・・めったに買うことはありません。、今回は「予言」ということばに、ぐらっときて、ゆっくり眺めてみることにしました。三島由紀夫氏は、この前の日曜日の講演会の講師が影響を受けた小説家。松本清張氏は、若い時は朝日新聞のデザイン担当の社員で43歳で芥川賞作家になった遅咲きの小説家。大作家とかかわりのあるかたのコメントや文章には興味あり、エピソードとかも、こういう時に知ったりします。コンサートのときのプログラムガイドと似たイメージ持ちます。 ●この中吊り広告の特集記事の数ページ前にちょっと厚紙のクラシックのコンサート案内広告があり、目に留まりました。バーバラ・ボニー、フィオーナ・キャンベル ジョイントコンサート9/7 サントリーホール S席12000円ホセ・カレーラス 「ロマンス」 テノール・リサイタル11/23 サントリーホール S席33000円席の値段に3倍の差があることと、ピアニストでも30000円以上の人は、だれもいないだろうという驚きと、かつてのサッカーワールドカップの3大テノールのひとりは、いまだに健在なのことと、いろいろ知ることとなりました。 メンデルスゾーン 歌の翼に (バーバラ・ボニー)http://www.youtube.com/watch?v=8NdUuPAAGxQそういえば、7月5日のブログにも、バーバラボニーの歌を載せていましたので、もう一度載せることに・・・。シューベルト 水の上で歌う (バーバラ・ボニー)http://www.youtube.com/watch?v=O405pK6BuUc プッチーニ トゥーランドットより「誰も寝てはならぬ」(ホセ・カレーラス)http://www.youtube.com/watch?v=ZGezqe7nQfw&feature=related
July 14, 2010
コメント(0)
-
選挙に行った小学校のあゆみと、できたころのクラシック音楽。
選挙に行く時くらいしか、近くの小学校の中に入らないのですが、そういえば去年も今年もこの時にお世話になったとおもいました。公園が隣にあり、とても雰囲気がよくて、気に入っています。大変歴史のある小学校のようで、今年で開校137年なのだそうです。ホームページもあるようでした。同じ場所でずっとこの国を見守っているようにおもい、学校の歩みを眺めてみました。1873年(明治6)学校開設1874年(明治7)○○小学校となる。1879年(明治12年)教育令公布により、公立○○小学校となる。 社会の出来事:エジソンが電球を発明する(1879)1886年(明治19年)公立○○尋常高等小学校と改称する。 社会の出来事:大日本帝国憲法(1889) 日清戦争(1894) 日露戦争(1904) 1923年(大正11年)震災により校舎を焼失する。 1931年(昭和6年) プールができる。 社会の出来事 満州事変(1931) 第二次世界大戦はじまる(1939)1941年(昭和16年)国民学校令公布により、東京市○○国民学校となる。 社会の出来事:太平洋戦争はじまる(1941) 広島・長崎原爆投下、太平洋戦争終わる。(1945) 日本国憲法公布(1946)1947年(昭和22年)学制改正で東京都○○区○○小学校となる。1953年(昭和28年)現在の校歌ができる。1973年(昭和48年)開校100年記念式典を行う。1987年(昭和62年)現在の新校舎落成式。1993年(平成5年) パソコン室ができる。2008年(平成20年)開校135周年。*****こうやってみると、前半は戦争ばかりやっていたのかと感じます。今はデフレの世の中ですが、戦後のハイパーインフレの時代も黙ってみていたのでしょうか。自分自身が通っていた関西にある小学校も明治6年からあったので、小学校に通っていた途中で開校100年の式があったこと、紅白饅頭ももらったこと。記念の冊子をもらったことは覚えています。昭和48年は高度成長の時代。田中角栄が首相のころ。勢いはありました。自宅には、まだクーラー(エアコン)というものがなかったし、黒電話だったし、テレビはがちゃがちゃチャンネルの取り合いだったし、狭い家だったし、1ドル=308円だったし、今に比べればまだまだ恵まれなかったような気もします。さっきのNHKニュースで1ドル88円って言ってました。●BGM:ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 Op.56(1873) http://www.youtube.com/watch?v=vB_5-LfF5y0 http://www.youtube.com/watch?v=DSxp9XV2G8U&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=E6RHpX97-8A&NR=1 (長い曲なので3ファイルに分かれています) ブラームス 大学祝典序曲 Op.80(1880) http://www.youtube.com/watch?v=8nZ0GKX97BM&feature=related日本に小学校ができたころに作られた曲と、エジソンが電球を作ったころの曲を聴いてみたくなりました。ブラームス中期の独特の明るさもあり、大好きな管弦楽曲です。交響曲1番はベートーヴェンを意識してとても力が入っている印象ありますが、これらはそういうことを意識していないということもあってか、肩に力が入っていなくて、思い切りがいいようにも感じます。
July 13, 2010
コメント(2)
-
蒲田の発車ベル
京浜東北線で品川から横浜方面に向かうことは、年に数回ほどしかありません。品川からすぐとなりの大井町、その次の次の駅の蒲田。電車に乗っていても、2つの駅のギャップの激しい発車ベル。なんだか妙に耳に残ります。大井町は、ヴィヴァルディの「四季」から、「春」と「秋」http://www.youtube.com/watch?v=xTlWehwZdKc蒲田は、「蒲田行進曲」http://www.youtube.com/watch?v=1en-lmDjSIg●大井町は、2週間ほど前に、きゅりあんというホールに立ち寄ったので、久々に耳にしました。蒲田は、このあいだミューザ川崎へ行ったときも東海道線に乗ったからしばらくご無沙汰です。 最近ではアプリコで音楽聴くときに耳にしているのかもしれません。蒲田の駅は、13年前の1997年の冬から春にかけて、この駅をよく使っていました。京急蒲田から3つほど乗って穴守稲荷で降りて10分ほど歩くか、JR蒲田からバスに乗って東糀谷6丁目というところへ行くかの選択肢でしたが、歩く気力があまりなく、JRを使うことが増えました。朝早くから夜遅くまでというだけならよかったのですが、そうもいっていられなくなり、泊まりで仕事をすることも増え、朝帰りも増え、昼夜逆転で家に戻ったこともありました。この年の3月終わりのこと、自宅を引っ越すことになっていました。土日に引っ越しをして、実家から両親が上京してくれて手伝ってくれたのはいいのですが、引っ越しの片づけのさなか、何度も電話で呼び出されて、ついに仕事へ行かなくてはいけなくなってしまいました。戦場のようなところでしたので、しょうがありませんでした。自分のことなのに、両親をほっぽりだしてということになってしまいました。なんだか情けなくなってしまいました。ようやくその日の仕事が終わったのですが、関西に戻った両親に電話をしたのが、この蒲田の駅のホーム。なんだか申し訳なくなって、涙ぐんで電話したこと覚えています。そのときに駅の発車ベルがなんともいい具合でというか、耳にこびりついている感じになっています。数年に1度、上京するときくらい、満足に接待しなければと心に決めました。この年はそのあと、サクラが咲いている時期もわからない年でしたが、身体も壊してしまいました。その後の健康診断で診療所の先生に、「こんなんだったらあと10年くらいしか生きられない。」と言われ、「趣味でもなんでもいいから仕事と全然関係ない時間をつくりなさい。」とそうとう厳しく言われました。次の年に、少し仕事の負担が軽くなるようなところへ異動したり、ピアノを習うことをはじめました。たぶんピアノのレッスンがあっても、ほとんど休むことなく通っているのは、この年のことがきっとあったからだと思います。蒲田の発車ベルのときの出来事は、ある意味出発点のひとつだったのかもしれません。13年経って、こうして普通に生活しているのだから、よかったのだと思っています。つかこうへいさんが62歳でお亡くなりになったとか。ご冥福お祈りいたします。
July 12, 2010
コメント(200)
-

東京国際ブックフェア/姜尚中・浅田次郎の読者推進セミナー
有明にある東京ビックサイトで催されている東京国際ブックフェアーに週末行きました。読書推進セミナーというものがあり、2つとも行きました。1600人のお客様が入っている大きな会場。実際の申し込み者は4200人、主宰者は入場者を断ることなく、入りきれない人は別室でテレビ中継。土曜日も日曜日もそれは同じでした。 ●土曜日:「読書の力-「自己内対話が開く世界」講師:姜尚中 氏1950年生まれ。熊本市出身現在は、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授。専攻は政治学、政治思想史著書:「ニッポンサバイバル」「悩む力」週間「AERA」 コラム愛の作法 など。http://www.kangsangjung.com/profile読書へのかかわり高校時代まで野球にあけくれていて、その後環境が変わって、不安な状態に。現実を直視するなかで読書することによって、何かにすがるようなものとなった。読書することによって、自己内対話のフィルターがかかり、自分の中で比較、対話をすることができた。読書をする→自分自身と対話をするーもうひとつの自分を発見する。ものを書く→自分のために書く-そのことによて新しいことを発見する。(浅田次郎氏の講演テーマより、感じたことを述べる)10代のときに読んだ本を読み返してみる。(通奏低音のような響きがある)文字を知るということー親が文字が読めなかったこともあり人類の恵みである。対話をすること---人間の人間たる所以孔子・キリスト・ソクラテスの残したものは話し言葉であることに注目。<影響を受けた本、映画>丸山真男 (自己内対話について)http://homepage1.nifty.com/kous/kelly/nihonnosiso.htmlボードレール 「悪の華 (鈴木新太郎 翻訳)黒沢明 「生きる」http://kurosawafan.livedoor.biz/archives/50064409.html吉野源三郎 「君たちはどう生きるか」●日曜日:「読むこと、書くこと、生きること」講師:浅田次郎 氏http://ss7.inet-osaka.or.jp/~takio21c/asada.html1951年生まれ、東京都出身。高校卒業後、自衛隊に入隊し(三島由紀夫の影響)、その後会社員生活を続けるなか、投稿生活のあとデビューしたたたき上げ作家。1997年鉄道屋(ぽっぽや)で第117回直木賞。時代小説、大衆小説がジャンル。<内容>活字と映像の情報量の差について、圧倒的に活字のほうが大きい。45分x35回分の自身作のドラマの構成では、実際の活字の題材で1/3程度の利用度でしかない。映像のみの情報に頼ると貧弱になる。利口そうに見えてばかになる。読書人→漢詩的に解釈すると、読み書きのできる教養をもった人。読むことが好きで書くようになった。江戸時代の教養人・・・40歳で定年となり、世代交代したあと、読書は道楽の世界として文化を築く。読書を道楽と見るのが正しい見方で、勉強だと思わないほうがいい。芸術と同じく、娯楽性と大衆性を持ち合わせたもの。小説を書く上で、いかに、面白く、美しく、わかりやすいものにするかが、自身の憲法。読書離れと言われていることについて昭和30年代前半、本を読むくらいしか娯楽がなく、せいぜいラジオくらい。今の携帯もPCもDVDもある時代と比較することがそもそもの誤り。浅田氏自身の生活午前:書く(執筆作業)午後:読む(資料とか仕事に関係あるものは極力読まない)読書の仕方1日1冊主義 >>>読書の基準4時間 400枚。 連続した時間。字を書くこと、日本語を書くことを忘れてはいけない。(手で書く。縦で書く。)●まったく違ったタイプの方の読書セミナー、どちらに対しても共感しました。姜さんは、学者としての視点からのアプローチ。自己内面からを通じて語られました。浅田さんは、大衆文学としてのアプローチ。エンターテイナーそのものでした。それぞれの人生観があってのものでした。興味のあるものは、本という形がネットのコラムになっていようが、好奇心旺盛にしていきたく、また感じたことは何か文章にしたい。音楽に関しても、アーチストの演奏を聴いて感動したり、自分自身では多くのことを感じながら演奏したいものだと感じています。●ブックフェアー、出版会社ごとのブースは個性的でした。本屋さんの本の置き方とはちがう、出版社そのままの主張がうれしかったです。
July 11, 2010
コメント(200)
-

有明→日の出桟橋から隅田川を上って、浅草寺・ほうずき市。
有明にある東京ビックサイトから、浅草へ行く経路として、ゆりかもめで新橋へ出て、銀座線に乗って浅草へ行くのが普通かなとおもっていたところ、「水上バス 浅草 60分」という看板が目に入りました。日の出桟橋経由でということで、船を乗り換えて、この経路で行きました。隅田川を上って浅草へ。海の風もあって涼しいものでした。観光客も多く、大盛況の隅田川ライン英語・中国語のちょっとした案内もあったり、http://www.suijobus.co.jp/cruise/line/su_line.html日の出桟橋を出ると、いくつもの個性的な橋を通過します。勝鬨橋>佃大橋>中央大橋>永代橋>隅田川大橋>清洲橋>新大橋>両国橋>蔵前橋>厩橋>駒形橋>吾妻橋これだけの橋を見た後、浅草に着きました。浅草に着くと、目の前に、スカイツリー。今の時点で490mくらいだそうです。障害物なしの至近距離からは圧巻でした。 ●浅草雷門の前は、人が多いこともあって、選挙演説が次から次へ有力議員が何時からきますとかの案内をたくさんありました。明日が明日だから、必死さも伝わってきました。昼間にほおずき市へ行くのも、久しぶり。四万六千日とあちこちに書いてあるのですが、これだけのご利益を期待して、こちらも大混雑。お参りするのに1時間ほどかかりましたが、四十五円(始終御縁)を入れました。今年も無事に来れたことはよかったです。つつがなく毎日が過ごせること・・・でありたいです。 かつて翻弄されたおみくじ、今日は平常心で受け止めようと思って久々に引きました。表の漢字しか今までみてなかったようですが、細かく裏に説明ありました。浅草寺 観音籤 (2010.7.10) 大吉紅日當門照暗月再重圓寓珍須得賓頗有稀心田朝日が輝いて門前を照らし、明るくなるように、天の恵みによる良い事があるでしょう。今までの闇夜に月が再び満月となり、周囲を照りわたすことでしょう。明るい心が周囲をなごやかにすることでしょう。珍しい財宝を得られることでしょう。名が有名となり、心叶うようになるでしょう。油断と慢心を慎むべし。(英訳もありました)THE BEST FORTUNEThe sun is shining so brightly that you will get the blessing of the heaven.The moon is shinig clearly again after a cloud passes.You may have rare treasure.Gaining fame, you can meet all your wishes.「大吉がでたからといって油断したり、また高慢な態度をとれば、凶に転じることもあります。謙虚で柔和な気持ちで人々に接するようにしましょう。また、凶がでた人も畏(おそれ)ることなく、辛抱強さをもって誠実に過ごすことで、吉に転じます。・・・」こんな解説も丁寧にありましたが、実感として本当にそうだと思っています。謙虚で柔和にならなければ・・・。 ほおずき、たくさん見てきました。なんだかほっとしています。とてもいい気分転換にもなりました。
July 10, 2010
コメント(0)
-
朝顔市に行けなかったけど、ほおずき市はやっぱり行きたい。
木曜日に、朝顔市にでも行きたかったのですが、打ち合わせやら何やらで、会社を出ようとしたのが20時過ぎ。さすがに無理だと思いました。金曜日、ピアノのおけいこのあと、銀座線に乗って、終点の浅草まで行って、ほおずき市でもと思ったのですけど、どしゃぶりの雨。とてもそんな気分になれませんでした。● 朝顔市http://www.kimcom.jp/asagao/index.phpほおずき市http://www.asakusa-kankou.com/schedule/hoozuki/ 備忘録がわりのブログも、物忘れがはげしくなろうが、その助けになったりします。毎年同じことを同じようにしていることが、はっきりしていること、年に何回かあります。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200907100000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200807100001/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200707100000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200607100000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200507100000/ここまできたら・・・・と意地をはってみたくなりそうな感じです。浅草寺のおみくじは、こわいのですが、今年は怖いものみたさになって、おみくじひいてみるのもいいかもしれません。(2004年のほおずき市のとき、大凶のおみくじひいて、そのあと、けがをしたり入院したり、ふんだりけったりだった年があったことも) ●金曜日の夕方には、いつも楽しみにしている雑誌が届くのですが、日本と上海が往復4000円の飛行機が飛ぶとか、日産のマーチが、ついに日本で作らず輸入されるとか・・・、安けりゃいいということもありますが、ぱらぱらとめくっていて、ほんとうにこれでいいのだろうかと、思うようなこと多いです。定期購読15年続きました。1年ごとに更新していたのですが、とことんこれも付き合いたくなったので3年契約で更新することにしました。雑誌のテーマがあまりに暗かったので、ぱあーっと、明るく、どこかに旅に出たくなりました。往復4000円で日本と上海まで行ける空港は、茨城県にできた新しい空港。そこにいくだけで4000円かかりそうなので、何だか変ですが、そういう変な経験をしてみるのも悪くないかもしれません。浅草寺で御参りして、ほおずき、また今年も育てることにします。
July 9, 2010
コメント(2)
-
ぶらあぼ7月号 開館10周年・20周年の広告をみて。
ぶらあぼ7月号を眺めていて、文京シビックホール開館10周年記念公演 (2000-)http://www.b-academy.jp/event/detail_dyn_j.html?iid=1190川口リリアホール開館20周年 (1990ー)http://www.lilia.or.jp/event/2010/20101102a/index.html(ウィーンフィルコンサート)というようなものがありました。10年、20年と地道な活動を続けていくなかでのちょっとした広告は励みになります。川口リリアホールは、2003年11月にキーシンのコンサートになんとかもぐりこんだ場所(東京公演すべて完売のさなか)でものすごく覚えています。このホールは、音楽仲間と「春に」という歌をみんなで歌ったこともあるのでそのこともとても覚えています。文京シビックホールは、2007年2月に東京シティフィルの定期でブルッフのヴァイオリン協奏曲聴いたこと、金聖響という指揮者で。なんだかよく覚えています。音楽ホールでは音楽仲間の演奏会を2-3度ここで聴いたこともあります。めったに行かない場所でもありますが、こういうことから、そのときの風景を思い出したりすることも。●せっかくなのでいろいろお世話になっているコンサートホールはいつ頃からあるのか、ちょっと調べてみました。サントリーホール 1986年~ 開館24年東京文化会館 1961年~ 開館49年NHKホール 1973年~ 開館37年東京芸術劇場 1990年~ 開館20年紀尾井ホール 1995年~ 開館15年東京国際フォーラム 1997年~ 開館13年横浜みなとみらいH 1998年~ 開館12年 ☆ちなみに、これらのホールにだいたい1時間以内でいけるところ・・・というのが、上京したころの家探しの基準。最寄駅から何分とか、会社から何分という前に、引き籠りにならないようにまず考えたことです。不動産屋さんに、あきれかえられ、やっぱり変な人だということを自覚してしまいました。 BGM:リスト 軽やかさ (ピアノ:エフゲニー・キーシン)http://www.youtube.com/watch?v=BZgtx2RxQKMリスト 森のささやき (ピアノ:エフゲニー・キーシン) http://www.youtube.com/watch?v=QWf9twoqXAI&NR=1 ものすごい若かりしキーシンの画像を見て、開館何年あたりの・・・・とタイムスリップしてしまいました。
July 8, 2010
コメント(4)
-

七夕とトロンボーン
七夕の日に、コンサートのお誘いもあり、浜離宮の朝日ホールへ行きました。 吉川武典トロンボーンリサイタルNHK交響楽団トロンボーン奏者のソロリサイタル。(ご参考)NHK交響楽団のメンバーhttp://www.nhkso.or.jp/about/member/player.htmlめったにない機会に感謝しないといけません。<プログラム>トロンボーン:吉川武典ピアノ:三輪郁ゲオルグ・フリードリヒ・ヘンデル 協奏曲第1番 変ロ長調バリス・ドヴァリューナス 主題と変奏ベルト・アッペルモント カラーズ*高橋圭子 トロンボーンとピアノのためのソナタ「風化賛礼」(委嘱作品)ドビュッシー 喜びの島 (ピアノソロ)ステファン・シュレッタ ソナタ「天使ガブリエリの声」音域の広いトロンボーン、多彩な音色もあり、曲ごとに惹きこまれていきました。はじめて聴くような曲ばかりでしたが、楽しそうに演奏されることも伝わってきました。温かい音、太い音、力いっぱいの音、トロンボーンの音を堪能しました。トロンボーン奏者を父にもつ伴奏ピアニストは冴えわたっていました。静かに伴奏する箇所も、大きな和音で盛り上げるところはもちろんですが、ソロでの喜びの島が、一層引き立つような感じになりました。委嘱作品があるのもいいですね。作曲家の前で演奏し、作曲家が舞台にあがり、とてもなごやかな雰囲気になります。こうして音楽のカルチャーは少しずつ進化していくのかと、演奏と演奏家と作り手のなかにいて強く感じました。拍手の鳴りやまない、とてもすばらしいコンサートに行けてよかったです。●それにしても、トロンボーンとピアノの組み合わせも面白いです。伴奏ピアニストのおかげで、いろんな楽器の組み合わせのコンサート、これまでも行きました。 視点が広がり、ピアノの可能性が広がり、自分自身もいろいろ広がっていけばいいかと思うようになっています。ヴァイオリンとピアノhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201005200000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200911130000/コントラバスとピアノhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200912250000/弦楽四重奏とピアノhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200904190002/フルートとピアノhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200903010000/フルートとチェロとピアノhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200806060000/クラリネットとピアノhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200507230000/☆☆七夕のたんざくは、作りませんでしたが、何年か前、家の近くの庭園に笹の葉があり、「ぴあのがじょうずになりますように」とこどものようなたんざくを作ったことをありました。今日はそんことを思い浮かべるようにします。
July 7, 2010
コメント(0)
-
サラダ記念日とピアノの日
7月6日はサラダ記念日とピアノの日なんだそうです。ネットであそんでいたら、教えてくださる方がいました。●「この味がいいね」と君が言ったから 七月六日はサラダ記念日」俵万智さんの短歌サラダ記念日という本は280万部のベストセラー、20年と少し前のこと、大ブームにあやかって、自宅にもあります。こういう感覚は、いつも持っていたいです。●ピアノの日というのは、1823年のこの日、シーボルトが日本にピアノを持ち込んだことから。1823年、ショパンもシューマンも少年時代、ベートーヴェンは、50過ぎの晩年時代。30番・31番・32番の後期ソナタが1822年、第九が1824年に発表。そんなご時世に、日本はクラシック音楽第一歩の日。黒船が来る30年前。この時代に日本にいたら、お百姓さんでもしていて、ピアノは知らずじまいなったのでしょうね。●ベートーヴェン ピアノソナタ第30番 Op.109 第2楽章たった2分半ほどの曲ですが、かっこいい、この楽章好きなんです。前後の楽章とは雰囲気ちがいますが、ぱりっとしていて、気が引き締まります。http://www.youtube.com/watch?v=kt4BlXE3g1Eダニエル・バレンボイム(pf) 第2楽章http://www.youtube.com/watch?v=WgB6zyFvAQoアルフレッド・ブレンデル(pf) 第1・第2楽章
July 6, 2010
コメント(4)
-
雨の日に、「水の上で歌う」 Auf dem Wasser zu singen 聴きたくなりました。
大雨でたいへんだった方もきっといらしたでしょう。幸い、小雨のときに歩いていたので、自分は大丈夫でしたが・・・。ブルーマンデーというわけでもないのですが、ドイツリートがふとあたまに浮かびました。● http://homepage2.nifty.com/182494/LiederhausUmegaoka/songs/S/Schubert/S345.htm「 水の上で歌う 」 (上記より引用) Auf dem Wasser zu singen 詩: シュトルベルク 波の上できらめく光につつまれて、ゆれながら小船はスワンのように滑っていく。穏やかに光る波の喜びにのって、私の心も小船と同じように滑っていく。大空から夕陽がさして、船のまわりの波の上で踊っているものだから。西側の木立の頂きの上から、夕陽の光が私たちにやさしく手招きし、東側の木立の枝の下では、夕陽の光の中で菖蒲が静かにそよぐ。夕陽に包まれた、大空の喜びと木立の中の安らぎで、私の心は満たされる。ああ、露にぬれて光る翼のような、ゆれる波の上で私は時が経つのを忘れる。昨日も、今日も、そして明日もこの翼の上で、時は失われていくだろう。ついには、もっと光る翼に乗って高みにまい上がり、私も過ぎ行く時の上から消え去るのだ。 http://www.youtube.com/watch?v=UdBwdtXJeEIイアン・ボストリッジ(テノール)http://www.youtube.com/watch?v=QwTrzF5KFVQフィッシャ・ディースカウ(バリトン)http://www.youtube.com/watch?v=O405pK6BuUcバーバラ・ボニー(ソプラノ)シューベルト=リストhttp://www.youtube.com/watch?v=FP_5-ARMtjE&NR=1エフゲニー・キーシン(ピアノ)●20年ほど前に見た、日本の作曲家をテーマにした映画での挿入でこの曲知りました。 この歌にはずいぶんと癒されています。今日もそうです。シューベルトのことをとても好きだったといわれるリストがピアノ版に編曲。面白い取り合わせです。いつか弾いてみようかなあ。
July 5, 2010
コメント(200)
-
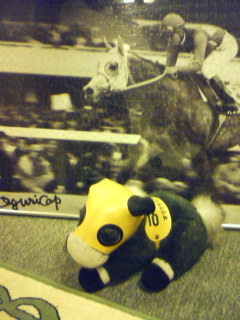
オグリキャップのこと、家にあるオグリのジグソーパズルの人形。
テレビのニュースでオグリキャップという20年くらい前に活躍していた馬が亡くなったということを聞きました。このときは、それほど自分自身は、普通のニュースとしてしか感じていませんでした。今日の午後、コンビニへ行く用があり、スポーツ新聞の数々を見たときのこと。スポニチ、サンスポ、日刊スポーツ、報知新聞、デイリー、みんなオグリキャップが1面でした。サッカーのワールドカップの日本の試合はなかったものの、サッカーでも大相撲のことでも、巨人阪神戦でもなく、すべてが1面。日のめぐりあわせもありますが、驚きでもありました。 自分の家にも、オグリキャップのジグソーパズルもあり、馬のぬいぐるみもあります。ジグソーパズルは、大阪の実家を海外赴任で離れるとき餞別がわりに弟からもらったもの、馬のぬいぐるみは、宝塚にある阪神競馬場でオグリキャップを見に行ったときに、はじめて買ったもの。 1987年に地方から勝ち上がって、中央へ入り連戦連勝したこと、それからの4年間は、昭和の終わりから平成のはじめのこと、活気がある時代に、世の中の変わりを感じました。赤鉛筆のおじさんだけでなく、若い人、女性が競馬場へ来始めたこと、そのなかに自分もいたように思います。ちょうど私自身は、1988年の入社3年目のときに病気で入院し、いろいろなところでぶつかり、仕事の内容を変えたきっかけの年。1989年から会社の中で職掌を変えたことで新人研修をもう1度受けなおした年。いろんな意味で励みになった中でのことだった感じです。芦毛同士で一騎打ちだった天皇賞、2400m2分22秒2という驚異的な日本レコードだったジャパンカップ、最後の有馬記念は、何度もテレビで流れたもの。最後の有馬記念はクリスマスイブの前の日曜日なのに、仕事していて、帰ってきてすぐにテレビみたこと覚えています。馬の年齢の25歳は、人間に直したら80歳くらい。余生を楽しんでいるなかでも、多くの人が記憶に残っているということに感激しました。パフォーマンスに多くの人が夢を求めていることもわかりました。「オリノコ・フロウ」・・・20年前にはやっていたポップスを聴いています。http://www.youtube.com/watch?v=xfVJ11GXzXQ
July 4, 2010
コメント(200)
-

詩と人生を語る・・・新宿紀伊国屋サザンセミナーにて
第70回紀伊国屋サザンセミナー「ぼくはこうやって詩を書いてきた-谷川俊太郎、詩と人生を語るー」刊行記念対談 谷川俊太郎x山田馨 ”詩では言えなかったこと”週末の夜は、この講演会に行きました。70歳をはるかに過ぎた男性の老人2人の対談ではありますが、生涯現役で人生を満喫されていること、素朴な生きざまを詩という形で素直に表現されていること、400人の聴衆はどういう人が来るのだろうと思えば、国語の教科書や合唱コンクールの作詞になっていたりすることもあってか、10代、20代の人も割と多く、これには驚きました。詩を書かれるだけではなく、詩を朗読されます。この日もCDとかテレビでしか聴いたことがなかったもの、はじめて生の声で聴いて感動しました。原稿料が自分自身の生活の支えとしていたと現実的なことも言われ、あたりまえのことにあらためて振りかえらせてくれることにもなりました。対談と詩の朗読のあと、聴衆とのやりとりが、面白かったです。簡潔な散文は詩に直結する・・・ということ、大変ひびきました。詩の朗読は、芝居のせりふではなく、ニュートラルに日本語に忠実に。・・・実際の詩の朗読を聴いて、その意味もあらためて感じました。苦しんでいるときは、長く続くはずがない・・・詩人であれ表現する人に鬱っぽい状態というのはありがちですが、長く生きられてきた方の達観された見方感動しました。推敲すること、これでもう完成という境目・・・他人の目でみてもらう、自分が他人のようになって判断する。・・・絵でも文学でも音楽でお同じなのかと感じました。外からの刺激があって、他人からの注文を忠実にこなしていくそんなことを言われていましたが、忠実にされているということが、このやりとりを見て感じました。700ページ以上して、2800円する本ですが、サインもいただき、握手もしていただき、また自分自身の財産が増えたということを素直に喜びたいです。北軽井沢とグランドキャニオンと講演のなかで出た地名も記憶に残りました。旅をするときの候補になりそうです。
July 4, 2010
コメント(0)
-
軽井沢と松本・・・夏の音楽祭のWEB案内から
軽井沢での音楽祭ロマンティック・シューマンhttp://www.karuizawa8.com/event/index.html野平多美さんが構成するプログラムを見て感激してしまいました。サイトウキネンフェスティバル「詩と音楽」http://www.saito-kinen.com/j/program/tanikawa/詩の朗読者が選んだ弦楽四重奏とのコラボレーション音楽祭もコンサートに加えて、企画がいいもの増えてきました。そうとう練られたものになってきているような気がします。
July 2, 2010
コメント(0)
-
東京国際ブックフェアの案内をながめて。
この前に東京ビックサイトへ行った時もかえりにちらしをいただいたりしました。ネットでも案内があり、次週の週末開催ですが、興味深い講演会もありそうです。第17回東京国際ブックフェア(上記URLより引用) 7/10読書の力-「自己内対話」が開く世界東京大学大学院教授姜尚中 氏 「情報の海の中で溺れずに、身の丈に合った人生やその価値を築くことが重要になっている。そのために今こそ読書が大切な時代はない。読書を通じて「自己内対話」を続けていくことで世界への窓が開かれていくはずだ。夏目漱石の著作を通して人生の思索を繰り返してきたという姜氏が、読書の大切さを語る。」7/11読むこと 書くこと 生きること作家浅田 次郎 氏 「読書人とは読書好きな人ではなく、読み書きできる人」という浅田氏。1日の半分を読書に、半分を執筆に費やすという。"泣かせの浅田"から、ついつい吹き出してしまうコメディー作品も得意とする浅田氏が、読書法から執筆作法まで、読み書きについての私論を披露する」●案内を見ていて、とても共感してしまいました。身の丈に合った・・・というキーワードは、自分自身でも思うこと多いですし。読み書きできる人・・・ということも、音楽にたとえたら奏でることも演奏を聴くこともということですし。この講演時間90分と、大学の講義ヒトコマだと思えば、貴重な時間になるかも。日曜美術館の司会者の生の姿は拝見したことがないのですが、ちょっと行ってみたいという気がしてきました。http://www.youtube.com/watch?v=COCIOtA0qBQシューベルトの未完成交響曲第2楽章、思いつきですが聴きたくなりました。
July 1, 2010
コメント(0)
全34件 (34件中 1-34件目)
1
-
-
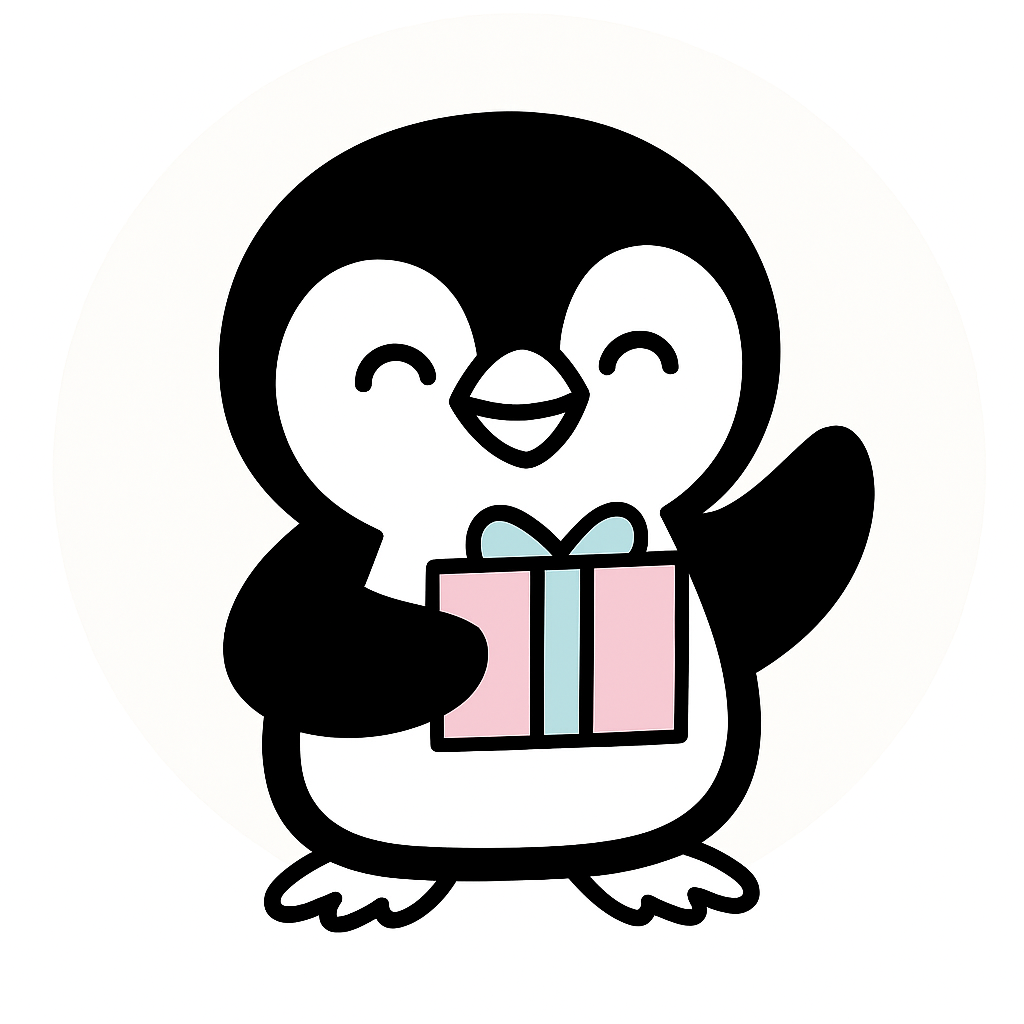
- いま嵐を語ろう♪
- 嵐コンサートツア決定! ARASHI LIVE…
- (2025-11-22 22:27:58)
-
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-
-
-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…
- KING of IDOL 踊るパワースポット!
- (2025-10-05 15:16:43)
-







