2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年01月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-

介添えボランティア・川畠成道ヴァイオリンコンサート
川畠成道さんのヴァイオリンのコンサート、聴きました。川畠成道(ヴァイオリン)、ロデリック・チャドウィック(ピアノ)<プログラム>ソナチネ(ドヴォルザーク)ヴァイオリンソナタ2番 イ長調 op.100 (ブラームス)***歌の翼に(メンデルスゾーン)ハンガリー舞曲第5番(ブラームス)コンソレーション(リスト)熊蜂の飛行(リムスキー=コルサコフ)アヴェ・マリア(グノー)カルメン幻想曲(ワックスマン)(アンコール)エクアーロ (ピアソラ)チャルダッシュ(モンティ)ひばり (ディニーク)G線上のアリア (バッハ)●デビュー10年の川畠さんのヴァイオリンのコンサート。毎年1月の終りに行くことが多いです。前半は少し重いプログラム、後半はカジュアルな感じ、ここ数年変わらないコンセプトのように思えます。そのなかで少しずつ新たなレパートリーを加え、いろいろ楽しませていただきます。 なかなか冴えわたっていました。ブラームスのソナタとかがプログラムに入るようになり、2番は特に個人的にも好きなので、聴き入っていました。ヴァイオリンの高音の彼独特の澄み切った音色は、いつもながら感動しました。伴奏ピアニストもいつもながら気になり、メンデルスゾーンもありましたし、ヴァイオリンの音とピアノの音のバランスとかも勉強になりました。小品をたくさん演奏されています。10年たって、ベスト盤といわれるCDは、かつての録音を再販するのではなく、全部録音しなおしたとか。それでどれだけ進歩しているのか自分で確かめたいと言われていました。たぶん、タイスの瞑想曲、ヴォカリーズ、歌の翼に、ロンドンデリーの歌、ツィゴイネルワイゼン・・・何千回も弾かれているからなのでしょうけど、高い境地を感じます。音の少ない曲は音そのものが問われるわけですし高い技術があっての演奏という気もしますし、人柄とか人間性とかそういったものも音に表れているのでしょうし、このCDは持っていないのですが、コンサートのなかで語られたこと、たいへん印象的でした。 このコンサート、私は介添えボランティアという役割であったりします。5回目になりましたが、今回は少し人生の先輩の男性の介添えをさせていただきました。なかなか音楽を生で聴く機会もなく、本当に楽しみにされておられたようで、そういうお役にたてたのはうれしかったです。質問された紀尾井ホールの、紀尾井の由来は、紀州徳川家、尾張徳川家、彦根井伊家の中屋敷があったことに由来しているそうです。たぶん・・・としかいいきれず、即答できずに、勉強不足でした。帰りのなかで、曲によって、拍手の大きさが、左のほうだったり、右のほうだったり、少しちがうのです・・・といわれたこと、非常に印象的でした。目が不自由ななか、他の五感は、それ以上のものになるのでしょうか、私なんか想像もできないような耳のよさです。もし、なにかのボランティアでピアノを弾くということになったら、自分はどういう風にすればいいのでしょうか。拍手の大きさのお話をうかがって、とてもごまかしでは弾けないとおもいました。せめていろんな聴き手のことも考えて、曲を選ぶところから、まじめに考えたいと感じています。BGM: メンデルスゾーン 歌のつばさに ヴァイオリン:川畠成道http://www.kawabatanarimichi.jp/
January 31, 2009
コメント(2)
-
テヌート・スタカート
インターネットでいろいろみていましたが、弦楽器の曲のほうがよくあるみたいです。スタカートの上にスラーがかかっているときのことです。いままでもあったのかもしれませんが、無意識だったかもしれません。スラーの最後の音だけスタカート、これはベートーヴェンのソナタとかでもあったようにもおもいますが。メンデルスゾーン op.62-6 と書けばぴんときませんが、無言歌集の春の歌。 20小節目くらいで、頻繁にこれがでてきます。音の数はたいして多くないかもしれませんが、こういう1小節を大事に、弦楽器で音をぽーんと放つかのように少しクレシェンドして、テヌートとスタカートと一見相反するようなことをピアノで表現できるようになりたいものです。だれでも知っている有名どころの曲、ちょっとなにか弾いてというとき、わかりやすい曲のひとつ。装飾音も多く、メロディラインを保つのは難しく、レガートで弾くとなると、弾いている途中で4→1とか5→1とか、細かく指をかえていかないと音が途切れてしまい、ペダルでごまかすことになってしまいます。舞台とかで弾くのはとても手こずるような雰囲気がただよいます。バッハとモーツァルトの影響を受けたら、こういう曲集になるのでしょうか。声部が多いところは、そうとう弾きこまないと、聴き手には伝わらないように感じ、曲全体というよりも、気になる2-3小節を深く練習してみたいです。
January 30, 2009
コメント(0)
-
作曲家コミュニティの数
mixiで、コミュニティをいくつかはいっています。ピアニストのコミュニティ、作曲家のコミュニティは、それがあったおかげで、ずいぶん知識を得たこともあります。ときどき、いろんなことを客観的に見たくなります。たまたまメンデルスゾーン・コミュニティが1318人という数をみて、その近所の作曲家あたりからシューマン 2676人ショパン 14709人シューベルト 1300人ブラームス 5087人<もう少し時代をさかのぼったら>バッハ 8413人ハイドン 568人モーツァルト 7639人ベートーヴェン 6435人<もうすこし20世紀よりに>ドビュッシー 8674人ラヴェル 5234人フォーレ 2158人メシアン 1318人<寒い国の作曲家>チャイコフスキー 5771人シベリウス 1709人グリーグ 608人ショパンはダントツのようです。ピアノ弾く人は、まず選ぶからでしょうか。微妙な人数のバランスを見て、時代や国のカテゴリーでならべてみて、なかなか興味深いものを感じました。ショパンの1割くらいがメンデルスゾーンということなのか。グリーグよりは多いとおもったけど、メシアンとほぼ同じとは。ちょっと少ない目のコミュニティのほうが、でも深い話ができたりします。グリーグイヤーの2006年には、旅の案内から、めずらしいノルウェーの留学話から、トロルドハウゲンでのコンサート案内から、一時帰国時のコンサート案内まで。雑誌の執筆された案内もいただきました。グリーグイヤーがおわって、2年たっても、バーチャルだけでなく、顔と名前が一致するのですから、文明の利器には感謝しないといけません。旅はしてみてよかったと、あの年ほどおもったことはありません。旅先もしかもトロルドハウゲンで日本人のかたですか?ということからはじまって、グリーグホール近くのベルゲンという駅前で、mixiってところでやっています?とかのはなしになって、お別れしたあとずっと飛行機にひとりでのったあと、成田空港についたら携帯でマイミク申請して、家についたころマイミクになっていたときはさすがに感動しました。こんなことは二度とないでしょうけど、一期一会ということばは、大切にしたいと思っています。世の中なにがおこるかわからないと、わくわくしつづけたいです。BGM: メンデルスゾーン チェロ・ソナタ 第2番 op.58 チェロ:ミッシャ・マイスキー ピアノ:セルジオ・ティエンポ
January 29, 2009
コメント(6)
-
メンデルスゾーン・マスターワークス 30CDのこと
http://www.hmv.co.jp/product/detail/2872242メンデルスゾーンの30枚のCDセットが出されていることを知りました。こういう全集ってあまり、買ったりすることもないのですが、ピアノの曲集で、弾いているピアニストの名前をみて、俄然興味もちました。30枚目のうち、Disk26 といわれているもの。(上記のURLから抜粋)・無言歌 第1番 ホ長調 Op.19-1・無言歌 第2番 イ短調 Op.19-2・無言歌 第38番 イ短調 Op.85-2・無言歌 第41番 イ長調 Op.85-5・無言歌 第9番 ホ長調 Op.30-3』 グレン・グールド(ピアノ) 録音: 1970年7月トロント・無言歌 第45番 ハ長調 Op.102-3『タランテラ』・無言歌 第18番 変イ長調 Op.38-6『デュエット』・無言歌 第34番 ハ長調 Op.67-4『紡ぎ歌』・カプリッチョ イ短調 Op.33-1 アリシア・デ・ラローチャ(ピアノ) 録音:1995年12月ニューヨーク(デジタル録音)『無言歌 第25番 ト長調 Op.62-1『5月のそよ風』 ルドルフ・ゼルキン(ピアノ) 録音:1962年12月ニューヨーク・無言歌 第40番 二長調 Op.85-4『エレジー』・無言歌 第30番 イ長調 Op.62-6『春の歌』・無言歌 第35番 ロ短調 Op.67-5『羊飼いの訴え』 ウラディーミル・ホロヴィッツ(ピアノ) 録音:1946年10月(モノラル録音)***この1枚だけでも、大変な価値を感じます。いままで、自宅にもそれなりに持っているほうだとおもってはいますが、びっくりです。上に書かれているピアニストで、ぱっと思いついたのは以下のような感じ。他のCDは持っているから、イメージもあるから、だからよけいにおもしろいです。グールドは、op.116-op.119のブラームスの抜粋のもの、孤独ななかでのピアニズムを感じました。ラローチャは、2回コンサート聴きに行ったことあるのですが、ショパンの舟歌と幻想ポロネーズ、深い人生のなかで弾かれた演奏に深く感動しました。シューマンの謝肉祭のCDもお気に入りのひとつ。ルドルフ・ゼルキンは、ベートーヴェンの後期ソナタのCDがまず聴いたなかでは思い出します。ホロヴィッツは、書き出すときりがありませんが、シューマンのトッカータではじまり、アラベスク・花の曲でおわるCDは、圧倒的に冴えわたったテクニックもあれば、愛らしい子供の情景は、語りかけるような演奏、毎日のように聴いていました。それぞれの好まれる曲を弾かれているのでしょうけど、個性を感じます。また楽しみが増えました。 BGM:メンデルスゾーン 歌の翼に op.34-1 女の手紙 op.86-3 無言歌「五月のそよ風」 op.62-1 無言歌「春の歌」op.62-6 チェロ:ミッシャ・マイスキー ピアノ:セルジオ・ティエンポ 無言歌を、メロディをチェロ、伴奏部分をピアノで聴けるので、 いろんな意味で楽しめませす。 音のバランス、絶妙です。でもこれをピアノ1台で無言歌ということになると、 いかに高度なテクニックがいるのだろうと、考えさせられました。 内声部がうるさいなーといわれないように、この際いろんなこと考えて ピアノも弾けるようになりたいものです。
January 28, 2009
コメント(2)
-
スコットランド交響曲の本は図書館で読まなければ。
メンデルスゾーンのスコットランド交響曲という著書があります。音楽之友社出版 星野宏美著483ページあり、8000円以上するらしいです。インターネットの本屋さんではお取り扱いできません。とあり、どういうことなのだろうと、いろいろ見ていましたら、絶版になっているらしいです。残念・・・どうしようと、いろいろ知恵を働かして検索してみたところ、東京中央図書館には、閲覧可能ということがネットでわかりました。たしか、広尾の駅から、歩いて、有栖川宮記念公園のそば。http://jin3.jp/annai/arisugawa.htmそういえば、昔だれかと一緒に行ったなあ・・・と思い出してしまいました。貸出はできないらしいけど、ゆっくり見る時間をつくってみようと思っています。スコットランド交響曲、完成するまで14年もかかっているのだそうです。けっしてさっと曲を書いてしまうだけの人ではなかったのか、ブラームスの1番の交響曲ではありませんが、それと似たように推敲を重ねる作曲家だたのかと、想像してしまいました。まだ読んでもいないのですが、この14年にかかった内容の本は楽しみです。東京芸大の楽理専攻され博士でもある星野先生はどのように解説されているのか、たった2週間ほど前、立教大学で少しレクチャーを聴いただけなのですが、大変興味もっています。BGM:サン=サーンス 序奏とロンド・カプリッチオーソ ヴァイオリン:豊嶋泰嗣 ピアノ:三輪郁 家にあるCDでは、メンデルスゾーンはなかったので、雰囲気が近いものを探しました。 きのうも書きましたが、豊嶋さんは、サイトウキネンオーケストラのメンバーであり、 九州交響楽団、新日本フィルのコンサートマスターでもあります。 知らないあいだに間接的に聴いていたりします。 意識したのは、2年ほど前、すみだトリフォニーでこのCDが出るからといって 15分ほど演奏を聴いたあたりから。音楽を楽しまれて演奏されるスタイルがとても好きです。● 2月3日のメンデルスゾーン生誕200年の日には、それにちなんだコンサートも いろんなところであるみたいです。2月3日(火)18:30 愛知県芸術劇場コンサートホール東邦ガス 名フィルコンサート in名古屋■指揮者/共演者■川瀬賢太郎(指揮) 森本千絵(ヴァイオリン)* 三輪郁(ピアノ)**■曲目■メンデルスゾーン 序曲『フィンガルの洞窟』作品26 ヴァイオリン協奏曲ホ短調 作品64* ピアノ協奏曲第1番ト短調 作品25** 交響曲第4番イ長調 作品90『イタリア』■問い合わせ■東邦ガス広報部 052-872-9321**** この日ならではのプログラム。見ているだけで楽しそうです。 名古屋の栄の駅のそばのコンサートホール、何回か行ったことあります。 めったにプログラムにのらないピアコン1番は、今年に限ってかもしれませんが、脚光を浴びているみたいです。 といろいろありますが・・・ ピアノを練習しなければ・・・・・・という気になってきました。
January 27, 2009
コメント(0)
-
「失われた幻影」op.67-2
http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200702040000/2年前に行ったコンサートで印象に残っているものがあります。オーケストラのコンサートだったのですが、アンコールで、メンデルスゾーンの無言歌だったから、はっとした感じはいまでも覚えています。 しばらく忘れていた曲集を思い出させてもらった感じがしています。メンデルスゾーン 無言歌集より op.67-2 嬰ヘ短調、アレグロ・レジェーロ 《失われた幻影》 弾いたピアニストはアンスネスでした。この年、このピアニストを追っかけ、ノルウェーのグリーグホールまで行ってしまったのですが、このとき弾いたモーツァルトのピアノ協奏曲より、強烈にこの2分少しの曲の印象が強かったです。 これも名曲のひとつだと思っています。和声が込み入ってて弾くのは大変かもしれませんが、とても興味もっているもののひとつ。●2月になると、この2007年もそうでしたが、メンデルスゾーンの交響曲の演奏会がいくつかあったりします。N響アワーの池辺先生がメンデルスゾーンのスコットランドという交響曲とシューマンのラインという交響曲が好きということで、この番組は欠かさずみるきっかけになる理由のひとつだったりして、共感したりしています。今年2月2日に紀尾井ホールで、「イタリア」「スコットランド」と2つ並べた交響曲の演奏会があります。4番→3番の順に演奏されるとのこと、私もこの順のほうが聴きやすいと思っているくらいで、うれしかったです。 これに伺う予定でいます。ちかしオーケストラ、という変わった名前のオーケストラなのですが、田中千香士さん(元N響コンサートマスター)の集まりの会だそうです。1/21に紀尾井ホールへ別のコンサートで行ったとき、1/19に田中千香士さんがお亡くなりになられたという訃報をホールの受付で伺い、でもこのコンサートやりますので、来てほしいと言われました。コンサートマスター豊嶋泰嗣さんが中心になってコンサートを行うとのことです。先日、雑司ヶ谷音楽堂で聴いたヴァイオリニストもメンバーに入っていて、いろんなご縁を感じます。こんな催しもありますので、ご案内まで。2月3日はメンデルスゾーン生誕200年の日。なんだか、この前後でピアノ弾く機会があれば、自分も少しでもいい演奏がしたくなりました。BGM:モンポウ 歌と踊り 1番 ピアノ:レイフ・オヴェ・アンスネス
January 26, 2009
コメント(2)
-
10回目のピアノの発表会にむけて
1月の土日はこれまでずいぶん出ずっぱりでした。正月明けからここまでピアノを弾いたり聴いたりという年もめずらしいかもしれません。今日はその気になれば行こうと思っている場所もあったのですが、少しのんびりすることにしました。家でのんびりするときは、「食う・寝る・弾く・・・」という感じで、あいかわらずの引きこもり状態でした。 それにしても、休日を休日らしく、つつましくする日もあっていいと感じました。1か月1日はこれといって何もしない日をつくろうとおもっているのです。ピアノは練習したほうかもしれません。昨日のこともあり、ずいぶん刺激をうけたことに、ちがいはありませんし。発表会まで気がつけばあと2か月になっているし。小品3曲をどういうテンションや流れにすれば、気分よく聴いていただけるのかということも含めて、考える機会にもなったかもしれません。あと2か月弾きこむ時間がどこまでとれるかということもありますが、ちょっとは楽しみになってきました。毎年3月に出る教室での発表会は今度で10回目になるので、やはりこの数字を見て感じるものあります。 習いたてのころよりは多少まともにはなっていると思いますが、そのときになってみないとわからない的なことは、減ってきているようにも思えます。2000年:ショパン バラード2番 op.382001年:シューベルト 3つの小品 D946-22002年:ベートーヴェン ピアノソナタ13番 第3・4楽章2003年:ベートーヴェン ピアノソナタ11番 第3・4楽章2004年;シューベルト 即興曲 D935-22005年:ブラームス 6つの小品 「バラード」op.118-3 「ロマンス」op.118-52006年:シューマン 謝肉祭 op.9 「パンタロンとコロンビーヌ」以降の曲2007年:ショパン 24の前奏曲 op.28-7,8,9,10,11,122008年:ベートーヴェン ピアノソナタ27番 op.90 第2楽章2009年:メンデルスゾーン 無言歌集より「眠れぬままに」「安らぎもなく」「瞑想」・・・予定たいした練習時間もないなか、1年かけてやったときもあれば、夏休み明けからと決めてかかったときもあります。自分自身の場合、納得して弾こうとおもえば、やはり半年くらいは、どんな曲目であれ、最低かかるとおもっています。小心者のわたしは、そうでないと、おそろしくてとても舞台になんかたてません。2月・3月は仕事上、何が起こるかわからないこともありました。3月1日付で東京を離れた年もあり、1か月新幹線で通い、たかが趣味の発表会であれ、意地をはって弾いたこともありました。2月に徹夜まがいの仕事がつづき、まったくレッスンどころではない時もありました。その2つがベートーヴェンのときだったので、いろいろ勧められたとき、いやだと断固拒否したこともあり、ようやく去年そういうことなしで弾きたい曲が弾けてよかったと思ったりもしました。体験レッスンのときにop.90が弾きたいといっていたくらいですので、やっぱりうれしかったです。準備期間が半年なかった年は1回だけありました。入院休養明けの年でした。松葉杖ついてレッスン通って、12月スタートでした。ぎりぎりまで苦労しました。ブラームスのバラードの譜読み、上記のなかでは難関でありました。発表会ではそれほど弾けなかったので、夏までいろんなところで弾き続けた記憶あります。それと、ブログはじめだしたころでして、知らない方から、発表会の早朝に応援メッセージもらって感動したこともありました。いくら譜読みができていても、そのときの精神状態のよくないとき、まったくといって弾けないのはシューベルトでした。この作曲家の曲は、いらいらしているときに弾くとけんかを売っているように聞こえるみたいで、穏やかな気分でいるように日常生活が問題になりました。ショパンはつくづく向いていないとおもいつつも、ブレハッチがショパンコンクール1次予選で弾いたプレリュードを少しはあやかりたいと思って1年半くらい前に弾く曲を決めたりしたこともあります。バラ2のときも感じましたが、左手のベースラインの重要性を思い知りました。演奏そのものより、選んだ曲そのものを気にいってくださることをときどき伺い、それがうれしかったことも何度かありました。今年も自分自身をあらわしているような感じかもしれません。不眠症きわまりないときもありますし、安らぎもないような日もしばしばですし。せめてよく眠れるように、安らぎのあるように、瞑想したいとおもっているのは本心です。多くのかたに励ましていただいて感謝しています。BGM:ベルリン・フィルハーモニー交響楽団 ヨーロッパ公演(inモスクワ) BS-2より 指揮:サイモン・ラトル ストラヴィンスキー 三楽章の交響曲 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲(vn:レーピン) ベートーヴェン 交響曲7番ブルッフのヴァイオリン協奏曲いまおわりましたが、こういう曲調がとても好きです。 何回聴いても感動します。
January 25, 2009
コメント(6)
-
月のホールにて/PTNAステップ熊谷冬季の巻き
高崎線で、熊谷のつぎが、籠原で、その次が深谷という駅だということ、覚えました。3年前に、熊谷と小山はどっちが手前にあるという、高崎線の宇都宮線をちゃんぽんにして、困らせるような質問はさすがにする必要がなくなりました。渋沢栄一記念館からもどって、夕方以降は、ピアノのおはなし。ベーゼンドルファーのピアノがあるからというわけではありませんが、PTNAステップに参加しました。12回目になります。熊谷には太陽のホールと、月のホールというところがあります。太陽のホールは、6年前、ミッシャ・マイスキーのチェロを聴きに行った場所、サインも貰った場所、シューベルトのアルペジオーネ・ソナタを聴いて感動した場所でもあります。そのホールのとなりが月のホール。ピアノを弾くにはちょうどいい感じのホールで、木目調のべーゼンのピアノがありました。きのう、ムジカノーヴァに書かれていたメンデルスゾーンの無言歌集から「浮き雲」と、それ以外では、「安らぎもなく」「瞑想」と、10分で3つならべてみました。ひとり前に弾かれたラヴェルのクープランの墓より、プレリュード、リゴードン、トッカータは、音大生が試験対策に弾かれていました。激しい曲であるにもかかわらず、なめらかな運びで、決してうるさく聞こえず、(無理して弾いているというイメージの演奏はあまり好まないです)、すばらしかったです。このようなあとでも、ずいぶん淡々と弾けるようになったかもしれません。今日はあまり気になりませんでした。10分の持ち時間は幾分ぎりぎりだったので、それはちょっと気になりましたけど、比較的気分よく弾いたほうなのかもしれません。3人のアドバイザーのうち2人がブラボーをだしてくれたので、ちょっと安心しました。2曲目と3曲目は発展途上なのは、自分でもわかっていて、いわゆるステップの感覚でした。内声部の音の出し方、バランス、アドバイザーによって意見が真っ二つに割れた感じのものもありました。試験のように減点法のように聴く人とは相性がよくなく、楽しんで聴いてくださるアドバイザーの方は、筆がすすみいっぱいコメントも書いてくださるようで、聴き手の好みにも左右される選曲なのかもとの印象も持ちました。最後に演奏する順番になったのですが、最後にこの無言歌を聴けてうれしいと書いてくださったアドバイザーの名前の方はずっと覚えていようと思いました。今日はたくさん歩きましたし、歴史も音楽も楽しめました。寒い1日でしたがよい週末になってよかったです。
January 24, 2009
コメント(2)
-

高崎線・深谷駅、渋沢栄一記念館
上野駅の13-17番ホームはいろいろご縁があって最近よく利用いたします。この駅にある、「ふるさとの 訛りなつかし 停車場の ひとごみの中に そを聴きにゆく」という石川啄木の歌碑は、何人の人を見てきたのだろうとおもいつつ、高崎線に乗りました。1時間半ほどたって深谷駅。写真のとおり、東京駅と似た感じです。よくよく伺ってみると、東京駅の煉瓦(レンガ)は、深谷で作られた煉瓦が運ばれて出来ているのだそうです。初めて知ることとなりました。そして、この煉瓦工場を明治時代につくったのが渋沢栄一という方ですが、この地の出身地だそうで、多くの観光スポットもあります。第一銀行(今のみずほ銀行)の創設者であることは、歴史の授業で習ったことありますが、帝国ホテルも王子製紙も東洋紡も東京証券取引所も・・・・といまも脈々と続いているものの原点を感じるような方の人物伝を地元ボランティアの方から伺い、たいへん勉強になりました。1840年生まれだから、音楽の歴史に直したら、ショパンとかシューマンとかメンデルスゾーンとか、活躍していたあたり。27歳が明治維新であるので、激動の時代を生きた方でもあります。明治維新の前後で、15代将軍徳川慶喜の弟とパリ万博へ行ったことが人生を変えたとか。歴史の教科書は実績を残した晩年のことしかかかれませんが、そこに到る背景とかを知ることとなりました。百年に1度の・・・ということばが、語られる今を生きられたら、なんと申されるのか、聴いてみたくなりました。家に帰って調べてみると、ピーター・ドラッガーのことば、印象的でありました。「明治の日本には、三人の重要な人物がいた。 福沢諭吉、渋沢栄一、そして岩崎弥太郎である。 彼らは個人としては、まったく異なっていた。 福沢は「実務家」、渋沢は「倫理家」、岩崎は「起業家」だった。 だが、同じ目標と未来像を描き、勇気と先見性と手腕をもって近代国家・日本を創ったのである。 今日、三人の偉業が意味するところは大きい。」 かつて千円札の肖像画で、伊藤博文と渋沢栄一が争ったらしいです。 偽造防止のための髭が決め手になり、かつての1000円札は伊藤博文にきまったとか。それだけの方ということなのでしょう。 東京にもゆかりのある場所はいくつもあるらしいので、折にふれて訪ねてみたいものです。
January 24, 2009
コメント(0)
-

ムジカノーヴァ2月号 特集1を読む。
銀座4丁目、2009年1月の定点観測・・・。クリスマスツリーのあとの季節は、早く春がきてほしいと願っているかのようです。そのとなりにある楽器屋さんへふらりと立ち寄りました。なんにも買うつもりもなかったのですが、なんだかひっかかるメンデルスゾーングッズ??ではありませんが、気になるのでこの際買ってしまったものいくつか。●CD:メンデルスゾーン交響曲3番「スコットランド」交響曲4番「イタリア」クルト・マズア指揮 ライプツィヒ・ゲバントハウス管弦楽団 http://mendelssohn.jp/ 先日、ここで紹介したメンデルスゾーン基金日本支部の代表はマズーア・トモコさんだから、旦那さんがクルト・マズアさんなんでしょう。 今日のBGMになりました。●音楽の友社出版のメンデルスゾーン 無言歌集の楽譜http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200901150000/先日、立教大学へメンデルスゾーンのオルガン曲を聴きに行きましたが、そこでレクチャーされていた星野宏美先生は、この楽譜でメンデルスゾーンの解説がありました。最近知ったのですが、メンデルスゾーン研究の第一人者のようです。かかれた論文とか過去の書籍とか見てみたくなりましたが、まずはこのあたりからと思って・・・。シューマンによる無言歌集に対する批評、興味深いです。(引用します)「夕暮れにピアノの前に座り(グランドピアノでは物々しすぎるような気がする)ファンタジーのおもむくままに楽の音を奏でているうちに、知らず知らずに、ピアノに合わせてメロディをそっと口ずさんでいた経験が誰しもあるだろう。もしもそのメロディと伴奏をピアノの鍵盤上で結びつけることができるなら、そこから世にも美しい無言歌の数々が生まれる」(1835年 音楽新報に掲載された、無言歌集第2集op.30の初版評)メンデルスゾーンの無言歌に対するコメント「人々は音楽について語りたがる。しかし、それに意味があるとはまずない。言葉は音楽を語るために十分ではないのだ。音楽は曖昧だと人々は嘆く。音楽は何かを考えさせるが、それが実に不明確である。一方、言葉は誰しもが理解するというのだ。しかし、私にはすべて逆である。つまり、言葉こそ曖昧で不明確で、誤解をまねくように思える。音楽が私に語りかけるものは、私にとってことばでとらえるにはあまりにも不明確なのではなく、逆にあまりにも明確なのだ。無言歌の作曲の祭に何を考えていたのかと問われるならば、それは、そこにある歌そのものだと答えよう」(1842年10月15日、メンデルスゾーンからの知人あての手紙より要約)作曲家自身のことばですので、深いもので多く尊重したい、ということを感じました。●ムジカノーヴァ2月号特集1 メンデルスゾーン、シューマン、ショパンで学ぶ、ピアノで歌うとは。メンデルスゾーン、浮き雲、ヴェネティアの舟歌が題材。浮き雲については、参考になりましたが、疑問に思うこともありました。「1-2小節目と9-10小節目では、フレーズのかかり方がちがうから、片一方はスラーがかかっていて、片方はかかっていないから、Bの音は必然的に違う弾き方をしなければならない・・・」のところ、雑誌では、たぶんヘンレ原典版で、たしかにそうなっていますが、自宅にある、ペーターズ版では、どちらもフレーズのかかりかたは同じで、どちらもスラーかかっています。子供のころに買ってもらった昭和50年ごろの全音の楽譜も、さっき上でみかけて最新版の音楽の友社の楽譜は、ペーターズ版をほぼ踏襲している感じですので、楽譜を忠実に読み取るということをするとき、本当にそうなのだろうかと、少し疑問に感じました。原典版、解釈版の良し悪しはあるものの、自分がどうしたいのかと考えた上で、弾いてもいいのではとも思っています。ペーターズ版の自然な感じでのフレージングは、歌うという観点から見ればそれもありのような感じがして、無理に音色変えなくてもいいんではと思ってしまいました。手首をつかってブレスする、フレーズを考えるというくだりも、自分はそうやって弾いていないのですが、いろいろな考えがあるのだということで、これは参考になりました。●偶然、ある場所で弾くことになっているので、ピアノの前で、いろんな版の楽譜をとっかえひっかえ見ていました。おかげでよい週末になってよかったとおもっています。
January 23, 2009
コメント(4)
-
「そうですか・・・」
日経アソシエという雑誌のコラムをネットで見ていました。(2008年12月25日号)梶原しげる氏の「人の声ほど情報が煮詰まったものはない」というものから、ちょっと面白いものをみつけました。「そうですか」という声にはいろんな意味があり、文字で「そうですか」と書いても、裏の意味を書くといろんな声が聞こえてくるそうです。なんと、10種類の「そうですか」を紹介していました。(ニュアンスは以下のような感じ)1.新たに発見したとき 「そうですか!」(目からうろこが落ちるような発見ですね。)2.納得したとき 「そうですか」 (ようやく納得できました。了解しました。)3.不安なとき 「そうですか・・・」(やっぱりそうなってしまうんですね。)4.感謝したとき 「そうですか」 (お買い上げいただけるのですね。ありがとうございます。)5.残念なとき 「そうですか」 (来ていただけないのですか・・・残念です。)6.疑いのとき 「そうですか?」(そんなことはないと思うのですが・・・)7.謝罪するとき 「そうですか・・・」(こちらの不注意でご迷惑おかけしました。)8.とぼけるとき 「そうですか・・・」(そんなこと聞いていないのですが・・・ほんとうですか。)9.あきらめるとき 「そうですか・・・」(チケット予定枚数終了ですか。残念です。)10ほっとしたとき 「そうですか」 (探しているものが見つかってよかったですね。)面識のある方を思い浮かべると、文字で書いていても、声が聞こえてきそうで、不思議なものです。●こんな感じで、同じような♪が楽譜に書いてあっても、伝えたい音が変化できるようになればいいのですが・・・。パレットにのっている水彩絵の具のように、いろいろ変わっていけるようになりたいものです。それができたらピアノ弾いていてももっとお話できるような感じになり楽しくなるでしょうね。BGM: ラフマニノフ リラの花 ガーシュイン そうとは限らない (It Ain't Necessarily So) ピアノ: 丹 千尋 http://www.tan-chihiro.com/archives/profile/index.html そうとは限るような感じで、たくさんの音色があって楽しんでいます。 偶然、間接的に、サンプルCDをいただきました。 日本音楽コンクールのチェロ部門本選でピアノパートを弾いていたと聴いています。
January 22, 2009
コメント(2)
-
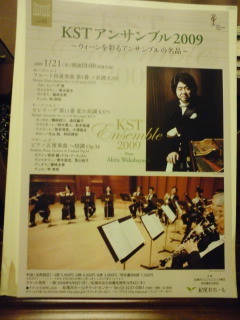
KSTアンサンブル2009 /紀尾井ホール
夕方からは小雨まじりの様相、 四ツ谷から上智大学のそばを通り、紀尾井ホールへと向かいました。迎賓館近くのこの通り、春先にはお花見もでき、初夏には紫陽花の花が見事です。冬まっただなかの中、あっというまにそんな時期もくるとおもい歩きました。KST(紀尾井シンフォニエッタ東京)アンサンブル2009~ウィーンを彩るアンサンブルの名品~さいきん、アンサンブルのコンサートづいていますが、メンバーがそろわないと、なかなかお目にかかれないプログラム。モーツァルト フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 KV285 (フルート、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)モーツァルト セレナード第11番 変ホ長調 KV375 (オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2)ブラームス ピアノ五重奏曲 ヘ短調 op.34 (ピアノ、ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ)多くの楽器の音色が心地よく、楽しく音楽が聴けました。モーツァルトのセレナード、アイネクライネナハトムジークのように弦楽合奏が主体かとおもえば、この11番のように管楽合奏のようなものがあるそうです。管楽合奏のことをハルモニー・ムジークということ、プログラムノートで知りました。左から、オーボエ、ホルン、ファゴット、クラリネットの順で並ばれていて、オーボエとクラリネットの主旋律の対比は聴いていておもしろいものがありました。モーツァルトのK375の第2楽章のメヌエット、木管楽器の音の温かさを感じながら聴き入りました。モーツァルト、ブラームスの並びでのプログラムは、コンサートではよくあることですが、相性がいいことも感じました。重厚なブラームスの演奏がますます映える感じ、ピアノパートは、若林顕さんの演奏で楽しみました。クララ・シューマンが「交響的なスケール感」という指摘をもとにかかれた作品。もともと弦楽五重奏曲のものをピアノ2台に改作し、さらにピアノ五重奏曲に改作されているとのこと、この間2年の歳月があり、練りに練った感じが伝わってきます。そういえば、午後3時半ごろ、会社で外部セミナーを受けていたのですが、コーヒーブレイクの休憩時間のBGMがこのブラームスでした。面白いとりあわせでもありました。 今日も演奏会に恵まれました。ひさびさに紀尾井ホールへ行けてよかったです。●ブラームスの曲は、また弾いてみたくなりました。あの混み混みの和声と重厚な感覚は弾いていてぞくぞくすることもありますし、譜読みは楽ではありませんが、展開部の泣けてくるようなきれいなメロディはおとなの音楽だとも思いますし。この作曲家特有のオーケストラや弦楽四重奏のようなことをピアノ1台での表現していくこと、いろいろ追求しがいがありそうです。紀尾井ホールでもらったちらしのなか、ツィメルマン来日コンサートのものがありました。バッハ、ベートーヴェン、ブラームスの作品とだけあって曲目未定です。op.118,op.119とかかつて聴いたことありますが、やはりこのあたりでしょうか。2年ほど前のヴァイオリンソナタ2番・3番のピアノパートも思い出されます。
January 21, 2009
コメント(1)
-
メンデルスゾーン音楽祭2009 の詳細をあつめてみる。
2年前のこのころ、ちがう作曲家で同じようなことをしていた気もしますが・・・。2009年はメンデルスゾーン生誕200年作曲家でもありますが、それ以外の功績もたくさんあるとおもっています。・100年以上埋もれていたバッハのマタイ受難曲を指揮した。・シューマンにショパンを紹介した。・シューマンが発見したシューベルトの「ザ・グレイト」を初演した。など。気になる音楽祭も含めて、関連のサイトを集めてみました。メンデルスゾーン音楽祭2009http://www.gewandhaus.de/gwh.site,postext,mendelssohn-festtage.html 音楽祭とてもいいプログラム、ラベック姉妹、ポリーニ、エマーソン弦楽四重奏団、ボザールトリオほか・・・。メンデルスゾーン財団http://www.mendelssohn-stiftung.de/ライプツィヒ市 http://www.leipzig.de/int/en/フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ基金 日本支部http://mendelssohn.jp/(この案内は、このあいだ立教大学に行ったときにありました。 名誉会長:クルト・マズア(指揮者)、日本支部理事長は、マズア夫人(日本人) 日本支部名誉理事長は、聖路加国際病院の日野原理事長、見て楽しむだけになるかもしれませんが、少し悩むことにします。ライプチヒ、バッハイヤーといわれた2000年の秋に1度だけ訪れたことあります。ザルツブルグでホテルでチェックアウトするとき、ホテルのお姉さんの長電話のおかげで、予定の電車に乗り遅れ、そのおかげで、ミュンヘンで飛行機に乗り遅れ、ペナルティをはらって、5時間空港で時間をつぶして、虎狩りになるのを覚悟で空港のヘアサロンで時間つぶしたこともありました。BGM:ファニー・メンデルスゾーン=ヘンゼル メロディ ロ長調op.5-4 ピアノ:仲道郁代 この作曲家の作品をいれたCDをはじめて聴いたのはこのCD. 姉のファニーのほうが才能があったという人がいて、隠れた作品がもっとあるのかもしれません。 CDには2000.1.15でサインの日付。 この日の朝、テレビで仲道さんが厳格な変奏曲を弾いていて、これ聴きたいとおもって、 探したら、その日の午後、三鷹の風のホールで同じプログラムがあり、 気がつけばホールにも足を運んだということで、8年前ですがよく覚えています。
January 20, 2009
コメント(0)
-
「静かなリーダーシップ」という本から、眠れぬままに。
静かなリーダーシップ・・・バダラッコという経営学の著書ですが、気になっています。英語では、Leading QuietlyAn Unorthodox Guide to Doing the Right Thing書評もたくさん出ているくらいです。http://www.silver.or.jp/tanshin/business/b031030.htmlhttp://www.shoeisha.com/book/hp/harvard/leader.asphttp://www.amazon.co.jp/review/product/479810261X「忍耐強くて慎重で、段階を経て行動する人、 犠牲を出さずに、自分の組織、周りの人々、自分自身にとって正しいと思われることを、 目立たずに実践している人」 のことを言うそうです。無意識のうちに自分もやっていそうなことがあるかもしれません。ゆっくりでいいので、深く読んでみたくなりました。●カリスマのあるものすごいヒーローに対して、さしていることばなのかもしれません。大声は出さなくても…という感じで。仕事のことはおいておいて、趣味のピアノの話に限定してみれば・・・。WEB上で、いろいろな相談ごとがたとえあったとしても、正面切ってああだこうだということなく、個別に聴かれたら答えたり、さりげなく励ましたり、ちょっと距離を置いてみたり。逆に、自分がちょっと相談めいたことや困ったことを書いた場合も、そういう気配りのあるかたのコメントは身にしみてうれしく感じること、いままでたくさんありましたので。きっとこういう風にしてみればいいのかとか、共感できるスタンスにたてるのはどんなときなのだろうかと、少し読んでいるだけですが、いろいろ感じました。●大きな音でバリバリピアノを弾かれるあとに、さらっと、素直な音で、静かに、歌うように流れるように弾く感じにもなんだか似ている感じもしないわけではありません。2ヶ月後のピアノの発表会、ラフマニノフの音の絵のあとの順番であっても、自分は自分のピアノの音をさらっと追及することにしよう・・・aditato で弾いた数小節あと、tranquilloの音にさっと変われるような音が出せるか時間が許す限り研究してみよう・・・。aditato:揺れた・興奮した・せきこんだ⇔tranquillo:静かな・安らかな・心が平安なBGM:メンデルスゾーン ピアノ・アジタート(眠れぬままに) op.19-5 この曲はとてもむずかしい。適当に弾いていたらぜんぜんつまらない曲。 無言歌はことばのない歌。 そのメロディラインを出せるようになるにはそうとう練習しないと。 きらきらした音もはらはらした音も出せるようになりたいです。 2か月かかりっきりで、どこまでできるかわかりませんが、 メンデルスゾーンの傑作のひとつとおもって表現したいです。
January 19, 2009
コメント(2)
-

「ベルリン・フィル 最高のハーモニーを求めて」 レイトショー
夕方見た美術展もそうでしたが、チケットをもったまま期限ぎりぎりのものがもうひとつありました。-1/23まで-21:00の1日1回上映のレイトショー-渋谷へ行かないと見れない。年末年始にその気になればというものもありましたが、ぜんぜんその気になれず、生のクラシックライブを聴いたあとには、ますますその気になれず、今日だったらとおもい、渋谷Bunkamura近くの映画館へ行きました。100人弱しか入らないところに、日曜日の夜遅く、終了間際の映画に何人見に来るのだろうとおもっていましたが、12-3人は、一緒に映画見ることができました。●2005年の来日公演、そういえば東京2公演だけで、なんて中途半端なのだろうとおもった年がありました。実はこのときのアジア・ツアーがこの映画であったようです。北京→ソウル→上海→香港→台北→東京2公演して1日移動日+リハ、これの繰り返しの強行軍、このなかでのベルリンフィル団員の様子、同時に試行期間として入団した団員の様子も。超一流どころのメンバーも、メンタルな面での調整のたいへんなこと、それと本番に向かって怖くなるときもあるとか、ヒューマニズム的な要素も興味深かったです。バイオリン16人、ひとりとして目立った音は出せず一糸乱れぬアンサンブルを聴かせること、孤独ななか、過酷なツアーを通じて睡眠時間3時間程度と疲れて行く様子がありました、香港での1日の休みの日とかで、みんな違うことに没頭し、だんだんコンサートの仕上がりがよくなっていく様子はなかなかのものでした。サイモン・ラトルという指揮者であるから、こういう企画もなりたつのでしょう。120回演奏すれば、自然に暗譜ができると、ベルリンフィルの団員がインタビューでいわれたこと、説得力を感じました。日本人のベルリンフィルメンバーとして、ヴァイオリンのコンサートマスター安永徹さん、ヴィオラ奏者の清水直子さんも出られていました。創立125年を超えたベルリンフィル、、しばらくライブもごぶさたですが、映画のスクリーンで、ベートーヴェンの第3「英雄」、リヒャルト・シュトラウス「英雄の生涯」を聴けてよかったです。オーケストラにふさわしい曲目も粋な演習だと思って聴いていました。映像のなかで、いろんな楽団メンバーが語ることばが気になったので、プログラム買ってかえりました。書かれているなかで、いちばん印象に残った言葉。ヴィルフリート・シュトレーレ(ヴィオラ)「もし"満足”という名の島に住んだら、もう成長は望めない」
January 18, 2009
コメント(4)
-
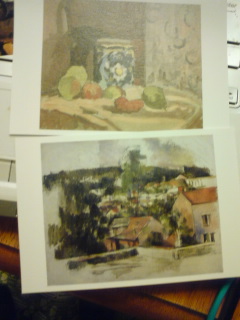
「セザンヌ主義」展/横浜美術館
横浜みなとみないへ行くときは音楽を聴くか絵画を観るかのどちらか。展示会や研修やらで来たことはあっても過去のはなしのよう。ピカソが父と呼ぶほど尊敬していた絵画がセザンヌ。「私にとっては、セザンヌこそが唯一かけがえのない先生である!」とまで、ピカソがセザンヌの絵画を研究してきたことを伝えた筆録(1943年)が残っているのだそうです。セザンヌ主義(セサニスム)と呼ばれ影響を受けた画家をふくめた展覧会でした。人物画(Figures)風景画(Landscapes)静物画(Still Lifes)3つのカテゴリーからセザンヌの作品、影響を受けた作品を展示していました。明治時代の終わりごろから、日本でもいち早く紹介され、そのころの日本人画家の作品がたくさん紹介されていました。風景画の淡いグリーンと赤茶色の家、静物画のリンゴなどの果物。本物をたくさん観れて堪能しました。雰囲気だけでも・・・。(ポストカード)セザンヌ主義展http://www.ntv.co.jp/cezanne/セザンヌ展ブログhttp://www.ntv.co.jp/cezanne/blog/index.htmlなお、横浜での開催は1/25までで、その後、北海道立近代美術館で、2/7-4/12までです。
January 18, 2009
コメント(3)
-
弦の響き Part2 /雑司ヶ谷音楽堂
1/12にも伺いましたが、後日、まだこれの続きがあるということを知りました。この日もチェロの発表会とコンサートのゲネプロのようなプログラム。途中からですが、以下が聴いたプログラムコダーイ 二重奏曲 (ヴァイオリンとチェロ)ゴルターマン 二重奏曲 (チェロとコントラバス)ロッシーニ 二重奏曲(チェロとコントラバス)ハイドン チェロ協奏曲第2番 第1楽章(チェロと弦楽合奏)モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」第1楽章(ヴァイオリンと弦楽合奏)ブラームス ピアノ四重奏曲第1番演奏されているのは、東京フィルハーモニー交響楽団の首席奏者を中心としたメンバー。それぞれに目的もあり、このあと控える大きな本番がありということですが、雑司ヶ谷音楽堂の2Fの最前列正面で、最高のひとときを堪能しました。最後のブラームスの曲でのビオラ奏者のプログラムは、その後控える大きな本番では、ピアノがチョンミュンフンに変わるとか。大きさの意味をあらためて感じました。弦の響き、音の響き、音楽に対する純粋な思いも伝わってきました。ヴァイオリン協奏曲、チェロ協奏曲のバックが、弦楽四重奏とコントラバスというもっともシンプルな編成でしたが迫力ありました。このホールの響きますます気にいってしまいました。●その後の大きな本番といわれていたもの・・・こちらで案内させていただきます。東京フィルハーモニー交響楽団http://www.tpo.or.jp/japanese/index.html東京フィル、2月の定期演奏会 第766回サントリー定期シリーズ 2/27 http://www.tpo.or.jp/japanese/concert/suntory2008.html#766金木博幸チェロリサイタル ヴァルト室内アンサンブル 4/12津田ホールhttp://www.plaza18.com/yoyogi-cmv.html●最近、聴きに行くコンサートの内容が少しずつ変わってきていることに、自分自身でも気づいています。特に意識してるわけではないのですが、客観的にみていたら面白いことになっているかもしれません。アンサンブルは多くなりました。ピアノ弾いていても音の響きを意識するようになって少しでもよくなればうれしいです。
January 17, 2009
コメント(0)
-

肉団子定食Part.9 in西新宿十二社
今日も仕事で西新宿にいました。夕方試験を受けたりもしました。四者択一の問題、作成したのはたぶんアメリカ人、試験の判定は答案用紙をそのままマレーシアに送られるとか。インターナショナルな感じ。問題の作り方が、日本人とアメリカ人では微妙にちがうらしい、それを知ることができて袋小路に入らずにすんだのかもしれません。日本人の四者択一は、どんなにひっかけ問題であっても、1つは〇で、残りの3つは×すなわち、誤り箇所があり消し材料があるもの。でもインターナショナルでは、そういうものがあるが、一番妥当なものを選択する感じ。◎〇△×と馬券みたいになるときもあり、出題者の意図を読み選択しないといけないようです。みんな正しいではないかと腹をたててはいけない。そういうことも知り鍛えられました。●西新宿にせっかく来たので、歩いて行けるところで、ひらめいたお店へ、仕事帰りにふらりと立ち寄りました。夕方6時と早すぎて準備中だったのかもしれませんが、白龍館というお店でご飯いただきました。http://www.hakuryukan.jp/(お店の前のライトアップ)モーツァルトの魔笛をモチーフにしたお店、3年前の冬の寒い日にはじめて伺ってからというもの、不思議なことがつぎつぎと起き、私にとっては縁結びの神様のようにも思ったりもしています。お店の方と私しかいないなか、オーダー待っているあいだピアノでも・・・ということになり、突然弾ける曲などそうそうないのですが、仕事帰りなので楽譜もない状態でしたが、最近よく人前で弾いていたを覚えている範囲で弾かせていただきました。調律したばかりのベーゼンドルファーのピアノで、自分にはもったいないようなお話でした。気ごころ知れた方に聴いていただくと安心するのか、楽しい時間でした。シューベルトの即興曲3番は気にいってもらえたようで、それもうれしかったです。アマチュアピアノの会の人がここで弾き会をしているのは、共通の知り合いは多数??、あの人はどうしているとかこうしているとかという話題にもなり、ますますお店も活況になってきていることも含めてよかったと思いました。藤子A不二男さんの漫画でかつてのお店のことを見せてくださったこともあって、そういえば、お店のマスターのお母さんが「オバケのQ太郎」のモデルだったとか、さっき弾いていたピアノには安川加寿子先生とフィッシャーディースカウのサインがあると教えていただいたことや、かつての楽しい出来事も含めて思い出しました。トマトたんめんは頼まず、いつものようにメニューに載っていない、肉だんご定食をいただきました。ときどきこの味を思い出したくなり、召し上がれてやはり堪能しました。●お店では、19:30-から、ポピュラーピアノを中心とした第1ステージが始まりました。といってもシューベルトのアベマリアあり、ヴィヴィアルディの冬ありで、やわらかな音の響きに堪能しました。このピアノは、弾く人によって特にいろんな音がして、むずかしい部類に入るとおもいますが、暖かい音をたくさん聴けてうれしかったです。●お店の方との共通の知り合いのピアニストのちらしをいただきました。わたしもどこかでいただいたかもしれないのですが、こちらで紹介させていただきます。松本あすか ピアノリサイタル 2月13日 グローリア・チャペルキリスト品川教会http://www.j-two.co.jp/asuka/バッハ=ブラームス編 シャコンヌ二短調(左手のための)リスト 伝説第2番 波の上を歩くパオラの聖フランチェスコラヴェル 夜のガスパール 第3番 スカルボヘンデル/松本あすか編 水上の音楽 ほか。以前このお店で聴かせていただいたのですが、メジャーになりすぎて、キャパが小さすぎるらしいです。以前、間近でカプースチンをはじめて聞かせていただいたのがこのお店。 BGM; プッチーニ オペラ:トゥーランドット (NHK教育テレビ) これから第2幕、ぴんぽんぱん の3人が登場します!! 見いってしまいそうです。
January 16, 2009
コメント(2)
-

メンデルスゾーン オルガンコンサート/立教チャペル
http://www.rikkyo.ac.jp/events/2009/01/3306/今日は仕事で西新宿にいたのですが、西池袋にある立教大学へ大急ぎで向かいました。メンデルスゾーン2009と、何気なグーグルで検索していたときに見つけたコンサート、大学のチャペルで、メンデルスゾーンのオルガン・ソナタを聴くという、ちょっと変わったレクチャーコンサートに伺いました。立教教会音楽研究所というところの主催、立教大学異文化コミュニケーション学部准教授のメンデルスゾーンの音楽背景の説明と、立教学院のオルがニストによるコンサートでした。オルガン・ソナタ第3番 op.65-3、第5番 op.65-5、第1番 op.65-1、オルガン演奏の前後にすてきな写真やメンデルスゾーンにまつわるお話、とても楽しめました。今年のドイツは10年ぶりの寒波で寒いという近況もありましたが、ライプチヒの写真、映像も紹介ありました。うれしかったお話は、1937年にナチスによって破壊されたメンデルスゾーンの銅像が去年10月、レプリカで復活し、バッハゆかりの聖トーマス協会の付近にあるとのこと。ドイツ人から見たメンデルスゾーンは、ヴァイオリン協奏曲や無言歌集のイメージよりもオルガン奏者として教会音楽の作曲家としてのものが大きいということ、印象に残りました。音楽そのものに少し物足りなさを感じるというよく指摘がある点については、静かにゆっくり終わることで、余韻を愉しむ大人の音楽だと評していて、共感しました。オルガン・ソナタは、それぞれに創作コラール(ドイツ語の讃美歌)が中にはいっているのですが、その題材となっている賛美歌を、それぞれに紹介し、起立してみんなで合唱しました。(慣れた方が多く、また聴いていて綺麗で、ハイセンス聴衆の方にすこしびっくりしました。)オルガン・ソナタについての楽曲構成についてもいろいろ説明ありましたが、天才的にさらっと作曲はしているものの、楽章を入れ替えたり、改作したりと、直筆譜には試行錯誤のあとが見られているということを教わりました。メンデルスゾーンが書いた水彩画(ライプチヒの風景)、オルガンソナタ5番の直筆譜。絵も楽譜も、ものすごく丁寧なタッチです。 きょう紹介あった資料その他から。気にいってしまいました。BGM:メンデルスゾーン 八重奏曲 変ホ長調 op.20/六重奏曲 ニ長調 op.110 ウィーン八重奏団 ヴァルター・バンホーファー(ピアノ)・・・op.110のみ ピアノトリオは、専門でやられている方が、メントリ・・・とかよくいわれるので、 聴いたことがあるのですが、この曲はCDでしか知りません。 ことしライブで聴くチャンスがあればうれしいです。 八重奏曲 1825年、メンデルスゾーン16歳のときの作品。 メンデルスゾーンのお父さんはおかかえのオーケストラを用意してくれたり、 他の作曲家にくらべれば恵まれ過ぎている時代のものです。 op.20・・・、op.19は無言歌集の第1巻なので、気になってしまいます。
January 15, 2009
コメント(200)
-

庄司紗矢香ヴァイオリン・リサイタル/サントリーホール
今年はじめてサントリーホールへ行きました。溜池山王の駅から久々に走りました。13番出口はやはり遠いところにあります。開演2分前についてほっとしました。ふらっと、足が勝手にうごいてしまった、気がつけば来てしまいましたという感じかもしれません。 テレビでもよく見かけますし、ラ・フォル・ジュルネ音楽祭とか短いプログラムでヴァイオリン聴いたりしていますが、リサイタルは久しぶりのような気がしました。ブログで過去に行ったリサイタルを調べていたら、2005年11月ですから。ちょっと地味目のプログラム、来日中のヴァイオリニスト、ヒラリー・ハーンと東京公演のコンサートスケジュールがまともにバッティングしているので、どんなものだろうかともおもいましたが、本当に彼女のヴァイオリンを聴きたいというお客様でいっぱいでした。●庄司紗矢香ヴァイオリン・リサイタル (ピアノ:イタマール・ゴラン)プログラム: シューベルト ヴァイオリン・ソナティナ 第3番 ト短調 Op.137-3 D.408ブロッホ ヴァイオリン・ソナタ第1番**アヴナー・ドルマン ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番(2008)ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ 第7番 ハ短調 Op.30-2(アンコール)http://www.suntory.co.jp/suntoryhall/perform/encore.shtmlチャイコフスキー:憂鬱なワルツ、クライスラー:ウィーン小行進曲エルガー:愛の挨拶クライスラー:ウィーン奇想曲ショスタコーヴィッチ 前奏曲Op.34-17ドイツの古典ものをはさみ、近現代の曲をはさむというめずらしいプログラム、またまた知らない作曲家が並びました。ドルマンの作品は、庄司紗矢香さんの委嘱による作品、庄司紗矢香さんへの献呈。演奏がおわったあと、作曲家が舞台へ上がり、ちょっと感動的なシーンでした。第1楽章、ヴァイオリンとピアノは2人の恋人、第2楽章、ヴァイオリンとピアノはライバル、そんなモチーフでの対比された曲でした。 いちばん感動したのは、ベートーヴェンのソナタ。7番のソナタを大きなホールで聴いたのはムターのコンサート以来でしたが、圧巻でした。c-mollのべートーヴェンならではの激しいヴァイオリンとピアノのかけあいですが、2楽章、Es-Durにかわりやわらかい包み込むような音色がとりわけ印象的でした。アダージョ・カンタービレそのものでした。この曲は、ハイリゲンシュタットの遺書が書かれた1802年の作品、ピアノソナタのop.31は、16番、17番「テンペスト」、18番のあたりと同時期。しっかりした形式のなか苦悩もありますがユーモアもある曲そのものにも感動しました。最近、ピアノパートのピアニストもやたら気になりまして、リトアニア出身のアンサンブル・ピアニストの軽いタッチでの伴奏もときおり、重い響きのフォルテの音がでてきたり、堪能しました。アンコールは、舞台で何を弾くのか決めている様子が微笑ましかったです。一転して、名曲アルバムになり、華やいだ雰囲気のもと、たくさん演奏聴けました。このヴァイオリニストのコンサートは一生通い続けるような気がします。楽しそうに音楽を奏でているのをみると元気になるのです。http://www.sayaka-shoji.com/index.html(過去ログ)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200805050000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200511290001/
January 14, 2009
コメント(2)
-
Made in the EU
昨日聴いていたチェロの演奏が今日は頭のなかずっとぐるぐる回っていました。ベートーヴェンのチェロソナタ3番は、最後に聴いた曲ですが、頭のなかで家にあるCDのなかにあるロストロボーヴィッチ(チェロ)・リヒテル(ピアノ)というのとマイスキー(チェロ)・アルゲリッチ(ピアノ)というのが交互に回っていた感じでした。それは帰りの地下鉄のなかでの出来事。こういうのがあるから、屋外ではCDを聴かず、アップル社のいい製品があっても知らないで通しているのかもしれません。部屋にもどって聴こうかとおもったら整理が悪いためもあって、また今度ということにしました。そのかわりというわけではありませんが、年末に買ってそのままにしていたものを見つけてそれを聴いてみることにしました。BGM: ベートーヴェン ピアノソナタ op.26,14,28(12番・9番・10番・15番) ピアノ:マレイ・ペライア http://murrayperahia.com/ なんといい組み合わせなこととおもって、見とれてしまいました。 12番・6番・31番・13番という順番ではいっているアニー・フィッシャーのCDは、 かつて1年中朝起きるときに聴いていたこともありますが、それと同じくらいな気分。 ある方にベートーヴェンの好きなソナタと聴くこと自体が邪道だといわれたことも ありますが、月光ソナタとか熱情とかテンペストでイメージ固めているかたに、 いろいろ勧めてしまったこともあります。 ソナタといいながら、ひとつもソナタ形式のない12番、1楽章の変奏曲はときどき聴きたくなります。葬送行進曲の3楽章のあと、はじめて4楽章を聴いたとき、しょうじょうじのたぬきばやしの童謡はこの曲のぱくりかとおもったりもしました。 9番のソナタは、全曲順番に聴いていた時、悲愴のあとだったからか、なんとほのぼのとした曲だろうと思いました。中間部のカンタービレな箇所が好きだったりします。3分少しの2楽章・3楽章、よくできた曲だなあと、たまに聴くと感動してしまいます。3楽章とおしても15分まで、さりげなく弾けるといいだろうなあと思っています。10番のソナタは、1楽章は、夫婦のかけあいのようだと、どこかに書いてあった記憶があり、そういう気分になれるときにはいいかもしれません。以前、音大付属の小学校高学年の可愛らしい演奏にぐらっときたことあります。●CDには、Made in the EU の文字が・・・。CDをつくるメーカーにしてみれば、ヨーロッパはひとつという意識のあらわれなのでしょうか。 こういうのを意識してみたのがはじめてだったので、はっとしてしまいました。それにしても、通貨がユーロになる前を多少でも知っていてよかったのかなあと、ふと思いました。ドビュッシーの20フランも、クララ・シューマンの100マルクも、ゴッホのひまわりでいっぱいの10ギルダーも現地で見たときは感動ものだったし。1万円札を両替して、16万リラくらいになり、お札が何倍にもなってよろこんでいたら、1万リラほど少なく、まったく、したたかなイタリア人にやられてしまったこともありますが・・・。いつの時代がいいとかわるいとか、あまり考えないで、平和な時代であれば、そのときそのときがいちばんいいと思えるようになりたいです。
January 13, 2009
コメント(0)
-
「弦の響き」はすばらしい! /雑司ヶ谷音楽堂
今日はたくさん音楽を聴ける日と楽しみにしていました。ピアノというより、弦楽器それも人の声に近いといわれるチェロが中心。年末にピアノ仲間から案内いただきました。12日空いてますか?といわれて、この日だけ空いているので行きますとものすごい夜遅くに答えた記憶もはっきりしています。そのあと日頃からお世話になっている人がピアノ弾くということも知りました。人は人を呼ぶ・・・というのは、こういうことをいうのだろうと、何と楽しいことだと思いました。人徳のある方にあやかりたいと思いました。久々に副都心線に乗り、池袋からひとつめの駅で降りましたが、ホールについたときは休憩時間中。出演者に応援しますといって、座る場所を確保したり紹介してくださった方にまず挨拶しました。このあと、トイレへ行く扉をあけたときのこと、なぜにそこにおられるのですかと、マンガのような場所で、想定外の方とお話できたのは、神のお告げのような気もしました。このコンサートとはまったく関係のない話からはじまるからおもしろいです。なんでここでべートーヴェンの後期ソナタのはなしに、きのうのテレビのフランス人のピアニストのはなしになるのだろうと・・・。なにはともあれ、同じ場を共有できてよかったです。●チェロの作曲家は知らない人も多数、教則本でだれでも弾く曲ですとか紹介もありましたが、ピアノが趣味の私にとっては縁の遠い作曲家もいました。小学生のまっすぐな演奏には感動しました。現役音大生、音大卒業後演奏活動している方、一般の趣味の方、ピアノパートの発表のためにチェリストが演奏するプログラム、その他もりだくさん、響きのいいホールで感動しきりでした。<弦の響き/聴いた演奏プログラム>ブレハル:チェロ二重奏曲第7番・第8番・第16番・第20番、ミシェック:コントラバス・ソナタ第2番第1-3楽章、スメタナ:弦楽四重奏曲「我が生涯」第1・2・3・楽章、ブラームス:チェロソナタ第1番第1楽章、マルチェロ:チェロソナタ第2番第1・2楽章、ゴルダーマン:チェロ協奏曲第4番第1楽章、ボッテジーニ:エレジー/タランテラ、メンデルスゾーン:チェロソナタ第2番第1楽章、ホフマイスター:ヴィオラ協奏曲第1楽章、ドビュッシー チェロソナタ、ドボルザーク チェロ協奏曲、シューマン:チェロ協奏曲、ベートーヴェン チェロソナタ3番第1楽章これだけのものを聴かせていただけることができ、ただただ感謝です。メンデルスゾーンのチェロソナタ、シューマンのチェロ協奏曲、ベートーヴェンのチェロソナタは、自宅のCDでもよく聴きますが、それ以外の曲もかぶりつきの席で、ピアノパートの方もチェロの迫力もわかる席で堪能できました。主催者は、東京フィルの首席チェリスト、Kitaraホールカルテットのチェロ奏者、曲の紹介は、とても興味深いものでもありました。備忘録がわりに・・・。スメタナの「我が生涯」の第3楽章は人生の最期に聴きたくなる曲、有名どころのシューベルトの「死と乙女」ドボルザーク「アメリカ」と並んで演奏したくなる曲。シューマンのチェロソナタはポジショニングがとても難解な曲で、これに匹敵する難曲は、ハイドンのチェロソナタ、ベートーヴェンの二重協奏曲(?)、シューベルトのアルペジオーネソナタなど。(演奏を見ていて、ピアノのオクターブやアルペジオをチェロで演奏するのはただごとではないと感じました。)●今日の日経朝刊のコラムに成人の日を祝して「つまるところ人生とは一冊の本、一人の女性、一人の親友、一本の酒、一つの言葉(詩)を求める旅・・・」と、 紹介されていますが、一冊や一人が複数になるかもしれませんが、そういうことをたくさん感じる日でもありました。雑司ヶ谷音楽堂http://homepage2.nifty.com/zoshigayaongakudo/響きのいいこのホールでいつかピアノが弾けるのでしょうか・・・。楽しみです。BGM: メンデルスゾーン チェロソナタ第2番 op.58 チェロ:ミッシャ・マイスキー ピアノ:セルジオ・ティエンポ ピアノパートのところがやたらと気になる曲になりました。 この日の演奏中も、ずっとピアノパートの手を見ていました。 華麗に、チェロがなっているときは控えめに。 というわけで、CDも聴きたくなりました。明るくていい気分になれそうなこのソナタ、 ちょっと気に入ってしまいました。
January 12, 2009
コメント(2)
-
男のコンサート~音と背中で~ Vol.7 参加しました。
A Concert of the men, by the men, for the men.こういうこともちらしに書いてあります。東京都文京区、有楽町線江戸川橋からすぐ、地蔵通り商店街のなかの、ピアノ・パッサージュというところへ行きました。http://www.pianopassage.jp/ここの場所は、スタジオを借りて、ピアノの弾きあい会をするときに伺うこともあります。ここ2-3週間でいろんなところでピアノ弾きましたがそういう方々とこっそり・・・ということもありました。こちらのお店の方は、なんとなくそういうことをお見受けされているみたいで、受付は顔パス状態でした。歌舞伎役者ではありませんが、男の人限定、そういう強いこだわりのなか、さまざまなパフォーマンスを拝見しました。パパと小学生の親子連弾、男子大学生ピアノサークル双子の演奏、おみごとでした。小学生の男の子の演奏をいくつか聴きました。フォーレのドリー組曲の子守歌(連弾プリモ)、ヘンデルのサラバンド、モーツァルトのピアノ協奏曲23番2楽章のソロパート、この時期にスタインウェイの状態のいいピアノで演奏できるのは、恵まれています。自分の意志でてているかどうかは定かではないものの、まわりのサポートそのものに尊敬の念でいっぱいでした。 12月中旬からシューベルト+メンデルスゾーンの組み合わせでいろいろ弾いてきましたが、たぶんそういうことをするのはここで最後。練習してそれほど日がたっていない曲と半年以上弾いた曲を組み合わせることには、苦心することが多いことにも気付きましたが、これは貴重な経験でした。どこでも同じプログラムにすることなく、持ち時間にあわせて少しずつ変化させることで、たとえ同じ人が聴きに来られることがあっても・・・とならないように、自分なりにも考えました。今回は1/4と同じ聴き手が3人、本を見たり、弾きなおしたり、いろいろありましたが、ここのスタインウェイは正直な音でとても弾きやすいです。そういう場所で弾けてよかったです。いろんな方にも感想うかがえましたが、小学生ピアニストのお母さん方と、妙に会話がはずみました。私自身の今に至っているいきさつや小学校のときにどんな曲をやっていたんかとか、どれくらい練習していたのかとか、やはり興味あるのは当然かと思いました。たいていの方はピアノは弾いていたかたのようで、あまり小中学生が選ばない無言歌集の曲目や、即興曲もop.90-2,4、op.142-3は弾いたことがありますが・・・という会話になったりもしました。この会に参加したのは、Vol,2の2年前の5月以来ですので、1年半以上たっていましたが、こちらのピアノサロンが総力を結集させて、つづけているなか進化していることを肌で感じました。出ていないときネットで出演者のプログラムを見ていたりもしましたが、それだけではわからないこともたくさん。音楽をいかに楽しむかという本質をわかった方々が運営するとこうもすばらしいパーティになるのかと実感しました。いちばんびっくりしたのは、プログラムでクーラウのソナチネアルバムにある曲を弾かれた方。そのときはちょっとたどたどしかったので、忙しいなか練習されているのかなあ・・・とおもっていたのですが、2次会で宴たけなわになったころ、突然ビリー・ジョエルのピアノ弾き語りがはじまり、ニューヨークの思い出、オネスティ、素顔のままでを完璧な披露され、おいしいところをみんなもっていってしまった感じになったこと。弾き語りの曲を本プログラムにいれず、どこで弾けばいいかわかっている、本当の意味でのエンターテイナーだと思いました。すばらしかったです。BGM:メンデルスゾーン ロンド・カプリチオーソ op.14 厳格な変奏曲 op.54 ピアノ:マレイ・ペライア10年くらい前、NHKでも放送されましたが、彼のメンデルスゾーン無言歌集のコンサート、 いまだに印象に残っています。好きなピアニストのひとり。このCDのライナーノーツ、吉井亜彦さんのピアニストのセンスのよさについて、「大向こうを意識した派手なアクションで目立とうとする者が、必ずしも勝利者になるとは限らない。また、大声でしゃべっている者が、常に真実を語っているとも限らない。・・・・・・・・・・外観的な要素よりも内面的な要素が最終的には優勢になる「芸術」という創作活動の分野においてはなおさらのことである。・・・・・・・・目立ちたがりではなくても、ゆたかな内容であれば、いつかひとびとに認められるようになってもおかしくはないし、また、たとえ大声の持ち主ではなくても、しゃべるべき内容を持っていれば、いつかひとびとに認められるようになってもおかしくはない、と・・・・・・・。」たぶんこういう傾向のピアニストを自分は好んでいるのだろうと、とてもよく表現されているとおもって引用しました。ロンド・カプリチオーソ、メンデルスゾーン15歳の作品。いろいろ言う人はいるけど、やっぱり天才だと思っています。素直な作風が好きで、素直に弾けるようになりたいと思っています。素直な面がありますねと、私のことを先日語ってくださったことを思い出しながら模索してみたくなりました。
January 11, 2009
コメント(4)
-
高速バスのたびはピアノざんまい
高速バスに乗って、那須塩原の方面へ伺いました。途中の休憩を含めて、2時間半ほど。旅のお伴がいると、あっというまでした。長電話の延長のようでした。旅のお供があると、これはこれで、どちらもおいしかったです。関東の地で、北海道と京都の銘菓の交換、これはなかなかのものでした。ピアノの前の第1ラウンドのようでした。六花亭:ストロベリー・チョコレート(ホワイト)http://www.rokkatei.co.jp/meika_w.html祇園萩月(ぎおんしゅうげつ):ちょこあられhttp://www.syugetsu.com/SHOP/chokoa.html●邸宅のリビングにはザウターというピアノがあるのですが、いっぱいピアノを弾かせていただきました。練習モードもあれば、ふだんから弾いている曲もあれば、ここで弾くつもりで準備した曲もあれば、いろいろ。気兼ねなく弾くことができる場は本当にありがたいです。今後のための備忘録・・・(たくさん聴かせていただいた曲と弾かせていただいた曲をまぜて覚えている範囲で)モーツァルト ソナタK.310第2・3楽章、ドビュッシー 前奏曲2巻より「花火」、ブラームス 6つの小品op.118-1、2、シューマン幻想小曲集より「夢のもつれ」op.12-6、子供の情景より「トロイメライ」op.15-7、シューベルト即興曲Op.90-1,Op.90-3,ハンガリー風メロディ D817,メンデルスゾーン 無言歌集より、プレスト・アジタートop.53-3、ピアノ・アジタート(眠れぬままに)op.19-5、浮雲op.53-2、瞑想op.30-1、安らぎもなくop.30-2、ベニスのゴンドラの唄op.30-6、春の歌op.62-6、ショパン、24の前奏曲よりop.28-11、op.28-15、バッハ フーガの技法第1曲、リスト 巡礼の年1年「スイス」よりウィリアムテルのチャペル、巡礼の年2年「イタリア」より婚礼、ラフマニノフ 楽興の時op.16-3、op.16-4,プレリュードop.23-4、ディズニーのメドレー曲(2台ピアノ)、ピアソラ:ブエノスアイレスの夏(2台ピアノ)、弾いていて楽しくなるピアノは、2時間半とすこし、いれかわりたちかわり、楽しい空間の場にいれてありがたかったです。私は名曲アルバムに出てくるような小品ばかりを弾いていたような気がします。それから、近々のレッスンの練習をしていたのかもしれません。メンデルスゾーン生誕200年ということではありませんが、無言歌集をなんだかたくさん弾いていました。素直な旋律と、短調で始まる曲が気がつけば我慢できずに長調に転調しているような曲がいくつかあったり、シューベルト即興曲との共通点をあらたに発見したりもしました。人なりも知っていて熱心に聴いてくださる方がいること、どれほどありがたいかと改めて感じました。とても風が強いなか、真冬であることを実感しましたが、そのなかでの暖かい団らんであったことは忘れもいたしません。帰りのバスの中、また長電話のつづきのような会話が2時間半以上つづきました。そういえば、ベートーヴェンがなかったということで、もし弾いていただけるのなら・・・と、好き勝手にリクエストしようということになりました。現地にいた方へは、op.10-2(6番)、op.14-2(10番)バスのお伴の方へは、op.7(4番)、op.31-3(18番)有名どころをことごとくはずして、なんだかこんなことになりました。イメージはあわせているつもりなのですけど、この先どうなることやら・・・です。この3連休、ピアノは弾く弾く聴く・・・といった感じになりそうです。おかげさまで楽しくすごしています。みなさまありがとうございます。
January 10, 2009
コメント(200)
-
another sky ザルツブルク 山田五郎さん
何気なく日テレをつけていたら、いきなり、魔笛の序曲が、鳴って、おもわず、テレビを観入ってしまいました。そのあとは、ハフナーの交響曲4楽章、モーツァルトだけでBGMになって、番組を作られて行く。景色は、ザルツブルクの光景、モーツァルトの家、ゲトライトガッセ、モーツァルトが通ったカフェのトマセリ、ザッハートルテ、サウンドオブミュージックの舞台になったところ。30年近く前に旅をされた山田五郎さんは西洋美術を専攻されていたのだとわかり、あまりにもちがうルックスに驚きましたが、深いお話をうかがえるのはうれしいです。価値観に絶対はない・・・とナレーターがいうことば、旅をして実際を知ることの大切さ、あらためて感じました。●http://www.salzburgerfestspiele.at/ザルツブルク音楽祭2009のWEBサイトいつのまにか動画サイトになり、昔にくらべれば格段に充実しています。ストラビンスキーの音楽が聴けます。このサイト、パソコン買って間もないころから、毎年見ていて、指をくわえてみているだけのときもよくありました。http://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/serie/serieid/629/sid/84/ハイドンイヤーならではのプログラムもあります。http://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/serie/serieid/636/sid/84/今年のリサイタルのプログラム、 祝祭大劇場でのアーチスト。アルゲリッチ/ネルソン・フレイレキーシンソコロフランランポリーニ近日日本公演があるピアニストの演目と同じだったりするので、そういう観点でも観てしまいます。去年より、ソロの人は少ない。それから引退してしまったブレンデルの名前はやはりないのもさびしい。●パリにいるツアーコンダクターの方に、東京のほうが、マネジメントがしっかりしていて、はるかにコンサートが多いのがうらやましい・・・と、わざわざ、冬の寒いときに、オランジュリー美術館のモネの睡蓮を見に来たのですといった私にいってくださったことば。そうおもって、日本にいることもありがたいと思うことにします。去年のいまごろの、ブログも同じようなことをしていたかもしれません。
January 9, 2009
コメント(2)
-
昨日書いたアニバーサリーのことがe-bookになり・・・
昨日、このブログで、アニバーサリーイヤーの紹介をさせていただいたかとおもえば、今日は、とあるメーリングで、ぴあクラシックがebook化されましたと、案内いただきました。http://www.pia.co.jp/piaclassic/このページのPDFファイルを表示したら、どこから抜粋したかすぐわかります。 丸写しのネタは5ページ目あたり。便利な世の中になりました。●長年、音楽雑誌で、コンサートの寸評とか評論とかよませていただいていますが、年始の挨拶とかで、ブログにも書いておられることがわかりました。http://concertdiary.blog118.fc2.com/この方と、直近でお会いしたのは、11月20日のフランク・ブラレイのコンサートが始まる前、東京文化会館小ホールで。ピアニストのコンサートがバッティングしまくっていて、私が選んだのはこのコンサートでしたが・・・。http://concertdiary.blog118.fc2.com/blog-date-2008.11.20.htmlこういう風に聴かれたのかと、納得しました。いいものはいいとすかっと書かれるので、読後感がとてもよく、本は買わなくても立ち読みしていることも実は多いです。楽器は弾かれませが、放送局でクラシック音楽のディレクターを長年されていたこともあり、聴いている量が半端ではありません。昨日、このブログでモーツァルトイヤー没後200年のことを書かせていただきましたが、右も左もわからない状態でいったザルツブルグ音楽祭で、スペシャルな解説をしていただき、音楽の楽しみ方を教わりました。以前カラヤンのお墓参りにいったとき、ブログに写真のせたことありますが、写真をとってもらったりしました。祝祭大劇場の楽屋へどさくさまぎれにすり抜けて案内してくださり、日本人指揮者の晴れ舞台に紹介までしてくださったのは、その後多大な影響をうけました。17年前は、まだ解説の記事とかは、ごくごくわずかでしたが、だんだん紙面に登場する機会は増え、テレビにでも出られるようになり、いろんな雑誌評論で楽しむようになりました。●ぴあは、フリーペーパーになり、音楽評論家の本に書かれるはずのものが、ブログになり雑誌を買わなくても、立ち読みしなくても、分かる内容が増えてきました。いったいこの世はどうなっていくのでしょう。21世紀は本物の人しか残れない・・・ときびしいことを言われたこともありますが、なんだか実感するようになりました。でもお金を出して、コンサートを聴いて、たくさん感動したい、本物のアーチストに出会いたい。ますますそう思うのかもしれません。BGM: メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリン:ヒラリー・ハーン ヒュー・ウルフ指揮 オスロ・フィルハーモニー管弦楽団 コンサート行こうとおもっていたら、今回の来日はどうもいけそうにありません。 書かれている評論をみて、家でCDを聴いて楽しむことにします。
January 8, 2009
コメント(2)
-
2009年アニバーサリーイヤー作曲家・・・
会社で七草粥があったので季節感を感じました。おかげさまで元気です。帰省からもどってきた人のお土産をたくさんいただきました。広島のもみじまんじゅう、北海道の六花亭の雪やこんこというクッキー、徳島の冬みかん・・・、今週はまだなかば、週末はいつになったらと思っています。あまりに部屋がちらかっていたので、少し片付けをしていたら、クラシックぴあ 最新情報 2008/2009冬というフリーペーパーが出てきました。祝2009アニバーサリー音楽家 ということで、以下ほぼ丸写しです。生誕350年 ヘンリー・パーセル 1659-1695没後250年 ジョージ・フリデリック・ヘンデル 1685-1759生誕200年 フェリクス・メンデルスゾーン 1809-1847没後200年 ヨーゼフ・ハイドン 1732-1809没後150年 ルイ・シュポーア 1784-1859生誕100年 古関裕爾 1909-1989没後100年 イサーク・アルベニス 1860-1909没後100年 フランシスコ・タレガ 1852-1909没後 50年 ヴィラ・ロボス 1887-1959没後 10年 ホアキン・ロドリーゴ 1901-1999年末の深夜2時半から4時前までに催された山手線ゲーム(古今東西作曲家・・・)に出ていない作曲家がいる・・・とお勉強になりました。 まだまだ知らないことばかりです。ピアノ曲におおいに関係ある作曲家も多数、個性派ぞろいです。♪六甲おろしにさっそうと・・・の古関裕爾氏は、歌のコーナーになりそうですが、(書き手は笑いをとりたかったのでしょうか)ヘンデル・ハイドン・メンデルスゾーン・アルベニスと、興味のある作曲家ぞろいです。ここ最近のテーマは、メンデルスゾーン無言歌集なのですが、もう少し落ち着いたらいろいろ広げていきたいです。●こういうアニバーサリーなことに最初に興味をもったのが、1991年のモーツァルト没後200年ですが、1999年ショパン没後150年、2000年バッハ没後250年、2001年ヴェルディ没後100年、2006年モーツァルト生誕250年、2007年グリーグ没後100年と、何か意識したり、そのために旅をしたり、弾けもしない曲を練習しようとしたり、いろんなことをしてきたのかもしれません。●過去は過去として、これからしばらく先、ロマン派作曲家の生誕200年がしばらくつづくので、たぶんそういう作品を選んでいくことになるのでしょう。2010:ショパン・シューマン2011:リストほおっておくわけがないのですが、シューマンって、没年はモーツァルトとかぶり、生誕年はショパンとかぶり、地味だなあということになって、なにかかかわってみたいとも思います。いま気になる曲は、幻想小曲集op.12から「なぜに」「気まぐれ」「夜に」、アレグロop.8、ノベレッテンop.21からであれば8番、森の情景op.82、暁の歌op.133、オーボエやチェロの伴奏でop.70、op.73,op.94. ショパン、op.28の前奏曲でまだやっていない曲、エオリアンハープop.25-1はそれなりに弾けるようになりたいのとそのつぎのエチュードop.25-2。 長い曲はあまりいまはちょっと・・・という感じ。リストは、演奏会用練習曲と呼ばれているものは、弾いてみたいのですが、ドビュッシー弾いているときみたいにベートーヴェンやブラームスの音になってしまっては、笑われてしまうので、レジェロで軽く弾けるようになりたいものです。森のささやき、軽やかさ、こんなところは前々から興味あります。とはいうものの「なぜに」という感じで、「夜に」「気まぐれ」なことばかりかもしれません。3年先まで弾きたい曲がそれなりに並ぶのは、「気まぐれ」であってもおめでたいかもしれません。BGM: リスト コンソレーション3番・・・ これもすてきな演奏聴いたら弾きたくなりました。
January 7, 2009
コメント(10)
-
すぽるとにて馬術の話題、テクニックのことばについて
夜中のスポーツニュース、すぽると。この番組、おちゃらけではなく、まじめにスポーツ報道をしたいというものが根底にあるようで、好感をもって見ていることが多いです。ここしばらく、マイナーだといわれている特集をしていたようです。偶然ですが、今日は「馬術」の紹介。一般の人にはわかりにくいと言われているものを、よくまとめられていた感じがしました。馬場馬術、障害馬術の違い、常歩(なみあし)、速歩(はやあし)、駆歩(かけあし)、オリンピックでメダルをとった西中尉の話、パッサージュ、ペアッフェ、ハーフパス、フライングチェンジ、ピルーエット、馬場馬術で魅せる技と番組では言っていましたが、試合ででてくる演技科目の一つ、フィギュアスケートの3回転ジャンプの種類を例に、ニュアンスを伝えていました。「馬術」と「乗馬」のちがいは何か?この問いに対して、テクニックを用いて馬を動かすかどうかという端的な答えを北京オリンピックに出られた方が述べられていました。テクニックということばに、奥の深さを感じてしまいました。ただ動かすだけではなく、決められた扶助によって、高度な内容を馬に調教し演技し、オリンピックに出るクラスになると9年くらいかかると。馬術部員だった、私も、身近な人や、入部希望の後輩の人に、同じようなことを何度も何度も聴かれたことを思い出しました。また乗馬クラブでも試合があったりアルバイトへ行ったりしましたので、そういう方々ともお話することがありました。乗馬クラブで、馬に乗っている人も、単に乗っているだけの人と、試合に出て、技術を極めようとしている人といろいろだったような気がします。大学の体育会と微妙な価値観の違いに考えこむことも記憶しています。●話がかわって、趣味でピアノを習っていますといっても、人それぞれなのだろうと思うようになりました。乗馬と馬術という区別できることばがあるようでないようでという感じもします。押せばなるピアノですが、テクニックってなんでしょうという、小学生に説明しようとすればどうなんでしょうと。いい歳になり質問されることも多くなったので。1分間でドレミファソラシドのスケールがどの程度弾けるかとか、速く弾くことについては説明がしやすいのですが、スピードを競うだけがなにもテクニックではないとも感じています。馬術も競馬と勘違いされていわれて、面食らったことも多かったかもと。アダージョの曲を聴かせる演奏をするのに、音が少ない曲に、ものすごいテクニックが必要ではないのか、ここ数年思い知らされていたりしますので。そもそものピアノの奏法そのものもテクニックでしょうし、脱力して弾くのもそうでしょう。最近、何時間弾こうがそれほど疲れなくなってはきていますが、いろいろ時間がかかることなのだと強く思っています。三声の曲で内声部で、主旋律がpであれば、pppくらいで弾かないといけないので、これは相当なテクニックが要求されるといわれ、昨年後半やっていたシューベルトの即興曲op.90-3は、一定のリズムがずっとずっと続くこともあって、こんないいエチュードはないとも言われました。音大に通われている途中、モーツァルトのK310の2・3楽章が学校での試験になったと伺ったことがあります。1楽章はアマチュアの方でも弾くのですが、後半のこの楽章のほうがはるかに難しいといわれました。1楽章は比較的一定の曲調なのに対し、2楽章は、つぎからつぎへと曲調が変わっていく静かなカンタービレな曲、試験とか課題曲にしやすいくらいいろいろな課題満載だとか。オペラのアリアのように、ここはチェロのように、ここは木管楽器のようにと、音色を微妙に変えて弾くことはレッスンとかではやりましたが、試験とかそういう立場になると、本当に弾きにくい曲なのでしょうね。●何年か前、カラヤンが番組のインタビューで、オーケストラの指揮をするときに、馬術でいうキャリーではなく、ドライブだといったとき、力任せに馬を誘導して走らせるのではなく、自然に走らせたいように誘導していくのだという意味を、馬に乗っていたときに教官に指導してくださったこと同じだとおもってちょっと感動したことあります。多少なりともニュアンスがわかってよかったと思いました。BGM:モーツァルト ピアノソナタ第8番 K.310 ピアノ:アルフレッド・ブレンデル 官能的なピアノ曲を弾くピアノの会がありそうです。 2楽章は、そういうのに対応できそうな気がしました。 でも最近弾いていないので他の曲を考えます。 それよりも何が飛び出してくるのか、他の方の演目が楽しみです。
January 6, 2009
コメント(4)
-
京のおみくじ、江戸のおみくじ
毎年、西と東でお参りにいっています。おみくじを引くのも習慣になりつつあります。1月1日 平安神宮第22番 吉みな人の祈るこころもことわりに背かぬ道を神や受くらむ(人の希望、願望は果ての無いものであり、神様に祈る時も種々祈願するものだが、其れが誠という天の理(ことわり)、地の理、神様の御心に叶わねばお聞き届け頂けない。常に心を清く、行いを正しくすれば、神様のご加護が頂けるものである。)<願望(ねがいごと)>心正しく小人すれば叶う邪(よこしま)な願いは必ず破れる故、心せよ。●1月5日 成田山深川不動尊 (門前中町)http://www.fukagawafudou.gr.jp/index.htm桂華春将到雲天好進程貴人相遇處暗月再分明(暖かい春になって、空のついもおぼろにかすんできた。また新しい季節が始まるのだ)(高く雲がたなびいて、旅に出るのによい時だ。大きな希望を抱いて、ことを始めるのにもよい)(そうすればきっと、地位の高い人やよい師にめぐり合い、取り立てられることだろう。)(雲がなくなって月が明るく輝くように、あなたの前途も開けて、幸せになる)<将来の見通し>種をまき、苗を植えるように、新しい仕事をはじめるのがよい。信仰厚く自然の恵みに感謝すること。●門前中町の夕方、この駅の近くには、深川不動堂と富岡八幡宮の2つがあるのですが、かなり多くの人でいっぱいでした。深川不動さんは、成田山新勝寺の東京別院、徳川5代将軍綱吉の母桂昌院が、成田山の不動明王を江戸でも参拝したいというのがことの始まりといわれています。江東区で最も古い木造建造物、関東大震災、東京大空襲とかで、このあたりは被害が大きいところですが、ずっと残り続けたご本尊があるとのこと、いろいろな歴史を感じました。今日引いたおみくじは、待人・来ない。 とかあっさりかいてあったりして、最初は・・・とおもいましたが、よく読んでみると、いいこともずいぶん書いてあって、とても気に入ってしまいました。会社のメンバーと新年会→何年ぶりかのカラオケ♪お嫁サンバ♪天使のウインク♪アジアの純真♪あずさ2号こんな感じのレパートリーでした。場がもりあがったので、それはそれでよかったです。今日はもう23時半、ピアノはぜんぜん弾けませんでした。あしたはさっさと帰って練習しなければ・・・。
January 5, 2009
コメント(2)
-
Wien-Offline!2009
日頃から、いいピアノでいいホールで弾く機会があれば・・・と思っているのですが、ベーゼンドルファー・インペリアル、杉並公会堂小ホール、とても贅沢な空間を堪能いたしました。ここのホールとピアノは、アマチュアピアノコンクール1次予選の会場で知人が出場するのに応援にいったり、海外で留学中のピアニストが一時帰国してコンサートするので聴きに来てといわれて行った場所だったりでありまして、ちょっと恐れ多くもあったのですが、素直に弾いて素直に楽しむということになればと、エントリーしました。ピアノだけでなく、ヴァイオリンあり、チェロあり、ホルンあり、ソプラノもテノールもバリトンもありで、時間があっという間にたちとても楽しいものとなりました。古希を過ぎられた方、米寿を過ぎられた方が、いまだに演奏されている方がおられまして、ただただ尊敬するばかりで聴かせていただきました。趣味とともに豊かな人生を送られていることがたくさん伝わってきまして励みになりました。ピアノのほうは、自分が出演した部のバッハ、ベートーヴェン、ブラームスの重厚な演奏が印象に残りました。ハイドンの「雄牛のメヌエット」といま弾くと旬な曲まで聴かせていただき感動しました。その合間をぬったように弾かせていただいたシューベルトとメンデルスゾーンのプログラムは、ちょっとちがった感じでとらえられたのかもしれません。かなりピアノが弾けるとおもっているかたから、いいように言っていただけたのはとてもうれしかったです。(実際は緊張するし、まちがいだらけですし、まだまだだなあと思うことばかりでしたが)べーゼンのピアノぶっつけでさわりましたが、pやppであっても、だしたい音がいちばん後ろに座っている方に届くようにと試行錯誤していました。めったに経験できない場にいるので、主催者と聴き手の方にはただただ感謝するばかりです。ありがとうございました。メンデルスゾーン、この作曲家の作品集も弾いていて気分がいいので、自分とは相性がいいのかもしれません。少しずつ弾ける曲を増やしていきたいという思いが強くなりました。●2次会、こういう場があまり得意でないのですが、何人かお知り合いになれてよかったです。面識のない方であっても聴いてくださっているのだと、実感しました。ウィーンに数年住まれていた方のお話、私が旅行なんかで行くのとは大違いで、住まれた方なりの音楽事情とか身近に知っておられる内容をうかがえて何よりでした。長野県から、歌いに来てくださった方も、自分と共通する話題は松本のサイトウキネンフェスティバルくらいしかないかとおもえば、そこから、いろんな話に発展していき、その地に住まれている方ならではの貴重なお話をうかがうことができました。来週も、ある場所でピアノを弾く予定をしているのですが、そこのメンバーの方が何人かいたり、ちょっとびっくりでもありました。少しプログラムを変えて、地道に場数を踏み続けていこうと思いました。BGM:シューマン交響曲1番、ラフマニノフピアノ協奏曲1番、ブルックナー交響曲1番 N響アワーより、きょうは1番シリーズのようで、楽しんでいます。
January 4, 2009
コメント(7)
-
かえりみち
きょうは、スポーツ中継のテレビ三昧 箱根駅伝を見ているともうすぐ東京へ自分も戻るのかと、たすきを渡す中継地点を見ながら感じています。 結果も終わって見なければわからない、長旅のロードレースをみていつも思います。 アメリカンフットボール、ライスボール。 物言いのような最後のインターセプト、ちょっとひやひやして見ていました。自分の母校が優勝する瞬間はやはりうれしいです。励みになりました。 その後1時間ほどピアノの練習。あしたせっかくベーゼンドルファのピアノで弾く機会があるので、いい状態で弾きたいものです。 新幹線のホームは満員、この日の東京行きは12月中旬には朝から夜まで指定席は満席状態でしたから当然のような状態。 新大阪では9分遅れ、名古屋では7分遅れ、東京では、ほぼとりかえすでしょう。 N700型、のそみ44号はよく使うもので好きな時間帯、三河安城のあたりを通過し日常に戻りつつあります。
January 3, 2009
コメント(5)
-
おとしだまのお返し
おとしだまを姪にあげたらベートーベンのメモ帳をプレゼントしてもらいました。 空飛ぶベートーベンなかなか愉快です。 ピアノは習っていないのですがライブハウスでときどきドラムを叩いているらしく、小学生の低学年でそんな人あまりいないので楽しみにしています。 ● お正月にみたベルリンフィルのジルベスタコンサート、アメリカものシリーズ。キューバ序曲、サマータイム、パリのアメリカ人、最高のプログラムだったと思いました。サイモン・ラトルだから実現できるものかもしれません。 ウィーンフィルのニューイヤーコンサート、こちらはこちらで華やかでした。コミカルなバレンボイムの指揮は明るい気分になりました。ハイドンの交響曲45番告別の第4楽章、オーケストラが一人ずつ去っていくプログラム、ハイドンイヤーに大きな印象を与えた気がします。見事でした。美しき青きドナウとラデツキー行進曲も聴けて、自分自身も新たな年になったこと実感しました。 こんな感じでのんびりしています。
January 2, 2009
コメント(4)
-
初春
明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 寝正月にするつもりでしたが、初詣にも出かけました。 みぞれが降っているなか大阪市内の実家を出ましたが京都に着いた頃は晴れ渡ったり、そしてまた曇ったり、ぱらぱらしたり、色んな景色に出会えてよかったと思うことにします。 平安神宮への初詣。 広い境内を見るとほっとします。 20年以上も前になりますが馬に乗って初詣に出かけた場所がここ。テレビの初詣ニュースのネタを提供したこともあります。 平安神宮は平安京を開いた桓武天皇と慶応2年まで天皇だった孝明天皇の二人が祀られています。 794(なくよ)うぐいす平安京から1100年たった1894年(明治26年)に建立されていまに至っています。 ● チョコレート色の阪急電車で実家に帰る途中に書いています。 今年も元気で過ごして皆さまとお目にかかりたいと思っています。 皆さまのご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます。
January 1, 2009
コメント(16)
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
-
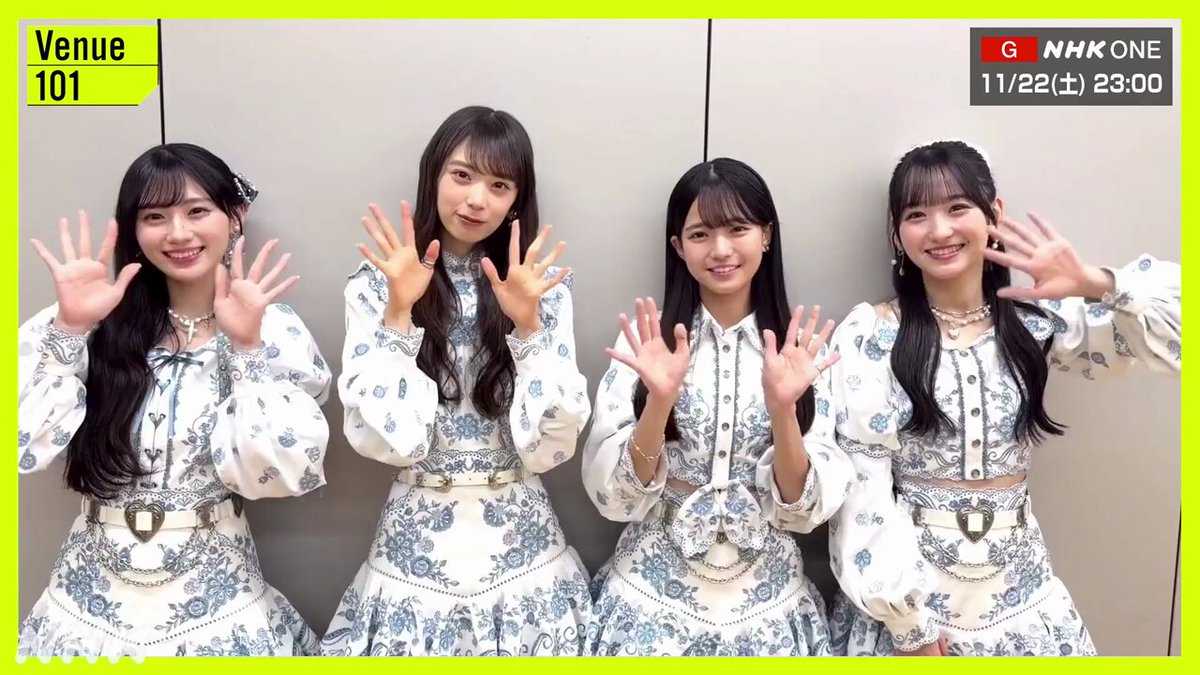
- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪本日『Venue 101』に出演…
- (2025-11-22 13:40:45)
-
-
-
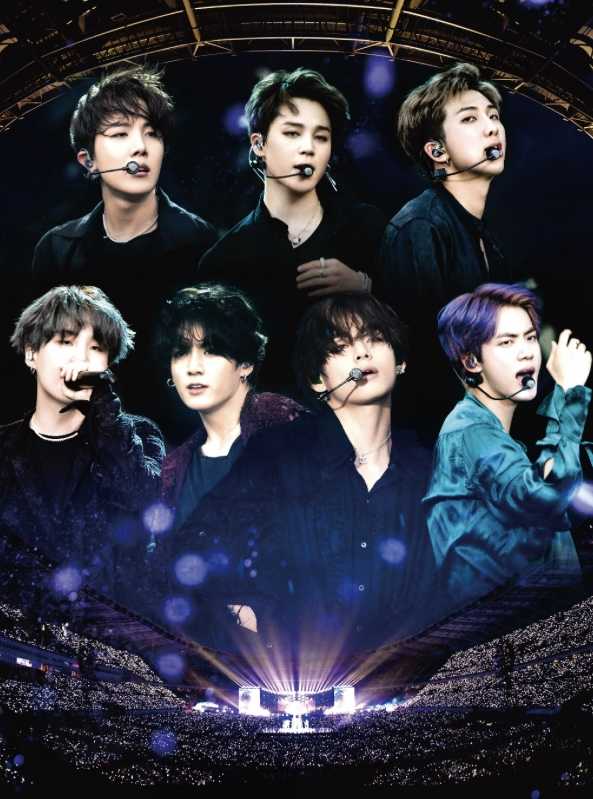
- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…
- (2025-11-21 18:37:01)
-
-
-
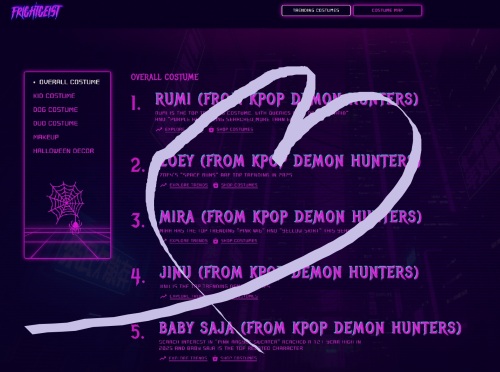
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-







