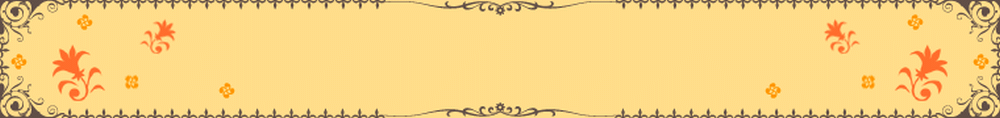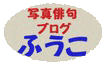2009年09月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

ヒガンバナ
26日の観察会で見たヒガンバナ。たくさん見かけましたが、ほとんど終わりかけている中で、1本だけ溝の中で咲いているのを見つけました。 今年はこれで見納めでしょうか。
2009.09.29
コメント(2)
-

里芋の花
大根の花は森繁久彌のテレビドラマ。サボテンの花はチューリップの歌。花の名前は数あれど、滅多に咲かない里芋の花。長年里芋を作っている農家でも見たことがないと言う。政権交代か、気候変動か、次に来るのは何か。
2009.09.28
コメント(2)
-

ツリフネソウ
千葉市主催の観察会「都川古道散策と丹後堰跡のツリフネソウ」に参加しました。車で行けば近いのだけれど、駐車場がないし、出発と解散の場所が違うので、JRとバスで行きました。公共バスなどこの数年乗ったこともなく、開いているドアから乗ったら「後から乗れ!」と怒られてしまいました。始発なのだから前のドアは閉めておけばいいのに。JRの切符を買えない代議士さんの気持ちがわかりました。千葉市の中心を流れる都川。下水道がほぼ完備され、有機汚濁指標は全国トップクラスになりました。狭い農道をくねくね行くと、古い農家の納屋?今、建てたらいくらかかるか。第一材料がないでしょう。 道沿いには庚申様がひっそりと。私には読めませんけど、右ハ大がん寺(大巌寺) 左ハなりた(成田)道とあります。このあたりは湧き水が多いそうです。なかでも田んぼの中の自噴井、通称「千葉の太郎」は1日200トンも湧いているそうです。小さなお風呂は1分で適量になる程の量です。丹後堰公園に着いて、お目当てのツリフネソウにご対面。想像していたよりたくさんあります。花はどんどん咲き、すぐにしぼんでいきます。わずかな開花の間に受粉させるため、うしろのほうのくるっと巻いているところに蜜があり、虫が蜜を舐めようと必死にもぐると背中に花粉が着いてめしべに受粉する仕組みだそうです。ほかにもハンノキ、ヤナギ、タコノアシなど湿地性の生物がたくさんありました。秋晴れの中、5kmぐらいを2時間半かけてゆっくり見てきました。
2009.09.26
コメント(4)
-

いなりそば
超ローカルネタです。「喜良素多」で検索すると千葉市緑区にある「まんじゅう研究所」がヒットすると思います。名前のとおり「まんじゅう」がメインです。1個80円から90円。おからまんじゅう、赤飯まんじゅう、中華まんじゅうはしょっぱ系、つぶ、こし、チョコ、さつま芋は甘系。その他いろいろありますが、少数手作りですので、予約しておくことをお勧めします。 で、まんじゅう以外のメニューが「いなりそば」。1個60円。注文があってからつくるので6分待てと書いてあります。話し好きのおばちゃんから開店当時の話や精製糖でなく三温糖を使うことなどを聞いていると、直、出てきます。食べかけですけど甘く煮たあぶらあげのなかに、ツユをちょっとかけた蕎麦、ねぎ、揚げ玉、自家製の紅でない生姜が入っています。揚げ玉のパリパリ感に生姜とネギの香りがマッチしていなりずしとは違った味です。 まんじゅう研究のあまり「喜良素多まんじゅう音頭」までつくってしまったそうです。近所にはアンクルベアーというベーカリーショップもあります。ここにもチョリソーパンとか黒カレーパンとかちょっと変わったパンがあります。秋の里山ハイクの途中に寄り道してはいかが。
2009.09.25
コメント(2)
-

ちたけうどん、再び
8月26日で書きましたが、チタケうどんをもう一度食べてみたい、というか、これが、毎年何人も命をかけて取りに行くという、チタケかという感じがありまして、再挑戦してみました。宇都宮市、若森というそばやさんです。インターネットでチタケうどんが食べられるということで検索してヒットしたところです。宇都宮市の東の方です。午後1時ごろでしたが次々お客さんが来て、なかなかはやっている様子。早速、チタケうどんを注文。チタケうどんは、チタケというキノコとナスを炒め、醤油で味付けした汁を別に作らなければならず、かつおぶしと昆布で作っておいた汁をつかう普通のうどんとは一手間違うようです。ちたけ自体がかなりお高いということもあって、種物うどんとしては値段が一番高いのも納得。中、左にある黒い円形のものがチタケです。油が浮いていて、すごく熱いです。チタケ自体はダシが出てしまっているのか、もそもそした感じで、椎茸のような舌触り、濃厚なうま味はありません。しかし、熱いおつゆは何ともいえないダシがでています。熱いのが苦手な人はつけめんのほうが、食べやすいです。着け汁の白いのは豆腐、ほかに湯葉が入っています。うどんはどちらもツルツルシコシコでおいしいです。薬味のネギが大量についてますが、全て入れても負けません。今度行くときは残った汁を入れる容器を持っていきます。絶対。
2009.09.21
コメント(0)
-

しんのみくうかんのベジタリアンメニュー
しんのみくうかんとは 「しんのみ」とはみそ汁の実のことで、農家の家では自家用の安全で新鮮な野菜をみそ汁の具にします。そんな野菜をみなさんに召し上がっていただきたいという思いをこめています。 また、くうかんは「空間」と「食う館」の両方の意味をこめてあえてひらがなにしています。(多古町旬の味産直センターホームページより)緑一色のなかに農家レストランはあります。本日のメニューは、御飯(黒米か新米の白米)、実だくさんのみそ汁、野菜かき揚げ、いも天、山東菜の煮浸し、揚げナス、トマト・コーン・キュウリ・ナスの温野菜に食後の珈琲。 完全予約制。人数が多いときはバイキングになります。 ローストビーフも大トロありませんが、中年にはなんかなつかしいメニューでした。食後の子供達はすぐに遊びに熱中。これは、ながしそうめんの残骸でしょうか。 くわしくは、しんのみくうかんで検索してください。
2009.09.19
コメント(4)
-

暑さ寒さも
暑さ寒さも彼岸までというとおり朝晩はめっきり涼しくなりました。今日の話題をいくつか。ががいもがもう実をつけていました。一寸法師の舟にはほど遠いですが、秋が深まるに連れてどう変わるでしょうか。 ゴーヤーの葉がだいぶ黄色くなりました。最後の収穫を含めて今年の収穫は109本。根本を切って枯れるのを待ちます。 近所にコンビニが出来ました。コンビニはよく利用しますが、開店の日に行ったのは初めてです。用もないのに覗いてみたら、結局、買ってしまいました。地価は下がっていますが都会に一歩近づきました。送料なしで本が買えるのが便利です。
2009.09.18
コメント(0)
-

ガガイモの花
家の近所でガガイモの花を見つけました。いわゆる園芸種ではなく雑草です。マダムヘクソカズラがまとうショールのような花です。昔からあったらしく、日本書紀にも出てくるとか。秋になると種が入った莢ができますが、ガガイモの莢を舟にしてスクナヒコナノミコト(少彦名命)が大国主命の所にやってきたとのこと。小さな神様で一寸法師の元祖のようです。雑草の莢から想像力をふくらまして一寸法師が生まれるなんて、昔の人は豊かな心を持っていたんですね。いつ種が出来るか、散歩の楽しみが増えました。
2009.09.11
コメント(0)
-

みずひき
家の庭のみずひき。ほっておくといくらでも増えます。たで科です。赤のほか白もあります。紅白揃って水引です。大文字山を食べるというブログがあります。京都の大文字山の近くに住んでいる方らしく、毎日のように大文字山に登って、ノグソを垂れることに生きがいをお持ちの方です。大文字山のものを取ってきて食べてる(ベジタリアン)ので食べた残りをお返しするんですね。で、そのブログにミズヒキがとてもきれいだと書いてあったので、よく見てみると本当にきれいでした。外は赤ですが中は白。もっとアップすると上半分が赤で下が白。おしべとめしべは白です。蟻もお気に入りらしく蜜を吸っていました。こうして蟻をさそって受粉するのでしょう。小さな花も必死に生きているのですね。
2009.09.05
コメント(6)
-

タコノアシ
どちらかというとかわいそうな名前に分類されそうな植物「タコノアシ」なぜタコノアシかというと、秋になると花の部分全体が赤くなって、イボイボが蛸の足の吸盤のように見えるからとのこと。環境省のレッドデータで準絶滅危惧種。多くの県で絶滅危惧種に指定されていますが、千葉県ではまだみられるようです。 どこで見たのかは、秘密。赤くなった頃、また、見に行ってみます。
2009.09.02
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1