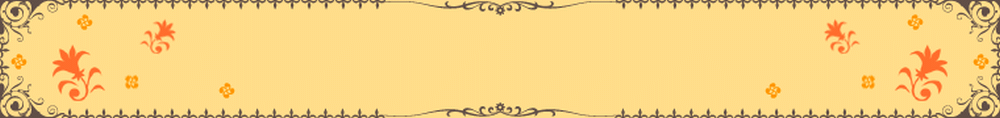2009年07月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

大原港 海鮮料理 船頭の台所
今日で7月は終わり、明日からは、暑い8月!のはずがとても涼しくなりました。クーラーが無くても快適で、むしろ寒いくらいです。今日のお昼は、いすみ市に住む I さんの常連のお店でいただくことになりました。大原漁港の目の前。「海鮮料理 船頭の台所」。名前からしておいしそう 店前の水槽には様々な魚、貝が泳いでいますが、店の裏には大きな料理用のいけすがあるそうです。おまかせ定食1500円。いさき、いか、ひらめ、まぐろのお刺身。いわしの煮付け。つみれ汁。それに、常連の顔でいわしの天ぷら大葉包み。つい、お酒が欲しくなりますが、我慢ガマン。 そのかわり御飯お代わり。ご主人鈴栄丸という釣り船をやっており、先代が外道だったしょうさいふぐ釣りを開拓、ふぐ免許も取って、今は大原の名物釣りになっています。そんな訳で朝早いので夜の営業は無しだそうです。こんなメニューで昼間しかやらないなんてもったいない。 漁港の売店でイカの塩から仕込み、「がんこおやじ」という干物屋でいわしの丸干しを買って帰り、久しぶりに日本酒 で一杯。ゴーヤもすくすく伸びて、静かな夏の日だ。
2009.07.31
コメント(2)
-

祇園祭(その3)
さて山鉾巡行はやっとスタートしました。いつも先頭と決まっている長刀鉾が四条烏丸をスタートするのが9時。新町御池に到着するのが11時30分頃。ラストは約2時間遅れです。御池通には前売り指定席の観覧席があるそうですが、山鉾が5分に1台ぞろぞろ歩くのを2時間座って見ているのもノウがないので、スタート地点よりもうしろの四条新町あたりで見ました。ここでは、スタート順に並ぶために山鉾が四条烏丸交差点を先頭にして自動車レースのスタートグリッドのように並んで出番を待つ様子や四条通に出てくるときに辻まわしするところを間近に見ることが出来るのです。さて、辻まわしですが、曲がる地点に青竹を割った物を並べて置くことから始まります。次に、竹の上に前輪をのせてストップ。次に、曲がる方向に綱を延ばし、音頭取りの号令のもと、一気に綱を引きます。 すると山鉾はズズッと向きを変えます。これを数回繰り返して、ようやく直角曲がりが出来るのです。最初の位置が悪いと引き手が歩道にまで入らねばならず、お巡りさんが汗だくになって見物客をどかせることになります。出番を待つのも一仕事です。 待つ間のおしゃべりも楽し。最後を行く南観音山。龍王渡海図を見送ると山鉾巡行もフィナーレです。マラソンと同じようにパトカーが通り過ぎると程なく車が走り始め、いつもの街並みに戻ってしまいます。
2009.07.18
コメント(4)
-

祇園祭(その2)
一夜明けて、山鉾巡行の日。天気も時々雨がちらつく程度でなんとか持ちそう。巡行は9時スタートですが、早朝から準備が始まります。宵山の混雑から守った鉾の周りの囲いはすっかり取り除かれています。山鉾は毎年組み立てられるので、クギは使わず荒縄で締め上げます。縄目がきれいですね。この山は雨を心配したのでしょうか、これから骨組みの周りを織物で飾りつけます。 山鉾を操縦するのは主にブレーキです。これを置くと急ブレーキがかかります。この棒は軽いブレーキ用。右車輪にチョット差し込むと、左車輪が前に出て右に曲がります。指揮を取るのは音頭取りのふたり。鉾のじゃまにならないよう交通信号機も回してしまうほどすごいお祭りなのです。約2kmを2時間かけて練り歩きます。準備も整って、出発を待つばかりです。
2009.07.17
コメント(0)
-

祇園祭
京の三大祭りのひとつ、祇園祭にやってきました。祇園祭とは、八坂神社の祭礼で869年に全国各地で疫病が流行したので疫病退散を祈願して始められた「祇園御霊会」が起源とされているそうです。(宵山・巡行ガイド2009より)新型インフルエンザが出た今年は起源にピッタリといえるでしょう。祭りの期間は7月1日から31日までですが、14から16日の宵山と17日の山鉾巡行がメインイベントでしょう。10日から鉾建てがあり、20m以上もある鉾をどうやって建てるか見てみたいのですが、次の機会としましょう。祭りの場所は、巡行が約800m角の3辺程度。山鉾が置かれるところもほぼこの範囲に入ります。京都駅から4条までは2kmぐらいあるので、京都の祭りといっても市内のごく一部で行われることがわかります。この町内に住んでいる人や企業にとっては大変な行事で、毎年のかなりの部分を祭の準備と後始末に追われることとなり、いわば祇園祭に捧げた人生を送ることとなりますが、そこからはずれると見物の対象にすぎないのです。山鉾は32あります。山と鉾の違いは鉾のある鉾と松が生えた山はわかりますが、よくわからないのもあります。船鉾は鉾はありません。四条傘鉾や綾傘鉾は鉾が無くても鉾です。宵山のうちは山鉾の周りに柵があります。最初見たときは、これ全体が山鉾でこのまま動くのかと思いましたが、巡行の時ははずします。なんでこのような柵があるのかは夜になるとわかります。この狭い路地に人があふれ、柵がなければ山鉾はたちまち壊されてしまうでしょう。鑑賞するなら昼間に限ります。また、山鉾ばかりでなく、着物屋さんなどでは秘蔵の屏風などを展示していて、これを覗いて歩くのも楽しみです。 こうしているうちに日も暮れ、コンチキチンのお囃子も入り、祭は、いやが上にも盛り上がります 。小遣いを握りしめた子供達で屋台は一杯。お天気もなんとか持ちました。明日は巡行です。 写真の中央を切り取りました。こうしてみると電線、電柱がいかに景観をだめにしているかがわかります。
2009.07.16
コメント(0)
-
千日
ブログデータを見たら2006年10月17日スタートから1000日になっていました。祝!開店千日千日というと囲碁の千日手、比叡山の千日回峰行、大阪千日前、花なら千日紅などがありますが、千葉県の地方紙「千葉日報」も千日です。 何日か前に3万アクセスでも言いましたが、今後ともよろしくお願いします。
2009.07.12
コメント(4)
-

手打ちそば 美郷
土日高速1000円を活用して久しぶりに長野県へ行って来ました。往路は八王子の料金所から相模湖まで、帰路は調布インター付近と首都高で渋滞しましたが、噂に聞く大渋滞には会わずに済みました。でも、来週からは学校の夏休みでどうなるかわかりません。で、行ったところは、長野県北部、大町市美麻にある手打ち蕎麦の店、美郷。木崎湖入口というバス停のある十字路の角なのでわかりやすいです。屋根の看板が壊れてますね。入り口は網戸です。右手のテントではワラビと、なぜか油粕を売っています。その奥にはなつかしい郵便ポストが見えますね。大ざるを注文すると、大根の漬け物とワラビ。それにそば粉を焼いて味噌をのせた薄焼きがサービス。(ひとり1個です。)ほどなくおそばが登場。写真ではわかりませんが、横から見るとアルプスのよう。緑色は山菜の天ぷら。地元のそば粉を使っているそうで、喉ごしよく、からめのカツオだしとマッチして、あっという間に食べてしまいました。そば湯は大きな急須にたっぷりで、漬け物をかじりながらそばの余韻を堪能することができます。お店からではありませんが、北アルプスが間近に見えます。朝早くなら、思わず手を合わせてしまうような景色に出会えるでしょう。
2009.07.11
コメント(2)
-

搾油機実験
3万アクセスになったまま更新できませんでした。6月は結局25日も働いてしまいました。週4日なら18日でよいのに、週5日出て、土日も出勤してしまった。仕事の愚痴をブログに書いても仕方がない(書いてるって?)。こういうときは、反動で手を動かしたくなります。包丁を研いで、鎌も研いで。爪に当てて、ちょっと柔らかく刺さる感じがすれば良いことにします。それから、菜種の搾油体験から、簡単な搾油機を作ってみました。大げさな機械を使わなくても、要するに菜種をつぶして油を出し、その油を外に取り出せばよいのだろうということで、手持ちの材料でやってみました。2×4の棒をねじでつなぎ、間に100円ショップで買ったマグカップとプラスチックのカップをはさみます。プラスチックのカップのなかに角材を入れ、プラスチックが割れないよう、すき間に熱で溶けるプラスチックの接着剤(名前は知りません)を流し込みました。マグカップとプラスチックのカップの間に菜種を入れてネジをしめれば油が出るだろうという予測です。問題はどのぐらいの圧力が必要か、材料がその圧力に耐えられるかです。使い方は、立てたままだとマグカップに穴をあけたりしなければならないので、横向きにして、マグカップとプラカップのすき間から油が垂れるようにします。菜種は、搾油体験でとれた滓を使いました。これなら種がすでにつぶれていて油が出やすいからです。ネジをレンチで思い切り締めて、一晩置いておいたら油が採れました。一応、うまくいったのですが、2×4材が曲がったのと、圧力を高めるにはマグカップが小さい方がよいので、さらに改良を試みてみましょう。ピーナッツとか椿のほうがつぶしやすそうなので、材料を変えてやってみると夏休みの研究になりそうですね。 でも、ヒマになるとゴロゴロしてしまいそう。
2009.07.07
コメント(7)
全7件 (7件中 1-7件目)
1