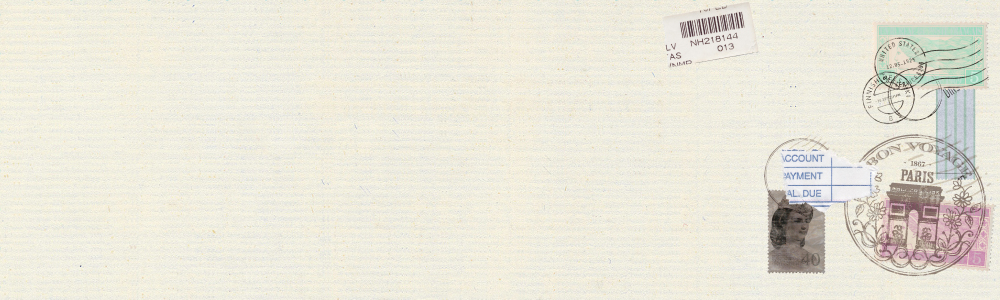PR
カレンダー
カテゴリ
前回の 記事
に引き続き秋学期の振り返りをしたい。うろ覚えの部分もあるため内容に誤りが含まれている可能性があることを予めご容赦いただきたい。
Week 1 Introduction
自己紹介、コースの概要説明、評価の仕方、課題の説明。
Week 2 Lexicon and Morphology
教科書(2冊)のチャプターリーディング。論文1本。
語彙の分類や生成方法について学んだ。接頭辞、接尾辞については学部生の頃に学んでいたので少しアドバンテージがあったのが大変助かった。改めて英語の語彙の形成プロセスは多様でかつダイナミックであることに大変驚かされる。Lexical rulesを用いて語彙学習をすると非常に効率よく覚えられるような気もするが、いかがだろう。backformationやblendingといった語彙形成プロセスについてもこの週に学んだ。
Week 3 Phonetics
教科書(2冊)のチャプターリーディング。論文1本。
この週から英語の音声学の分野を学んだ。自然に身につけた音も科学的な視点から学ぶと新たな発見が沢山あった。口腔図(口の中の断面図)は大学生の頃から何度も眺めてきた図である。こちらも大学生の頃の知識が大変役立った。卒業して10数年経過しても染みついた知識は脳内にしっかり記憶されていたことが嬉しかった。努力して獲得した知識は決して無駄ではないらしい。母音と子音の違い。そして一つ一つの音声の出力方法を学んだ。Labiodental, fricatives, affricatesといった基本的な音声学の用語もこの週に学んだ。
課題1提出:インタビューを行いその発言を書き起こした上で分析するという課題であった。発話の形態素や語形変化(inflections)を詳しく見ることで発話者の誤りや癖を見つけ出すことができた。
Week 4 Phonology
教科書のチャプターリーディング、論文3本。
前週に続き言語の音声について学んだ。音声学は物理的な側面に焦点を当てるのに対し、音韻論は実際の発話に焦点を当てているように思えた。詳しくphonological rulesについて学ぶのは初めての経験だったが、大変有益だった。この2週だけでだいぶIPA(International Phonetic Alphabet)の正確な表記方法について学ぶことができた。
Week 5 Syntax
教科書(2冊)チャプターリーディング(3章)、論文2本。
Syntaxはいわば文法構造の学問分野である。学部生の頃にも散々学び既習事項であるもののかなり苦手意識のある分野でできれば避けたかった箇所である。特にTree structureと呼ばれる文の分析(parse)は非常に難解でほろ苦い大学生の頃の記憶が一気に蘇ってきた。卒業しても苦い記憶は脳裏の奥底にしっかり残っていて自分でも驚いてしまった。この辺りもNoam Chomskyの生成文法(Generative Grammar)についても学んだ。
課題2提出:インタビューを行いその発言を書き起こした上で分析するという課題であった。書き起こす作業にかなり手こずったが様々な分析方法を学ぶことができ大変参考になった。
Week 6 Semantics
教科書チャプターリーディング、論文3本。
MetaphorやModalityについて学んだ。言語によって比喩の使い方、指示語の使い方が異なるのは非常に興味深かった。
Week 7 Pragmatics
教科書(2冊)のチャプターリーディング、論文2本。
この週は文脈が発話に与える影響について学んだ。新出情報と既知の情報を相手にどう提示するか、それによって発話のイントネーションや文の構造にどのような変化が生じるのか文献を読みながら学んだ。英語を外国語として学んできた身としてはまさに目から鱗であった。また、とある研究によると英語学習者はpolitenessがネイティブ話者より低いという結果も出ているようで教育的示唆に富む内容であったと思う。
課題3提出:3人にインタビューを実施して、そのインタビュー結果を元に分析を行うという課題だった。10個の文を与え、文法的に許容できるかできないかを判断してもらう。ネイティブと非ネイティブで文法の寛容度に大きな乖離があり非常に興味深い結果が得られた。研究の大変さと楽しさを垣間見た気がする。
Week 8 Speech act and Conversation
教科書のチャプターリーディング、論文3本。
この辺りからだんだん言語学から社会言語学の色彩が強くなってきた印象がある。最初の5週は古典的な言語学を学んだが、後半に行くにつれて社会の中で言語がどのように機能しているか学んだ印象がある。相手によってどのように話し方が変わるか考察した。言語のformalityやpolitenessについて知識を深めることができた。
Week 9 Digital Tech and Language Use
論文4本。
機械翻訳やテクノロジーの進歩が言語学習にどのような影響をもたらしているか学んだ。機械翻訳の歴史や生成AIの基本的な仕組みについて学ぶことができ、非常に知的好奇心をそそられた週であった。この週で中国からの留学生と一緒にグループプレゼンテーションを行った。オンラインで入念なリハーサルもして本番を迎えたが、発表時はやはり緊張した。なるべくアイコンタクトを取って、英語の発話ペースにも気をつけるようにした。教授からは”Thank you for your great presentation!”とお褒めの言葉をいただいた。
課題4提出:自分で作文した文章を機械翻訳にかけて、その正確さを評価するという課題であった。昨今はChatGPTやDuolingoの台頭で外国語教育の意義そのものが問われつつある。機械翻訳もまだまだ改善の余地があることがこの課題から判明した。
Week 10 Age factors in Language Acquisition
教科書チャプターリーディング、論文2本。
臨界期仮説(The Critical Period Hypothesis)に関する論文を読み込み授業内でディスカッションをした。言語はとにかく早期に始めるのが良いという考えがあるがそこには問題がいくつもあることがわかった。家族をつれてアメリカに住む者としては大変興味深かった。自分の子供たちが言語をどのように吸収するのか近くで観察したいと思った。
Week 11 Language and Thought
教科書チャプターリーディング、論文2本。
この週ではSapir-Whorf Hypothesisという有名な仮説を文献を読みながら検証した。言語が思考にどれほど影響を与えているかという問いだが、決定的な答えがまだ導き出せていないというのが個人的には興味深かった。詳しく調べるためには被験者を隔離して言語との接点をなくす必要があり、倫理的な問題があるようだ。英語ではよく”Which came first: the chicken or the egg?”ということがあるが、言語と思考の関係を学びながらこの質問がふと脳裏をよぎった。
Week 12 Language Variation
教科書チャプターリーディング、論文4本。
この週のトピックは言語の方言だった。英語学習者は「スタンダード英語」を学んでいるが、実は英語の方言は多種多様で奥が深いことがリーディングで明らかになった。また、ネイティブスピーカーの文法への寛容度も年代によって変化をしていることも大変興味深かった。またこの週でKachruのWorld Englishesについても学んだ。African American Vernacular English(AAVE)についても学んだのもこの週だ。
※エッセイ課題1を提出した。
Week 13 No Class
Week 14 Language Acquisition
教科書チャプターリーディング、論文2本。
第一言語、第二言語問わず「言語の習得プロセス」について学んだ。babblingから始まり、赤ん坊がどのように言語を学んでいくかを学んだ。まさに自分の子供が言語を学んでいる真っ最中で重なる部分が多々あった。言語習得には特殊なインタラクション(交流)が必要であることもわかった。テレビの前に置いておくだけでは言語の習得はなかなか促進されないらしい。これは大人の言語習得にも同じことが言えるような気がした。
※エッセイ課題2を提出した。
Week 15 Presentation and Discussion
最終週は自分が作成したレポートについてプレゼンテーションを行った。最後の方は意識が朦朧になりながら課題に取り組んでいたため、正確に自分が何をしていたのかあまり正確に覚えていない。
※エッセイ課題3を提出した。
最終的にこの授業の成績でAをいただくことができた。読み込む論文の量も他の2つに比べて一番多く最も苦労した科目であったのは間違いない。そんな大変な科目でAをとれたことは自分にとって大きな自信となった。サイのツノのように一歩ずつ進めばゴールに辿り着けることがわかった。春学期以降も今回得た教訓を胸にどんな困難が待ち受けようとも一歩一歩確かな歩みを続けたい。
上記からお分かりの通り、大学院では扱う文献の量が桁違いに多い。授業は 3 つしか取らないのだが、とにかく一つの授業の課題の量が日本とは比べ物にならないのだ。文献を読んだことを前提に授業が展開するため、文献をスキップした上で授業に臨むとディスカッションにうまく入っていくことができない。
-
2024 Atlanta Fulbright Seminar後の自由… 2024.05.21
-
2024 Atlanta Fulbright Seminar(Day 3) 2024.05.16
-
2024 Atlanta Fulbright Seminar(Day 2) 2024.05.15
コメント新着
キーワードサーチ