2006年06月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
陸上女子1万メートルの福士加代子選手のレースから
最後のスパートを見ていたら、その鮮やかさに「あっ、ディープインパクトそっくりだ」 思わず、先だっての宝塚記念でのディープインパクトのスパートが重なって見えた。 レース後の福士選手のまさかのコメントがあった。「あそこはディープインパクトをイメージしてレースをしました!」 あとで、ネットで調べてみると新たな事実が!不世出の5冠馬ディープインパクトは、福士と同じ3月25日生まれ。なるほど~。
2006年06月30日
コメント(1)
-
キャンドルをともして「スローな夜」を!
「電気を消してスローな夜を」 習志野市民に対して「15万7056人のキャンドルナイト」を呼びかけて、先日このイベントが催された。 キャンドルナイトは省エネを目的に、ロウソクを灯して過ごそうというもの。全国でちょっとしたブームだ。 夜2時間ほど。市役所前グラウンドではイベント「キャンドルナイト・タイム」を開催し、1000本のキャンドルを並べ、幻想的な光の世界を演出したとのこと。 今回、環境月間に合わせて企画された。 「テレビを消して、家族の会話や、考える時間になれば」とメンバー。 残念ながらこれを知ったのは後日。 今後、ライトダウンのイベントはより広範囲にいろいろなものを巻き込んで常態化していくと考えられる。 デジタル、人口のものを一時断ち切って、一歩原始の社会に引き下がることにより、忘れていたもの、無くしてしまったものが蘇る。 まずはひと時、電気を絶ってみる。幸せとは何か?繁栄とは何か?を考える機会を持つことにきっと皆が魅せられる。 家族皆で、友人同志で、ろうそくの幻想的な光を見ながら過ごす時間の貴重さに気付きはず。 きっと何かが生まれるはず、忘れていた大事なものを思い出すはず。きっと何かが甦るはず。 これから今後このようなイベントが絶対に広がっていくはず。
2006年06月28日
コメント(1)
-

今、イヤースコープが売れている!
先日の日経に載っていた。 今、イヤースコープが爆発的に売れているという。 なるほど、片手でディスプレイを持って覗きながら、もう一方で耳かきをする。想像しただけでも面白い。
2006年06月27日
コメント(0)
-

葬儀を縁として
お寺の住職が亡くなったので葬式に参列した。2000人くらいの参列者があり、焼香に1時間。 以前に、亡き父が、昔、植木等氏に家に来てもらい、お経を読んでもらったことがあると言っていたが、その植木氏も参列していた。もう80に近い年齢だが矍鑠とした姿であった。 ところで、会葬御礼に入っていたリーフレット 「葬儀を縁として」 にとても良いことが書かれていたので、以下抜粋引用。 ---------------------------------------------------------仏事としての葬儀 今、私たちはかけがいのない人の死に出会いました。こころの中では様々な思いが駆け巡っていることでしょう。 つい先日まであたたかい言葉を交わしていた方も、今は無言のまま静かに身を横たえているだけです。何も語らない亡き方を前にして死という事実に直面した私たちには使命があることを感じます。それは、生きて在る私たちが、その死を確かに受けとめて、亡き方の声なき声を聞き届けていくということです。 遺族の方はもとより、会葬の方も亡き方と真向かいになって、1人の人間の死という事実を、どこまでも自分自身の問題として受けとめていくことが「仏事としての葬儀」になるのです。 一般に、通夜・葬儀の場は形式や世間体が重んじられますが、くれぐれも遺族と会葬者の挨拶だけに始終しないよう心がけたいものです。最後の贈り物 三十九歳で癌告知を受けた平野恵子さんは、病床から子どもたちへメッセージを送り続けました。 「人生には無駄なことは、何ひとつありません。お母さんの病気も、死も、あなた達にとって、何ひとつ無駄なこと、損なこととはならないはずです。大きな悲しみ、苦しみの中には、必ずそれと同じくらいの、いや、それ以上の大きな喜びと幸福が隠されているものなのです。(略) たとえ、その時は、抱えきれないほどの悲しみであっても、いつか、それが人生の喜びに変わる時が、きっと訪れます。深い悲しみ、苦しみを通してのみ、見えてくる世界があることを忘れないでください。そして、悲しむ自分を、そっくりそのまま支えていてくださる大地のあることに気付いてください。それが、お母さんの心からの願いなのですから」 『子どもたちよ ありがとう』(法蔵館)より 平野さんは「死は、多分、それがおかあさんからあなた達への最後の贈り物になるはずです」と書き遺していかれました。悲しみをとおして 愛する人、親しい人との別離ほど悲しく寂しいことはありません。しかし、どれほど辛くても亡き方の死を「最後の贈り物」として受けとめ、仏法にふれる縁とすることが願われています。 私を支える大いなる大地のはたらきを感じ、自分自身の生き方を根本的に見つめなおす縁を亡き方から贈られたのです。 “ひとりの人の死は悲しい。 しかし、残された私が そのことから何も学ばず、 何ひとつ新しく生み出せないとすれば、 それは、もっと悲しい。”---------------------------------------------------------
2006年06月26日
コメント(6)
-

大前研一の本
著書名「下克上の時代を生き抜く即戦力の磨き方」 著者はアメリカに精通している。以前から日本国内の流れを先取りして色々な提言をしているが少し先を走りすぎているため、受け入れてもらえない側面もあったが、いよいよ大前流の考えが幅を利かしてくる。今まで以上の流れでアメリカ化が益々加速する。 昔読んだ企業参謀や富国論などでの歯切れの良さが、相変わらずというか、益々冴えると同時に円熟味を増してきている。 以下、本の中身から 序 章 下克上の時代 第一章 語学力を磨く 第二章 財務力を磨く 第三章 問題解決力を磨く 第四章 勉強法を身につける 第五章 会議術を身につける 終 章 人生設計は自分でやるしかない 要はここ30~40年続いた安定雇用の時代は終わり、今は下克上の時代で、当てになるのは自分の能力だけであるから、人生設計は自分でやるしかないということ。 日本国民のほとんどが、取り分け中高年がユデがえる的な状況にあり、ほとんどこの状況に対応できていない。 以下、面白い部分を抜粋‥‥日本人が英語が苦手なのは、国内で勤勉に働き、いいものを作って輸出していれば、それなりに金が入ってくるという従来の発想から、いまだに抜け出られていないのが最大の原因だ。‥‥ソフトバンクの孫正義。彼は40代である。「同じ世代がかったるい方がこちらは楽だ」というのが彼の口癖である。宮本雅史氏も孫さんと同じ歳。彼の口癖も「同世代がリスクをとらないから僕でも事業ができた」である。‥‥ヒルズ族に憧れるのは田舎者である。人と同じことをしていると、ライフスタイルはより「ロウアー」になっていく。‥‥「自分はこれで勝負できる」というものを、一つ決めておくこと。分野はなんだっていい。その代わり、それに関しては余人を持って代えがたいくらいのレベルを目標にしなければ意味がない。 わかっちゃいるけど‥‥。
2006年06月25日
コメント(0)
-
我が町でも人口が減り始めた?
市の広報が毎月2回配布されるが、そこに記載されている人口の変化を何気なく見たら、何と‥‥。前月に比べて人口が減っている。東京のベッドタウン的な街でも人口が減り始めている? 何でも増えていくのが常識だったが、 今までとは違う潮流にどのように対応していくのか? 人口減少時代の消費について日経に面白い記事が載っていた。“人口減少時代は小商圏でより幅広い世代の顧客を開拓し、買い物の頻度を高める創意工夫が欠かせない。 成熟化しても飽和しない消費。買い手の変化は売り手の予想を超えて進む。売り手がたぐり寄せる手掛かりは逆説の中にある。” うまく対応するヒントは「逆説」の中にありそう?
2006年06月25日
コメント(0)
-
念願の環境セミナーに参加して
以前からブログ記事に興味をそそられ、注目していたいいこと探険家さんが東京でセミナーを開催するとの情報をつるり子さんのページで見つけて参加した。 何故注目していたか?その一つは、何と10歳から環境に興味を持ち始め、以来ずっと継続して活動をしているということであった。 講演を聴いて何故なのかが理解できた。 ブログも毎日書き続けているという。使命とはこういうものなのか! 真摯に真面目に取り組んでいる姿勢に感銘を受けた。 立派な方であり、また、このセミナーに集まった方々の環境に取り組む意識の高さにも脱帽した。
2006年06月24日
コメント(1)
-

神田界隈から銀座方面を散策
御茶ノ水から神田淡路町、須田町を経て内神田、大手町、東銀座まで約1時間かけて散策をした。 土曜日でもあり、ひとけも少なく、ぶらぶら歩くには格好のときである。 あんこう鍋の「伊勢源」、鳥すきの「ぼたん」、甘味「竹むら」、「藪そば」など、裏通りにやはり趣があるものが多い。 コンクリートの立派なビルよりも、古くから守られてきた木造物が心を和ませてくれる。
2006年06月24日
コメント(1)
-

共感が広がるコミュニティ作り
本を読む際に著者の年齢を見る癖がある。1971年生まれとのことで大変に若いが、米国での企業経験やシリコンバレイでの生活経験もありまんざらでもない。内容をチラッと見ても得るものがありそうと判断し購入した。 掲題は増田真樹著「超実践ブログ革命」の副題である。 以下、断片的にエッセンスを抜粋 ‥‥ブログという"個人メディア"を持つことが、情報発信者の立場で情報を得ることができるようになる。実はこの部分が今後の情報収集の大きな指針となる。 ‥‥「移動量は発想量に比例する」という。移動することにより、考えもつかなかった物事に出会うことになり、発想の源泉になるという。 ‥‥現在の社会は世代を超えた価値観の共有が抜け落ちている状態。 ‥‥「人生は旅である、目的ではない」ブログを続けること自体が人生そのものなのです。 なかなか考えが柔らかい! ブログを通じての共感できる人との思わぬ出会いが、ここ1~2年で急速に広がっている。共通の夢や目的を持った人とのコミュニティが簡単に作れる時代。 このような横串がいとも簡単にさせる時代の過ごしかたはこれからの人々の時間の使い方に、大きな変革をもたらすとの予感がいよいよ現実のものになってきている。 ------------------------------------------------------------ダイヤがダイヤで磨かれるように、人は人によって磨かれる。どんな人と出会うかで人生は大きく変わります。どうせなら、熱き思いを持った仲間が集まるパーティーにアナタも参加して刺激を受けてみませんか? 【倶楽部カカトコリ】オフ会in銀座日時 7月1日(土) 14:00~17:00 (受付開始 13:30~)場所 銀座ファゼンダ 中央区銀座5?9?11 電話 03-3572-3711 http://www.fazenda.jp/party/welcome_party/index.html会費 10,000円(税込み)当日会場でお支払いください今回参加者の名簿を 作成予定していますので、参加申し込みフォーマットで、書きたいだけ書いてくださいね。詳細お申し込みは今すぐこちら⇒ http://cacatokori.opal.ne.jp/6_01.php ------------------------------------------------------------
2006年06月17日
コメント(1)
-
最近ようやく肩の力が抜けて‥‥‥
今日の日経に「井上陽水ライブ新作で熱唱」という記事が載っていた。 最近ようやく肩の力が抜けて羽目を外して騒げるようになったとのこと。 最近、テレビでたまたま耳にして衝撃を受けた歌があるという。子供の頃におぼろげに聴いた記憶があるという、村田英雄の昭和の名曲「皆の衆」 腹が立ったら空気をなぐれ 癪にさわれば水をのめ どうせこの世はそんなトコ そうじゃないかえ皆の衆~~ 「世の中を達観した上で、苦労があっても楽しもうぜという感じがね、すごくいいなあと。 まだ僕はそこまでいっていないけど、少しずつその境地に近づいていきたいですね」 そんな境地。いいなあ~。
2006年06月17日
コメント(0)
-

茂木健一郎著 「ひらめき脳」
本書に一貫しているのは、人間に備えられた機能を肯定的に捉える姿勢であり、これが取りも直さず、人生を愛するということに繋がっている。 ともすれば難しくなる話を冒頭の「アハ!体験」で引きつけ、そのアプローチを継続させて最後まで読ませてしまう内容である。 「ど忘れの構造」の中では記憶の編集の重要性について述べている。記憶が編集されることで新しいものが生まれてくる。この「新しいもの」を生み出す「記憶の編集力」こそが「ひらめきを生み出す力」であり、ひらめきは記憶の編集過程で出てくるといっても過言ではないとのこと。 ペン・ローズの「創造することと思い出すことは似ている」というテーゼを興味深く捉えている。 ひらめきや創造性は人間が生きるうえで必要である。それは直面する不確実性に上手く対処するため。生きるということは何が起こるかわからない。不確実性にいかに向き合うかということが本質である。 そして不確実な状況自体が脳にとっては喜ばしいことであり、人間とは、まさに「不確実性」-未知の可能性にかけずにはいられない動物なのである。 不確実だからこそ嬉しい。 人生を充実させる-人生を変える、やり直すには一瞬のひらめきこそが最高の妙薬であり、それを起こすためのインフラは誰の頭の中にもある。 会話はひらめきの連続とのことであり、そのようなことを意識しながらこれから過ごしていければ‥‥。
2006年06月11日
コメント(1)
-

斉藤孝著「コミュニケーション力」
3章から構成されている。文脈という基本、響く身体・温かい身体、沿いつつずらすの3本柱で構成されているが、特に沿いつつずらすのが会話の妙味と感じた。以下、印象に残った部分を要約抜粋 「人の話を聞いたという証はその話を再生できるということである」 この原則を共有することでコミュニケーション力のレベルは桁違いに 高くなるはず。 「会議で肝心なことは現実を変える具体的なアイディアを一つでも いいから出すこと。それがゴールである。それ以外のことは全くパスに 過ぎない。人の出したアイディアを否定しているだけの人はバックパスを しているだけ」 「私がいつも不満に思っているのは日本は否定的な意見を言う人が それなりの評価を受けているということだ」(P156) ←この部分は 全く持って同感である。「過去・未来を見通す」という章での内容が特に圧巻である。 「ルドルフ・シュタイナーの本を読んでいるときに、人間を種子として 見よという言葉があった。相手を現在のあり方だけで見るのではなく、 その人の遥か過去と未来を見通して見ろということであった。 どこから来てどこへ行くのか。どういう過去からやってきてどういう 未来に向かって行こうとしているのか、そういう途上の人として現在の 相手を見る。 これは一種の宗教的とも言える眼力トレーニングだ。 そのような連続した生として相手を見ること自体が、相手に対する 見方を変えるのである。遺伝子という決定的な運命を担う存在として 人間はその生を生きなければならない。そうした宿命を負う者同士として お互いを見ることができれば、コミュニケーションの余裕も変わってくるに 違いない。」最後に 「コミュニケーションを通じて人は生きる意欲を湧かせている。 コミュニケーションこそが生命力の源なのだ。川が流れることによって 川であるように、人は感情や意思を他と交流させることで人であり続け られる。 コミュニケーションという営為は人間の根幹を成している。 どんな状態でもどんな相手とでもコミュニケーションは可能だ。そう 確信することで現実は明るさを増してくるだろう。」何とも中身が濃い本である。
2006年06月10日
コメント(2)
-

ゼロから1を生み出す起業力
表題は澤田尚美著「ゼロから起業で月収100万稼ぐ」の副題である。 プロローグにはこんなことが‥‥、 これを読めば、飛び越える前は暗く深いと思っていたゼロの谷が実はそれほど深くはないということを一人でも多くの起業志望者に知っていただければ幸いとのコト。 ゼロから1を作るまでの過程、無から有を生み出す過程には、人それぞれの人生観や価値観が絡むことも多く、万人に共通したノウハウが存在しない。 そこが面白い。そこに目をつけた書である。 この本は、ゼロからはじめて「1」を作るまでのステージに特化した起業の入門書である。 ひとりで何もないところから始め、限りなくゼロに近い状態から人脈(人)、商品(もの)、資金の流れ(金)といった「有」を作り出すために何をすればいいのか? ゼロから1を作る力。この起業力を身につけさえすれば一生仕事に困ることはない。イントロに始まり、人を作る、ものを作る、お金を作る、流れを作る、1から2を作るという経営の3要素を中心にアドバイスも含めて順を追ってわかりやすく紐解いている。 -----------------------------------------------【あなたの劣等感・コンプレックスを埋める方法】最新心理学NLPと斉藤一人さんのお話でつづる、自分をもっとスキになる方法http://www.kokoro-ya.jp/category/1155803.htmlあなたは、自分のことが好きですか?そして自分の劣等感と、どう付き合っていますか?もし自分の劣等感を埋める方法があるとしたら・・・毎日が笑顔で満たされ、愚痴の無い素晴らしい人生が開き始めます。・自分を許す方法・相手を許す方法・性格を変える方法・あなたの個性を活かす方法日本一のお金持ち、斉藤一人さんの言葉を借りながら、最新心理学NLPを使った性格を変えていく方法の第一弾をお届けします。http://www.kokoro-ya.jp/category/1155803.html---------------------------------------------------------------------------------【アパパのゆかいな健康講座】からのお知らせ 梅雨を吹き飛ばしてストレス解消しましょう♪ ------------------------------------------------------ ● カンタン呼吸法講座 『TANDEN BREATH』 (タンデンブレス) ~気功(内気)と、レイキ(外気)の融合~ 【日 時】 6月11日(日)13:00~15:00 ・ 的確な誘導によって“丹田”を意識でき、“気”が回り始めたのがわかりました。 “気”が見えたのが嬉しかった。 (Y.Kさん 女性 会社経営)------------------------------------------------------ ● 力のいらない護身術講座 『SENT-RAY』 (セントレイ) ~女性と子供の防犯対策、オヤジ狩り対策に!~ 【日 時】 6月18日(日)13:00~15:00 ・ 簡単で実用性があり、大変役に立ちました。 ありがとうございました。 (M.Aさん 女性 プロデューサー)------------------------------------------------------ ● ラクラク武術ウォーク 『AXIS WALK』 (アクシスウォーク) ~カッコイイのに疲れない 美しい歩き方と立ち姿に!~ 【日 時】 6月24日(土)15:00~17:00 ・ 意識する事の大切さを、再認識致しました。 (J.Yさん 女性 美容師)------------------------------------------------------ ※ 【お申し込み】など詳 しいことは、こちらでどうぞ ■アパパの講座情報 ⇒ http://senseinspire.hp.infoseek.co.jp/seminar.html お子様連れ、大歓迎です♪ (小学生低学年以下のお子さんは無料)----------------------------------------------------------------------------------------
2006年06月04日
コメント(3)
-

竹内一郎著 「人は見た目が9割」を読んで
よく研修などで使われる話題である「メラビアンの法則」をメインに取り上げて書かれている本である。 劇作、漫画原作者の筆者が、ノンバーバルコミュニケーション(非言語伝達)の方が伝達力が高いとの観点から、多くのテーマを扱って記されている。 日本が生んだマンガの長所もふんだんなく紹介されている。マンガが面白いのは、こんなにもいろいろな工夫がもりこまれているからか。なるほど~~。 日本固有の文化についても、「語らぬ」、「わからせぬ」、「いたわる」、「ひかえる」、「修める」、「ささやかな」、「流れる」文化という7つの切り口から特徴をとらえている。 これを読んで、色やにおいのメッセージ、間(ま)の伝達力など、普段何気なく、やり過ごしていた日常的な行動にも見方が広がった。 あとがきに「言葉の呪縛から解き放たれて、もっと総合的にコミュニケーションを考えてみてもいいのではないか」と問題提起されているが、確かにそのような「非言語」をもっともっと注目すると面白いと感じた。 ----------------------------------------------------『プレゼンテーションの極意』1日セミナー・実践編 in 大阪一部上場企業でも採用されているセミナーが大阪で!ひさびさにプレゼンテーション専門家の田中省三さんが大阪でセミナーをやってくれます! ●人前でちゃんと話せたら・・・ ●自分の伝えたいことを、もっと上手く表現できたら・・・ ●順序よく伝えるのって、どうすればいいの・・・ そんなあなたには、ぴったりです! http://presemi.com/semi-day.html『プレゼンテーションの極意』1日セミナー・実践編日時 2006年7月1日(土) 10:30~18:30場所 釣鐘倶楽部(大阪・天満橋駅から徒歩5分)実践編では、プレゼンターのプレゼンをビデオ撮影して、その場で指導があります。オブザーバーとして参加するだけでも、いろいろ氣付きが得られますよ!!東京では、定期的にセミナーが開かれているので、東京方面の方も要チェック!プレゼンテーションの極意 http://presemi.com/----------------------------------------------------
2006年06月03日
コメント(1)
-

邱 永漢 著 「起業の着眼点」を読んで
起業は時の流れにうまく乗ることを考える。そしてお金の流れに気をつけるのが基本とは邱永漢氏の事業を見ていると納得がいく。 世の中は偶然の連続であり、偶然を拒否する姿勢をとってはいけない。むしろ、自ら偶然に出会うチャンスをつくり、偶然をできるだけ多く迎え入れる姿勢をとることが必要である。「偶然は成功の父」であるという項には共鳴した。 ------------------------------------------------------そろそろ周囲に振り回されるのは終わりにしましょう。教材『自分ブランドの作り方』http://www.lifesolution.jp/info-page/brand.html自分ブランドで成功した立石剛氏。(立石氏の実績は、http://www.lifesolution.jp/info-page/zisseki.html)彼が、自分ブランドを構築している人たちに共通する法則を発見した。それをまとめたのが、この教材『自分ブランドの作り方』。 答えは全てあなたの中にある! http://www.lifesolution.jp/info-page/brand.html 6月末までは、特典付き!------------------------------------------------------
2006年06月02日
コメント(0)
-
あるメルマガに書いてあった記事から
検索サイトで検索された言葉の中で4月に入って約5倍に増えた『検索ワード』がある。 それは「大企業病」とのこと。 研修を終えた新入社員 ではないかと推測しているが、この感覚は企業に長年勤めている人にとって、分かっているようで、多分皆、大きな勘違いと錯覚をしているということなのであろう。 戦後60年続いたサラリーマン社会は、勤めている人々のすべてをゆでガエルにして、既に崩壊しているのかもしれない。 そんな気持ちをこの5~6年抱いている。
2006年06月01日
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…
- 川崎行ったり、銀座行ったり
- (2025-11-25 01:00:05)
-
-
-
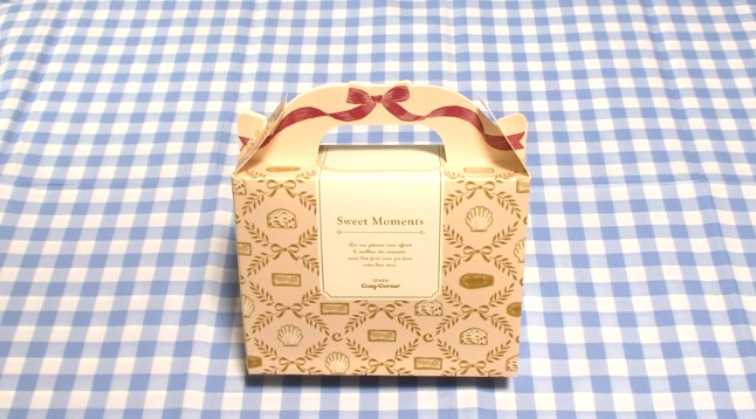
- 模型やってる人、おいで!
- EF58(その17) サンダーバー…
- (2025-11-24 18:45:16)
-
-
-

- 一口馬主について
- カーミングライツ出走(11/24福島9R…
- (2025-11-25 01:05:29)
-







