2005年10月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
『トゥルーへの手紙』
犬を主人公にした、フォト・エッセイならぬ、ムービー・エッセイ。トゥルーは、写真家にしてこの映画の監督、ブルース・ウェバーの飼い犬です。エッセイなので、特に筋はありません。冒頭、監督が言うように、「一種のホーム・ビデオ」。それが立派に「作品」として昇華されているのはさすが。何より、「絵」が美しいのです。いくつもの詩が朗読され、様々なエピソードが、犬の映画が引用されます。それは、平和に向けたメッセージ。特にマーティン・ルーサー・キングJr.の演説音声は、すごく力強くてメッセージフル。音楽のセンスも最高!オープニング近くでかかっているのは…「荒城の月」のジャズアレンジバージョン?パンフレットを見たら「Japanese Folk Song」となっていました。音楽に力があるから、映像も引き立つ。映像が美しいから、音楽が引き立つ。素敵な関係性だなぁ、と思います。--------------------------全体的に、「良かったなぁ」なのですが、農場のおばちゃんのシーンには、「アメリカ的マッチョ」に対する違和感を感じてしまいました。このおばちゃん、明るくて良い人、なんでしょうけど、その発言には首を傾げざるを得ません。「子供たちが投げ縄で遊んで、他のお客さんを標的にしてたら、お店を追い出されたのよ」って、明るく語ってますが、いや、そりゃそうでしょう。「お母さんが一番楽しんでいたじゃないか」「そうね、ふふふ。」って、いや、あんたたち、迷惑親子ですから。しかも、全然悪びれていないし。「自由」と「無法」をはき違えてないか?「働かない犬なんて、蹴っ飛ばす以外に役に立たない」というセリフも何だかなぁ。--------------------------このおばちゃんが9.11に関連して「いつ死ぬか分からないって恐怖」について語ってましたが、それを日本人は第2次大戦の末期にはずっと感じさせられていたのですよ。アメリカ人は、防空壕がある生活なんて、考えたことないでしょう?(日本やナチスの犯罪については今回は触れずにおきます。)そして、その恐怖をアメリカはイラクに与えた…与え続けているのですよ。「家宅捜索」として、勝手に家に外国人兵士が侵入してくる恐怖、犠牲になった民間人、刑務所で横行する蛮行。おばちゃん、気付いていますか?想像できていますか?「誰が悪いのでもない、悪いのは戦争だ」って言うのは簡単ですが、私はこのおばちゃん的な「想像力の欠如」を弾劾します。自分が傷つかないと、いや、自分が傷ついても、他人の痛みを知ることが出来ない、そんな人々が戦争を助長しているのだと。その意味では、私だって戦争に加担しているのだ、という自戒を込めて。--------------------------『ボーリング・フォー・コロンバイン』でしたっけね、ベトナム戦争の退役軍人が、イルカの保護運動をしている話。彼にとっては、黄色人種よりイルカの命の方が尊いという歪みが、映画の中で語られていました。今回の映画の中で、犬が特権的に扱われれば扱われるほど、それと同種の違和感を、ほんの少し感じてしまいます。いや、もちろん、それで良いのですよ。私だって、犬は大好きですし。別に、イラクで苦しむ人々の映画を撮れとか、そんな野暮なことは言いません。声高に「反ブッシュ」を叫んでみせた『華氏911』より、多くの人の心にじんわり伝わる映画でしょうし。だから、そうですね、感想、というより、自戒ですね。「この映画に感動する前に、忘れてはいけないことがある」という。--------------------------今朝の新聞に、「災害とペット」の話が載っていました。地震、台風、その他の災害が起きたとき、避難所ではペットをどう扱うか。「ペット可」の避難所を作る…ペットの食料は?ワニは避難所に連れてこれるのか?先日のアメリカでのハリケーン被害の時、お金持ちの方々は「ペット可」のホテルに避難したそうです。その気持ちは、分かります。しかし、その一方で、多くの貧しい人々の命が奪われてしまった現実。その時、自分に出来ることは何なのか、自分がその立場なら、何をするのが「正しい」のか。考えなければならないことが、あまりにも多すぎて、私の貧しい想像力は悲鳴をあげそうです。この映画の中で、ジョン・レノン&オノ・ヨーコの、あの言葉が引用されます。「War is over.....if you want」- 「戦争は終わった! もしあなたがそう望むなら」考えること、想像すること、願うこと、そこからしか、何も始まらない。考えて、想像して、願って、そして何をするのか。何が出来るのか。Think - Imagine - Wish - Do the Action.世界が平和でありますように。世界が平和になりますように。--------------------------青山で、この映画に関連して、ブル一ス・ウェバーの写真展をやっていたのですが…終わってしまいましたね。写真展の感想はこちら。-------『トゥルーへの手紙』 - "A letter to True"2004年 キネティック 78分http://www.excite.co.jp/cinema/special/alettertotrue/index.dcg監督:ブルース・ウェバー出演:True,Palomino,Sailor,Polar Bear,Big Skye and so on★★★★☆
October 30, 2005
コメント(2)
-
『ジグマー・ポルケ展』@上野の森美術館
「不思議の国のアリス」の副題がなければ、行ってませんでしたね(苦笑)。現代ドイツ美術の旗手って言われても、知らない…リヒターくらいは聞いたことありますけど。で、副題に使われた「不思議の国のアリス」は、チラシにも使われた、初期の代表作だそうです。プリントされた生地に、ドットの手法でテニエルのイメージを描いた作品。思った以上に大きく、プリント地がサッカー模様だったりと、たくらみに満ちています。えっと、ところが、「アリス」関連の作品はこの1作だけだったので…。昔行った、「不思議の国のアリス展」みたいに、アリス的ガジェットの横溢を期待していた私にとっては、欲求不満。------------------------今回並んだ作品の中では、魔方陣の作品は好きですね。「魔方陣」は数字を綺麗に整列させたもの。それを1から順に線で結んだ結果現れる、ランダムなようでありながら、幾何学的な図形。偶然性と作家の計画性が緊張感を生んでいる、シンプルで力強い作品です。------------------------あと、イラスト小品が並んでいたのも、色彩センスが素敵で、可愛らしくて良かったのですが…正直、日本の作家さんにも、これくらいの作品を描かれる方はいらっしゃるわけで。そういう方々が、「ポルケの影響を受けてます」って言うのなら、「なるほど」ではありますし、それこそ、これらが「アリスの挿絵」作品だったら(つまり、この絵の元になったイメージを共有できていれば)、「こういう解釈なのかぁ」と乗ることも出来たのでしょうけど…。------------------------で、他の作品なのですが…。何と言いますか、「情念」の作品が苦手なのですね、私。特に、暗い情念を、そのまま形にされると、反発を感じてしまうのです。いや、それを別な形にするために、素材を変えたり、色々されているのでしょうけど。私は、それを突き抜けた「観念」の作品が観たいのですよ。うーん、今回は作家さんと「物語」を共有できませんでしたねぇ。------------------------上野の森美術館、なんだか久しぶりにお邪魔しました。しばらく、ピンと来る展覧会がなかったので…昔は良く行ったんですけど。キュレーターとか経営方針が変わったのかな?次回は『ガンダム展』。面白いことするなぁ、とは思いますが、あまりガンダムに思い入れがあるわけではないので、行かないかなぁ…。------『ジグマー・ポルケ展』~不思議の国のアリス@上野の森美術館[会期]2005.10/01(土)~30(日)作者:ジグマー・ポルケ(1941-)★★★☆☆
October 30, 2005
コメント(0)
-
冬将軍
天気予報によると、そろそろ冬将軍がお越しになられるそうです。このぐずついた天気が去るとともに、冷え込みがきつくなるのでしょうね。ああ、そうだ。将軍様をお迎えするために、鍋の準備をせねば。鍋奉行、鍋奉行!皆様も体調には十分気をつけて。
October 30, 2005
コメント(3)
-
DIVING in UKISHIMA(IZU)
9月末、寝坊で行き損ねて(ごめんなさい)、代わりに『吉原御免状』を観たという経緯が…。という訳で、7月のマラソンダイブ以来のダイビングです。前日に小田原入り。天気予報は雨。海に入れば濡れますから、とは言え、やはり晴れている方が気持ち良いわけで。水温はそんなに低くないとのことなので、ウェットスーツ。まだドライは持ってないですからね。間に合って良かった。ここ浮島は、地形が楽しいダイビングスポット。洞窟っぽいところを抜けてみたり、迷子になってみたり(重ねてすいません)と、すっかり楽しみました。陸に上がっても、天気は悪いものの風はなく、さほど寒くないかったですし。写真を…今回は結構きれいに撮れたのがあったのですが、確認中に全部吹っ飛んでしまいました。何故?もったいないですけど、良いです。なんか。仕方ないや。多少上手くなってきた気はしますし。---------------------------潜水地:伊豆 浮島天気:曇 時々 雨気温:16℃ 水温:23℃深度:max;8.6m / Av.;4.7m透明度:10-15mDIVE本数:2本(No.21,22)お魚さん:サツマカサゴミナミハタンポクロアナゴナンヨウツバメウオミツボシクロスズメダイ
October 29, 2005
コメント(0)
-

『イサム・ノグチ展』@東京都現代美術館
飽きない。飽きませんねぇ。いつまでも作品の傍にいたい。作品を眺めていたい。刻々と変わる自然の光に、作品が揺らぐのを感じてみたい。えっと、いや、とにかく、作品をご紹介しましょうか。-----------------------------------------入ってすぐ、2mの「あかり」。岐阜提灯を原型にした、シンプルな造形。和紙を通して放射される光。とにかく大きい。温かい。見ているこちらが、引き込まれそうになります。これをエントランス空間として、本格的な作品展示に入るのですが、こんなに「解説」を読まずに作品を観たことはないかも。目が、解説を読んでいる暇なく、作品に吸い寄せられてしまうのです。*--*--*「レダ」など、金色に輝く真鍮の作品群。その光沢を持った表面が、お互いの作品を映しあい、見ている我々も巻き込んで、新しい小宇宙を作りだします。見る角度、見ている観客、見る方向、によって千変万化する、美しきフォルム。同じ流れで、不思議な木の物体「赤い種子」。壁に掲げられたドローイングは、それらを再び2次元化したような、押し花みたいなイメージの作品。そこから、「身ごもった鳥」「母と子」という温かみのある石の作品を経て、ブロンズの組み立て彫刻へ。イメージの拡散が面白い。また、ここにある小部屋では、子供たちがノグチに挑戦できるコーナーも。これは楽しそうです。*--*--*次の部屋は、同じブロンズを扱いながらも、それを折り紙のように細工して見せた、軽やかな作品群。ほとんど題名を気にせずに楽しみましたが、思ったとおりだったと言う意味で「びっくり箱」、そう言われたらそうしか見えないという意味で「リス」の両作品に軍配。そして、屋外彫刻へのつながりを感じさせる、「オリジン」「この場所」などの待つ部屋へ。石と対話して作られたとしか思えない作品群。ここから、これまた見飽きない傑作「無言の歩み」を経て、いよいよ今回の展覧会のクライマックスに至ります。すなわち、*--*--*「エナジー・ヴォイド」黙って佇む、高さ3.5m余の捻れた黒い石の円環。鈍い光沢が光を反射し、吸収しています。天井の高く吹き抜ける同じ空間を、オノ・ヨーコさんは、天空からの光とも慈雨とも見える作品で、軽やかに表現してみせてくれました。大地から立ち上がってきたかのような「エナジー・ヴォイド」は、この1作の存在感だけで空間を包み込みます。その物理的な大きさは圧倒的なのに、観ているうちに、掌に乗りそうな、自分が石の中に入ってしまいそうな、そんな不思議な錯覚を覚えます。オーディオ解説で、禅の「円相」に触れられていました。そうか「イサム・ノグチの円相」なのですね。その筆勢は勢い良く、真円としては歪んでいるのに、観ているものの心に美しい円として刻まれます。立体の円相は、観ているものを思索にいざない、自分自身との対話を促します。あるいは、これは「モノリス」なのかもしれない。サルをヒトに進化させた究極の物体は、我々をどこに導こうとするのか。天才の生み出した問答無用の作品の周りをゆっくり歩きながら、溜息をつくばかりでした。*--*--* 「オクテトラ」「プレイ・スカルプチャー」の2作の遊具は、夜&雨のため、とても遊べず。残念。でも、この触れる彫刻、というコンセプトが良いではありませんか。ヴェネチア・ヴィエンナーレを飾った「スライド・マントラ」について、本人はこう言われたそうです。「子供のお尻で完成される作品」と。*--*--*そして、そのコンセプトの究極形とも言えるのが、最後のコーナー。「大地を彫刻する」作家の面目躍如。計画のみに終わった数々の「遊び山」模型。そして、今年完成した「モエレ山公園」模型。今、ここでは、語りますまい。いつか、この地を訪れた時のために、感動の言葉は取っておきましょう。数々の作品世界に、時間を忘れて浸ってしまいました。おっと、そうそう、映像ギャラリーの奥では、「あかり」と「家具」が展示されていて、実際に座ることも出来ます。たっぷりのエネルギーを受けて疲れたら、こちらでお休みするのがオススメ。-----------------------------------------しかし、これだけ作品を並べても、彼の作品世界の一端を垣間見たに過ぎないわけで…。初期の肖像彫刻作品や、数々の庭園作品、陶芸作品、大阪万博の噴水、草月会館、などはちっとも触れられていないわけですよ。今回の作品解説ではなく、「イサム・ノグチ」を知りたければ、「BRUTUS-CASA 2004 vol47 イサム・ノグチ伝説」がオススメ。宇多田ヒカルとイサム・ノグチのコラボレーションを初め、偉業の大まかな流れを概観することが出来ます。そして、宇多田さんも読んで感動したという、ドウス昌代作『イサム・ノグチ - 宿命の越境者』は必読。ただし、これらの本を読んでいようがいまいが、そんな小賢しさとは関係なく、作品が勝手に語りかけてきます。美術館のプログラムも充実、なのですが、今から間に合うのは、11/13(日)のアート・ピクニックくらいですか。「おとなでもこどもでも」っていう所が楽しそうですね。-----------------------------------------今回は、雑誌ぴあの「おいしい御招待」で行ってきました。これは、少人数で閉館後のイサム・ノグチ展を貸切り、というスペシャル御招待♪当たった時は嬉しくて、思わず、ふぇっふぇっふぇっふぇっふぇ~、と笑ってしまいそうになりました。(『亀は意外と速く泳ぐ』より)でもね、平日の6時半までに、また、清澄白河って、あんた。あたしゃ、最近モーターショーで人ごった返してる、「海浜幕張」勤務や、っちゅうねん。電車を選べば、帰宅途中にディズニーランドの花火が見れる「京葉線」ユーザーや、っちゅうねん。分かってて申し込んだ私も私ですけど。当たると思ってなかったからなぁ…。ま、行けたから良し、です。------『 イサム・ノグチ展』 彫刻からデザインへ~その無限の創造力@東京都現代美術館(木場・清澄白河)[会期]2005.09/16(金)~11/27(日) 作者:イサム・ノグチ(1904-1988)▲▼▲▼▲
October 26, 2005
コメント(11)
-
動物王国。
上手く使いこなせていないmixiなのですが、今日自分のページを見てて苦笑。マイミクさん(3人だけですけど)の写真、全部動物!私はこちらのプロフィールと同じ写真、加えて、犬とミナミアリクイとダチョウ。あまりに微笑ましくて、ついネタにしてみました。
October 24, 2005
コメント(5)
-

「しかと」する。
2年位前に昔のHPでやった、辞書引き小ネタ再録です。「無視する」を意味する「しかと」。実は、漢字で書くと「鹿十」。元は賭博用語でした。〔花札の十月の絵柄の鹿が横を向いている〕ところから来たそうです。…いや、十月が終わる前に載せておこうかと。雑学ネタ流行りで、ご存知な方も多いのかしら?-----------------------------私は基本的に賭け事をやらないことにしています。人生自体が大きな賭けですのに、これ以上のリスクは背負えません。というのが、表向きの理由。本当は…。-----------------------------さて、おまけのうんちく。花札は、もともと西洋カルタ=トランプから派生したものです。詳しくはこちら。また、これも有名な話ですが、任天堂さんはもともと花札製造の主力メーカー。今でも商品を扱われています。任天堂さんによる花札紹介はこちら。花札を花鳥風月のイメージと絡めて解説したこんなページもあったので、ついでに。
October 24, 2005
コメント(2)
-
時間との戦い?
ようやく日記が日付に追いつきました。すぐ遅れちゃうのでしょうけど。ま、いっか。おっと、「時間と戦う」なんて、時間に喧嘩うるようなこと言ってると、どっかの帽子屋さんみたいに、ずっとお茶の時間にされてしまいます。あぶない、あぶない。「アリス」ネタでした。
October 23, 2005
コメント(2)
-
松竹『夢の仲蔵千本桜』@日生劇場
うーん、自分の教養不足を思い知らされました。が、それでも十分楽しめました。「義経千本桜」を下敷きに、その名場面を散りばめつつ、バックステージで起こるドラマを描いた作品。つまり、私は「義経千本桜」を知らないのですね。歌舞伎に詳しいわけでもないですし。しかし、しかし、早替わりあり、宙乗りあり、踊りありと、ケレン味たっぷりの歌舞伎シーンは、科白が分からないなりに楽しめましたし、バックステージでの虚実の駆け引き交じり合うストーリーは、サスペンスフルで起伏に富んで面白い。バックステージ物としての普遍性、ドラマ性は、殿堂入りのレベルの高さなのだろうと。狂気ギリギリで綱渡りを演じる役者魂、「格式」を重んじる守旧派との対立、それぞれが心に秘めた確執。生と死、光と影、ショー・マスト・ゴー・オン。---------------------------------能と歌舞伎、文楽は、もう少しちゃんと勉強するようにしましょう。中途半端に「知識」は詰め込んでいるのに、芝居を観るのにちっとも生かせていないですもんねぇ。今回のお芝居にしても、ストーリーの二重性だとか、歌舞伎ネタとかが分からない。そもそも、あの独特の科白回しとか、聴き取りきれないわけですよ。もう、何て言うか、もったいない、と。---------------------------------追記。ドラマ「古畑任三郎」の堺正章さんの回でも、堺さん演じる歌舞伎役者によって、狐忠信のシーンが演じられていましたね。松本幸四郎さんと市川染五郎さんの親子が共演されているお芝居を観たのは「By Myself」以来でした。えっと、両方三谷幸喜さんネタですね…。---------------------------------松竹『夢の仲蔵千本桜』@日生劇場2005.10/06 - 10/27出演:松本幸四郎、市川染五郎★★★★☆
October 22, 2005
コメント(7)
-
『岡本敏子のメッセージ』展@岡本太郎記念館
早いもので、岡本敏子さんが亡くなられて、半年が経ちました。本当にエネルギッシュな方だったので、未だに亡くなられたことが信じられません。青山あたりを歩いていると、ひょっこり出くわしそうな、そんな気がします。-------------------------------------------------根津美術館まで寄ったので、岡本太郎記念館まで足を延ばしてきました。この記念館は、岡本太郎氏の旧アトリエを、記念館として開放したもの。生命力に満ち満ちていた作家のエネルギーを、放射し続けている異空間です。-------------------------------------------------『岡本敏子のメッセージ』ということで、今回は、今までの企画展に敏子さんが寄せられた「メッセージ」「企画意図」を、各展の代表作とともに。しかし、えっと、常設はちゃんと観れたのですが、各作品は全然観られませんでした。今回は、上京していた父母を伴っての来館だったのですが、父親がさっさと飽きちゃって、やたら急かすのですもの。(父は、丁寧できちんとした絵が好きなのです。)うーん。やっぱりなぁ。お昼もまだ食べてないから、お腹も空いてますもんね。まぁ、私はまた行くから良いです。想定内、想定内。本当は、もう少し、ゆっくり、哀悼の気分に浸りたかったのですけど…。-------------------------------------------------最近、よしもとばななさんとの本が出されましたよね。『恋愛について、話しました。』恋愛モノは苦手なのですが、敏子さんのご本なら買って良いかな、と。ところが、この本は記念館内では売っていませんでした。あらら。せっかくなので、ここで買おうと思っていたのに。『 岡本敏子のメッセージ 』展 @岡本太郎記念館(表参道)[前期]2005.10/05(水)~12/26(月) [後期]2006.01/05(木)~04/03(月) 作者:岡本太郎&敏子▲▽▲▽▲
October 22, 2005
コメント(6)
-
雨の降る日は天気が悪い
今年の10月は雨の日が多い上に蒸し暑く、季節がずれ込んでしまったかのようです。表題は、「荒城の月」作詞者、土井晩翠先生の随筆集より。仙台の「晩翠草堂」を訪れた時に教えてもらいました。題名から面白そうなのですが、絶版本とのこと。岩波文庫あたりから、出ないかしら。10/19は、命日「晩翠忌」です。http://www.d-score.com/ar/A03032801.html
October 19, 2005
コメント(0)
-

『特別展 国宝 燕子花図』@根津美術館
言わずと知れた名品『燕子花図』。「国宝」の基準って良く分かりませんが、この作品が圧倒的な訴求力を持った作品である、ということには賛成です。日本文化を、絵画芸術の面から紹介するとなると、琳派、浮世絵、水墨画は外せないでしょう。浮世絵の特徴を構図に求めるならば、琳派の特徴はデザイン性にあります。そのデザイン性の行きついた表現とも言えるのが、この『燕子花図』。ぼってりとした一面の金をバックに、リズミカルに並ぶ燕子花。葉は青々と瑞々しく、花は端麗に咲き誇る。ただ無造作に燕子花を並べただけに見えるのに、何とも言えず美しい。…いやはや、これ以上言葉を重ねても、野暮に成り下がるばかり。今回の展覧会に出品された、他の作品に触れるとしましょう。-------------------------------------------------今回、一番印象に残ったのは、七福神を描いた2作。簡単な描線で表現された、何とも言えない福々しい笑顔が、こちらの微笑を誘います。なんか、漫画みたい。また、今回は草花の図が充実していました。どれも丁寧で、見ごたえがありますが、目を引くのは、着物に描かれた草花図。とても端整で、溜息が出そうなくらい色合いも上品。-------------------------------------------------常設サイドで気になったのは、何と言っても、「蟹の蓋置」ですね。すごいですよ。今にも柄杓を載せたまま歩き出しそう。…しかし、こんなの、どうやって扱うんだろう。てか、何と合わせれば良いのかしら?そんなことを考えて楽しめるようになったのも、お茶を始めたおかげですね。-------------------------------------------------で、庭ではお茶会が(いや、参加はしないですよ)。この庭、本当に広くて、いつ来ても迷子になりそう。散策していたら、水面に浮かぶ舟発見。小屋造りになっているってことは、あれもお茶室?どなたも使ってらっしゃいませんでしたが…風流だなぁ。これで、もうちょっと晴れていてくれればねぇ。なお良かったのですが。-------------------------------------------------前期・後期に分かれています。後期には、八橋蒔絵硯箱も出品されるそうですので、そちらの方が良いかも。岡本太郎記念館、スパイラル・ホール(展示替中でした、残念。)、ブルース・ウェバー展も近所です。『特別展 国宝 燕子花図』- 光琳 元禄の偉才 -@根津美術館(表参道)[前期]2005.10/08(土)~10/23(日)[後期]2005.10/25(火)~11/06(日)作者:尾形光琳(1658-1716)◆◇◆◇◆
October 16, 2005
コメント(0)
-
茶会記:不白敬和会@護国寺
10/15は、お茶会でした。先生が席を持たれるので、ちょっと早めにお水屋入り。---------------------------------------早いもので、お稽古を始めて4年目になりました。物覚えが悪いもので、ちっとも上達しないままですが、なんとか続けています。私が習わせて頂いているのは、江戸千家。「三千家」(表千家・裏千家・武者小路千家)との関係で言えば、表千家の流れを引く流派です。ま、流派が何であれ、お茶は「服の良きよう」頂ければ良い訳で。強いて言えば「表さんのでも、お裏さんのでも、良いなぁと思ったお道具は使ってよいのよ。」というこだわりのなさが、「江戸」の小粋さ、なのかしら。---------------------------------------さて、天気予報では雨となっていたので、着物姿には酷だなぁ、と思っていたのですが、なんとか終日天気が持ってくれて助かりました。一時ぱらっと降っていたようですけど。舞台は護国寺。文京区音羽にある名刹です。「月窓軒」に川上閑雪先生、「艸雷庵」に小川宗洋先生。「牡丹の間」に清楽会さんが入って、中村宗正先生は「不昧軒」。20名くらいが入れる、程々のお茶室です。それにしても、蒸します。気温はそんなに高いと思わないのですけど、どうにも朝から汗が。午後はさらに人いきれで室温が上がり、ちょっと障子を開けてのおもてなしとなりました。会記に興味がある方は、こちら。写真はないです。撮っておけば良かったですねぇ。---------------------------------------10時から第一席が始まって、お茶のお運びからお手伝い。いやぁ、緊張しますねぇ、やっぱり。しかも、袴の裾が気になって仕方ない。私の順番は5番目。前の方のお半頭さんをなんとか務めて…。うーん。本茶碗の正面が分からない。ごまかせたことを祈りましょう。いよいよ本番。お正客には、何度かお見かけしたことのある、ちょっとお若いおば様。お次客には、その娘さん、かな?何となく見知った顔なので、気が楽です。問題は、客席の角のほうにいる(らしい)、私の母。そう、偶々のタイミングで上京していたので、お茶会に呼んでいたのです。母の前でちゃんとお手前を披露するのは初めて。実家で、普通に点てて飲んだりしたことはありますけど。ま、でも、気にせずに、ご挨拶。なるべく客席を見ないようにして、亭主の位置に座ります。準備して一礼。道具を清めて、お茶を入れて、お茶を点てて出す、と。で、道具を清めて、お片付して、拝見を所望されたものをお出しする、と。平たく言って、これだけ、なんですよね。はは。それが難しいのですが。蓋置きになかなか蓋が乗らなかったのと、袱紗をつけるタイミングが分からなかったことを除けば、上手く出来たかな、と。お半頭さんが、大ベテランの方でしたので、安心してお手前が出来ました。後ろで、お茶がこぼれるハプニングがあったようですが…。気にしている余裕はありませんでした。---------------------------------------自分のお手前が終わった後は、先生のお言葉に甘えて、母と共に、おしのぎ(お昼のお弁当)を頂いて、食事処から廊下で繋がっている、清楽会さんの所へ。えっと、待ち時間、板間で正座していたせいで、本番の最中に足が痺れてしまいました。そういえば、最近久しく足が痺れることなかったなぁ。お稽古始めて最初の一年くらいは、自分の手前の最中でも痺れてましたから…。母はその後、他の2席を回り、私は水屋に帰って、お手伝いの続き。最後の回で、自分の所でお客さんをさせて頂いたのですが、いやぁ、美味しかったです。及ばずながら、お片づけの手伝いをして、解散。最後まで天気がもって良かったです。それにしても、例年より疲れたのは…母がいたせいですね、きっと。
October 15, 2005
コメント(2)
-
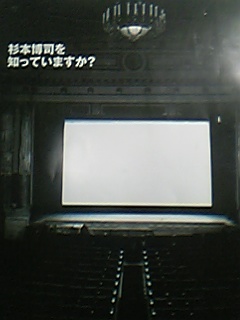
『杉本 博司:時間の終わり』展@森美術館
時間と空間の狭間に「美術」という罠を仕掛けるモノクロの狩人。「一瞬を切り取る」のではなく「一瞬を作り出す」、時を操る時空の魔術師。杉本博司さん、今回は初の回顧展だそうです。世界では日本が最初で、NYなどは展示量が3割カットだそうですから、世界に先駆けた、しかも完全版として、主要シリーズが出揃っているとのこと。というわけで、今回は主要シリーズごとに感想をば。-------------------------------------------------「Conceptual Forms」幾何学立体を撮って、大きく引き伸ばしたシリーズ。数学的美に満ちた抽象図形が、幻想的モダンの世界への入口を飾ります。これらの被写体となった「作品」は、数年前、「東京大学120周年記念展」で一部を見たことがあります。100年近くを経てまだ滑らかに動く歯車や、何万年経とうと普遍である数学模型は、遥かに「真理」に近しい存在なのかも知れません。-------------------------------------------------「Dioramas」ジオラマを、モノクロで撮ることによって、その過剰な装飾=嘘臭さを消してしまう、と言う作品。どこかの一瞬を切り取って造られたジオラマを、一瞬を切り取る写真で写すことによって、「リアル」を表現しようという、その発想がそもそもありえない。この発想の飛躍と、モノクロの陰影を扱うテクニックの確かさが、観ている者を不思議な浮遊感に導きます。-------------------------------------------------「Seascapes」世界各地の水平線を、全く同じ構図で撮ったシリーズです。これは、このシリーズは、すごい。あえてモノクロで撮っているからこそ、見えてくる普遍性。もし、カラーなら、海の色の違いを楽しむ作品になっていたでしょう。白黒のグラデーションによって「いずこもおなじ」を表現することで、これらの作品群は、人類の深層意識のレベルまで降りてきます。能舞台を中心に展開される、世界の海の持つグラデーションのリズムが、我々を心地良い酩酊感にいざないます。-------------------------------------------------「Portraits」肖像画なり絵画から起こして造られた蝋人形を、肖像画のように撮ったシリーズ。私が杉本さんの作品で初めて見たのはこのシリーズでした。一瞬「え、この時代に写真なんてあったの?」と思わされて、とにかく度肝を抜かれ、そのあと笑いが込み上げてきたのを覚えています。「蝋人形という虚」と「モノクロ写真という虚」が掛け合わされて、「実」に見えてくるという倒錯。この意味では、「ジオラマ」のシリーズに似ていますね。現代の人物についてはもう少し複雑。本物を写真に撮るのではなく、蝋人形を写真で撮ることによって、彼らは歴史上の人物と同列に並べられ、普遍化されます。それは能面の写真に似て、どこかで「感情」「表情」が昇華され、本物を撮った写真とは少し違う、別な像を我々の中に結びます。-------------------------------------------------「Theaters」劇場でシャッターを開きっ放しにして、フィルムを感光させるのだそうです。そこに写るのは真っ白なスクリーンと、それによって照らし出された、劇場の風景。ドライブインシアターのバックには、夜空を動く星が写っているのも面白い。余談ながら、私なら、映画の題名もあわせて併記するなぁ、と思いました。つまり、クラフト・エヴィング商會さん風に「この写真をじぃっとご覧あれ。この中には、なんと丸々一本の映画がおさまっておるのです。」っていうのが私の好み。-------------------------------------------------「Architecture」有名建築を、わざと焦点をぼかして撮ることで、建築家が最初に持っていたであろうイメージを再現・具現化した作品、だそうです。これは一方で、我々の「記憶」を作品化している、という言い方も出来ます。面白い中に、どこか、「記憶」のもどかしさを思い知らされる作品でもあります。-------------------------------------------------その他の作品について-----入口にある、マルセル・デュシャン「大ガラス」に捧げられたオマージュ作品は、自身の作品が、その系譜に連なることの宣言、と捉えたら良いのでしょうか。表裏で白黒を反転させているのは、ポジーネガのイメージ。-----松林図は…個人的には再度チャレンジして頂きたいですねぇ。杉本さんなら、もっともっと「本物」(絵なんですけど)に近づいた写真(本物なんですけど)が撮れるのでは、という期待があるのですよ。そう、この人の手にかかれば、「写真による水墨画」は可能だと思います。いつか、その完成作と、長谷川等伯の絵を並べて見せる展覧会をやって頂きたいなぁ、と。-----護王神社社殿は、日本文化に対する造詣の深さと、センスの良さが見事に止揚された作品(?)本殿に架かるのは、氷のきざはしを連想させる透明な階段。この階段は地下墳墓を想起させる、地下の巨石空間へと連なっていきます。しかし、この階段を下ることが出来るのは、光のみ。別な入口から入った参拝者は、帰り道、遥かなる水平線を臨むことになります。(ここで展示されている模型の通路部分からも海を見ることが出来ます。)彼岸と此岸を結ぶ多様なイメージを美しく配置して、新しい時代の拝殿を創りあげた手腕は、お見事。いつか本物を見に行くのが楽しみです。-------------------------------------------------杉本さんは古美術蒐集家としても有名で(主に平安時代らしい)、そのコレクションとのコラボレーション展覧会もやったことがあるそうです。それは機会があれば、是非観てみたいですね。「BRUTUS」9月号に詳しい解説が載っています。安藤忠雄先生との対談など、かなり充実した内容。展覧会カタログは6000円と少々高価なので、600円のこちらがオススメ、かな。『杉本 博司:時間の終わり』- HIROSHI SUGIMOTO : End of TIME -@森美術館(六本木)2005.9/17 ~2006.1/9(月・祝) 作者:杉本 博司★★★★★
October 10, 2005
コメント(3)
-
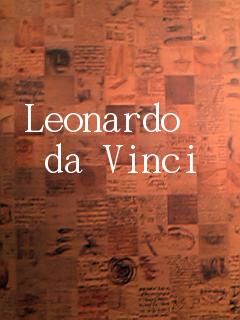
『レオナルド・ダ・ヴィンチ展』@森アーツセンターギャラリー
「天才」という言葉が、これほど似合う巨人がいるでしょうか。土木工学から航空工学、自然科学に通じ、絵を描けばモデルの魂まで写す。その知識は当時の学問領域を遥かに超えて、ニュートンやガリレオ以前にキリスト教の固定観念を打ち破り、世界の成り立ちまで到達していました。人類史上、神に最も愛された男、という形容もあながち間違いではないでしょう。その天才は、当時の最先端メディアであった紙に、自らの思想を、アイデアを書き残していました。そのうちの一部、現在、ビル・ゲイツ氏が所有する「レスター手稿」、日本初公開です。-------------------------------------------------展覧会の構成が秀逸。最近構成の上手い展覧会が増えましたねぇ。嬉しい限りです。レスター手稿は、主に自然科学の基礎に関する論考からなります。構成は、天文・地学・水の3つに分けられるということで、第一室はそれに基づいた構成になっています。もう、この部屋の「実験」設備がねぇ。何て言うか、またたびですよ。月球儀、波紋実験(あれとは違います。ただの水の波紋です。)に、水流実験、空気圧と水圧の関係、組み立てられるブロック、ああ、書いているだけで、胸がドキドキ。なんて、浮かれてしまいましたけど、観察眼の鋭さと着眼点の的確さを味わうことの出来る、素晴らしい展示でした。-------------------------------------------------そして、次の部屋では、「レスター手稿」についての解説。鏡を使った演出も楽しい。そう、これらの手稿は全て鏡文字で書かれていたのです。だから、鏡に映さないと、字を読むことが出来ない。どんな頭脳が、そんな手法を可能とするのか。そしていよいよ。その「レスター手稿」実物とご対面です。両面見られるように配慮された展示、手稿を傷めないように制御された光量。この展示風景だけでも、一見の価値あり。しかし、いや、あの、正直、両面見られても、鏡文字じゃなかったとしても、イタリア語は読めない…。うー。図の部分を見て納得するしかないですねぇ。直筆を見られて感激!というより、ただぽかんと、すごいなーと呟くばかり。-------------------------------------------------次は再び科学関連。狭い部屋の中に、飛行機、潜水兵器、数学図形の考察、ありとあらゆる知識が、これでもかと詰め込まれています。宙に吊られた、飛行装置や幾何学立体に頬が緩みます。そして壁いっぱいの年表と、圧巻のファクシミリ版(復刻版)の展示。67年の人生の中に、どれだけの業績を詰め込めば済むのだろうかと。世界のどれほどの学者が、どれほどの時間をかければ、彼の業績の全貌が見えるのでしょう。-------------------------------------------------とどめは『絵画論』にある「絵画も学問である」の一言。しびれますねぇ。飽くなき探究心と好奇心、その実践であり、研究成果としての絵画。彼の作品の優美さは「真理」に触れているからこそ、なのかもしれません。-------------------------------------------------実は、ミーハーな私は「ウィトルウィウス的人間」(円の中に人体が入っている図です)とかの原画が観られるかなぁ、なんて期待をしていたのですが、なかったですね。どちらかと言うと、基礎科学とそれに基づく論考が中心。でも、十二分に満足と納得のいく展覧会でした。『レオナルド・ダ・ヴィンチ展』 直筆ノート「レスター手稿」日本初公開@森アーツセンターギャラリー(六本木)2005.9/15(木) ~11/13(日)作者:レオナルド・ダ・ヴィンチ (1452-1519)★★★★☆
October 10, 2005
コメント(3)
-

『ブラウン展』@AXISギャラリー
ブラウン…髭剃りメーカー?という疑問は、あながち外れていませんでした。でも、何て言うか総合メーカーだったんですね。ブラウン社 HP髭剃り-刃物の連想で、ミキサーは納得しましたけど、TVやレコードプレーヤー、ビデオカメラに時計。日本で言うと、ナショナルとかサンヨーとかみたいな感じですか。「プロダクト・デザインとは何か」というのが、イサム・ノグチ展を観に行くに向けての私自身の宿題です。自分が物を買うときの基準は何?と考えた時、機能性とシンプルさは重要な要素。-------------------------------------------------で、ごたごた私が言うより、会社のコンセプトをご紹介した方が早いですので。「ブラウンのデザイン哲学」の7項目は下記だそうです。革新性 :デザインは、視覚形態における総合革新を表現する。 機能性 :機能的特性と有用性を支援するデザインアプローチ。 識別性 :傑出した製品デザインは、好感を持たれ、自然である。 細部にわたる品質 :細部にわたるデザインと視覚的表現への配慮の基準を設定する製品デザイン。 視覚的な明快さ :視覚的なシンプルさと説明を要しない自明さをもたらす基本要素。 約束を守る誠実さ :デザインは、開放性、総合性、自信を表現する。 審美性 :デザインは、美しさと視覚的バランスという普遍的な目的を達成する。 -------------------------------------------------うーん。なるほど。ブランドってこういうコンセプトで作られているのですね。なんか、もう付け加えることないや。使いやすくて美しい。無駄がなくてバリアフリー。温かみがあって頑丈。使う人のことを考えるって、言葉は簡単ですけど、難しい。それにしても、この哲学って、日頃の仕事にも通じるよなぁ…。全然程遠いところにおりますけど。-------------------------------------------------AXISギャラリーは、六本木から東京方面に向かった右手にあります。ビル全体に、デザイナーズショップが入って、かなりお洒落。うーん、私も本社勤務なら近いんですけどねぇ。『ブラウン展 - 形を超えたデザイン』@AXISギャラリー(六本木)2005.9/22(木)~10/16(日) 作者:ブラウン社★★★★☆
October 10, 2005
コメント(0)
-
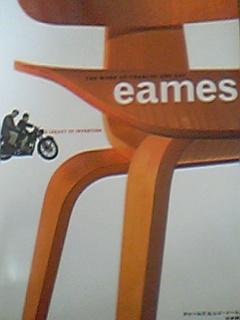
『チャールズ&レイ・イームズ』展@目黒区美術館
家具だってアートだ、ということを誰が始めたのか私は知らないのですが、ジョージ・ナカシマ、チャールズ&レイ・イームズらが、同時代に活躍していたことは、大変面白いと思います。プロダクト・デザインという括りで言えば、イサム・ノグチも、バウハウスの運動も、含めてしまって良いかも知れません。ロシア(ソ連か)のロトチェンコが活躍したのも、同時代と言って良いのかな?そのキーワードは、「シンプル」と「機能性」でしょう。削ぎ落とした上で、機能性を追及し、一ひねりされたデザインセンス。かっこ良くて使いやすい、お洒落の効いた大量生産品。イサム・ノグチが彫刻家のスタンスで「あかり」をデザインしたのに対し、チャールズ&レイ・イームズのアプローチは非常に理詰めです。しかし、その上に加わる遊び心がとても温かい。デザインセンスに、使い心地の良さが加味されることで、生き生きとした「プロダクト」が生み出されているわけです。------------------------------------1Fにある最初の展示室は夫婦の略歴を紹介。2Fに上がった所に、合板を加工するための手作り機械が置いてあります。熱を与えて合板を加工する、魔法のような機械。そっかぁ、新しい素材を使いこなすためには、工具から手作りなのですね。さて、順路右手は、そのイメージの源泉をたどる部屋。その雰囲気は、まるでおもちゃ箱を引っくり返したかのよう。様々な写真、様々なイメージの断片に、「プロダクト」の合理性と非合理性の両側面を垣間見ることが出来ます。------------------------------------階段の所に戻って、左手は、実際のプロダクトを拝見するコーナーになっています。いくつかの「作品」には座ることも可能。いわゆる「代表作」が並んでいて、思わず、「へぇ、これも?」の連続。楽しいのは、壁にかけられたパネル写真。なんと、椅子の脚をピン代わりに、壁に二人が張り付けお二人とも、仕事も含めて、生きることを楽しんでいたのだなぁ、と微笑ましくなります。------------------------------------ちょっとびっくりしたのは、科学教育映像も手がけていたことでした。上から覗き込む形で鑑賞する独楽の映像は、まるで万華鏡を覗いているみたい。その彩りの鮮やかさと、不思議な独楽の「生態」についつい引き込まれてしまいます。お見事。そして、快作「パワー・オブ・テン」。公園でピクニックをしているカップルを、上空からの俯瞰で1メートル四方切り取って見せます。ここからカメラはずっと上空へ引いていくのです。どこまでも。1m四方-10m四方-100m四方-1km四方-10km四方-100km四方-スピードはどんどん上がっていって、宇宙から見た地球、太陽系、銀河系、さらにカメラは遠ざかり、銀河系すら星団に見えるようになってから、また地上へと戻ってきます。そして今度はミクロの世界へ。男の手に当てられたフォーカスは、細胞レベルからどんどんミクロに迫り…。どうやって撮ったのだろう、という疑問は、パネル展示で氷解されますからご心配なく。それにしても、そのアイデアといい、映像の整合性の取りかたといい、もう、素晴らしい、としか言いようがありません。------------------------------------再び1Fに戻って、今度は椅子の耐久実験装置と、「パワー・オブ・テン」のパネルの続き、他の映像作品。この展覧会の素晴らしい点の一つは、映像作品の多くをイームズ・チェアに座って眺められることですね。映像を全部観ると、それだけで2時間くらいかかるのではないかしら?「つくる」ということを考えさせてくれる、充実した展覧会でした。-------------------------------------------------それにしても、アグレッシブですよね、目黒区美術館。この展覧会の前は、「スター・ウォーズ展」ですよ、やってたの。いやはや、やるなぁ。ところで、数年前に、上野でイームズ展ってやってましたよね?あの時は行かなかったのですけど…。ま、いっか。『チャールズ&レイ・イームズ ~創造の遺産~』@目黒区美術館2005.10/8(土) ~12/11(日)作者:チャールズ&レイ・イームズ◆◆◆◆◇
October 9, 2005
コメント(2)
-
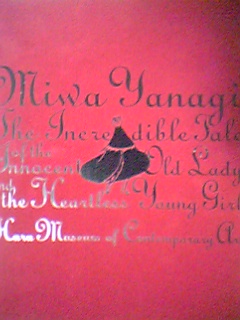
in 『やなぎみわ展 』@原美術館
太宰治曰く「人間のうちで最も残酷なのは、えてして、このたちの女性である。」「女性にはすべて、この無慈悲な兎が一匹住んでいる」 (『お伽草子』カチカチ山 より)----------少女という存在は、いつでも美しくて、どこかちょっぴり残酷だったりする存在です。それは、子供の無垢さが、善悪を超越して存在するのことの、延長としての残酷さ。少女アリスは、不思議の国で、何気なくネズミに「猫のダイナ」の話をしますが、そこに悪意はありません。でも、それはネズミにとって、とても残酷なお話。こういう「無垢な残酷さ」を子供はみんな持っているのです。----------さて、しかし、寓話の中の子供達は、親の意向を反映してか、何故か「素直で良い子」が多く、一方、魔女は老婆と相場が決まっています。==========やなぎみわさんの、「寓話」 シリーズは、この「少女=無垢 / 老婆=無慈悲」の図式に揺さぶりを仕掛ける、挑戦的と言って良い作品。寓話を下敷きに、「老醜の仮面」を被った少女が老婆役を演じて、物語の1シーンがモノクロの写真によって切り取られます。----------しなやかな手足を持つ「魔女」は、その仮面によって、我々の意識下で「残酷な老婆」に変換されますが、その過程で気付かされるのです。「老婆」もまた、かっては「少女」だったことに。「残酷な少女」の延長線上に「老女」が存在することに。----------そして、それに気付き、写真を改めて見る時、我々の良く知っているはずの物語は、別な意味を持って立ち現れてきます。写真の美しさと裏腹に、「封印された物語」は、ゾッとするほど妖艶で、恐ろしい。----------原作を知らない寓話がいくつかあったのが、残念でした。こういうのは、元ネタのイメージがちゃんとあればあるほど、そのギャップを楽しめる訳ですから、自らの無知を恥じるしかないですねぇ。==========「砂女」 シリーズは、一見、不気味でありながら、どこか郷愁と親しみを感じさせる不思議な作品群。写真が数点展示され、映画が2本上映されています。----------1Fの映画はテントの中に入って、テントから外の光景を覗きみた映像を見る、というもの。映し出される風景も示唆的で、自分が「砂女」になった気分を味わえます。----------2Fで上映されている映画も、寓意に富んでいて、映像的にも結構面白い。祖母が語る実体験の昔話、という体裁を取っているのですが、ラストの祖母のセリフがすごい。そして、それに対する「私」の反応 -「私は出会えるだろうか。私の砂女に。」こそが、今回の展覧会に流れるテーマを示唆しています。すなわち、「少女」の「母」からの継承と自立。そう、自らの「砂女」と出会って、少女は大人になっていくのです。==========階段の所に掲げられた、大きなカラー写真パネル作品「AI」は、「My Grandmothers」 シリーズの1作。パネル脇の詞書とセット。この詞書には、思わずにやりとさせられます。こちらは、本人が本人の50年後を特殊メイクで演じているのだそうです。==========それにしても原美術館の居心地の良さは、すごいですね。自転車で、いや、歩いてでも行ける ご近所美術館なのに、今まで行っていなかったことが悔やまれました。『やなぎみわ展 - 無垢な老女と無慈悲な少女の信じられない物語』 @原美術館(品川)2005.8/13(土)-11/6(日)作者:やなぎみわ◆◆◆◆◆
October 9, 2005
コメント(2)
-
『チャーリーとチョコレート工場』
オープニングからティム・バートン節全開!次々に出来てゆくチョコレートを追うオープニングから、カメラは一気に街外れの主人公の家へ。その傾き具合といい、妙な既視感といい、ここまでで既に凡百の映画とは違う、妖しい魅力満載です。その期待に応えてなお余りある出来映え。ようやく、「あの」ティム・バートンがスクリーンに帰って来ました。-----------------------------------原作はロアルド・ダールの名作『チョコレート工場の秘密』。子供達を魅了してやまないウォンカのチョコレート。産業スパイ事件があってから、工場への出入りが閉ざされたにもかかわらず、世界最大の工場はいつの間にか再開され、夢のようなチョコレートを世界中に出荷していました。その工場のある町に住むチャーリーの家はとても貧しくて、彼の楽しみは誕生日にだけ買ってもらえるウォンカのチョコ。そんなある日、ウォンカ氏が世界中の子供から5名を紹待する、そのチケットはチョコの中に入っていると発表したものですから、世界中が大騒ぎ。ずっとお菓子を食べ続けているいやしんぼ、甘ーいパパにおねだりしてチョコを買い占めてもらったわがまま娘、ガムをずっと噛んでいる負けず嫌いの女の子、TV好きで現実主義者のきかん坊、と続々に当選者が発表される中、最後の1枚を彼は手に入れることができるのでしょうか。そして、まさしく夢のようなチョコレート工場の世界の扉が開かれます。「お菓子の家」に憧れなかった子供はいないでしょう。その原作を忠実に再現した世界観、キモかわいい(?)ウンパ・ルンパ達。部屋毎にテイストの違う音楽が、映画を彩ります。そして、ちょっとアドリブの効いたラストヘ。-----------------------------------いやはや、帰ってきたバートン×ジョニー・デップ×児童文学の名作 の答えは、「傑作」でした。実はこの作品の前に、同じ原作を映画化した、71年の『夢のチョコレート工場』という作品があります。今回の映画が封切られる前に、妹が借りて来たのを見せてもらったのですが、これも結構な名作。こちらのウォンカ氏もウンパ・ルンパ達もなかなかです。原作から引かれたもの、足されたものを比べると、今回の方が、原作に忠実でかつ原作を掘り下げている感があります。その掘り下げた部分のイメージに息吹を与え、作品を支えているのが、子供以上に子供らしい役どころを演じて魅せるジョニー・デップと、子供心に怖さと温かさを感じさせるクリストファー・リーの二人。いや、作品全体を通じて役者のレベルの高いこと!ティム・バートンの横溢するイメージと、それを形にする役者・美術・音楽。何とも言えない独特のユーモア・センスも秀逸。しかし、ホント、クリスマスが似合う監督ですねぇ、と。公開遅らせて、クリスマスまで引っ張ってファミリー映画にしちゃえば…あ、私みたいなのが観に行きにくくなるや。-----------------------------------『チャーリーとチョコレート工場』 - "Charlie AND THE CHOCOLATE FACTORY"2005年 ワーナー 115分監督:ティム・バートン出演:ジョニー・デップ,フレディー・ハイモア,ディビット・ケリー,ディープ・ロイ,クリストファー・リーhttp://wwws.warnerbros.co.jp/movies/chocolatefactory/♪♪♪♪♪
October 7, 2005
コメント(3)
-
『ルパン』
かの有名な怪盗紳士がこの世に登場して100年。銀幕の世界を舞台に、華麗なる怪盗の活躍が蘇りました。産業革命の狭間、フランスが最も華麗だったベル・エポックの時代を背景に、謎を追い、闇を駆ける怪盗紳士。女性に弱くて紳士な主人公、美しく妖艶な「魔女」、ライバルの意外な正体、フランス王家の秘宝を巡る冒険。語られざる、「ルパン・ザ・ファースト」の物語は、ひたすらロマンチックな冒険活劇でした。-----------------------------------うーん、あの、小学生の頃は断然、ホームズ&明智小五郎派でしたから…「III世」に親しんできた世代ですし。ルパン物が、本格ミステリの宝石箱だと知ったのは、有栖川有栖先生のエッセイで、でしたので。あー、つまり、何が言いたいかというと、そんなに原作を読んではおらず、あまり思い入れなく映画を楽しみました、ということです。ミステリファンとしては、本格テイストが足りないなぁ…。まぁ、そういう期待は最初からしてなかったですけどね。でもって、フランス映画なのに、何故かテイストはハリウッド。派手なテロシーンは現代世相の反映か、はたまたラストシーンへの伏線か。しかし、別にそこまでしなくても良いんじゃない?と思ってしまいました。とは言え、「全編英語」じゃないだけでも、フランスで作った意味はあるのかしら。(「ハリウッド」で作られると、ロシアが舞台でも全編英語になりますから…ある意味スゴイですけど。)カルチェも全面協力らしいですし。そうそう、宝石とか小道具とかは本物、ということなのですが、残念ながら私はこちらもそんなに興味ないんですよね…。-----------------------------------産業革命を受けて変わりゆく世相を、物語に上手く取り込んで、「時代劇」にしているところは、非常に面白かったです。特にラストシーン、架空の物語であるルパン譚と現代史とが結びつく一瞬。ルパンの活躍した時代背景ってそうなのか、と目から鱗でした。パンフで「ルパン・ビギンズ」というフレーズが使われてましたが、言い得て妙だと思います。でも、やっぱり、個人的には、原作をシャッフルして「一発芸の大作」として撮るのではなく、原作に忠実に、じっくりと1作ずつ丁寧に撮ってくれた方が嬉しかったなぁ。-----------------------------------------------『ルパン』-"Arsene Lupin"2004年 フランス 132分監督:ジャン=ポール・サロメ出演:ロマン・デュリス,クリスティン・スコット=トーマス,エヴァ・グリーンhttp://www.arsene-lupin.jp/★★★☆☆
October 7, 2005
コメント(0)
-
やさしさ~加納朋子先生によせて
やさしさって、想像力なんだと思います。相手のことを思いやるというのは、言葉では簡単でも、ちゃんと相手の立場に立つことが出来ないと難しいこと。だからこそ、想像力こそが、やさしさの源なんだと思うのです。自己啓発セミナーなんかで使われる教材で、「電車の中で騒いでいる子供を注意しない父親」というネタがあります。「この状況を見て、あなたならどうしますか」と、グループ討論をやるのですが…さて、あなたならどうしますか?----------------------------------『ななつのこものがたり』出版記念のサイン会に行ってきました。私が敬愛してやまない、加納朋子さんと、その挿絵をずっと手がけられている菊池さんの合同サイン会です。実はサイン会って、行き合わせたことは何度かありますが、こうやってちゃんと貰いに行くのは初めて。池袋ジュンク堂で2時からだったので、いつもは午後に行くお茶の稽古を午前にさせて頂いて、着物姿のまま駆けつけました。(いや、山手線に乗って行った訳ですから、「駆けつけた」ってのは、比喩ですよ、むろん。)時間通り♪と思ったら、既にすごい人の列。一階がサイン会場で、地下への階段から列が始まっているのですが、地下のマンガ売り場をぐるっと一回り。何となく嬉しくなりながらも、線の細そうな先生がこの数をこなされることを思うと、ちょっと心配と申し訳なさを感じました。2時から始まって、待つこと1時間ちょっとくらいでしょうか。ようやく1階へ。先生は、真っ赤な…ワンピースで良いのかしら?を上品に着こなされ、微笑を絶やすことなく丁寧に挨拶をかわされていらっしゃいました。想像以上に気さくで、とても落ち着いた雰囲気の、おねーさん、という感じの方でした。もうねぇ、自分が何言ったかとか覚えてないです。皆さんお土産とか用意されていて、ああ、私も何か買ってくれば良かったかな、と思ってみたり。結局2時間くらい、サインを続けられていたわけですよね。すごいなぁ。私はサインを頂いた後、お昼を食べに行って、戻ってきたら、ちょうど片付けが終わったところで、お友達の方々と談笑されていました。それを横目に見て、3Fあたりをうろうろしていたのですが、その後4Fに行ったら、奥の喫茶店で、お店の方々も交えてお話されているのをお見受けしました。うーん。羨ましい。かなうなら、参加したかったです。でも、何を話して良いものやら。きっと何も喋れなくなってしまうに違いない。----------------------------------さて、最初の話に戻りましょう。この話の「真実」はこうです。男は妻を亡くした帰りで、呆然として、子を叱る気力もなかったのです。母が死んだことを理解できていない子供たちは、久しぶりの遠出にはしゃいでいたのでした。この「真実」を聞いて、聞く前と同じ答えで臨めますか?----------------------------------加納朋子さんの作品は、こういう「やさしさ」に満ちています。人を気遣うということ。相手の気持ちを思いやる、ということ。ミステリの形式を借りた その作品群は、どのメルヘンよりもやさしくて、どの人情話よりも人間に向ける眼差しの温かさが感じられる、珠玉のような物語。今回の『ななつのこものがたり』は、デビュー作『ななつのこ』のスピンアウト・ブック。『ななつのこ』で紹介された架空の絵本が、本になりました。え?ストーリー紹介?しませんよ。そんな野暮なこと。ただ、『ななつのこ』は先に読んでいた方が良いでしょうね。『ななつのこ』は抜群に名作です。これを読んだら、『ななつのこものがたり』も買わずにいられなくなること、請け合いです。ちなみに。私は加納朋子さんの作品集の中では『掌の中の小鳥』が一番好きです。なお、『ガラスの麒麟』を読んでしまうと、「世界で一つだけの花」が涙なしで聞けなくなりますのでご注意あれ。
October 1, 2005
コメント(0)
-
『Sin City』(シン・シティ)
This Story is based on the American Comics - Graphic Novels , "Sin City" written by Frank Miller.But I havn't read this book.罪と悪の街、シン・シティ。そこは、ありとあらゆる快楽と悪徳が渦巻く、現代のバビロン。オープニングに轟く銃声は、血の色に染め上げられた物語の開幕を告げる号砲。スタイリッシュな映像で彩られた、この背徳の街を舞台に、愛に命を捧げて殉じる男共が主人公を演じる、3つのオムニバス・ストーリーが綴られます。--Episode 1-------天使を抱いて目覚めた時、彼女は誰かに殺されていた。そう、天使の敵は神に魅入られた悪魔。天使の敵を討つため、男は復讐を開始する。--Episode 2-------その下衆野郎は、男の彼女に暴力をふるった。そいつを懲らしめたのは良いが、それは予期せぬ展開をもたらし、女達の自治と自由に危機が迫る。男は自分のプライドを賭けて女達を守ることを誓うが…。--Episode 3-------この街にもまだ正義は残っている。凶悪で卑劣な殺人魔の正体が、街を牛耳る権力者の息子であることは、公然の秘密だった。そいつに戦いを挑み、少女を救った警察官の、その後の物語。白を黒に塗り替え、彼から全てを奪おうとする巨悪。彼は彼女を守ることが出来るのか?------------------各エピソードの中で、それぞれがそれぞれの物語を抱え、何も知らずに擦れ違い、絡み合う男と女。ハードボイルドでタフ - 不器用で無様な男共の生き様。それと正面切って向き合い、時に銃を取り、車を駆って、共に敵に立ち向かう女達のかっこ良さ。白黒のエッジの効いたシャープな映像センス。時に使われるカラーが、ヴァイオレンスを際立たせ、一方で非現実感をもたらします。------------------この街には、神もいなければ悪魔もいません。その代わりにいるのは、人間という、その両面を合わせ持った存在。他人を踏みにじり、地獄に落とすのも人間なら、人を愛し守るのも、人間自身。この姿は、しかし、現代社会の縮図そのもの。罪深き街、罪深き時代、罪深き人よ。神無き時代に、人は何をもって生きるのか。Movie "Sin City"'s HP is here.
October 1, 2005
コメント(0)
-
『蝉しぐれ』
公式ページはこちら。原作は端整な時代小説なのだろうな、と。すいません。藤沢作品は未読なのです。-------------------------------懐かしくも美しい日本の四季を背景に描かれる、幼馴染の女性を思い続けた、一人の青年の成長の物語。横に広く世界を捉える画面構成によって切り取られる日本の四季。「作り物」の殺陣ではなく、リアルと幻想の二つを駆使して見せる殺陣。-------------------------------主役の市川染五郎さん、木村佳乃さんの惚れ惚れするほど美しく誠実な演技。特に、クライマックスでの染五郎さんの、芝居としてのリアルな殺陣表現は秀逸です。そして脇を固める豪華でユニークなキャスティング。緒形拳さんの心優しくも芯の通った父としての存在感。柄本明さんの、敵だか味方だか掴み所のないキャラクター。大滝さんのオヤジな味。加藤武さんの「人間味」あふれる役作り。ふかわさん、今田さんが出てきた時は驚きましたが、なかなか面白いキャスティングだと思います。ただ、今田さんは関西のイメージ強いから、そこはちょっと…。少年時代で、主人公の友人逸平を演じる久野さんも、かなり良い味を出していました。いや、役者として、これから注目だと思いますよ。TV「少年H」や「天切り松…」の主人公役をやっていたそうで、DVD借りて観ようかな。ヒロインの佐津川さんも、セリフが少ない分、ひたむきさがにじみ出ていました。ただ、少年時代の主人公が、顔は良いのですが、お芝居がイマイチ。冒頭、主人公とヒロインが言葉を交わす重要なシーンで、セリフ棒読みって。最初があまりにイタかったので、最後まで乗り切れませんでした。早く染五郎さんに替わらないかな、と思ったら、意外と少年時代長いし。-------------------------------えっと、良くも悪しくも「スタンダードな日本映画」でした。厚ぼったい和菓子みたいな感じ。好きな人は好きなんだろうと思います。私も決して嫌い、という訳ではないのですが…。-------------------------------うーん。私は「恋愛至上主義」的風潮って、苦手なんです。だから、ラストのやり取りなんかも、ちょっとやり過ぎでしょう、と思うわけで。(これ以上は、ネタバレぎりぎりなので、詳しくはコメントか別リンクで書きます。)私の倫理観が古風過ぎるのかなぁ?『マディソン郡の橋』『失楽園』あたりから語られている「純愛」って、言葉は綺麗ですけど、何かを大切にしているようにみせて、別の何かを傷つけているって、私は感じるのですよ。藤沢さんの原作がそうだとは思わないのですけど、監督の解釈は(例えプラトニックなものにせよ)明らかにその系譜で、それを前面に押し出されると、ちょっとつらい。役者がそれを表現できるだけの力量を持っているだけに、余計。パンフに監督がこだわりを見せたシーンとして、「坂道」のシーンを挙げていて、びっくりするやら納得するやら。映画を観ていて、違和感を感じたシーンの一つだったのですが、なるほど。監督は「友情」を切り捨ててでも、「恋愛映画」を撮りたかった訳ですね。原作は読んでないですけど、物語としては、ここで「掟」-「周りの目」を越えても存在する友情と愛情を描くことが、後の全員が集結する場面への伏線になっているはず。私は「物語」を大切にするなら、ここは切り捨てられないと思うのですけどねぇ。-------------------------------ついでに、もう少しだけ苦言。フラッシュバックの使い方も、くどくて少々しんどかったです。「教科書通り」で「分かりやすい」んだろうなぁ、とは思うのですが。あと、全体的にワンシーンずつが長い上に、場転時に意味のないカットが多いのもちょっとマイナス。「美しい日本」を挿入しているつもりにしては、長さが中途半端なんですよね。時々暗転使ってますし。季節感の演出?それにしても中途半端かな。エンディングも、一青窈さんのイメージソングを流してくれれば泣けたでしょうに。結局劇中一回も使わないんですもの。もったいない。なんか、どうにも、いや、良い映画なんですけどね。上品で、ユーモアもあって、役者も上手い。繰り返しですけど、好きな人は好きだと思います。私は…そうですねぇ、全体を2/3くらいにカットしてくれたら、もう少し好きになれるかも。場転時の時間配分を変えるだけでも、もっと良くなるのに。
October 1, 2005
コメント(0)
-
9月の記憶
早いもので10月になりました。このブログは9月の1週に始めたので、ちょうど1ヶ月です。でも、何故か7月分から存在している、前月分のトピック集成をば。(8/1,9/1の日記参照。)と、その前に。拙い文章にお付き合い頂いている皆様、本当にありがとうございます。「聞いている人がいるかどうか分からないけど、ささやかな幸せと情報をお伝えする地方FM」みたいな気分で続けておりますが、少しでもどこかに届いている、というのは やはり嬉しいものだな、と。これからも、お付き合い頂ければ幸いです。改めて。よろしくお願いいたします。---------------------------------さて、まずは映画から。今月は9本ですね。大人計画の世界が映画に 『真夜中の弥次さん喜多さん』(09/02)不条理SF 『ワースト☆コンタクト』(09/06)たまには真面目に 『映画 日本国憲法』(09/07)あの伝説の映画を映画館で 『さらば、わが愛~覇王別姫』(09/16)困ったことに笑える映画 『銀河ヒッチハイク・ガイド』(09/17)美しき伝奇 『SHINOBI』(09/20)それでも涙は温かい 『メゾン・ド・ヒミコ』(09/20)新感覚ハッピーコメディ 『運命じゃない人』(09/21)スローライフ&セカンドライフ 『ライフ・オン・ザ・ロングボード』(09/25)そろそろ、映画観るのは小休止にして、DVDとかで名作を観るようにしようかと。(と言いながら、今日は映画の日だったので2本観て来ましたが…。)---------------------------------美術系は10くらい。ムットーニさんの作品を鑑賞できたのは感動でした。目くるめく幻想の小箱 『MuttoniMuseuM-自動人形師ムットーニの機械仕掛けの迷宮博物館』(09/11)赤の支配者 『奥田元宋回顧展-小由女とともに』(09/17)作家の脳内世界に溺れんばかり 『しりあがり寿展』(09/17)現代アートの遊園地 『ローリー・アンダーソン『時間の記録』展』(09/18)建築家の自宅拝見 『建築家清家清展』(09/23)先鋭なる陶芸の世界 『加守田章二展』(09/23)心の優しさが滲む水彩 『マーカス・フィスター絵本原画展』(09/23)白黒写真の色っぽさ 『ブルース・ウェバー展』(09/25)天才の最高傑作が集結 『全揃い富嶽三十六景展』(09/25)スイスから来た作家達の競演 『テンポラリー・イミグレーション展』(09/25)10月は横浜トリエンナーレ、イサム・ノグチ、ダヴィンチ、とメインディッシュだけでお腹がいっぱいになりそう。---------------------------------お芝居は2つ。やばいなぁ。今年観たお芝居、全部「当たり」です。嬉しい誤算。現代社会の一側面を見事に切り取った ジャブジャブサーキット 『しずかなごはん』@シアターグリーン(09/19)新感線新時代の開幕を告げる 新感線プロデュース 『吉原御免状』@青山劇場(09/23)今月も、どこかでふらっと良いお芝居に出会いたいものです。---------------------------------色分けは…私の興味に応じて、緑を濃くしてみました。(特A,A or B,C以下,の三段階)()内の日付で日記を書いていますので、興味をもたれた方は、ご笑覧下さい。
October 1, 2005
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
-

- おすすめ映画
- 侵攻前の ウクライナを描いた映画 …
- (2025-11-14 06:47:24)
-
-
-

- ペ・ヨンジュンさま~♪
- 「ヨン様」の名付け親が初めて語る韓…
- (2023-12-02 17:40:56)
-
-
-

- 芸能ニュース
- 水上恒司(26)『中学聖日記』から7…
- (2025-11-19 17:50:25)
-






