2002年08月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
サイモンとガーファンクル
日記、読んでも、ツッコマないでください。って言うけど、ムリです。てきとうに、流して下さい、と言ってもムリです。てつろうさんと私の共通点は、映画が好き、二コール・キッドマンが好き、村上春樹が好き、日記を書いてる。それくらいかと思いきや、なんと今日は、サイモンとガーファンクルが、出てきてビックリしましたよ。私も大好きなんです、サイモンとガーファンクル。話は、30年くらい前。映画「卒業」を見に行きました。そして、その映画の中に使われていたのが、サイモンとガーファンクルの曲。「スカボロー・フェアー」「サウンド・オブ・サイレンス」「ミセス・ロビンソン」。映画館から、レコード屋(その頃は、CDはなくレコードでした)へ直行。その後も「明日に架ける橋」も買ったし、・・・。でも、解散して残念。そうそう、解散後、何年もしてNYのセントラル・パークで行った野外コンサートのビデオ、持ってるし・・・。私の世代は、ビートルズに影響を受けたという人が多いけど、私は、サイモンとガーファンクルです。あの、メロディと詩が好きなのかな・・・。私も、聞いてみよう、お茶を飲みながら・・・。てつろうさんの想いが叶ったらいいですね・・・。~かなたよりスカボロー・フェア聞こえ来つ やさしい人と呼ばるる夕べ~ 大辻 隆弘-----------------------------------------------------------8月見た映画★爽春・・・・・・・岩下志麻主演★我が家はたのし・・岸恵子のデビュー作。笠智衆★ボロ家の春秋・・・佐田啓二主演★紀ノ川・・・・・・有吉佐和子の小説「紀ノ川」。司葉子が主演、東山千恵子他★惜春・・・・・・・新珠三千代
2002.08.31
コメント(0)
-

オタンコナスとドテカボチャ
おいしそうな、茄子。水茄子でっか?ところで、何年か前、友人に「なんで、オオタンコナス、言うんやろ。」と聞かれ、「う~ん・・・。茄子がかわいそうやんね。」と答えました。続いて、彼女は「ドテカボチャも謎やわ。」と真剣に悩んでました。私は「*『探偵!ナイトスクープ』*に聞いた方がええよね。」と答えたのですが、その後、上岡龍太郎が、探偵局長を、おりたので、ショックのあまり、投稿できませんでした。そうそう、その友人は看護婦さんでしたので私達は「オタンコナース」とよんでました。**「探偵!ナイトスクープ」**関西人ご贔屓の、TV番組。視聴者が、しょうもない、ナゾの解明を探偵局に依頼し、探偵は、しょうもない答えを出すという、しょうもない番組。(しょうもない、と言うわりには、よく見てます)*謎1.「カーネルサンダースを救え」以前、阪神が優勝したときに、興奮した、ファンが「ケンタッキー」のカーネルおじさんを、道頓堀に、投げ込み、そのタタリで阪神は弱くなったという、ナゾがあった。探偵は、カーネルおじさんを救うべく、道頓堀川に飛び込んだが、見つからず、阪神は、相変わらずのありさま。**謎2.あほばか分布考関東の人は、馬鹿といい、関西では、あほ。さて、そのあほとばかは、どの辺で変わるのか。本にもなった有名なナゾ。番組のプロデューサーの松本修著「全国アホ・バカ分布考」:大田出版は私の愛読書。追記****今日は月末で、家に帰ったら9時だった。残業手当なし。
2002.08.30
コメント(0)
-
夕顔つながり
干瓢(かんぴょう)をつくった話を8月19日に書いたのは、しねま。干瓢は、夕顔の実なんですよね、と教えてくれたのはmihonaさん。えっ、干瓢って夕顔の実なんですか、驚いたのは、のぶさん。干瓢って、植物だったの!!と驚いたのは、stardustさん。そして、夕顔の花をおしえてくれたのが、せつこさん。他にも、いろんな人からコメント頂きました。みんなが、つながってるみたいで、うれしい。私は、お礼に、夕顔の歌と作った人を紹介します。正岡子規さんで~す。子規は、もちろん、ハンドルネーム。*来る日の二十あまりのニ日頃にさちお来るとう君来給はずや 訳:(22日頃にさちお君が来ます。君もこない?)と、友人にメール(はがき)を送って、いたそうです。さちおって、「野菊の墓」で有名な、伊藤 左千夫です。その左千夫は*十日の昼過ぎごろゆ呉竹の根岸へゆかな雨は降るとも雨が降っても根岸の子規庵に行こうと友人をオフ会に誘ったそうです。子規は、病気で、寝込んでいたのですが、その人柄を慕って多くの人が出入りしたとか。「子規は、仲間、一人ひとりの違いと長所を認め、交わりを深め合って、表現によく生きたのである。」・・・松山市立子規記念博物館長・長谷川 孝士~夕顔の棚作らんと思えども 秋待ちがてぬ 我が命かも~ 正岡 子規
2002.08.29
コメント(0)
-
塗りの下駄
♪雨が降ります、雨が降る/遊びにゆきたし 傘はなし/紅緒のかっこの緒が切れた昨日は夜空を見ようと思っていたのに雨。今日も、降ったりやんだりの雨模様。でも、琵琶湖の水位が下がって心配しているので、うれしい雨。黒い艶やかな塗りの、華やかな鼻緒の下駄が好き。からんころんと軽やかな音が好きで、よくはく。回覧板回すとき、ごみを出すとき、水まきをするとき、はくのは決まって下駄。黒塗りの下駄から見える素足は妙に色っぽいと思うのは、私だけ?普段、陽にあたらない足は、黒塗りの下駄という舞台の上で、いっそう白くなまめいて見える。ところが、そのお気に入りの下駄の塗りが2年前に少し剥げた。新しいのを買おうと、デパートの呉服売り場に行ったが気に入ったのがなかった。鼻緒が、赤、一色では、いけない。今の下駄は、赤が半分と黄色に格子の鼻緒。そして、去年また、塗りの部分が大きく欠けた。今年こそ買おう。そう、思って夏がはじまった頃からさがしているのに、夏の終わりの今、まだ手に入れてない。~黒塗りの下駄より見ゆる わが足の なまめく 夏が終わろうとしている~ しねま
2002.08.28
コメント(0)
-
♪月がとっても青いから・・・
♪月がとっても青いから、遠回りして帰ろ~いやあ、思わず歌ってしまいましたよ。昨日、50年前の古い日本映画を見たためか、思わず古~ぃ歌を歌ってしまいました。そうそう、この超ナツメロ、1~2年前に若い人がカバーしたそうですね。私の月の記憶は、もう、何十年も前。1~2歳頃にまでさかのぼります。私は、父に手をとられて、歩いていました。もらい風呂からの帰りでした。歩いていた、私は急に立ちどまり、「ネンネ、ネンネ」と自分の影法師を指差して言ったのでした。歩くとついてきて、止まると、止まる、影法師。それを見て、「ネンネ=あかちゃん」と言ったと父は昨日のことのように、よく話してくれました。私には、小さい頃の写真がありません。けれども、月夜の晩の親子づれの姿がモノクロの映画のように、残っているのです。ひさしぶりに、今日は、夜空を見てみよう。・・・・・夏は夜。月の頃はさらなり、闇もなお、蛍の多く飛びがいたる。また、ただ一つ、二つなど、ほのかに、うちひかりて行くもおかし。雨など降るもおかし。・・・・ 「枕草子」 清少納言
2002.08.27
コメント(0)
-
生きている間に、お会いしたかった・・・
日記に書くべきか、どうか、さんざん迷った。でも書いておこう。あの人の供養のために・・・。先月、見知らぬ人から、手紙をもらった。開けてみると、5月のはじめに、弟さんが亡くなったという知らせ。私には、その人に心当たりは無かったけれど、読んで胸が締め付けられる思いがした。亡くなった彼(仮にAさんとしておこう)は、生来の自然児で探求心旺盛。若い頃から社会や、自然環境問題に関心と情熱を傾けていたという。こよなく、自然と生き物を愛し、夢多く、読書好き。多感で正義感強く独身で自由奔放。弱き側に身を置く優しさを持ち、頑なに清貧を貫いた人。環境調査の帰り、カメラを下げ、ザックを背負い自宅の近くで心臓発作で倒れ、亡くなったAさん。稲妻、雷鳴、雨、雹の乱天候の夜、旅立たれたAさん。手紙を読んで、涙がこぼれる。Aさんの住所禄には、私の名前があったんですよね。だから。こうして、手紙が来ているんですよね。どこで、お会いたのでしょう?それとも誰かを通じて私の住所を聞いたのですか?私と同年代のAさん。生きていたら、きっと、どこかで知り合えて、いい友達になれたろう人・・・。Aさん、私の父が、あなたより一足お先にあの世とやらへ行ってます。年は、離れているけど、あなたの人生と重なるところがあるので、きっと気が合うと思いますよ。私が行くまで、相手をしてやって下さい。でも、生きている間にお会いしたかった・・・。
2002.08.25
コメント(0)
-
川は流れる・・・。
里山で月に一度遊ぶ。今日は、久しぶりに、川で「もんどり」(7/19の日記参照)や網を使って魚と遊んできた。電車に乗って、友達の車に乗せてもらって・・・。その道のりの遠いこと・・・。お金/弁当/タオル/水筒/着替え/帽子/日焼け止めクリーム/雨具/眼鏡/サングラス、それにケイタイ・・・。持って行く荷物の多いこと・・・。子どもの頃は、こうではなかった。*お金は、歩いて行くのでいらない。*弁当は、昼ご飯を食べてから行くのでいらない。もし、小腹がすけば、畑のナスビ を採って食べればいい。キュウリもトマトもある。*喉が渇けば、山から湧き出す水が飲めた。だから水筒はいらない。*雨が降るのに泳いだりしないから、雨具はいらない。着替えも、帽子も日焼け止めクリームも、眼鏡もサングラスも、ましてや、ケイタイなど持たなかった子どもの頃。里山が、自然が遠くなっていく度に、私の荷物は増える。*****言葉のものおき*****人間は、なしですませるものが多いほど、それに比例して生活は豊かである ヘンリー・D・ソロー
2002.08.24
コメント(0)
-
地蔵盆
今日は地蔵盆。お盆の15日の夜と16日の夜は、村中総出のにぎやかな盆踊りがありました。15日は小学校の校庭で、16日はお寺の境内で・・・。高い櫓が組まれ、音頭とりも3人いました。太鼓をたたく人も数人いて、踊りの輪も2重、3重、老若男女が踊る大盆踊り。夜店が出ていました。若い男が娘を暗闇へと誘ったり・・・。なぜか子どもの私までドキドキする雰囲気が盆踊りの夜にはあったのでした。でも、地蔵盆の盆踊りは、地区のおばちゃん達が、主催の小規模なもの。場所も、地区の中で、おばちゃん達は、自分で音頭をとりながら、子どもと一緒に踊ったものでした。ひとしきり、踊ると「さあ、並んで・・・。」とうながされ、並ぶと、白い紙に白砂糖を一つまみ。甘いものと言えば、スイカかサトウキビくらいしか食べない当時の子どもにとって、白砂糖は、ショックな甘さ。とっといて、砂糖水にしよう、と思い、眺めているうちに・・・。「チョットだけ・・・。」舐めたいという誘惑に負けて、ついつい舐めてしまいます。砂糖をもらうのは、嬉しいのですが、もうすぐ夏が、夏休みが終わる・・・と感傷的になる日でした。*****てれてれテレビ8/22*******●麦客(まいか)● NHk~麦刈りに集まる中国の出稼ぎ農民/機械と鎌の激突~かつては麦客(まいか)と言えば鎌一丁の出稼ぎ日雇い農民。ところが、いまや機械にとって変わられ、鎌で刈る麦客(まいか)は、稼ぎも少なく労働条件が悪くなっている。機械を使う麦客(まいか)を鉄麦客(てつまいか)、鎌で刈る麦客は老麦客(ろうまいか)というそうだ。
2002.08.23
コメント(0)
-
茶の湯は日本人の種子
彩貴さま、ごきげんよう。しねまですことよ。偶然ですわね、実はワタクシも昨日、お茶の、お稽古でしたのよ。オーッホホホ・・・。(白鳥麗子笑い)ああ、しんど、普通に書きますね。昨日は、おひさな、お茶の稽古。7月3日に行ったきり、行ってなかったもんな。7月8月は暑いから冬眠ならぬ夏眠したい私。会社から帰ったら、そのままバテてました。秋風が立ってきた。さて、これから、お茶のお稽古に励むのだと、夕方から張り切っていったものの、1ヶ月半のブランクに、いやだ、忘れてる。何回もダメだしされてしまいました。えーん。*****言葉のものおき*****■茶の湯は日本人の種子■・・・茶の湯には日本人の生活文化全体のエッセンスが詰まっています。それも、何百年という伝統の累積が、地層の断面図を見るように整然と積み重なっています。茶の湯を伝えることで日本の美風の粗方(あらかた)を伝えることができると確信しています。茶の湯を取り入れることによって、今私たちが失いかけているものや忘れているものを、精神や生活の上に蘇らせることが可能なのです。茶の湯には日本文化の租型(そけい)ともいうべきエッセンスが種子のように残っているわけです。・・・■茶遊人・鈴木 皓詞 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~所作は忘れても、ワタクシ、ウンチクは忘れませんことよ。オーッホホホホ・・・。(白鳥麗子笑い)
2002.08.22
コメント(0)
-

オードリーのように・・・
先日、会社から帰ったら娘が来ていた。彼女は、ひとり暮らしをしているので、ときどき帰って来る。「友達の結婚式に、これを着て行こうと思って・・・。」と持ってきた袋をあけた。 中から出てきたのは、ノースリーブの黒い身ごろと白地に黒の大きな花が散る木綿のワンピース。これに真珠のネックレスをしたいから貸して欲しいという。「ううん・・・、この服、ちょと地味じゃない?」と私。「これに、黒いレースの手袋をつけるねん」と娘。「オードリーヘップバーンみたいやろ。」そう言って娘は、にんまり笑った。ほんと、いいわ・・・。と私は心の中で彼女がその服をきて、手袋を着けているところを想像した。娘が美しく装うさまは、見ていてうれしい。自分が年をとるのも許せる気がする。「あっ、ネックレスは、これがいいわ、これにする。」と彼女が選んだのは、アンティックのガラスの首飾り。80歳になる夫の母が若い頃に身につけていたものだ。服は質素かもしれない。けれど彼女には趣味のバレーで鍛えたしなやかな体と若さというお金では買えないアクセサリーがある。「オードリーみたいに髪はまとめるん?」と聞くと娘は、うなずいて、また、にんまり笑った。~~~~~~~・・・・~~~~~~~・・・・~~~~~~~・・・~~~~ワンピースとネックレスをマウスで絵にした。でも、アップできないよー。10/2:友人が日記に絵をアップしてくれました。ありがと。
2002.08.21
コメント(0)
-
台風のあと・・・魚とり
秋よ、来い!!8月16日の日記に書いたら、ほんとに今日は、秋が来ましたよ。ははは。台風の後の、吹く風は涼しいし、あの空の高さは、もう秋ですよ。子どもの頃、台風が好きでした。いつもと違う緊張感に、つつまれて過ごす夜。そして台風の去った後のお楽しみ。大水の出た、台風の翌日、川原に近い畑に行きます。川原の近くの畑は2枚。そのうち低い方は、昨日の雨がまだ溜まっています。ひとりがソウケ(目の細かいザル)を受けて、もうひとりが、水溜りをバシャバシャと音をたてて、歩きます。すると、魚がおもしろいようにとれるのです。大水は川を越え川原を越えて、近くの畑まで入り込み、それにつられて魚が畑まで入ってきたのです。子どもたちが、魚を追い込んでいる間に、上の畑で、父が鎌でサトウキビをきってくれます。噛めば、ジワッと甘い汁が出るサトウキビは、子どもの大好きな夏のおやつ。魚が食べられるし、サトウキビは甘いし・・・。川原や田畑という*遊水地*があった頃、台風の残して行くものは、負のものばかりではなかったのです。**遊水地(ゆうすいち)**降った、雨の一時預かりのような所。田畑、池、川原、などなど。現在それらは、埋め立てられたり、「開発」されて家が建ったりしています。川原も、草が生えている方が、今の3面コンクリート張りの川よりも保水能力が大きい。
2002.08.20
コメント(0)
-
干瓢(かんぴょう)つくり
干瓢。おすしに使う、あの干瓢です。干瓢はアメリカン・フットボールのように、枕のような横長です。<干瓢つくり>*1cmの巾に輪切りにします。*外の皮(スイカでいえば緑と黒のストライプの部分)を包丁でむきます。*皮をむいて輪切りにした干瓢を「干瓢剥き器」?でむきます。 (干瓢むき器に輪切りにしたのを取り付け、左手に薄くむく道具を持って右手で ハンドルを回します。) *種のところまでむいたら、次のをむきます。*おっと、円く残った種の部分を捨てないで下さい。それは、それでおいしいのです。*後は川原で。川原には、石が焼け付いています。この上にのせれば、すぐ乾きます。*これで、1年中の干瓢はできました。種があるため、円形のまま乾したのは、甘辛 く炊けばおいしいおかずです。紫外線のことなど気にせずに過ごしたあの頃・・・。太陽を恵みとして感謝していたあの頃・・・。~~~・~・~・~・~~~~~~~・~・~・~・~~~~昨年の秋、父母と妹と一緒に故郷に帰りました。その時、父の友人で90歳をゆうに越えた人が私と妹に「ワシが作った干瓢じゃ」と言って一くくりくれました。「また、来年、会おう」と約束して老人2人は名残惜しそうに別れました。父が死んであの時が、話好きな、仲良し2人の最後になりました。
2002.08.19
コメント(0)
-
麦茶とケナフと地球温暖化
「鉄は熱いうちに打て。麦茶は冷やして飲め」なあ~んてね。昨日の、日記のタイトル「麦茶とケナフと・・・」。その「・・・」は地球温暖化だったんです。麦茶をそのまま、入れてお茶にすればいいものを、ケナフ紙だからと自分に言い聞かせて、パックのお茶を使うところに私の限界があるのですね。パック紙を作るために何十年という歳月をかけて育った木を伐る。木は、温度を下げる役目をしてるんですよね。木は、2酸化炭素を吸ってくれる役目をしていたんですよね。それを、忘れて、バンバン木を伐ったんで、地球規模で温度が上がり、氷河が溶け、日本の夏は熱帯になったんです。オゾンホールができて紫外線が降り注いで、子どもが太陽の恵みに感謝なんかできなくなったんですよね。ほんとうに、なんとかしなくちゃと思います。やっぱり、私もケナフについては、生態系の問題から疑問ありなんでが、ケナフという選択肢もありという提案です。ケナフじゃなくて日本古来からある成長の早い植物、例えば竹なんかで紙が作れないかな。たかが麦茶、されど麦茶。麦茶から考えよう、地球温暖化。*********ルイボス茶*********南アフリカ共和国セダルバーグ山脈の高地で栽培されるマメ科の針葉樹ルイボス。茶葉は1900年代初頭にはヨーロッパ各国各国に紹介され、今では先進数十カ国で愛飲されています。ルイボスは地下8~10m深く根をはり南アフリカの大地に眠る養分やミネラルを吸収し成長。ノンカフェインです。なんだかな。これも実は気になったのですが・・・。やはり、アフリカのものはアフリカの人が使うのが一番いいのですよね。
2002.08.18
コメント(0)
-
麦茶とケナフと・・・
ゴクゴクゴク・・・。うう~~ん。今日も元気だ、麦茶がうまい!夏は、お茶を炊いて、冷やして飲みます。その日の気分で、ウーロン茶、ルイボス茶、ほうじ茶になったり・・・。今日は、先日買った「ほのかに甘い焙煎麦茶」です。「じっくり焙煎 香りまでおいしい麦芽麦」です。私がこの麦茶を買ったのは「16袋入り」という量と「未晒しのケナフ」がパック紙であったこと。子どもたちが家にいた頃は、毎日、朝晩2回大きな薬缶で炊いていました。ザラザラと麦を入れて炊くお茶は、いつも気をつけておかないとすぐ無くなるくらいの売れ行きでした。子どもたちが、ひとり暮らしをするようになると、薬缶は、一回り小ぶりになり、一日おき。だから「16袋入り」がよろし。パック紙に疑問を持ってる私だけど、ケナフ使用ってことで自分の中で折り合いをつける。まだ、半分以上残ってる、この麦茶が終わる頃には、暑さも終わっているでしょうか。●ケナフ●別名、ホワイトハイビスカスアオイ科・ハイビスカス属。植えて5~6ヶ月で3~5mに成長し。5~10cmのクリーム色の花を咲かす、そうです。(くわしくは「ケナフ」で検索してください。)*成長が早いため、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を普通の植物より多く吸収すると、ここ最近にわかに注目をあびてきました。「ケナフ使用」と書いたの名刺や、ポケットティシュをもらったことがあります。ケナフなら、いくら使ってもいい、なんてことは、大間違いだと思う。だって、それを加工するときには、エネルギーを使ってるもんね。*******てれてれテレビ************★爆笑オンエアバトル★今日はスペシャルだ!見るぞ。わくわくわく。
2002.08.17
コメント(0)
-
うら盆
今日はうら盆。お盆も今日で終わりです。うちの会社は、昨日までが休みで、今日は出勤。この、日曜日まで休みという所もあるし、お盆は休まないという会社もあります。地獄の窯の蓋も開くと言って、皆そろって休んでいたのは、過去のこと。お盆は13日から16日までと決まっていたのは、もう昔の事となりにけり、です。今では、各自の家で、迎え火や送り火を焚きますが、昔、昔には、お盆は共同体の行事だったとか。死者があの世から村に帰る時と、あの世へ帰る時、送迎は村中で行ったそうです。そして、死者の魂をねんごろに弔うために行われたのが、盆踊り。そう言えば、手火(てび8/8の日記参照)も村中で行う行事のなごりだったのかと思うと合点がいきます。そうだ、京都の「大文字」も共同体の名残なのかな。もう、十数年もすれば、私が「八朔」(8/1の日記参照)を知らないように「えっ、昔はお盆は会社が休みだったの?」なんて時代が来るかも知れない。でも、盆踊りぐらいは、残って欲しいな・・・。父の初盆だというのに、お墓参りもせず、盆踊りに行かなかったくせに、そう思うのです。**********まみむメモ8/15*****************美容院の後、お買い物。化粧品を買いました。秋よ来い。
2002.08.16
コメント(0)
-
初盆
2月26日に死んだ父の初盆。老人ホーム暮らしの父母。去年は、故郷でお盆を過ごせると、喜んでいたのに・・・。暑いのに、畑に生えた草を抜きたがるので、風呂用のイスを持ってきて母と2人で草取りしたのに・・・。好物の刺身を肴に大酒飲んで、ぐうぐう寝たのに・・・。私や、親戚の人を相手に話しをしたのに・・・。家には仏壇などないから父の位牌は、誰もいない私の生家にあります。でも、父の写真を飾ってるコーナーに「おもちゃカボチャ」と一輪の花、かわいいキャンドルを飾ってみました。「なんちゃって仏壇」。お墓参りもしません。それが分かってたのか、墓石には父の川柳が彫ってあります。~墓建つも 手向ける花は まだ咲かず~ しねまの父******まみむメモ******8/14・久々に映画3本。古い日本映画*紀ノ川*惜春*爽春亡くなった俳優さんが沢山出ていました。お盆だから?
2002.08.15
コメント(0)
-
ボニゴ
麦秋が終わった頃から、背に荷物を担いで行商のおばちゃんが村に来る。荷物の中身は、下着や子ども服。「これを子どものボニゴに買(こ)おてやって。」おばちゃんは、隣の県からくるので関西訛り。それが、珍しくて、私はじっと聞いていた。「金がないんで・・・。」と母。「金は、今度でええから。」とおばちゃん。「ほんなら、これをもらおうか。」と母。商談成立。かくして、私は「ボニゴ」の洋服を買ってもらった。正月には「ショウガツゴ」として、必ず新しい下着を一枚買ってもらった。「ボニゴ」、「ショウガツゴ」と言うのは、「盆号」「正月号」だと子どもの頃は、思っていた。恥ずかしいなあ。変な言葉を使って・・・と。しかし、大人になってから、「ボニ」は「盆」の古語だということが分かった。「ボニゴ」とは、盆に着る晴れ着の古語。「ボニゴ」、「ショウガツゴ」、「マツリゴ」・・・。昔、昔、人々は旅の商人から品物を買った。商人は、物を置いて帰るだけでなく、言葉をも伝えたのだ。私が恥ずかしがっていた、それらの言葉は、雅な京の都を出発し、長い旅をする。そして、京の都が忘れた頃に私の田舎で生きていた言葉たちだ。***************まみむメモ*************友人と3人で友人の家でお茶。本をまた貰う。*香港市民生活見聞/島尾伸三 *死の棘/島尾敏雄 *牡丹の庭/芝木好子 *霧の中/田宮寅彦 *日本の文学/ドナルド・キーン(以上、文庫本)*煎茶への誘い/渡辺琢山 *Mother Goose/Kate Greenaway
2002.08.14
コメント(0)
-
民具:団扇(うちわ)
この頃、村の商店から、お中元に、うちわが配られます。盆前は、団扇か手拭い、正月前は、カレンダーか餅を焼くアミでした。普通の家には、クーラーはおろか扇風機もない時代、団扇は涼をとるための必需品でした。ですから、人数分が必要。涼をとるばかりでなく、台所の火を焚く時にパタパタ。風呂の焚き口で、火を焚く時にパタパタ。七輪で炭を熾すときにもパタパタ。ご飯をさます時にも、パタパタ。蚊帳の中に入る前にもパタパタ。年中、、使ってました。団扇の材料は、竹と紙。最近は、プラスチィックの団扇も多いのですが、やはり、竹でないと、雰囲気がでません。*****涼を呼ぶ、竹林の音*******京都、嵯峨野の野宮神社から俳優の大河内伝次郎が建てた大河内山荘までの両側に竹林が続く。昼間も薄暗い。タレントショップや土産店が並ぶ表通りとは、うって変わった静けさだ。サラサラサラ。竹の葉が風にそよぐ。じっと耳を傾けていると、波間に漂っているようだ。風が強くなった。竹林全体がうねる。竹と竹がぶつかり、鋭い音をたてる。カーン、カーン・・・。 (音風景百選より)*ヤバイです。休みとオッチャン(続柄:夫)がいないのをいいことに、連日、遅くまでおきていたら昨日から、口の横がキレてしまいました。お疲れのサイン。今日の仕事に備えて、昨日は予定していた映画にも行かず家に「ひきこもり」でした。皆さんも、気をつけて下さいね。
2002.08.12
コメント(0)
-
川遊び・・・花咲く、合歓(ねむ)の木の下で
jinennjyo7月14日に合歓の木(ねむのき)の記事を見て、一月早いなと思った。私の思い出の中で、合歓の木は、夏休みの川の中に咲く8月の花です。子どもの頃、毎日毎日、明けても暮れても川で泳いでいました。泳ぐというより、川で遊ぶ・・・。場所は、何箇所かあって、人数、子どもの年齢、持ち時間に合わせて選んでいました。お気に入りの一つは、山の真下に川が流れる、合歓の木のある淵。胸までの深さで、ゴツゴツした岩場が無く、のんびり泳げます。水の中で、魚を追いかけたり、ジャンケンや鬼ごっこ・・・。遊び疲れると、あお向けに川の中に漂います。目に映るのは、薄紅色の花と優しげな葉っぱ、花咲く合歓の木・・・。~我妹子(わぎもこ)を聞き都賀野辺(つがのへ)の しなひ合歓木(ねぶ) 我(あ)は忍び得ず 間なくし思へば~<現代語訳>いとしい、あなたの声を聞きつぐといえば、都賀野のあたりにしなう合歓の木。しなうといえば、隠そうたってムリムリ。いつも思ってるんだもん・・・。●合歓の木(ねむのき)●<万葉名>ねぶマメ科の落葉高木。夏、小枝の先にうす紅色の花が咲きます。花が化粧用の刷毛のような姿に見えるのは実は、オシベ。うっそうと茂る葉がすべて夕方から閉じたれる。眠りの木の意から合歓の木。一つの花と見えるのは10~20の小花の集合。葉は線香に使うそうです。
2002.08.11
コメント(0)
-

里山
日本には身近な数多くの里山が残っている。里山は、山から連なる水田や小川、集落も一体となって、形作っており人と自然が混在し、一つの輪につながっている。「人も自然の一部」とみる日本人の精神活動と深く結びついた空間だ。里山から学べることは、昔、日本人が手を加えながらも他の生き物への配慮を忘れなかったことである。 自然写真家:今森光彦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~里山という言葉に出会ったのは、1980年代の後半。まだ環境問題という言葉が市民権を得ていない頃である。ごみ問題、エネルギー問題、地球温暖化問題、文化・・・。さまざまな、問題があることを知り、一市民として、なにもできない、もどかしさを感じていた。 そんな時、聞いた里山という言葉。ああ、これだとピーンとくるものがあった。例えば、ごみ。野菜くずなどの生ごみは、畑に返すことで、肥料となる。地元の米や野菜や材木を使うことが遠くからトラックで運送される時に出る、地球温暖化に関係大有りの排気ガスを減らし、石油エネルギーを使う事を減らす。もちろん、これだけやってれば全てよし、なんて思わないけど、私には、子どもの頃の豊かな里山の体験がある。・・・ということで、里山で遊ばせてもらっています。でも、明日からオッチャン(続柄・夫)がまた、旅行に行くのでPCに遊んでもらいます。 ★★★★★★綺羅星のごとき美女たちの競演★★★★★★岡田茉莉子、岸恵子、岩下志麻、桑野みゆき、有馬稲子、倍賞千恵子、司葉子・・。「女優の都」松竹大船が生み出した、綺羅星のごとき美女たちの競艶。★女性映画の名匠・中村登の世界8/10から8/30(金)までシネ・ヌーヴォ 06-6582-1416http://terra.zone.ne.jp/cinenouveau/
2002.08.10
コメント(0)
-
長屋改造ギャラリー「ふう」
大阪市住吉区万代6丁目の、築80年の2軒長屋を改造し、建築設計事務所を移転した、建築家・竹山通明さんが内部に長屋ギャラリー「ふう」をオープン。長屋は約90平方メートル。竹山さんが購入し、4ヶ月かけて改造。残っていた柱や照明具などをできるだけ生かし、塗り直した土壁の土も現場から採った。●長屋ギャラリー「ふう」電話 06-6672-0886*****************************************これからは、古いものを捨てるのではなく、文化として生かして使うという発想が必要。住吉大社周辺の地域と組んで、拠点づくりをしたい。 (竹山通明さん)行くぞ~。(しねま)********てれてれテレビ8/8********●恋愛偏差値ひさしぶりにTVドラマを見た。先週から始まった「恋愛偏差値」。SMAPのごろうちゃんが、いい演技してる。来週も見ようっと。
2002.08.09
コメント(0)
-
手火(てび)
七夕の翌日、近くの川原で行われていたのが手火。大人も子どももお楽しみの行事でした。*川原に長くて太い竹を用意する。*麦わらで先端に漏斗のような円錐形を作る。*その漏斗のような三角錐の中に、花火や藁などを入れる。*それを、川原に立てておく。*松のワリキに縄をつけ、火をつける。・・・松明(たいまつ)*夕方、子どもたちは手に手に手火を持って、高い棒の先めがけて投げ込む。と書いて、なんとまあ危険な遊びをしていたのでしょうと思うが本当に危険です。手がそれて、松明(たいまつ)があらぬ方に飛んでいくたび、「キャー」「ワー」と大騒ぎで、逃げ惑うのです。投げ込むのは、子どもだけ。大人は橋の上で、夕涼みをしながら、見ていました。みごと、火のついた松明が中に入ると歓声が・・・。藁や、麦わらが燃え花火がひかり、なにもない、質素な毎日が一瞬、夢の世界へ・・・。火の始末をして・・・。何ごともなかったように、夏の夜がはじまります。盆の迎え火、送り火の変形、火祭りの一種ともいう、この手火は、私が小学校に入ってしばらくして、しなくなりました。
2002.08.08
コメント(0)
-
七夕
★朝露を集める子どもたちは、朝、早くとびおきる。朝露を集めに行くのです。右手にお盆、左手に、茶碗を持って。まだ陽の昇らない、静かな朝、七夕がはじまります。我が家の前に、一軒の家。そしてその前は、田んぼ、田んぼ、田んぼ・・・。田んぼには、あおあおとした、稲がまだ、露にぬれて揺れています。さっ~。さっ~。持ってきた、お盆で、稲をはらえば、露がいっぱい・・・。もう一度、さっ~。田んぼの隅に植えてあるサトイモ。その葉に溜まったコロコロと丸い露。これも茶碗に入れます。さあ、露はいっぱい。意気揚揚と家に・・・。★★短冊に願いごとを・・・。持って帰った、露は硯に入れ、墨をすります。墨のにおい、好きだな。なんてゴシゴシ・・・。その間に父は、家の横の竹やぶから、竹を三本、切り出してくれます。裏の縁側に二本の竹をたてて、もう一本は、葉を払い1mくらいの長さに切ります。そして、立てた2本の竹をつなぐように結び付けます。その、竹には、ホウズキやナンバキビ(トウモロコシ)などを、ぶら下げるのです。願いごとを書いた短冊を笹につけましょう。その時使うのが「ヒメクグ」。こよりの代わりに、使うのです。これは、近くの川原で、前の日に調達済み。★★★なにか、忘れていませんか。そうです、ナスビの牛とキュウリの馬。ナスビにマッチ棒を4本突き刺して、はい、牛の出来上がり。キュウリにもマッチ棒を4本、それにトウモロコシの茶色の毛をとって、シッポにします。それらを、机にならべる頃には、母の特性の「流し焼き(小麦粉に砂糖を入れ、焙烙で焼く)」も出来、それも並べましょう。夏休みの最初のイベント、一月遅れの七夕は、かくして家族総出で行われます。セピア色の夏の思い出・・・。
2002.08.07
コメント(0)
-
雨の名前:洗車雨(せんしゃう)
陰暦7月6日の雨。一説に七月七日の雨。牽牛が織女との逢瀬のために乗る牛車を洗う水が雨となって降るという言い伝えがある。「雨の名前」 高橋順子より~月遅れに七夕をするとしたら今日。*****言葉のものおき*****人は誰か、何かとともに歩いているものだ。その相手が、たとえ人間でなくとも、子どもの時代、青春時代、そして大人になっても、その人のかたわらには誰か、何かがそばにいて、喜び、哀しみをともにだいてくれている。孤独な人には「孤独」が隣にいる。 「きみとあるけば」 伊集院 静
2002.08.06
コメント(0)
-
金子みすず
jinennjyoわあ、ここにも、金子みすず(本当のずは打てない)のファンがいたと嬉しくなりました。好きです、金子みすず。「大漁」 金子みすず朝焼け小焼けだ大漁だ大羽鰯(いわし)の大漁だ。浜は祭りのようだけど海の中では何万の鰯のとむらいするだろう。何年前か、この「大漁」という歌にであって、以来、本を読んだり、テレビドラマ(松たかこが、みすず役でした)を見たり、金子みすずの発掘者、矢崎節夫氏の講演を聴いたり・・・。すさんだ、世の中、金子みすずがブームになるのは分かるような気がします。***「声に出して読みたい日本語」斎藤孝*****金子みすずは、宮沢賢治と並ぶアニミズムの巨匠である。アニミズムは、あらゆるものに生命を認める考え方だ。動物や植物をはじめとして、場合によっては石までも生きているとする世界観である。原始的な宗教や子どもの心性に典型的に見られる。(略)金子みすずは、石ころを「きのうは子どもを/ころばせて/今日はお馬を/つまずかす」と歌っている。みすずの作品を発掘した矢崎節夫はみすずの童謡を「小さきもの、力の弱いもの、無知なるものに対する、祈りの歌だった」と言っている。(略)
2002.08.05
コメント(0)
-
「読書からはじまる」
「読書からはじまる」 長田 治すべて読書からはじまる。本を読むことが読書ではありません。自分の心のなかに、失いたくない言葉の蓄え場所をつくりだすのが読書です。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。納得・・・。なぜだか、残しておきたい言葉や文章にであうと書き抜いてしまうクセがあります。肝心なときにあれ、どこにいったんだろうと、探す毎日。日記を言葉の蓄え場所にしよう。
2002.08.04
コメント(0)
-
ごちそうさん歌・なすび
♪チャンチャカ、チャカチャカ、チャンチャンチャン・・・ (なぜか、NHKの料理番組のテーマソングが・・・)みなさん、こんばんわ。しねまの「ごちそうさん歌」の時間がやってきました。今日は、今が旬のなすびを使った料理を作ってみましょう。<材料>なすび、ピーマン、油、味噌、砂糖<作り方>①なすびは半分に切ってから、小口切り。ピーマンも半分に切って種を出し小口切 り。②フライパンに油(あれば、ごま油)を熱し、ピーマンを入れる。少ししてなすび を入れる。③柔らかくなったら、味噌と砂糖少しで味付けする。いかが、でしたか?簡単でしょう?是非、皆さんも作ってみて下さいね。それでは、今日はこのへんで・・・。ごきげんよう。♪チャンチャカ、チャカチャカ、チャンチャンチャン・・・~高い山から、谷底 見ればよ 瓜やなすびの花ざかりよ アレハヨイヨイヨイ~ 盆踊り唄***********てれてれテレビ8/2**********★探偵!ナイトスクープ~恐るべし!5歳なのにフ-リガン/おシッコのベランダ/爆笑?かしまし主婦~今日は、みたいテレビがいっぱいあったのに、残念。ぬかった。
2002.08.03
コメント(0)
-
2002朝日ベストテン映画祭
「八朔までには、なんとかしますから・・・。」 byしねまのおばあちゃん。なんとかしたい事は、2002朝日ベストテン映画祭を記録しておくこと。海外10作品、のうち観た映画、3本。3「初恋のきた道」4「リトル.ダンサー」7「山の郵便配達」日本の10作品のうち観た映画・4本。1「GO」5「リリィ・シュシュのすべて」6「こどもの時間」7「満山紅柿」以外に少ないな。観に行っても、ベスト10に選ばれない映画もあるし・・。今年は、どうなんだろう。そうそう、今年6月にやってた映画「父よ」は昨年11月の大阪海外映画祭で観た。来ていた主演のヴァンサン・ルクールにサインしてもらった~。肩までかかるロン毛のチョウ美形で私と友人は、おくち、あんぐり状態。彼の主演映画「サルサ」は、まだ観ていないのでみたいみたい。7月の映画「少年の誘惑」「海辺の家」・・2回「ミルクのお値段」「ニューヨークの恋人」
2002.08.02
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-
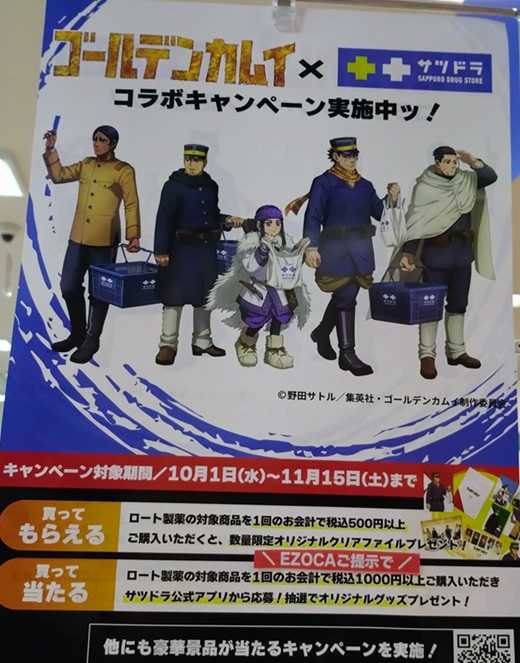
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…
- (2025-11-15 17:02:59)
-
-
-

- 楽天市場
- Zoff│LISA LARSON オリジナルメガネ…
- (2025-11-16 12:11:52)
-
-
-

- 徒然日記
- いや、誰もいねーなw
- (2025-11-16 07:44:29)
-






