2006年10月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-

ハロウィンは*いのこ*に似てる
ハロウィン(Halloween)は、キリスト教の諸聖人の日(万聖節)の前晩(10月31日)に行われる伝統行事です。諸聖人の日の旧称"All Hallows"のeve(前夜祭)であることから、Halloweenと呼ばれるようになりました。古代のケルトの人たちは、収穫の季節である秋が深まるにつれ、どんどん日が短くなり、夜が長くなっていくのは、Samhain(あの世を支配する王)が太陽の光を奪ってしまうからだと考えました。そこで、収穫物をお供えして崇め、死者の魂をなだめ、大きなかがり火を焚いての暗さに対抗し、翌年の幸運を祈りました。 そのかいがあって、冬至を境に日が長くなり始め、彼らの願いが聞きいれられたと喜びました。この夜は死者の霊が家族を訪ねたり、精霊や魔女が出てくると信じられていました。これらから身を守る為に仮面を被り、魔除けの焚き火を焚いたのです。***ハロウィン・ファン***よりへえ~、へえ~!!!ハロウィンを日本のお盆に似てるという人がいるが、私は*いのこ*にそっくりと思う。季節も秋が深まった頃だし、夜、子どもたちが、家々を回って、お菓子をもらうというのもそっくり同じ。最近は、「いのこ」をいまだにやってるってこと、聞いたことがないけどね・・・。「いのこ」は、私の子どもの頃の大切な思い出・・・。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月31日*柿は女の生涯/地名:「ふるさとの小字(こあざ)」*UP
2006.10.30
コメント(4)
-

10月のおしゃれ手紙:来る人、去る人
はるなです。(「ヒロシです」風に)■長い間、ブログを通してお付き合いしていた方が楽天を去られました。★はなびらさんが、休筆します 。■と思えば、ブログで知り合った人とオフ会。(^▽^)/ あずーるさんと私の「おしゃれ手紙」の相手、河内カルメンこと、浜辺はるか嬢。オフ会といっても、あずーるさんは、ライコス時代からのお友達。もう知り合った4年にもなり、何回も会っています。カルメン嬢は私がブログデビューする前から、もう10年以上前からの古い友人。彼女の家にお邪魔したり、私の家に泊まってもらったりした仲。オフ会とはいえないか・・・。二人とも*緑の縁*がとりもった仲です。■今月も、日記にリンクしてくれる方がおったとです。 ◆◇◆2006.10月の日記メイト◆◇◆POUR ANNICK ONLINE STORE BLOGのpourannickさん。ありがとうございますm(_ _)m■今月も書き残したことがあったとです。*「3dasチケット」*大阪の紅葉の名所*絵本*「芋たこなんきん」*かわいそうな木*手作り・・・・・・・*飛騨高山*地名*人気ブログランキング*打ち水*校庭映画会*環境首都*映画「嫌われ松子の一生」■□■10月の映画■□■★紙屋悦子も青春★フラガール***見たかった映画****マッチポイント*アガサ・クリスティーの奥さまは名探偵*トンマッコルへようこそ*薬指の標本*旅の贈りもの 0:00発*幸福(しあわせ)のスイッチ*ミラクルバナナ*サンキュー・スモーキング*トリスタンとイゾルデ*チーズとうじ虫*ディア・ピョンヤン*三池 終わらない炭鉱(やま)の物語*太陽*天使の卵 *シネヌーヴォの中国の映画特集 ◆◇◆2006.9月のおしゃれ手紙◆◇◆ 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月29日*雨の名前:凄雨(せいう)*UP
2006.10.29
コメント(4)
-

郵政公社、一転、職員採用
日本郵政公社は27日、2006年度の一般職外務職員(高校卒業程度)の採用凍結方針を見直し、07年4月も例年並みの2100人を新規採用すると発表した。外務職員は、郵便物の配達や簡易保険、郵便貯金のセールスを行う。郵政公社はコスト削減のため、外務職員の代わりにアルバイト職員(ゆうメイト)の配置を進め、今年4月には外務職員の採用中止を打ち出していた。しかし、景気回復を受けて、都市部を中心にアルバイトの確保などが難しくなる傾向にあることなどから、方針を転換した。(2006年10月28日1時43分 読売新聞)・・・・・・・・・・・・・・・・・*アルバイトの年収は200万円程度、請負労働者の時給は1000円程度。*昇給やボーナスは基本的になく、年収は200万円程度だ。 ある試算によると、子どもを1人育て上げるのに2000万円かかる。ところが非正規雇用者(請負、派遣、パートなど)の生涯賃金は6000万円程度で、正社員の3分の1。 子育てどころか結婚さえあきらめている人も多い。 旧UFJ総合研究所が昨春発表した調査では、25~39歳の非正規雇用者が正社員になれないことで婚姻数は年間5.8万~11.6万組減り、毎年生まれる子供の数は13万~26万人も減少する。 請負労働者は、非製造業も含めると、200万人を超えるともいわれる。「おそらくこの人たちは、一生浮かび上がれないまま固定化する」と労働局の幹部さえ言う。正社員をひとりも雇わず、低賃金でクビを切りやすいアルバイトで賄おうとした郵政公社。いかに人件費を安くあげるかのみを考え、働く人のことなんか、かまっちゃいられない。このままだと、社会の基盤さえ揺らぎかねないほど、雇用の問題が深刻化している。 郵政民営化って、けっきょく、アルバイトを増やすことだったのに、*「郵政民営化」*に賛成した、議員たちは、安倍総理は知っていたのだろうか。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月28日*みのりの秋:イチジク&枝豆・・・送別会にて *UP
2006.10.28
コメント(10)
-

新庄効果
日本ハム優勝!おめでとう、新庄選手、日ハム選手、北海道のみなさん!!\(゚▽゚*)/第5戦目は、地元、札幌地区は52.5%、瞬間最高視聴率が73.5%という驚異的な数字。関東地区は25.5%、関西地区は26.5%、名古屋地区は31.4%、北部九州地区は24.2%と軒並み高い視聴率。シンジラレナ~~イ!!私も第1戦から見ていて視聴率を上げるのに協力しました。♪(* ̄ー ̄)この人気、ひとえに新庄効果。最後の試合になった日、使っていたグローブ。それは、阪神に入団した18年前に7500円で買ったものという。以来、阪神時代にも、アメリカの大リーグ時代にも、日本ハムに移ってからも大切に使っていたという。湿気から守るために、テレビの上に置いたりして、大切に使っていたという。新庄といえば、派手なパフォーマンスで有名。けれども、このグローブに、商売道具を大切にするプロのこだわりのようなものが感じられた。ものを大切に長く使う・・・。こっちも新庄効果を期待したいな。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月27日*「鎮守の森」考 *UP
2006.10.27
コメント(4)
-

昔語り:「フシのくちあけ」
子どもの頃からお喋りで「口上でこ」と呼ばれていた父から聞いた話です。「ワシのおかぁは・・・」と父が言いました。「ワシのおかぁは(私の祖母)は、手八丁、口八丁じゃた。」父の話は続きます。父の母、リョウは、そろばん片手に、山から採って来る*「フシ」*の仲買をしていました。フシは農家の大切な現金収入。みんな、競って、山へ採りに行きます。そうすると、まだ大きくなってないのまで、採ることになります。だから、皆で、きまりを作り、大きくなるまで、採らないと決めます。ところが、どこにもズルイ人がいるものです。「フシのくちあけ」の前日に山に入って採り、隠しておき、さも、その日に採ったような顔をして、リョウに売るのです。でも、誰かが、見ているものです。「○○さんは、前の日に、採ってた。」「そんなことを耳にすると、おかぁは、もうその人の採ってきたフシは買わなんだ」と父が言いました。掟を破る者を許していると、山の資源は守れないのです。「フシのくちあけ」とは、フシの解禁日、その日を決めるのは、人間と自然です。**フシ**(写真)ヌルデに虫がつくるコブのようなもの。私は、小さい時は、果物かなと思ってた。フシは昔は「おはぐろ」や白髪染めに使われていたそうです。父が採りに行ってた頃、「おはぐろ」をしている人はいなかったし、何に使ってたんだろう。染料かな。聞いとけばよかった。■2002年11月02日に書いたものを加筆しました。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月26日*ハレとケ/父の麦わら帽子:ドンゴロスいっぱいの松茸 *UP
2006.10.26
コメント(0)
-

白州正子、森 茉莉、ターシャ・テューダー:憧れの老女
白洲正子、森 茉莉、それにターシャ・テューダー。私のあこがれの三大老女。でもどれもなれそうにないな・・・。ってあたりまえやん、だから憧れの人だもん。*白州正子*白州正子は、骨董などに造詣が深く多くの本を出している。美食家にして陶芸家という、かの有名な魯山人に「それにつけても魯山人、あの人は美術品に関してはそれは大変な目利きでした。けれども全く教養のない人でしたね。ほんものの目利きなら、使用人に対しても気配りするはず。ところが、やたらに自分だけが威張りたくるの。私、あれほど教養のなくて目だけ利く人がいるのが珍しくてしかたなかった」と散々。白州正子、ちょい怖ばあさん。**森 茉莉**明治の文豪、森鴎外の娘、森 茉莉は、超お嬢様!離婚後、貧しいアパート暮らしをするも、持ち前のノウテンキさと妄想癖で「アパルトマンに住む」と言い切る。( ̄m ̄*)彼女の73歳の時の夕食は、材料がないところからはじまっている。バターも卵もなく、肉類もない。ご飯を炊いたとしてもおかずがないのだ。そこで彼女は紐育(ニューヨーク)製の即席珈琲(コーヒー)でアイスコーヒーをつくり、パンを焼き、そして白桃の缶詰を開ける。普段のちょっと手をかけた夕食とは違うが、彼女は、「アメリカの独身の男の、メイドが俄(にわか)に休暇を取った日の、カリフォルニアの桃のジャムと珈琲とパンである。」森 茉莉、贅沢貧乏ばあさん。***ターシャ・テューダー***アメリカのバーモンド州に住み、広大な庭園で、19世紀の服を着て花の世話をするターシャは、おん年、90歳。これまでに、100冊近くの絵本や物語の挿絵を描いた画家。でも、その質素で優雅なその生活スタイルの方が有名。1830年代が一番ぴったりくると、日常のもののほとんどを手づくりしながら、19世紀風の生活をしています。ターシャの美意識で選ばれた食器・調理器具・衣類・靴・ガーデン用品・雑貨などと共に約30万坪の庭には季節ごとに、たくさんの花々が咲く、園芸家としても有名。ターシャ・テューダー、スーパーばあさん。・・・・・三人に共通するのは、強烈な個性と執着心。骨董品が好きだけど、モノがない生活にも憧れる私は、持っている古いモノを売ろうかと思ってます。個性も執着心もない私。でも、妄想癖はある。( ̄m ̄*)■□■テレビしびれて■□■★のだめカンタービレのだめの着ていたワンピース、マリメッコだった♪ 人気blogランキングへ
2006.10.24
コメント(20)
-

「霜降」だけど・・・。
霜降。立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。霜降(そうこう)は二十四節気の1つ。10月23日ごろ。および、この日から立冬までの期間。太陽黄経が210度のときで、露が冷気によって霜となって降り始めるころ。楓や蔦が紅葉し始めるころ。この日から立冬までの間に吹く寒い北風を木枯らしと呼ぶ。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』10月も下旬だというのに、まだ会社には半袖で行ってます。通勤にはさすがに長袖を着るのですが、会社に着くと半袖に。コピー、パソコン、ファックス・・・。会社には、熱を発するものがいっぱい。昔ならとっくに「衣替え」で秋の衣装だったのに、町を歩いていても、まだ半袖の人もいたりします。*朝顔も咲いてるし*、ほんと、地球温暖化をひしひしと感じる今日この頃。とはいえ、朝夕は冷え込みます。霜降の次は「立冬」。本格的な秋はこれから。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月23日*宵越しの茶は飲むな*UP
2006.10.23
コメント(8)
-

お寒い大阪のヒートアイランド対策
1階部分にカフェをつくり、人が集まるような御堂筋にしようと、御堂筋のビルの高さ制限を緩和すると、企む大阪府。きちんと揃ったた高さが壊れバラバラになると、御堂筋の美しい景観が壊れる。それと共に*「ヒートアイランド」*現象にも拍車がかかる。「ヒートアイランド」とは、都市部の気温が周辺部より高くなる現象。その主な原因は、*都市への人口の集中により各種のエネルギーの使用量が増え、排熱量が増加する。 *アスファルトの道路が昼間の太陽の熱射で深層まで高温となり、夜間に蓄積された熱が放出される。 *ビルなどの壁面が太陽熱で熱くなることなどがなどが、あげられます。+++大阪府は1977年、「府有施設の緑化基準」を定め、敷地面積に占める「緑化割合」を20%以上、府立病院といった医療施設は30%以上としました。2005年、大阪府がこれを守っているかというアンケートを900の施設に出したそうです。すると、達成したのは、900施設のうち、たった77施設。400施設は回答もしなかったそうです。(怒) (ノ`Д´)ノ彡┻━┻(朝日新聞2005.10.19)こんなお寒い「ヒートアイランド対策」の上、まだ御堂筋の高さ制限を緩和するなんて・・・。御堂筋のビルの高さを高くするということは、とりもなおさず、ヒートアイランド現象に拍車をかけることになるのが分かってやっているのだろうか・・・。 _| ̄|○ 写真は京都白川。水と緑がヒートアイランド化を防ぎ、見た目にも美しい。だから、人は京都に魅かれる・・・。決してカフェをつくれば人が集まるってもんじゃないのに・・・。美しい御堂筋を守ろう! 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月22日*みのりの秋:つるし柿*UP
2006.10.22
コメント(0)
-

大阪の宝、御堂筋がピンチ。
大阪のキタからミナミへと走る*御堂筋*。イチョウ並木とともに美しい御堂筋を演出しているのが、規律良く揃ったビルのスカイライン。これはビルの高さを一律「百尺(約31m)」に揃えるというもので、この制限により御堂筋の美しい景観が守られ大阪のシンボルといわれています。御堂筋の道幅と建物の高さは黄金比といわれる位に美しい。なのにこの美しい景観が今壊されようとしています。1995年に高さの制限が50mに緩和された時にも、「伝統ある景観が崩れる」と市民や建築学者が反対し、制限の存続を市に出しました。ビルが高くなるとどうなるのか。●バラバラの高さでは、全体として統一感に欠ける。●名物のイチョウ並木は、これ以上ビルが高くなると、ボリューム感が無くなる。建物のみが強調されて、イチョウ並木とのバランスが崩れる。●今の広々とした御堂筋は、高さ制限あってのもの。もし、高くなると、堂々とした御堂筋の品位が無くなる。1F部分にカフェなどをつくり、客を集めるための高さ制限撤廃というけれど、御堂筋じたいに魅力がなければ、カフェをつくっても人は来ないのに・・・。東京・銀座では、建物の高さは原則56mに制限。景観悪化への懸念から、例外を認めないという条例が可決された。なにかと評判の悪い*大阪市、*なにを考えているのか・・・。 _| ̄|○。美しい御堂筋を守ろう! 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月21日*大阪しぐれ:あもも団子も/イチョウのまな板 *UP
2006.10.21
コメント(6)
-

公園づくりの仲間になって下さい!
「いなか」がどんどん姿を変えています。ここ南河内でも例外ではありません。これまであった田畑は住宅に、川は排水路にと変わってしまい、30年前のおもかげもありません。私たちのふるさと・・・いつまでも変わらない場所・・・田んぼがあって雑木林や竹林のある場所・・・私たちの原風景・・・そこには野草摘み、花見、田植え、川あそび、稲刈り、たこあげ、とんど、と四季折々の行事があります。私たちの祖父母がやっていた、藁仕事や竹細工の伝承されます。自然を生かし、人が自然にはたらきかけ、その恵みを受け、それに感謝できる・・・。ほんの30年前には、そんな生活があたりまえでした。 私たち「****会」は、失われたそんな生活を再びとりもどせるような公園をつくりたいと思っています。単に木が植えてあって、きれいな花が咲いている、それだけの公園では、断ち切られた自然とのきずなを復元することは困難です。人と自然とを身近に結びつけるためには、季節ごとの農作業や遊びなど、生活に密着した活動ができる公園が必要です。**駅から南へ1Kmほど歩いたところにある**緑地があります。大きな木が繁り、小川や田んぼがあるところです。私たちはこの**緑地を市民の手で、人と自然とを結びつけるための公園にしたいと思っています。どうぞ、あなたも、公園づくりの仲間になって下さい!! ●今から17年前に、私が書いたチラシの一部です。文中、「30年前」となっていますが、今からだと50年近く前。●当時はまだ耳慣れなかった「環境問題」という言葉は市民権を得ましたが、地球環境は悪くなるばかり・・・。●**緑地は、国体のための体育館が建てられ、里山の風景は消えました。写真はうちの家の近所に残る田んぼの風景。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月19日*祭:♪祝ぉ~て三度 *UP
2006.10.19
コメント(2)
-

「島人(しまんちゅ)ぬ宝」:ウチナーグチ
僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知っているんだろう輝く星も 流れる雲も名前を聞かれてもわからないでも誰より 誰よりも知っている悲しい時も 嬉しい時も何度も見上げていたこの空を教科書に書いてある事だけじゃわからない大切な物がきっとここにあるはずさそれが島人(しまんちゅ)ぬ宝僕がうまれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう汚れてくサンゴも 減って行く魚もどうしたらいいのかわからないでも誰より 誰よりも知っている砂にまみれて 波にゆられて少しずつ変わってゆくこの海をテレビでは映せないラジオでも流せない大切な物がきっとここにあるはずさそれが島人(しまんちゅ)ぬ宝 僕が生まれたこの島の唄を僕はどれくらい知ってるんだろうトゥバラーマも デンサー節も言葉の意味さえわからないでも誰より 誰よりも知っている祝いの夜も 祭りの朝も何処からか聞えてくるこの唄をいつの日かこの島を離れてくその日まで大切な物をもっと深く知っていたいそれが島人(しまんちゅ)ぬ宝 それが島人(しまんちゅ)ぬ宝それが島人(しまんちゅ)ぬ宝 ・・・・・・・・・・・・・・京都市内を流れる鴨川の飛び石を飛んで入ったのが、*韓国カフェ「李青」*。その後、通りかかった京都大学の敷地で賑やかにお祭が・・・。沖縄の音楽をやっていて、BEGINの曲、「オジー自慢のオリオンビール」が流れていた。BEGIN、大好き!!!つい、聞き入ってしまった。なんでこんなに私はBEGINが好きなんだとうと考えてみた。彼らは、沖縄方言(ウチナーグチ)で歌詩の中に入れている。この「島人(しまんちゅ)ぬ宝」の<島人(しまんちゅ)ぬ>や「涙そうそう」の<涙(なだ)そうそう>。 ウチナーグチ(沖縄方言)は沖縄のアイデンティティだ。テレビが普及してから、言葉がどんどん、東京化して、その土地の持つ、方言=アイデンティティが失われて行く。昭和30年代の日本の歌謡曲の中にはまだ、望郷の思いを歌ったものが多かった。今や、電話にメールなどの発達によって都会との距離感はなくなった。それに、地方の川はダムで水量が減り、三面コンクリートの味気ないものになった。田んぼもやる人がいないなどかつての、日本人の心のよりどころだった「里山」は失われてしまった。でBEGINのウチナーグチ(沖縄方言)の詩と沖縄古来からのメロディからなりたっている。BEGINの歌からは、自分の生まれ故郷・沖縄の自然や文化に愛着を愛しているというメッセージが感じられる。そんなBEGINの曲に私たちは魅かれるのではないだろうか。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月18日*ごみ箱のない生活*UP
2006.10.18
コメント(6)
-

鴨川の飛び石でアイスブレイク
日記メイトのあずーるさんと京都に住む友人、カルメン嬢(仮名)←(本名だったら怖い)と京都で会った。京都の京阪・出町柳駅で待ち合わせて、橋を渡って近くのカフェにと思いきや、「ここから行きましょうか?」とカルメン嬢が、川の方を指差す道を降りると、川が目の前に・・・。そしてそこには、大きな平たい石や亀の形をした飛び石が!!!その飛び石をひょいひょいと飛びながら川を渡る。「わー!メダカがいてる」とか、「写真とっとこう」とか言いながら・・・。途中に中州がある。この中州で、去年の大ヒット映画*「パッチギ」*が撮られたそうです。(カルメン嬢は語る)中州を越えてまた、飛び石を飛んで・・・。途中、飛び損ねて、川に落ちた子どももいました。( ̄▽ ̄) 私たち3人は川に落ちることもなく、無事、向こう岸までたどり着いたのでした。それから3人のトーク炸裂!!( ̄▽ ̄) あずーるさんとカルメン嬢は初対面。なのに最初から、こんなに盛り上がったのは、飛び石が*「アイスブレイキング」*の役目を果たしたのではないだろうか・・・。「アイスブレイキング」とはなにか。かたい氷が解けるように、人間関係が溶け合って、リラックスして会話や会議がスムーズにいく為の行動。最初から、挨拶などをするよりも、体を使った方が人間関係もリラックスするといいます。実は、カルメン嬢と私はかつて、「里山に来た人がリラックスして過ごすのにはどうしたらよかろう」などと考え、アイスブレイキングの講習を受けた仲。この飛び石は、カルメン嬢の作戦?そうか、カルメン、おぬし、腕を上げたのう。( ̄ー ̄)■あずーるさんのブログ■ 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月17日*柿の木のある家*UP
2006.10.17
コメント(10)
-

50代の女性が「孫」を代理出産
娘の卵子使い、50代の女性が「孫」を代理出産したという仰天ニュースを読んだ。ということは、生まれた子どもの母親は、おばあちゃん?この事実を知ったら、生まれた子どもは将来、どんな気持ちで過ごすのだろう。代理出産した女性は閉経して子宮が委縮していたため、ホルモンを投与が行われたという。なんとも、不自然な出産だ。人間って、欲しいものがあったら、それが神の領域であったも、手に入れるのかと思う。赤ちゃんはかわいい。それは否定しないけれど、こういう記事を読むと、落ち込んでしまう。自分の血の繋がった子どもしか愛せないのだろうかと思って・・・。この子どもの親は、「家庭には子どもがいてあたりまえ。いないのが不自然」と思っているのではないのだろうか。先日、兵庫県に行った時泊まった友人は60代の独身。子どもはいないけど、親のいない子どもを年に一度、里子として迎えている。彼女の家には里子のための食器があった。血の繋がらない子どもに優しくする友人を私を立派だと思う。娘が2人いて、子どものいないもののことを知らないものがなにをいうのかという批判もあるだろうけれど、私は、代理出産には、反対です。代理出産と共に、臓器移植にも疑問が湧いてきます。このどちらも、人間の究極の欲望だと思うのです。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月16日*みのりの秋:山の幸・・・アケビ、フシ・・・/父の麦わら帽子:ないものあります*UP
2006.10.16
コメント(12)
-

京都妖怪通り
京都に今夜、妖怪が出る。京都・北野天満宮に近い一条通沿いの大将軍商店街(京都市上京区)に「妖怪」が現れた。平安時代、人に捨てられた古道具が妖怪になり、一条通を行進したという説話にちなみ、まちおこしのために古着や古道具を再利用してつくったオブジェだ。14日夜は、商店主や若者たちが仮装して「妖怪ストリート」と呼ぶ商店街を練り歩く。(略)まちおこしを始めたのは昨年の夏。古道具の妖怪が一条通を行進した説話が出てくる「付喪(つくも)神絵巻」や、釜などの妖怪が描かれた京都・大徳寺真珠庵(あん)の室町時代の「百鬼夜行(ひゃっきやこう)絵巻」から着想し、持ち寄った古着や破れ傘などでつくった。 約60人が参加する妖怪の仮装行列は14日午後6時半から。「リサイクル妖怪の力を借りて、環境にやさしい商店街を目指したい」と話している。 +++日本にはモノには、魂があると考えられてきました。折れた針一本でも壊れた人形でも、役目を終えたモノに対して、人間と同じように「供養」という言葉で処分したのでした。それは、今の捨てるとは違う、行為。捨てればすっきりと、暮らせるけれど捨てられないモノ。なら、買う前に、もう少し考えよう。そんなことを思う。**妖怪ストリート** 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月14日*みのりの秋:ヤッコメ(焼米)*UP
2006.10.14
コメント(4)
-

平成神無月
<第十一段 神無月>神無月のころ、栗栖野といふ所を過ぎて、ある山里に尋ね入る事侍りしに、遥かなる苔の細道を踏み分けて、心ぼそく住みなしたる庵あり。木の葉に埋もるる懸樋の雫ならでは、つゆおとなふものなし。閼伽棚に菊・紅葉など折り散らしたる、さすがに、住む人のあればなるべし。かくてもあられけるよとあはれに見るほどに、かなたの庭に、大きなる柑子の木の、枝もたわわになりたるが、まはりをきびしく囲ひたりしこそ、少しことさめて、この木なからましかばと覚えしか。<意訳>神無月の頃に、ある山里を訪れる事があった。その途中で栗栖野というところを通りかかると、長い苔の細道が踏み分けられその奥にはひっそりとした佇まいの庵がある。木の葉に埋まる懸け樋の水音だけ、何の音もしない。仏さまに供物をささげる閼伽棚には、菊や紅葉が折り散らされ供えられている。さすがに住む人があるからなのだろう。こんな生活もあるのだなと哀れを感じて見ていると、むこうの庭に枝もたわわに実る大きなミカンの木があった。その木の周りをミカンを盗られまいときびしく柵で囲っている。少し興ざめして、こんな木はない方がましかなと思った。・・・・・・・・・・・・10月10日の夜から12日まで、友人Y子と一緒に、山里に住んでいるH子を訪ねた。クネクネとした細い地道を踏み分けた奥にH子の家はあった。家の前には、ミズヒキソウが咲き乱れ、物音ひとつしない。街灯もない真っ暗な闇の世界・・・。こんな生活もあるのだなと思って感心した。家の中に入って、がっかり。モノがいっぱい。モノがなければなと思った。+++私たちはどこに住んでもモノから開放されないのかと思った。でも楽しい2泊3日の旅でした。(^-^)H子、Y子、ありがとう。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月13日*ごめんね、母さん・・・祭のごちそう *UP
2006.10.13
コメント(0)
-

木造住宅今昔:「大改造!!劇的ビフォー アフター」
大昔の農家の自宅は、山から切り出してきた材木を1年以上も庭に寝かしてから建てました。夏をむねとする家づくりだから、冬の寒さは着るものの量で調整していました。現在は、コストと施主の欲望と国の政策の問題からか、見た目を気にした防カビ材漬の生木を使い、短期工法で手間を押さえ、省エネと言って隙間をなくしてきています。では、はたして住宅の耐久性としてはどちらが上なのでしょうか。もちろんいろいろなことが研究されてきた現在の住宅が上に決まっています。でも、構造材のおかれている環境が良好なのは昔の住宅ですから(木は動く空気に触れていれば腐らない)、同じ理解のもとで造られていたとしたら長期的に見てどうでしょうか。人間が暮らしていく環境には自然の材料でできた住宅が一番適しているはずですから、もっと現在の木造住宅の問題を真剣に受け止め、人間と共存していける工夫をして造っていくことが大切な事だと思います。 ・・・・・・・・・テレビで「大改造!!劇的ビフォー アフター」という番組を見た。玄関から入れないような家も「匠」の力を借りれば、あら、不思議。ステキな家に変身\(゚▽゚*)/でも、床暖房に壁の防音防寒などなど、文明の知恵を駆使したやり方に一抹の不安が残る。かつて、火事に強いといわれ使われた、*アスベスト*によってもたらされる病気が問題になっている。今、なにも問題がなくても、これが、将来、病気を引き起こさないか・・・。効率やコストを重視するより、木が本来もっている力や性質を利用した方がいいと思うのだが・・・。それにしても、うちもフォームしたい・・・。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月12日*里山の歌:村祭 /トリビアの井戸:「胴上げ」は、厄落としだった。/運動会デビュー:おもちゃとり *UP
2006.10.12
コメント(4)
-

知らない町を歩いてみたい。
友人と一緒に、兵庫県・三田市と*丹波篠山*に行くことになった。兵庫県には、12年間住んだことがあるし、大阪の隣なのでよく行っている。母がいるし、妹が結婚して暮らしている。若い頃、龍野市で過ごした関係で出来た友人が姫路にいる。神戸にも時々行く。なのに、三田には行ったことが無かった。どこにあるのかさえも知らなかった。調べてみたら、けっこう神戸から近い。そして、その三田市からデカンショ節で有名な丹波篠山は近いのだった。私たちは、東京のことはよく知っている。東京のどこに、どんなショップがあるとか、あそこは、なにが美味しいとか・・・。けれど、東京までの間にも、いろんな町があり、いろんな店があり、いろんな人の暮らしがある。そんなガイドブックに載っていない小さな町を見るのも楽しいかもしれない。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月9日*落穂拾い*UP
2006.10.09
コメント(2)
-

トリビアの井戸:道普請
秋祭の前の準備に、*道普請(みちぶしん)*があります。道の草を刈ったり、邪魔になる木の枝を払ったり、階段を直したり・・・。祭の客が歩きやすいようにとこの時期やるのです。ところで、道普請の「普請」とは。普請とは、普(あまね)く請(こ)う、つまり、「大勢の人々に労力をお願いする」という意味の禅語で、起源は鎌倉・室町時代にさかのぼります。へえ~、へえ~!!昔は道だけでなく家を建てることも「普請する」といってました。お寺、道、水路などの修繕、維持は地域の人々が、お互いの思いやりの気持ちをもって、力を合わせて行いました。道路は、もともと、地域を支えるコミュニケーションの場でした。しかし、車社会になり、行政が道路をつくり、管理するようになってから、人々の心は道から離れ、地域からも離れてしまいました。今、道路をはじめとする公共事業のあり方が問われています。豊かな暮らしの創造に向けて、「個」がお互いに力を合わせて「公」をつくる、これこそが「公共」のあるべき姿ではないでしょうか。 「ひと みち くらし」より市民が無関心だと、行政は、いらない道路や新幹線までつくってしまいます。そういう意味でも、無関心ではいられません。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月8日*「雨の名前:通草腐らし(あけびくさらし)」*UP
2006.10.08
コメント(0)
-

満足ですか?
「夏が一番きれいね」と 私が言へばあの人は 「いいえ秋です」さう言って とても寂しく微笑んだ 榊原敦子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・すっかり秋になってしまった。あの暑かった夏はどこに行ったのだろう。+++秋祭り、ご馳走、出店、栗、柿、松茸、稲刈り、はざかけ、収穫、アケビ、椋の実・・・。子どもの頃、秋には、楽しみがいっぱいあった。中でも一番の楽しみ、秋祭りを障子を貼りなおして、明るくなった部屋でウキウキしながら待った。村のはずれには、田んぼが広がり、刈り取られた稲が天日干しされていた。あの頃の村は、人々は、秋が来ると、輝いていた。あの頃の人々は、貧しかったけれど、満足感のある生活をしていた。今はモノに囲まれても、まだ足りない、まだ足りないと買い求める。しかし、決して満足は買えない。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月7日*芋名月*UP
2006.10.07
コメント(2)
-

「ストーブ貸してくんちぇ」で思い出したこと。
「ストーブ、貸してくんちぇ。」話題の*「「フラガール」*に出てくる、心優しき人たちが、椰子の木を暖めようとストーブを集めるシーンがある。閉鎖に追い込まれた福島県・常磐炭鉱に代わりのウリとして「ハワイアンセンター」をつくる。そのために、椰子の木が送られてきて、冬を越させるというシーン。温室の中で、ストーブをガンガンたいて、暖めようとするシーンです。+++「ストーブ貸してくんちぇ」で思い出したことがある。長野県は野菜や果物の産地。けれど、冬は寒い。その寒さを乗り越えるために、温室でストーブを焚かなければなりません。ところが今年は、燃料費が高い。そこで、「JA長野」は、農家が使う温室用の燃料費の一部を負担するというニュースをテレビで見ました。うーーむ。農家のとっては、嬉しいことかもしれない。消費者にとっても、灯油の値段を野菜に上乗せされないから、嬉しいことかもしれない。でも、環境問題を考える私としては、やっぱりこれは、困ります。ただでさえ、長野県から大阪までのトラックの運送に、CO2が排出されるのに・・・。寒い地方にしか出来ない野菜を作るとか、温暖な地方が冬場は負担するとか、ごみ処理の熱を利用するとか・・・。これ以上の地球温暖化を防止するためには、私たちも、なにかガマンしなければならないことがあるはず。「私たちの地球は私たちの地球であると同時に、死者たちの地球であり未来者たちの地球なのだ。彼らの同意なしに私たちが勝手に処理してよいわけではない。」 高橋睦郎『未来者たちに』(みすず書房) 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月6日*「鎮守の森」考 / 台風のあと・・・椋(むく)の実ひろい *UP
2006.10.06
コメント(2)
-
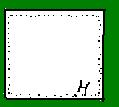
国体は必要か
ハンカチ王子こと斎藤祐樹投手と駒大苫小牧の田中将大(まさひろ)投手で大いに盛り上がった、国体の高校野球。二人の対決を見たいと徹夜組が続出したとか。でも、他の競技はどうだったんだろう?他の競技が人気があったということを聞かない。国体は必要なのだろうか? 4年に一度、オリンピックがあるし、サッカーはワールドカップがある。○○マラソンとか□△陸上といったものもある。高校野球だって、春夏の甲子園大会がある。それらで勝った方が国体で優勝するより、選手にとっても名誉なことだろう。 私も国体に対してなんの疑問も持たずに過ごしてきた、今から15年ほど前までは・・・。大阪で開かれた「なみはや国体」のために、体育館が建てられることになった。たった数日のために、私の住む町の市街地に残された一万坪の里山が壊されたのだ。なんとか残そうと、みんなで署名を集めたり、市長との対談をしたり、チラシをまいたり・・・。しかし、国体という目的で建てれば、国からの補助金が沢山出る。だから今しか建てるときはないとばかりに、建てられてしまった。何十年、いや、何百年もかけてつくられた里山の風景があっというまいに味気ないコンクリートのハコモノになってしまった。その時、はじめて国体は、自然破壊に加担するものと知った。国の税金を使って意味のないことをやるのは、もういい加減にして欲しい。国の税金を使って、自然破壊をするのは、やめて欲しい。 ←「かつめし」は高校野球の会場となった高砂市の名物です。■お月様0015の日記■それぞれの種目の強化には程遠いですし、選手や関係者が勝ちに行く大会でもない。人気のある大会ではないので地元の学校の先生と生徒が大量動員され客席を埋めるだけ。開催自治体が優勝するのが通例となっている事もやる意味を失わせるのを加速しています。それぞれの自治体が持ちまわりで、そのたびに土地が余っている辺鄙な場所に使い勝手の悪い箱物を建築し、その後始末に困るだけ。◆◇◆おしゃれ手紙25天使のメッセージ◆◇◆ 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月4日*トリビアの井戸:運動会と綱引き *UP
2006.10.04
コメント(12)
-
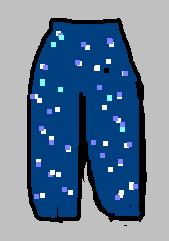
「紙屋悦子の青春」★静かに反戦を描く
■あらすじ■映画は病院屋上の老夫婦の「回想」からはじまる。敗戦の色濃い昭和二十年・春。両親を失ったばかりの娘・紙屋悦子は、鹿児島の田舎町で優しい兄・安忠、その妻・ふさと肩を寄せ合う慎ましい毎日をおくっていた。そんな彼女が胸に抱く願いは家族の平穏と、密かに想いを寄せる兄の後輩、海軍航空隊に所属する明石少尉の無事だけである。ところがある日、兄は別の男性との見合いを悦子に勧めてきた。それも相手は明石の親友・永与少尉で、明石自身も縁談成立を望んでいるらしい。傷心を押し隠し、永与との見合いに臨む悦子。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人を好きになることさえも許されないそんな時代でも、今と同じように、ご飯を食べる・・・。この映画は、食べるシーンが多かった。悦子と兄夫婦が揃って食事をするシーンが何回もあった。そんな時に食卓にのぼるものは、「配給」で手に入れた食材であり、何年か前のお土産のお茶だったりする。客を迎えるために、大事にとっておいた、小豆を炊いて、おはぎを作る悦子を兄嫁。戦時下の庶民の姿を淡々と描いた映画です。そんな、つつましい生活の中からも戦争に対してのやりきれなさが感じられます。赤飯とラッキョウは、敵の弾に当たらないという迷信を泣きながらいう兄嫁。「赤飯は赤飯らしく、ラッキョウはラッキョウらしく食べたい。」映画は、華やかなものは、なにも出てこない。場所は、紙屋家。衣装は、男は軍服、女はもんぺ。戦争という制約のある時代、人は華やかな服を着ることも美味しいものを食べることも許されなかった。出演は、悦子、兄、兄嫁、明石少尉、永与少尉のみ。戦闘機が出ていなくても、逃げ惑う人を描かなくても、戦争映画は作れると思った。★黒木和雄作品★「TOMORROW 明日」(1988年)1945年8月8日、長崎。看護婦のヤエと工員の庄治は、ささやかな結婚式を挙げた。その宴に来ていたツル子は、記念写真を撮り終えたところで陣痛を訴える。その夜、ヤエと庄治は初夜を迎え、ツル子は男の子を出産した。そして、それぞれに希望に満ちた明日を迎えようとしていたのだが…。黒木監督の真摯な演出が光る、戦争レクイエム三部作第1弾。「美しい夏 キリシマ」(2003年)1945年の夏。満州から引き上げてきた中学生・日高康男は、空襲のショックで病となり、祖父の住む霧島で療養生活を送っていた。敗戦の影が色濃くなるなか、罪悪感を募らせていく康男は、空襲で爆死した沖縄出身の親友の妹に会いに行くのだが…。黒木和雄監督が少年期を過ごした宮崎の美しい村を舞台にした、戦争レクイエム三部作第2弾。「父と暮らせば」(2005年)原爆投下から3年後の広島。愛する者たちを失い、自分が生き残っていることに負い目を感じている美津江の前に、原爆資料を収集している木下が現れた。幽霊となった父親は、木下への恋心を押さえつける美津江を励まし続けるのだが…。井上ひさし原作の同名小説を映画化した、戦争レクイエム三部作第3弾。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月3日*大阪しぐれ:打たれ叩かれ*UP
2006.10.03
コメント(0)
-

「フラガール」★頑張る女たち
人生には降りられない舞台がある。まちのため、家族のため、友の人生のために、そして自分の人生のため、少女たちはフラダンスに挑む。*「フラガール」*、(♪音が出ます)見てきました。映画『フラガール』は、常磐ハワイアンセンターのオープンまでの実話を背景に、東京からきたダンス教師と、炭鉱の娘たちとの感動コメディ。笑って、泣いて、感動して、いやー、いい映画でした。「フラガール」見てくんちぇ。(福島の方言)( ̄m ̄*)■あらすじ■昭和40年、エネルギーの主役がかつて「黒いダイヤ」とまでいわれた“石炭”から”石油”へと変わり、閉鎖に追い込まれた福島県・常磐炭鉱。炭鉱会社はヤマの地熱と捨てていた温泉を利用してのハワイアンセンター建築を計画を打ち出した。目玉となるのは、フラダンスのショー。早速、本場ハワイでフラダンスを学び、松竹歌劇団で踊っていたという平山まどか(松雪泰子)を東京から招き、地元の娘たちのダンス特訓を始める。半裸の衣装が、保守的な人々の目にはストリップと混同されてしまうなど、“ハワイ”を作る計画に大反対。かつては花形ダンサーであったものの、旬を過ぎ、やむを得ず東京からいわきにやってきたダンス講師、まどかはやる気なし。習う方も「フラでもやるべ」という簡単な考え。当然、教える方も、習う方もしっくりいかない。ある日、少女達は、まどかの踊りを見て、少女たちがフラを見直す。「フラでもやるべ」から「フラが踊りたい」という気持ちになり、猛特訓が始まる。母に猛反対されながらもフラに魅了されていく少女を蒼井優が、地元の男たちを豊川悦司や、炭鉱に生きる気丈な母役を富司純子が演じる。人生には降りられない舞台があると知った少女達の成長が描かれた映画だ。いつもの私なら、東北になんでハワイ?と怒るところだけれど、いやー、こんなわけがあったんですね・・・。見所は沢山あるけれど、★フラダンス&タヒアンダンス。大勢で繰り広げるフラは、見もの。また、フラには、手話の要素があるが、東京に帰ろうとする、まどかに紀美子(蒼井優)らが、電車の窓越しに「話しかける」フラなど、フラの魅力満載。知人にフラを習っている人がいるけど、私も今度、教えてもらおう( ̄▽ ̄) ★蒼井優若手ナンバー1というだけあって、すごい存在感。小さい時から、バレエをやっていたという蒼井優のフラはよい♪彼女の顔から、なんだか、憂いを感じてしまうのだけど、役柄のせい?★60年代ファッションまどか(松雪泰子)の60年代ファッションは、新鮮でかっこいい!!まどかのモデルになった人は、70歳の今も健在で、指導者なんですって。+++豊川悦司扮する、紀美子の兄が言う。「お前も(紀美子)も、ダンス教師も、母ちゃんも、ほんと、強いな!!」「フラガール」は頑張る、元気女たちの映画だ!■おまけ■「フラガール」が、米アカデミー賞最優秀外国語映画賞部門に日本代表として出品されることが決定しました! 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月2日*道普請(みちぶしん)*UP
2006.10.02
コメント(14)
-

インテリア歳時記:なにはともあれ、おかたづけ
朝夕の空気が冷たさを増してキュッと身の引き締まる季節です。10という区切りの月がやってくると、かたづかないこと、先延ばしにしていたこと、なんとかしなくっちゃと反省します。「おかたづけはインテリアの基本です。なにはともあれ、おかたづけをしないと、他の発展的なことを考える余裕など生まれません。」とセミナーでは昔の家庭科の先生のようなことをいいます。自分でも耳が痛いのですが、これはどんな目的の部屋にも共通の課題だから、避けては通れません。「インテリア・レッスン」津田晴美・・・・・・・・・・・・・・・・インテリアのことを考えるのって大好きなのに、部屋が片付かない。(ノД`)理由は優柔不断な私の考え方。例えば、新聞。整理整頓がキチンとできる人は、新聞を読み終わったら、即、ゴミ箱に捨てる。が、しかし私は出来ない。新聞って、廃品回収に出せば、また紙としてよみがえるやん、とか、新聞に載ってる、ここに遊びに行ったみたいから、切り抜いておこう、とか、これは、ブログのネタになるから切り抜いておこうとか・・・。もちろん、利用しています、ブログのネタに。でも、新聞紙だけではなく、映画のチラシも、雑誌も・・・。今日、見てきた映画、「紙屋悦子の青春」の時代は昭和20年。テレビも、PCもなく、茶の間には、ちゃぶ台が、悦子の部屋には、小さな机が・・・。モノが溢れかえる私たちの暮らしは、得たものと同じくらいに失ったものが多いと思った。嗚呼、すっきりとした部屋で暮らしたい!!なにはともあれ、おかたづけしないと・・・。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★10月1日*「園芸家12ヶ月:10月の園芸家」:収穫の秋 *UP
2006.10.01
コメント(4)
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- 【レポ】内容違いで販売中「訳あり黒…
- (2025-11-15 20:12:44)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-
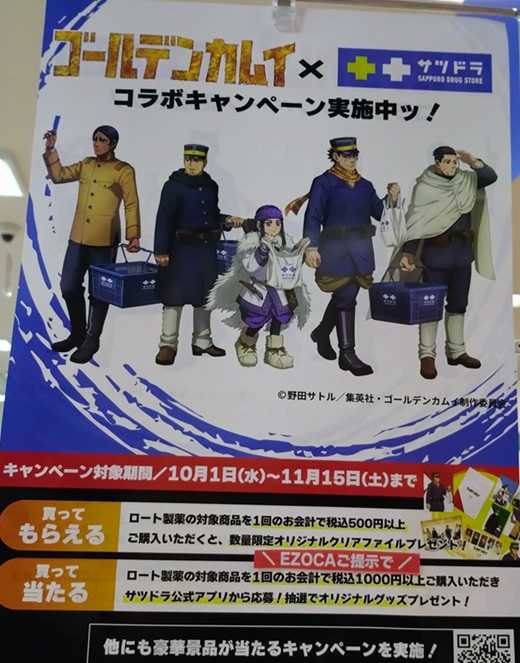
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…
- (2025-11-15 17:02:59)
-






