2007年03月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
小説 上杉景勝(76)
三成は島左近と練り上げた戦術方針にたって、畿内の東軍の諸城を陥し、濃尾平野に進出し、西上してくる家康の軍団と決戦にもち込む作戦であった。 それには真っ先に伏見城を陥す必要があった。 七月十九日の夕刻から攻城戦がはじまった。双方とも銃撃戦で終始し双方とも軽微な損害をだしたにすぎない。 二十二日に西軍の主力部隊が到着した。総大将、宇喜多秀家。その下に小早川秀秋、毛利秀元、吉川広家、島津維新入道、長曾我盛親、小西行長、毛利勝信、鍋島勝茂、立花宗茂、安国寺瓊等である。総勢、四万名が鳥居彦右衛門を城代とする、千五百名の籠もる伏見城を包囲したのだ。 だが、西軍の士気はあがらず、緩慢な銃撃戦で日々を空費している。それは西軍の総帥毛利輝元が大阪城に居座り、積極的に戦闘に参加しないことが原因であったが、関東の家康の動向を気にした日和見の諸侯が居たことも一因であった。佐和山城に拠る石田三成は、この戦況を知り伏見に駆けつけ諸将を叱咤した。 「銃撃戦では城は陥せん」 例の顔つきで宇喜多秀家に噛みついた。「治部少輔、言葉が過ぎる」 宇喜多秀家が声をあらげた。 彼等、西国、九州の大名は朝鮮の役で、嫌というほど戦闘に明け暮れた大名たちである。合戦を知らぬ三成に苛立ちをつのらせた。「さらば総がかり為されよ」 こうまで云われたら引き下がれない。 これが功を奏し西軍諸侯が奮い立ち猛烈な攻撃を始めた、八月一日に伏見城が陥落し、守将の鳥居彦右衛門は壮烈な戦死を遂げた。 気勢のあがった西軍は伊勢を席巻し、石田三成は六千名の兵を率いて大垣城を攻略し東軍への圧迫を強めた。「上様、なぜ小山に居座っておられます、諸将の動揺が烈しくなっておりますぞ」 心配した本多正信が家康の本心を訊ねに訪れた。「わしは思案中じゃ」 「上杉家攻略のことにございますか?」「そうじゃ。わしの謀臣といわれた男じゃ、思慮をかさねよ」 家康の苛立ちの声を背に、正信は陣屋にもどり思案を重ねていた。「内符は、何を恐れておられる」 陣屋の外から声が聞こえる。「佐竹殿を恐れておるのじゃ」 唐突に正信の顔がほころびた。 この下野の東に常陸(ひたち)の地がある、そこを領する水戸城主が佐竹義宜で、五十四万五千石の大名である。すでに家康に加担するとの使者は訪れていた。併し、義宜は石田三成とは格別の間柄の武将として知られている。さらに会津の上杉家とは昵懇の家である。両家がひそかに連携しておれば大変な事態となる。 「これじゃ」 本多正信が膝をたたいた。「上様、策ができました」 聞いた家康が肉太い頬をくずした。「正信、ひそかに噂を流せ。佐竹義宜(よしのぶ)は我が味方とな」「畏まりました」 人とは可笑しなものよ、真実を話しても信用せぬが、噂は信用する。本多正信の流布した噂話が諸将連の耳に届いた。「流石は内符殿じゃ、もし佐竹家と上杉家が同盟いたしおれば、腹背から挟撃され我等の墓所は会津の地となった」 諸将連の動揺がぴたりと治まった。 家康は秘かに間者を佐竹領に放った。彼等のもちかえる情報は佐竹家に不穏の形跡あり、と一致したものであった。 家康の顔が曇った。情報が正しいならば一大事である。上杉家と佐竹家の領土は、優に百七十万石を超えるものである。 ここで軍団を上方に転進させるには、余りにも危険が大きすぎる。 家康の使者が伊達政宗と最上義光のもとに奔った。上杉家の北方を脅かす、これが目的であった。両人とも信頼できぬが仕方があるまい。 さらに越後の堀秀治にも越後口への出陣を促した、これは軍団を反転させる際の、上杉勢の追撃を牽制するための策であった。 家康は矢つぎ早に次の手をうった。上杉家の封じ込めを狙った伊達政宗、最上義光、向背定かでない佐竹義宜の牽制役として宇都宮に結城秀康を配した。結城秀康とは家康の次男として生まれたが、秀吉の養子となり、のちに乞われて下総(しもふさ)結城城主の結城晴朝(はるとも)の養子となっていたが、 豊臣家に対し好感に近い複雑な思いをもっていた。 それは上杉家に対しても同様な感情を抱いていたのだ。小説上杉景勝(77)へ
Mar 31, 2007
コメント(12)
-
小説 上杉景勝(75)
家康一行は京極高次の大津城下をへて五奉行の一人、長束正家の居城の水口を経由し、六月二十一日に三河に入った。 会津征討の総帥家康は諸侯に江戸参集を命じておいた。 家康は悠々と東海道を下り、七月二日に本拠地の江戸に到着した。 江戸では家康の会津征伐に従軍する、諸侯の兵士が駐屯し総兵力は五万名におよんでいた。まだ、遠国ゆえに参集の送れた者もいるが、全兵力が揃えば六万ほどの大兵力になろう。 家康は彼等が、豊臣家恩顧の大名であることに満足していた。(三成、早う挙兵いたせ、わしはこれ等の大名を引き連れて上方にもどる。これらの者共の力で天下を手中にいれる) と嘯いていた。 諸大名は江戸城で質素な饗応をうけ、その後に軍議が行われた。家康は会津征伐の基本方針を述べた。「先鋒は我家の榊原康政(やすまさ)に申しつけまする。 諸大名から不満の声があがった。「内符の仰せながら、その儀を納得まいらぬ」 福島正則や黒田長政等の荒大名たちであった。「おのおの方の申しでは有り難いが、この度の合戦は我家の戦法で行う所存。榊原康政が先鋒は徳川の戦法、ご異存のある方々は、この場からお引取り頂いて結構にござる」 肥満した体躯の家康が分厚い瞼から眼を光らせた。 一同は家康の気迫に押され引き下がった。「この征討軍の総大将は中納言秀忠に命じます、勿論、わしも出陣いたすがの」 家康が、ゆっくりと一座を睥睨するかのよう眺め、腰をおろした。代って家康の謀臣、本多正信が痩身を晒し、しわがれ声をあげた。「軍議の基本方針を述べます。我等は白河口より攻め寄せ会津領に侵入いたす。合戦の命は、当家の下知に従って頂きます。抜け駆けの功名なんぞは一切慎まれたい」 「抜け駆けも成りませぬのか?」 正則が吠えた。「左様、上杉勢は万全な備えで待ち受けております。万一、抜け駆けなんぞで失敗したら、我等は援軍を送らねばなりません。それは上杉にとり、もっけの幸いとなりましょう」 正信が細い眼で正則を盗みみて口を閉ざした。「諸侯に申し聞かせる。正信が申したとおり、抜け駆けなんぞしたら会津一帯に戦火が拡大いたす。日和見の諸大名が、これ幸いと反旗を翻したら一大事じゃ」 家康の躯から往年の気迫が滲みでている、そのまま言葉を継いだ。「まずは各々方は出馬の準備を為されよ。榊原康政は十三日に出陣いたせ」「畏まりました」 榊原康政が戦場焼けした声で応じた。「中納言殿は翌日に全軍を率いて出馬なされよ。わしはゆるりと参る」 家康は言葉どおり二十一日に江戸を発足し、二十四日に下野の小山(おやま)に宿営した。諸将連から不審な声があがった。「何ゆえに小山に軍団をとどめおかれる、今回の出馬は会津攻めじゃ。何ゆえ会津に近い要衝の地に宿営なされぬ」 それは当然の疑問であったが、家康には他の思惑があった。彼は三成の挙兵の知らせを待っていたのだ、その知らせと同時に軍団を上方に反転させねばならない。(正則、長政よ、わしの心がよめるか) 家康が胸中で毒づいた。 石田三成挙兵の知らせがもたらされた。それは昨夜の夜半のことである、上方から駆けつけた忍びの者の知らせであった。「とうとう動きよったか」 家康の顔が興奮で赤らんでいる。 七月十七日、五奉行の長束正家、増田長盛、前田玄以の三名の連署で、徳川家康を弾劾する。「内符ちかひの条々」が発せられた。 これは家康が太閤の遺命に叛いている罪科十三ケ条をあげ、諸大名に挙兵を促す決起書であった。同時に五大老の毛利輝元、宇喜多秀家による、家康への弾劾書も発せられた。 これは当然、石田三成が首謀者として五奉行を動かした結果である。西軍総帥として毛利輝元が四万の兵を率い、大阪城西ノ丸に駐屯してきた。政治の補佐として五奉行の増田長盛がおり、軍事面の補佐官として岡山城主の宇喜多秀家がいたが、三成の名前はない。 しかし両軍とも石田三成が、西軍の事実上の総大将であると認めていた。小説上杉景勝(76)へ
Mar 30, 2007
コメント(9)
-
小説 上杉景勝(74)
左近は数日滞在し、佐和山城にもどり会津での会談の模様を復命した。「こと敗れれば、上杉家は全滅を覚悟されると申されたか?」 三成は直江山城守の強烈な美意識をその言葉から感じとった。 (反転) 家康は西ノ丸で一人思案している、明日には本丸にあがり秀頼公に暇乞いをする。わしが出陣すれば阿茶ノ局など側室が困ることになろう、あくまでも豊臣家の御為に、会津に出陣する、これが名目である。 幕下に連なる諸大名は、妻子を人質として大阪城に残してゆく。 家康一人だけが、連れ去るという訳にはいかない。 「不憫じゃ」「佐野肥後守を呼べ」 と近習に命じた、家康はこの男に側室を任せることにした。 翌朝、家康は秀頼のもとに伺候して会津出陣の報告をした。これは形式的な儀式である。この行事で家康は秀頼の名代として、豊臣家の反逆者である上杉景勝討伐の資格が得られ、豊臣家の家臣の諸大名を率いて往けるのだ。 秀頼は近臣に教えられたとおり、「苦労である」と、幼い声で述べ、小さな手で餞別を下賜した。 慶長五年六月十六日の早暁、家康は大阪城を出立した、彼は京橋口から三千名の将兵を率い城門をでた。家康は天満の川岸から船に乗り、淀川をさかのぼった。行き先は伏見城である、そこで彼は為すべきことがひとつあった。 御座船には葵の定紋を染め抜いた幔幕がはられ、船上には旗、指物が風にひるがえり、その御座船を人夫たちが両岸より綱で引き上げてゆく。 夕刻に伏見城に着いた。 「暑さと船酔いでまいった」 家康は誰とも会わず湯漬けを口にして寝所に入り、疲れのために熟睡した。 翌、早暁には老人特有の癖ではや目覚め、跳ね起きた。よほど眠ったのか、疲労の欠けらも感じない。家康は小姓も連れず、肥満した体躯を長廊下に現し、軽々とした足取りで歩んでいる。近習の者たちが慌てて追従している。 家康は千畳敷きと云われた大広間にでた。ここで太閤に謁見したものだ、思い起こすと忌々しい思いがする。 この金殿玉楼(きんでんぎょくろう)の豪壮な城を灰にしてやる、その思いが家康を支えていた。「三成っ、わしが会津にむかったら挙兵せよ」 独りごとが口をついてでた。「誰ぞ、彦右衛門を呼べ」 と、命じた。彼と会うことが目的であった。 待つあいだ家康は上段の間に座したみた、気持ちの良いことじゃ。独りでに笑みがこぼれてくる。「上様、彦右衛門にございます」 しわがれ声とともに下座に人影が現れた。「彦右衛門か?」 家康が上段の間から駆け下りた。「お目出度う存じます」 「いよいよ、天下取りのはじまりじゃ」 家康が声を低め、骨ばった肩に手をかけた。「勿体ない」 男は伏見城代の鳥居彦右衛門元忠(もとただ)であった。 家康より三才年上で、今川家の人質の時からの守役であった。「わしは会津攻めに参るが、そなたに一働きしてもらいたい」「有り難いことで」 「今生では再び会うことは叶わぬぞ」「承知にござる」 鳥居彦右衛門元忠は平然と答え、家康が言葉に窮した。「この城を灰にしても宜しいな、治部少輔に煮え湯を飲ませてやりましょう」「おう、そなたが伏見城の主人じゃ。好きなようにいたせ」「この城には兵が二千ほどおります、どうせ城を枕に討ち死にする身。五百名ほどの若武者を連れ帰って下され」「彦右衛門、その言葉はそなたしか言えぬ」 感極まった家康の肉厚い頬に涙が滴っていた。 家康と彦右衛門は主従を越えた関係であった。今川家の人質の頃は家康と彦右衛門は、真冬に肌と肌で暖をとった兄弟のような関係であった、苦労を分かちあった男同士の別離である。「上様、ひとつ所望がござる、弾薬が不足しております」「この城には金銀が腐るほどあろう、それを鋳つぶして弾薬となせ」「それでこそ天下人。天下をとれば黄金なんぞいくらでも手に入りますな」 鳥居彦右衛門が、嬉しそうなしわがれ声をあげた。「雲霞のごとき大軍が押し寄せよう、時を稼いでくれよ」「畏まりました。上様、きっと天下人になって下され」 家康は鳥居彦右衛門と、命を捨てた千五百名の将兵に見送られ、伏見城をあとにした。小説上杉景勝(75)へ
Mar 29, 2007
コメント(13)
-
小説 上杉景勝(73)
「白河の南に芦野という宿場がござる、我等はここに軽兵でもって家康の軍勢に当たります。戦いつつ偽りの敗走をいたし盆地に誘い込みます。お屋形は一万五千名で長沼に布陣いたす」 山城守が絵図の一点をさした。「拙者は三万の精兵をもって白坂に陣を敷き、充分に敵を盆地に引き入れて三方から叩きます。これなら勝ちを制すると考えております」「うむ」 島左近が再び絵図を睨んだ。「妙案ですな、拙者でも左様にいたしますな」 妙に明るい声であった。「左近殿の賛意が得られれば万全じゃ」 ここに天下の軍師二人の意見が一致した。「あとは家康の思惑しだい、いずれにせよ我等は東西から家康を挟撃いたし、殲滅するのみ」 直江山城守が興奮も示さずに断じた。「山城守殿、僭越(せんえつ)ながら忠告を申しあげる」 「何事かな」「旧領の越後を調略なされ」 左近の言葉に山城守が柔和な笑みをみせた。「これは、いらざる事を申し上げましたな」「いやいや、合戦とは念を入れねばなりません。既に越後の諸豪族には決起を促してござる」 山城守が懐中から書状を取りだし左近に示した。「拝見いたす」 書状には数十名の越後の豪族の名が書きつらねてあった。 彼等は上杉家が越後から会津に転封する際、やむを得ないことで越後に残留した者たちであった。 宇佐美定賢、万貫寺源蔵、柿崎景則、丸田清益、朝日采女、長尾景延、七寸五分(くずはた)監物、竹俣壱岐(いき)などそうそうたる名が書かれていた。 左近は改めて山城守の、深慮遠謀の才を知らされたのであった。「左近殿、治部少輔さまに、お伝え願いたき儀がござる」 「・・・・」「家康は野戦の名人、悪戯に決戦を急がれないよう、この山城が申しておったとお伝い願いたい」「心得申した」 答えつつ左近は面白くない、わしも天下に聞こえた軍師。その自負があった。すかさず山城守が左近の胸中を察した。「お怒りあるな、この合戦は長引くほど西軍に有利となります。家康の幕下にある大名共は、いずれも故太閤殿下恩顧の者共。大阪城におわす秀頼公のことをお忘れあるな」 直江山城守が白皙の顔をみせて述べた。「拙者ともあろう者が手抜かりにござった」 島左近が、カラリと言った、豊臣家の内情は左近よりも山城守が精通していた。左近の情報元は、主人の三成のみであった。事実、福島正則なぞは三成を嫌う理由のみで家康に肩入れしているが、彼や加藤清正なぞは強烈なほど殿下や秀頼を慕っている。この事を山城守は指摘したのだ。(長引けは、お味方衆が増える)左近は戦略的に山城守の言葉を捉えていた。「さて、いずれ中央の地でお会いいたすでしよう。我が上杉家はすでに臨戦態勢となっております」 「・・・」 左近が首を傾けた。「さる三月十三日は先代謙信公の二十三回忌にあたり、追善法要を盛大につかまつりました。この法要に領内諸城の将を若松に集め、義戦を起こすべきことを打ち明け、戦略を説明してござる。何時でも合戦の支度は出来ておると治部少輔さまに、お伝いいたして下され」 あとは酒宴となり、二人は心行くまで酒を楽しみ談論風発した。「山城守殿、今宵は久しく戦略を論じました。この左近の生涯にとり二度とない楽しい一時にござった。最後にお聞きいたす」「改まって何事ですか」 山城守が白皙の顔を褐色の左近の顔にむけた。「合戦とは理でもっても勝てぬ場合がござる、それは運気と云うものと思っております。もし万一、こたびの合戦で敗北いたしたらいかが為される」「他家は知らず、我が上杉家は主人景勝以下、家臣一同揃って討ち死につかまつる。それが上杉家の家法にござる」 山城守が毅然とした態度で言い放った。 「これが、山城守殿の義にござるか?」 島左近は、眼の覚める思いで直江山城守の顔をみつめた。「左様、武士たる者は爽やかに身を処すべきと勘考いたす」小説上杉景勝(74)へ
Mar 28, 2007
コメント(7)
-
小説 上杉景勝(72)
この真田昌幸とは信濃上田城主である。信濃は代々、周囲を大国に囲まれ数々の辛酸を舐めてきた地帯であった。 それ故に狡知に長け、昌幸は稀有の局地戦の戦術家として知られていた。 彼は三成の要請に夢をかけた。何よりもまして彼は無類の家康嫌いであった。半生、謀略に明け暮れてきた昌幸は、はじめて家康に騙された。 それは上州沼田城の帰属問題であった。 「家康、信用ならぬ」と骨のずいまで家康を憎み、誕生したばかりの秀吉のもとに奔った経緯があった。 今こそ思い知らせてやる、この老人は家康の天下とりの夢を阻止すべく知恵を絞っていた。東西両軍の激突地は関ヶ原とよみ、上田城で徳川軍団を釘付けにする戦術を練った。反面、長男の信幸の嫁は家康の武将の一人、本多平八郎の娘であり、真田家の名跡を残すために信幸を家康側につかしめ、彼と次男の幸村で徳川軍団と対決すると決意を固めた。 これは勝敗を度外視した武人の意気込みであった。 事実、昌幸のよみ通り、家康は徳川軍団を二手に分け、東海道は家康自身が軍勢を引きつれ、中山道へは秀忠と榊原康政に三万余の大軍を授け、関ヶ原に進ましめた。昌幸、幸村親子は上田城に拠り、この大軍を翻弄し、ついに昌幸は徳川直営軍の半数を、関ヶ原合戦に参陣させることんなく、信濃に釘付けとしたのだ。昌幸、幸村親子の勝利であった。「流石は島左近殿じゃ、上方の戦略は磐石とみました」「天下に聞こえた山城守殿のお墨付きじゃ、安心いたし申した、だが、この策は我が主人の描いたものにござる」 左近が寂びた声で告げた。「左様にござろう、治部少輔殿とは旧知の間柄。五奉行筆頭としての力量は衆を抜きん出ておりましたな」 山城守が往時を偲ぶ眼差しをした。昔、越水城で会った頃が懐かしく思いだされた。「さて、我が上杉家の現状をお知らせいたす」「お聞きいたす」 左近が簡潔に答え居ずまいをただした。「若松城の改築と会津十六城の改修はすべて完了いたした。会津の要塞化は出来ましたが、神指原城をいかがするか迷っております」「迷いがあると仰せか?」「すでに九割りがた完了いたしたが、主戦場となる白河城がもろい」 白河口攻めは家康が、担当すると決めた攻め口であるが、両人は知らない。「多分、家康率いる東軍の主戦場は白河口とよんでおります」 山城守が断じた。 「急造の城を頼りとするのは兵法の鬼門にこざる」「・・・お屋形に中止を進言いたす」 山城守が冷めた酒を左近の杯に注いだ。 「頂く」 左近が飲み下し。 「上杉家の戦略をお聞きいたす」 左近の褐色の戦場焼けした顔が厳しくなっている。「拙者の考えは、家康は我が領内には攻め込んで参らぬとよんでおります」「下野の小山(おやま)付近で陣をとどめましょうな」 直江山城守と島左近の意見が一致した。「だが万が一の事態を想定いたした、左近殿のご意見を拝聴いたしたい」 山城守が、傍らの領内の絵図をひろげた。「我等は家康を領内に引き込み痛撃を与えたい、その場所がこの白河口の南にござる」 山城守が絵図の一点をさした。「そこが白河口にござるか?」 「左様、ここに革籠原(かわごはら)と申す広大な盆地がござる。ここを予定戦場としたい」 左近が食い入るように絵図をみつめている。山城守は左近が口を開くまで待った。四半刻(三十分)ほど左近は思案していたが、顔をあげて訊ねた。「この地に、敵を引き込む戦術はいかがにござる」 小説上杉景勝(73)へ
Mar 27, 2007
コメント(10)
-
小説 上杉景勝(71)
景勝は挨拶の言葉をはっしたのみで、あとは、一言も口を利かずに大杯をあおっている。髭跡が濃く粛然(しゅくぜん)とした態度を保っている。 何を考えておられるか、左近をしても理解できない武将であった。「松籟(しょうらい)の音が心地よく聞こえますな」 取りつく間を持て余し、寂びた声をあげた。「この大広間は常にそうでござる」 直江山城守が答えた。「風流の極みにござるな」 答えつつ左近は内心、舌をまいていた。 景勝公は故謙信公の化身であらせられる、人伝で聞いた話が脳裡を過ぎった。日頃から無口で家来たちは、敵よりも景勝公を恐れているという。 大将とは、ただ床几に腰を据え、戦況に関係なく前方を見据えているのみ、これが景勝の武将としての生き様と聞いた。ゆえに景勝の本陣の将兵は前方を見据えて折り伏し、咳払いをたてることもなく静まり、無言の軍団として敵に恐れられているという。大将が本陣で泰然自若としておれば、全軍は動揺せず、兵士等は合戦に勝てると信ずるものである、これが景勝の考えと聞いた。 島左近は景勝を前にして、その思いを募らせていた。 景勝には謙信を崇拝し、己を高めようとする気概があった。 そうするように山城守が導いてきたことも承知している、景勝はすでに己の出生の秘密を知っていた。己の体内に流れる血潮には、謙信の血と謙信の姉である母親の血が、濃く交わっていることを。ならば及ばずとも不識院公のような、果敢な戦いをやろうと思っていた。事実、景勝は戦機を見逃さず一騎駆けで敵中深く駆け込み、勇猛果敢な武者働きを何度となくしてきた。 島左近は己の主人の石田三成と比較していた、主人に目前の景勝の資質のひとつでもあれば、孤立せずに家康と対等の力量を発揮できた筈である。が、三成にはそれが欠けていた。だが三成には壮大な構想力がある。 左近が杯をもって暫し思いに耽った。「左近、わしは下がる。あとは山城と天下のことを計れ」 景勝は一声かけ、前田慶次と上泉泰綱をともなって退出していった。「山城守殿、上方の戦略をお話申す」 左近が威儀をただした。「お聞きいたす」 山城守が白皙の顔を引き締めた。 島左近が三成からの言付けを淡々として語った。「大阪城に毛利輝元さまが、西軍の総帥として入城なされるか?」「左様、吉川(きっかわ)広家殿、安国寺恵瓊殿、毛利秀元殿もご一緒される。総兵力は三万五千名にござる」 「それは重畳」 左近はなおも語る。「長曾我部盛親殿が六千名、いささか危ういが小早川秀秋さまの一万六千名、さらに九州勢としては島津殿、立花宗茂殿の参陣がござる」「野戦軍の総帥は、宇喜多秀家さまか?」「一万七千名が主力でござる。そこに小西行長殿の六千名と我家の八千名、大谷刑部殿と与力大名の四千名が、西軍の総兵力となります」「よくぞ成し遂げられた、西軍の総兵力は九万五千から十万ほどの大兵力となりますな」 山城守の顔面が紅潮している。「左様、まずは家康が御家討伐の軍を発し、会津領に近づく頃を見計らい挙兵いたす」 「畿内は、いかが為される」「伏見城の攻略をいたす。さらに大阪におる家康側の大名家の者を大阪城に移し人質といたす」「それは火に油をそそぎませぬか」 山城守が端正な顔をしかめた。「これも戦略にござる」 左近がかまわずに話を進めた。「合戦の帰趨は美濃にござる。我が軍勢は大垣城を攻略いたす」 山城守が大きく合点の肯きをみせ、突然、話題をかえた。 「左近殿、信州に面白い人物がおられる」「上田城主の真田昌幸殿にござろう」 「承知にござるか?」「すでにお味方にござる」 左近が当然といった顔をしている。 この真田昌幸という武将は禄高、五、六万の小名であるが、奇妙人として天下に知られている。戦術家として局地戦では彼の右にでる者はいない。その昌幸は稀に見る家康嫌いであった。故秀吉に心酔することが滑稽なほどで、日夜、秀吉の画像に香を焚き礼拝を欠かすことがなかった。三成は昌幸に書状を送り、勝利の暁には甲斐、信濃の二ケ国を与えると書き送った。 昌幸にとっては生涯二度とない機会である、まして次男の幸村の室は三成の盟友である、大谷刑部の娘である。ふたつ返事で同意した。小説上杉景勝(72)へ
Mar 26, 2007
コメント(7)
-
小説 上杉景勝(70)
(軍師二人) 十名の深編み笠をかむった武士が、下野街道を足早に歩んでいた。いずれも手練者としれる男たちである。 中央の武士の腰をおとして歩む姿が印象的であった、かなりの遣い手とみえる。渋柿色の野袴を着用し羽織を風になびかせていた。「そろそろ会津に入るの」 「あと、二里くらいにございましょう」「遠路、苦労をかけたの」 戦場焼けした声に男の色気が感じられる。「拙者、先駆けをいたします」 若々しい声の武士が足早に道を急いでいった。「あの茶店で休息いたそう」 新緑の若葉を茂らせた樹木の側に茶店がある。 それぞれが腰をおろし街道を警戒している。羽織姿の武士が編み笠を脱ぎ茶を啜っている。戦場焼けした古武士風の風貌と知的な眸が印象的である。「天下の島左近さまが会津を訪れるとは、直江さまも驚かれるでしょうな」「なんの、驚かれる訳がないわ」 褐色の顔色をした武士が明るい声を発した。 この武士が、上杉家の直江山城守と天下を二分する、島左近の偉丈夫な姿であった。 「騎馬が参ります」 警護の男たちに緊張が奔りぬけた。「流石に手まわしが良い」 島左近が眼を細め街道をみつめた。 五頭の騎馬に空馬が一頭、猛烈な勢いで茶店に駆け寄ってきた。 先頭の武士が、名乗りをあげた。 「拙者、上泉泰綱にござる」「ご貴殿が新陰流の上泉殿か?」 「島左近さまにござるな」 精悍な顔立ちの上泉泰綱が、左近に声をかけた。 「左様」「殿と山城守さまがお待ち申しておられます、これ、馬をお渡し申せ」「はっ、遠路ご苦労に存じます、この騎馬をお使い下され」 武骨な顔をした武士が、空馬の手綱を左近に渡した。「かたじけない」 左近が物慣れた様子で鞍上(あんじょう)に飛び乗った。「わしは一足さきに往く、あとからゆるりと参れ」 左近が馬腹を蹴った、六頭の騎馬が砂埃をあげて疾走してゆく。「おうー、見事なお城じゃ」 「会津若松城にござる」 上泉泰綱が騎馬のまま城内に案内してくれた。大阪城や伏見城にはひけをとるが、流石に会津百二十万石に相応しい豪壮な城塞である。 武骨一点ばりの城内を、左近が物珍しげに眺め廻している。「宿舎にご案内いたす、そこで汗を流し着替えて下され」(行き届いた手配りじゃ)左近は宿舎で汗を流し、うら若い腰元たちの手によって用意された裃(かみしも)に着替えた。「さっぱりいたした」 宿舎の座敷には酒の用意がしたあった、左近が無類の酒好きと知った山城守の配慮であろう。「ご免ー」 声と同時に直江山城守の白皙の長身が現れた。「これは、これは山城守殿、お久しぶりにござる」「左近殿も、お変わりなく結構。まずは一献まいられよ」「頂戴いたす」 注がれた酒を飲み下し、左近が嬉しそうに破顔した。「江戸の狸が、蠢きだしましたな」 山城守が端正な顔つきで訊ねた。「左様、いよいよ面白くなって参った」 左近が戦場焼けした声で応じた。「お話は今宵、殿とお伺いいたす。ご家来衆もおいおいと着かれましょう、長旅の疲れを癒して下され。・・・ところで治部少輔殿はお元気にごぞるか」「張り切っておられます」 「左様か、では後刻」 会津盆地に夜の帳(とばり)がおとずれた、左近は泰綱の案内で景勝の待つ、大広間にむかった。部屋のなかは灯火で煌々と真昼のようである。 正面に青味をおびた顔つきの景勝が無言で座している。傍らには山城守が控え、それぞれの前に酒肴の膳がならんでいる、それは山海珍味の豪華なものであった。 「左近殿、殿の前にお座り下され」 山城守の言葉に従い左近が静かに腰を据えた。傍らに上泉泰綱と前田慶次の二人も加わっていた。「お屋形、石田治部少輔殿のご家老の島左近殿にござる」 山城守が如才なく紹介した。 「お初にお目にかかります。拙者が石田家の島左近にございます」「わしか中納言景勝じゃ。遠路ご苦労であった」 と、短く答えた。 山城守が前田慶次利大を紹介した。 「前田利家さまは叔父にござったな」「左様、いささか風狂に過ぎましてお屋形さまに拾って頂いた」 雑談に花がさき、一同は膳部に箸をつけ酒を楽しんでいる。小説上杉景勝(71)へ
Mar 24, 2007
コメント(9)
-
小説 上杉景勝(69)
「何と仰せです」 両奉行が顔色を変えた。「何ゆえの討伐にござる、拙者には得心が参らぬ」 増田長盛が息巻いた、彼は大和郡郡山城主で三十万石を領している五奉行の一人である。 「拙者も反対にござる」 長束正家も猛然と反駁した。彼は水口五万石の小名ながら五奉行である。 二人は日頃の家康の、独走に嫌気がさしていた。「ほうー、ご両所は会津征伐に異を唱えなれるか?」 家康が肉厚い瞼を細め両人を眺めやった。「内府には私曲が多うござる」 珍しく長盛が家康を非難した。「わしに私曲が多いと云われるか?」 家康がぎらりと眼を剥いた。「豊臣家安泰のため、故太閤殿下は勝手な縁組はならぬと遺命を残された。それを内府は無視され、我等五奉行の印もなく縁組を為されておられる」「・・・・・」 家康は口を閉ざしている、無言こそ最大の威圧である。「前田家の芳春院さまの件もござる、豊臣家の人質である筈に、勝手に江戸にお連れする。我等奉行をいかが見ておられます」「・・・・わしは家臣の本多正信に、いかなる事もご相談いたすように申してござる。手違いにござるゆえ、わしからご両所にお詫びを申す」 天下の実力者に詫びられ、両人は言うべき言葉を失った。「こたびの会津攻めじゃが、明日にも本丸に参上いたし、秀頼公に会津征伐を奏上いたす積もりにござる」 そう云うことか、またもや前田家同様に秀頼公の名代とし、豊臣家の逆臣として、上杉景勝殿を討ち果たすか、考えたものだ。 家康の傍若無人な態度に、増田長盛は怒りで蒼白となった。「上杉討伐の名目はなんでござる」 長束正家が訊ねた。「わしへの愚弄じゃ」 家康が平然と答えた。 「何とー」「仮にも豊臣家の筆頭大老にござる、そのわしの上洛命令を無視いたした。これは反逆そのものじゃ」「それは私怨にござる、確たる謀反の証拠でもござるのか?」「黙らっしゃい。関東二百五十万石の大名で豊臣政権の執行官の、わしの命令に叛いたならば、これは豊臣家に対しての謀反じゃ。明日の件は淀殿と秀頼公に、よしなに伝えてもらいたい」 一方的に二人に命じ、肥満した躯を持て余すように退出していった。「悔しいが、豊臣家の天下も終ったの」 長束正家が無念の涙をみせていた。「治部少輔はいかがしておる」 「佐和山城の改築をいたしおる」「正家、わしは佐和山城に使いをだそう、奴の頭脳がこの急場の手立てを考えだしてくれよう」 増田長盛が決断した。「あの、横柄者(へいくわいもの)が懐かしいわい」 その晩、西ノ丸は遅くまで灯火が消えなかった。家康は家臣の主だった者と極秘の軍議をもようしていた。 会津には七口の攻め口がある。南山口、白河口、信夫(しのぶ)口、米沢口、仙道口、津川口、越後口の七道である。「軍勢の分散は避けねばならぬ。主力は白河口じゃ、わしと秀忠が当たる。仙道口は佐竹義宣、信夫口は伊達政宗、米沢口は最上義光じゃ、越後口は前田利利長と堀秀治に命ずる」 「仙道口が、いささか危ういかと」「正信、佐竹義宣の件は考えてある。諸大名には江戸に参集を命じよ、出来るかぎり早くじゃ」 「上様のご出立は何時頃にございます?」「御本丸さまに暇乞いをいたし、準備の出来しだい大阪を離れる。正信、先鋒大将は豊臣恩顧の福島正則、細川忠興、黒田長政に命じよ」「畏まりました」 本多正信が痩身をみせ肯いた。 五月三日、秀頼に暇乞いをした家康は、諸大名に会津出兵を命じた。 いよいよ、徳川さまが会津討伐に向かわれる。大阪城下はその噂がたちこめた。家康は陰湿な笑みを浮かべている。 わしが大阪をあとにして会津討伐に向かえば、光成め、必ず挙兵するだろう。わしは、それを首を長くして待っておる、これで天下が、わしの掌に転がってくるのじゃ。併し、謀臣の本多正信は楽観できずにいた。 上杉勢は先の前田家とは違う、景勝という男は無類の戦狂い。その配下の将兵は、景勝の秋霜烈日の気象を、敵勢よりも恐れていると云う。 聞くところによると富士川の渡船の折、供の者が乗りすぎ川の半ばで船が傾いた。景勝が無言で杖を振るうと、泳ぎの出来ない者まで流れに飛び込んだと云う。 さらに天下を二分する軍師の直江山城守と、謙信に育てられた歴戦の武将が控えている。 「心せねばな」 正信が一人呟いた。小説上杉景勝(70)へ
Mar 23, 2007
コメント(11)
-
小説 上杉景勝(68)
さかのぼって津川城の藤田能登守信吉を年賀に上洛せしめた、時に家康に懐柔され、上杉家より出奔した事件があった。 藤田信吉は武蔵の出身で謙信時代に、越後にきて謙信に仕えた。戦国乱世の世を泳ぎぬいた男の嗅覚に、上杉家の衰亡を嗅ぎ取り見限ったのだ。彼は景勝謀反を徳川の謀臣の本多正信に訴えでた、家康にとり待っていた事態であった。家康の態度がこの件より一変したのだ。 家康は伊奈昭綱(あきつな)と五奉行の増田長盛の家臣の河村長門の両名を、四月一日に門罪使として会津に下向させた。 両名は景勝への非違(ひい)八ケ条の弾劾状をもっの下向であった。 これは直江山城守と親しい、京の相国寺の西笑承兌(さいしょうしょうたい)に家康が命じて作らせた書状で、弾劾状の宛名は直江山城守兼続であった。 これは山城守から景勝に諫言させ、景勝が家康に詫び状を書くよう、仕向けさせる意図が含まれていたのだ。「お屋形、狸よりの使者がこのような弾劾状をもって会津に現われましたぞ」 兼続が書状を差し出した。 景勝は一読し例の顔で兼続に視線を移した。「これは、そち宛ての書付じゃ。狸爺の使いそうな手じゃな、よきに計らい」「はっ、分りましてございます」 兼続は屋敷にもどり書院に座し、料紙を前にして暫く思案した。 (笑止なり) この思いがした。彼は、この弾劾状に対し一片の妥協も示さぬ 反駁文を書くために筆をおろした。「尊書、昨十三日に下着す。つぶさに拝見、多幸、多幸」『当国については、さまざまな雑説が京、伏見に流布され内府もご不審の由、仕方のないことです。会津は遠国で景勝は若輩であり、このふたつが雑説を生むことになりますが、いたって苦しからず。尊意を安んぜられ、このような流説に心を労されるな』『景勝に上洛を命じなされるが、二年前に国替し程なく上洛いたし、昨年の九月に下国いたした。又も上洛せよとは何時、国の仕置きをいたすべきか得心がまいらぬ』『景勝に別心なき旨、誓紙を差し出せと申されるが、誓紙なんぞは何枚書いても意味はない。景勝が律儀の人物であることは太閤殿下が、もっとも良くご存知でおられた。その心は今も変わってはおりません。この世間の朝変暮化とは縁のない者と思って頂きたい』『武具を集めていると非難されておられるが、上方武士は今焼茶碗、炭取瓢といった人たらしの道具を所持なされるが、田舎武士は槍、鉄砲、弓矢の道具を支度仕る』『景勝に逆心あって籠城するならば、国境の出入口を塞ぎ、道路をこぼつのが普通である。それを十方に道を作っている。もし天下の軍に包囲されれば、十方に兵を出し防戦せねばならず、人数も足りぬ。やがては攻め落とされてしまう。道路開発き敵意のない証拠とみられよ』 全文十六ケ条からなる、直江状から抜粋したが、景勝主従には自分たちが、非難される謂れがない自負があった。 領内の統治を優先させることが、豊臣家への忠節と考えていた。その意味で直江状の最後に、『家康、秀忠が当地に下向されると云われるが、そんな事で驚くものではない、万事はそれを見たうえで当方の態度を明らかにしょう』 と結んでいる。これは、正に家康への挑戦状であった。 それに五大老の一人として同僚の家康に、とやかく言われる筋合いはないという思いもあったのだ。 家康は大阪城の西ノ丸で直江状に目をとおし読み終わった。「わしは、この年までこのような無礼な書状をみたことがない」 と、呟き呆然としたといわれる。この直江状は慶長五年十四日に書かれている。 家康の反応も素早い、豊臣家の奉行の増田長盛、長束正家の二人を呼び出し、会津討伐を公式に伝えた。 小説上杉景勝(69)へ
Mar 22, 2007
コメント(12)
-
小説 上杉景勝(67)
「わしは徳川の狸爺が憎い、ありもせぬ流言を撒き散らし豊臣家の御為と称し、己の地盤を固めておる」 景勝の額に青筋がういている。「お屋形、奴の狙いは利長殿の母上の芳春院(ほうしゅんいん)さまではござらぬか」 兼続が思慮しつつ訊ねた。「なにっー」 景勝の顔色が変わった。 芳春院さまとは加賀前田家の亡き利家の妻、お松のことである。 利家の死により髪をおろし、芳春院と称していた。彼女は夫の利家を助け、賢夫人として故太閤殿下も彼女の存在に一目おいていた。 家臣たちも新藩主の利長より、彼女に心を寄せていたのだ。「狸め、前田家を征伐すると威嚇し、芳春院さまを人質とする積もりか」「左様に心得ます、そうなれば前田家は徳川に反抗できませぬ」「汚し」 景勝が怒声をあげた。「来るべき合戦には前田家は、豊臣方として当てには出来ませぬな」「山城、上方から目を離すな」 「心得てごさる」 家康は兼続のよみどおり、前田家に謀反の疑いありと在阪の諸将を招集し、加賀攻めの陣ぶれを発し、陣立てを評議した。それは十月三日のことである。 この命令も大阪城の秀頼の名でもって行われたのだ。 これを知った温厚な利長も激怒し、ただちに家康への迎撃体勢を固めた。 併し、老臣らは大いに利長の器量を危惧し、しきりに利長を諌めた。 ここに利長も、家康への陳謝と誤解を解くための使者を遣わすことに決め、胆力と交渉事に秀でた横山長知(ながとも)を急遽、大阪に派遣した。 家康は横山長知の陳謝には耳を貸さず、芳春院を差し出すよう要求した。 前田家の当主の利長は、豊臣家に対する二心はないと抗弁したが聞き入れられず、芳春院がみずから人質となり事は決着をみた。 芳春院は息子の利長の器量では、前田家の存続はないとみたのだ。彼女は身を犠牲として家を守る決意をした。 こうして豊臣最大の忠臣であった前田家は、徳川の軍門に屈したのだ。 後日談だが、家康は芳春院が大阪に到着すると、彼女は徳川家の人質であると勝手な理屈をこね、大阪から江戸に送ってしまった。 これより十五年間、江戸に留め置き、利長が病重くなり死に目に会いたいと願い出たが、許さず、死後ようやく帰国を許すのであった。 この知らせを受けた景勝は、徳川家との徹底抗戦を覚悟し、領内統治を強め、国境の城塞に兵力を集中した。 さらに彼は自ら国境付近の、戦場予定地の視察を精力的に行い、下野に至る軍事道路の整備を急いだ。 慶長五年の年明けと同時に家康の態度が豹変した、突然に問責書が家康より景勝に送りつけられて来たのだ。「陰謀の疑いがあり、釈明のために上洛せよ」と、命じてきたのだ。それまでは景勝と家康との関係は、比較的平穏に過ぎていたのだ。 百二十万石の大藩の上杉家に緊張が奔りぬけた。ただちに山城守の伝令が各城塞に駆けつけ守りを固め臨戦体勢となった。 前田家を屈服させた家康の次ぎの標的が、上杉百二十万石であった。 彼は巧妙な手を使っていた、何としても謀反の疑いをかける。その役割をになった者が、越後の堀秀治であった。堀家は越後に入封当時の年貢の一件で遺恨を残していた、さらに越後支配が思うにまかせない情況にあった。 越後各地に一揆が頻発していたのだ。 この原因は、旧領主の上杉家が後方から支援していると考えた、堀秀治は景勝の会津での行動を入念に探り、徳川家の榊原康政(やすまさ)に一部始終報告していた。だが、会津転封時に故太閤殿下から許されていた、領国統治としての城の築城や改修、道路の修理や新築、建設などは問題視されなかった。 併し武具の調達や、浪人の新規召抱えが謀反の疑いとされたのだ。小説上杉景勝(68)へ
Mar 21, 2007
コメント(7)
-
小説 上杉景勝(66)
景勝と山城守兼続は、久方ぶりに酒を酌み交わし、大阪の情勢を語りあっていた。 「いよいよ徳川の狸爺、本性を現してきましたな」 兼続が常の白皙の相貌を厳しくさせて景勝に話かけた。「大阪城の西ノ丸の件か」 景勝が大杯をあおり問うた。「左様、北政所さまを京に追いやり、狸め念願の西ノ丸に入りましたぞ」 景勝の会津帰国は、慶長四年八月十日であったが、それを待っていたかのように、十月一日に大阪城の西ノ丸に乗り込み、居座ったのだ。さらに本丸同様の天守閣を急造した。「奴の独走を止める者が居らぬのじゃ、石田治部少輔殿が下野した結果が、明白に影響しておる」 「さほどに残りの奉行らは腑抜けにござるか?」「彼等は、武人にあらず官僚にすぎぬ」 景勝は一言で断じきった。 家康は周到であった。三成が佐和山に去り、政局が小康状態に入るや。三奉行の浅野長政、増田長盛、長束正家を呼び出し告げた。己が秀頼公に代わって政務をみるに、大阪、伏見の諸大名は朝鮮の役で国許の統治がおろそかとなっておる。太閤殿下が存命ならば、それぞれに恩賞があるべきじゃが、秀頼公は幼少。何も計らい難い、よって翌年の秋まで国許に帰還いたし、在国を許す。これは、わしの一存じゃが宜しく手配を頼む。 こうして諸大名たちを伏見、大阪から追い払ったのだ。「ならば、大阪は真空状態ですな」 「そうじや」「お屋形は、いかがなされます」「いざとなったら、治部少輔殿が動こう。佐和山城には一万余の軍勢が居ろう。狸爺の軍勢は、たかだか半数にも満たぬ」「合戦に及んだ時は、いかがなされます」「知れたこと、わしは領内を空にして大阪城に馳せつける。これが大老たる、わしの勤めじゃ」 景勝が顔色も変えずに平然と嘯いた。「それをお聞きいたし、安堵いたしました」 兼続が白皙の顔をほころばした。「山城、そちも狸じゃのう、そのような事は起こらぬ。わしは会津に居座り上洛を見送る積もりじゃ、・・・ところで治部少輔殿とは連絡がついておるのか」「ございます、天下分け目の合戦の戦略は、着々と整っておる様子にござる。誤算は、土佐の長曾我部元親(もとちか)殿の死去にござる、跡目は四男の盛親殿が継がれましたが、なんせ若輩の身にござる」「大戦(おおいくさ)ともなると心細いか?」 「御意に」「そうよな、元親殿が存命ならば長曾我部勢は頼りになったであろうな」「なんせ四国を平定された武将ですからな、盛親殿は未知数にござる」「やむをえないことじゃ」 景勝が瞑目し額に親指をあて顔を俯(うつむ)けた。「いかが為されました」 「山城、金沢が危ういな」「なんとー」 兼続が驚きの声を発した。「山城、家康の大阪城づめの魂胆がよめるか?」 景勝が冷酒を飲み下した。 山城守兼続が透明な笑みをうかべた。「分らずに上杉家の執政の職は勤まりませぬ。故太閤殿下のご意思は、家康を大阪城に入れぬことにございました。それ故に前田利家殿を大阪城に配され、家康には伏見づめを命ぜられました。それは幼君の名を騙り、天下の諸侯らに勝手な命令を出させぬ用心のためにござった」「その通りじゃ、だが前田利家殿が亡くなられ、好機到来とばかりに大阪城に入りよった。がんらい利家殿は秀頼公の傅役じゃ、利長殿はなにが起ころうと大阪城を出てはならぬのじゃ。父の跡をついだのじゃからな、国許には弟の利政殿が居られる」「利長殿は家康の甘言に弄され、八月に金沢に帰国なされた。既に雪が降り積もり越年は必定、それを理由に前田家に謀反ありと、金沢攻めを宣言いたしますか」 「そうじゃ、秀頼公のお名のもとにな」 景勝の眼が燃えていた。「前田家は秀頼公の名代の内府との、合戦を回避いたしますな」「仕方があるまいて、いたさねば秀頼公への謀反と言われよう。既に先鋒は小松城の、丹羽長重が取り沙汰されておる」 「お屋形、何ゆえにご存じです」「わしにも間者の一人や二人はおる」 「なんと」兼続が驚き顔をみせていた。小説上杉景勝(67)へ
Mar 20, 2007
コメント(11)
-
小説 上杉景勝(65)
「待たれえ、わしは徳川家の統領じゃ。助けを求めて参った者を殺されると承知でお渡しできぬ、秀頼公の補佐役のわしが豊臣家の重臣を、承知で引渡したとしたら、豊臣家にたいし反逆」 家康が分厚い瞼から一同をねめ廻した。 福島正則が蒼白となっている。「春に喪を発せられ、まだ二ヶ月あまりじゃ。豊臣家の家臣が争いごとを起こすなぞ、もっての沙汰。この様子をみて反逆者が現れたらいかが思しめす」 家康は内大臣としての地位と、豊臣家の五大老筆頭としての執政官の務めを、迫真の演技で演じてみせた。「事を分けて話しても治部少輔殿を、手にかけると申されるなら、わしが相手をいたす。・・・・返答はいかに」 七将は凄まじい家康の威圧感と一喝で、悄然と徳川屋敷を辞していった。 これは、考えに考えたすえの家康の行動であった。陰で本多正信が含み笑いを堪えていた、上様の、あの灰汁の強さよと感心していた。 この一件から世間は、家康が豊臣家の第一人者と改めて思い知る筈である。 翌朝、家康は三成に会って一時的な隠退を勧めた。「それがしに五奉行の職を退けと申されるか」「左様、全ての争いごとが貴殿の存在より起こっておる、これは秀頼公のおん為によろしからず」 言葉柔らかに諭した。 家康が隠退を勧めることは、三成も当然に承知していた。現に佐和山城に引き上げようかと、自らも考えていたところであった。 わしが去ったら狸爺め、如何なる本性をみせる。それが楽しみに思われた。 三成は家康の勧めをのみ、三月十日に居城の佐和山城に退くことにした。 家康は七将の挙動に不審を強め、次男の結城秀康の軍勢に守らせ、瀬田まで三成を送らせた。この時、常陸五十四万五千石の佐竹義宣(よしのぶ)は、三成の警護とし、隠密に二千名の家臣を護衛につけていたと云われる。 彼は太閤検地のさいに三成の世話になり、肝胆相照らす仲となっていたのだ。こうして石田三成は豊臣政権の奉行の地位を失い、ご政道にたいしての発言権をなくした。 前田利家の死と三成の隠退により、政局はますます家康優位に展開した。 大老は筆頭の徳川家康を除き、毛利輝元、宇喜多秀家、上杉景勝となり、そこに利家の死去により、嫡男の前田利長が勤めることになった。 家康は十三日に本格的に伏見城に移り、ここで政務をみるようになった。 三成を欠いた五奉行や中老らは、誰も異を唱える者がいなかったのだ。この意味は大きい、大阪城についで天下第二の城塞を家康が手にしたのだ。 (直江状) 八月を迎え景勝は、家康をはじめとする大老に帰国を申しでた。会津移封となってから、藩主として領内統治のお務めがおろそかとなっていた。これが帰国の理由であった。「中納言殿には気の毒にござった、転封と同時に太閤殿下がお亡くなりになられ伏見で政務をとっておられたが、一応の治まりはつきました。帰国なされ領民の安堵をなされえ」 大老筆頭の内府が承認したので、残りの大老も景勝の帰国を許した。 景勝一行は、八月中旬に会津に到着した。同時期に五大老の独り前田利長も大阪を発し、利家の遺骸をともない金沢に帰国した。 景勝は大老筆頭の内府に、会津到着の日時を書状で知らせている。これに対し家康からは、九月十四の日付で『御心、安かるべく候』と返書が届いた。 だが家康に好機が訪れた訳である、二人の大老の帰国と三成の隠退で、本格的に牙を剥きだすことになる。 彼は篤実な豊臣政権の執政官として、秀頼の補佐を務めていた。これは次ぎの、一手を打つための布石であった。 景勝は道路建設と城の改修を急ぎ、神指原城の築城進捗に意を注いでいた。さらに武器弾薬、兵糧の備蓄を進め、浪人の新規召抱えを行った。 これは故太閤殿下の了解の上での施策の実行で、誰にもはばかることではなかった。百二十万石の大藩の体面を整える、領内統治の一環であった。 季節は十月を迎え、会津の地に初雪が降った。小説上杉景勝(66)へ
Mar 19, 2007
コメント(10)
-
小説 上杉景勝(64)
この神指原城とは、景勝が会津に入封した時、兼続と将来を見越して築城を急いでいる巨城であった。若松城の西北に位置する神指原に築いていた。 兼続が縄張りをした城で本城は東西約百八十メートル、本丸は南北約三百メートルの規模で、それを五百メートルの二ノ丸が取り囲む回廊式の近代城塞であった。人夫だけでも十二万名を徴発しての大工事が、今も懸命に行われていた。 閏三月四日、伏見の石田屋敷は慌しい雰囲気におおわれていた。 加藤清正を頭とした武断派の荒大名どもが、石田屋敷を襲撃すると軍勢を整いていたのだ。それが洩れた。疎漏(そろう)もはなはだしい出来事である。 石田家の誇る三家老の島左近、蒲生郷舎、舞兵庫らが手をこまねいている。「面白い、奴等と一戦いたすか」 この三名は、合戦の名手として天下に聞こえた名士であった。「清正や正則なんぞ錆槍の餌食にしてやるわ」 蒲生郷舎と舞兵庫が嬉しそうに破顔している、彼等も合戦に飢えていた。「左近、伏見城下で豊臣家の家臣が争っては、天下に聞こえが悪い。わしは逃げる」 三成が平然と島左近に語りかけた。「どこに行かれます」 島左近の問いに三成が、童顔をほころばしている。「窮鳥ふところに入れば、漁師も殺さぬと申す。わしは内府の屋敷に隠れる」「なんとー」 三家老が唖然として言葉を失っている。「供はいらぬ、わし一人で参る」 流石の島左近も主人の蛮勇に仰天した。 七将をけしかけているのは、ほかならぬ家康である。「七将どもが参ったら、わしは逃げたと申せ。だが屋敷内に踏み込む気配なれば存分に相手をいたせ」 島左近は三成の胸中を素早く看破した。「畏まりました」 「わしは、これから家康に会いに参る」 三成の小柄な躯が、すっと闇に溶け込んで行った。「驚いた、お方じゃ」 三家老が毒気にあてられ改めて主人を見直した。 三成が向島の徳川屋敷を訪れていた、家康の謀臣の本多正信が玄関に出迎えている。 「治部少輔の三成じゃ、佐州であるな」 と、三成は官名で正信をよんた。 「本多正信にございます」「わしは困っておる。荒大名の七将に追われ、ご当家を頼って参った」「加藤主計頭(かずえのかみ)殿にございますか?」 「そうじゃ」「お匿い申しあげましょう」 正信が陰鬱な声で応じた。「存外と奴等をあおっておるのは、佐州、そちではないのか」 三成の言葉に毒がある。「滅相な、お寛ぎいただく部屋にご案内いたします」 枯れ木のような痩身の正信が三成を先導した。 このままこの小男の命を絶つか。正信の胸に強い欲望が奔りぬけた。 三成は慣れた様子で足を運び、 「わしを殺すか」 声に艶がある。「お揶揄いなされますな、かりにも内大臣のお屋敷内ですぞ」「腹が減った、湯漬が所望じゃ」 「畏まりました」 部屋に通され、三成は庭に面した障子戸をからりとあけた。何度となくみた光景である、秀吉存命のおりは別荘として使っていた屋敷である。 三成は行儀よく饗された湯漬をかきこんでいる。さて家康、どうでる。今の境遇を楽しんでいるように呟いた。 その頃、奥の部屋で家康は思案にふけっていた。傍らに本多正信がひっそりと座し黙している。 「三成は、おとなしくしておるか?」 「いかがなされます」「あの荒武者どもの説得が面倒じゃな」 「このまま生かしておきますのか」「殺せば、わしの苦労が水の泡じゃ。奴が楯突けば楯突くほど、わしのもとに天下が転がり込んでくる」 家康が低く笑い声をあげた。「申し上げます。七将の方々が石田殿を渡せと息巻いてお見えにございます」「先のよめぬ者共じゃ、書院にでも通しておけえ」 家康が不機嫌な声を発した。 「拙者が応対いたしましょうか」「正信、そちでは荷が重い」 家康が肥満した躯をもとあげ書院にむかった。 家康の姿をみるや清正が吠えた。「内府殿、治部少輔を匿われておるとお聞きいたした」 「それがいかがなされた」 肥満した家康の顔が厳しく変貌している。「我等にお引き渡し願いたい」 「それはならぬ」「あれほど内府殿に逆らった男にござるぞ、我等が奴のそっ首を刎ねてやります」 清正が身を乗り出し叫んだ。小説上杉景勝(65)へ
Mar 17, 2007
コメント(9)
-
小説 上杉景勝(63)
「佐吉、お主の心意気はかう、じゃが内府に匹敵する大軍が集められるか。 合戦とは拮抗(きつこう)する戦力がなくては勝てぬ、その戦略があると申すか」 大谷刑部が盲目の視線を三成にむけ訊ねた。「ある」 童顔を朱色に染めた三成が決然として云いきった。「まことに、あると申すか?」「それがしも五奉行の筆頭、すでに大老の毛利輝元殿と宇喜多秀家殿の内諾は頂いておる」 「承諾なされたか?」 三成が頬をくずした。「四国の長曾我部殿も、参陣を決意なされた。さらに西国大名の大半も調略いたし、信濃の真田昌幸殿も我等の味方じゃ。・・・・そこでじゃ」 三成が言葉を切り、直江山城守をみつめた。「申されるな、我が上杉の決起が必要にござるな」「左様、会津百二十万石の景勝さまがお味方に、加わって頂けるなら必ず勝てます」 三成が兼続の眸を覗きこむようにして言葉を添えた。 直江山城守と大谷刑部が言葉を失っている、まさか、三成がここまで調略を進めておるとは思い及ばぬことであった。「合戦の予定地は何処とお考えか、それにより上杉の方針も変わります」「美濃の関ヶ原を予定いたしてござる」 三成が打てば響くように断言した。「あの地なら良い。早速、我が主人に言上いたしましょう」 兼続と大谷刑部は、三成の戦略眼の正しさと壮大な計画に瞠目した。 徳川勢の直営軍団は二つに分かれる筈、一軍団は家康みずから率い、江戸からの軍団は、秀忠を総大将として信濃をぬけ関ヶ原にむかう、そうなれば信濃の真田昌幸の出番が来る。「佐吉、当面の荒武者対策はいかがいたす」「紀之助、五奉行を辞め佐和山城に逼塞(ひっそく)いたす」 石田三成が、思いきったことを口にした。「佐吉、出来るか」 「逃げおうせなんだら豊臣家は滅亡いたす」「うむ、・・・・分った、わしの命を預けよう」 「紀之助っ」 病み衰えた大谷刑部の答えに、三成の双眸から涙が光った。「石田殿、伏見は何時に出立なされる」 兼続が低い声で問うた。「今のところは分りませぬ、荒武者どもの出方次第」「そこもとは加藤、福島らと事を構える積もりにござるか?」「おめおめと伏見を去っては、石田三成の武がすたり申す」 三成の言葉に大谷刑部が反応した。「奴等の襲撃を待って合戦に及ぶつもりか?」「殿下の喪中に騒ぎは起こしたくない、併し、仕かけられた喧嘩は買わずばな」 珍しく三成が好戦的な言葉を吐いた。 「佐吉、それは無謀にすぎる」「心配いたすな、佐竹義宣殿の屋敷に隠れ、宇喜多家に匿われるつもりじゃ」「隠れおおせられるか」 「駄目なら、敵の情けにすがるまでじゃ」「なにっー」 「おおさ、徳川内府の懐にもぐりこむ魂胆じゃ」 三成が平然と驚嘆すべき事柄を口にした。二人が声を飲み込んだ。 矢張り傑物(けつぶつ)じゃ、山城守は目の覚める思いで童顔の三成を眺めた。 「佐吉、そこまで覚悟を固めたか。ならば何も云うまい」 大谷刑部が、しわがれた声で応じた。「石田殿、徳川家には曲者がおることをお忘れあるな」「謀臣の本多正信(まさのぶ)にござろう。山城守殿の忠告、心しておきます」 三人は、あらためて酒肴を重ね、家康討伐の秘策を語りあい、夕暮れを迎え、それぞれが屋敷をあとにした。 兼続は上杉邸にもどり、景勝に今日の会談の様子を報告した。 景勝は例のとおり青味をおびた顔つきで、無言で聞いている。「石田三成殿、稀有(けう)の武将じゃの」 景勝がぼそっと呟いた。「徳川内府を関ヶ原に、誘(おび)きよせるには餌が必要となります」 兼続が景勝の反応を窺がった。「わしは政務が済みしだい会津に戻る。天下をむこうに廻した大戦の支度を整えねばな、そちは暫く伏見にとどまり、ことの一件を見届け帰国いたせ」「お任せくだされ、徳川の狸爺の命を頂戴する謀なぞ考えてみましょう」「山城、上杉家の頭脳は、とうにそちに任せてある」「お屋形、神指原城(こうざしはらじょう)の築城を急がねばなりませんな」「あの城が完成いたせば、ずいぶんと面白い合戦が出来るな」 景勝は家康を誘きよせる餌になろうと決意したようだ。小説上杉景勝(64)へ
Mar 16, 2007
コメント(8)
-
小説 上杉景勝(62)
朝鮮の役では太閤殿下の寵をえ、ことごとに我等に難癖をつけたと三成を腹の底から憎んだ。それは一種の嫉妬であったが、彼等は気づかずにいる。 太閤や北政所(きたのまんどころ)を親のように慕っていた彼等は、父親を三成に奪われたと感じ、憎悪の炎を燃やしていた。 天下に恐れられた荒武者が、子供のように拗(す)ねているのだ。 北政所も豊臣家から心が離れていた、余りにも淀君と秀頼に心を配る三成一派を心良くは思っていなかった。その反動が武断派の武将たちにむけらた。 彼女は昔のように彼等に慈愛を注いだ。その心理を家康が巧に衝き、彼等を己の側に取り込んだのだ。家康の謀略の才がまさった結果であった。 直江山城守兼続は上杉屋敷にとどまり、引き連れてきた隠密集団に、徳川家の内情を探らせていた。そんな時期に三成から招待の知らせをうけた。 兼続は白皙長身の体躯で定められた屋敷に向かっていた。 伏見郊外の小奇麗な屋敷であった、風流な門を潜りぬけ案内(あない)を講うた。 小袖姿の可憐な乙女が顔をみせ、「山城守さま」 と小首をかたむけた。「左様」 「ご案内申し上げます」 庭の樹木の間から日差しが差し込んでいる。 部屋には二人の人物が待ち受けていた、一人は石田三成で、いま一人は顔面を白布で覆った人物であった。「これは大谷刑部(ぎょうぶ)殿か、お久しうござる」 彼は越前敦賀五万石の城主で、三十歳ころから癩病を病み、顔面が崩れ両眼を失っていた。故太閤は刑部の武将としての才能を高く評価していた。そうした人物である。 「山城守殿も息災でなにより」 刑部が低いしわがれ声を発した。 三成は年齢とともに才気走った顔つきとなっていた、人々にとり、それが豊臣政権の中枢の筆頭としての貫禄、威厳と受ける者もいるが、逆に小面憎いと反感をもつ者もいた。 「さあ、座ってくだされ」 三成が座をしめした。 兼続がふわりと座し、「いかがなされた」 と三成に訊ねた。 童顔の三成が嬉しそうな笑みを浮かべている。「荒武者どもが、お命を狙ってござるぞ」「流石は、直江山城守殿じゃ、もうお耳に達してござるか」「ご貴殿らしくない策にござるな」 「左近の独り相撲にござる」「左様か」 「それがしでは内府に勝てぬと申しましてな」 三成が、からりと云った。「島左近は恐ろしい男にござるな。もし内府の暗殺に成功すれば、近隣の諸侯に檄をとばせば、伏見の徳川勢など殲滅できましょうな」「山城守殿は左近の計画に同意なされるか」 三成が気色ばんだ。「我が主の景勝も、石田殿と同様な気象の持ち主。左近の策には乗りますまい」 兼続がほかごとを云った。「佐吉、内府暗殺の噂は伏見の者は皆知っておる、用心することじゃ」「紀之助、わしは負けぬ」 三成が顔をひきしめ甲高い声で断じた。 紀之助とは、大谷刑部の幼名である。この頃、大谷刑部は病がすすみ顔を白布で覆うようになっていた。その白布が三成に向けられた。「天下の名士、島左近が合戦では勝てぬとよんだ。そこが分らぬのが、お主の欠点じゃ」 ずばりと刑部が言った。「左近の申すことは分る。だが、それがしには勝算がござる」 三成が頬を赤くさせ答えた。「考えてみよ、お主には人を引き付ける武功があるか」 刑部の言葉に三成が声を失った。三成は豊臣政権の中枢にいながら、華々しい戦場での活躍に欠けている。彼の目前に居る大谷刑部や、直江山城守には戦塵にあっての数々の武功がある。 この二人の前では、加藤清正、福島正則でも一目おく筈である。それだけの実績と凄味を兼ね備えている。「だが、このまま見過ごす訳にはいかぬ、狸爺に天下が簒奪される」「それを、お主が阻止すると申すか」 刑部が、しわがれ声で訊ねた。「わしが遣らずば、誰が豊臣家を守る」 三成が昂然と胸をはった。 流石じゃ、たかだか佐和山城十九万石の小名が、二百五十万石の大大名の徳川家康を相手に戦いを挑むとは、故太閤殿下が信頼したとおりの男じゃ。直江山城守は三成の意気込みを買った。小説上杉景勝(63)へ
Mar 15, 2007
コメント(9)
-
小説 上杉景勝(61)
加藤清正や福島正則なぞは、幼少の頃から秀吉に育てられ、太閤に特別な感情を抱いていたが、戦場での恩賞の判断が五奉行に任された時期から、石田三成との確執が強まりはじめたのだ。 三成の判断基準は、利害や情に流されず成果や正邪であった。 彼は眼で確かめ、容赦なく秀吉に武断派の武将らの違法行為を逐一報告した。朝鮮在陣の武断派の武将らは戦功争いに明け暮れ、日常的に先陣争いや、抜け駆け行為に意を注いでいた。それを容赦なく弾劾した。 そのために加藤清正、福島正則らは秀吉から叱責を浴び、それが三成ら吏僚派の讒訴(ざんそ)と取った。 その三成の矛先が徳川内府にむけられた。徳川家康は故太閤の遺命を無視し、積極的に大名とのつながりを深め、福島家や蜂須賀家などの太閤譜代の大名と姻戚関係を結んでいた。 その真意を三成は看破(かんぱ)できずにいた。 五大老筆頭の家康は、前田利家の病死をさかいとし、天下盗りに動きだしたのだ。そのために秀吉子飼いの荒大名を自家薬籠(じかやくろう)中とすべく接近しだしたのだ。彼等も戦場往来の生き残りの家康の好々爺ぜんとした、態度に惑わされ家康に心をひらくようになった。 家康の心情は小心なほどの、根深い猜疑心に裏打ちされていた。彼は大名たちの離反を恐れ、細やかな気遣いをみせていたが、大名たちは家康の心の襞を知らないでいる。 三成は本能的に家康の心の奥を見極め、家康の行動の理非を糾弾していた。その三成の動きに武断派の武将らは反発し、益々、家康への接近を強め た。そんな折に兼続が伏見に姿をみせた。 「山城、来てくれたか」 景勝が上機嫌で出迎えた。「領内統治もひと山こえました。お屋形のご尊顔を拝したく罷りこしました。伏見の情勢はいかがにございます」「山城、伏見は魑魅魍魎(ちみもうりょう)の棲家じゃ」 景勝が剽悍な眼をした。「弱音を吐かれますな。豊臣家を救うことの出来るお方はお屋形のみにござる」 兼続が声を低め深謀な瞳で景勝をみつめた。「大老は内府の動きを阻止できぬし、五奉行には腰の据わった者がおらぬ」 部屋の外は物音ひとつしなく静まりかえっている。「石田殿がおられましょうが」 「一人で何ができよう、殿下子飼いの武将どもは内府の飼い犬同然じゃ。このまでは政事も内府の思うままじゃ」「お屋形、石田殿は内府暗殺を企てております」 兼続が声を低めた。「なにっー」 「家老の島左近殿が、秘かに動いております」 石田家の家老、島左近は当代に知られた石田家の軍師である。もと筒井順慶の家臣であったが、破格の待遇で石田三成に招かれた武将であった。彼の考えは、家康の暗殺であった。姑息な手段で天下を簒奪(さんだつ)せんと企む徳川家康などと、堂々の勝負は無用、奴を殺せば豊臣の御世は安泰と三成に迫ったが、三成は反対した。しかし、島左近は諦めずに機会を狙っていたのだ。「危ういぞ、そのような姑息な手段は内府にとり好餌(こうじ)となる」 景勝が反対した。彼の気象ならは仕方がない選択であろう。 家康は三成の動きを察知していた、彼の隠密集団の頭、服部半蔵から仔細な報告を受けていた。 「動きだしたか?」 家康は、それを待っていた。家康暗殺の動きが意図的に加藤清正にもたらされた。家康は三成一派が、過激に動き廻ることを望んでいたのだ。「治部少輔め、内府の暗殺を企てるか」 それが福島正則、加藤嘉明、黒田長政、浅野幸長、細川忠興らの知るところとなった。正則などは激高し、「これから石田邸に斬りこむ」 と意気込んだ。「正則、ここは伏見じゃ、まずは内府殿を守らねばならぬ」 清正が懸命にとめた。彼等は豊臣家の大名であることを忘れさっていた。小説上杉景勝(62)へ
Mar 14, 2007
コメント(11)
-
小説 上杉景勝(60)
二人は朝鮮在陣の諸大名の苦労をねぎらい、太閤殿下の病が快癒(かいゆ)したとの偽の情報を流した。 こうして秀吉の喪を秘して、石田三成は朝鮮への使者として美濃高松城主の、徳永寿昌と蔵入地代官の宮木豊盛を派遣した。「太閤殿下の死は味方の諸侯には洩らすな」と云い含められていた。 そうした中で景勝は、上杉屋敷にとどまり政務の処理に追われていた。 巷間、人々の口から太閤殿下死去の噂が飛びかうなかでの、政務は戦塵に明け暮れてきた、景勝にとり大きな負担となっていた。 山城守を呼び寄せたい誘惑にかられるが、伏見城での尊大な態度の家康を思いおこすと、国許の整備を優先させねばと思い我慢していた。 いずれは戦う運命にある二人じゃ、景勝はそう信じていた。 朝鮮では日本軍が善戦していた。三万八千七百名もの首級をあげた島津勢が大勝利をあげ、彼等は鼻を塩漬けとして秀吉の閲覧にあげようと日本に送りつけたきた。さらに小西勢と加藤勢も明国、朝鮮の連合軍を破り意気をあげていた。これが日本軍の最後のあがきであった。 そうした最中に撤兵命令を受け、十月中旬から順次、諸大名の兵士が帰路についた。最後尾は、島津勢で彼等は小西行長勢の撤退を助け、甚大な損害を被りながらも撤退を完遂させた。 皮肉にも秀吉の死去で慶長の役が集結をみたのだ。 これまで世間に秘匿されていた秀吉の死が、慶長四年の年明けを迎えた一月五日に公表された。庶民は日本の絶対者の死を知り喜びに沸き立っていた。晩年の秀吉は血を求める魔王その者であった、だが絶対者の死を境として、新しい独裁者が権力の中枢に座り、徐々に正体を現しはじめた。 彼は亡き太閤の遺命のほころびを見つけだそうと、秘かに蠢きだしていた。 (謀略) 家康は堺の豪商、今井宗薫を仲人にたて六男の忠輝(ただてる)と、伊達政宗の長女の五郎八姫(いろはひめ)との縁組を画策した。 忠輝は八歳、五郎八姫は六歳の幼子で政略の臭いがあるが、家康は強行した。『勝手に婚姻を結んではならない』 と、秀吉は生前に掟を定めていたが、家康はこれを無視し伊達家と縁組を結んだのだ。「大老や五奉行がなんじゃ、わしの力でねじ伏せてやる」 これを知った五奉行の石田三成と大老の前田利家は激怒した。 太閤殿下の喪を発したばかりの時期に、これみよがしと遺命を無視する家康の態度が許せなかった。「家康と刺し違える」 前田利家は激高したが、結局、家康に丸め込まれてしまった。利家はその時期すでに病に侵され、家康の術中に填められたのだ。 利家は己の死を意識し、倅の利長に家康が不埒な真似をするなら武力でもって討ち取れと指図をしていた。これは石田三成には心強い言葉であったが、利家は豊臣家と秀頼の将来を案じながら、閏三月三日に他界した。 彼の死は石田三成等の反家康派にとり、大きな衝撃となった。倅の利長は年若で父の利家のように合戦の実績がない。 五大老の合戦経験者は毛利輝元、宇喜多秀家、上杉景勝の三将のみであった。石田三成は景勝に期待した、だが彼の領国は遠国の会津の地である。その背後には、奥州の覇者と異名とる伊達政宗と、曲者の最上義光がいる。 そうした最中に朝鮮渡海の秀吉子飼いの、武将連が家康に籠絡されていた。 彼等は一様に石田三成を憎んでいた。利家が生きていた頃は、彼等も遠慮して利家の指示を守ってきたが、その歯止めがなくなったのだ。 秀吉の子飼い大名のうち、奉行として行政面を担当した石田三成らを吏僚派(りりょうは)と呼ぶ。一方、戦功により大名に取り立てられた、加藤清正、福島正則、黒田長政、細川忠興らは武断派と呼ばれていた。 秀吉の全国制覇の段階では、武断派が必要とされたが、天下統一がなると行政面の強化が必要となり、吏僚派が台頭し両派の対立が激しさを増した。特に朝鮮の役でそれが顕著となった。小説上杉景勝(61)へ
Mar 13, 2007
コメント(10)
-
小説 上杉景勝(59)
八月五日、伏見城で病床にあった秀吉は、秀頼の将来を五大老に託し、五奉行と誓紙を交換させた。五大老は帰国中の上杉景勝をのぞき、それぞれ五奉行に誓紙を提出し、秀頼への奉公と法度の遵守を誓った。 この行事は秀吉の、妄執のなせる仕儀であった。 既に何度となく彼等は、誓紙の交換と提出を行っていたのだ。 そのあと秀吉は『秀頼のことを宜しく頼む』との内容の遺言状を五大老に託したのだ。 慶長三年(一五九八年)八月十八日、諸社寺の病気平癒の祈祷もむなしく、秀吉は波乱の生涯を閉じた。享年、六十二歳であった。 秀吉の死で一時、徳川家康の周辺に不穏な空気が流れた。家康を恐れた三成の家康暗殺の噂が流れたが、秀吉の死去を家康に知らせたのは石田三成であった。家康は秀吉の死を知り驚喜したといわれる。 いずれ天下は己の手に転がり落ちる、そう思ったのだ。 今川家の人質、織田家の人質、そうした経験をへて信長に忠節を誓い、 織田家の天下布武のために多くの血を流してきたのに、明智光秀の討伐を秀吉にしてやられ、天下を取りそこなったのだ。 家康は、嫡男の秀忠(ひでただ)を秘かに江戸に帰した。これは織田信長父子の、本能寺における故事を恐れた結果であった。親子が一緒に伏見におってはならぬ。この行動をみても家康の野心のいったんが知れる一事である。 秀吉の遺骸は隠密に伏見城に安置された。秀吉の死去が公となると、朝鮮軍や渡海の日本軍への影響が大きいとみた配慮であった。 日本六十余州の天下人としては、余りに淋しい最後である。 秀吉の遺骸は、翌年の慶長四年の四月十三日に、東山の阿弥陀ケ峰に葬られるのであった。 太閤殿下の訃報が会津の景勝にもたらされた。この知らせは三成からのものであった。「とうとう亡くなられたか」 景勝が天を仰いだ。「お屋形、すぐに伏見にまいらせませ。五大老の責務を果たすことで大老の身分が保証されます。それが無になれば、ただの大名にござる」「分った。これより騎馬で発つ、何事かあれば伏見に知らせよ」 景勝の決断は素早い、軽騎で手練者の家臣を率い会津を発った。 八月二十三日に伏見の上杉屋敷に着き、ただちに石田三成と会談した。三成が太閤の遺言や誓紙の交換等を細々と説明した。 聞くにつれ、景勝の青味をおびた顔つきが険しくなった。「いよいよ、徳川の狸爺が本領を発揮いたしますな」「景勝さまも、そう思われますか」 三成の顔色が曇った。「拙者は明朝にも伏見城にのぼります、お手配をお願いいたす」 秀吉死去後、五大老がはじめて顔をそろいた。「景勝殿、遠路大儀にござった」 家康が如才なく慰労の言葉をかけた。「転封のために政務をおろそかにして申し訳ございませぬ」「いやいや、このように早く亡くなられるとは思いもせぬことにござった」 肥満した体躯の家康が、柔和な笑顔で応じた。「五大老さまに相談がございます」 石田三成であった。「治部少、何事かな」 前田利家が痩身の躯に似合わない太い声を発した。「朝鮮の件にございます。小西行長殿より相談がございましたが、我が日本軍は敗色濃厚とのこと。五大老の了解を得まして撤兵命令を出してはいかがかと思います」 石田三成が前田利家にむかって進言した。「流石は五奉行筆頭の石田治部少殿じゃ、前田殿、殿下の喪を秘して五大老の連署で撤兵命令を出しましょうぞ」 すかさず家康が賛意を示した。「愚につかぬ戦であった」 前田利家も賛成し三人の五大老も了解した。 八月二十五日、徳川家康と前田利家の連盟の撤退命令書が出され、それを持って石田三成と浅野長政が名護屋に赴いた。小説上杉景勝(60)へ
Mar 12, 2007
コメント(12)
-
小説 上杉景勝(58)
山城守が城にもどるや、大広間の上座に景勝が不機嫌な顔をして堀家の使者を見下ろしていた。「お待たせ申した。拙者が執政の直江山城守にござる、お使者の口上をお聞かせ頂く」 長身白皙の体躯を晒し使者の前に座した。「拙者、堀家の家老堀直正(なおまさ)にござる。先般、我等は旧領の北ノ庄を去るにわたり、年貢の下半期分を新領主に引継ぎ越後に着任いたした」「それは祝着にござった」 山城守の声に揶揄がこめられている。「祝着ではござらん、年貢の半分は新領主に残しておくことが天下の仕置きにござる。何ゆえもって一年分を持ち去られました」 堀直正が歴戦の武将らしい顔を歪め声を強めた。 直正の云うとおり、年貢の半分を跡を継ぐ領主に残しておくことが通例であった。ところが越後に入封すると、上杉家は一年分の年貢を徴収し会津に持ち去っていたのだ。それを返還するよう、堀直正は言いたてた。「堀家の申したての儀は分ります。が、それは堀家の怠慢にござる」「なんとー、我が藩の怠慢と申されるか」 堀直正が声を荒げた。「左様、事前の調べもなく入封されるは怠慢の謗(そし)りを受けても当然にござる。我が家は会津転封のお沙汰を受け、旧領主の蒲生家の仕置きを調査いたした。蒲生家は一年分の年貢を持って宇都宮に移られた。従って我等も越後の年貢を全て持参いたし当地に参った。堀家が越前より年貢の徴収を怠ったのは、そちらの落ち度、当家の知るところにあらず」 山城守が滔々と弁じた。「それは非道と申すものにござる」 堀直正が顔面を朱として喚いた。「ただ今、釈明したとおり、そちらの手落ちと存ずる。その手落ちを上杉家としては負担いたす謂れはござらん」 直江山城守が毅然とした態度で断じた。「中納言さま、上杉家の主人としての見解はいかに」 堀直正は矛先を景勝にむけた。「当今の大名は余りにも考えが甘い。山城の申したとおり返納は拒否する」 景勝の容儀に取りつく余裕を与えぬ気迫が込められている。「もしも、これが合戦ならば物見の手落ち、堀家は座して滅亡されるか?」 堀直正は返答に窮した。「大老としてのご答弁にございますか」 「左様」 例の青味をおびた横顔をみせ景勝がそっぽをむいた。 堀直正は云うべき言葉を失い城を下がって行った。この件から両家に遺恨が残ることになった。 五月となり朝鮮渡海の諸大名のうち、宇喜多秀家、毛利秀元、吉川広家、藤堂高虎、脇坂安治らの五名が帰国してきた。 相変わらず、朝鮮各地の戦況は不利のままである。 太閤殿下の病状はますます悪化し、ほとんど食事も咽喉を通らない状態におちいっていた。七月十五日。豊臣政権の諸侯は前田利家の屋敷に参集を命じられた。太閤殿下死去の後も、遺児の秀頼を守り立ててゆく誓詞署名のためであった。石田三成、浅野長政、増田長盛、前田玄以、長束正家等の五奉行が一座の世話役であった。 会場として前田家が選ばれた経緯は、利家が秀頼の守役を仰せつけられたからである。併し、誓詞の宛先は太閤秀吉ではなかった。 内大臣の徳川家康、大納言、前田利家の両名への宛先となっていた。 これは秀吉の構想で、己の死後は、この二人の連合により政局を安定させ、秀頼を粗略に扱うことのないようにと思慮した結果であった。 諸侯は誓詞に署名花押(かおう)を押し、両人に提出して退出していた。 五奉行の石田三成も、たわいのない行事に加わっていた。 その後、前田利家は大阪城に入り秀頼の守役となり、徳川家康は伏見城で政務を司ることに決した。諸侯から二人の大老の職務をみれば、次ぎの権力者が徳川内府と映ることは、自然の成行きであった。 秀吉と光秀がもっとも意を注いだことは、徳川内府を絶対に大阪城に入れないことであった。伏見城から諸侯への指示命令と、大阪城からの命令では事の重さが違う。そうした意味では伏見城に孤立させることに意味はあったが、狸爺の家康は伏見城で、思いのままに権力を振るうことになる。 小説上杉景勝(59)へ
Mar 10, 2007
コメント(9)
-
小説 上杉景勝(57)
「そちたち、試みに慶次と立ちあってみよ」 景勝が揶揄いぎみに言った。 四人の武辺者が名乗りをあげた。いずれも練達の士であったが、瞬時にして槍を巻きあげられ、馬上から突き落とされたという。 慶次は景勝の武将としての生き様に惚れ、一生を上杉家の家臣として終えた。後年、景勝が米沢三十万石に減封されたときも五百石の少禄で従った。 さらに有為な浪人がいた。剣聖と云われた新陰流の祖、上泉伊勢守信綱の孫にあたる、上泉主水泰綱(もんどやすつな)、蒲生家浪人の岡左内、佐竹浪人の車丹波などそうそうたる人物が、会津に集まった。 ちなみに車丹波善七は、倅の代になり徳川幕府に仕え、将軍秀忠の引き立てにより非人頭となり、善七の名を世襲し徳川幕府滅亡まで犯罪者の処刑、その始末などの血の穢(よ)れの政事を、裏から支えつづけたのだ。 こうした最中に、米沢から直江山城守兼続が姿をみせた。 彼は上杉家の執政であり、米沢藩主として止まる訳にはいかなかった。上杉家の新領内の整備と民衆の統治が、彼の最大の務めであったのだ。「山城、米沢城下の整備はいかがいたした」「米沢城下は鄙びた町にござる。武家屋敷をのぞくと八百余の戸数と、人口六千に過ぎない田舎町。家老の静田彦兵衛に任せてきました」「わしは大いに助かるが、最上勢への備えは大事ないか」「米沢城に兵を一千名残して来ました。馬場孫助に鉄砲隊二百名をあずけて参りましたので、ご心配は無用に存じます」「そうか、与板衆が守りを固めておるか」 浅黒い顔つきの景勝に安堵の色が浮かんだ。「お屋形、殿下は醍醐寺(だいごじ)で盛大な花見の宴を催されたそうにござるな」「流石に早耳じやの、わしにも知らせが参った」 景勝は転封間際のために光秀に使者を送り会津にとどまっていたのだ。 秀吉は慶長三年、三月十五日に、醍醐寺三宝院の山々で盛大な観桜の宴を催した。これが有名な醍醐の花見である。 この宴は、朝鮮の役が戦線膠着し秀吉は苛立ちを募らせていた。まだ嫡男の秀頼が六歳では将来を案じられる、その憂さをはらす意味があった。 この時期を境として秀吉は体調を崩し、五月頃から床に臥せる日々が多くなった。秀吉は豊臣家の行く末を案じながら、病魔と闘うことになる。 ようやく秀頼が六歳となったが、あと十年の余命を祈っていた。あと十年経てば秀頼は十六歳となるのだ。 四月となり、上杉家は執政の山城守が総奉行として懸命に、領内整備を行っていた。若松城から最上に通じる道路は拡張され、橋の新築や架け替えにも目処がたってきた。「泰忠、これが完成した暁は最上領への軍事道路となる」「お屋形さまが申されたように、最上攻めを行いますのか?」「その時期が参ったらな」 兼続が早咲きの桜を愛でながら答えた。 城内では武器奉行が武器の購入を図り、鉄砲二千五百挺が武器庫に納められていた。火薬や火縄は自前で製造し、謙信時代に創設された段母衣組(だんぼろぐみ)のほかに、新たに百挺鉄砲隊が創設された。「泰忠、その方に明日より下野方面の道路建設の総奉行を申しつける。もしも徳川と一戦におよぶ場合は、下野方面が主戦場となろう」「心得申した」 こうして二人が語らっていると、城より急使が駆けつけてきた。「山城守さま、急ぎお城にお帰りを願います」 「何事じゃ」「堀秀治さまより使者が参っております」「ようやく参ったか」 山城守の白皙の顔に笑みが刷かれた。「堀秀治さまとは、旧領の越後に入封された大名にござるな」 傍らの黒金泰忠が不審そうな顔を山城守にむけた。「そうじゃ、さだめし怒髪天を衝く勢いで怒っておろうな」 直江山城守が笑い声を残し、城に向かい騎馬で疾走していった。小説上杉景勝(58)へ
Mar 9, 2007
コメント(11)
-
小説 上杉景勝(56)
「酒の用意をいたせ、なんとのう飲みたい心境じゃ」「心得ました」 黒金泰忠が厳つい背をみせ足早に去った。 景勝は一人天守閣にのぼり、あらたに領土となった若松一帯を見渡した。 (この地で力を養う、あの向こうに最上と伊達が牙を剥いておるか) 磐梯山の山頂が雪をかむり輝いている。「百二十万石か」 景勝は己の分限を独語し、殿下存命のうちに最上勢と一戦したいと願った。景勝の胸にふつふつと闘志が湧いていた。 居室にもどると膳部の用意がととのっていた。「泰忠、そちも一緒いたせ」 「有り難き幸せに存じまする」 二人は黙して飲んだ、ここでも景勝の肴は漬物であった。「わしの務めは関東の徳川と奥州の伊達、出羽の最上への備えじゃ。内府との合戦は、わし独りで為したい。そのためには最上の領土が欲しい、そちは領内の整備をいたせ」 景勝は庄内の飛地を思った。己の領土と言っても最上義光の領土内にある、なんとしても最上の領土を併合したかった。「道路と橋が先じゃ」 景勝が念押しした。「畏まりました。兵卒の移動に支障なきょう、拙者が奉行となり執り行います」「民衆の信をえることを忘れるな」 「心得てございます」 景勝は元の大杯で酒を呷り、ぽりぽりと小気味の良い音を響かせている。「わしは五万の直営軍団が欲しい。わしは必ず徳川勢を叩きふせる自信がある」「それには領土が不足にございますな」 「最上が欲しいのよ」 景勝が青味をおびた顔つきで平然ときわどい言葉を発した。「徳川勢の総兵力は、いかほどにございましょうな」「わしの目立てじゃが、十二万の兵力は擁しておる筈じゃ」「そのような大軍を我が家一手にて叩きまするか」 泰忠が驚いている。「合戦に投入できる兵力は八万名とよむ、わしは領内を空にして決戦を挑む。我が家の猛烈な突撃には耐えられまい、不識院公から引き継いだ我らは、どこの大名の兵より精強である」 景勝が珍しく大見得をきった。「これは驚きました、だが領土を空にしては伊達勢が侵攻いして参りましょう」「内府の首を刎ねたら、関東に乱入し江戸を占拠いたす。そうなれば会津なんぞに執着することはない」 黒金泰忠が唖然として主人を仰ぎ見た。「腑抜けた面をするな。各城代に使者を遣わせ、我が軍法を守り、陣形と行軍の調練をいたせと申せ」 「はっ、早速手配つかまつります」「そちにも一手の将にいたさねばなるまいな」「待ちくたびれましたぞ、野戦攻城の指揮を執らせてくだされ」「先刻、申しつけた領内整備が優先じゃ。その後に考える」「お約束にござるぞ」 景勝がにこりともせず大杯を呷り、訊ねた。「若松城の城代を誰に申しつける」 「大石綱元さまはいかがですか?」「そちにしては上出来じゃ、綱元れば安心じゃ。だが領内統治をなした後じゃ。その時には綱元にかわり保原城代にいたそう」「有難う存じます」 黒金泰忠が精悍な顔で平伏した。「これからの合戦は鉄砲じゃ、唐人丹後守から学んでおくのじゃ」「心得ました」 黒金泰忠が不敵な面魂をみせ肯いた。 これを境として景勝は領内の経営に追われることになる。これは当然の帰結であるが、城代の黒金泰忠のみに任せる問題ではない。 若松城にも数々の欠陥がみつかり、城郭の修理や増築が行われた。 同時に百二十万石に相応しい人材確保も必要となり、積極的に浪人の召し抱えが行われた。 上杉家の招きに応じて集まった面々のなかに、異彩を放つ快男児がいた。 加賀藩主、前田利家を叔父にもつ前田慶次利大(とします)である。 彼の上杉家への仕官には二説ある。文禄の役以前に直江山城守兼続の知己となり、五千石で景勝に仕官したと云う説と、上杉家が会津に転封された後に仕官したとする説とがあった。 彼は傾奇者(あぶきもの)として奇矯と才知を兼ねた文武の将であった。 松風と名づけた駿馬の馬上に、大武辺者と書いた大旗をかかげ、朱槍の大身槍をひっさげた、かぶき武将として名を轟かせていた。 この朱槍に抗議する者が現れた。元来、上杉家の軍法としては武功にぬきんでた者が、朱槍を持つことを許されていたのだ。 彼等、武辺者の意地が云わせる言葉であった。小説上杉景勝(57)へ
Mar 8, 2007
コメント(15)
-
小説 上杉景勝(55)
「山城、そちは石田治部少殿を買いかぶってはおらぬか?」「はて、彼のご仁は殿下に似た才気がござる」 「そうか」 景勝はその話を打ち切り話題をかえた。景勝は石田三成という五奉行筆頭の武という資質に疑問を感じていたのだ。「山城、いかに二百五十万石の所領の狸でも、四大老には対抗できまい」「拙者には些か懸念がござる」 「何を懸念いたす」「小早川秀秋殿は暗愚(あんぐ)で頼りになりますまい。一番の懸念は前田さま、さして殿下と年の差がございませぬ。二代目の利長殿が父上さまのように勇猛であれば、前田家、宇喜多家と我が上杉家のみでも内府に対抗できましょうがな」 兼続の話に耳を貸していた景勝が、驚くような言葉を発した。「我が上杉が関東に乱入いたせば、狸爺、さぞ仰天いたすであろうな。伊達や最上なんぞ問題ではない、旧領の越後に檄をとばせば、信濃の真田家と越後の一揆勢は関東に攻めのぼれる」「お屋形、本気でお考えか?」 「冗談でこんな話ができるか」「いずれにしても徳川殿と石田殿との駆け引きとなりましょうな」 兼続の慎重な態度に比して、景勝は青味をおびた顔に満々たる闘志をみせている。狸爺の牽制役として会津の鎮将となった身なら、それなりの戦略をもたねばならない。景勝の頭脳には鮮明な戦略が描かれていた。 会津から南下して下野(しもつけ)にある宇都宮の蒲生秀行を葬り、家康の居城、江戸城に進攻する。越後の一揆勢は信濃をへて真田勢と合流し江戸をめざす。この二面作戦ならば勝機は確実である。 さらに有利に戦闘を進めるならば、常陸(ひたち)の佐竹義宣(よしのぶ)と同盟し、家康の倅の結城秀康(ゆうきひでやす)の守る下総(しもふさ)を攻め、一気に武蔵に進攻する。こうして家康の留守中に江戸城を占拠すれば、狸爺は関西で孤立する。うるさいのは伊達政宗と最上義光、越後の堀秀治の三名であるが、家康の後ろ盾を失いば、自然と温和しくなる。「お屋形、恐るべき戦略ですな」 兼続は景勝の計画を聞き身震いした。矢張り、不識院公の血筋だけはあると改めて知らされた。「まずは、徳川殿の動きを注視いたしましょう」と、釘をさした。 (太閤死す) 景勝一行は春日山城にもどり、重臣や主だった者たちに太閤秀吉の命を伝えた。故謙信から景勝の代まで手を砕き、血であがなった越後の地を去る、これは辛いことであった。だが主人の景勝が五大老となり、会津、庄内、米沢、佐渡の百二十万石の太守となられることは、栄誉なことである。 越後は会津転封でゆれ、二十数名が上杉家の浪人となって景勝に心を寄せながら、越後の地に残った。 景勝は一万の軍勢を先発させた。目的は最上勢への備えであった。主将は荒砥(あらと)城代となる泉沢久秀、副将は金山城代の色部光長が務め、ほかに五将が含まれていた。さらに伊達勢の備えとして白石城を守る甘粕景継の姿もあった。三月を迎え、三千名の将兵を率い直江山城守が米沢にむかった。 景勝は二万余の残存兵力を擁し会津に発った。諸将連は南山城代の大国実頼、梁川城代、須田長親、浅香城代の安田能元(よしもと)福島城代、本庄繁長、そのた上杉家が誇る十二将達であった。 景勝は無事に若松城に入城を果たし、各地の城塞の将は赴任地に赴いた。 長年にわたり奥羽と関東に睨みをきかせた要衝の地にある、若松城は堅固な大城塞で、本丸には五層七階の天守閣が偉容を誇っていた。 名将として名高い蒲生氏郷が手を加えた城だけに、非のつけどころのない城であった。武家屋敷も行き届いたもので禄高に応じて、家臣達は屋敷を与えられた。春日山城時代とおなじく黒金泰忠は、六千二百石の知行をうけ、城代を務めることになった。「お屋形さま、天守からみる景色は雄大ですな。磐梯山、猪苗代湖が見事にございます」 「海が見えぬのが不満じゃ」 景勝が癇癪の筋をみせ呟いた。会津に赴き、営々と築きあげた越後の地が恋しいのだ。 「住めば都と申します」 黒金泰忠が慰めていた。小説上杉景勝(56)へ
Mar 7, 2007
コメント(13)
-
小説 上杉景勝(54)
一時、沈黙が漂った、重苦しい沈黙を秀吉みずからが破った。「景勝、わしは老いた。・・・もし、わしに万一のことがあれば徳川内府や、不逞の輩(やから)の動きが恐い。秀頼が成人いたすまで彼等の押さえを務めてもらいたいのじゃ、これがわしの願いじゃ」 景勝が、はっと秀吉を仰ぎみた。目前に老いた老人が涙を浮かべていた。「上杉家は戦国大名とし、豊臣政権に初めて投じてくれた。それに精強で鳴らした家柄じゃ。わしの頼みを聞き届けてくれえ」 景勝は故謙信の生き様を標榜してきた漢(おとこ)であった、故に、義侠心の塊のような性格をしていた。天下人にこのように言われては否やは云えぬ。「殿下、謹んでお受けいたしまする」 背後で直江山城守も平伏していた。「おう、わが頼み聞き届けてくれたか、山城守、そちにも褒美として米沢六万石をとらす」 「ははっー」 景勝主従が平伏した。「殿下、ひとつお聞きいたします。不逞の輩とは徳川内府に伊達、最上とみても宜しゆうござるか」 景勝が剽悍な眼差しで秀吉をみつめた。「景勝、会津の位置を考えよ」 太閤秀吉の細い眼が強まった。「畏まりました」 もはや、何も聞くことはない。「景勝さま、先年、小早川隆景殿の急死により五大老の座に空席がございます。この転封を機会とし、五大老の就任をお願いつかまつる」「三成、よう申した。これで豊臣家は磐石じゃ」 秀吉が老醜の顔を歪め、歯のぬけ落ちた歯ぐきを見せて肯いた。 (甘い、五大老とはいっても所領の大きさが徳川の狸爺とは、桁違いに隔たりがある。いずれは徳川家の独断場に化してしまう、あの明敏であった殿下はかくも年老いられたか) 景勝は往年の越水城の溌剌とした秀吉を思いだしていた。 こうして景勝主従は思いもせぬ、命令を受け屋敷にもどった。「山城、酒を酌み今後のことを計ろう」 「宜しゅうござる」 二人は時を忘れ語りあった。胸中には営々として築きあげた越後の風景が去来する。それが無念極まりないが、事ここに至っては前に進むしか道はない。「お屋形、太閤殿下の命運は極まり申したな」「あのご様子は、ただ事とには見えぬな」 景勝が無意識に沢庵を口にし、小気味のよい音をたてた。 この当時、五十万石以上の大名は全国で九人しかいない。 徳川家康 二百五十万七千石 毛利輝元 百二十万五千石 上杉景勝 百二十万石 前田利家 八十三万五千石 伊達政宗 五十八万石 宇喜多秀家 五十七万四千石 島津忠恒 五十五万五千石 佐竹義宜 五十四万五千石 小早川秀秋 五十二万二千石 ついで、加藤清正は二十五万石、最上義光は二十四万石、福島正則は二十万石であった。いかに秀吉が景勝を買っていたか分る禄高である。「殿下は徳川殿を恐れながらも、秀頼さまの後見を頼むことになりましょう」「徳川の狸爺の思惑をどうみる」 浅黒い肌をみせ景勝が兼続に問うた。 兼続が虚空を凝視し、景勝は無言で酒をあおっている。「恐れ多いことながら、殿下にもしもの事があれば、朝鮮の役は終りましょう。そうなった暁には、太閤殿下の子飼いの武将と石田三成殿の確執が強まりましような」 兼続が断言した。「狸爺は、殿下子飼いの武将と手を握るか」 「御意に」「子飼いの武将とは、加藤清正、福島正則、黒田長政、浅野幸長、池田輝政、細川忠興、加藤嘉明等じゃな」「左様、朝鮮での功名争いで石田殿を恨んでいる者にござる」「子飼い同士のいがみ合いとは、厄介なことじゃ」 景勝が太い吐息をはいた。「山城、狸爺は己の年齢からみて野望を急ぐ筈じゃ。秀頼さまの代官として豊臣家に忠誠を誓うような、悠長な策はとるまい」「大大名としての実力と、百戦練磨の合戦の実績とで味方を増やすことになりましょうな。その際に五奉行筆頭の石田三成殿が、どうでるかが鍵となりましょう」小説上杉景勝(55)へ
Mar 6, 2007
コメント(11)
-
小説 上杉景勝(53)
景勝と山城守は百名の供を率い上洛の途についた。豪雪のなか騎馬で三国峠をこえ、上野(こうずけ)から関東に出て京に着いた。 伏見城は増築工事の最中で、諸大名の兵や人夫でごったがえしている。 一行は京の上杉邸に入った。この屋敷は敷地三万坪の豪邸である。ここに景勝の正室のお菊の方と、兼続の夫人のお船の方が入邸していた。 景勝は伏見城の石田三成に到着の使者をつかわし、居室で寛いでいた。 御館の乱で景勝に輿入れした、お菊の方は顔色が優れず、挨拶を述べ席を退出していった。すでに二十年がたとうとしていた。兼続の夫人のお船の方は兼続より三才年上ながら容色衰えず、しばらく談笑し部屋を辞していった。「お屋形、お菊の方さまお躯が悪いのでは」「うむ」 景勝はそれに答えずに酒を口にしている。「少しは心配なされ」 みかねて兼続が忠告した。「京と越後は遠い、心配しても詮なきことじゃ」と取りあおうとはしなかった。 お菊の方は政略結婚で上杉家に嫁してきて今は、豊臣家の人質の境遇である。景勝は強情にも、未だにお菊の方に指一本も触れてはいない、相変わらず不犯をとうしていた。「お屋形も良い年になられた、少しは女子に興味をもたれませ」「面倒じゃ」 兼続の薦めに景勝は、例の顔色をみせ一言で断った。「女子とは心休まる者にござる」 「山城、そちには三人の子がおったの」「はい、一男二女にござる」 「嫡男は景明と申したの、何歳となる」「四歳となりました」 「早いものじゃ」 景勝が珍しく感慨にひたっている。「定勝さまも、そろそろ元服になられますな」「それも、お船のお蔭で元気に育っておる、そちには礼を申す」「滅相な、主人が家臣に礼など申すべきではござらん」「それにしても京の青空を見よ、心が晴れ晴れといたすは」 二人は翌日の登城の件に触れずに、たわいのない会話を続けていたが、お互いの胸のなかに、共通の胸騒ぎを感じていた。 翌日の一月九日、景勝一行は伏見城に登城した。待ちかねたように三成が顔をみせた。 「遠路、ご苦労に存ずる」「何事かと急ぎ参上つかまつりました」 景勝に代り山城守が挨拶を述べた。「殿下がお待ちにございます」 三成の案内で奥に導かれた。「豪華なお城にござるな」 景勝が城内を見まわし感嘆の声をあげた。「明国との交渉団を念頭にいれて造ったお城にござる」「朝鮮の戦況はいかがじゃ」 景勝の問いに三成の顔が曇った。「はかばかしくございませぬ」 大広間に太閤秀吉が豪華な衣装を纏って待ち受けていた。「景勝、よう参った。山城守もご苦労じゃ」「ご尊顔を拝し恐悦至極に存じ奉ります」 景勝が挨拶し主従が平伏した。「景勝、歯の浮くような世辞はやめえ」 「これは」 景勝の青味をおびた顔に困惑の色がはかれた。「武骨者には武骨者の、もの云いがあろう」 相変わらず、ひょうきんな口調ながらも声に張がない。顔色も変に浅黒い、ご病気かと景勝の胸に不安が走りぬけた。 秀吉が軽い咳払いをし、懐紙で口を拭い言葉を発した。「景勝、そちに相談があって呼び寄せた。話の内容は三成が申し聞かせるが否とは言わせぬ」 主従が秀吉を仰ぎみて視線を三成に廻した、童顔の三成の顔が引き締まって見える。沈黙の中で三成が口をひらいた。「言葉を改め申す。蒲生秀行、家中不行き届きにより会津九十万石より、宇都宮十八万石に転封。上杉景勝、そのほう儀は領国の越後より会津に移封を命ずる」 「なんとー」 景勝と兼続が思わず声を洩らした。「これは豊臣政権としての命令にござる。さらに申し添います、蒲生家の旧領、会津九十万石に加え佐渡庄内三郡を安堵いたす。総禄高百二十万石を下しおかれる」 景勝が黙然と平伏した。一切の感情をみせないが心中は揺れ動いている。長年にわたり経営してきた越後の地に未練があった、それは言葉なんぞに表せぬ心の叫びであった。「景勝、そちは不満か?」 秀吉が声をかけた。「恐れながら申し上げます。越後は上杉家累代の領土にございました。この度の転封の理由をお聞かせ願いまする」小説上杉景勝(54)へ
Mar 5, 2007
コメント(15)
-
小説 上杉景勝(52)
今度の慶長の役は前役と違い、征明ではなく朝鮮の南四郡を実力で獲得することにあった。それを受け五月八日に明国の副総兵、楊元(ヨウゲン)が、三千名の兵を率い漢城に入城した。 この戦闘ま前回の文禄の役どうよう、初戦は日本軍が優勢に戦闘を進めた。 七月には、日本の連合水軍が朝鮮水軍を破っている。 こうして慶長三年を迎えた。この年は上杉家にとり運命的な年となるが、日本にとっても震撼(しんかん)する重大な事態が持ち上がるのであった。 上杉家は出兵もなく豪雪の中で新年を迎えていた。景勝は四十四歳となり人品に武将としての貫禄が滲み出てきた、一方の兼続も三十九歳を迎え、いよいよ智謀が深まり、風貌に相応しい挙措を見せていた。だが、時に応じ人々の意表をつく振る舞いに及ぶことが多くなった。 伏見城の石田三成から、一月九日に登城するよう書状が届き、城をあげて上洛の準備がすすめられていた。 そんな最中に景勝と兼続は、新年を祝う盃ごとをしていた。「お屋形、またも無謀な朝鮮侵略をはじめましたな」 兼続は最近、お屋形さまと言わずに、ただお屋形と呼ぶようになっていた。「上洛のおりに拝する、殿下のご尊顔が年々と悪うなっておられる」「最後の足掻きにござるか?」 「わしにはそう見えるな」 景勝が盃を干した、最近は自慢の大杯を止め少し大きめな盃を使っている。「殿下に、もしもの事あれば重大事じゃ」 景勝が愁い顔をしている。「四日の早朝には城を出立せねばなりませんな」「九日には伏見城に着かねばならぬ」 「年賀から何の御用にござろう」「そちに分らぬことが、わしに分るか」 景勝がぼそっと言葉を発した。「朝鮮渡海のお話ではない筈にござる」 兼続も首をかたむけている。「難しい話はなしじゃ。まずは一献参れ」 景勝が手慣れたようすで兼続の盃を満たした。兼続は拝礼し何事か思案している。軍用金の運上額も文禄の役当時と比較して格段にあがっている、殿下は何を申される、兼続の胸中に不思議な胸騒ぎがしていた。「道中が厄介じゃな」 景勝が外の景色を眺め呟いた。「騎馬なら大丈夫にござる、三国峠を越えさえすれば雪の心配はござるまい」「手土産にぬかりはあるまいな」 「白金を千枚用意いたしました」 暫く相手をし、直江山城守は居室から引きあげ長廊下を伝っていた。「山城守さま」 廊下に三人の男が平伏して待ちうけていた。「そち達は三宝寺勝茂の家臣か?」 「先日は懇ろな香華を賜り有難う存じました」 彼等は旗本の山宝寺勝茂の家臣達であった。年末に勝茂が家臣の行為を怒り、手討ちにした事件が起こった。 それは些細な一件であったが、手討ちにさりれた家臣達の兄弟等が兼続に訴えでた。兼続は勝茂の手落ちもあると判断し、金子を与え懇ろに弔うように諭したのだが、兄弟はごねる事でもっと金子が貰えると浅ましい考えをおこして兼続を待ち受けていたのだ。 「それで何事じゃ」「はい、山宝寺の殿さまに死人を生き返らせるよう申しつけて下され」 直江山城守が白皙の顔を三名に注いだ、いずれも強欲な顔をしている。「聞けば勝茂の大切な物を壊したそうじゃな」「はい、されど手討ちとは非道にございます」「その方等は、死者を生き還らせよと申すのか?」 無表情に三人を見つめた。 この者達は無理を承知で欲の皮をつのらせておる。 「お願いにございます」「それほど申すなら聞き届けてやろう」 兼続の胸に怒りがたぎっていたが、微笑を浮かべ、傍らの者に筆と紙の用意を命じ、さらさらと一文をしたため兄弟に与えた。一読した兄弟達の顔色が蒼白となった。『未だ御意を得ず候えども、一筆啓上つかまつり候、山宝寺勝茂が家臣、不慮の儀にて相果て申し候、兄弟ども嘆き悲しみ候て、呼び戻してくれ候様申し候につき、三名の者を迎えに遣わし候、かの死人お返し下さるべく候、恐惶謹言。 閻魔大王殿 直江山城守 』「これを持って迎えに参れ」 兼続が促した。三人は仰天して逃げ出したが、「あの世に送ってやれ」 と、傍らの近従に命じ屋敷にもどっていった。 人々は、この兼続の奇矯(ききょう)な振る舞いに眼を剥いた。武士とは欲得を離れ爽やかに振る舞う者、これが兼続の考えであった。それにしても閻魔大王に一筆啓上する機知はさすがと、改めて兼続の度量が人々の話題となった。小説上杉景勝(53)へ
Mar 3, 2007
コメント(17)
-
小説 上杉景勝(51)
石田三成の手が関白秀次にも伸びた、それは秀吉がお拾を得たことからはじまった不幸な出来事であった。秀吉に嫡男が誕生したことで秀次の立場が微妙に変化した。秀次は関白となると異常な性癖を見せはじめた。 殺生を好み、女にも凄まじい興味を抱きはじめた。白昼、公然と辻斬りをおこなったり、妊婦の腹を割いて楽しむなど、悪逆非道を行った。 秀吉は名護屋城に出陣するさいに、豊臣家二世の主と定め、細々とした訓戒を与えたが、秀次はその誓約を裏切ったのだ。 人々は殺生関白と陰口をたたき秀次を恐れた。だが、天下の継承者となった秀次に接近する大名が日毎に増えた。それは世の中の趨勢(すうせい)である。 伊達政宗を筆頭として池田輝政、浅野幸長、最上義光、細川忠興等の武将であった。太閤秀吉はお拾を得て継承問題に悩んでいた。 一旦は秀次にと考えを纏めたが、嫡男の誕生で心が揺れ動いていた。 そんな秀吉の心の迷いを三成はいち早くさっした。最近の関白秀次の行状はいちじるしくない、ここに眼をつけ増田長盛と秀次の身辺を洗い出し秀吉に報告した。こうした情報に接し、太閤秀吉は関白秀次に対し信頼を失っていった。 六月末、秀次に謀反の疑えがかけられた、訴えたのは石田三成であった。謀反のきっかけとなったのは、病死した蒲生氏郷の遺領問題であった。 氏郷の遺領を遺児の秀行に認めようとする秀次に対し、秀吉が反対したのだ。その対立する事態の収拾を図ろうとした、秀次の朝廷工作の献金が謀反と見なされたのだ。秀吉は我が命に反対する関白秀次に激怒した。「三成、関白秀次を糾弾いたせ、どのような釈明も受け入れてはならぬ」 秀吉の怒りは頂点に達していたのだ。「殿下は、さほどに関白殿を毛嫌いされてか」 これが偽らない三成の感慨であった。太閤秀吉は、三成に秀次の切腹を命じてきた。 豊臣家の行く末を思うと、三成は前途に暗雲を禁じえなかった。ここは秀次をたて、お拾さまの成人を待つのが上策とは思ったが、ここに至っては秀吉の命に従うしか道はなかった。 文禄四年七月三日、秀次は石田三成と増田長盛の糾明をうけ、翌日には官職を剥奪されて高野山に追放された。秀次は、その日のうちに切腹を命じられ命を絶った。さらに八月二日、秀次の正室以下の妻妾、子等三十九名が京の 三条河原で斬殺された。 この事件から太閤秀吉は、人代わりしたように残虐非道となっていった。 この一件で伊達政宗が秀次との連座をとわれ居直っている。「太閤殿下が関白殿下に天下を譲られたので取り入ったまでのこと、もし、これを咎と思し召すなら是非もなき、我が首を刎ねられよ。本望なり」 決然と言い放った。流石は奥州の曲者伊達政宗だけはある。「政宗、わしの誤りじゃ。そちと同じ境遇ならばわしもした、今回は見逃そう。じゃが、わしを少し甘う見たようじゃな、わしの後継者はお拾じゃ。忘れるでない」 天下の主、秀吉が細い眼を光らせた。「ははっー」 奥州の覇者、伊達政宗の脇の下から冷や汗が滲み出ていた。 この事件の功績をかわれ石田三成は、秀次の遺領をついで佐和山城十九万四千石の大名に取り立てられた。時に三成、三十六歳であった。 こうして三成は豊臣政権のなかで、五奉行としての地位を築いてゆくことになるが、秀次と連座を疑われた大名達からも敵として憎まれることになる。 慶長二年(一五九七年)一月、明国との講和交渉が不調に終わり第二次朝鮮の役が再開された。先陣は、またしても小西行長と加藤清正が命じられた。 両人は出陣日を待たずに渡海し、烈しい先陣争いを繰りかえし先を争った。 二月二十一日に、秀吉は在朝諸将の陣立を発表した。総勢十四万一千五百名を八陣に編成し、諸将連の布陣を定めた。 今回の秀吉は名護屋城に下向せず、伏見城から指示を出していた。 明国も二月十一日に、朝鮮救援を決定し戦闘準備に入った。小説上杉景勝(52)へ
Mar 2, 2007
コメント(10)
-
小説 上杉景勝(50)
こうした会話が交わされ、直江山城守兼続は九月から念願の定納員目録の作成をはじめた。景勝主従は、此の年から内政の充実を最優先として力を注ぐことになった。 明けて翌年の一月十七日、上杉景勝は越後、佐渡両地の金山支配を秀吉から命じられた。その朱印状には直江山城守を代官となし、金銀の運上額を確かめるようにと認められていた。景勝は内心、名護屋城で大見栄をきった己の失敗を悟ったが、後の祭りでであることを知らされたのだ。 浅野長政より朝鮮出兵の軍事費の増大に対応するための施策の、一環との知らせを受けた。同時に、この春に石見から金銀採掘の技術者が訪れ、石見銀山の最新技術が伝授されるとの連絡が書き添えてあった。このお蔭で相川金山、銀山の採掘量は飛躍的に伸びたのである。 文禄四年となり、日本と朝鮮で数々の出来事が起こった。二月となり上杉家にとり運命的な人物が亡くなることになる、会津九十万石の領主、蒲生氏郷が急死したのだ。「限りあれば吹かねど花は散るものを 心みじかき春の山風」 四十歳の若さで死去した氏郷(うじさと)の辞世の句である。 彼の死は巷間(こうかん)に色々な憶測を呼ぶことになる。謀殺、毒殺死、などなどであった、 氏郷は織田信長の娘婿であった。彼は信長と秀吉に従って数々の武勲をたてた武将である。 秀吉は氏郷の器量を買うと同時に、過去の煌びやかな栄光に嫉妬していた。これを疎ましく感じ、会津に移封されたと氏郷は思った。彼にとり左遷人事であった。「たとい小禄なりとも都近くにあれば、やがては天下も望めよう。会津では遠すぎる、何が出来ようか。志は虚しくなった」と嘆いたといわれる。 彼には大志があったのだ。会津に移ってから体調を崩し、臥せることが多くなった。彼には奥羽守護としての大役があった、伊達、最上への牽制役としての任務と徳川家康の監視役であった。 彼の資質を妬んだ石田三成の讒訴(ざんそ)による、秀吉の毒殺説などが風聞として流れたが、それを裏付ける証拠はない。むしろ秀吉と三成は氏郷の器量を買って会津に移封したのだ、根も葉もない風雪であった。 ともあれ、会津の要衝の地は十三歳の氏郷の倅の秀行が継ぐ事になる。 朝鮮でも異変が生じていた。初戦の華々しい連勝も制海権を失い、大明国が大軍を擁し、朝鮮救援に駆けつけてからの日本軍は、漢城を失い、釜山近郊まで押し詰められていた。 依然として朝鮮の亀甲(きっこう)水軍は優勢で、充分な物資の補給のないままで戦いを繰り返していた。そんな最中に日本兵の朝鮮軍への投降が激しさを増していた。朝鮮軍はそんな日本兵を降倭(こうわ)と呼んでいた。 その数は数千名にのぼったと云われている。 初めの頃は、朝鮮軍は降倭を殺害する方針であったが、練達した戦闘力と優秀な鉄砲技術をもつ日本兵を、貴重な戦力とみて朝鮮軍は「投順軍」と名づけた部隊を編成し、日本軍同士を戦わせるようになった。 その代表的人物が、金忠善(キムチュンソン)であった。忠善は加藤清正の部下で沙也加(さやか)と云う。彼は戦況が有利な時期に朝鮮軍に投降した、秀吉の朝鮮侵略戦争への抗議を示すものであった。こうした現状を石田三成は正確に秀吉に報告した、秀吉の矛先は加藤清正に向けられた。 朝鮮で苦戦する諸将達は、三成の報告に激怒したが秀吉の信任のあつい三成の言い分が勝り、彼等は太閤から叱責をうける羽目となった。 諸将にも言い分はあったが、三成は事実を告げることを厭わなかった。 奉行としての立場を貫いたのだ。三成に多少の情けがあれば事は大きくならなかったが、彼は律儀にも一切の隠し事もなく報告した、これが石田三成という男の性格であった。 朝鮮在陣の武将は、三成の讒訴(ざんそ)と感じた。彼等のほとんどが秀吉子飼いの武将連であったことが、のちに豊臣家を不幸にする要因となった。小説上杉景勝(51)へ
Mar 1, 2007
コメント(11)
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月12日分)
- (2025-11-25 23:58:33)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-
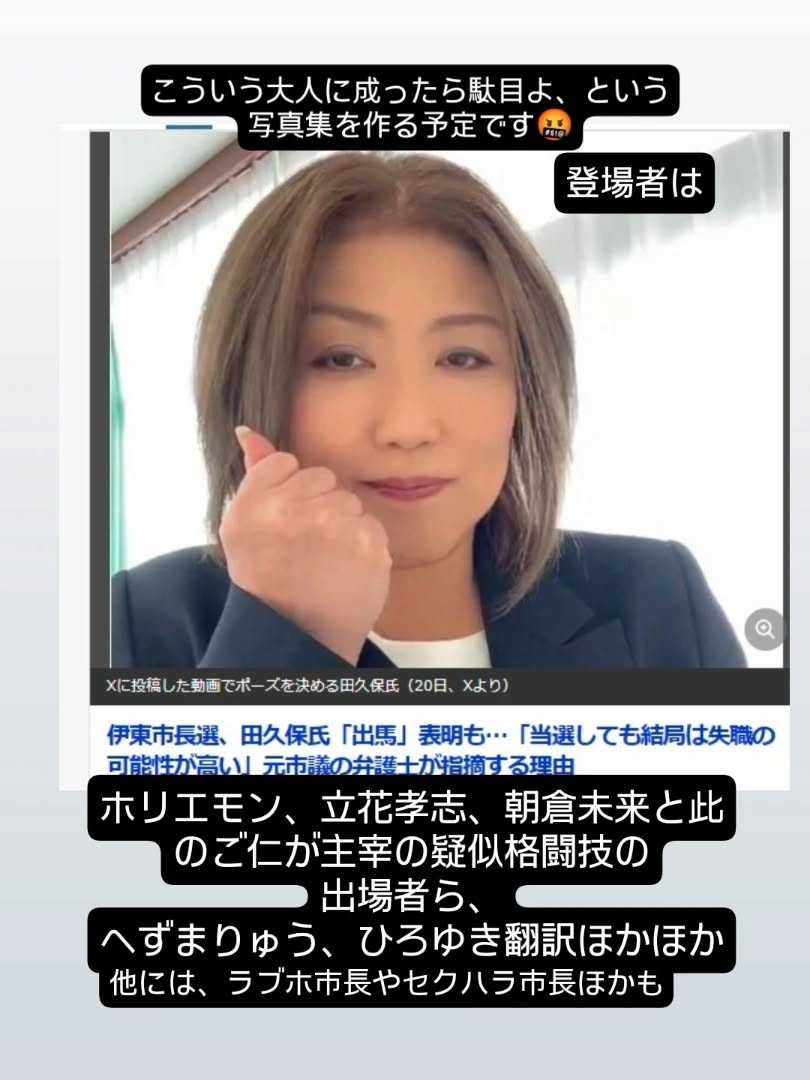
- 人生、生き方についてあれこれ
- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…
- (2025-11-23 19:32:35)
-







