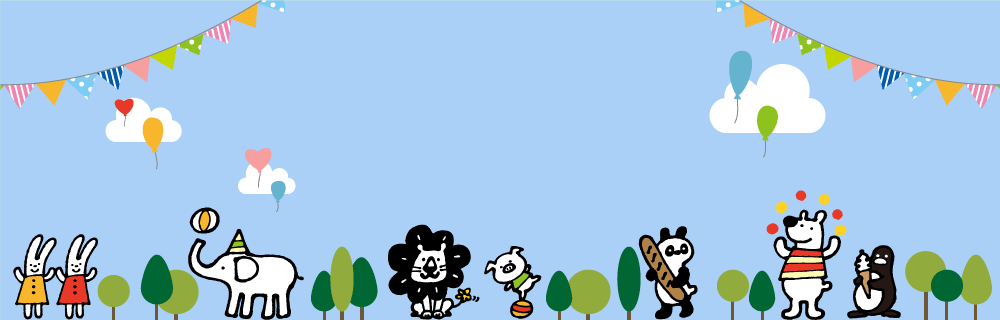2012年06月の記事
全56件 (56件中 1-50件目)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (16)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (16)それでは銀行同盟はどうでしょうか。こちらはユーロ共同債のように、各国の財政自主権を制約するような、各国政府の飲み難い条件をつける必要がありません。その分、実現に向けてのハードルは、ユーロ共同債に比べるとかなり低いのです。今回のEU並びにユーロ圏会合で、首相不参加のギリシアの問題は脇において、スペインとイタリアの危機対応に集中し、両国の金融機関救済に一定の道筋を提示しようとし、その道筋を提示できたのは、まさにこうした事情からです。この点を考えてみます。今回のユーロ圏首脳の合意事項は以下の通りです。1) 単一の金融監督メカニズムの新設を提案する。2) 1)の設置後、ESM(欧州安定メカニズム)による金融機関への直接資本注入を可能 とする3) EFSF(欧州金融安定基金)とESMの活用で、ユーロ圏の金融安定に必要な措置を とる。4) スペインへのEFSFとESMによる支援融資には、優先弁済権はつけない。この第4の点が特に好感され、先進国の金融市場は週末にかけ、やや落ち着きを取り戻していました。マスコミでは、南欧とフランスの連合軍に包囲されたドイツのメルケル首相が譲歩したとの報道が流れれいますが、市場の評価は、やや楽観的に過ぎるように思われます。第1に、ユーロ圏の金融機関を一元的に監督する金融監督機関の中味が、まだ何も詰まっていないことです。誰が何処の金融機関を監督し、検査するのか。その匙加減をそのように定めるのか。何も決まっていません。実はこの金融監督の問題は、日本の金融危機当時を思い返してみると、理解しやすいです。大蔵省銀行局の金融監督が槍玉に上がり、金融庁の独立が実現した当時のことです。大蔵の不良債権分類が緩すぎ、実態と遊離していると、厳しい批判がありました。ですから、正味の不良債権は、大蔵省の公式発表を大きく凌駕していたのです。スペインの金融機関の金融検査をスペイン財務省や中央銀行がやるのでは話になりません。国家の枠を離れた金融監督局を作り、他国出身の検査官が厳しく査定する体制を作らなければ意味がありません。それも、スペインの銀行はイタリアの検査官が査定し、イタリアの銀行はポルトガルの検査官が調べるのでは、これまた茶番です。 続く
2012.06.30
コメント(4)
-
『風と共に去りぬ』誕生 30日の日記
クロニクル 『風と共に去りぬ』誕生1936(昭和11)年6月30日76年前、1936年は2,26事件の年です。その年の今日、アメリカジョージア州アトランタで生まれ育った、マーガレット・ミッチェル女史の大河小説『風と共に去りぬ』が出版されました。1900年生まれのミッチェル女史は、母方の伯母を通じて南北戦争の目撃談を詳しく教えられ、そうした記憶を下に、長い時間をかけて、この作品を書いたと言われます。作品は大ベストセラーとなり、3年後の1939年に映画化されました。ヴィヴィアン・リー、クラーク・ゲーブル主演の映画は、3時間を大きく超える長編でしたが、大変な人気を博し、評判が評判を呼んで大ヒットとなりました。日本での初公開は戦後の1952年でした。私が映画館で見たのは、1960年代のリバイバル上映だったように思います。
2012.06.30
コメント(18)
-
ソウルで5階建百貨店崩落 29日の日記
クロニクル ソウルで5階建百貨店崩落 お詫びと訂正1995(平成7)年6月29日 タックンさんのご指摘で、ソウルの三豊百貨店は火災で焼失したのではなく、突然崩落して大惨事となったことを思い出しました。皆様に御迷惑をかけました。日本と韓国には時差がありません。事件はこの日の午後5時57分に起きました。5階建の建物が、突然一部を除いて、音を立てて崩落したのです。営業中で、しかも夕方5時過ぎですから勤め帰りの買い物客も多い時間でした。当然被害は膨らみました。その結果、死者508名、負傷者937名という大惨事になりました。17年前になりますが、日本でも午後7時代のニュースから、映像を交えた報道が、生々しい惨状を伝えてくれましたので、御記憶の方も多いと思います。 三豊百貨店の経営母体は、三豊建設産業です。同社は当初4階建のオフィスビルを建設する予定だったのですが、それを5階建てのデパートに計画変更したのです。この計画並びに設計の変更を、施行業者の宇成建設は、この設計変更は、建物の強度からして危険が大きいとして拒否しました。そのため三豊建設産業は、自ら直接施行する道を選びました。三豊建設産業は、ダパートにするのですから、各階の売り場に防火シャッターを設ける必要があります。そのためビル中央部の柱の25%を撤去したのです。外にも見た目を重視して、柱の太さを削るなど、ビル自体の構造には、最初から欠陥があった事が、その後の調査で明らかになりました。ほかにも様々な問題点が指摘されていますが、要するに強度不足の違反建築であり、しかもその違反は多岐に渡っていたのです。次に事故に至る経過です。前日28日に5階の従業員が天井のひび割れに気付き、当日の朝には、そのひび割れが拡大していたことから、上司に報告しています。報告を受けた経営陣は、午前9時から緊急会議を開いたのですが結論を得ず、午後3時にやってくる建築士の判断を仰ぐことになり、やってきた建築士は、閉店後の補修を提案し、そのままズルズルと営業を続けた結果、大惨事に至りました。崩落は違反建築の結果ですが、惨事を招いたのは、明らかに経営陣の判断ミスでした。三豊百貨店の経営幹部は、軒並み業務上過失致死傷容疑で立件され、当然のように全員が有罪判決を受けました。最高刑は当時の会長の懲役10年6ヶ月、全財産没収でした。この会長は2003年10月に、病気のため一時入院が認められ、そのまま病院で死去しています。そういえば、事故からかなり経って救出された女性のことを取り上げた番組もありましたね。
2012.06.29
コメント(4)
-
ソウルで百貨店火災 29日の日記
クロニクル ソウルで百貨店火災1995(平成7)年6月29日17年前になりました。この日韓国ソウルの三豊百貨店で火災が発生、全館がほぼ焼失する大火災となって、512人の来店客や店員が死亡する大惨事となりました。人混みでの火災は怖いですね。<追記> 皆さんにお詫びです。 この記事にある「三豊百貨店の火災」は、建物の崩落の間違いです。また「全館がほぼ焼失」は、全館の崩落の誤りです。タックンさんのご指摘で、間違いにに気付きました。タックンさんありがとうございました。一瞬のうちに5階建デパートの全館が倒壊した大事故でした。 後ほど、訂正版をアップします。
2012.06.29
コメント(14)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (15)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (15)ここでユーロ共同債の発行と銀行同盟の可能性を検討してみましょう。まずユーロ共同債です。響きは大変結構なのですが、実現には越えなければならないハードルがヤマのようにあります。国債とは国家が発行する借用証書です。当然、返済期日と利子率が明記されています。ですから、ユーロ共同債という名の借用証書は、ユーロ圏諸国が共同で発行する借用証書ということになります。17もの国家が共同で借用証書を発行するとなると、誰が責任をとるのか、発行額をいくらにし、どの国がいくら受け取るのか、その国別の必要額を誰がどう決定するのかなど、様々な問題が出てきます。発行主体はECB(欧州中央銀行)になるのでしょうが、ユーロ加盟国の財政一元化(単純に言えば、財布の1本化です)がなされない状態で、どうやって発行額や国別の分配額を決めるのでしょう。これは全く不可能です。ですから、各国の申請額を、ユーロ圏の首脳や蔵相、各国中央銀行の総裁などが集まった会議で、決めるしかないのです。すると問題があります。ユーロ圏で財政規律が緩く、国債発行が難しくなっている国は、共同債なら発行が可能で、金利も下がります。逆に財政不安がなく金利も低い国々は、自国だけで発行するよりも、高い金利(財政規律の緩い国と混ぜ合わされるからです)を祓わなければならなくなります。まして、規律の緩い国が、自国で使った分を必ず返せる保障はありませんから、その分の返済責任を押し付けられる可能性も、かなり高いのです。友人や仕事仲間に連帯保証人になってくれと頼まれ、つい引き受けたがために、多額の借金を負わされた友人や知人は、皆さんにもいらっしゃるのでは…。 ユーロ共同債というプランは、まさにこの可能性が高い案なのです。これをドイツやオランダなどが、引き受けると思いますか。こんなリスクの高すぎる計画を推進するというのなら、各国が完全に財政自主権を放棄し、ユーロ圏で一本の財政とすることを承知するのでない限り、引き受けられないとノンを発するのは当然です。そして財政自主権の放棄は、現時点で各国がウィと言う可能性は、まずありません。ユーロ共同債は、ギリシアやスペイン、イタリアなどが期待を寄せ、こうした南欧諸国の国債を保有する銀行などが、声高にその発行を主張し、その主張をIMFや米国のFRBなどが後押ししている構図になっています。つまり、自らの損失を少なくしたい諸勢力が、導入を呼びかけ、実際にその負担を押し付けられる側が拒否しているのです。これが現実です。この状態でユーロ共同債、実現する可能性はまずないと、私は考えています。 続く
2012.06.28
コメント(2)
-
ヒマワリ6号本格運用へ 28日の日記
クロニクル ヒマワリ6号本格運用へ2005(平成17)年6月28日7年前のことです。。気象観測衛星ヒマワリ6号が、この日から本格的に運用されるようになり、気象観測データが、刻々と送られてくるようになりました。確かに、この頃から、天気予報の精度が格段に向上してきたのは、日々の実感として、私も感じ取っていました。皆さんはいかがですか。
2012.06.28
コメント(12)
-
中国プロレタリア文化大革命を全面否定 27日の日記
クロニクル 中国プロレタリア文化大革命を全面否定1981(昭和56)年6月27日31年前のこの日、中国共産党は胡燿邦の主席昇格を発表すると共に、1966年8月からのプロレタリア文化大革命を全面的に否定する声明を発表しました。時に文革当時の毛沢東主席が1976(昭和51)年9月に死去して以来5年が経過していました。文革の10年が、中国の経済・文化・市民生活・教育そして政治に残した傷の回復に、どれだけの時間が必要だったかは、今後も検証を続けないと明らかにできないように思いますが、少なくとも、文革なかりせば、中国経済は、今よりも相当先を走っていただろうことだけは、確かなようですね。
2012.06.27
コメント(16)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (14)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (14)ギリシアの連立内閣がやっと始動しました。しかし反緊縮派の勢いは衰えていませんから、出発からして及び腰に見えます。まず呆れたのは、体調不良を理由に、ようやく決まった進首相が、ギリシア問題を協議の中心とするEU並びにユーロ圏会合を欠席したことです。EUやECBの支援なしでは、7月上旬にやってくる国債の償還(実質借換え)が出来ず、出来なければその時点でデフォルトとなる国の首相のとる態度ではありません。ここは担架に担がれてでも、会議中に倒れたとしても、一国の首相たるものは、その職席上出席すべきところです。おそらくEU各国の首脳もあきれ果てているでしょう。緊縮容認派にして、自国の危機を子の程度にしか認識していないのです。これがギリシアなのです。緊縮容認派は、欧州各国が反緊縮派が勝利しては大変と、選挙戦の最中に次々に自分達を援護してくれたことから、自分達が要求するEU等の科す支援条件を緩めてもらえるものと、勝手に思い込んでいるようです。しかしこれは不可能でしょう。EUやECBにとって、今やギリシアに続いてスペインやイタリアへの支援の必要が現実のものとしてのしかかってきています。現在はスペインに対する支援条件を相談中なのですが、もしここで、あれだけ長時間をかけてようやくまとめたギリシアへの支援条件を、国民が納得しないからと見直すことになったとしたらどうなりますか?スペインもイタリアも、「交渉条件は何度でも再交渉が可能なんだ。選挙をやって国民にノーと言ってもらって脅せば、EUもECBも簡単に再交渉に応じてくれるんだ。これはいくらでも金を引き出せるぞ、沢山借りてしまえば、借りた方が強いんだ」と考えるに違いありません。そうなることがミエミエの状態で、ギリシアの主張が通る可能性は、どのくらいあるでしょうか。皆さんはどうお考えになりますか。 続く
2012.06.26
コメント(4)
-
日本のビール事始 26日の日記
クロニクル 日本のビール事始1877(明治6月26日)「明治は遠くなりにけり」と言われて久しいですが、今年は大正元(1912)年生まれの方が100歳を迎えられます。というわけで、今日の話は135年前のことです。この日、北海道開拓使は、札幌で製造したビール1箱を明治天皇に献上しました。これが新聞でも報じられ、天皇ご自身が「これは美味しい」と語られたと言う話が、まことしやかに伝えられ、一般庶民の間にも、そもビールとは何ぞやと、大いに関心が高まったのです。頃や由、気を良くした開拓使は、ビールを北海道の産業として興すべく、秋には、大瓶1本を16銭で、一般にも売り出しました。そういえば、ラジオ時代のコマーシャルソングにありましたね。「ミュンヘン、サッポロ、ミルウォーキー、うまいビールの合言葉…」という、サッポロビールの宣伝が…
2012.06.26
コメント(18)
-
雪印集団食中毒事件発生 後日談
雪印集団食中毒事件発生 後日談食中毒の原因について、会社側は7月1日にようやく開いた記者会見で、「大阪工場の逆流防止弁の洗浄不足による汚染」によるものと発表しました。大阪保健所もそれ以上の追及はしませんでした。しかし、大阪府警は、逆流防止弁の洗浄不足のみが原因とは限らないと考え、その後も調査を継続しました。その結果、大阪府警は、大阪工場の製品の原料にあたる脱脂粉乳を製造していた、北海道大樹工場の汚染が原因であることを突き止めたのです。大樹工場では、同年3月31日に氷柱の落下によって3時間の停電が発生、病原性黄色ブドウ球菌が増殖して毒素が発生していたのです。電源回復後、大樹工場では生産再開を急ぐあまり、食品加工工場に必要な、ラインの衛生検査を行なわずに、生産を続けていたのです。これが真の原因でした。大阪保健所には、北海道の工場に検査に入る権限はありません。しかし大企業である雪印乳業には、大阪工場の製品による食中毒事件であっても、大阪工場の最終製品に関連する施設、さらには同社の全工場での、衛生状態を点検して安全を確認する程度のことは、企業の社会的責任と自覚し、実践する経営陣が居なかったのです。これが同社の不幸でした。大阪府警の活躍で原因が特定された結果、雪印グループ各社の全生産工場の操業は全面的に停止されました。雪印のブランドイメージは大きく傷つき、全国のスーパーや小売店から、油印の製品は一斉に撤去されました。 消費者の雪印への抗議は、それだけ強かったのです。経営者が対応を誤った結果でした。トップは素早くマスコミに登場し、不明を詫びると共に、全社一丸となって食の安全と再発防止に取り組む姿勢を見せるべきだったのです。それをせず、ひたすらマスコミを避けようとしたトップの姿勢も、厳しく糾弾されました。こうした雪印グループの姿勢が、2年後にはBSE問題に絡んでのグループ会社「雪印食品」の牛肉偽装事件として表面化する事態に繋がりました。こうして雪印グループは無惨に解体され、今日に至ることになります。トップに人を得ない企業が、ブランドだけで生き残れる時代は、既に終っているのですね。
2012.06.25
コメント(16)
-
雪印集団食中毒事件発生 25日の日記
クロニクル 雪印集団食中毒事件発生2000(平成12)年6月25日12年前のことですから、御記憶の方も多いと思います。この日雪印乳業(当時)の大阪工場で製造された「雪印低脂肪乳」を飲んだ子どもが、嘔吐や下痢などの食中毒症状を起こしました。これが近畿地方中心に、認定患者数14,780人を記録した、戦後最大の食中毒事件のプロローグでした。2日後の27日、大阪市内の病院から、市の保健所に食中毒の疑いが通報されました。調査の結果、市の保健所が大阪工場に製品の回収を指導したのは、30日になってのことでした。27日頃からは、兵庫県や和歌山県などからも、続々と食中毒発生の報が寄せられてきたのですが、雪印側の対応は遅く、マスコミ発表と自主回収の動きは、ようやく29日になってのことでした。マスコミの報道後、被害の申告は爆発的に増え、最終的には14,780人が被害に会うという、記録的な被害となりました。比較的症状が軽かったのが、不幸中の幸いだったのですが、雪印乳業の対応の遅さ、食品会社としての社会的使命の自覚という、企業モラルの欠如が、浮き彫りになった事件でした。この話には、後日談があります。その点は後ほど…
2012.06.25
コメント(12)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (13)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (13)ユーロの問題が複雑なのは、ドルに対抗しうる強い通貨をという、大陸欧州の政治的思惑が介在しているからです。その上、そこには大陸外にあって、しかし近代西欧のリーダーでもあったイギリスの影もちらついていることです。イギリスはアングロサクソンのよしみで、米英同盟に傾いたり、欧州の一員としてEUに加わって、かき回し役になったりしていますが、さて何処までポンドの意地を張り通すことが出来るのでしょうか。今やユーロ圏では、現在の危機を逆手にとって、各国の財政自主権を制限する財政統合へ向けてのプランが語られたり、各国別の銀行監督を一元化する銀行同盟の結成が話題となったり、ユーロ共同債の発行が望まれたりしています。現実は、どの国も総論賛成の各論反対状態ですから、まず短期的に実現する可能性は、ほとんどゼロの机上プランばかりです。実際の問題として、こうした長期的に取り組むべき課題ばかりが、大きな声で語られているのは、すぐにでも実現可能な妙手が見当たらないことを示しています。そのために、当面将来の課題を語ることで、お茶を濁していると考えると、ユーロが抱える当面の困難が透けて見えます。今週早々、いよいよスペインがEUとECBに対して、公式に支援を要請するということになったようです。支援の仕方も、工夫を凝らすようで、スペイン国際に対する信用不安は、一時的に和らぐ可能性が出てきたと受け止められ、週末には円に対してユーロは買われ、1ユーロは100円台に戻しています。しかし、日銀の白川総裁が、何度も発言している通り、こうした対応は、危機の先送り、一時の時間を買っただけの対応を繰り返しているだけで、本質的な解決には遠い状況にあります。 続く
2012.06.24
コメント(4)
-
趙紫陽総書記解任 24日の日記
クロニクル 趙紫陽総書記解任1989(平成元)年6月24日23年前のことです。開会中の中国共産党第13期4中全会は、この日第2次天安門事件の責任を問う形で、趙紫陽総書記を解任しました。総書記が、学生寄りの姿勢をとったことが、事件を加速度的に大きくし、反革命暴乱にまで至らしめたというのが、解任の理由でした。公認には、とう小平氏の推薦で、上海閥の江沢民氏が選ばれ、総書記に就任しました。追記 とう小平氏のとうの字は、機種依存文字にあたるそうで、このブログで使用しようとエラーになりますので、仮名のままとさせて戴きました。
2012.06.24
コメント(12)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (12)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (12)ユーロ圏で、経常収支(貿易収支並びに貿易外収支の合計とお考えください。貿易外収支とは、投資収益や出稼ぎ者の送金、観光収支などを含みます)の黒字を溜め込んでいるのは、御承知の通りドイツです。経済力に勝るドイツは、ユーロ圏加盟国が増えたことで、マルク高ならぬドイツユーロ高に悩まされることなく、南欧や東欧諸国への輸出を伸ばし、経済的には我が世の春を謳歌してきました。ですから、ギリシアやスペイン、ポルトガルなどは、ドイツは我々を踏み台にして儲けてきたのだから、文句ばかりつけずにもっと助けてくれても良いではないかと主張しています。しかし、この認識は、正しくありかつ間違いでもあります。確かにドイツ経済は好調ですが、それは2002年~2007年にかけての日本経済の史上最長の景気拡大局面と同じなのです。企業収益は好調で、史上最高益を更新した企業も相次ぎました。しかし、労働分配率はほとんど増えず、むしろマイナスになった企業も多かったのです。利益は企業の懐に留まり、給料は上がりませんでした。正社員は減り、パートや派遣社員が増えたことで、労働賃金の総額は減少を続けていました。実はドイツも同じなのです。ドイツの労働賃金は、決して高くありません。フランスよりも低く、ギリシアの公務員と比べて高くありません。労働時間の長短を加味して、1時間当りの賃金に直すと、ギリシアの方が高賃金なのです。ですから、ドイツの市井の人々が、「あんなギリシア人を、あんなスペイン人を、そしてあんなイタリア野郎を、我々が必死に働いて支払った税金で助けてやるなんて、とんでもない。絶対に反対だ!」と主張するのは、尤もなのです。ドイツ世論の80%が、国費によるギリシア支援に反対したのは、こういうわけなのです。その結果メルケル与党は、各地で行われた地方選挙で連戦連敗を喫し、遂に議会は、欧州救済にこれ以上の資金を出す場合は、議会の承認を必要とすると、政府の反対を無視して、圧倒的多数で決議してしまったのです。広くなったユーロ圏の維持は、大資本や財産家には大きなメリットがあるけれども、庶民には関わりがない。もしろ以前に比べて生活は苦しくなっている。その現実に繋がっている。こういう思いが、各国での選挙のたびに、政権政党が敗北を続ける原因になっているように見えます。メルケル首相が、議会や国民を説得できる可能性は、次第にせばまってきているのが現実です。 続く
2012.06.23
コメント(4)
-
国際オリンピック委員会誕生 23日の日記
クロニクル 国際オリンピック委員会誕生1894(明治27)年6月23日118年前になります。この日パリのソルボンヌで、国際オリンピック委員会の設立が決議されました。決議を主導したのは、皆さん御存知のピエール・ド・クーベルタン男爵です。男爵は、「オリンピックを通じて、世界平和を実現しよう」と、熱弁をふるい、その第1回大会を2年後の1996年に、ギリシアの首都アテネで開くことも。合わせ提案しました。男爵の熱弁は、拍手をもって迎えられ、この日の国際オリンピック委員会(IOC)の設立に繋がりました。なおIOCの本部はスイスのローザンヌにおかれ、現在は205ヶ国が加盟しています。
2012.06.23
コメント(14)
-
有権者1億人突破 22日の日記
クロニクル 有権者1億人突破2000(平成12)年6月22日12年前のことです。この日、第42回衆院選が行なわれました。与党は後退しましたが、多数を確保し、他方で民主党も議席数を伸ばしました。しかし、この選挙で特筆すべきことは、選挙人名簿の確定の結果、名簿に登載された20歳以上の有権者数が、初めて1億人を超えたという事実です。総人口は1億2千万人台でしたから、いかに少子化が進んでいたかが分かりますね。
2012.06.22
コメント(14)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (11)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (11)ギリシアがユーロを離れ、新ドラクマ通貨を導入するとどうなるでしょう。ユーロである限り不可能だった、自国通貨の切り下げが実現します。となると、ギリシアの製品は輸出競争力を回復します。農業生産物では、世界3位のオリーブ、8位の綿花、10位の葉タバコなどの輸出に弾みがつきます。主要な輸出品目だった繊維、果実、オリーブ油、アルミなどの輸出も上向きます。そしてなんと言っても、ギリシアの大事な外貨獲得源である観光産業が大きく上向くことが期待できます。 日本人でも古代ギリシアへの憧れから、ギリシア観光に出かける方は多いのですが、何と言っても欧米人のギリシア観光に弾みがつきます。考えてみてください。リーマンショック後のアメリカ経済は、底は脱したとはいえ、まだまだ思うような回復に至っていません。中産階級の家計は住宅価格が回復しないことから、火の車の状態が続いています。欧州はユーロ不況の最中にあります。当然、安上がりの旅行が出来ないとなると、旅程を切り詰めたり、近場にしたり、旅行そのものを取りやめたりすることになります。それが、ギリシアの通貨が切り下げられたとなれば、ユーロの価値が上がることになるのですから、ギリシア旅行は大変安上がりな旅行になるのです。しかも欧州からは比較的近いのです。当然観光客は大きく伸びるでしょう。客が増えれば、仕事も増えます。緊縮一辺倒、雇用も縮小と明るい話題のなかったギリシアに、かすかな灯りが点ることになります。勿論、そこに至るまでには、通貨の切り下げによる物価高、外国との取引の縮小による打撃など、最初は辛いことが目立つでしょう。しかし、それは、ユーロに留まっている限り、描き得なかった先の展望を持ちうる辛さなのです。真っ暗闇の先が全く見えない中で、ただ我慢しろと強いられるよりも、一時は今より厳しくなるけれど、その坂にかすかな光が見える辛さの方が、人には耐える力が湧くものだと、私は考えます。繰り返しますが、デフォルトに瀕した国で、通貨の大幅切り下げなしに、建て直しに成功した国は、私の知る限り今までないように思います。 続く
2012.06.21
コメント(4)
-
ILOとユネスコに加盟 21日の日記
クロニクル ILOとユネスコに加盟1951(昭和26)年6月21日61年前のことです。この日、いずれも国際連合の機関であるユネスコ(国連教育科学文化機関United Nations Educational Scientific and Culural Organization 本部パリ)と、ILO(国際労働機構 International Labor Organzation本部 ジュネーヴ)は、相次いで日本の加盟を承認しました。 ここに戦後の日本は、最初の国際社会復帰を果したのです。しかし、当時の首相吉田茂が、自ら主席全権を務めたサンフランシスコ講和条約の調印式は、5ヶ月近く後のこの年11月であり、講和条約の発効は翌年4月28日でしたから、この時の日本は、なおGHQによる占領下にあり、非独立国が加盟を認められた点で、疑問の余地が残る決定でしたが、国内では大いに喜ばれました。当時小学生だった私達にも、ユネスコ(UNESKO)の名は、国際赤十字の名と共に、大切な国際機関として印象づけられたものです。 ところで、日本の国連加盟はソ連との国交回復後の1956(昭和31)年まで待たされることになりました。国連本体は、なかなか日本の参加を認めなかったのですが、補助機関はいともあっさりと、日本の加盟を承認したわけですから、まさに国連内での諸機関の独立振りが眼に浮かびますね。
2012.06.21
コメント(16)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (10)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (10)オイルショオク以降の世界経済で、破綻の危機に立ち至った国は、IMFや世銀の支援を受ける条件として、何処も超緊縮財政の導入(日本流に表現すれば、「欲しがりませんか勝つまでは」でしょうか)を迫られ、ひたすら我慢を強いられることになりました。メキシコ、アルゼンチン、インドネシア、タイ、マレーシア、韓国と枚挙に暇がありません。貸付の条件として、国家予算の作成にまで、IMFの監視がついたのです。まさに箸の上げ下ろしにまで口を出す姑さながらといえましょう。ロシア相手には、さすがにそこまでできなかったようですが…その結果は、インドネシアでは革命が起き、スハルト体制が吹っ飛びなど、IMFのやり口に厳しい批判が起き、放漫財政が危機の原因担っているわけではない国に、緊縮財政を強要するのは間違いであるという認識が広がりました。そうはいっても、ギリシアの場合は、財政赤字を隠してユーロに加盟し、財政の大盤振る舞いを続けたのですから、放漫財政は明らかです。緊縮を迫られるのは、まさに自業自得といえます。しかし、これは政府の責任です。現実に痛い目にあっているのは国民です。問題は、今後3年とか5年といった限られた機関、我慢の日々を耐え抜けば、立ち直ることが出来るか否かです。その点で、デフォルトから立ち直った国々は、どのような手を打ったのかを眺めると、いくつかの共通点が浮かびます。それは主要国通貨や貿易相手国の通貨に対し、自国通貨を思い切って切り下げていることです。当然輸入品の物価は高騰しますから、激しいインフレに悩まされます。ですから、一時は厳しい目にあいます。しかし、思い切った切り下げによって、自国商品は競争力を回復します。高価になった輸入品の輸入は減ります。こうして貿易収支は均衡し、通貨切り下げで、借金は自国通貨建てに直すと増えますけれども、デフォルトでかなりの部分を踏み倒していますから、これで何とかなるのです。ギリシアの場合、既に管理されたデフォルトが行なわれ、実質80%強の踏み倒しに成功しているのです。ですが、ギリシアの場合、ユーロにとどまり続ける限り通貨の切り下げは出来ません。南米諸国などが用いた通貨の大幅切り下げ策は使えないのです。こうなると緊縮策だけで財政を立て直すことが出来るのでしょうか。これは無理というものです。ですから、このままではギリシア政府と国民は、超長期に渡って緊縮策を続けるしかないことになります。ですから私は、ギリシア国民の立場に立てば、早期のユーロ離脱を選ぶほうが、ベストではないですが、ベターな選択だと考えるのです。
2012.06.20
コメント(4)
-
米ソホットライン協定締結 20日の日記
クロニクル 米ソホットライン協定締結1963(昭和38)年6月20日49年前のことです。この日、米ソ両国は、クレムリンとホワイトハウスを結ぶ、直通電話(ホット・ライン)回線を設置することで合意、協定書を作成して、ただちに発表しました。 前年10月のキューバ危機に際して、あわや3回目の世界戦争勃発かと、大いに心胆を冷やしたのですが、米ソ両首脳は、相互の話し合いを密にする必要を感じ,直通電話の設置を共に了承したのです。 ここに、東西両陣営の緊張緩和策が日の目を見ることになり、キューバ危機の教訓が、大きく生かされたと言えましょうか。誰もがホットした瞬間でした。
2012.06.20
コメント(14)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (9)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (9)ギリシアの再選挙、EU恭順派が勝ちましたね。保守中道派とも中道右派とも言われる新民主主義党(SD)が30%弱の得票で第1党になり、連立相手の全ギリシア社会主義運動(PASOK)と合わせ、300議席中の161議席を確保、下院議席の過半数を確保しました。反緊縮派は、得票数では50%以上を獲得しましたが、議席や得票率を伸ばしたのは、ツィプラス党首の急進左派連合(SYRIZA)のみで、共産党などが大きく得票を落とし、全体で139議席に留まりました。EU恭順派の勝利は、第1党に与えられる50議席のボーナス議席のおかげではありますが、前回選挙では、このボーナス議席を加えても149議席だったのですから、当面ギリシア国民が、ユーロ残留の道を選んだことは間違いありません。EUやユーロ圏のみならず、米・日などの資本主義経済大国が、ユーロを離脱すると大変なことになると、マスコミまで動員して、ギリシア国民に猛烈な圧力をかけていたことは、皆さんも御存知でしょう。その猛烈な圧力が功を奏した形になったのですね。SYRIZA第1党の確率60%と見た私の読みは、残念ながら外れました。これでギリシア問題は、またまた先送りになりました。90年代から2000年代前半にかけての日本の経験でお分かりの通り、先送りは国家負担を膨らませ、多額の税金の無駄遣いになち、そして国民に多大な犠牲をもたらすだけなのですが… 続く
2012.06.19
コメント(4)
-
牛肉・オレンジで合意 19日の日記
クロニクル 牛肉・オレンジで合意1988(昭和63)年6月19日まだ24年しか経っていなかったのですね。24年前の今日、日米の貿易摩擦の焦点になっていた牛肉・オレンジの自由化問題が、遂に決着しました。当時の佐藤隆農林水産大臣とアメリカ合衆国のヤイター通商代表部代表との閣僚交渉で、日本側が折れ、3年後の完全自由化で合意したのです。牛肉については、その後BSE問題の発生で、1度輸入が禁止されました。その後、生後2年以内の若い牛に限って(2年以内にBSEを発症する可能性は、低いからとされています)、危険部位を除いた輸入を認めるとの合意が交わされ、現在はそのように運用されています。
2012.06.19
コメント(16)
-
豊田商事会長刺殺 18日の日記
クロニクル 豊田商事会長刺殺1985(昭和60)年6月18日金のペーパー商法を利用した豊田商事の詐欺事件を、ご記憶の方も多いと思います。会社が契約者に金を売るのですが、実物の金を持っても仕方がないでしょうと、その金を会社が預かることにして、預り証即ち証券を渡すのです。実際の金を会社が保管していれば、それは詐欺ではありません。しかし、その金を保管していなかったとすると、これは立派な詐欺になります。この詐欺がばれて、約3万人の被害者と2千億円と言う被害金額、詐欺にあった人たちの大半が1人暮らしの老人であったことなどから、大きな社会問題となりました。その豊田商事の会長永野一男が、この日夜10時過ぎにTV中継中のカメラの前で、彼の住まいのマンションにガラスを割って侵入した男に刺殺されました。その1部始終がTYでナマ中継されたのです。警察が捜査中の事件の容疑者が、各局のTVクルーがカメラを構え、レポーターがしゃべっているその前で、刺し殺されたのです。2人の争う声も収録され、そのままTVに流れました。カメラもマイクを持ったレポーターも、誰一人機材を置いて止めに入ることをしなかったのです。これはマスコミの姿勢として、当時大きな問題となりました。また責任者の死亡で、集めた資産をどこにどう隠したのか、或いは使ってしまったのか。社員にいくら渡したのかといったことが、わからなくなってしまったため、被害者に返却できる金額が、非常に少なくなってしまうという、残念な結果にも繋がりました。マスコミの姿勢が問われた事件でした。
2012.06.18
コメント(14)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (8)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (8)スペインの金融危機が話題になっている最中に、バルセロナを州都とするカタルーニャ州が、州債の返還が出来ないと、中央政府に支援を求めたというニュースが小さく報じられました。スペインは、国土面積にして、日本の1,4倍強の面積を持ち、スペイン本土は15の州50の県に分かれています。カタルーニャ州は、東京・神奈川・千葉・埼玉の首都圏の4都県と同じくらいの規模でしょうか。本土の15の州のなかでは、財政はもっとも健全だとされていた州なのです。その州が白旗をあげたのです。これは結構大きな意味をもって居ます。日本では地方債。東京都債、神奈川県債、横浜市債などは、国債に次ぐ安全債権として流通しています。それがありますから、日本でも、ユーロで発行されたスペインの州債を証券会社が勧め、地方の信用金庫や農協などが、かなり所持しているのです。日本ですらそうなのですから、元々スペインとの関係の深い、フランス、イギリス、オランダから、アメリカの金融機関までもが、相当量の州債を抱えていることが知られています。金融機関の支援でアップアップのスペイン政府、州の救済にまで手がまわるのかどうかが、危ぶまれています。EUとECBによるスペイン救済、急ぐ必要があるのですがm、さて… 続く
2012.06.17
コメント(4)
-
中国水爆実験に成功 17日の日記
クロニクル 中国水爆実験に成功1967(昭和42)年6月17日45年前のこの日、中国政府は水爆実験を実施、成功した旨を発表しました。前年8月に始まった文化大革命が、益々激しく続けられている最中の出来事でした。こうして中国は米ソに続く核大国への道を、フランスと共に走り出しました。
2012.06.17
コメント(10)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (7)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (7)スペインの財政危機の根底には、土地バブルの崩壊があります。ユーロの発足当時のスペインは、物価の安い国として人気がありました。土地や住宅の価格も安く、気候の良いスペイン南部に住宅を買い、かの地で優雅に老後を送ろうとした日本人も、時を追って増えていたと聞きます。私にも商社勤務で、スペイン南部のマラガに長く駐在した友人がいます。彼もまたマラガで老後を過ごす計画を立てていました。しかし、ユーロの導入後、欧米人中心にスペインにリゾート用の住宅を構える人が増え、あれよあれよという間に住宅価格は高騰、激しい土地バブルが発生しました。釣られて激しい物価上昇も起きました。その結果、一時的には、スペイン政府や地方自治体の税収は増え、有頂天になった政府や自治体の財政規律は緩み、それがさらにバブルを煽ったのです。こうした事情から、スペイン経済の変調は、リーマンショック以前から始まっていたのです。日本の年金を下にスペインで老後を送る計画を立てた友人は、物価高騰とユーロ高から、日本で得られる年金では、スペインでの生活を維持できなくなり、2007年の初めに、現地の住宅を処分して日本に戻りました。こうした人が増えて結果、税収は減少に向かったのです。土地価格も緩やかな低下に向かいました。そこに起きたのがリーマンショックです。スペインに流入していたマネーの逃げ足は、こうなると速いです。土地バブルは崩壊し、大量のマネーがスペインから流出します。金融機関からの多額の資金を借入れ、土地を購入した企業や個人(日本では彼らをバブル紳士と呼びました)は、入手した土地の急落によって、多額の負債を抱えて行き詰まります。書い手のつかない土地は、値下がりを続けます。担保権を行使して、担保の土地を回収し、売りに出しても売却価格は、貸付金をはるかに下回ってしまいます。大量の不良債権を抱えた金融機関は、行き詰まるしかなかったのです。不良債権の穴を埋め、経営の健全性を保つために、金融機関は貸し出しを圧縮し、手持ち現金を厚くする必要に迫られます。当然企業の資金繰りは苦しくなります。こうしてスペイン経済は、深刻な不況に陥ることになります。税収は大きくダウンします。固定資産税も、所得税も法人税も、そして消費税も…。こうして財政赤字は拡大を続けました。とりわけ国家に比べれ経済規模の小さい州政府の受けた打撃は、極めて大きかったのです。危機は金融機関に留まるものではないのです。 ザビ
2012.06.16
コメント(2)
-
工場の就業時間制限撤廃 16日の日記
クロニクル 工場の就業時間制限撤廃1943(昭和18)年6月16日もう69年前のことになります。アジア・太平洋戦争中の出来事です。この日、政府は、女性や子どもに対する工場労働の保護制限規定を撤廃しました。激化し、悪化する一方の戦局に対応して、青年男性を兵士として戦場に送り出した結果、労働人口の減少に悩む政府は、19世紀に始まる子どもや女性に対する労働制限法、すなわち子供や子を産む存在である母性の保護を目指した就業時間の制限を廃止し、同時に女性や子どもに対する作業規定を見直し、従来は禁じていた作業に従事することを認めました。このことにによって、女性や子どもが、鉱山での坑内作業への参加が解禁されましたが、これは明らかに、労働者保護という世界的な労働行政の流れからの、明白な後退を意味していました。
2012.06.16
コメント(18)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (6)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (6)EUとECBが1千億ユーロ(=約10兆円)の支援を決定したスペインの危機が深刻化しています。ギリシアのように、徹底した財政緊縮策を提示しない限り支援をしないという脅しをかけることもなく、無条件の貸付です。それにも関わらずスペイン国債の金利は上昇し続け、価格は下落を続けました。1千億ユーロの支援がスペイン政府への貸付であり、スペインの金融機関に対する直接の貸し出しでないことを問題視したのです。しかし、EUやECBにしてみれば、スペイン政府への貸付とすることは、当然のことでした。ECBの資本が棄損し、ECBの信用が劣化するとなると、スペイン国家の危機どころではない、より深刻な事態に立ち入るからです。スペインの金融機関に、直接貸し出すとすれば、その金融機関が長銀や日債銀のように倒産した場合、貸付金の回収が難しくなるからです。これに対し、スペイン政府を経由しての貸付(スペイン政府が借り受け、借り受けた資金を国内金融機関に転貸しするのです)の場合、借主はスペイン政府ですから、EUとECBは、他の債権者に先立って、貸付金の返還を受けることが出来るのです。 EUやECBに先行する権利があるのは、IMF(国際通貨基金)だけなのです。そして、EUとECBによる1千億ユーロが、万一の際には先に回収されてしまうのですから、民間の投資家は、手持ちのスペイン国債の払い戻し率が、大きく減額されてしまうのです。ECBなどが回収した残りを、分配することになるからです。その結果、スペイン国債は満額が返還される確率が下がり、一部は返還されなくなるかもしれない。こういう発想が、スペイン国債の所有者の間に広まったのです。スペイン政府は、自力でスペインの金融機関に投入する公的資金を用意できない。だからこそ、EUとECBに支援を要請したのです。その結果、スペイン財政の借入金依存率は大幅に高まりました。スペイン政府の信用不安が広まったのは、こういう経過によるのです。実は、スペインの財政と信用不安には、もう一つ別の爆弾が隠されています。明日は、その点を記します。 ザビ
2012.06.15
コメント(2)
-
樺美智子さん死す 15日の日記
クロニクル 樺美智子さん死す1960(昭和35)年6月15日52年前のことです。この年5月19日に前代未聞の強行採決によって衆院を通過した。改訂安保条約の批准を巡る問題は、衆議院に警官隊を導入して、その警官隊の力で野党議員(社会・共産両党の議員、当時は民社党も公明党も存在しませんでしたし、共産党も3議席程度の小党でしたから、ほとんど社会党議員を排除するためでした)が、議場に入場するのを阻止して採決したことがテレビや新聞で報じられると、国民各層の強い反発を招きました。その結果、「新安保条約反対、衆院に差し戻して再審議せよ」と要求する声は日増しに高まり、日々デモ隊は国会を取り囲むようになりました。強行採決の主として国民に評判の悪い岸首相は、ハガチー事件以後は、国会から外へ出ることも出来ず、国会内に篭城せざるをえない状況に追い込まれていました。 しかし、一般の法は、参院の審議期間は2ヶ月が保証されているのですが、予算と条約の批准については、1ヶ月しか認められていないのです。そのため、何事もなく6月19日になってしまえば、その日の24時を回れば、新安保条約は自然承認されたことになってしまうのです。 この遺された時間を意識するがゆえに、安保反対闘争は、大きな山場を迎えていました。そうして巡ってきたのが、6月15日でした。この日安保改訂阻止国民会議は、全国で第二次実力行使に訴えたのです。労働者はストを打ち、学生は授業をボイコットして、デモの隊列に加わりました。全国で580万人が参加した空前絶後の規模でしたが、若い学生たちは、ただのデモで安保改訂阻止は勝ち取れないとばかりに、実力行動に訴えたのです。こうして全学連主流派による国会突入が計画されたのです。ここに突入を図る学生と警官隊が衝突し、デモに参加していた東大生樺美智子さんが、命を落したのでした。樺さんの遺体は家族の希望で解剖にふされ、警官隊によって首を締められ、倒れたところを、踏みつけられて死亡に至った事実が解明されます。眼のひどい欝血が首を締められたことを示し、ひどい膵臓出血が上から強く踏みつけられたことを証明したのです。 ラジオ関東の実況放送が「警官隊によって、今首を掴まれております。…いま実況放送中でありますが、今警官隊が,私の頭を殴りました…」とナマナマしい事実を報じたこともあって、樺さんの死は、さらに安保反対の声を高めたのでした。翌日16日から、連日続いた学生の抗議行動には、各大学とも空前の参加者が集まり、それまで、8000人程度だった学生デモの参加者は、一挙に5万人を超えるに至りました。 樺さんの死は午後7時過ぎだったのでしょうか、当時高校3年だった私は、丁度修学旅行先の別府の宿で、夜間の外出から戻ったところで、ロビーのテレビでこのニュースを知ったのでした。さすがに皆興奮して、深夜まであれこれと、日頃はまずしなかった政治談義を交わしたことを覚えています。
2012.06.15
コメント(20)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (5)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (5)そこで、ギリシアの選挙がどうなるかです。欧州各国のマスコミは、「SYRIZA(急進左派連合)が勝利した場合、SYRIZAのあまりに手前勝手な主張を認めず、ギリシア支援を打ち切るだろう。そうなれば、ギリシアは立ち往生し、デフォルトを宣言してユーロから離脱せざるをえなくなる。新しいギリシア通貨『新ドラクマ』はユーロに対して、大幅に切り下げるしかないので、輸入品の価格は高騰し、ギリシアは悪性インフレに悩まされることになり、国民は塗炭の苦しみに会うことになる」と、競って書いています。ギリシア国民を脅して、ユーロ圏諸国やECBとの協調路線をとるSDとPASOK中心の連立派が勝利するよう、盛んに側面支援しています。連立維持派も、ユーロを離脱したら大変だと、3月の合意を維持することへの支持を訴えています。 この「ユーロを離脱させられたら大変だ」というプロパガンダは、一定の成功を納め、マスコミ報道では、両派の支持は会い拮抗するところまで、穏健派が勢力を盛り返したとなっています。そこへ、飛び出したのが、9日土曜日の、EUとECBがスペインの金融機関へ1千億ユーロ(約10兆円)の資本支援を行なうと、発表したのです。詳細は今後に委ねられていますが、年々もスッタモンダしたギリシア支援に比べると、何とも素早く、しかも緊縮財政の履行の約束などの難しい条件もつけられていません。素早い支援決定は、危機の連鎖を押さえ込むためには、ありがたい措置で、大いに歓迎されるべきことなのですが、あまりにタイミングが悪すぎました。8日後が、ギリシアのやり直し総選挙の日だからです。スペインは、緊縮の約束もせず、10兆円もの支援を受けた。然るに我々はどうだ。スペインに許されて、我々はダメだとは何事だ。SYRIZAの主張は尤もだ。ここはスペイン並みの待遇を要求して、SYRIZAに再交渉してもらおう。ギリシア国民がこう考えたとしても何の不思議もありません。そうです。スペインに対するEUとECBの支援決定は、皮肉なことに、彼らが警戒するSYRIZAにとっての追い風となり、SDとPASOKに対する逆風となったことは否めないのです。 続く
2012.06.14
コメント(4)
-
ドイツ軍パリ占領 14日の日記
クロニクル ドイツ軍パリ占領1940(昭和15)年6月14日72年前のこの日、ドイツ軍はパリに無血入場を果たし、フランスの首都パリを占領しました。ヒトラー体制下のドイツは、前年1939年の9月1日に、全軍をあげてポーランドに侵攻、ここにイギリスとフランスも対独開戦を決意、9月3日に宣戦を布告、第二次世界大戦が始まりました。英・仏はすぐにもドイツとの戦端が開かれるものと、勢い込んでいましたが、ヒトラーは巧みなジラし戦法に出て、ポーランドから、北欧・中欧・南欧の攻略を優先し、翌40年春までは、いっこうに西部戦線のドイツ軍を動かそうとせず、巧みに英仏連合軍の気勢を削ぐ作戦を取りました。宣戦布告後、すぐにも独軍との戦闘が始まると受け止めていた英仏軍は、次第にこの戦争を「奇妙な戦争」と呼び、無意識の内に士気は緩んでいたのです。このため、5月に入って、突如ベネルックス3国に侵攻したドイツ軍が、進撃の速度を緩めずに、対仏国境を越えると、士気の緩んだ英仏連合軍は、そのスピードについて行けず、30万人の大部隊は敗走を重ねて、遂にダンケルクに包囲されたのです。ここで、到着した英海軍船に、辛うじて救出されたのです。緒戦は見事な敗北に終ったのです。勢いに乗ったドイツ軍は、ベルギー国境からフランスに進出。この日、無血でのパリ占領となったのです。それにしても、英仏連合軍、なぜ攻めてこないドイツ軍に付き合って、自ら仕掛けなかったのでしょうね。 敵が攻めてこなければ、何か攻められない事情があるに違いないと、自ら仕掛けるのが普通です。攻めていれば、指揮が緩むこともなかったでしょう。英仏連合軍の緒戦の敗退は、将軍達の無能に寄る所が大きかったように思います。 フランス軍で、積極攻撃を主張したのは、まだ若かったドゴール大佐(開戦時の肩書き)ただ1人でした。
2012.06.14
コメント(16)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (4)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (4)どの国でも同じですが、各国中央銀行の最重要の使命は、通貨価値を守ることです。ですから、自らの資産を劣化させることは、なんとしても避けなければなりません。ですから、3月にようやくまとまったギリシア支援策では、民間企業や個人の債権放棄は、実質で70~80%という大きなものになりましたが、その際もECBが支援の一環として保有したギリシア国債は、その全額が残存期間の短い、従って債権放棄の対象にならない国債に、引き換えられていました。つまり、ECBは1銭も身銭を切らなかったのです。そして、その事実にクレームをつける民間金融機関もひとつもありませんでした。ECBに睨まれたら困る欧州の金融機関のみならず、米国の金融機関も何も言っていませんから、中央銀行は別格にしておく必要があると、誰もが理解しているのですね。しかし、今回はどうでしょう。本日13日付けのロイターの報道によれば、昨日12日のギリシアにおける預金の引き出し額は、6月に入っての最高額を更新したそうです。ECBはその全てに対応しています。ギリシア政府がデフォルトを宣言し、借金は返せないとなった場合、ECBが提供した繋ぎ資金もまた、一部を除くと返済されない資金となってしまいます。ですから私は、17日の再選挙で、ツィプラス党首のSYRIZA(急進左派連合)が勝利した場合、ECBはギリシアの金融機関への支払い資金の提供を打ち切る可能性があるように考えています。その時点で、ギリシアの金融機関は、北海道拓殖銀行や山一證券と同じように頓死です。ギリシア政府も、身動きが取れなくなりますからデフォルトを宣言するしかありません。この可能性が否定できないゆえに、昨今の世界の金融市場の空気が、重く澱んだものになっているのですね。 続く
2012.06.13
コメント(4)
-
金融ビッグバン最終答申出る 13日の日記
クロニクル 金融ビッグバン最終答申出る1997(平成9)年6月13日15年前のことです。この日、証券取引審議会・金融制度調査会・保険審議会は、金融制度の抜本的改革、「日本版金融ビッグバン」を最終答申しました。 「日本版金融ビッグバン」の口火を切ったのは、当時の橋本首相の諮問機関だった経済審議会の行動計画委員会ワーキンググループでした。同グループは「2000年3月までに、金融の規制を撤廃し、利用者本意の金融システム」を作ることを提言したのです。 幅広い競争を実現する、資産取引を自由化する、規制・監督体制を見直すの3点の目標も示されました。橋本首相は、この提言を受け、銀行・証券・保険の相互参入の促進や、株式売買手数料の自由化など、金融分野全般にわたる規制緩和策を、2001年までに実施するよう指示しました。この日の答申は、この首相指示を受けてのものでした。しかし、この指示と答申には、次ぎのような限界がありました。第1に、不良債権処理の仕組みが明示されていないこと、第2に、肥大化する公的金融や財政投融資は蚊帳の外におかれていたこと、第3に、税制の問題が棚上げされていること、です。 果せるかな、多額の不良債権を抱えた金融機関の破綻が相次ぎ、日本版ビッグバンは、多難な船出を迎え、最終的に実現する時期は少し遅れますが、現在では、政府系金融の整理も一応進行し、財政投融資も整理されつつあります。 なお、NYやロンドンの市場には見劣りがしますが、答申から,ちょうど15年の節目で見ると、変化はゆっくりとしか進まない日本にしては、まずまずのペースで進んでいるように思えます。郵政民営化の後退は、甚だ残念ですが…バブルの崩壊と、どうしようもない財政の窮状が政治家や官僚、そして金融関係者の背中を押し続けた成果なのでしょうね。
2012.06.13
コメント(10)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (3)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (3)ギリシアの議会選で連立与党が過半数を取れずに敗北したことを契機に、欧州危機が再燃しました。すったもんだの挙句に、ギリシアに対する民間の債権放棄がようやく決着し、ユーロ圏並びにEU、さらにはFRBまで加わった支援がようやく決着し、小康状態に入って間もなくのことでした。欧米中心の民間の金融機関の債権放棄は、金利の減免を含めると、優に80%を越えましたから、実質的には破綻処理に近い棒引きだったのです。それにもかかわらず、総選挙の結果を受けての新たな連立の枠組みが整わず、再選挙で「借金踏み倒し」を主張する極左政党が勝利する可能性が出てくると、またまたユーロ不安が顕在化したのです。ギリシア危機が最初に顕在化したのは2009年ですから、それから3年近くが経過しています。その間に世界の富裕層や欧米の大手金融機関は、いずれも危険な債権と化したギリシア国債やギリシアへの融資は、引き上げてしまっています。何度も危ない危ないと言われながらも、何とか凌いできたのは、こうした大資本が安全に危険な債権を処理するための時間が、必要だったからでもありました。ですから、ことここにいたって、やっぱり破産だと開き直られても、もはや「そうですか。勝手にどうぞ」で済むはずなのです。それなのになぜ。顕在化しているユーロの最も弱い環がギリシアです。ギリシアがユーロから離れるとすると、次の弱い環が狙われ、次々と連鎖反応が広がります。事実スペインやイタリアという、経済規模でギリシアとは比較にならない国々の国債が狙われ、金利の上昇(価格の下落)が起きました。欧州金融不安の再燃です。ギリシアでは、日々金融機関から預金が流出しています。資産家達は、とっくに国外に資産を移していますから、現在の預金流出は、市井の市民や農民が、僅かな預金を引き出し、現金を自宅に置いていることの現われです。近い将来、ギリシアはユーロを離れ、ドラクマに戻るかもしれない。そのときドラクマは、間違いなくユーロに比べてかなり低く評価される。当然公定レートよりも実勢レートは低くなります。それなら、ユーロのうちに現金化し、ユーロ紙幣を抱えているほうが、預金を強制的にドラクマに替えられるよりも有利だ。そうしたささやかな自衛行動が、日々続けられている預金の引き出しに繋がっているのです。当然、大量の預金が流出する金融機関は、資金不足に陥ります。資金は政府に頼ってユーロ紙幣を提供してもらうしかありません。しかし、ユーロ紙幣はECB(欧州中央銀行)しか印刷できません。ユーロ圏諸国やECBなどの支援を受けるギリシア政府には、国内金融機関に提供するユーロ紙幣などありません。ですから、ギリシアで日々流出を続ける預金の支払いに当てるユーロ紙幣は、日々ECBから供給されているのです。 続く
2012.06.12
コメント(2)
-
教科書検定訴訟始まる 12日の日記
クロニクル 教科書訴訟始まる1965(昭和40)年6月12日47年前のこの日、家永三郎東京教育大学教授は、ご自身で執筆された高等学校日本史の教科書『新日本史』が、検定不合格となったことに対し、国及び文部省を相手として、損害賠償と不合格処分の取り消しを求めて提訴しました。 いわゆる教科書裁判はここに始まりました。 氏の論旨は、教科書の検定が年代や事実の誤記に対する訂正に留まるなら問題はないが、学界で市民権を得ている定説や有力な新説に対する訂正命令になるなら、教科書検定は事実上の検閲になっており、それは、「検閲はそれをしてはならい」と明記されている憲法21条違反である、というもので、教科書検定違憲論を全面に出して、裁判所に憲法判断を求めたものでした。一般に教科書は数名の著者による分担執筆がふつうなのですが、三省堂が出版元になっていた家永教科書だけは、家永教授の単独執筆であったこと、書店もまた教授の裁判に訴えるという姿勢に協力的で、著者以外に、出版社に対しても行なわれる文部省の指導や要請についても、著者に協力して裁判資料として提供するなど、家永教授を後押しする要素もあったことなどが、裁判に踏み切る一助となったことも確かですが、学問的良心と言論の自由を守ることが、何よりも大切であるとする教授の固い信念が、訴訟を起こし、20年を越えるロングラン裁判に耐え抜く原動力となったことは間違いありません。検定で訂正しなければ不合格とするされるA意見には、「安保条約で、日本には米軍の基地が置かれることになった」の部分に対し、「基地ではなく、施設であるから、この叙述は間違っている」とか、「太平洋戦争は、侵略戦争ではない」といった、学界の定説を真っ向から否定する暴論が含まれていましたから、裁判では、原告側証人として、歴史学界や憲法学界の錚々たる重鎮が次々法廷に立ちました。その豪華なネームバリューがまた法廷が開かれるたびに、マスコミを賑わしたことも度々でした。
2012.06.12
コメント(16)
-
日本列島改造論 追記
日本列島改造論 追記クロニクルに記した、田中角栄元首相の日本列島改造論について、少し追加させて戴きます。まず「日本列島改造計画」の内容ですが、当時一般に伝えられた通りで、およそ次ぎの3点にまとめることができるように思います。 (1)人口の過密と過疎を同時に解消するために、工業地帯を再配置する (2)地方に25万人の都市を建設する (3)全国に新幹線・高速道路・情報網を整備するこの3点を柱として、農村と都市、太平洋側と日本海側の格差を是正しようという壮大なビジョンでした。雪国出身の政治家ならではの発想といえましょうか。国内の格差はいまだ埋まらず、地方の悲鳴は、当時よりむしろ切実で悲痛なものとなっているのは、構想は理解出来ても、実現に向けての手法に大きな問題があり、その時受けた大きな傷がいまだに癒されないままに、現在まで引きづっているからと、言えなくもありません。 当時彼の構想を実現するには、「ペルシャ湾のホルムズ海峡から、延々日本まで原油を運ぶタンカーの行列が続くほどに、大量の原油輸入が必要になるが、果してそれは可能なのか」という至極まっとうな批判がありました。それは世界の原油消費のバランス、世界の経済秩序を意識した批判だったのですが、この懸念は翌年秋、第一次オイルショックの発生によって、現実のものになりました。72年当時の原油価格の平均は、1バーレル3ドル以下でしたから、列島改造計画そのものが、原油は無尽蔵であり、安価でいつまでも輸入出きるという、幻想の上に立っていたということになります。オイルショックの結果、この計画は、地方を含む土地価格の急騰、物価の急騰とインフレを誘発しただけで、実現不可能となりました。とりわけ、地方の工業化計画に淡い期待を抱いた地方に、大きな爪あとを残したのです。この地方の傷が、85年以降のバブル期に、「あの時やれなかったことを、今なら」という雰囲気を醸し出し、今度は工業都市ではなく、リゾート計画として、再び過大な投資を促して、再度の大きな傷を残すことになりました。 現在の地方の困難は、この2度の誤算によって増幅された結果であるように思います。
2012.06.11
コメント(2)
-
日本列島改造論発表 11日の日記
クロニクル 日本列島改造論発表1972(昭和 47)年6月11日ちょうど40年前のこの日、田中角栄通産大臣が、持論の日本列島改造論をまとめて発表しました。 沖縄返還を花道に総理・総裁の辞任を表明していた佐藤栄作首相の後継総裁を決める総裁選へ望む、角栄流の事実上の政策発表でもありました。 この公約を引っさげて、田中角栄は7月5日の総裁選に勝ち、7日に第一次田中内閣が誕生する運びとなります。
2012.06.11
コメント(14)
-
ペルー大統領にフジモリ氏 10日の日記
クロニクル ペルー大統領にフジモリ氏1990(平成2)年6月10日22年前のこの日、南米のペルーで行なわれた大統領選挙で、日系人のアルベルト・フジモリ前国立農科大学長が、下馬評を覆して当選しました。日系人が、その移住先の国で、政治上のトップの地位につくことは、近代日本にとって、初めての事でした。この年の選挙で、本命視されていた候補者は、クリオーリョ(現地化した白人)層の地主と利害を共有し、社会の多数を占める貧農層の要求は、無視し続けていたのです。当初、前評判の高くなかったフジモリ氏は、土地改革を公約に掲げて、貧農の支持を受け、下馬評を覆して、当選しました。
2012.06.10
コメント(16)
-
有島武郎心中死 9日の日記
クロニクル 有島武郎心中死1923(大正12)年6月9日89年前のこの日、白樺派に属した作家の有島武郎が、婦人公論記者の波多野秋子と、軽井沢の有島の別荘で心中しました。時に有島46才、波多野30才でした。有島は『白樺』の同人で、『カインの末裔』や『生まれいずる悩み』で、文壇にデビュー。『或る女』や随想風の評論『惜しみなく愛は奪ふ』などで、多くの読者に親しまれていました。そこに、第一次世界大戦後の不況と相俟って、社会運動が高まり、知識人への批判が高まる中で、有産階級の知識人の苦悩を『宣言一つ』として発表し、北海道の有島農場を小作人に開放するなど、人道的な社会主義者として、注目を集めていました。有島と波多野は、共に配偶者がいたのですが、作家と編集者の立場を超えて、互いに惹かれ合うようになり、愛人関係となったのです。それを知った波多野の夫が、2人の心中の前日、有島に金銭を要求、人道主義者の有島に出来ない事を知りながら、金で妻を売ると有島に迫りました。これがきっかけとなり、前途を悲観した2人は、発見の遅れる場所をと、有島の別荘に逃避、そこで心中に至りました。2人の死体の発見は、約1ヶ月後の7月7日、涼しい軽井沢とはいえ、腐乱し、変わり果てた姿だったと報じられています。これがおそらく、谷崎や佐藤春夫であったなら、大喜びで金を払い、妻と離別して、堂々と再婚していたのでしょうね。人道主義者の悲劇がここにあったように感じられてなりません。
2012.06.09
コメント(12)
-
日本競馬史上最高の珍事発生 8日の日記
クロニクル 日本競馬史上最高の珍事発生1929(昭和4)年6月8日福島競馬場は、1918(大正7)年に完成した、中央競馬の競馬場です。その年6月28日から競馬が開催されていますから、史上最高の珍事が発生したのは、それから11年後ということになります。83年前のこの日、笑うに笑えない珍事が起きました。この日のレースが進み、第5レースがスタートした直後でした。何に驚いたかスタートした馬たちが突然暴れだし、馬上の騎手たちが1人残らず落馬してしまったのです。騎手がいなくなった馬たちは、てんでに動きますから、もはやレースにはなりません。かくてレースは、全頭落馬により不成立という、非常に珍しい結果を招きました。世界ではどうかは、調べていませんが、日本競馬史の上では、最初で最後の珍事でした。
2012.06.08
コメント(4)
-
大鳴門橋開通 8日の日記
クロニクル 大鳴門橋開通1985(昭和60)年6月8日27年前のこの日、大鳴門橋が開通しました。本州四国連絡橋の3本のうちの1本、神戸ー鳴門ルートのうち、淡路島と徳島県鳴門市を結ぶ、鳴門海峡をまたぐ橋でした。大鳴門橋の開通で、橋上から鳴門の渦潮を見ることが出来るようになり、明石海峡大橋も完成すると、徳島の皆さんが関西に出る上では、格段に利便性が向上しました。私は5月に2度、8月に1度の3度もこの橋を通っているのですが、残念ながら橋上から鳴門の渦を見ることは出来ませんでした。3度のうち2度は快晴だったのですが、そのために水蒸気が吸い上げられ、海面上は白濁してしまっていたのです。ついてないですね。
2012.06.08
コメント(16)
-
G7の黄昏とEUの憂鬱 (2)
G7の黄昏とEUの憂鬱 (2)リーマンショック後の欧州の政治状況を見てみましょう。ギリシアのパパデモス政権、イタリアのモンティ政権のように、選挙を経ずに政権が交代した国もありますが、2010年のイギリスを先頭に、選挙のたびに政権が交代しています。イギリスでは、ブラウン労働党政権から、保守党と自由党の連立によるキャメロン政権へ、そして、御存知の通りフランスでは、現職のサルコジ大統領が敗れて、社会党のオランド大統領が誕生しました。総選挙の行われたギリシアは、再選挙となったことは御存知の通りです。リーマンショックの翌年、危機の深化に先駆けて行われたドイツの選挙では、メルケル首相の政党CDU(キリスト教民主同盟)と姉妹政党のCSU(キリスト教社会同盟)が圧勝しましたが、最近行われた州議会選挙では、軒並みメルケル与党が大敗北を決しており、来援の下院選挙でのメルケル続投の可能性は、ほとんどないように思われます。2年前の総選挙で政権の交代したイギリスでも、財政再建を目指して公約通りに緊縮政策を推進してるキャメロン内閣が、選挙公約を忠実に実行している(この点、「公約はあいたけれど、必ず実施するとは言っていない」と呆れたセリフを吐く、どこかの国の政党とは全く異なります)にも関わらず、各地で行なわれる補選などで、連戦連敗を続けています。オランダでも極右の政党がキャスティングボートを握り、半年以上予算がたなざらしとなり、遂に連立政権が崩壊、秋に総選挙となりそうな雲行きになっています。これは何を意味するのでしょうか。 財政状態の悪化が著しい南欧諸国では、救済を受けるための緊縮政策の実施に国民がノーを突きつけている。他方、救済する側の独仏蘭などでは、南欧諸国の救済とやはり緊縮財政の実施に、国民がノーを突きつけている。こういう構図が浮かんできます。 続く
2012.06.07
コメント(6)
-
日本勧業銀行の設立認可 7日の日記
クロニクル 日本勧業銀行の設立認可1897(明治30)年6月7日115年前のこの日、政府は申請書類の提出されていた、株式会社形態の日本勧業銀行の設立を認可し、開業免許を付与しました。この結果、同行は8月2日に営業を開始しました。この日本勧業銀行は、戦後財閥系の第一銀行と合併し、第一勧業銀行となり、バブル崩壊後の不良債権処理の重荷から、さらに富士銀行、日本興業銀行と3行で合併することになり現在はみずほフィナンシャルグループの一員となっています。最近は、金融機関を取り巻く景色もすっかり変わりましたね。
2012.06.07
コメント(8)
-
ルイ14世の宮廷生活 (102)
ルイ14世の宮廷生活 (102) サロンで何度か上演されたとなると、街中での上演も拒めなくなります。こうして『フィガロの結婚』は、ボーマルシェの予測通りになったのです。一般公開は、1784年の4月末でした。劇場は超満員の盛況、パリ中の話題となり、町中は興奮のルツボに巻き込まれたと、『18世紀パリ生活誌』の中で、著者のメルシエは語っています。パリ市民たちは、フィガロに自己の代弁者を、特権に対する怒りの正当性の擁護者を見出していました。現状に不満な人々は、揃ってこの芝居に熱狂したのです。それから5年後、1789年5月1日の三部会の開会がきっかけとなって、フランス革命の幕が上がったのです。ルイ14世の宮廷とサロンの始まりを、20回くらいで書くつもりが、つい長々と時代と筆を伸ばしてしまいました。お付き合いありがとうございました。 完
2012.06.06
コメント(6)
-
レッドパージ序曲 6日の日記
クロニクル レッドパージ序曲1950(昭和25)年6月6日62年前のこの日、GHQ(日本占領軍司令部)司令官のマッカーサーは、吉田首相宛て書簡で、日本共産党中央委員24名の公職追放を指令しました。時に朝鮮戦争勃発が同月25日ですから、その19日前でした。米国が国民党の勝利を信じて疑いもしなかった中国の内戦は、前年10月1日に共産党の勝利で終りました。この事実が、GHQをして、反共への傾斜を強める結果に繋がったのですね。
2012.06.06
コメント(8)
-
ルイ14世の宮廷生活 (101)
ルイ14世の宮廷生活 (101) モーツァルトの歌劇では、カットされているのですが、フィガロは、主人に当たるアルマヴィヴァ伯爵を、次のように面罵するのです。「あなたは金持ちのお殿様というところから、自分ではひとかどの人物だと思っていらっしゃる。貴族身分、財産、勲等に位階、あれやこれやで鼻高々と。 ですが、これほどの宝を手に入れるについて、あなたはそもそも何をなされました? 生まれるだけの手間をかけた、ただそれだけじゃありませんか。 おまけにあなたは、人間としても根っから平々凡々じゃありませんか…」これはもう、実際にはありえない、フィクションの世界だからこそ言えるセリフです。しかし、そこには、率直で真実の平民の声がありました。生まれの違いが特権に繋がる、貴族身分に対する庶民の思いを、ボーマルシェは代弁していたといえましょう。そこには、明らかに貴族身分に挑戦状を叩きつける、ボーマルシェの気概が溢れていました。それゆえルイ16生の政府が、『フィガロの結婚』を危険な作品と受け止め、その上演を禁じたのは、ある意味で王権としての当然の行動でした。ボーマルシェは不思議な人物です。彼は、上演禁止の措置にも泰然としていたと言います。彼は、心配する友人に向かって、次のように言ったとされています。「国王が上演を望んでおられないって、それだからこそ、この芝居は上演されると思うよ。」1780年代、革命直前のフランスでは、あちらでもこちらでもサロンが開かれており、貴族やブルジョワは勿論、召使を3人程度しか雇っていない中流の家庭でも、サロンが開かれる時代となっていたのですが、そんなサロンの一つで、まず『フィガロの結婚』は上演されたのです。1783年のことでした。当然そのサロンは、由緒ある公爵夫人のサロンで、見物客は宮廷人や大貴族ばかりだったと伝えられています。観客の中には、お忍びで加わった王妃マリー・アントワネットの姿もありました。大貴族たちは、ボーマルシェの予想とおりに王権を押し切って、『フィガロの結婚』を上演させ、自分達が笑いものにされ、皮肉られ諷刺されている作品に、笑い転げていたのです。当然、こういお目出度き人々に、未来は保障されません。 続く
2012.06.05
コメント(10)
-
第3次中東戦争始まる 5日の日記
クロニクル 第3次中東戦争始まる1967(昭和42)年6月5日55年前のこの日、午前8時45分、イスラエル空軍がエジプト空軍の全ての基地を奇襲、滑走路を破壊し、空軍機を破壊し尽くしました。素早い隠密行動にあって、エジプト空軍機は一機も応戦に飛び立つことも出来ないままに、なすすべなくイスラエル軍機の攻撃に晒されたのでした。遮るもののない地域では、制空権を握った側が大勝するのは自然なことです。この戦争では僅か6日間の間に、イスラエルはエジプト領シナイ半島に、エジプトが実効支配していたガザを、東エルサレムを含むヨルダン領のヨルダン川西岸地域を、さらにシリア領ゴラン高原までも占領することに成功します。まさにイスラエルの大勝利でした。エジプトの指導者ナセルは、自慢の空軍が一戦も交えずになすすべもなく、敗れ去ったことにショックを受け、一時は辞意を表明するほどに落ち込んだのですが、アラブの危機とパレスチナ難民問題の深刻さを認めて、翻意する一幕もありました。しかし、この戦争は大量のパレスティナ難民を生みます。この時難民となった人達は、先祖伝来の地をイスラエルに奪われて難民となり、以来現在まで、自分の郷里と土地に帰ることも出来ずに、難民としての生活を送っています。そうした彼等、彼女等が苦心の末に築き上げたのがパレスティナ解放機構(PLO)だったのです。 その後、イスラエルは、国連決議で、第3次中東戦争での占領地の一切を関係各国に返還するよう命じられながらも、それを無視し続け、僅かにイスラエルとの関係を改善したエジプトにシナイ半島を返還したのみで、今日まで占領地域に居座り続けているのです。 これでは、中東地域に平和が訪れるわけがありません。中東地域は、なおしばらくの間は。きなくさい状態が続きそうです。
2012.06.05
コメント(17)
-
ルイ14世の宮廷生活 (100)
ルイ14世の宮廷生活 (100)ブルボン王朝や貴族の支配に対する、ブルジョワや庶民の不満は日増しに高まっておりました。そんな折に発表されたのが、ボーマルシェーの『フィガロの結婚』でした。1781年のことです。現在では、ボーマルシェーの原作を下に、1786年にモーツァルトが作曲したオペラの方が有名ですが、オペラでは原作にくらべて、貴族社会に対する諷刺は、かなり薄められてしまっていますから、原作が発表された当時の騒ぎは、半端ではありませんでした。原作のあらすじを簡単に紹介します。主役のフィガロは、アルマヴィヴァ伯爵の下僕です。この下僕のフィガロが、侍女のシュザンヌのハートを射止め、伯爵夫人のロジーナや召使のシュリバンを味方にして、主人のアルマヴィヴァ伯爵のよこしまな野心を打ち砕いて、伯爵からシュザンヌを奪うことに成功、彼女と結婚してしまうというものです。そこでは、下僕が主人と体等の立場で、1人の侍女を争って、恋の鞘当に勝利するのです。下僕の方が、知恵や才覚においても主人より優れており、何度も主人の鼻を明かすのです。舞台こそ、フランスを避け、前作の「セビリアの理髪師」同様、スペインのセビリアに設定していましたが、当時の身分制社会において、とりわけ保守派貴族からすれば、ただならぬことでした。この作品は、戯曲でしたが、王政は、この作品の上映を固く禁じたのです。 続く
2012.06.04
コメント(8)
-
張作霖爆殺 4日の日記
クロニクル 張作霖爆殺1928(昭和3)年6月4日94年前のこの日、関東軍(日本の満州派遣軍は、当時こう呼ばれていました)の河本大作大佐らは、満州軍閥の張作霖を奉天(現瀋陽)郊外で爆殺しました。この年5月、蒋介石の率いる国民革命軍による北伐は勢いを増し、北京解放を間近に控える勢いを示していました。ここにおいて、日本の田中義一内閣は、戦火が満州に飛火し、東三省(奉天、吉林、黒竜江の3省)における日本の権益が内戦に脅かされることを嫌い、張作霖に戦いを避けて満州に避難する事を勧めました。張作霖は、迷った末に勧告を受け入れ、前日3日の早暁に北京を経ったのでした。河本らは、張を爆殺することで、生じるであろう混乱を利用して、関東軍を出動させ、満州を占領しようと企んだのでした。しかし、予想された混乱はおきず、関東軍は出撃のチャンスを掴むことは出来ませんでした。この計画は失敗しました。 日本の田中内閣は、事件の真相を国民に隠し、「満州某重大事件」としか発表しなかったのです。
2012.06.04
コメント(16)
-
ルイ14世の宮廷生活 (99)
ルイ14世の宮廷生活 (99)もう50年以上も前のことになります。1人の若い歴史家が、古くからあるフランス全国の図書館という図書館を訪ね歩き、18世紀後半から19世紀前半の蔵書冊数を徹底的に調べ上げました。大学図書館から、地域の教会の図書館、そして州や市の図書館をも調べつくす悉皆調査でした。こうした苦心の成果をまとめて世に問うた書物が、フランス革命に関する不滅の名作の一冊に数えられる、ダニエル・モルネの『フランス革命の知的起源』です。彼は、啓蒙思想の勝利が歌われ、識字能力に恵まれあいフランスの民衆までもが、路上や居酒屋(当時のカフェは高級で、庶民が気軽に立ち寄れる場所ではありませんでした)での読み聞かせや解説を聞くことで、次第に革命思想に染まっていった時期に、いったいフランスの知識人や庶民は、並みいる啓蒙思想家のどんな書物を読んでいたのかを、図書館の蔵書数から推計したのです。革命の書と言われ、日本での最初の翻訳を中江兆民が手がけた、ルソーの『社会契約論』は、大きな図書館しか所持しておらず、それも決まって1冊だけでした。ところが、ヴォルテールの『カンディード』、ディドロの『ラモーの甥』、そしてルソーの『新エロイーズ』や『エミール』は、中小の図書館でも3冊、5冊と所蔵していたのです。閲覧希望者が多く、常に借り手が何人も待っている書物は、複数冊備えられ、貸し出し希望に備えたのです。読み手の少ない本は、1冊で十分なのです。良くぞ、検閲の眼をくぐって出版されたものだと意外感をもった、『社会契約論』は知識階級以外には受け入れられず、本棚で誇りを被っていた事実まで、彼は明らかにしたのです。何のことはない、使われている言葉も、難しく純粋論理の世界で貫かれた『社会契約論」は、絶対王政の検閲官が、この内容なら広く読まれることはあるまいと判断したからこそ、発売禁止とされず、出版が許可されたと思われるということまで、モルネは突き止めたのです。啓蒙思想の勝利は、思想家達が思想の普及のために、誰もが理解しやすい小説を著したことによって、庶民の知るところ、受け入れるところとなったのです。 続く
2012.06.03
コメント(6)
全56件 (56件中 1-50件目)