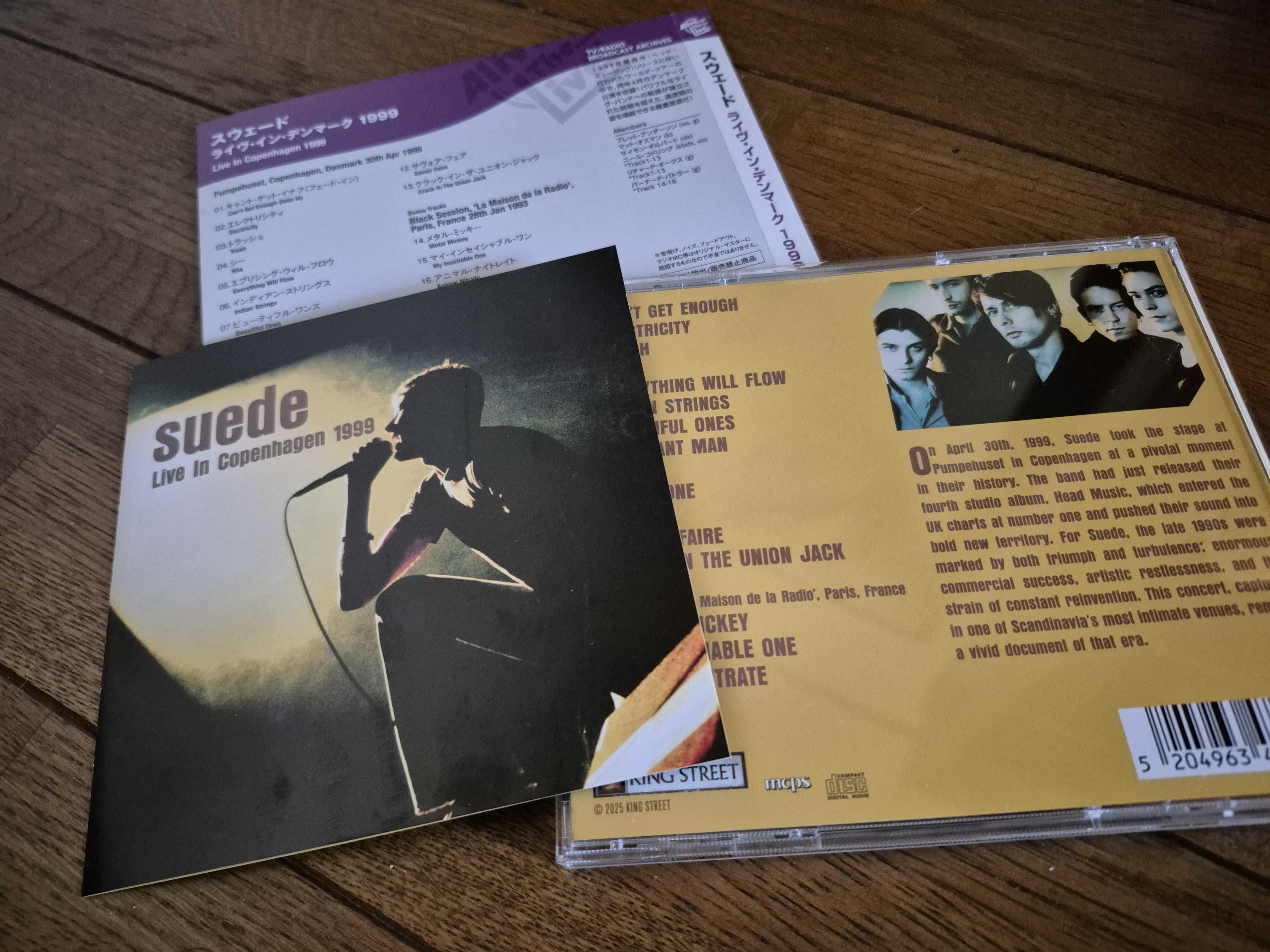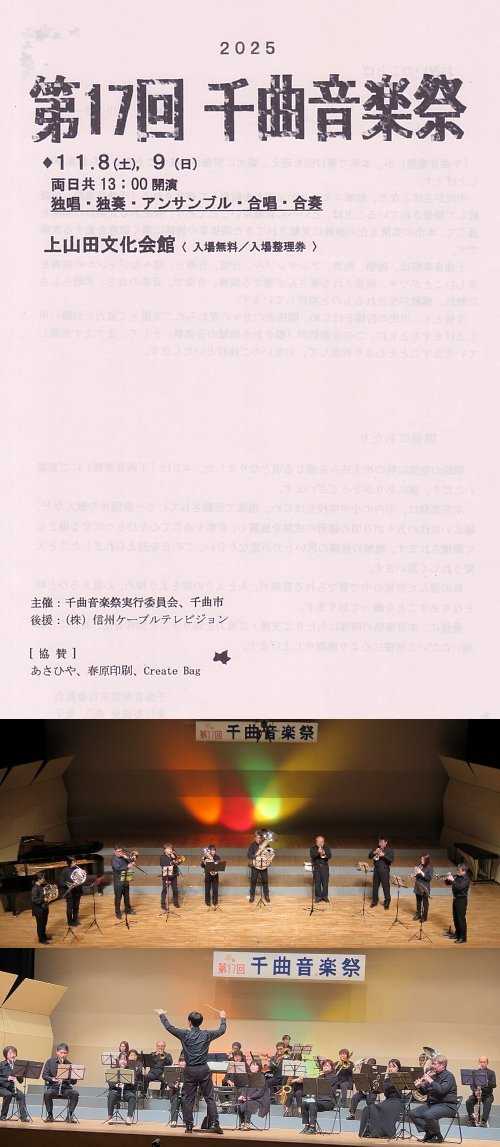2015年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
ロバよりミケーレ、理髪師より伯爵〜メトライブビューイング「セヴィリヤの理髪師」
おなじみ、メトロポリタンオペラのライブビューイング。シーズンが始まったと思ったら、早くも4作目の「セヴィリヤの理髪師」まで来てしまいました。大好評だった第2作「フィガロの結婚」を見逃した(ジェノヴァに行っていて)のがかえすがえすも残念ですが、これからは全作品制覇したいものです。 さて、その「セヴィリヤ」。プロダクションじたいは2005−6シーズンに配給されたバートレット・シャーのもので、歌手も当時(フローレス&ディドナート!)とは異なるフレッシュな顔ぶれですが、ワクワクする軽快な作品だけに、若手中心のキャストで見るのも楽しいもの。シャーのプロダクションも、何度見ても新鮮でおしゃれな舞台です。なかでも、オケピットを囲む花道?は圧巻。ピットの前まで出て行って観客を身近に感じながら歌うのは、ある意味歌手冥利に尽きるのではないでしょうか。 さらに期待していたのは、指揮のミケーレ・マリオッティ。ロッシーニの生地ペーザロのロッシーニ・フェスティバルの総裁の御曹司で、「(ペーザロの)ロッシーニ劇場のなかで育ったようなもの」(本人談)のマリオッティは、まさにロッシーニの申し子。1979年生まれの若さながら、すでにメトのロッシーニ上演には欠かせない顔ぶれになっています(新国立劇場がロッシーニをやるときにはぜひ招聘してほしいのですが。。。)。 やっぱり、極上の指揮でした。 まず序曲が素晴らしい。澄んだ、伸びやかな、カンタービレな旋律。はじけるような音の数々。何より魅力的なのは、人肌というか、心臓の鼓動や血液の循環のように温かく軽快で、血の通ったリズムです。このリズム、プリズムのようにさまざまに色合いを変えてゆくのが何ともチャーミング。そして幕があがれば、ロッシーニの音楽の快楽が広がります。マリオッティが卓越していると思うのは、音楽が疾走しているように感じられるのに、決してオーケストラや歌手を取り残して走り出したりせず、歌手をうまく乗せて行くそのセンスです。知的なのです。 加えて今回、「!」と思ったのは、「嵐の音楽」の処理の素晴らしさ。「セヴィリヤ」の「嵐の音楽」といえば、普通、間奏曲のように演奏される印象ですが、今回はしっかりドラマトゥルギーが感じられました。考えてみれば、嵐のどさくさに伯爵とフィガロがロジーナの家に忍び込むのですから、物語の上でもなかなかに劇的な場面ではあるのです。それをきちんと解釈して伝えてくれた指揮には脱帽でした。マリオッティ、ロッシーニのオペラ・セリアを数多く振っている経験も役に立っているのではないでしょうか。 唯一残念なのは、マリオッティのインタビューがないこと。彼、昨シーズンはライブビューイングで「リゴレット」を指揮したのですが、その時もインタビューがありませんでした。代わりに?動物調教師嬢のインタビューがありましたが、それはそれで面白くはありますが、やはりマリオッティの肉声が聴いてみたい。作品の魅力を語ってほしい。「ロバよりミケーレ」(ある関係者と話しているうちにこぼれたフレーズ)。いや、まったく。ヴィジュアルもいいしね〜。 「ロバよりミケーレ」といえば、もうひとつ言いたいのが、 「理髪師より伯爵」 です。 「セヴィリヤの理髪師」と呼ばれるこの作品、初演当時は「アルマヴィーヴァ(=伯爵)」と呼ばれていたことは、ロッシーニの専門家がこぞって触れています。なぜなら初演時に伯爵を歌った名テノール、ガルシアを想定して書かれ、だからこそ、幕切れ近くに伯爵の大アリア「もう、やめるのだ」が置かれたからです。けれどこのアリアは至難であることもあって、ガルシア以外の歌い手はほとんど歌わなかったため、間もなくオペラは「セヴィリヤの理髪師」と呼ばれるようになり、フィガロが主役となってしまったのです。 けれど昨今のロッシーニ・ルネッサンスとともにすぐれたテノールが輩出し、伯爵の大アリアも復活しました。このアリア、何しろ幕切れにありますし、全曲のなかで一番長大で難しいですから、完璧に歌われればそれまでのすべてがかすんでしまうほどの強烈な印象を与えます。「アルマヴィーヴァ」と呼ばれたのはもっともだ、とうなずいてしまうのです。 今回も、やってくれました。伯爵役のローレンス・ブラウンリー。柔らかで軽やかな声の持ち主で、ロッシーニ・テノールとして世界的に活躍しています。新国立劇場でもこの役を歌ったことがありますし(その時は残念ながら幕切れのアリアはなかったと記憶しています)、実演で接した中では、ドレスデンで聴いた「チェネレントラ」が印象的でした。柔らかく伸びのいい、まさにレッジェーロな声と抜群のテクニックに魅了されたのを覚えています。 今回のブラウンリー、少し声が太くなったよう。ちょっとフローレスに似た輝かしさが加わりました。調子はとてもいいようで、安定した歌いぶり。最後のアリアも完璧で、高音も見事に決め、えんえんと引き延ばす余裕の歌唱。これを聴いてしまうと、やっぱりこの作品は「アルマヴィーヴァ」だと(しつこいですが)またまた納得してしまうのです。うーん、伯爵役がこのアリアを歌うときは、タイトルを「アルマヴィーヴァ」に変えたらどうでしょうか。こんなに客席を痺れさせている役が、そのすぐ後のカーテンコールで最後から3番目に出てくるって、納得できません。 ロジーナ役のイザベル・レナードは、歌唱的に完璧というところまでは行きませんが、清純な雰囲気といかにもメッゾらしい深い声が魅力的。そして美人!どの角度から見ても整った顔立ちで、完璧な美女とは彼女のようなひとのことを言うのでは?などと見とれてしまいました。 ロッシーニ節満開の指揮と、本来のタイトル通りの実力発揮の伯爵、おしゃれな舞台に美女のロジーナ。「セヴィリヤの理髪師」、再演でもやっぱり、見応え聴き応え満点です。 上映に関する情報はこちらです。 http://www.shochiku.co.jp/met/program/1415/index.html#program_04
January 27, 2015
-
新年のドジと日本人の優秀なお仕事の巻
たまーにここでも書いているように、そそっかしい性分です。 新年早々、大ドジをやってしまいました。それも2回も。 同時に2回とも、日本人の仕事ぶりの優秀さ、を思い知らされる体験になりました。 まずは忘れもしません、お正月の3日。宛名書きをしていない年賀状を、大量に投函してしまった!のです(泣)。 なんでそんなバカなことをしてしまったのかというと、宛名書きをしたものの山と、していないものの山を、裏面(つまり宛名を書かない面)を表にして並べて置いておいた。それで、宛名面を見ずに、宛名を書いていないほうの山を、書いていると勘違いして持ち出し、投函してしまったんですね。 たぶん30分後くらいに気づきました。でももう自宅にもどっていた。それで、呆然として、フェイスブックで呟きました。 そうしたら、(フェイスブックってスゴイです)、慰めと呆れコメントにまじって「郵便局に言えばなんとかしてくれますよ」のコメント。 「だって、郵便局休みだし」と返したら、「大丈夫です。年賀の時期なので24時間稼働しています」というお返事。そうか、本局へ行けばいいんだ、と思わず呟くと、「そうです」とまたまた頼もしいお返事。これは、行くしかありません。 まず電話を入れましたが、呼び出し音が空しく鳴るばかり。しょうがない、行ってしまいましょう。 某郵便局に到着。24時間窓口にはこの時期だけあってさすがに列ができていましたが、並んで待つこと20分あまり。係員さんに事情を話すと(どこのポストに何時頃投函したかはさすがに覚えていましたので)、 「全部拾えるかどうかはわかりませんが」 と何度か念を押されつつ(当たり前ですね)、 「探してみます」と言ってくれました。あいにく輪ゴムでまとめていなかったので(まとめるのも重要と、改めて痛感)、ばらけてしまっているリスクもありますし、全部見つかることは諦めてはいました。何度も御礼をいい、ひとまず退散。 と、その夜です。 出先から帰る途中の車のなかで、郵便局から電話が入りました。なんと58枚!救い出してくれたという。 諦めていましたので、本当にラッキーでした。さすが、日本の郵便局です。しかもこちらが取りに行かなくとも、送ってくれるという。他の国では、まず考えられません。 果たして翌日の夜、速達で届いたのです。しかもそこで回収できなかった分も、翌々日、また使えるような形(消印がないのは年賀状だから当然ですが、「宛先不十分で配達できません」という貼り紙がはってあり、それを剥がせば使える)で何枚か戻ってきたのでした。 それから1週間もたたないある日の夕方。もう一回、やらかしました。今度は電車の網棚に、買ったばかりのブーツを置き忘れ。これは、乗り換えて2駅くらい行ったところで思い出したのです。 次のアポまでそう時間はないので一瞬悩みましたが、とりあえず電車を下りて引き返しました。ブーツといってもスウェードの安物なので、「諦め」の二文字もよぎつたのですが、だめもとだと思いなおしたのです。 駅の忘れ物取扱所に駆け込み、何時の電車のどのへん、と事情を説明。と、ラッキーなことに、その列車が間もなく折り返してこの駅に来るという。「その時に車内に入って探して下さい」とのこと。なるほど。そういえば、他人のそういうケースは目撃したことがあったのでした。 待つこと数分。到着した列車の、このへんだったかしら?という車両に入ってみましたが見つからず。いったんホームに出て、列車に沿って小走りになりながら、窓越しに網棚をチェックします。 あった!!! 車内に飛び込んでショッピング袋を確保し、滑り出る。と同時に、列車は出発して行きました。3分くらいのことだったと思います(お待たせしたみなさま、すみません)。 「ちょうど列車が戻ってきてよかったですね」 御礼を言われながら、係員の方、ちょっと誇らしげでした。うーん、日本の鉄道会社って、すごい。 こういうところ、頼まれたことに誠意を尽くす日本人の長所だと思います。他の国ならまず考えられません。 日本人のこういうところは、本当にスーパーだなと、迷惑をかけた自分のドジぶりを脇に置き、つくづく感服してしまったお正月の出来事でした。
January 19, 2015
-
ロッシーニの使徒アルベルト・ゼッダ ロッシーニオペラの魅力を語る
オペラファンならご承知の方も多いと思いますが、オペラの世界では「ロッシーニ・ルネッサンス」ということがよく言われます。20世紀の末から、ロッシーニの知られていなかった作品が知られるようになり、劇場のレパートリーとして復活してきた現象です。 その震源地になっているのが、生地ペーザロで行われる「ロッシーニフェスティバル」なのですが、そのフェスティバルの芸術監督であり、ルネッサンスの立役者であるアルベルト・ゼッダ氏が、藤原歌劇団「ファルスタッフ」のため来日をしている機会に、ロッシーニについての講演会を行いました。春に大阪フェスティバルホールで「ランスへの旅」を指揮するので、同作の魅力の紹介もかねてのことです。 ゼッダ先生、ロッシーニのクリティカルエディションの校訂作業でも有名なので、学者肌のところもあるわけですが、もともとは指揮者。校訂を始めたきっかけも、自分で指揮した「セビリヤの理髪師」のレンタル譜を自筆譜とつきあわせてみたらあまりにも違っていて、訂正を書き込んだ、それがきっかけということらしい。自分は指揮者だからということで初めは辞退したのだが、やることになった。 で、各地の図書館で、まだ出版されていないロッシーニのいろんな作品の自筆譜にあたったら、これがすごく魅力的で、「ロッシーニに恋をしてしまった」。「セビリヤ」など軽い作品の作曲家だと思われていて、ドラマティックなセリアの存在は知られていなかった(出版されていなかった)が、それらの作品が素晴らしかった。ロッシーニの真の偉大さ、独創性、神秘性がそこにはあった。 (今では考えられませんが、ゼッダ先生がはじめそのようなことを周囲に言ったら、おかしなことを言いだした、と言われたそうです ) そんな経緯があり、ロッシーニの魅力を知らしめるために、1979年に生地ペーザロに財団を創設して批判校訂版による全集を刊行しはじめ、80年からはロッシーニフェスティバルを創設。セリアをはじめ知られざる作品の上演に取り組んでいます。このフェスティバルにより、「新しいロッシーニ像が広まった」(ゼッダ先生)。とくに、1984年に蘇演された「ランスへの旅」は一大センセーションを巻き起こしました。オペラの常識を超えたオペラだったからです。その理由は、筋らしい筋もないのに、「ロッシーニの中でももつとも美しく作られている」から。「ロッシーニのオペラのすべてがわかる」。 ゼッダ先生いわく、「「ランス」には、ロッシーニが理想とした「感情」が描かれている」という。それはヴェルディやプッチーニの描いたリアルな感情ではなく、抽象的なもの。個人のレベルを超えた、人間を理想化した上での感情。それを音楽、歌で行うのが、ロッシーニの大きな魅力ということらしい。 「だからロッシーニの音楽はモダンなんです。彼がオペラの作曲をやめたのは、モダンすぎたからなんです。知的。頭脳的。」 それは分かる気がします。 けれど、魅力はそれだけではない。 「ロッシーニは、感情を軽くほほえみながら表現する。セリアのような悲劇でも喜劇的だし、ブッファのような喜劇でも悲劇的。両面がある。」 そして音楽的な快感。「リズム、スピード感」。これは、バロック音楽にも共通する部分がありますね。 日本にも、熱烈なロッシーニファンがかなりいて、毎年ペーザロもうでをしているひとも少なくありません。とはいえ新国立劇場での上演は少なく、ロッシーニの本格的な受容はこれからという面もあります。けれど、日本人はその分、「ロッシーニに対する偏見(=軽い作曲家という)がないので、幸運なのではないでしょうか」というのがゼッダ先生の意見でした。そして知的な日本人に、ロッシーニの音楽は受け入れられやすい、という意見も。 1928年生まれ、87歳になったばかりのゼッダ先生。信じられないほどお元気で、お話もよどみなく、興味深く、引き込まれました。ゼッダ先生というマルチタレント(演奏も研究も教育も)な使徒を得て、天国のロッシーニもほんとうに幸運なことと思います。 4月の大阪「ランスへの旅」の情報はこちらです。 http://www.festivalhall.jp/program_information.html?id=574 そしてゼッダ先生、今回の来日は、最初に書きましたが藤原歌劇団「ファルスタッフ」の指揮のため。これは今年の初めに一番楽しみにしている公演です。あるところのインタビューで、「ファルスタッフ」は「ポッペアの戴冠」とならんで、イタリアオペラ史上の傑作だ、と語っていらっしゃいました。それについても別の機会を設けて語ってほしかった、と切に思います。 今回の講演でも、「ファルスタッフ」について、ヴェルディがロッシーニ的なものを獲得した作品、だとちょっと触れていました。悲劇のエッセンスがある喜劇。(モーツァルトの「ドンジョヴァンニ」や「コジファントウッテ」も同じだそうです。)悲劇ばかり書いてきた、分かりやすい大衆的な部分を棄てなかったヴェルディが、ロッシーニ的な抽象的な世界に足を踏み入れた作品ということでしょう。それは、どちらが上ということではなく、ヴェルディはヴェルディのやり方を全うした上で、最後にそのような世界に遊んだ、というこだと思います。 そういえばリッカルド・ムーティは、「ヴェルディの作品は2つに分けられる。「ファルスタッフ」以前と「ファルスタッフ」だ」と語っていたのでした。 藤原歌劇団「ファルスタッフ」の公演情報はこちらです。 http://jof.or.jp/2015falstaff/
January 18, 2015
-
新国立劇場、2015−16シーズンラインナップ発表!個人的な注目は。。。
新国立劇場の、2015−16シーズンラインナップが発表になりました。 具体的な内容は劇場のサイトにアップされていますが、ここではオペラ部門の演目について、個人的な注目点を交えながらご紹介しようと思います。 一見したかぎりでは、芸術監督の飯守マエストロの「色」がはっきり打ち出され、納得のいく、そしてキャスト面でも相当に充実した内容だと感じました。主役級の招聘キャストも、世界の一流劇場で活躍している面々が大半で、相当に魅力的です。とりわけ(予想されたことですが)ドイツものは世界最高レベルの顔ぶれが揃っているといってもいいのではないでしょうか。 一シーズンにオペラ10本、うち新制作3本というラインナップは、ここ数年通りです。開幕が「ラインの黄金」なのはまさに飯守カラー。これから「指環」が1作ずつ登場するのでしょう。シーズンの最後から2本目にも、再演ですがやはりワーグナーの「ローエングリン」が登場。この2本は飯守マエストロがタクトを執り、「ライン」はラジライネンやグールド(なんとローゲ役ですが、マエストロは「適役」だと自信たっぷりでした)、日本人では安藤赴美子さんがフライアを歌うのが目を引きます。「ローエングリン」はやはりというか、天下無敵のローエングリン王子、フォークトの再登場。これは大騒ぎになりそうです(とくに女性ファンが)。 ただ、飯守マエストロの痛恨事は、新制作なのに予算の関係で、プロダクションレンタルになってしまったこと(故ゲッツ・フリードリヒによるフィンランド歌劇場のプロダクション)。「劇場の経済的な破綻を避けるため」とまでおっしゃっていたので、苦渋の決断だったことがうかがえました。 新制作=プロダクションレンタルというパターンは、2つめの新制作である「イェヌーファ」も同じです。こちらはベルリンドイツオペラのプロダクション(ロイ演出)。でも面白そうですし、何より新国にヤナーチェク作品が登場するのは初めてですから、それだけでも快挙です。飯守マエストロのおつしゃるとおり、ヤナーチェクは今やメジャーなオペラハウスではレパートリーですし。そして彼の作品で最初にどれか、ということになれば、以前二期会でも上演された「イエヌーファ」でしょう。指揮にはチェコ人のトマーシュ・ハヌス、歌手は新国「アラベッラ」が魅力的だったミヒャエラ・カウネ、なつかしい名前!のジェニファー・ラーモア、新国「サロメ」のヘロディアスなどでおなじみのベテラン、ハンナ・シュヴァルツなど。大半はベルリンドイツオペラで本作を歌っているメンバーだそうです。 もうひとつの、そしてこちらは純粋に「新しく制作」するプロダクションは、「ウェルテル」。これまた待望のフランスものです。そう、フランスものも長い間欠けていたのでした。五十嵐監督時代にサッバティーニ!(あのころ「サバさま」人気でした)の主演で上演されて以来。フランスものやロシア・東欧ものと、欠けていたところが新制作に入ってきたのは嬉しい限りです。 「ウェルテル」はキャストも贅沢で、指揮はなんとあのマルコ・アルミリアート。最近はメトのライブビューイングでおなじみですね。演出はベテランのニコラ・ジョエル。最近はパリ・オペラ座の監督をやってました。きれいだけど一癖あるプロダクションを作るひとだという印象です。歌手は若手中心ですが、タイトルロールにアメリカの若手、甘い声のマイケル・ファビアーノというのがなかなか魅力的。これがロールデビューだそうで、大抜擢でしょう。 飯守さんのたってのリクエストのようです。シャルロットのエレーナ・マクシモワも新鮮。アルベールは新国でおなじみのエレート、そしてソフィーに砂川涼子さんというのも楽しみです。 再演演目も充実。ドル箱の11月「トスカ」はスペインのテノール、デ=レオン(2013スカラ座来日公演、演奏会形式「アイーダ」のラダメス役)、イタリアのベテラン・バリトン、フロンターリが出演。これもドル箱、1月の「魔笛」は指揮(パーテルノストロ)を除いてオールジャパンキャスト、佐藤美枝子さんの夜の女王が期待大です。12月の「ファルスタッフ」は、タイトルロールにスカラ座来日公演「リゴレット」でタイトルロールを歌ったガクニーゼ、フォードにやはりスカラ座来日公演「ファルスタッフ」で同役を歌ったカヴァレッティ(スカラ座来日メンバーが多いというのはそこで決まったのでしょうか?とこれは憶測。)。クイックリー夫人のザレンパはちょっとなつかしい名前、アリーチェのミコライは新国の常連ですね。指揮が売れっ子オペラ指揮者のイヴ・アベルだというのも楽しみです。 キャストの豪華さでいえば、3月「サロメ」は注目。カミッラ・ニールンドのタイトルロールは贅沢です。ヘロデにクリスティアン・フランツというのも。ヘロディアス役のロザリンド・プロウライトもなつかしい名前!(1980年代にベローナで歌った「トロヴァトーレ」の映像は愛聴盤でした。) とはいえ、今回のシーズンを通じて個人的に一番楽しみなキャストといえば、4月の再演「 アンドレア・シェニエ」を振るイタリア人指揮者、ヤデル・ビニャミーニです。 この名前、見つけたときは驚きました。まだまだ無名だからです。なにしろイタリアでも、2013年のパルマ「シモン・ボッカネグラ」で注目されたばかり。それは聴きそびれたのですが、昨年秋のパルマ「運命の力」の指揮がとてもよく、これから要チェックの名前だと思いました。その後偶然、ミラノで「レクイエム」も聴けて。(ヴェルディ交響楽団)。イタリアの若手三羽がらす=マリオッティ、バッティストーニ、ルスティオーニに続いて出てくるだろうと想像していたのです(あとイタリアの若手で注目しているのは、オーレンの弟子のチャンパです。彼のほうがパリのオペラ座でダムラウ主演「椿姫」を指揮したりと、ビニャミーニより先に世に出ていますが)。 もちろんフォークトだニールンドだと、定評のある一流の歌手を日本で聴けるのは嬉しいですよ。でも個人的にわくわくするのは、これから出てくるだろう、というアーティストをちゃんと聴けることなのですね。今回のキャストでは、なのでビニャミーニ。飯守マエストロ、「カリスマ性がある」とおっしゃっていましたので、お聴きになっているでしょう。 「シェニエ」、歌手はこれもかなりおなじみ、カルロ・ヴェントレとヴィットリオ・ヴィッテッリ、そして前回のスカラ座来日公演でバレンボイム指揮「アイーダ」に出ていたホセ・シーリ。上江隼人さんがルーシェ役というのも頼もしいかぎりです。 シーズンの最後は日本オペラの定番「夕鶴」。これは名作だと思っていますし、日本人が初めて見るオペラには、実は一番いいんじゃないかと思っています。何より日本語がきれいだし(演劇台本をそのまま使っていることもあり)、音楽もわかりやすいし、コンパクトな物語だけれど「人間性」と「経済」の対立というテーマはとても普遍的(それこそ「指環」のテーマでもあるわけで)。今の日本に、必要な物語ではないかと思っています。 劇場のサイトにアップされている新シーズンラインナップです。 http://www.nntt.jac.go.jp/release/detail/150116_006190.html
January 16, 2015
-
究極の精緻が可能にした究極の「自然」〜テオドール・クルレンツィス&ムジカエテルナ「フィガロの結婚」
前回は、「想い出のアーティスト」について書きましたが、今回は、昨年一番衝撃を受けたディスクをご紹介します。 テオドール・クルレンツィス指揮、ムジカエテルナによる「フィガロの結婚」です。 クルレンツィス。1972年、ギリシャ生まれだというこの指揮者についての評判は、しばらく前から耳にはしていました。ショスタコーヴィチのディスクなども高く評価されていたようです。一昨年には2012年に録音されたこの「フィガロ」、昨年は「コジ・ファン・トウッテ」のCDが発売されました。気になっていたのですが、長い間、「積ん聴く」状態になっており、ようやく、この年末年始にかけて、全曲を聴き通すことができました。どちらも凄い演奏ですが、以下、こちらから聴き始めた分よけい衝撃的だった「フィガロ」について書こうと思います。 とにかく、衝撃でした。いままで聴いてきた「フィガロの結婚」は一体なんだったのか。私にとっては、そのようなレベルの演奏でした。 嵐のように沸き起こる序曲から「こんなフィガロ、聴いたことない」という体験の連続。音の響きもそうですし(もちろんピリオド楽器)、リズムも、アーティキュレーションも、あっ、と息をのむ瞬間ばかりが続くのです。歌手たちの即興演奏もふんだんだし(それもこれまで聴いたことのないような)、楽器のほうも負けてはいない。フォルテピアノなど、レチタティーヴォばかりでなく、アリアや重唱でも関係なくずかずかと入り込んで即興をまき散らす。それがちっとも不自然ではなく、わくわくさせてくれるのです。 歌唱法も、これまでとは違います。古楽の団体が演奏する場合、ノンヴィヴラートで歌われることが多いわけですが、それがより徹底している。結果、音楽は奏でられているのに、かぎりなく語りに近く聴こえます。声を張り上げて歌うことは一切なく、音楽に伴われている人間ドラマに徹している。 なぜ、こんな演奏が可能になったのか。それを、解説に含まれるロングインタビューで、指揮者のクルレンツィス自身が詳細に語っています。それが、すごく面白い。このインタビューだけでも、CDの定価(6000円)の何分の一かの価値があると思えます。 インタビューの冒頭でまず驚くのは、この「フィガロ」の録音が、構想から実現にいたるまで10年という歳月をかけたことです。クルレンツィスによると、フィガロを録音しようと思ったきっかけは、モスクワのホスピスでフィガロを演奏した時、そこにいた人々に「この音楽が与えた効果は、私にとって決して忘れられないものになりました」(クルレンツィス。以下同)ことだといいます。「指揮をしながら私は、この傑作を一度もきくことなく終わる人生があるとしたら?などと考えずにはいられませんでした。」 彼のそんな思いは、たんにフィガロを聴いたことがないひとばかりではなく、フィガロを知っていると思い込んでいるひとにも向けられたのです。 「そういう危険はわれわれすべてにあり得るのではないか、録音やコンサートを通じてこの作品をよく知っている人たちにもあり得るのではないか、と、つまり、モーツアルトのスコアの研究によって、そういうわたしたちの耳がなじんでいるのとはかなり異なったものが明らかになっているとしたら?」 モーツアルトのスコアを徹底的に研究し、同時に他の音楽の研究も進めることによって、できるだけ、本来あるべきフィガロの姿に到達すること。録音に当たって、それが、クルレンツィスの目的となった。それが、この録音の第一にユニークな点でしょう。 その目的のために、彼ら(クルレンツィスと、彼が創設したピリオド楽器のアンサンブル、ムジカエテルナ)が何をやったか。 「フィガロ」の自筆譜の研究はもちろんですが、「ベートーヴェンの交響曲をやり、中世とルネサンスの音楽で即興演奏を経験し、モーツァルトにもどってたとえばピアノ協奏曲の第23番をやり」、さらに、「モーツアルトと彼の同時代の作曲家たちの作品のファクシミリ版を収集するという作業も始めました」 そこまで徹底したやり方を進めるうち、何が見えてきたか。 「そういうスコアを長年にわたって研究しているうちに、私たちは、モーツァルトがはっきりと書き表している意図と、私たちが聞き慣れている演奏との間の食い違いを見つけて何度も驚くことになりました」 「私たちが聞き慣れているものは20世紀のオペラの伝統に根ざしていますが、それは要するに物事を単純化するという伝統です。その伝統のおかげで、オーケストラはリズムや強弱法といった複雑なことに無頓着でいられるようになりました」 一例をあげれば、むらなく美しい音=美しい、という価値観でしょう。 このあたりのことは、ピリオド奏法を積極的に展開している演奏家や、それになじんでいる聴き手には当然のことといえるでしょうが、クルレンツィスのやり方は、より徹底しています。 「この録音では、初めてちゃんと録音されたそのような部分を数多く聴くことができると思います。(中略)私たちは、そうした細部に注意を向けることによって、どこかの素晴らしいアーカイヴ、書庫のなかで幸せに暮らす虫に、古い紙を大喜びで味わい、その複雑な香りを吸い込んで楽しむ、飽くことを知らない虫に、なりたいと思ったのです」 研究者のような態度ですが、彼のやり方は、同時に創造的でもあります。スコアにないことも、わざわざ取り入れている。それは研究から彼が汲み取った成果であり、同時に霊感の賜物でもあります。「フィガロ」の初演時の演奏ではやらなかったようなことも、音楽を生かすためにあえて取り入れている。ただしそれはあくまで場面にふさわしいからであり、たんなる思いつきではありません。 「音楽演奏に関して歴史的真正さをどうこう言うのは無意味だと考えています。モーツアルトが実際に耳にしていたサウンドを知ることは、彼の肌の感触を知ること同様、不可能です」 「モーツアルトの場合、私たちは時代楽器またはレプリカを使います。歴史的真正さに近づけるからではなく、それらの楽器がもたらす(中略)サウンドが、この音楽のスリリングな感じをフルに表現してくれるからです) これも、多くの音楽家に共通する認識だと思いますが、その先どうするか、という段になって各人の個性が発揮されます。たとえばクルレンツィスはこんなことをやる。 「 普通のピリオド演奏の枠組みからは外れている、リュート、ギター、ハーディガーディといった楽器も使いました。それらの楽器はモーツアルトの時代にはまだ演奏されていましたが、オーケストラでは使われていませんでした」。 そんな楽器も、場面によっては、効果を考えて取り入れてみるのがクルレンツィス流です。たとえば、音楽により田舎らしい雰囲気を与えるためにハーディガーディを使ったりする。「歴史的真正さという点からは、これらの楽器を使うのは間違っているかもしれませんが」、「私たちは単にモーツアルトのサウンドだけを再現したかったのではなく、それと同時に、音楽を本当の意味で生き生きしたものにするために、その登場人物たちが存在している空間や、彼らが呼吸している時代の空気までも再現したいと思ったのです」 モーツアルトの「時代の空気」。そこには「革命」がありました。そのことについて、そして「革命」と「フィガロ」との関連について、クルレンツィスは鋭い洞察を示しています。「フィガロ」はまさに(フランス)革命の申し子であり、「革命的」な作品だった。内容においても音楽においても。だから彼の演奏する序曲は、革命前夜のように聴こえるのかもしれません。 クルレンツィスの言葉があまりにも魅力的なので、つらつらと引用してしまいました。が、個人的にこの演奏が、自分がこれまで聴いた「フィガロ」とどこが違うのか、一言で言えと言われれば、 「自然」 だ、ということでしょう。 これほど徹底的に考え抜かれた「フィガロ」が、なぜ「自然」なのか。 以下はまったく個人的な好みと照らし合わせた上の意見なので、そのことをご承知のうえお読みいただければ幸いです。 繰り返し書いているように、私はオペラ作曲家ではヴェルディが一番好きです。1にヴェルディ、2、3、4がなくて5がモーツァルトといったところでしょうか。念のために申しますが、あくまで「好き嫌い」です。凄い凄くないではありません。(以前「モーストリークラシック」誌で、好きなオペラ10選をあげるという特集記事で10作すべてヴェルデイにしましたが、好き嫌いではなく、凄い作品をあげろといわれたら、全然別のリストになると思います。「ペレアスとメリザンド」とか「ボリスゴドゥノフ」といった作品も入るでしょう) ヴェルディが「好き」な理由のひとつは「シンプルイズベスト」。最小限の音でドラマを表現できるところです。それに慣れてしまうと、他の作曲家は饒舌に感じられてしまうのです。お叱りを承知でいえば、(簡潔でいながら凝っている)モーツアルトですら「音楽がまさりすぎ」と感じてしまうのです(このことは、拙著「ヴェルディ」(平凡社新書)のあとがきにも書きました)。 ところが、クルレンツィスの「フィガロ」は、音楽が勝っているという感じがほとんどしないのです。過激なのにとても自然。今そこで繰り広げられている人間ドラマを見ているような。これこそ、モーツアルトの時代にあり得た、少なくともこれまでの演奏のなかでもっとも近づいた部類の演奏なのではないだろうかと感じられたのでした。 やはりこれは、画期的な演奏なのではないだろうか。 きわめて個人的な基準で恐縮ながら、そう思った次第です。 ちなみにクルレンツィスのヴェルディ、「マクベス」のDVDを持っていました(パリ、オペラ座)。チェルニャコフの演出が苦手で音楽はあまり聴けていなかったので、引っぱりだして再見しました。オペラ座ですから当然ピリオド演奏ではないですが、やはり面白い。ところどころ「おっ」(こんなことしている!)と思います。そしてボーナストラックのインタビューで、ヴェルディに関して言っていることがまた腑に落ちてしまった。「楽譜はシンプルです。けれどその奥へ下りて行くと、ヴェルディが意図している鉱脈を探り当てることができる」。そんなような内容ですが、まったくその通りだと思うのです。 ギリシャ生まれながらロシアが本拠で、パルミという街のオペラハウスで活動しているクルレンツィス。80年代生まれの指揮者がどんどん出てきている今では、若手、という範囲からは抜け出ているかもしれません。ですが、近い将来、チューリヒで「マクベス」を振るという。これはぜひ行かなければと、心に決めてしまったのでした。 「フィガロ」、CDの情報はこちらです。 http://www.hmv.co.jp/news/article/1312250042/
January 5, 2015
-
ネルソン・フレイレのこと
あけましておめでとうございます。 本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 さて、2015年の最初のブログは、「初めての追っかけ」アーティストについて書こうと思います。 ネルソン・フレイレ。クラシックファンならご存知の方もそれなりにいらっしゃるでしょうか。70歳になる、ブラジルのピアニストです。 そう、追っかけ第一号は、ピアニストでした。今でこそ歌手だ指揮者だと騒いでいますが、クラシックの原体験はピアノです。ど下手な「習い事」だった時期もありました(誰でもピアノを習っていた時代なので)。親戚にピアニストがいて、その彼女から最初にもらったLPが「フレイレ」だったのです。忘れもしません、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番と「死の舞踏」のカップリング。ルドルフ・ケンペ指揮ミュンヘン・フィル。それと、シューマン「謝肉祭」とシューベルト「即興曲」の組み合わせ。ちょうど習い事ピアノで、「即興曲」を弾いていたのです。なので、聴き込むうちに惹かれて行きました。 その時、フレイレがうたい文句で何と呼ばれていたかというと、「若き巨匠」だったのですね。超絶技巧のヴィルトゥオーソという売り方でした。今のフレイレをご存知の方なら、へえ?という感じなのではないでしょうか。でもたしかにこの録音は、テクニカルな面を前面に押し出していてまばゆいばかりという印象です。 当時、南米のピアニストがブームでした。アルゲリッチ、ゲルバー、バレンボイム、そしてフレイレ。あの吉田秀和さんが彼らのことをしばしばとりあげたことも、話題になるきっかけとなったように思います。クラシックの世界にとって新しい大陸から出てきた新鮮な人材、という位置づけでした。その後の彼ら、とくにアルゲリッチやバレンボイムの活躍についてはご承知の通りです。(考えてみると、今のオペラ歌手も同じような状況、つまり本場であるヨーロッパ(特にイタリア)の人材が枯れてきて、南米とかロシア東欧など、その方面の新興国に頼っているわけですね。) デビュー後しばらく、フレイレは、ひんぱんに来日していました。高柳音楽事務所というところが呼んでいたのです(今はもうありません。。。)。前後してシューマン&グリークの協奏曲、ショパンのピアノソナタ3番とリストのピアノソナタのカップリング、母国の作曲家であるヴィラロボスのアルバム、ショパンアルバムなど、LPもたくさん出していました。 けれど、コンサートは残念なことに入りがよくありませんでした。日比谷公会堂あたりで聴いたこともありますが、正直、がらがらで、気の毒なくらいだった時もありました。なので、LPも売れていなかったと思います。 ちょうど、美形?ピアニストがブームの時でもあり、「ハンガリー三羽がらす」と呼ばれたラーンキ、コチシュ、シフ、ちょっと後にポーランドのまさに美形のツィンメルマンが続きました。彼らのリサイタルには音大生をはじめとする女性ファンが列をなし、カーテンコールでは花束贈呈の行列ができて話題になったのを覚えています(世代がわかりますね)。フレイレは、そんな「ブーム」とは、まるで離れたところで音楽を奏でていました。私も何度か彼のコンサートで「花束嬢」を自演しましたが、私以外に花束を持って来ている女の子なんて誰もいなかった。そして彼も、そういうのがあまり得意ではないようでした。花束を受け取るときの表情も、とてもシャイ?でしたので。 そのうちフレイレは来なくなり、録音も発売されなくなりました。 彼が「復活」しはじめたのは、アルゲリッチとデュオをしたあたりでしょうか。「ラ・ヴァルス」などを収めたアルバムが話題になりました。その後、留学していたドイツで、「ミュンヘン ピアノの夏」というフェスティバルで2人を聴いて痺れた記憶があります。 そしてまた、フレイレの名前をしばらく放念していました。 ここ7、8年ではないでしょうか、彼が(ソリストとして)本格的に「復活」してきたのは。 日比谷公会堂ががらがらだったピアニストは、今やシャイーやゲルギエフといった売れっ子指揮者から「ぜひ」と指名される人気ピアニストにして、(若き、ではない)「巨匠」になっています。 昨年10月、マリインスキー歌劇場管弦楽団と来日したフレイレは、ブラームスのピアノ協奏曲第2番を披露しました。ちょっとマイペース気味なのですが、ゲルギエフがちゃんとサポートして、ほどよいスケール感と繊細な表情に富んだ「いい味」の演奏を堪能することができました。 そして昨年の終わりには、(3月に一緒に来日もした)シャイー&ゲヴァントハウス管との共演で、ベートーヴェンの「皇帝」と、ソナタの32番のディスクを聴くことができました。 よかった。 しみじみと、心に落ちてくるピアノでした。とくに32番のソナタの、それも第2楽章のあたたかな美しさは涙が出るほど。繊細で、優しい。テクニックは相当なものですが、それを見せることをためらう、フレイレにはそんなところがあります(昔から)。 追っかけをしていたときも感じたのですが、彼はたぶん、相当にナイーブでピュアなアーティストなんですね。(たしか結婚もしていなくて、ペットの犬と暮らしているそう)。マイペース。インタビューもあまり受けないらしい。 (そういえば、「追っかけ」時代に目にした音楽の友誌のインタビューで、ときどき質問と答えがずれていて、今風に言うと「不思議君」みたいだなあ、と思った記憶があります) この時代に彼がブレイクしているのは、そんな部分の魅力もあるのかもしれません。 派手で華麗で天才肌のピアニストはとかく目立ちます。たとえば、ラン・ランとか。ラン・ランは天才だと思いますが、ずっとこのタイプばかりだとちょっと疲れる。癒しという言い方は安易で好きではないですが、今時のフレイレの人気は、それに近いスタンスにもあるのかもしれない。 今はともかく、頭がよく、知識もあり、打てば響くように話もうまいアーティストが大半でしょう。それはもちろん素晴らしいし、必要なことです。けれど、フレイレのような、マイペースを守り続けている、それも孤高とかそういうのではなくて、自然にそうなっているアーティスト、外向きではなく内向きで、どこまでも自分と、音楽と向き合いながら、けれどそれが溢れ出してきて外の世界に伝わるようなピアニストの味わいも、いいなあ、と思われているのではないだろうか。 32番の、抑えていてもきらきらと湧き出てくる音の群れを聴きながら、そんな思いに捕われたことでした。 CDの情報はこちらです。 http://store.universal-music.co.jp/fs/artist/uccd1404
January 3, 2015
全6件 (6件中 1-6件目)
1