2016年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
バッティストーニがヴェルディオペラと「イル・トロヴァトーレ」の魅力を語る講演会、盛況のうちに終了いたしました!
前回のブログでご紹介した、日本ヴェルディ協会の主催による、指揮者アンドレア・バッティストーニがヴェルディ・オペラと「イル・トロヴァトーレ」の魅力を語る講演会、本日、無事終了いたしました。およそ230名のお客様のご来場をいただきました。ありがとうございます。 前半はヴェルディのオペラ全般、後半は、来月彼が二期会で振る「イル・トロヴァトーレ」の話でしたが、昨年の「リゴレット」に先立っての講演同様、新鮮な発見の多い講演会でした。 たとえば、ヴェルディが同時代の、イタリアに限らずさまざまな国の要素を吸収していること(シューベルトやベートーヴェンも)。 よく言われるヴェルディ最晩年のオペラへのワーグナーの影響が、ボーイト経由であること。(ボーイトの「メフィストーフェレ」が、「オテッロ」に大きな影響を与えたというのは興味深くまた納得できる指摘でした) 「イル・トロヴァトーレ」には、アズチェーナの語りなどに、フランス・オペラの影響が見られること。 また、客席からの、「本作の解釈でどれが一番気に入っているか」との質問に対して、「決定的な解釈には残念ながら出会っていない。ドイツ的な演奏は後期のヴェルディ作品を通して解釈するので重くなりがちで、逆にその前の時代の様式に応じた解釈もちょっと違うと感じる」と答えたこと。 などは、ヴェルディ・ファンであっても新鮮に聞くことができたのではないかと思います。 「イル・トロヴァトーレ」について、バッティストーニは、この作品が初演で大変成功し、その後も成功を続けているのは、伝統的な形式に沿っていたことが受け入れられやすかったのではないかと分析した上で、革新的な作品である「リゴレット」の後だから、伝統的な枠組みにちょっと戻ってみたのではないかと語っていて、これも納得ができる推論でした。 音楽への愛と情熱あふれるバッティストーニの語りは、いつも始まったらなかなか止まらず、とくに前半部のヴェルディオペラ全般の解説は、およそ半時間にわたって壮大なスケールでヴェルディオペラの流れを細部にわたって解説し、聞くだけでヴェルディに通暁してしまったと錯覚?してしまうような説得力でした。 本講演会のもようは、来月発売の「ハンナ」「音楽の友」誌でもレポートされる予定です。 講演会後はすぐ「イル・トロヴァトーレ」のリハーサルに向かったマエストロ。 来月の本番が楽しみです。 二期会「イル・トロヴァトーレ」の公演情報はこちらでごらんください。 http://www.nikikai.net/lineup/iltrovatore2016/
January 31, 2016
-
二期会公演「イル・トロヴァトーレ」に先立ち、指揮のアンドレア・バッティストーニが作品の魅力を語る講演会を開催いたします。
このブログでもたびたびご紹介しているイタリアの若手天才指揮者、アンドレア・バッティストーニ。 12月には、昨年春から首席客演指揮者をつとめている東京フィルで「第9」を指揮。情熱みなぎる炎のような指揮で喝采を浴びました。 日本では、デビューとなった「ナブッコ」以来、舞台上演のオペラは今のところ二期会の公演で指揮しています。 2012年の「ナブッコ」、そして昨年の「リゴレット」に続くバッティストーニの舞台上演のオペラ3本目は「イル・トロヴァトーレ」。ヴェルディらしい雄渾な旋律美みなぎる「歌」が次々と紡ぎ出される、魔法のような傑作です。 その「イル・トロヴァトーレ」公演に先立ち、「トロヴァトーレ」と、彼がいままで10作以上指揮しているヴェルディ・オペラの魅力を、バッティストーニに語ってもらう講演会を、日本ヴェルディ協会の主催で開催することになりました。 バッティストーニは、昨年2月の「リゴレット」の前にも、やはりヴェルディ協会の主催による、「リゴレット」の魅力を語る講演会に登場し、作品に対する深い読み込みと豊富な知識を、音楽同様の熱い語り口で語りつくして大好評を得ました。 「リゴレット」講演会のもようはこちらで。 http://plaza.rakuten.co.jp/casahiroko/diary/201502180000/ 今回の講演会でも、彼の音楽づくりに共通する、真摯で熱気あふれる話がきけることと思います。 講演会は1月31日(日)、午後2時より、九段下のイタリア文化会館。井内美香さんの名通訳つきです。 詳細およびお申し込みは以下をご参照ください。 http://www.verdi.or.jp 二期会公演「イル・トロヴァトーレ」のサイトはこちらです。 http://www.nikikai.net/lineup/iltrovatore2016/
January 17, 2016
-
ようやくベルカントの王道が!新国立劇場新シーズンラインナップ発表
新国立劇場の新シーズン(2016−17)のラインナップが、今日発表になりました。 新国立劇場のサイトにはすでにアップされています。(こちらはオペラ) http://www.nntt.jac.go.jp/release/detail/160115_007941.html シーズンの最初と最後が、「リング」の第2作と第3作(新制作)だというのはきいていましたが、個人的に一番嬉しかったのは、新制作3本の残り一本が、ドニゼッティの「ランメルモールのルチア」だということでした。うれしいというか、「ようやく」または「やっと」という気分が近いでしょうか。以前から何度かここでも書いているように、新国立劇場の公演ラインナップに(今世界では「旬」の)ベルカントものの上演が少ないことが、不満だったからです。ベルカントの王道レパートリーといえる「ルチア」も、初代の五十嵐監督時代にやったきり、10年以上上演なし。セットも破棄してしまったとききましたので、残念に思っていました。 それが、ようやく、2度目の新制作です。「満を持して」であったらいいなあ、と思います。実際、キャストはなかなか魅力的。ヒロインのルチアには、ベルカントの若手プリマとして大活躍中のオルガ・ペレチャッコ。指揮は、イタリアの若手指揮者のなかで注目されているひとりであり、(そしておそらくベルカントものにかなり適性がある)ジャンパオロ・ビサンティなのですから。(イタリアの若手といえば、今シーズンの再演ものの「アンドレア・シェニエ」を振るビニャミーニも注目です)。また、エンリーコにはザルツブルクでドミンゴの代役で「トロヴァトーレ」に出るなどこれも大活躍中のアルトゥール・ルチンスキが出演します。 ベルカントものといえば、再演ですが「セビリヤの理髪師」には、 伯爵役にマキシム・ミロノフが登場。注目のロッシーニテノールのひとり。柔らかな声と高い技術、王子さまのような外見も魅力的です。新国の「セビリヤ」では、伯爵の大アリアを歌わない歌手がしばしばキャスティングされますが、ミロノフなら歌ってくれそうです。 「セビリヤ」以外の再演は、「ボエーム」「フィガロ」「蝶々夫人」「オテロ」「カルメン」とポピュラー作品のオンパレード。個人的な注目キャストは、「フィガロ」のスパニョーリ(伯爵)とヴェルバ(フィガロ)、「オテロ」のヴェントレ(オテロ)、ファルノッキア(デスデモナ)、ストヤノフ(ヤーゴ)、「蝶々夫人」の安藤赴美子、「カルメン」のジョルダーノ(ホセ役。ジョルダーニではありません)、「ボエーム」のフローリアン(ミミ)。(ワーグナー2作品はもちろん揃っていますが、詳しい方があちこちでお書きになるでしょう) 指揮者も聴きたいひとが少なくありません。「ボエーム」のアリヴァベーニ、「カルメン」はアベル!「蝶々夫人」はオーギャン、「オテロ」はカリニャーニ、「フィガロ」はトリンクス。それぞれ得意な分野で活躍している面々が揃っています。 「リング」2作とベルカントという新制作、それ以外はポピュラー作品をそれなりにうなずけるキャストで。次シーズンの新国立劇場のオペララインナップは、オペラハウスのひとつの「王道を行く」という印象を受けました。
January 15, 2016
-
バロック、ベルカント、クルレンツィス、そして…2015年を振り返って
あけましておめでとうございます。 大変遅まきながらのご挨拶で恐縮ですが、本年もよろしくお願いいたします。 この年末年始は、いつもにも増してマイペースで、あっという間に時間が過ぎてしまいました(苦笑)。 今更、という感じではありますが、2015年の音楽体験を振り返ると、 国内のベストワンは ビオンディ&エウローパ・ガランテ ヴィヴァルディ「メッセニアの神託」 国外できいたベストワンは メトロポリタンオペラ「湖上の美人」 というわけで、昨今のオペラ界の、バロック&ベルカントの充実ぶりを、改めて感じた年でした。 「メッセニア」は、今のバロックオペラのレベルの高さを日本でまざまざと見せつけた公演でしたし、「湖上」は、MET初演という点でも、そしてそれが驚異的にレベルが高いという点でも、文字通り歴史的な公演だったと思います。 国内の公演では、新国立劇場の「椿姫」も素晴らしかったですが、オペラ公演として画期的、という点で、メッセニアの印象は強烈でした。 以下、両公演の感想です。 「メッセニアの神託」 http://plaza.rakuten.co.jp/casahiroko/diary/201503030000/ 「湖上の美人」(これは、現地観劇の後にライブビューイングのメルマガやeぶらあぼに書いた記事ですが、正直な感想でもあります) http://ebravo.jp/archives/17392 「湖上の美人」については、wowwowのMetライブビューイング放送のなかで、解説も担当しますので、wowwowをご覧になっている方はぜひご覧ください。 さて、CDやDVDは、正直生の舞台に比べるとぐっと数が減りますが、年末になって、すごい1枚と出会ってしまいました。 テオドール・クルレンツィスとムジカ・エテルナによる「春の祭典」です。 ギリシャ出身の指揮者クルレンツィスについては、「フィガロの結婚」「コジ・ファン・トウッテ」のCDでの、古楽系の延長線上とはいえあまりにもエキサイティングで精緻で革新的な演奏に瞠目し、ずっと注目していましたが、今回の「春の祭典」の衝撃は、この2つの録音を上回るほどでした。 とにかく、はらわたをえぐられ、つかまれるような演奏なのです。 ここでの「春」は、私たちが思い描く明るいそれではありません。もっと野蛮で、あらあらしく、荒涼とした大地をゆさぶり目覚めさせる怪物のようなもの。ある日突然訪れ、予告もなく体内に侵入してくるもの。轟音とともに押し寄せ、体も心もかきさらっていく津波のようなもの(地下から吹き上げてくる不気味な旋風のようなパーカッションの波!調子外れのクラクションのような金管!)。それがここでの「春」なのです。その大地で繰り広げられる「祭典」で、生贄が踊り狂い、もだえ、泡を吹いて死に到達するのはあまりにも当然に思える。そんな演奏です。 クルレンツィスは、ギリシャ生まれですがロシアでのキャリアが長い。そして、民俗音楽に親しんでいる(CDのライナーに寄せている文章で、「民俗音楽は私にとって真実を得る酸素として機能する」と記しています)。そんな彼ならではの、つまりヨーロッパ古典音楽の本場から外れている彼だからこそ可能な演奏なのかもしれません。 http://www.amazon.co.jp/ストラヴィンスキー-春の祭典-テオドール・クルレンツィス/dp/B012LBMK1M/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1452436541&sr=1-2 さて、音楽以外で昨年感銘を受けたものといえば、村上春樹氏の著書「職業としての小説家」(スイッチ・パブリッシング)です。 本書で、村上氏は、え、そんなところまで?と感じるくらい、小説家としての「手の内」を見せてくれています。それ自体も面白かったですし、一方で、 いろいろな疑問?が解けると同時に、個人的に、とても勇気をもらえた本だったからです。 解けた疑問の代表は、たとえば、「小説家」とはどんな人種か、ということ。 村上氏はいいます。小説家という人種は、ある意味「頭が良くない」。たとえ話として出てきたのは、富士山見物に出かけた2人の男。頭が良い方の男は、富士山を麓のいくつかの角度から見ただけて、富士山というものはこういうものだと納得して帰る。良くない方の男は、そんなに簡単には富士山を理解できないから、実際に時間と手間をかけて登ってみて、その結果、理解するというか腑に落ちる。小説家に向いているのは後者。前者は、評論家とかそういう人種に向いている、と。 すごく、わかりやすいたとえでした。 私も、ふだんはあまり小説というものを読みませんが、それは、その手の「まわりくどさ」がしんどい、と感じることがままあるからです。たとえば昨年大ベストセラーとなった又吉秀樹さんの「火花」も、そのような意味でみごとに「小説」でした。だから、読みましたし、それなりに面白かったし、そして彼が才能のあるひとなのだろうな、ということは感じたのですが、では自分がこういうものが好きか、書きたいか、と言われるとちょっと違うというのが正直なところ。(もちろんのことですが、私が「頭がいい」人種に分類されるといっているのではありません。要はせっかちなのです。私だけではないと思いますが) まあ、小説にもいろいろありますから、すべてがすべて「まわりくどい」と感じるわけではないですが、それにしても、自分がしばしば、「小説」という形式にたいして、なんだかごちゃごちゃしているなあ、と感じるのは、つまり私はそういう形式にあまり向かないのだな、と腑に落ちたのでした。 村上氏が「小説家」になった「運命」を感じたくだりや、小説家として現在でも持ち続けている心構えにも、感銘を受けました。 彼は、喫茶店のマスターをやりながら本を読み漁る生活をしていたある日、神宮球場で野球をみている最中に、「空から何かがひらひら落ちてきて、それを両手でうまく受け止められたような気分」とともに、「僕にも小説が書けるかもしれない」と思ったのだそうです。 「それを境に僕の人生の様相はがらりと変わってしまったのです」(42ページ) そして処女作を書き上げ、でも満足できなくて、一度英文で書き直してみたら、新しい文体が獲得できたように感じ、それを今一度日本語にして、「群像」の新人賞に応募します。 そしたら、「最終選考に残った」という電話がかかってきた。 その電話を受けた後、村上氏は散歩に出て、傷ついた伝書鳩を拾います。その鳩を、両手にそっと持ち、交番まで運んで行った 。春の、よく晴れた、気持ちのいい日曜日のお昼前だった。 その時氏は再び思います。 「僕は間違いなく群像の新人賞をとるだろうと。そしてそのまま小説家になって、ある程度の成功を収めるだろうと。(中略)なぜかそう確信しました。とてもありありと。それは論理的というよりは、ほとんど直観に近いものでした」(52ページ) 人生には、そういう瞬間が訪れる時がある。 それは、わかる気がします。 直観ですが、でも確信的にそのことを予測する瞬間。とてもまれなことですが、私にも、経験はあります。そういうときは、その直観に従う?ほうがいい、というか、そういう風に自然となっていくのではないでしょうか。 そうやって小説家になったことを、村上氏は「とても幸運」なことだと感じています。 「僕が長い歳月にわたって一番大事にしてきたのは(中略)、「自分は何かしらの特別な力によって、小説を書くチャンスを与えられたのだ」という率直な認識です。(中略)僕としてはそのようなものごとのありように、ただ素直に感謝したい。そして自分に与えられた資格をーちょうど傷ついた鳩を守るようにー大事に守り、こうして今でも小説を書き続けていられることをとりあえず喜びたい。あとのことはまたあとのことです」(54ページ) こういうくだりも、共感を覚え、また感銘を受けながら読みました。 こうして(ご本人の認識として)「幸運」なことに小説家になった氏は、小説家であることを徹底的に大事にしています。 その一例が、 「注文を受けて小説を書いたことがない」 ということでしょう。 正直、驚きました。人気作家といえば、締め切りに追われる、というのが常だと世間では思っているでしょうし、実際大半の人気作家はそうだと思うからです。 要するに、書きたいと思うまで書かない、というのが氏のスタイルなのです。自分のなかに材料がたまり、書きたくてたまらなくなるまで書かない。その間は、翻訳をしたりしている。 うなってしまいました。氏はとことん、「小説」、それも本人が「向いている」という長編小説を書くことを、徹底して最優先事項にしているのです。優先順位が実に明確なのです。 一流のひとたちというのは、優先順位がはっきりしている場合が少なくないと思いますが、それにしても、繰り返しですが村上氏の優先順位のつけかたは明確です。大きな理由は、彼は小説を書くことが好きで仕方がないから。「小説を書くという作業に関して言えば、1日5時間くらい、机に向かってかなり強い心を抱き続けることができます」(177ページ)。そのために、体も鍛え、フルマラソンを走る(小説を書くのは体力だし、自分の内面を掘り下げるためにもフィジカルな部分を鍛えることは重要だという考え方はよくわかります。作家だけではなく、どんな仕事でも当てはまることでしょう)。 そんな強い心を持つ村上氏は、徹底してマイペースです。講演もサイン会もめったにやらない。その代わり(というのも変ですが)作品で応える、というのが氏のスタイルです。もともと群れないし(学校やサークル活動のようなものも苦手だったらしい)、縛られるのが嫌いな性格。文壇などというグループ?にもはなから興味はなかったらしい。そのような自分の性分を強みに変え、もちろんもともとの才能もあるのだと思いますが、ずばぬけた集中力と胆力で小説を書き続けている。うーん、理想ですね。 読んでいて、似たようなタイプのアーティストの本を以前読んだな、と思ったら、千住博さんの「ルノワールは無邪気に微笑む」(朝日新書)でした。千住氏も凄まじい努力(集中力)家で、どちらかというと一匹狼で群れることなく、自分がこれと思った大きな仕事に集中するタイプだったのです。 さらに2人に共通しているのは、NY を拠点としているということです。村上氏は定住しているわけではないようですが、少なくとも世界へ向けての出版の拠点にしている。キャリアのはじめのうちから、「世界」を視野に入れて、具体的な行動を起こしている。そのような努力もあって、今の世界的な「ハルキ」ブームへとつながっているのですね。 世界的作家が明かしてくれた「手の内」、当然ながら、真似などできようもないことも多いです。でも、自分がこれまで感じていた、優先順位を徹底することの大切さ、身体を快調に保つことの重要さを、村上氏のようなアーティストが体現していると知ったことは大いに励みになりましたし、そして何より、今、自分が、子供の頃から夢見ていた「本を書く」ことを許されている、その「ものごとのありように感謝する」ことの大切さをこの本から学べたことは、大きな喜びでした。世界のハルキ氏に、そして今のありようを実現させてくださった皆様に、今年の始まりにあたって、改めて、心からの感謝を捧げたいと思います。
January 10, 2016
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-
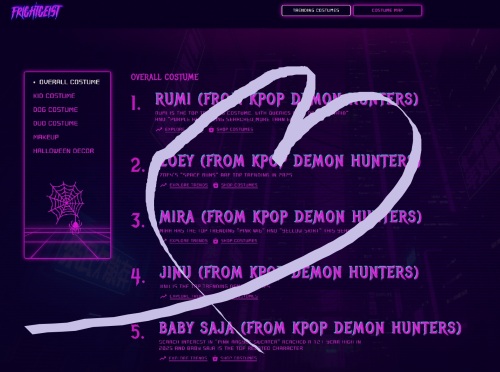
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-








