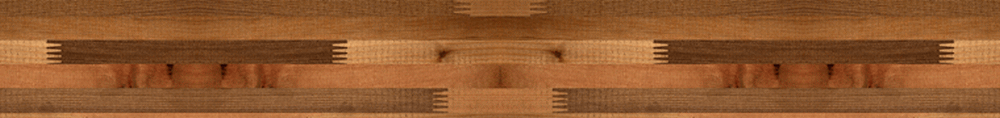2012年06月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

1-2-2 , 3-2 のゾーンについて考察する その3
こんにちはenoです。 前回【図1】、のボールがトップからウィングに移動したときは、【図2】のように、(2)の選手がボールマンにプレッシャーをかけます。 『 図2:ボールがウィングにあるとき 』 この時、ディフェンスは、レシーバーにボールが渡った瞬間、スクエア・スタンスで守ることを心がけます。 ボクサー・ステップのような、ワンウェイを守るスタンスでは、ギャップをつかれて簡単に抜かれてしまう可能性があります。 そもそも、ボールをもらった瞬間というのは、オフェンスはまずシュートを狙う訳ですから、スクエア・スタンスで付かなくてはいけません。その後、ピボットが始まってから、ボクサー・ステップにスイッチしましょう。 これはマンツーマンンも同じです。 スクエア・スタンスでディフェンスをして、ピボットが始まってからボクサー・ステップに切り替えるという練習を必ず行なってください。 ローテーションは、(2)がいた場所に(1)が入り、プラグします。 2-3の場合も同じですが、必ずボールに対して、1-2-2という形を取ることになります。2-2の部分でプラグを行うことが原則です。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年06月30日
コメント(0)
-

1-2-2 , 3-2 のゾーンについて考察する その2
こんにちはenoです。 ゾーンを組む場合は、まずはプラグを守ることを優先するのが基本です。ですから、図1のようなポジションどりがベストだと考えます。 『 図1:ボールがトップにあるとき』 まずは、ボールマンにハンズアップしてプレッシャーをかけます。 残りの4選手は、制限区域内に両足がかかるようにプラグします。 脚力が向上したり、予測能力がついてきたり、選手の個々の能力が向上した場合、片足だけ制限区域内にいれる形にすると、より効果のあるゾーンになるでしょう。 まずは、両足を入れるところから始めてください。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年06月27日
コメント(0)
-

1-2-2 , 3-2 のゾーンについて考察する その1
こんにちはenoです。 それでは、具体的に1-2-2-の説明からしていきたいとお思います。 3-2と呼ぶ方もいらっしゃるでしょうが、ポジション、ローテーションは、ほぼ同じですので、ここでは一緒に扱います。 よく、ウィングの選手が張り出している形の1-2-2を組んでいるチームがあります。 しかし、これではエルボーをプラグしなければいけないポジションが2か所も開いてしまいます。(プラグ=フリースローの4隅) ショットの成功率の話を思い出してみてください。 3ポイントよりもボックス内のショットのほうが、高確率で決まるわけです。 そしてプラグの位置にボールが入っただけで、ディフェンスは最も不利な状況に立たされてしまいます。 このゾーンを組む場合も、まずはプラグを守ることを優先するのが基本です。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年06月20日
コメント(0)
-

基本はボールマンとボックスを守ること その4
こんにちはenoです。 「ゾーンだとリバウンドが取れない」ということを言う指導者の方がいますが、私は、まったくそんなことはないと思います。 リバウンドを取るために必要なことは、ボックスアウトです。 現在はボックスアウトという言葉を使いますが、以前は、スクリーンアウト、ブロックアウトという言葉を使っていました。 なぜボックスアウトという言葉を使うようになったかというと、ボックスの中に落ちるシュートは、実に90%以上だからです。 よって、ボックスの中にオフェンスを入れさせないように徹底できれば、90%以上の確率でリバウンドが奪えるのです。 従って、マンツーマンだから、ゾーンだからということで、リバウンドが取れるか、取れないかは決まりません。 ボックスアウトが出来ているか、出来ていないかで、リバウンドが取れるか、取れないか、が決まるのです。 ゾーンでリバウンドが取られてしまう場合、システムの見直しよりも、まず、ボックスアウトを徹底することから始めてはいかがでしょうか。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年06月19日
コメント(0)
-

基本はボールマンとボックスを守ること その3
こんにちはenoです。 最も確率の高いショットは、レイアップショットです。確率で言えば、ほぼ100%でしょう。 次に、ボックスの中での2ポイントショット。その次に、ミドルレンジ、そして3ポイントショットという順に確率は下がっていきます。 リングから遠ざかれば遠ざかるほど、ショットの確率は下がっていくのですから、ボックス内を守るという約束は、ゾーン・ディフェンスのみならず、すべてのディフェンスにおいて基本となります。 つまり、ボックスの中にボールを入れさせないということが、確率的に考えれば、良いディフェンスということなのです。 ですから、ゾーンにも、2-3,3-2,1-3-1など、様々なスタイルがありますが、どれも制限区域の4隅をプラグして、ボックス内を守るという点は共通しています。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年06月11日
コメント(0)
-

基本はボールマンとボックスを守ること その2
こんにちはenoです。 ゾーン・ディフェンスの基本についてお話しする前に、指導者の方はゾーンを組む際の選手のポジションを細かく指示しているでしょうか。ローテーションは選手任せになっていないでしょうか。 個々の能力(脚力、予想能力、経験等)だけに任せてしまうと、メンバー・チェンジが行われた場合のように、他の選手が入るとそのゾーンは全く機能しなくなってしまいます。 ゾーンは5人が一体になってこそ、効果があるものです。 ですから、誰がいつ入っても同じゾーンにするためには、チームとしての共通理解、すなわち「基本」というものが大切になってくるのです。 私が考えるゾーン・デイフェンスの基本とは、ボックス内を守ることです。 そのためには、まずボックス(フリースロー・エリア内)の4隅を守ることが大切です。私はこれを"プラグ"すると名付けました。 このエリアは、ディフェンスが、オフェンスに奪われたら一番嫌なポジションです。 ここにボールが入ってしまったら、守るのが難しくなってしまうので、オフェンスよりも早く、そのポジションに移動しなければなりません。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年06月09日
コメント(0)
-

基本はボールマンとボックスを守ること その1
こんにちはenoです。 ゾーン・ディフェンスに限らず、全てのプレーや戦術には、基礎・基本というものが存在します。 そして、私は、その基本というのが、最も大切ではないかと思います。 従って、指導者の方々には、"型"ではなく、『基本』の部分、そして、さらにはバスケットの本質は何かということを、選手に指導していただきたいと願っています。 ではまず、なぜゾーンを組むのか?ということからお話ししたいと思います。 これは、ゲームの流れを変えたいときや、ディフェンスを不得意とする自チームの選手が、相手のキー・ポイントになるプレーヤーとマッチアップしなければならない場合などがあります。 また、マンツーマンのオフェンスが得意なチームと対戦した場合、相手のほうが、オフェンス関して練習時間の絶対量が多いときなど、マンツーマンで守っていてはチームにとってマイナスになってしまいます。 ですから、そんなときにはマイナス部分を削除するために、選択肢として、ゾーンを組むことなどもあるでしょう。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年06月06日
コメント(0)
-

プランニングも基本から その3
こんにちはenoです。 練習段階においては、このドリルは何のためにあるのか、チームにどんな場面で生かしたいのかなどをしっかりと理解して、基本から段階を追って取り組むことが必要なのに、ただ反復したり、基本が出来ていないのに次の段階へと急ぎ過ぎているだけという場合も多く見られるようです。 これはゲームプランニングという視点でも同じことが言え、基本というものがまずあって、それをしっかり行えるということが大前提です。 奇抜というと語弊がありますが、スペシャル・プレー的な奇を狙うばかりのプレーでは、良いバスケットを組み立てられるはずがありません。 初めはノーマルな中で工夫をして、体力、技術力、経験などの段階を追って、チェンジング・ディフェンス等のスペシャル・プレー、またはそれを利用するプランが出てくるという考え方をして欲しいと思います。 特に若い選手を指導されているコーチの方々には、プランを作成するうえで、基礎を大切にしたものの考え方を第一として考えていただきたいということを最後に添えさせていただきたいと思います。 結果的には、ゲームプランニングの基本はチーム作りの基本に繋がりますし、それは同時に、選手個々のプレーの基本作りに全てのスタートを発するものではないでしょうか。 この章、END ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年06月04日
コメント(0)
-
プランニングも基本から その2
こんにちはenoです。 ディフェンスが素晴らしい選手ならばプレスディフェンスを起用し、その力を活かしたり、シュートが素晴らしい選手をワンポイントで使うなど、ゲームのイメージを広げていくことで、メンバーを構成していけます。 それによって、ゲームで起用できる選手が増えて、それがそのままプランのバリエーションの数にも比例していくはずです。 「これはダメだ」という否定から思考に入るのではなく、色々な発想からプランを立てることが望ましいのです。 最低でも、常に7人~10人くらいのメンバーでゲームを展開するのが理想ですし、そうできるように努力するべきなのではないでしょうか。 選手起用ということに関して、ある意味では、控えの選手を使うことで、オフェンス、ディフェンスのどちらかが犠牲になることがあるかも知れません。 しかし、近年のバスケットのスピーディ、かつパワフルな展開においては、ゲームは5人だけで出来るものではありませんから、その状況をコントロールしながら利用していくことを、ゲームプランとして初めから頭に入れておかなくてはならないと思います。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年06月01日
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1